-
1

あ、麻の着物が色ヤケしてましたー!
麻の着物、去年百貨店のリサイクルで買ったものです。○○上布と言うようなものでしょう。何上布かは分からないのですが...とても涼しく、出会う人も「良い着物着てますね。」とおおむね好評で、去年数回着た着物です。と、ところが...!ハンガーで干した時、一番上で一直線になっている肩と袖のところ、色ヤケして、色が抜けていたのです!!ものすごくはっきりしているわけではないので、着る時も気づかず、襟を抜くと肩線は後になるので、鏡で見ても気づかなかったのですが...なぜ分かったかと言うと…先日、日本和装のセミナーにこの着物を着て行ったのです。そして、薄いグレーのその麻の着物の色や、私の好きな薄紫の色の着物は、日焼けして色が抜けやすい、と、しきりに言われていました。お買い物タイムが終わった位の時に色ヤケしていると教えてもらい、お出かけ用にせず、近所位にしておいた方が良い、と、言っていただきました。ショック!!!もっと早く言ってよ!リサイクルなので買ったときから抜けていたのか、去年色ヤケしたのか...あるお店で聞くと、1万1千円位で、ヤケ直ししてもらえるようで、どうしようか迷ったのですが、バチ襟で、長襦袢と襟が合ってなかったこともあり、外出着にすることはあきらめました。麻の着物の写真をここに載せて、記録として残しておこうと思います。麻の着物よ、今まで有難う気が向いたら、おうちで着てみましょう...
2009.07.17
閲覧総数 495
-
2

小物の目印
着物を着る時の小物類に、桜の花の簡単な刺繍を入れています。名前を入れる代わりに、自分の物と分かる目印に入れています20年位前ですが、初めて着物を習いに行った時、大勢の生徒さんの中で、自分の小物が分からなくならないように入れ始めました。 腰紐、足袋、補正具、タオルなどに入れています。 腰紐…初め紐の端に入れていましたが、中心に入れると、すぐ真ん中がわかって便利になりました。 足袋も見えないところに入れています。下は、呉服屋さんで、割安で自分サイズに名前を入れて作ってもらったもの。全部ひらがなか、子だけ漢字か選べました。 腰紐に印を入れておいたお陰で、他の方の所に紛れたのが戻って来た事も有ります。思いつきで始めたのですが、ちょっと便利で、なんとなく可愛く、愛着がわいて気に入っています
2009.10.16
閲覧総数 623
-
3
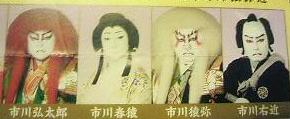
その1♪新歌舞伎座 ?葺落興行 二十一世紀歌舞伎組公演 行ってきました♪
新歌舞伎座、建て替えの為、しばらく休館していましたが、難波から上本町に移って、新しく開場となりました。建物のことは、後日“その2♪”に譲るとして、新歌舞伎座、新築の、?葺落(こけらおとし)の興行、16日に、母と、「二十一世紀歌舞伎組公演」見に行ってきました。 歌舞伎は、以前、大阪松竹座の「NINAGAWA十二夜」を見たのですが、古典的な歌舞伎は、今回初めて見ます。昼のAプログラムを見ました。太閤三番叟(たいこうさんばそう)口上(こうじょう)連獅子(れんじし)吉野山(よしのやま)と言う演目です。 太閤三番叟は、「三番叟」を、太閤秀吉が、大阪城の落成を祝って、三番叟の踊りを見せるバージョンにしていて、新歌舞伎座が大阪に開場されたので、ご当地もののご祝儀舞踊です。側室の松の丸と北の政所と太閤秀吉が踊ります。側室の松の丸はあでやかな感じ、北の政所は落ち着きがあり、その後秀吉が、三番叟を踊ります。そこに、柴田勝家の残党が乱入し、鈴を振りながら、踊りながら制圧するという、カッコイイ秀吉でした。夜のBブログラムでは、淀の方、松の丸、そして北の政所がAプログラムの秀吉の所を舞うようです。口上は、市川右近を始めとする、二十一世紀歌舞伎組の俳優達が裃姿で舞台に居並んで、お祝いの口上を申し上げました。難波の新歌舞伎座での思い出を語りながら、口上してくれました。私は見た事がなかったのですが、その頃からのお客様とは、共感する物が広がってよかったのではと思います。口上を聞ける機会ってあんまり無いと思うので、そう言う意味でも聞けてよかったです。連獅子は、よくテレビで、長い髪の頭をぐるぐるまわす場面は見た事があったのですが、前半の、親獅子が、子獅子を千尋の谷に突き落とし、子獅子が駆け上がってきて、喜んでいる所から見れて、良かったです。とても迫力が有りました。間の狂言師達の踊りも面白かったです。ボタンは百花の王、獅子は百十の長。獅子身中の虫で、苦しんで暴れる獅子も、そのボタンの花の露、3露で治まるそうです。ボタンの中が安らぐのですね。それで、清涼山のボタンの花の中で戯れたり、踊っているのですね。義経千本桜の中の吉野山源の義経の後を追う静御前と佐藤忠信が、吉野山に分け入っていく姿を舞踊にしているそうです。吉野山の中を歩いて行くのですが、静御前は美しい着物に頭飾り。こんな姿で山は歩けないでしょうと思いますが、そこは、魅せる舞台ですものね。華やかでないと。忠信は、静御前が義経からもらって所持する初音(はつね)と言う鼓の皮に用いられた狐の子です。3階席で見て、花道がほとんど見られない席だったので、花道での演技がほとんど見れず、残念でした。一瞬乗り出して覗いた時、狐が後にのけぞっているポーズのところが見れて良かったです。横から見える座席、3階席は右側のほうが、お客さんが多く入っていたのですが、花道が見られるからかな~っと思いました。海老蔵が、京都の南座で演じていますが、そちらはどんなでしょうね~。Bプログラムは、ここは「黒塚」と言うロシアバレエの動きを取り入れたものだそうです。今回、イヤホンガイドを借りて、解説を聞きながら見ました。歌舞伎のことは全然分からないので、解説を聞きながら、場面の意味を分かりながら見れて、より、歌舞伎が楽しめました。意味を分からずお芝居や踊りだけ見ても、美しいな、とか動きが面白いとは思えたとは思うのですが、踊りの意味や話の筋を分かってれた方がずっと良いですよね。歌舞伎ど素人の私にはイヤホンガイドの案内が有って良かったと思いました。二十一世紀歌舞伎組は、市川猿之助さんが作られた歌舞伎のグループのようです。もう観れませんが、宙吊りの猿之助さん、観て見たかったです。これから、機会があれば、又歌舞伎を観てみたいです。新歌舞伎座、歌やお芝居の演目が多く、来年の8月までのプログラムに歌舞伎はありませんが、もっと歌舞伎を観せてもらえたらな~と思いました。 弘太郎・子獅子の精、春猿・松の丸、猿弥・親獅子の精、右近・佐藤忠信、実は源九郎狐 笑也・北政所、笑三郎・静御前、段次郎・関白秀吉 ?葺落(こけらおとし)を観ると寿命が延びるー(パンフレットより)そうですが、めでたく、何年か延びてると嬉しいな~
2010.09.19
閲覧総数 24
-
-

- ワンピース・ドレス
- ベルーナから、ベロア素材の紺・緑の…
- (2025-11-11 23:54:10)
-
-
-

- ★福袋特集★
- 27日12時 ニューイヤーズバッグ2026 …
- (2025-11-27 11:30:04)
-
-
-

- 楽天市場の激安で素敵なファッション…
- 仕事を頑張る息子&楽天ブラックフラ…
- (2025-11-26 16:47:41)
-







