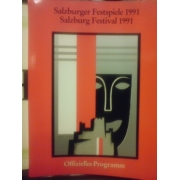PR
キーワードサーチ
フリーページ
Concert Review since1986

★2001-2010

★1996-2000

★1991-1995

★1986-1990

★2011-
PianoLesson

Playing the piano

Lesson Archives
Omikuji-Words

2005 大御心

2006-2008 大御心

2009 大御心

2010 大御心

2014 大御心
Favorite Words

YOKO ONO

Eihei-ji

座右の銘ファイル
Favorite CD(曲目別)

Brahms op.118-3

Mendelssohn 無言歌集

Schumann Arabeske
Favorite CD (ピアニスト別)

マリア・ジョアン・ピリス

内田光子

ブレンデル
CD Present MEMO
名古屋 ピアノ練習スタジオ
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
May , 2025
April , 2025
March , 2025
February , 2025
菊池寛という小説家のことをさっき調べていました。
小説家でもあり、文芸春秋社を創設した実業家でもありと、そこまでは知っていましたが、
複雑な学歴と経歴には思わず笑ってしまいました。
東京師範学校で除籍になったあと、明治大学を中退し、早稲田大学を中退し、京都大学をようやく卒業した後、社会部記者の仕事を経て小説家になったそうです。
私費で文芸春秋社を創設したことが大成功し実業家としての歩みも始まります。
直木賞、芥川賞も創立した人で、大映という映画会社の初代社長。
のちのノーベル賞作家の川端康成の金銭的なスポンサーになったり世話好きなところもあったようです。
表の経歴から見れば、バイタリティあふれる感じもしますが、
究極の遊び人のようでもありました。日本麻雀連盟の初代総裁とか、馬主として競走馬を所有していたり。
それでも、極めることは極めている感じもしました。
●
桜の季節が来ると、いつも宝塚にある阪神競馬場へお花見がてら桜花賞というレースを見に行くことでした。
関西在住のころは、ライフワークのようでもありました。
そんなことを思い出しながらJRAのホームページをみたところ、こんなものを見つけました。
「菊池寛の我が馬券哲学」
http://www.jra.go.jp/topics/column/etc/tetsu.html
20カ条以上もあります。昭和の初めに書かれたものであっても、この時代も今の時代も何にも変わらないとも思いました。
面白いものも多く、いくつか紹介します。
一、馬券は尚お禅機の如し、容易に悟りがたし、ただ大損をせざるを以て、念とすべし。
一、なるべく大なる配当を獲んとする穴買主義と、配当はともかく勝馬を当んとする本命主義と。
一、堅き本命を取り、不確かなる本命を避け、たしかなる穴を取る。これ名人の域なれども、容易に達しがたし。
一、穴場の入口の開くや否や、脇目もふらず本命へ殺到する群集あり、本命主義の邪道である。他の馬が売れないのに配当金いずれにありやと聞いて見たくなる。甲馬、乙馬に幾何の投票あるゆえ丙馬を買って、これを獲得せんとするこそ、馬券の本意ならずや。
一、しかれども、実力なき馬の穴となりしことかつてなし。
一、実力に人気相当する場合、実力よりも人気の上走る場合、実力よりも人気下走る場合、最後の場合は絶対に買うべきである。
一、その場の人気の沸騰に囚われず、頭を冷徹に保ち、ひそかに馬の実力を思うべし。その場合の人気ほど浮薄なるものなし。
一、「何々がよい」と、一人これを言えば、十人これを口にする。ほんとうは、一人の人気である。しかも、それが十となり百となっている。これが競馬場の人気である。
一、剣を取りて立ちしが如く、常に頭を自由に保ち、固定観念に囚われる事なかれ。レコードに囚われることなかれ、融通無碍しかも確固たる信念を失うことなかれ。馬券の奥堂に参ずるは、なお剣、棋の秘奥を修めんとするが如く至難である。
一、一日に、一鞍か二鞍堅い所を取り、他は休む人あり。小乗なれども、また一つの悟道たるを失わず。大損をせざる唯一の方法である。
一、損を怖れ、本命々々と買う人あり、しかし損がそれ程恐しいなら、馬券などやらざるに如かず。
一、よき鑑定の結果たる配当は、額の多少に拘らず、その得意は大なり。まぐれ当りの配当は、たとえ二百円なりとも、投機的にして、正道なる馬券ファンの手柄にすべきものにあらず。
一、人にきいて取りたる二百円は、自分の鑑定にて取りたる五十円にも劣るべし(と云うように考えて貰いたいものである。)
一、サラブレッドとは、いかなるものかも知らずに馬券をやる人あり、悲しむべし。馬の血統、記録などを、ちっとも研究せずに、馬券をやるのはばくち打ちである。
一、同期開催の各競馬の成績を丹念に調べよ。そのお蔭で大穴を一つ二つは取れるものである。
一、厩舎よりの情報は、船頭の天気予報の如し。関係せる馬について予報は詳しけれども、全体の予報について甚だ到らざるものあり。厩舎に依りて、強がりあり弱気あり、身びいきあり謙遜あり。取捨選択に、自己の鑑定を働かすにあらざれば、厩舎の情報など聞かざるに如かず。
一、自己の研究を基礎とし人の言を聞かず、独力を以て勝馬を鑑定し、迷わずこれを買い自信を以てレースを見る。追込線に入りて断然他馬を圧倒し、鼻頭を以て、一着す。人生の快味何物かこれに如かんや。しかれどもまた逆に鼻頭を以て破るるとも馬券買いとして「業在り」なり、満足その裡にあり。ただ人気に追随し、漫然本命を買うが如き、勝負に拘わらず、競走の妙味を知るものに非ず。
☆
同じように思うことずいぶんありました。
まじめに考えようと思えば1日3レースくらいがせいぜいかと思うこともありましたし、
てきとうに買ってたまたまあたったとしてもちっともうれしくなかったですし。
頭でストーリー考えてはまったときは、今でもはっきり覚えているくらい喜んだことありますし。
人気というものは何なのかと考えさせられるときもあって、相対的なものか絶対的なものかわかっていないと間違えることとか。
ブラッドスポーツの醍醐味を、よくぞこんなきれいな哲学になっているものだと感銘受けました。
親が競馬中継を家のテレビで見ていたあたりは、あしたのジョーのようなハイセイコーという馬が活躍していた時代。
その頃の小学校の音楽鑑賞で聴いたのが スッペの軽騎兵序曲
、かっこいい音楽は授業でもずいぶん盛り上がりました。
カレンダー
11月17日同仁キリス…
 ひっぷはーぷさん
ひっぷはーぷさんLIVEやります!
 SEAL OF CAINさん
SEAL OF CAINさんパニック障害と共に… kanayuineさん
Tyees_Cafe tyeesさん
ほしあかりのノクタ… ふゆのほしさん
nyantasistaのピアノ… nyantasistaさん
MY FAVORITE THINGS リタ0826さん
「のり2・クラシカ… のり2さん
☆MyuのどきどきMぶろ… myu20054000さん
コメント新着