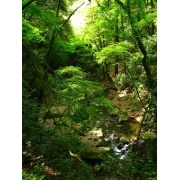PR
Freepage List
Calendar
Keyword Search
Comments
 出雲・神魂神社
出雲・神魂神社
蘇我氏の故郷は出雲??
蘇我氏の信仰(氏神)の謎。
古代大豪族たちの信仰は、今でも多くが神社という形で残っています。
物部氏系の石上神宮や河内の弓削神社、矢作神社など。
鴨氏の賀茂別雷(上賀茂)神社、賀茂御祖(下鴨)神社。
秦氏は松尾大社など京都や大阪に多くの神社を残していますし、
意外にもあの伏見稲荷大社は秦氏分家の氏神と言われています。
そして藤原氏の春日神の神社(奈良・春日大社、大阪・枚岡神社など)。
その他葛城氏や平群氏など、例をあげればきりがありません。
 天理市・石上神宮
天理市・石上神宮
蘇我氏系の神社はと言えば、実は無いわけではありません。
蘇我入鹿を祀った 入鹿神社 は別として、
奈良県橿原市に宗我坐宗我都比古神社(そがにますそがつひこ)があります。
この神社については後述します。
蘇我氏と言えば、やはり仏教のイメージがありますね。
しかし伝来当初の仏教は、宗教と言うよりは
最新の学問や文化色が強かったのではないでしょうか。
奈良の歴史ある主な寺には、今でも墓地がありません。
学問をする場所という性格が、今も色濃く残っているのだそうです。
薬師寺の僧が説教で「奈良のお寺ははかない寺です」とシャレながら
学問所としての寺の話をされていたことを思い出します。
 奈良・薬師寺
奈良・薬師寺
私が蘇我氏と出雲について考えるきっかけになったのは、
「蘇我」という文字についての気づきでした。
「われ よみがえる」という意味を持つその名は、根の国・黄泉の国を連想します。
大和の「陽」に対して出雲の「陰」
根の国、黄泉の国という出雲のイメージは
古事記などの神話で意図的に作られた可能性が高いと思います。
したがって「蘇我」と出雲を結びつけることは出来ないかも知れません。
それでも「われ よみがえる」という意味の名は、
根の国の氏族ということを連想します。

数年前から、年に200~300の神社巡りをしています。
そんなマニアックな趣味でも、ちょっとした気づきと思いつきがありました。
大阪や京都には、スサノヲ(素盞嗚尊・須佐之男命)を祀る神社が数多くあります。
ところが、奈良にはスサノヲを祀る神社がほとんど無いのです。
統計をとったわけではなく、あくまでも私のイメージです。
しかも大阪や京都に比べ、奈良の神社はそれほどこまめに廻ったわけではありません。
それでも奈良の古社には、スサノヲを御祭神とする神社が思い当たらないのです。
神仏習合により、スサノヲは牛頭天王という祇園精舎の守護神と同神とされました。
したがって八坂(弥栄)神社など、牛頭天王を祀った神社と
いわゆる出雲の須佐之男を祀った神社とは区別する必要があるのですが。
スサノヲという神が、奈良では人気がなかったというわけではないと思います。
そして思いついた「理由」は
・スサノヲを氏神とする氏族は、大和(奈良)の歴史の表舞台から消えたのではないか
↓
その氏族の没落と共に、スサノヲを祀る神社も消えた
・その氏族の「悪評判」により、スサノヲを祀る神社は新しく造られることもなかった
こうくれば、想像してしまうその氏族は蘇我氏。
そして、古事記に書かれてある出雲の須賀宮の存在。
須賀≒蘇我
古代史好きの方ならおわかりでしょうが、
地名と人名って関連していることが多いのです。
「すが」と「そが」なので、オヤジの苦しいダジャレみたいですが
ま、一応見逃せない「類似」ということで注目しました。
出雲の須賀宮は、現在も須佐之男命を祀る神社に「日本初之宮」として伝えられています。
・奈良にはスサノヲを祀る神社がない(少ない)
・須佐之男命の(最初の)宮は須賀(≒蘇我)だった
・「蘇我」という名は「根の国・黄泉の国」を連想する
いくら妄想とは言え、蘇我氏と素盞嗚と出雲を結ぶ根拠としてはちょっと苦しいデス。
今回の出雲旅行でのメインイベントは、もちろん出雲大社本殿特別拝観でした。
しかし須佐之男命を祀る神社を訪ね、
蘇我氏とのつながりを探すことも楽しみにしていました。
訪問した須佐之男命を祀る神社は
八重垣神社、熊野大社、須賀神社、日御碕神社、須佐神社。
残念ながら、それらの神社では何のヒントも得られませんでした。
駆け足で廻った旅でしたので、詳しく調べて廻ったわけでもないのですが・・・。
ところが意外な場所に、「ちょっとビックリ」なものを見つけてしまいました。
それは出雲大社の境内。
本殿の裏手にある摂社、素鵞社。
 素鵞社
素鵞社
この「素鵞社」はなんと、「そがのやしろ」と読みます。
御祭神はスサノヲノミコトです。
そして出雲大社を取り巻くように流れている川の名も素鵞川(そががわ)。
素鵞(そが)と出雲大社は関係ないと思うでしょうが、
そうでもないようなのです。
出雲大社と言えば御祭神は大国主命。
しかし、ある時代には須佐之男命が御祭神だったのです。
しかも大国主命を祀る「杵築大社」が造られたのは、7、8世紀頃という説もあります。
出雲大社と言えば、古事記や日本書紀の「国譲り神話」を思い出すので、
太古からある神社と思いがちですが。
それ以前は、杵築地区の氏族の神社であった可能性もあり
御祭神も大国主命ではなかったと言われているのです。
出雲大社の素鵞社。
苦しいオヤジのダジャレが、ちゃんとしたクリーンなダジャレになりました。
俄然はりきった私は、
こうなりゃ宗我坐宗我都比古神社にも行かなくてはいけません。
さて、何か掴んで来ることが出来るでしょうか?
つづく
-
いましろ大王の杜(今城塚古墳)その2 2011.04.14
-
いましろ大王の杜(今城塚古墳)その1 2011.04.13 コメント(4)
-
応神天皇陵調査 その3 2011.03.05 コメント(2)