2025年01月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
東京天気予報の雪ダルマさん
きょう降るか明日降るかと思いながら降雪に備えているが、東京の天気予報に雪ダルマさんマークがついた日も降らずに来ている。 雪を待っているわけではない。降らずにすめばそれに越したことはない。今朝の予報でも週末は都心でも雪になりそうだと言っていた。週明けは早、2月。そして節分である。 我が家の降雪の準備のなかに節分用の煎り大豆が入っている。これを他人が聞けば笑うかもしれない。しかし、豆まきをする、しない、にかかわらず、山の上から雪の中を買い物に出るのはいささかならずしんどい。準備怠りないというのは、実はそんな地理的な問題からである。歳をとれば、いくら足腰元気な爺ちゃんでも、やらないほうが良いことはやらない。これも元気でいる秘訣かもしれない。 かの家の垣の蝋梅見に行かん 青穹(山田維史)
Jan 30, 2025
コメント(0)
-
モナリザの新しい部屋
フランスのマクロン大統領がルーヴル美術館の改修工事を今後10年ほどをかけて行うと発表した。観客が殺到している「モナリザ」のために新たに専用の部屋を設け、一度の入場者数を制限するという。また、ユーロ圏を除く国々からの訪問者の入場料を現在の22ユーロ(約3.500円) から値上げするという。昨年は年間約870万人がルーヴル美術館を訪れているが、この改修によって1,200万人の観客を受け入れが可能になる。予算は日本円に換算して約1,100億円〜1,300億円。マクロン大統領はこのプロジェクトを「新ルネサンス」と称した。 さて、わが日本の状況は、といういと・・・ 国立東京博物館の年間入場者数は、令和5年(2023) に 過去最高の259万人。 ルーヴル美術館とはまるで比べ物にならない。2024年度の訪日客は過去最高の36,869,900人であった。これらの人々が必ずしも美術館・博物館を訪れるはずはないだろうが、それにしても日本の美術館・博物館が観光ルートから外れているか除外されているであろうことは推測できる。 ・・・何が問題なのだろう? 何か問題がありそうな気がする。・・・第一に、マクロン大統領が「ルーヴルをフランスばかりでなく世界の美術史の中心にする」と演説してそれを実行する行政措置に手をつけるようなことを、日本の首相が世界に向かって演説する「文化的な知性と政治力」は持ち合わせてはいなさそうだ。どうだろう?
Jan 29, 2025
コメント(0)
-
俳句・寒椿、大寒
寒椿 垣添いに花びら散りて寒椿 青穹(山田維史) いろどりの乏しき冬の椿かな 大寒 ぬくぬくの布団にもぐる寒い朝 寒けれど今日も始まるありがたさ
Jan 26, 2025
コメント(0)
-
すばらしい修復職人
どんな分野にも格別に優れた技術を有する職人がいる。広く世間に名が知れた人もいるが、一般にはほとんど知られず、ただその職人の仕事の結果の素晴らしさだけに惹かれている人たちに知られているだけの職人。あるいは同業者だからこその経験と見識によって知られている職人も決して多くはないかもしれない。私もそのような職人の仕事に心底からの敬意を抱いている。その人たちは「物の理」を知った上におのれの感覚を磨いているのである。物との対話によって己の人格を陶冶している、と私は思って来た。 ところで新しく物を作り上げることばかりが職人仕事ではない。使い捨てるばかりの物品や数百年前の物品を、驚嘆にあたいする技術と根気で「修復」する人たちがいる。近頃はインターネットの動画でそういう人たちの仕事をつぶさに見ることができる。美術館や博物館の展示品の裏にある修復家の仕事や、その仕事のための科学的見識や器具の発展状況である。のみならず一般の顧客に開かれた各種の修復工房の存在や、実際の作業の様子も、モニター越しではあるが見ることができる。 私は自作絵画の制作の参考にすることもあるが、物の修繕なども自分でできないかをまず最初に考え、先述した「物の理」の勉強の一助として優れた職人仕事を観察する。道具類を買い集めるのは大変だが、入手できないものを工夫するのもおもしろい。 20年前、不動産会社を通して依頼した職人の仕事がまったく気に入らず、結局一年半ほどかけて居間の床板の全取り替え、壁塗り、全部屋の壁紙張り替え、浴室のタイル貼り等々、すべて私がやった。昨年も玄関の張り出し屋根の一部の修繕工事を依頼したが、一部を除いて不完全だった。理由を問うと、一部を破壊しないと手がとどかない、と言った。それで仕事を断った。私は自ら調査して、道具を工夫し、三日ほどかけて私自身がやった。・・・見事に修繕できたのである。 ことほどさように、職人はたくさんいるが、私が尊敬する職人はどういう人を指すかお分りいただけるだろう。 いつもYouTubeの動画のURLを並べて恐縮だが、次に私が敬意をもって見ている修復家の仕事を紹介してみる。【絵画・美術品】「ヴェルサイユ宮蔵の家族の肖像画の修復」「ルーヴル美術館蔵ヤン・ファン・エイク絵画の修復」「絵画修復 - ドキュメンタリー・グランプリ動画」「フィゲイレード美術修復所の絵画洗浄」「ヴェルサイユ宮蔵振子天文時計の修復」【ポスター】「インディー・ジョーンズ・ポスターの洗浄修復」「バット・マン日本版ポスターの洗浄」【版画】「古い汚れたエッチングの修復」【コスチューム・テキスタイル】「メトロポリタン美術館のテキスタイルの保存」「メトロポリタン美術館のテキスタイル保存と電子機器」「ハンプトン・コート城蔵の360年前の貴重ドレスの保存」「V&A美術館蔵ジュリー・アンドリュース使用の舞台衣装」【古書】「400年前の本の修復」「自然史博物館図書館の古書洗浄と保護」「EICAPの貴重書籍修復プロジェクト」【家具】「V&A美術館の家具修復」「トーマス・ジョンソン・アンティーク家具修復工房」「ジョン家具修復工房」【玩具】「チプ・チャンネルの米トンカ製玩具修復」「チプ・チャンネルの61年前の錆た玩具修復」「チプ・チャンネルの1957年トンカ社の除雪車玩具修復」
Jan 25, 2025
コメント(0)
-
福島県会津檜枝岐の地震
福島県の会津檜枝岐を震源とする地震が1月23日以降頻発しているというニュース。震源は浅く、10km未満。近くに火山が存在するが、火山との関連は薄いようだ。 この地震情報を聞いて、昔住んでいた八総鉱山が檜枝岐の近くだったので、気になりつつ子供時代の当時の記憶を掘り起こしていた。 昭和28年から38年までのちょうど10年間、八総鉱山での地震の記憶が私にはまったく無いのである。私の記憶から抜け落ちているのではなく、地震が起こっていなかったと思う。八総鉱山の主産物は銅であったが、約46億年前の地球誕生とその後の地質時代を経て、八総一帯が火山地帯であったことは柱状節理が露出していることでわかる。私自身がその柱状節理をごく普通に目にしていた。そして画家になってから、その思い出を描いた作品もある。地質時代の火山脈はすでに死火山であるが、檜枝岐の震源近くの火山とはたして地質学的に関連があるのかどうか・・・。 私はさらに会津若松市に一人暮らししたが、その6年間にも、地震の記憶が無い。身寄りのない町での一人暮らしだったから、災害や地震などには鈍感ではなかったはずだが、地震を経験した憶えがまったくない。 私が大学に入った年、東京住まいするようになって3ヶ月目の昭和39年 (1964) 6月16日の昼過ぎ、私は突然巨大地震を体感した。私は昼食後、法政大学の市ヶ谷田町校舎に着いた。ほぼその途端だった。一辺が50cm以上あるコンクリートの角柱がグラグラ揺れた。「新潟地震」である。 その直後の夏休み、私は札幌の両親のもとへ帰省する途中に、新潟の伯母の家を訪ねた。じつは地震災害の状況を見るためではなく、佐渡へ渡って飛び込みで交渉して烏賊釣り漁船に乗り込むのが目的だった。しかし、伯母の家の近所で私は大きな地割れを目撃した。巨大地震に対する私の認識を変える深淵を見たのである。 子供の頃に住んでいた八総鉱山は檜枝岐からさほど離れていない。八総鉱山という名称の元である八総という昔からの集落は、八総鉱山とは別なのだが、その八総は檜枝岐へ通じる道の途中である。旧八総鉱山小学校跡地には公的機関の地震測候所が地下(?)に設営されている、と私は東日本大震災からしばらく経ったころに聞いた。そのとき私はその地震観測機器は、あるいは福島第一原子力発電所の災害とも関連があるのではないかと推測した。かの地は旧八総鉱山とはずいぶん離れていると思う人がいるかもしれないが、じつは直線距離にすると意外に近いのである。旧八総鉱山は山また山の奥地。いまでは人も車も入らない、森閑という表現がぴったりな土地である。東日本地震を思えば、地震計を設置してここほどふさわしい場所はないかもしれない。 そのおそらく無人の地震測候所が、現在も稼働しているなら、今回の会津檜枝岐を震源とする頻発地震も観測されていることだろう。檜枝岐の地震情報を聴き、何事も怒らないことを願いながら、思いがけなくも子供の頃の旧八総鉱山を思い出した。【1月26日追記】 21日の会津檜枝岐を震源とする地震は23日にもっとも頻繁に起こっていた。26日午前2時49分に起こった地震はM5.2、震源の深さ4km、震度5。(週刊地震情報より) 会津檜枝岐近辺一帯で震度5以上が観測されるのは、観測が始まった1919年以降初めてだそうだ。
Jan 24, 2025
コメント(0)
-
日本軍捕虜と英詩集
イギリスの古書商、特に稀覯本の売買を専門にしているらしいトム・アイリングという人物がいる。この人の動画が本好きの私にはなかなか面白く、ときどきYouTubeでみている。イギリスの古書事情を薄々ながら知ることができる。また、稀覯本と一口に言うが、いったいどのような点に価値を見ているのか、商人の「目」・・・その見識を窺うことができる。また、いずれ販売するのかもしれないが、トム・アイリング氏自身が稀覯本コレクターなのかもしれないというフシもある。 さて、同氏の最新の動画を見ていたら、話としては取り上げた古書のいわばセールス・ポイントをのべているのであるが、太平洋戦争中の日本がシンガポールに設営した捕虜収容所に関することだった。そして、その話は東南アジア戦線の正史記録には書かれていないようなことだった。英語で話してい、英語同時字幕を掛けてみたが、ところどころAIが聞き取れていないと思われるところもある。それで、私はこの話は記録しておこうと思い、トム・アイリング氏の話すのを、同氏に断りなく、私自身が日本語に訳してみた。以下にその翻訳を掲載するが、同氏の動画と一緒にごらんくださればと思う。この本には暗い秘密がある トム・アイリング この本には秘密がある。一見しただけではわからないが、人間の条件の最も暗い要素のいくつかを見てきた。表紙からはわからないが、中身を見て、この本がどこを通り、何を見てきたかを知れば、戦争と孤立の悲劇だけでなく、この本がどのようにして二人の命を救ったかがわかる。 先週末、私はヨーク・ブックフェアにいた。人々に本を売ろうとする仕事の真っ最中、この本が棚に置かれているのに気づいた。見た目はたいしたことがなかったので、なぜ手に取ったのかよくわからない。でも、手に取ったら、オックスフォード英語詩集の刊本だった。これはかなり標準的な詩集で、この刊本は1924年に出版されたので、101年前のものだ。それ自体は価値のある、または収集価値のある本ではない。この本の刊本は、日が良ければ5~10ポンドで売れるかもしれない。しかし、この本を持っていた人が数百ポンドで売っていたので、興味をそそられた。もう少し何かあるかもしれないと思ったのである。 外見はあまり良くない。明らかに何度も何度も使われてきた。本の上部からは紙のリボンが突き出ている。表紙はかなりボロボロに見え、実際、歴史上のある時点で誰かが本の表紙を交換しなければならなかったほどボロボロなのだ。収集価値のある、あるいはあえて言えば売れる本を探す上ではあまり有望なスタートではない。中を見ると、見返しに識語がいくつかある。前面には鉛筆で大文字で書かれた「C.W.DAWSON K37」とある。反対側の前面の遊び紙にはさらに2つの識語「CW DWSON」があり、その名前と「Changi Prison 1942」と書かれている。現時点での私の考えでは、これは正式な明示のようで、右側の手書き文字は、1942年にチャン刑務所でこの本を実際に所有していた人物のしるしのように見える。 1942年、チャンギはシンガポール東部のシンガポール・モンテ地域のひとつで、今では最初の空港があることで知られているかもしれない。1930年代のイギリス占領時代には刑務所が建設され、第二次世界大戦中にイギリスが日本に降伏した1942年、その刑務所は日本軍の捕虜収容所になった。 本の表紙を見ると、これは確かに1924年のオックスフォード英語詩集の刊本であることがわかるが、ここには日本語で書かれた語句がある。これを日本の本に詳しく、言語知識のある友人に見せたところ、この語句は、この本がすでに官憲の検閲済みであることを示していると教えてくれた。そしてそのすぐ下に、本の所有者である C.W. ドーソンが書面でこれを確認し、日本軍のこの印章のおかげでチャンギ刑務所に本を保管することができ、彼はそれに CW D と署名したと述べている。これは非常に興味深いことである。なぜなら、本は捕虜に提供されるものの、実際に捕虜に渡される前に検閲官の承認を受けなければならなかったことを示しているからである。1942 年から 1945 年にかけて、チャンギ刑務所と捕虜が収容されていたその周辺では反乱があったが、少なくともこの英語の詩集は軽い内容で、深刻ではなく、反乱が長引く可能性は低いとみなされていた。 しかし、私にとってこの本の魅力的な点は、その存在と存続だけでなく、本に目を通し、これから皆さんと一緒にやろうとしているように、ページをめくるだけで、その収容所でどのように使われていたかを正確に知ることができることである。この捕虜がどんな詩を読んでいたかを正確に知ることができる。彼らが捕虜についてどう思っていたかを私たちは知る。そして、彼らがどのように秘密裏に捕虜生活を記録していたかが分かるのである。 本全体を通して鉛筆で注釈が付けられており、その一部はまさに詩集に期待されるような注釈である。ここでは文学的な参照があり、ページをまたいで本の中の別の詩を相互参照している。しかし、本の他の部分には、詩について語っているように見える注釈はあるが、実際には捕虜収容所での生活を記録している。ウィリアム・デュバーズのキリスト生誕に関する記事の下には、2ページにわたる注釈があり、そこには「シムロード収容所、シンガポール 1944年クリスマス、 雨が降り嵐の夜の後の晴れた朝 、収容小屋53の外の夜明けの朝食」と書かれている。ジョン・ミルトンの作品を含むページは特によく読み込まれており、「サムソンの闘士」の箇所に行くと、少なくともこの箇所の横にはもっと識語があり、ハイライトされていることが分かる。そして、ミルトンの詩は、翼のあるエクスペディション・スウィフトが稲妻の視線で邪悪な者たちに使命を果たすように読み上げられる。彼らは驚いて防御を失い、気を散らされている。そして驚嘆し、その隣の余白には、ミルトンの韻律や韻律の使用に関するコメントはなく、「連合軍の爆撃機を初めて見、救援を期待する」と書かれている。44年11月5日。私たちの捕虜がミルトンのこれらの詩をどれほど頻繁に読んで、そして、翼のある探索隊が来ることを望み、そして、空を飛ぶ飛行機を見ると、370年前に書かれたミルトンの詩を読み返して、その希望は近いかもしれないと記録した。 1944年の聖ジョージの日に、彼らはキーツの「明るい星」を読み、その詩の下に「この聖ジョージの日の体重は100ポンド(約45kg)です」と書いた。チャンギ、そして、ちょうど1年後、さらに1年後、1945年の聖ジョージの日に、シムロードキャンプ(収容所)。1942年の日付の最初の食料包みは、今では米も野菜も残りはわずか。1945年までに、彼らはチャンギから、より広いスペースのシムロードキャンプに移った。チャンギ刑務所は、もともと600人から800人の居住者を念頭に置いて建てられたもので、この収容所の開始時にさえ、そこには3,000人の囚人がいたが、1945年4月に送られてから3年後にようやく小包が彼らに届いたのは興味深いことだが、日本の兵士はまばらで、戦争はまだ 7 か月残っていた。これらの識語から、この戦争の本は軽く使われた本ではなく、頻繁に参照されていたことがわかる。この期間、つまり少なくとも 3 年間は彼らが持っていた唯一の本だったと考えられる。 本の最後、ページが少し薄くなっているところに戻ると、実際の見返しの紙に番号のリストがある。これは 155 の番号のリストで、それぞれの番号が本の中の詩に対応している。したがって、リストの一番上にある 9 番は、本の中の 9 番目の印刷詩に対応する。本の始めに戻ると、9 番目の詩はジョン・バーバーの自由詩であることがわかる。このリストから少なくとも私が言えるのは、詩の素晴らしい点の 一つは、読んだものに印を付けて戻って読み返すことができることである。そして、それらの読み返しで、詩について、あるいは自分自身について何か新しいことを発見することができる。そして、私にとって、そして少なくとも私たちにとって、最も想像を絶するものでそれができるということは、命を救うことになるかもしれない。 最後にもう 1 つ、皆さんと共有したい識語がある。これは、この囚人がチャンギから釈放された後に書かれたもので、本の冒頭の詩の最後の白紙部分に書かれていて、今度は刑務所での収容所の鉛筆ではなく、W・ドーソンのごく短い識辞の中にこう書かれている。 「この本は、私とジルが1942年から1945年にかけてシンガポールで日本軍に抑留されたときに、生き延びるのに大いに役立ちました」 C.W.ドーソンはクリストファー・ウィリアム・ドーソンで、イギリス人。戦争当時はシンガポールで働いていた公務員で、妻のジルと一緒にそこに住んでいた。彼らは1924年12月に結婚した。この本が最初に出版されたその日に、彼らがシンガポールに持ってきた結婚祝いだったのではないかと私は思っている。彼らは二人ともチャンギに収容され、後に、私が述べたように、シムロード収容所に収容されたが、幸いにも二人とも投獄を生き延び、戦後を長生きした。クリストファーは 1983 年に亡くなり、妻のジルはそのちょうど1 年後の 1984 年に亡くなった。しかし、クリストファー自身がメモに書いているように、この本がなかったら、もっと早く亡くなっていたかもしれない。トム・アイリング「この本には暗い秘密がある」
Jan 22, 2025
コメント(0)
-
二つの金属考古学の話題
私の亡父が鉱山技術者だったので、子供の頃の私の机の抽斗には鉱石や岩石の小さな欠けらがいくつも入っていた。川原などから拾ってきた摩滅した石を父に見せると、父は舌でチョンと湿らせて、「これは花崗岩だよ」とか「片麻岩だよ」などと教えてくれた。私はそれがおもしろくて、いろいろな石を拾ってきては父に見せたものだ。あるいは鉱山採掘の主目的である鉱石の生成過程、・・・すなわち地球誕生から数十億年の気が遠くなるような年月を経て、マグマの上昇の繰り返しによって、やがて我ら人類が有用とする鉱物を形成するわけだが、・・・鉱山学的には、主目的の鉱物にはマグマと共に上昇してきた「随伴鉱物」が存在するため、鉱山採掘以前の問題として重要となる。一例が、金の場合は柘榴石が随伴鉱物である。そんなことを教えてくれたのも父だった。 後年、私は「湯浅泰雄全集」を白亜書房から刊行した。企画から編集・造本まで、要するに全集本を刊行する作業を、そばに白亜書房社員のコンピューター・オペレイターを一人置いただけで、全部たった一人でこなした。御茶ノ水の湯島聖堂の近くに在った白亜書房は、その数年前に経営者が変わる以前は社名に表されているように鉱山学の書籍を出版していた。巻数ものの大部の書籍は、ある一人の学者が日本全国の鉱山を実際に踏破調査したもので、おそらく後にも先にも類書が無い知る人ぞ知る優れた専門書籍だった。私は子供の頃からさほど意識するでもなく白亜書房の社名に親しんでいた。大学生になり学校に通う電車の中から、神田川河岸の石垣の上の小さな木造社屋に掲げられた白亜書房の社名看板を、なんとなく懐かしく見ていたのだった。まさかその出版社で私が上述の日本学・東洋思想史・宗教学・心理学・身体論・ニューサイエンスの湯浅泰雄博士の広範な分野にわたるすべての論文を、湯浅博士の知己と認可を得て刊行をすることになるとは思ってもいなかった。しかし刊行が決まって同社を訪れて驚いたのは、白亜書房の名を子供の私に知らしめた鉱山学書の在庫分は、会社を引き継いだ経営者がすべて廃棄したと聞いたことだ。「湯浅泰雄全集」を購入してもらうために私自身が各大学の図書館関係者を訪ね歩いていたとき、或る大学でその鉱山学書の名が出た。私は「やっぱり!」と名にし負う書物を思いながら、在庫は廃棄されたことは黙っていたが、内心で冷や汗をかいたのだった。 さて、私事にわたる前置きばかり長くなった。といっても表題の「二つの金属考古学の話題」は、ごく短い紹介だけである。金属とか鉱石という文字を見るとつい読んでしまう私が関心をもった話題である。【古代火入れ法による辰砂採掘】 本日1月20日の朝日新聞朝刊が〔世界基準の採掘法 弥生時代にも?〕という見出しを掲げて、〈朱の原料となる鉱物「辰砂(しんしゃ)」の採掘跡、若杉山辰砂採掘遺跡(国史跡、徳島県阿南市)で、弥生時代後期(1~3世紀)に火を利用して採掘したとみられる国内最古の痕跡が見つかった。市が19日発表した。〉と報じた。(吉田博行記者) 記事はつづけて、〈火入れ法〉は硬い岩盤の表面をまきなどを燃し、もろくしてから採掘する技術で、古代ローマや中国・漢にあった方法、と解説。国内ではこれまで江戸時代初期の山形県の延沢銀山遺跡が最古とされていた。〈火入れ法〉が若杉山辰砂採掘遺跡で使われていたとすれば1400年以上さかのぼる。 吉田博行記者は記事の結びで『魏志倭人伝』の記述を引きながら「朱」と「丹(に、たん)」とを同一の物質として書いていられる。必ずしも誤解とは言えないのだが、しかし古代絵画彩色材料学の見地からはもう少し細かく朱(赤)と丹(橙)とに分類されている。 高松塚古墳壁画の研究では、使用されている色料は、東壁北側女子像と東壁南側男子像とにすべて表れているとされているが、女性の衣服の赤は朱である。また朱の濃淡で表現している部分もある。 しかしながら消失した法隆寺金堂壁画の阿弥陀如来像の赤色系色料は、丹(に;橙)の上に紅殻(べんがら)を重ねていたことが分かっている。同じく薬師浄土図の薬師如来の衣には丹と密陀僧(黄)とを混合して用いている。これらの色料はいずれも高松塚古墳壁画には用いられていない。(文化庁監修、渡邊明義『日本の美術 10』参照) 古代絵画における「朱」と「丹(に、たん)」の分類は辰砂の構成物質の違いで、朱は硫黄と硫化水銀の化合物であるが、丹は鉛はの酸化物である。【ツタンカーメンの神の短剣の鉄】 エジプト・グラン・ミュージアムが完工し、膨大な古代遺物が運び込まれた。その中に5千点以上になるツタンカーメンの遺物がある。未盗掘墳墓から英考古学者ハワード・カーターによって1922年11月に発掘された。その後、100年の間、確実な精度が期待できる検査技術が発明発展するまで手を触れることなく、博物館の倉庫に眠っていた遺物がある。それらがいま、世界的な専門研究者の調査になり、実体が明らかになりつつある。 金属考古学の見地から最も重要だったのは、ツタンカーメン王の遺体(ミイラ)の胸の上に置かれていた短剣である。「神の短剣」は美しい柄(つか)に鉄の刃が付いている。しかしながらその時代、鉄はエジプトで発見されていなかった。どこか他国から入って来たのか? そうだとしたなら、その産地はどこか? ・・・これがこの短剣に関する問題であり、また引いては古代エジプトの地政学上の問題であった。 100年間待った。そして、時が来た。検体(この場合は短剣)を破壊せずに、X線照射によって「鉄」の組成分析ができるようになったのである。その成分によって鉄の産地を知ることができる。世界各地に鉄の産地があるが、それぞれ成分に違いがあるからである。 分析の結果、ツタンカーメンの短剣の鉄にはニッケルが突出して含まれていた。・・・世界のどこにもそのような鉄は産出していなかった。 それは何万年もかけて地球にとどいた「隕石」であることが判明したのである。エジプトの砂漠から集められたそれは、まさに宇宙からツタンカーメン少年王に贈られた「神の短剣」だった。 このすばらしい考古学・科学物語は、ナショナル・ジオグラフィックがドキュメンタリー動画をYouTubeで期間限定で公開している。日本語のナレーション付きである。ここには金属に関してもうひとつの研究成果が述べられている。装飾に用いられバラバラに剥落した金の細片を、ジグソーパズルを繋ぎ合わせるように原型に復元する技術が、いま、一人の研究者によって実現したのである。 このドキュメンタリー動画は、古代エジプト皮細工技術や匣(はこ)や弓に描かれた絵についての新たに判明した意味等々、現代の考古学の進歩を一般にわかりやすく、しかも余計な画像で感傷をあおらないすぐれた作品である。また、研究分野によっては時至るまで「待つ」ということの重要さを私に教えた。以下にYouTubeのURLを掲載しておく。ナショナル・ジオグラフィック「ツタンカーメン 〜財宝に隠された真の素顔」
Jan 20, 2025
コメント(0)
-
二人の映画人を追悼
映画監督デイヴィド・リンチ氏が1月15日に亡くなられたという。享年78。 「エレファント・マン」(1980年:日本公開 '81年)、「ヂューン 砂の惑星」(1984)、「ブルー・ベルベット」(1986)、「ワイルド・アット・ハート」(1990)、「マルホランド・ドライヴ」(2001)等、いずれも私に強烈な印象を残す作品を発表した。デイヴィド・リンチ監督を追悼します。 映画キャメラマン上田正治氏が1月16日に亡くなられた。享年87。 黒澤明監督作品の「影武者」(1980)、「乱」(1985年)、「夢」(1990)、「八月の狂詩曲」(1991)、「まあだだよ」(1993)、黒澤明脚本・小泉堯史監督の「雨あがる」(2000),、同じく小泉堯史監督「阿弥陀堂だより」(2002)、「蜩の記」(2014)等々の撮影監督として多くの栄誉を受けられた。 私はまた、上田正治氏が監督助手を務めらえた東宝怪獣映画、本多猪四郎監督「モスラ」(1961)をここに記そう。会津若松市で、中学1年生の次弟と彼の同級生につきそって観に行ったことを思い出す。映画撮影監督上田正治氏を追悼します。
Jan 18, 2025
コメント(0)
-
15日粥(小豆粥の日)
1月15日は、古来、「十五日粥」あるいは「赤小豆粥(あずきがゆ)」と称して、小豆を入れて炊いた粥を食する年中行事の伝統があった。現在でも実際におこなわれている地域あるいは家庭があるかもしれない。この粥を三日後まで蓄えておいて食すると疫病に罹患しないといわれた。おそらく正月明けの餅でもたれた腹休めと滋養補給の面からの習わしだったと思われる。現代の栄養学では、赤小豆(あずき)には食物繊維やポリフェノール、鉄分、ヴィタミンB1、カリウム、サポニンが含まれているため、便秘や高血圧の解消、貧血やコレステロールの予防に効果が期待できるようだ。 さて、我が家ではこの昔ながらの年中行事を継承してきた。特に私は、信仰心はまったくないけれど、季節の移り変わりを感覚しようという気持ちが強く、またダラダラとした日常にちょっとした変化をつけようと思う気持ちもあり、日本古来の伝統行事を心にさしさわりがないと考えることだけ家庭内でそっと営んで来た。いや、そんな大それた考えよりも、ただおもしろがっていると言うのが本当だ。 というわけで、今日は小豆粥のかわりに善哉汁粉をつくった。朝のうちに小豆を洗って準備をし、差し水をしながらとろとろと煮て、ちょうど昼食に間に合った。 変われかし祈りつづけて小豆粥 青穹(山田維史) 短かくも命思えばあずき粥 短かくも命うるわし小豆粥 少なきは俺がいのちと小豆粥 先見えぬ八十路越さんと小豆粥 彼方行く列車のひびき冬木立
Jan 15, 2025
コメント(0)
-
19時1分、わずかな揺れを感じた
19時1分、わずかな揺れを感じた。地震か? 先日も就寝中に背中にごく微弱な揺れを感じた。その後、しばらく経って青森県を震源とする地震があったと報じられたが、私が感じた微弱な揺れはこの地震と関係があったのかどうか、東京の状況に関する報道は一切無かった。・・・報道するまでもない微弱地震が実は意外に頻繁に起こっているのか否か。ちょっと私に疑念がわいているこの頃である。【追記】 ただいま21時30分を過ぎたところだ。21時19分に高知県・宮崎県にマグニチュード6.9の地震があった。津波注意報が出た。 ・・・私が2時間半前に体に感じた微弱な揺れは、この高知県・宮崎県に発生した地震とはまったく無関係だろうか? 過日、青森県の地震のときも、私は発表のずっと前にあるかなしかの極微弱な揺れを感じたのだけれど・・・
Jan 13, 2025
コメント(0)
-
列車:ヘミングウェイそして私自身
ふたたびヘミングェイの『汽車旅行』について。 カナダ旅行に出発した父子は列車に乗り込む。通路を挟んで親子の隣に四人の男たちが座っている。窓際の二人の男はまるで凸凹コンビのように背丈が違う。そしてその男の右手には手錠がはめられ、隣の男の左手とつながっている。通路側に座った男二人はデテクティヴ(刑事)と、サージェント(巡査部長)と呼ばれている男である。・・・窓際の男と背の低い男とに手錠がはめられていることを不審に思った父親が尋ねる。「何をしたんですか?」「殺し」、と刑事が言う「イタリア人を殺したんですよ」。「イタリア人なんか殺しちゃいねぇ」と手錠の男は言い、父子にちょっと笑みを浮かべながらウインク(目配せ)する。そうして2度ほどウィンクを送られた父親は、「別の車両に移ろう」と息子を促して席を立つ。 殺人の容疑者である男の笑みを浮かべたウインクについて、ヘミングウェイはまったく何も説明していない。父親の感想も、一切書いていない。殺人容疑者二人と刑事ら二人、そして父子、この四人が列車内で遭遇し短い会話をした、その事実だけを書いている。・・・ヘミングウェイの小説はほとんどこうした書き方である。事実を積み重ねてゆくだけ。私が面白く思うのはそこだ。読者の想像を掻き立てる、まさに「小説」がある、と。読者自身の人生経験によって、・・・つまり年齢を重ねると読み方も変わってくるのである。 ・・・この短いエピソード(挿話)を読みながら、実は私自身が高校三年生の夏休み、帰省する列車の中で、殺人事件の刑期を終わって出所したばかりの青年と向かい合って同席したことを思い出したのである。 そのことについてはこのブログの左フリー・ページに英語で『That Man』と題して掲載してある。当時の日記をそのまま写したもので、日本語の文章を英訳して掲載したのは、フィクションではないからだった。会話もすべて事実、ありのままである。 ・・・あの青年が現在存命ならば86,7歳。90歳にはなっていないだろう。獄中で読んだのだろうか、永井荷風と椎名麟三の小説に感銘を受けたと言っていた・・・そして、文学の世界から現実社会に戻ってきた、と。
Jan 12, 2025
コメント(0)
-
鉢植え植物に雪囲い
東京の明日に雪予報が出ている。鉢植えの植物に雪囲いをした。 寒灯に過ぎ行く薄き影ふたつ 青穹(山田維史) 寒灯や遠くに灯油売りの声
Jan 11, 2025
コメント(0)
-
ああ、新兵器の実験場
昨日ヘミングウェイの短編小説『A Train Trip』の煙突にバケツをかぶせる記述を思い出したと書いた。ついでなので現代の戦争状況に重なるヘミングウェイの見解が、映画『誰が為に鐘は鳴る(For Whom The Bell Tolls)』にあるので書いておく。ヘミングウェイの同名小説の映画化である『誰が為に鐘は鳴る』は、1943年のアメリカ作品。第二次世界大戦中に公開された映画である。監督はサム・ウッド、主演ゲイリー・クーパー、イングリッド・バーグマン。 物語はスペイン内戦(1936~1939)。共産主義ソビエト連邦の支援を受けた第2スペイン共和国政府の人民軍とナチス・ドイツとファシスト・イタリアの支援を受けたフランシス・フランコ率いる国民党派との内戦。物語における史実は、スペイン共和主義の破滅的な内部分裂の前段階を描いている。付言すれば、この後、世界は第二次世界大戦へと突き進むが、スペイン内戦時にはアメリカ合衆国は参戦していない。 ・・・アメリカ本国で大学教授だったロベルトは共和国側の義勇軍に参加し、将軍の命を受けてフランコ軍の高架橋を爆破にのりだす。その困難を極めた作戦のさなかに、ロベルトは次のように言う。 「さまざまな勢力がいる。ドイツにイタリア、それにロシアもいる。スペイン人は間に挟まれている。ナチもファシストも実際は敵対関係にある。この国は新兵器の実験場で、その兵器を使い民主主義を倒そうとしている。こちらの態勢が整う前にだ」(邦訳字幕より) 私が注目したのはロベルトによって解き明かされるこの戦争の裏にある本当の姿、現代戦争の「秘密」である。90年前の戦争の実態と現代2025年の戦争の実態・・・大国主義(覇権主義国家)の裏にある真相は、まったく変わっていない、ということである。ウクライナが新兵器の実験場として戦争を仕掛けられたということ。威力が試された新兵器を買い求める「顧客」を獲得するために仕掛けられた戦争。戦争商人となった権力者(もちろんその人間に支配された国家)にとっては、人間の生命など屁でもない。その大量死は兵器の威力を証明するにすぎない。 ・・・ああ、誰がために鐘は鳴る、である。ヘミングウェイは戦争の裏にある本当の姿を鋭く見抜いていた。
Jan 10, 2025
コメント(0)
-
ヘミングウェイ短編小説の細部
昨夜、雪にならなければ良いがと思いながら、ふと、幼少年の頃の薪ストーブを思い出した。私のはっきりした記憶がはじまる昭和20年代半ばから30年代末頃までのことだ。どこの家にも煙突があり、冬空に白い煙が流れていた。雪が降りしきる寒い外から帰り、その煙を見ると、足早になったものだ。 そんなことを思い出しながら、私は同時に、ヘミングウェイの生前には未発表だった短編小説『A Train Trip(汽車旅行)』のおもしろい記述を思い出した。 湖を望む林のなかの小さな家に二人きりで暮らす父と息子ジミー。親子はこれからカナダへ旅に出るところである。父親は息子に家の中を良く見回して記憶するように、と言う。それから、ジミーに外に出て梯子で屋根に登り煙突にバケツをかぶせるように、と。 私がおもしろいと思ったのは、ここである。煙突にバケツをかぶせるようにと言ったのは、つまり、留守中に火の気のない煙突に雨が入るのをふせぐため。そしてリスや北米固有種のシマリスが入り込むのをふせぐためである。この煙突も薪ストーブ用である。ジミーが屋根の上からWoodshed(薪小屋)を見る、と書かれている。・・・私は他の小説家や著述家でこんな記述を読んだ記憶がない。私が幼少期に過ごした雪国で、煙突にバケツをかぶせているのを見たことがない。たしか円錐形の覆いがついてた記憶もあるが・・・。しかしヘミングウェイのこのバケツは、言われて初めて「なるほど」と思う。 ヘミングウェイがおもしろいのは、物語もさることながら、こういう細部に出逢うことだ。ときにクドイと思う繰り返しに私は読みながら辟易することもあるけれども、英語表現の特徴かもしれない(私は門外漢なのでまったくわからないが、ヘミングウェイの英語表現はいささか特異じゃないかしら?)。・・・まあ、それはさておき、こういう日常的な細部をさりげなく書いている小説・・・そしてその細部が人物の生活環境のみならず性格や人物関係を表現しきっている小説に、私は小説を読むおもしろさを感じている。80歳にもなればエキセントリックな物語などに興味がないのである。
Jan 9, 2025
コメント(0)
-
東京も雪になるか
日本海側の地方に大雪警報が出ている。青森県では経験したことがないような積雪量だとか。 さて、東京も12日(日曜日)以降の数日に降雪予報がある。備えは大丈夫か?と、自分に問うている。我が家のこれまでの最大の被害は、駐車場の上を横切っていた電線に積もった大きな雪氷が落下して、車を直撃。廃車にしなければならないほど破壊した。人間が乗っていなかったことを幸いとした。 幼年時代、少年時代と、雪国で育ったので東京の雪くらいでオタオタはしないが、年をとるとそのわずかな雪を掻くのが億劫になる。つい数年前までは高齢者の家の前の雪掻きをしてあげていたが、もうとてもそれをできそうにない。 雪国の会津若松で一人暮らしをしていたときに書いた詩の一編を次に掲げてみよう。62年前、17歳の詩である。 漂白 山田維史 淋しい心で 魂魄となり 午前零時の 窓を出れば そとは雪颪 街は瞑目し 死相表われ 大地氷結し 遠々に哭く 仏神よ聞け 地球が哭いているのだぞ 環境の一切が凛烈として せつない感動をよぶから 俺は泣きながら焦がれて 死んだ街から街を漂おう 帰る当なく滄浪とすれば 宇宙の瞳の慈愛も凍てる 仏神よ地球を去るがいい 淋しい心で 魂魄となり ほとほとと ほとほとと 尸柩を尋ね 大路を駆け 小路に蹲る 闇だまりに 雪霏霏たり ついに悔恨の裸体を焚く (1963年作)
Jan 8, 2025
コメント(0)
-
正月中の「初」雨
「初雪」という成句はあるが、まだ明けぬ正月に降る雨を表す成句はない。夕方から雨が降り出した。その音が今は闇のなかに聞こえている。雪にならなければ良いが・・・ 城ヶ島歌にそぼ降る寒椿 青穹(山田維史) *】北原白秋作詞、簗田貞作曲/山田耕筰作曲「城ヶ島の雨」 寒聲や隣近所を気にしつつ 小寒の名を違へたき寒さかな
Jan 6, 2025
コメント(0)
-

描き初めは自画像
山田維史「2025年1月4日マフラーの自画像」紙に鉛筆Tadami Yamada "Self-portrait with maffler"
Jan 4, 2025
コメント(0)
-
仕事始め
三が日が過ぎた。早い早い、今年も残り362日だ。ハハハハ。 三が日オリオン天に輝けり 青穹(山田維史) 疾く来たり疾く去りゆくや去年今年
Jan 4, 2025
コメント(0)
-
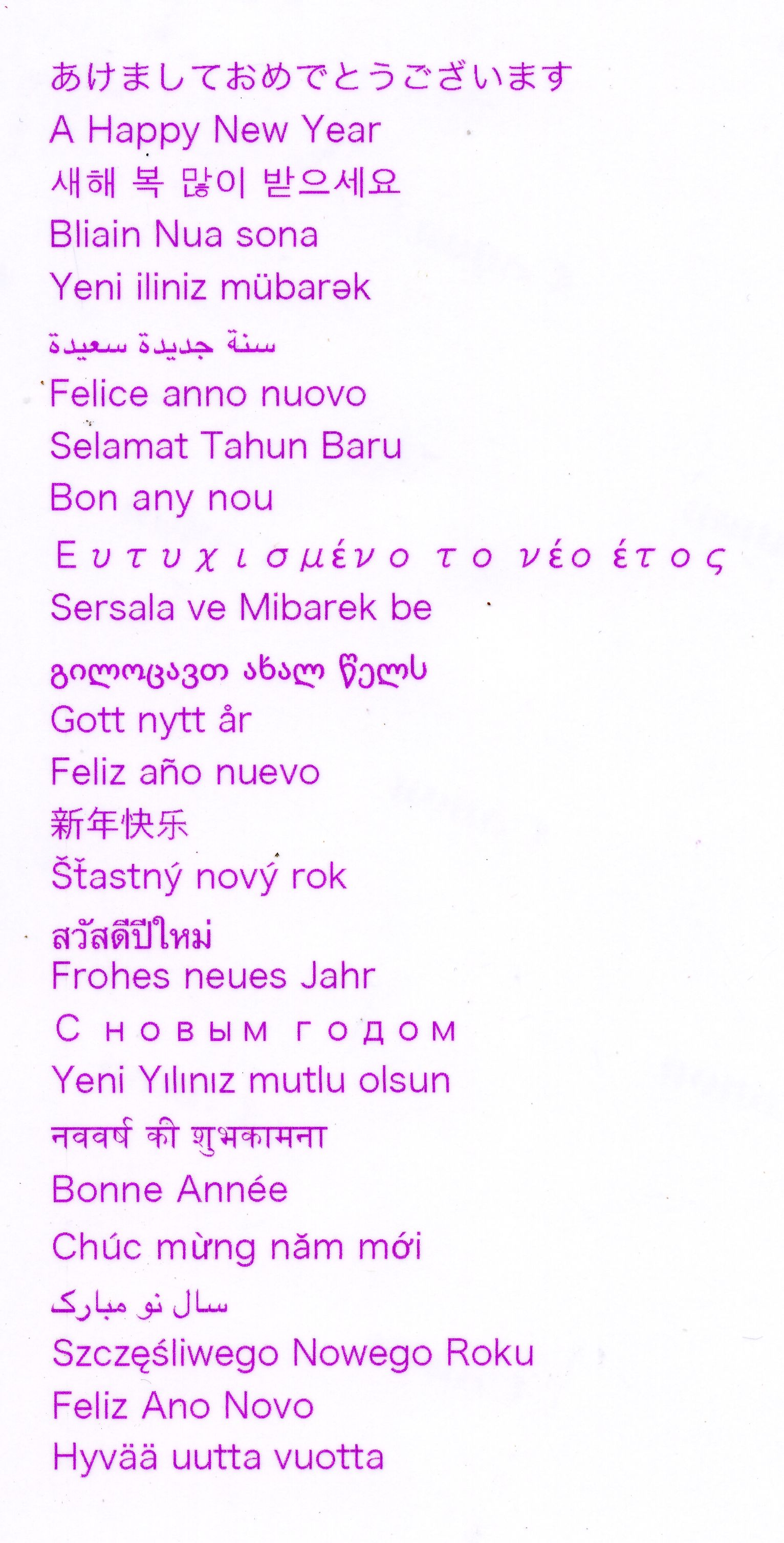
2025年明けましておめでとうございます
山田維史「朝のテラスに」1992 キャンヴァスに油彩山田維史「お出迎え」1985 キャンヴァスに油彩
Jan 1, 2025
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(浅暮三文)・・その百六十
- (2025-11-19 20:55:43)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
-
-

- マンガ・イラストかきさん
- お絵描き成長記録 DAY2
- (2025-11-21 09:24:57)
-







