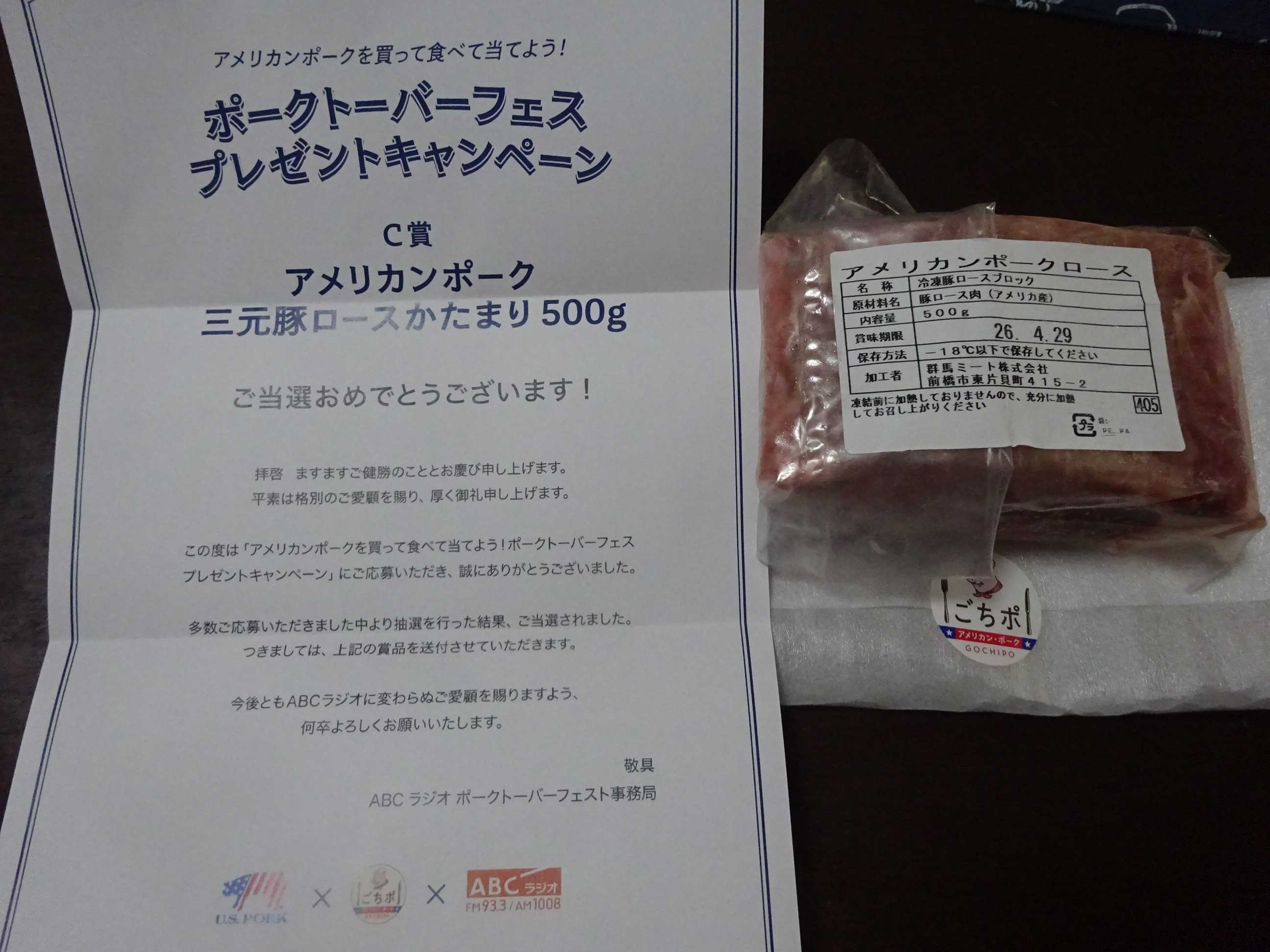-
1

【北野異人館7】
こんばんは北野異人館街には南北の道路が東から"不動坂""北野坂""ハンター坂""トアロード"とあり、東西の道路が北から"北野通り""異人館通り""パールストリート""山手幹線"とあります。今日は北野通りの南の通りで山本通り、通称“異人館通り”の町並みをご紹介します。この通りにはたくさんの飲食店が並び、いろんな国の料理が楽しめます。 ざっと見回しただけでも、中華料理、インド料理、イタリア料理、フランス料理、パナマ料理など、様々です。そして、北野の中心地付近にある料理店より価格的にも比較的リーズナブルなお店が多いのもうれしいですね。もちろん、この通りにも洋館があります。【シュウエケ邸】明治29年(1896年)、建築家A.N.ハンセルの自邸として建設されたゴシックを基調するコロニアルスタイルの西洋館。広い庭園は芝生に石灯籠を配置した和洋折衷で、他にも屋根に鯱がのるといった和の要素が随所に見られます。 現在もシュウエケ家の自邸として使用されていますが庭園と1階の一部が一般に公開されており、館内は年代物のフランス製家具や大きなシャンデリア、暖炉等クラシカルなインテリアで統一されています。そのすぐ東隣にはこのような洋館があります。そしてそんな通りを彩るのが沢山のショップです。雑貨や洋服、アンティーク、宝石屋さん、そして珍しい昆虫の標本が売っている店もあったりとかなりバラエティーに富んでます。歩き疲れたらカフェテラスでお茶でも飲みながら、のんびり街の景色をながめるのもいいですよ。 ずらりと並ぶ街灯が異人館街の雰囲気を醸し出しています。そして、すべての街灯がこのようにかわいい花で、歩く人を笑顔にします。神戸の異人館街に行かれたら、異人館通りまで足を伸ばしてくださいね。
2013/01/24
閲覧総数 268
-
2

禅の言葉(以心伝心)
『以心伝心(いしんでんしん)』 ~心から心に伝わる~ 『以心伝心』ももとは仏教用語です。特に禅宗で、言葉や文字では表せない奥深い仏教の真髄を、師から弟子の心へ伝えることをいったものです。『景徳伝灯録』に「仏の滅する後、法を迦葉に対し、心を以て心に伝う」とあり、ここから生まれたものです。言葉を使わなくても、心と心で意思の疎通が出来る事。また、そう試みる事。ということが現在の意味ですが、自分と相手との信頼関係が十分でない場合、多くは失敗します。 毎日一緒に生活している夫婦や親子の場合はどうでしょう。仲の良い家族では、何かをしてあげるときもしてもらうときも、互いに黙ってやっていて、感謝する気持ちを持っているであろうことも互いに疑う余地がありません。「ひとこと」が無いことにより、怒る人もいません。誰も、何も言わなくても言われなくても、いつも家族は家族のことをとても大切にしているし、家族のためにやれることは黙ってやっている。「ありがとう」の口は重いけれど、言わない分放出しない分、ずっとずっと心の中に溜まっていて、いつも溢れるほどにそこにあり滲んでいる。夫婦間でも、相手がいま手に持った荷物が邪魔になっているなと感じたら、「持とうか?」などと言わないで黙って荷物を取る。相手が少し寒そうな素振りをしたら、「大丈夫?」などと言わないで、黙って上着を持ってくる。相手も特に変わった風もなく黙ってそれを受け入れるけれど、ひそかに通じ合えていることを喜び、また自分も必ず相手の役に立とうと心に決めている。これは、日本の仲の良い家族にというか、昔の日本人の家族関係には少なからずあったことだと思います。私も、相手を良く思っていることほど言わないでいて、自分の中で微笑んで終わっていることが多くあります。 でも、ほんとうにそれで良いのでしょうか。たった一言がなかったために、自分の気持ちが伝わっていると思っていたつもりが伝わっていなかったり誤解されていたり、ということはよくあることだと思います。このような一方通行的な感情やそこから起こる誤解やすれ違いが、多くの恋愛ドラマや刑事ドラマの内容を形作っています。あの時にちゃんと気持ちを伝えておけば良かったとか、一言謝って置けば良かったとか、後になって思うことがありませんか・・・・・・。 「ありがとう」や「ごめんね」の言葉を、長年連れ添ってもなれ合いにならず、いつも互いに掛け合っているご夫婦や親子関係を見ると、私は素晴らしいなぁと本当に感心します。野球の野村監督の名言の中に、『「見えない戦力」づくりのポイントは監督と選手の以心伝心とも言える信頼関係にある』という言葉があります。監督と選手の間に信頼関係があれば、何も言わなくても監督の考えていることを選手がやってくれるようになるということでしょうが、そこに相手を認める言葉やほめる言葉が加わわることで、その信頼関係はさらに強くなり、以心伝心に磨きがかかるのではないでしょうか。 よく間違えるのが「意心伝心」、現在はメールのやりとりが増えたからといっても「以心電信」と書くのは誤りですね。 大事なことはメールではなく言葉で伝えましょう。それが、何も言わなくても分かり合える『以心伝心』の関係づくりへの第一歩だと思います。
2014/05/13
閲覧総数 648
-
3

京都の歴史 八重と襄7
八重と襄 同志社墓地 ここには、襄と八重の周りに"山本家""新島家"の人々の墓碑や関わりの深い人たちの墓碑がある。 【山本覚馬の墓】【山本家の墓】新島八重の両親の山本権八と佐久そして新島八重の弟の山本三郎の墓碑。 山本三郎は京都鳥羽伏見の戦いで負傷し、その傷がもとで江戸にて没した。一番奥にあるのは、山本覚馬と小田時栄との間に生まれた山本久栄の墓です。山本久栄は新島八重、母佐久、みねと一緒に兄覚馬の家で世話になることになった。明治4年に生まれている。山本久栄は同志社女学校、神戸英和女学校(現:神戸女学院)で学んでいる。徳富蘆花の小説「黒い眼と茶色の目」に描かれた「茶色の目」事件のヒロインで、明治26年(1893)で若死にしている。徳富健次郎(蘆花)(1868-1927)と山本久栄の出会いは明治19年(1886)9月蘆花が同志社英学校3年に編入してからである。山本久栄の母時栄(1853-?)は明治19年(1886)に山本覚馬と離婚、その関係で同志社共同墓地に墓碑がない。【新島家の墓碑】新島襄の父親の新島民治と母親の新島登美(とみ)の墓碑。新島襄の両親の左手には3番目の姉の美代さんの墓がある。【徳富蘇峰の墓】覚馬の墓碑の右隣りには“徳富蘇峰”の墓がある。徳富蘇峰は、上京して東京英和学校(第一高等学校の前身)に通学するが満足せず、京都の新島襄に感化し同志社英学校に入学。 1880同志社卒業直前に退学し、熊本に戻る。1882大江義塾を開き、父が漢学を、蘇峰は英学・歴史・経済・政治学等を教えた。ジャーナリスト、思想家、歴史家、評論家として活躍。また、政治家としても活動し、近代日本に大きな影響をあたえた。徳富蘇峰は、同志社の創立者・新島襄を生涯の師と崇め、また、新島襄の良き理解者として彼を支えた一人。そんな蘇峰ですが、同志社時代、八重に対しては無礼な振る舞いをしています。封建的な風潮が残る中、襄は日本に『近代』を根づかせるためにアメリカ式の生活を実践。八重は夫を『ジョー』と呼び捨てにし、また夫より先に人力車に乗る。そんな姿に周囲は『悪妻』とののしるが八重は気にしなかった。『頭と足は西洋だが、胴体は日本、まさに鵺(ぬえ)のような女性がいる』同志社英学校の学生達の演説会に夫婦で出席した際、蘇峰は演壇より八重を強く非難。これに対し八重は全く動じなかったと伝わっている。襄の臨終の床で蘇峰に過去の非礼を詫び、八重と和解した。蘇峰は『貴女を先生の形見と思って終生お仕えさせて頂きます』と言い、八重も受け入れる。結局、蘇峰は八重が亡くなる昭和7年まで40年以上支え続けることになる。 このように、この敷地内には山本家や新島家以外の人たちも葬られている。 その中には、このような人物もいた。 1879年(明治12年)から同志社で賄方として働き始め、その後小使(用務員)となった。松本五平の仕事ぶりは真面目だったが、松本五平は英語が喋れないのに、英語だと言って、訳の分からない言葉で演説の真似事をするような変わり者だったため、生徒から「五平」と呼び捨てにされ、馬鹿にされていた。また、松本五平は小柄で身長が120cm程度しかなかったため、「エスキモー」と呼ばれて生徒にからかわれていた。しかし、誰にでも平等に接する新島襄は、松本五平に対しても「五平さん、用事をお願いします」と丁寧に用事を頼んでいた。用務員の松本五平を「さん」付けで呼ぶのは新島襄だけだった。このため、松本五平は新島襄を敬愛し、洗礼も受けた。そして、学生に呼び捨てにされると、「お前達は学が無いから呼び捨てにするんだ。新島先生を見習え」と言い返すようになっていた。松本五平は新島襄の死後も同志社に仕えたが、やがて、松本五平も病床に伏した。松本五平は自分の命が長くないことを知ると、死んでも新島襄の近くに行きたいと思うようになっていた。そこで、松本五平は人を介して、新島八重に「私が死んだら、どうぞ新島先生の墓の門の外に埋めてください。死んだ後も新島先生の門番をしとうございます」と頼んだ。すると、新島八重は「貴方が亡くなったら、門の外ではなく、内に葬りましょう」と約束した。それを聞いた松本五平は安心して死んでいった。松本五平の死後、新島八重は約束を守って、若王子山にある同志社墓地内の出入口の直ぐ側に松本五平の墓を建ててやった。新島八重が墓の敷地内に葬る約束をしたのは、松本五平だけであった。墓地入口の右側に松本五平の墓があり、松本五平は今も同志社墓地の入口で、新島襄の墓守をしている。【五平の墓】同志社墓地で、幕末から明治という時代の大きなうねりの中を生き抜いた人たちのそれぞれの生きざまに思いを馳せながら、ゆっくりした時間を過ごさせてもらった。
2013/12/25
閲覧総数 342