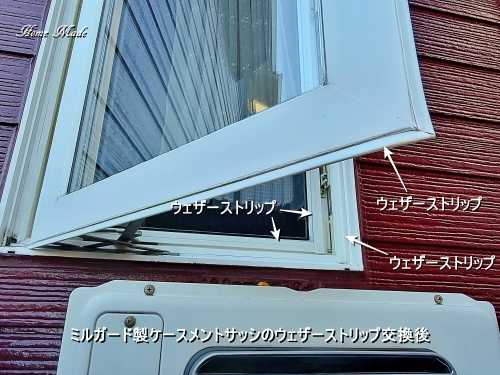-
1

茶道教室~逆勝手の稽古
1月は真台子や長板総荘を稽古しました。2月は大炉(だいろ・裏千家のみと聞いています)の時節で、逆勝手の稽古です。逆勝手の点前をすると、本勝手のときなぜそうするのか、その理屈が見えてきて、興味深いものです。たとえば、道具を拝見に出すのは座本位、返すのは亭主本位、など。本勝手での茶器の蓋を置く位置は、茶入れは茶碗の右横、甲拭きの棗は右膝先、二引きの棗は茶碗と膝の間、となりますが、逆勝手では全て茶碗と膝の間となります。亡くなったN先生が、以前、「ねえ、東風庵さん、どうして逆勝手では全部膝前になるのでしょうね」と尋ねられたので、お点前中の私は、とっさの思いつきで、「お客様から見えるようにではないでしょうか」、とお答えしたことがありました。先生は「ふーむ」と考え込んでいらして、そのままになってしまいました。今度のわたしの稽古でW先生・C先生にお聞きしてみようとは思いますが、他のお流派ではいかがですか、どのように考えたらいいのでしょう。
2006年02月07日
閲覧総数 593
-
2

向切の稽古
新年最初の教室は、いつも使う八畳で、大日本茶道学会のグループの初釜があったので、少し離れた長四畳の小間で、向切(むこうぎり)の稽古をしました。向切の点前は、炭手前で逆勝手の要素が入り、『それは左から右に持ち替えて』とか、『左手で斜めに』など、いつもの本勝手より説明が多くなりました。濃茶が始まり、道具の位置が定まると、松風の音に導かれた清寂のときが訪れます。亭主は、茶杓を取り、濃茶入れに手を伸ばしました。長四畳の部屋でしたが、亭主と客は半畳空けて三畳間のように座っています。これであと半畳進めば、妙喜庵の待庵と同じです。今でさえ、亭主の息遣いが伝わってくる近さなのに、二畳の茶室で、相対する利休と秀吉、息詰まる時間だったことは想像に難くありません。利休の庭の朝顔が見事に咲いていると聞いた秀吉が、朝駆けで利休の屋敷を訪れてみると、朝顔は花ひとつ残さず刈り取られている。驚いた秀吉は露地を駆け抜け、にじり口から茶室をのぞくと・・・、右手、黒く塗りこめられた室床(むろどこ)の真ん中に、ほの明るく朝顔が一輪。秀吉は驚き、怒り、憤り、そして哀しみ、手は震え、顔には脂汗が・・・。利休は、涼やかな顔で静かに濃茶を練る・・・。 『おのれ、利休、この秀吉を超ゆる気か・・・』そのとき、すっと影が動いて、あっ、あぶない、と思ったら。亭主が濃茶を練った茶わんを出し、正客がにじって取りに出たところでした。その後、後炭、薄茶と稽古し、小間のよさを存分に味わいました。炉縁が、床の框(かまち)とおそろいの、めずらしい椿でした。
2007年01月15日
閲覧総数 173