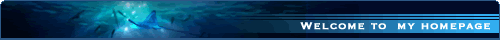全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
医療費の節約について考える6
世の中は、決算発表のシーズンですね。医療費を糧に儲かりまくっている製薬会社も決算発表を行っています。それによると、例えばゼネコン(意外に利益回復している!)と比較すると、製薬会社の大手と、ゼネコン大手では、売り上げは5分の1,利益は2倍、といったところでしょうか。要するに、製薬企業はゼネコンの10倍儲かる、という事になります。製薬会社の決算ランキングをみると、1位は武田、2位三共、以下山之内、エーザイ、藤沢、第一、大正、三菱、塩野義、田辺・・・という順番になります。しかし、これはあくまで「連結決算」すなわち、関連会社も含めた数字です。ここにマジックがあります。要するに、外資系が入ってこないのです。本当のランキングは、1位武田は変わりませんが、ファイザー、中外(ロシュ)、GSK、アストラゼネカ、万有(メルク)といった会社がベスト10に入ってくるのです。山之内と藤沢は合併しますから、要するにランキング10位の半分は外国の売り上げになるのです。経済の詳しいことは分かりませんが、なんか気になりませんか?
2004年05月21日
コメント(1)
-
医療費の節約について考える5
薬が「効く」ことについて世の中、EBMの時代です。多くの医師は、エビデンスに基づき、患者さんの治療薬を選択する時代になりつつあります。(まだ製薬会社の言いなりの人も大勢いますが)このことについてケチをつけようというのではありません。ただ、服用する側としては、よく考える必要があります。要するに、効果が高いというのは、確率の問題だという事です。すなわち、効くはずの薬でも「自分には効かない」事はいくらでもあり得るという事です。例えば、アスピリンは脳卒中や心筋梗塞の予防に効果があります(というエビデンスがあります)が、アスピリンを飲んでいるがゆえに命が助かる(飲まなかったら死んでいた)という人は200人に1人と言われています。あとの人は、飲まなくても死ななかったか、飲んでも死んでしまうか、という事になるのです。こういう確率を統計では「有意に効果がある」と呼びます。逆に、殆どの健康食品は、科学的には効果がありません。外見が全く同じにせ薬と、どちらか分からないように服用すれば(二重盲検といいます)統計的には効果がない、という事に恐らくなります。だから健康食品や民間療法はお金の無駄か?というと私は必ずしもそうではないと思います。要するに自分だけに効けばいいのですから。科学的には有効率1%のサプリメントでも、それが自分に当たれば100%の有効率なのです。これは科学ではありません。要するに満足できればいいのです。ですから、とにかくこのテの製品は、無料サンプルを試してみる、自分で実感できたものだけを購入する。ダメなら他の物にすぐに変えることが重要です。他人の評価は一切耳を貸さないことがポイントです。医者が処方する薬も同様ですが、薬によって効果の出方が違いますからよく説明を聞く(受け身ではなく質問する)事が大事です。また、教えてくれない(質問に答えない)医療機関は変えてしまうことがポイントです。なぜなら我々は、指導料を(知らないうちに)取られているのですから。
2004年05月20日
コメント(0)
-
医療の節約について考える4
昨日私は、「服薬指導」こそが薬剤師の生き残る道であり、それは「健康コンサルタント」的な、患者さん一人一人にオーダーメイドな情報を提供することで満足を与えられるレベルにまで高めていくべきだ、と書きました。しかし、薬剤師は医師が発行した処方箋の通りに調剤するのが仕事であり、自分で患者さんに合う薬を決めることができません。医師が指示した薬の飲み方の注意点をサポートするだけでは、とうてい高い料金を支払う気にはなれない、という人が多いことでしょう。それでは、どうしたら良いのでしょうか?例えば、こんな考え方はどうでしょう?患者さんは、すでに病気になっているから病院に来ているのです。その病気を治す(ための手段を考える)のは医師の仕事です。医師は、病気になっていない人を治療することはできません。ただ、併発しやすい病気というのがあります。例えば、閉経後の女性で尿もれで悩んでいる人は骨粗鬆症になりやすいとか、糖尿病の人は感染を起こしやすい、とか。まだ起こっていないけれどリスクの高い病気の予防を指導すれば患者さんの満足度は高いし、医療費の節約効果にもなるのではないでしょうか。これもオーダーメイドである必要があります。すなわち、万人向けの(製薬会社からもらった)パンフレットを配るのではダメで、話を聞いて患者さんに合わせた資料を「次回来院時」に渡すようにする、というのはいかがでしょうか。
2004年05月19日
コメント(0)
-
医療費の節約について考える3
やまっちです。なかなか本題にたどり着けませんが、本日は薬剤師の役割について。このたび、薬学部の修了年数が6年になることが正式に決まりました。薬剤師会、病院薬剤師会などでは「待ちに待った」実現だそうです。それとともに新設大学ラッシュであり、現在の1.5倍に薬学部卒業生が増えるだろうと言われております。薬学部といえば、学生の7割は女の子です。現役で入学したとして、薬剤師の資格を得るのは24歳。そこから就職して、せめて学費分は元を取るまで仕事をすると何歳になるのでしょう?人気が落ちるのでは?と私は危惧しているのですが・・・。ところで、薬剤師の方々は、もっと危機感を持つべきであるというのが私の結論です。「服薬指導」こそが生き残る道であり、それは「健康コンサルタント」的な、患者さん一人一人にオーダーメイドな情報を提供することで満足を与えられるレベルにまで高めていくべきだ、と考えています。決してカラープリンタで薬の写真と用法用量を印刷した紙を渡すことではありませんよ!え?薬剤師の仕事は調剤だって?確かにそうですが、錠剤の棚からシートを千切って袋に入れるのなんか誰にでもできます!(少々暴論ですが)副作用と相互作用のチェック?どこに1つの薬の全ての副作用を空で言える薬剤師がいるのですか?コンピュータで検索しなければ誰もチェックできません。コンピュータを操作するのに薬剤師の資格は必要ありません。要するに国家資格を持っているだけで、中身はマックの店員なみのスキルで十分務まる仕事なのです。(明らかに暴論なのは承知の上です。反論大歓迎です。)でもこんな薬剤師、多いと思いませんか?現実は病院で処方箋をもらい、薬局でカラープリンタで印字された紙ぺらを読まれるだけ、生活習慣病などで薬が長期に服用される時に一言注意されるだけ、それでも「技術料」を我々は取られているのです。値段が明確になっていたら、「誰がそんなものに金を払うか!」と思う人も多いのでは?少なくとも私はそう思っています。毒薬劇薬や麻薬の管理を担う人は絶対必要ですから、不要な資格とは言いません。ただ、将来は医師と同じく、資格の上にあぐらをかいていると、単なる「ブルーカラー」の職業になってしまう、と言いたいのです。(つづく)
2004年05月18日
コメント(0)
-
医療費の節約について考える2
医療費で儲かっているのは誰?もはや破綻寸前とさえ言われる医療費ですが、この30兆円の巨大マーケットで大いなる利潤を得ている人々がいます。これは果たして誰でしょう?答え:医者!と真っ先に思い浮かぶ人が多いことでしょう。「白い巨塔」や「ブラックジャックによろしく」のような世界は確かに実在する、と私も思います。また、合格発表(入試)から合格発表(医師国家試験)まで1億かかる、といわれる私学の二流大学医学部の学生さんの親御さんの職業は7割は「医師」であるといわれています。しかし現代においては、医師であることの金銭的うまみは縮小しつつあるといえます。これからは、多くのサービス業と同じく、医師の世界にも「勝ち組」と「負け組」が生まれ、淘汰の時代が来る、いやもう始まっていると私は思います。「提供する側の論理」がまだ通用している数少ないサービス業、それが医療の世界だといえるからです。この点については、また話題にしたいと思います。誰が儲けているか?私が考えているのは「製薬企業」それも「外資系」です。製薬企業は、古くは「薬九層倍」といわれるほど、利益率の高い業界です。製造業のくせに、原価こすとが平均25%、中には10%台の企業もある位です。外資系の会社は、海外での豊富な研究費を元手に、ガッポリと利益を得始めています。EBMの時代であり、海外の豊富なエビデンスを背景に国内企業を蹴散らす時代がすぐそこに来ています。確かに優秀な薬は患者さんにとって利益であり、外資系の参入を否定するものではありません。ただ意外に知られていない事実として、ここでは指摘しておきたいと思います。また続きをご覧下さい。
2004年05月17日
コメント(0)
-
医療費の節約について考える1
日本の医療費は高いのでしょうか?安いのでしょうか?どちらの側に立っても、それなりに根拠のある意見を聞くことが出来ます。最近実感として「医療費って高いな・・・」と感じる場面が多いと思いませんか?「医療費を節約する」ためにどうすれば良いか?これから私が考えられる範囲でいくつかの選択しを提示したいと思います。節約というと、まず医療費控除で税金を節約するという手段があります。これは国税庁のサイト(http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm)に丁寧に解説があります。ほかにも検索エンジンをちょっと使えば、いくらでも出てきますのであらためて詳しくは紹介しません。ポイントは、高額所得の人で、所得税の税率が高い人ほど還元される割合が高いという事です。多くの人にとっては、せいぜい交通費とお昼ご飯代1食分の還元、という所だと思います。次に考えられるのは、「まだ飲み残しの薬が余っているのなら医師にきちんと断る」という事です。医師に自分の考えを伝えるのは絶対に必要なことです。これは、「将来淘汰されてしまうダメ医者かどうか」を見分けるための手段としても有効です。臆せずに自分の考えを伝え、かつ相手の説明をよく聞いて理解する(鵜呑みにする、ではありません)ことができるように努力すべきです。このことについては、いずれ改めて述べたいと思います。また、調剤薬局では、必ずしも必要のない費用を取られている事があります。その点についてもいずれ詳しく調べてお知らせします。マスコミは医療費というと、政府と日本医師会が癒着していることが原因であるかのような報道が多いのですが、最も医療費を少なくするために必要なことは患者さんが自分の病気を知る、ということなのです。広くは、健康な人が病気にならないようにするという事も含まれます。「患者さんが悪い」という書き方をすると購読部数や視聴率に影響が出ることを恐れ、このことには踏み込まないようになっているようです。その辺についてもおいおい述べていきたいと思います。
2004年05月16日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 今日の体重
- 2025/11/20(木)・「プラスマイナス…
- (2025-11-20 13:00:00)
-
-
-

- 糖尿病
- 「オセンピック」という気持ち悪くな…
- (2025-10-13 13:53:35)
-
-
-

- スピリチュアル・ライフ
- ★11月20日はコンタクト記念日★
- (2025-11-20 08:58:48)
-