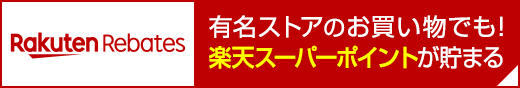サイド自由欄
日本の財政赤字への懸念に関連して、物価上昇(インフレ)や賃上げが国の税収にどう影響するかを考えるのは、将来の財政健全化を考えるうえで非常に重要です
以下では、仮定を置いて ①消費税の物価2%上昇による税収増と ②所得税の5%賃上げによる税収増を簡易に試算してみます。
① 消費税:物価上昇2%による国税収増
● 基本的な考え方:
消費税は「消費支出 × 税率(10%)」で決まります。
したがって、物価が2%上昇すると、理論的には同じ数量の消費が行われた場合、消費支出も2%増加し、税収も2%増えると考えられます。
● 最新の国税としての消費税収(参考):
令和5年度(2023年度)実績ベース
👉 消費税収:約22.6兆円(国税部分)
● 試算(物価2%上昇):
増加分 = 22.6兆円 × 2% = 約4,520億円の増収
② 所得税:賃金5%上昇による税収増
● 基本的な考え方:
所得税収は「個人の所得 × 税率(累進)」で決まります。5%の賃上げが起きると、給与所得が増えるため、税収も増えます。ただし、税率が累進構造なので、一律には増えません。
● 最新の所得税収(参考):
令和5年度(2023年度)実績ベース
👉 所得税収:約23.8兆円
● 仮定:
雇用者報酬全体が5%上昇すると仮定
所得税収はこれに対し「約1.2~1.5の弾性」で増えると仮定(弾性1.3と仮定)
● 試算:
増加率 = 5% × 1.3 = 6.5%
増加分 = 23.8兆円 × 6.5% = 約1.55兆円の増収
試算まとめ:
項目税収増加額の試算
消費税(2%物価上昇)約4,520億円
所得税(5%賃上げ)約1.55兆円
留意点
実際には、消費量の変化、節約行動、課税対象外消費(食料品等の軽減税率)も影響します。
賃上げによって控除額の影響もあるため、単純に税収が比例して増えるわけではありません。
必要であれば、法人税や社会保険料への影響、より精緻なモデル(例えば税制弾性やマクロ経済モデル)も使って試算することが可能です。ご希望があればそちらも対応します。
あなた:
法人税や社会保険料への影響、より精緻なモデル例えば税制弾性やマクロ経済モデル
物価上昇や賃上げが財政収支に与える影響を考察していきます。
【前提設定】
以下のような前提で進めます。
物価上昇率:+2%
賃上げ率:+5%
法人の利益や名目GDPも影響を受けると仮定
対象:主要3税目+社会保険料
【1. 法人税への影響】
● メカニズム
法人税は「法人所得 × 税率(約23.2%)」で決まります。
賃上げで人件費が上昇しますが、それ以上に物価上昇と名目売上が伸びれば、法人所得(≒利益)も増えると想定できます。
● 法人税収(令和5年度):約14.3兆円
● 試算仮定:
名目売上が**+4%(物価+2%、実質+2%成長想定)**
利益率が維持または改善されると仮定(保守的に+3%の所得増)
👉 税収弾性(法人税)はGDPに対して 1.6〜2.0 程度(内閣府推計)
● 試算:
増加率 = 3% × 1.6 = 4.8%
増加分 = 14.3兆円 × 4.8% ≒ 6,860億円
【2. 社会保険料(厚生年金・健康保険など)への影響】
● メカニズム
給与総額に対して一定率を掛けて算出(企業+労働者)
厚生年金:約18.3%
健康保険:約10%
雇用保険、介護保険を含めると、合計約30%が標準的
● 給与総額(ベース):雇用者報酬約300兆円(名目)
👉 5%の賃上げで報酬総額が315兆円に
差額:+15兆円
保険料率30%で:15兆円 × 30% = 4.5兆円の増収
(※ 厳密には公的収支の一部であり、政府間の移転も含まれる)
【3. 税制弾性・マクロモデルでの精緻化】
● 税制弾性とは?
「税収の伸び率 ÷ GDPの伸び率」で表され、
景気が拡大したとき、税収がどれくらい増えるかを測る指標。
税目弾性の目安(内閣府/財務省推定)
所得税1.2〜1.5
法人税1.6〜2.0
消費税≒1.0
社会保険料≒1.0
● マクロモデル的アプローチ(簡略版):
項目ベース数値増加率増収見込
消費税(22.6兆円)22.6兆円2%約4,520億円
所得税(23.8兆円)23.8兆円6.5%約1.55兆円
法人税(14.3兆円)14.3兆円4.8%約6,860億円
社保(全体90兆円規模)90兆円5%約4.5兆円
👉 合計の税収・社会保険料の増収:
約 7.5兆円(税収)+4.5兆円(社保)=12兆円規模
【総括】
賃上げ5%、物価上昇2%のシナリオでの財政への影響は:
税収全体で+7~8兆円規模の増収
社会保険料で+4~5兆円規模の増収
合計約12兆円前後の財源余地が生まれる可能性あり
-
自民・公明の与党が次の選挙で👇 ✅ 全国… 2025年06月13日