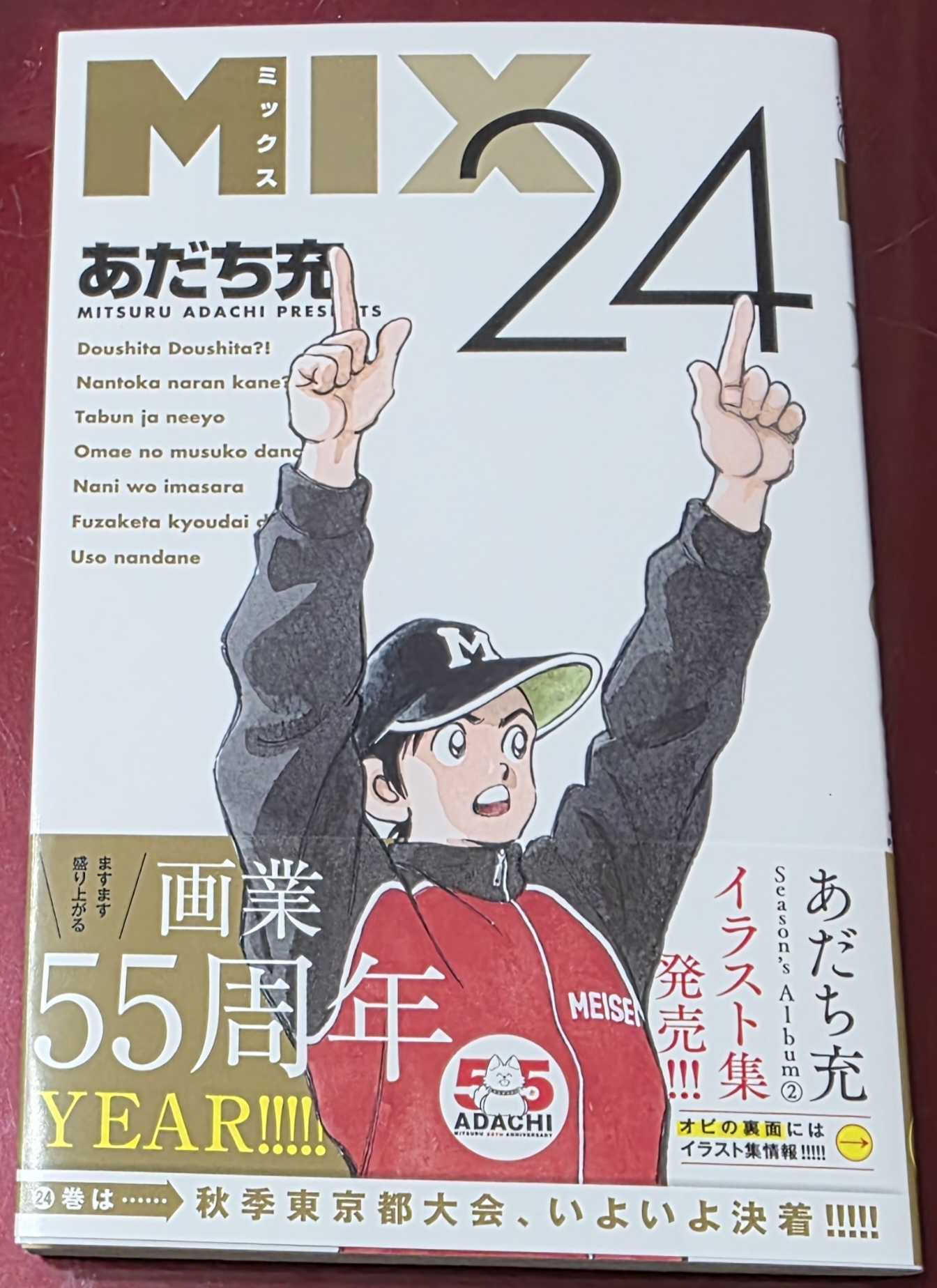-
1

日本のシュールレアリスム小説の第一人者
『燃えつきた地図』安部公房(新潮文庫) 先日京都の美術館で開催していました「ルネ・マグリット展」に行ってきました。 マグリットと言えば、知る人ぞ知る20世紀のシュールレアリスム絵画の巨匠ですね。 有名な作品がいっぱいあります。 実はわたくし、絵画鑑賞もとっても好きなんですが、好きだというわりには、絵画に対して特に定見もなく、だらだらと絵を見てきました。 そんな私ではありますが、今回展覧会を見て、マグリットの作品は晩年に一気によくなる感じがしました。 なぜそう思ったか、つまりなぜ晩年の作品を見ている方が心地がよいのかという理由についてちょっと真面目に考えたんですが、結局のところそれは、作品から精神的な広がりを感じることができるからではないかと思いました。だから深い感情移入ができ、そして、うーん、すばらしい、に至ったのではないか、と。 でも、そもそもシュールレアリスム絵画運動にとって、感情移入できることは本当によいことなんだろうかと、わたくしはふと気付きました。 そこでさらにさかのぼって考えてみると、溶けた時間のサルバドール・ダリだとか、陰の毛髪画家のポール・デルヴォーなどを思い出してみるまでもなく、シュールレアリスムにとって感情移入できることは、さほど肯定的な要因ではないんじゃないか、と。 うーん、なかなか難しいものでありますなぁ。 さて、我国が誇るシュールレアリスム作家、安部公房であります。 と書きましたが、文学の場合どこまでをどう「シュールレアリスム」と呼んでいいのか、本当の所、私はちっともわかっていません。 例えば、詩なら、西脇順三郎って方はかなり本格的な(そして評価も高そうな)シュールレアリスム詩を書いていらっしゃったように記憶しますが、小説になると、はて誰の名が挙がるのでありましょうか。 とりあえずはやはり安部公房だと思いますが、公房にしたところで、いかにもシュールレアリスムらしいシュールレアリスム作品は、初期の短編と芥川賞受賞の一連の『壁』連作くらいしか浮かびません。 結局それは、文学は意味からの離陸が極めて困難だからでしょうね。 意味とは、因果律と言い換えてもいいかもしれませんが、抽象画が、でかいキャンバスの作品でも成立するようには、文学作品は因果律なしには長編作品が成り立ちません。 (モザイクにするという手はありそうですね。公房の『箱男』なんかはそれに近い感じですし、そこまで含めたら、高橋源一郎なんて作家も含められそうです。) というわけで、冒頭の長編小説は、ビミョウにシュールレアリスムな公房作品です。 ただ読んでみて、やたらと殺風景な感じがするんですねー。 シュールレアリスム絵画の共通した特徴に作品世界の静謐性があると思うんですが、小説におけるそれは、この殺風景さにあるのでしょうか。 そもそも安部公房作品には、例えば同時代の三島由紀夫作品にみられるような、文体や描写の絢爛豪華さはありませんでしたが、その代り表現の随所にきらりと輝くような詩性溢れるイメージがありました。 まずそれが、なんとなーく、本作には感じられません。文体の殺風景。 次に、前作『砂の女』には確かにあったサスペンス感覚溢れる物語の展開、これもぐぐっと抑えられたような感じです。 もっとも、砂丘の中にアリジゴクのような家があり、そこに一人の女が住んでいるという、このようにまとめただけでも色彩豊かなストーリー展開が予想される『砂の女』の設定と本作の設定とでは、当然異ならざるを得ないであろうとは思いますが、しかしストーリー展開の殺風景。 ただこれらの小説の二大要素の抑制が、作品にどんな効果をもたらしたかというと、それはシュールレアリスムがおそらく表現として目指したであろう現代都市文明の孤独と不安にほかならず、その意味では、きっちり効果的にシュールレアリスム小説を成立させています。 なるほどそう考えると、本作中の失踪者と彼を追い求める現代人の心象風景は、例えばマグリットが描いた空に浮かぶ巨岩の風景が齎す不安感情と、見事に共振しているような気がしますね。 よろしければ、こちら別館でお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末にほんブログ村
2015.08.08
閲覧総数 4543
-
2

ヘンな「宇平」をどう考える
『護持院原の敵討』森鴎外(岩波文庫) 本短編集には三つのお話が入っています。これです。 『護持院原の敵討』(大正二年) 『安井夫人』(大正三年) 『生田川』(明治四十三年) 最後の『生田川』は戯曲ですが、二十ページほどの極めて短い作品です。『大和物語』の「津の国の乙女」説話の話で、確か、室生犀星も短編小説にしていたと思います。 なかなかファンタジックなお話ではありますが、この短編集の眼目は、やはり総タイトルにもなっている『護持院原…』でありましょう。 実はこの短編小説は、鴎外の短編の中では珍しい「変な」小説であります。 いえ、「変な」小説だと、私は思うわけですが。 例えば鴎外の文学的全業績をまとめる言葉として、「諦念」というものがあります。 (考えてみれば、こんな小さな言葉でまとめてしまうのは、とても「不遜」というか、「無意味」というか、ちょっと困ったことなんですがー。) 「諦念」の詳しい中身はちょっと置いておくとして、とにかく、作品にあまり混乱が見られないのが、鴎外作品の大きな特徴であります。作品内世界を筆者がきっちりとコントロールしきっているという感じであります。 (そんなの当たり前だと思われるかも知れませんが、近代日本文学小説界の鴎外と並ぶ二大巨頭のもう一方、漱石の作品は、大いに混乱しまくっており、しかしそれが「漱石的破綻」なんて呼ばれて、漱石作品の魅力の一端になっているという、うーん、どちらが優れているのやら、なかなか難しいところでありますなー。) ところが、本作『護寺院原…』には、珍しく、落ち着きのない「変な」人物が出てくるんですね。 本作を読めば、必ずや最後まで気にならずにはいられない人物であります。 さらに、この人物の書きぶりが鴎外らしくありません。こんな感じです。 宇平は矢張黙つて、叔父の顔をぢつと見てゐたが、暫くして云つた。「をぢさん。わたし共は随分歩くには歩きました。併し歩いたつてこれは見附からないのが當前かも知れません。ぢつとして網を張つてゐたつて、来て掛かりつこはありませんが、歩いてゐたつて、打つ附からないかも知れません。それを先へ先へと考へて見ますと、どうも妙です。わたしは変な心持がしてなりません。」宇平は又膝を進めた。「をぢさん。あなたはどうしてそんな平気な様子をしてゐられるのです。」 宇平の此詞を、叔父は非常な注意の集中を以て聞いてゐた。「さうか。さう思ふのか。よく聴くけよ。それは武運が拙くて、神にも仏にも見放されたら、お前の云ふ通だらう。人間はさうしたものではない。腰が起てば歩いて捜す。病気になれば寝てゐて待つ。神仏の加護があれば敵にはいつか逢はれる。歩いて行き合ふかも知れぬが、寝てゐる所へ来るかも知れぬ。」 宇平の口角には微かな、嘲るやうな微笑が閃いた。「をぢさん。あなたは神や仏が本當に助けてくれるものだと思つてゐますか。」 九郎右衛門は物に動ぜぬ男なのに、これを聞いた時には一種の気味悪さを感じた。 簡単に説明をしておきますと、「宇平」という若者の父が殺されたわけですね。そして叔父(殺された宇平の父親の弟)と共に敵討ちの旅に出るのですが、まー、現代人の我々では、そんなものどうしたら敵が見つかるのだろうと思うと同様に、なかなか見つからないまま長旅にも疲れ、宇平は精神に変調を兆す、という展開であります。 引用部分に「妙」「変な」「一種気味の悪さ」などの、得体の知れないものに対する表現が出てきます。鴎外作品には珍しいと私は思うのですが、そんなことないでしょうか。 そしてこの後、宇平は、私は勝手にさせて貰うと言って部屋を出ていき、そのまま作品内から姿を消してしまいます。 この展開もまた、まるで鴎外らしくないと、私は思うのですがいかがでしょう。 この「宇平」の存在をどう考えるのかというのは、本作をちょっと一生懸命読んだ人は必ず考えることであります。この後、宇平を除いた遺児達は見事敵を討つのですから、まず考えられるのは「近代的知性の限界」とでも言えそうな気がしますが、それにしては、筆者自身が少し気味悪がっていませんかね。 といって、仮にも、海千山千の鴎外ですから、作品の破綻、ってことはありますまい。(まー、一応。) ……うーん、とわたくしも、考えたのですがね、よくわかりません。 あれこれ考えて、ひょっとしてと思った、それこそ「思いつき」程度のことを最後に書いてみます。 まず、この「宇平」の存在が変だと言うことは、誰もが気づくことです。 ということは、鴎外も、きっと誰もがそう思うだろうということを分かっていながら、そのまま放っておいたということですね。なぜなんでしょ? ここがポイントですよね。 思いつきなんですがね、本当に思いつきに過ぎないんですがね、筆者がそこまで思って放っておいた人物なら、本当に放っておいて構わないんじゃないか、と。 そう思って宇平を放っておいて本作を読めば、本作の持つ雰囲気は、俄然この後の鴎外の「史伝」に近い感じがしてくるような気がするんですが、どうでしょうか。 「史伝」に近いとはどんな感じなのかといわれると、少し困るのですが、簡単にいえば「愛想がない」ということであります。 この愛想のなさは、本短編集収録のもう一つの作品、『護寺院原…』の翌年に書かれた『安井夫人』よりもさらに愛想がないように思います。 行きつ戻りつしながら、ひょっとして、「予行演習」? もちろん、愛想がないことと、面白くないこととは、全く別次元のものでありますが。 よろしければ、こちら別館でお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末にほんブログ村
2012.07.22
閲覧総数 570
-
3

「いたちなく」はそんな小説ではない・後編の2
『穴』小山田浩子(新潮文庫) 前回の続きです。「ゆきの宿」のクライマックスの部分。友人斉木君の家に泊まった翌朝、「僕」が雪の庭で斉木君に会う場面です。 斉木君は、昨晩僕が先に寝た後、妻が泣いていたという話を切り出して、そしてヘンな言葉を使います。「妻は最近仕事が忙しいんだ。それは知っているよ。大変なんだ。毎日すごく遅くまで残業でさ……」「ふーん」斉木君は僕を見た。「まあ俺は倫理的な人間でもないし、口は挟まないけれど、少し心配になったもんでね。奥さんが、元気なら、いいんだ。なんだか気の道のようなことだろう」 どうですか。斉木君のセリフには、二つのヘンな言葉がありますね。 しかしその前に、斉木君が「僕」のセリフを全く受けた返答をしていないことに気が付きます。受けた返答をしていないというより、わざと外している(少々強調すれば「別にごまかさないでもいいんだ」とでも言っている)ようなやり取りの描写です。 そして斉木君のセリフですが、まずひとつ目、「気の道」って何でしょうか。前回にも少し触れましたが、これは筆者の造語でしょうか。 昔、私の祖母が、今思うと婦人病のことでしょうか、「血の道」(きっとこんな漢字だと思うのですが)という言葉を使っていたのを思い出します。 その辺のイメージを重ね合わせると、女性の生理に結びつくような「精神的な塞ぎ」「疑心暗鬼」といった感情を表すと思える言葉です。 次のもう一つのヘンな言葉。 「倫理的」とありますね。「倫理的」という語を、斉木君はなぜこんなところで使っているのでしょう。 妻が泣いていたという話題の場面です。結婚した男女の間で妻が泣いていて「倫理的」とくれば、それは「不倫」以外に何が想像されますかね。 では少し遡って、前回書いた「X年12月頃」の妻のsperm採取依頼の時の描写を詳しく見てみます。 妻はsperm採取容器らしきものを持って、「妙に真剣な顔をして」、会社から帰宅直後の「僕」にまずこう言います。「ねえ、あなたは最近でも自分でしたりするの」 その後「自分でしたり」の意味についてのやり取りが少しあって、さらにこんな風に展開していきます。「どうして一体そんな……」「何かを疑ったり責めたりしているんじゃないのよ」妻は浮かべていた薄笑いを引っ込めた。額に脂が浮いた顔で、しかし頬は白く粉を吹いていて、足元を見るとストッキングを片方だけ脱いでいるのだった。よほど急いで出て来たらしい。「どうしたんだい」 妻は急に早口になった。「あのね、面倒なことを頼んであなたには気の毒なんだけれど、自分で精〇を出して、この容器に入れて欲しいんです」 妻のセリフがヘンに夫に説明的ですね。前回にも触れましたが、不妊治療について両者の間で共通理解ができているとはとても思えないような話しぶりです。(そもそもこの夫婦は、二人一緒に産婦人科に受診しているんでしょうか。疑わしい記述です。) 特に私が少しヘンだと思う部分。「ねえ、あなたは最近でも自分でしたりするの」「何かを疑ったり責めたりしているんじゃないのよ」 ……さて、ここまでかなりしつこく文字数を使ってきましたが、以下、わたくしの「妄想的読み」を一気に書いてみたいと思います。 たぶんそれは「妄想」だろうとは思いますが、でも今のところ私にはこうとしか読めない展開であります。 と、思ったところで、あ、とても以下に書ききれそうもない。 すみません。次回に続きます。次回こそ、終わります。 よろしければ、こちらでお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末 にほんブログ村 本ブログ 読書日記
2019.08.13
閲覧総数 1226
-
4

「山月記」の李徴はなぜ虎に(③)
『山月記・李陵』中島敦(岩波文庫) 「山月記」についての報告の3回目になります。 今回は、三つのその理由を考えたいと思います。特に三つめが、この度「勉強」をしていて新しく「はっ」と思ったものでありますが……。(1)李徴の説く虎になった理由・その一 ……「存在論的な不安」 李徴の告白の中に、なぜ虎になったかの自己分析が、三点に分けて描かれています。それを順に追っていこうと思います。 まず一点目は「存在論的な不安」ですが、李徴の告白が最初に触れているのがこれですね。 「理由も分らずに押付けられたものを大人しく受取って、理由も分らずに生きていくのが、我々生きもののさだめだ。」という李徴の言葉は、ほぼすべての中島作品に通底する「世界のきびしい悪意」であり「存在の懼れ=存在論的不安」であります。 中島は、自らのそんな思考傾向を「狼疾」と解釈し説明しています。 中島の説く「狼疾」とは、そもそもの中国古典においては、指一本が惜しいばかりに、肩や背まで失うのに気が付かない、それを狼疾の人という、というものです。 その概念を中島は、例えば自分が自分であり他者でないことの孤絶感など、根源的な「存在」や「観念」の無根拠性に囚われるあまり、現実の世界や人間存在を見失ってしまう人間、つまり自分がそうであると感じています。 中島のそのような思考傾向の原因については、母親をめぐる出生期から少年期にかけての「不幸・不安」(2歳で両親が離婚し父のもとで育てられ、5歳で最初の継母と住むが14歳でその継母が亡くなり、15歳で二人目の継母と住む)や、青春期に発症し中島の宿痾となった「喘息」という病気の存在がまず挙げられます。(喘息の発症は、彼の小説制作活動の始まりと重なっています。) また、「狼疾記」には、主人公が小学4年時に教師から、地球がいずれ冷却し人類は滅亡するという話を聞かされ激しい肉体的恐怖に襲われたという逸話があり、ここには単なる自我の不安では言い表せないもっと根源的な恐怖感覚が、中島の生来のものとしてあったことをうかがわせます。 「山月記」の「化虎」の論理も、いわば中島の持って生まれたこのような思考傾向の延長上に展開されていることがわかります。(2)李徴の説く虎になった理由・その二 ……「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」 本文の展開から考えれば、おそらく「化虎」の理由の中心として描かれている「臆病な自尊心」と「尊大な羞恥心」です。 この部分こそが、「山月記」のテーマが自我の分裂という近代知識人の問題であり、人間の心のダイナミズム、人間の内面劇の葛藤を描いた名作と言わしめた部分であります。 中島の妻(中島たか)は、中島亡き後の文章で、「山月記」を読み「まるで中島の声が聞こえる様」だと書きましたが、確かに中島の生涯にも同様の傾向がみられます。 作品内の話ですが、そもそも李徴の時代に詩人として名を挙げるにはどのような方法があったのでしょうか。 詩集を出せるわけもなく、社交の場で漢詩を読み上げることで名を挙げるしかありませんでした。そんな時代に、李徴はまず最重要な、人と交わることをしなかったのであります。 中島も積極的に小説を世に問おうとしませんでした。 一高在学中は文芸部員として校友会雑誌に作品の発表もありました(昭和5年)が、その後、「中央公論」新人賞に応募した作品(「虎狩」)一作を例外として、出世作「古潭」(昭和17年・「文学界」)まで発表作品は空白となっています。 中島は、李徴と同様、本来作品を世に問うことで自分の文学に新しい展開が開けるはずであったのに、それをほとんどなさなかったのです。 それについては、3点の指摘があります。 ①中島が正真正銘、天性のはにかみやであったという指摘。 ②「虎狩」が選外佳作であったことによる屈辱感。 ③発表の空白期間中に書いていた長編小説「北方行」(未完)の 失敗による自信の喪失。 しかし、李徴の行動からもうかがえますが、中島の行動には、小説家になることを強く願いながら、同時に、小説家(=表現者)になり切ることを恐れ、そのために努力を拒絶しているとしか考えられないような不可解なものがあります。これは、一体何なのでしょうか。 それは、「理由・その三」につながるものです。 次回、「理由・その三」を考えて、一気に最後まで行きます。 すみません、続きます。 よろしければ、こちらでお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末 にほんブログ村 本ブログ 読書日記
2020.04.21
閲覧総数 582
-
5

なぜにこんなに「暗い」のか。
『雁の寺・越前竹人形』水上勉(新潮文庫) この文庫本には、上記タイトルからも分かるように、二つの小説が収録されています。『雁の寺』は直木賞受賞作です。 しかしここだけの話ですが(って、ブログに「ここだけの話」って意味ないですがー)、めちゃめちゃ暗い話ですねー。 そもそも私は、この筆者の本もあまり読んだことがありません。 昔、戯曲『ブンナよ、木からおりてこい』ってのを何かの拍子に読んだような気がするんですが、あまり内容を覚えていません。 だから、この筆者の作品が、ほぼ「常時」暗いのかどうかについては判断ができませんが、少なくとも今回の二作品は、とってもとっても暗いです。 なぜこんなに暗いのかというと、まー、これらの作品が「人生の孤独」を描いているからですね。しかし、「人生の孤独」を描くというなら、ほとんどの文学作品が描くところでありましょう。 例えば、はやりの村上春樹なんか、いえもっと限定して例示しますと『ノルウェイの森』なんかも、「人生の孤独」を描いた作品でありましょう。 しかし、『ノルウェイ…』は、さほど暗くは、たぶん、少なくともトータルな読後感としては、ありませんよね。 結局この暗さはどこから出ているかと考えますと、それは肉体的ハンディキャップを書いているからじゃないでしょうか。 もちろん肉体にまつわる劣等感が、個人の人格形成に大きな影響を与えることは考えられるのですが、うーん、なんというのか、そういったアプローチからは、いわゆる普遍的な「人生の孤独」には、到達しにくいような気がします。(ちょっと、誤解を生みそうな表現になっていますかね。) 『雁の寺』に出てくる「小僧・慈念」は、「頭が大きく、躯が小さく、片輪のようにいびつ」な少年と描かれています。さらに彼は非人間的に厳しい修行を課せられる中で、極めて孤独な少年となっていきます。(この辺、併せて仏教界の腐敗が描かれるのですが、これが変なリアリズムを持って、気分悪くも面白いところではありますが。) その慈念が、一人で寺庭の池端にじっと立っているのを、寺の住職の愛人・里子が陰から覗くという場面です。 里子は慈念が何をみているのか気になった。池の鯉かと思った。と、とつぜん、慈念は掌を頭の上にふりあげたと思うと、水面に向ってハッシと何か投げつけた。鉢頭がぐらりとゆれて、一点を凝視している。里子もしゃがんだ。廊下から池の面を遠目にみつめた。瞬間、里子はあッと声を立てそうになった。灰色の鯉が、背中に竹小刀をつきさされて水を切って泳いでいくのだ。ヒシの葉が竹小刀にかきわけられ、水すましがとび散った。それは尺余もある大きなシマ鯉であった。突きさされた背中から赤い血が出ていた。血は水面に毛糸をうかべたように線になって走った。 里子は、慈念を叱りつけようと思ったがやめた。〈こわい子や。何するかわからん子や〉 里子は廊下をそっと本堂の横にそれ、隠寮にもどった。 慈念の殺人に至る動機について、それを「孤独」のみでやっつけてしまうには、少し書き込み不足のような気がします。 そこで上記のような「人格のゆがみ」が描かれます。(途中に出てくる「鳶の巣穴」のグロテスクさは、この慈念の人格や心理を象徴するように描かれ、少し面白くもあり、しかしよく考えれば、餌の貯蔵庫である「鳶の巣穴」の中でうごめく瀕死の小動物というのは、「食」という生物の本能についての話と集約することもできます。) しかし終盤、寺のお堂の縁の下から慈念がひもじさの余りこっそり食べた鯉の骨が多く出てくるに至って、慈念の鯉殺しの行動は単なる「食」の話になってしまい、上記の引用部から読める、人格のゆがみによる「迫力」が薄められてしまいます。 そうすると、慈念の殺人の動機は、その他に幾つか細かいものが描かれているとしても、集約してしまうと、里子からのセクシャルハラスメントというだけになってしまい、あれこれ書かれてある割に稔るものは少ないと、つい私は思ってしまうのでありました。 上記に、村上春樹の作品について少し触れましたが、この慈念の孤独と、特に初期の村上春樹の作品に見られる「生きることの孤独」との違いを考えると、水上勉がその原因を、親子関係(貧を含む)と外見の特異性に置いていることが分かります。 これが、いわばこの作品のイメージを暗くし、そして「普遍的な孤独」への広がりを妨げているのじゃないかと感じました。 村上春樹が描く孤独は、これもやはり生存の孤独ではありますが、このような「実存的」な孤独が真の姿を現すには、やはり近代都市の発展が不可欠なのかも知れません。 都市生活の中にひっそりと普遍的にある孤独、これはあまねく存在するが故に、別の一面に於いては、作品全体を「暗く」させることなく、それを描くことを可能にしているのかも知れぬなと、私は暗く密かに愚考するのでありました。 よろしければ、こちら別館でお休み下さい。↓ 俳句徒然自句自解+目指せ文化的週末にほんブログ村
2010.12.29
閲覧総数 1651