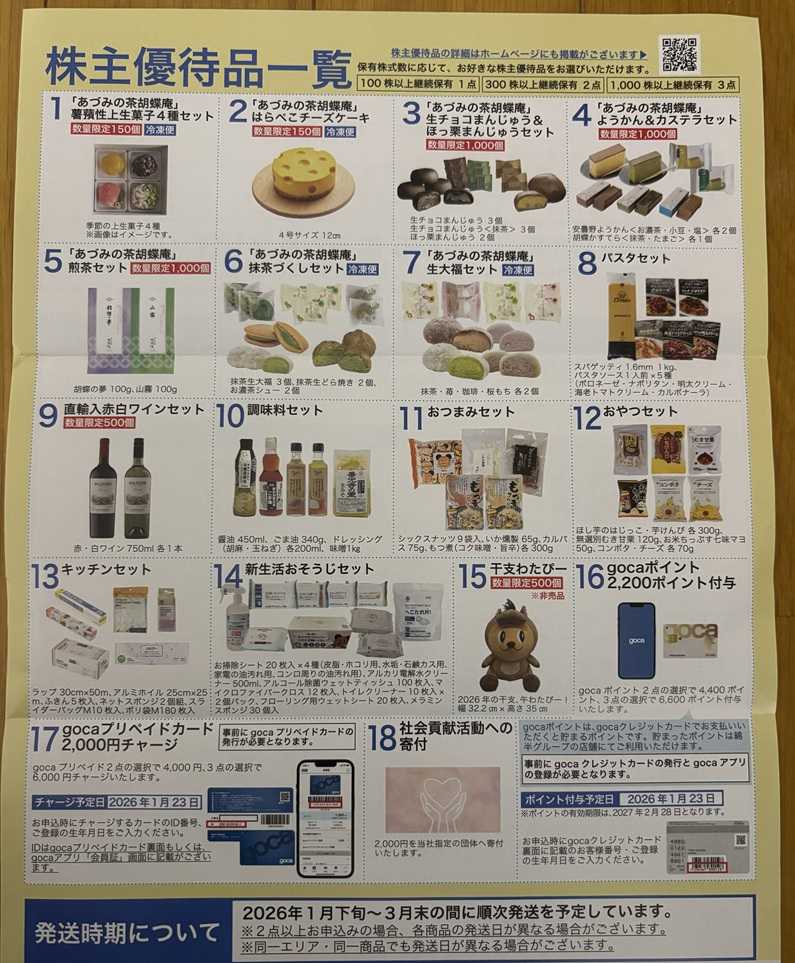全337件 (337件中 1-50件目)
-
なつかしい場所
ふときまぐれで帰ってきてみたら、ずっと不在だった場所に今でも訪ねてくれる人がいることを知った。ほとんどは広告をはってるような人たちだろうけど、アクセス記録の中には僕が書き込んでいた頃に見たプロバイダの名前や携帯電話の名前が混ざっていた。ひょっとして、あの頃訪ねてくれた人がきてくれたのかな、なんて想像する。ずいぶんご無沙汰したけれど、お元気でしたか?幸せですか?僕は定時制を離れたけれど、今も教師を続けています。相変わらずの日々ですけど、それなりに楽しく過ごしています。ちょっとつらい別れもあったけど、前を向いて生きています。どうか、これからもお元気で。また、いつか。 ゆき
2009.12.19
コメント(1)
-
師走の後
1月一杯は個人的な用件で文字通り「忙殺」され、それがやっと終わったと思ったら、今度は本来の教師としての用件にこれまた「忙殺」され、酷いときには一日中で職員室の椅子に十分以上すわることなく校内を駆け回っていた。で、やっと本当に一段落が付いたと思ったら、昨日までの一週間、風邪でダウン。寝込んだ最初の日は、熱にうなされながら「なんでこんなに忙しいんだ?」と何度も呟いていた記憶だけがある。皆様もお気をつけあれ。
2007.02.13
コメント(1)
-
いわゆる履修不足問題に関してとても瑣末なことを二つほど考えてみる(その1)
下の文章は、下調べ、下書き等を一切せず、少し酔った頭で思い付くままに書き連ねました。中には事実誤認や言いがかりに近いこともあるかも知れません。ので、どうか眉に唾をつけてから、お読み下さい(笑)一つめ教師1人あたりが1週間に持つ授業のコマ数は、だいだい16前後。そして、教科によってコマ数の偏りが出ないように、教員の人数は調整されている。で、今回の履修不足問題。どの教科をどれに置き換えたのかは、はっきりないところが多いけれど、例えば世界史なのに現代社会を教えるというように同じ教科内で処理できるものはともかく、全く別の教科にすり替えていた場合、一つ疑問が出てくる。そう。教員1人あたりのコマ数に大きな差が出てくる。一例として、世界史を英語に置き換えたケースを考えてみたい。世界史が必須となっているが、その場合2単位(週2時間の授業)の世界史Aでも、4単位(週4時間)の世界史Bのどちらでもいいことになっている。もし、一学年7クラスの学校で表向きは世界史Aを必須とした場合、週2時間を7クラスだから、14コマ分が社会ではなく英語に移動することになる。この場合、英語の教員が7人いると仮定すると、増えたコマ数を全員で公平に負担する、つまり1人あたり週2コマ授業を増やすことで処理できるが、社会のほうとなると、全員のコマ数を平等に減らせばいいというものではない。本来世界史Aを担当するはずだった教員のコマ数から、世界史A分を削らねばならないのだ。つまり、もし2人で分けて担当するなら、本来16コマ持つところを週10か週8だけしか授業がない教員が2人できることになる。だが、これはあまりに不公平すぎて、他の教員の反対で却下されるだろう。ならば、1人で担当することにして、社会の教員を一人削る方法をとると思う。つまり、何が言いたいかというと、まずは、上に挙げたケースの場合、社会科教員1人分の枠が他の教科に行ってしまうことになる。それが教諭にしろ講師にしろ、社会を担当する人間が1人教壇に立てなくなることに違いはない。同じ社会を担当する者として、こうした欺瞞から職を得られない事態が生じてることに、強い憤りを感じている。報道などを見てると、世界史を削るケースが多いようだけれど、理科や芸術、家庭科でも削られるところもあり、同じような思いを抱く他教科の先生もいるのではないだろうか。ま、振りかえた先の科目を本来行われるべき科目の担当教員が行ってるのなら、話はちょっと違ってくるが(それはそれで問題ありだと思うけど)。それと、こんなことを続けていれば、その学校での教科ごとの教員数に矛盾が生じることになる。どんなに誤魔化そうとしても、年数を経るうちに、おかしな点がどこかに現れるに違いない。で、教員人事は、本来教育委員会の管轄であり、こうした矛盾点などに教育委員会が気付いていないはずがない。更に言えば、上では教員の数についてだけ取り上げたけど、振り替えを行うときには教科書とか、いろいろ準備しなければならないものもあり、そうした物の中には、教育委員会に申請または報告しなければならないものも多いだろう。今回の問題は、教育委員会が黙認、または深く関わっていないと起こりえない問題のはずだ。テレビなどでは当該校の校長や教頭が生徒や保護者に説明や釈明している場面が流れているけど(これまた、視聴者の怒りをあおるため、わざとやってるんじゃないかと思うくらい、要領を得ない喋りをする校長や教頭がばかり映っているけど)、教育委員会の担当幹部が会見に応じているところは、まだ見たことがない。(僕が見てないだけかも知れないけど)もし、今回の問題で、責任と後始末の義務は各学校の教員にあり、割を食ったのは生徒たち。そんな結末に落ち着くのなら、少なくとも高校教育の先行きは暗いと思う。それにしても、こうした振り替えを行っていた学校の教員たちは何を考えていたんだろう。もし自分が担当する教科や大学時代に学んできた教科が別のものに振りかえられたとしたら、自分がいらない教師だと言われたような気になり、自分の存在理由を疑いたくなるではないか?そう思うと、なぜか言いようのない悔しさがこみ上げてくる。2つめも書こうと思ったけど、眠いので、続きは次回。
2006.10.30
コメント(0)
-
蒸気機関車
よく晴れた午後、窓辺でうつらうつらしながら本を読んでいたら、突然蒸気機関車の汽笛がボーッ!と聞こえてきた。この辺りは線路からも遠く、電車の音など聞こえてこない、いや、それよりもこの近くを蒸気機関車が走ってるなんて聞いたこともない。いったい何なんだろう?結局分からないまま、立ち上がって新しいお茶を淹れにいく。急須を片手にポットのボタンを押すと、お湯と一緒に蒸気機関車が急須の中に駆け込んでいった。なぁんだ。ここからだったのか。ガラス製の急須の中では、お茶っ葉が舞う中を蒸気機関車がぐるぐるぐるぐる回っている。せっかちな黒出目金みたいだった。
2006.10.08
コメント(0)
-
JET STREAM ── ノスタルジア・スケッチ XX ──
二つの針が天を指し、昨日と今日が出会う頃。ふと手を止め、コンポのチューナーに手が伸びることが、今もある。いつも近くにいてくれる子がいた。別に示し合わせたわけでもないのに、気がつくと彼女は近くにいてくれて、僕もさりげなく彼女のそばに近づいた。見えないときには周りに気取られないように彼女の姿を目で追い、遠くにいる彼女と視線が合い互いに照れ笑いを浮かべたこともあった。お互いの気持ちを確かめたことはない。気恥ずかしさとこの関係を壊すのではないかという臆病さ、そしてこの微かに体温を感じられるこの距離に、若さ特有のナルシズムの混じった心地よさを感じていたからかもしれない。言葉にしなくとも互いの気持ちは分かり合っている。僕はそう思っていたし、彼女もそう思っていると思っていた。あれは何の話をしていたときだったろう。ふいにラジオの深夜放送は何が好きかと彼女が聞いてきた。幾つかの番組を挙げた後で、「あと、ジェットストリームも聞いてるよ」というと、彼女の顔がぱあっと明るくなった。「私も大好き! 毎晩聞いてから寝てるんだ」それを聞いて恥ずかしくなった。僕は時々しか聞いていなかったから。その日から僕の生活に新しい習慣が加わった。深夜十二時近くなるとラジオをつけFMにダイアルを合わせ、ミスターロンリーのメロディが聞こえてくると、それからの一時間はじっと音楽に身をゆだねる。同じ時間に彼女と同じ曲を聴いている。僕はラジオの音楽に耳を澄ませ、音楽の向こうに彼女の気配を感じていた。心地よい音楽と共に城達也が語る夜の街角、秋の陽射しの中の公園、夕焼けに染まる南の夏の海辺。それを聞きながらまだ見ぬ異国の風景を頭に描き、見知らぬ土地を彼女と歩く様を夢想し眠りについた。笑わば笑え。十七歳だったのだ。
2006.09.26
コメント(0)
-
見えない配達夫
たとえば校門横の花壇の花々や、たとえば夜の帳に包まれた叢の中の声や、たとえば湯宇連野中に浮かんでいる細く薄い雲にしか見えなかった秋がいつの間にか街全体を包んでいることに気付いたときのように、季節の移ろいを目にすると、ふと、この詩が頭の中をよぎっていく。 三月 桃の花はひらき 五月 藤の花々はいっせいに乱れ 九月 葡萄の棚に葡萄は重く 十一月 青い蜜柑は熟れはじめる 地の下には少しまぬけな配達夫がいて 帽子をあみだにペダルをふんでいるのだろう かれらは伝える 根から根へ 逝きやすい季節のこころを 世界中の桃の木に 世界中のレモンの木に すべての植物たちのもとに どっさりの手紙 どっさりの指令 かれらもまごつく とりわけ春と秋には えんどうの花の咲くときや どんぐりの実の落ちるときが 北と南で少しずつずれたりするのも きっとそのせいにちがいない 秋のしだいに深まってゆく朝 いちぢくをもいでいると 古参の配達夫に叱られている へまなアルバイト達の気配があった 茨木のり子「見えない配達夫」より
2006.09.25
コメント(0)
-
猫のユキさん
最近お気に入りのブログ。ため息が出るほど美しい岩手の自然を切り取った写真に、文字通り吸い込まれそうな気持ちになる。ああ、秋はここまで来てるんだなぁ……。やまねこ宅急便(by 猫のユキさん……の飼い主さん)
2006.09.14
コメント(0)
-
休み明け
夏休みが終わって憂鬱なのは、生徒だけじゃない。教師だって同じだ。夜の学校に夏の陽射しを纏ったままの生徒たちが戻る。始業式の出席率の悪さは相変わらずだけど、とりあえず登校した生徒たちの顔はどれも笑顔で、来てない生徒についても特に深刻な話は聞いてない。みんな無事に夏休みを過ごしてくれた。また慌ただしい日々が始まるけれど、今夜はそのことだけが、ただ、ただ、嬉しい。
2006.09.01
コメント(0)
-
海
背の高い人ほど水平線は遠くなるどういう人ほど 海は深くなるかどんな言葉でなら あなたの身近に迫れるか ── 川崎洋「海」 ──
2006.07.16
コメント(0)
-
今年、最初の向日葵
梅雨の晴れ間、通りすがりに見かけた向日葵。天気予報は梅雨空を告げているけど、この向日葵は顔を上げ空を見つめている。雨の日も、この向日葵は俯かず、曇り空の先の夏空を見つめている。
2006.06.25
コメント(1)
-
赤い蕾 ── ノスタルジア・スケッチ XIX ──
薄暗い午後の図書室には、雨の音だけが小さく流れていた。校庭に面した窓からいつも聞こえる歓声も今日はなく、耳を澄ましても、聞こえてくるのは雨音と本を捲る音だけ。気まぐれで手に取った俵万智の『あなたと読む恋の歌百首』を読んでいると、ある歌に目がとまる。それはページの最初にちょっと大きな活字で飾られた歌とは違って、活字の列の中に紛れ込んでいて流し読みだと見逃してしまいかねない歌なのだけど、静かに流れる雨の音に共鳴して、僕の目を離そうとしない。寺町通りに繋がる路地の先、女子大の裏あたりになる、一軒家を部屋毎に貸し出すという形の下宿に住んでいたのは、大学三四年の二年の間だった。元は四畳半の部屋二つの間の壁を取り払って一つにしたこの部屋は、流しこそ付いていたけれどコンロは各階の廊下に一つずつで、トイレ共同風呂なしという時代から取り残されたようなところだったけれど、京都という町に馴染んだ風情と驚くほど安い家賃が魅力だった。そしてその部屋の持つ雰囲気を彼女も気に入っていたのだろう。何かと僕の部屋で過ごしたがっていたし、ゼミで遅く帰ってきたときなんか、戸を開けると彼女が僕のベッドに寝そべって本を読んでいるのが見えたりもした。古い下宿で過ごす僕たちの時間は、静かにゆっくりと流れていて、まるで古い歌に出てきそうな日々を送っていた。下宿には風呂がなかったので、二人で銭湯に行くことも多かった。まさに気分は「神田川」。歩いて五分ほどのところにある銭湯は戦前からありそうな佇まいで、お客も何代にもわたって通っていそうな家族連れが多かった。そんな中で毎日のように通う学生は珍しかったのだろう。番台の横に立つおじいさんは、変わらぬ笑顔で僕たちを迎えてくれては何かと話しかけてくれていて、閉店間際に行ったときなんかはコーヒー牛乳をおごってくれたりもした。あれはちょうど今頃、今にも泣き出しそうな雲が空を覆っていて、天気予報も梅雨の戻りを告げていた日曜の夕暮れだった。二人で銭湯に出かけようとしたときには一時間ぐらいなら持ちそうだと思っていたのに、僕が先に上がって脱衣所で一服していると外から雨の音が聞こえだした。耳を澄ますと雨音は時間とともに強くなり、磨りガラス越しの外には闇が雨音に合わせるように急速に濃くなっていった。そうしている内に番台越しに彼女が下足置き場に行くのが見え、僕も外に出た。サンダルを履いて空を見ると、雨はなかなか止みそうにもなく、かといって街灯に浮かぶ雨の勢いを見ていると、この雨の中を下宿まで駆けていくのも少し躊躇われた。二人で顔を見合わせ、自分たちの不注意を悔やみながら走り出そうとしたとき、後ろから声をかけられた。「よかったら、持ってくかい?」振りかえると銭湯の主人が、いつもの好々爺然とした笑顔で古ぼけた赤い傘を差しだしていた。聞けば、置き忘れたままの傘を整理して、雨の時には顔馴染みの人に貸しているらしい。僕たちは何度もお礼を言って、その傘を借りた。赤い傘は小さくて、二人で肩をくっつけ合っても反対の肩が外に出てしまう。仕方なく、できるだけ傘が彼女にかかるようにしながら、雨の中を歩き出した。人通りの絶えた道を、二人で一つの傘の中で歩く。その時、えも言えぬ香りが鼻の中に流れ込んできた。それは僕の肩先から漂ってくる。彼女の髪の香りだった。その香りに僕は言葉を失い、そんな僕を彼女は不思議そうに見上げた。雨は世界を小さく切り分け、その世界の中で時間は止まる。あの傘の中、僕たちは小さな世界を作り、その世界を彼女の髪の香りが包んでいた。薄暗い図書室に、雨の音が流れる。あの歌と雨の音が共鳴し合い生まれた音の先には、あの傘の中の小さな世界が浮かんでいた。 シャンプーの香りに満ちる傘の中 つぼみとはもしやこのようなもの (早川志織)
2006.06.18
コメント(2)
-
乳母車
母よ―淡くかなしきもののふるなり紫陽花いろのもののふるなりはてしなき並樹のかげをそうそうと風のふくなり時はたそがれ母よ 私の乳母車を押せ泣きぬれる夕陽にむかってりんりんと私の乳母車を押せ赤い総(ふさ)ある天鵞絨(びろうど)の帽子をつめたき額(ひたひ)にかむらせよ旅いそぐ鳥の列にも季節は空を渡るなり淡くかなしいもののふる紫陽花いろのもののふる道母よ 私は知ってゐるこの道は遠く遠くはてしない道 ── 三好達治「乳母車」 ──*上の詩をクリックすると、男声合唱曲「乳母車」(木下牧子作曲 男声合唱組曲 「Enfance finie ~過ぎ去りし少年時代~」より)を聴くことができますが、 その際には Real Player (RealOne Player) が必要です。(無料)
2006.05.21
コメント(0)
-
春に
朝、出勤前に少し歩いていると、どこかからピッコロのような鳥の声が聞こえてくる。聞き慣れない声のほうを見ると、電線にツバメが止まっていた。ツバメは短いタンギングを繰り返しながら、まるで留守の間にこの辺りがどう変わったのか確かめるように周囲を見回し、それが済むとすーっと電線を離れ、別のところに飛んでいった。ツバメが立ち去った方に目をやると、白い花の間から青々とした新芽が顔を出している桜が並んでいた。夜、そぼ降る雨の中を歩いていると、足下で何かが跳ねるのが目に入る。立ち止まって目をこらすと、そこにいたのは小さなカエル。カエルはしばらく身を潜めるようにじっとしていたが、やがてまたぴょんぴょんと跳ねると、道路脇の生け垣の中に消えていった。カエルが最初にいた辺りを見ると、小さな水たまりに桜の花びらが散っていた。見上げても、見下ろしても、春。この気持ちはなんだろう目に見えないエネルギーの流れが大地からあしのうらを伝わって僕の腹へ胸へそうしてのどへ声にならいさけびとなってこみあげるこの気持ちはなんだろう枝の先のふくらんだ新芽が心をつつくよろこびだ しかしかなしみでもあるいらだちだ しかもやすらぎがあるあこがれだ そしていかりがかくれている心のダムにせきとめられよどみ渦まきせめぎあい今あふれようとするこの気持ちはなんだろうあの空のあの青に手をひたしたいまだ会ったことのないすべての人と会ってみたい話をしてみたい明日とあさってが一度にくるといい僕はもどかしい地平線のかなたへと歩きつづけたいそのくせこの草の上でじっとしていたい大声で誰かをよびたいそのくせひとりでだまっていたいこの気持ちはなんだろう 谷川俊太郎「春に」 *この詩に作曲家の木下牧子さんがこんなメロディを付けています。一度聴いてみてください。
2006.04.11
コメント(0)
-
ルール破り
ここでは、昨今の話題となっている社会的事件について取り上げたり、批評を加えたりすることは意図的に避けてきました。(全く取り上げなかったワケではありませんが、それはちょろっと忍ばせる程度にして、 メインは別のものになるよう、意識的、あるいは無意識的にしてきました)その理由として、一つはこれがそうした性質の日記ではないこと、もう一つは、マスコミの尻馬に乗って弱みを見せている人物を攻撃することが、社会派を気取ったストレス発散、またはある種の弱いものイジメに思えることがあるからです。一例を挙げるなら、ライブドア問題で堀江貴文氏を批判したり揶揄するニュース系ブログは多いけど、その中で強制捜査以前に堀江氏やライブドアに疑問の目を向けたものはいくつあったでしょうか?個人的なものであったとしても、多くの人が目にする場で書くのなら、独自の視点や思わず唸らされる文章の「芸」というものを披露すべきであり、ただ単に新聞やニュースで既に語られることをさも自分の意見であるかのように書き散らすことは自分はすまい、そう思ってきました。ですが、今日はそのルールを破ります。今日(2月6日)に行われたホテル東横イン西田社長が会見で謝罪を繰り返していた模様は、ニュース等でも取り上げられていたので、見た方も多いかと思います。最初の会見での西田社長の悪びれない態度もニュースで見ていて不快でしたが、今回のただ一方的に頭を下げるだけの態度は、謝罪ですらないだろう、そう思いました。貴社からの質問にはほとんど答えようとせず、ただ謝罪の言葉を繰り返すだけというのは、誠実な態度とは思えません。本当に心から申し訳なく思っているのであれば、なぜこのようなことを行ったのか、このようなことを行える意識が社内に芽生えるようになったのはなぜか、きちんと応対すべきでしょう。あれでは、ただ頭を下げて非難の嵐が過ぎ去るのを待っているだけに見えて仕方がありません。社長が頭を下げて施設を改善すればそれでいいだろう、そんな意識すら感じ取れてしまいます。実際、駐車場を元に戻しても、身障者用の駐車スペースにベンチを置いていた、なんてホテルもありましたし。また、愛知県の障害者団体がホテルに講義に行った際、支配人は「違反だったとは知らなかった」と答えてるそうですが、それが本当だとしたら支配人としてあまりにも無知ですし、サービスを提供する人間として想像力と能力に欠けると言わざるを得ません。その上、本社から言われたことにそのまま従っているようでは、果たしてホテル東横インで偽装されていたのは障害者関連の施設や駐車場だけか、とすら考えてしまいます。目に見えない設備や非常用の設備は大丈夫かと。火災などが起こった際、たとえ多少の手抜きがあっても最低限の設備が整っていたとしても、表示と違うところがあるだけで、人はパニックになりますよ。そんな疑念のあるホテルで、安心して眠ることができるでしょうか。少なくとも僕はできません。今回の一連の問題は、ただ単に社長の意識のみならず、ホテル全体の意識の問題でしょう。ホテルはサービスを提供する際に人を選ぶのか?ホテルは誠意ある態度で人に接しようとしているのか?あまりにも馬鹿にしています。そう言えば、上で取り上げた会見での社長の態度。身体を丸めて同じ言葉を繰り返すって言うのは、夜回り先生こと水谷修氏が、「悪い仲間に無理矢理誘われそうになったときの断り方」として紹介していたものと同じですね。相手は根負けして諦めてくれるのを待つというやり方です。個人的な感情からお目汚しの文章を書き散らしてしまいました。不快に思われる方がいましたら、お詫びします。
2006.02.06
コメント(0)
-
雪踏み ── ノスタルジア・スケッチ XVIII ──
最後まで残っていた雪が、雨のに消えてゆく。昨日までは固く引き締まり足を乗せても踏み堪えていた雪も、今日はサクサクと崩れていく。僕が通っていた小学校では、3学期の体育はスケートとスキーだった。スキーは校庭の脇に三角柱を横にしたような築山の斜面を使って行われ、スケートは校庭の真ん中にリンクを作り、そこで行われた。心の中で冬休みへのカウントダウンが始まる頃、全学年の児童が校庭に集められる日がある。その日が近づくといつも以上に防寒対策を口酸っぱく言われ、足下もしっかりした長靴で来るように何度も念を押された。その時間になると、校庭に出た児童がまず学年ごとに集められ、それぞれが割り当てられた場所の雪を踏み固める。校庭に積もった雪は連日氷点下の気温に晒されてある程度固まっているが、それでも上に乗れば膝ぐらいか、場所によっては腰まで埋まってしまう。みんな必死になって腿を上げ、さながら雪の上で繰り広げられる陣取りゲームのように、踏み固めた部分を広げていった。最初の頃は先生の言うとおり、あるクラスは一列になって、またあるクラスは押しくらまんじゅうのように一塊になって動くのだが、小学生だからそんな地道な作業もすぐに退屈し、いたずら心をうずかせる子も出てくる。一人、二人と友達に向かってダイブする子や友達を雪の上に引き倒す子が出てきて、それはすぐに伝染し、いつの間にか最初の目的はどこへやら、ちょっとした運動会が始まる。校庭のあちこちで鬼ごっこやプロレスごっこ、積もった雪は適度なクッションにもなるので、ずっと雪と寒さで閉じこめられていたエネルギーをここぞと爆発させる。普段おとなしい子や運動の苦手な子も、じっとしていると寒いからみんなに加わって動き回る。そんな僕らを先生たちは注意することなく笑ってみていて、中には一緒になってかけずり回っている先生もいた。一時間も経てば校庭の真ん中に耳だけ残して食べたパンのようにぽっかり空いた空間ができあがる。チャイムが鳴ると遊びの時間は終わり、皆教室へ帰っていく。靴や手袋を脱げば、汗や長靴の脇から入った雪で靴下や手袋の中はぐっしょり濡れ、上着を脱ぐとほてった身体に、ストーブでガンガンに温められた教室の熱気も心地よい涼しさを感じる。教室に戻ると皆新しい靴下に履き替え、用意のいい子はシャツも交換。大きなストーブを囲うように付けられた柵には、濡れた靴下が万国旗のように並んでいる。踏み固められた校庭には用務員さんが何度も水をまき、表面を平らにしてスケートリンクができあがる。そして2学期の終業式の日にスケートリンク開きが行われ、冬休みの遊び場が一つ増える。スケートの授業は2月半ばで終わるのだが、リンクそのものはその後も昼休みや放課後の遊び場になり、週末は一般にも開放された。そして気温が少しずつ上がり、いくら水をまいてもリンクの氷が荒れたままになると、リンクはお終い。放っておかれるようになったリンクの上には新しい雪が積もるようになり、雪が完全に無くなるまで、校庭から子どもたちの声は消え、校庭は、つかの間の白い眠りに包まれる。
2006.02.02
コメント(2)
-
The Lord bless you and keep you
The Lord bless you and keep you.The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you.The Lord lift up the light of his countenance upon you and give you peace.Amen.死せる者たちへは永遠の安らぎを。生ける者たちへは等しく満面の笑顔と隠し味程度の涙を。
2005.12.24
コメント(0)
-
サンタクロースっているんでしょうか?
*これは、2004年12月3日の日記を、一部削除の上掲載したものです。 一度お読みになっておられる方もいらっしゃるとは思いますが、年に一度のこと、 ご容赦のうえ、もう一度目を通していただければ、と思います。 サン新聞社さま── わたしは8歳です。 わたしの友だちに「サンタクロースなんているもんか」っていっている子がいます。 パパは「サン新聞にきいてごらん。サン新聞のいうことがいちばん正しいだろうよ」 といっています。 どうか、ほんとうのことを教えてください。 サンタクロースっているんでしょうか? ニューヨーク市西95丁目115番地 バージニア・オハンロン1897年というから、今から100年ほど前のこと。ある秋の日、こんな手紙がニューヨークのサン新聞に届いた。誰もが子どもの頃に抱く疑問、そして多くの親たちにどう答えたらいいのか悩ませた質問。そんなことが書かれた少女の真摯な手紙をから、フランシス・チャーチ氏の手によって、こんな社説が生まれた。 バージニア、あなたの友だちは 「サンタクロースなんているもんか」 といってるそうですが、その子はまちがっています。 このごろは、なんてもかんでも「そんなのはうそだ」と疑ってかかる人が 多いけど、その子もそんな疑りやさんなのでしょう。 そういう子は、目に見えるものしか信じようとしないし、 自分の頭で考えても理解できないものは、「あるもんか」と思ってしまうのです。 しかし、自分の頭で考えられることなど、おとなだってこどもだって、 そんなに多くないのですよ。 (中略) そう、バージニア、サンタクロースはいるのです。 サンタクロースがいる、というのは、 この世の中に愛や、やさしさや、思いやりがあるのと同じくらい、たしかなものです。 わたしたちのまわりのある愛や思いやりは、 あなたの生活を美しく楽しいものにしているでしょう? もし、サンタクロースがいなかったとしたら、 この世の中はどんなにつまらないことでしょう! サンタクロースがいないなんて、バージニアみたいな子どもがいない、 というのと同じくらいさびしいことだと思いますよ。 サンタクロースがいなかったら、 すなおに信じる心も、詩も、夢のような物語もなく、 人生はちっとも楽しくないでしょう。 わたしたちが、喜びを感じるのも、 目で見たりさわったり聞いたりできるものだけになってしまいます。 そして、子どもたちが世界中にともした永遠の光も、消えてしまうことでしょう。 (中略) サンタクロースを見た人は、だれもいません。 でも、だからといって、サンタクロースがいない、といえるでしょうか。 この世の中でいちばんたしかでほんとうのもの、 それはおとなの目にも、子どもの目にも見えないのです。 (中略) 目に見えない世界は、一枚のカーテンでおおわれていて、 どんな力持ちでも、力持ちが何十人集まっても、 そのカーテンを引きさくことはできません。 そのカーテンを開けることができるのは、 信じること、想像力、詩、愛、夢見る気持ちだけなのです。 そういう心さえあれば、カーテンのむこうにひろがる、 美しく、きらきらした輝かしい世界を見ることができるのです。 そんな世界は幻ではないかって? バージニア、カーテンのむこうのそんな世界こそが、 ほんとうであり永遠なのです。 サンタクロースがいないだなんて! うれしいことに、サンタクロースはちゃんといるし、 これからもずっと生きつづけるでしょう。 今から一千年たっても、いえ、その百倍の月日が流れても、 サンタクロースは子どもたちの心の喜びとして、 ずっとずっと、生きつづけることでしょう。ちなみにこのエピソードはアメリカ人なら誰もが知っているそうで、クリスマスシーズンに何人かで集まっている時などに「そう、バージニア」と口にすると、必ず誰かが「サンタクロースはいるんです」と返してくれるそうだ。引用文献 村上ゆみ子著・東逸子絵『サンタの友だち バージニア』 1994 偕成社
2005.12.21
コメント(0)
-
Save,Hope and Love
英語はあまり得意じゃないから牧師の言葉はほとんど分からなかったけど、最後に牧師がキミたちへ贈った「Three words」だけは耳の奥に残ったよ。キミたちの心の中でも、この「Three words」は息づいていくんだろうね。「Three words」と一緒に憶えていて欲しいことがもう一つある。式の翌日、渡し忘れた預かりものを届けにホテルに行ったとき、僕を待ってロビーのソファに並んで座っているときに浮かべていた式の最中やカメラの前での整然としたものとは違う柔らかくてまるで光でできているかのようなあの笑顔。まるで共鳴するかのように、キミたちは同じ笑顔をしていたんだ。キミたちの目に映った相手の笑顔を忘れなければ、これから先、つらいことがあったとしても、その笑顔の記憶が再び共鳴し合い、キミたちは強くあることができるだろう。結婚おめでとう to my brother and my new sister.
2005.12.11
コメント(0)
-
武勇伝
♪1日3ミリバス停ずらす ♪2年をかけて自宅の前へ最近流行のオリエンタルラジオのネタだが、これ、本当にやった人がいたと聞いたことがある。昔ラジオで紹介されていたのだが、ある女子高生がいつも寝坊してバスに乗り遅れるので、自宅前にバス停があれば大丈夫だと考え、1日10センチずつバス停を自宅の前に持っていたとか。2年もかけるつもりでいればばれなかったかもしれないが、彼女の場合はあまりにも性急すぎたためすぐにばれてしまい、その女子高生は大目玉を食らってバス停も元の位置に戻されたそうだ。そしてその後、その彼女の通う高校の校則に新しい条項が加わったという。「バス停を勝手に動かさない」(笑)本当かどうかは、知らない(笑)
2005.11.15
コメント(1)
-
山オランダ人
1823(文政6)年、シーボルトが初めて日本にやってきたときのこと。シーボルトは長崎の出島に着くやいなや、役人たちと会うことになったのだが、その時その場にいた通詞がシーボルトのオランダ語の発音がおかしいと騒ぎ出した。ドイツ人であったシーボルトのオランダ語は、かなり流ちょうだったろうが微妙な違いは消すことができなかったのだろう。通詞たちはオランダ語の読み書きはできないが、会話はしょっちゅうしているのでオランダ語の発音にはかなり敏感だ。事実、シーボルト以前にもイギリス人(?)が日本を調査しようと出島に来たことがあったが、通詞にオランダ人でないことを見破られて強制送還となったことがあった。通詞たちに疑いのまなざしを向けられたシーボルトは、どのようにしてこの苦境を脱したのだろうか。シーボルトは、余裕の笑みを浮かべながらなのか脂汗を額に滲ませながらなのかは記録に残っていないが、このように言ったそうだ。「私はオランダの山岳地方出身で、ひどい田舎のために言葉に訛りがある」通詞たちはこのシーボルトの弁明聞いて、納得したのか一抹の疑いを残したままなのかは記録に残ってないが、とりあえずシーボルトが出島に逗留することを認めた。それにしても「この世界は神が造りたもうたが、オランダはオランダ人が造った」と言われ、国土の4分の1が海面下にあり高い山など全くないオランダの、山岳地方出身とはよく言ったものだと思う。キチンと調べたわけではないが、これが記録に残る日本人が聞いた外国人のジョークの最初のものではないだろうか。以上、授業の際のネタ帳からでした。
2005.11.01
コメント(1)
-
笑っていいんだよ
前にも少しだけ書いたが、情報の授業はTT、すなわち2人1組で行われている。1人がメインとなってホワイトボードの前で授業を行い、もう1人が生徒の間をまわって個別指導を行うという形だ。僕は個別指導のほうを見ているのだが、これが結構難儀だったりする。授業に集中しない生徒の注意から、授業が分からなくなった生徒への対応まで、教室中を始終行ったり来たりしている。何かある度にあちこち移動して片付け、あるいは片付く前に別のところへ行かなくてはならなくなる。まるでモグラたたきをやってるような気分だ。最初の頃はメインで授業をやらなくていいから楽できそうだと思っていたのだが、甘かった。その日もいつものように慌ただしく動き回ってはいたのだが、課題の締め切り日ということもあってか、いつもに比べたらふざける生徒も少なく、注意の手間が省けて少しは余裕があった。のんびり生徒の進行状況をチェックしながら歩いていると、女子生徒が二人、画面を覗きこみながら何か囁き合っている。見てみると、課題であるHP作成を一応終わらせたのだが、実際にIEで表示させてみると、イメージ通りに出ないらしい。「なんか、ヘン~っ」HPBの編集画面に表示されたものと見比べてみたが、僕にはそれほど違いがあるようには見えなかった。だが、作った本人にしてみれば、このズレが気になって仕方ないのだろう。僕は他の場所で急を要することがないのを確認すると、そのHPの修正に付き合いはじめた。HP作りにおいて、この授業ではHPBを使ってきた。僕もHPBなら一応一通りのことはできるが、修正する際にはタグを見たほうが手っ取り早い。「じゃ、とりあえずHTMLソースを開いてみろ」「は?」生徒二人は訳が分からないという顔で僕を見ている。「HTMLソースの出し方って、授業でやっただろ」「えっ、HTMLソースって……何に使うの?」「だから、タグを見たいから、HTMLソースを出すんだよ」僕がちょっとイライラし始めていると、彼女たちは突然抱きついた。「……何やってる?」「だから、タグ」「そりゃ、ハグだろ」呆れながらツッコむと、彼女はヘヘッと笑いながら離れる。授業内容を忘れていたことへの照れ隠しもあったのかな、と思った。「ったく、なにオヤジギャク言ってんだか」「えーっ、オヤジギャクじゃなくて、お姉さんギャクだよ」ガキのくせに何がお姉さんだ、とツッコもうとすると、生徒の1人が笑いながら僕の顔を覗きこんでいた。「先生、授業中だってそんな風に笑っていいんだよ」僕は一瞬はっとして言葉を失ったが、すぐに「なに言ってんだよ」とぶっきらぼうに言うと、自分でHTMLソースを表示させて修正を加えた。やがて授業は何事もなく終わり、生徒はコンピューター室を後にする。僕はその日の授業はこれでお終いだったが、もう1人の先生はこの次の時間も授業があったので、僕1人で授業の後片付けを行った。1人になれる時間と場所があってよかった、と思った。授業が終わってからも、いや、言われた直後から彼女の言葉がずっと引っかかっていた。笑ってもいいんだよ。僕はずっと普通に過ごしてきたつもりだったけど、いつの間にか笑わなくなっていたらしい。そして、笑わなくなっていたことに、僕自身気付いていなかった。一体、僕はどんな顔で生徒の前に出ていたんだろう。ここ最近の授業を思い出してみたが、僕がどんな顔をしているのかは全く分からなかった。当たり前だけど。僕は片付けを終えると、コンピューター室の電気を消して鍵をかける。電気の消えた暗い廊下は、生徒の声も聞こえずひどく静かだ。真っ暗な闇の中、僕はとぼとぼ歩いていく。
2005.10.31
コメント(0)
-
秋の夜
ケータイの光を浴びて浮かびおり夜のガラスに映る自画像砂浜のごとき液晶に綴られし文字は時の波に洗われぼやけ真夜中のシャワーの音ぞ喧しき流るる音に吾の声も消え吾の身にシャワーのお湯を叩きつけ全てを流し明日を迎える読み返すメールが呟く「ありがとう」読み返しつつ吾も呟く
2005.10.16
コメント(0)
-
指先の記憶 ── ノスタルジア・スケッチ XVII ──
恋と呼ぶには淡く、静かに僕の中に生まれてはいつの間にか通り過ぎていく。彼女への想いは、秋の日の午後のように僕の中に静かに佇んでいた。北の地にある僕が通っていた高校の文化祭が開かれたのは、一足早く陽射しが秋のものに変わった頃だった。地味な学校だったせいか文化祭と言ってもお祭りの要素は薄く、1年がやることと言えば合唱コンクールの練習とバザーの出店の支度、あとは文化祭で何らかの発表がある部にいる人はその手伝いと、その準備さえも校風に合わせたかのように地味に静かに進んでいた。そんな文化祭の中で唯一と言っていいほどの華やぎを持っていたのが、前夜祭だった。セピア色に変わりかけた写真のように地味な古さを感じさせる学校だったせいか前夜祭では全校生徒が校庭に集まってのフォークダンスが行われていて、地味で素朴な学校の生徒たちは女子と手を繋げるという何とも時代遅れな喜びに胸躍らせていた。夕闇迫る校庭に文化祭の準備を終えた生徒たちが集まり、クラスごとに整列してから3つの円を描く。最初に踊るパートナーはその円ができあがったところで決まるのだが、僕の横に立っていたのが彼女だった。白い肌に整った目鼻立ち。学校中で誰もが目に留める子だった。今ほどスカート丈も短くないし、高校生が化粧をする習慣もない時代だったから今時の高校生の南国の花のような華やぎはなかったけれど、草原の中に一本だけ顔を空に向けている鉄砲百合のような凛とした華やぎを持った人だった。そんな彼女と同じクラスにいた僕は、他の男子と同じように教室や体育館にいる彼女の姿を追い、たまに彼女と視線が合うとぶっきらぼうに顔を背けたりしていた。彼女に恋していたのかと聞かれたら、僕は少し考えた後で首を横に振るだろう。自分とは釣り合わないという悲しみの混じった諦めの中、美少女と同じクラスにいるという喜びを感じる。そんなあまりにも淡い想いだった。彼女の斜め後ろに立ち、いよいよフォークダンスが始まる。彼女の最初のパートナーになれるという喜びが顔に出ないよう硬い表情をしていると、体育の先生がマイク越しにこう告げた。「まず、ダンスをちゃんと覚えているか確認するので、 しばらくパートナーチェンジせずにやるから」あの時の驚きと戸惑いとときめきは、今でも微かに憶えている。僕は右手を彼女の肩の上、左手を彼女の腰の横に持って行き、彼女の指先に触れると音楽が流れ、僕は指先の感触と鼻をくすぐる髪の匂いに感じながら彼女と同じステップを刻む。短い旋律が繰り返される中、僕と彼女は踊り続けた。踊り続ける中、最初は薄紙を挟むように触れるか触れないかという距離を保っていた指先も、そのうち少しずつ距離を縮めていく。すると、彼女の指先が荒れていることに気付いた。そしてその荒れが水仕事によるものであることもすぐに分かる。明るい華やぎを持ち、友達と遊ぶことが何よりも楽しそうな彼女には似合わない荒れだった。その意外な荒れに驚いてはいたが、同時に家族と一緒にいるときの彼女をかいま見たような気がして、多分他の男子は知らない彼女の一面を僕だけが見つけたような喜びが沸き上がってくる。僕はそんな喜びを無理矢理押さえつけるように、わざと大げさに動きながらステップを確認するように「いち、に、いち、に」と声を出し始めた。そんな僕に彼女はクスリと笑うと、少し振り返って僕にほほえみかけた。四分の一周ほど回ったところでステップの確認は終わり、もう一回踊ったところで彼女は去っていった。お互いのパートナーは次々に変わっていき、彼女は夜の中に消えていく。母校の前夜祭ではもうフォークダンスもなくなり、僕自身もあの時憶えたステップを忘れてしまった。全ては記憶の彼方に消えてしまったが、夕闇迫る中文化祭の準備にいそしむ生徒たちの声を聞くと、あの時感じた彼女の記憶が指先に蘇るような気がしてくる。
2005.10.09
コメント(1)
-
月夜を歩く
満月の下を歩く。秋の月は眩しくて、いつもは暗闇に同じ間隔で街灯が電柱の足下を照らす道も、今日は粉雪が降った後のように一面薄く輝いている。満月の下を歩く。見上げた月は冴え冴えと輝き、その透き通った光を反射するかのような虫の声が、静寂という名の喧噪を奏でている。満月の下を歩く。いつもは街灯の横を通る度に自分の影が現れては消えていくが、今日はそんな影の横に薄い影がもう一つ。その影はどこまで行ってもいつまで歩いても、今日だけはちゃんとついてくる。いつもは見えにくいものだけど、いつもちゃんと見ていてくれる。いつもちゃんとついてきてくれている。
2005.09.19
コメント(1)
-
初デートの終わりに
気になる相手と初めてデートすることになったとしよう。当然あなたはその相手との仲を深めていたいと切に願っていて、デートもこれ一回でお終いとなることは絶対に避けたいと思っている。そのため、これが最初で最後ではなく長いお付き合いの第一歩となるよう、綿密に(と少なくとも自分は思っている)計画を練ることになるのだろう。料理で言えばまずメインとなる場所や行事を決め、その日一緒にいられる時間からその場所での滞在時間をまず引き、前菜やデザートの中身を決めるように、残った時間をどのような場所で過ごすのか考える。まずどこで待ち合わせるのか、メインディッシュまで時間があるのならどんな店に行こうか、もしメインディッシュが食事でないのなら、食事にはどのタイミングで行こうか、その店がちょっと背伸びをした場所なら、一度下見にでも行っておこうか、実際に店には入らなくてもとりあえず店の前まで行って道の確認だけでもしておこうか、万一道に迷ったりしたら格好悪いしな、そうそう、デートの間どんな話をしたらいいのか一度脳内シミュレーションをしておこうか、どんな話題がいいのかさりげなく下調べしておかないと、あっとその前に、どんな服を着ていくのか決めておかないと。なんて脳の普段使わない部分を必死に動かして考えるものだろう。(ちょっと脱線するが、そろそろブームも終わりかけの『電車男』だが、 あの第1章は「脱オタクファッションマニュアル」や「初デート入門編」として 実に有用なのではないかと思っている)さて、そんな風にデートの中身が決まったところで、重要な問題が浮かび上がる。デートの終わりをどうするか、だ。次のデートの約束ができれば申し分ないわけだけど、そこまでできなくてもせめて自分に好印象を持たれたまま別れたい。せっかくデートがうまく運んでも、最後に失敗したら全て水の泡だ。ベルエキップのギャルソン千石武も言っている。フレンチにおいて、デザートはお客様の最後の口に入るものだから、このデザートの印象を持ったままお客様は店を出るのだ、と。プレゼントなんかどうだろう。あんまり高価ものだと、初デートでそれほど親しくないから逆効果かもしれない。花なんかいいかもしれないけど、花束は結構かさばる。まさか最後に渡す花束を最初から持ち歩くなんて格好悪いし、うまい隠し場所を見つけるのは難しい。ドライブだったらまだ車の中に置けるからいいかもしれないけれど、後部座席だと見つかってしまう。トランクの中は?いやいや、デートの最後にトランクを開けて、茶色くなって汚れた新聞紙の上でタイヤや工具の横に置かれた花束を喜んで受け取ってくれるだろうか?あまり高価なものではなく、自分に好印象を持ってもらえて、かさばらないもの。そんなものがあるだろうか?と、ここまでが前置き。大学時代の先輩の話だ。先輩は卒業後地元に戻って就職したのだが、ある時、気になる女性とデートすることになった。聞いた話では、その先輩、デートの約束を取り付けた日は嬉しさのあまり、酔っぱらったまま知り合いが麻雀しているところに乱入し、朝まで卓を囲んでいたそうだ。デートはドライブとなり、先輩とその女性は郊外にある風光明媚な場所を回ったそうだ。季節もよく、さぞいいデートとなったことだろう。そしてドライブであるから、デートの終わりに彼女の家まで送っていくことになった。彼女の家の前に車を止め、名残惜しくはあるけど日曜日なので彼女の父親は家にいるかもしれない。いや、それだけじゃなく、じっと外の物音に耳を澄ましていて、娘の帰りを待っているかもしれない。だとしたら、車が止まっても彼女がなかなか玄関のドアを開けなかったら、こっちにやってくるかも。それどころか、ひょっとしたら娘の相手がどこの馬の骨か見てやろうと、窓越しにこっちを覗きこんでいるかもしれない。そこまで考えたかは分からないが、簡単な言葉を交わしただけでデートは終わりとなった。彼女はシートベルトを外し、ドアを開いて車を降りようとしたとき、先輩は後部座席に手を伸ばしながら声をかけた。「あ、もしよかったら……」さて、先輩はデートの終わりに何をプレゼントしたのだろうか。先輩が彼女の目の前に差し出したものは、パイナップル。青々とした葉もちゃんとついたものを丸ごと一つ。袋にも入ってなければ、のし紙一つついていない、むき出しのまま。彼女は面食らった顔のまま、そのパイナップルを受け取ったそうだ。ここまでお読みになった女性の方々、初めてのデートでパイナップルを目の前に差し出されたら、あなたはどう思うだろうか?ここまでお読みになった男性の方々、初めてのデートでパイナップルを贈ろうと思うだろうか?この後、その先輩と彼女はどうなったのか。それは、僕がこの話を聞いたのが、その先輩の結婚式の2次会の余興で出されたクイズだった、と言えばお察しいただけるだろう。ちなみに、彼女曰く、その初デートで一番嬉しかったのは、最後にもらったパイナップルだったとか。
2005.09.18
コメント(1)
-
九月の夜
授業がやりにくい月の一つに九月を挙げるのは、教師の経験がある人なら誰しも納得してくれるのではないだろうか。残暑が厳しい上に夏休みで気持ちが緩みきっているから生徒も集中できずにいるし、そんなだらけきった生徒を前にすると、こっちまで授業のテンションが下がってしまう。そしてそれは定時制も同じ。日は沈んでも暑さは教室に居残っていて、生徒たちの動きもどこか緩慢としている。そんな夏の埋み火が燻る時期がしばらく続いたが、ある日を境に空気が変わった。生徒たちの顔はまだ夏のだるさを引きずっているけれど、教室の中には涼しい風が吹き抜けている。一日の仕事を終え、秋の虫たちが自分たちの番だと言わんばかりにざわめく夜に足を踏み出す。僕は微かに身体を震わせると、数ヶ月ぶりにYシャツの袖を降ろした。
2005.09.16
コメント(0)
-

ヴィオロンのため息の
どこかから風が吹く。それはどこか切なくて、どこか爽やかで、その風に吹かれながら、時々風の吹く彼方に思いを馳せたりもした。ふいに空気が変わったその日、道を歩いていたら、一陣の風が通りすぎる。あの風だった。立ち止まり、風の来た方向を、風の向かう方向に目をやり、最後のその二つを思いながら空を眺める。空には、オレンジ色の秋の雲。秋風のヴィオロンの節(ふし)ながき啜泣(すすりなき)もの憂き哀しみにわが魂を痛ましむ。時の鐘鳴りも出づればせつなくも胸せまり思ひぞ出づる来(こ)し方に涙は湧く。落葉ならね身をば遣(や)るわれも、かなたこなた吹きまくれ逆風(さかかぜ)よ。ポール=ヴェルレーヌ 堀口大学訳「秋の歌」
2005.09.15
コメント(0)
-
晩夏の光
窓辺に腰掛けて外を見ると、遠くの空にはいくつもの夏の雲が連なり山裾を縁取っていた。そんな眩い光に白く輝く雲を見ていたら、あの上を飛行機で飛んだら声も出ないくらいきれいな雲海を目にすることができるんだろうな、なんてことが頭に浮かぶ。そんな風に雲も光も空の色もまだ夏のものだけど、この前までの夏とはどこか違っていた。カレンダーが一枚捲られる前には、夏の光を跳ね返すように鳴いていたあんなにやかましかった油蝉やミンミン蝉、ヒグラシの声はいつの間にか消えて、今はツクツクボウシが一匹鳴いているだけ。ツクツクボウシは孤独なのかもしれない。目の前の木立で一匹のツクツクボウシが夏の光に消え入るように鳴き、それが止むとどこかからその声に応えるような別の鳴き声が起こり、それも止むと、また目の前の木立でツクツクボウシが鳴く。そんな儚い音信が繰り返されていた。僕はそんなツクツクボウシのいる木の辺りに目をやる。と、枝先の葉がきらりと光ったように見えた。何があるんだろうと目をこらすと、光はゆっくり枝を離れる。蜻蛉が一匹、僕の目の前をゆっくり横切っていった。
2005.09.14
コメント(0)
-
教師とは、学校におけるギャルソンである
(森本レオの声をイメージして読んでみてください)あらゆるところに、名文句は溢れている。例えば、道を歩いているとき、すれ違いさまに耳にした一言が、いつまでも心に残ることがあるように。また、誰かが何気なく発した戯れ言が、時として人生のヒントとなるように。名文句とは、その言葉を口にした人が作ったものではない。どれだけ心に響いたか、聞いた人がその言葉を名文句とするのである。ここに、一つ、僕にとって名文句に溢れたドラマがある。ドラマの名は、『王様のレストラン』。放送終了後十年が経っても、今なお多くのファンの心を掴んでいる、人気脚本家三谷幸喜の手による、珠玉の名作である。ある晴れた昼下がり、ビデオテープの整理をしていたら、このドラマの再放送を録画したものが出てきた。整理そっちのけで全話を見てしまったのだが、今なお、このドラマは眩い光を放っているように、思えた。その中の一条の光を、ご紹介しよう。山口智子扮する、未知の可能性を秘めたままの、つまりは、まだまだ班に前のシェフに、松本幸四郎扮する伝説のギャルソンがハッパをかける、場面だ。あなたには才能があるという千石(松本)にたいして、しずか(山口)が反発をする。「あんたは『才能がある、才能がある』って言うけど、 あたしにはそんなもの、これっぽっちもありません! あたしのことは、あたしが一番よく知ってます」それにたいして、千石は澄ました顔で、こう答えるのである。「あなたは、自分のことしか知らない。 けど、私は百人のシェフを知っています。 あなたなら大丈夫です」誰かが、言った。教師とは、学校におけるギャルソンである、と。縁あって学校に集まった生徒たちに、学校で言い時間を過ごせるよう、あらゆるものを用意し、彼らの目の前に差し出し、場を和ませ、時にはさりげないユーモアを交えながら注意したりもする。そして、いい時間を過ごせた生徒たちが学校を後にするとき、明日への扉を大きく開いてやり、その背中を見送るのである。果たして、僕はギャルソンで有り得たであろうか。伝説のギャルソンが自分の可能性に気付いていないシェフに言ったように、「僕は百人の生徒を知っている。あなたなら大丈夫」と声を掛けられるだろうか。そして、その生徒の持つ可能性に気付いてやれるだろうか。そんなことを思った夏の午後で、あった。実は、このドラマは僕自身の人生において大きな意味を持っており、また、このドラマによってある危機を脱することができたのだが、それはまた、別の話(笑)
2005.09.01
コメント(2)
-
From Unknown
誰から聞いたのかどこで出会ったのか、忘れてしまったけれど、忘れられない言葉がいくつもある。これもそんな一つ。 「運命」とは「命を運ぶ」と書く。 だが、これが分からない馬鹿者は「命が運ばれる」と読んでしまう。 命をいっぱい使って生きていけ。 それが「使命」というものだ。
2005.08.25
コメント(0)
-
掌の中の沈黙
メールは難しい。そう改めて思った。些細な行き違いがきっかけだった。それがあっという間にこんがらがり、もつれ、突然ぷつんと切れた。メールというのは気軽にやり取りができる反面、言葉が一人歩きしやすい。自分が発した言葉を相手がこちらの考え通りに受け取ってくれるとは限らないのだ。もし面と向かって話していたなら、ニュアンスや表情、仕草でいくらでも言葉を補うことができる。いや、それよりも、言葉の行き違いが生じればすぐにそのことに気付くことができただろうし、こんなにもつれることもなかっただろう。そのことは十分分かっていたはずだったのに、きがついたら手遅れになってしまった。つまり、分かっていなかったのだ。メールというものは、返信がなければ相手が何を考えているのか分かりようがない。返信がないから相手が何を考えているか分からず、こちらが言葉を尽くした(つもりの)メールを送っても、それが相手の心に届いたのか、それと余計にもつれさせたのかも分からない。いや、相手が僕の言葉を受け取ってくれたのかすら分からない。メールは会話を打ちきるのも簡単にできる。朝から数え切れないほど携帯電話を手に取る。でも携帯電話はじっと黙ったまま、ディスプレイのデジタル時計だけが無言で時を刻んでいた。
2005.08.24
コメント(1)
-
敵わない
敵うわけがない、勝てるわけがない。本心からそう思った。伯父のPCがおかしくなったというので、メンテナンスに呼ばれる。久しぶりに触るWindows98に軽い戸惑いを覚えながらもとりあえず応急処置を施し、リビングでお茶。ケーキを戴きながらミニチュアダックスフンドのココと遊ぶ。テレビでは駒大苫小牧の逆転をアナウンサーが興奮して叫んでいた。しばらくココを膝に抱いてテレビ桟敷での野球観戦をしていたら、さっきまで一緒にココと遊んでいた伯父の孫、従兄弟の子どもである真帆ちゃんは、ココを僕に取られて退屈したのか、マンガ雑誌を読み始めていた。どんなマンガを読んでいるのかと、テーブルの上に置かれた「ちゃお」の先月号を手にとってパラパラ捲ってみる。幾つかさらりと流し読みしていくうちに、僕は思わず唸っていた。いや、敵わないな、と思ったのだ。そこにあったのは、恋愛マンガだった。恋愛マンガを小学2年生が読んでいる。僕の小学2年生と言えば、確かドラえもんに夢中になっていた頃だ。愛読誌のコロコロコミックには、恋愛マンガなんか一つもなかった(その頃は)。きっと、僕が小学2年生の頃の教室では、僕がドラえもんの道具でこんなのはどうだろうなんて考えていた横で、女子たちは恋愛マンガを読みながら恋愛のイメージトレーニングに励んでいたんだろう。敵うわけがない。男が、というか少なくとも僕は、恋愛の駆け引きや恋愛の進め方で女に勝てるわけがない。年季が違いすぎる。もう、僕はこの場で両手を挙げて白旗を振りたい気分だった。僕がは小さくため息をつきながらマンガをテーブルに戻す。隣の真帆ちゃんは不思議そうな顔で僕を見上げると、僕の膝の上のココにちょっかいを出し始めた。
2005.08.17
コメント(2)
-
夕景
幸せはきままな夢の一雫ネビル・シュートの『パイド・パイパー』を読んでいたらこんな言葉が出てきた。イギリスでは食前酒についてこんなことを言うらしい。この言葉がなぜ食前酒に結びつくかは分からないけれど、手帳の片隅にでも書き残して置きたいような言葉だった。清少納言は「夏は夕暮れ」と言っているけど、夏の夕暮れの美しさは千年後の今も変わっていないと思う。一秒ごとに色が変わる風景の、夜が足下から空に広がっていく様を眺めながら、アペリティフなりビールなりを飲むのは、夏ならではの楽しみだと思う。手元が暗くなってきたのを合図に、ゆがいたソーセージとマスタードを皿に並べ、素焼きのビアジョッキを傾けながら窓の外を眺めるのは、夏の日の夢の一雫。
2005.08.11
コメント(0)
-
蝉の声
昭和20年8月9日。長崎市内から見て稲佐山の裏側で、一人の少年が蝉取りをしていた。まさに「しぐれ」という言葉がふさわしい山いっぱいに響き渡る蝉の鳴き声の中、少年らしいひたむきさと狩猟本能で蝉を追いかけ回していたという。蝉はたくさん捕れた。籠いっぱいになっても、少年の狩猟本能は満足しない。新たな獲物を求めて息を潜めているとき、山裾が光った。刹那に、しかし鮮やかに。そしてその光りに煽られたかのように、生暖かい風が少年を通りすぎていった。そんな時でも蝉は鳴き続けていたという。うるさいくらいに、自分たちの生を鼓舞し、自分たちはここで生きていると訴えるかのように。やがて少年は大人になり、この話をいろいろな人にしたそうだが、誰も信じなかったそうだ。あんな時に蝉が生きていたわけがないと。だが、その話を聞いた中にいた一人の青年はその話に深い感銘を受けたのだろう。後年、青年はそのエピソードを織り込んだ曲を作り、毎年8月6日、広島に原爆が落ちた日に、同じ被爆地である長崎でこの曲を歌っている。 蝉は鳴き続けていたと彼は言った あんな日に蝉はまだ鳴き続けていたと 短い命惜しむように 惜しむように鳴き続けていたと (さだまさし「広島の空」から)今年もまた夏がやってきた。テレビでは広島と長崎の様子が流れ、敬虔な鎮魂と未来への希求の儀式が伝えられる。世界へ向かって放たれたメッセージを伝えるマイクは、蝉の声も拾っていた。あれから60回目の夏も、蝉は鳴き続けている。澄み切った夏空に、己の命を刻み込むように。*毎年さだまさしさんが8月6日に長崎で行っている野外コンサート、 「夏・長崎から」の模様が今年もNHK-BSで放送されます。 「平和の祈り 2005夏・長崎から」 8月13日(土) 13:00~16:30 NHK-BS2
2005.08.09
コメント(0)
-
遠花火 ── ノスタルジア・スケッチ XVI ──
夕焼け空にヒグラシの声が溶けて夜になる。夕食後、エアコンで淀んだ空気を夜気と入れ換えようと窓を開けると、ポン、ポン、と花火の音が聞こえてきた。窓から身を乗り出して見回すが、屋根の隙間には夜があるだけだった。はるか遠くの花は、見えない。だが、耳を澄ませば、遙か遠くの花がまぶたに浮かんでは消えていく。高校時代、北国の夏はここほどではないがやはり暑く、熱気のこもった音楽室で、入道雲を見ながら秋のコンクールに向けて練習に励んでいた。午前中の練習が終わり、昼食となる。昼食はパートで固まって摂ったり、少人数の部だったから全員で車座になって摂ったりもしたけれど、その時は自然に学年で固まる形となった。最後の夏休み、最後のコンクールや受験のことも気にはなっていたけれど、ずっと一緒にやってきた仲間が集まったのだ。そう言ったことは一切忘れて、他愛のない話をスパイスにランチは和気あいあいと続いた。そんな中、だれかがふいにこんなことを言い出した。「花火、行かない?」その日は市民公園側の河原で市の花火大会があった。その花火のように、賛同の喚声がわっと広がる。そうなるとこういう時に活躍する仲間がイニシアチブを取って、あっという間に集合場所と集合時間が決まった。部長の僕の権限で部活が1時間早く終わり、とりあえず散会。僕もいったん家に帰り、学生服から私服に着替え、集合場所へ向かう。陽射しの弱りはじめた空の下、はやる心を煽るように、自転車を漕ぐ足に力が入る。3年になって初めて同じクラスになってから、ずっと気になっている子がいた。今は他にやることがあるから、と自分の弱気に言い訳しながらも温め続けていた思いだった。市民公園の中にある図書館の駐輪場に自転車を止め、先に来ていた仲間とまだ来ない仲間を待つ。集合時間にはまだ間があったけど、どんどん膨らむ河原へ向かう人の波に少しずつ焦りを覚えはじめていた。時間ギリギリになって、あの子が親友と一緒にやって来た。あの子を見た仲間から、冷やかすような喚声が上がる。彼女だけが、髪を上げ浴衣を着て現れたのだ。男子は眩しい気恥ずかしさに顔を伏せ気味にちら見し、女子は自分も着てくればよかったと羨ましそうに話しかける。全員集まったところで河原に移動。もういっぱいにふくれた河原ではなく、近くの見晴らしのいい土手から花火を眺めることになった。僕は隠し味程度の作為の混じった自然な流れに沿って、彼女の隣に並んだ。まだ昼の名残が山の稜線を微かに染める中、最初の花火が上がる。花火のドンと地に響く声に続いて一斉におおっと言う歓声が空に向かって続く中、彼女の横顔が赤く染まった。花火を見終わった後は、しばらく公園内の縁日で遊んだが、賑やかな公園を歩いているときも、彼女の下駄の音だけははっきりと聞こえていた。今となっては、彼女の浴衣の柄すらもよく憶えていない。だが、夏の雑踏の中、女性の下駄の音が聞こえてくると、ふいに彼女の下駄の音が蘇り、あの時の気恥ずかしさと彼女の横顔が浮かんでくる。遙か遠くから聞こえてくる、遠花火のような音がほの甘く響く。
2005.08.08
コメント(0)
-
朝
朝、少し静かで少し空気が透き通って見える校舎に入ると、なぜか少しの戸惑いと少しの気恥ずかしさを感じる。定時制に来る前は毎朝のように見てきた風景なのに、いつものようにお昼休みの喧噪の中を出勤するのとは違っているから、足音もつい抑え気味になる。職員室もどことなくすがすがしい空気が流れていて、まだ半分眠っている頭にも心地よい。カバンを置いて、眠気覚ましの一服へといつもの非常階段へ。朝露に濡れてひんやりした壁に手を添えながら、最上階手前の踊り場に向かう。今日も暑くなりそうな予感を孕んだ風に吹かれながら下を見下ろすと、グラウンドでは陸上部員がトラックにハードルを並べ、野球部員が秋に向けてキャッチボールをはじめている。彼らの先には、竈に入れたばかりのパン生地のような入道雲が、朝日を浴びてゆっくり立ち上がろうとしていた。
2005.08.03
コメント(0)
-
夜の海へ
明るく照らされた水槽の中を熱帯魚が泳いでいる。あるものは光りに己の身を輝かせ、あるものは鮮やかな衣をひらひらなびかせながら、1m四方の閉ざされた海の中を泳いでいる。そんな熱帯魚の泳ぐ様をぼんやり眺めていたら、店の入り口あたりが少し騒がしくなってきたことに気付いた。顔を向けると、浴衣を着た女性が何人もいる。店員が次々と席に案内していくが、浴衣の群れはどんどん入ってきて、あっという間に入り口あたりに順番待ちの混雑ができる。ちょっとしたラッシュアワーを眺めていたら、この近くで花火大会があったことを思いだした。花火見物の帰り、仲間たちのおしゃべりや混み合う電車を避けるためにこの駅前のファミレスに立ち寄った人たちなのだろう。順番待ちの群れはどんどん膨らみ、中には店に入ってもすぐに立ち去る人も出てきた。それを見ていると、大きなテーブルを独り占めしていることに少し罪悪感を覚える。僕は伝票を手に、レジへ向かった。車に戻りながら、振り返って店のほうに目を向けると、明るいガラスの中は、鮮やかなTシャツや浴衣が行き交う。それを見ていたら、さっき見た水槽の熱帯魚が重なった。あの熱帯魚たちは、ここでしばし泳いだ後、水槽から放たれるのだろう。夜の海へ向かって。
2005.08.02
コメント(0)
-
石綿の網
アスベストという言葉を初めて聞いたのは、中学の理科の授業だった。当時教わっていた先生は何となくピーター・フォークに似た雰囲気を持っていて、どこか飄々としていてちょっと粗野だけど下卑たところは全くない、当時の僕の理想の大人像の一人でもあった。その時何を勉強していたのか、どんな話の流れでアスベストが出てきたのかは、よく憶えていなくて、雑談の好きな先生だったから何かのついでという感じで脈絡もなく口にしたのかもしれない。それなのにアスベストという言葉をはっきり憶えているのは、学校にはアスベストという危険なものが普通に使われていると聞かされたからだ。うちの学校はまだできて数年だから大丈夫だけど、古い学校には壁にヒビが入って、壁の中のアスベストがむき出しになっているところもあると言われ、思慮の足りない子どもだった僕は、ただ単純に自分が新しい学校にいることを幸運に思ったりした。ただ、先生はその後で、アスベストはこの学校でも誰もが触れられるような場所に使われている、と言った。それは、理科の実験などで使う、アルコールランプやガスバーナーでビーカーを温めるときにビーカーを乗せる網だ。理科の時間のことを思い出して欲しいのだが、そうした網には中心に白い円があったのを憶えている人も多いと思う。その白い部分がアスベストだ、と先生が口にした。だから、その網を使うときは炎が直接アスベストを焼くのだから、理科室にはアスベストを含んだ熱気が充満することになる、とも。そう言って先生は僕たち生徒を脅かした後、突然ニタリと笑い、だけど、去年か一昨年だかにアスベストの網は危険だからということで一斉に安全な網に取り替えられたから今は安全だ、と言われ、教室中から安堵の息が聞こえた。自分が安全だということで安心したせいだろう。その後先生が言われた、だけど理科の先生は何十年もアスベストの空気を吸ってきたわけだから、他の教科の先生よりも早く死ぬかもしれない、という言葉は、ただ聞き流すだけだった。それ以来、本当に久しぶりにアスベストという言葉をニュースで聞き、連日のアスベスト報道を見るにつれ、アスベストの危険性はかなり前から指摘されていたのに、最近まで野放しに近い状態で、未だに苦しんでいる人が多いことに、愕然とさせられ、怒りすら覚える。そして、アスベストのことを教えてくれたあの先生は今もお元気だろうか、と考えるのだ。掠れかけた記憶の中で、小柄で頬がこけた感じのするあの先生が「理科の先生は早く死ぬかもしれない」と言ったとき口元に浮かんでた笑みには、自虐的な笑いが混ざっていたように思え、僕は身体をぶるりと震わせた。
2005.07.29
コメント(0)
-
ショートショートはじめました
きまぐれでショートショートを書き、せっかくだからとホームページビルダービルダーの練習も兼ねて、そっとネットの片隅に置いてみました。お暇で奇特な方がいらっしゃいましたら、読んでいただければ、と思います。ショートショートはこちらに置いてあります。よろしければ、下のコメントかメールで感想を寄せていただけると、嬉しいです。ホームページを作るって、技術よりもセンスだな、と思う今日この頃。
2005.07.25
コメント(0)
-
社会科教員のつぶやき
ふとした気まぐれで、この週末はホームページビルダーをいじる。あれ、なんかうまくいかないぞ。……2学期は情報の授業でホームページの作り方を教えないといけないのに。
2005.07.24
コメント(0)
-
A4 ─ 1枚
うだるような暑さの中、うんざりする成績会議は進む。赤点や欠席、欠課時数の多い生徒、1学期中に移動(退学、休学)のあった生徒の最終確認が行われたところで会議は終了し、通知表の印刷となる。僕の手元に成績関係のデータが入ったMOが回ってきて、LANに繋がっていないPCを使って印刷開始。全日制だと業者に印刷してもらった通知表に担任が手書きで成績を書き込むところが多いが、うちでは僕が作ったExcelの表を印刷して通知表として渡す。表はマクロを使って成績データにリンクしてあり、学年と出席番号だけ打ち込めば、生徒の氏名から成績まで自動で表示される。印刷するのは、担任が指定した上質紙や、わら半紙。事務室の横の倉庫に行けば、500枚や1000枚ずつ袋に入って積み上げてある、ごく普通の紙。はっきり言ってしまえば、授業プリントやお知らせの印刷に使うのと同じ紙だ。わざわざ上等な紙を使うのがもったいないと言うことで、こんな紙を使うようになったのだが、なぜもったいないかというと、別に定時制の通知表だからと言うわけではなく、通知表の回収率が悪いからだ。全日制のように、学期の終わりに受け取った通知表を保護者に見せ、新学期には保護者の印鑑を貰って学校に戻すということを、ちゃんとできる生徒が少ない。だから、通知表はお知らせの紙と同じように生徒を通じて保護者に渡すだけで、回収しないことにしているので、ごく普通の倉庫にいくらでも置いてある紙を使う。回収の悪さについては、県下有数の進学校であるうちの全日制も通知表の回収率が下がっていると言うから、別に定時制だけの問題ではなく、最近の高校生やその保護者全体の問題だろう。プリンターから排出された通知表を眺め、その左上に記された氏名の生徒の顔を思い浮かべる。これらは、ある生徒にとっては1学期自分がどれくらい頑張ったかを確認するものであり、ある生徒には赤点を免れたことや、欠課時数の数を確認するものであり、ある生徒にはただ単に数字が羅列してある紙だったりする。果たして、子の生徒にとって通知表はなんなんだろう、と考える。1学年分の印刷が終わったところで、抜けや汚れがないことを確認して、担任に渡す。受け取った先生は、すぐに生徒所見を通知表に書き込む。生徒所見は、今でも手書きの人がほとんどで、一つ一つ刻まれた文字の持つ意味や思いは、どんな紙を使った通知表でも変わりはない。
2005.07.19
コメント(0)
-
天文薄明
天文薄明 地平線(水平線)下の太陽高度が-18°となる時刻.太陽光の影響が全くなくなり完全に暗くなる時刻. (財団法人日本水路協会 海洋情報研究センターHPより)2005年7月19日の東京の日の出は4時39分。同じ日の東京の天文薄明は2時55分。実は、日の出の2時間近く前から、朝は始まっている。暗い道を進んでいると思っていても、どこかで微かな光が差し始めている。その光は静かに力を増し、暗い道はゆっくり明るい道へと変わり始める。
2005.07.18
コメント(0)
-
チケットの裏側
もし手元に展覧会のチケットがあったら、ちょっと裏返して見て欲しい。細々とした注意事項の中に「会場内での鉛筆以外の筆記用具の使用はご遠慮ください」と書いてあると思う。なぜ会場内では鉛筆しか使ってはいけないのか?それは、万年筆などインクを使った筆記具の場合、誤ってインクが飛び展示物を汚す危険があるからだとか。ルーブル美術館展のチケットを見ていたら、学部時代の博物館学の授業で聞いたことを思い出す。明日は一日休みを取って、横浜へジェラールを見に行く。
2005.07.14
コメント(1)
-
言葉のTPO
天文22年(1553)、美濃国の戦国武将斎藤道三は娘婿である織田信長と初めて会見することとなった。衣の袖を脱ぎ、人前でもはばからず立ったまま瓜などを食い、仲間と騒ぎながら練り歩く信長のうつけぶりは道三の耳まで届いており、道三は娘婿とはいえこの会見に余り乗り気ではなかったらしい。実際、道三は衣服のだらしないうつけ者と会うのだからと、平服のまま会見の場に姿を現している。ところが、会見場で道三が眼にしたのは、正装をした信長の姿だった。更に会見における信長の作法も見事であり、道三はその間汗をかき通しだったらしい。会見の後、道三は過信に信長の印象を聞かれ、「自分の子どもたちは将来信長に仕えることになるだろう」と答えたという。文化庁が平成7年度から毎年行っている「国語に関する世論調査」の平成15年度調査結果が発表された。この調査に関する報道も、それぞれ報道機関における着目点の違いが現れて面白いのだが、例えばTBSの「NEWS23」は「若者における言葉の乱れ」が伺えるものとして取り上げていた。最近の日本語ブームや、日本語を扱ったバラエティ番組が増えてきたこともあってか、「正しい日本語とは何か」とか、「所謂『言葉の乱れ』は間違いと言い切れるのか」という議論が起こっているが、今回の文化庁の調査でまたそれが活発化するのだろうか。あくまで個人的な意見だが、国語学的な観点からは置いておくとして、「正しい日本語」という議論は、あまり意味がないと思っている。言葉は意志の伝達ツールであるわけだから、「正しい日本語」か「間違った日本語」の前に「通じる日本語」と「通じない日本語」があり、また相手や状況によっては、不快感や違和感を与える言葉遣いというものがあるのではないだろうか。例えば、近年は「いい」という意味でも使われるようになった「やばい」だが、普通に使う人が増えたと言っても、その使い方を知らない人や違和感を覚える人がいるのは当たり前で、その人たちがその言葉遣いは間違いだというのに「最近の日本語はこうなのだから、違和感を訴えるのは間違っている」と逆に批判するべきではないだろう。また、同年代の人たちとファミレスで話す言葉と、かなり年の離れた初対面の相手と話す言葉は、違っているのが普通だ。相手や状況において使うべき言葉や使うべきではない言葉は、自ずと変わってくる。それなのに、そうした言葉選びに無頓着だったり、自分の真意がうまく伝わらないのは自分の言葉をちゃんと受け止めない相手が悪いと思いこむことが多いように思う。ここまでくると、もう単に言葉の問題ではない。所謂「若者言葉」や「言葉の乱れ」の問題は、高校生や大学生が限られた身近な人としかコミュニケーションが取れず、それ以外の人とコミュニケーションを取ろうしてもその場にふさわしい言葉を持ち合わせていない、所謂コミュニケーション能力の不足や、どんな状況に置かれてもその状況を把握しようとせず我を通そうとするコミュニケーションに対する意識の欠如の問題だろう。これは、かなり深刻な問題だと僕は思っている。学校で生徒たちと話しているとき、まるで同年代の友達と話すような言葉を使う生徒が多い。そんな時僕は冒頭の斎藤道三と織田信長の会見のエピソードが頭に浮かび、相手や状況によってそれぞれふさわしい言葉遣いがあると言いながら言葉遣いを注意することがあるが、ほとんどの生徒は何を注意されたのか理解できず、戸惑った顔をしている。
2005.07.12
コメント(1)
-
ちょっと一息
本日にて授業は全部終了。後は期末試験をやって、成績つけて、穴埋め的な行事をこなせば、1学期は終了。1学期は新入生はいるし、各学年1クラスと言っても顔ぶれは若干変わってるから学校がなかなか落ち着かず、日々生徒への対応に追われて慌ただしく過ぎていく。だから、1学期の終わりが見えてくると、他の学期よりもほっとする気持ちが強いと思う。特にこの1週間は期末試験の準備やちょっとした事件に追われて、本当に気の休まるときがなかった。家に帰ってからも学校のことを引きずってしまい、PCや本を開いても、そこには文字や絵が無造作に並んでいるようにしか見えなくて、気に入った曲をかけてもやかましいとしか思えないときもあって、妙にハイになったかと思えば妙に沈んでしまうときもあった。でも、ま、とりあえず一段落つきました。夏休みまでまだもうちょっとあるけれど、明日も仕事があるけれど、仕事の前日は飲まないことに決めてるけれど、今夜はウィスキーをワンショット。綾戸智絵でも聴きながら飲みましょう。
2005.07.04
コメント(0)
-
お気をつけあれ
ツツジの花も散り緑の葉だけが残った生け垣に、夏の陽射しが光る。梅雨も明けきらないのに一足早く訪れた夏の日に、廊下を歩く全日制の生徒たちの足取りもほんの少しスローに見える。定時制は授業の開始が陽射しの弱くなる夕方からだからまだ楽だけれど(それでも今の時季は1,2時間目はまだ日が出ているから教室内は暑い)、スタートは午後1時からという一日で最も暑い時間帯から始まるので、特に年配の先生方にはキツいらしい。全日制なら朝のまだそれほど気温の高くない頃から仕事や授業をしながら徐々に身体を慣らしていくという形になるのに、定時制だと午前中締め切って気温が上がっている上に冷房もなく風通しの悪い職員室でいきなり仕事をしろというのは、はっきり言って酷だ。僕も1時の打ち合わせが終わってから職員室で汗だくになって期末試験の問題を作っていたけど、頭がぼーっとなって全く集中できなかった。そう言えば、午前中、全日制の生徒が授業中に倒れたらしい。体育の時間にグラウンドで、じゃない。数学の時間に教室で、だ。まだ夏の暑さに身体が慣れていないこの時期、ちょっとしたことで体調を崩したり、急な目まいに襲われたりすることが多い。どうぞ、お気をつけあれ。
2005.06.27
コメント(0)
-
愛読書の定義
郵便受けの錆びた金属の唇が おい と軋んで閉じ鋭いハサミで開封してみれば やあ軽やかな足取りの文章を綴られている「水の都の流れ星」の著者であるきらさんからののどかなご挨拶につづいいて「愛読書について定義してください」(以上、川崎洋さんの詩「愛の定義」のパロディでした)というわけで、きらさんから受け取った「BOOK BATON」に答えたいと思います。1.持っている本の冊数う~ん。何冊あるんでしょう?とりあえず部屋には80×180の本棚が3つ。ここには学部、大学院時代に買った日本史の史料や論文集で埋まっています(最近手に取る機会が減ったのが少し悔しい)。あと、部屋には本棚に入りきらない本が段ボールに4つ。他にも本棚の上やノートPCを買ってから使わなくなったPCデスクの上、本棚の前の床、枕元に積み上げられています。そんなところからご想像ください。あ、あと学部以前に買った小説を中心に詰めた段ボールが実家に数箱あったっけ。2.今読みかけの本 or 読もうと思っている本歩いて数分のところに図書館があるので、最近読む本は新刊以外ここで借りて読んでいます。とりあえず今借りている本は、石村博子『「喪」を生きぬく』(2005 河出書房新社)川崎桃太『フロイスの見た戦国日本』(2003 中央公論新社)鹿島茂『怪帝ナポレオンIII世 第二帝政全史』(2004 講談社)中村健二『カクテルの贈り物』(1996 オリジン社)青木淳悟『四十日と四十夜のメルヘン』(2005 新潮社)江國香織『とるにたらないものもの』(2003 集英社) 『間宮兄弟』(2004 小学館)大崎善生『ロックンロール』(2003 マガジンハウス)多和田葉子『旅をする裸の眼』2004 講談社)山田太一『異人たちとの夏』(1987 新潮社)石村さんのは、愛する家族を亡くした人たちがどのようにその悲しみと向き合ったかを追ったノンフィクション。最初、授業の資料として軽い気持ちで読み始めたけど、すぐに居住まいを正してここに描かれた思いに向き合わねばいけないような気になる本です。川崎さんのは、ここ数年織豊時代のキリスト教について調べている関係で借り、『馬車が買いたい』(1990 白水社)以来その軽妙洒脱な文章が大ファンの鹿島さんの話題の本に、中村さんの見ているだけで心地酔いを感じるカクテルの写真集。小説は知り合いに勧められたり、図書館の本棚で思わず手に取ったもの。何分移り気なもので(笑)、一冊読み終えてから次へということができません。ですから、読みかけのままほったらかしの本もたくさんあります(笑)3.最後に買った本(既読、未読問わず)谷川俊太郎・文 大竹伸朗・絵 『んぐまーま』(2003 クレヨンハウス)甥の2歳の誕生日プレゼントとして買ったもの。自分が読むために買ったのだったら、島本理生『ナラタージュ』(2005 角川書店)。この本、まだ半年ありますけど、今年のマイベスト決定です。いや、すごい。4.特別な思い入れのある本、心に残っている本5冊(まで)これは難しい。たくさんありすぎて、とても5冊に絞れません。ですので、一応高校の教師をしていることにひっかけて、十代の頃の愛読書5冊とさせてください。・常盤新平『遠いアメリカ』(1986 講談社)まだピザもハンバーガーもティッシュも遠い世界のものだった時代の、翻訳家に憧れる青年の青春物語。漠然とした夢はあるけれどその夢の遠さに恐れおののき、またその夢に向かってなかなか一歩を踏み出せないことに自己嫌悪になる。いつの時代も変わらぬ青春像がここにあります。・上温湯隆『サハラに死す』(1975 時事通信社)海外、それもアフリカや南米といった辺境の土地の旅行記ばかりを読み漁っていた時期がありました。その中でも忘れられない一冊がこれ。ラクダに乗ってサハラ砂漠を横断しようとし斃れた青年の日記をまとめたもの。サハラ砂漠という想像すら難しい風景に魅せられ、何十回読み返したか分かりません。・連城三紀彦『恋文』(1984 新潮社)高校生の頃はミステリーばかり読んでいて、この本もミステリー作家の連城三紀彦が恋愛小説も書いていたんだ、という気持ちで手に取ったもの。当時は面白かったけどそれほど響くものはなかったけれど、一昨年ある女性に勧めるために再読したら夢中で一気読みし、「私の叔父さん」では電車内でぼろぼろ泣いてしまいました。ほとんど人のいないボックスシートの車両でよかった(笑)・中島敦『山月記』(1942)高校2年の現代文の授業で出会って以来何度読み返したか分からない座右の書。現代文の先生の「この李徴はな、お前たちと同じなんだよ」という言葉。今ならよく分かるし、未だに李徴のままだと思うこともしばしば。・中沢新一『雪片曲線論』(1988 中央公論社)十代の一冊といわれたら迷わずこれ。高校三年だからどこまで理解できたかは心許ないけど、人の思考はここまで飛翔できるのかとただ、ただ感嘆するしかなかった。これ以外にも、書名が分からなくて挙げられなかった現代詩人の叢書や、池澤夏樹、遠藤周作、北杜夫、アーウィン・ショウ、太宰治、村上春樹、西江雅之、etc.他にも忘れているけど僕の中では大切な本がいっぱいあります。5.次にまわす人5人までこれも困りました。本棚を覗いてみたいと思う人をピックアップしていったけど、十人から先絞ることができません。いっそのこと十人全員書いてみようかと思いましたが、さすがにそれはちょっと、と思い、くじ引きで次の五人の方に次のバトンを渡したいと思います。「紫苑の日記は、”紫苑の吐息” 」の紫苑さん「ちぇんしんの日々是好日」のちぇんしんさん「和妓の枕草子」の和妓さん「アメリカで教育学」の登別市立青葉小学校の卒業生のやすさん「reversible」のゆかさんこちらが勝手に指名していますので、リンク先に回答があるとは限りませんので、その点はご了承ください。それにしても、本について語るのは楽しいですね。上の文章も、どの本を挙げようかと迷ったり、だれにこのバトンを回そうかと考えるのは、至福のひとときでした。これから、読み終わった後誰かに語りたくなるような本に出会ったら、ここに書くようにしようかな。きらさん、楽しい機会をありがとうございました。
2005.06.25
コメント(1)
-
赤チンキ ── ノスタルジア・スケッチ XV ──
たぶん僕らが赤チンキ、通称赤チンを使った最後の世代だろう。とはいっても僕も幼稚園に入った頃には塗られた記憶がないから、赤チンが日常的に使われた世代には入らないのかもしれない。小さい傷にはオロナインの白が塗られ、駆けているときに転んでできた大きな擦り傷には赤チンが塗られたような気がする。僕の赤チンの記憶は、肘や膝に塗られた赤い色だ。あの赤は子供心にもあの毒々しい感じがして嫌だった憶えがあるが、ビンの中では黒に近いドロリとしたものが蓋についている刷毛で塗られると途端に透き通った赤になるのが不思議で、塗られるときは嫌だと思いつつもじっと見ていた記憶がある。塗られた赤チンの色は画用紙に走らせた赤絵の具や目の前にかざした赤セロファンの赤とも違い、鮮やかな赤が日の光に映え(今なら薄いラメでも入っているようなと表現するだろうか)、毒々しくはあったがどこか頼もしい色だった。その頼もしさは、夢中になって遊んでいる最中、ふと肘や膝に赤チンがべったり塗られているのが目に入り、まるで転ばないようにと注意されているような気がして、転ばないようにというお守りのようにも思えた。と、ここまで書いて、そう言えば僕が憶えている赤チンは、むき出しになった肘や膝に塗られたものだったことに気付いた。むき出しになった肘や膝。赤チンの赤は、僕にとって夏の色だったのかもしれない。
2005.06.21
コメント(3)
-
梅雨の晴れ間の夕方は
久しぶりに顔を出した太陽が空気をさっと絞るのか、朝からからりと乾いた空気が辺りを包む。やがて日が傾いてくると、それにあわせて気温もさがり、涼風が部屋に流れ込む。そんな夕方は今すぐやることもなく、ちょっと眠気に包まれていれば、なおいい。窓辺のベッドに横になり、アイマスク代わりに左腕を眼の辺り乗せて目を閉じる。まどろむ僕を涼風が撫でている。子守歌のように撫でている。
2005.06.19
コメント(0)
-
次の季節へ
天気予報で梅雨という言葉が聞こえ始めたある日、いつもなら店先の花をちらりと見て通り過ぎる花屋につい吸い込まれてしまう。この向日葵に引きつけられてしまったからだ。初夏という言葉で呼ばれるけれど夏にはまだ少し距離があるこの時期に、まるで夏の予告編のように鮮やかに咲いた向日葵。値もそれほど張らなかったので、一鉢を手にレジへ向かう。その夜、天気予報では雨と言っていたので、雨に濡れる前にと写真に撮る。夜の中の向日葵はどこか元気がなく、気のせいか花も少々俯きがち。翌々日の晴れた午後、向日葵にふさわしい空の下で改めて写真を撮る。夜の闇と雨を越えた向日葵は、元気に笑っていた。向日葵はやはり青い空と眩い光が似合う。向日葵にふさわしい季節は、すぐそこに、ちゃんと来ている。
2005.06.18
コメント(0)
全337件 (337件中 1-50件目)