What is a Unit Study?
(さすがに算数の1・2年はいわゆるワーク、 小学1・2年自由自在 算数 [ 小学教育研究会 ]
を使いました。これは学校のカリキュラムをガン無視した問題集なので、合う合わないがあります)
興味のある事象から、教科の概念にとらわれず自由に学びを深めていく学習法を単元学習というそうです。
たとえば、料理から化学、ゲームからプログラミング、ハイキングから地学など。
日々の生活の中から学びを見つけ出すという考え方は、昭和24-35年の間施行されていたようです。
教科書いまむかし 生活単元学習時代
日常生活に沿って学びが進んでいくので、「こんなの勉強して将来何の役に立つのか分からない」という「勉強あるある」が出ない学習法だね^^
うちの娘は化学好きなので、本棚に忍ばせたこの本を見つけてくれることを願う。

めんそーれ!化学 おばあと学んだ理科授業 [ 盛口 満 ]
我が家は今、科学漫画サバイバルシリーズにハマっていて、小2の娘は隅々まで、幼稚園年長の長男は漫画ページをメインに楽しく読んでいます。周回できる良本です。1200円くらいだから、そんなに値段高くないし。
娘は人体のサバイバルと山火事のサバイバル、長男は植物世界のサバイバルが好きで
学んだことを細かく教えてくれます。

人体のサバイバル(1) 生き残り作戦 (かがくるBOOK 科学漫画サバイバルシリーズ) [ ゴムドリco. ]
先日買い置きした自由自在を本棚から出して
「もうちょっと詳しく知りたかったら、ここらへんに書いてあるかもね~」
「あれ、違ったかな?どこやったかな~忘れた、まいっか」とフワッと言って放置したら
夜中起きた時に一生懸命調べてました。そして頭が疲れたのか、そのあとスッと寝ました^^
次の日。
「読み込むのは大変だから、読もうとせずにパラパラ~とめくって、ちょっと気になったとこに付箋を貼って、パラパラめくるのを7回も繰り返せばこの分厚い1冊頭に入っちゃうかもね」
と言ったんですね。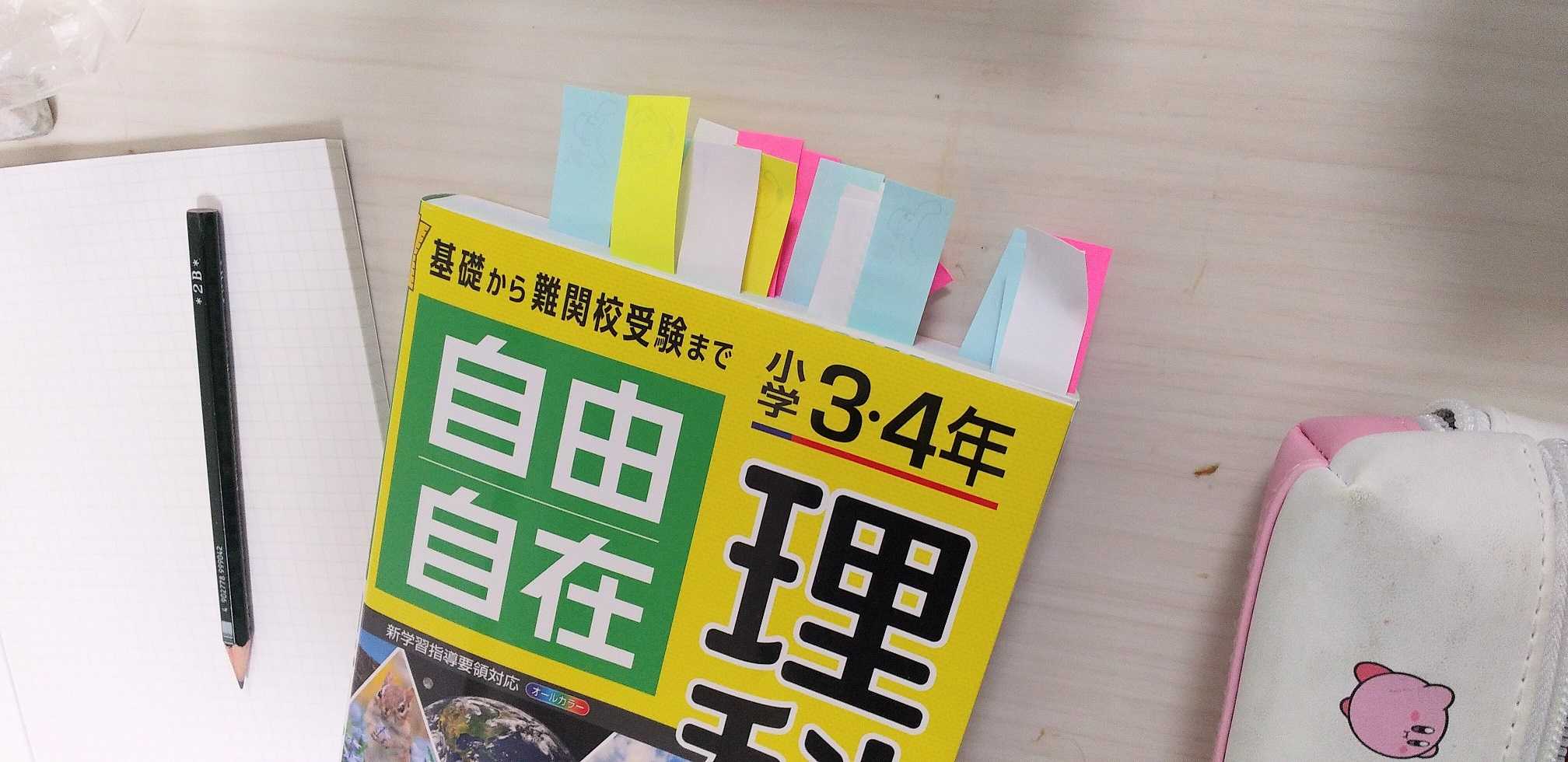
で、朝起きて見てみると、付箋だらけになってました。「付箋付けたとこは、後からゆっくり読み返すところ」だそうです。辞書的に使うのが良いと思うね。

小学3・4年 自由自在 理科 [ 小学教育研究会 ]
ホームスクールするといいながら、完全には吹っ切れてなくて
ちょいちょい学校ネタを娘に吹っ掛けては喧嘩しちゃうんですけど
学校に行ってくれたら私が楽なだけで、娘にとっては全然良いこと無いし、
学校に行かないという権利を侵害するのはダメだから、もう腹をくくるしかないですね^^;
つづきます
PR
Freepage List
Category
雑記
(139)お役立ちグッズ
(43)きょうのごはんを紹介!
(42)-★実際に使った育児準備品まとめ★
(5)-★ねんねこ半纏について★
(9)-★昔ながらのおんぶ紐について★
(2)-★手作りグッズ★
(6)転勤妻の仕事
(39)結婚・婚活
(13)サイトから表示したくない広告を消す方法
(1)マタニティ日記
(77)マタニティ日記【2人目】
(42)ドタバタ育児日記(0~2歳前まで)
(143)-★ベビーグッズ★
(7)ドタバタ育児日記(2歳)
(43)ドタバタ育児日記娘3歳~
(24)ドタバタ育児日記☆息子編
(43)鉄分強化メニュー
(6)きもの大好き!
(15)ダイエット
(5)3人目
(31)アラサーの美容ネタ
(2)貿易実務・TOEIC
(8)家計簿
(4)投資・NISA関連
(20)通関士試験
(0)Comments
Keyword Search
Calendar











