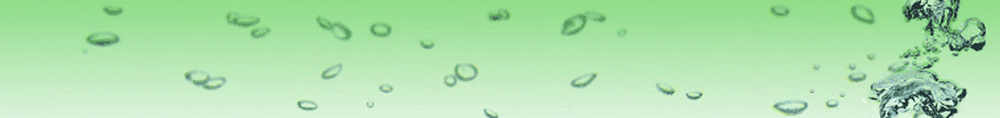ウェブ援隊総本部
年末の振り返りは今でも毎年こちらに書いているので、こちらで復活しようと思います。
ということで本題
本書は東條英機のひ孫にあたる東條英利さんと、近代史研究科であり神社の知識も深い久野潤先生の対談本。
まず率直な感想で言うと、いかに自分がまだ歪んだ歴史観から脱せておらず、また知識も浅いことを認識し、忸怩たる思いだ。対談本とあって読みやすく、一気に2回読んだが、まだ咀嚼しきれていない。
そんな状況ではあるが整理したい。
【靖國神社の建立】
もとは地方での国士の殉難者を招魂祭として一時的に場を整えて執り行っていたものが、遂には恒久鎮座の社殿を構えるに至ったもので、建立は明治二年の東京招魂社が前身、靖國神社と社号を改めたのが明治十二年。
御柱は約二四六万六千あり、その大半はもちろん大東亜戦争での殉難者。ただし忘れてはならないのが、これは明治維新において国のために命を捧げた人達、例えば吉田松陰らも鎮座されているのであって、決して大東亜戦争賛美のための神社ではない。
【国士殉難者鎮魂のための神社】
そもそも日本の歴史を辿れば、殉難者を神様として祀るという行為は、神武東征の際に命を落とした瓊瓊杵尊を祀った龜山神社に端を発する。それ以来神話ではなく実在の人物が御祭神となる神社は数多く建立されてきた。
残念ながらルール上官軍側ではない人達は祀られていない。過去に西郷隆盛など賊軍とされた側の人たちも合祀してはどうかという動きがなかったわけではないが、結果としては未だ合祀されるに至ってない。
また、靖國神社には軍人以外が祀られているのも大きな特徴。
というわけで、靖國神社だけが明治以降にできた戦争賛美のための新たな風習という言説は、全くの嘘。
また形は違えど、殉難者を鎮魂し顕彰するという意味での石碑や博物館は世界各国に見られるものであって、日本だけが非難される話では決してない。
【靖國神社のイメージ】
靖國神社は、歴史ではなく公民で、国際問題に取り上げられる神社として教育される。靖国問題として学生は靖國神社を認識する。これが一番悪いイメージを植え付けられる諸悪の根源。ただし最近では学生のアンケート結果からも一時期より靖國神社に対しフラットに考えることが出来る土壌が出来ているようだ。
戦後取り壊しの対象になりかけた靖國神社の生き残り戦術でもあったかもしれないが、盆踊りをやって、楽しく慰霊しようじゃないか、という祭りが始まって、今ではみたままつりといって、年に一度催される夏の風物詩的イベントが開催されており、殉難者たちからしても、このように楽しい場を提供する神社という立ち位置になることは歓迎されるべきことではないかとのご意見であった。
【靖国問題と政教分離】
度々神社や奉納に公金が投じられることで訴訟に発展することがあるようだ。政教分離に抵触するからというのが表向きの理由だが、実際は共産系議員の偏った意図によって訴訟を起こしているようだ。全ての訴訟において違法の判決が出ているわけではないが、難しい線引きの中でそれぞれ判決が下されている。
ただ、神道は経典もなければ、戒律もなく、およそ宗教的な色はなく、日本の慣習と言っていいようなもの。これを宗教として扱い、神社を宗教法人として内務省管轄から外し、結局神社そのものの影響力を日本から消し、弱体化させるのが、つまりは共産党の活動なのだ。
また、A級戦犯合祀を中国側が抗議する動きもあるが、これも元を辿れば中曽根元総理が参拝した時に、朝日新聞が猛反発、これに呼応して中国側が反発。これ以降毎年のように靖國神社参拝が問題化した。
さらには在任期間中参拝し続けた小泉元首相の靖国参拝最後の年に、日経新聞記者が富田メモという天皇陛下の非公式の言葉の記録が流出し、A級戦犯への議論が紛糾した。
このようにして靖国問題は国内の反日分子や経済的関係性から作られ、大きくされている。
【日本を守ってきた人への感謝】
神道の根底にあるのは自然信仰、皇祖霊信仰、御霊信仰などであり、それが日本人の信仰心を形作ってきた。言い換えると、おかげさまの心を大事にしてきたのだが、今その心が薄れつつある。
今や人は、自分の人生一度きり、自分のためにやりたい事をやろう、という風潮が主流だが、果たして幸せを掴むことは出来ているのだろうか。おかげさまの心があると、いかに人や自然に生かされているかに気付くことができ、人に感謝する心が生まれてくる。なによりご先祖様を大切にすることは、今の自分の存在に感謝する心である。
神社のお参りに打算的に願い事する人も多いようだが、感謝を述べ、またお礼参りをして神様に報告をする、といった姿勢で参拝するのが本来のあるべき姿。
この辺りは異論の余地もないことで、私も以前より共感する点だ。
【自問自答と雑感】
恐らく本来功績を残して神社に祀られるのは、その功績を称える賛同者が多い、また時代が過ぎて振り返った時に、その功績が大きい場合に、その気持ちが神社建立を後押しするし、人々の支えによってその存続が可能となる。
今の私の明治維新の理解は、やはりペリー来航以来、西洋列強に立ち向かうべく、国のあり方を見直さなければ飲み込まれてしまう恐れがあったからこそ、一致団結する必要があり、結果として大政奉還という国の中心的存在を天皇陛下に戻すに至った。その結果として日本は急激に近代化を遂げ、西洋列強と肩を並べ、遂には日露戦争に勝った。確かに日本のために戦った人がそこにはいた。
しかし大東亜戦争時は、メディアが戦争を煽り人々を熱狂させ、軍部は国のために殉難することこそが国民の進むべき道と洗脳し、現存の靖國神社に祀られるというある種の死後の魂をも保証する形で戦争に参加させた。そういう意味において、靖國神社は興奮剤として利用された点がないとは言えないだろう。
勿論これも今の価値観の人間が判断したらそう見えることなので、非難するわけではない。当時の世界情勢からすると、共産主義の脅威、西洋列強の傲慢さ、植民地化の恐れ、エネルギー安全保障の危機など、全方位で日本は危機に陥っており、より強固な団結は必要だった。
そう思うと、なるほど東條英機の幻の遺書にある、『しかし国際的の犯罪としては、無罪を主張した。いまも同感である。ただ力の前に屈服した。自分としては国民に対する責任を負って、満足して刑場に行く。ただこれにつき、同僚に責任を及ぼしたこと、また下級者にまでも刑が及んだことは実に残念である。天皇陛下に対し、また国民に対しても申し訳ないことで、深く謝罪する。』が全てなのかもしれない。軍部はある種今風に言うと、天皇陛下を政治利用したのであり、靖國神社も利用した。そして左翼風に言えば国民を捨て駒として戦わせ、靖國神社に祀られるという事を担保に、お国のために命を捧げさせた。横井庄一氏と小野田寛郎氏の二人が日本軍の生き残りとして見つかったが、この二人の対照的な主張、つまり一方は捧げさせられたのであり、もう一方は捧げたという受け取り方の差異こそが、当時の日本人の心情を物語っているのではないか。
この雑感を今後の思想構築の種としておく。