PR
Keyword Search
eco-blog 環境エン… 拓也@エコブログさん
ちあき!の徒然なる… ちあき1212さん
仕事に趣味に全力投… GARASHIさん
高原の営農日誌 fuji0522さん

普通救命講習でAEDの使い方を教わりました。
次男の小学校の昇降口にあったり、駅で見かけたりするAED((自動対外式除細動器)。誰がどうやって使うのかな、と思っていましたが、私たち市民が使うんですね。
意識なく倒れている人がいたら、救急車とAEDを手配しながら気道確保、呼吸の確認。
呼吸がなかったら人工呼吸と心肺蘇生。
AED到着したら電源を入れ、メッセージにしたがってパットを当てたりスイッチを入れたりします。 電気ショックが必要かどうかは機会が判断し、メッセージを出します。
「判断はどうやってするのだろう」というのが一番の不安だったので、それがあっけなくふきとびました。
初めて知ったこと → AEDは細動を止めるだけであって、そのあとただちに心肺蘇生を再開し、はじめて心臓が戻るそうです。 ショックを与えたあと、ぼけっとしていてはいけないそうです。
慣れている人が「AED持ってきてください!」と叫んだら、さっと持ってこれるように、公共機関や学校の中のどこに置いてあるのかチェック必要ですね![]()
愛知万博では、4名の方がこれで社会復帰できたそうです。 地下鉄でもよく使われるそうです。 機械のメッセージにしたがえばいいのでした。
小学校にもせっかくあるので、保護者会のときなどにみんなで中を見たり、意識しておくといいかな?
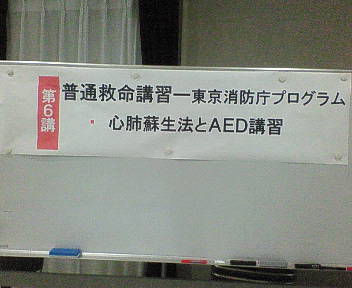

ところで、心肺蘇生の実習、ほめられました。
学生時代に小学校のプール監視員のアルバイトをしたこともあり、なんどか実習をうけたことがあります。 最新は7年前とはいえ、少しは体が覚えていたようです。
年に一度はやらないと、忘れてしまいます。 今年は赤十字やパルシステムと連携して、学習会を地域で実施しようかな☆
講師からは「心肺蘇生の練習、胸骨圧迫は普段の人間相手にしちゃだめだよ~ 人工呼吸の練習はいくらやってもよろしい」との補足がありました
-
次男くん、専門コースが確定☆ 2012.03.18
-
長男くんの卒業と進路☆ 2012.03.18
-
長男くんの第一志望校受験日です☆ 2012.02.25












