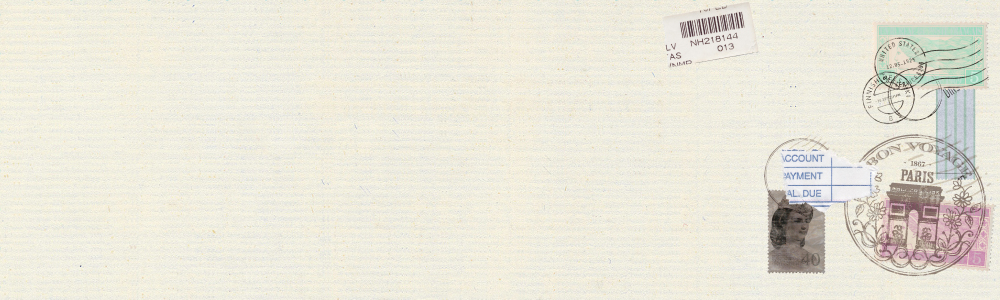テーマ: 暮らしを楽しむ(400732)
カテゴリ: 季節
こんばんは。
二十四節気、七十二候という言葉を聞いたことがありますか?
太陽の動きをもとに、1年を春夏秋冬4つの季節に、さらに6つに分け24に区切ったのが
「二十四節気(にじゅうしせっき)」。例えば、「春分」「秋分」「立秋」などがこれにあたります。
さらにそれをおよそ5日ごとに区切ったのが「七十二候(しちじゅうにこう)」。
最近は耳にする機会はほとんどありませが、カレンダーのない頃、
人々は、この
「七十二候(しちじゅうにこう)」を参考に、農作業をしていたそうです。
そしてこの
「七十二候」。
例えば、今、「春分」を5日ごと3つに分かれています。
●雀始巣(すずめはじめてすくう) スズメが巣を作り始める頃
●桜始開(さくらはじめてひらく) 桜の花が咲き始める頃
●雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) 雷が遠くの空で鳴り始める頃
春分には雀、桜、雷という漢字が使われていますが、
「七十二候」には必ず
動植物、天気を表す漢字が使われています。
7
世紀に中国から伝えられた二十四節気、七十二候は、日本の気候に合わせて
江戸時代に改定されたそうです。
まさに「桜始開」頃。
昔の人も私たちと同じようにお花見を楽しんでいたのかもしれませんね。
今日、明日の陽気で桜の花が一気に開花しそうですね。
人混みを避けてお家でのお花見もいいですね。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[季節] カテゴリの最新記事
-
今日、東京都千代田区の靖国神社にあるソ… 2025.03.30
-
東京の今日の天気は雨。桜が咲く頃に降る… 2025.03.29
-
南から北上する桜前線。東京の開花予想は… 2025.03.18
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.