-
1

解の公式の伝説
七日に放送された「林先生が驚く初耳学!」を見ていたら終わりの方で驚いたことがあった。 林先生がある人のブログの内容を紹介していて、その中で印象に残った話として、こんなものを紹介していた。 中国の農村に数学の才能のある子供がいた。それを知った数学者が進学させて数学を学ばせることを勧めたが、両親は農家を継がせるからと進学させなかった。 時が流れ、学者がその少年に再会した。少年は大人になっても独学で数学の勉強を続けており、「大変な発見をした、どんな二次方程式でも解ける方法を見つけた」と言っていたが、彼が発見したと言っていたのは二次方程式の解の公式だった。 というもの。 この話は私は40年ぐらい前に聞いたことがあり、その時は日本の話になっていた。おそらくかなり昔から都市伝説のように語り伝えられてきたものなのだろう。 林先生はこの話を知らなかったのだろうか。 いくら独学だって、参考書ぐらい買うだろうから二次方程式の解の公式ぐらい知っていて当然のはず。 参考書も何も無く、全くのゼロから数学の勉強をしていたのだとしたら、解の公式以前に二次方程式にたどり着いたことに驚くべきではないだろうか。 この話の出所はわからないが、もともとは寓話だったのではないかという気がする。何かを勉強するのに、自分一人だけで勉強していたのでは危ういというような。 また、二次方程式の解の公式というあたり、ヨーロッパ由来のものではないかという気もする。
2018.01.10
閲覧総数 2667
-
2

伊勢参拝・猿田彦神社
猿田彦といえば、「火の鳥(黎明編)」に登場する鼻の大きなキャラクター。 ヤマトを都とした勢力の先導者。 あまり大きくはないのだが、駐車場は広く、QRコードで神社の説明が読み込めるカードが置かれていたりした。
2024.11.01
閲覧総数 15
-
3
「世間息子気質《せけんむすこかたぎ》」
1960年に出た「江戸小説集(上)」(筑摩書房)というのを読んでいる。 江戸時代の小説を現代語訳したもの。 巻頭は江島其磧の「世間息子気質」。訳は小島政二郎。 百姓気質、侍気質、太鼓気質と、一五種の気質の息子の話を語る短編集。 「こんな息子がいたそうだ」という軽い語り口。 最初の話は、「小さい時から甘やかして子供をだめにしておきながら、長じてこの不始末を嘆くとはなにごとだ」ということを登場人物の口から語らせるもので、これといった筋がある訳ではない。強いて言えば、還暦すぎて子がないのを嘆く人に、子がない方が幸せだと言い聞かせる話。 江戸時代から親バカや溺愛で子供をだめにしてしまう親は多かったのだ。 次の話は、町人の子でありながら武芸に熱中し、最後には侍になってしまう、という、立身譚といえば立身譚。 しかし、物騒な息子だというので勘当されている。 総じて、親の思いと子の思いは違うもの、という話が多い。古今東西、事情は同じだろう。 楽天ブックスで検索したら江島其磧は2冊ヒットした。
2005.02.07
閲覧総数 430
-
4
「戊辰戦争 敗者の明治維新」 【佐々木克】
戊辰戦争(著者:佐々木克|出版社:中央公論新社) 大政奉還から、新政府による東北諸藩への処罰が終わるまでを、列藩同盟の側から描く。 東北が戦地となるまでに曲折があるのだが、やはりもっとも大きいのは慶喜の優柔不断ぶりである。 薩長と戦うなら戦う、帰順なら帰順と一貫していればいいものを、身内をも欺いて保身に汲々としている姿が目立つ。 著者も、「幕府終末の危機に立ちながら、慶喜はそれを乗り越え収拾しようとする意欲も気力も、また能力もなかった」(p31)と切って捨てる。 「大政奉還」というのは、今日から見れば、大きな出来事だったが、その当時としては、徳川は、「むしろこの時点では、なにも失っていない」(p10)というのは意外だった。 著者は秋田出身で、子供の頃から戊辰戦争の話を聞かされ、当然、東北諸藩に同情的である。しかし、さすがに学者で、感情的ではない。 誰もが悪役として描く世良修蔵について、勝者の側までが、「戦争の全責任を世良に負わせ」「いけにえの役を世良にふりあてている」(p109)と述べている。 全国的な動乱をよそに、水戸藩は内紛に明け暮れていたこと、榎本武揚には独自の考えがあり、列藩同盟とは一線を画していたことなど、この本を読むとよくわかる。 それにしても、読んでいて心を打つのは、二本松の少年たちの悲劇と白虎隊の最期である。 慶喜がもっとしっかりしていれば、新政府軍がもう少し感情的にならずにいたら、と「たら、れば」が心に浮かぶ。 この本によれば、戦争を避ける機会は何度もあったのだ。 朝敵の汚名をきせられ、東北各地で無念の最期を遂げた人たちの心を思うと、歴史の冷酷さに慄然とする。 戊辰戦争が東北に残した負の遺産は、あまりにも大きい。
2000.11.21
閲覧総数 17
-
5

堺雅人(「新選組!」の山南敬助)
この人のことは、「新選組!」を見るまで全く知らなかった。 いつも微笑をたたえた知性的な表情で、温厚そうな口調。 山南にぴったりだと思ってみていた。 微笑を絶やさないのは、そういう役なので意識してそうしているのだとおもっていた。 ところが、日曜日の相撲中継にゲストで呼ばれていたのをみたら、なんと、もともとそういう顔立ちなのだ。 山南を演じているときは、見た目では年齢不詳だったが、普段の姿はいかにも若い役者、という感じで長めの髪。 調べたら1973年生まれだそうだ。 細身に見えていたが、切腹の場面で着物をはだけたのを見たら、鍛錬された筋肉質の体だった。そこでまた感心。 「新選組!」は、主な隊士に、いかにもそれらしい役者を当てていて、演じていると言うより、その役者そのままで入り込んでいる。 近藤に香取慎吾を、というのは脚本家の意向だそうだが、ほかのキャストにも脚本家の強い意向が働いているのではないだろうか。 役者に合わせて書いているのではないかと思われるほどはまっている。それでいながら、実際の新選組の隊士も、きっとこういう人だったのだろうと思わせるところがたいしたもの。
2004.09.21
閲覧総数 9
-
6

十手を持つ身分
【『私家版 差別語辞典』上原善広氏インタビュー】「″差別用語″を使って何が悪い?」過剰な自主規制にモノ申す!という長い見出しの記事を読んで疑問を感じた点。部落問題で言えば、時代劇に穢多・非人が出てこない。武士が十手を持っていたりする。十手を持っているっていうのは、穢多か非人身分なんです。そういう時代考証も、わざとかどうかまで分かりませんが、間違っている。些細なことかもしれませんが、それって歴史を捻じ曲げているとも言える。 岡っ引きは日常的には持っていなかったが、同心などは十手を持っていたはず。 明治になってからの聞き書きに、十手の房がきれいに流れるように練習したとあったはず。 岩波文庫で読んだもので、今でも我が家のどこかにはその本があるはずなのだが、見つからない。 死刑執行係と混同しているのではないか。 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2011.07.03
閲覧総数 879
-
7
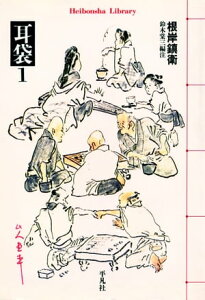
「人情噺小判一両」
BS松竹東急の「土曜ゴールデン劇場」で昔の歌舞伎の舞台中継の放送があるというので見てみた。 「人情噺小判一両」と「新皿屋舗月雨暈 魚屋宗五郎」の二本立て。 一本目の「人情噺小判一両」を見ていたら、途中で、「これは根岸鎮衛『耳嚢』にあった雪駄直しの話にそっくりだ、と思ったら、解決によると、作者の宇野信夫はその話を元にしたのだそうだ。 情けをかけなかった武士の、「侍には情をかけないのが情」というあたりから元の話とは違ってきて、最後は武士の言葉の方が正しかったことが明らかになる。 もう一度読み直してみようかと思った。
2022.07.25
閲覧総数 39
-
8
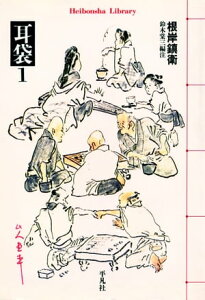
非人に賢者ある事
天明二年のことであったが、人が語った話。 あらめ橋のたもとで仕事をしていた雪駄直しがいた。往来の侍が雪駄を踏み切ったが、持ち合わせがないことに気づかず、雪駄を直させた上で懐中を見ると一銭もなく、家来はほかへ使いにやっているのではなはだ当惑し、その訳を雪駄直しの非人に断って、「明日にも持ってくる」と言ったが、その非人はもってのほか憤ってあれこれ言い、後には悪口雑言を並べたが、その侍が無念をこらえていろいろ申しなだめたが、そばにいた同職の非人が、中に入ってその侍に対し、「同職の非人は甚だ不届きです。まことに御難儀なことでこざいます。彼へはいかようにも私がなだめて納めます、人も見ていますから、どうでしょう、早々お帰りなさっては」と言ったところ、その侍はありがたいことと思い、「その方の住まい小屋はいずれで、名前はなんと申す」と訪ねたけれども、「お礼などいただこうとは思いません。少しでも早くお帰りください」とたって勧めたので、その侍もその意に任せ帰ったという。 そのそばに町人がいたが、一部始終を見て取り、「そなたの小屋はどこか」と尋ねると、「鎌倉河岸あたりです」と言ったので、「それならば帰り道だ、少し頼みたいことがあるので一緒に帰ろう」と言って同道し、途中で、「そなたは生まれながらの非人には見えない」と言うと、「なるほど、生まれながらの非人ではございません。若気の心得違いからこのような身分になりました」と答えた。「それならば、そなたの今日の取り計らいは感ずるに余りある。用に立つ者だ、今の身分から引き出して召し抱えよう」と言うと、「近頃かたじけないお話ですが、その望みはございません。すべて橋詰めに出て雪駄直しなどいたします非人は、御武家方そのほかの方がお困りの歳は、代金にかかわらずお役にたつべきもので、非人としてはめずらしいことではございません。あの悪口雑言いたしました非人は者を知らぬ者で。また、武家方の難儀を見受けましたので、非人の私がよんどろこなく中に立ち、ことを納めたのでございます。しかし、お侍の身分ではさこそ無念にお思いででしょう。あなた様は終始様子をご覧になっていたのに、どうして中に立ってお侍の難儀をおたすけなさらなかったのですか。そのようなお心得の方に、今の身分から引き出されてお仕えするようなことは、望むところではございません」と答えたので、その町人も赤面して帰ったという。非人ながらおそろしいものだ、と人が語った。 深く印象に残った話だ。 また、非人はなったり抜けたりすることができるものだということがはっきり書かれていることも興味深い。
2022.07.27
閲覧総数 44
-
9

Amazonを名乗る詐欺メール
Amazonを名乗る迷惑メール。 文面を変えていろいろ来る。Amazon Logo Imageユーザーの皆様、このメールは、アカウントの確認のためにアカウントが永久に停止されることをお知らせするものです。これにより、メールの送受信ができなくなります。次の 24 時間後にアカウントにアクセスできなくなります。アカウントの停止を避けるために、アカウントを確認してください。今すぐアカウントを確認してくださいありがとう無断複写・転載を禁じます *****.or.jp
2023.06.01
閲覧総数 40
-
10

イカの駅つくモール 能登半島ツアー(4)
なぞの巨大イカ像のある道の駅。 遊覧船もあるらしい。 港はあちこち崩れていてまだ危ない。
2025.11.24
閲覧総数 8
-
11

ホテルクラウンヒルズ金沢香林坊 能登半島ツアー(6)
泊まったのは金沢。備長炭の湯 ホテルクラウンヒルズ金沢香林坊(BBHホテルグループ)というホテル。 大型バスが寄せられないので、大通りから少しだけ歩いた。 ウェルカムドリンクがあって、コーヒーのほかに日本酒と焼酎があった。 日本酒も焼酎も一升瓶から紙コップに注ぐのだった。これじゃあ、思いっきり飲んで酔っ払う人もいるのではないか。 シングルの部屋にソファーがあるのが珍しい。 大浴場があるが時間制で男女入れ替え。温泉ではないが気持ちがいい。男性の時間になって少し経ってから行ったら貸し切り状態。気持ちがよかった。 BBHグループにはマンガがあるはずだと思って案内を見たら、二階に置いてあった。 部屋からの眺め。 大通りから少し外れているので静かなのがいい。朝食も、贅沢ではなかったが十分満足できた。
2025.11.26
閲覧総数 15
-
12

語り部観光列車「のと里山里海号」 能登半島ツアー(7)
のと鉄道の七尾駅から語り部観光列車「のと里山里海号」に乗った。 海が見やすいように工夫されている特別車両なのだが、二人で参加した人用の席で、わたしのように一人で参加した者は、4人まとめて山側のボックス席だった。 語り部は、地震発生時にホテルで働いていた、という男性。話すことになれていて聞きやすい。 ホテルはまだ営業が再開できていないそうだ。 特に海のそばは被害が大きい。 穴水駅で下車。のと鉄道はポケモンとコラボしていた。
2025.11.27
閲覧総数 2
-
13

擬態蛾
朝、網戸にとまっていた。 枯れ葉かと思ったら違う。蛾だ。 こんな蛾はそんなにはいないだろうと思って検索したのだがわからない。 わかる人にはわかるんだろうけど、素人の悲しさで同定できない。 何という虫なんだろう。楽天ブログランキング←クリックしてください 楽天会員以外の方のコメントは「輾転反側掲示板」へ
2008.09.28
閲覧総数 4009
-
14

浜焼き能登風土 能登半島ツアー(5)
ツアー初日の夕食は「能登半島風土」というチェーン店の千里浜店。 千里浜は「せんりはま」かと思っていたが「ちりはま」なのだった。 砂浜をバスで走ることができるところとして知られているが、海岸を走るのはコースに入っていなかった。砂浜は年々狭くなってきているそうだ。 夕食のメニューは能登ブタ料理。 能登ブタというものを初めて知った。おいしく頂いたが、店自体は海鮮焼きの店らしい。 店頭のメニューを見ても能登ブタ料理がない。 団体用の特別メニューらしい。公式サイトを見たら、「能登豚陶板焼き御膳」らしい。 店の外には、砂で作ったこんな像がいくつかあった。昼間だったら海も見えるらしい。 翌日、このそばを通ったのだが、海が荒れていて、その日は通行止めになっているということだった。 ただ、通行止めになっていなくても海岸を走る予定はなかったそうだ。
2025.11.25
閲覧総数 6
-
-

- ジャンプの感想
- 週刊少年ジャンプ2025年52号感想その…
- (2025-11-26 13:50:15)
-
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- ウィニング勝利の経営 =4章 発言権と…
- (2025-11-29 00:36:41)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 雑誌『映画秘宝 2026年 1月号』 ガメ…
- (2025-11-26 21:00:05)
-







