全5979件 (5979件中 1-50件目)
-
反省しないと気が済まない人達【最終回】(9)北海道社説
《石破茂首相は戦後80年となる全国戦没者追悼式の式辞で、戦争への「反省」に言及する一方、アジア諸国への加害責任に触れなかった。 2013年に安倍晋三首相が反省と加害責任への言及をやめて以降、最近の首相も避けてきた。石破首相は「戦争の反省と教訓を今改めて深く胸に刻まねばならない」と述べ、反省を13年ぶりに復活させた。 ただ、反省が加害に向けられているかは読み取れない。節目の年に不戦の誓いを明確にするためにも、加害の歴史を直視した言葉が必要ではなかったか》(8月16日付北海道新聞社説) 自虐史観論者は、戦前の日本を罵(ののし)ることに酔い痴れてしまっている。日本は悪い国だったと言う自分の「正義」に酩酊(めいてい)しているのだ。悪いものを悪いと言うのは正しいことではないか、自分は正義を貫いているだけだと思っているのであろう。が、それには戦前の日本が悪かったという判断がまず必要だ。そのためには、自虐史観ではない意見がどのようなことを言っているのかにも一定の理解が必要となる。でなければ、ただ自虐史観の尻馬に乗って騒いでいるだけになってしまうかもしれないからだ。 例えば、大東亜戦争は、自衛戦争だったという意見がある。が、それは自己弁護だろうと言うなかれ、そのように述べているのは、かのマッカーサーである。マッカーサーは、朝鮮戦争を経て日本への見方を変え、米上院軍事外交合同委員会で次のように述べた。There is practically nothing indigenous to Japan except the silkworm. They lack cotton, they lack wool, they lack petroleum products, they lack tin, they lack rubber, they lack great many other things, all of which was in the Asiatic basin.They feared that if those supplies were cut off, there would be 10 to 12 million people unoccupied in Japan. Their purpose, therefore in going to war was largely dictated by security.(蚕以外日本には原産のものはほとんどない。綿花も、羊毛も、石油製品も、錫も、ゴムも、その他多くのものも不足している。それらの供給が途絶えれば、日本には1千万から1千2百万の人々が職を失うことになるだろうと彼らは恐れた。従って、彼らが戦争に踏み切った目的は、安全保障によるところが大きかった) 勿論、このようなことになったのは、ABCD包囲網で米英支蘭が日本を締め上げたからである。かの戦争は日本の侵略戦争であるというのとは随分違う話である。 もう1つ戦中に開かれた「大東亜会議」についても見ておこう。大東亜会議とは、1943(昭和18)年11月5日から6日にかけて東京で開催されたアジアの首脳会議のことで、これには中華民国(汪兆銘政権)、満洲国、フィリピン、ビルマ、タイ、インドといった国や地域が参加した。日本が亜細亜を侵略しようとしているのであれば、このような会議が開かれるはずもない。 勿論、私は、このような事実をごり押ししたいわけではない。が、大東亜戦争は侵略戦争であったなどと単純に言えないということを確認したかっただけである。かの戦争を思い込みだけで反省する前に、もう一度いろいろな意見に触れられることをお勧めしたい。【了】
2025.08.24
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(8)東京社説その2
《節目の年に過去の過ちを振り返り、戦争への反省と不戦の決意を内外に表明することは、平和国家の道を歩んできた日本政府として当然の責務だ》(8月16日付東京新聞社説) 例によって〈過去の過ち〉という抽象的な言葉が具体的に何を意味するのか分からないが、おそらくは自虐史観よろしく、大陸を侵略したことが誤りだったということなのだろうと思われる。一方、私は、かの戦争における最大の過ちは、日本が戦争に負けたことだと思っている。「歴史のもし」を許してもらえるなら、もし日本があの戦争に勝利していたなら、共産主義国の台頭を許すことはなかっただろうと思われるのだ。It is an ironic fact that today our past objectives in Asia are ostensibly in large measure achieved. The Western powers have lost the last of their special positions in China. The Japanese are finally out of China proper and out of Manchuria and Korea as well. The effects of their expulsion from those areas have been precisely what wise and realistic people warned us all along they would be. Today we have fallen heir to the problems and responsibilities the Japanese had faced and borne in the Korean- Manchurian area for nearly half a century, and there is a certain perverse justice in the pain we are suffering from a burden which, when it was borne by others, we held in such low esteem. What is saddest of all is that the relationship between past and present seems to be visible to so few people. For if we are not to learn from our own mistakes, where shall we learn at all? -- George F. Kennan, American Diplomacy(今日、わが国の以前のアジアにおける目標が表向きにはほぼ達成されたというのは皮肉な話である。欧米列強は、シナにおける特別な地位のすべてを失った。日本はついに、完全にシナから手を引き、満洲と朝鮮からも離れた。これらの地域から日本が排除された結果は、賢明で地に足の着いた人達がずっと警告してきた通りのものとなった。今日、わが国は、日本が半世紀近くに亙って朝鮮・満州地域で直面し、背負ってきた問題と責任を引き継ぐことになったのだ。他者が背負っていたときは、その重荷を軽んじていたわが国が、その重荷に苦しむのは、ある種倒錯した正義である。何よりも悲しいのは、過去と現在の関係を認識できる人があまりにも少ないことだ。もし自らの過ちから学ばないとすれば、わが国は一体何から学べようか(学べはしないからだ))――ジョージ・F・ケナン『アメリカ外交』《日本国内でも一部の政治家が歴史をゆがめ、排外主義を扇動するなど戦前回帰の言動が目立つ。だからこそ、日本の指導者が政府として戦争を謙虚に反省し、世界の平和と繁栄に尽くす姿勢を示すことの意味は増している》(同) 果たして自虐史観を批判することは、歴史を歪めることなのか。批判されるべきは、日本だけが悪かったという自虐史観、東京裁判史観の方ではないか。自虐史観批判は戦前回帰を目指すものであるかのように言って批判を躱(かわ)そうとするのは卑怯なやり方である。米国の原爆投下や大都市絨毯爆撃、ソ連の一方的な不可侵条約の破棄や捕虜のシベリヤ抑留強制労働といったことはすべて免責し、日本だけが悪かったということは、例えば国民主権を破棄し神国日本に戻せといったことと決して同義ではない。 また、日本は、日本の先人が築いてきたものであり、これを継承する日本人が第一に扱われるのは当たり前のことである。にもかかわらず、外国人に日本人と同じ権利を与えようとすることを「排外主義」という言葉で否定しようとするのは共産主義的な危険思想でしかない。戦後日本人は、「平等」だの「人権」だのといった革命思想に由来する言葉にあまりにも鈍感すぎるのだ。【同】
2025.08.23
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(7)東京社説その1
《戦後50年以降、10年ごとの節目に、時の内閣は首相談話を閣議決定してきた。石破氏も戦後80年に当たり、軍部の独走を許した戦前戦中の歴史を、文民統制の観点から検証する考えを示してきた》(8月16日付東京新聞社説) 軍部の暴走の裏に、尾崎秀実(ほつみ)やゾルゲといったコミンテルンのスパイの関与があり、共産主義革命、そして、資本主義国家同士を嚙み合わせ漁夫の利を得ようとする「敗戦革命論」が日本を覆っていたことにも目を向けるべきである。が、反省好きの人達は、なぜかそのことに触れようとはしない。 また、軍部の暴走を文民統制によって防ぐという考え方も短絡に過ぎるだろう。なるほど、満洲事変は軍部の暴走である。が、「国民政府を対手とせず」と言ってシナ事変を泥沼化させたのは近衛政権であるし、北進か南進かの選択で南進を決めたのも政治である。また、石油確保のための大東亜戦争に加え、不可解にも真珠湾攻撃を同時敢行することを決定したのも政治である。つまり、文民統制がなかったから、戦争を止められなかったというのは間違いだということだ。 では、最大の問題は何かと言えば、帝国憲法 第11条 天皇ハ陸海軍ヲ統帥スが逆手にとられ、「統帥権干犯問題」が起こって以降、政治が軍部を抑えられなくなったことである。つまり、憲法上の不備がそこにあったということだ。が、これは立憲制の限界と言った方がよいのかもしれない。つまり、成文憲法は、どれほど精緻に作られようとも、抜け落ちもあれば、言い足りないところもある。そのことを補うために、憲法をどのように解釈し運用するのかということが重要になってくる。戦前で言えば、当初は帝国憲法を作った元勲たちがいたから、憲法を的確に解釈し運用することが出来たが、元勲がいなくなってから、憲法の精神を歪めるものたちが増えてしまったのだ。 軍は天皇に直属するという形になっているため、押さえが利かなかった。が、間違ってはならないのは、これは政治に軍を抑え込むだけの力がなかったということなのであって、軍が暴走したのではないということである。当時、陸軍と海軍は仲が悪かった。だから、お互い牽制し合っていたため、暴走しようにもできなかった。政治と陸軍と海軍が三竦(すく)みとなって、何も決められずに時代に流されていった結果、戦争せざるを得なくなったというのが本当のところであり、軍が暴走したなどというのは、実体のないただの印象論に過ぎない。【続】
2025.08.22
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(6)読売社説
戦後保守然として、読売社説子は、《先の大戦の終戦から80年となった。惨禍の記憶を風化させないための取り組みを強化し、不戦と平和の誓いを次世代に継承せねばならない》(8月16日付読売新聞社説)と言う。ここで、戦後保守とは、敗戦後GHQによって敷かれた体制、すなわち、「戦後レジーム」を保守するという意味である。また、かの戦争は日本だけが悪かったという「自虐史観」を保守しようとするのも戦後保守の特徴である。《惨禍の歴史を伝える取り組みは一層重要となる。 戦後世代が、戦中・戦後の暮らしや労苦を学び、学校などで伝える「語り部」の活動が各地に広がっている。戦争体験者が健在なうちに、さらに育成を進めたい。 体験者の証言を映像などで残す活動も加速させる必要がある。各地の戦争遺跡も、戦時下の地域の歴史を学ぶ場となるはずだ》(同) 惨禍の歴史を伝えなければどうなるのか。若い世代が惨禍の歴史を知らなければ、また同じように他国を侵略しようなどと邪(よこしま)なことを考えかねないとでも思っているのか。日本民族は、しっかり箍(たが)を嵌めておかなければ、何をしでかすか分からない野蛮民族だとでも思っているのだろうか。 それとも、戦争は懲り懲り(こりごり)だ、平和が一番、だから、少しでも平和を掻き乱すことは許せない、という平和潔癖症ゆえ、戦争の悲惨さは語り続けなければならないと思っているのだろうか。 が、戦争とは相手のあることであって、いくら自分たちが非暴力を貫こうが、吹っ掛けられたら御仕舞だ。実際、大東亜戦争は、石油を止められた日本が自存自衛のために打って出たものであり、決して亜細亜を侵略しようなどと考えたものではなかった。 相手が責めてきたら「白旗」を挙げて迎えればよいという絶対平和主義の立場もあろう。が、チベットやウイグルがどうなったのかを見れば分かるように、それは最悪民族浄化(ethnic cleansing)となりかねないし、少なくとも徹底した搾取に遭(あ)うであろうことは容易に想像できる。 必要なのは、戦争に巻き込まれないようにすることだ。相手に攻め込まれないための自衛力を保有し、利害を共有する国との連携を深めることも大事である。はたまた、他国と友好関係を築き、敵を作らないための外交努力も不可欠である。つまり、国際社会における平和の構築に汗をかくことが重要だということだ。 戦争を自国の問題としてだけ考えること、すなわち、一国平和主義は、大海を知らぬ井の中の蛙的思考でしかない。【続】
2025.08.21
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(5)毎日新聞社説
石破茂首相が、戦後80年談話を見送ったことに対し、毎日社説子は言う。《先の大戦に対する反省と教訓を明確に示し、再び惨禍を招かない決意を内外へ発信する機会とすべきだった》(8月16日付毎日新聞社説) 戦後日本は、軍事に関し、非常に抑制的に振る舞ってきた。にもかかわらず、どうして今〈再び惨禍を招かない決意を内外へ発信〉しなければならないのか。〈先の大戦に対する反省と教訓〉が具体的にどういうものなのかが明確でない。明確でないものを明確に示すことなど出来るわけがない。 毎日社説子の頭の中には明確な〈先の大戦に対する反省と教訓〉があるつもりなのであろう。が、それが何なのかを具体的に出せば、世の非難を浴びることは避けられない。どんなに正しかろうと、世間には様々な考えをもった人々が存在するのであるから、唯一無二の〈先の大戦に対する反省と教訓〉などあろうはずがない。首相たりとも同じことで、首相が公式な場で自分が考える〈先の大戦に対する反省と教訓〉をさも日本全体の総意であるかのように述べるのは独善に過ぎ、民主制における首相の権限を逸脱している。それが出来るのは、シナのような権威主義国家である。《きのうの全国戦没者追悼式での式辞では、大戦の「反省と教訓」に言及した。「反省」は村山氏の時から式辞に盛り込まれたが、2013年の安倍氏以降は消えていた。13年ぶりに復活させた形だ。 しかし、何を反省し、教訓とするのかについては、「進む道を二度と間違えない」などと曖昧に述べただけだ。日本が侵略し植民地支配したアジア諸国への加害責任には触れていない》(同) が、このような自虐史観は、もうそろそろ御仕舞にすべきだ。 社説子は、日本がアジア諸国を侵略し植民地支配したと言う。が、この問題で未だにぐじゃぐじゃ言っているのはシナと韓国だけである。が、シナの侵略に関しては次のよう逸話がある。 1964年7月、日本社会党の佐々木更三率いる訪中した際、日本の侵略戦争を謝罪すると、毛沢東は言った。「何も申し訳なく思うことはありません。日本軍国主義は中国に大きな利益をもたらし、中国人民に権力を奪取させてくれました。みなさんんの皇軍なしには、われわれが権力を奪取することは不可能だったのです」(『毛沢東思想万歳』(三一書房)下巻、p. 187) 実際、日本が戦ったのは中華民国であって、1949年に建国された中華人民共和国(中共)ではなかった。だから、日本は中共建国の恩人ということなのだ。 また、戦前日本は朝鮮を「併合」したのであって「植民地化」してはいない。だからこそ「持ち出し」だったのだ。赤字経営の殖民地など有り得ない。朝鮮を差別しない「内鮮一体」政策は、併合であったことの証(あかし)である。【続】
2025.08.20
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(4)朝日社説その2
《きのうは石破内閣の閣僚である加藤勝信財務相、小泉進次郎農林水産相のほか、自民の高市早苗、小林鷹之、萩生田光一氏らが靖国神社に参拝した。参院選で躍進した参政党は、国と地方の議員が大挙して参拝した。 戦前の軍国主義を支えた国家神道の中心的施設に、政治指導者が参拝することは、戦争への反省を忘れ、過去を正当化しようとしていると見られても仕方あるまい》(8月16日付朝日新聞社説) 社説子はしらっとこのように靖国参拝を非難するが、戦前の社説では真逆のことを言っている。《征途(せいと)に出でたつつわものの唯一の念願は靖国の御社(おやしろ)に凱旋(がいせん)することである。戦場で戦友が交わす訣別の挨拶は九段での再会を期することである。父を子を、夫を兄を御国(みくに)に捧げた遺族は、靖国の御社へ詣(もうで)れば懐(なつか)しの対面が叶(かな)うのである。靖国神社こそは護国の忠魂を永世に追慕する崇敬の的であると同時に日本国民一人一人の魂の故郷であるのである。靖国神社大祭が国家的大典たる所以(ゆえん)も実にここにあるのである》(「靖国神社に行幸啓」昭和17年4月25日付社説) 朝日のこの二枚舌こそ最も指弾(しだん)されるべきことであり、反省すべきことであると思われる。《靖国神社は、畏(おそ)れ多くも、命を国事に殯(ひん)せる勇士の英霊を祭り勲(いさお)を後世に伝えしめんとの明治天皇の有難き大御心(おおみこころ)により建立せられた神社であり、祭神はみな陛下の有難き思召(おぼしめし)によって祀(まつら)せられるのである。『水清く屍(かばね)、草むす屍』は建国の古より未来永劫に変らざるわが国民精神の伝統であり、われわれ国民のひたすらなる念願である。ここに合祀されること誠に至上の光栄たること申すまでもない》(「御親拝を仰ぎ奉る」昭和18年4月24日付社説) 軟弱化してしまった現在の新聞人にはこれほど荘重たる文章を物すことは能(あた)わないだろう。今や「社会の木鐸」は消え去ってしまった。《多大な犠牲の上に築かれた戦後の歩みを顧みることなく、不都合な事実から目を背けていては、同じ過ちが繰り返されかねない》(8月16日付朝日新聞社説)という批判は、まさに天に唾するがごときものだ。戦前とまったく異なる主義主張を行う新聞社が、何の反省もなく同じ社名を名乗り続けていること自体が不道徳そのものであるように思われる。【続】
2025.08.19
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(3)スパイ尾崎秀実と共産主義革命
コミンテルンのスパイ尾崎秀実(ほつみ)は、かつて朝日新聞にも在籍していた。共産主義革命を夢見る尾崎は言う。《欧洲に戦争が始まった時人々はこれを英独の決闘であると見た。しかしながらソ連をも捲きこんだ現在ではこれを第二次世界大戦と見ることに何人(なんびと)も異義を挿(はさ)まないであろう。 私見ではこれを世界史的転換期の戦と見るのである。 英米陣営では独ソ戦が起った時、ひそかに英米旧秩序陣営の勝利に導びくものとしてほくそ笑んだのである。この種の見解はひとり英米陣営側のみならず中立的陣営乃至(ないし)反対側にすら多少浸透しつつありと見られる理由がある。英米側は旧秩序の再建――修正的復元――を夢みつつある。しかしながらこれは全くいわれなきことであって、それは今次の大戦の勃発するにいたった根本の理由を見れば明らかなことである。旧世界が完全に行詰り、英米的世界支配方式が力を失ったところから起った世界資本主義体制の不均衡の爆発に他ならないこの戦争が、英米的旧秩序に逆戻りし得る可能性は存在しないのである。戦争はやがて軍事的段階から社会・経済的段階に移行するであろう》(「対戦を最後まで戦い抜くために」:『尾崎秀実著作集』(勁草書房)第3巻、p. 268) 尾崎は、近衛文麿首相のブレーンでもあり、政界や軍部にも大きな影響力があった。尾崎の暗躍から、当時の日本がいかに左傾化していたかが分かる。《当局は日本国民を率いて第二次世界大戦を戦い切る。勝ち抜けるという大きな日額に沿うて動揺することなからんことである、日米外交折衝もまたかかる目的のための一経過として役立たしめた場合にのみ意味があるものといい得る。又今日日本には依然として支那問題を局部的にのみ取扱わんとする見解が存在している。これは世界戦争の最終的解決の日まで片付き得ない性質のものであると観念すべきものであろう。 私見では第二次世界戦争は「世界最終戦」であろうとひそかに信じている。この最終戦を戦い抜くために国民を領導することこそ今日以後の戦国政治家の任務であらねばならない》(同) ここから見えてくるのは、日本が共産主義革命に利用されていたということだ。支那事変が長期化し、英米と戦うことになったのも、資本主義体制を終わらせるためのコミンテルンの陰謀だったのだ。 が、今日、軍部の暴走を反省することはあっても、その思想的根拠たる共産革命思想を反省することはない。私はここに「反省」という言葉の恣意(しい)性を感じざるを得ないのである。【続】
2025.08.18
コメント(0)
-
反省しないと気が済まない人達(2)朝日社説その1
《戦後80年の節目に「首相談話」を見送ったことは、歴史の教訓を世代を超えて継承する責務にもとるものだ》(8月16日付朝日新聞社説) 要は、70年の安倍談話が気に入らないから上書きせよということなのだろう。が、いつも思うことであるが、彼らの言う「歴史の教訓」とは何か。それをはっきり言わず、何か大切なもののように匂わせるいつものやり方に辟易(へきえき)する。 私のような戦争を知らない世代は、戦争を止められなかったことを当事者のように反省することはできないが、逆に客観的に当時の情勢を分析することは可能であり、そこから何らかの教訓を得ることも可能であろう。が、分析は様々な角度から可能であろうから、そこから得られる教訓は自ずから複雑なものとなる。朝日社説子のように、世代を超えて継承する「歴史の教訓」などというものを固定化して考えることはできない。 ここで深入りすることは避けたいが、私が戦後平和主義に最も不満であるのは、当時の情勢判断を国内問題だけで行っていることである。戦争とは相手のあるものであるから、国内のみならず国外の情勢にも目を向け、当時の日本が国際的にどのような状況に置かれていたのかを判断する必要がある。日本が大陸に進出したから戦争になったなどという単純な話で反省をし、そこから教訓を得るなどということ自体が、大いに反省すべきことなのだと思われる。 つまり、戦後平和主義は、典型的な井の中の蛙的発想に基づくものであって、日本が戦争を起こさなければ平和だなどと考えるのは間抜けというしかない。実際、かの日米決戦は、米英にふっかけられたものであり、ソ連が裏で糸を引いていたものだったことは戦後明らかとなった様々な資料から窺い知ることが出来るのである。《(首相式辞は)…「反省」が13年ぶりに復活したが、アジア諸国への加害責任には触れておらず、何を反省し、教訓とするのかは明確でない。短い式辞で意は尽くせない。戦後50年の村山談話、戦後60年の小泉談話、戦後70年の安倍談話と同様、首相談話を出すべきだった》(同) が、先に反省すべきは朝日新聞である。販売部数を伸ばすために軍の太鼓持ちとなった朝日新聞などのマスコミは、行け行けどんどんと国民を戦争へと煽った。今なおマスコミは、事実を報道するというよりも、自分たちの都合の良い方向に国民を誘導しているところがある。どうして国民は、いとも簡単にマスコミに騙され続けるのか。日本人は本当にお人好しである。【続】
2025.08.17
コメント(0)
-
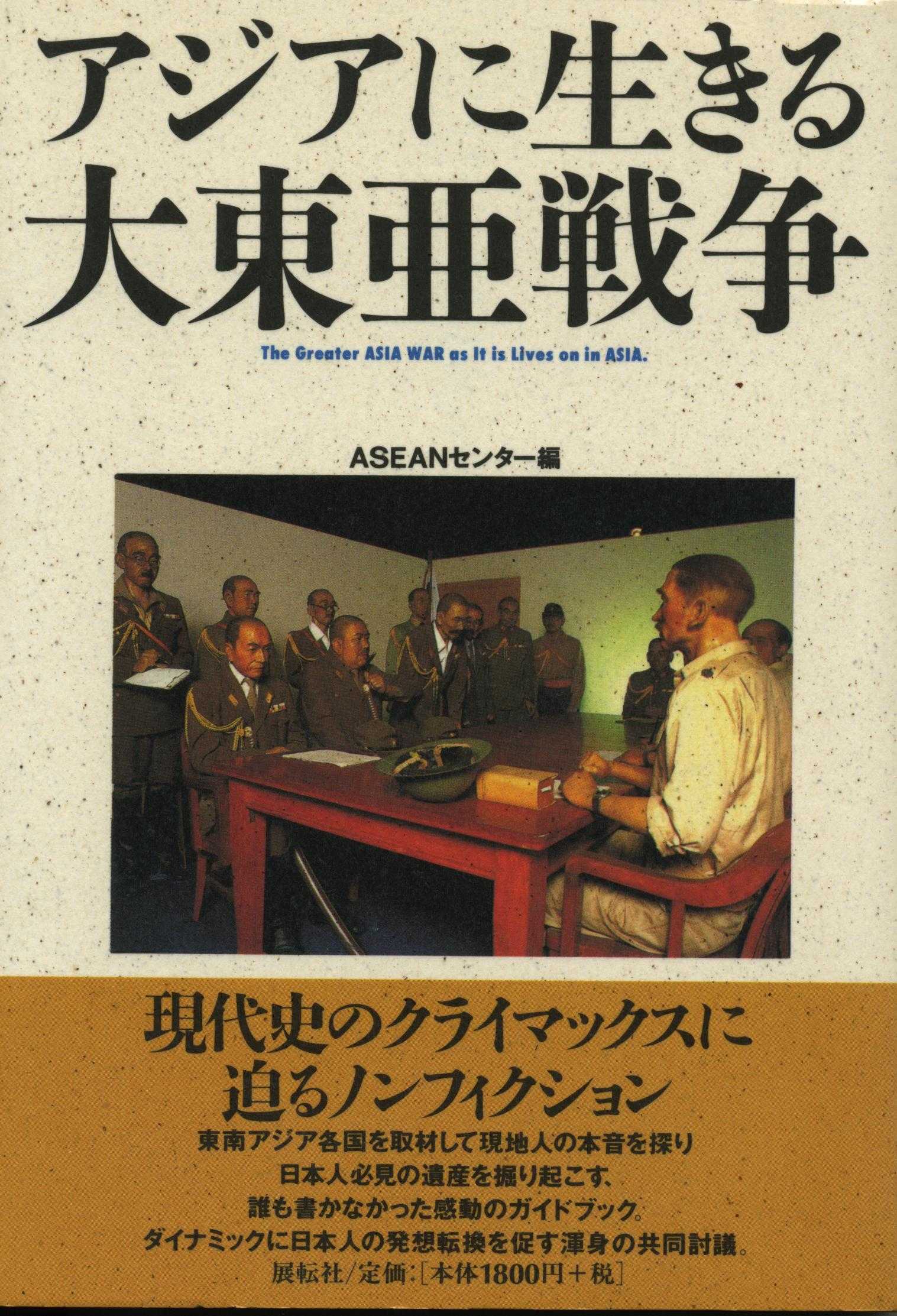
反省しないと気が済まない人達(1)
石破茂首相は、政府主催の全国戦没者追悼式の式辞で次のように述べた。《先の大戦から、80年が経(た)ちました。今では戦争を知らない世代が大多数となりました。戦争の惨禍を決して繰り返さない。進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばなりません》 ここに言う「反省」とは、大東亜戦争は、「侵略戦争」であったという認識の下でなされる反省なのであろう。なるほど、日本では侵略戦争であったと考えている人が多いのであろう。おそらく戦後教育がそう国民に刷り込んで来たからであろう。が、侵略された側の亜細亜は、必ずしもそのような認識ではない。《平成6年、自社さ連立政権が誕生し、村山富市元首相と土井たか子元衆院議長の社会党出身コンビが相次いでアジアを訪れた。連呼したのは、日本の戦争への反省やおわびだった。 「戦争にかかわる問題は胸の痛む問題であり、反省とおわびの気持ちを持っている」とフィリピンで村山元首相。土井元議長は、「二度と過ちを繰り返さない」「歴史への反省」などと各地で述べた。 マハティール首相は村山元首相にこう話した。 「50年前に起きたことを日本が謝り続けることは理解できない。過去は教訓とすべきだが、現在からさらに将来に向かって歩むべきだ。アジアの平和と安全のために、すべての役割を担ってほしい」》(論説委員・河村直哉「日曜に書く」:傾聴に値するマハティール氏の“日本への提言” 未来を問うことこそ重要:産経新聞 2018/5/27) また、ビルマ元国家元首バー・モウも、『ビルマの夜明け』に次のように書いている。「真実のビルマ独立宣言は、1948年1月4日ではなく、1943年8月1日に行なわれたのであって、真のビルマ解放者はアトリーの率いる労働党政府ではなく、東条大将と大日本帝国政府であった」(序)「歴史的にこれを見るならば、日本はどアジアを白人支配から離脱させることに貢献した国はない。しかしまた、その解放を助けたり、あるいは多くの事柄に対して範を示してやったりした諸国民そのものから、日本ほど誤解を受けている国はない。これはまた日本が、その武力万能主義者と民族の夢想とのために謬(あやま)られたためである」「もし日本が武断的独断と自惚(うぬぼ)れを退け、開戦当時の初一念を忘れず、大東亜宣言の精神を一貫し、南機関や鈴木大佐らの解放の真心が軍人の間にもっと広がっていたら、いかなる軍事的敗北も、アジアの半分、否、過半数の人々からの信頼と感謝とを日本から奪い去ることはできなかったであろう。日本のために惜(おし)むのである」――『アジアに生きる大東亜戦争』(ASEANセンター編)、p. 288 当たり前だが、物事は多面的である。まして戦争などという一大事業においては尚更(なおさら)である。大東亜戦争にも否定的な側面、肯定的な側面が入り混じっている。反省すべきだと思うことも可能であるし、反省する必要はないとすることも可能である。つまり、意見見解は多種多様であり、反省しなければならないという個人的な意見を国家的な意見として一国の首相が述べることなどあってはならないことなのだ。首相は最大権力者であるから、好き勝手に振る舞ってよいなどと考えることは児戯(じぎ)に等しいと言わざるを得ない。【続】
2025.08.16
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(50)【最終回】愛国心なき平和教育は醜悪
教育基本法第2条5には、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。とある。教育基本法改正に当って、「国と郷土を愛する心を養う」と表現するのを連立与党の公明党が嫌い、「国と郷土を愛する…態度を養う」などとあいまいな表現になっているのは無惨であるが、それは措(お)こう。問題は、平和教育がこの条文に反しているのではないかということである。 戦後80年が過ぎようとしている中で、平和教育は、その必要性が薄れてしまった。平和教育の必要を言うためには、戦前の日本の有ること無いことを穿(ほじく)り返さねばならない。戦前の日本の暗黒だけを、否、戦前の日本を暗黒として論(あげつら)わねばならない。「国と郷土を愛する…態度を養う」こととは正反対の教育とならざるを得ないということだ。 戦前の日本を美化せよと言いたいのではない。悪いところは悪いと言って構わない。が、それは程度問題である。あらゆるものには光と影がある。にもかかわらず、影の部分だけを強調し、光の部分を捨象するのは平衡を欠くと言わざるを得ない。戦前の日本の暗部ばかりを暴き立てる教育では、愛国心や郷土愛を育むことなど不可能である。 日本に生まれ育ち、そして、これからの未来を日本と共に歩んでいく若者たちに戦前の日本の暗部を殊更(ことさら)強調し、その反動を利用して行う平和教育とは一体何なのだろうか。平和主義者は、平和を訴える自分に酔い痴れてはいないか。が、本当に重要なのは、社会の平和を維持することであって、平和というスローガンを唱えることではない。 平和を唱えるだけで社会が平和になるのであれば苦労ない。が、平和は、魑魅魍魎(ちみもうりょう)うごめく、どろどろとした国際社会の中で、押し合いへし合いしながら汗をかき、時として泥水をも啜(すす)りながら交渉することによってはじめて得られるものであろう。外交の外側から独り平和というスローガンを唱えるだけで得られるような甘いものでは決してない。 教育の目標の1つが「愛国心」を涵養(かんよう)することであることは本来言うまでもないことだ。が、戦後日本人は、羹(あつもの)に懲(こ)りて膾(なます)を吹くかのごとく、異様に愛国心を警戒する。が、言うまでもなく、国民から愛国心がなくなれば、国の存続は危うい。問題は、愛国心の中身なのであって、健全な愛国心すら忌避してしまっては、日本人が日本人でなくなってしまうだろう。 日本を皆が愛せる国にするためには、日本人一人ひとりが愛国心をもつことが欠かせない。再び戦争への道を進むのではないかと危ぶみ、いくら戦前の日本の悪事を言い立てたところで、日本を愛する気持ちは生まれない。愛国心を涵養する教育に対する安全弁として平和教育もまた必要であったとしても、愛国教育を否定するかように平和教育がしゃしゃり出るのは、みっともないと言うか醜悪そのものではないかと思う次第である。【了】
2025.06.27
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(49)「平和ごっこ」の平和主義
最後に歴史教育の目的について考えておこう。戦後日本における平和主義者は、二度と戦争を起こさないために、平和教育の必要性を説く。が、犯罪者が再び罪を犯さないように教育するというのなら分からなくもないが、戦争を知らない世代に二度と戦争を犯さないように教育するというのは少し筋が違うのではなかろうか。日本人には好戦的なDNAが深く刻まれているというのであれば、永遠に平和教育を施す必要もあろう。が、そのような国民性があると言えるはずもない。 ならば、戦前の日本は、大陸の人々に多大なる苦難を被(こうむ)らせた悪しき国であるということを強調するしかない。その結果、実質的に、平和教育が自虐教育と化してしまっているのだ。戦前の日本は悪い国だったということを、それが正義だと信じ、一所懸命に教える。これが自虐的でなくて何なのであろうか。 マッカーサーも米議会公聴会で証言した通り、大東亜戦争は自衛の戦争であった。また、亜細亜の解放という側面もあった。にもかかわらず、戦後日本における平和主義者は、こういった視点を無視し、戦勝国史観よろしく大東亜戦争を侵略戦争と決め付けている。まさに自虐的と言うしかない。 また、日米戦たる太平洋戦争は、あまりにも不可思議な戦争であった。大東亜戦争と太平洋戦争の2つの戦争を同時に戦うなどというのは非常識であることは言うまでもない。また、大東亜戦争には、自衛や亜細亜解放という大義があったが、太平洋戦争には、戦う名分がない。もちろん、侵略戦争でもなかった。 ここには日本と英米を戦わせて漁夫の利を得ようとする力が働いたとしか思われない。そこには共産主義のスパイ尾崎秀美(おざき・ほつみ)やゾルゲの存在もあった。こういった話が大東亜・太平洋戦争の総括からずっぽり抜け落ちてしまっている。 ところで、平和教育を必要とするのは、むしろ戦後多くのミサイルをぶっぱなしている米国やロシアをはじめとする国連常任理事国(P5)の方だろう。彼らに平和教育の必要性を訴えてみればよい。一蹴(いっしゅう)されるのが落ちである。平和の論理が彼らとは異なるのだ。戦後日本は、戦わぬのが平和だと考えているが、彼らにとっては、平和は戦って勝ち取るものだ。戦争は政治の延長線上にあり、政治的駆け引きの中に戦争という手段が含まれている。さらに悪いことに、世界には戦争を金儲けの手段と考えている国も少なくない。要するに、戦後日本の平和主義など「平和ごっこ」に過ぎないということだ。【続】
2025.06.26
コメント(0)
-
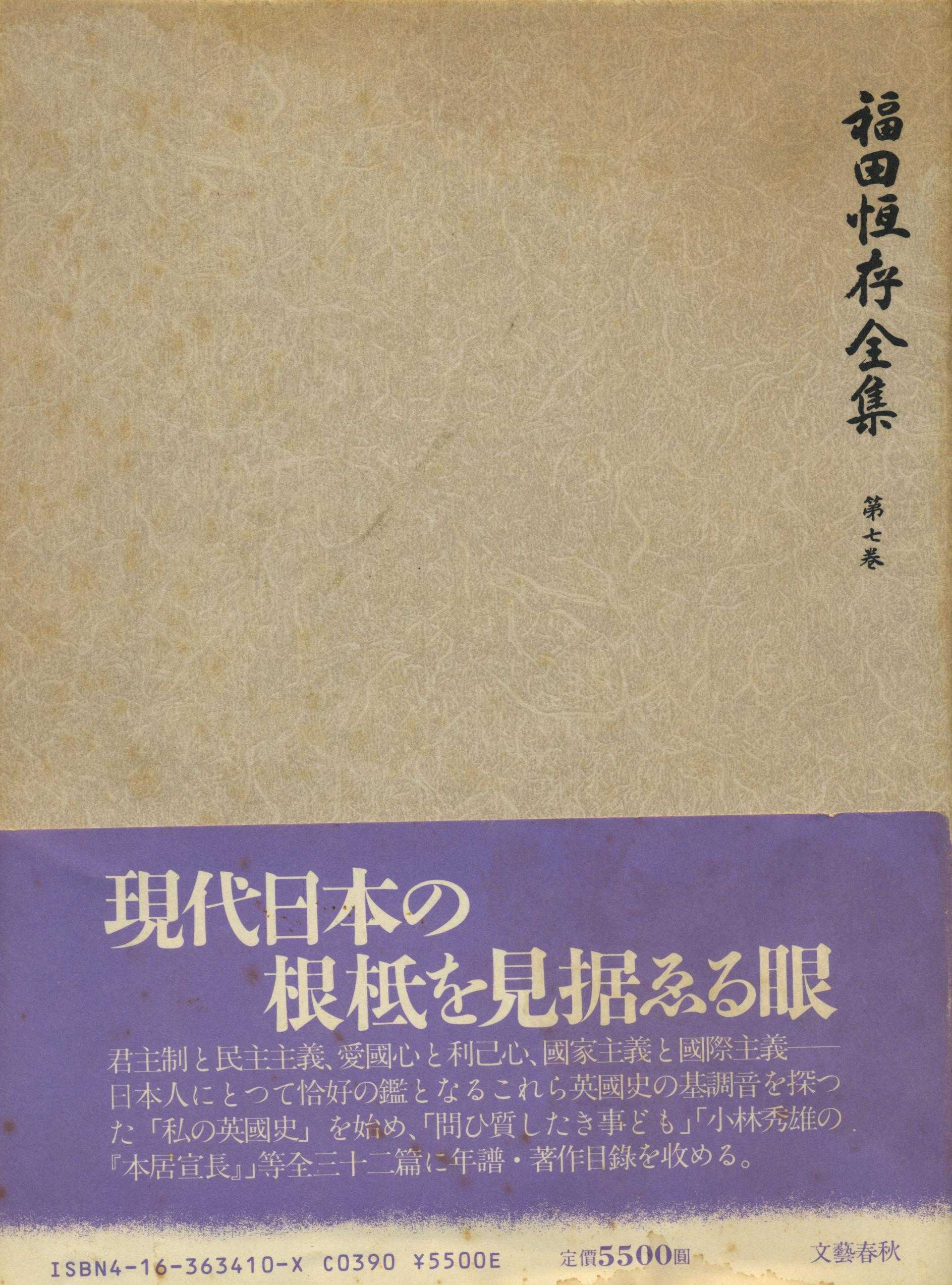
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(48)歴史を実体験せよ
《自然と人間とは離す事は出来ないが、両者は、それぞれ、その「倫」を異にする、その秩序を異にするもので、両者を一丸となすが如き原理は空想に過ぎない。さういふはっきりした考へが、徂徠の思想にあつた、両者は一丸とはならない、両者は、彼に言はせれば「出合ふ」のである。この 「出合ひ」が、人間の生活経験の基本形式であり、これに、人と人との出含ひが加はり、「無尽の変動」が出来するところに歴史がある。道の問題が、この出合ひに集中するものなら、「学問は歴史に極まり候事ニ候」と彼が言ふのは当然な事である。従つて、彼の考へによれば、もし自然の道といふ名が仮名なら、自然の歴史といふ名も仮名に過ぎない》(「考へるヒントII 歴史」:『新訂 小林秀雄全集』(新潮社)第12巻 考へるヒント、p. 250)《学問ハ飛耳長目之道と荀子も申候。此国に居て、見ぬ異国之事をも承候ハ、耳に翼出来て飛行候ことく、今之世に生れて、数千載(せんざい)の昔之事を今日ニミることく存候事ハ、長き目なりと申事ニ候。されバ見聞広く事実に行わたり候を学問と申事ニ候故、学問ハ歴史に極まり候事ニ候。古今和漢へ通し不レ申候へは、此国今世の風俗之内より目を見出し居候事にて、誠ニ井の内の蛙に候》(「徂徠先生答問書 上」:『荻生徂徠全集』(河出書房新社)第6巻、p. 178) 自分の体験や経験はごく限られたものであるから、それでは井の中の蛙にしかならない。が、歴史を学ぶことによって、自らの見聞を広げることが出来るということだ。《小林秀雄が荻生徂徠(おぎゅう・そらい)に学んで学問は歴史に極(きわま)ると考へるのは至極当然である。吾々は歴史が在る様(あるよう)にしか、歴史が書かれる様にしか生きられないからだ。吾々の人格は吾々の過去によって成立つ。吾々は吾々の過去であり、吾々の過去以外に吾々は存在しない。その吾々はまた歴史の中に生れて来るのである。確かに吾々自身の過去や歴史が無ければ、吾々は存在しないのだが、その過去や歴史は既に在るからといって吾々の所有には成らない。無為にして放って置いたのでは、吾々は禽獣(きんじゅう)と同じ様に唯(ただ)瞬間的現在しか所有出来ない。それは何も所有しないといふ事である。吾々は己れを空しくして過去を、歴史を自分のものにしようと努めなければならぬ》(「小林秀雄の『考へるヒント』」:『福田恆存全集』(文藝春秋)第7巻、p. 649) 我々は、歴史の積み重ねの上に存在している。が、その歴史が如何なるものかを理解しようと努めなければ、存在基盤は失われてしまうに違いない。歴史を有(も)たぬ存在は、ただ本能の赴(おもむ)くままに生きる禽獣に等しい存在でしかない。人間として生きようとするのであれば歴史を学ばなければならない。そして、日本人として生きようとするのであれば国史を学ばなければならない。《それは今日の歴史学が好んでさうする様に現在の自分を正当化するのに好都合な資料の集成を意味しない。歴史を追体験し、それを生きる事、さうする事によってしか、吾々は吾々の過去や歴史を自分の所有と化する事は出来ないのである。そして、過去や歴史を所有出来なければ、人格が成立しないとすれば、歴史とは人間の本性であるといふ小林秀雄の言葉は充分に納得出来ようし、学問は歴史に極り、学問は人倫の学だといふ考へ方も極(ご)く当り前の事に思へて来る筈である》(同) 他者の歴史観を鵜呑みにしてはならない。歴史そのものに降りて行って、自ら過去を「経験」しなければならない。歴史を知識として身に付けるのではなく、自らを歴史の中に置き、「実体験」しなければ、自家薬籠中(じかやくろうちゅう)の物とは成り得ない。【続】
2025.06.25
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(47)酸いも甘いも嚙み分けよ
林 それに対して、やらなければいかぬ。やれば勝つ、天が祐(たす)け神が助け拾ふから―――君が云ふ神風は何時も吹くから――さういふのがその頃の右翼なんだ(小林秀雄・林房雄「歴史について」(対談):『文学界』昭和15年12月号、p. 66) これが危険思想であるのは言うまでもない。天佑神助(てんゆうしんじょ)を信じ、大国ロシアと戦おうとするなど狂気の沙汰である。否、ある意味、狂気なしに戦争に踏み切るなど有り得ないとも言えるのであるが、最後の一押しが右翼の嚇(おど)しであったとすれば、それはそれで問題だったと言わざるを得ない。頭山満翁が何処(どこ)かの料理屋にゐたら、二階で伊藤博文が飲んでゐた。二階に上つて行つて、伊藤さん、ロシアと一つやつてもらひたいものです。さうかね、やらなければ殺すと諸君は言つてゐるさうだが、俺を殺せばロシアに勝てるかね。さあ、別に殺しもすまいが、とにかくロシアとやつてもらひたいものです。さうかね、とにかく君たちは怖いよと言つて笑ひ合つたといふ秘話がある。(同) 林氏は、「理論」について次のように語る。理論といふものは、人間がつくるものだが、人間自身がそれに仕へ、それに動かされるまでも行かなければ、真の理論ではない。左翼の理論は道具なんだから駄目なんだ。いつでも人が勝手に改めることができるからいかん。そこへ行くと、右翼の理論は天であり、神であるから、人間が勝手に理論を変へることが出来ない。人間が理論の方に仕へてしまふ。だから仕事が出来るのだ。(同) 左翼の理論は、人工的な拵(こしら)え物である。万物物事には、紆余曲折が付き物だ。が、理論は、それを嫌い、直線的な道筋を描こうとするから、無理がある。一方、右翼の理論は、自然に積み重なった堆積物である。試行錯誤があり、成功もあれば失敗もある。だからこそ、そこには「英知」が宿る。別言すれば、左翼の理論は「観念」であり、右翼の理論は「信仰」とも言われるだろう。 天の理論と人の理論を区別しなければいかん。人の理論は人の道具であって、これが天の理論を押しのるけやうなことがあつては間違ひが起る。科学振興にはどこまでも賛成だ。科学なしには戦争にも勝てぬし、現代生活も成り立たない。しかし科学主義が人間を支配するやうになつてはおしまひだ。合理主義者のインテリゲンチュアの考方がそれだ。人間の理論と天の理論を混同してゐる。人の理論によれば、純粋で無経験な青年は煽動出来るけれども、出来上るものは妙なものだよ、人の理論で煽動した奴は資本主義か共産主義かその結果は頽廃(たいはい)、ニヒリズム、闇取引、さういふものでしかないのだよ。天といふ無理論の理論に我々は一度参入しなければならぬ。それに参じない奴は結局自滅する。(同) 我々は、先人の営みの上に存在する。だからこそ、その営みを引受けることが始めなければならない。そして、酸いも甘いも嚙み分けることが必要なのだ。【続】
2025.06.24
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(46)神という理論
林 思想家の役割は真理の発見や発明ではない。たゞ1つの真理を如何(いか)に掴(つか)んで如何に表現するかによる…真理には古いも新しいもない。思想家が相手にしてゐるのは、たゞ1つ真理だといふことを君は言つた 小林 聖人には常の道無し――と老子は言つた。真理は1つだからこそ道は臨機応変になる。(小林秀雄・林房雄「歴史について」(対談):『文学界』昭和15年12月号、p. 64) 状況に応じて柔軟に形を変え得るから「真理」なのか、それとも、いつ何時(なんどき)でも決して形を変え得ないからこそ「真理」なのか。ここでは時間と真理の関係について深く足を踏み入れることは本筋から大きく逸れてしまうので避けるが、いずれにせよ難しい問題である。 林 日本の歴史を動かしてゐるのは右翼なんだよ、実は――。何故かといふと、右翼に理論が無いと言はれてゐるが、実は大理諭を持つてゐる。左翼や中間派は合理主義の埋諭しか持つてゐなかつた。誰の眼にも理論らしく見えるが、人を動かす力はない。だが、右翼は大変な理論を持つてゐる。神といふ理論――これ程大きな理論は他に無い。だから、右翼は日本を動かすことができた。(同、pp. 65-66) 「神」をどのように定義するのかもまた難しい問題であるが、西洋のGodとは一線を引いて考えるべき存在だと思われる。林氏の言う「神」とは、おそらく宗教的なものではないだろう。今を生きる者たちを見守る先人、俗世を離れ聖域に住まう超越的なる存在、それこそがここで言うところの「神」というものなのだろう。日本には、悠久の歴史がある。それが我々には神々が付いているという意味だ。伊藤博文といふハイカラが日露戦争を何故起し得たかといふと、その頃の右翼に嚇(おど)かされて引きずられた。伊藤博文のやうな第二流の英雄といふ者は皆んな合理主義者なんだ、だから数字や現象に頼る。日本よりイギリスが強く、日本よりロシアが強い、何故なら軍艦がこれだけあつて兵隊がこれだけあつて、鉄道が、電信がこれだけ延びてをり、それにくらべて日本の文明程度は未だ貧弱にして云々といふのが伊藤博文の総理大臣としての「理論」であつた。(同、p. 66) これは「理論」というよりも「理屈」程度のものであろう。ロシアのような大国と戦争に踏み切るには相当な勇気と覚悟が必要だ。が、伊藤にはそれがなかった。だから、やれない理屈を組み立てた。が、それではロシアは南下し、いずれ日本は蚕食(さんしょく)されてしまう。したがって、伊藤に必要だったのは、やれない理屈を組み立てることではなく、やれる方法を見付けることでなければならなかった。【続】
2025.06.23
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(45)新体制はむしろ復古である
小林 世の中には新しいものもなければ古いものもない…さう言へるのが歴史家の奥儀だよ。 林 合理主義と進歩主義の歴史観によれば、後から生じたものが、必らず新しく立派だといふことになる。これは誰しも陥り易い迷信だ…新体制とは何もかも新しくするといふ意味ではない。むしろ昔にかへることだ(小林秀雄・林房雄「歴史について」(対談):『文学界』昭和15年12月号、p. 64) 歴史も科学だということで進歩史観は創られた。なるほど、科学は進歩してきた。が、人間の営みである歴史は科学ではない。だから、歴史を進歩という直線的な尺度で捉えることは出来ない。それどころか、林氏は、天が下に新しきものなし、新体制はむしろ復古であると言う。 実は、英語のrevolution(革命)も、昔は「復古」という意味であった。The word 'revolution' was originally an astronomical term which gained increasing importance in the natural sciences through Copernicus's De revolutionibus orbium coelestium. In this scientific usage it retained its precise Latin meaning, designating the regular, lawfully revolving motion of the stars, which, since it was known to be beyond the influence of man and hence irresistible, was certainly characterized neither by newness nor by violence. On the contrary, the word clearly indicates a recurring, cyclical movement; it is the perfect Latin translation of Polybius's ανακύκλωση, a term which also originated in astronomy and was used metaphorically in the realm of politics. If used for the affairs of men on earth, it could only signify that the few known form's of government revolve among the mortals in eternal recurrence and with the same irresistible force which makes the stars follow their preordained paths in the skies. Nothing could be farther removed from the original meaning of the word 'revolution' than the idea of which all revolutionary actors have been possessed and obsessed, namely, that they are agents in a process which spells the definite end of an old order and brings about the birth of a new world. ―― Hannah Arendt, On Revolution(「革命」という言葉は元来、コペルニクスの『天球の回転について』によって自然科学における重要性が増した天文学用語であった。この科学的な用法では、ラテン語の意味を正確に留め、星が規則的、法則的に回転運動することを意味し、人間が影響せぬ、したがって不可避的なものだと知られていたので、確かに新しさや暴力性によって特徴付けられるようなものではなかった。逆に、この言葉は明らかに、周期的に繰り返される動きを示しており、まさに天文学に由来し、政治の領域で比喩的に用いられていた言葉、ポリュビオスの「リサイクル」のラテン語訳である。地上の人事に用いられれば、数少ない既知の政治形態が、人間たちの間で永遠に繰り返され、星を予め定められた天空の道に従わせるのと同じ抗いがたい力で回転しているということしか意味はしない。すべての革命家が抱き、取り憑かれてきた、自分たちは旧秩序の終焉をはっきりと告げ、新世界の誕生をもたらす過程の代理人であるという考えほど、「革命」という言葉の原義からかけ離れたものはないだろう)-ハンナ・アーレント『革命について』The fact that the word 'revolution' meant originally restoration, hence something which to us is its very opposite, is not a mere oddity of semantics. The revolutions of the seventeenth and eighteenth centuries, which to us appear to show all evidence of a new spirit, the spirit of the modern age, were intended to be restorations. It is true, the civil wars in England foreshadowed a great many tendencies which we have come to associate with what was essentially new in the revolutions of the eighteenth century: the appearance of the Levellers and the formation of a party composed exclusively of lowly people, whose radicalism came into conflict with the leaders of the revolution, point clearly to the course of the French Revolution; while the demand for a written constitution as 'the foundation for just government', raised by the Levellers and somehow fulfilled when Cromwell , introduced an 'Instrument of Government' to set up the Protectorate, anticipates one of the most important achievements, if not the most important one, of the American Revolution. Yet the fact is that the short-lived victory of this first modern revolution was officially understood as a restoration, namely as 'freedom by God's blessing restored', as the inscription runs on the great seal of 1651.―― Ibid(「革命」という言葉が、もともとは復古を意味し、したがって我々には正反対のことを意味したという事実は、単なる意味論の妙ではない。 17、8世紀の革命は、新しい精神、近代の精神の証拠をすべて示しているように我々には見えるが、それは復古することを目的としたものだった。確かに、イングランドの内戦は、18世紀の革命の本質的な新しさと関連づけるようになった非常に多くの傾向を示していた。すなわち、平等主義者の登場と、下層民だけで構成された政党の結成は、その急進主義が革命の指導者たちと対立するようになり、フランス革命の経過を明確に指し示している。一方、平等主義者によって提起され、クロムウェルが護民官を設置するために「政府文書」を導入したときになんとか実現に漕ぎ着けた「公正な政治の基礎」としての成文憲法の要求は、アメリカ革命の最も重要な成果ではなくても、最も重要な成果のひとつを予期させるものである。けれども、実は、この最初の近代革命の短期間の勝利は、1651年の国璽(こくじ)に刻まれたように、復古すなわち「神の加護による自由」として公に理解されたのだった)- 同【続】
2025.06.22
コメント(0)
-
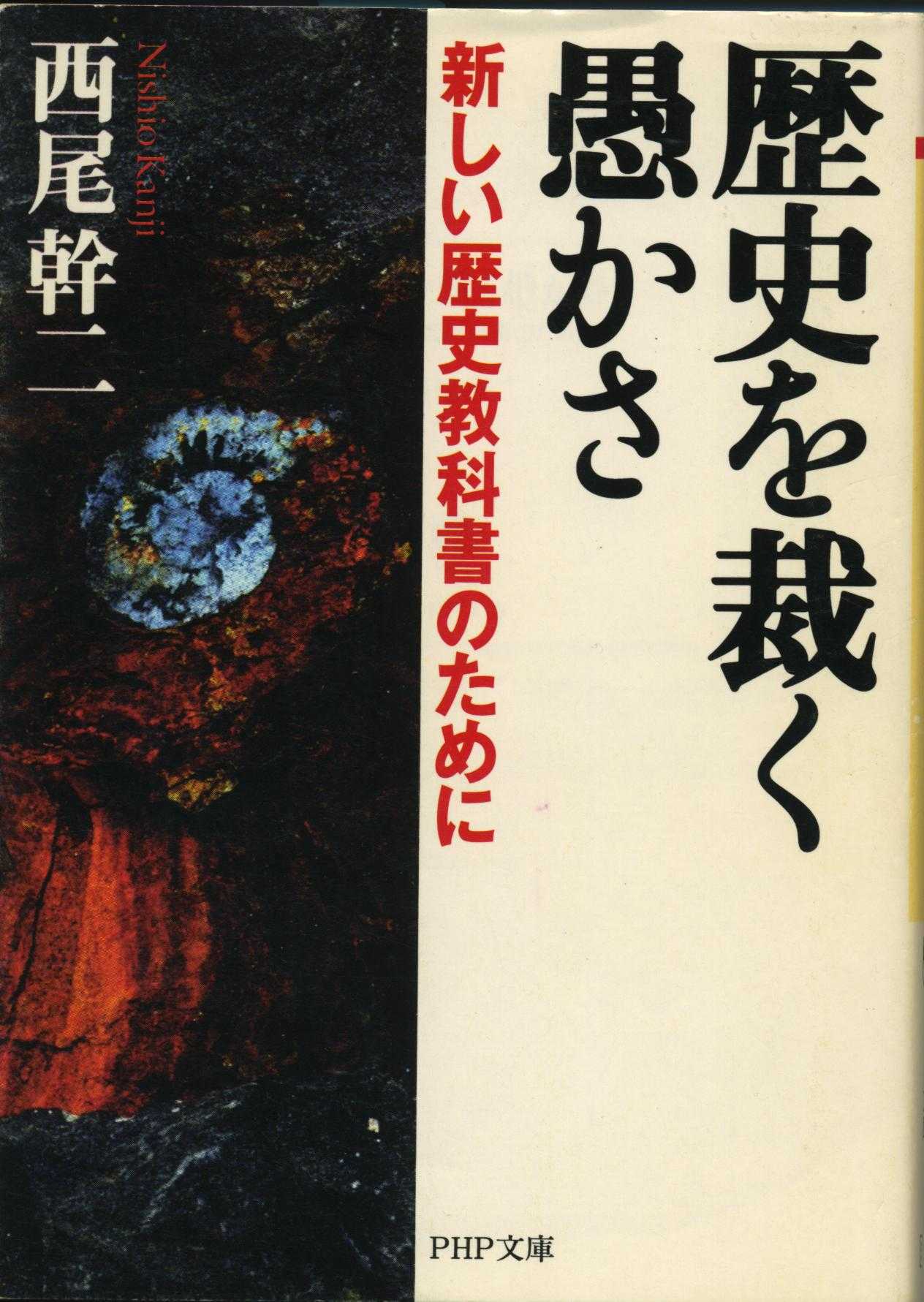
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(44)歴史は過去の事実について過去の人々がどう考えていたかを知ることである
小林 自由、平等、進歩…そんな幻影を持ってゐては歴史のリアサティは決して掴(つか)めない。ある理想から歴史のリアリティに達するのではない、歴史のリアリティに突き当る事が、歴史の理想を悟らせるのだ。(小林秀雄・林房雄「歴史について」(対談):『文学界』昭和15年12月号、p. 63) 自由、平等、進歩、これらは西欧産の観念である。なるほど、西欧には、このような観念を生む土壌があっただろう。が、日本は違う。日本は、自由や平等を求めて革命を起こさねばならないような抑圧に満ち、差別に打ちひしがれるような状況にはなかった。だから、日本の歴史をこういった西欧産の観念を用いて分析し、理解しようとすることは出来ないだろうし、すべきでもない。 小林 進歩主義者は、歴史を直線的に見たがるものだ。歴史の河がどういふ風に流れやがて終末の大海に注ぐか、さういふ風に見たがるものだ。歴史上の人物が、さういふ流れとは垂直にどう生きてどう死んだかを見ない。彼が山に登つて何米突(メートル)迄(まで)登ったかといふ事が測量てきなければ歴史家ではないのだよ。歴史家といふ者は飛行機から見下してはいけないのだ。やっぱり山は此方から観れば幾つも重(かさな)つてゐて、登らなければ向ふの山が見えぬといふ態度を取らねばいけない。立派な歴史家は皆さうしてゐる。1つの山を越せばまた向ふに雪を被った山といふものが現はれる。それが歴史だよ。歩いて行くに連れて――。(同) 進歩主義者は、偏(ひとえ)に「マルクスの予言」通りに社会が進んでいるかどうかにしか関心がない。かつて人々が実際どのような生活を送っていたのかはどうでもよい。つまり、進歩主義者は、歴史自体には興味がないのだ。 が、歴史家は、地に足をつけて、過去の出来事に向き合わねばならない。《歴史は、過去の事実を知ることではない。事実について、過去の人がどう考えていたかを知ることである。過去の事実を直に知ることはできない。われわれは過去に関して間接的情報以外のいかなる知識も得られない。 間接的情報を組み立てて直接的事実に近づくのは、われわれの側の意志的作業である。できるかぎり過去の人の身になってみる想像力と、われわれが見えない未来を今どう見て生きようかという切なる祈願と――この相矛盾する2つのものの相剋(そうこく)が、歴史である。 ところが、どういうわけか、現代の知識人は過去の事実を正確に把握できると信じている。事実が歴史だと思いこんでいる。そして、その事実について過去の人がどう考えていたかは捨象して、自分が事実と勝手にきめこんだ事実を以て、現在の自らに必要な欲求を満たす。 それは事実の架空化による事実への侵害である》(西尾幹二『歴史を裁く愚かさ』(PHP文庫)、p. 289)【続】
2025.06.21
コメント(0)
-
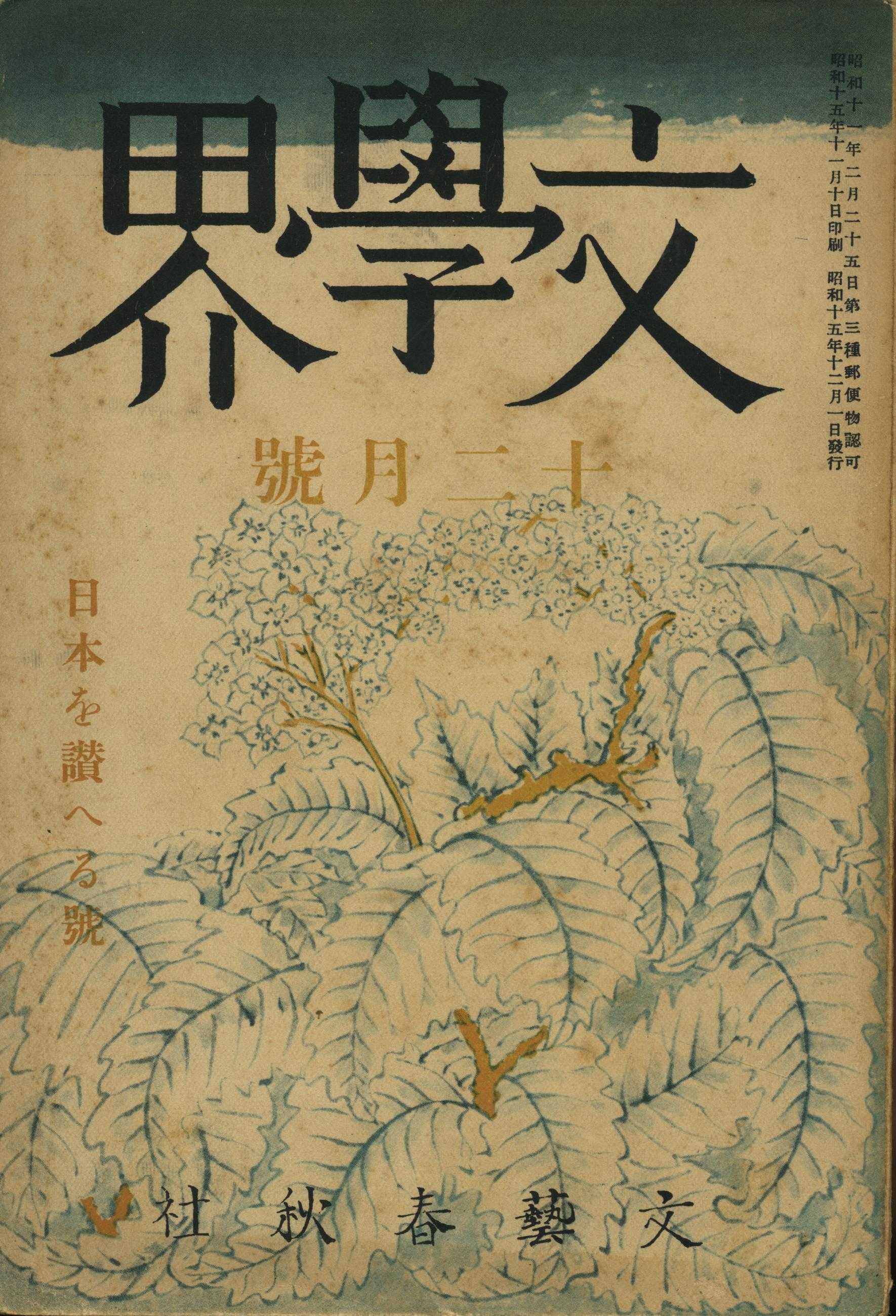
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(43)魂に触れる歴史教育
小林 歴史の力はそれが文学である処に於(お)いて、最大なのだ。唯物史観といふものは、歴史の魂に決して触れやしない。(小林秀雄・林房雄「歴史について」(対談):『文学界』昭和15年12月号、p. 59) 唯物史観とは、カール・マルクスが提唱した「進歩史観」である。社会は、生産手段の発展に伴って発展するという考え方だ。が、ここには、実際に時代を生きた人々の声がない。関心があるのは「物」だけである。このような歴史観が一面的なものであることは言うまでもない。 林 君は歴史教育は日本勤王史をやるべきだと言つたさうではないか。 小林 歴史の初等教育や、中等教育で、日本史を上古から現代までならしにして浅薄に教へてはいかぬといふのだ、事件とか時代とかに目安を置いて一貫した風景の鎖を教へ込まうとしては駄目だ、と言ふのだ。さういふ方法で歴史といふものは、国民思想的なものだ。国民道徳的のものであると学生に納得させる事は非常に難かしい。(同) 例えば、1333年に鎌倉幕府が滅び、翌年後醍醐天皇が建武の中興を始める。が、1338年足利尊氏が室町幕府を立て、後醍醐天皇は追われて吉野に南朝を開く、などといった年代記を身に着けることはそれなりに大切なのであるけれども、それだけでは、国の歴史の奥底に流れる思想や精神というものが見えてはこない。それでは、日本の「伝統」も分からないし、日本人としての帰属性も高まらない。歴史は、受験に必要な知識でしかない。さういふ風な方法で日本歴史を一と通り覚え込ませれば、いゝかね、覚え込ませれば、だよ、学生は国体観念といふものを理解するだらうと考へる。実にお目出度い考へだ。国体観念といふものは、覚え込ませるのではない、感得させるものだ。だから感得させる様に歴史を教へねばならない。(同) 何年に何が起こった、誰が何をしたのかという年代記には、「国体」というものがない。日本という国がどのような国なのか、その「国柄」を知れるような歴史教育が必要だということだ。それには、歴史に教へるべき重点を置き、例へば建武の中興とか明治維新とかいふ処をくはしく教へるのだ、暗記しようと思つても、暗記出来ない程くはしく教へて、学生の興味といふものを喚起するのだ。興味を喚起するといふ事が一番大切なのだ。学生が面白くてたまらぬ様な話は、慥(こしら)へなくても歴史の上にあり余るほどあるではないか。(同、pp. 59-60) 教育は受験のためにあるのではない。受験のための歴史教育によって、歴史は、表面をなぞっただけの歴史に矮小(わいしょう)化されてしまっている。実際に学生がほんたうに虚心坦懐に歴史に対して最も興味があるものは何と言っても美談或は人間的なエピソードといふものだよ、不確実な美談であつても心を唆(そそ)らぬ正確な史実といふ様なものより勝る事万々だ。心を唆られるといふ処に、歴史のほんとうのセンスが生れるのだ。だから、僕に言はせると、初等の歴史教育では、歴史なぞ教へる必要はない、歴史に対する正しいセンス、正しい情操を教へよ、と言ふのだ。それが出来ないから、歴史についていかに精(くわ)しくなつてもをかしな事になるだけなのだ。(同、p. 60) 歴史をただ過去の出来事として見るのではなく、その時代を生きた人々の心にまで入り込まこまなければ、歴史に流れる「精神」に触れることは出来ないということだ。【同】
2025.06.20
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(42)歴史は己を空しくして見るべきもの
《芭蕉は自分の態度を風雅と名づけました。彼に言はすと風雅といふものは、造化に従ひ四時を友とすといふのでせう。風雅といふことが今日非常に誤解されてゐるけれども、それは、消極的な態度でも洒落れた態度でもない。少くとも日本人が抱いて、大地に根ざした強い思想です。己(おのれ)を空しくして、いろ/\な思想だとか、意見だとか、批判などに煩(わずら)はされないで自然の姿が友となって現れて来る、自然と直接につき合ふことが出来る。さういふ境地は易しくはないのです。さうなると見るもの花にあらずといふ事なし、といふ事になる。即(すなわ)ち美は、やさしくはないのです、また芭蕉は虚にあって実を行ふといふ事を言つてゐるが、それは己を空しくするといふことは決して消極的な態度ではない。結局それがものを創造する唯一の健全な状態なのだと言ふ意味だと思ひます》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 117) 思想に惑わされず、周りの意見に惑わされないこと、そして自分の感情に惑わされないこと、それがすなわち己を空しくするということだ。先入観なしにあるがままを感じ取る。それが芭蕉言うところの「風雅の誠」ということなのではないか。《歴史は第2の自然である。その意味で、歴史に従ひ歴史を友とし、見るもの花にあらずといふ事なし、といふ様に歴史が見えて来る、つまり芭蕉の考へた風雅といふやうな強い精神のなかに歴史も亦(また)現れて来なければ、さういふやうな純粋で創造的な状態に至らうとしなければ伝統に根ざした創造といふことは空言だらうと思ふ、出来ないことだと思ふ。だから僕はさういふ精神にさへ達すれば新しい工夫、新しい解釈といふ様なものにとらはれる事はない。たゞ吾々は常に伝統に還(かえ)ればいい、自然に還ればいいのだ。そこに自ら新しい創造の道が開かれる》(同) 「見る処花にあらずといふ事なし、おもふ所月にあらずといふ事なし」(松尾芭蕉「笈の小文」)。眼前は花に満ち溢れ、心の中はすべて月明かりに照らされている。それらを見えなくしているのは、己の心の中の雑音、すなわち、「雑念」である。だから、雑念を払い、己を空しくすればよいのだ。が、己を空しくすることは、口で言うのは容易(たやす)いが、誰にでも出来るようなものではない。 歴史もまた、己を空しくして見なければならない。雑念に塗(まみ)れた歴史など美しくはない。【続】
2025.06.19
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(41)歴史を見る透徹した目
《のつぴきならない或る過去の形に対する愛情、尊敬を言ふので、凡庸な考証家の頭に、記憶によつて詰つてゐる歴史的な事実の群れといふやうなものを申すのではない。歴史が因果の鎖として、又は合理的な発展として理解されるといふ事と、歴史の厳(いか)めしい形といふものがまざまざと感じられるといふ事とは自ら別事でありまして、例へば、鎌倉時代とは上代の文明形式のどういふ様な崩壊の結果であり、又、どういふ具合に近世の文化形式を用意した時代かといふ様な事を理解するのはやさしい事ですが、鎌倉時代の思想なり人間なりの形を感得するといふ事は難かしい業(わざ)である。別の言葉で言ふと、歴史を記憶し整理する事はやさしいが、歴史を鮮やかに思ひ出すといふ事は難しい。これには詩人の直覚が要(い)る》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、pp. 116-117) 例えば、社会は共産社会に向けて進んでいくという「マルクスの予言」に合わせて史実を解釈する場合、そこには過去の人々や社会の営為には何ら愛情も尊敬もありはしない。あるのは、搾取に対する怨念であり、不平等に対する不満である。つまり、マルクス史観とは、「革命」を引き起こすための下ならしのようなものなのである。《芭蕉は非常によく自然を見た人です。己を空しくして……。己を空しくして自然を余程観察しなければあんな俳句は出て来やしません。だけれども芭蕉のとった態度は決して客観主義といふものではないでせう。僕が己れを空しくして歴史に接すると今申してゐる事も客観主義といふ様な事を言つてをるのではないのです。客観主義といふ様なものは現代に於(お)ける1つのスローガンに過ぎぬ。客観主義者は己れを空しくするどころか、このスローガンによってどれほど歴史を小賢(こざか)しく歪(ゆが)めて見てゐたか知れない》(同、p. 117) 西洋哲学における主観と客観の二項対立は、簡単に言えば、「私の目」と「神の目」の対立とも言われるだろう。が、西洋における「神」(God)は日本にはいない。だから物事を客観的に見るなどということは日本人には出来ない芸当である。 人には、何かを目にすれば、それを評価する習性がある。「己を空しくする」とは、目にしたものを評価することを拒絶するということだ。ここに言う「目」とは肉体的なものだけではなく精神的なものも含まれる。つまり、五感で感知することだけに特化するということだ。言い換えれば、物事に対して透徹した目をもつということ、そこにあるものをあるがままに理解するということだ。そこに観念の入る余地はない。【同】
2025.06.18
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(40)不信教育に堕した平和教育
《歴史の本当の魂は、僕らの解釈だとか、批判だとかさういふやうなものを拒絶するところにある…吾々の解釈、批判を拒絶して動じないものが美なのだ。本当の美しいものはさういふものなのだ。吾々の解釈で以てどうにでもなるやうなものは本当の美ぢやない。本当の美しい形といふものが、歴史のうちには儼然(げんぜん)としてあつて、それは解釈しようが、批判しようが、びくともしない》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 116) 小林氏の慧眼(けいがん)がこのように言わしめているのであるから、然(さ)もありなんとしか言い様がない。《本居宣長の 「古事記伝」…あの本が立派なのは、はじめて彼が古事記の立派な考証をしたといふ処だけにあるのではない。今日の学者にもあれより正確な考証は可能であります。然(しか)しあの考証に表れた宣長の古典に対する驚くべき、愛情は無比のものなのである。彼には古事記の美しい形といふものが、全身で感じられてゐたのです。さかしらな批判解釈を絶した美しい形といふものをしっかりと感じてゐた。そこに宣長の一番深い思想があるといふことを僕は感じた。僕はさういふ思想は現代では非常に判りにくいのぢやないかと思ふ。美しい形を見るよりも先づ、それを現代流に解釈する、自己流に解釈する、所謂(いわゆる)解釈だらけの世の中には、「古事記伝」の底を流れてゐる、聞える人には殆(ほとん)ど音を立てゝ流れてゐる様な本当の強い宣長の精神は判りにくいのぢやないかと思ひます》(同) 対象に向かう感情に応じて、如何様(いかよう)にも歴史は解釈され得る。差し詰め、「平和教育」が暗い相貌(そうぼう)を纏(まと)っているのは、日本に対する憎しみに端を発するからではなかろうか。成程(なるほど)、大陸と日本本土の狭間(はざま)にある沖縄は、一再ならず政治的綱引きの困難に直面してきたに違いない。沖縄戦においても多大なる苦難を強いられた。沖縄の平和教育の裏には、おそらく日本に対する強い不信があるのだろう。 が、戦争を知らない世代は、日本に対する不信感は強くない。だから、幾ら平和を唱えても響かない。であれば、日本に対する不信を煽るしかない。そこに平和運動の歪(ゆが)んだ構造があるように思われる。 平和主義者の歴史には、宣長のような愛情がない。むしろ憎しみがある。平和教育が不信教育へと堕してしまっている。【続】
2025.06.17
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(39)自分たちが戦争を欲しなければ平和でいられるという「偏執病」
小林氏は、《スローガンといふものを離れて歴史が見られるやうになることは容易でない》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 115)と言う。《歴史の新しい見方、或(あるい)は新しい解釈といふやうなものは非常に魅惑的なものです。何か非常に面白さうなことです。つまり巧言令色なのである。結局歴史といふものは決して新しい解釈だとか、現代的な考へ方といふやうなものでびくともするものではないといふことが僕には段々判つて来た。歴史といふものは僕らの現代の見方だとか、解釈といふやうなものでぐらつくやうな弱いものぢやありません。そんな事でビクともするものではない、さういふ事がわかつて来た》(同) 戦後日本における「平和主義」は巧言令色のスローガンなのである。平和主義を唱えれば平和が得られると本気で思っているのかどうか分からないけれども、とにかく戦後日本人は、平和主義というスローガンに取り憑(つ)かれてしまっている。《古典はどうして僕らに残つたのか。若(も)しも万葉集を現代的に解釈することが本当に正しいことであるならば、万葉集はなくなつてをりますよ。万葉集それ自体よりも解釈の方が立派なら、解釈の方が残つてをればいいぢやないか。だけれども残らない。万葉集はあの書いたその儘(まま)の姿を保つてゐる。昔あつたがまゝの形が今も眼の前にあるのだ。歴史も亦(また)形です。厳かな形である。その形といふものは、新解釈といふ様なものを通してはじめて解るといふものではない、歴史的遺品から僕等が直接感得するより他はないものであります》(同) 古典と歴史を同列に扱うことは出来ない。古典作品は実存するが、歴史は解釈を施すことによって描かれるもので、謂わば「実体なき観念」でしかない。例えば、万葉集は昔も今も万葉集であることに変わりがないが、歴史は時代とともに変遷し、戦後は、戦前の皇国史観とは対極に位置する東京裁判史観となるといったことも起こり得るのだ。 蓋(けだ)し、明治以降、日本の歴史は政治に翻弄(ほんろう)され続けてきたと言えるだろう。明治政府は、自己を正当化するために歴史を用いた。日本は天皇を中心とする神の国であるという歴史観、すなわち、「皇国史観」である。皇国史観が西欧列強を押し返すのに一役買ったことは間違いない。が、その行き過ぎが英米との衝突を生んでしまったこともまた事実であろう。 日本は戦いに敗れた。そして、米国は、日本が再び脅威とならないよう、日本人に暗黒の歴史を刷り込んだ。それが東京裁判という政治的復讐劇で最高潮と迎えた歴史観、「東京裁判史観」である。以降、日本人は、自分たちが戦争を欲しなければ平和でいられるという「偏執病」(paranoia)的症状を呈している。侵略戦争は愚か自衛戦争をも否定し、もし他国が日本を侵略してくれば、白旗でもって迎え入れればよいという「妄想」(delusion)に支配されてた人さえ存在する。【続】
2025.06.16
コメント(0)
-
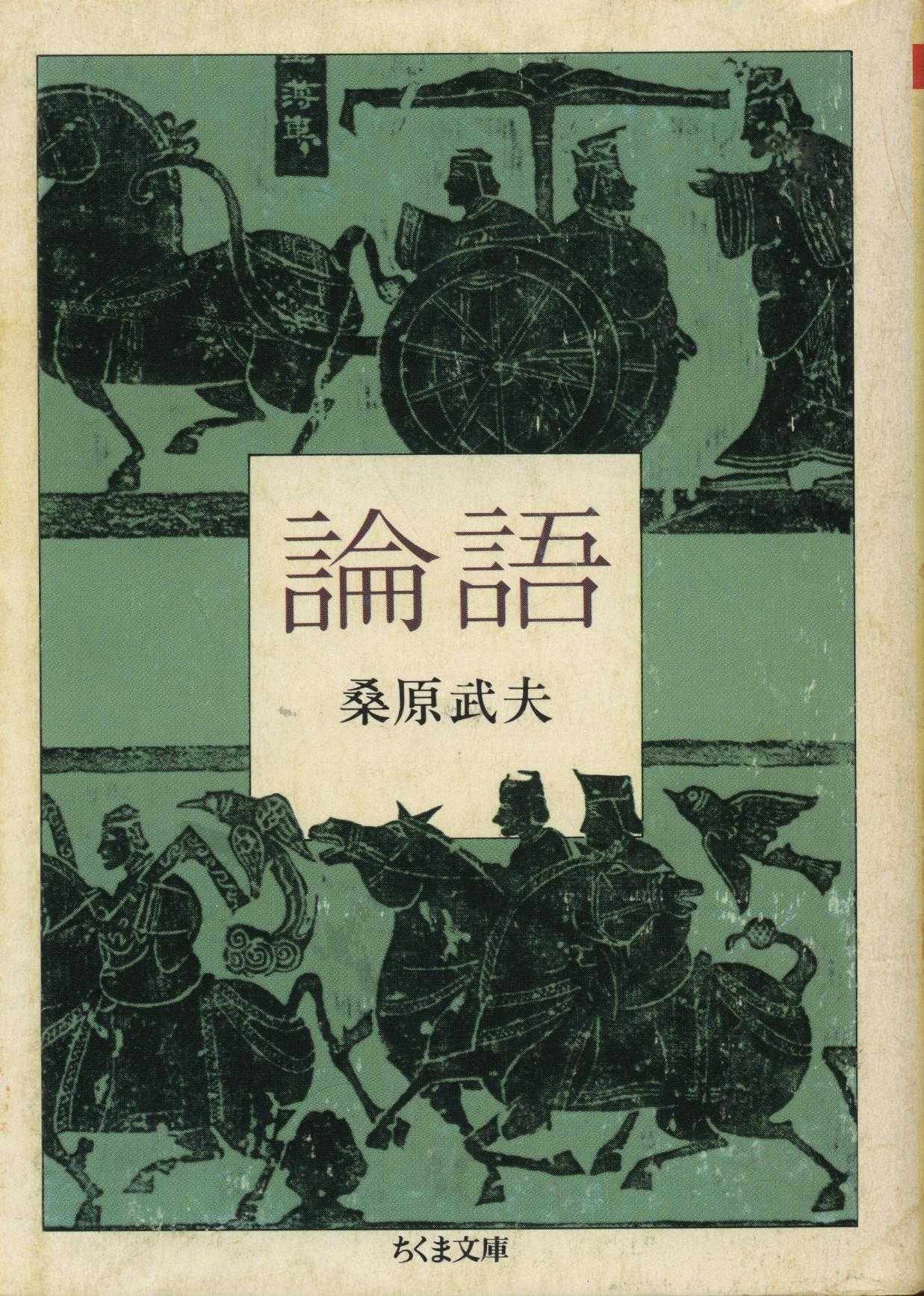
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(38)桑原武夫氏の誤解
《誰が見ても堂々と見える思想といふやうなものを僕はどうも信用出来ない。僕等はさういふものにどのくらゐうまく、ごまかされたか判らない。「巧言令色鮮仁」といふ言葉は有名です。然(しか)し巧言令色といふものも時代によって変ります。今日では雄弁だとか、美文などは信用する人はないでせう。だけれども今の人はすぐ理論を信じますよ。理論は現代に於(お)ける巧言令色です。美文が廃(すた)れれば理論がはびこります。つまり巧言令色がはびこることに於ては決して変りはない》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 115)巧言令色鮮(すくな)し仁。(論語:学而第一)(言葉を巧(たく)みにし・外貌を飾って人を悦(よろこ)ばせようとすると、己の本心の徳がなくなってしまうものである)(宇野哲人『論語新釈』(講談社学術文庫)、p. 18) このような解釈に桑原武夫氏が異論を唱える。《「子路第十三」の27に、「子日わく、剛毅木訥(ごうきぼくとつ)は仁に近し」という言葉がある。孔子は礼楽を重んじながら、しかも表面的な行動のなめらかさを嫌い、いささか鈍重であっても毅然としたものへの好みをもっていたように思われる。しかし、文学を学ぶとは内容を伝達するだけでなく、言葉を巧みにすることであり、礼儀作法を知るとは容色を柔らげることではないのか。家庭内において父母にたいするとき、巧言令色は孔子の立場からはむしろはめるべきことではなかろうか(「為政第二」8)。孔子は恋愛を語らないが、愛する異性にたいして私たちは不可避的に巧言令色となってしまう。人間性に明るい孔子が簡単に巧言令色を否定し去ったはずはない》(桑原武夫『論語』(ちくま文庫)、p. 13) 言葉遣いに気を配ることも大切であるが、だからといって言葉を「文(かざ)る」のは良くない。「巧言」とは、言葉巧みに思ってもないことを言うことであり、「令色」とは、愛想よく取り繕うことであるから、巧言令色は否定されて然(しか)りである。《孔子は社会生活全般において粗野を奨励したのではない。それが一般原理として受けとられてしまい、特にことあげすることを好まない日本国民性の上に乗ったとき、はなはだ悪い影響を残したのではないかと思われる。真実は堂々と公言すべきである。しかし、正しいことならどんなにまずい表現で仏頂面をしてわめいてもよい、ということには決してならない》(同) 孔子は、「剛毅木訥は仁に近し」と言っているのであるから、強い意志と飾り気のない気性を好ましいとしたのである。それを勝手に〈粗野〉という言葉に置き換えて、否定しても始まらない。ましてや、〈正しいことならどんなにまずい表現で仏頂面をしてわめいてもよい〉などという話ではないことは言うまでもない。《文明の社会とは、内容の真実を美しい形式と調和させる努力ということではなかろうか。儒教を基本とする中国、少なくともその読書人の世界では、そうした努力があったと考えられるが、素朴実在論を基調とする日本社会は、巧言令色を排撃するのあまり、個物における美的洗練は実現しえたけれども、社会的人間関係における洗練と調和を十分に育てえなかったのではなかろうか。秀れた言葉がまずい結果を生むことがあるのである》(同) が、孔子は、文るのは好(よ)くないと言っているだけであるから、巧言令色を嫌うということと〈内容の真実を美しい形式と調和させる〉ことは矛盾しない。桑原氏の指摘は、巧言令色という言葉の誤解に基づくものであろう。【続】
2025.06.15
コメント(0)
-

西田議員の「歴史の書き換え」発言について(37)スローガン
《現在吾々はかういふ所謂(いわゆる)歴史上の転換期に来て、いろ/\な形で理想が説かれてゐるが、理想を持つのはいいのだけれども、理想といふものは一番スローガンに堕し易い性質のものです。自分で判断して、自分の理想に燃えることの出来ない人はスローガンとしての理想が要るが、自分でものを見て明確な判断を下せる人にはスローガンとしての理想などは要らない。若(も)しも理想がスローガンに過ぎないのならば、理想なんか全然持たない方がいい》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 114) 理想は、現実と平衡してはじめて意味をもつ。一方、地に足の着かぬ理想は、ただの空想に過ぎない。そして、内実を伴わない空想がただのお題目になって「スローガン」化するのだ。スローガン化してしまった理想など有害無益でしかない。《孔子の抱いた理想は仁でせう、或は聖といふものであった。聖とか仁といふものが孔子の理想であったのですが、論語を読んで御覧なさい。どこにも孔子は仁とはかういふものだ、聖とはかういふものだといふことは書いてない。正にそれの逆です。いかに聖だとか仁だとかいふものがスローガンになり易いかといふことを警告してゐるのであります。人間は理想を――スローガンではなくて真の理想を抱くことがどれくらゐむづかしいかといふことを、孔子様は説いてゐるので、それを見ると2500年前から人間の弱点は同じだといふことを痛感する次第です》(同) 観念は、融通無碍(ゆうずうむげ)な生き物である。が、その観念を言葉で無理やり固定化してしまえば、身動きが取れなくなって死滅する。だから、「仁」だの「聖」だのと観念を言語化することには注意が必要なのだ。己に克(か)ち礼に復(かえ)るを仁と為(な)す。一日も己に克ち礼に復れば天下仁を帰(ゆる)す。仁を為すこと己に由る、人に由らんや。(論語:顔淵第十二)(仁は心の全徳で天の与えた正しい道であり、天の与えた正しい道が形に表れて中正を得たものが礼である。しかし、仁は私欲のために壊(やぶ)られるものである。故に己が私欲に打ち勝って礼に反(かえ)るのが仁を行う方法である。仁は天下の人の心に同じく具(そな)わっているものであるから、誠に能(よ)く一日の間でも己か私欲に打ち勝って礼に反れば、天下の人が皆我が仁を与(ゆる)す程、仁を行う効果ははなはだ速(すみ)やかでありかつ至って大きいものである。このような仁を行うのは己自身の修行によることで他人に関係のあることではない)(宇野哲人『論語新釈』(講談社学術文庫)、pp. 335-336) つまり、問題なのは、己に打ち勝つことであり、「克己」なのだ。【続】
2025.06.14
コメント(0)
-
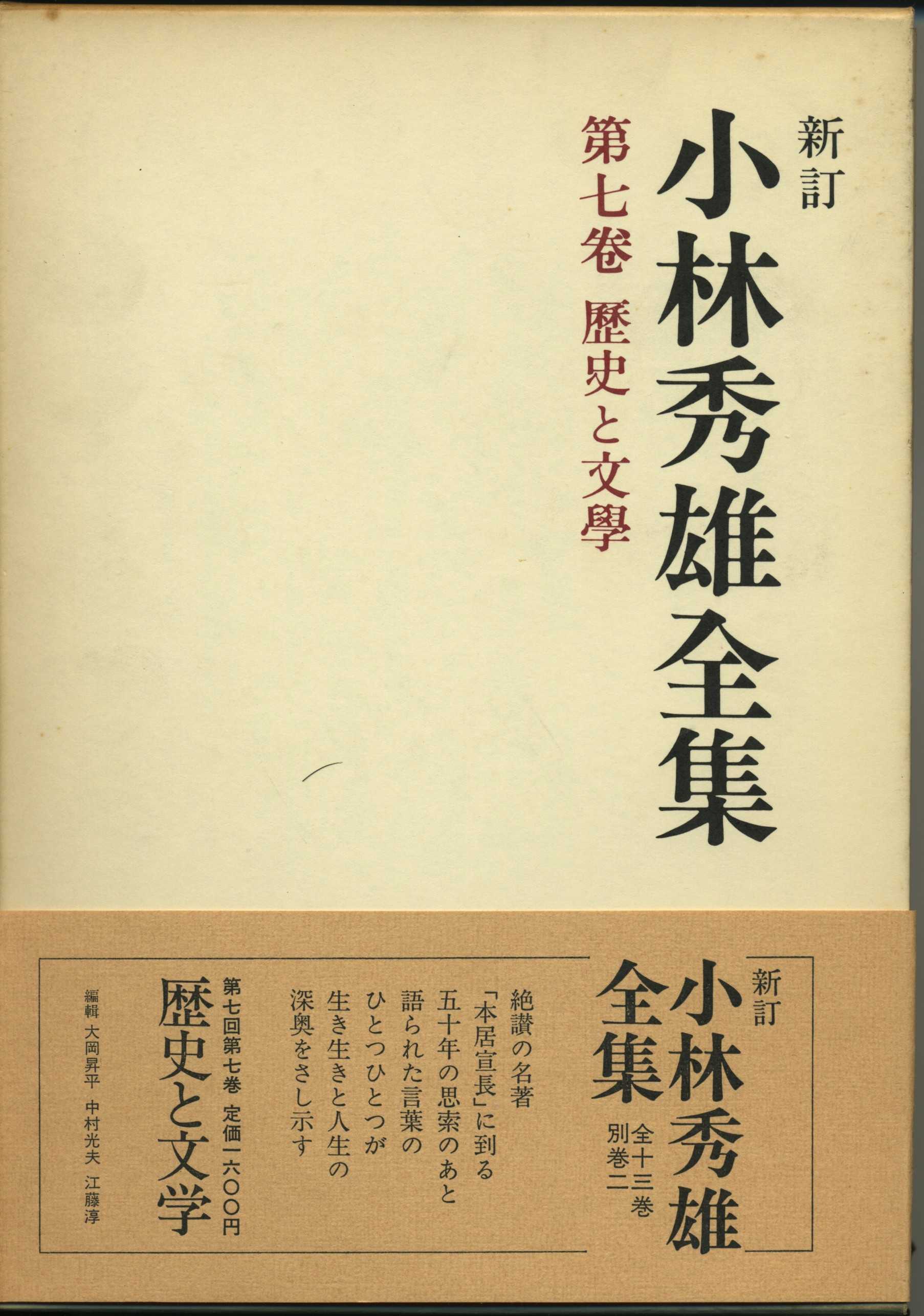
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(36)世間に跳梁するスローガンという幽霊
《思想家は、唯一の思想目的、即(すなわ)ち己(おの)れに克(か)つて思想を創り出す事を知るのみである。この信條は、己れ以外のものを相手とするあらゆる抗争は、思想家にとって徒爾(とじ)であるといふ徹底した認識からしか生れない。敵が負けたところに、自分が勝った証拠を見ようとする愚昧(ぐまい)が、論戦といふ何物も産まぬ浪費に望みをかける。やがて思想戦といふスローガンが生れる》(「ゼークトの『一軍人の思想』について」:『新訂 小林秀雄全集』(新潮社)第7巻 歴史と文学、p. 173) 議論に勝ったからといって、思想が優れていることが証明されるわけではない。思想の優劣は、議論の勝敗によって決まるのではない。 思想は、思想家が己に打ち勝つことによってしか優れたものとは成り得ないのである。議論によって思想の綻(ほころ)びが露呈することもあるだろう。だから私は、議論することが思想にとって無意味、徒爾だとまでは思わないし、思えない。甘い、覚悟が足りぬ、自分の外に活路を意味出そうとすれば「思想ごっこ」にしかならない、思想とはもっと透徹したものだ、と言われれば、返す言葉がないが…《世間に跳梁(ちょうりょう)するスローガンといふ幽霊に対する唯一の護符は、「明らかに考へることだ」とゼークトは言ふ。この忠告も明らかに考へてみなければならない。裏は恐らくかうなる。勿論、幽霊の信者等も亦(また)その護符を持ってゐる、明らかに考へる事。従つて抗争は徒爾である、と》(同) 小林氏は、別のところで次のようにも言っている。《人間の精神の最大の敵は3つある。1つは馬鹿だ。それから官僚といふものがある。それからスローガンといふものがある。そのスローガンといふものが人の精神に対して一番厄介な頑固な敵だと言ふのです。あの時にウイルソン大統領が提げたのは平和主義といふスローガンだ。或はソーシャリズムといふスローガンを提げたものは帝国主義打倒といふスローガンを叫ぶ。さういふやうなスローガンは皆んな自分で以て考へる力のない人のためにあるのだと言ふのです。自分で以てものをはっきりと見て、明確な判断を下せる人間にとってスローガンは要らない。けれどもさういふ人間ばかりはゐないから自分で物を見、考へられない人がゐる、さういふ人は何を考へて何を仕出かすか判らないから、さういふ人にはスローガンを与へる。かういふやうにお前には自分で考へる力はないのだから、世の中はこんなものだといふことを知らせるためにスローガンを与へれば、これは滅多なことをしない。それがスローガンの用途だ。だけれども自分で以てものを見て、自分で以て判断を下せる人には、スローガンなんといふものは要らない》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 114) 差し詰め戦後日本における「平和主義」も、自分で物を見、判断しない人達に与えられた「スローガン」なのであろう。自分で考えることを放棄した人に限ってすぐ感情的になる。そこには思考の余地はない。【続】
2025.06.13
コメント(0)
-
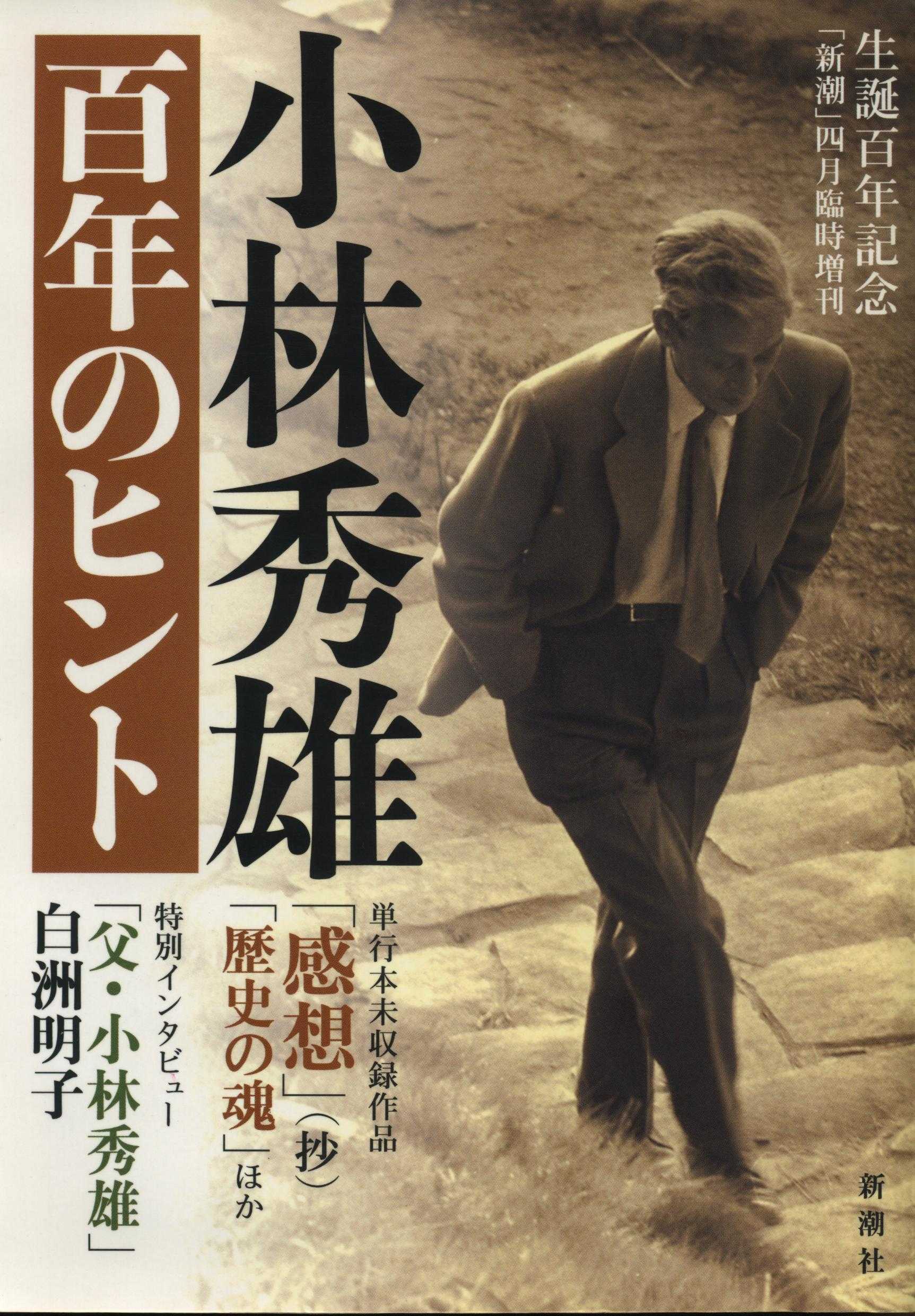
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(35)機が熟するのを待つ
《政治家の意見だとか、議会だとか、外交だとか同盟だとか、條約だとか、そんなものが人類の戦争とか平和とかを決定するのではない。私の体験観察に依(よ)れば、戦争とか平和といふものはもつと運命的な大きな力で左右されてゐるもので、たとへば民族の興亡といふやうな永遠の法則があつて、人力では如何ともし難い大きな力があつて、それが戦争を勃発させるのである》(小林秀雄「歴史の魂」:『小林秀雄百年のヒント』(新潮社)生誕百年記念「新潮」4月臨時増刊、p. 112) 戦争は起こるべくして起こるものなのであって、平和教育を行えば戦争を防げるなどといった安直な話ではないということだ。《なるほどこの前の世界大戦に従軍した人はたくさんある。こんな悲惨な戦ひの後には、人類から戦争を絶滅しようといふことを考へるのは当然だ。こんな悲惨な戦争が今行はれたばかりだ。だから将来こんな戦争は止(よ)さうぢやないかといふと皆んなの考へが直ぐそこに飛び移ってしまふ。そして様々な預言的思想がはびこる》(同、p. 113) 憲法9条が日本の平和を守るというのも、そして平和教育が日本を平和へと導くというのも戦後日本に蔓延(はびこ)った〈預言的思想〉である。が、実際に戦後日本の平和を守ったのは、在日米軍が睨(にら)みを利かせていたからであろう。また、教育によって、たとえ日本が平和を愛する国家となったにしても、他国が日本を攻めてくるかどうかとは何の関係もないことである。 小林氏は、第1次大戦後ナチスドイツの軍隊を立て直した参謀総長ゼークトを例に語る。《ゼークトはぢつとしてゐた…ぢつとしてゐてこの世界大戦といふ悲惨な戦争は一体どういふ性格を持ち、どういふ特徴を持つてゐるだらうかといふことをよく考へて見た…戦争が終って皆んなホッとして、将来戦争をなくさなければならぬと考へ先走つてゐる時に、今やつて来た戦争の性格をぢつと考へてゐた…皆んな先頭をきつて駈け出した、それが皆んな途中で疲れてしまって、遂(つい)にはぢつとしてゐる人が先頭を切る事になつた…預言者となるといふことがむづかしいのは、将来を見るのがむづかしいのぢやない。将来はああであらう、かうであらう、或(あるい)はかういふやうな理想、希望を持つといふことは易(やさ)しいことだ。けれども実際自分の眼の前にある事態のなかに将来の萌芽が、ちら/\見える、さういふ萌芽が見えるまでぢつと現在の事態を眺めてゐる人が稀(まれ)なのです。さういふことをゼークトがやつたに過ぎない。原理は非常に簡単だ。彼の思想が実に打てば響くといふやうな調子を持つてゐるのも、やはりそこから生れてゐるのだ。ちつとも空想がない》(同) 環境が整わないうちに動いても物事はうまく行かない。だから、ひたすら機が熟すのを待つ。時が来ればすぐ動き出せるようにじっと待っていればこそ、機を捉えることが出来るのだ。【続】
2025.06.12
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(34)米対日戦は「オレンジ計画」通りに進んだ
《1906年から29年の間に、第3段階作戦は、特定の地理的・経済的目的を達成するための一連の攻撃作戦へと発展した。 統合アジア方面軍は西太平洋の安全な基地に足場を固めた後、直ちに第3段階の作戦を開始し、基地の拡張と増援部隊の到着を待って攻勢を強める。米艦隊は迅速に日本本土と台湾南部を結ぶ通商路を断ち、日本海軍を東シナ海から追い払い、フィリピンにいる部隊への輸送路を遮断する。コレヒドール要塞がそれまで持ちこたえていた場合は救援を行う。増強された統合アジア方面軍は、南フィリピンから日本本土まで、大陸の海岸線と平行して並ぶ島々に沿って北に進みつつ大攻勢を開始する。ルソンの日本軍は大地上戦で一掃するか、あるいは放置するかのどちらか。いずれにしても海軍力と航空力で台湾を制圧する。琉球諸島で勝敗を決する水陸両面作戦を展開し、激しい抵抗を押えてこれを攻略する。やがて艦隊基地が日本本土から数百キロの地点に建設される。日本軍は全段階を通して用兵に長(た)けた消耗戦を展開するが、米軍の連戦連勝に追い詰められるまでは主力艦を温存するだろう。しかし、ついに主力艦の出撃を余儀なくされ、ルソンと日本本土との間の海上で大海戦が戦われるが、優勢に立つ米艦隊が勝利する。制海権を確実にした米国は日本封鎖を強める。アジア東北部からの輸入路を完全に封鎖するため、必要に応じて日本本土により近い島々も攻略する。1920年代には日本本土の生産設備と輸送機関に対する大空爆がプランに加えられた。日本が完全に疲弊して講和を求めてくるまで、仮借ない包囲が続けられるであろう》(エドワード・ミラー『オレンジ計画』(新潮社)沢田博訳、pp. 152-153) 「オレンジ計画」は、日本が日露戦争に勝利した直後、米国が行った対日戦想定計画であるが、太平洋戦争はこの計画通りに進められたと言っても過言ではない。《最大の決戦場が琉球諸島となることは、戦略家たちの意見の一致するところだった。琉球諸島は台湾と日本列島の南端の間に千キロにわたってのびている。マバンはすでに1911年、琉球諸島こそ米艦隊にとって最も有益な地点であると指摘していた。琉球諸島の基地から艦隊が出動すれば、全日本軍を南方に孤立させ、大半の輸入路を断ち、日本艦隊を戦闘に引きずり出すことができる。また琉球諸島に飛行場を作れば、次々と爆撃機を出撃させて日本経済を破壊することもできる。1906年から45年の最後の戦闘に至るまで、琉球諸島の攻略は米国戦略の主要テーマであった》(同、p. 158) 沖縄が激戦地となるのは、地政学上の要衝である限り、避けられぬことであったのだ。《琉球諸島を含めて南西諸島の中では、良港を有する奄美大島が最高の攻略地点であると見なされた。しかし奄美大島の守りは固く、また日本本土の九州からは300キロしか離れていないため充分な支援が受けられる。琉球諸島の最大の島である沖縄本島にもよい停泊地が発見されるはずである。沖縄は奄美大島の南240キロに位置しており、シムズは1921年、中間の目標地点としては賢明な選択であると注目していた》(同)【続】
2025.06.11
コメント(0)
-
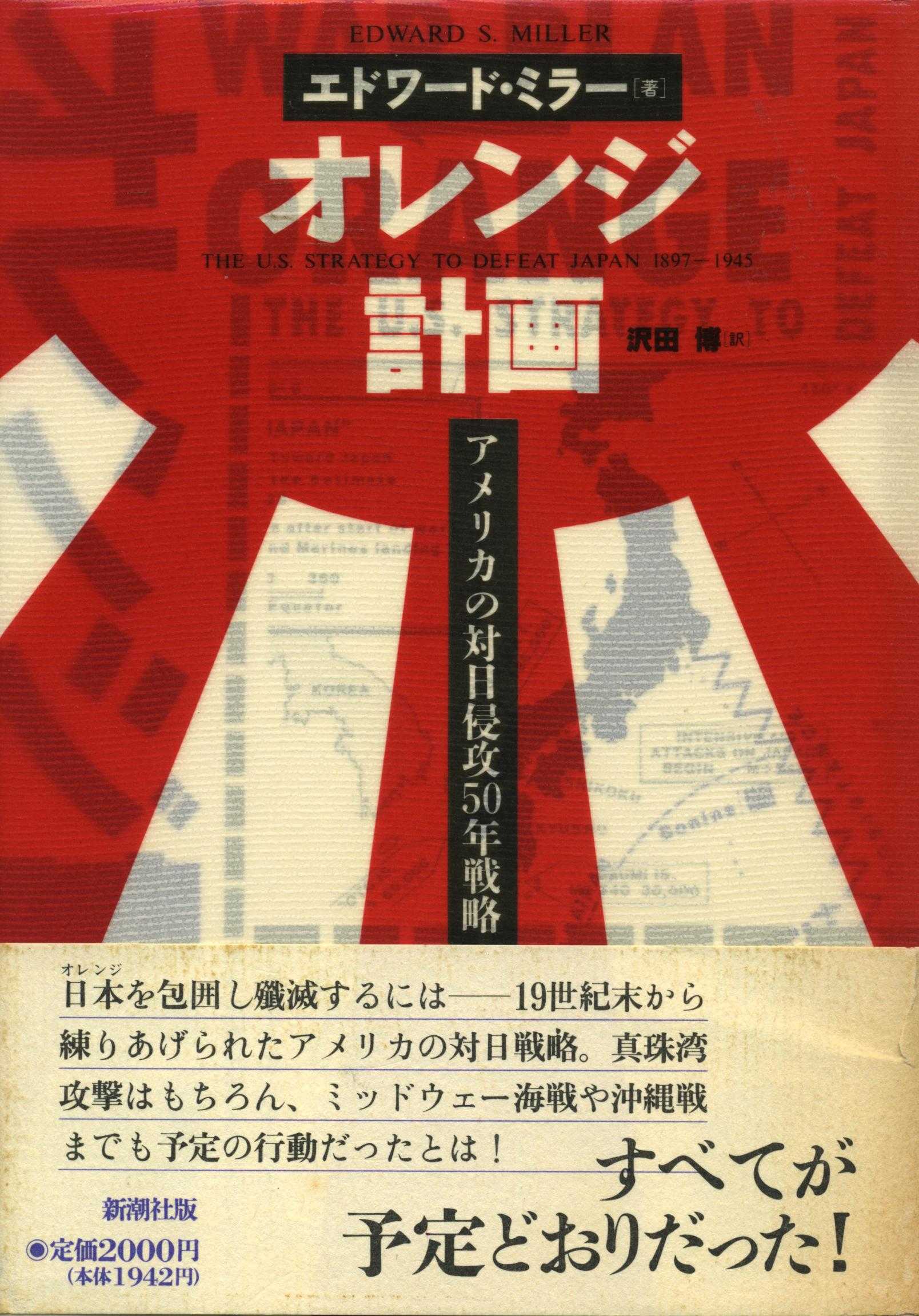
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(33)対日戦争シミュレーション「オレンジ計画」
《去る4月13日夜半より14日にかけての東京空襲の夜、自分の家の周囲も火の海と化したが、雨と降る焼夷弾(しょういだん)を踏み越えながら、自分の頭にふと浮かんだことは、沖縄に健闘せらるる諸君の愛国の至誠に燃えた尊い姿であつた、今や前線銃後の別はない、前線銃後渾然(こんぜん)一体となつて戦闘に生産にたゞ決死敢闘あるのみである、希(こいねがわ)くは沖縄の戦域にある諸君、この一戦に皇国の興廃(こうはい)を担(にな)つて健闘せらるる軍官民各位、既に洋々たる戦果が日を逐(お)うて興(おこ)りつつある、また世界の何(いず)れの国も真似のできない日本精神の権化(ごんげ)とも申すべき我が肉弾による特攻兵器の威力に対しては敵は恐怖を来しつつある、今後着々として行はるべき日本独特の作戦に対し敵の辟易(へきえき)することは火を見るよりも明かである、私は諸君がこの神機を掴(つか)み勝利への鍵を確(しか)かと握られることを期待してやまない、私ども本土にある国民もまた時来らば一人残らず特攻隊員となり、敵に体当りをなし、如何(いか)なる事態に立ち到らうとも絶対にひるむことなく、最後まで関ひ抜いて終局の勝利を得んことを固く決意してゐる、繰返していふが、沖縄戦に打ち勝ちてこそ敵の野望を挫折せられ、戦局の打開を見ることとなるのである、私も今老躯(ろうく)を提げて諸君に負けず生死を超越して御奉公の誠を致さんとするものである。呉々(くれぐれ)も沖縄の諸君の御健闘を祈る》(『朝日新聞』昭和20年4月27日付3面:『朝日新聞に見る日本の歩み』(朝日新聞社)焦土に築く民主主義Ⅰ(昭和20年-21年)、p. 46) 沖縄捨石論というと、蜥蜴(トカゲ)の尻尾切のように沖縄だけが本土から切り捨てられたかのように思われるかもしれない。が、本土も度重なる空襲に見舞われていたのであり、〈前線銃後の別はない〉状態にあったことだけは理解しておくべきである。 それどころか、沖縄が本土より先に狙われたのは、「オレンジ計画」なる米国の戦略によるものであった。驚く勿(なか)れ、「オレンジ計画」は、日露戦争後直ぐに策定されている。ということは、米国は40年も前から日本を仮想敵国として見ていたということになる。実際、沖縄戦は、この計画通りに実行されたものなのだ。《日本を海から包囲して降伏させる――アメリカがオレンジ・プランを立てるようになって以来、この戦略は一度も変わっていない。この考え方は、陸の戦力を海の戦力で圧倒するというオレンジ・プランの基本理念と一体になっていた。単独であれ連合軍の一員としてであれ、日本本土あるいはアジア大陸に展開する日本陸軍を叩くことは必要ない、と米国は判断していた。空からの攻撃を加味した1923年の「全体構想」によれば、対日戦争の第3段階では「日本を取り囲む全海域を制圧し、封鎖作戦に相当するものを実施し、日本領の遠隔の島々を残らず攻略・占領することによって日本を孤立させ、その領土に空襲をかけて圧力を加える」ことになっていた。戦争の大詰めは、激しい抵抗に対する長期の作戦になるだろう。そして戦線が日本本土に近付くにつれ死傷者がうなぎ登りに増える。それでもなお、日本包囲は完全勝利を果たすための最良の方法であると確信されていたのである》(エドワード・ミラー『オレンジ計画』(新潮社)沢田博訳、pp. 152-153)【続】
2025.06.10
コメント(0)
-
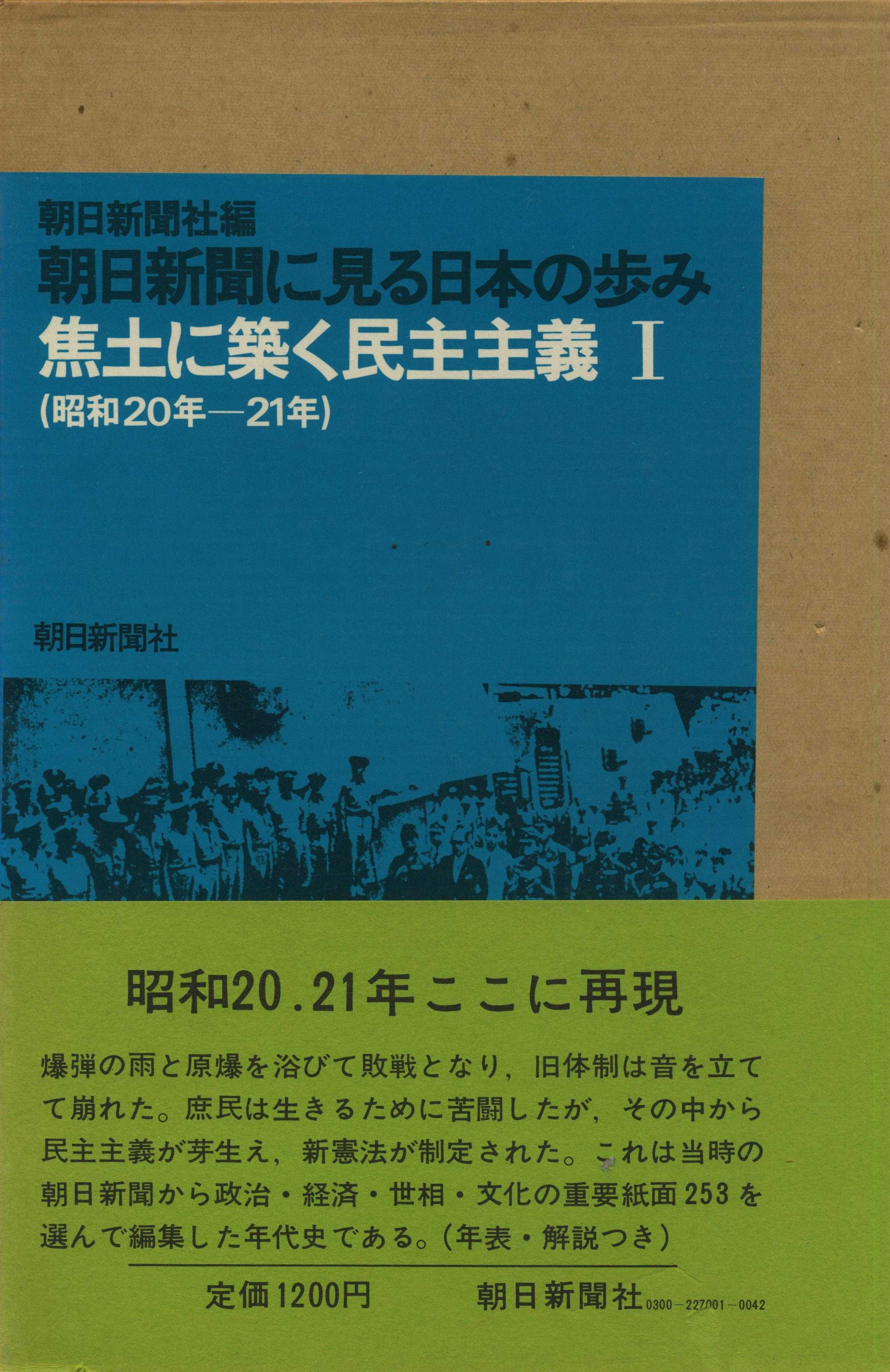
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(32)鈴木首相のラジオ演説
鈴木貫太郎首相(当時)は、沖縄戦激しい最中(さなか)、次のようなラジオ演説を行った。《沖縄全戦域に一致団結して全員必死特攻敢闘せらるる将兵各位並に官民諸君、私共一億国民は諸士の勇戦奮闘に対し無限の感謝を捧げてゐる、日々相ついで報ぜられる赫々(かくかく)たる戦果こそは、国民が斉(ひと)しく身をもつて感ずる大なる喜びである、しかしその喜びの蔭にはあの特攻隊諸士が大君の御盾となり、欣然(きんぜん)として敵の大艦船に突入してゆく神々しい姿や、あらゆる科学兵器を利して上陸し来つた敵の大軍に敢然斬(きり)込みを断行せらるゝ陸上部隊の壮烈なる姿を想ひ浮べ、ただ/\感激を覚ゆるばかりである21日の放送により特攻隊として出立つ勇士諸君がその出発の直前に凛然としてマイクの前に立ち、全国民に対し最後の別れの言葉を残して行かれたのを私は確(しか)とこの耳で聞いた、私どもが皇国に生れた喜びをしみ〴\と感ずるとともに、沖縄に戦ふ諸君の忠勇無比なる敢闘に対し、心からなる感謝を捧げたのである沖縄に在(あ)る全軍官民諸君、不肖私このたび大命を拝し、内閣を組織して肇国(ちょうこく)以来最も重大なるこの難局に当ることとなつた、私のただ思ふところは 大詔を奉じ一億国民共々に一致団結し、もつてこの大戦争を最後まで戦ひ抜き勝ち抜き米、英の野望を飽(あ)くまで粉砕しもつて 大御心(おおみごころ)を安んじ奉(たてまつ)らねばならぬといふことである、今や本土の一角にたどり着いた敵に対し諸君の敢闘を期待するとともに不肖私自らも一億全国民の先登に立つて戦争一本の旗印の下に総突撃を敢行する所存である》(『朝日新聞』昭和20年4月27日付3面:『朝日新聞に見る日本の歩み』(朝日新聞社)焦土に築く民主主義Ⅰ(昭和20年ー21年)、p. 46) もちろん、これは、存分に政治的なものではあろう。が、たとえ建前的であったとしても、これは、沖縄県民の献身努力を称えようとするものであることに変わりはない。一方、沖縄捨石論は、沖縄の人達を被害者と見ることで日本の悪事を暴こうとするものであろうから、国や同胞を想い勇敢に戦った沖縄の人達の頑張りを無にするものである。それどころか、沖縄捨石論は、戦後更なる精神的苦痛を沖縄の人々に与え続けるものとも成り得るのである。《今や一億国民は連日の空襲にも断じてひるまず、その戦域にあつて沖縄における戦に相呼応し夜を日についで戦力の増強に努めつつある、敵の暴虐なる無差別爆撃により、帝都を始め大都市は相当の被害を受けたが、家を失ひ財をなくした人々はそのためかへつて士気ます/\揚がり、敵を撃滅しもつてこの仇を報いようと烈々たる気魄をもつて生産に従事してゐる、こゝに私は日本人の真の尊き強さを見るのである》(同)【続】
2025.06.09
コメント(0)
-
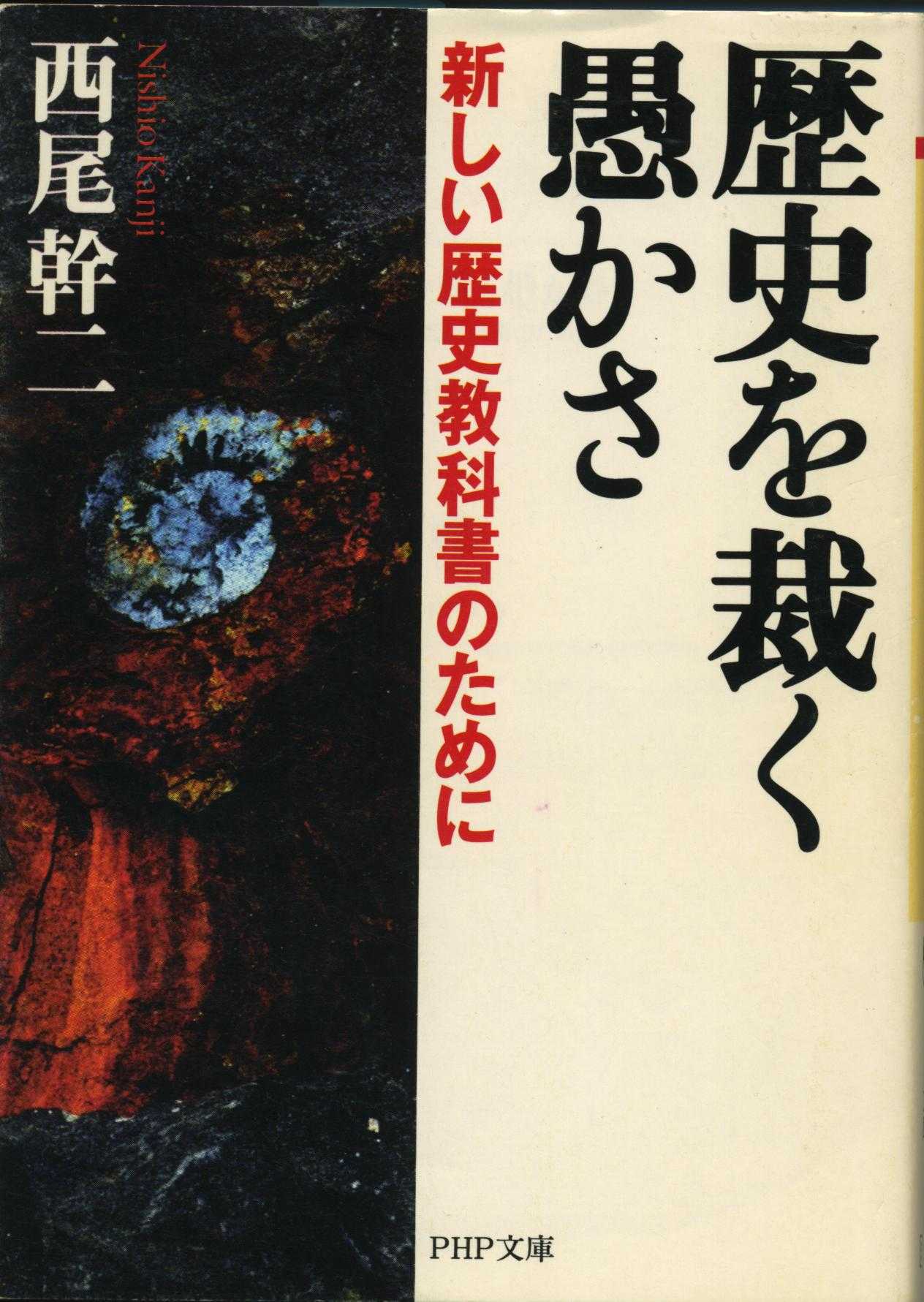
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(31)あるがままの歴史を理解することが先決だ
《歴史は科学ではない。そこに統一的な原理などあろうはずがない。歴史は言葉の世界、どこまでも言葉の世界である。したがって解釈と表現の世界である。固定的、確定的な世界ではなくて、どう解釈していくかという基準は常に相対的で揺れている。そして、現代の人間の未来に対する意識や夢といったものと切り離して考えることができない世界である。それが歴史というものである。過去という動かない科学的な真理がどこかに1つあるわけではない》(西尾幹二『歴史を裁く愚かさ』(PHP文庫)、pp. 213-214) 歴史とは、相対的なものなのだ。大東亜戦争が日本の侵略戦争だったというのは戦勝国が押し付けた1つの歴史観でしかない。最大の問題は、そこには「相手」がいないということだ。例えば、日本の満洲への進出は、ソ連の南下を防ぐのが目的であった。満洲事変は、満洲を独立国にし、緩衝地帯とすることが狙いにあったと考えられる。また、日本がなぜ仏印に進出したのかといえば、ABCD包囲陣で石油を止められたからである。 侵略か否かは、当事者の判断に委ねられるというのが国際的判断であって、自ら「侵略戦争」だったと言う必要はない。にもかかわらず、戦後日本は、唯々諾々(いいだくだく)として、東京裁判によって押し付けられた歴史を受け入れ続けている。憲法も、自衛の戦争すらままならぬ条文で日本を縛り続けている。《世界中のどこにも普遍的な歴史像というものはなくなっている。文明の数だけ歴史があり、国の数だけ歴史があり、民族の数だけ歴史がある。そう思った方が正しいのかもしれない。ところが日本人はそのことを徹底して考えようとしない。いまだになんとなく世界的に統一した歴史像というものがあるように思い込んでいる》(同、pp. 214-215) 差し詰め日本人に必要なのは、日本の歴史、すなわち、「国史」である。国史とは日本の歩みである。先人がどのような栄華を誇り、はたまた、艱難辛苦を耐え忍んできたのかを知ることが自我の形成に欠かせない。その意味で、歴史教育は、日本の来歴をあるがままに理解することがまず必要だ。歴史の教訓などというものは、国史の全体像が把握できてからはじめてなされるべきものである。 歴史から教訓を得ようとすれば、その暗部ばかりに目が行ってしまって暗黒史観となる。逆に、歴史に虹を見ようとすれば、史実が利己的に解釈されて歴史が美化されかねない。 結果として日本の歴史が暗黒に見えたり輝いて見えたりすることと、端(はな)から国史を暗黒に描いたり美化したりするのとは、決して同じではない。【続】
2025.06.08
コメント(0)
-
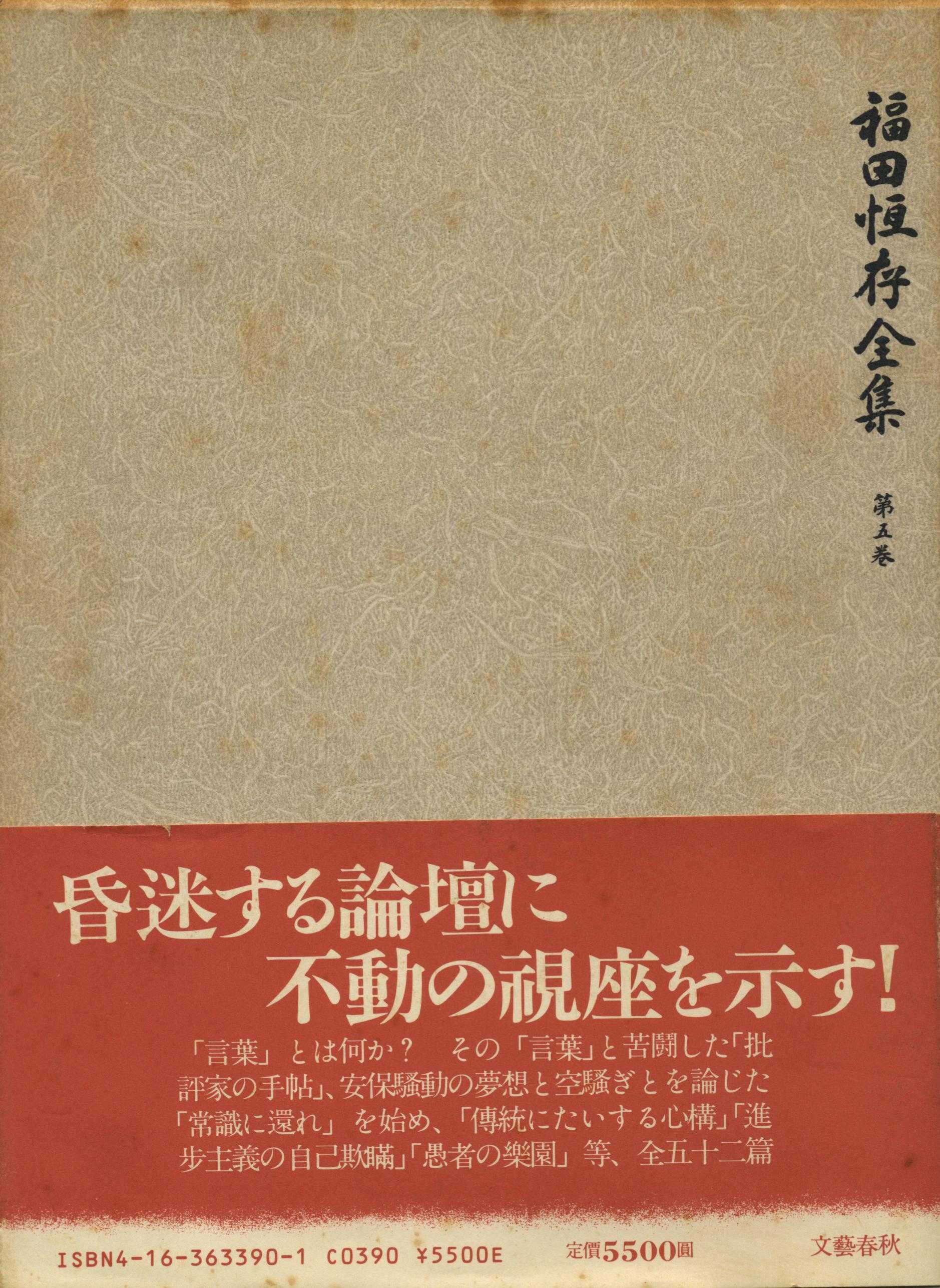
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(31)歴史の平衡感覚が重要だ
《今日「史実」と呼んで顧みない記紀の記述も、しよせん解釈に過ぎず、歴史的事実そのものではない。その意味では、1200余年前の「日本書紀」も、唯物史観によって照し出された某氏の「日本古代史研究」も、さらにをこがましいが、私の芝居も、さう径庭(けいてい)はないやうに思はれる。ただし嘘を書いてはならぬといふかもしれぬが、どこそこを嘘ときめつけるための鏡となる本当の事が、実はさう解つてゐないのだ。 私は単なる懐疑主義を述べてゐるのではない。疑ひを捨てるところから歴史は始る。歴史といふのは過去との附合ひであり、「人の振り見て、わが振り直せ」といふやうな啓蒙の仕事は、ただ歴史研究の結果として生じてくるだけのことであって、それを目的とするのは間違つてゐる。家族や他人と附合ふのは、相手の行動から自分に対する教訓を引張りだすためではない。同様に、過去と附合ふのも、それ自体が目的である。したがって、特定の過去を背負つてゐる事は、私達の与(あずか)り知らぬ事でありながら、やはり背負はねばならぬ廻り合せと考へるべきで、その意味で、過去はいまだ消滅せざるもの、現在と同時存在してゐるものなのだ》(「愚者の楽園」33:『福田恆存全集』(文藝春秋)第5巻、pp. 557-558) 我々は、過去の積み重ねの上に現在がある。が、過去は、こちらから手を差し伸べなければ、何か特別な意味を有(も)つことはない。だから我々は、過去を有意味にするために解釈を施(ほどこ)すのだ。そしてそれが「歴史」となる。我々は、歴史を踏まえて現在を生きている。それは、我々の行動が歴史によって制約を受けているということを意味する。だからどのような歴史観を有(も)っているのかがとても重要なのだ。 先人が戦った大戦争は、侵略だったのか、自衛のための戦いだったのか、はたまた亜細亜の開放の大義があったのか。 自虐的な人たちは、歴史から教訓を得ることがさも大事であるかのように言う。が、教訓を得ようとだけ過去を見ることは歴史を歪(ゆが)めることになるに違いない。我々は、自らの存在基盤として、良いことも悪いこともひっくるめて過去を背負わなければならないのであって、過去から教訓だけを抜き出しても意味がない。 今を生きるためには、推進力が必要だ。教訓は、制動力ではあっても推進力とは成り得ない。力強く前進するためには、誇りを有てる歴史が必要なのだ。自虐史観では、前へ進めない。 が、私は過去を美化しろと言っているのではない。過去には、成功もあれば、失敗もある。その両方を公平公正に理解することが大事なのだ。平衡を欠いて、自愛に過ぎるのも、逆に、自虐に過ぎるのもよくないということだ。【続】
2025.06.07
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(30)「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」の真意
しばしば「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」(ビスマルク)という格言を見聞きする。ために、我々は、歴史に学ぶ賢者とならねばならない、歴史を教訓としなければならない、という強迫観念に縛られがちである。が、歴史解釈は、前提の置き方次第で違った様相を見せる。皇国史観もあれば、マルクス史観もある。歴史から得られる教訓もまた一様(いちよう)ではない。が、戦後日本には別の歴史解釈を許さない「東京裁判史観」という絶対的歴史観が存在する。 戦勝国によって押し付けられた「東京裁判史観」の呪縛から自由になるにはどうすればよいのだろうか。我々はいつまで、日本だけが悪かった、日本が侵略しなければ世界は平和だったなどという戦勝国が押し付けた一方的な歴史観に閉じ込められ続けなければならないのだろうか。 ここで、「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」という格言を少し掘り下げておこう。Nur ein Idiot glaubt, aus den eigenen Erfahrungen zu lernen. Ich ziehe es vor, aus den Erfahrungen anderer zu lernen, um von vorneherein eigene Fehler zu vermeiden. (自分の経験から学べると思っているのは馬鹿でしかない。始めから自分の失敗を避けるために、他人の経験から学ぶことが望まれる) 原文では、自分が経験したことだけからしか学ばないのは愚かなことであり、自分以外の人が経験したことからも学ぶのが賢い人間だ、言い換えれば、愚者は主観的にしか物事を捉えられないが、賢者は客観的に捉えることが出来るということだ。 『沖縄ノート』における大江氏は、反日という主観的世界の中で生きているという意味で、私の目には「愚者」に映る。沖縄戦における「集団自決」という史実に基づくのであれば、『沖縄ノート』は客観的な著作と言える。が、実際には「自決命令」は発せられていない。だとすれば、それは客観を偽装しているに過ぎないということになる。「自決命令」の真偽如何では、『沖縄ノート』は、客観を装って日本への主観的怨念を詰め込んだ著作でしかなくなってしまう。だからこそ、自らが調べることもなく、独り他人の著作を引用し、「自決命令」があったと一方的に決め込んで断罪するなどということは絶対にやってはならないことなのだ。 沖縄に足を踏み入れていない大江氏には、「自決命令」がなされたという一次資料はない。引用元の『沖縄戦史』も『鉄の暴風』をなぞったものであるから、一次資料はない。つまり、一次資料なく書かれたのが『沖縄ノート』という著作なのであり、どう転んでみても賢者のものとは言い難いのである。【続】
2025.06.06
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(29)『鉄の暴風』の不自然な記述
《恩納河原に避難中の住民に対して、思い掛けぬ自決命令が赤松からもたらされた。「こと、ここに至っては、全島民、皇国の万歳と、日本の必勝を祈って、自決せよ。軍は最後の一兵まで戦い、米軍に出血を強いてから、全員玉砕する」というのである》(『沖縄戦記 鉄の暴風』(沖縄タイムス社)、p. 34) これは一体「誰目線」の記述なのだろうか。このように書けるのは、本来その場にいた人間である。が、それが誰なのかが示されてはいない。つまり、誰も責任を負わない体(てい)で書かれているのだ。この文章は、謂(い)わば「神の視座」で書かれているということになる。が、人間は神ではない。「神の視座」で書かれたとすれば、それは「偽りの神」でしかない。だとすれば、『鉄の暴風』は、事実に基づく「ルポルタージュ」ではなく、事実を装った「創作」と言うべき代物(しろもの)でしかないということだ。《この悲壮な、自決命令が赤松から伝えられたのは、米軍が沖縄列島海域に侵攻してから、わずかに5日目だった。米軍の迫撃砲による攻撃は、西山A高地の日本軍陣地に迫り、恩納河原の住民区も脅成下にさらされそうになった。いよいよあらゆる客観情勢が、のっぴきならぬものとなった。迫撃砲が吠えだした。最後まで戦うと言った、日本軍の陣地からは、一発の応射もなく安全な地下壕から、谷底に追いやられた住民の、危険は刻々に追ってきた。住民たちは死場所を選んで、各親族同志が一塊(ひとかたま)り塊りになって、集まった。手榴弾(しゅりゅうだん)を手にした族長や、家長が「みんな、笑って死のう」と悲壮な声を絞って叫んだ。1発の手榴弾の周囲に、2、30人が集まった》(同、pp. 34-35) 滑(なめ)らかな筆致である。が、滑らかすぎやしないか。人の記憶とは、どこかぎこちないところがあるものだ。が、この文章にはそれがない。それがあまりにも不自然なのだ。《住民には自決用として、32発の手榴弾が渡されていたが、更にこのときのために、20発増加された。 手榴弾は、あちこちで爆発した。轟然(ごうぜん)たる不気味な響音は、次々と谷間に、こだました。瞬時にして、――男、女、老人、子供、嬰児(えいじ)――の肉四散し、阿修羅の如き、阿鼻叫喚の光景が、くりひろげられた。死にそこなった者は、互いに棍棒で、うち合ったり、剃刀で、自らの頭部を切ったり、鍬で、親しいものの頭を、叩き割ったりして、世にも恐しい情景が、あっちの集団でも、こっちの集団でも、同時に起り、恩納河原の谷川の水は、ために血にそまっていた。 古波蔵村長も一家親族を率いて、最後の場にのぞんた。手榴弾の栓を抜いたがどうしても爆発しなかった、彼は自決を、思いとどまった。そのうち米軍の追撃砲弾が飛んできて、生き残ったものは混乱状態におち入り、自決を決意していた人たちの間龍、統制が失われてしまった。そのとき死んだのが329人、そのほかに迫撃砲を喰った戦死者が32人であった。手榴弾の不発で、死をまぬかれたのが、渡嘉敷部落が126人、阿波連部隊が203人、前島部落民が7人であった。 この恨みの地、恩納河原を、今でも島の人たちは玉砕場と称している。かつて可愛い鹿たちが島の幽遠な森をぬけて、おどおどとした目つきで、水を呑みに降り、或は軽快に駈け廻ったこの辺り、恩納河原の谷間は、かくして血にそめられ、住民にとっては、永遠に忘れることのできない恨みの地となったのである》(同、pp. 35-36)【続】
2025.06.05
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(28)住民たち自ら「集団自決」を望んだ
梅澤少佐は回顧する。《マルレ(船舶特攻)もなくなり出撃不能だから、明日26日は陸戦になるだろうと。基地隊と整備中隊を集めて、一番高い番所山、高月山の下にとにかく陣地を作って敵が上陸するのを迎え撃つ方針を定めた。 すると、夜10時頃、村の幹部ら5人が来て、驚くべきことを言い出したんです。その5人とは役場の助役・宮里盛秀、収入役の宮平正次郎、小学校長・玉城政助、役場の事務員、及び女子青年団長宮城初枝でした。助役が代表してこう言いました。「いよいよ最後の時が来ました。お別れの挨拶を申し上げます。 私たちは申し合わせが出来ているから、死ななければならない。覚悟しています。私たちは島の指導層だから、知らん顔できないから一緒に死にます。 村の忠魂碑前の広場に女子供、老人をはじめ、みんなを集めるから、敵の船にぶつける爆薬、ドラム缶に入った125キロの爆薬を、みんなが集まっている真ん中で爆発させてください。老幼婦女子が集まりますから、ふっ飛ばしてください。だめなら小銃弾をください。手榴弾をください。そうしないと、私たちは死ねと言われてもどうやって死んだらいいかわからんのです」》(梅澤裕少佐独占手記「私は集団自決など命じていない!」:『WiLL』(ワック・マガジンズ)2008年8月号増刊、p. 52) 自ら死を選ぶなどということは、今の平和な日本からすれば想像し難いことに違いない。が、住民たちはそれを望んだ。 が、梅澤少佐は、住民たちが死に急ぐのを諫(いさ)めた。《去年(昭和19年)11月3日の、沖縄県の決起大会から決議されて指令が出ている。死ななきやいけないんだ、と言う。戦う人達の後顧の憂いをなからしむために自決して、死にます、弾をくださいと言われて、私は愕然としました。 考えたこともない、とんでもない話です。村の人達はおとなしくて純朴で親切で、本当によくやってくれた。女子青年団もよくやってくれた。日本の内地の女よりもよほど立派だと感心していたんです。 私は玉砕の申し出に、びっくりすると同時に唖然として、強い口調でこう言いました。「我々は明日から戦おうと思っているのに、なんてことを言うのか。とにかく死んではいけない。どうして死ぬなんていうのか」と。「我々も必死で、この後ろの山で戦う。山の後ろの方、島の東の山の中に隠れて避難してくれ。山の向うには密林があって、密林の中に壕も掘ったじゃないか、食糧も蓄えたじゃないか。それをやったのはみんな、そこで生き延びてくれと言うことだ。死んでどうなるんだ、絶対に生きなければならない。死んではいけない」 こう強く諭(さと)すのですが、「いや、私たちは上の方から言われて、申し合わせており、どうにもなりません」と思い詰めた表情で言う。特別の空気があった。一番最初に言ったのが、村の助役をしていた宮里盛秀です。 彼は、鹿児島で除隊した退役軍人です。非常に優秀な兵隊だったと思う。私はその男が非常に好きだった。私が村の人達と大事なことを話す時、いつも彼が窓口でした。 だから私がこんこんと「死ぬ必要はない」と止めているのに、「覚悟は出来ています」と言って開かない。それで私は怒鳴りつけたんですよ、「弾丸はやれない、帰れ!!」と》(同、pp. 52-53)【続】
2025.06.04
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(27)日本の歴史を揺るがす「嘘」
梅澤裕(うめざわ・ゆたか)少佐は、「自決命令」を出していないと言う。《私は座間味島の村人たちに「死ね」などという無慈悲な自決命令など出していない(中略) あの日、昭和20年3月25日の夜、玉砕したいと申し出てきた村の幹部に対して私は「自決してはならぬ」と厳しく怒鳴りつけました。それでも粘って帰ろうとしない彼らに、私は「死んだらいかん、何を言うとるか、とんでもないことを言ったらいかん。何で死ぬ必要があるんだ」と強く制止し、激励して帰したというのが真相です。 それなのに当時、女学生だったような生き残りの人たちが相手側に篭絡(ろうらく)されて、「梅澤さんが命令した」という風に言わされている》(梅澤裕少佐独占手記「私は集団自決など命じていない!」:『WiLL』(ワック・マガジンズ)2008年8月号増刊、p. 44) 梅澤隊長は、本当は「自決命令」を出していない。宮村幸延氏は次のように真相を吐露(とろ)したという。《援護の件で、厚生省に行って話をしても法律がないから自決した老幼婦女子に補償金は出ない、諦めてくれと言われる。しかし、村では田中村長からこっぴどく言われる。復員して帰ってきた村人からは、お前の兄が自決をさせたと責められる。 3回目に行った時にやっと、厚生省の課長が頭を下げて、隊長が命令したということにでもして申請をしたらあるいは……という話だった。それを村に帰って報告したら「それだ!」となって、それから1カ月かかって色々なことをしました、と》(同、p. 57) つまり、国から補償金を得んがために隊長が集団自決を命じたことにしたということだ。《私が宮村氏に「いくらぐらい貰っているのか」と問いたら、「毎年、3億円ほど出た」、今でも貰い続けていると。それで村が生き返って、それで梅澤さんにみんな感謝しておりますよという。 昔は港もなかった島に立派な港ができ、公共施設も充実し、村は随分と豊かになったと開いています》(同) 困窮した村が、已(や)むに已まれず吐(つ)いた「嘘」が、一人の人間の名誉を傷付けた。それだけではない。旧日本軍の名誉も、そして日本の名誉も傷付けたのである。何とも後味の悪い話である。 「嘘」は絶対にいけないなどと青臭い優等生のようなことは言わない。時として、「高貴な嘘」(プラトン)のようなものも考えられなくもない。が、残念ながら、「集団自決を命じた」という「嘘」は、日本の歴史を揺るがしかねない大事件となってしまったことだけは疑いようのないことである。【続】
2025.06.03
コメント(0)
-
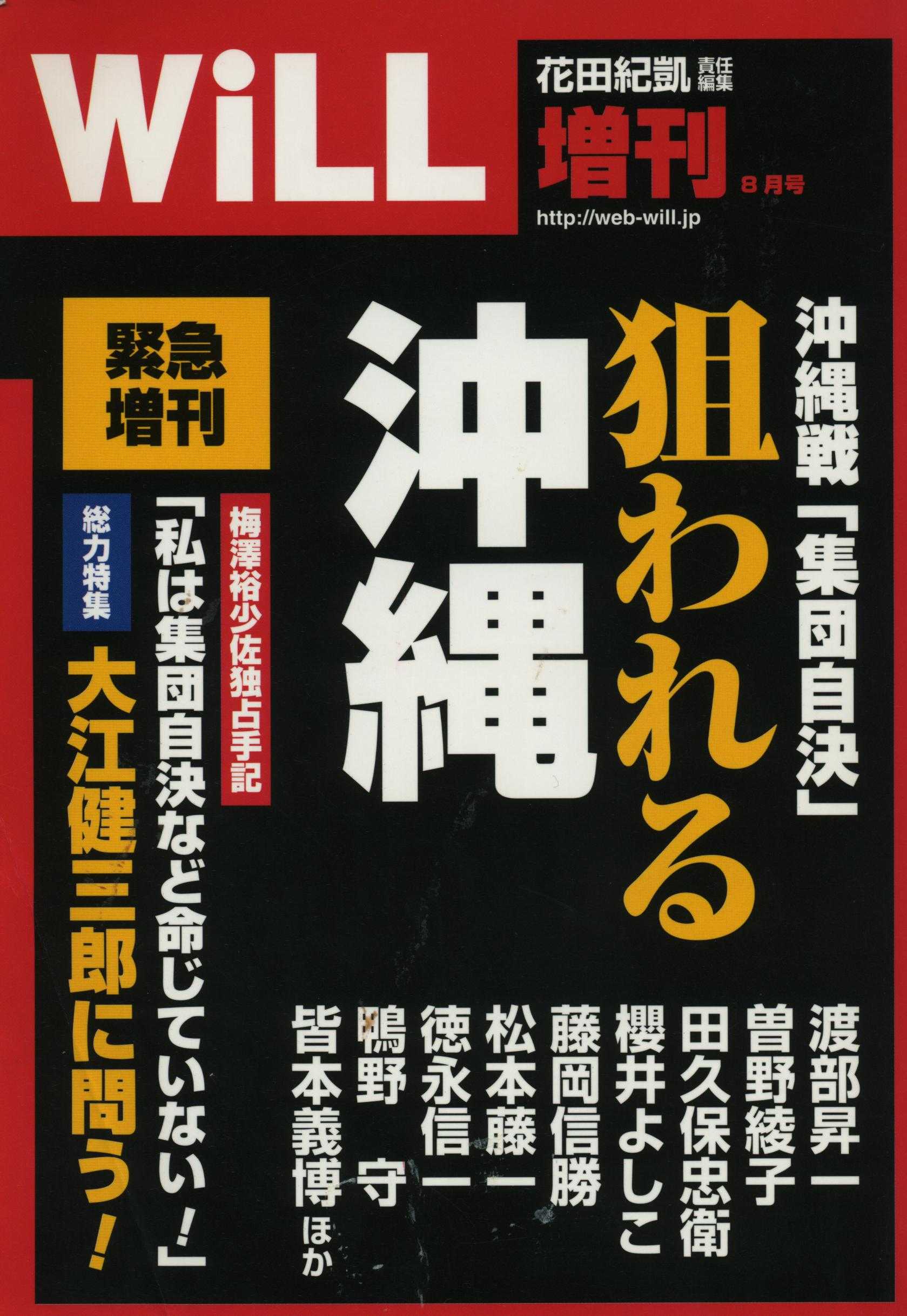
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(26)『沖縄ノート』「自決命令」は『鉄の暴風』の孫引き
《『鉄の暴風』(沖縄タイムス社編著)を、昭和25年に沖縄タイムス社と朝日新聞社が出版したところから(現在は沖縄タイムス社発行)、すべてははじまっていますが、『鉄の暴風』自体にでっち上げの嘘が書かれていた。その『鉄の暴風』を参考にして書かれたのが、沖縄タイムス社社長だった上地一史の『沖縄戦史』(昭和34年、時事通信社刊)です…この『鉄の暴風』『沖縄戦史』などを参考に昭和45年、大江健三郎氏が『沖縄ノート』を岩波書店から出版しました》(田久保忠衛・櫻井よしこ「『沖縄的なるもの』の正体」:『WiLL』(ワック・マガジンズ)2008年8月号増刊、p. 12) つまり、『沖縄ノート』は、孫引きの資料を元に書かれたものということになる。《大江氏はでっち上げの嘘を元にして、『沖縄ノート』を書いています。 これは、嘘の玉突きのようなもので、『鉄の暴風』からどんどん嘘が広がって一人歩きしたと見るべきです》(同、p. 13) 大江氏は、おそらく都合の良い資料として『沖縄戦史』を利用しただけであって、「自決命令」が実際にあったかどうかなど関心がなく、『沖縄戦史』は、日本を呪詛(じゅそ)するための切掛(きっかけ)にすぎないということなのだろう。《その『鉄の暴風』を発端にした書籍は、「反日」という点で共通しています。つまり、「日本軍は悪の権化」「日本軍は鬼」で、沖縄の人々はその日本軍にいじめられ、アメリカ軍がそれを救ったという物語を作っている》(同) 大元の『鉄の暴風』(1950年刊初版)のまえがきには、次のようなことが書かれていたらしい。「われゝ沖縄人として、おそらく、終生忘れることができないことは、米軍の高いヒューマニズムであった。国境と民族を越えた彼らの人類愛によって、生き残りの沖縄人は、生命を保護され、あらゆる支援を与えられて、更生第一歩を踏み出すことができたことを、特筆しておきたい」(同、p. 14) 第2販ではこの記述は削除されたようで、私の所有する第3版にも見られない。が、いずれにせよ、西田議員の言う「日本軍がね、どんどん入ってきて、ひめゆりの隊がね、死ぬことになっちゃったと、そしてアメリカが入ってきて、沖縄は解放されたと、そういう文脈」がここに見られることは事実である。《渡嘉敷島とともに座間味島は慶良問列島戦域における、沖縄戦最初の米軍上陸地である。 座間味島駐屯の将兵は約1000人余、1944年9月20日に来島したもので、その中には、12隻の舟艇を有する100人近くの爆雷特幹隊がいて、隊長は梅沢少佐、守備隊長は東京出身の小沢少佐だった。海上特攻用の舟艇は、座間味島に12隻、阿嘉島に7、8隻あったが、いずれも遂に出撃しなかった。その他に、島の青壮年100人ばかりが防衛隊として守備にあたっていた。米軍上陸の前日、軍は忠魂碑前の広場に住民をあつめ、玉砕を命じた。しかし、住民が広場に集まってきた、ちょうど、その時、附近に艦砲弾が落ちたので、みな退散してしまったが、村長初め役場吏員、学校教員の一部やその家族は、ほとんど各自の壕で手榴弾を抱いて自決した。その数52人である。 この自決のほか、砲弾の犠牲になったり、パイの嫌疑をかけられた日本兵に殺されたりしたものを合せて、座間味島の犠牲者は約200人である。日本軍は、米兵が上陸した頃、2、3カ所で歩哨戦を演じたことはあったが、最後まで山中の陣地にこもり、遂に全員投降、隊長梅沢少佐のごときは、のちに朝鮮人慰安婦らしきもの2人と不明死を遂げたことが判明した》(『沖縄戦記 鉄の暴風』(沖縄タイムス社)、p. 41) が、梅澤裕(うめざわ・ゆたか)少佐が実際に亡くなったのは平成26年のことである。【続】
2025.06.02
コメント(0)
-
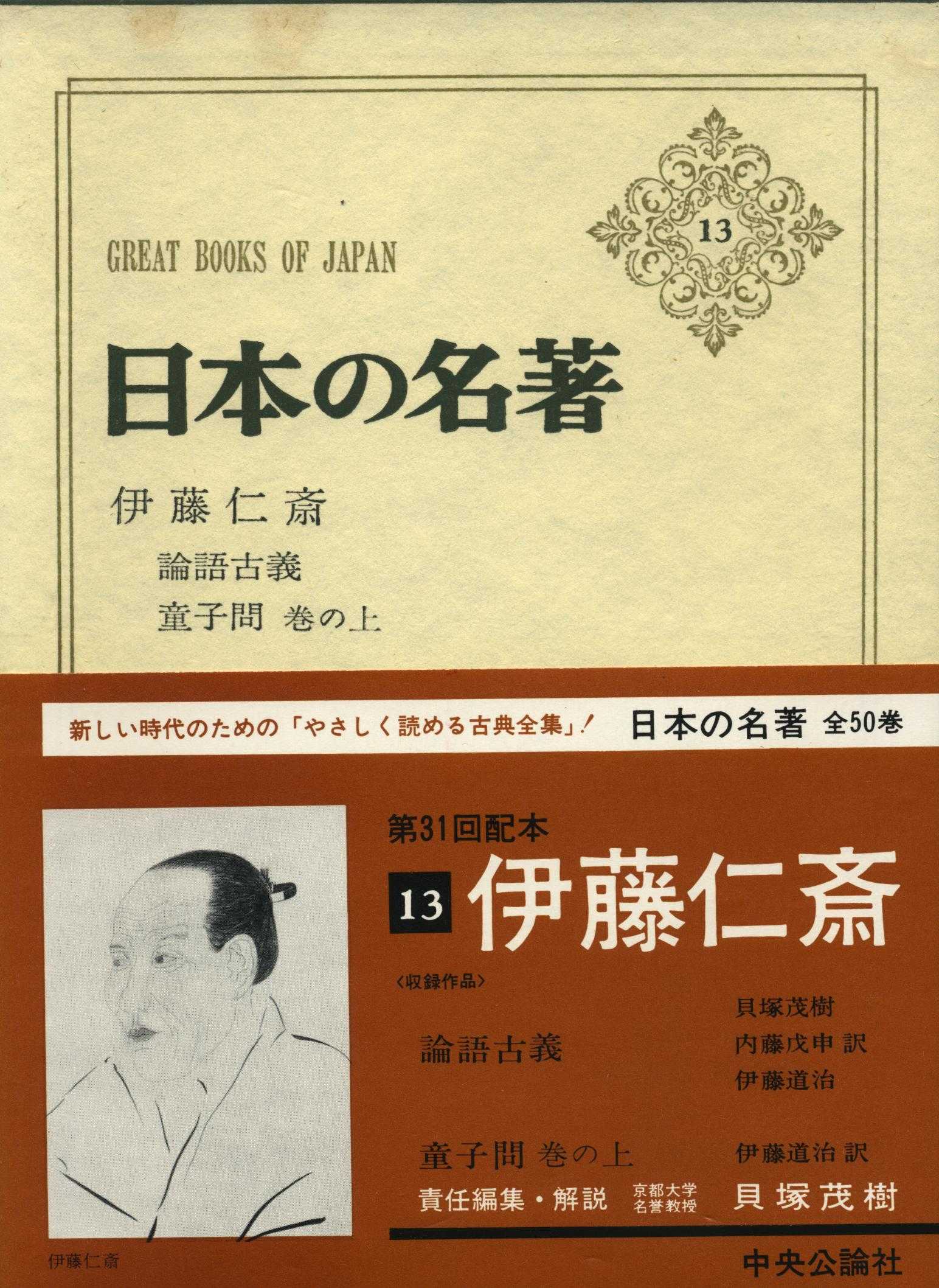
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(25)知り難く覚え難いものは「邪説」
江戸前期の儒者・伊藤仁斎(いとう・じんさい)は書く。大抵詞直理明。易知易記者。必正理也。詞難理遠。難知難記者。必邪説也。子以此求之。於天下之書。百不失一。(おおむね言葉が素直で、その筋道がはっきりしていて、理解しやすく、記憶しやすいものは、必ず正しい真理である。言葉が難解で、筋道が迂遠で、理解しがたく、記憶しにくいものは、必ず邪説である)(『童子問(どうじもん)』巻之上 第4章:『日本の名著 13 伊藤仁斎』(中央公論社)伊藤道治訳、p. 452) 複雑さこそが大江氏の真骨頂ということなのかもしれないけれども、少なくとも『沖縄ノート』は「小説」(fiction)ではない。史実に元にした「論説文」のはずである。したがって、読者が難解な文章をそれぞれ独自の解釈を施して理解すればよいというようなものではない。沖縄戦における「集団自決」を元にして、沖縄の人々が被った苦難を理解し、それを教訓とすることが求められるはずだ。が、本書は、史実を出汁(だし)にして、日本に対する自分の怨念を吐き出そうとした感がある。だから、「自決命令」が事実か否かなど気にも留めていないのだ。 難解なことを読者に理解してもらうためには、読者に理解できることを1つひとつ積み重ねてゆかねばならない。だからこそ平明な文を心掛けねばならないのだ。難解なことを難解なまま読者に突き付けて理解させようとするのは著者の傲慢である。否、著者自身その内容を本当に事実に基づいて理解しているのか疑わしい。分かったつもりでいるだけだから、嚙み砕いて分かりやすく説明することが出来ない。 否、大江氏の場合、端(はな)から史実を理解してもらおうなどとは思っていないのだろう。だから、「集団自決」が起こった状況や「自決命令」を発した経緯(いきさつ)には無頓着なのだ。つまり、史実などどうでもよいということだ。 難しい言葉を用いれば高尚(こうしょう)なのではない。簡単な内容を難解な言葉を用いて高尚に見せようとするのはただの粉飾である。内容が難しくなれば難しい言葉を用いざるを得なくなる場合もあろうが、それでも出来るだけその内容を咀嚼(そしゃく)し、平明な言葉で読者に伝えることが求められるだろう。我々は、如何なる高みであれ、一歩一歩段階を踏めばこそその頂に辿(たど)り着けるのであって、段階も踏まずに一気に飛び上がろうしても、多くの場合、ただ弾き返されるだけである。 『沖縄ノート』は、読者の理解を促そうとするものではない。日本への怨念を難解な表現法によって文(かざ)り、吐き出しているだけではないか。【続】
2025.06.01
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(24)悪臭を放つ大江氏の独善
《愛! 人間性! わたしはそれを知っている、自分の民族に嫌悪をしめすために、もそもそと口にされるこの理論的愛と教条的人間性を。わたしは、知っている、当節の文学のはやり文句を。そのはやり文句が吐かれる芸術作品をも。こういう作品に出て来る人間性は、知的要請、文学的教義、意識的なもの、意図されたもの、受け売りものにすぎない。つまるところ、そこには人間性などかけらもありはしないのだ。これらの作品は、一般読者や批評家たちが修辞的政治的な人間性要請を人間性そのものと取りちがえてくれるおかげで、かろうじて生きながらえているにすぎない》(トーマス・マン『非政治的人間の考察 下』(筑摩叢書)前田敬作・山口知三 訳、p. 161) 観念の世界の中で美しく輝く「愛」と「人間性」。そこには真の「愛」も「人間性」もない。「愛」や「人間性」は、現実世界においてこそ意味がある。現実を捨象してしまっては、それは「虚構」でしかない。「憎悪」という現実があるからこそ、「愛」が意味を有(も)つ。現実を生きるからこそ、人間性が問われることになる。《戦争は、たしかに身の毛がよだつほど忌(いま)わしい。しかし。この戦争のさなかに政治的文学名がのさばり出て、わが胸には万物の愛の息(い)ぶきがかよっているなどと宣言するのは、あらゆるおぞましいことのなかでも最もおぞましい光景であり、正視するに耐えない。おろかな取り巻き連中は、「まったく、この人は、偉大な芸術家というだけではない。なによりもまず、りっばな人間である!」ともてはやす。こんなことをいわれると、ご本人は、穴にでもかくれたいほど恥ずかしい思いがしないだろうか。というのは、かれは、りっぱな人間ではけっしてないし、しかも、かれ自身そのことを知っているからである。感傷的な威勢のよさでごまかしたいじけた仏頂面、教条的硬化症、傲慢不遜、頑固で冷酷な不寛容、「きみたちは、堕落するがいい。わたしは、光のなかに住む」というパリサイ主義的な他者犠牲のパトス――これらのものがりっぱな人間をうみだすはずがない。独善は、「世界正義」より千倍も始末におえない。世界正義は、共感や愛にもとづくこともあるかもしれないが、独善は、赦(ゆる)されざる罪である》(同、pp. 161-162) 赤松大尉をこれでもかと罵倒できるのは、自らが神のごとく絶対的正義を有(も)つと信じて疑わないからであろう。つまり、この上なく独善的なのだ。が、大江氏が赤松大尉、日本軍、そして日本に呪いの言葉を投げつければつけるほど、その独善は悪臭を放つ。【続】
2025.05.31
コメント(0)
-
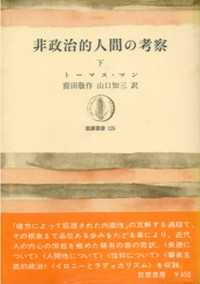
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(23)トーマス・マンの訴え
《世界は、戦争になる前には『人間の品位にふさわしくない』悲惨で充満していた…破廉恥きわまる不正行為がおこなわれながら、加害者は罰せられることもなく、大きな顔をして歩き廻り、被害者にはなんの補償も与えられない。骨盤骨折や火傷をともなったような肉体的苦痛、病気、放蕩、情事、悔恨、老齢、そして苦しい死――これが戦前の生活であった。苦悩を目的論的に解し、困窮のみが文化をうみ出す、苦悩がなければ同情もありえない、不正のみが正義感をめざめさせる、苦痛がなければ道義心は地に墜ち、人間の生活は無為徒食(むいとしょく)に終始することになるが、そのような生活を幸福と呼ぶことはできない、苦痛こそが快楽を引きたたせるのだ、とほざくのもよかろう。あるいは、キリスト教徒流に、彼岸(ひがん)への期待でみずからを慰めるのもよかろう。それとも、厭世(えんせい)主義者となって、人生を罪にけがれ、罪過そのものであるこの生を――人間どうしたがいに狼であり、自分がよじ登ろうと思えば他人を蹴(け)おとすしかないこの人生を、改善の見込みがないとして告発するのもよいし、生の批判者となって、殲滅(せんめつ)的な言葉で生を糾弾し、懲罰にかけるのもよかろう。芸術を炬火(たいまつ)に仕立てて、存在のすべての怖ろしい深みを、恥辱と痛恨にみちた奈落の深淵をのこるくまなく慈光(じこう)で照らすのも結構だろう。精神を炎と化し、それで、世界のあらゆる隅々まで放火し、世界を燃えあがらせ、救済しようとする同情の念をもって世界をそのすべての汚辱や責苦もろとも滅ぼし去るのもご自由だ》(トーマス・マン『非政治的人間の考察 下』(筑摩叢書)前田敬作・山口知三 訳、pp. 161-162) この西欧的思考をそのまま沖縄問題に当て嵌(は)めることは出来ないのだけれども、次の意見には、私は諸手(もろて)を挙げて賛成する。《だが、戦争反対という政治的・博愛主義的な悲願を得々としてうたうことだけは、やめてもらいたい!》(同) なるほど、戦争は悪である。が、だからといって、戦争が悪であることを政治的、博愛主義的に語るのは止めてもらいたいということだ。《まるで戦争が地球の顔を汚したかのような――戦前には子羊のそばで虎が平和に草を食んでいたかのような態度をとることだけは、やめてもらいたい。こんどの戦争で博愛主義者になった文学者は、この戦争を畜生道におちた恥辱であり汚辱であると感じない者はすべて反精神的人間であり、犯罪者であり、人類の敵であるなどと吹聴(ふいちょう)してまわっているが、わたしはこの宣言ほどたわけた出鱈目(でたらめ)を知らない》(トーマス・マン『非政治的人間の考察 下』(筑摩叢書)前田敬作・山口知三 訳、pp. 161-162)【続】
2025.05.30
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(22)日本を呪う大江氏の呪文
大江氏の妄想は止まらない。《おりがきたら、とひたすら考えて、沖縄を軸とするこのような逆転の機会をねらいつづけてきたのは、あの渡嘉敷島の旧守備隊長のみにとどまらない。日本人の、実際に厖大(ぼうだい)な数の人間がまさにそうなのであり、何といってもこの前の戦争中のいろいろな出来事や父親の行動に責任がない、新世代の大群がそれにつきしたがおうとしているのである》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 214) 大江氏は、〈沖縄をねじふせ〉、〈事実に立った異議申立ての声を押しつぶ〉そうとしている膨大な数の日本人の存在をどうやって確認したと言うのだろうか。ただの病的な幻覚ではないか。《現にいま、若い世代の倫理的想像力の世界において、在日朝鮮人をめぐりどのような事態がおこっているかを見よ。ごく一般の愚かしい高校生が、なにものとも知れぬものにつながる使命感、「或る昂揚(こうよう)感」に揺り動かされて、その稚(いとけな)い廉恥(れんち)心すらそこなうことなく、朝鮮高校生に殴りかかる実状を見よ。この前の戦争中のいろいろな出来事や父親の行動と、まったくおなじことを、新世代の日本人が、真の罪責感はなしに、そのままくりかえしてしまいかねない様子に見える時、かれらからにせの罪責感を取除く手続きのみをおこない、逆にかれらの倫理的想像力における真の罪責感の種子の自生をうながす努力をしないこと、それは大規模な国家犯罪へとむかうあやまちの構造を、あらためてひとつずつ積みかさねていることではないのか》(同、pp. 224-225) 日本の高校生が倫理的想像力を失い、朝鮮の高校生に暴力を振るう。そのようなこともあったのだろう。が、一体このような事件はどれくらい起こっているのか。私は、おそらく一般化できるような話ではないと推察する。ごく僅かな事例が、大江氏の頭の中でただ膨らんだだけなのではないか。《沖縄からの限りない異義申立ての声を押しつぶそうと、自分の耳に聞こえないふりをするのみか、それを聞きとりうる耳を育てようとしないこと、それはおなじ国家犯罪への新しい布石ではないのか》(同、p. 225) 普通の日本人には聞こえない声が独り大江氏には聞こえているらしい。が、それは感度が高いからなのか、それとも単なる幻聴なのか。《佐藤・ニクソン共同声明のあと、われわれの政府がおこなっている工作と宣伝は、まったく剥(む)きだしにその方向づけにある。「沖縄問題は終った」という呪文は、じつはそれをくりかえしとなえることによって、沖縄への罪責感、戦争責任・戦後責任はもとより、沖縄からの異議申立ての声ともども、「沖縄」そのものが実在しなくなることすらをめざしての、まことにその根源において全破壊的な、恐しい呪文である》(同) 大江氏は、沖縄は本土復帰すべきでないと考えているのであろう。であればそう言えばよいのであって、こんな日本を呪う「呪文」を唱えられても迷惑なだけだ。【続】
2025.05.29
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(21)断罪されるべきは大江氏の方ではないか
《日本本土の政治家が、民衆が、沖縄とそこに住む人々をねじふせて、その異議申立ての声を押しつぶそうとしている》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 211) 本土復帰問題を「ウチナンチュウ」と「ヤマトンチュウ」の対立構造の中で考えようとすることが間違いなのだ。確かに、本土と沖縄を同列に論じることは出来ないのだろうが、かといって、端(はな)から本土と沖縄を相容れないものと考えてしまってはなる話もならないだろう。 沖縄にも色々な声があるはずだ。が、大江氏は、本土復帰反対派の声こそが沖縄の声だと一般化し、本土復帰を願う人たちの声を押し潰(つぶ)す。 大江氏は、さらに赤松隊長を断罪する。《ひとりの戦争犯罪者にもまた、かれ個人のやりかたで沖縄をねじふせること、事実に立った異議申立ての声を押しつぶすことがどうしてできぬだろう? あの渡嘉敷島の「土民」のようなかれらは、若い将校たる自分の集団自決の命令を受けいれるほどにおとなしく、穏やかな無抵抗の者だったではないか、とひとりの日本人が考えるにいたる時、まさにわれわれは、1945年の渡嘉敷島で、どのような意識構造の日本人が、どのようにして人々を集団自決へと追いやったか、およそ人間のなしうるものと思えぬ決断の、まったく同一のかたちでの再現の現場に立ちあっているのである。 罪をおかした人間の開きなおり、自己正当化、にせの被害者意識、それらのうえに、なお奇怪な恐怖をよびおこすものとして、およそ倫理的想像力に欠けた人間の、異様に倒錯した使命感がある》(同、pp. 211-212) ここには、ひょっとすると赤松隊長が自決命令を発していないかもしれない、などという疑念は一切ない。自決命令を発した赤松大尉は紛(まが)うかた無き「犯罪者」なのだ。赤松大尉は、「犯罪者」なのだから、罵倒しても構わない。否、大江氏は、軍国主義日本の権化たる赤松大尉は徹底的に叩き潰さなければならないとでも思っているかのようである。が、赤松大尉は自決命令を発していない。だとすれば、断罪されるべきは大江氏の方だということになろう。《私はそろそろ沖縄のあらゆる問題を取り上げる場合の1つの根源的な不幸にでくわす筈(はず)である。 それは、常に沖縄は正しく、本土は悪く、本土を少しでもよく言うものは、すなわち沖縄を裏切ったのだ、というまことに単純な論理である。沖縄をいためつけた赤松隊の人々に、一分でも論理を見出そうとする行為自体が裏切りであり、ファッショだという考え方である。 或る人間には一分の理由も見つけられないとする思考形態こそ、私はファシズムの1つの特色だと考えている》(曽野綾子『沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実』(WAC)、p. 292)【続】
2025.05.28
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(20)根拠薄弱な大江氏の妄想
《慶良間の集団自決の責任者も、そのような自己欺瞞(ぎまん)と他者への瞞着(まんちゃく)の試みを、たえずくりかえしてきたことであろう。人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 210) 大江氏はこのように赤松隊長を糾弾する。根拠は、上地一史『沖縄戦史』だけであるから、真偽は甚(はなは)だ頼りないはずなのであるが、そんなことは意に介(かい)さない。日本軍人のやることは悪いに決まっているかの如く、罵声(ばせい)を浴びせるのだ。《かれは、しだいに稀薄化する記憶、歪められる記憶にたすけられて罪を相対化する。つづいてかれは自己弁護の余地をこじあけるために、過去の事実の改変に力をつくす。いや、それはそのようではなかったと、1945年の事実に立って反論する声は、実際誰もが沖縄でのそのような罪を忘れたがっている本土での、市民的日常生活においてかれに届かない。1945年の感情、倫理感に立とうとする声は、沈黙にむかってしだいに傾斜するのみである。誰もかれもが、1945年を自己の内部に明瞭に喚起するのを望まなくなった風潮のなかで、かれのペテンはしだいにひとり歩きをはじめただろう》(同) 時間とともに人の記憶は稀薄化し、歪められる。自己弁護のために、事実を捻じ曲げる。なるほど、そういう人もいるかもしれないが、すべての人間がそうではない。おそろしいほど自分勝手な一般化であり、捻じ曲がった人間観と言うしかない。《本土においてすでに、おりはきたのだ。かれは沖縄において、いつ、そのおりがくるかと虎視眈々(こしたんたん)、狙いをつけている。かれは沖縄に、それも渡嘉敷島に乗りこんで、1945年の事実を、かれの記憶の意図的改変そのままに逆転することを夢想する。その難関を突破してはじめて、かれの永年の企ては完結するのである。かれにむかって、いやあれはおまえの主張するような生やさしいものではなかった。それは具体的に追いつめられた親が生木を折りとって自分の幼児を殴り殺すことであったのだ。おまえたち本土からの武装した守備隊は血を流すかわりに容易に投降し、そして戦争責任の追及の手が27度線からさかのぼって届いてはゆかぬ場所へと帰って行き、善良な市民となったのだ、という声は、すでに沖縄でもおこり得ないのではないかとかれが夢想する。しかもそこまで幻想が進むとき、かれは25年ぶりの屠殺(とさつ)者と生き残りの犠牲者の再会に、甘い涙につつまれた和解すらありうるのではないかと、渡嘉敷島で実際におこったことを具体的に記憶する者にとっては、およそ正視に耐えぬ歪んだ幻想をまでもいだきえたであろう。このようなエゴサントリクな希求につらぬかれた幻想にはとめどがない。おりがきたら、かれはそのような時を待ちうけ、そしていまこそ、そのおりがきたとみなしたのだ》(同、pp. 210-211) さすがノーベル文学賞受賞者である。根拠薄弱なことをここまで押し広げられるのは本当に恐れ入る。が、このようないかにも人の心に深く入り込み、その深層心理を描き出した話も、赤松隊長が自決命令を発していなければ、ただの妄想に過ぎなかったということになってしまうのだ。【続】
2025.05.27
コメント(0)
-
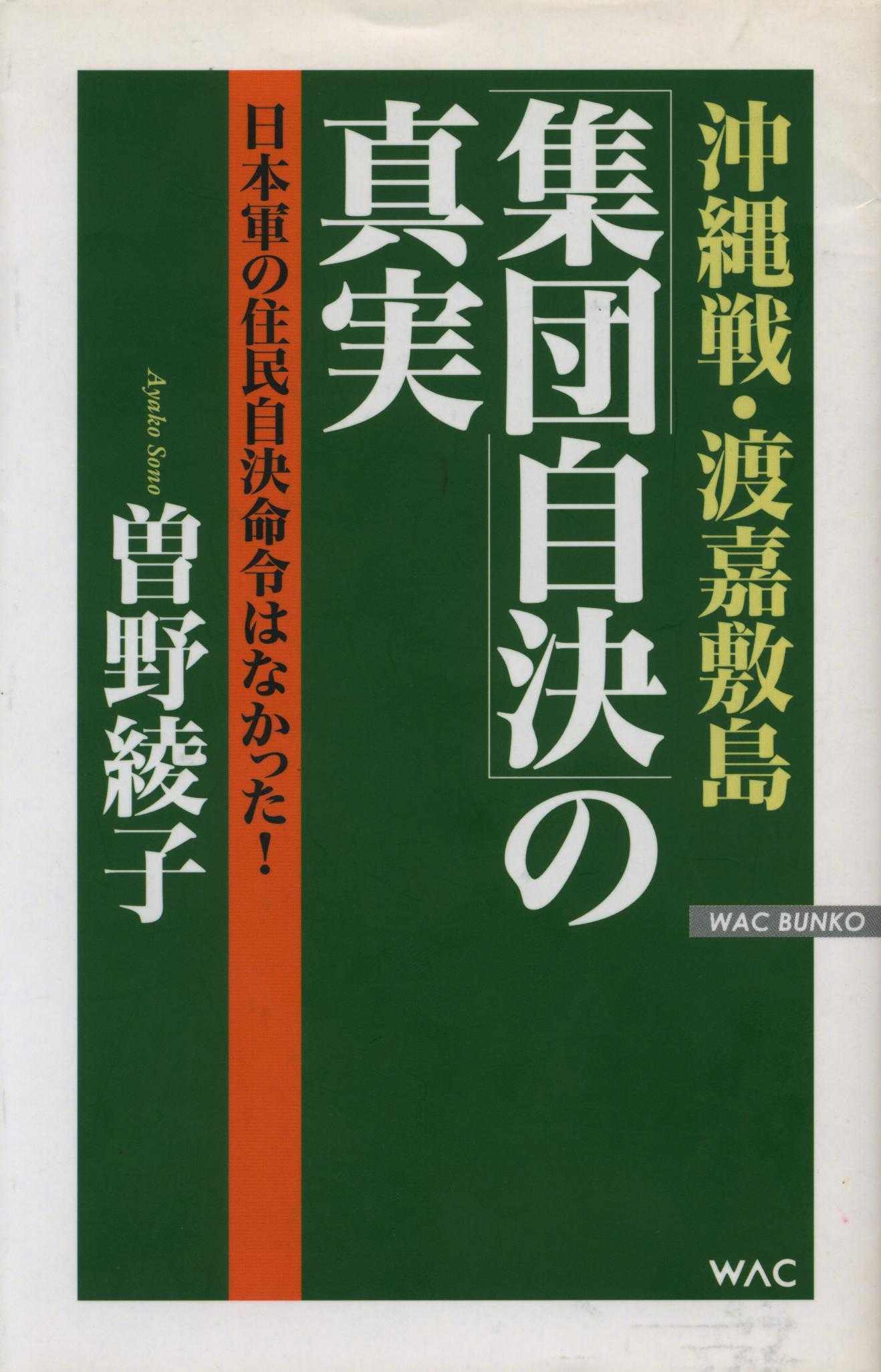
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(19)赤松大尉は自決命令を下していない
《慶良間列島の渡嘉敷島で沖縄住民に集団自決を強制したと記憶される男、どのようにひかえめにいってもすくなくとも米軍の攻撃下で住民を陣地内に収容することを拒否し、投降勧告にきた住民はじめ数人をスパイとして処刑したことが確実であり、そのような状況下に、「命令された」集団自殺をひきおこす結果をまねいたことのはっきりしている守備隊長が、戦友(!)ともども、渡嘉敷島での慰霊祭に出席すべく沖縄におもむいたことを報じた。僕が自分の肉体の奥深いところを、息もつまるほどの力でわしづかみにされるような気分をあじわうのは、この旧守備隊長が、かつて〈おりがきたら、一度渡嘉敷島にわたりたい〉と語っていたという記事を思い出す時である》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 208) が、〈集団自決を強制したと記憶される〉赤松嘉次大尉は、自決命令を否定する。《私に対する抗議の内容は、私の知らないことが大部分だが、いくつかの不祥事件については責任者である私が責めを負うのは当然だし、遺族や島の方々に心からおわびしたいと思う。いろいろ事情があって、渡嘉敷島に渡れなかったが、私としては、自分の口からおわびとお世話になったお礼をいいたかった。私は自決命令は下さなかった。(中略)私は自決をきいて早まったことをしたと怒ったほどだ。また隊は陣地の中にいたと言われているが、艦砲を避けてはいった山で、陣地、壕などあるはずがない。糧まつの強奪なども事実ではない。島の悲劇をつくった原因は、わずかな兵員と村民が小島の中で米軍の猛攻を受け、硬直状態に追いこまれたことだ。 当時の島の責任者として、あの惨劇を目のあたりにしたもののひとりとして、戦争は二度とあってはならないと思う。私どもの来島が、日本の再軍備体制につながるという人もいるようだが、私の気持ちは反対だ。再びああいうことがあってはならないと祈るからこそ、沖縄を訪れたのだ》(沖縄タイムズ1970年3月30日付:曽野綾子『沖縄戦・渡嘉敷島 集団自決の真実』(WAC)、pp. 286-287) 勿論、本人が否定したからといって、それを鵜呑みには出来ないのだけれども、自決命令あった派が次のように論点をずらしていることからすれば、赤松大尉の話は逆に信憑性を帯びてくる。もし、自決命令の根拠があるのなら、論点をずらす必要がないからである。《赤松氏は『集団自決を命じたのは私ではない』と釈明しているが、当時、同氏が渡嘉敷島の日本軍の、防衛隊長の地位にあり、軍の最高責任者であったことは事実である。同氏が直接、薬用自決の命令を下したかどうかのせんさくはともかく、軍の責任者としてなんらかの形で、これに関与したことは否定できない》(琉球新報「卵の話」1970年3月27日付:曽野綾子、同、pp. 285-286) 自決するよう命令していなくても、関与があったことは事実である。だから責任を免れないということは、自決命令は事実ではないと認めたということに等しい。【続】
2025.05.26
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(18)大江健三郎の単純化思考
《沖縄戦にむりやりひきずり出されながら、生き延びることの可能性については客観的にも、主観的にもそれを想像する力をうばわれている者たちとして、酷(むご)たらしく死んだ沖縄の娘たちの死は、いわば琉球処分以後のすべての沖縄の、望ましい日本人たろうとつとめた女性たちの歴史的つながり総ぐるみにおいての死であった。しかし首相の涙は、それらの沖縄の娘たちの死を、抽象的な架空の娘たちの死と同一のものへと単純化したのである。本土の日本人はかれにならって、とにかく若い娘が戦場で死ぬということは痛ましいことだ、というかたちに一般化し、そうすることによって本土の日本人には誰にとってもかれの人間としての根源を刺してくるはずの沖縄の毒から身をまもり、安穏(あんのん)に涙を流すことができた。そして涙が乾けば、もう「沖縄問題は終った」と、のほほんとする段取りができあがっていたのでもあろう》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 192) <首相の涙は、それらの沖縄の娘たちの死を、抽象的な架空の娘たちの死と同一のものへと単純化した>などと言うのは、明らかに言い掛かりであろう。このように単純化されたのは大江氏の頭の中だけの話である。人の涙はそんなに単純なものではない。にもかかわらず、〈単純化した〉などと決め付けるのはあまりにも短絡的である。 さらに大江氏は、本土の日本人を一般化し、佐藤首相(当時)の涙に倣ってひめゆり学徒隊の娘たちを悼(いた)むことで「禊(みそ)ぎ」とし、これで沖縄問題を終わらせようと目論(もくろ)んでいるなどと妄想を膨らませる。言葉とは裏腹に、問題を一般化、抽象化し、そして単純化しているのはむしろ大江氏自身なのではないか。それは単純化だ、一般化だと非難する前に、自身が物事を単純化し、一般化していることこそ反省すべきである。《真暗な深い裂けめを覗きこまねばならぬところへ、ほとんど首筋をつかまれてみちびかれるようにして近づきながら、土壇場でそれをかわす。沖縄について本土の日本人がくりかえしてきた定石のやりくちが再びもくろまれ、それがそのまま佐藤・ニクソン共同声明、72年返還という方向にむけて完了しようとしているのである》(同) 佐藤首相の涙は、沖縄返還に向けての一種の儀式(ceremony)であって、心から沖縄の人々の苦難に寄り添ったものではないという決め付けであり、単純化である。《ここでは沖縄への無知からの単純化も、意識された頬かぶりによる単純化と同様に、こすっからく冷酷な日本人の、アジアにおける百年来の生きざまをあらわにする。侵略的に猛(たけ)っていない間も、アジア人への単純化された認識が、そのまま差別の実体をなすというかたちで、日本人はアジアに存在してきたのであり、沖縄的なるものから根こそぎひきぬいたかたちでの、戦場で死んだ娘たちへの涙は、乾くまでもなく、その涙のうちに、差別の種子としての、単純化された沖縄認識をはっきりやどらせていたのである》(同、pp. 192-193) 日本人には、飽くなき「侵略欲」があるという単純化である。日本人は、〈こすっからく冷酷〉だというのも悪意のある単純化である。【続】
2025.05.25
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(17)戦後沖縄が手に入れた「自由」とは
投書は続く。《…諸君の国琉球は、独立すべきである。そして、諸君の政府を作りたまえ。財政の心配はない。これは観光とトバクでまかなえばよい。財源はこれから生まれる。国営トバクだ。ただし、琉球国民はやってはならない。あくまでも、外国人に来てもらって楽しんでもらうのだ。歓楽の国にすることだ。戦争の被害などは早く忘れることだ。大きな台風に出合ったと思えばよい。…自由の国琉球、どうだ諸君の国だよ。政治は自由投票にする、人種は差別しないことだ。主席、または大統領は沖縄に一定年以上住んだ者と言うことにして、人種の差をつけない。日本人でもよい、米人でもよい。自由な国、朗(ほがら)かな国、ケンカのない理想郷を諸君の良識で作ってみないか。つまらん本土復帰の悲願なんかやめたまえ。諸君に与えられた最良のチャンスだ》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、pp. 78-79) こんな風に焚(た)き付けるから、余計に沖縄の人たちの心が掻き乱されるのだ。実際、沖縄の人々は、周辺国との力学に翻弄(ほんろう)されながら生きてきた。独立したいから独立しますと言えるような安直な話ではない。沖縄は、シナにとって太平洋への出入り口にあたる。つまり、地政学的に見て、沖縄は要衝(ようしょう)に位置するということだ。そのような状況で独立しようとすれば、シナにとって飛んで火にいる夏の虫でしかない。 戦後沖縄は、日本の手を離れ、米国の施政下に置かれることとなった。これが「自由」なのか。なるほど、戦前の沖縄には「自由」と呼べるような状況とは程遠かっただろう。が、それは日本が戦時下にあったからであって、「自由」が回復された(かのように思われた)のは米国のお陰ではなく、ただ終戦によって戦闘が止(や)んだことによるものだ。《佐藤栄作首相は、日本の首相として戦後初めて沖縄を訪問。到着翌日のこの日午後、ひめゆりの塔や日本軍玉砕の地、摩文仁(まぶに)海岸など、かつての戦地を巡った。ひめゆりの塔では祭壇に献花後、女子学生たちが命を落とした壕をのぞき込みながら、金城遺族会会長の話を聞いたが、同会長の娘二人が亡くなったくだりで、感極まったのか、白いハンカチで目がしらを拭った》(共同通信1965年8月19日) この涙を大江氏は、次のように想像力豊かに形容する。《ひめゆりの塔…の前で首相が流した涙は、沖縄戦において真暗な深い裂けめがひらき、そこに意識の光をあてさえすれば、琉球処分以後のすべての歪(ゆが)みひずみが、単に歴史にきざまれたもの、物質として把握できるものをこえて、なぜ沖縄の日本人が本土の日本人よりもなお「忠誠心」に燃えるにいたったかという、民衆の意識の内部にはいりこむものまでをこめて、複雑な層をなしてあらわれてくるはずの、その決定的な瞬間に、なにもかもを単純化してしまった、ほとんど暴力的な涙であった。その深い裂けめからふきあげてくるはずの悪臭は、じつはそこを覗(のぞ)きこんでいる者自身の悪臭であったにちがいないが、涙が鈍感な厚い蓋(ふた)となって裂けめを閉ざした》(大江、同、pp. 191-192) 常人には見えないものが感性豊かな大江氏には見えるのだろう。が、それは「妄想」と紙一重のところがある。【続】
2025.05.24
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(16)「なぜ独立しないのか」という投書引用の意図
大江氏は、ある栃木県の医師が『琉球新報』に投書したとされる文を引く。《琉球国人よ、諸君は元来が独立国であったはずだ。徳川時代、それ以前、唐の時代には薩摩、または中国に責物を捧げてやっと独立してはいたものの、立派な独立国ではなかったか。それが、明治維新のドサクサにまざれて、日本の沖縄県民にされて領有されたのである。そして、内地官僚の左遷された役人によって統治され、日本の赤字県とされていたのである。…非常に幸運なことに、第二次世界戦争のおかげで、諸君は日本を離れ、米軍の施政下にはいっているが、そのために諸君はまだ知らなかった世界を知ったことになる。諸君の左右や街頭を見てごらんなさい。全く自由である。軍事施設以外は、全く内地では想像もつかねはどの自由を持っているのだ。同じ領土でも、朝鮮は独立した。台湾も独立した。諸君の琉球は、なぜ独立しないのか》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 78) このような投書を引用した以上、この投書には少なからず大江氏も賛同するところがあり、この投書が何がしか自分の意見を代弁してくれると思っているはずであるが、例によって大江氏は直截(ちょくさい)簡明には言わず、つかみどころのないことを言う。《僕はまずこの投書を分析したり批判したりするまえに、その用語と文体をそのままここに提示するだけで、僕がなにを感じているかをつたえるには十分すぎるほどに感じる。僕はほかならぬ本土の日本人が、誰に要請されてというのでもなく、なにやらえたいの知れぬ情熱にとりつかれて、(しかもその情熱は、破壊的な性格あるいは下降的、反社会的な性格ではなく、本人に意識されているかぎり、いかにも道徳的な性格のそれなのであるが)、このような文章を沖縄の新聞に送りつけたのだ、ということを、ひどい船酔いにかかったような気分で反芻(はんすう)する。それが沖縄の民衆の意識に喰いこんだかどうかは疑わしいが、ともかく広く読まれた、ということが動かしがたい以上、悪夢の残り滓(かす)のような具合に、この文章は僕にとりついて離れない。日本人とはこのような人間なのだと、僕はあらためてこの医師と自分とをつなぐ血の紐帯(ちゅうたい)を、はっきり見すえないですますわけにはゆかないのである》(同、p. 80)『沖縄ノート』が小説であるなら構わない。が、これが、「集団自決」を鍵に、沖縄の苦難を世間に知らしめたいルポルタージュというのであれば、読み手によってどのようにも解釈可能な、曖昧模糊(あいまいもこ)とした表現は避けるべきではないか。【続】
2025.05.23
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(15)自決命令はなかった
《沖縄の民衆の死を抵当にあがなわれる本土の日本人の生、という命題は、この血なまぐさい座間味村、渡嘉敷村の酷(むご)たらしい現場においてはっきり形をとり、それが核戦略体制のもとの今日に、そのままつらなり生きつづけているのである。生き延びて本土にかえりわれわれのあいだに埋没している、この事件の責任者はいまなお、沖縄にむけてなにひとつあがなっていないが、この個人の行動の全体は、いま本土の日本人が綜合的な規模でそのまま反復しているものなのであるから、かれが本土の日本人にむかって、なぜおれひとりが自分を咎(とが)めねばならないのかね? と開きなおれば、たちまちわれわれは、かれの内なるわれわれ自身に鼻つきあわせてしまうだろう》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、pp. 69-70) 大江氏の豊かな表現力が沖縄の悲劇をより一層浮かび上がらせる。が、それは物事の本質とは関係のない「虚飾」である。むしろ、「自決命令」があったかなかったかを見ようとする目を曇らせるものである。 実際、「自決命令」は虚偽であった。《梅澤裕少佐は、「戦傷病者戦没者遺族等援護法を適用できるようにするために、島の長老達から『軍命令だった』と証言するように頼まれ、それに従った」と証言しています。 また、座間味島の宮城初枝氏(当時青年団長)は「1945年3月25日に村の有力者5人と隊長にあった際に、隊長は『自決命令』を発していない」と手記に遺しており、娘の宮城晴美氏が2000年に『母の遺したもの』としてその手記を出版しています。 その中で「厚生省の職員が年金受給者を調査するため座間味島を訪れたときに、生き証人である母(宮城初枝)は島の長老に呼び出されて命令があったと言って欲しいと頼まれ、(本当は命令はなかったが)命令があったと証言した」と告白しています。 そして座間味島の宮村幸延氏は、当時の助役・兵事係であった兄・宮里盛秀氏が、「軍から自決命令を受けていない。隊長命令説は援護法の適用を受けるためにやむを得ずつくり出されたものであった」という証文を梅澤裕少佐に与えたと言っています。 渡嘉敷島では遺族の援護業務を担当していた照屋昇雄氏が、遺族年金を受給するために赤松大尉が自決を命令したことにして自ら公式書類等を偽造したと認めています。 つまり、単に自殺したというだけでは「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が民間人を適用外としていることから年金がもらえないため、「軍命令」があったということにしたのです。そうすれば「軍協力者」ということで年金がもらえるからです。 梅澤少佐や赤松大尉は戦後の村の困窮を見かねて、「命令書を作成してきなさい。そうすればサインをしてあげます」と「軍命令」の書類を作成したというわけです。 そしてすでに、右のようにその書類の作成を頼みに行った人たちが、良心の呵責(かしゃく)に耐えかねて、あれは自分たちが頼んで梅澤少佐や赤松大尉が親切でサインしてくれたものだということを証言しています》(渡部昇一「歴史教育を歪めるもの」:『WiLL』(ワック・マガジンズ)2007年12月号、p. 64) おそらく大江氏は、「集団自決」の悲劇を書きたかったのではない。日本を腐(くさ)すために「集団自決」を利用しただけだ。したがって、大江氏にとって、自決命令があったかなかったかなどどうでもよかったに違いない。【続】
2025.05.22
コメント(0)
-
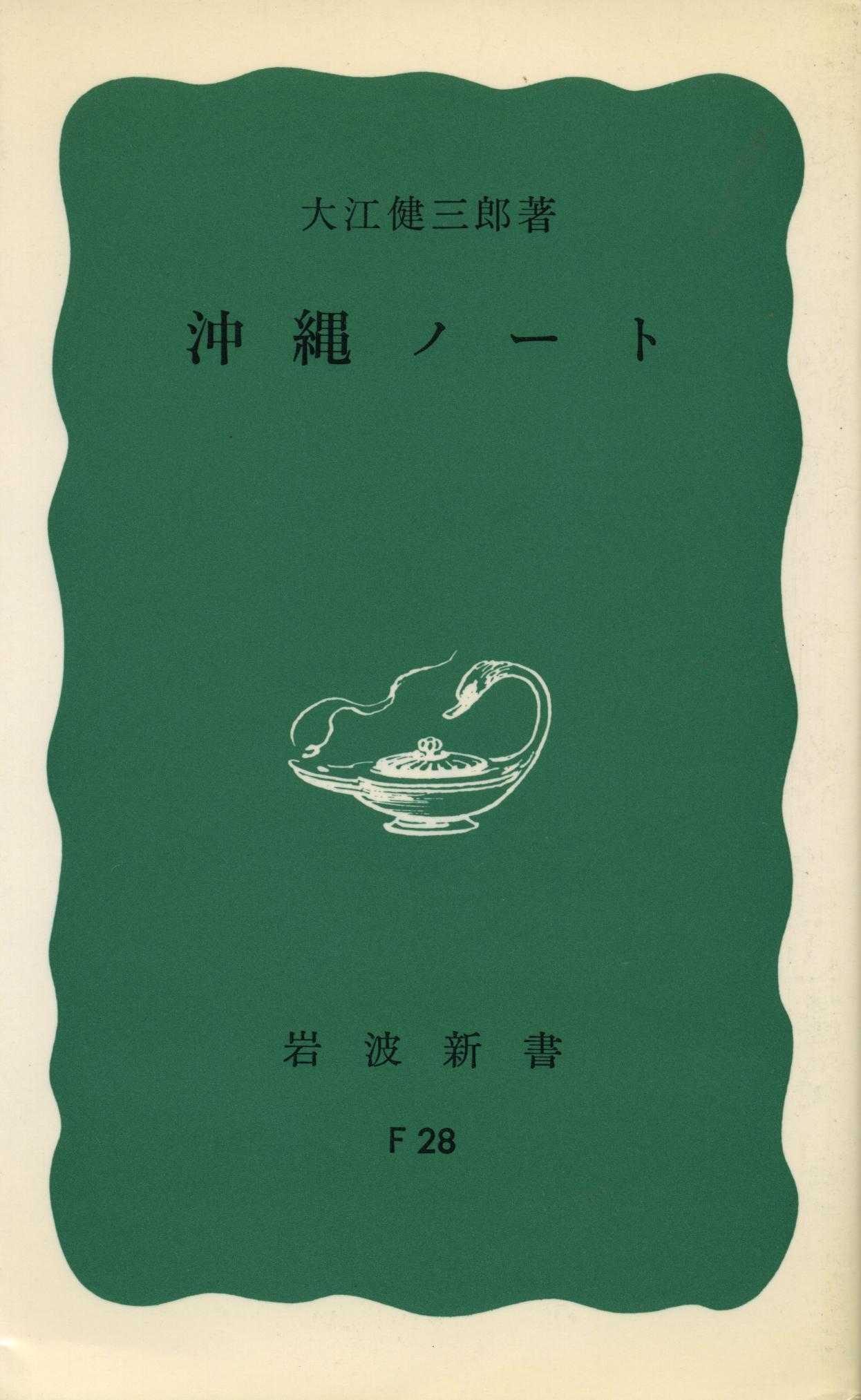
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(14)集団自決
ここで沖縄戦における「集団自決」について考えよう。《慶良間(けらま)列島においておこなわれた、700人を数える老幼者の集団自決は、上地一史著『沖縄戦史』の端的にかたるところによれば、生き延びようとする本土からの日本人の軍隊の〈部隊は、これから米軍を迎えうち長期戦に入る。したがって住民は、部隊の行動をさまたげないために、また食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ〉という命令に発するとされている》(大江健三郎『沖縄ノート』(岩波新書)、p. 69) 引用されている『沖縄戦史』をもう少し詳しく見ておこう。《住民にとって、いまや赤松部隊は唯一無二の頼みてあった。部隊の集結場所へ集合を命ぜられた住民はよろこんだ。日本軍が自分たちを守ってくれるものと信じ、西山A高地へ集合したのである。しかし、赤松大尉は住民を守ってはくれなかった。「部隊は、これから、米軍を迎えうつ。そして長期戦にはいる。だから住民は、部隊の行動をさまたげないため、また、食糧を部隊に提供するため、いさぎよく自決せよ」とはなはだ無慈悲な命令を与えたのである。 仕民の間に動揺かおこった。しかし、自分たちが死ぬことこそ国家に対する忠節であるなら、死ぬよりほか仕方がないではないか。あまりに柔順な住民たちは、一家がひとかたまりになり、赤松部隊から与えられた手榴弾で集団自決を遂げた。なかには、カミソリや芹、鍬、鎌などの鈍器で、愛する者をたおした者もいた。住民が集団自決をとげた場所は渡嘉敷島名物の慶良間鹿の水を飲む恩納(おんち)河原である。ここで329名の住民がその生命を断ったのである》(上地一史『沖縄戦史』(時事通信社)、pp. 48-49) この記述には、どこか違和感がある。〈「…いさぎよく自決せよ」とはなはだ無慈悲な命令を与えたのである〉と言えるのは命令を下したものだけであろう。でなければ「神の視座」である。でなければ、「小説」である。 確かに、「集団自決」は、動かし難い悲惨な出来事である。が、問題は、自決するよう命令がなされたか否か、そこにある。《当初、沖縄での「集団自決」には「隊長の命令があった」、つまり「軍命令があった」とされており、1982年以降の高校教科書では「日本軍に強いられた、追い込まれた」という表現がとられていました。 しかし「隊長の命令はなかった」という事実が判明したため、教科書の記述から事実無根の「軍命令」を削除し、書き換えたわけです。 それに反応した人たちが沖縄で「大集会」を開いて抗議し、いまやまた事実と異なる「軍関与」を教科書に記述する方向に世論が動こうとしています》(渡部昇一「歴史教育を歪めるもの」:『WiLL』(ワック・マガジンズ)2007年12月号、pp. 62-63)【続】
2025.05.21
コメント(0)
-
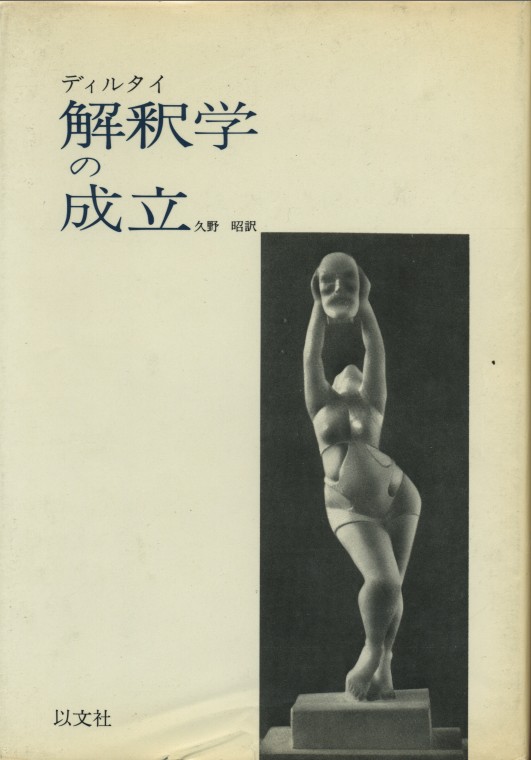
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(13)問題は歴史観の違い
哲学に、「理論負荷性」という概念がある。端的に言えば、たくさんの「事実」が集められて、帰納的に「理論」が創り出されるのではなく、先に「理論」が存在し、その「理論」を通して「事実」が見える、言い換えれば、「理論」という先入見があってはじめて「事実」が確認されるということだ。 「歴史」も同じで、「皇国史観」だの「唯物史観」だのといった歴史観が先に在り、それを通して1つひとつの出来事が「史実」として確認されるのだ。今回の騒動は、「歴史観」の違いによって見える「史実」が異なっているということが根っ子にある。にもかかわらず、「史実」をさも絶対的なものであるかの如く考え、これを受け入れようとしないのは、人の道から外れているかのように批判するのは、独善的に過ぎるということだ。 歴史とは、史実の連鎖や流れの「解釈」である。そして、歴史の解釈には、部分と全体双方の了解が必要である。《個別から全体を、だがまた、全体から個別を。しかも、ある作品の全体は、(著者の)個性への、その作品が関連をもっている文献群への前進を、要求する。つまるところ、個別的な作品のそれぞれ、いや、個々の命題も、比較という手続きあってはじめて、私は、それを自分が前に了解していたよりも深く、了解できるのである。だから、個別には、全体からの了解が必要だし、他方、全体は個別から了解されねばならない》(ディルタイ『解釈学の成立』(以文社)久野昭訳、pp. 50-51) 部分が全体を規定し、全体が部分を規定する。したがって、歴史の解釈とは、史実という部分を理解するために全体としての歴史観が参照され、逆に、全体の歴史観を理解するために部分としての史実が参照されるということになる。つまり、部分と全体が循環的に参照されることで、歴史認識が深まるということだ。 さて、沖縄には、「ウチナンチュウ」という方言がある。これは、沖縄人という意味であるが、これと対になるのが、「ヤマトンチュ」(本土人)がある。このような言葉の存在は、沖縄には、沖縄と日本本土との間に少なからず「垣根」があるということを示唆する。当然、そのことは歴史認識にも表れる。日本人が有(も)つ「国史」とはどこか相容(あいい)れないウチナンチュウ独特の歴史観が存在するのではないかということだ。 沖縄の人々には、歴史的に、自分が日本人なのかそれとも琉球人なのかで意識が錯綜する「心の葛藤」があるように思われる。このことが、今回の問題にも少なからず影響しているのではないだろうか。ウチナンチュウとヤマトンチュで見える歴史が異なるところがある。だとすれば、有無を言わさずウチナンチュウの歴史観やそこからくる教育方針を批判するのではなく、ウチナンチュウの心の問題に寄り添う優しさも和解には必要だろうと思われる。《政治とは、情熱と判断力の2つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっと穴をくり貫いていく作業である》(ウェーバー『職業としての政治』(岩波文庫)脇圭平訳、p. 105)【続】
2025.05.20
コメント(0)
-
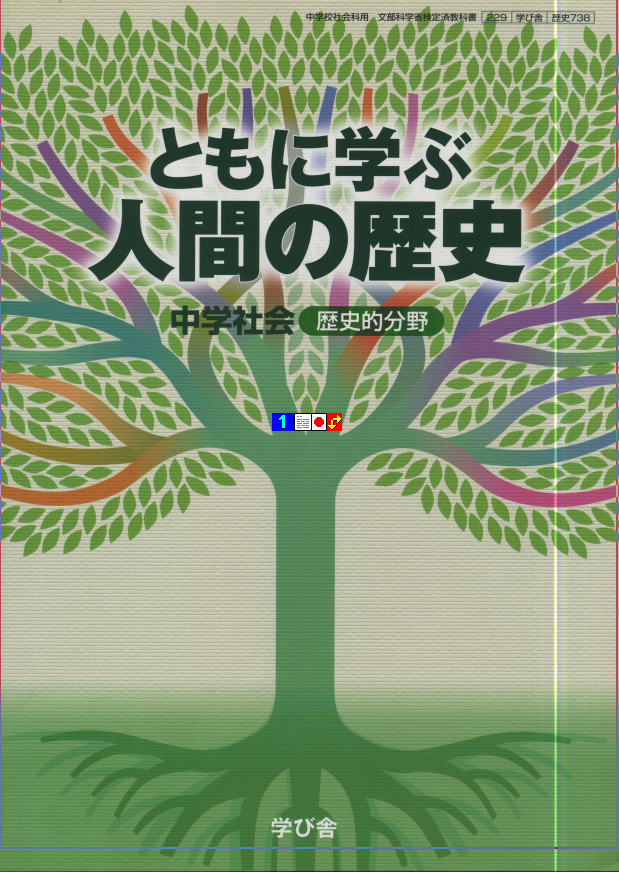
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(12)歴史教科書は左右2冊読み比べるべきだ
《沖縄の旧制中学や師範学校の生徒は、旧日本軍から鉄血勤皇隊や通信隊などに動員され、戦場へ送られた。 ひめゆり学徒隊の女子生徒も1945年3月、傷病兵の看護要員として配属され、戦闘に巻き込まれた。 沖縄本島南部に追い込まれた軍は6月18日、勝利を信じて献身的に働いていた学徒隊に解散を命令した。砲弾が飛び交う戦場に放り出され、手りゅう弾で自ら命を絶つ女子生徒もいた》(5月9日付西日本新聞社説) つまり、日本軍が沖縄を「捨て石」にしたことで、沖縄の人々は悲劇へと追いやられたと言いたいのだろう。中学歴史教科書にもそのような記述が見られる。《日本軍は沖縄の戦闘で.「敵の出血消耗」をはかって米軍を少しでも長く足止めし.日本本土の防衛(本土決戦)の時間稼ぎをしようと考えていた。沖縄を「捨て石」にする作戦だった。 沖縄の日本軍司令官は「兵員は最後まで戦うべし」と命じて,6月下旬に自決した。そのため,残された日本兵はこのあとも絶望的な戦闘を続け.犠牲者は増え続けた。沖縄の日本軍が正式に降伏したのは9月7日であった》(『ともに学ぶ人間の歴史 中学社会 歴史的分野』(学び舎)、p. 249) また、この教科書には、「集団自決」の話も詳しく書かれている。《住民は,壕やガマ(洞窟)にひそんで戦火を避けていました。日本兵がいたガマでは,食料を出させられ,赤ん坊は外に連れ出すように命じられました。米軍は,降伏してガマから出るように呼びかけましたが,日本兵がガマの出口で銃をかまえていました。 住民は日ごろから,捕虜になるなら帝国臣民として死を選べ,米軍は鬼畜だから捕まったら残虐な目にあうと教えられていたので,ガマから出ていくことをためらいました。ガマから出て保護される人もいましたが,米軍に攻撃されて死亡する人や自決する人もいました。 日本軍は,最後には玉砕を決意して,住民にも手相弾を配りました。住民がこの手相弾を爆発させ,家族や近所の人たちといっしょに自決した例が数多くあります。 座間味島では,自決したとされる135人(年齢などがわかる人たち)のうち,12歳以下の子どもが55人,女性が57人を占めていました。これらは「集団自決」とよばれています。また,住民が日本軍に殺害される事件も起こりました。その多くは,日本軍の情報を米軍にもらしたのではないか,という疑いによるものでした。 こうして,沖縄戦での沖縄県民の死者は15万人(人口約60万人)にのぼったと推定されています。鉄血勤皇隊員となった県立一中生254人のうち171人が,「ひめゆり学徒隊」の女学生222人のうち123人が,戦闘のなかで死亡しました》(同) 表現の自由を尊重するということから、日本の歴史を暗黒史として描こうとする教科書があることは仕方のないことではあるけれども、記述内容に大きな開きがあるのであれば、左右2冊の歴史教科書を採用し、見比べることもまた必要となるのではないだろうか。【続】
2025.05.19
コメント(0)
-
西田議員の「歴史の書き換え」発言について(11)平和教育はナルシストの自己満足
《太平洋戦争の末期、沖縄は本土決戦までの「捨て石」とされ、激しい地上戦などで、日米合わせ20万人余りが命を落とした。うち一般県民の犠牲者は9万4千人にのぼるとされる。単に戦闘に巻き込まれたというものではなく、「軍官民共生共死」を掲げた軍による動員の帰結である》(5月9日付朝日新聞社説)《沖縄は本土防衛の時間を稼ぐための「捨て石」とされ、住民を巻き込んだ苛烈な地上戦の場となった。日米の戦死者約20万人のうち、沖縄県民は約12万人に上り、4人に1人が犠牲となった》(5月9日付毎日新聞社説) これもむしろ西田議員が言う「文脈」を裏付ける話である。《看過できないのは、西田氏が「自分たちが納得できる歴史をつくらないと、日本は独立できない」と語ったことだ。証言や研究に基づく史実を都合良く書き換える行為がまかり通れば、過去から教訓を学び、将来に生かすことができなくなる》(同) 歴史は「解釈」であり、絶対的なものはない。前提の置き方次第で白にも黒にも成り得る、それが歴史というものなのだ。ましてや大戦の相手国を捨象し、自国だけの教訓を学んだところで、平和は得られない。《沖縄戦で組織的な戦闘が終結した1945年6月23日からまもなく80年となる。戦争を体験した世代が少なくなる中、その実相を正しく伝え、二度と国民を戦火にさらさないことこそが政治の責任である》(同) 日本が戦争を好まなくても、周辺には好戦諸国が存在し、虎視眈々と日本を狙っている。そのような状況の中で、独り善(よ)がりの教訓など何の抑止にもならない。日本が平和を愛好しようがしまいが、そんなことは関係ない。実際、北朝鮮はミサイル実験を止めず、ロシアは北方領土を占領したまま、シナは琉球が自分たちのものだと言い張り、韓国は竹島を実効支配し続けているのである。《西田氏は「地上戦の解釈を含めてかなりむちゃくちゃな教育のされ方をしている」とも語った。沖縄では悲劇を繰り返さないために体験者の証言に耳を傾け、平和教育を充実させてきた。県外から訪れる修学旅行生らの平和学習にも生かしてきた。戦後積み重ねてきた教育を踏みにじる暴言というほかない》(5月9日付神戸新聞社説) が、沖縄に平和教育が必要だとすれば、それは、沖縄人が伝統的に好戦的であるからということを意味してしまわないか。そうではなく、悲劇を被った沖縄県民は、平和の範を垂れる義務があるとでも言いたいのだろうか。 が、残念だが、沖縄県民が平和教育によっていかに戦争を嫌い自制的になろうとも、世界には何の影響も与えない。つまり、沖縄の平和教育は、ナルシストの自己満足でしかないということだ。【続】
2025.05.18
コメント(0)
全5979件 (5979件中 1-50件目)











