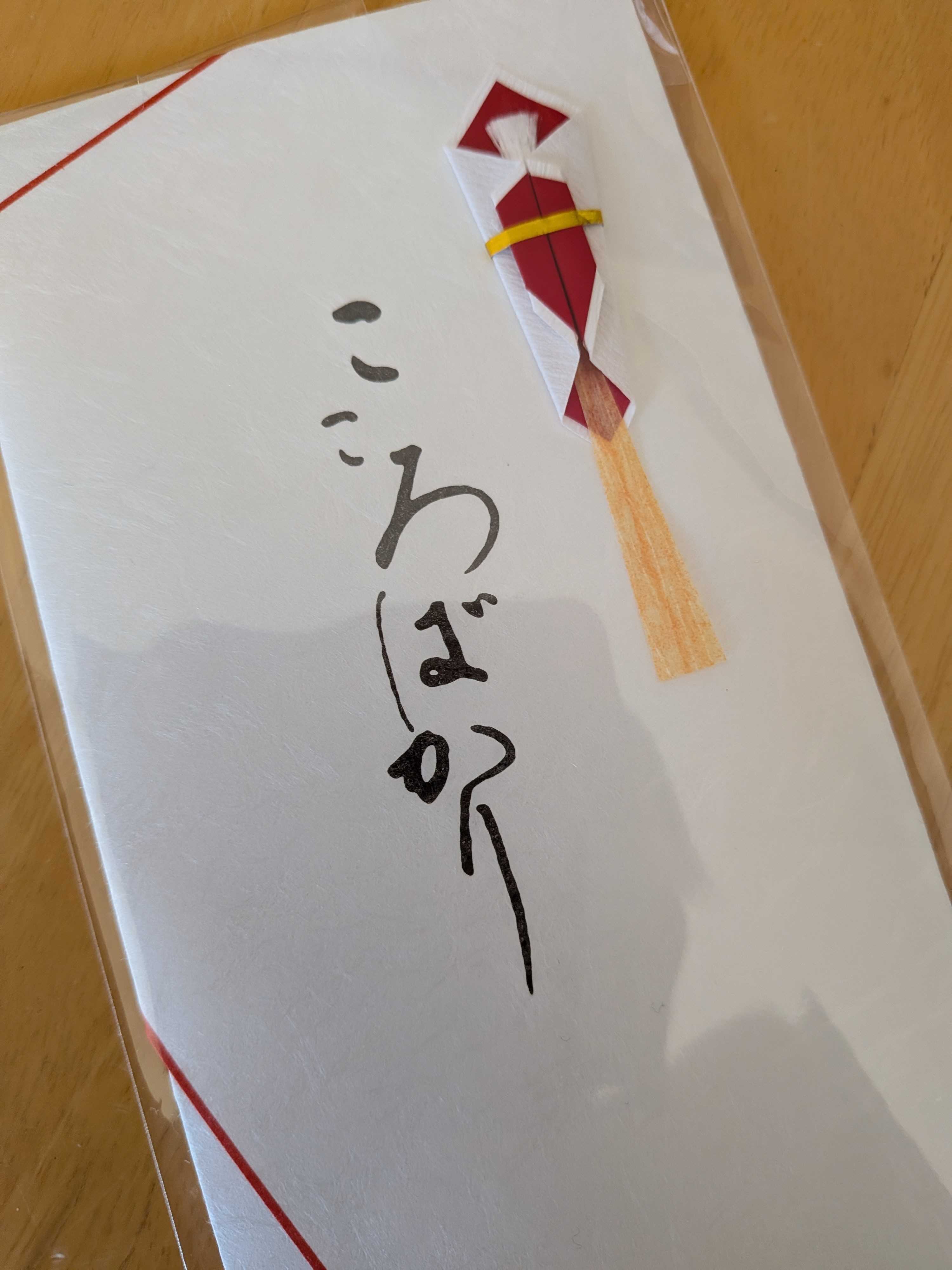全128件 (128件中 1-50件目)
-
念のため、再度、連絡です。
1月より、タイプパッドのblogを利用することにしました。URLはこちらです。http://ryu2net.typepad.com/
2004年02月02日
コメント(54)
-
日記を引っ越しました!
http://ryu2net.typepad.com/今後はこちらをご覧ください。よろしくお願いします。
2004年01月01日
コメント(0)
-
Job OfferとOPTの重要性
ある会社からJob Offerがきた。といっても年俸も仕事内容も明らかにされていないので判断のしようがないが。でもアメリカに残る選択肢になるのなら、かなり有力なオプションになると思っています。アメリカで働く場合、グリーンカードは必須であることがほとんど。とすると、(1) グリーンカードの抽選に当たる(2) アメリカ人と結婚するというようなオプションしかなかったりする。これではアメリカで就職するのは至難の業だと思っていい。ところが、学校を卒業した後1年間は、OPT (Optional Practical Training)といって、学生の身分で働くことが可能。これだと会社もビザ発行の手間がかからないので、「OPT期間なら」といって採用されることも多い。働きに応じて、その後の労働ビザ発行などを考慮してくれるというわけ。これでかなり就職活動がしやすくなる。一方でこれは、少なくとも2年制程度の学校を卒業する必要があり、かつ、何度も申請はできない。今回のチャンスを逃すと、それこそ、2年間大学を入り直す時間とお金とを無駄にすることになるといってもいい。アメリカで働く、数少ないオプションを失ってしまうのだ。留学を考えている人には、このOPT期間をどのようにすごすのか、ということも含めて、計画を立てておいた方がいい。
2003年12月28日
コメント(0)
-
三菱商事アメリカの小川さんと昼食
三菱商事アメリカの小川さんと昼食をご一緒。通信一筋、技術のことから市場の動きまでさすがに詳しい。今後のインターネットはどうなっていくのか、僕のアイデアである「個人向けVPNのキモ」「Eラーニングの将来性」など聞いてもらいつつ、小川さんの仕事術のごく一部を教えてもらったり。最近は、三菱商事OBがベンチャーなどに入って活躍するケースも多く、たとえばドコモからPalmまで採用されているモバイル向けブラウザのアクセス、ADSLのイーアクセスとのディールを行った人など、活躍がめざましいとか。面白かったのが、「日本は組織力が強いと言うけれど、むしろ個人の忠誠心など、個人に頼っている側面が大きい。アメリカは個人主義といいつつも、組織がしっかりしていないと人は働かない。綿密なジョブディスクリプションを提供し、成果を評価するなど、本当の意味で組織力があるのはアメリカだと感じる。」という話。なるほど。夕方、日本へのフライトチケットの手配を進めるが、なかなか決まらない。結局、出発を遅めにずらすことになった。どれもこれも、お役所の仕事が遅いせい。
2003年12月26日
コメント(0)
-
クリスマスパーティ
クリスマスパーティにでたのですが、やはりイラク戦争の話になり、全員がBush反対。でも、「戦争が続き、景気が上向きになれば再選はやむを得ないだろう」とも。なかでも興味深かったのが、一人の女性のボーイフレンドがイラクに行っているという話。彼女もこの戦争には反対。ただ、命令であり役割だから受け入れないといけない、という葛藤。現地の話にはなりませんでした。クリスマスには血なまぐさすぎます。その後の会話。「上院議員の半分がパスポートをもっていないんだよ」「じゃあ、外国に行ったこともない?」「ブッシュだって、大統領になって初めて、海外に行くようになった」・・・これが事実かどうかはわかりません・・・。が、国際色豊かなシリコンバレーらしい会話だと感じました。
2003年12月24日
コメント(0)
-
クライアントとのミーティング
今日は、生島さんとのビジネスにおけるクライアントの社長と打ち合わせ。打ち合わせ中もいろんなアイデアがでてきた。やっぱりこういう、「いっしょに考えよう」というのがいい。日本だと、お金を出す側が偉い、という暗黙のルールがあって、それなりに態度に表さないといけない。これはでもほんとうではない。お金を出す分、こちらは知恵を出す。知恵とお金、対価として適当であるから取引が成り立つと言うことを考えれば、ここに上下関係はない。発注に上下関係が発生すると、下から適切なアドバイスができないこともありうる。それにあらゆるヒエラルキー構造は、イノベーションを阻害する要因になりうる。これが僕の考え。信念にはまだ至っていないが・・・。そろそろ覚悟を決めろ、とKozyさんに言われて以来、考え中が続いています。
2003年12月22日
コメント(0)
-
ついにMacintoshを購入
この数ヶ月間、毎週、Apple Storeに通い詰め、そのたびにPowerBookの美しさに惚れ込んでいたんですが、ついに購入を決意!改めて、美しさにほれぼれ。ソフトウェアも購入しないといけないことを考えると、かなりの出費になるが、それに見合うものだと思う。いい点・ユーザーエクスペリエンスを考えている。 こまごまとした細部に、気配りがある。・フォントがきれい おなじウェブサイトを見ていても、すっきりきれい。・なにか作りたくなってくる 実はこれが一番大きい要因。悪い点・データが移行できない可能性・ソフト購入費がかさむ結局、将来の人生設計において、今Macを使い始めるのが一番であろう、という結論に落ち着いた。購入の判断というのは、さまざまな情報を集めながらも最後は直感的なもの。道具は、「生産性」ではかるべきで、Windowsはビジネス上の生産性においては、Macに勝るだろうけど、デザインをやろうとは思わない。これは昔、Mac (Performa)からWindowsに乗り換えたときの違和感から、ずっと引きずっているトラウマ。同じソフトなのに、使いたいと思えない。つれづれに、「なぜ同じソフトなのに使いたいと思えないか」を考えてみると、以下の要因があるように思う。・Wondowsのフォントが醜い これは、未だにwordで書類を作っていても感じる違和感。ワープロ全盛の時代には、ワープロそれぞれのフォントがありましたよね。印刷したフォントの感触にワープロの性格が現れていた。文字をうつ、印刷するということに関して、フォントはすごく大きな意味をもつ。というか、そこにこそ注意を払うべきなのだけど、Windowsは無関心なのだ。 もちろん、新しいフォントをいれてそれで表示、印刷すればいいのだけど。と書いて、そうすればいいじゃん、って思った。その手があったよ。なんで今までやってなかったんだろう。メニューもあらゆる表示もすべて、お気に入りのフォントで表示すればよかったんだ。あとでお古のPCでやってみよう。・画面描画が不自然 (ものをドラッグするとカクカクする)これは僕のPCのマシンパワーにもよるんだろうけど、ものをドラッグするとかくかくっと残像が残るというか、動きがぎくしゃくする。これがどうにも醜い。またある動作をすると(ソフトウェア立ち上げなど)、画面がぱぱっとちらつく。画面を書き換えてるんだと思うんだけど、それも、馴染まない。そういうのを見せてほしくない。なんてつらつら書いていると、Macユーザーの典型的Windows批判だなあ。こんなこと、どうでもいい人にはどうでもいい。ちなみにUnixだからどうの、とかは僕は気にしない。映画のフィルムの肌触りのような、味わいのある画面の肌触りだとか、人の目に馴染むなめらかなカメラワークみたいなアナログ部分が、要は僕にとって重要なのです。
2003年12月20日
コメント(0)
-
昼食セミナー「ブロードバンド時代のKDDIの戦略」に出席
今日は「ブロードバンド時代のKDDIの戦略」に出席。・ユビキタスになる・P2PからP2M、さらにM2Mになる・あらゆるものがネットワークにつながるという趣旨。ヤフーBBの市場破壊ともいえる低価格攻勢にときおり苦情を挟みながら、ある程度、概略を説明してくれた感じ。ふと思いついたアイデアを講師の方に送付。反応が返ってくるといいな。鹿児島大学の京セラ経営学の助手の方も来られていて、遠距離教育について熱く語る。さっそく「ISIS編集学校」を紹介しておいた。教育は、ネットワークによって行われるもので、教育者はあくまで場を提供するコーディネーターにすぎない。そういう基本がわかっていないEラーニングが多すぎるのだ。(僕自身、いつくかやってみてすぐ挫折した)
2003年12月19日
コメント(2)
-
JETRO XMAS Partyで起業家社長に会う!
ジェトロのクリスマスパーティに出席すると、おそらく200人くらいがきているのではないか。大盛況。話によると500人以上に案内を送っているのだとか。偶然にも、先日話をした起業家の社長とあう。日本進出をサポートすることになっている会社だ。彼がなぜフランスを離れ、アメリカで起業し、一社目は成功を収め、また今、新しい会社を興したのか。その意味と、彼のビジョンを聞き込んだ。さらに親近感を感じた。起業するのは、もちろんお金のためというのが大きい。アメリカでは大金を手にする手段として、多くの人が起業という選択肢をとる。実力さえあれば成功するはず、という強い確信があるからだ。しかし、その奥底には、起業せずにはいられない、という逼迫した思いがあったりするのだ。いい励ましをもらった気がした。
2003年12月11日
コメント(0)
-
GMO島影氏とブレーンストーミング
夕方からGMOの影武者・島影さんとお会いしてブレスト。なかなか刺激をうけて、面白いアイデアがでてきた。1998年ころ、やられた~~!って思ってたんだけど、5年たって、なんだまだまだ可能性がいっぱいあるじゃん、って安心したんですよ。1995年からウェブ日記を書いていて、当時のはもう手元にないけど、そのときから、「ウェブはコミュニケーションツールである」ということには気づいていたわけで、ソーシャルネットワーキングがようやく話題になってきていて、まあ、「いまさら」というか「ようやく」という感慨に浸っているわけです。夜は、SVJENが主催する、中国ビジネスのセミナーに参加。前日の徹夜が響いて、ついうとうとしてしまったが、実際、内容はごくごく一般的で表面的な内容に終始していて、うーん、ちょっといまいちだったかな。
2003年12月10日
コメント(0)
-
月刊コロンブスからの取材
10月の朝日新聞の取材に続き、「月刊コロンブス」という雑誌から取材がきた。失礼ながら、名前も聞いたことがなかったのだけど、地域経済にフォーカスした出版社のよう。中国系にも強いみたいだ。今回の取材は、例の「ワンコイン翻訳」。収益というよりは翻訳の勉強をお金もらってやれる、という趣旨のものなのだけど、紹介されるのはいいことだ。「勉強」とはいえ、翻訳者はビジネススクールの学生だから、質は相当なもの。念のため「ワンコイン翻訳」のURLを書いておきます。もし依頼があったら、お気軽にお問い合わせくださいね。http://www.translate.jp/
2003年12月09日
コメント(0)
-
千賀さんと昼食会
渡辺千賀さんと昼食を一緒に。千賀さんハイテク産業で日米企業の技術アライアンスを行っている。スタンフォードでのMBAの話、仕事の見つけ方、アメリカでのビザ取得の秘訣、ヤギ夫の話まで、散弾銃のように繰り出される話題に、ついていくだけで必死! 一緒にいったMayumiも感激の様子。千賀さんの男は生物学的に話を聞けないようにできている、なんてあたりでは、「いやあそのとおりデス」と防戦一方。前にも書いたっけ? 今、千賀さんのウェブサイトを制作中。かならずクリスマス前には仕上げます!
2003年12月08日
コメント(0)
-
mayumiのfarewell party
夜からMayumiのFarewell Partyを開く。なべ!なべ!なべ! 博学、英語ほぼネイティブの村山さんが、メインシェフとして腕をふるったなべは、まあ、ほんとうにうまかった。はらいっぱい。村山さんの博学っぷりはここで確認だ!http://naotakeblog.typepad.com/ いろいろ話したけど、忘れてしまった。「日本では『へえボタン』がはやっているらしい」とか、そういう日本ネタで盛り上がった。日本だったら絶対に盛り上がらないだろう、時代遅れの話ばかりだけど。こういうとき、ちゃんと日記を毎日、その日の夜につけれいればと思うんだけど、相変わらず2週間遅れのダイアリー。
2003年12月07日
コメント(0)
-
うぁ~だまされた・・・
今日は、EAの人などがくる忘年会がSFであるっていうから言ってみたら、「実は昨日でした」だって! あーだまされた!でも、代わりにポルシェの3Dをもらったので満足!わださん、埋め合わせはお願いしますよ。
2003年12月06日
コメント(0)
-
金型が日本を救う!?
昼からサンフランシスコで金城さんと会う。金城さんは先日のJTPAの会合で知り合った人。相当変わった経歴の持ち主で、京都大学の経済学大学院をでてから、金型を扱う中小企業に就職、製造、プレスから経理、経営まですべての経験をしたあと、海外進出事業部を設立。アメリカ、アジア、ヨーロッパなど渡り歩く。今は、サンフランシスコを拠点にして、アメリカ企業と日本企業のビジネスアライアンスを行っている。金城さんは、金型に対する知識を生かして、中小企業の金型技術を紹介している。アメリカのクライアントは大企業ばかり。アメリカでは到底作れない金型を、日本の中小企業に発注する、そういう提携を行うのだ。その一方で、東京でデザイン会社、卓球場などを経営。将来は、多数の事業を経営する経営者になりたいという。年齢は聞いていないけど、見た目は若く、20代後半に見える。おそらく30代半ばかな。(注)大学院で勉強していたときには、将来、研究者になるつもりでいたという。その道をあきらめて就職するときには、・世界に通用する技術をもっていながら、世界にまだでていない企業という評価軸で企業を探したのだとか。そこで世界進出を引き受けるというキャリアプランが明快にあったからこそ、可能になったのだろう。一緒に、ワダトモコとも話す。彼女は、Academy of Artの学生。同じ京都大学文学部の出身だ。今はなぜか3Dモデリングの勉強をしていて、今はちょうど卒業制作で大忙し。将来は、「大人向け完全3Dアニメ」を作ること。浅尾さんのVMXtremeの話をしたら興味をもってくれたので、早速、紹介しようと思う。それにしても、こういう覚悟を決めた人にあえるのが、僕にとって今一番の刺激です。【注】1971年生まれの32歳。ご本人から指摘をうけました・・・。半ばなんて言ってしまってすみません。
2003年12月05日
コメント(0)
-
3Dモデリングをやるベンチャー
元パナソニックの浅尾さんの紹介で、3Dグラフィックをやっているベンチャーを訪問。VMXtremeという会社で、たとえばhttp://vmxtreme.com/user/mt21/3d/model1/mot.html 右ドラッグでズーム左ドラッグで回転などができる。主にインドで制作することによって、コストを劇的に下げることに成功。技術的にも優れていて、この1月に公開されるCGIを使ったインド映画にも参画している。日本では、大手印刷会社との提携をはじめ、いくつか実績がではじめた。車関連の仕事も多くなってきているとか。車!というキーワードから、Academy of Artの俣野さんを紹介することに。僕を介してネットワークがつながっていくのは、とてもうれしい。ちなみに、日本進出に関して、以下のような人材を募集しているので、もし興味があったら、連絡を取ってみてはいかがでしょうか?・3Dグラフィックのソフトが扱える。 (おおまかなコンセプトとなるデータを作成、あとはインドで仕上げをする、という流れになります)・英語が堪能 (インド人と英語でコミュニケーションします)詳しくは、VMXtemeに直接問い合わせてみてください。http://vmxtreme.com/
2003年12月04日
コメント(0)
-
富士通アメリカの勝股さんに話を聞く
勝股さんは、富士通の北米HQである富士通アメリカのライフサイエンス部門のVPをやられている方。富士通は日本でこそ強いブランド力を持つが、アメリカではコンシューマプロダクトがそれほど強くないこともあって、あまり認知が高くない。そのため、いろいろな苦労をされてきた。一番の違いは、日本製ソフトウェアはどこまで言っても「しょうゆ味」だということ。アメリカ製とは使い勝手が微妙に違うのだという。たとえば日付にしても、日本は2003/12/3だが、アメリカは12/3/2003、ヨーロッパは3/12/2003である。こうした違いが、とっかかりの場面で大きな影響を与えてしまう。また、サポートについても要求は高い。結局、サポートの近くに開発者を常駐させることになる。ということは、アメリカ向けのソフトは最初からアメリカで開発すればいい、そうすればアメリカ風のソフトになる、ということで、ソフトウェア開発はもっぱらアメリカで行っているという。アメリカでは、マニュアルもプロジェクトマネジメントの一部に組み込まれて、テクニカルライターがきちっと仕上げるが、日本にはそうした発想がない。その点でも、アメリカでのソフト開発はよいのだとか。面白かったのが、グローバル、という言葉の意味の違い。グローバルという場合、地球を宇宙から眺めるような視点をもつことを意味するが、日本のグローバルは、足は日本についたまま、ちょっと背伸びしてほかの国を見渡すような感じだ、と。この比ゆはなかなか分かりやすい。その点、中国人はグローバルな視点を持って活動しているように感じると勝股さんはおっしゃっていた。さっそくドリームゲートのMLでこの話をしたら、Kozyさんが「コスモポリタン」というふうに区別しているという返信がきた。なるほど!
2003年12月03日
コメント(0)
-
生島さん、帰国
夕方、生島さんが帰国。あっという間だったが、ずいぶん面白いことがあった。今回はとにかく可能性を広げられたことが一番で、今後、成果を出せるかどうかはこれからのがんばり次第。夜は、サンダーバード国際経営大学院の月一回の同窓会に参加。アップルに勤め始めた人など、いろんな人に会えた。そろそろ自分の英語版ウェブサイトを作らないとと思い始めた。サイトを紹介しても、日本語だから、彼らは読めない。(といいつつ、今回しゃべった3人のうち2人は日本語ばっちりだったのだが・・・。サンダーバード国際経営大学院って、その点、すごい。)その後、炎のクリエーター、JUNとICHI Restaurantで食事兼写真撮影。おいしい!めっちゃおいしい!もう、びっくり。撮影後は貪り食うように、平らげた。
2003年12月02日
コメント(0)
-
そにーかぶ
朝から、テレカンファレンス。と思ったら急にキャンセル。せっかく準備したのに・・・。昼は組み込みデータベースの会社に。サンフランシスコのちょっと南に位置する会社。まわりに高いビルもなく、ダウンタウンの町並みも見渡せる、景色のいいオフィスだ。もともとビール工場だったとかで、フロアの中でアップダウンがあったり、ビルのつくりがずいぶんユニーク。商品自体は、なかなか販売が難しそう。おしゃべり好きの人が出てきて、「まえの会社では日本とも付き合いがあって、ずいぶんいろんな経験をしたよ(以下略)・・・」って話に付き合っていたら、あっというまに時間が過ぎ去っていった。そのあと、郵便局にいったら、そこでも大行列。すっかり遅くなってしまった。夜からはJTPAの忘年会。ここでは、GMOの島影さん、日本の金型企業とアメリカ企業とのビジネスアライアンスを仕掛けている金城さんと話し込む。二人とも、「また後日話そう!」ということになった。こういうところから新しいビジネスの話がでてくるというのが、シリコンバレー流。ソニーの方との話で、PSXのすごさを感じる。ソニーの株を買っておこうかな。つぶれるかもしれない、という危機感があるなかで勝負に出る会社は、ついつい応援したくなる。まるでニッサンのよう。
2003年12月01日
コメント(0)
-
アメリカの生卵
アメリカの卵はばい菌がたくさん繁殖しているので生で食べない、というのが通説なのですが、実は日本の卵ともそう変わらない、なんて話も。もともと中は無菌状態なので、表面上をきっちり熱湯消毒すれば安全と言う説も。いずれにしても、生卵を今日食べたら見事に腹痛に襲われて、でもたいしたことはなかったので、単なる疲れなのだろう。ぐっすり休む・・・。
2003年11月30日
コメント(0)
-
ぐっすり休む
最近、働く時間が大半を占めていたので、今日はゆっくり休む。風邪を引いたかも・・・。買い物など。
2003年11月29日
コメント(0)
-
シリコンバレーの仕事術
シリコンバレーで生島さんと一緒に仕事をしているのですが、その途中報告をメルマガ(【週刊☆ビジマ】 http:://www.mankai.biz/)に載せました。ここに転載しますね。←日記の手抜きとも言う。====================================================================☆彡☆『ビジネス門前小僧 -習わぬ起業の奮闘記-』第12回 「シリコンバレー突撃ビジネス」 MBA学生起業家 小山龍介========================================================================こんにちは、小山龍介です!今、【週刊☆ビジマ】 の執筆者の一人、生島さんがシリコンバレーに遊びに来ています! って、単に遊びに来るだけじゃつまらないので、「クライアントを見つけてビジネスをはじめる」ことにしました。ビジネスをはじめるといっても、こちらにあるものは、知的財産だけです。でもシリコンバレーにしばらくいた僕は、知的財産と「何かをやろう」という情熱だけで、ビジネスが成り立つことを知っています。▼会う理由を作るところから始める突然、生島さんから「シリコンバレーに行きます」とメールが来たんですね。「シリコンバレーの今を知りたい」という。今を知るには、企業を直接訪問するのが一番。だけど、残念ながらアメリカの企業は理由もなしに会ってくれない。まずは「会ってくれるための理由づくり」からスタートしなくちゃいけない。いつもは、技術評価サービスをベンチャーキャピタルへ提供している生島さんですが、今回、「アメリカ企業に対する日本市場への技術マーケティング支援」とサービスの内容を刷新。これなら、日本市場進出を考えている会社であれば、会ってくれる。リストアップした日本進出希望の会社に電子メールを送ってみたら、なんとおよそ半数から返事が返ってきた! これが第一歩です。▼顧客視点のウェブサイト制作ウェブサイトで一番重要な情報は、こちらの会社情報ではない。お客さんが何に困っているか、ということを「的確」に捉えていることが大切なんですね。日本市場進出について、「適切な人に会えない」「決定に時間がかかって大変」というような悩みがあるとするなら、それを指摘した上で、「解決できます、なぜなら」とやるのがスマート。もし、困っていることを指摘もせずに自社の話や自分の技術の話をするなら、それは自慢話でしかない。そんな独り言を聞くほど人は暇ではないですよね。顧客視点というのは、言い換えると、「あなたの悩みをまずは聞かせてほしい」ということでもあります。実は電子メールでは、いきなりセールスの話なんかはしませんでした。> 日本市場への参入ではいろんな困難がありますよね? それについてぜひお聞> かせいただけないでしょうか? 私は日本でこれこれこういうことをしていて、> お力になれると思うのです・・・このメール内容も、メールの反応を高めたひとつの要因だと思っています。▼ホリデイもなんのその今回、一番の懸念が、タイミング。今週はサンクスギビングのホリデイウィーク。サンクスギビングは普通、家族が集まってターキーを食べる、日本のお盆のような日。こんな大切な日に仕事をする人はいない。マクドナルドですら休みになる。サンクスギビングは木曜日・金曜日だけど、月曜日から休みを取る人も多い。よりによって、そんな週の前の金曜日にメールを打った。お盆前に「お盆の間にあってくれませんか?」と頼むようなもの。それでもなんとか会うことができたのは、ほんとに運が良かった。▼分かりやすい実績の示し方プレゼンテーションファイルは、生島さんの実績をまとめるかたちになりましたが、そのまとめ方にもちょっとしたアイデアを盛り込みました。通常、アメリカのプレゼンでは、リファレンスといって、かならず顧客の名前を出す必要があります。名前の出せないものは「実績」にならない。ところが日本の商慣行の中では、顧客名を出しにくい場合が多い。日本では、お金を出す発注側が偉くて、受注側は下という考え方が一般的。名前を出すだけでも顧客に確認をしなければならないし、あとで面倒なことにならないか、ライバルも顧客としてももっていることがバレたらまずい、なんてことも。でもそういう状況を知る人は、アメリカにはいない。生島さんの場合、これまでの精力的な活動から、相当な「数」をこなしてきた実績があった。僕はそのままずばり、「これだけの数の企業を扱ってきました!」と具体的な数でプレゼンしたのでした。▼「二人」が出発点ゲイツにはポール・アレン、ジョブズにはスティーヴ・ウォズニアックが必要であるように、なんて大げさなことを言わずとも、二人でお互いの強みを生かしあうことが、どれほど重要かを感じます。今回の場合、技術の生島、マーケティングの小山という組み合わせ。誤解してはいけないのが、これが「役割分担」ではないということ。僕がマーケティング担当ではなく、あくまでエキスパート(の卵)として、技術の問題にも口を出す。というか、しつこい質問攻めで生島さんを困らせたりしてます(^^;生島さんも、マーケティングについていろんな発想をぶつけてくる。あくまで、強みの多様性が重要であって、役割を縦割りにすることが目的ではない。役割に分けることは本当に嫌いで、学校のグループワークではすぐに「役割に分けて」なんてやろうとする。で、僕は強固に反対する。これは、広告代理店の営業時代に上司に叩き込まれた習性。役割分担した時点で、そのチームからは新しい発想は生まれてこない。言い方をかえると、イノベーションを起こす最も基本的で、日本に欠けている要素が、チームの多様性であり、チームの中での対等な立場である。日本の企業におけるチームは一般的に、(1)上司と部下という立場に分かれる、(2)異なる部署間のコミュニケーション不足、(3)異色な人間がいない、金太郎飴、という問題を抱えていて、ここからはイノベーションは生まれない。▼世の中にない新しい製品を作り出すプロジェクト今回のビジネスミーティングの合間に、生島さんを連れて、とある「新しい製品」を作るプロジェクトに参加しました。まったく異なったバックグラウンドの人があつまって、「夢の新製品」を打ち合わせるのだけど、これが本当にスリリング。僕は技術も多少分かるけど、基本的には利用者側からのアプローチで物事を考える。「新製品は新技術を使うことではない。「概念」を変えてしまうことである」これが僕のこのプロジェクトに対するスタンス。ミーティングは7時半から始まり、ふと気づいたら、あっというまに10時になっていた。生島さんも、このミーティングには大いに刺激を受け、「このままプロジェクトにかかわりたい!」と何度も言っていた。シリコンバレーの企業に勤めるプロフェッショナルが、企業での仕事を超えて新製品を作ってしまう。これこそシリコンバレーのダイナミズムであり、こういう場所からいくつのベンチャー企業が生まれたか、想像するだけでも楽しい。▼2回目の起業です生島さんと一緒に、ベンチャー企業へプレゼンテーションに出かけていくと、「実は二回目の起業なんです」なんてCEOが話し始める。1回目も成功を収めたうえで、2回目に挑戦しているのだという。改めて感心するのが、マーケティングフォーカスの的確さだ。「こうこう、こういう市場が考えられるが、短期的にはこの分野、長期的にはこの分野」というストーリーが出来上がっている。限られたリソースの中でいかに効率的に販売していくか、ということを本当に考え抜いている。また、面白いのがアメリカの起業プロセス。彼は6ヶ月間、プロトタイプを制作しては、VCやエンドユーザーに製品を試してもらっていたのだという。僕たちが訪問したときは、ちょうど完成したタイミング。いよいよ販売していこうというところだった。最近は市場の低迷でなかなか少なくなってきたけど、優秀なアイデアでもって資金を集めて製品を市場に出す、という典型的ベンチャー。来年あたり、投資のお金もシリコンバレーに戻ってくるという予測もある。先の「夢の新製品」プロジェクトも、うまくそういう流れにのって、「いざ、ベンチャー立ち上げ」なんてならないかなあと、思う。それが失敗しても、成功しても、「2回目の起業です」といえるのがシリコンバレーなんです。▼未来に対する取引生島さんは実は、アメリカ企業へのコンサルティング経験はあまりない。おもに日本企業へのコンサルティングに携わってきた。「経験がないのなら、だめ」というのが日本なら、アメリカは「経験が少なくても、やってくれそうだ」というので頼んでくれる。プレゼンテーションで重要なのは、だから、未来への約束なのだ。過去の実績があって、そのうえで将来何ができるか。プレゼンは、「今まで日本企業に提供していたサービスを、アメリカ企業にも応用したい。そのほうが効果がある」という話にしている。日本企業へ行ってきたサービスが、そのままアメリカ企業にも有益でしょ!というストーリー。「ぜひ、やらせてほしい。きっと面白いことが起こる!」という未来への期待感が、契約締結に大きなポイントとなるのだ。#そうそう!この「期待感」という言葉も、広告代理店時代の上司の言葉。自分#でクライアントを見つけるようになって、今ようやく本当の意味を理解しつつ#あるように思います。
2003年11月28日
コメント(0)
-
ゲイのサンクスギビングパーティ
アメリカではじめてのサンクスギビングパーティに出席したら、ゲイパーティだったという。なんともすごい経験をしてしまいました。まあ、普通は家族が集まってのパーティとなるわけで、インド系からフィリピン系、中国系と多様なメンバーが、それも男性だけが集まるのは変だなあと思ったんです。徳重さんと「びっくりしたなあ」と苦笑い・・・。日本の感覚でいえば、お得意さんから誘われたら、行くしかないわけで・・・。
2003年11月27日
コメント(0)
-
一本、筋のとおった履歴書にするには・・・。
朝は、電話会議。i-kitのプレゼンを行ったけれども、日本進出についてはすでにメドが立っているそうで、今回は見送りとなった。午後は、元パナソニックでシリコンバレー研究所の所長をされていて、今はスタートアップのコンサルティング支援を行っている浅尾さんにお会いする。見事な経歴で、一貫性がある。すっと一本、ストーリーになっているんです。アメリカでは、「レジュメをどう構築するか」というのは非常に重要なポイントで、たとえば、会社に導入するシステムも「レジュメ栄えする」という個人的な思惑から選ばれたりすることも少なくない。(オラクルと書けたほうが将来の転職に有利、とかそういった感じ。)夕方からは、システムインテグレーター向けに開発支援のミドルウェアを開発している会社を訪問。とても好感触で、こちらが提供できるサービスしだいで、かなりいい契約が取れそう。夕方からはJTPAの分科会のPDAプロジェクトに参加。あいかわらず濃いメンバーでの議論は面白い。あっというまに3時間が過ぎ去るこの感じは、ひさびさ。やはり、それぞれに専門性を持った人がお互いの立場を尊重しあいながらやる打ち合わせが、もっともイノベーティブだと思う。日本はジェネラリストが多すぎる。
2003年11月26日
コメント(0)
-
シリコンバレー:セキュリティ関連のスタートアップを訪問
午後、最初の訪問先であるセキュリティ関連のスタートアップカンパニーを訪問。小さなオフィスにCEOが一人現れて説明をしてくれた。彼自身、二回目の起業になるという。一度目は文字認識のソフトを作っていたそうで、2million Copiesを販売したと言っていた(数字の聞き違いがあるかも)。二度目はセキュリティ関連。生島さんいわく、「すごくいい!」ということ。感心したのは3点(1)製品のロードマップが描けている(2)独自の商品力で勝負している(請負仕事はしない)(3)マーケティングフォーカスがはっきりしているまた、最近はVCが出資をしないので、当面のキャッシュを得ることが重要だと言う点。なんとか助けてあげたいと思う。
2003年11月25日
コメント(0)
-
Guy Kawasaki講演会
日米商工会議所(http://www.jaccsv.com/ )が主催して、アメリカで活躍するアジア系起業家を招いてのセミナーがあった。なかでも目玉はアップルのエヴァンジェリストであるガイ・カワサキ。(http://www.jaccsv.com/english/pages/AAR%20Guy%20Kawasaki.htm )僕は仕事の関係で結局見れなかったのだけど、ウェブでMP3を販売していたのでゲット。会の前にはドイグチ会長とミーティング。日本とアメリカの橋渡しの重要性と課題について、情報交換を行った。
2003年11月24日
コメント(0)
-
返信のメールが来た!
17社ほどダイレクトメールを送ったら、3社ほどからメールが返ってきた。なかなかいい反応! アポイントは火曜日。以下はメルマガ(【週刊☆ビジマ】 http://www.mankai.biz/ )の編集後記【編集後記】◆今日、生島さんとシリコンバレーのベンチャーに営業に行ってきました。なかなかすごい技術で、生島さんがすっかり興奮。「こんなん、めったにないよ」と。◆それにしても、向こうにしてみれば、非常識なお客。サンクスギビングの休暇直前の金曜日にメールをよこして、普通なら休暇中である週に会え!っていうわけですからね。それでも、アポイントは6件獲得。◆技術者とマネジメントの組み合わせは、やっぱり強い。生島さんのキャリアがあるからこそ、向こうもあってくれるわけだし、それをマーケティングする僕の戦略や戦術も、それなりに効果をあげている自負はある。◆最初のお客さんがあまりに良すぎたので、次回はちょっとがっかりするかも・・・。まあ、いい経験と思って、突撃です。
2003年11月23日
コメント(0)
-
生島さん到着!
夕方、生島さんが空港に到着。ちょっと早く到着したようだったけど、結局お互いを見つけたのは到着から1時間30分ほどしてから。
2003年11月22日
コメント(0)
-
渡辺千賀さん昼食会セミナー
渡辺千賀さんを招いての昼食会セミナーに参加。東大→三菱商事→マッキンゼー→スタンフォードMBAという黄金の経歴をもつ千賀さんだが、話はものすごくストレート、直球勝負。文化的な違いから、日米の技術アライアンスを組む場合の問題となりやすい点を指摘していく内容は、今すぐにでも応用できそうだと感じた。質疑応答の中で「渡辺さんのような方に日本の大企業が仕事を頼むようになったのは、大きな進歩ですよね」という質問に対して、「それには秘訣があるのですが、企業秘密です」と答えられていた。ぜひそのひみつをしりたいものだ。セミナーの後、ウェブデザインをしている話をしたら、「ぜひやってください」と制作依頼を受けた。blogをやるためにちょっとしたプログラムを入れる必要があるのだけど、やってみよう。
2003年11月21日
コメント(0)
-
i-kitアメリカ向けウェブサイト
i-kitのアメリカ向けのウェブサイトを作成。英語の間違いはゆるせ!ってな具合で、急遽こしらえる。http://www.i-kit.jp/business/english.html
2003年11月20日
コメント(0)
-
起業家Lu Dongとの食事
先日のマッキンゼー説明会で見つけたスタンフォードのLuと昼食、すっかり話が盛り上がり、「よし今日の夕食会に参加してよ」と。夕方からは、日本に行く一郎の壮行会。アメリカ企業の日本支社立ち上げのミッションを背負い、一人行く。---Luについては、メールマガジンで書いたので、そちらを観ていただければと思います。以下、転載====================================================================☆彡☆『ビジネス門前小僧 -習わぬ起業の奮闘記-』第11回 「典型的な?ビジネススクールの学生」 MBA学生起業家 小山龍介========================================================================よく日本でビジネススクールの状況を知らないで批判する人が、咲本さんを筆頭としていたりしますが、はっきり言って、正しくない。反論しておかないと、やはり歯がゆい思いがある。今回は、昨日会ったスタンフォードのMBA学生をネタに、ビジネススクールでどういうことが「体験」できるのかを、書いてみたい。▼暗黙知は学べないのか?ビジネススクールは、誰もが理解できる「形式知」を学ぶ場所である、という前提でいくと、「暗黙知を無視している」という指摘は正しい。教科書に基づいて、教科書に書いてあることを学び、それ以外のことは学ばないということなら、ビジネススクールに行く必要はないだろう。自分で勉強をすればよい。ところが、ビジネススクールはわざわざ教授を通じて学ぶのである。世界中から集まった学生とやりあうのである。ここに潜む「暗黙知」は非常に豊かである。ひとりひとりが、それぞれまったく違う目的を抱えながら、同じクラスルームに席を並べる。このことを、「ビジネススクール批判側」は過小評価している。先日、マッキンゼーの説明会に出席したが、正直、会社説明は退屈なものであった。(GEのほうが正直、興味深かった。)だけど、僕の興味は会社になんかなく「面白そうなやつがきているかどうか」であって、僕の予想通り、やっぱりそこには面白いやつがいてくれたのである。(謝々!)彼の名は、ルー。日本語をネイティブのように操る中国人である。▼組立てPC販売ビジネス大学一年のとき、ルーがファッションデザイナーの夢に挫折したとき、彼はひとつのビジネスをスタートさせた。組立てPCの販売である。その当時、PCは非常に高価で、カラーモニターを持っていると「すげえ」といわれた時代。とはいえ、教育熱心な中国の家庭でのPCのニーズは非常に高いものがあった。ルーは、部品を海外から輸入し自分で組み立てることで、コスト削減を図った。このPCは大学生を中心に、飛ぶように売れた。こんなことをやっていてもしょうがない、と見切りをつけたのが、ルーのすごいところだ。長期的に先細りであることを直感、そのときたまたま機会のあった日本への留学のチャンスをつかむ。埼玉大学でビジネスを学んだルーは、日本語とビジネスバックグラウンドの新しい2つの武器を手に入れた。IT知識を生かして投資銀行のIT部門に就職したが、それは「ビジネスとITの接点」だと感じたからだった。数年後に、ITバブルが迫っていた。▼投資銀行での転身IT部門では、学ぶことがたくさんあった。PCを販売していたといってもネットワークやデータベースの知識はほとんどない。一気にさまざまなことを吸収していった。無我夢中にやっていた仕事も、しかし、徐々に退屈なものになっていく。金融のバックボーンは、「安全性」が重視され、新しいことはやらせてもらえない。ルーはここで新しい戦術に出た。投資銀行はさまざまな部署があるが、部署同士の交流は少ない。ルーは「どの部署ともコンタクトを取る」IT部門の利点を生かし、会社内で誰も作ることができないような、部署を超えた人脈ネットワークを作り上げたのである。そうこうしているうちに、ITバブルが到来。突然、IT部門にスポットライトが当たることになった。投資銀行のITを扱っていたとなれば、さまざまなところからひっぱりだこ。会社も給料をあげるだけでなく、さまざまな報酬制度で引止めをはかった。それでもやめていく。ところがルーはその波に乗らなかった。静かに見送った。「これはおかしい。いつかは破綻する。」これがルーの判断だった。かわりに、投資銀行のフロントラインに異動を願い出た。もともと彼がビジネスバックグラウンドであったこともそうだが、IT案件が多くなるなかで、ITの分かるメンバーが必要であったこともあり、異例の転身を遂げる。▼お金が目的じゃ幸せになれないいよいよ投資銀行で活躍の場を得たルーは、でもすこし違和感を覚える。周りを見るとみな、大金を稼ぐ。年収1億も珍しくない。社長ともなれば、年収20億なんてこともある世界。だけど、幸せそうに見えないのだ。年収で人の価値を判断するような雰囲気がある。君は1億か、まだまだだね。と、まあこんな感じ。これでは一向に幸せになれない。投資銀行ならではの、成功企業の社長に会う機会を生かして彼らを観察していると、どうやら二つの成功パターンが見えてきた。ひとつは、成功には業種は関係ないこと。「ITが儲かる」なんて成功を求めて群がるけれども、牛丼でも成功するし、ディスカウントストアで成功することもある。もうひとつは、それが好きなことだという点だ。好きなことをやるんだったら、それが成功であろうと失敗であろうと、それは幸せなのだということを悟る。日本に来て10年がたっていた。会社をやめMBAをとるのに一番のタイミングだった。スタンフォードでは、「チャンスと言うバスは5分ごとに来る。あわてるな、次の大きなバスに乗るのも重要」という教授であり成功した起業家の言葉に、MBAという選択が間違っていなかったことを感じる。彼は今、カリフォルニアの青い空の下、バスを待っている。夢は「日中」でビジネスの橋渡しをすること。彼に中国支社作りを任せるような企業を探している。「日本と中国が好き」という、ルーの見つけた「やりたいこと」であり、幸福への出発点なのである。▼教科書から学ばない、人から学ぶMBAこうした出会いがあるのがMBAなのだと思うんですね。マッキンゼーの説明会には、冷やかしてもいいから行ったほうがいい(笑)。世界の変なやつと接近戦をやる、絶好の場なんです。これを「教科書どおりの頭でっかちのバカ」を切り捨ててしまうのは、ちょっと早まりすぎだろう。
2003年11月19日
コメント(2)
-
Friendsを大量購入
シーズン5まで出ている「Friends」のDVDをすべて購入。ビジネス英語はできても、アメリカ人の日常の会話はなかなか理解しにくい。理解できない会話に入るのも勇気がいるので、「Friends」みたいなドラマは、いい教材だ。Jerkなんて単語も、まあビジネスではなかなかでてこないし、いい勉強になる。
2003年11月15日
コメント(0)
-
マッキンゼー説明会
◆コンサルティングファームのマッキンゼー説明会に行ってきました。◆この組織の強みは徹底した「知識の共有」にある。グローバル企業を名乗りながらも、アメリカと日本の法人ではほとんど交流がないような企業もあるが、マッキンゼーは「海外トレーニング」や「海外赴任」を制度化することで、人の交流を促す。人と人のつながりというアナログなところから、世界規模の知識共有のベースが作られる。◆突然電話やメールで、会ったこともない人から質問が来たりする。そこで質問に答えない、なんてことはありえない、という。どんなに忙しくても、迷惑に感じても、そこで答えないことは、マッキンゼーのメンバーであることを自ら否定することになる。その点、GEと同じく、文化になっている。◆NTT出身の人がそれを聞いて、「会社の同僚に知識を与えて、相手に利するようなことをすると出世に響く。知識共有にマイナスのインセンティブが働いているから、ナレッジマネジメントが定着しない」と嘆いていた。◆目に見える形の知識共有と同時に、徒弟制度が重要な社内教育のメソッド。いわゆるコーチングだ。マネージャーは僕の質問に、「ものまね集団」という言い方までした。この人のこの部分、あの人のあの部分というように、ものまねをしながら自らのスキルを高めていく。◆ただ、だからこそ「マッキンゼー・ウェイ」が浸透している必要がある。もし、個人個人が自分の成功経験からのみ徒弟制で教育するなら、それがマッキンゼーという場で行われる必要はないからだ。マッキンゼー・ウェイに沿っているかどうか、ということは「ナレッジマネジメント」を通じて、世界中のメンバーから常にみられている。その緊張感がある。◆世界のメンバーから問い合わせが来るようになって初めて、ようやくメンバーとして認められる。そういう環境だからこそ、知識共有の仕組みが成り立つ。ひとこと「文化」と言っても、こうした実体があってこそのものなのだろう。
2003年11月14日
コメント(0)
-
ものづくり×Design
ものづくり×Designが日本の将来だと思っているんです。そのために、Design力をつけたい、今そのために、いろいろ将来の可能性を探っているところです(^^;どこかで日本の美の伝統が途切れてしまっている。新しい美の伝統を、いろんな分野で創造していくのが僕たちの仕事だと思っています。
2003年11月13日
コメント(0)
-
ウェブサイト制作の打ち合わせにいってきました
◆さきほど、ウェブサイト制作の打ち合わせにいってきました。日本企業のアメリカ子会社で、売り上げは倍々ゲームになっている好調な企業。すでにアメリカに三つも工場があるとのこと。リニューアルをしたい、という。◆B2Bの会社なので、「買い手が何を知りたがっているのか」ということを基準にして、情報を整理して見せることになりそうです。最終的に「資料請求」のアクションまで結びつけるのが、ウェブサイトの仕事。◆僕の得意分野の「映像」も絡んできそうで、うれしい限り。社長は「すべてはパフォーマンスベース。実績は関係ない」という。日本だとありえないことだけど、アメリカだったらありうるんですよね~。
2003年11月12日
コメント(0)
-
シリコンバレー訪問
> さてさて、渡米の件ですが22日のフィリピン航空でマニラ経由> サンフランシスコになりました。> トランジットがうまくいけば、24日の週はそちらで活動できそ> うです。
2003年11月10日
コメント(0)
-
ウェブデザイン制作
こっちで活躍するウェブデザイナーとの出財から、ベイエリアでウェブ制作デザインのお仕事を始めました。今週から来週には、最初のお客さんとなる会社へ打ち合わせです。今から、ウェブ制作プロセスのチェック。ビジネスの視点と、シンプルで上品な色使いのデザインスキルを組み合わせて、ウェブサイトデザインに新風を吹き込む野望。まずはベイエリアの日本企業がターゲット!
2003年11月09日
コメント(0)
-
「目的」と「手段」の関係
Date: Sat, 08 Nov 2003 12:45:13 -0800From: Ryusuke Koyama To: Subject: Re: 手段と目的僕の勝手な芸術観で、「すぐれた芸術はすべて、アンビバレントな思いを秘めている」というのがあって、たとえば、生命への賛歌を描く晩年のピカソの筆は、老いによる震えがでてくる。「目的」→「手段」とスムーズに行くと、「ほんまかいな」と思ってしまう。そこに格闘がないのか? その格闘そのものが人生(ライフ)じゃないか、その格闘が含まれない「ライフデザイン」ってなんだ?って思ってしまうのです。僕にとっては、目的を達成するSkill(手段)の習得そのものが、ライフデザインの一部。そういう場合はどうなのでしょう?> 最初に目的ががくる。> > 目的→手段←→目的くらいが適当かなと。そうですね!で、僕はこの目的→手段←→目的 ^^^^^^この部分に、人生の面白さがあるのだと思います。人生を芸術作品にたとえると、ここに作品の面白さがある。ぜひこの面白さを、ライフデザインの要素の一部としたい。> 「宇宙ホテル」が突拍子も無い目的だから、百年かかるから> 論外、ではなく、あくまでもそれはオリジンであって、なにかがはじまる> 原点と考えるべきではないでしょうか。> > それが今回の議論の論点となっている「目的」を考えることではないでしょう> か。「宇宙ホテル」が現実的になってきたという「手段の現実味」がじゃあその「目的」はなに?という問いを生み出す。ここで初めて語りうる「目的」、想像しうる「目的」がある。だから「目的」←→「手段」なんだと感じるんです。
2003年11月08日
コメント(0)
-
今後の会社の発展方向性
デザイナーのJUNと打ち合わせ。今後のビジネスの方向性について話し合う。いくつか現状の仕事の話も進んでいるので、その内容についても話し合う。早速コンタクトを取っていこう。JUNとしては、できるだけリファレンスとなるような仕事を数こなしていくことが重要で、僕にとってもそれは同じ。お金のことはなんとでもなる(というか後からついてくる)ので、とにかく、ここにいる間に実績を残すよう考えてみる。
2003年11月07日
コメント(0)
-
ウェブをみて問い合わせが。。。
最近、ウェブサイトをみて問い合わせてくる人も多いが、今日は社長みずからの問い合わせで、ちょっとびっくりした。Loren Pleetさんは、Abecta Corporationの社長。メールを使ったマーケティングなどを手がけている。日本の中小企業にコンタクトしたいのだと言う。卒業してから、いろいろビジネスについて話そう、と言うことになった。何が起こるかわからないが、面白そうな話。日本企業がアメリカに進出する場合、なによりもましてマーケティングが重要になってくる。
2003年11月06日
コメント(0)
-
ロードスターのデザイナーの考えること
◆GMやBMWにつとめ、最後はマツダのデザイナーとして、ユーノス・ロードスターをデザインされた俣野さんを訪問しました。現在、サンフランシスコにある「Academyof Art College」の産業デザイン部門で教えられているんです。◆俣野さんが強調していたのは、アメリカのデザイナー部門のディレクターはかならずビジネスの知識がある。50%くらいはビジネスバックグラウンドで、残りの半分がデザイナーとしてのバックグラウンドという具合。◆ところが日本の場合、腕のいいデザイナーということでやってきた人がディレクターになる。デザイン100%でビジネス0%。アメリカだと、「どういうものが求められているか」というマーケティングの視点や、費用対効果の点から議論するから、日本のデザイナーはなかなかついていけない。フォードがマツダを買収したあと、のデザイナー同士のやりとりも、レベルの違いを感じる。◆俣野さんは、ビジネスとデザインの両方を教えられる学校にしていきたいと考えているそう。テクノロジーとデザインとビジネスが融合してはじめて、「プロダクトデザイン」となる。◆僕はその「プロダクトデザイン」の部分に、「イノベーション」を置き換えて考えたりする。テクノジーとデザインとビジネスが融合してイノベーションが生まれるのだろう。---夜は、アメリカで日本のアニメ、漫画を紹介する出版社に勤める泉さんに会う。いろんなプロジェクトのことについて話した。彼女は会社とは別に、ベイエリアでの日本の音楽イベント、日本人によるイラストレーションの出版、映画本の出版など、個人的なプロジェクトをいくつも抱えている。すっかり意気投合。家に帰ると、疲れてしまってすぐ眠った。
2003年11月05日
コメント(0)
-
ネットレイティグス・大谷さんと食事
一日、雨が降り続いて肌寒い。ネットレイテリングスの大谷さんと夕食。
2003年11月04日
コメント(0)
-
真弓がきた
サンダーバード国際経営大学院からビジネスカフェへの3人目のインターン、真弓が到着。さっそく夜遅くまで仕事。ずいぶん助かる。
2003年11月03日
コメント(0)
-
「猫の恩返し」「ナウシカ」は売り切れ・・・
今日もバークレーの日本アニメフェスに行こうと思ったんだけどチケットは売り切れ。。。しょうがないので、EbayでDVDを購入したら、「猫の恩返し」以外のジブリ作品が全部そろうボックスセットがたった30ドルで手に入った! すげぇ。夜はバイオ関連の人のところへお邪魔して、お別れパーティを楽しんできました。「はじめまして」がすぐ「さようなら」になってしまい、ちょっとびっくりですが、ちょこっと参加させてもらって楽しんできました。
2003年11月02日
コメント(0)
-
「火の鳥2772」「おもひでぽろぽろ」
◆バークレーで日本アニメの上映会がありました。「おもひでぽろぽろ」というジブリアニメ。日本人にしか(それも特定の年代しか)分からないような内容も含まれてたけど、すごく受けてましたね~! 日本じゃ、ああいう受け方はしてなかった。すごく良質な観客。わざわざ大学内の映画館まで見に来るだけのことはありますね。◆面白かったのは、高橋さんというジブリのプロデューサーによる質疑応答。「どうしてこれを実写じゃなくて、アニメなの? すごくリアリティがあるのに」という質問に、「細かい議論はできないですが、これはアニメじゃないとできないと思います。高畑さん(監督)はつねづね、線で書かれたアニメは実際の役者よりも多くのことを伝えると言っています」と答えたら、観客が驚いていた。まだまだ、アニメの表現力がそれほど認められていない。ピクサーがあれだけがんばっても・・・。◆高橋さん自身も、「見直してみて、いい映画だと思った」と述懐していましたが、僕も同感。小さいころに映画館で見たけど、今回再発見が多かった。何よりも、アニメの質として、絵のタッチという点でも、最高品質である。日本の古い映画(小津など)を見ている感触があった。同時代ではなく、時間を経て理解できるものも多い。◆それに編集に驚き。ものすごく間を重視してるんですね。高橋さんに質問したかったのだけど(いつもはね、質問するんです。でも今回は他のアメリカ人に機会を譲った)、アニメーションが動きを止めて、じっとしてしまうんです。動かさずにとめる。アニメーションが「動き」を意味するのに対して、あれはアンチ・アニメーションというか、あそこに監督のこだわりを垣間見ました。----もうひとつが、「火の鳥2772」。こちらは1980年の作品と、古い。時代を感じさせるアニメ表現だけれども、扱われているテーマにしても、キャラクタの魅力という点でも、手塚漫画が生きている感じがする。同じように手塚キャラクターの出てくる「メトロポリス」という映画は、「火の鳥2772」でのブラックジャックや猿田博士がいない点で、やはり片手落ちかなあ。ああいう、憎まれない悪役が活躍しないと話に深みが出てこない気がする。
2003年11月01日
コメント(0)
-
「コーチングの思考技術」 ダイヤモンド社
コーチングを単に「部下の教育方法」と捉えていては、この本の問題提起は見えてこない。一言で言えば、コーチングは教育方法にとどまらない、創造のためのプロセスである、というのである。本は8章にわかれる。メンター、メジャーリーグ流コーチングなどの話題から、さらにキャリア・デザイン、リーダーシップ・スタイルまで幅広く取り扱われている。このうち、第8章の「エンパワーメントの幻想と矛盾」を取り上げて、この本の主張を取り出してみたい。ハーバード組織行動学の教授によって書かれたこの論文は、実は問題提起だけで「こうすればよい」というような明確な結論は書かれていない。しかしそのことが逆に、この論文を魅力的にしているし、この本の最後にそうした論文をもってきたことに、「コーチングの議論はそう簡単ではない」という主張を見て取ることができる。具体的には、エンパワーメント(権限委譲)をするといいつつ、マネジメントは管理を強め、数値目標の達成を強要する。ここには内部矛盾があるという。従業員の創造性を信じていないCEOと、権限委譲などといいつつ単に仕事を増やそうとしているだけなのだと疑心暗鬼になる従業員。この確執が、さまざまなエンパワーメントのプロジェクトを頓挫させている。ただ、この問題のシンプルな解決方法はない。対話を続けるしかない、という。そもそも、エンパワーメントは何のために行われるのか? 従業員の自主的な創造力の発揮、問題解決能力の発揮にあるはずである。ビジネス環境はどんどんスピードを増しており、以前のようなトップダウンでは対応しきれない今、柔軟に対応できる「現場の力」が大切になってきている。ここにコーチングの本質も見え隠れする。コーチングはなにも、「何かを教え込む」ことではない。コミュニケーションを通じ、お互いの信頼に基づいた、創造性を引き出すプロセス、イノベーションを引き出すプロセスなのである。http://plaza.rakuten.co.jp/aff.phtml?url=http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4478373884/ryu2-22
2003年10月31日
コメント(0)
-
朝日新聞(大阪版)への掲載
ワンコイン翻訳(http://www.translate.jp )の記事が、朝日新聞大阪版に掲載された。さっそくいくつかの注文がマイコンで、さすがにマスコミの力ってすごい、と感心した。今回は、「ワンコインのサービス」というテーマでの記事連載ということで、記者の方が僕のサービスを見つけてきてくれた。ワンコインというキーワードがひっかかったわけ。うまくここから、ビジネスを広げていければと、思案中です。
2003年10月30日
コメント(0)
-
イノベーションを生み出す仕組み
◆季節柄、いろんな会社の人事の人に会うことが多いのですが、必ずしている質問があります。「イノベーションを生み出す仕組みはなんですか?」GEの田中さんは、「文化」だというんです。◆積極的な変化の追求。これはGEの伝統のひとつ。変化を求めないものは、GEの社員ではない、という風潮があるのだとか。改善案を出したときに、否定されない、評価される。いやむしろ、改善案も出せない社員はまじめに働いていないと評価を落としてしまう。◆これはGEの大切にするバリューである。パフォーマンス(能力)は教育で改善できるが、価値観はあとから直るものではない。そういう意味で、文化とは合うか合わないかだ、と。◆「イノベーションを生み出す」のが文化だとすれば、もし一度イノベーションへの精神が会社から失われたら、取り戻すのは難しい。ちょっと絶望的な気分になる。GEの変化を求める文化は、ジャック・ウェルチによって確立されたが、確実なものとなるまでにやはり、相当な時間がかかった。◆もうひとつ面白いことを聞いた。GEのジャック・ウェルチからジェフ・イメルトに変わって、GEの文化に一つ新しい要素が加わった。顧客主義である。「私たちの成功は、お客さまの成功によって測られます」。ジェフ・イメルトが営業畑出身であることから来ている。◆この顧客主義が徹底している。ACFCという仕組みができた。具体的には、GEの社員がお客さんのところへいき、シックスシグマなどの手法によって業務改善を行うというもの。顧客が利益を上げられるようになれば、GEも潤う。このACFCは無料で提供している。◆ACFCとは、at the customer for the customer=お客さまのもとでお客さまのために、という意味の言葉の頭文字をとったもの。その言葉どおり、顧客のもとにGEが入り込む。◆って、GEの宣伝のようになってしまいましたが、要はイノベーションは文化に負うところが大きい。そしてその文化は、トップマネジメントのコミットメントなしではつくられない、ということなんです。
2003年10月29日
コメント(0)
-
細分化、特化したコンサルタント事業
今日は、バイオインフォマティクスのシステム構築に関するコンサルタントと話をした。アメリカだと、なんでもかんでもフォーカス、フォーカスで、コンサルタントも「バイオインフォマティクス」のさらに「システム構築」という落とし込み方をする。これはすごい。そうなるためのバックグラウンドをきちっと持っていることが重要で、だからこそアメリカにおいてレジュメ(履歴書)の意味はとても大きい。彼の場合、バイオ企業のIT部門にいた経歴が、バイオブームの続く今、その分野のコンサルタントとして事業が成立しているのだろう。僕は、じゃあ、どういうキャリアをレジュメに書き込んでいくか。慎重に考えないといけない。
2003年10月28日
コメント(0)
-
GEの説明会
Subject: 先日はありがとうございましたX-Mailer-Plugin: AntiSpam for Becky!2 Ver.1.001MIME-Version: 1.0X-Mailer: Becky! ver. 2.06.02Content-Type: text/plain; charset="ISO-2022-JP"Content-Transfer-Encoding: 7bit先日のサンフランシスコでの説明会に参加させていただいたサンダーバード国際経営大学院の小山龍介です。田中さんの説明をお聞きして、GEは「世界最高の教育機関」という言葉がぴったりくると感じました。芸術分野とビジネスのバックグラウンドが必要なものとして、最近は、「銀行のプロダクトデザイン」というものを考えています。こちらは、スターバックスの併設されたウェルズファーゴがありますが、コーヒーを飲みながら見る銀行は、ちょっと雰囲気が違って見えたんです。ホテルのロビーに近い印象をうけました。銀行のコアコアコンピタンスは、Securityです。上記のホテルへの連想は、Securityという意味で、つながってきます。お客さんを番号札で呼びつける日本の銀行は、こうした「安心」の感覚から程遠いと感じています。どうしたら優れた顧客体験を提供できるか。私のようなバックグラウンドでもGEの新しい「顧客主義」の方針にわずかながらも貢献できると思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
2003年10月27日
コメント(0)
全128件 (128件中 1-50件目)