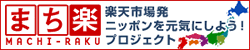カテゴリ: カテゴリ未分類

写真:初狩 唐沢の土石流
こんにちは、資料館です。
『明治40年の大水害』の3回目、いよいよ最終回となります。
水害罹災者の移住先とその後について見ていきましょう。
水害罹災者の移住先とその後について見ていきましょう。
洪水後の復旧を図るに最も必要なるものは、財力其一に居るは説を待たずと雖も、人力の豊富なるも亦其一に居る、我県に於て災後良民を他に移住せしむるの可否に就いては、種々なる説を聞く処ありしも、住むに家なく、耕やすに田畝なき者をして、堵に安んぜしむるには移住を断行するの外なし、茲に於て県は其移住者に相当の補助を与え北海道亦厚き便宜を与ふることゝなりて有志団体の大移住行はれ、翌四十一年四月北海道に着す。
此年団体移住を為したるもの三、一は中巨摩郡の団体にしてワツカタサツプを根拠とし、二は東八代郡の団体にしてペーペーナイに村を樹て、三は東山梨郡の団体にしてヌプリカンベツに部落す、蓋し是等の土地は何れも倶知安市街を距ること二三里の処にして、現今甚だ利便なりとは言ふ能はざるも最も有望の地たるを失はず、而して以上の三団体は各幾何の戸口と土地とを有するやと言ふに、最近の調査に依れば、左の如きものもあり。
<中略>
之によりて見る時は一戸平均約六丁歩の土地を有し、移住以来僅々三年にして既に殆んど全部を成墾地と為したり、作物は馬鈴薯、玉蜀葱、蕎麦、小麦、大麦、燕麦、裸麦、大豆、小豆、蕓苔、牧草等可ならざるはなく、養蚕、牧畜、養鶏の業亦大に適す、然れば即ち是等移住は安んじて其業を楽しみつゝあり、勿論移住の当時にありては一面の草叢なりしを以て二三の人自失したりと雖も、今や却て移住の天地の安楽なるを喜べり四十一年又郡内地方より団体移住ありしが、是等も遠からず好成績を挙げて到る所に殷富なる甲州村を樹立するならん。
『山梨県水害史』 第9章 明治四十年水害史 第13節 北海道移住
水害により住む家はもちろん、山林の崩壊や田畑の流失などで生計を立てるための収入源を失った人々を救済する方策として北海道への移住が提唱されます。
その背景にあった主な理由は次の2点です。
ひとつは、災害によって相対的に余剰人口が増えたために他地区への人口移動が必要になったこと。
ふたつめは、移住先としては、国力を充実させるために北海道の開拓が明治初年より国策としてあったこと。
北海道移住への動きは、あたかも発災前から既定路線であったかのようなスピード感を持って行われました。
山梨日日新聞は水害発災からわずか4日後の8月29日付の紙面で、明治22年の奈良県十津川村の水害罹災民が北海道へ団体移住したことを引き合いにして、山梨県でも同様に団体移住すべきとの論説を掲載します。
翌月早々には武田千代三郎山梨県知事が「移住」の方針を打ち出し、月末には北海道の移住地の調査に着手します。
そして、12月半ばから翌年1月の半ばまで県内の21カ所で移住の説明会が開催されました。
説明会では、移住地が北海道庁の指導を受けて羊蹄山(蝦夷富士)の麓であることや、開拓当初の一ヶ年分の食糧費や家財道具などについて補助が出ることなどが提示されました。
その3か月後の明治41年4月には北海道への移住が行われ、新天地での生活が始まりました。
発災からわずか8か月、1年間の生活が保障されていたとはいえ、行ったことも見たことも無い全く知らない場所への移住を決断しなければならないほどの惨状であったことがわかると思います。
では、郡内地方(南北都留郡)の人々の北海道への移住はどう行われたのでしょう。
【北海道移住】
奮然愛郷の念を断ち、親戚古旧と別れ、祖先墳墓の地を棄つるに至れる笹子村坂上保義外郡下各村の水害罹災民は、明治四十一年四月三十日郡長飯島篤雄郡書記長望月於菟作に引率され、同日午後六時三十三分笹子駅を発車し順次大月、猿橋、鳥沢、上野原各駅にて同志と合しつゝ目的地北海道胆振国虻田郡弁辺村庄瀧別(壮滝別)(此路程 本郡大原村ヨリ青森迄汽車五〇三哩八、青森ヨリ弁辺迄汽船一〇九浬 弁辺ヲ経テ移住地迄四里十八丁)に向かひ進行せり。
『北都留郡誌』第三十五章 變災 第二節 水害 1175p
この文に続いて、引率した飯島郡長、望月郡書記が武田県知事に提出した復命書の抄録が掲載されています。
それには、抄録とはいえ、上述した行程と移住地の割り振りについての詳細が書かれています。
さらに具体的に知りたい方のために次の2書を紹介します。
この2つの論文によると、明治40年4月30日に山梨県を発った北都留郡を中心とした移住者93戸441名は、5月4日に北海道虻田郡弁辺村(現在の豊浦町)ソータクネベツに到着したとあります。
さらに、明治42年、明治44年と移住は続き、3次にわたる北都留郡全体の移住者の戸数・人数は次の通りとなります。
北都留郡 県全体
明治41年 69戸 311人 301戸 1437人
明治42年 66戸 352人 106戸 0524人
明治44年 17戸 081人 253戸 1169人
合計 152戸 744人 660戸 3130人
明治40年、43年の大水害により、被災からの復興が困難なために故郷を離れ、北海道へ移住した人たちは、その後どうなっているのでしょうか。
論者である小畑氏は、移住後の様子について次の様に述べています。
こうして三か年度にわたって、660戸3130名もの人々が、住み慣れた山梨を旅立ち、「蝦夷富士」羊蹄山の麓に新たな「山梨村」を築きはじめた。
ただし、もともと傾斜地かつ寒冷地で雪深く、たびたび冷害や霜害にも見舞われたこともあって移住者たちの再移住が進み、現在でも山梨からの移住者がそのまま定住している例は極めてわずかである。
「山梨県における明治40年の大水害被災者の北海道団体移住」7p
「山梨県における明治40年の大水害被災者の北海道団体移住」7p
移住先でも様々な困難に見舞われ、再移住を余儀なくされるなど、とても成功とは言えない状況だったようです。
※おまけ
大月市旧町村別移住者数
1908年4月30日 1909年3月2日 1911年4月18日 合 計
戸数 人口 戸数 人口 戸数 人口
戸数 人口
笹 子 15 0
66 0
1 00
5 11 49 0
27
120
初 狩 0
7 0
32 0
2 00
8 0
3 16 0
12
0
56
広 里 26 104 23 115 0
1 0
2 0
50
221
賑 岡 0
1 00
4 0
1 00
5 0
0 0
0 00
2
00
9
七 保 0
0 00
0 0
1 00
5 0
0 0
0 00
1
00
5
大 原 0
6 0
28 10 0
60 0
2 14 0
18
102
富 浜 0
2 00
9 0
6 0
33 0
0 0
0 00
8
0
42
梁 川 0
1 00
5 0
2 00
4 0
0 0
0 00
3
00
9
合 計
58
248
46
235
17
81
121
564
『北都留郡誌』北海道移住者調 1181p
明治41年4月の移住者数が小畑氏の論文で引用する資料(若尾資料)と一部一致しません。
その理由は不明です。
明治41年4月の移住者数が小畑氏の論文で引用する資料(若尾資料)と一部一致しません。
その理由は不明です。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.