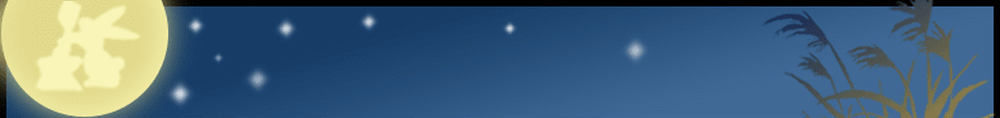PR
X
Freepage List

【フリーページ紹介】

御所名簿

【強烈家族の会】会員名簿

体験談1

体験談2

体験談3

体験談4

体験談5

体験談6

有名人転職提案

意外な相似点

有名人編

中年の主張

家族に言いたい!

考える人

戦争と平和1

多言語の森

兄弟喧嘩英語講座

多言語育児1

多言語育児2

多言語育児3

多言語使いの頭の中

日本語・英語・中国語の敬語感覚の違い

多文化の海

演奏マナー

飛び級と親

飛び級体験談

駐妻局1

駐妻局2

駐妻局3

手結川家流育児

出産編

【異文化の謎】

タライ様・瞑想修行室

英国流おまじない

関西女へ100の質問

Ats短期連載小説(^^;)

The Quest For The Lost Amulets

マルチリンガル夫育て

昭和16年「週刊朝日」平出海軍大佐に聴く

平出海軍大佐に聴く(2)
テーマ: 子供に英語。どうしてますか?(2743)
カテゴリ: 旧(多言語★国ぎわ族)
【多言語育児の悩みと提案1(コミュニケーションの為の第二言語習得方法3)】
ある一定の年齢を過ぎると完璧に習得する事は不可能だとする説だ。
日本では、これを悪用した「英語商売」が盛んな様だ。
「○歳では遅すぎる!」
初めて子を持った親にとって、こんなに焦る言葉は無いだろう。
ましてや、日本には、英語コンプレックスを持つ人が少なくない。
自分がこんなに苦労した英語の習得(あるいは挫折)過程を
我が子には味合わせたくない...
そう思うのは自然な親心だ。
だが、どうも、ネットで聞いたり眺める限りでは
日本の英語商売は、本当に玉石混交で(石の方が多い?)
なかには悪徳としか思えないものもある様だ。
海外在住者の集まるサイトの掲示板では
日本の英語熱に向けて警鐘を発する声が高い。
そして、その海外組の警鐘に対して、
「英語に触れる機会が高い有利な位置にいる人達には理解らない」
という日本在住組の反発もあるのだそうだ。
双方とも、もっともだと思う。
海外に住み子供に苦労しながら日本語を教えている日本人には
自らの体験から「一目瞭然」である事が多い。
バイリンガル環境など多言語環境にある家庭にとっては
第二言語どころか、第一言語の確立でさえ大変なのだ。
日本語ネイティブである日本人親が一緒に生活しながら教えていても
日本から離れて暮らす子の日本語は、維持するだけでも一苦労なのだ。
悪条件である事の方が多い。
それが、悪徳商売の大胆な宣伝文句の様に
「ちょっとやそっと英語の幼稚園や塾に通って
ネイティブ並みになるはずがないだろっ
(そもそも、幼児のネイティブ並みって....??!!)」
「英語ができない親がネイティブ並みの英語力を持つ子を
家庭で育てられるはずがないだろっ」
「どんな高額でも学習教材中心でネイティブ並みになるはずがないだろっ」
「そんな事より、肝心の日本語はどうするんだよっ」
.....等々、自分自身の普段の苦労も重なって、つい
「目を覚ませよ~っっっ」的発言となってしまいがちだ。
だが、日本で精一杯、英語を、と頑張っている親には
その発言は「おせっかい」「上から見下げた意見」と聞こえるるのではないか?
そもそも幼児に英語学習・英語育児を実行している親は親で
やはり玉石混交(...と人を評するのは失礼なので言い替えると)
各人各様の事情があるのに、海外からくる批判は
時として「全ての日本で子供に英語早期教育をしている親」に
向けて一般論として発されがちな印象を与える。
これでは、「海外で日本語」と同様の真剣さと知識を持ちながら
「日本で英語」と努力・試行錯誤している親は
苦い気持にならざるを得ないだろう。
しかし、駐在員家庭や帰国子女や国際結婚家庭は
内情を知らない第三者から
自分達の置かれている(いた)環境を
気軽に見当違いに「うらやましがられ・ねたまれ」たり、
苦労と努力の成果を自然の成り行きの如く軽視される事が少なくない。
特に、学校や家庭で常に現実と直面し、
時には親からの理解も得られず
何とかがんばる以外には選択肢も与えられない子供達にとって
「外国に住んでいたから・親が外国人だから」
外国語が喋れると、うらやましがられたり、ねたまれたりするのは
怒り・我慢・絶望(・その他もろもろ)の限界への挑戦かもしれない。
もっとも、よく理解っていない人から「大変ね~」と妙に同情されるのも
また迷惑なんじゃないかと思うが....。
だから、多言語環境の波にもまれながら生きて来た
という意識が強ければ強いほど
「必要性が無いにも拘わらず」多言語教育を選んだ家庭に対し
複雑な心境が生まれるのは無理も無い。
真面目に多言語教育に取り組む家庭はともかく
脳天気に悪徳英語商売の宣伝文句を信じている親を見たら
思いっきりカツを入れたくなるだろう。
悪いのは、悪徳商売人で無邪気な親じゃないとわかっていても..だ。
だが、反目し合う可能性があるのは
「海外組」と「日本組」の組み合わせだけではない。
海外組には海外組なりに「派閥」ではないが
それぞれの事情によって、自他ともに細かく分類され
他グループに対し、時には、排他的な感情を持つこともある。
例えば、日本語補習校。
これは、基本的に、海外駐在員家庭の子供が
日本人学校以外の学校(現地校=その国の学校や国際学校)に通う場合、
日本に帰国した際、日本の学校へついて行けるように
土曜日に、日本の学校に即したやりかたで国語を教える学校だ。
国によっては、算数や理科まで教える学校も少なくないようだ。
そして、時々、海外在住者の参加が多いネット掲示板で、話題にのぼるのが、
この補習校での「駐在組」と「永住組」の静かな対立だ。
(実際には、たとえ表面的だけでも、仲良くやっているんじゃないかと思うが....)
どうも、自分達で選んだわけでもないのに命令で
就学児童をかかえながら外国に駐在させられ
その期間さえ定かではない事が多く、帰国したら帰国したで、
金銭的余裕があり他の道を選べる家庭以外は
確実に日本の受験戦争に巻き込まれる....
そんな駐在員家庭にとって
「日本へ帰国する予定も無いのに」
「日本語が得意でない子供を無理に補習校に入れて」
「補習校のレベルを下げる」永住組、
特に国際結婚家庭は、疎ましい存在らしい。
(この傾向は、中学受験を控えた小学生を抱える家庭に強いようだ。)
手結川家の子供達は、週末中国語学校に通っているので
ロンドンの補習校とは縁が無く、友人から小耳に挟んだ情報しかないが
ここでは、確か数年前、補習校の本校(?)とは別に「国際部」が設けられた。
(↑現在も存続しているかどうか詳細不明。)
日本語を、読み書き以前に、まず満足に話す事どころか
少数だが理解する事さえできない子供達には
本人にあった教え方で日本語を習得させるべきだ
という考えで生まれたのだと思うが、その設立には
将来の帰国に備えて真剣に勉強せざるをえない子供達の邪魔をしないでくれ、
とい隠れた本音がありそうだ。
しかし、もともと、子供を補習校に通わせる国際結婚家庭にとっては
日本語を母国語とする日本人の子から刺激を受けさせたり
子供達どうし日本語を使える環境を与えるのが目的でもあるため
日本語のできない(あるいは達者でない)子供達が集まる国際部は
いまひとつ人気が無かったらしい。
また、現実的に、補習校へ通わそうとする国際結婚家庭の子供が
日本語を理解できないくらい日本語初心者であることは少なく
幼稚園・小学校入学レベルでは、まだ、なんとか
日本人家庭の子についていくことが可能だという印象を与えることも
その理由のひとつだろう。
もちろん、以上に挙げた例とは異なり
異なる言語環境にある家庭が情報交換する集まりも、たくさんあるのだが
(その方が多い、と思いたいが)
異なる言語環境にある家庭間での交流が少なかったり、
利害関係が複雑に絡んでくると
お互い排他的・反目的な印象を抱くこともあるのではないだろうか。
だが、海外での日本語教育・育児、
日本での早期外国語教育・外国語育児にせよ
出発点が「親心」であるところ
習得させたい言語に子供が触れる時間も体験も限られているところ
など、共通点はたくさんあるのだから
お互いの意見を交換する事は大変良い刺激になるはずだ。
同じ環境にある家庭の体験談の方が、より具体的で
即効的に役立ったり、励みになるのは事実だと思うが
異なる環境にある家庭の体験も、実は、非常に参考になる。
うらやましいと思ったり、お気楽と思ったりした他グループにも
そのグループ独自の悩みがある事に気づくだけでも大きな収穫だ。
☆☆☆
さて、ここからは、まず、多言語育児について
個人的体験から生まれた提案を書かせていただこうと思います。
(↑つまり、専門的な意見では、無いという事です。^^;)
ちなみに、ここで、「多言語育児」と総称するのは
バイリンガル育児・バイリンガル教育・早期外国語教育など....
幼児・小学生を対象にした、
学校教育ではない、家庭や塾中心の育児や教育のことです。
☆☆☆
多言語育児を考えている人に、まず、提案したいのは
「臨界期論(○歳までにやらないと習得できない)」に、惑わされない事と
子供の人格を尊重するという事だ。
母国語以外の言葉を導入するのは何歳でも構わないと思う。
生まれてから、すぐに始める方が反抗期に入ってから始めるより楽だろうが
何歳だから手遅れという事は無い。
逆に、国際結婚などで海外に住み、子供に日本語を教えたいと思っている人は
赤ちゃんがおなかにいる時から(特に妊娠後期)
日本語で話しかけたり、日本語で本を朗読したり
意識的に日本語で話す機会を多く設けると良い。
臨月の胎児は、母の声、母の言葉を聞き
生まれた時点で、母の声だけでなく、母の体内で聞いていた母の言葉
(語感・リズム感など)つまり母国語を認識して反応するそうだ。
もっとも、胎児時代話しかけていなければ駄目、というわけでは全く無い。
多言語育児は何歳からでもできる。
ただ単に、子供の年齢が大きくなればなるほど
より多くの工夫と努力が必要になるだけだ。
だが、この外国語の導入で注意が必要なのは、
母国語以外の言葉を導入する場合だ。
親が、語感・発音を完全に把握していない言語を
「無闇に」乳幼児に話しかけるのは、やめた方がいい。
周囲にその言語の話者がいない場合は特に要注意だ。
親にとっての外国語を導入する場合は
子供が、「いつも使っている・聞いている言葉とは違う言葉だな」と
意識できるような「特別な時間や状況」を作って
耳だけでなく、体全体で、その言葉に触れられるようにしたら良いと思う。
英語の導入に関しては、私のお勧めは「Nursery Rhymes」だ。
「Nursery Rhymes」とは、韻をふんだ児童詩(詞)のことで
民間伝承も創作もある。
日本ではマザーグースが有名だ。
児童詩といっても、古い「Nursery Rhymes」には、
歴史的背景の濃いかなり残酷な内容の歌もあるが
ここでは、深く意味を考える必要は無い。
これは、まず、韻を楽しむものだ。
この韻が身についていると、英語のリズム感だけではなく
将来、スペルを学習する時にも役に立つ。
この「Nursery Rhymes」が朗読されたCDを
子供を抱っこし、韻に合わせて体を動かしながら聴いたり
時には、声を出して部分的に繰り返したりしては、どうだろう。
「Nursery Rhymes」には手遊びが入っている事もあるので
DVDやビデオで楽しむのも一案だ。
小学生や幼稚園児が先生と一緒に
「Nursery Rhymes」を朗読したり歌ったり遊んでいるようなDVDも
英国では、たくさん出版されている。
日本でも、同様のDVDやビデオは製作・発売されていると思う。
DVDやビデオでの場合も、やはり、子供一人で見るのではなく、
親が一緒に体を動かし、ところどころで反応・反復しながら楽しむのが重要だ。
英国の児童教育に関する本でも
「Nursery Rhymes」は「読み書きの基礎」となる、と強調されていた。
小さい時に覚えておけば将来的に非常に役立つと思う。
(続き)
ある一定の年齢を過ぎると完璧に習得する事は不可能だとする説だ。
日本では、これを悪用した「英語商売」が盛んな様だ。
「○歳では遅すぎる!」
初めて子を持った親にとって、こんなに焦る言葉は無いだろう。
ましてや、日本には、英語コンプレックスを持つ人が少なくない。
自分がこんなに苦労した英語の習得(あるいは挫折)過程を
我が子には味合わせたくない...
そう思うのは自然な親心だ。
だが、どうも、ネットで聞いたり眺める限りでは
日本の英語商売は、本当に玉石混交で(石の方が多い?)
なかには悪徳としか思えないものもある様だ。
海外在住者の集まるサイトの掲示板では
日本の英語熱に向けて警鐘を発する声が高い。
そして、その海外組の警鐘に対して、
「英語に触れる機会が高い有利な位置にいる人達には理解らない」
という日本在住組の反発もあるのだそうだ。
双方とも、もっともだと思う。
海外に住み子供に苦労しながら日本語を教えている日本人には
自らの体験から「一目瞭然」である事が多い。
バイリンガル環境など多言語環境にある家庭にとっては
第二言語どころか、第一言語の確立でさえ大変なのだ。
日本語ネイティブである日本人親が一緒に生活しながら教えていても
日本から離れて暮らす子の日本語は、維持するだけでも一苦労なのだ。
悪条件である事の方が多い。
それが、悪徳商売の大胆な宣伝文句の様に
「ちょっとやそっと英語の幼稚園や塾に通って
ネイティブ並みになるはずがないだろっ
(そもそも、幼児のネイティブ並みって....??!!)」
「英語ができない親がネイティブ並みの英語力を持つ子を
家庭で育てられるはずがないだろっ」
「どんな高額でも学習教材中心でネイティブ並みになるはずがないだろっ」
「そんな事より、肝心の日本語はどうするんだよっ」
.....等々、自分自身の普段の苦労も重なって、つい
「目を覚ませよ~っっっ」的発言となってしまいがちだ。
だが、日本で精一杯、英語を、と頑張っている親には
その発言は「おせっかい」「上から見下げた意見」と聞こえるるのではないか?
そもそも幼児に英語学習・英語育児を実行している親は親で
やはり玉石混交(...と人を評するのは失礼なので言い替えると)
各人各様の事情があるのに、海外からくる批判は
時として「全ての日本で子供に英語早期教育をしている親」に
向けて一般論として発されがちな印象を与える。
これでは、「海外で日本語」と同様の真剣さと知識を持ちながら
「日本で英語」と努力・試行錯誤している親は
苦い気持にならざるを得ないだろう。
しかし、駐在員家庭や帰国子女や国際結婚家庭は
内情を知らない第三者から
自分達の置かれている(いた)環境を
気軽に見当違いに「うらやましがられ・ねたまれ」たり、
苦労と努力の成果を自然の成り行きの如く軽視される事が少なくない。
特に、学校や家庭で常に現実と直面し、
時には親からの理解も得られず
何とかがんばる以外には選択肢も与えられない子供達にとって
「外国に住んでいたから・親が外国人だから」
外国語が喋れると、うらやましがられたり、ねたまれたりするのは
怒り・我慢・絶望(・その他もろもろ)の限界への挑戦かもしれない。
もっとも、よく理解っていない人から「大変ね~」と妙に同情されるのも
また迷惑なんじゃないかと思うが....。
だから、多言語環境の波にもまれながら生きて来た
という意識が強ければ強いほど
「必要性が無いにも拘わらず」多言語教育を選んだ家庭に対し
複雑な心境が生まれるのは無理も無い。
真面目に多言語教育に取り組む家庭はともかく
脳天気に悪徳英語商売の宣伝文句を信じている親を見たら
思いっきりカツを入れたくなるだろう。
悪いのは、悪徳商売人で無邪気な親じゃないとわかっていても..だ。
だが、反目し合う可能性があるのは
「海外組」と「日本組」の組み合わせだけではない。
海外組には海外組なりに「派閥」ではないが
それぞれの事情によって、自他ともに細かく分類され
他グループに対し、時には、排他的な感情を持つこともある。
例えば、日本語補習校。
これは、基本的に、海外駐在員家庭の子供が
日本人学校以外の学校(現地校=その国の学校や国際学校)に通う場合、
日本に帰国した際、日本の学校へついて行けるように
土曜日に、日本の学校に即したやりかたで国語を教える学校だ。
国によっては、算数や理科まで教える学校も少なくないようだ。
そして、時々、海外在住者の参加が多いネット掲示板で、話題にのぼるのが、
この補習校での「駐在組」と「永住組」の静かな対立だ。
(実際には、たとえ表面的だけでも、仲良くやっているんじゃないかと思うが....)
どうも、自分達で選んだわけでもないのに命令で
就学児童をかかえながら外国に駐在させられ
その期間さえ定かではない事が多く、帰国したら帰国したで、
金銭的余裕があり他の道を選べる家庭以外は
確実に日本の受験戦争に巻き込まれる....
そんな駐在員家庭にとって
「日本へ帰国する予定も無いのに」
「日本語が得意でない子供を無理に補習校に入れて」
「補習校のレベルを下げる」永住組、
特に国際結婚家庭は、疎ましい存在らしい。
(この傾向は、中学受験を控えた小学生を抱える家庭に強いようだ。)
手結川家の子供達は、週末中国語学校に通っているので
ロンドンの補習校とは縁が無く、友人から小耳に挟んだ情報しかないが
ここでは、確か数年前、補習校の本校(?)とは別に「国際部」が設けられた。
(↑現在も存続しているかどうか詳細不明。)
日本語を、読み書き以前に、まず満足に話す事どころか
少数だが理解する事さえできない子供達には
本人にあった教え方で日本語を習得させるべきだ
という考えで生まれたのだと思うが、その設立には
将来の帰国に備えて真剣に勉強せざるをえない子供達の邪魔をしないでくれ、
とい隠れた本音がありそうだ。
しかし、もともと、子供を補習校に通わせる国際結婚家庭にとっては
日本語を母国語とする日本人の子から刺激を受けさせたり
子供達どうし日本語を使える環境を与えるのが目的でもあるため
日本語のできない(あるいは達者でない)子供達が集まる国際部は
いまひとつ人気が無かったらしい。
また、現実的に、補習校へ通わそうとする国際結婚家庭の子供が
日本語を理解できないくらい日本語初心者であることは少なく
幼稚園・小学校入学レベルでは、まだ、なんとか
日本人家庭の子についていくことが可能だという印象を与えることも
その理由のひとつだろう。
もちろん、以上に挙げた例とは異なり
異なる言語環境にある家庭が情報交換する集まりも、たくさんあるのだが
(その方が多い、と思いたいが)
異なる言語環境にある家庭間での交流が少なかったり、
利害関係が複雑に絡んでくると
お互い排他的・反目的な印象を抱くこともあるのではないだろうか。
だが、海外での日本語教育・育児、
日本での早期外国語教育・外国語育児にせよ
出発点が「親心」であるところ
習得させたい言語に子供が触れる時間も体験も限られているところ
など、共通点はたくさんあるのだから
お互いの意見を交換する事は大変良い刺激になるはずだ。
同じ環境にある家庭の体験談の方が、より具体的で
即効的に役立ったり、励みになるのは事実だと思うが
異なる環境にある家庭の体験も、実は、非常に参考になる。
うらやましいと思ったり、お気楽と思ったりした他グループにも
そのグループ独自の悩みがある事に気づくだけでも大きな収穫だ。
☆☆☆
さて、ここからは、まず、多言語育児について
個人的体験から生まれた提案を書かせていただこうと思います。
(↑つまり、専門的な意見では、無いという事です。^^;)
ちなみに、ここで、「多言語育児」と総称するのは
バイリンガル育児・バイリンガル教育・早期外国語教育など....
幼児・小学生を対象にした、
学校教育ではない、家庭や塾中心の育児や教育のことです。
☆☆☆
多言語育児を考えている人に、まず、提案したいのは
「臨界期論(○歳までにやらないと習得できない)」に、惑わされない事と
子供の人格を尊重するという事だ。
母国語以外の言葉を導入するのは何歳でも構わないと思う。
生まれてから、すぐに始める方が反抗期に入ってから始めるより楽だろうが
何歳だから手遅れという事は無い。
逆に、国際結婚などで海外に住み、子供に日本語を教えたいと思っている人は
赤ちゃんがおなかにいる時から(特に妊娠後期)
日本語で話しかけたり、日本語で本を朗読したり
意識的に日本語で話す機会を多く設けると良い。
臨月の胎児は、母の声、母の言葉を聞き
生まれた時点で、母の声だけでなく、母の体内で聞いていた母の言葉
(語感・リズム感など)つまり母国語を認識して反応するそうだ。
もっとも、胎児時代話しかけていなければ駄目、というわけでは全く無い。
多言語育児は何歳からでもできる。
ただ単に、子供の年齢が大きくなればなるほど
より多くの工夫と努力が必要になるだけだ。
だが、この外国語の導入で注意が必要なのは、
母国語以外の言葉を導入する場合だ。
親が、語感・発音を完全に把握していない言語を
「無闇に」乳幼児に話しかけるのは、やめた方がいい。
周囲にその言語の話者がいない場合は特に要注意だ。
親にとっての外国語を導入する場合は
子供が、「いつも使っている・聞いている言葉とは違う言葉だな」と
意識できるような「特別な時間や状況」を作って
耳だけでなく、体全体で、その言葉に触れられるようにしたら良いと思う。
英語の導入に関しては、私のお勧めは「Nursery Rhymes」だ。
「Nursery Rhymes」とは、韻をふんだ児童詩(詞)のことで
民間伝承も創作もある。
日本ではマザーグースが有名だ。
児童詩といっても、古い「Nursery Rhymes」には、
歴史的背景の濃いかなり残酷な内容の歌もあるが
ここでは、深く意味を考える必要は無い。
これは、まず、韻を楽しむものだ。
この韻が身についていると、英語のリズム感だけではなく
将来、スペルを学習する時にも役に立つ。
この「Nursery Rhymes」が朗読されたCDを
子供を抱っこし、韻に合わせて体を動かしながら聴いたり
時には、声を出して部分的に繰り返したりしては、どうだろう。
「Nursery Rhymes」には手遊びが入っている事もあるので
DVDやビデオで楽しむのも一案だ。
小学生や幼稚園児が先生と一緒に
「Nursery Rhymes」を朗読したり歌ったり遊んでいるようなDVDも
英国では、たくさん出版されている。
日本でも、同様のDVDやビデオは製作・発売されていると思う。
DVDやビデオでの場合も、やはり、子供一人で見るのではなく、
親が一緒に体を動かし、ところどころで反応・反復しながら楽しむのが重要だ。
英国の児童教育に関する本でも
「Nursery Rhymes」は「読み書きの基礎」となる、と強調されていた。
小さい時に覚えておけば将来的に非常に役立つと思う。
(続き)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[旧(多言語★国ぎわ族)] カテゴリの最新記事
-
欧州を日本の県に例えると May 19, 2008 コメント(1)
-
日本の英文に悔し涙 March 16, 2008
-
多言語家庭教育我が家の実態1 March 12, 2008
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.