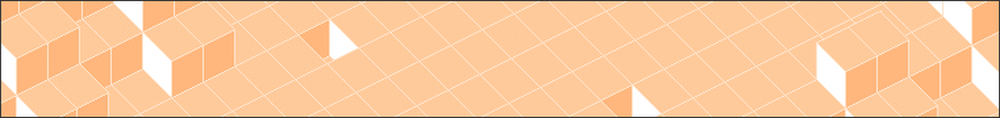PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
カテゴリ: カテゴリ未分類
快晴
眠いボォ~(  ̄‐ ̄)゚*。゚
いいともテレフォンショッキング桜塚やっくん ノ。★・:祝:♪+゚・,。・:
その後のコーナーにも飛び入り??参加(^_^)v 最後まで,,
ライオンキング8周年
(\mmmm/)
m´・ ・`m
m( =●= )m
mm ⌒ mm
*エルメスは、フランスの会社、エルメス社が展開するファッションブランド、商標名のこと。エルメス社は馬具工房として創業したが、自動車の発展による馬車の衰退を予見し、鞄や財布などの皮革製品に事業の軸足を移して成功した。
現在でも、馬具工房に由来するデュックとタイガーがロゴに描かれている。デュックは四輪馬車で、タイガーは従者のこと。主人が描かれていないのは「エルメスは最高の品質の馬車を用意しますが、それを御すのはお客様ご自身です」という意味が込められているため。
歴史
エルメス社の母体になったのは、ティエリ・エルメス(1801年~1878年)が1837年に開いた馬具工房である。ナポレオン3世やロシア皇帝などを顧客として発展した。
ティエリの孫にあたる3代目のエミール・モーリス・エルメス(1871年~1951年)は事業の多角化に着手した。1890年代には、馬具製作の技術を基にエルメス最初のバッグサック・オータクロアを製作。1927年に時計を発表。さらに服飾品・装飾品・香水などの分野にも手を広げ、それらの製品のデザイン、製造、販売をすべて手がける会社になった。
特に馬蹄柄のスカーフとケリーバッグで人気を獲得していった。ケリーバッグは1935年に発売されていたが、当初は「サック・ア・クロア」と呼ばれていた。後に女優のグレース・ケリーが愛用、特にカロリーヌ皇女を懐妊し、写真を撮影された時とっさにお腹を隠したのがこのバッグであったことから有名となり、1955年に正式に改名された。「サック・ア・クロア」=ケリーバッグは本来、サドルバッグ(鞍に付けるバッグ)を婦人用に改良した物である。
ケリーと同様の人気を誇るバーキンの名も、当時のエルメス社社長であったジャン・ルイ・デュマ・エルメスが飛行機の中でたまたまイギリス出身の女性歌手ジェーン・バーキン(当時の夫はセルジュ・ゲンスブール)と隣合わせになり、彼女がボロボロの籐のカゴに何でも詰め込んでいるのを見て、整理せずに何でも入れられるバッグを作らせて欲しいと申し出たエピソードに由来する(なおバーキンの原型はオータクロアであるが、いまやオータクロアをはるかにしのぐ人気である)。
このように、エルメスのバッグには発注者ないし最初の所有者の名が付いたモデルが多く存在する。比較的時代が新しいものでは、スーパーモデルのエル・マクファーソンが発注したエル(巾着型で、底の部分に化粧品を入れるための外から開閉可能な引きだしが付いている)、日本人男性が発注した大型旅行鞄マレット・タナカがある。
日本では女性の支持率が高いが、バッグなどでは男性からの支持も高く人気も絶大であり特にフールトゥやエールラインは価格も手ごろな為に定番バッグとして活躍している。
またエルメス社が初めて作った社史は 漫画形式で、日本の漫画家竹宮恵子(中央公論社 (1997/04) )に依頼して制作した。
2004年、マルタン・マルジェラの後継として、ジャン=ポール・ゴルチエがデザイナーに就任。2004年パリ・コレクションではエルメスの伝統である馬具・皮革製品を意識し、伝統に配慮しつつ、オレンジ・黒を中心とした鋭角的でかつブランドの風格を意識したデザインを発表した。
本来の意味は、リンゴ酒(仏:シードル cidre 、英:サイダー cider )のこと。リンゴの果汁を発酵して作られた酒で、6%前後のアルコールを含む。
近年は飲料の多様化、茶など無糖飲料の人気が高まっていることからサイダーの飲料全体に占めるシェアは低下傾向にある。その一方で、画一化した大手メーカーの味に飽き足らなくなった消費者が地方に残った小規模メーカーのサイダーを見直し始めている。これらは「地サイダー」と呼ばれている。
*自転車(じてんしゃ)とは、狭義では、二つの車輪がついている、自走できる動力源が付いてない乗り物をさし、広義には車輪の数に関わらず、人力を主たる動力源として車輪に伝えて移動するものをさす。
自動車などと比較して、移動距離あたりに必要とするエネルギーが少ない、排気ガスを発生しないなど、地球温暖化問題が叫ばれる現在、クリーンな移動手段として見直されている。
自転車の歴史
1860年にはフランスでミショー型が発明された。これは現在の三輪車と同じようにペダルを前輪に直接取り付けたものであった。オリバー兄弟がピエール・ラルマンの発明に商機を感じ取り、ピエール・ミショーと組んで製造販売を始めたもの。(ベロシペードも参照。英国ではボーンシェイカー、日本では「がたくり」ともよばれた。)
英国のジェームズ・スターレーが1870年頃に、スピードを出すために前輪を巨大化させたペニー・ファージング型自転車を発明。スピードが出、デザインも洗練され、スポーツ好きの紳士の間で好評を博する。この当時は自転車レースが盛んであり、スピードを追求するために、ペニー・ファージング型自転車の前輪はどんどん拡大し、大きなものでは直径が1mを越えるようになった。日本にも輸出され「だるま車」と呼ばれた。これはレース用には人気があったが通常用としては乗車が困難であり、安定性が悪く転倒すれば頭から落ちるようなものであった。気軽に乗れるようなものではなかったが、このタイプで長距離のクロスカントリーライドまでおこなわれたことから、スポーツ用としてはかなりの力を秘めていた仕様だった。
1879年 ローソンによる後輪チェーン駆動車の発明がなされ、1884年、ハンバー、マッカモン、BSAなどがチェーンで後輪を駆動しより低く長い格好となった自転車の販売をはじめる。ジェームズ・スターレーの甥ジョン・ケンプ・スターレーが1885年にローバー安全自転車(Rover Safety Bicycle)として販売を開始。これは車体の中心付近にペダルとクランクを設け、後車輪とチェーンで連結することで動力を伝える現在の形であり、危険なペニー・ファージング型に対してセーフティ型(安全型)と名前をつけて販売された。この時点でペニー・ファージング型はオーディナリー型(普通型、従来型)と呼ばれセーフティの先進性を引き立たせるような名称とされた。このローバー安全自転車が現在の自転車の原型とされている。(*自転車博物館サイクルセンター シマノによる運営)
その後、セーフティ型にフリーホイールやダンロップが発明した空気入りタイヤが装着され、現在の自転車がほぼ完成された。
高度成長期には日本の自転車輸出量は世界一となり、世界中で日本製の自転車が乗られていた。現在では円が強くなったことで自転車の輸出は激減し、中国製を主とした外国製自転車が日本の市場に多数出まわっている。2005年現在、自転車の輸出量は中国が世界一である。
*うどん(饂飩)とは、日本旧来の麺類のうち、小麦粉を原料とし、ある程度の太さ、幅を持った麺を指す。
うどんのルーツ
古くは「うんどん」と発音された。中世に中国から伝来したと言われる。
延喜式には唐菓子の一種として紹介されるが、これは現在のうどんとはかけ離れた、餡入りの団子、すなわち「ワンタン」である。
現在のうどんは、その昔、切麦(きりむぎ)と呼ばれ、うどんと呼ばれるようになったのは江戸時代に入ってからである。切麦には暖かくして食べる温麦と冷やして食べる冷麦があり、総じてうどんと呼ばれた。
後に、日本農林規格等により、冷麦とうどんが明確に区別されるに至った。
麺による分類
麺の形
一本うどん - 切らず、引き伸ばさず、押して作る
太うどん
細うどん
ひもかわうどん
薄く、幅広(10~30mm程度)の麺。同類でローカライズされたものに、きしめん(愛知県)、ほうとう(山梨県)、おっきりこみ(群馬県・埼玉県)、だんご(大分県など)などがある。
*おにぎり(御握り)とは、ご飯を三角形、俵形、球状などに握り作った食べ物のことである。
握り飯ともおむすび(御結び)とも呼ばれる。広島市を中心とする地方ではむすびと呼ぶ傾向にあるが、無論おにぎりでも通じる。握りまま(青森県)、おにんこ(栃木県)といった方言もある。おむすびというのは、もとは御所の女房言葉であった。日本でおにぎりと言えば三角に握ったものというイメージが強く、「おにぎり型」というように三角形をした物のことを指す代名詞としてよく例えられる。
近年、日本の大手コンビニエンスストアが海外進出をすると同時に、世界中で日本のおにぎりが食べられるようになってきた。
日本での歴史
弥生時代後期の遺蹟であるチャノバタケ遺蹟(石川県鹿西町、現・中能登町)から、1987年12月におにぎりと思われる米粒の塊が炭化したものが出土している。この炭化米からは、人間の指によって握られた痕跡が残されている。また、北金目塚越遺蹟(神奈川県平塚市)からもおにぎり状に固まった炭化米が発見されている。
おにぎりの直接の起源は、平安時代の「頓食(とんじき)」という食べ物だと考えられている。この頃のおにぎりは楕円形をしていて、かなり大型(1合半)で、使われているのは蒸したもち米であった。
鎌倉時代の末期ごろからはうるち米が使われるようになった。おにぎりといえば海苔だが、板海苔が「浅草海苔」などの名で一般にも普及したのは元禄のころよりで、栄養もあり、手にごはんがくっつかない便利さもあいまっておにぎりと海苔の関係ができた。
天むす(てんむす)は、塩味を効かせた海老の天ぷらを具にしたおにぎり。名古屋(中京圏)の名物として知られる。 名古屋めしのひとつ。
1957年頃に、三重県津市大門にある天ぷら定食店「千寿」の賄い料理として考案されたのが発祥であるとされている。 「千寿」の持つ登録商標は第3199878号、「めいふつ天むす」と登録されている。 天むす関連の商標は、2006年11月現在、これ以外にも2件登録されている。 「千寿」のパンフレットによれば、昭和30年代の初め、初代水谷ヨネが忙しくて昼食を作る暇もないので、夫のために車えびの天ぷらを切っておむすびの中に入れたのが始まりだという。 現在の「千寿」は天むす専門店となっている。
一般には、名古屋市中区大須の惣菜店「天むす」が有名である。名古屋の「天むす」は「千寿」からのれんわけされたようである。
一口サイズで非常に食べやすく、冷めてもおいしいため、テイクアウトとしても人気がある。
付け合せは、沢庵漬け等の漬物ではなく、きゃらぶきである場合が多い。発案者が沢庵漬けが嫌いだったからとされる。
現在、主に天むすに使われる海老はあかしゃえびと呼ばれる海老である。夏が旬の体長12センチほどのエビであり、天むすのほかに海老せんべいの材料としても使われる。
ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~
眠いボォ~(  ̄‐ ̄)゚*。゚
いいともテレフォンショッキング桜塚やっくん ノ。★・:祝:♪+゚・,。・:
その後のコーナーにも飛び入り??参加(^_^)v 最後まで,,
ライオンキング8周年
(\mmmm/)
m´・ ・`m
m( =●= )m
mm ⌒ mm
*エルメスは、フランスの会社、エルメス社が展開するファッションブランド、商標名のこと。エルメス社は馬具工房として創業したが、自動車の発展による馬車の衰退を予見し、鞄や財布などの皮革製品に事業の軸足を移して成功した。
現在でも、馬具工房に由来するデュックとタイガーがロゴに描かれている。デュックは四輪馬車で、タイガーは従者のこと。主人が描かれていないのは「エルメスは最高の品質の馬車を用意しますが、それを御すのはお客様ご自身です」という意味が込められているため。
歴史
エルメス社の母体になったのは、ティエリ・エルメス(1801年~1878年)が1837年に開いた馬具工房である。ナポレオン3世やロシア皇帝などを顧客として発展した。
ティエリの孫にあたる3代目のエミール・モーリス・エルメス(1871年~1951年)は事業の多角化に着手した。1890年代には、馬具製作の技術を基にエルメス最初のバッグサック・オータクロアを製作。1927年に時計を発表。さらに服飾品・装飾品・香水などの分野にも手を広げ、それらの製品のデザイン、製造、販売をすべて手がける会社になった。
特に馬蹄柄のスカーフとケリーバッグで人気を獲得していった。ケリーバッグは1935年に発売されていたが、当初は「サック・ア・クロア」と呼ばれていた。後に女優のグレース・ケリーが愛用、特にカロリーヌ皇女を懐妊し、写真を撮影された時とっさにお腹を隠したのがこのバッグであったことから有名となり、1955年に正式に改名された。「サック・ア・クロア」=ケリーバッグは本来、サドルバッグ(鞍に付けるバッグ)を婦人用に改良した物である。
ケリーと同様の人気を誇るバーキンの名も、当時のエルメス社社長であったジャン・ルイ・デュマ・エルメスが飛行機の中でたまたまイギリス出身の女性歌手ジェーン・バーキン(当時の夫はセルジュ・ゲンスブール)と隣合わせになり、彼女がボロボロの籐のカゴに何でも詰め込んでいるのを見て、整理せずに何でも入れられるバッグを作らせて欲しいと申し出たエピソードに由来する(なおバーキンの原型はオータクロアであるが、いまやオータクロアをはるかにしのぐ人気である)。
このように、エルメスのバッグには発注者ないし最初の所有者の名が付いたモデルが多く存在する。比較的時代が新しいものでは、スーパーモデルのエル・マクファーソンが発注したエル(巾着型で、底の部分に化粧品を入れるための外から開閉可能な引きだしが付いている)、日本人男性が発注した大型旅行鞄マレット・タナカがある。
日本では女性の支持率が高いが、バッグなどでは男性からの支持も高く人気も絶大であり特にフールトゥやエールラインは価格も手ごろな為に定番バッグとして活躍している。
またエルメス社が初めて作った社史は 漫画形式で、日本の漫画家竹宮恵子(中央公論社 (1997/04) )に依頼して制作した。
2004年、マルタン・マルジェラの後継として、ジャン=ポール・ゴルチエがデザイナーに就任。2004年パリ・コレクションではエルメスの伝統である馬具・皮革製品を意識し、伝統に配慮しつつ、オレンジ・黒を中心とした鋭角的でかつブランドの風格を意識したデザインを発表した。
本来の意味は、リンゴ酒(仏:シードル cidre 、英:サイダー cider )のこと。リンゴの果汁を発酵して作られた酒で、6%前後のアルコールを含む。
近年は飲料の多様化、茶など無糖飲料の人気が高まっていることからサイダーの飲料全体に占めるシェアは低下傾向にある。その一方で、画一化した大手メーカーの味に飽き足らなくなった消費者が地方に残った小規模メーカーのサイダーを見直し始めている。これらは「地サイダー」と呼ばれている。
*自転車(じてんしゃ)とは、狭義では、二つの車輪がついている、自走できる動力源が付いてない乗り物をさし、広義には車輪の数に関わらず、人力を主たる動力源として車輪に伝えて移動するものをさす。
自動車などと比較して、移動距離あたりに必要とするエネルギーが少ない、排気ガスを発生しないなど、地球温暖化問題が叫ばれる現在、クリーンな移動手段として見直されている。
自転車の歴史
1860年にはフランスでミショー型が発明された。これは現在の三輪車と同じようにペダルを前輪に直接取り付けたものであった。オリバー兄弟がピエール・ラルマンの発明に商機を感じ取り、ピエール・ミショーと組んで製造販売を始めたもの。(ベロシペードも参照。英国ではボーンシェイカー、日本では「がたくり」ともよばれた。)
英国のジェームズ・スターレーが1870年頃に、スピードを出すために前輪を巨大化させたペニー・ファージング型自転車を発明。スピードが出、デザインも洗練され、スポーツ好きの紳士の間で好評を博する。この当時は自転車レースが盛んであり、スピードを追求するために、ペニー・ファージング型自転車の前輪はどんどん拡大し、大きなものでは直径が1mを越えるようになった。日本にも輸出され「だるま車」と呼ばれた。これはレース用には人気があったが通常用としては乗車が困難であり、安定性が悪く転倒すれば頭から落ちるようなものであった。気軽に乗れるようなものではなかったが、このタイプで長距離のクロスカントリーライドまでおこなわれたことから、スポーツ用としてはかなりの力を秘めていた仕様だった。
1879年 ローソンによる後輪チェーン駆動車の発明がなされ、1884年、ハンバー、マッカモン、BSAなどがチェーンで後輪を駆動しより低く長い格好となった自転車の販売をはじめる。ジェームズ・スターレーの甥ジョン・ケンプ・スターレーが1885年にローバー安全自転車(Rover Safety Bicycle)として販売を開始。これは車体の中心付近にペダルとクランクを設け、後車輪とチェーンで連結することで動力を伝える現在の形であり、危険なペニー・ファージング型に対してセーフティ型(安全型)と名前をつけて販売された。この時点でペニー・ファージング型はオーディナリー型(普通型、従来型)と呼ばれセーフティの先進性を引き立たせるような名称とされた。このローバー安全自転車が現在の自転車の原型とされている。(*自転車博物館サイクルセンター シマノによる運営)
その後、セーフティ型にフリーホイールやダンロップが発明した空気入りタイヤが装着され、現在の自転車がほぼ完成された。
高度成長期には日本の自転車輸出量は世界一となり、世界中で日本製の自転車が乗られていた。現在では円が強くなったことで自転車の輸出は激減し、中国製を主とした外国製自転車が日本の市場に多数出まわっている。2005年現在、自転車の輸出量は中国が世界一である。
*うどん(饂飩)とは、日本旧来の麺類のうち、小麦粉を原料とし、ある程度の太さ、幅を持った麺を指す。
うどんのルーツ
古くは「うんどん」と発音された。中世に中国から伝来したと言われる。
延喜式には唐菓子の一種として紹介されるが、これは現在のうどんとはかけ離れた、餡入りの団子、すなわち「ワンタン」である。
現在のうどんは、その昔、切麦(きりむぎ)と呼ばれ、うどんと呼ばれるようになったのは江戸時代に入ってからである。切麦には暖かくして食べる温麦と冷やして食べる冷麦があり、総じてうどんと呼ばれた。
後に、日本農林規格等により、冷麦とうどんが明確に区別されるに至った。
麺による分類
麺の形
一本うどん - 切らず、引き伸ばさず、押して作る
太うどん
細うどん
ひもかわうどん
薄く、幅広(10~30mm程度)の麺。同類でローカライズされたものに、きしめん(愛知県)、ほうとう(山梨県)、おっきりこみ(群馬県・埼玉県)、だんご(大分県など)などがある。
*おにぎり(御握り)とは、ご飯を三角形、俵形、球状などに握り作った食べ物のことである。
握り飯ともおむすび(御結び)とも呼ばれる。広島市を中心とする地方ではむすびと呼ぶ傾向にあるが、無論おにぎりでも通じる。握りまま(青森県)、おにんこ(栃木県)といった方言もある。おむすびというのは、もとは御所の女房言葉であった。日本でおにぎりと言えば三角に握ったものというイメージが強く、「おにぎり型」というように三角形をした物のことを指す代名詞としてよく例えられる。
近年、日本の大手コンビニエンスストアが海外進出をすると同時に、世界中で日本のおにぎりが食べられるようになってきた。
日本での歴史
弥生時代後期の遺蹟であるチャノバタケ遺蹟(石川県鹿西町、現・中能登町)から、1987年12月におにぎりと思われる米粒の塊が炭化したものが出土している。この炭化米からは、人間の指によって握られた痕跡が残されている。また、北金目塚越遺蹟(神奈川県平塚市)からもおにぎり状に固まった炭化米が発見されている。
おにぎりの直接の起源は、平安時代の「頓食(とんじき)」という食べ物だと考えられている。この頃のおにぎりは楕円形をしていて、かなり大型(1合半)で、使われているのは蒸したもち米であった。
鎌倉時代の末期ごろからはうるち米が使われるようになった。おにぎりといえば海苔だが、板海苔が「浅草海苔」などの名で一般にも普及したのは元禄のころよりで、栄養もあり、手にごはんがくっつかない便利さもあいまっておにぎりと海苔の関係ができた。
天むす(てんむす)は、塩味を効かせた海老の天ぷらを具にしたおにぎり。名古屋(中京圏)の名物として知られる。 名古屋めしのひとつ。
1957年頃に、三重県津市大門にある天ぷら定食店「千寿」の賄い料理として考案されたのが発祥であるとされている。 「千寿」の持つ登録商標は第3199878号、「めいふつ天むす」と登録されている。 天むす関連の商標は、2006年11月現在、これ以外にも2件登録されている。 「千寿」のパンフレットによれば、昭和30年代の初め、初代水谷ヨネが忙しくて昼食を作る暇もないので、夫のために車えびの天ぷらを切っておむすびの中に入れたのが始まりだという。 現在の「千寿」は天むす専門店となっている。
一般には、名古屋市中区大須の惣菜店「天むす」が有名である。名古屋の「天むす」は「千寿」からのれんわけされたようである。
一口サイズで非常に食べやすく、冷めてもおいしいため、テイクアウトとしても人気がある。
付け合せは、沢庵漬け等の漬物ではなく、きゃらぶきである場合が多い。発案者が沢庵漬けが嫌いだったからとされる。
現在、主に天むすに使われる海老はあかしゃえびと呼ばれる海老である。夏が旬の体長12センチほどのエビであり、天むすのほかに海老せんべいの材料としても使われる。
ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~ ξ=(;^田)/~
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.