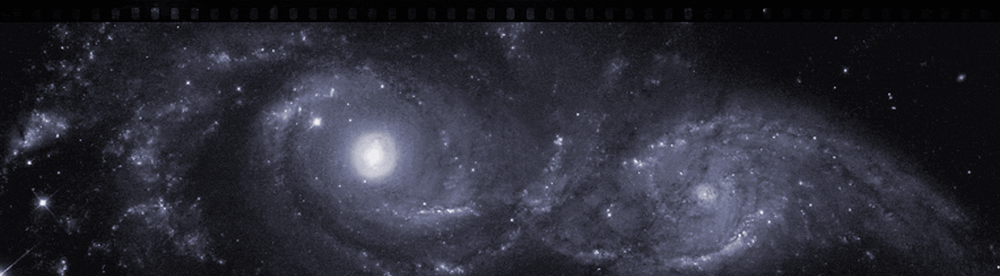全1723件 (1723件中 1-50件目)
-

『君たちはどう生きるか』とユングと東洋の思想。
久しぶりに荘子です。先日、宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』を鑑賞しまして、これは当ブログのテーマとも共通する部分が多いので、整理もかねてアップいたします。今回、おそらく多くの人が『君たちはどう生きるか』に関連させて指摘するであろうというのが、C.G.ユングとの関係であろうと思います。大まかにいって、これまでの宮崎作品の印象的なカットのダイジェストを入れ込んだり、宮崎監督の人生に大きな影響を与えた実在の人々をアニメに登場させたりして、いわば宮崎駿の人生を構成する「こころの風景」をアニメーションとして楽しむような作品であると思うのですが、その構造にはユングの思想の影響がはっきりと見えます。たとえば主人公の眞人(まひと)は自我、事実上のヒロインはそのアニマ鷺男はトリックスター大叔父は老賢者母は太母(グレートマザー)等々。もともと『千と千尋の神隠し』や『ハウルの動く城』でも使われていたユングの元型(アーキタイプ)の理論が今回も使われています。参照:Wikipedhia 元型https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%83%E5%9E%8Bそれと『君たちはどう生きるか』の重要な舞台となる塔のモデルは、ユングがチューリッヒ湖畔に建築したボーリンゲンの塔でしょう。母親と死別したユングがその喪失を乗り越えるために自ら石を積んで作り上げた塔で「最初から塔は私にとって成熟の場所となった。子宮、あるいは、その中で私が再び、ありのままの現在、過去、未来の自分になれる母の姿だったのである」というユング自身の言葉は、『君たちはどう生きるか』における塔の意味とぴったり合致します。参照:ユングと自然https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5150/ただし、『君たちはどう生きるか』における展開はユングの思想だけでなく、日本の神話世界や東洋思想ををベースにしたものが多いので、宮崎監督と親交もあったユング研究の大家・河合隼雄さんの影響はあると思います。参照:ユングと河合隼雄の道。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5092/一つが、イザナミの死です。『古事記』においてイザナミは火の神カグツチを産んだ後に死んでしまいます。その後イザナミを忘れられないイザナギは黄泉の国まで彼女を追いかけていくわけですが、火事によって失った母を追いかけるという展開は、宮崎監督自身のお母さんの死とも一致するストーリーですが、これを日本神話における「妻の死」とも重ね合わせています。参照:Wikipedia 黄泉比良坂https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E6%B3%89%E6%AF%94%E8%89%AF%E5%9D%82さらに、ポスターにもなっている鷺(さぎ)男ですが、おそらくこれも日本神話の死のシーン、天若日子(アメノワカヒコ)の葬儀です。≪故、天若日子之妻、下照比賣之哭聲、與風響到天。於是在天、天若日子之父、天津國玉神、及其妻子聞而、降來哭悲、乃於其處作喪屋而、河雁爲岐佐理持。鷺爲掃持、翠鳥爲御食人、雀爲碓女、雉爲哭女、如此行定而、日八日夜八夜遊也。此時阿遲志貴高日子根神。到而、弔天若日子之喪時、自天降到、天若日子之父、亦其妻、皆哭云、我子者不死有祁理。我君者不死坐祁理云、取懸手足而哭悲也。其過所以者、此二柱神之容姿、甚能相似。故是以過也。於是阿遲志貴高日子根神、大怒曰、我者愛友故弔來耳。何吾比穢死人云而、拔所御佩之十掬劒、切伏其喪屋、以足蹶離遣。此者在美濃國藍見河之河上喪山之者也。≫(『古事記』上巻五)→天若日子(アメノワカヒコ)の妻、下照比賣(シタテルヒメ)の哭き声は、風と共に荷まで天にまで響き渡った。天において、天若日子(アメノワカヒコ)の父、天津國玉神(アマツクニタマノカミ)と、その妻子がこれを聞いて、降り来て哭き悲しみ、そこで喪屋(もや)を建てて、河雁を食べ物の運び役として、鷺を掃持、カワセミを御饌人、雀を米搗き役として、雉を哭女として定めて、八日八夜の間、歌舞をした。そこに阿遲志貴高日子根神(アヂシキタカヒコネノカミ)が天若日子の弔問に天からやってきた。天若日子の父、その妻、皆、声をあげて哭いて、「我が子は死なずにここに生きている。」「我が君は死なずにここに生きている」と、その手足をとって声を上げて悲しんだ。阿遲志貴高日子根神を天若日子と見間違えたのは、この二柱の神の容姿が大変よく似ていたためである。それがこの勘違いの原因であった。阿遲志貴高日子根神はこの時、大いに怒って「私は愛する友を弔いにやってきただけだ。なぜ私を穢れた死人と比べるのか」と言って、佩いていた十掬剱を払って、その喪屋を切り伏せ、足で蹴散らした。これが美濃国の藍見(あゐみ)の河上の喪山である。日本の神話において唯一記載されている「葬儀」の記録です。内容は儒教における葬儀とほぼ同じですが、『古事記』ではさまざまな鳥たちに葬儀の仕事を分担させています。このなかで鷺は「鷺爲掃持」、すなわち墓の掃除役を担っています。(また、このお葬式の記述の中に死者とよく似た神が出てきて勘違いするシーンなどとも映画のストーリーと一致します。)参照:記紀と儒教の葬儀のかたち。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201407200000/で、もう一つが道教、もしくは老荘思想的な観点です。まずは主人公の名前の「眞人(まひと)」は『荘子』に登場する理想的な人間の呼称です。死を乗り越えた存在として秦の始皇帝もこの眞人を名乗っていますし、道教とのかかわりの深い日本の天武天皇の諡号「天渟中原瀛眞人(あめのぬなはらおきのまひと)」にも使用されています。『古之眞人、不知説生、不知悪死、其出不訴、其入不距、翛然而往、翛然而来而已矣、不志其所始、不求其所終、受而喜之、忘而復之、是之謂不以心揖道、不以人助天、是之謂眞人、』(『荘子』大宗師 第六)→昔の真人は、生を喜ぶこともなく、かといって死を憎むこともなかった。生れてきたからといってことさら喜ぶわけでもなく、死に行くからといってむやみに嫌がるわけでもなかった。悠然として行き、悠然として来るだけであった。どうして生まれたのかを知ることもなく、またどうして死ぬのかを知ろうともしなかった。ただ、生をうけたことを率直に受け取り、万事を忘れて元の場所へ返す。これを、「私心によって道を操ろうとしたり、道を外すようなことをせず、作為をもって天を助けるようなことをしない」というのである。こういう人を真人というのである。参照:始皇帝と道教https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410120000/この「眞人(真人)」は『日本書紀』においては厩戸皇子(聖徳太子)の片岡山伝説(飢人伝説)にも聖徳太子のセリフとして「先日臥于道飢者、其非凡人、必眞人也。」とあります。この片岡山伝説は道教における尸解仙の記録でもあり、それを踏まえて『日本書紀』でも「眞人」という道教の用語を使っています。参照:尸解の世界。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5197/こう見ると、『君たちはどう生きるか』において、宮崎監督のまなざしが「古代の人々の死」に向けられていることが分かります。ユングも禅や老荘思想に大きな関心を持ち、その影響を公言していましたが、『君たちはどう生きるか』における最大のテーマである「死」もまた東洋的な思想をベースにしています。『莊子妻死、惠子弔之、莊子則方箕踞鼓盆而歌。惠子曰「與人居長子、老身死、不哭亦足矣、又鼓盆而歌、不亦甚乎。」荘子曰「不然。是其始死也、我獨何能無慨然。察其始而本無生、非徒無生也,而本無形、非徒無形也,而本無気。雑乎芒勿之間、変而有気、気変而有形、形変而有生、今又変而之死、是相與為春秋冬夏四時行也。人且偃然寝於巨室、而我激激然随而哭之、自以為不通乎命、故止也。」』(『荘子』至楽 第十八)→荘子の妻が死んだ。恵子が弔問に訪れると、荘子は足をだらんと伸ばしたまま、お盆を太鼓代わりに歌を歌っていた。恵子曰く「あなたは、共に子供達を育て上げ、長年連れ添ってきた奥さんが亡くなったというのに、哭きもせずにお盆を叩いて歌を歌っている。ひどいではないか!」 荘子曰く「恵子よ、そうではない。妻が死んだ時には、私だって嘆き悲しまずにいられなかったさ。当たり前じゃないか。だけど、そのうち、こう考えるようになったんだ。人間生まれてくるときは、そもそも命なんてなかった。肉体だってなかった。もちろん、肉体を形作る氣だってなかったんだ。もともとぼんやりしたわけの分からないものから混ざり合っていた状態から、陰陽の気が生じて肉体というのが生まれて、肉体が変じて生命あると考えたのだ。今、妻の体は再び変じて死んでいくんだ。自然に春夏秋冬の移り変わりがあるのと同じように、妻は、天地という大きな空間に安らかに眠っている。それなのに、自分がいつまでもめそめそ泣いていては、天命を知らないことになりやしないかと思って、哭くのを止めたのだ。」・・・「大切な女性の死」を乗り越えるというのは、『荘子』の重要なテーマの一つでもあるし、ユングにもその影響が見られます。また、河合隼雄さんが日本に初めて紹介した『千の風になって』の世界観にも通じるものがあり、その意味でも荘子との共通性が見られます。参照:マスターヨーダと老荘思想。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5026/で、確定しているのがもう一つ。<桓公讀書於堂上、輪扁?輪於堂下、釋椎鑿而上、問桓公曰。「敢問公之所讀者何言邪?」公曰「聖人之言也。」曰「聖人在乎?」公曰「已死矣。」曰「然則君之所讀者、古人之糟魄已夫!」桓公曰「寡人讀書、輪人安得議乎!有説則可、無説則死。」輪扁曰「臣也、以臣之事觀之。断輪、徐則甘而不固、疾則苦而不入。不徐不疾、得之於手而應於心、口不能言、有數存焉於其間。臣不能以?臣之子、臣之子亦不能受之於臣、是以行年七十而老断輪。古之人與其不可傳也死矣、然則君之所讀者、古人之糟魄已矣。」(『荘子』天道 第十三)≫→桓公が書物を読んでいると、輪扁なる車輪を作る職人が「何を読んでいるんですか?」と聞いてきた。桓公は「聖人の言葉だよ」と答えた。すると職人は「その聖人様は生きているんですか?」桓公「いや、亡くなっておられる」職人「なんだ、あなたさまは死んだ人の残りかすみたいなものを読んでいるだけじゃないですか。」桓公が怒って「お前なんぞの身分でわしの学問をバカにするのか、答え次第によっては命はないぞ!」というと、輪扁は「車輪を作るときに、軸をぴたりとはめるためには、ゆるすぎても、きつすぎてもいけません。この技は自分で何度も何度も試して手で憶えていくことでしかできないのです。言葉でいくら言ってもダメでして、ついに私は自分の息子に伝えることすらかないませんでした。自分の経験と勘を継がせる事ができませんし、私の代わりになる者もおらず、七十の今になっても私は車輪を作る仕事をしています。さて、今でも働いて報酬をもらっている私に言わせてもらえば、お殿様の読んでいる本は、今を生きていない死んだ人の書いたもの。いわば、古人の糟魄ではありませんか?」『君たちはどう生きるか』において、嘴の穴をペコペコとはめ合わせたり、自分の息子に継がせる云々というシーンがありますが、あれは荘子で確定。あのシーンを『荘子』の古人の糟粕以外で説明することは不可能でしょう。証拠があるわけでなく、公表されることもないでしょうが、もし『ゲド戦記』を自分ではなく息子にさせると宮崎駿が言ってきたとするならば、老荘思想に造詣が深い「西の善き魔女」は、必ずや『荘子』にあるこの寓話を以て宮崎駿を諭したであろうと、私は確信しています。参照:ジブリ映画「ゲド戦記」に対する原作者のコメント全文http://hiki.cre.jp/Earthsea/?GedoSenkiAuthorResponse参照:アーシュラ・K・ル=グウィンと荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5164/参照:ル=グウィンと荘子 その2。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5165/後で推敲します。今日はこの辺で。
2023.08.08
コメント(4)
-
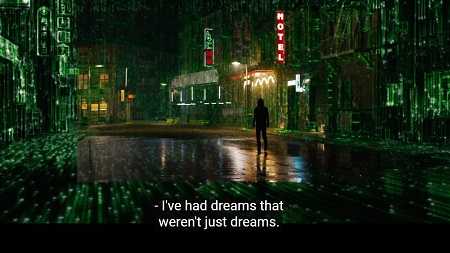
新・マトリックスと胡蝶の夢。
『マトリックスリザレクションズ(The Matrix Resurrections)』公開決定記念。久々に更新。参照:映画『マトリックス レザレクションズ』予告 2021年12月公開https://www.youtube.com/watch?v=mBRWwAqJ--U新作の『マトリックス』の予告には、前作までのつながりを暗示するシーンがいくつも挿入されています。一つが引用元の本そのものが登場しているルイス・キャロルの『不思議の国のアリス』。"Follow the White Rabbit "というセリフは第一作の導入部分に使われています(さらにこの予告のBGMはジェファーソン・エアプレインの「 White Rabbit (ホワイト・ラビット)」)。二つ目が、カウンセリングのようなシーンに映し込まれている”蝶”です。本棚にモルフォ蝶(Morpho)と呼ばれる蝶が飾られています。主に南アメリカに生息する生きた宝石とも称される大変美しい蝶ですが、この蝶の名前は「モルフェ(morphe ギリシャ語で「形作る」という意味)」という言葉に由来していて、これは「モルペウス(Μορφεύς)」というギリシャ神話の神様の由来としても有名です。参照:Wikipedia モルフォチョウ属https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E5%B1%9Eこのモルペウスはギリシャ神話の眠りの神・ヒュプノスと、夜の神・ニュクスの間の子で、夢を司る神です。このモルペウスの名前は、麻酔薬や麻薬としても知られる「モルヒネ(morphine)」の由来でもあります。モルペウスの英語名は、「Morpheus(モーフィアス)」。『マトリックス』において重要なキャラクターの名前です。参照:Wikipedia モルペウスhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%82%A6%E3%82%B9 この『アリス』と「モルペウス」をつなぐのは、もちろん「夢」です。新マトリックスの予告の中でも、旧作と同じように子猫が出ていますが、これは『鏡の国のアリス』からという暗示、『鏡の国』では夢にまつわる大変象徴的なシーンがあります。❝「さあ子ネコちゃん、こんどは、あれをすべて夢にみたのがだれだったかを考えてみましょう。(中略)つまりね夢を見たのはあたしか赤の王さまかのどっちかにまちがいないのよ。赤の王さまはあたしの夢の一部よね、もちろん――でも、そのあたしは、赤の王さまの夢の一部でもあったのよ! (中略)ねえ、おねがいだから、考えるのを手伝ってよ! 前足なんかあとでいいでしょうに!」 でも意地悪な子ネコは、反対側の前足をなめはじめただけで、質問が聞こえないふりをするばかりでした。 あなたはどっちだと思いますか?❞(ルイス・キャロル『鏡の国のアリス』「どっちが夢を?」より)参照:ルイス・キャロル 鏡の国のアリス どっちが夢を?https://open-shelf.appspot.com/ThroughTheLookingGlassAndWhatAliceFoundThere/chapter13.html西洋文化圏からのアプローチだけでは、ここで止まってしまいます。しかし、夢と蝶をテーマを結びつけるならば、タクラマカン砂漠から東では、この人の寓話を抜きには語れません。❝昔者荘周夢為胡蝶、栩栩然胡蝶也、自喩適志與。不知周也。俄然覚、則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與、胡蝶之夢為周與。周與胡蝶、則必有分矣。此之謂物化。❞(『荘子』斉物論 第二)→昔、荘周という人が、蝶になる夢をみた。ひらひらゆらゆらと、彼は、夢の中では当たり前のように蝶になっていた。自分が荘周という人間だなんてすっかり忘れていた。ふと目覚めると、彼は蝶の夢から現実の人間・荘周に戻っていた。そのとき、荘周が夢で蝶になったのか、蝶が荘周を夢見ているのか分からなかった。荘周と蝶には大きな違いがあるはずである。これを物化という。今回、わざとらしく蝶を映し込ませたのは、おそらく中国大陸での公開を見越して、荘子との関係性を隠さないという製作者側の意思表示だと思われます。参照:『マトリックス』と胡蝶の夢。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5102/参照:『マトリックス』と荘子 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5053/もう一つ、『マトリックスリザレクション』での蝶は、青いモルフォ蝶を多用した今敏監督の『パプリカ(Paprika)』を意識した可能性もあります。『マトリックス(1999)』と『パプリカ(2006)』は、機械を使って夢を共有するという設定や、胡蝶の夢をモチーフとして扱っているという共通性もありますし、何より日本の漫画・アニメーションのファンを公言するラナ・ウォシャウスキーが、『パプリカ』を素通りできたとは思えないのです。参照:パプリカ(アニメ映画) 予告編https://www.youtube.com/watch?v=yveN7tIWUZs参照:アニメーションと胡蝶の夢。 https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5159/今日はこの辺で。
2021.09.13
コメント(2)
-
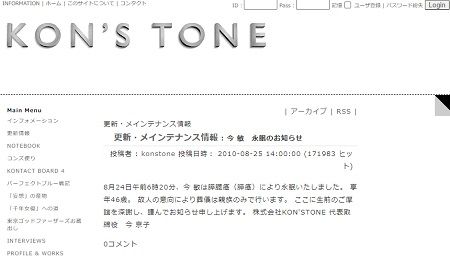
パプリカとインセプションと胡蝶の夢・改。
今敏(こん・さとし)監督が、46歳の若さで亡くなりました。本当に惜しい逸材であったと思いますが、ご本人は納得されていたようなので、あまり未練がましいのもどうかと思われます。いずれにせよ、ご冥福を。--------(以下引用)------------------------------2010年7月21日(水曜日)某映画その映画のTVスポットCMを初めて見たのは公開直前のことだったと思うが、私は見た途端大笑いした。映像的なことにせよセリフにしてもキャッチコピーにしても「あ・ん・ま・り」じゃないか(笑)すぐに名付けたぞ。「パクリカ」でも、別にそれでもいいじゃないか、というか、私にはどうでもいいし。どうせ植民地なんだしさ。--------------------------(引用終わり)------------------(以下引用)------------------------------2010年7月25日(日曜日)よく分からないが他人に影響を受けたことを隠さなくてはならない、という心理規制が私にはよく分からない。いいじゃん、何に影響を受けようが真似ようが。滅多なことじゃ盗作になんかならないんだしさ(笑)オープンにしている方が心身ともに風通しがいいだろうに。恥ずかしいことなのかね、それ。二十代のようなチンピラや若僧ならともかく、世間にちゃんと認知され評価されているような人がそうしたことをことさらに隠すという意味が私にはうまく想像出来ない。どんな表現物だって何か先行するもののアレンジでしかないだろうに。オリジナル神話の信奉者がいまだ世に蔓延っているというせいもあるだろうけど、例の件については宗主国と植民地の関係も忘れちゃなんねぇべ。考えるまでもなく、漫画やアニメや日本映画をちゃんと文化として評価しようという気配を感じるのは、先の大戦で仲間側だった国か直接殺し合わなかった国だという気がするもんね。商売になるかどうかは別の話だが。相変わらずだよね、まったく。ギブミーチョコレート。ま、日本のチョコの方がはるかに美味しくなったけど。--------------------------(引用終わり)----------以上、今敏監督のブログより引用いたしました。亡くなる一ヶ月前、すい臓がんの宣告を受けて闘病中の記録です。 もちろんこれは『インセプション(Inception)』(2010)が、ご自身の『パプリカ』(2006)に似すぎているのではないか?ということへの率直な感想ですね。参照:KON'S TONEhttp://konstone.s-kon.net/modules/notebook/archives/525今敏監督の最後の更新「さようなら」はこちら。http://konstone.s-kon.net/modules/notebook/archives/565で、この論争で、今監督のサイトの掲示板に当ブログが貼られまして、そのせいで海外からいろんな方が、このヘッポコブログに訪問なさっておいでだったようです。Re: Inception vs. Paprika controversy , 開始対パプリカ論争http://konstone.s-kon.net/modules/bbs/index.php?post_id=364宗主国云々というのは、手塚治虫の『ジャングル大帝』と『ライオン・キング』、庵野秀明の『不思議の海のナディア』と『アトランティス』が有名ですね。参照:Disney's Lion King Was to be a Remake of Kimba the White Lion?http://www.kimbawlion.com/rant2.htmナディアとアトランティスの比較http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Ocean/9219/atlantis.htm・・・現状において、ライオンに保護される権利はなく、ネズミには保護される権利があるのわけです。ジャングル大帝は収益を含めて、さすがに許されていいレベルを超えていますが、なんと言っても宗主国様ですから。後々の話になりますが、今敏監督というと、『Perfect blue』(1997)が『Black swan』(2010)に盗用されたことも話題となりました。こういった疑惑が取りざたされる作品が彼の没年に上演されているのは、ファンとしても釈然としない部分があります。『パプリカ』と『インセプション』で明白に類似しているというのは、例えば、ビルの廊下で重力に引かれるシーンや、鏡のシーンですが、これはそうだというべきでしょう。『パプリカ』は筒井康隆のSF小説をもとにしていて、DCミニという端末によって他人の夢を共有するという物語です。登場人物たちは夢と現実を行き来しながらさまざまな体験をするわけですが、夢の世界の目印としておびただしい数の蝶が登場します。もちろん、これは『荘子』の胡蝶の夢をモチーフにしたものです。『東京ゴッドサーザーズ』はユングのシンクロニシティだし、今敏監督は、こういった「意識の問題」において卓越した才能をお持ちでした。『昔者荘周夢為胡蝶、栩栩然胡蝶也、自喩適志與。不知周也。俄然覚、則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與、胡蝶之夢為周與。周與胡蝶、則必有分矣。此之謂物化。』(『荘子』 斉物論 第二)→昔、荘周という人が、蝶になる夢をみた。ひらひらゆらゆらと、彼は、夢の中では当たり前のように蝶になっていた。自分が荘周という人間だなんてすっかり忘れていた。ふと目覚めると、蝶の夢から現実の人間・荘周に戻っていた。まどろみの中で自分は夢で、蝶になったのか?蝶が自分を夢みているのか、分からなくなった。荘周と蝶には何らかの違いがあるはずである、これを物化という。この「オハヨウ」という短編もそうです。たった一分で「夢」と「うつつ」、意識と無意識の間を綺麗に表現しています。これも「胡蝶の夢」の一側面であり、シュレーディンガーの猫ですよね。これって、東洋人の得意分野です。ただし、「胡蝶の夢」ネタというのは、『カウボーイビバップ』の劇場版「天国の扉」(2001)にも見られる表現なんです。夢と現実、その構成要素としての「蝶」。『この世界は、蝶たちが俺に見せている夢なんじゃないか?それとも蝶のいる世界が現実で、俺がいた世界は夢だったのか・・。俺には分からないんだ。』参照:アニメーションと胡蝶の夢。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5159/これは、手塚治虫以来の伝統と言うべきかも知れませんが、オタク文化で「胡蝶の夢」ほど多用されるものはないと思います。多用されてもマンネリと感じないのが荘子の効用の一つなんですが(一定期間を経過するときれいさっぱり忘れてしまう)、そういった中でも、今敏監督は、王道を行っていた人なんです。今敏監督の遺作となってしまったのが『夢みる機械』というのも、東洋思想の王道なんです。簡単なようでいて、これを描ける才能ってのは、そうはいないんです。彼は確実にそれをやってのけていたんです。参照:夢みる機械 http://yume-robo.com/ただし、『インセプション』に関していえば、一部のシーンは酷似していますが、クリストファー・ノーランが総体として『パプリカ』をパクったとは思っていません。彼が元ネタだと主張しているボルヘスの『円環の廃墟』や「MATRIX」も『パプリカ』と同様のテーマですし、すべて「胡蝶の夢」との関係性も辿れます。参照:インセプションと胡蝶の夢。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5062/さらに言えば、クリストファー・ノーラン監督の前作の『ダークナイト(Dark knight)』(2008)こそ、荘子の引用が多くて、もともと興味があったんだと思います。参照:『ダークナイト』と荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5131/今日はこの辺で。
2020.08.24
コメント(0)
-

インセプションと胡蝶の夢・改。
『インセプション』再上映記念!以前書いたものを手直しします。今回はクリストファー・ノーランの『インセプション(INCEPTION)』(2010)について。重層的な夢の世界を描いた複雑な作品ですが、荘子の世界観にかなり近い作品と言えます。・・・いろいろあるんですが、とりあえず『荘子』と『列子』にあるお話を列挙します。❝昔者荘周夢為胡蝶、栩栩然胡蝶也、自喩適志與。不知周也。俄然覚、則遽遽然周也。不知周之夢為胡蝶與、胡蝶之夢為周與。周與胡蝶、則必有分矣。此之謂物化。❞(『荘子』斉物論 第二)→昔、荘周という人が、蝶になる夢をみた。ひらひらゆらゆらと、彼は、夢の中では当たり前のように蝶になっていた。自分が荘周という人間だなんてすっかり忘れていた。ふと目覚めると、彼は蝶の夢から現実の人間・荘周に戻っていた。自分は夢で蝶になったのか、蝶が自分の夢見ているのか分からない。荘周と蝶には大きな違いがあるはずである。これを物化という。まずはおなじみ「胡蝶の夢」。❝「夢飲酒者、旦而哭泣。夢哭泣者、旦而田獵。方其夢也、不知其夢也。夢之中又占其夢焉、覺而後知其夢也。且有大覺而後知此其大夢也、而愚者自以為覺、竊竊然知之。君乎、牧乎、固哉。丘也與女、皆夢也、予謂女夢、亦夢也。」❞(『荘子』斉物論 第二)→夢の中で酒を飲んでいた者が、目覚めてから「あれは夢だったのか」と泣く。夢の中で泣いていた者が、夢のことを忘れてさっさと狩りに行く。夢の中ではそれが夢であることはわからず、夢の中で夢占いをする人すらある。目が覚めてから、ああ、あれは夢だったのかと気付くものだ。大いなる目覚めがあってこそ、大いなる夢の存在に気付く。愚か者は自ら目覚めたとは大はしゃぎして、あの人は立派だ、あの人はつまらないなどとまくし立てているが、孔子だって、あなただって、皆、夢の中にいるのだ。そういう私ですら、また、夢の中にいるのだがね。❝仲尼曰「(中略)吾特與汝其夢未始覺者邪。且彼有駭形而無損心,有旦宅而無情死。孟孫氏特覺,人哭亦哭,是自其所以乃。且也,相與吾之耳矣,庸詎知吾所謂吾之乎。且汝夢為鳥而厲乎天,夢為魚而沒於淵,不識今之言者,其覺者乎,夢者乎?造適不及笑,獻笑不及排,安排而去化,乃入於寥天一。」❞(『荘子』大宗師 第六)→仲尼は言った「(中略)私もお前もお互いにまだ夢から覚めないだけかもしれない。彼は身体は変わりながらも心は変わることがなく、死とは住処を移すくらいのものだと思っている。孟孫氏は,すでに目覚めていて他人が泣けば彼もまた泣く、そこには何のはからいもないのだ。それに我々はよく「自分とは何なのか?」ということを疑問に思うものだ。たとえばお前が夢の中で鳥になって天を舞ったり、魚になって淵を潜っているとき、その時に「自分は今目覚めている」と感じるのだろうか?それとも「自分は今夢を見ている」と感じるのだろうか?人は「笑顔になるべきだ」と考える前はすでに笑っているものだよ。生も死も事の成り行きに任せてしまえば、天なる一と合一することも叶うだろう。❝鄭人有薪於野者、遇駭鹿、御而擊之、斃之。恐人見之也、遽而藏諸隍中、覆之以蕉、不勝其喜。俄而遺其所藏之處、遂以為夢焉。順塗而詠其事。傍人有聞者、用其言而取之。既歸、告其室人曰「向薪者夢得鹿而不知其處。吾今得之、彼直真夢者矣?」室人曰「若將是夢見薪者之得鹿邪?詎有薪者邪?今真得鹿、是若之夢真邪?」夫曰「吾據得鹿、何用知彼夢我夢邪?」薪者之歸、不厭失鹿、其夜真夢藏之之處、又夢得之之主。爽旦、案所夢而尋得之。遂訟而爭之、歸之士師。士師曰「若初真得鹿、妄謂之夢。真夢得鹿、妄謂之實。彼真取若鹿、而與若爭鹿。室人又謂夢仞人鹿、无人得鹿。今據有此鹿、請二分之。」以聞鄭君。鄭君曰「嘻!士師將復夢分人鹿乎?」訪之國相。國相曰「夢與不夢、臣所不能辨也。欲辨覺夢、唯黃帝、孔丘。今亡黃帝、孔丘、孰辨之哉?且恂士師之言可也。」❞(『列子』周穆王 第三)→鄭の国に原野で薪を拾う男がいた。男は原野でばったり鹿と出くわして、驚く鹿を擊ち倒した。男は仕留めた鹿が他人に盗まれはしないかと恐れ、干上がった池に隠し、芭蕉の葉で覆った。しめたものだと男は喜んだ。ところが、ふとしたことで、男は肝心の鹿を隠した場所を忘れてしまい、いつしか「あれは夢だったのではないか」と考えるようになった。家路に着くまでの間、鹿のことを順を追ってつぶやきながら帰った。そのつぶやきを盗み聞きした者がいて、その者がまんまと鹿をわがものとした。 盗み聞きをした男は帰って妻に言った「薪拾いのヤツが鹿を獲って隠しておいたんだが、そいつは隠した場所を忘れてしまってな、「あれは夢だった」と考えたらしい。ところが、そいつのつぶやきどおりに探してみたら、ちゃんと鹿がありやがった。あいつは正夢をみたんだろうよ。」 すると妻が答えた「お前さんこそ、薪拾いの男の夢をみていたかも知れないわ。その薪拾いはどこの誰なのさ?でも、鹿は確かにここにあるから、お前さんの方こそ正夢をみたかも知れないわ。」 「目の前に鹿はあるじゃねえか。俺とあいつのどちらかが夢をみていたなんて考えることもあるめえ。」 そのころ、薪拾いの男は、鹿をなくしたことをくやしがった末、ふてくされて眠っていた。その夜の夢で、男は例の鹿を隠した場所で、他人がその鹿を盗んでいる様子をまざまざと見た。 翌朝、薪拾いの男は昨夜の夢の出来事を思い出し、鹿を盗んだ男を突き止めて裁判を起こした。 判事はこう結論づけた「一方は現実に鹿を得たにもかかわらず、自分でそれを夢だとみなした。その後、夢の中で忘れた鹿の在処を見ていながら、現実には鹿を盗まれたと主張している。相手方は、現実に鹿をせしめていて、現に争っているわけだが、相手方の妻によると、その者は夢で鹿の在処を知ったのであり、誰からも盗んだわけではないと言う。今、現実に鹿がある。両名で分けるがよい。」 鄭王がその話を耳にして「その判事も夢の中で鹿を二分したのではあるまいか?」と言い、大臣に意見を求めると大臣はこう答えた「夢か夢ではないか、臣にはとてもその区別などできません。黄帝や孔子のような方ならばそれを分けたがったでしょうが、黄帝、孔子なきこの世において、だれがそれを区別しましょうや?この判決に従っておいてよいと思われます。」こちらは、『列子』にある夢の中で盗まれた鹿の所有を争う裁判の寓話。このお話は日本では謡曲の題材にもなっていて「芭蕉葉の夢」と呼ばれます。 道家(道教)の代表的な書物である『荘子』『列子』には、太極図で表されるような、夢と現実との相補的な関係性を示す言葉が随所に見られます。そのうえで、この予告をご覧ください。ちなみに、監督のクリストファー・ノーラン(Christopher Nolan)本人は、『インセプション(Inception)』に影響を与えたものとして、アルゼンチン出身の作家、ホルヘ・ルイス・ボルヘス(Jorge Luis Borges)の『円環の廃墟』やウォシャウスキー兄弟の『MATRIX』を挙げています。参照:A Man and His Dream: Christopher Nolan and ‘Inception’https://artsbeat.blogs.nytimes.com/2010/06/30/a-man-and-his-dream-christopher-nolan-and-inception/『円環の廃墟』の作者、ホルヘ・ルイス・ボルヘスは、講演でこのように発言しています。❝前回の講義で中国の哲学者、荘子の話を引用したかどうか、私には記憶がありません(私はこれまでにその文章を、しばしば、繰り返し引用し続けたものですから)。ともあれ彼は、自分が蝶になった夢を見たが、目覚めたときには、果たして自分が蝶である夢を見た人間なのか、それとも自分が人間であると夢を見ている蝶なのか分からなくなっていた。この隠喩はあらゆる隠喩のなかで、もっとも精妙なものだと私は思います。まず、第一に、それは夢で始まり、やがて目が覚めてからも、その生が依然として夢のごとく感じられているわけですから。そして第二に、ほとんど奇跡に近い幸運により、詩人はあの昆虫を選んでいるからです。(『詩という仕事について』「2 隠喩」より 鼓直訳 岩波文庫)❞参照:ボルヘスと荘子https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5163/また、『MATRIX』のコミック版やゲーム版では荘子は「Chuang Tzu(チャン・ツー)」というキャラクターで登場しておりまして、公式に認めています。参照:MATRIX Wiki Butterflyhttps://matrix.fandom.com/wiki/Butterflyマトリックスと荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5053/"You ever have that feeling where you are not sure if you're awake or still dreaming?"→起きてるのかまだ夢をみてるのかはっきりしない感覚って味わったことないか?クリストファー・ノーラン監督が表明している『インセプション』の元ネタであるの二つとも、荘子の「胡蝶の夢」との影響が見られます。 ❝一方では君の世界は嘘の世界であるといえるが、そういっている人の方がまた一方から見ると嘘の世界であるかもしれない。荘子の夢が胡蝶となってフワリフワリと花の上を飛んで歩いて暮らしておった。自分が蝶であるか、蝶が自分であるか、どうか、分からぬのである。また「夢」の荘子がほんとうの荘子か、「現(うつつ)」の荘子がうその存在か、どっちがより多くの現実性を持っているのか。夢に夢見るということもあって、ある角度からすると、この問題は必ずしも閑問題ではないのである。面白いところもないとは言えない。今日われわれが、こうしているとこう思っているけれども、それほど非現実性を持ったものではないかも知れぬ。ほんとうに現実性を持ったものは、そう思っているものを、もう一つ突き抜けたところにあるのではなかろうか。自分にはそう思われてならないのである。これは改めて申し上げたいと思います。 そういうわけで、何が現実であり、何が非現実であるかということは、これはお互いに議論をしてわかるものではない。この今われわれに面していると考えられる世界は、もともと一元であるが、それが意識の発生で、二元の世界にわかれて、それから次へ次へと千差万別の世界になったから、お互いに私のほうが現実だ、お前のほうが非現実だといって暮らすようになって、自分の生きている世界だけが一真実の世界のように思われるようになった。そういう私の方が非現実だ、非現実だと言われるお方があるかもしれない。それにはまたやむをえぬところがあると思う。❞(鈴木大拙 「禅の世界」昭和16(1941)年の講演より)・・・「夢」は、東洋思想においては大きな位置を占めます。紀元前の荘子が提起したパラドックスは、21世紀の今でも大問題なんです。君や蝶 我や荘子が 夢心 芭蕉今日はこの辺で。
2020.08.16
コメント(0)
-

鬼滅の刃とブルース・リー ~水の呼吸と”Be Water”~。
いつの間にか、いらすとやにイラストが出回ってました。ひさびさに荘子です。❝吹呴呼吸、吐故納新、熊經鳥申、為壽而已矣、此道引之士、養形之人、彭祖壽考者之所好也。』(『荘子』刻意 第十五)❞ →ゆっくり深く呼吸をする。冷たい空気を吸って古い空気を吐き出し、熊が木にぶらさがるような、鳥が飛び立つような伸びをして運動に専心する。これは、導引の人、養生をする人、彭祖のように長生きをしたい人の好むところである。 ❝古之真人,其寢不夢,其覺無憂,其食不甘,其息深深。真人之息以踵,衆人之息以喉。屈服者,其嗌言若哇。其耆欲深者,其天機淺。(『荘子』 大宗師 第六)❞→いにしえの真人は寝ていても夢を見ず、覚めていても憂いがない。ものを食べても甘いとせず、その呼吸は深々としていた。かつての真人はかかとでゆったりと呼吸していたが、今の世俗の人間は浅はかな議論にうつつをぬかして、あえぐようにのどで呼吸している。屈服をしたような者は、うめくように言葉を吐き出す。欲の深いものは天機が浅いものだ。紀元前の『荘子』という書物には、様々な寓話や事象について記録されていますが、その中には「吐故納新(とこのうしん)」や「真人の息は踵を以てし、衆人の息は喉を以てす」といった呼吸にまつわるものがあります。現在も連載中の王欣太(きんぐ ごんた)の「達人伝-9万里を風に乗り-』でも荘子が教えたとされる「大呼吸」という技法が重要な役割を果たしています。『荘子』の後継、魏晋南北朝時代葛洪(かっこう)の著作とされる道家の書物『抱朴子』では、このような言葉も出てきます。❝老君曰:忽兮恍兮,其中有象;恍兮忽兮,其中有物。一之謂也。故仙經曰:子欲長生,守一當明;思一至飢,一與之糧;思一至渴,一與之漿。一有姓字服色,男長九分,女長六分,或在臍下二寸四分下丹田中,或在心下絳宮金闕中丹田也,或在人兩眉閒,卻行一寸為明堂,二寸為洞房,三寸為上丹田也。此乃是道家所重,世世歃血口傳其姓名耳。一能成陰生陽,推步寒暑。春得一以發,夏得一以長,秋得一以收,冬得一以藏。其大不可以六合階,其小不可以毫芒比也。(『抱朴子』 地真 第十八)❞→老子も「忽たり、恍たり。その中に象(かたち)あり。恍たり、忽たり。その中に物あり。一とはこれを言うなり。」とある。いにしえの仙道の書物には「長命を欲するならば一を守れ。(中略)男性の一は9分、女性の一は6分にある。ヘソの下二寸四分には下丹田があり、心臓の下には中丹田があり、眉間から一寸ほどのところに上丹田がある。一こそが道家の重んじるところであり、代々口伝のみでその姓名を伝えることが許される存在である。一は陰陽を生成し、寒暑のはたらきを司る。春は一を以て発し、夏は一を以て長じ、秋を一を以って収め、冬は一を以て蔵じる、それは宇宙よりも大きいとも言えるし、針先よりも小さいとも言える。」ともある。『荘子』では「喉ではなく踵(かかと)で息をする」とまで行きますが、『抱朴子』ではヘソの下です。腹式呼吸が求められる時などに「丹田(たんでん)を意識するように」と言われる時の、あの丹田です。『抱朴子』では三つの丹田の位置を示しています。日本では仏教の用語として認識されていることもありますが、丹田は道教(道家)の言葉です。参照:Wikipedia 丹田https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%B9%E7%94%B0#:~:text=%E4%B8%B9%E7%94%B0%EF%BC%88%E3%81%9F%E3%82%93%E3%81%A7%E3%82%93%EF%BC%89%E3%81%AF,%E3%81%A8%E5%91%BC%E3%81%B6%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%82%E3%81%82%E3%82%8B%E3%80%82❝服藥雖為長生之本,若能兼行氣者,其益甚速,若不能得藥,但行氣而盡其理者,亦得數百歲。然又宜知房中之術,所以爾者姓,不知陰陽之術,屢為勞損,則行氣難得力也。夫人在氣中,氣在人中,自天地至於萬物,無不須氣以生者也。善行氣者,內以養身,外以卻惡,然百日用而不知焉。夫人在氣中,氣在人中,自天地至於萬物,無不須氣以生者也。善行氣者,內以養身,外以卻惡,然百姓日用而不知焉。吳越有禁祝之法,甚有明驗,多炁耳。知之者可以入大疫之中,與病人同床而己不染。又以群從行數十人,皆使無所畏,此是炁可以禳天災也。或有邪魅山精,侵犯人家,以瓦石擲人,以火燒人屋舍。或形見往來,或但聞其聲音言語,而善禁者以炁禁之,皆即絕,此是炁禁鬼可以神也。(『抱朴子』 至理第五)❞→薬の服用が長生の基本ではあるが、もし同時に氣を行うことができれば、その益はたちどころに早くなる。もし長生の薬を得られずとも行氣の道理を知る者は齢百歳まで生きることもかなうだろう。しかし、また房中の術についても知る必要がある。気息について知っていても陰陽の術を知らなければ、むやみに労力を失い、氣の力を得るのも難しくなるのだ。そもそも人は氣の中に存在し、同時に氣は人の中にも存在する。天地から萬物に至るまで、氣によって生じないものはない。氣をよく行う者は内には身を養い、外には邪なものを退けることができる。俗人は日夜、氣に生かされながらその存在を知らずにいる。呉・越には「禁祝の法」があり甚だ霊験がある。多くは気息を操るものである。この法を知るものは疫病の流行する中に足を踏み入れて、病人と共にいても感染せずにいる。仮に数十人の同行者がいても恐れることはない。気息を調整する方術には天災を退ける効能があるからである。邪悪や魅(すだま)や山の精が人家に侵入し瓦や石を人に投げつけたり、人の屋舍に火をつけたりする場合がある。また、形を伴ったり、音や言葉だけが聞こえるというこのもある。「禁祝の法」に精通した者はこれらを絶つことができる。気息によって鬼神を禁ずることも可能だからである。 また、『抱朴子』の中では「行氣」の技法についても書いてあります。一部は日本でも「呪禁師」の技法として導入された術ですが、『抱朴子』では、この「氣」を操ることでさまざまな超自然的な能力を獲得し、鬼神をも退けることも可能であると記述しています。その一部が武侠小説などで描かれる(氣)を用いた特殊能力です(いわゆる「内功」)。現在の気功もそうですがこれには呼吸が大きな位置を占めます。(「呼吸」に注目して視聴してください。)「呼吸」と「鬼神」。というわけで、今回は、『鬼滅の刃』と老荘思想について。 『鬼滅の刃』は吾峠呼世晴(ごとうげ こよはる)の人気漫画で、昨年アニメ化されて昨年社会現象を引き起こすまでに至った作品です。鬼を倒す技法として、作中にいろいろな呼吸法が出てきますが、このうち最も重要な「水の呼吸」のベースになっているのは、ブルース・リーの言葉です。❝水はどんな形にもなれる。升に入れば四角に、瓶に入れば丸く、時には岩すら砕いでどこまでも流れていく。(『鬼滅の刃』第24話「元十二鬼月」より)❞主人公の竈門炭治郎(かまどたんじろう)の師・鱗滝左近次(うろこだきさこんじ)のセリフ出典はブルース・リーの”Be water”です。“Empty your mind, be formless, shapeless - like water.Now you put water into a cup, it becomes the cup,you put water into a bottle, it becomes the bottle,you put it in a teapot, it becomes the teapot.Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.”(Bruce Lee)(「心を空っぽにして、どんな形態も形も捨てて水のようになるんだ。 水をコップに注げば水はコップとなるし、 水をティーポットに注げば水はティーポットになる。 水は流れることも出来るし、激しく打つことも出来る。だから、友よ、水のようになるよう心掛けることだ。」(日本語訳は『Cowboy Bebop』#XX よせあつめブルース より))この言葉の大本は、『荀子』の「水は方円の器に随う(水随方円)」と『老子』の言葉を組み合わせて作られています。『天下莫柔弱於水、而攻堅強者莫之能勝、其無以易之。弱之勝強、柔之勝剛、天下莫不知、莫能行。』(『老子』第七十八章)→天下に水よりも柔弱なものはないが、堅強な者を攻めるのに水に勝るものはなく、水に代わるものはない。弱が強に勝ち、柔が剛に勝ちうる事を、天下に知らぬ者はいないが、それを行いうる者もない。その後、❝「どんな形にもなれる。決して流れは止まらない。」(同第24話「元十二鬼月」より)❞というセリフに続きますが、これも、❝Running water never goes stale so you gotta just keep on flowing.(流れる水が古びることはない、だから流れ続けるんだ。)❞というブルース・リーの言葉とも一致します。これらは全て1971年に収録された「ピエール・バートンショウ」というカナダのトーク番組のインタビューでの発言です。参照:ブルース・リーと東洋の思想 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5180/実は、炭治郎の師匠の言葉だけでなくて、吾妻善逸(あがつまぜんいつ)の祖父の、❝一つのことしかできないなら それを極め抜け 極限の極限まで磨け(『鬼滅の刃』第33話「苦しみ、のたうちながら前へ」より)❝という教えも、ブルース・リーの有名な言葉と一致しますので、偶然ではありません。“I fear not the man who has practiced 10000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10000 times.”(Bruce Lee)→私は一万種類のキックを一回ずつ練習した人を恐れることはないが、一つのキック練習を一万回した人を恐れる。『合抱之木、生於毫末。九層之臺、起於累土。千里之行、始於足下。為者敗之、執者失之。是以聖人無為故無敗。無執故無失。』(『老子』第六十四章)→一抱えもある巨木も、小さな新芽から生まれ、九層の城も、一盛りの土から築かれ、千里の道のりも、まず足下の一歩より始まる。はからいのある者は敗れ、固執する者は失う。聖人は無為であるが故に無敗であり、執着がないが故に失わない。参照:ブルース・リーと東洋の思想 その4。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5183/ また、当ブログで何度か引用しています、2008年に公開された『ドラゴン・キングダム』という映画もブルース・リーや老荘思想の影響が濃厚な作品ですが、これも「水」と「呼吸」がテーマとして使われています。 ❝For it is like water. Nothing is softer than water yet it can overcome rock. It does not fight. It flows around the opponent, formless, nameless.(それは水のようなものだ。水よりも柔らかいものはないが、硬い岩をも砕くことができる。争うことなく、流れるように包み込む。形も、名前もない。)❞このシーンでは、老子や荘子の言葉を借りて水の教えを説いています。 このシーンでは、❝Don't forget to breathe (呼吸を忘れるな)❞と、呼吸の大切さも説いています。 (「呼吸」に注目して視聴してください。)この教えが、最終的に結実するわけですが、これも「水と呼吸」ですよね。というか、その後に、胡蝶さん家の「明鏡止水」とある掛け軸の前で訓練するとかも、どう見ても老荘思想を意識してのものです。この「機能回復訓練」の回では、訓練方法はカンフーものでよくあるものですし、寝ている間に呼吸を鍛えるとか、呼吸法によって他の身体技法も上達するなんていうのは、金庸の武侠小説『射鵰英雄伝(しゃちょうえいゆうでん)』からだと思われます。参照:スターウォーズと武侠。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5200/(「呼吸」に注目して視聴してください。)ちなみに、金庸の武侠小説の中にもさまざまな呼吸法(内功)が登場しますが、最も有名なものは「ガマの呼吸(蝦蟇功)」です。参照:Wikipedia 内功https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%8A%9F・・・『北斗の拳』や『ドラゴンボール』、『幽遊白書』、『魁!男塾』など、ジャンプの黄金時代に多用された「氣」を使う超自然的な能力は、多くが道教(道家)由来のものでして、波紋(仙道)が用いられた『ジョジョの奇妙な冒険』の初期の作品には『荘子』からのセリフも多く見られます。『鬼滅の刃』もその系譜に連なる作品のうちの一つと言えるでしょう。参照:ジョジョと荘子 ~波紋と仙道~。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5140/後で推敲します。今日はこの辺で。
2020.08.02
コメント(5)
-
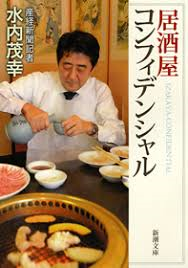
首相と腹痛。
ちょっと気になったことを。-------(以下引用)-----------------------------------------佐藤浩市が首相を揶揄?「すぐにおなかを下してしまう設定にしてもらった」映画インタビューが物議俳優の佐藤浩市(58)が発売中の漫画誌「ビッグコミック」に掲載されているインタビューで発言した内容が、インターネット上で物議を醸している。 インタビューは佐藤が内閣総理大臣役で出演する映画「空母いぶき」(24日公開)に関する内容で、佐藤は総理大臣役について「最初は絶対やりたくないと思いました(笑)。いわゆる体制側の立場を演じることに対する抵抗感が、まだ僕らの世代の役者には残っているんですね。でも、監督やプロデューサーと『僕がやるんだったらこの垂水総理をどういうふうにアレンジできるか』という話し合いをしながら引き受けました」とし「彼はストレスに弱くて、すぐにお腹(なか)を下してしまうっていう設定にしてもらったんです」と発言した。 安倍晋三首相が難病の潰瘍性大腸炎を患っていることから、ネット上ではこの発言に対し、安倍首相を揶揄(やゆ)している」などの発言が相次いでいる。 佐藤は13日、都内で映画「ザ・ファブル」完成披露試写会に出席する予定。発言が注目される。-----------------------------------------(引用終わり)-----参照:https://hochi.news/articles/20190513-OHT1T50079.html佐藤浩市さんが、「彼はストレスに弱くて、すぐにお腹(なか)を下してしまうっていう設定にしてもらったんです」と言っただけで、潰瘍性大腸炎を患っている安倍さんへの揶揄になるそうです。そんなこと一言も言ってないのに。腹を下してしまうという設定⇒潰瘍性大腸炎という理由で総理を辞職した安倍さん⇒揶揄⇒けしからんというセットで、呪文のように同じ言葉が延々と流れ続けるというネットの様相も壮観です(そもそもま安倍さん本人はアサコールという薬で完治したと証言しております)。まぁ、私はマッコリを手酌でがぶ飲みしたり、災害時にも酒盛り開いたり、夜な夜な有名人と会食をされる安倍さんが難病の患者だなんて思えません。参照:マッコリとホルモンと安倍晋三。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201211200000/総理大臣なんていう仕事は、ストレスが大きいのは当然です。安倍さんのみならず、多くの総理大臣が内臓を痛めています。たとえば、橋本龍太郎元総理の場合などもストレスが原因だと思われます。-------(以下引用)-----------------------------------------2006/06/15 断腸の思い(6月11日) 11日は、東京の病院に入院した、兄の見舞いに行きましたが、その病名を聞いて、「断腸の思い」という言葉を思い起こしました。 兄が救急車で緊急入院をしたのは、4年前の心臓手術の時以来2回目ですが、今回は、心臓や脳には全く異常はありませんでした。 ところが、お腹の痛みを訴えたため、開腹したところ、大腸が壊死した状態になっていたため、大腸を取り除く手術を受けました。 何が直接の引き金になったのかはわかっていませんが、何らかの原因で、大腸に血液がまわらなくなったために、わずかな時間の間に、大腸が壊死をしたとのことで、消化器が専門の医師の話では、数十年の経験の中でも、これが2例目ということでした。 それだけ、めったにない珍しい症状ということですが、数時間のうちに、たちまち腸が機能しなくなったと聞いて、「断腸の思い」という、中国の故事に基づく言葉が頭をよぎりました。 これは、中国の晋の時代の昔話ですが、桓温という武将が、舟で三峡を旅していた時に、従者が小猿を捕まえました。 これを悲しんだ母猿が、川沿いの岩づたいに、どこまでも追いかけてきたあげく、ついに舟に飛び移ったのですが、そのまま息絶えてしまいました。 そこで、その母猿のお腹を開いてみると、腸がずたずたになっていたことから、はらわたが千切れるほどの悲しみや辛さを、「断腸の思い」と言うようになりました。 兄も場合も、長く政治の世界で仕事をする中で、誰にも言えないような、辛いことや悲しい出来事が、積もり積もっていたことでしょう。 しかし、根っから我慢強い男ですし、言い訳も一切口にしないタイプですので、もしかすると、それが断腸につながっていったのかもしれません。 ただ、やるだけのことはやったのですから、今は全てを忘れて、ゆっくりと休んでほしいというのが、弟としての思いです。-----------------------------------------(引用終わり)-----以上、「橋本大二郎です」2006/6/15よりhttp://daichanzeyo.cocolog-nifty.com/0403/2006/06/post_36b5.html今日はこの辺で。
2019.05.13
コメント(0)
-
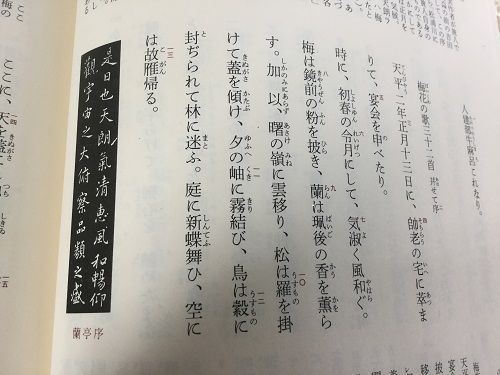
令和の典拠と江戸の研究。
しつこく、新元号「令和」の話を。 今回、元号の典拠として歴史上の初めて日本の古典として採用された『萬葉集』の「梅花歌丗二首并序」、ですが、一般書を開くと、中国古典との関係を説明する文章が多いです。例えば、図書館などではおそらく最もポピュラーな小学館の新編日本古典文学全集などでも、有名な「蘭亭序」の画像を並べて、「梅花歌丗二首并序」の引用元であることを強調しています。この種の研究で有名なのは江戸期の契沖の『万葉代匠記』。❝此(序ノ)発端ハ義之カ蘭亭序ニ、永和九年、歳在癸丑、暮春之初、會于會稽山陰之蘭亭、修禊事也トカケルニ效ヘル欤。篇中ニ彼記ノ詞モ見エタリ。萃ハ孟子云。出於其類,拔乎其萃。注曰。萃(ハ)聚也。師は帥ニ改ムルヘシ。于時初春令月氣淑風和、張衡歸田賦云。仲春令月時和氣淸。蘭亭記云。是日也天朗気清、恵風和暢。杜審言詩云。淑氣催黄鳥。梅披鏡前之粉ハ、宋武帝女壽陽公主人臥含章簷下。梅花落公主額上、成五出花。拂之不去。自是後有梅化粧。珮後之香。未考得。」(以下略)(以上岩波書店刊「万葉代匠記」『契沖全集 第三巻』より)契沖が引用元として指摘しているのが、『文選』の中の張平子(張衡)の「帰田賦(きでんのふ)」、王羲之の「蘭亭集序(蘭亭記)」、杜審言の「和晋陵陸丞早春遊望」の三作です。 対比すると、 于時 初春令月 気淑風和(『萬葉集』「梅花歌丗二首并序」) 於是 仲春令月 時和氣清(『文選』「帰田賦」)是日也 天朗気清 恵風和暢 (『蘭亭集序』) 淑氣催黄鳥(『和晋陵陸丞早春遊望』)となります。全体を見ると『蘭亭集序』の影響が大きいと感じますが、「令和」の引用部分は「帰田賦」で確定でしょう。 『雨月物語』で有名な上田秋成も帰田賦との関係を指摘しています。❝帰田賦、仲春令月、時和気清。宋武帝女壽陽公主人臥含章簷下。梅花落公主額上、成五出花。払之不去。自是後有梅化粧。此公主を銀公と云し事、物に見ゆ。(中央公論社刊「楢の杣(ならのそま)」『上田秋成全集 第二巻 萬葉集研究篇一』)❞ ❝◯帰田賦。仲春令月。時和気清。◯鏡前之粉。宋武帝女。寿陽公主。日賦含章。簷下梅花。落公主額上。成五出花。払之不去。自是後有梅化粧。(中央公論社刊「金砂(こがねいさご)」『上田秋成全集 第三巻 萬葉集研究篇二」)❞・・・この種の研究は江戸の頃には盛んなようでして、今回の元号の騒動の200年以上前から「ここは『文選』でしょ」と、ほぼ判明していたようです。まぁ、慶雲、神護景雲、嘉祥、元慶、延長、貞元、永観、元仁、保延、建仁、建永、文暦、延応、興国、建徳、康応、長享、明応、元亀、天正、元文、寛延、安永、享和、慶応と、これまで20数回(並列を含めて)元号の典拠となった『文選』を無視して『萬葉集』とするのは、伝統の破棄と言っていいでしょう。あとで追記します。
2019.04.05
コメント(0)
-
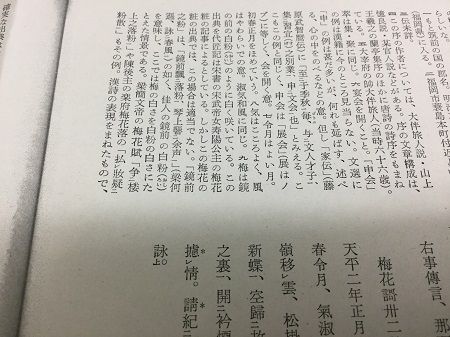
先達はあらまほしきことなり。
今回の元号の「令和」の典拠であると政府が主張していた『萬葉集』の巻五、「梅花歌丗二首」の該当箇所を、『日本古典文学大系』で調べてみると、注釈にこう書いてありました。❝この序の作者については、大伴旅人説・山上憶良説・何某官人説などがある。序の文章構成は、王羲之の蘭亭集序のほかに唐詩の詩序をもまねている。❞❝梅は鏡の前の白粉(おしろい)のように白く咲いている。この出典を代匠記は宋書の宋武帝女寿陽公主の梅花粧の記事によるとしている。しかしこの梅花の粧の出典では、この場合は適当でない。「鏡前之粉」は、「鏡前飄落粉、琴上響余声」(梁何遜、詠春風)の如く、佳人の鏡前の白粉を意味し、ここでは梅の白さを白粉の白さにたとえた情景である。梁簡文帝の梅花賦「争楼上之落粉」や陳後主の楽府梅花落の「払妝疑粉散」もその例。漢詩の表現をまねたもので、確実な出典はない。❞(岩波書店刊 『日本古典文学大系5 萬葉集二』 巻第五 p.72より)『萬葉集』巻五を読めば、普通分かると思いますが、あれだけ漢籍の影響の強い部分を引用しておいて「典拠は日本の古典」などとは、主張できるものではありません。一般の本でも、当該部分についてちゃんと「漢籍の書物の模倣」として指摘しています。日本の古典が由来だとしたいのなら、他にもあったはずなのに、なぜ、指摘を無視して漢籍由来の文言だらけの文章から元号案を抽出したのか?民間で使用するだけでなく、令和の名は次期天皇となられる皇太子殿下は即位中も、即位後もこの名前を使用されます(好むと好まざるとにかかわらず)。それを知ったうえで行われているはずなのに、全くでたらめな今回の元号の選考に、政府の皇室に対する悪意すら感じます。歴史学を専攻している皇太子殿下への当てつけでしょうか?無知で済まされる話でもないので、今後の検証が必要でしょう。今日はこの辺で。
2019.04.03
コメント(2)
-

『文選』を読まずに元号が作れる時代。
元号が「令和(れいわ)」と決まったようです。一部で報道されていたとおり、平安時代から連綿と続いていた中国古典からの出典ではなく、『万葉集』からでした。ただし、引用元が『万葉集』の「巻五」の❝初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす❞ということで、ちょっと「?」がついていました。万葉集というと「万葉仮名」のイメージですが、今回の「令和」の出典とされている巻五は漢文の影響を受けたものが多く、場所を聞くだけで日本オリジナルとは到底想像できない箇所です。当ブログでも触れた『抱朴子』の引用の多い山上憶良の『沈痾自哀文(ちんあじあいぶん)』もこの巻五にあります。参照:憶良の病と『抱朴子』。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410260000/ようやく報道ベースでもこの問題を取り上げられるようになってきたのでメモ。-----(引用はじめ)----------------------------------------------令和の出典、漢籍の影響か 1~2世紀の「文選」にも表現 毎日新聞2019年4月1日 20時54分(最終更新 4月1日 21時22分) 初の「和風元号」の出典となった「万葉集」の「初春令月、気淑風和」との文言について、複数の漢学者らから、中国の詩文集「文選(もんぜん)」にある「仲春令月、時和気清」の句の影響を受けているとの指摘が出ている。 万葉集が8世紀末ごろの成立とされるのに対し、中国の美文をまとめた「文選」は6世紀に成立。7~8世紀の遣隋使(けんずいし)・遣唐使が持ち帰ったとみられ、日本でも文章を作る上での最高の模範とされた。「仲春」の句は、1~2世紀の文人政治家の張衡(ちょうこう)の作品。張衡は地震計の作製など科学者の先駆としても知られる。 万葉集と文選の当該部分は、初春と仲春と時期がやや違うが、「令月」との表現や、陽気の説明の「和」が一致する。 平安前期ごろまでに成立した日本書紀をはじめとする古典は、中国古典の表現を元にして書かれた部分が多いとされる。元号の出典にする場合、「中国の古典の表現を孫引きすることになる」との指摘が出ていた。だが、元号に詳しい所功・京都産業大名誉教授は「日本人は外国から取り入れたものを活用してきたわけで、単なるまねではなく、自分たちのものとして利用してきた」と評価する。 中国古典学の渡辺義浩・早稲田大教授は、文選の句について「意味は万葉集と基本的に同じ。文選は日本人が一番読んだ中国古典であり、それを元として万葉集の文ができていると考えるのが普通」と指摘する一方、「東アジアの知識人は皆読んでいた。ギリシャ、ローマの古典を欧州人が自分たちの古典というのと同じで、広い意味では日本の古典だ」と意義づける。 今回初めて漢籍から選ばれなかったことに関し、中国哲学の宇野茂彦・中央大名誉教授は「日本の文化というのは漢籍に負うところが非常に多い。文化に国境は無い。漢籍を異国の文化だと思わないでほしい」と語る。 政府は「文選」が原典に当たるかなどについて評価は避けている。 今回の出典についてどう評価するか。江戸末まで改元時に公家らが行った審議「難陳(なんちん)」で、中国古典だけでなく日本書紀も引用されたことがあったことを先月論文で初めて指摘した水上雅晴・中央大教授は「文選との類似性が考えられ、隠れた典拠にやはり漢籍があることになる」としつつ、「日本で1300年以上使い続けられている元号の典拠がはじめて国書になったのだから、『令和』は画期的な年号と言える」と意義づける。 水上教授は、江戸時代末に「令徳」の元号案が出た際、「徳川に命令する」という意味にも読めることから幕府が撤回させた、と不採用の経緯を指摘する。 過去のこのような事案は、公家らが多数の記録を残したおかげで判明した。今回の有識者懇談会での審議のあり方などに問題はなかったのか。平成改元の記録未公開をどう考えるか。水上教授は「改元手続きについては、慌てて準備するのではなく、制度をきちんと整えることを考えるべきだ。『令和』改元からは、いつ公表するかは別問題として、細部に至るまでの記録をしっかり残してほしい」と要望した。【畠山哲郎、竹内麻子】 ----------------------------------------------(引用終わり)-----・・・『文選』は、日本人の基礎教養の一つであり、日本の元号の典拠としては『書経』、『易経』に次いで三番目に多い書物です(最近の元号では「慶応」の典拠)。❝ひとり、燈のもとに文をひろげて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。文は、文選のあはれなる巻々、白氏文集、老子のことば、南華の篇。この国の博士どもの書ける物も、いにしへのは、あはれなること多かり。(『徒然草』第十三段)❞→ 燈火の下で一人、書物を広げて知らない世界の人を友とするのは、この上もない安らぎだ。文では『文選』の感銘深い巻々、『白氏文集』、『老子』、『荘子』。日本の博士たちが書いたものでも、古いものであれば深みのあるものが多い。『文選』のチェックすらしていないなどというのは、ミスとしてもあまりにもお粗末。Wikipediaのコピペしただけの学生のレポートにA評価を与える教授に等しいです。さすがにこの典拠は訂正すべきでしょうね。今日はこの辺で。
2019.04.01
コメント(2)
-

山中教授と「塞翁が馬」。
明日、新しい元号が発表されるんだそうで。今回の元号の選考に関しては、安倍内閣ということもあり、中国古典や中国文学の専門家の数も削減され、平安以来続いてきた中国古典からの出典という元号の伝統が断絶される可能性も報道されています。また、今回の「元号に関する懇親会」のもメンバーにも中国古典に造詣のありそうな方が少ないですが、そのなかで、中国古典のお話を好んでなさる方がいらっしゃいます。京都大学のips細胞研究所所長で、ノベール生理学・医学賞を受賞された山中伸弥教授です。参照:「平成27年度近畿大学卒業式」iPS細胞研究所 山中伸弥教授メッセージhttps://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=m0OqmlwJfMI・・・山中教授が好んで使うのは『淮南子(えなんじ)』の有名な寓話「塞翁が馬」のお話です。-----(以下引用)--------------------------------------------- ということで、卒業生の皆さん、今日、皆さんに私の大好きな中国のことわざをお伝えしたいと思います。それは、「人間万事塞翁が馬(じんかんばんじさいおうがうま)」。略して「塞翁が馬」。こういうことわざです。 「塞翁が馬」塞というのは、お城です。中国のお城の近くの村に、「塞翁」の翁というのは「おきな」おじいさんですね。おじいさんが、いたらしいです。そのおじいさん、唯一の財産は、一頭の馬。そして、一人息子さんと住んでおられたらしいです。 ところがある日、その唯一の財産の馬が逃げてしまいました。すぐ、村人たちが集まってきて、おじいさんを「大変ですね」と慰めにきました。でも、おじいさんは冷静に「いやいや、これは何か良いことの始まりかもしれない」と言いました。 そうすると、2,3日すると、その馬が帰ってきて、しかも、その馬よりもさらに良い名馬を一緒に連れて帰ってきました。すると、村人はまたすぐ集まってきて「いやーおじいさん素晴らしい。良かったですね」とやってきました。でも、またおじいさんは「いやいや、これは何か悪いことの始まりかもしれない」と。すると、その息子さん、やってきた名馬に乗っていましたが、落っこちてしまって、足を複雑骨折してしまって、歩けなくなってしまいました。 また村人がやってきて「おじいさん、えらい災難ですね」とやってきました。しかし、おじいさんは「いやいや、これはなにかいいことかもしれない」と。しばらくすると、戦争が起こりました。村の若者は、ほとんど全員が死んでしまいました。でも、おじいさんの一人息子は、脚を怪我して歩けなかったので、戦争に行かずに生き残れました。 そういう話らしいです。村人の様に、一喜一憂するのではなくて、おじいさんの様に、こうどっしり構えよう。そういう意味だと思います。---------------------------------------------(引用終わり)-----参照:「塞翁が馬」から生まれた/山中伸弥 iPS細胞研究所長 (動画&全文)https://kindaipicks.com/article/000441内容それ自体も、スティーブ・ジョブズの有名なスピーチと大変よく似ています。実は、現代でいうところの「偶然性」は、タオイズムを語るうえで重要な命題です。参照:スティーブ・ジョブズと禅と荘子 その5。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5177/❝夫禍福之轉而相生、其變難見也。近塞上之人有善術者、馬無故亡而入胡。人皆吊之。其父曰「此何遽不為福乎?」居數月、其馬將胡駿馬而歸。人皆賀之。其父曰「此何遽不能為禍乎?」家富良馬、其子好騎、墮而折其髀。人皆吊之。其父曰「此何遽不為福乎?」居一年、胡人大入塞、丁壯者引弦而戰、近塞之人、死者十九、此獨以跛之故、父子相保。故福之為禍、禍之為福、化不可極、深不可測也。』(『淮南子』人間訓)❞→幸福が不幸に、不幸が幸福に転じる人間社会のありようは、その変化を見極めるのが難しい。城砦の近くによく道術をわきまえた人がいた。その人の馬が勇壮な胡の国に逃げてしまった。人々は皆彼に同情した。するとその人は「このことが幸福に転じるかどうか分からないさ」と呟いた。数ヶ月経ってみると、逃げ出したはずの彼の馬が、胡の国の駿馬を何頭か連れ立って帰ってきた。人々は皆彼をお祝いした。すると彼は「このことが不幸に転じるかどうかわからないさ」と呟いた。駿馬のおかげで家は豊かになり、彼の息子は騎馬が巧みになったが、ある時息子が落馬して骨を折る大怪我をした。人々は皆彼に同情した。すると彼は「このことが幸運に転じるかどうか分からないさ」。一年ほど経って、胡の国の兵が城砦に攻め上ってきた。城砦の若者は全て駆り出され、十人のうち九人が命を落とすほどの激戦の末、城砦は辛くも守られた。大怪我をおった彼の息子は、徴兵されず息子の命は奪われずに済んだ。幸福が不幸となり、不幸が幸福となる、その変化は見極めがたく、又、推し量り難いものである。・・・『淮南子』は、『日本書紀』の天地開闢や「民のかまど」のお話のネタ元でもありますが、日本人が最初に出会った中国古典の中の一冊です。参照:『淮南子』と『日本書紀』 ~天地開闢~https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5187/参照:「民のかまど」と中国古典。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5190/山中教授がおっしゃる、「一喜一憂しないという態度」を、はっきりと示しているのは『荘子』もまた同じです。たとえば、朝三暮四のお話もその一例です。参照:荘子と進化論 その207。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201811100000/偶然、といえば、山中教授と同じ京都大学出身でノーベル賞を受賞した湯川秀樹さんも、素粒子理論について『荘子』の渾沌の寓話で説明をすることがありますし、山中教授がされている夢の話なども、夢の中のアイディアを活用する湯川さんの逸話とも重なります。タオイズムというのは、理系と相性がいいとつくづく思います。参照:湯川秀樹と渾沌。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5118/参照:長岡半太郎と荘子 その2。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5117/今日はこの辺で。
2019.03.31
コメント(0)
-

王安石が綴る元日。
明けまして王安石です。今回は、王安石の漢詩から11世紀、今から950年ほど前のお正月の様子について。『元日』 王安石爆竹声中一歳除 爆竹の声中一歳を除(つ)き 春風送暖入屠蘇 春風は暖を送りて屠蘇(とそ)に入らしむ 千門万戸曈曈日 千門万戸 曈曈(とうとう)たる日 総把新桃換旧符 総て新桃(しんとう)を把(と)って旧符に換ふ 爆竹の音の中一年が過ぎ新春の風は屠蘇の中にぬくもりを運ぶ千門万戸を初日の陽光が照らすその日に新しい桃符をすべて旧年のものと取り換える参照:中国アニメ『元日~ 中国唱詩班~』日本語字幕付きhttps://www.youtube.com/watch?v=UUjmqkhuLw0&list=PLc2MAB7JH4M0-ik0A7BL6eZuJ_G3KnYRX「爆竹」「屠蘇」「桃符」と、荊楚歳時記に描かれている事物が全て描かれているので、あとで該当の記事に足します。もちろん、これらの風俗は旧暦の正月の出来事です。あしからず。参照:『荊楚歳時記』の正月https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5206/次はちゃんと更新するはず。今日はこの辺で。
2019.01.02
コメント(0)
-

荘子と進化論 その207。
ちょっと気になったので。-------(引用始め)------------------------------------------------サルが“ストライキ” 餌への不満爆発、山にこもる 大分の高崎山 2018年11月08日 06時00分 大分市の高崎山自然動物園で、餌をやる寄せ場にサルが現れなくなっている。サル数を抑制しようと餌の量を年々減らしてきた園に対し、不満を募らせたサルが山奥に引きこもり“ストライキ”に打って出たのが原因で、群れの力関係も影響しているとみられる。書き入れ時の7、8月の来園者は例年より計1万人以上も減り、普段は穏やかな園で緊張感が高まっている。 園によると、高崎山はもともと農作物を荒らす野生のニホンザルに餌付けし、観光資源にした施設。山にはB群(約640匹)とC群(約590匹)が生息し、寄せ場には午前にC群、午後にB群が現れるのが一般的だった。 異変が顕著になったのは今春以降。C群は毎月10日ほどの“欠勤”が続き、9月は連続11日を含む22日間、10月も12日間、姿を見せなかった。B群も来ない日があるほか、わずかな時間で山に帰っていくなど、不安定な状態が続いている。 園では、一時2千匹を超えたサルを800匹まで減らそうと、約30年前から1匹あたりの餌を少しずつ減量。B群で「餌への不満が爆発した」(職員)ため、餌が豊富な夏から秋にかけて山奥に引きこもるようになったと推察している。さらに餌場を広げようと山の外に出る様子も目撃され、寄せ場に来た時に木の実をたくさん頬張っているサルも確認されている。 C群は、かつてのリーダー格が恋人を求めて次々にB群に入ったため、急激に弱体化。2016年以降、山の木の実などが減る冬場はB群が寄せ場を占拠するようになった。近づけなくなったC群は「寄せ場に来る習慣自体、なくなった可能性がある」という。 サルの減少に伴い来場者は大幅減。7月は1万4166人(前年同月比4573人減)、8月は3万1290人(同6758人減)、9月は1万3421人(同4059人減)となった。園は今夏、デザートの芋を「紅あずま」などのブランド芋に変え、「スイーツの魅力」でサルを誘ってきたが、結果には結びついていない。 さらに園が懸念するのはC群の消滅だ。今の群れの様子は、覇権争いに敗れて寄せ場に来なくなり、02年に消滅を確認したA群と似ているという。C群には、英国の王女と同名で有名になり、「選抜総選挙」で連覇した人気者のシャーロットもいる。 A群が消滅した直後には、園を去ったサルが付近の畑などで農作物を食べる「猿害」が多発しており、同様の事態も心配している。 サルたちの今後の動きは予断を許さない。園側は「慎重に経過を観察しながら対策を考えるしかない」と気をもんでいる。=2018/11/08付 西日本新聞朝刊=------------------------------------------------(引用終わり)------参照:サルが“ストライキ” 餌への不満爆発、山にこもる 大分の高崎山 西日本新聞https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/463831/道家思想を代表する成語、「朝三暮四」を想起させるニュースです。「朝三暮四」は『列子』と『荘子』の両方にあるんですが、今回は両方とも。❝宋有狙公者,愛狙,養之成群,能解狙之意。狙亦得公之心。損其家口,充狙之欲。俄而匱焉,將限其食。恐衆狙之不馴於己也,先誑之曰「與若茅,朝三而暮四,足乎。」衆狙皆起而怒。俄而曰「與若茅,朝四而暮三,足乎。」衆狙皆伏而喜。物之以能鄙相籠,皆猶此也。聖人以智籠群愚,亦猶狙公之以智籠衆狙也。若實不虧,使其喜怒哉。(『列子』黄帝第二)❞→宋国に猿回し・狙公(そこう)という者がいた。猿を愛して群れを養い、猿の考えを理解することができた。猿たちもまた彼の心を理解していた。狙公は自らの家計を削ってでも、猿たちの腹を満たそうとしたが、ある時それも難しくなり、猿たちの餌を減らそうとした。狙公は猿たちが自分の言葉に従わないことを恐れて先に欺いて言った「お前たちにトチの実をやるのは朝に三個、夕方に四個で足りるか?」と。それを聞いてサルたちはみな怒り出した。そこですぐに「お前たちにトチの実をやるのは朝に四つ、夕方に三つで足りるか?」と言うと、今度はサルたちがみな伏して喜んだ。物事というのはおおよそこのような丸め込む話が多いものだ。 聖人が英知を以て衆愚を丸め込むのも、狙公がサルの群れを丸め込むのと同じような道理だ。実質はなんら変わらないのに、他人を喜ばせたり怒らせたりするのだ。・・・『列子』で言っているのは、たとえば、こういうことです。 --------(引用始め)---------------------------------------------------統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響 2018年09月12日 06時00分 政府の所得関連統計の作成手法が今年に入って見直され、統計上の所得が高めに出ていることが西日本新聞の取材で分かった。調査対象となる事業所群を新たな手法で入れ替えるなどした結果、従業員に支払われる現金給与総額の前年比増加率が大きすぎる状態が続いている。補正調整もされていない。景気の重要な判断材料となる統計の誤差は、デフレ脱却を目指す安倍政権の景気判断の甘さにつながる恐れがある。専門家からは批判が出ており、統計の妥当性が問われそうだ。 高めになっているのは、最も代表的な賃金関連統計として知られる「毎月勤労統計調査」。厚生労働省が全国約3万3千の事業所から賃金や労働時間などのデータを得てまとめている。1月に新たな作成手法を採用し、調査対象の半数弱を入れ替えるなどした。 その結果、今年に入っての「現金給与総額」の前年比増加率は1月1・2%▽2月1・0%▽3月2・0%▽4月0・6%▽5月2・1%▽6月3・3%-を記録。いずれも2017年平均の0・4%を大きく上回り、3月は04年11月以来の2%台、6月は1997年1月以来21年5カ月ぶりの高い伸び率となった。安倍政権の狙い通りに賃金上昇率が高まった形だ。 しかし、調査対象の入れ替えとならなかった半数強の事業所だけで集計した「参考値」の前年比増加率は、1月0・3%▽2月0・9%▽3月1・2%▽4月0・4%▽5月0・3%▽6月1・3%-と公式統計を大きく下回る月が目立つ。手法見直しで、計算の方法を変更したことも誤差が生じる要因とみられる。 誤差に対しては、経済分析で統計を扱うエコノミストからも疑義が相次いでいる。大和総研の小林俊介氏は「統計ほど賃金は増えていないと考えられ、統計の信頼性を疑わざるを得ない。報道や世論もミスリードしかねない」と指摘。手法見直し前は誤差が補正調整されていたことに触れ「大きな誤差がある以上、今回も補正調整すべきだ」と訴える。 厚労省によると、作成手法の見直しは調査の精度向上などを目的に実施した。調査対象の入れ替えは無作為に抽出している。見直しの影響で増加率が0・8ポイント程度上振れしたと分析するが、参考値を公表していることなどを理由に「補正や手法見直しは考えていない」(担当者)としている。 =2018/09/12付 西日本新聞朝刊=--------------------------------------------------(引用終わり)-------- 参照:統計所得、過大に上昇 政府の手法変更が影響 専門家からは批判もhttps://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/448833/次に『荘子』の朝三暮四を。 ❝可乎可,不可乎不可。道行之而成,物謂之而然。惡乎然、然於然。惡乎不然、不然於不然。物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可。故為是舉莛與楹,厲與西施,恢恑憰怪,道通為一。其分也,成也。其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。唯達者知通為一,為是不用而寓諸庸。庸也者,用也。用也者,通也。通也者,得也。適得而幾矣。因是已。已而不知其然,謂之道。勞神明為一,而不知其同也,謂之朝三。何謂朝三。曰狙公賦芧,曰「朝三而莫四。」衆狙皆怒。曰「然則朝四而莫三。」衆狙皆悅。名實未虧,而喜怒為用,亦因是也。是以聖人和之以是非,而休乎天鈞,是之謂兩行。(『荘子』斉物論 第二)❞→一般的に可とされるものが可となり、不可とされるものが、不可となる。道(tao)は、その対象を通じて成り、物は名前を呼ばれて然りとなる。どうしてそうなるのか?それはそうなるべくしてそうなっているのである。どうしてそうならないのか?それはそうならざるべくして、そうならないのである。物はそうなるべくしてそうなる要素があり、本質的にそうなるべき要素を備えている。したがって、すべての物はあるがままの状態で不可なるものはなく、すべての物は可なのである。 茎と柱、ハンセン病患者と伝説の美女・西施、珍しい物と怪しげな物は、道を通じて全てが一である。分裂は完成であり、完成は破壊の始まりである。おおよそ、物が完成した状態であれ、破壊された状態であれ、道においては一である。万物が一であるのは、ただ叡智と共にある人にしか知ることはできず、その人は自分の知見を用いず、全てをあるがままの中庸に委ねる。庸とは用であり、用とは通であり、通とは得である。自適し、自得すれば道(tao)に近づく。あるがままの状態で、人為を加えず、自然の成り行きに任せる。それでいて、そのときに意識を働かせない。これを道(tao)という。精神を議論や分別に使い果たし、本質の一たることを見抜けない、これを「朝三」という。 なぜ「朝三」というのだろう?それには、こんな話がある。狙公(そこう)という猿回しの男が猿たちの前で「朝にはトチの実を三つ、夕方にはトチの実を四つあげよう」と言ったところ、猿たちは怒り出した。そこで猿回しの男は猿たちに「ならば、朝は四つ、夕方には3つでどうだ?」というと猿たちは喜んだ。数字と内容をもてあそび、猿回しの男は猿たちの喜怒を利用してる。これは、猿の本性を見抜いてそうするのである。さればこそ、聖人と言われる人は、事物に囚われず、是非の調和につとめ、自然の成り行きに任せるが、これを両行という。・・・『列子』の場合には、猿回しと猿との間の騙し騙される関係性が強調されており、『荘子』場合には、<道>や<一>といった荘子の思想の根本的なテーマの中に組み込まれています。『荘子』の「朝三暮四」は斉物論の最後「胡蝶の夢」まで繋がっていく部分ですので、いわゆる故事成語としては『列子』的な使われ方の方が多いと思います。 参照:朝三暮四の認識論。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5101/今日はこの辺で。
2018.11.10
コメント(2)
-

金庸先生が亡くなった。
飛雪連天射白鹿笑書神俠倚碧鴛Wikipedia 金庸https://ja.wikipedia.org/wiki/金庸先生、ありがとうございました。
2018.10.31
コメント(0)
-

荘子と進化論 その206。
荘子です。❝子祀、子輿、子犁、子來四人相與語曰「孰能以無為首,以生為脊,以死為尻,孰知生死存亡之一體者,吾與之友矣。」四人相視而笑,莫逆於心,遂相與為友。俄而子輿有病,子祀往問之。曰「偉哉。夫造物者,將以予為此拘拘也。曲僂發背,上有五管,頤隱於齊,肩高於頂,句贅指天。」陰陽之氣有沴,其心閒而無事,跰足而鑑於井,曰「嗟乎。夫造物者,又將以予為此拘拘也。」(『荘子』(大宗師第六))❞→子祀(しき)、子輿(しよ)、子犁(しり)、子來(しらい)の四人が共に語り合っていた「無を頭と為し、生を背中と為し、死を尻と為すようなことを誰ができるだろうか?生死存亡を一体のものとを知る者がいるのだろうか?我々はそういった人物と友諠を結びたいものだ。」四人はお互いに見合ってから笑い、すっかりうちとけて友人同士であることを認めた。その後、子輿(しよ)が病を患った。子祀(しき)が見舞いに行って様子を尋ねたところ、子輿(しよ)は言った。「偉大なるかな。造物者よ、私の身体をこんなにまでひん曲げてしまった。背中はせむしとなるわ、五管は頭の上につくわ、あごはへそを隠すほどに垂れるわ、肩は頭より突き出すわ、挙句に髻は天を向いてしまっている。」陰陽の氣が乱れてそのようになったが、子輿の心は落ち着いたままであった。彼は足を引きずって井戸を覗き込み、自分の姿を眺めながら言った。「ああ。かの造物者は私の身体をこんなにまでひん曲げてしまった。」今日は、「造化(ぞうか)」について、もう少し。『荘子』『列子』には、「造化」という存在につて幾つか記述があります。単純に「化」と言う場合もありますが、『荘子』では「造物者」という言い方もしています。造化は人間の身体な変化だけでなく、精神的な変化にもその影響を及ぼします。 ❝子祀曰「汝惡之乎。」曰「亡,予何惡。浸假而化予之左臂以為雞,予因以求時夜。浸假而化予之右臂以為彈,予因以求鴞炙。浸假而化予之尻以為輪,以神為馬,予因以乘之,豈更駕哉。且夫得者時也,失者順也,安時而處順,哀樂不能入也。此古之所謂縣解也,而不能自解者,物有結之。且夫物不勝天久矣,吾又何惡焉。」俄而子來有病,喘喘然將死,其妻子環而泣之。子犁往問之曰「叱、避、、無怛化。」倚其戶與之語曰「偉哉造物。又將奚以汝為、將奚以汝適、以汝為鼠肝乎、以汝為蟲臂乎。」(『荘子』(大宗師第六))❞→「お前は造化を憎むのかね?」と子祀(しき)が尋ねたので、彼は答えた「そんなことはないな、なんで私が憎む道理があろうか。造化の力が私の左ひじを鶏に変えるのならば、私は鶏として時を告げよ。造化の力が私の右ひじを弾弓に変えるのならば、私はそれでフクロウを落として焼き鳥にしてしまおう。造化の力が私の尻を車輪に変えて、私の心を馬にしてしまうのならば、君を乗せてどこかへ繰り出そう。馬車をあてにする必要はないさ。それに、時が来たら生まれ、時が来たら死ぬ。この命に順えば、哀楽の感情なんてつけ入る隙はない。古人の言った県解の境地だ。自分を解放できないのは、外物の形に囚われているからだ。物が天の理に勝てないのは、今に始まった話ではない。どうして私が造化を憎むなんてことがあるだろう。」急に子來が病に倒れた。息も絶え絶えになり死を迎えそうな子來を取り囲んで妻子が泣き出したことろ、子犁が彼らに向かって言った。「シッ!下がりなさい造化を脅かすんじゃない。」戸のそばから子來に向かって話しかけた。「偉大なるかな、造物者は。お前をどこに連れて行こうとしているのだろう?お前を鼠の肝にするのだろうか?お前を虫の肘にするのだろうか。」この『荘子』の内篇「大宗師篇」には、宗教的な表現が非常に多いんですが、一神教と相通じるような箇所も見受けられます。 ❝子來曰「父母於子,東西南北,唯命之從。陰陽於人,不翅於父母,彼近吾死而我不聽,我則悍矣,彼何罪焉。夫大塊載我以形,勞我以生,佚我以老,息我以死。故善吾生者,乃所以善吾死也。今之大冶鑄金,金踊躍曰『我且必為鏌鋣』,大冶必以為不祥之金。今一犯人之形,而曰『人耳人耳』,夫造化者必以為不祥之人。今一以天地為大鑪,以造化為大冶,惡乎往而不可哉。成然寐,蘧然覺。」(『荘子』(大宗師第六))❞→子來は言った「子が父母に言われたのならば、東西南北のどこにでも、命じられるままに行く。陰陽のはたらきと人との関係は子と父母の間柄と比べるべくもない。かの造化が私を死に誘おうとするのにそれを聞かないのならば、私が強情なだけだ。造化に何の罪があろうか。天地は我を載せるために身体を与え、私を働かせるために生を与え、私が永遠には働けぬよう老いを与え、私を安息にするよう死を与える。すなわち、生を善しとするということは、死を善しとするということである。今、偉大な鋳物師が青銅を溶かして剣を作っているとき、ドロドロになっている青銅が「どうか私を伝説の名剣である鏌鋣の剣(ばくやのつるぎ)にしてください」と叫んだとしよう。鋳物師は「できの悪い青銅だな」と思うことだろうよ。人だって同じように死ぬ間際になって「人間だ、人間以外に生まれたくない。」といえば、造化は「できの悪い人間だ。」と思うだろうよ。天地は大きな炉、造化は鋳物師だとすれば、次なる生はどんな形であったとしても構わないさ。身も心も安らかに眠り、ゆっくりと目覚めるだけだ。」ここまでで一連の造化のお話。最後の鋳物師の例え話などは、生まれ変わりの思想とも読めます。人間の身体が鶏となったり、弾弓になったり、虫になったり。特に最後の「成然寐,蘧然覺。(安らかに眠り、ゆっくりと目覚めるだけだ。)」という部分などは、胡蝶の夢とも対応するところですが、カフカがいかにして『荘子』の影響を受けたのかがよく分かる部分だと思います。参照:カフカと荘子。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5106/で、今回は、「浸假而化予之尻以為輪,以神為馬,予因以乘之,豈更駕哉。(造化の力が私の尻を車輪に変えて、私の心を馬にしてしまうのならば、君を乗せてどこかへ繰り出そう。馬車をあてにする必要はないさ。)」のお尻を車輪にする方です。Lady Gaga-Born this way https://www.youtube.com/watch?v=xl0N7JM3wZk2011年に大ヒットしたレディ・ガガの❝Born this way❞って荘子っぽいんです。特に、サビが荘子の言っている「懸解の境地」にやたら近いんです。ちなみに「懸解」というのは、「天帝の軛から解放された人」くらいの意味です。『適來、夫子時也。適去、夫子順也。安時而處順、哀樂不能入也、古者謂是帝之縣解。』(『荘子』養生主 第三) →彼がたまたま生まれたのはその時に巡りあったからであり、彼がたまたまこの世を去るのは、彼がその順に従ったまでのこと。天の道理にしたがって、時に安んじれば、哀楽の入り込む隙はない。古人はこれを天帝から解放された縣解の境地と言ったのだ。参照:人間万事、ツァラトゥストラの偶然。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5090/「時に安んじて順に處(お)れば、哀楽も入る能(あた)わず」。「人はどう生まれ、どう死ぬのか」なんていう事柄は、哲学的な命題としては必要ですが、これを完全に把握するということは不可能です。我々は選択権をもって生を得たわけでもないし、人の死の日時を予言する帳簿をもっているわけでもありません。そういう重要なことについて人間は一喜一憂しがちですが、いくら喜んだり憂いたりしても、いくら他人の論評を聞いたとしても、結果が変わるわけでもないんですよね。上記の荘子の言葉は「いかなる運命をも受け入れて、あとは今ある現実を生きる。」くらいの意味だと私は解釈しています。❝I’m beautiful in my wayCause God makes no mistakesI’m on the right track babyI was born this wayDon’t hide yourself in regretJust love yourself and you’re setI’m on the right track babyI was born this way(上記「Born this way」より)❞(私はこのままで美しいだって、神はミスを犯さないから私は今正しい道にいるbaby,私はこうやって生まれたの自分を隠したり、後悔なんてしないでただ、自分を信じてあげて私は今正しい道にいる私はこうやって生まれたの)参照:Lady Gaga with Maria Aragon / Born This Way LIVE レディーガガhttps://www.youtube.com/watch?v=TH4NLl3REN4❝You’re black, white, beige chola descentYou’re Lebanese, You’re OrientWhether life’s disabilitiesLeft you outcast, bullied or teasedRejoice and love yourself todayCause baby you we’re born this way(同上)❞(あなたが黒人だろうと白人だろうとベージュだろうと、混血(チョーラ)だろうとレバノン人だろうと 東洋人だろうと障碍者であろうと 仲間はずれにされていじめられようと今日一日自分を受け入れて愛してあげてbaby,だってあなたはこうやって生まれたの)❝No matter gay, straight, or biLesbian, transgendered lifeI’m on the right track babyI was born to survive(同上)❞(ゲイでもストレートでもバイでもレズでもトランスでも関係ないわ私は今正しい道にいる私は生き抜くために生まれたの)この❝Born this way❞は、マイノリティの人びとの応援歌でもあるわけですが、レディーガガは『聖書』の記述を根拠に、キリスト教徒が歴史的に迫害してきた同性愛者に対してもエールを送っています。語彙そのものはキリスト教徒っぽいんですが、実は内容は挑戦的です。参照:戦国日本とソドムの罪。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201806110000/-----(引用始め)---------------------------------------------ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 ローマ(CNN) ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王が同性愛者の男性に、創造主である神が「あなたをそのようにつくった」との言葉をかけ、性的指向は「問題ではない」と言明したことが分かった。 チリのカトリック聖職者らによる性的虐待問題をめぐり、先月バチカンで法王と面会した虐待被害者の1人、ホアン・カルロス・クルーズさんが、CNNとのインタビューで語った。 クルーズさんは法王と3日間にわたって面会した。この中で自身が同性愛者だと告げると、法王は「それは問題ではない。神はあなたをこのようにつくり、このままのあなたを愛している」「あなたも自分自身を愛しなさい。人々の言うことを心配してはいけない」と話したという。 同性愛を「客観的な逸脱」と見なすローマ・カトリック教会の立場とは、一線を画した発言といえる。 バチカンの報道官は21日、CNNの取材に対し、「法王の個人的な会話については通常コメントしない」との方針を示した。 クルーズさんを虐待した人物は2011年、バチカンで有罪を言い渡されている。 チリのカトリック教会では性的虐待問題の発覚を受け、34人の司教全員が先週、辞任を申し出た。---------------------------------------------(引用終わり)-----参照:ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 CNN.co.jphttps://www.cnn.co.jp/world/35119558.html・・・で、今のローマ法王はまんざらでもないんです。ちょくちょく推敲します。今日はこの辺で。
2018.09.02
コメント(0)
-

ラビオ氏の夢を思う。
本題に入りたいものの、気になったので。------(引用はじめ)----------------------------------------------------ロシアW杯 北海道のタコ「全試合的中」…でも既に出荷毎日新聞 2018年6月29日 11時37分(最終更新 6月29日 12時34分) サッカーのワールドカップ(W杯)ロシア大会を巡り、北海道小平(おびら)町のミズダコ「ラビオ君」が日本代表の1次リーグ3試合の結果予想をすべて的中させ、話題を呼んでいる。 小平町はタコ箱を使ったミズダコ漁が盛ん。地元漁師の阿部喜三男さん(51)が特産品を広く知ってもらおうと思いついた。 19日に水揚げされたミズダコに小平を逆さまにした名を付け、直径約2メートルのビニールプールに「日本」「対戦相手」「引き分け」のかごを入れてどこに近づくかで占った。ラビオ君は初戦のコロンビア戦で「勝ち」を予想。セネガル戦は「引き分け」、ポーランド戦は「負け」とすべて的中させた。 3戦全部を当てる確率は27分の1。阿部さんは「全部的中したうえ、日本代表が予選突破を果たせてうれしい」と笑顔を見せた。ラビオ君はすでに出荷され、決勝トーナメントは新たに捕獲するタコで占う予定で、「第2のラビオ君にも全試合を的中させてもらい、日本が優勝してほしい」と話した。【渡部宏人】----------------------------------------------------(引用おわり)------❝宋元君夜半而夢人、被髮?阿門、曰「予自宰路之淵、予為清江使河伯之所、漁者余且得予。」元君覺、使人占之、曰「此神龜也。」君曰「漁者有余且乎?」左右曰「有。」君曰「令余且會朝。」明日、余且朝。君曰「漁何得?」對曰「且之網、得白龜焉、其圓五尺。」君曰「献若之龜。」龜至、君再欲殺之、再欲活之、心疑、卜之、曰「殺龜以卜、吉。」乃刳龜、七十二鑽而無遺筴。打開字典顯示更多訊息。仲尼曰「神龜能見夢於元君而不能避余且之網。知能七十二鑽而無遺筴。不能避刳腸之患。如是、則知有所困、神有所不及也。雖有至知、萬人謀之。魚不畏網而畏鵜?。去小知而大知明、去善而自善矣。」嬰兒生無石師而能言、與能言者處也。❞(『荘子』外物 第二十六)→宋の元君が夜中に夢を見た。髪を振り乱した男が門の外から覗き込むようにして「私は宰路の淵というところから参りました。清江の使いとして河伯のところへ向かう途中、余且という名の漁師に捕らわれてしまいました。」と訴えていた。元君はそこで目が覚めた。家来に夢占いをさせると、「それは神亀です」という。元君は「漁師の中に余且という名の者はおるか?」と尋ねると、左右の家臣が「おります」という。元君は「明日、その余且なるものを連れて参れ」と命じた。翌朝、余且に「漁をして何を獲った?」と尋ねると、余且は言った「私の網に白い亀がかかりまして、その大きさは五尺四方にもなります。」「ならば、その亀を献上せよ」と元君は命じた。その亀を元君は、殺すべきか、生かすべきかを悩んだ末、占いに頼ることにした。占いでは「亀を殺して、その甲羅で占えば吉」との結果が出た。そこで、亀の甲羅を裂き、占ってみると七十二回ともハズレがなかった。この話について仲尼曰く「この神亀は元君の夢枕に立てるほどのちからがありながら、漁師の網から逃れる術を知らなかった。七十二回も未来を的中させながらも、腸をえぐられる苦しみから逃れることがかなわなかった。このように、知にも人知を越えたちからにも行き詰まるものがあり、そのちからの及ばぬところで俗人の網にかかるものだ。魚は、鳥におびえていながら、人の網を恐れることを知らない。さかしらな知に囚われず大いなる叡智と共にあり、世俗の善を捨てされば、自ずと善のこころが芽生える。赤ん坊が生まれたままの状態から、大先生の教えなど請わずに立派に言葉を話せるようになれるのは、ただ、話のできる者と共にいたからだ。」❝莊子釣於濮水、楚王使大夫二人往先焉。曰「願以境?累矣」莊子持竿不顧、曰「吾聞楚有神龜、死已三千?矣、王巾笥而藏之廟堂之上。此龜者、寧其死為留骨而貴乎、寧其生而曳尾於塗中乎?」二大夫曰「寧生而曳尾塗中。」莊子曰「往矣、吾將曳尾於塗中。」❞(『荘子』秋水 第十七)→荘子が濮水のほとりで釣りをしていたところ、楚王の二人の使者がやってきて「あなたに楚の国の政をお願いしたい」と言ってきた。荘子は釣竿を持って、釣り糸を見つめながらこう言った。「楚の国には神龜という亀がいるそうですね。死んでからすでに三千年も経っていて、楚王はこれを大事にして、廟堂に祀っていると聞きます。その亀の身にすれば、死んで骨を大事に祀られていることを望んだのでしょうか?それとも、泥の中で尻尾を振ってでも生きていくことを望んだでしょうか?」使者は「泥の中でも生きていたいと望んだでしょうな」と答えた。すると荘子はこう言った「お行きなさい。私も泥の中で生きていたい。」ラビオ氏のご冥福をお祈りいたします。蛸壺や はかなき夢を 夏の月 芭蕉今日はこの辺で。
2018.06.29
コメント(0)
-

戦国日本とソドムの罪。
ちょっと古いニュースですが。-----(引用始め)---------------------------------------------ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 ローマ(CNN) ローマ・カトリック教会のフランシスコ法王が同性愛者の男性に、創造主である神が「あなたをそのようにつくった」との言葉をかけ、性的指向は「問題ではない」と言明したことが分かった。 チリのカトリック聖職者らによる性的虐待問題をめぐり、先月バチカンで法王と面会した虐待被害者の1人、ホアン・カルロス・クルーズさんが、CNNとのインタビューで語った。 クルーズさんは法王と3日間にわたって面会した。この中で自身が同性愛者だと告げると、法王は「それは問題ではない。神はあなたをこのようにつくり、このままのあなたを愛している」「あなたも自分自身を愛しなさい。人々の言うことを心配してはいけない」と話したという。 同性愛を「客観的な逸脱」と見なすローマ・カトリック教会の立場とは、一線を画した発言といえる。 バチカンの報道官は21日、CNNの取材に対し、「法王の個人的な会話については通常コメントしない」との方針を示した。 クルーズさんを虐待した人物は2011年、バチカンで有罪を言い渡されている。 チリのカトリック教会では性的虐待問題の発覚を受け、34人の司教全員が先週、辞任を申し出た。---------------------------------------------(引用終わり)-----参照:ローマ法王、同性愛男性に「神があなたをそのようにつくった」 CNN.co.jphttps://www.cnn.co.jp/world/35119558.html例えば、『聖書』の記述の中で神がソドムの街を滅ぼしたきっかけが同性愛であるという暗示からもわかるように(現代でも使われる「ソドミー」の語源はソドム。)キリスト教圏においては、伝統的に同性愛は「罪」として認識されていました。この見解は、戦国時代に日本に来てキリスト教を布教しようとしたイエズス会の宣教師たちも同様です。したがって、フランシスコ・ザビエルの日本での布教活動についての記録にも、当時日本人の習俗であった男色についての記録があります。参照:Wikipediya ソドミーhttps://ja.wikipedia.org/wiki/ソドミー -----(引用始め)--------------------------------------------- ファン・フェルナンデス〔鹿児島で信者になったベルナルド〕と私とは日本〔で最強〕の領主(大内義隆。一五〇七-五一年)がいる山口と呼ばれる地へ行きました。この町には一万人以上の人びとが住み、家はすべて木造です。この町では武士やそれ以外の人びと多数が私たちの説教する教えがどんな内容のものか、知りたがっていました。 そこで私は幾日間にもわたって街頭に立ち、毎日二度、持って来た本を朗読し、読んだ本に合わせながら、いくらか話ををすることにしました。大勢の人が説教を聞きに集まってきました。私たちが〔街頭で〕説教していた教えについて質問するために高い身分の武士の家に呼ばれて〔キリスト教が〕彼らが信じている教えよりも優れているなら、帰依したいと言われました。神の教えを聞いて多くの人びとは喜びましたが、ある人たちは神の教えをあざ笑い、またある人たちは嫌悪しました。私たちが街の中を歩いていると、子供や大人が後についてまわって、私たちをあざ笑い、「この人たちは、私たちが救われるためには、神を拝まなければいけないし、天地万物の創造主のほかに私たちを救える者はいないと言っている人たちだよ」といい、他の人は、「この人たちは、一人の男は一人の妻しか持ってはならないと説教している人たちだよ」と言い、〔また〕他の人は「この人たちは男色の罪を禁じている人たちだ」と言いました。つまり、これらの悪事が彼らのうちにごく普通に行われているために、〔このようにはやしたてるのです〕。さらに他の人たちは、私たちの教えの十戒を一つひとつ取り上げては私たちをあざ笑いました。 このようにして私たちが家いえに〔招かれたり〕街頭に立って説教して宣教する幾日かが過ぎたのち、その町に住んでいる山口の領主は、私たちを招くよう命令され、種々様々なことをお尋ねになりました。どこから来たのか、どのようなわけで日本へ来たのか、などと尋ねられました。私たちは神の教えを説くために日本に派遣されたもので、神を礼拝し、人類の救い主なるイエズス・キリストを信じなければ誰も救われる術はないと答えました。領主は神の教えを説明するように命じられましたので、私たちは〔信仰箇条の〕説明書きの大部分を読みました。読んでいたのは一時間以上にも及びましたが、そのあいだ、領主はきわめて注意深く聞いておられました。その後私たちは〔御前を退出し〕領主は私たちを見送ってくださいました。私たちはこの町に幾日も逗留して、街頭や家の中で説教しました。多くの人びとはキリストの生涯を聞くのを喜び、ご受難の件(くだり)に至ると涙を流しました。(東洋文庫刊『聖フランシスコ・ザビエル全書簡3』「書簡第九六 ヨーロッパのイエズス会員にあてて 一五五二年一月二九日 コーチンより」河野純徳訳)---------------------------------------------(引用終わり)-----フランシスコ・ザビエルが山口で布教した際の出来事について書かれた手紙からですが、ザビエルが当時の日本の風習の中で、男色は『聖書』の教えと相いれないものであり、布教の際にも日本人に指摘していたことが分かります。当時の男色といえば武田信玄や織田信長が有名ですが、山口の戦国大名・大内義隆についてはルイス・フロイスの『日本史』に詳しいです。-----(引用始め)--------------------------------------------- こうした苦労の多い旅を数日重ねた後、一行は周防国の首都で、非常に人口も多く上品な山口の市(まち)に至った。そこ(にいる)国主は大内(義隆)殿といい、当時にあっては日本でもっとも有力者であった。彼の身分と家臣たちから受ける奉仕に際しての栄華は、他のすべての(諸国王)のそれに優り、浪費と放恣な邪欲にひたっていたが、とりわけ、彼もまたあの自然に反する破廉恥な罪悪にひどく溺れていた。司祭は一人の身分の高い貴人に対し、自分が国主の前に罷り出られるように、そしてさらに自分が説く教えを聞いた後、(国主)がその国で布教する許可を与えてくれるように国主に働きかけてもらいたいと懇願した。(中略)国主は上機嫌で彼らと語り、彼らの(日本までの)航海やインドならびにヨーロッパのことについて幾つかのことを質問した後に、彼らが自領で説きたがっている新しい教義についてどのようなことを言(おうとするの)か聞きたがった。そこで司祭はジョアン・フェルナンデス修道士に、彼らが先に日本語に翻訳しあった(例の)帳面(カルタペシオ)によって宇宙の創造とか(デウスの)戒律のことを(国主)に読み聞かせるように命じた。そして彼らが偶像崇拝の罪とか、日本人が溺れこんでいる(種々の)誤りについて述べているうちに、ソドマ(の罪)に(関する箇条に)及んだが、そのような忌むべきことをする人間は豚よりも汚らわしく、犬その他理性を備えない禽獣よりも下劣であると述べた。この箇条を読みあげられると、国主はただちに心に強い衝撃を受けたらしく、この教えに対して激昂したことを表情に表したので、(上記の)貴人は彼らに退出させよと合図した。それで彼らは国主に別れを告げたが、(国主)は彼らに一言も応答しなかった。(国主)は彼らに一言も応答しなかった。(ともあれ)修道士は、(国主)が自分たちを殺すように命じるだろうと考えた。(中央公論社刊 『日本史6』松田毅一・川崎桃太訳)---------------------------------------------(引用終わり)-----前述のザビエルの書簡に書かれてある部分、ザビエルが大内義隆に謁見したときの証言をもとにルイス・フロイスが記述した箇所です。同性愛について言及した部分も直接的な表現になっています。ザビエルの書簡では大内義隆に歓迎されていたように書かれてありましたが、ルイス・フロイスの『日本史』では、ソドムの罪として指摘したザビエルの側が大内義隆の不興を買ったというような書き方になってます。実際、山口での布教は成功とは言えなかったわけで、フロイスの記録もあまり矛盾はないと思われます。-----(引用始め)--------------------------------------------- 彼らは、人の集まりがより多い街路や道の四つ辻に立って、修道士がまず(翻訳した)書物から世界の創造(に関する箇条)を読んだ。そして彼はそれを読み終えると、ついで人々に向かい、日本人はことに次の三つの点で何という大きい悪事を行っていることかと大声で説いた。 第一は、(日本人)は、自分たちを創造し、かつ維持し給う全能のデウスを忘れ、(デウス)の大敵である悪魔が祀られている木石、その他無感覚な物(質)を礼拝している(ことである)。 第二は、(日本人が男色という)忌わしい罪(に耽っていることである)。---(修道士)は彼ら(聴衆たち)に、その(罪が)いかに重く汚らわしいか訓戒し、天地の主なるデウスがこの悪行のために、極度の重い懲罰をこの世で与え給うことを人々の眼前に思い浮かばせた。 第三は婦女は子供を産むと、養育しなくてよいように殺してしまったり、(胎児を)おろすために薬をを用いること。---それはきわめて残忍かつ非人道的なことである。 修道士が人々に(このように)説教していた間、司祭は彼の傍に立って、修道士の説教に好い成果が上がるようにと、また聴衆たちのためにも心の中で祈っていた。(同上)---------------------------------------------(引用終わり)-----街頭で行われた説教でも男色についての部分は触れられています。日本人の悪事を指摘する場合に、偶像崇拝批判の後、子殺しの前に男色をあげつらうというのがいかにも。しかし、こういった宣教師の言動を通してみると、現在の法王の発言というのは、まさに隔世の感というような趣きです。ちょっとここについてはいろいろと足します。今日はこの辺で。
2018.06.11
コメント(0)
-

万暦二十六年のPM2.5。
-----(引用始め)--------------------------------------------------世界人口の95%超、汚染された空気を吸って生活 米研究2018.04.18 Wed posted at 16:47 JST 世界各地の大気汚染を調べている米民間機関、健康影響研究所(HEI)は17日に発表した年次報告書の中で、世界の人口の95%以上が汚染された空気の中で暮らしている現状を明らかにした。 汚染した空気を長期間吸っていたために脳卒中や心臓発作、肺のがんや慢性疾患を起こし、2016年に死亡した人は、世界で計610万人に上ったと推定される。死因となる健康リスクのうち、空気の汚染は高血圧、不適切な食生活、喫煙に次ぐ第4位に入っているという。 報告書によると、空気の汚染による死亡例の半数以上が中国とインドで起きている。16年にインドと中国で報告された屋外での大気汚染による死者は、それぞれ110万人に上った。大気汚染の状況は中国でやや改善されたのに対し、インドとパキスタン、バングラデシュでは10年以降で急激に悪化した。 報告書は、調理や暖房にまきや炭などの固体燃料を使うことで起きる屋内の空気汚染も取り上げている。16年には世界で計25億人がこうした汚染にさらされていた。 大気汚染と屋内での空気汚染の両方にさらされている人の大半は、アジアやアフリカの中・低所得国に住む。空気の汚染が原因で死亡した人のうち、インドでは4人に1人、中国では5人に1人が屋内外の両方で汚染した空気を吸っていた。 ただし、世界で固体燃料に頼って生活している人の数は、1990年の36億人から16年には24億人に減少していたという。--------------------------------------------------(引用終わり)-----参照:世界人口の95%超、汚染された空気を吸って生活 米研究https://www.cnn.co.jp/fringe/35117971.htmlUnder the Dome (English subtitle,Complete) by Chai Jing: Air pollution in Chinahttps://www.youtube.com/watch?v=V5bHb3ljjbc・・・このニュースを読んで思い出したものがあったので、メモ。以下は、今から400年ほど前、1598年(万暦26)に北京を訪れた宣教師の記録です。-----(引用始め)-------------------------------------------------- 〔一五九八年九月八日 - 一二月五日〕 この王都は王国全土の北端に位置し、王国全土の北の城壁(万里の長城)から100ミリオと離れていない。広さと人口はナンキーノ(南京)よりやや少ない。また道路および建物の堅牢さと美しさの点でもナンキーノに一歩を譲るが、軍人と官吏の数ではまさっている。(中略)王宮(紫禁城)は内側の市壁の奥にあり、内側の門(正陽門)を入ってすぐのところから北側の門にまで達し、その中心部分全部を占める。したがって、他の人々は王宮の両翼に住んでいるということになる。そのため、王宮の全市を占めているように見える。ナンキーノの王宮に比べると小さいが、はるかに壮麗である。何と言っても、あちらの宮殿は、国王が行くということはまったくなく、不在であるために、日に日に荒廃しているが、こちらの宮殿は、それとは逆に国王が居住しているので、日ごとに新しくなってゆく。 煉瓦や石を敷き詰めた街路がごくわずかしかないので、いつも埃や泥で汚れている。しかもここではあまり雨が降らないので、地面がたいへん埃っぽい。不思議なのは、かすかな風が吹いただけでも、ひどい埃が立つことだ。それが家の中に入りこみ、一番奥まった部屋にまで侵入してきて、防ぎようがない。それゆえ、いつもすっかり汚れてしまう。 それゆえ、ここには珍しい習慣がある。すなわち、身分の高低にかかわりなく、馬に乗る人も徒歩でゆく人も、あらゆる人びとが、必要に応じて、頭からすっぽりと黒い覆いの袋をかぶってゆく。それもこの埃のためである。しかもそれには道で人から気づかれずにすむという効用がある。道で友人同士の挨拶やお辞儀のために、いちいち馬から降りずにすませる口実にそれをつかう。そのほか、貧しい人びととか、召使いである自分の身分を隠して外出したい他の人びとも、このおかげで自由に歩くことができる。わたしたちにとっても、この習慣は大いに役に立った。というのも、あのころは外国人が街路を公然と歩きまわるのは危険であったし、多くの物見高い人びとが神父たちのうしろについてくることになったからである。このおかげで、この第一回目のときも、次回のときも、神父たちは市内を隈なく歩きまわり、門を出入りして、望みの場所へ行っても、誰からも見咎められずにすんだ。 市街は広く、泥と埃にひどく汚れて、そこを徒歩でゆくのは困難である。それゆえ、人びとは誰もが必要に応じて、馬や他の駄獣に乗ってゆくことが広く慣習化している。そうした駄獣は市の門とか王宮の門、また橋やアーチなのど主だった場所にだくさん置かれている。そしてわずかな金を出せば、老練の口取りがうしろについたり、馬の手綱をとって、市内のどこへでも望みの場所につれていってくれる。彼らは官吏や貴人を知っているばかりか、役所や主要な場所なども知っている。街路、通り、路地に至るまで、すべてがその名称とともにたいそう正確に記された本も刊行されている。また、覆いつきの轎に乗ることもできる。各所にたくさんの轎かきが雇われるのを待ってたむろしているからだ。しかし、ナンキーノや他の土地に比べると料金は高い。 この地には一切の必需品が豊かにあるが、大部分は他の土地から来たものだ。このために、また、こうであるからこそ、王都とか国王の座所では、すべてがきわめて高価なのだ。わずかに薪だけはひどく不足しているにもかかわらず、例の凝灰岩ないし瀝青(石炭)が豊富に地中から採掘されるので、この不足を補っている。これは食べ物を料理するのに用いたり、冬がひどく寒いこの地の暖房に利用する。それゆえ、一般に人びとは夜になると煉瓦の寝台に寝る。その内側には溝があり、室内でこの凝灰岩を燃やした火が、あるいは火の熱気が、この溝をとおして入ってくるようになっている。この凝灰岩は、いったん燃えつくと、たいへん火持ちが良いので、一昼夜のあいだずっと火のたえることがない。この習慣はこの都市に限らず、この北部諸省ではどこにもある。 この地の人びとは南部の人びとにくらべて素朴である。戦争には強いが、科学とか文学の才能という点では劣っている。 この王都に来て、神父たちはついに、この王国が大カタイオ(契丹)であり、このパッキーノ市がカンバルー(汗八里、大都)、すなわち、チーナ国王大カーン(可汗)の王都であると改名することができた。(岩波書店刊 大航海時代叢書第Ⅱ期8『リッチ 中国キリスト教布教史Ⅰ』より)--------------------------------------------------(引用終わり)-----マテオ・リッチが北京を訪れた当時の様子なんですが、北京市街の埃っぽさについて詳細に書いてあります。また、中国ではすでに定着していた石炭(おそらくコークス)を利用した調理法や、現在でも活用されている暖気(ヌアンチー)などについての記録もあります。これ、一部は現在でいうところのPM2.5の原因ですよね。あと、埃を防ぐために住民が顔を覆うという風習とその副作用ともいうべき効能についての記載も興味深いです。参照:Wikipedia 粒子状物質https://ja.wikipedia.org/wiki/粒子状物質#PM2.5(微小粒子状物質)参照:中国冬の必需品「暖気」 大気汚染の原因の1つに 中国ビジネスヘッドラインhttp://www.chinabusiness-headline.com/2013/11/39523/-----(引用始め)-------------------------------------------------- アメリカでマスクをする時はご注意をアメリカに長く滞在している人は気付くかもしれないが、アメリカ人はマスクをしない。最近、急に冷え込んできたため咳が出始め、周りの人に風邪をうつさないようにと、職場にマスクをしていくことにした。浮いた存在になることは間違いないが、健康と引き換えなら仕方のないことと腹をくくった。考えてみると、アメリカでマスクをするのはこれが初めてのことだ。しかし、駐車場からオフィスまで歩いていると、人事のパトリシアが近づいてきて、「オフィスで何かあったの」と不安げな表情で聞いてきた。やっぱりきたかと思いながら、「いや、ただ、風邪をひいてるだけだよ」と説明。アメリカ人がマスクを見て想像するのは、鳥インフルエンザのような深刻な疫病の流行であって、やたらめったらにしていると、不安をかきたててしまう。そしてオフィスに足を踏み入れると、みんなの鋭い視線を感じた。警察担当記者のビアトリスは、ボクを見るなり、「あんた、ほんとアジア人ね」と大爆笑。空港で見かけるアジア人はマスクをしているというのが、彼女のイメージらしい。追い討ちをかけるように、市政担当記者のブルックが、「他人にうつさないためにしてるの?それとも自分が風邪を引かないようにするためなの?どっちにしろあんまり意味がないと思う」と言い放ち、面白がってiPhoneでとった写真をfacebookにのっける始末。アメリカでは、うがいやマスクが日本のように浸透していない。むしろ、どちらも医学的に効果がないという見方が一般的である。教育担当記者のナターシャは、「アジア人はファッションにうるさいのに、どうしてマスクはするの」と質問してきた。逆にこっちから、「どうしてマスクをしないの」と聞いてみると、周りの目が気になるからという意見が大半をしめた。アメリカ人の目から見ると、マスクはダサいのだろう。ある光景が、見る人の育った文化によって、全く異なった見え方をしてしまう例であろう。ちなみに、アメリカで男性が小さなカバンを持っていると、man purse(男のハンドバッグ)と呼んで馬鹿にされる。その後もデスクの横を誰かが通る度に、「それは何なの」と尋ねられた。ボクがいない間に、ナターシャにコソコソと、トモヤに何があったのかと聞く輩もいたらしい。正直、予想以上の反応であった。みんなのためにと思ってやったことが、逆に同僚の不安をあおってしまった。意地もあって、今日はマスクをつけてずっと仕事をしたが、さすがにマスクをして裁判所に行くのはやめようと思う。--------------------------------------------------(引用終わり)-----米国記者生活 2010年12月9日 アメリカでマスクをする時はご注意をhttp://www.tomoyashimura.com/2010/12/blog-post_08.html 自分を隠したい 広がる“マスク依存”http://www.nhk.or.jp/ohayou/digest/2017/02/0201.htmlあとで推敲します。
2018.05.07
コメント(0)
-

荘子と進化論 その205。
------(引用始め)-------------------------------------------------- 「働かない働きアリ」が組織に必要な深いワケ自然科学に学ぶマネジメントの「理(ことわり)」(前編)2018.3.26 川本裕二 物理学、生物学、化学など自然界に存在している様々な法則性、「理(ことわり)」を明らかにする自然科学。ガリレオ・ガリレイ、ニュートン、ダーウィン、アインシュタインなど誰もが名前を知っている偉人から名もなき科学者まで多くの先達の努力によって様々な知見が発見され、現代においても日進月歩で研究が進み続けています。 この自然科学によって見出された知見から人と組織が織りなすマネジメントの世界を見てみることで、これまでには見えづらかった、しかし、本質的なマネジメントの「理(ことわり)」が見えてくることがあります。「自然科学に学ぶマネジメントの『理(ことわり)』」では、物理学、生物学、大脳生理学などの自然科学の知見をご紹介しながら、マネジメントの「理(ことわり)」を2回にわたって探求していきます。 働かない「働きアリ」がいる? 今回のテーマは、「アリの生態学×ダイバーシティ」です。 皆さんは「働きアリ」という言葉を聞いたことがあると思います。アリのコロニー(巣)の中で、餌を採取してきたり、卵の世話をしたりと、巣の外や中での様々な仕事をする種類のアリを働きアリと呼びます。 働きアリという名前が付いているぐらいなので、さぞかし働き者なのだろうと思いますが、実は、アリのコロニーには働かない働きアリがたくさんいます。 アリのコロニーを観察してみると7割の働きアリは、目的もなくフラフラしている、自分の体を舐めている、動かないなど、働いていません。また、1カ月間継続的に観察したとしてもほとんど何もしない働きアリが2割もいます。極め付けは、生まれてから死ぬまでほとんど働かない働きアリもいるそうです。もはや、さぼりアリですね。 その一方で、9割の時間は働いている働きアリも存在します。 違いは“腰の重さ”にあった! 同じアリにもかかわらず、なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。 アリは思考能力を持たないので、人間のように「バレなさそうだから手を抜いておこう」と考えているわけではなさそうです。北海道大学大学院農学研究院 准教授の長谷川英祐氏の研究によると、働くアリと働かないアリの違いは、ズバリ「腰の重さ」にあるそうです。例えば、餌が見つかったなどの特定の刺激に対して、反応しやすい(腰が軽い)、しにくい(腰が重い)、という違いをアリは遺伝的に持っているのです。これを専門的には「反応閾値(はんのういきち)」と呼んでいます。 アリの前に何らかの仕事が現れた時には、まず最も反応閾値が低い(腰が軽い)アリが動き、次の仕事が現れた時には次に閾値が低いアリが動くというかたちで仕事の分担がなされています。そのため、一定量以上仕事が増えないかぎり、閾値が高い(腰が重い)アリはいつまでたってもふらふらしたり、自分の体を舐めていたりしているということが起きているのです。 働かない働きアリは、なぜいるのか? このようなアリの社会生態は、一見、非効率に見えるかと思います。全ての働きアリが一生懸命働いた方が、コロニーは繁栄しそうですよね。 しかし、実際には、このような社会生態を持ったアリが滅びるのではなく、種として生き延びているということは「生存戦略としては、実は、適している」ということを意味します。逆に言うと、全員が“働き過ぎの働きアリ”だと、種が存続していく上では不都合なことがあるのです。 例えば、全てのアリの反応閾値が同じだった場合、餌が発見されたら一斉にみんな出て行ってしまいますよね。すると次の餌が発見された時に誰も対応できなくなります。外敵が現れるなんてことがあったらもう大変ですよね。 それから、アリにも「過労死」があると言われていて、全員が働き過ぎると一気に働き手が死んでいってしまうということが起きる可能性があります。 もし、自分がそんな習性を持つアリの女王アリだったとしたら心細すぎて夜も眠れません。 また、実は、反応しにくいアリも、全ての刺激に反応しにくいわけではなかったりします。「餌の発見!」という刺激には反応しにくいアリでも、「敵襲来!」という刺激や「巣壊れた!」「卵壊れた!」といった別の刺激には反応しやすかったりします。 つまり、反応閾値の違いは優劣ではなく個性・個体差であり、多様な個性・個体差がある(ダイバーシティがある)からこそ、状況や環境の様々な変化に適応し、種として存続する確率を高めることができているのです。 全体を見てこのような社会生態を計画をした存在がいるわけではありません。個々の遺伝子レベルでこうしたシステムが形づくられていることを考えると、長い年月を経ながら生物の生態に自然と備わっていった叡智の偉大さを改めて感じます。 組織には多様な価値基準が必要 さて、アリの生態を見てきたところから、今度は私たちのフィールドであるビジネスの文脈に頭を切り替えていきたいと思います。働かない働きアリがいるというアリの社会生態から見えてくるマネジメントの「理(ことわり)」は何でしょうか。 様々なことが言えますが、中でも大きなものは、「多様性は組織が生き残る確率を高める」ということでしょう。 ダイバーシティ(多様性)のない組織は一時期的にとても繁栄することがあったとしても、劇的な環境変化が起こった際には一気に崩壊する危険性が高まります。 私たちがマネジメントを行う際、業績へのプレッシャーからどうしても短期的な成果に結び付く特定の価値基準だけで人を評価判断しがちになります。しかし、そのことは組織に多様性が生まれる余地を徐々に奪い、長期的には生き残る確率が下がってしまう危険性を孕んでいます。 もし、10年、20年、さらには100年と長く栄え続ける会社を創ろうとするのであれば、多様な価値基準を持ち、多様な人が活かされる組織にすることが重要なのです。-------------------------------------------------(引用おわり)------参照:「働かない働きアリ」が組織に必要な深いワケhttp://jbpress.ismedia.jp/articles/-/52640非常に荘子的なのでメモ。❝夫富者、苦身疾作、多積財而不得盡用、其為形也亦外矣。夫貴者、夜以繼日、思慮善否、其為形也亦疏矣。人之生、與憂俱生、壽者惛惛、久憂不死、何苦也!其為形也亦遠矣。烈士為天下見善矣、未足以活身。吾未知善之誠善邪、誠不善邪?若以為善矣、不足活身。以為不善矣、足以活人。故曰「忠諫不聽、蹲循勿爭。」故夫子胥爭之以殘其形、不爭、名亦不成。誠有善無有哉?今俗之所為與其所樂、吾又未知樂之果樂邪、果不樂邪?吾觀夫俗之所樂、舉群趣者、誙誙然如將不得已、而皆曰樂者、吾未之樂也、亦未之不樂也。果有樂無有哉?吾以無為誠樂矣、又俗之所大苦也。故曰「至樂無樂、至譽無譽。』天下是非果未可定也。雖然、無為可以定是非。至樂活身、唯無為幾存。❞(『荘子』至楽篇 第十八)→ 富む者は我が身を磨り減らして働き、多くの財を積み上げながら、その全てを使うこともできない。これは財貨という外物を得るために働いているのであって道にはほど遠い。身分の高い者は、夜を日に継いで、仕事の成否に思い悩んで休むこともない。これもまた外物を得るために働いているのであって、道には遠い。人の一生は、生まれてから死ぬまで憂いがつきまとうものだ。長生きをする者は、ぼんやりとしていて憂いを抱えながら死ねずにいる。何とも苦しい一生だ。これもまた外物のための生であり、道には遠い。勇ましい戦士は天下の英雄としてもてはやされても、我が身を活かすには至らない。私には、世間で善とするものが本当の善であるかが分からない。もし世間の善が本当の善とするならば、私を活かす道はないのだろう。もし世間の善が善でないとするならば、むしろ私を活かす道も拓けよう。(中略)世俗の人々が今楽しんでいるところを見ても、私にはその楽しみとやらが本当の楽しみであるか理解できない。私が見る限り、世俗の楽しみというのは、死ぬまで止まらぬ獣のような勢いで、群れをなして何かに駆り立てられているかのようだ。彼らは口では「楽しい」と言っている。私もそれにつきあうことはあるが、それらを楽しいものだとは到底思えない。 果たして、人間にとって本当の楽しみとは「ある」のだろうか、「ない」のだろうか。私にとっては無為こそが至上の楽しみと言えるが、世俗の人にとってはそれは大きな苦しみとなるようだ。古語にもある「至上の楽しみは楽しみを超えたところに、最上の名誉は名誉を超えたところにある」と。 天下は是非(肯定・否定)によって割り切れるものではない。しかしながら、是非を超えた無為の境地にあればその是非を定めることもできよう。同じく、我が身を活かす至上の楽しみも無為なればこそ見いだされるだろう。参照:兼好法師と荘子 その4。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5174/ ❝伯昏瞀人北面而立,敦杖蹙之乎頤,立有間,不言而出。賓者以告列子,列子提屨,跣而走,暨乎門,曰:「先生既來,曾不發藥乎」曰:「已矣。吾固告汝曰『人將保汝』,果保汝矣。非汝能使人保汝,而汝不能使人無保汝也,而焉用之感豫出異也。必且有感,搖而本才,又無謂也。與汝遊者,又莫汝告也,彼所小言,盡人毒也。莫覺莫悟,何相孰也。巧者勞而知者憂,無能者無所求,飽食而敖遊,汎若不繫之舟,虛而敖遊者也。」❞(『荘子』列御寇 第三十二)→伯昏瞀人(はくこんむじん)は北に向かって立ち、杖にあごをあててたたずんでいたが、そのうちに無言で立ち去った。お付きの者がそのことを列子に告げたところ、列子は靴を持ったまま、門まで裸足で走っていった。列子が「先生はせっかくいらしたのですから、薬になりそうな言葉をいただけませんか。」と聞くと、伯昏瞀人(はくこんむじん)は言った。「もうやめよ。わしはお主に『人々がきっとお主に付きまとうだろう』と言ったな、果たしてお主は人気者になった。お主が望んでそうなったのか、望まずにそうなったのかにも関わらず、今のお主にこれを止める術がないのだ。人の歓心を買うために己が本性をむやみに揺さぶらねばならず、何ら意味はないものだ。お主と遊ぶものがこのような忠告をすることはあるまい。わしに言わせれば彼らの小言こそ人を毒するものだ。自ら覚ることもなく、他者を悟らせることもない。巧みな者は気苦労が多く、智者は憂いが多いものだ。無能な者は他人に何かの求めるということがなく、腹が満ちていれば、あとはのんびりと遊ぶ。繋がれない小舟が波に揺られているように、ただ無心に漂っているのである。」ここは、『論語』の宰予の昼寝にも対応する部分です。❝宰予晝寝、子曰、朽木不可雕也、糞土之牆、不可朽也、於予與何誅、子曰、始吾於人也、聽其言而信其行、今吾於人也、聽其言而觀其行、於予與改是。」❞(『論語』公冶長)→弟子の宰予(さいよ)が学問を怠けて昼寝をしていた。先生はこうおっしゃった。「朽ちた木では彫る事は出来ない。ボロボロの土塀を塗りなおすことはできない。宰予を叱ることはできないね。かつて、私は人の言葉を聞いてその行いを信じた。しかし、今は人の言葉を聞いたらその行いを見守るようになったよ。あの宰予のおかげで改めたのだ。」今日はこの辺で。
2018.04.03
コメント(0)
-
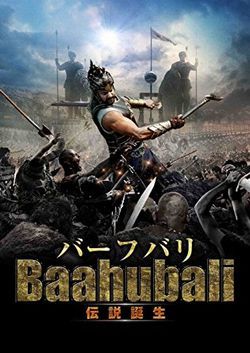
『バーブバリ』と「神話」。
ジェイ!マヒシュマティ!先週DVDと映画館で『バーフバリ』2部作を観賞いたしました。というわけで、『バーフバリ』と神話について。今回は一作目の『バーフバリ 伝説誕生』を中心に。『バーフバリ』は、インドにあったという架空の国家・マヒシュマティ王国で繰り広げられる、親子三代を中心とした壮大な叙事詩的娯楽映画です。監督・脚本は、インド南部カルナータカ州出身の、S.S.ラージャマウリ。参照:Wikipedia バーフバリ 伝説誕生https://ja.wikipedia.org/wiki/バーフバリ_伝説誕生S.S.ラージャマウリ監督本人がインタビューの中で答えていますが、『バーフバリ』は、『ラーマーヤナ』と並ぶインドの二大叙事詩『マハーバーラタ』の影響が大きな作品です。シヴァやカーリーやガネーシャ、ヤーヴァナといったヒンドゥーを代表する神々が登場するだけでなく、脚本やキャラクターの設定にも『マハーバーラタ』を想起させるものがよく見られます。たとえば、主人公のシブドゥが生まれて川に流されるとか、その後兄弟ともいうべき存在と争うなどは、大英雄アルジュナの宿敵・カルナの人生に近い。参照:Wikipedia カルナhttps://ja.wikipedia.org/wiki/カルナWikipedia マハーバーラタhttps://ja.wikipedia.org/wiki/マハーバーラタ❝──「マハーバーラタ」の影響についてお聞かせください。 監督:私はいつもインド神話の数々に魅かれてきましたし、私自身も私の作品も当然、その影響を大きく受けています。『バーフバリ』2部作の登場人物の多くは、「マハーバーラタ」の何人かの登場人物の性格や特徴を受け継いでいます。私のすべての作品だけでなく、実際問題、インド人のほとんどが神話の影響を受けています。❞『バーフバリ 王の凱旋』S.S.ラージャマウリ監督インタビューhttp://www.moviecollection.jp/interview_new/detail.html?id=757&p=1・・・ただし、実際に作品を見てみると、『バーフバリ』は、同じ古代を題材にしたインド以外の物語(特に映像作品)からの影響もはっきりと見て取れます。❝──『バーフバリ』2部作を見ると、『十戒』、『ベン・ハー』、『クレオパトラ』、『グラディエーター』、『ロード・オブ・ザ・リング』、『300 〈スリーハンドレッド〉』といったハリウッドの歴史超大作の数々が次々とを思い浮かびます。あなたはそれらの映画を意識し、それを超えようと意図しましたか?監督:『バーフバリ』は古代の王族と彼らの闘いの物語です。そしてそれらのハリウッド映画もそうです。そのため、キャラクター設定や衣装、そしてそこで繰り広げられる感情などは、まったく違う国の違う物語にもかかわらず、どうしても似てしまいがちです。それは、こうした物語が普遍的で万国共通のテーマを持っていることに他ならないからだと思います。 私が『バーフバリ』を製作した理由のひとつは、この物語がそうした世界規準の物語だったからです。 (前掲『バーフバリ 王の凱旋』S.S.ラージャマウリ監督インタビュー』より)❞たとえば、シヴドゥの出生や、アマレンドラ・バーフバリとバラーラデーヴァとの関係は、『十戒』におけるモーゼとラムセスの関係に符合しますし、 戦車戦や物語の展開は『ベン・ハー』の影響が強く、戦闘シーンや盾の使い方は『300』『ヘラクレス』などです。インドのように見えて実際にはギリシャやローマなど、他の地域を舞台にした映画のオマージュが多いです。同じアジアの作品でいうと、盾を使った陣形や火刑による戦術には『Red cliff』の影響が見られます。王道と覇道との対立軸などは、『三国志演義』の劉備と曹操、『史記』の劉邦と項羽の図式と一致します。他にも、二人の主君に仕えながらその双方に対して忠節をを守り、元主君の妻をかばう最強の剣士・カッタッパのキャラクター設定なども『三国志演義』の関羽を思わせますし、母親思いのバーフバリの行動などとも相俟って忠孝の精神を鼓舞している作品とも言えます。デーヴァセーナが不自然な場所で薪を集めたりするのは「臥薪嘗胆」の故事に通じるところがありますし、バラーラデーヴァによる行為にも「死屍に鞭打つ」シーンがあったりと(それぞれ奇抜な方法で恨みを晴らそうとする行為)、古代インドよりも、むしろ古代中国の歴史にも通じるものもあります。 あと、ラージャマウリ監督は、その着想においてコミックやアニメの影響が強いです。奇抜な発想や、荒唐無稽とも見える構図などが、『バーフバリ』の神話的な世界の非現実性をより効果的に演出していますが、これは、漫画やアニメの表現を実写にそのまま取り入れているのも原因でしょう。監督がはっきりと「お気に入り」としている『ライオンキング』は脚本にもその影響が見られますし、ほかにも『ムーラン』、『美女と野獣』、『アラジン』などのディズニーアニメの構図も取り入れているフシがあります。後はドリームワークスの『プリンス・オブ・エジプト』。それと、これはあくまでも推測ですが、日本のアニメでは『ナウシカ』はあってもおかしくないと思います。参照:Carmen Twillie, Lebo M. - The Lion King - Circle Of Lifehttps://www.youtube.com/watch?v=GibiNy4d4gcMulan - The Avalanche - Flemish HDhttps://youtu.be/jyq-9eX1eA4?t=1m10sしかし、そういったインド内外からの夥しい数のオマージュを差し引いても、『バーフバリ 伝説誕生』には、なお不思議な魅力が残ります。たとえば、もう一度赤ん坊が川に流されるシーン。前述のように、『マハーバーラタ』のカルナや、『旧約聖書』のモーゼは、産まれて間もなく川に流され、川下で拾われて養われます。他にも、ギリシャ神話のペルセウス、日本における桃太郎の物語も同じ部類に属するでしょう。最近でいうと、去年発売の『ドラゴンクエストⅪ』の主人公もそうでしたし、今年観た大陸のアニメ『西遊記』(原題は『大聖帰来』)でも赤ん坊が川に流されて、見ず知らずの人物に育てられます。「川に流される赤子」というのは、世界中の神話や伝説に登場する、英雄の出生の共通のモチーフです。『バーフバリ』には、『マハーバーラタ』のみならず、こういった世界中の神話に通じるモチーフのを意図的に配置した形跡があります。他にも、ストーリーの骨組みついては、昨年完結した『アルスラーン戦記』で、インドをモデルにしたシンドゥラ国の王子様二人が王位めぐって骨肉の争いを繰り広げ、父王が審判を下すという、非常によく似たお話があります。そもそも『アルスラーン戦記』も『バーフバリ』と同じように、貴種流離譚に分類される普遍的なモチーフを共有しています。参照:Wikipedia 貴種流離譚https://ja.wikipedia.org/wiki/貴種流離譚 こういった世界中の神話を通して、英雄の神話にみられる共通項ついての研究を、アメリカの比較神話学者ジョゼフ・キャンベルは1949年に『千の顔を持つ英雄(The Hero with a Thousand Faces) 』という書物にまとめました。アメリカの学者さんですが、東洋思想に造詣の深い人物ですし、当然、ヒンドゥーの神話の引用も多いので、『バーフバリ』の世界観とも馴染みやすいです。この『千の顔を持つ英雄(The Hero with a Thousand Faces) 』(1949)において、ジョセフ・キャンベルは' hero's journey(英雄の旅)'という、世界の英雄の神話に共通してみられるパターンを説明しています。箇条書きにすると以下の通りです。Ⅰ.出立(Departure) 1 冒険への召命(The call to adventure) 2 召命拒否(Refusal of the call) 3 自然を超越した力の助け(Supernatural aid) 4 最初の境界を超える(Crossing the threshold) 5 クジラの腹の中(Belly of the whale)Ⅱ. イニシエーション(Initiation) 6 試練の道(The road of trials) 7 女神との遭遇(The meeting with the goddess) 8 誘惑する女(Woman as temptress) 9 父親との一体化(Atonement with the father) 10 神格化(Apotheosis) 11 究極の恵み(The ultimate boon)Ⅲ.帰還(Return) 12 帰還の拒絶(Refusal of the return) 13 魔術による逃走(The magic flight) 14 外からの救出(Rescue from without) 15 帰還の境界越え(The crossing of the return threshold) 16 二つの世界の導師(Master of two worlds) 17 生きる自由(Freedom to live)上記「英雄の旅」のうちの「Ⅱ.イニシエーション」の部分は、『バーフバリ 伝説誕生』の展開のまんまです。参照:『バーフバリ伝説誕生』ダイジェスト映像https://www.youtube.com/watch?v=5MCIeIj6jeM このパターンは『スター・ウォーズ・シリーズ』への影響が有名ですが、他にも『ライオンキング』、『マトリックス』、『指輪物語』の映画版や『マッドマックス 怒りのデス・ロード』でも活用されています。S.S.ラージャマウリ監督のいう「普遍的で万国共通のテーマ」というのは、まさにこの「英雄の旅」にみられる共通性であり、その王道のど真ん中を踏みしめるバーフバリの歩みであるともいえるでしょう。参照:What makes a hero? - Matthew Winklerhttps://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCAThe Hero's Journey and the Monomyth: Crash Course World Mythology #25https://www.youtube.com/watch?v=XevCvCLdKCUちなみに、神話ではないですが、幼馴染と共に明治維新を成し遂げたにもかかわらず、その後逆賊として扱われる西郷隆盛も、アマレンドラ・バーフバリの生涯によく似ていまして、彼もまた神話的な英雄であると言えるかも知れません。後で推敲します。今日はこの辺で。
2018.02.15
コメント(0)
-

荘子と進化論 その204。
本日は、人日の節句、いわゆる「七草」の日です。一月七日が「人日の節句」、三月三日が「上巳の節句」、五月五日が「端午の節句」、七月七日が「七夕の節句」、九月九日が「重陽の節句」。日本では江戸時代に五節句として定められています。古来、奇数は陽であり、陽が重なることによって陰に転じる〔奇数(陽)+奇数(陽)=偶数(陰)〕日にあたるので、その象徴性から五節句となったわけですが、日中共に現在も祝日であるのは「端午の節句(端午節)」のみであるというのも興味深いです。参照:Wikipedia 節句https://ja.wikipedia.org/wiki/節句で、以前も書いたんですが、およそ1500年ほど前に書かれた『荊楚歳時記』の続きを。❝正月七日為人日,以七種菜為羹,翦綵為人,或鏤金箔為人,以貼屏風,亦戴之以頭鬢,亦造華勝以相遺,登高賦詩。❞(『荊楚歳時記』)→正月七日は人日の日となる。七種の菜によって羹を作り、綵(あや)を切ったり金箔を飾って人形を作って、屏風に貼り付けたり、頭鬢の上に載せたりする。華勝(髪飾り)を作って相手に送り、高楼を上って詩を賦す。「正月七日為人日,以七種菜為羹」という部分が七草の由来です。実は『荊楚歳時記』にはもう一つ七草にまつわる記録があります。❝正月夜,多鬼鳥度,家家槌床打戶,捩狗耳,滅燈燭以禳之。按︰《玄中記》云︰「此鳥名姑獲,一名天帝女,一名隱飛鳥,一名夜行遊女。好取人女子養之,有小兒之家,即以血點其衣以為誌,故世人名為鬼鳥。荊州彌多。」斯言信矣。❞(『荊楚歳時記』)→正月の夜、多くの鬼鳥が渡るため、家々では槌で床や戸を叩いたり、犬の耳をねじったり、灯火を消してこれを避ける。『玄中記』によると、「この鳥は姑獲といい、またの名を天帝女、隠飛鳥、夜行遊女ともいう。女児をさらって養うことを好み、幼子のいる家には、血で衣に印をつける習性がある。このようなことから世の人は鬼鳥と名付けた。荊州では鬼鳥はとても多い。」この記録は信用できるのだろうか。『荊楚歳時記』には、『玄中記』からの引用として「鬼鳥(キチョウ)」もしくは「姑獲(コカク)」などと呼ばれる鳥についての記載があります。日本の七草の童歌にある「七草なずな 唐土の鳥(とうとのとり)が 日本の国へ 渡らぬ先に」 の「唐土の鳥(とうとのとり)」の由来となった伝説上の鳥です。『荊楚歳時記』では、この鳥を避けるために、当時の荊や楚の国の人々が、床や戸を槌で叩いていたと記されています。日本でもこれに倣って、「薪、包丁、火箸、すりこぎ、杓子、銅杓子、菜箸」といった調理器具で、まな板を叩いたり、7×7で49回切るという風習もありました(「七草叩き」)。葛飾北斎も「十干の内」という浮世絵で、この「七草叩き」の風習を描いています。参照:七草粥の作法https://www.youtube.com/watch?v=JISgRvIYY6E七草囃子https://www.youtube.com/watch?v=Akkcq-bYPu0わらべうた ななくさなずなhttps://www.youtube.com/watch?v=YadqhzZI06wこれらの風習は『荊楚歳時記』や日本の『本朝歳時記』などの書物によって、江戸時代ぐらいに広まったものであろうと思われます。参照:『荊楚歳時記』の正月。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5206/ちなみに、『荊楚歳時記』の原文では、七種類の野菜で作るのは「七種菜為羹」、つまり「羹(あつもの)」でして、お粥ではなくていわばスープです。『荊楚歳時記』では、「お粥」を食べるとされる風習は、一月十五日と、冬至から百五日後の「寒食」の日、冬至の日の赤豆粥の3つの時期で食べるものだと記してあります。このうち、冬至の頃に食べられる赤豆のお粥が、現代中国で十二月八日の「臘八節(ろうはちせつ)」に食べられる「腊八粥(ラーバージョウ)」の原型です。❝冬至日,作赤豆粥,以禳疫。量日影。按:共工氏有不才之子,以冬至死,為疫鬼,畏赤小豆,故冬至日作赤豆粥以禳之。又晉魏間,宮中以紅線量日影,冬至後,日影添長一線。❞(『荊楚歳時記』)→冬至の日に、赤豆で粥を作り、疫を退ける。また、太陽の影を計測する。共工氏の不才の子が冬至の日に死んだあと疫鬼と成った。疫鬼は赤豆を畏れたため、冬至の日に赤豆で粥を作り、これを攘った。また、晋や魏の時代には宮中で日の影を計測し、冬至の影は赤線で、それ以外の日には一本の線を添える。日本の七草は七種類ですが、十二月八日に食べられる、「腊八粥(ラーバージョウ)」「八宝粥(バーバオジョウ)」は八種類の食材(赤豆や黒米、龍眼など)を使います。『荊楚歳時記』では、鬼を祓うために豆を使うということが何度も書いてあるんですが、冬至の赤豆のお粥もその一例です。(ちなみに、旧暦の十二月八日は、今年の新暦でいうと一月二四日なんだそうです。本来日本の伝統である七草も、旧暦の一月七日に採れる野菜を基準にしているので、実際は一ヵ月ちょっとズレています。今年の旧暦の七草は二月二二日となります。)参照:Wikipedia 臘八節https://ja.wikipedia.org/wiki/臘八節❝按:董勛《問禮俗》曰︰「正月一日為雞,二日為狗,三日為羊,四日為猪,五日為牛,六日為馬,七日為人,以陰晴占豐耗,正旦畫雞于門,七日帖人於帳。」今一日不殺雞,二日不殺狗,三日不殺羊,四日不殺猪,五日不殺牛,六日不殺馬,七日不行刑,亦此義也。古乃磔雞令畏鬼,今則不殺,未知孰是。荊人於此日向辰,門前呼牛羊雞畜,令來。乃置粟豆於灰,散之宅內,云「以招牛馬」,未知所出。❞(『荊楚歳時記』)→董勛(とうくん)の『問禮俗』いわく「正月の一日を雞の日とし、二日を犬の日とし、三日を羊の日,四日を豚の日、五日を牛の日、六日を馬の日、七日を人の日とする。陰晴により、豊作か不作かを占う。元旦には門に鶏の画を、七日には人の画を貼る。」一日は鶏を殺さず、二日は犬を殺さず、三日は羊を殺さず、四日は豚を殺さず、五日は牛を殺さず、六日は馬を殺さず、七日は刑罰を行わないのもまた、この意味である。昔は、鶏を門前に括り付けて鬼を畏れさせたものだが、今は鶏を殺さないようになった。その理由は不明である。荊人はこの日に辰の方角に向かい、門前で牛や羊や雞などの家畜を呼び寄せる、または、灰の上に粟豆をまき、それによって家の中に牛馬を招き入れようともするが、何に由来するかは不明である。そもそも、「一月七日」はなぜ「人日の節句」と言うのか。『荊楚歳時記』においては、一月一日を「鶏の日」として、それから順々に動物の日が巡り、七日目が「人の日」となるため、「一月七日」は「人日」であるという説明がなされています。❝神はまた言われた、「地は生き物を種類にしたがっていだせ。家畜と、這うものと、地の獣とを種類にしたがっていだせ」。そのようになった。(1:24)神は地の獣を種類にしたがい、家畜を種類にしたがい、また地に這うすべての物を種類にしたがって造られた。神は見て、良しとされた。(1:25)神はまた言われた、「われわれのかたちに、われわれにかたどって人を造り、これに海の魚と、空の鳥と、家畜と、地のすべての獣と、地のすべての這うものとを治めさせよう」。(1:26)神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。(1:27)神は彼らを祝福して言われた、「生めよ、ふえよ、地に満ちよ、地を従わせよ。また海の魚と、空の鳥と、地に動くすべての生き物とを治めよ」。(1:28)神はまた言われた、「わたしは全地のおもてにある種をもつすべての草と、種のある実を結ぶすべての木とをあなたがたに与える。これはあなたがたの食物となるであろう。(1:29)また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもの、すなわち命あるものには、食物としてすべての青草を与える」。そのようになった。(1:30)神が造ったすべての物を見られたところ、それは、はなはだ良かった。夕となり、また朝となった。第六日である。(1:31)❞(『旧約聖書』第1章 創世記 より)『旧約聖書』の創世記では6日目に行われていることが、「人日」の物語においては、一月一日からの七日間で行われている、と読むこともできます。❝南海之帝為儵,北海之帝為忽,中央之帝為渾沌。儵與忽時相與遇於渾沌之地,渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德,曰「人皆有七竅,以視聽食息,此獨無有,嘗試鑿之。」日鑿一竅,七日而渾沌死。❞(『荘子』応帝王第七)→南海の帝王を儵(しゅく)いい、北海の帝王は忽(こつ)、中央の帝王は渾沌(こんとん)という。儵(しゅく)と忽(こつ)とは、たまたま中央の渾沌の土地で出会った。渾沌は心から二人の帝王を歓待した。儵と忽はそのお返しに何をしたらよいかと相談したところ「人間はみな目、耳、口、鼻に七つの穴を持っている。それらのおかげで見たり聞いたり、食べたり呼吸したりすることができるが、この渾沌にはそれがない。御礼として、ためしに穴をあけてみよう。」という話となった。二人は毎日一つずつ穴を掘っていったが、七日目に渾沌は死んでしまった。同じ七日間で、『荘子』の場合には、渾沌が死んでしまいます。そういう話を続けます。今日はこの辺で。
2018.01.07
コメント(2)
-

西郷隆盛と儒教。
大河ドラマ『西郷どん』放送開始記念。 本日は、西郷隆盛(1828-1877)と儒教について。参照:Wikipedia 西郷隆盛https://ja.wikipedia.org/wiki/西郷隆盛言わずと知れた維新の元勲、西郷隆盛は、歴史的な功績はもちろんのこと、その人柄も多くの日本人に親しまれてきました。しかし、生来寡黙な人物で、また、西郷自身から進んで思想を発信したということも少なく、著作というものもありません。ただし、戊辰戦争以降に西郷と親交を深めた出羽庄内藩(現在の山形県庄内地方)の藩士たちが取りまとめた言行録『南洲翁遺訓』がありまして、この『遺訓』によって、我々は西郷の思想を窺い知ることができます。❝命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。此の仕末に困る人ならでは、艱難を共にして國家の大業は成し得られぬなり。去れ共、个樣(かやう)の人は、凡俗の眼には見得られぬぞと申さるゝに付、孟子に、「天下の廣居に居り、天下の正位に立ち、天下の大道を行ふ、志を得れば民と之に由り、志を得ざれば獨り其道を行ふ、富貴も淫すること能はず、貧賤も移すこと能はず、威武も屈すること能はず」と云ひしは、今仰せられし如きの人物にやと問ひしかば、いかにも其の通り、道に立ちたる人ならでは彼の氣象は出ぬ也。(山田済斎 編 『西郷南洲遺訓』岩波文庫より)❞❝學に志す者、規模を宏大にせずば有る可からず。去りとて唯此こにのみ偏倚(へんい)すれば、或は身を修するに疎に成り行くゆゑ、終始己れに克ちて身を修する也。規模を宏大にして己れに克ち、男子は人を容れ、人に容れられては濟まぬものと思へよと、古語を書て授けらる。恢宏其志気者。人之患。莫大乎自私自吝。安於卑俗。而不以古人自期。古人を期するの意を請問せしに、堯舜を以て手本とし、孔夫子を教師とせよとぞ。(同上)❞・・・幕末の武士ですから、西郷に儒学の素養があるのは当然です。「命もいらず、名もいらず、官位も金もいらぬ人は、仕末に困るもの也。」という有名な一節は『孟子』が引き合いに出されています。『論語』でいうとこのあたり。❝子曰。飯疏食飮水。曲肱而枕之。樂亦在其中矣。不義而富且貴。於我如浮雲。 (『論語』述而第七)❞→先生はこうおっしゃった「野菜を食らって水を飲み、肘を曲げて枕にする。そんな生活の中にも楽しみはある。義に背いてまで豊かになったり高い位に就くなんて、私にとっては浮雲のようなものだ。」「命もいらぬ」というと、「志士」の語源のこちら。子曰「志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。」(衛霊公第十五)→先生はこうおっしゃった、「志士、仁人は仁を損なってでも生を求めるものではない、我が身を殺してでも仁を成すのである。」また、西郷が「堯舜を以て手本とし、孔夫子(孔子のこと)を教師とせよ」という箇所がありますが、「克己(こっき)」「修身」など儒教において重要な字句が並んでいます。特にここは朱子学で強調されるところですが、己に克つ、「克己(こっき)」は『論語』に由来する言葉です。❝顏淵問仁。子曰「克己復禮為仁。一日克己復禮、天下歸仁焉。為仁由己、而由人乎哉?」(『論語』顔淵第十二)❞→顔淵が「仁」について質問した。先生はこうおっしゃった「己に克ち、礼に復して仁を為す。一日自分に打ち克って礼に立ち戻ることができれば、天下は仁に帰するであろう。仁を為すというのは己自身の問題である。他人に頼ったところで意味があるだろうか?」・・・別名『西郷論語』とも称される『南洲翁遺訓』は論語からの影響が特に濃厚でして、例えば『論語』における「仁」の使い方に注視して照らし合わせると、西郷の意図を汲み取り易いのではないかと思います。❝文明とは道の普く行はるゝを贊稱せる言にして、宮室の壯嚴、衣服の美麗、外觀の浮華を言ふには非ず。世人の唱ふる所、何が文明やら、何が野蠻やら些(ち)とも分らぬぞ。予嘗て或人と議論せしこと有り、西洋は野蠻ぢやと云ひしかば、否な文明ぞと爭ふ。否な野蠻ぢやと疊みかけしに、何とて夫れ程に申すにやと推せしゆゑ、實に文明ならば、未開の國に對しなば、慈愛を本とし、懇々説諭して開明に導く可きに、左は無くして未開矇昧の國に對する程むごく殘忍の事を致し己れを利するは野蠻ぢやと申せしかば、其人口を莟(つぼ)めて言無かりきとて笑はれける。(上記『西郷南洲遺訓』より)❞❝子曰。不患人之不己知。患不知人也。 (『論語』学而 第一)❞→先生はこうおっしゃった、「他人が自分を理解してくれないと心配しなくてよい。自分が他人を理解していないことを心配しなさい。」❝子曰、「默而識之、學而不厭、誨人不倦、何有於我哉。」(『論語』述而 第七)❞→ 先生はこうおっしゃった、「静かに事物を知り、学ぶことを厭わず、倦(う)まずに人を教え続ける。私にはそれだけなんだよ。」❝西洋の刑法は專ら懲戒を主として苛酷を戒め、人を善良に導くに注意深し。故に囚獄中の罪人をも、如何にも緩るやかにして鑒誡(かんかい)となる可き書籍を與へ、事に因りては親族朋友の面會をも許すと聞けり。尤も聖人の刑を設けられしも、忠孝仁愛の心より鰥寡(かんか)孤獨を愍(あはれ)み、人の罪に陷るを恤(うれ)ひ給ひしは深けれ共、實地手の屆きたる今の西洋の如く有しにや、書籍の上には見え渡らず、實に文明ぢやと感ずる也。(上記『西郷南洲遺訓』より)❞西郷が、西洋の制度を評価する場合にも、徳治主義に近い部分についての共感があります。❝子曰、道之以政、齊之以刑、民免而無恥、道之以徳、齊之以禮、有恥且格。(『論語』 為政第二)❞→先生はこうおっしゃった「人々を導くのを政によって、人々を正すのに刑罰をよってすれば、民はその政や罰から逃れる事ばかりを考え、恥じることがなくなるだろう。人々を導くのを徳によって、人々を正すのを礼によってすれば、人々は恥を知り同時に道理をわきまえるようになるだろう。❝漢學を成せる者は、彌漢籍に就て道を學ぶべし。道は天地自然の物、東西の別なし、苟も當時萬國對峙の形勢を知らんと欲せば、春秋左氏傳を熟讀し、助くるに孫子を以てすべし。當時の形勢と略ぼ大差なかるべし。(上記『西郷南洲遺訓』より)❞ちなみに、西郷のオススメは「左伝」なんだそうで、ここは福沢諭吉と同じですね。参照:靖国神社と中国古典https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201403070000/・・・西郷といえば「敬天愛人」。西郷はここでも「克己」を強調します。❝道は天地自然の道なるゆゑ、講学の道は敬天愛人を目的とし、身を修するに克己(こつき)を以て終始せよ。己れに克(か)つの極功は「毋意毋必毋固毋我(いなしひつなしこなしがなし)」と云へり。総じて人は己れに克つを以て成り、自ら愛するを以て敗るるぞ。(上記『西郷南洲遺訓』岩波文庫より)❞❝道は天地自然の物にして、人は之れを行ふものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛し給ふゆゑ、我を愛する心を以て人を愛する也。(同上)❞ ❝子絕四「毋意,毋必,毋固,毋我。」(『論語』子罕第九)❞→先生は以下の四つを断たれた「意地になるな、拘るな、頑なになるな、我を張るな。」・・・「敬天愛人」の思想は、朱子学や陽明学ではよく見られる展開ですが、今回は王陽明の『伝習録』から。❝夫聖人之心,以天地萬物為一體,其視天下之人,無外內遠近,凡有血氣,皆其昆弟赤子之親,莫不欲安全而教養之,以遂其萬物一體之念。天下之人心,其始亦非有異於聖人也,特其間於有我之私,隔於物欲之蔽,大者以小,通者以塞,人各有心,至有視其父、子、兄、弗如仇仇者。聖人有憂之,是以推其天地萬物一體之仁以教天下,使之皆有以克其私,去其蔽,以復其心體之同然。其教之大端,則堯、舜、禹之相授受,所謂「道心惟微,惟精惟一,允執厥中」而其節目,則舜之命契,所謂「父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信」五者而已。(『伝習録』)❞→聖人の心とは、天地萬物をもって一体となし、天下の人を見るのに内と外、遠近の区別なく、およそ血の通う者であれば、身近な親類の子弟のように安んじて見守り、万物一体の教えへと導こうとするのである。天下の人心も、その始まりにおいては聖人の心と異なることはない。己が内に我執がはびこり、物欲が感性を隔てるようになると、ゆったりとした心がちまちまとなっていき、やがてふさぎこんでしまう。そのうち人心がバラバラとなって、親子や兄弟ですら、まるで敵同士のようにいがみ合うようになった。聖人はそこを憂い、天地万物と一体の仁を天下に教え広め、皆にある我執や物欲に打ち克ち、本来人間の有する聖人と同様の心に復しようとした。その教えの始まりは、すなわち堯、舜、禹の時代に授かり「道心はただ微妙であり、ひたすら精神を一とし、中庸をとらえて失うな」という教えのみであった。その守るべきものというのは舜が契(ケイ)に命じて教授した「父子に親有り、君臣に義あり,夫婦に別有り、長幼に序有り,朋友に信有り」という五者のみであった。ちなみに、『論語』の中で、「仁」について問われたとき、孔子は「愛人(人を愛することである)。」と説いています(顔淵第十二)。❝忠孝仁愛教化の道は政事の大本にして、萬世に亙り宇宙に彌り易(か)ふ可からざるの要道也。道は天地自然の物なれば、西洋と雖も決して別無し。(『西郷南洲遺訓』岩波文庫より)❞参照:教育勅語と儒教。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201705070000/・・・西郷の場合には、薩摩の郷中教育や、私淑していた藤田東湖、『言志四録』の著者である佐藤一斎などの影響は明白で、大塩平八郎や、三島由紀夫などと同じように、西郷と新儒教、特に陽明学との関係を指摘することが多いです。例えば、内村鑑三の『代表的日本人』。西郷隆盛はその筆頭に挙げられています。“(西郷は)若いころから王陽明の書物には興味をひかれました。陽明学は、中国思想のなかでは、同じアジアの起源を有するもっとも聖なる宗教と、きわめて似たところがあります。それは、崇高な良心を教え、恵み深くありながら、きびしい「天」の法を説く点です。わが主人公の、のちに書かれた文章には、その影響がいちじるしく反映しています。西郷の文章にみられるキリスト教的な感情は、すべてその偉大な中国人の抱いていた、単純な思想の証明であります。あわせて、それをことごとく摂取して、あの実践的な性格を作りあげた西郷の偉大さをも、物語っているのであります。 西郷は、ほかにも、仏教の中ではストイックな禅の思想に、いくらか興味を示しました。のちに友人に語った言葉からわかるように、「自分の情のもろさを抑えるため」でありました。いわゆるヨーロッパ文化なるものには、まったく無関心でした。日本人のなかにあっては、たいへん度量が広くて進歩的なこの人物の教育は、すべて東洋に拠っていたのであります。 ところで、西郷の一生をつらぬき、二つの顕著な思想がみられます。すなわち、(一)統一国家と、(二)東アジアの征服は、いったいどこから得られたものでしょうか。もし陽明学の思想を論理的にたどるならば、そのような結論に至るのも不可能ではありません。旧政府により、体制維持のために特別に保護された朱子学とは異なり、陽明学は進歩的で前向きで可能性に富んだ教えでありました。 陽明学とキリスト教との類似性については、これまでにも何度か指摘されました。そんなことを理由に陽明学が日本で禁止同然の目にあっていました。「これは陽明学にそっくりだ。帝国の崩壊を引き起こすものだ。」こう叫んだのは維新革命で名をはせた長州の戦略家、高杉晋作であります。長崎ではじめて聖書を目にしたときのことでした。このキリスト教に似た思想が、日本の再建にとって重要な要素として求められたのでした。これは当時の日本の歴史を特徴づける一事実であったのです。(『代表的日本人』内村鑑三著、鈴木範久訳 岩波文庫)”朱子学と対比する形で、陽明学を「革命思想」ととらえ、西郷の思想の源泉とする内村鑑三の見方は、伝統的な西郷論としてオーソドックスなものですが、当ブログとしては、西郷の言葉は儒教全般にわたり、陽明学の影響はあるものの、西郷の思想を「陽明学」の棚に分類するのには抵抗があります。彭祖、何ぞ希わん 犬馬の年塵類に牽かれず 閑権を握る新生祝賀 人と異なる静かに誦す 南華の第一篇彭祖のように長生きができても、犬馬のように縛られた年月を経たくはない塵や芥のような世事に流されず、長閑に時を過ごしたい新年を祝うめでたい日にすら、世間の人とは違ってしまったのだな静かに荘子の第一篇を読み、天地を逍遥するのだもちろん、儒教の枠だけに留まるものでもありませんし。本年はこの辺で。
2017.12.31
コメント(0)
-

荘子と進化論 その203。
さきほど、『スターウォーズ/最後のジェダイ(Star Wars: Episode VIII The Last Jedi)』を観賞してきました。東洋的な要素をほとんど取り除いて展開された『フォースの覚醒』と、道教の技法を積極的に使った『ローグワン』という流れからある程度予想はしていましたが、『最後のジェダイ』は、かなり東洋寄りの構造となっています。スターウォーズと道教 ~フォース(Force)と氣(Qi)~。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5204/尸解の世界。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5197/スターウォーズと道教 ~呪禁と弾除け~。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5209/当ブログは一応荘子ブログですので、今回は直接『荘子』に関わるものだけ挙げておきます。❝桓公讀書於堂上、輪扁斲輪於堂下、釋椎鑿而上、問桓公曰。「敢問公之所讀者何言邪?」公曰「聖人之言也。」曰「聖人在乎?」公曰「已死矣。」曰「然則君之所讀者、古人之糟魄已夫!」桓公曰「寡人讀書、輪人安得議乎!有説則可、無説則死。」輪扁曰「臣也、以臣之事觀之。断輪、徐則甘而不固、疾則苦而不入。不徐不疾、得之於手而應於心、口不能言、有數存焉於其間。臣不能以?臣之子、臣之子亦不能受之於臣、是以行年七十而老断輪。古之人與其不可傳也死矣、然則君之所讀者、古人之糟魄已矣。」(『荘子』天道 第十三)❞ →桓公がお堂で書物を読んでいたとき、お堂の下では輪扁(りんぺん)という職人が車輪を作っていた。ふと、輪扁(りんぺん)は鑿を置きお堂に上がって桓公に尋ねた。「お教えください。お殿様は今、何について書かれたものを読んでおいでですか?」。桓公は「聖人の言葉だ」と答えた。「その聖人様は生きているんですか?」「いや、亡くなっておられる」。すると「なんだ、あなたさまは死んだ人の残りカスを読んでいるだけじゃないですか」と言うので、「お前なんぞの身分でわしの学問をバカにするのか、答え次第によっては命はないぞ!」と桓公が激怒したところ、輪扁なる職人はこう答えた。「わたくしの知る道理というのはこのようなものです。車輪の軸を作るときに、ぴたりとはめ合わせるように削るには秘訣が要ります。削りが多すぎると強くはまりませんし、削りが少なすぎると窮屈で差し込みづらいものです。この秘訣は、自分自身でやってみて、手応えを心で確かめることで初めて体得されるものです。これはどれだけ言葉を連ねたところで伝わるものではありません。私はせがれにをそれを言葉で教えることができず、せがれが私からそれを受け継ぐこともできませんでした。そして、齢七十の今になっても私は車輪を作る仕事をしています。あなた様の読んでいる本を書いた聖人様も、私と同じように全てを伝えきれずに亡くなった人であろう。そう考えたので、私はそのご本を「死んだ人の残りカス」、ただの『古人の糟魄』であると申しあげたのです。」マスター・ヨーダと老荘思想 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5025/ジェダイ(Jedi)と道教(Taoism)。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5203/フォースの説明などにしても、経典からそのまま引用しているのではないかと思わせるセリフがあったり、ジェダイの本質にかかわる部分にも原典そのままの表現が多かったです。「古人の糟魄」はその好例だと思います。詳しくはいずれ。今日はこの辺で。
2017.12.16
コメント(0)
-
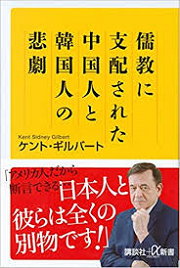
ケント・ギルバートと孟子。
久々の更新。-----(引用始め)------------------------------------トランプ氏のアジア歴訪で再確認 金正恩氏、文在寅氏、習近平氏に「至誠」は通じない 長州藩の松下村塾で高杉晋作、久坂玄瑞、伊藤博文らに多大な影響を与えた吉田松陰の存在を抜きにして、明治維新の成功はなかったと思う。 松陰は「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」(=こちらがこの上もない誠の心を尽くしても感動しなかったという人にはいまだあったためしがない)という「孟子」の一節を好んで口にしたそうだ。 松陰は「至誠」の気持ちで多くの人々の心を動かし、行動も起こさせた。死後も、その思想を通じて日本が植民地化を逃れて近代化を達成する明治維新に貢献した。 松陰の功績は永遠に色あせないが、残念ながら「至誠」の考えは、共通の常識を持つ相手にしか通じない。それも儒教思想の影響が色濃く残る北朝鮮と韓国、中華人民共和国(PRC)の指導者には絶対に通じない。ドナルド・トランプ米大統領のアジア歴訪を見ていて、それを再認識した。 北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)朝鮮労働党委員長は、核兵器とICBM(大陸間弾道ミサイル)を自国で開発して米国を脅迫すれば、祖父の金日成(キム・イルソン)主席から3代続く「金王朝」を存続できると信じている。 ところが、多くの米国人は「自由と民主主義と人権を無視して領土や国民の生命を脅かす敵国は、国際社会の批判など気にせず先制攻撃すべきだ」と考える。だから、米国人の常識で見ると正恩氏の行動は自殺行為そのものだ。米朝の常識の差は「至誠」を尽くしても埋まらない。 韓国の文在寅(ムン・ジェイン)大統領の非常識は、もはや韓国を滅ぼしかねない危険水域だ。 トランプ氏を歓迎する晩餐(ばんさん)会に「独島エビ」なるものを出して、島根県・竹島をめぐる日本との争いを主張した。TPOと外交儀礼をわきまえない無礼者が、政権中枢にいる事実をアピールしたようなものだ。また、元慰安婦を招待してトランプ氏に抱きつかせた。米国が仲介した慰安婦問題の日韓合意を、「韓国は守る意志がない」と世界中に伝わった。 さらに、韓国警察は、反トランプデモの暴走を食い止めることができなかった。今回の訪韓中に韓国が演じた失態の数は片手では足りない。 沖縄県の翁長雄志知事と同様、文氏は米国が見放すように行動している印象だ。トランプ氏の訪韓を、自分自身が「反米・反日・親北・親中」である事実をアピールする機会に、最大限に利用したのか。 中国の習近平国家主席の手のひらで踊ることが、韓国国民の総意なら仕方ない。だが、民主党政権下の日本人と同様、甘言に目がくらんだ詐欺被害者にしか見えない。------------------------------------(引用終わり)-----zakzak ケント・ギルバート ニッポンの新常識 2017.11.18 トランプ氏のアジア歴訪で再確認 金正恩氏、文在寅氏、習近平氏に「至誠」は通じないhttps://www.zakzak.co.jp/soc/news/171118/soc1711180009-n1.htmlベストセラー『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』 (講談社+α新書) でおなじみのケント・ギルバートさんによるフジサンケイグループの『夕刊フジ』のコラムであります。文中にある「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり(至誠而不動者未之有也)」は、本来は『孟子』にある言葉でして、日本では孟子を手本としていた吉田松陰の好んで引用としたものとして有名です。ケントさんがこの言葉を持ち出したのは、安倍ちゃんが座右の銘として何度も引き合いに出しているからなのだと推察します。❝「身はたとい 武蔵の野辺に朽ちぬとも 留め置かまし 大和魂」 十月念五日 二十一回猛士 第一節 一 余、去年已来、心蹟百変挙て数え難し。就中趙の貫高(かんこう)を希い、楚の屈平(くっぺい)を仰ぐ。諸知友の知る所なり。故に子遠(しえん)が送別の句に、「燕趙多士一貫高荊楚深憂只屈平のこと」と云うもこの事也。然るに五月十一日、関東の行を聞しよりは又一の誠字に工夫を付けたり。時に子遠死字を贈る。余、これを用いず。一白綿布を求めて「孟子至誠而不動者未之有也」の一句を書し、手巾ヘ縫い付け携て江戸に来り。(吉田松陰著『留魂録』より)❞吉田松陰の思想における孟子の存在というのは、必要不可欠の要素です。門下生に向けて孟子の内容を説いた『講孟余話』なども有名です(ちょっと古い本だと『講孟箚記(こうもうさっき)』という表記をしていましたが、現在は『講孟余話(こうもうよわ)』というタイトルが多いです)。他にも松陰が提唱していた「草莽崛起」の「草莽」も『孟子』に由来します。ちょうど今年のトランプの訪中の時にアラベラちゃんが『三字経』を暗誦していましたが、これも孟子との関りが深い書物です。日本でも江戸時代には寺子屋などで教えていた基本的な漢文のテキストでした。この『三字経』の冒頭「人之初 性本善」(人の初まりにおいて、その性は善である。)は孟子の代表的な命題である「性善説」ですし、その後の「昔孟母 擇鄰處 子不學 斷機杼」(昔、孟子の母は擇鄰にいたときに、子供が学問を怠ったことの戒めとして、自らの機杼を断った)という「孟母断機」の有名な逸話も載っています。参照:Trump shows Xi and Peng video clips of his granddaughter Arabella Kushner singing in Mandarinhttps://youtu.be/uzM7XoVVGQc?t=1m5s参照:三字経 - 漢字文化資料館http://kanjibunka.com/download/sanjikyo.htmlちなみに、アラベラちゃんが暗誦していたのは最初のくだりから「人不学 不知義」までです。ちなみにちなみに、彼女が披露したのは『我们的田野』、『三字経』、李白の『望廬山瀑布(廬山の瀑布を望む)』『早発白帝城(早(つと)に白帝城を発す)』、『我的好妈妈』の順です。 儒教の一部を「孔孟の教え」とも言いますし、聖人孔子に準じるかたちで「亜聖」とも呼ばれる孟子は、当然のことながら儒教を代表する思想家です。参照:Wikipedia 孟子https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%9F%E5%AD%90で、もう一度最初のケント・ギルバートさんのコラム。 ❝松陰は「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」(=こちらがこの上もない誠の心を尽くしても感動しなかったという人にはいまだあったためしがない)という「孟子」の一節を好んで口にしたそうだ。 松陰は「至誠」の気持ちで多くの人々の心を動かし、行動も起こさせた。死後も、その思想を通じて日本が植民地化を逃れて近代化を達成する明治維新に貢献した。 松陰の功績は永遠に色あせないが、残念ながら「至誠」の考えは、共通の常識を持つ相手にしか通じない。それも儒教思想の影響が色濃く残る北朝鮮と韓国、中華人民共和国(PRC)の指導者には絶対に通じない。ドナルド・トランプ米大統領のアジア歴訪を見ていて、それを再認識した。”「儒教を代表する思想家・孟子の「至誠」の考えというのは、儒教思想の影響が強く残る国の指導者には絶対通用しない。」というこの展開に、まだまだ私には産経力が足りないなという思いを深くしたわけです。そもそも「絶対通用しない」のならば、最初から「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」という言葉が成立しなくなるわけですが、孟子の言葉なのに、なぜ儒教の思想の影響が色濃く残る国では通用しないなどいう発想が出てくるのか・・・?今見てみたら、私と同じような疑問を持った人が直接本人に聞いてます。今日はこの辺で。
2017.11.19
コメント(2)
-

『ベストキッド』と荘子・改。
ちょっと修正版を。だいぶ古いやつですが。昨夜は『ベスト・キッド』のリメイク版を鑑賞いたしました。『ベスト・キッド』というタイトルなのは日本だけで、原題は『KARATE KID』のままなんですが、中身は功夫映画です。もともと空手というのは、中国拳法が琉球に伝わって「唐手」として発展したものだし、アメリカでの『ベスト・キッド』の技法は中国武術のものばかりだし、カラテブームの下地をつくったのは、ブルース・リーのカンフーブームものなわけで、しょうがないといえば、しょうがないんですけどね。参照:ベスト・キッド Wikipediahttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%89_(2010%E5%B9%B4%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB) 基本はアメリカ映画ですし、アメリカ人が描く東洋という意味では、『キル・ビル』の1と2の関係みたいなものとして、日本と中国の位置を捉えるのが自然かなと。参照:Daryl Hanna vs Uma Thurman kill bill vol.2 http://www.youtube.com/watch?v=nQluEsgdK-E&feature=related『キル・ビル』は東アジアのB級モノを見事に織り込んでいましたが、今の日本人の意識も大して変わらないんじゃないかと思われます。アメリカではよくある武士道とクンフーの混合物・・・。今回の『ベスト・キッド』では、ロケ地として武当山が選ばれています。武当山は、湖北省十堰市にある道教の聖地で、「武当拳」発祥の地でもあり、1994年には世界遺産にも指定されています。通常カンフーモノというと少林寺のイメージで仏教からのアプローチというのが多いですが、リメイク版の『ベスト・キッド』は道教の思想をベースに描かれています。参照:Wikipedia 武当山https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E5%BD%93%E5%B1%B1典型的なものとしては、「氣(Qi/Chi)」の理論です。Dre Parker: So what are we learning today?(それで、今日は何を勉強するの?)Mr. Han: Chi. Internal energy. The essence of life. It moves inside of us. It flows through our bodies. Give us power from within.(今日は「氣」について学ぶ。生命の本質だ。我々の内に流れるもの。我々の身体にあって、活動の源となるものだ。)Dre Parker: I get it. Like the Force in Star Wars. You're Yoda and I'm like... I'm like a Jedi.(分かった。『スター・ウォーズ』のフォースみたいなもんだね。なら、ハンさんがヨーダで、僕がジェダイの騎士だ。)❝生也死之徒、死也生之始、孰知其紀。人之生、氣之聚也。聚則為生、散則為死。若死生為徒、吾又何患。故萬物一也。其所美者為神奇、其所惡者為臭腐。臭腐復化為神奇、神奇復化為臭腐。故曰『通天下一氣耳。』聖人故貴一。❞(『荘子』知北遊 第二十三)→ 生には死が伴い、死は生の始まりである。だれがその初めと終わりを知り得よう。人の生は【氣】が集まったもの。集まれば生となり、散じれば死となる。生と死とが一体であるとすれば、私は何を思い煩うことがあろうか? 故に万物とは一つのものなのだ。人は美しく立派なものを尊び、腐って汚いものを憎む。しかし、腐って汚いものいずれは変化して、美しく立派なものとなり、かつて尊んでいたものも、やがては腐って汚いものと変化する。故に『天下は全て一つの氣の巡り』という。聖人はそこに貴賤を設けず、その「一」を貴ぶのである。生命の根源としての「氣」について、荘子の記述とも変わらない、道教の側からの説明をしています。また、氣の説明を聞いて『スター・ウォーズ』の「フオース(Force)」と絡めるのも特徴的です。ジャッキーもセリフの中で「Kung Fu is for knowledge, defense. Not to make war, but to create peace.(クンフーは防御のための知恵であって攻撃のためのものではない、平和を守るための知識である。)」と、ジェダイの説明をする場合の、ヨーダと同じことを諭します。「The best fights are the ones we avoid.(最良の戦士は戦いを避けるものだ)」「You've seen only with your eyes, so you are easy to fool. (目に見えるものばかり信じていると、簡単に愚かになるぞ)」といったセリフにも、道教の思想とジェダイの騎士の道との関連性を想起させます。❝善為士者、不武。善戰者、不怒。善勝敵者、不與。善用人者、為之下。是謂不爭之徳、是謂用人之力、是謂配天古之極。❞(『老子』第六十八章)→優れた士は武力を用いない。戦上手は怒ることがない。善く敵に勝つ者は、相手に飲まれない。よく人を用いる者は、自らを下手に置くものだ。これを「不争の徳」といい、これを「人用の力」といい、これを「天に配される古の極み」という。参照:マスター・ヨーダと老荘思想 その1。https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5025/老荘思想や禅と武術との関係は、ジャッキー・チェンと、ジェット・リーが共演した、『ドラゴン・キングダム(The Forbidden Kingdom 2008)』の方が上手く表現されています。 ❝カンフーの習得には、長くつらい修行が続く画家もカンフーの達人そして熟練の包丁人は骨に触れずに、肉を切ることができる型を学び、型を追い求めず無音の音を聴く全てを学び、全てを忘れる古からの技を学び、独自の技を見出す音楽家もカンフーの達人詩人は言葉の絵画で、帝(みかど)の涙を誘うこれもカンフーそのパワーは水の流れと同じ限りなく柔らかく、だが、硬い岩をも打ち砕く相手に逆らわず、流れるように包み込む名前も型も無い極意は己の内にあり解き放てるのは己だけ❞(以上、『ドラゴン・キングダム』より引用)参照:Wisdom of Two Masters [Forbidden Kingdom] - YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=d4zqELsPOhA・・・これは、職人の妙技に見える身体的技法や、芸術を通して悟りに到達するという方法論で、道教や、中国化した仏教であるところの禅宗の特色のひとつです。今回の『ベストキッド』では、ジャッキー・チェンが師として功夫を教えるという立場だったので、ブルース・リーを意識したつくりになっていたかな、と思います。作品の良し悪しはともかく、いかに功夫の知恵を伝えるか、ということに関しては成功だったと思いますね。“Empty mind."であったり、“Fighiting without fighting.”もちゃんと組み入れてあります。“Empty your mind, be formless, shapeless - like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup, you put water into a bottle, it becomes the bottle, you put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.”(「心を空っぽにして、どんな形態も形も捨てて水のようになるんだ。 水をコップに注げば水はコップとなるし、 水をティーポットに注げば水はティーポットになる。 水は流れることも出来るし、激しく打つことも出来る。だから、友よ、水のようになるよう心掛けることだ。」(日本語訳は『Cowboy Bebop』#XX よせあつめブルース より))参照:Tao of Bruce Lee - Be like waterhttp://www.youtube.com/watch?v=V3B1JtMA0Fcもう一つ気になったのが「竜の泉」なる湧水を飲むシーン。Mr. Han: Look.What do you see?(見てみろ、何が見える?)Dre Parker: Me. Well, my reflection. (僕・・・うん、反射した僕)Mr. Han:Yes. Now what do you see? (そうだな。(水面をかき混ぜて)何が見える?)Dre Parker:It's blurry.(波立って見えないよ。)Mr. Han:Yes. The woman was like still water. Quiet, calm. In here and in here.So, the snake reflects her action, like still water.(そうだな、さっきの女性はまるでこの水のようだった。心も、身体も静かで穏やかなままだった。だから、蛇の方がずっと水のようでいる彼女の姿をまねるようになった。) Dre Parker: Like a mirror. (まるで鏡のように。)Mr. Han:Yes. (そうだ。)Dre Parker:So she controlled a snake by doing nothing? (彼女はなにもしないまま、蛇をコントロールしたってこと?)Mr. Han:Being still and doing nothing are two very different things.(「そのままでいること」と「なにもしないこと」というのは、同じようでいて全く違う事柄だ。) 水と鏡のたとえ。日本人にもおなじみの、「明鏡止水」の境地です。❝仲尼曰「人莫鑑於流水、而鑑於止水、唯止能止衆止。受命於地、唯松柏獨也在、冬夏青青、受命於天、唯舜獨也正。幸能正生、以正衆生。夫保始之?,不懼之實。勇士一人、雄入於九軍。將求名而能自要者、而猶若此、而況官天地、府萬物、直寓六骸、象耳目、一知之所知、而心未嘗死者乎!彼且擇日而登假、人則從是也。❞(『荘子』 徳充符 第五)→仲尼はこう言った。「流れている水は人の姿を映す鏡にはならない。静かな水面こそ万物の姿を映す鏡になる。静かな心であるからこそ、王駘は他人の心を映し出し、人々の足を止めることができるのだ。大地に命を受けたものの中では、松や桧が夏も冬も変わらずに青々としているように、天に命を受けたものの中では、ただ舜帝一人のみが、正しく行いをなしえた。彼だけが民衆を正しい道へと導けたのだ。生来受けた本性を保ち得るならば、人は何者にも恐れることはない。勇士が大軍を前にして、たった一人でも怯まずに突き進むのは、ただ、名誉を求めるがためのことである。俗事にとらわれた勇士であっても、その調子なのだから、天地を司り、万物と一体となり、五臓六腑も、耳も目も仮のものとして、さかしらな知に惑わされず叡智と共にあるの者ならば、死の恐怖など気にも留めない。かの王駘は、脚の不自由な障害者でありながら、その境地にあるがゆえに、人々は彼を慕って従うのだ。」❝心は明鏡止水のごとし、といふ事は、若い時に習つた剣術の極意だが、外交にもこの極意を応用して、少しも誤らなかつた。かういふ風に応接して、かういふ風に切り抜けうなど、あらかじめ見込みを立てゝおくのが、世間の風だけれども、これが一番悪いヨ。おれなどは、何にも考へたり目論見たりすることはせぬ。❞(『氷川清話』より 勝海舟の言葉)"Your mind is like this water my friend, when it gets agitated it becomes difficult to see. But if you allow it to settle the answer becomes clear."(友よ、そなたの心はまるでこの水のようだな、波立っていると何も見えない。しかし、その事象を受け入れ、落ち着きを取り戻せば、答えは自ずから見えてくる。)参照:Master Oogway's wisdom http://www.youtube.com/watch?v=lElihYvhSqA&NR=1&feature=endscreen・・・『ベスト・キッド』もうひとつの収穫は「物极必反(ウージービーファン wùjíbìfǎn)」です。「何事もやり過ぎはよくない」という意味で使われた言葉ですが、日本語の漢字にあてると「物極必反(物事は極まると必ず反する)」となります。大変道教的な、中国的な言葉です。今日はこの辺で。
2017.09.24
コメント(4)
-

荘子と進化論 その202。
荘子です。 -----(以下引用)-----------------------------------------------------(CNN) 人間は墓の中に入っても環境へ影響を与え続ける。安らかに眠っている間も、伝統的なひつぎに一般に使われる木材や合成物質のクッション材、金属類が地球を汚し続けている。 米テネシー大学のジェニファー・デブルイエン准教授は「こうした素材の製造にも多くのエネルギーが投入されているが、ごく短時間使用しただけで埋められてしまう。分解するのも早くない」と指摘する。イタリアのデザイナー、ラウル・ブレッツェルとアンナ・チテッリの両氏はこの問題の解決策を見つけたかもしれない。その名も「カプスラ・ムンディ」(ラテン語で「世界のカプセル」の意味)。有機材で作られた卵形のひつぎで、遺灰を収めるのにも適している。 ひつぎが地中に埋められると、生分解性プラスチックの殻が分解する。遺体は上に植えられた苗木に栄養を送るという。墓石ではなく樹木で覆われた墓地を作り、廃棄物を減らして、死から新たな生を生み出すのが目標だ。カプスラ・ムンディの発想が生まれたのは2003年。イタリア北部ミラノで行われた国際見本市の終了に伴い、大量の家具が廃棄されるのを2人が目の当たりにしたときのことだ。ブレッツェル氏は「新しいものをデザインする大会だったのだが、将来的な影響や、実際に誰がこうしたものを使うのかについて、ほぼ誰も気に懸けていなかった」と話す。2人は現在、製品の第1弾を販売中だが、その用途は遺灰のみに限られる。今後のモデルは遺体の収容に適したものとなる見通しだ。 まず地中の微生物がバイオプラスチックを分解すると、遺灰は徐々に土壌と接触していく。この過程で土壌の化学的なバランスが過度に変化することはない。カプスラ・ムンディの上に種をまくという考えも魅力的かもしれないが、米テキサスA&M大学のジャクリーヌ・ペターソン准教授は、もう少し成長した木を使う必要があるとの見方を示す。遺体は1年以内に殻の外に出るために栄養物はかなり早く土壌内に放出されると指摘。「従って、ある程度の大きさの木を上に植えるのが鍵となるだろう」と述べた。 だが本当に環境に良いのだろうか。デブルイエン氏は、「伝統的な埋葬法の問題点は完全に無酸素状態であることだ。遺体は地中深くに埋められ、ひつぎの中に密閉される。十分に分解されない部分が多い」と説明する。 「今回のカプセルの場合、一定の酸素流入を維持できる可能性がある。(主にデンプンで作られたバイオプラスチックから)炭素ももたらされる。人体の分解に当たって制約や課題のひとつになるのは窒素が豊富な点だ。こうした窒素をすべて分解しようとする微生物には、バランスを取るため一定の炭素が必要になる」(同氏)環境に対する意識の変化も、埋葬にまつわる文化的障壁の打破につながっている。 北米の環境団体「グリーン・ベリアル・カウンシル」のケイト・カラニック氏は、「環境に優しい埋葬方法への関心は この2年間で高まってきた」と言及。その背景にはベビーブーム世代の環境意識や、自身の遺体の処理方法への関心があるとの見方を示す。 法的な問題に関しては、北米全域で合法だという。ただ、他所では話が変わってくるようだ。ブレッツェル氏は、イタリアではこの種の埋葬方法は許可されない可能性があると指摘。「合法化に向けた請願の署名を集めているが、規則変更の実現はだいぶ先のことになるだろう」と話す。-----------------------------------------------------(引用終わり)----- 死から生へ――生分解性の埋葬カプセル、遺体を樹木の栄養にhttps://www.cnn.co.jp/fringe/35103340.html この不思議なカプセルを「カプスラ・ムンディ(Capsula Mundi)」というそうです。 参照:Capsula Mundihttp://www.capsulamundi.it/en/ 参照:Youtube Capsula Mundi - Burial Podshttps://www.youtube.com/watch?v=fHkZZNlxLzo ❝莊子將死,弟子欲厚葬之。莊子曰「吾以天地為棺槨,以日月為連璧,星辰為珠璣,萬物為齎送。吾葬具豈不備邪。何以加此。」弟子曰「吾恐烏鳶之食夫子也。」莊子曰「在上為烏鳶食,在下為螻蟻食。奪彼與此,何其偏也。以不平平,其平也不平;以不徵徵,其徵也不徵。明者唯為之使,神者徵之。夫明之不勝神也久矣,而愚者恃其所見入於人,其功外也,不亦悲乎。❞(『荘子』列御寇 第三十二)→ 荘子が臨終を迎える間際、弟子たちは彼を手厚く葬ろうと考えていた。しかし、荘子はこう言った。「天地を棺とし、太陽と月を一対の璧として、天空の星々を飾りにすれば、葬式などはいらない。死にゆく私の死を見届けるのはこの世界の万物だ。何もしなくとも私の葬儀の準備は終わっている。何が他に要るというのか?」弟子たちは、「亡くなっても何もしないとあっては、あなたの死体がカラスやトビに食べられてしまいます。私たちはそれを心配しているのです。」と答えた。荘子は言った。「地上にあってはカラスやトビについばまれ、地下にあってはオケラやアリに齧られればいい。埋葬するというのは、トビやカラスの獲物をわざわざえり好みして、オケラやアリに与えるようなものだ。なんとも手前勝手な理屈だ。本来公平でない「知」によって公平にしようとも、それは公平にはならない。自然に根差さない人為に基づく感性によって自然を感得しようとも、それは自然の姿ではない。明知の者は外物に使役されているだけの者であり、神知の者こそが自然の感性を体得しているのである。人為による明知が自然の神知に及びえないは古くから言われることであるが、世の愚か者たちは、自らの明知を恃んで人を見ようとする。そのはたらきが外物によることも知らずに。悲しむべきことではないか。」 荘子っぽかったのでメモ。オチもないまま、今日はこの辺で。
2017.09.17
コメント(0)
-
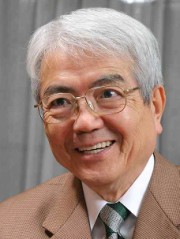
静岡新聞『論壇』における屋山太郎さんのパクリについて考える。
ちょっと、今日は屋山太郎(ややまたろう)さんの以下の文章について。6月28日付の静岡新聞、屋山さんの連載「論壇」からです。------(引用始め)----------------------------------------「国際法規を無視する中国・韓国」 ―「公」より「私」を優先する儒教国家の神髄― - 屋山太郎 韓国の文在寅大統領はロイター通信とのインタビューで日本について「慰安婦問題を含め、韓国との過去の歴史問題を解決するために、最善の努力をしていない」と批判した。 歴代、韓国大統領は日本に対して「謝り足りない」との決めゼリフを吐くが、日韓両国は1965年、「日韓基本条約、経済協力協定で一切の貸し借りはない」ことを約束したのである。条文を読めば両国関係はきれいに清算されているのがわかる。しかし国交回復後も韓国政府は何度も請求した。宮沢喜一氏の訪韓に当たっても“河野談話”で譲歩し“協力資金”も与えた。それでも対日要求が止まらないから、安倍首相は米政府や国際監視の下で新たな譲歩案を出した。10億円の見舞金とともに慰安婦問題については「最終的かつ不可逆的な解決」にすると朴前大統領と約束したのである。 安倍首相は「不可逆的」との言葉が入ることで問題を終着させたと思い込んでいる。しかし文大統領は「韓国国民が合意を受け入れられない」と述べ、「合意」の見直しを要求する構えである。日本では「約束」すれば「武士に二言はない」と庶民でも受け入れる。首相の発言を認めないというのでは日本という国が成り立たないと、国民の誰もが思う。 ところが、韓国の常識では「公」が優先するわけでもなければ絶対でもない。韓国は自ら“本家”だと自称する儒教国家である。儒教は紀元前5、4世紀に活躍した孔子の教えであり、その言葉を弟子達がまとめたものが「論語」である。日本にも江戸の上期に朱子学として入ってきたが、戦国時代が終り、武家社会の安定期に入ってきたから、中国や韓国とは致命的な部分で解釈が違う。 孔子にある村長が判断を求めてきたという。「子供が自分の親が羊を盗んだ、と告げてきた。どうすべきか」。孔子は「子供が親の罪をかばうのを正直という」と答えた。儒教には「公」の意識はなく、まず守るべきは家族なのである。 秦の始皇帝は紀元前220年に建国した際、儒教の弊害を見抜いて壮大な「焚書坑儒」を断行した。460人の儒学者を殺害し儒教書を焼き、道教を国教と定めた。華美ではなく教えも優しいからだったという。だが紀元前1世紀の漢末には、道教は廃れて儒教が復活した。「公」の精神がなく、際限なく「私」を追求するのが儒教であって、その本家の朝鮮で半数近い奴隷が発生したのも不思議ではない。 「公」より「私」を重視するからこそ、文大統領が“国際文書”あるいは“国際公約”についてさえ「国民が納得しない」という反応を示すのは不思議ではない。「私」「一族」を最重視するから、役に就けば役得を得るのは当然だ。とどのつまり韓国は10ほどの財閥があらゆる財と利権を握ることになった。今の韓国の社会構造は日本併合時の韓国。つまり両班(やんばん)(貴族)が4~5%で、残りは平民と奴隷が半分ずつだったのと本質的に変わらない。また中国にも韓国にも「恥」という概念がない。中国も毎年10万人単位で高位の役職者が金を持って国外に逃亡するという。南シナ海に対する国際仲裁裁判所の判決について中国の王毅外相が「そんなものは紙屑だ」と切って捨てた。儒教の神髄というべきか。(平成29年6月28日付静岡新聞『論壇』より転載)------(引用始め)----------------------------------------参照:「国際法規を無視する中国・韓国」 ―「公」より「私」を優先する儒教国家の神髄― - 屋山太郎 http://blogos.com/article/231483/・・・義務教育の段階で学ぶ知識ですが、百済から五経博士が渡来した継体天皇の7年(西暦513)を日本における儒教の伝来とみるのが一般的です。❝七年夏六月、百濟遣姐彌文貴將軍・洲利卽爾將軍、副穗積臣押山百濟本記云、委意斯移麻岐彌貢五經博士段楊爾、別奏云「伴跛國、略奪臣國己汶之地。伏願、天恩判還本屬。」秋八月癸未朔戊申、百濟太子淳陀、薨。(『日本書紀』巻第十七)❞→継体天皇の七年夏六月。百済は姐彌文貴将軍(さみもんくいしょうぐん)・洲利卽爾将軍(つりそのしょうぐん)の両名を派遣して穂積臣押山(ほづみのおみのおしやま)〔百済本記によると「委(やまと)の意斯移麻岐彌(おしやまきみ)」のこと。〕にて五経博士の段楊爾(だんように)を同行させて遣わしました。また別に 「伴跛国(はへのくに)は、我々の己汶(こもん)の土地を略奪しました。伏して願わくは、天恩により本属へお返しくださいますよう。」と、奏上しました。 その秋の八月二十六日、百済の太子の淳陀(じゅんだ)が亡くなりました。❝科賜百濟國、若有賢人者、貢上。故受命以貢上人名、和邇吉師。即論語十卷・千字文一卷、并十一卷、付是人即貢進。〔此和邇吉師者、文首等祖〕(『古事記』応神天皇記)❞→応神天皇が百済の国に「もし賢人がいるのならば遣すように」とお命じになられた。その命を受けて遣わされた人の名を「和邇吉師(わにきし)」という。すぐさま『論語』十巻、『千字文』一巻、合わせて十一巻が和邇とともに献上された。(この和邇吉師が、文首(ふみのおびと)らの祖である)儒教の最も著名なテキストである『論語』は、応神天皇の時代、百済から王仁(古事記では和邇吉師)と共にもたらされたと『古事記』に記されています。『論語』は少なくとも五世紀初頭には日本に伝来したと思われます。儒教における重要な「書物」と儒教の「専門家」がいつ日本に来たのか、その重要性を知るからこそ、先人は記紀の両方に記録してあります。参照:Wikipedia 王仁https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E4%BB%81>日本にも江戸の上期に朱子学として入ってきた・・・などという屋山さんの主張とは、千年ほどずれてしまいますけどね。さらに、屋山さんは、>孔子にある村長が判断を求めてきたという。「子供が自分の親が羊を盗んだ、と告げてきた。どうすべきか」。孔子は「子供が親の罪をかばうのを正直という」と答えた。儒教には「公」の意識はなく、まず守るべきは家族なのである。>秦の始皇帝は紀元前220年に建国した際、儒教の弊害を見抜いて壮大な「焚書坑儒」を断行した。460人の儒学者を殺害し儒教書を焼き、道教を国教と定めた。華美ではなく教えも優しいからだったという。だが紀元前1世紀の漢末には、道教は廃れて儒教が復活した。「公」の精神がなく、際限なく「私」を追求するのが儒教であって、その本家の朝鮮で半数近い奴隷が発生したのも不思議ではない。・・・と続けるわけですが、ここはモルモン教の宣教師であるケント・ギルバートさんのべスセラーの丸パクリです。------(引用始め)---------------------------------------- 儒教を説いた孔子は紀元前五五二年に生まれ、同四七九年に亡くなったと伝えられています。その後、孟子を筆頭とする孔子の思想の継承者たちが、儒教を中国大陸に広めました。 紀元前二二一年に中国最初の統一王朝である秦が成立します。すると儒教は始皇帝の命令で禁じられます。有名な「焚書坑儒」が行われました。儒教の書物は燃やされ、儒教の学者四六〇人余りが生き埋めにされて、虐殺されました。 始皇帝は儒教ではなく、道教を政治に採り入れます。道教は儒教と比べると簡素な教えで、儒教が好む華美さを持たない点が始皇帝に好まれたといいます。 始皇帝が亡くなると、秦は漢を建国した劉邦に滅ぼされます。やがて漢王朝が数世代続くうちに、簡素な教えの道教よりも、敬礼威儀を主張する儒教へと、為政者たちは傾斜していきます。(『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』 (講談社+α新書)より)----------------------------------------(引用おわり)------------(引用始め)----------------------------------------儒教と共産主義は最悪のコンビ それでは、儒教思想二五〇〇年の「呪い」とは何でしょうか。 この話に入る前に、儒教の聖典ともいうべき『論語』について、もう少し説明する必要がありそうです。 たとえば、『論語』に次のような一節があります。<葉公語孔子曰、吾黨有直躬者、其父攘羊、而子證之、孔子曰、吾黨之直者異於是、父爲子隱、子爲父隱、直在其中矣>【書き下し文】葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰わく、吾(わ)が党に直躬(ちょくきゅう)なる者有り。其の父、羊を攘(ぬす)みて。子之を証せり。孔子曰わく、吾が党の直(なお)き者は是れに異なり。父は子の為めに隠し、子は父の為に隠す。直きこと其の内に在り。(『論語の講義』諸橋轍次著、大修館書店、P300)これは次のような話です。葉(しょう)という県の長官が、「私の村の直躬(ちょくきゅう)という正直者は、父親が羊を盗んだのを知って、子どもなのに訴え出ました」 と孔子に話しました。すると孔子は、「私の村での正直とは、この事例とは違います。父は子のために罪を隠してかばい、子は父のために罪を隠してかばうものです。この罪を隠すことのなかにこそ、正直の精神があるのです」と諭したのです。 中国では、孔子以前から祖先崇拝の精神が強く伝えられ、その家族愛や信義などを孔子が『論語』にまとめました(正確には孔子の弟子たちが編纂しましたが)。この精神は脈々と受け継がれ、中国大陸の十数回に及ぶ「易姓革命」や、封建的な伝統文化のすべてを悪と決め付け、破壊しようとした中国共産党の「文化大革命」という逆風のなかでも生き残ったのです。 その一方で、「仁・義・礼・智・信」といった道徳心や倫理観は、文化大革命の影響で最終的には失われてしまったのです。 先ほど述べた「公」よりも家族愛を上に置く価値観を突き詰めていくと、結果的に「公」よりも「私」を重んじる方向へ向かいます。それは「私」や「一族」の利益のためなら、法律を犯すこともよしとする風潮へ変化していったのです。(『儒教に支配された中国人と韓国人の悲劇』 (講談社+α新書)より)----------------------------------------(引用おわり)------・・・このケント本自体も、序盤から飛ばしていまして、焚書坑儒を肯定的にとらえたり、始皇帝が道教を国教とするとか、道教が簡素で儒教が華美さを求めるという謎の傾向とか、著者のファンタジーがいろいろと散りばめられております。参照:田母神論文を継ぐ男。 https://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201510250000/しかし、まずは40万部以上売れているベストセラーから堂々とパクる屋山さんの勇気を称えたいですね。静岡新聞の関係者や読者にとってはどうでもいいのかもしれませんが、私なんかはタイトルを読んだ瞬間にビビっときてしまいます。ちなみに、この丸パクリさんが、『新しい日本の歴史』という教科書を育鵬社という会社から発行している「改正教育基本法に基づく教科書改善を進める有識者の会」の代表でいらっしゃいます。Wikipedia 教科書改善の会https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8%E6%94%B9%E5%96%84%E3%81%AE%E4%BC%9A・・・パクリ元のケントさんの本にも屋山さんの「論壇」にも最後の方に『論語』の子路第十三にある「直躬(ちょくきゅう)」の話が載っています。解釈云々以前に、実は、このお話における命題は、日本の刑法に同じ趣旨のものがあります。第103条(犯人蔵匿等)罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。第105条(親族による犯罪に関する特例)前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 明治期に刑法ができたころにはすでにあったそうですが、現行の日本の刑法典にも載っています。犯罪を犯した者の親族が、犯罪を犯した者を隠したり、隠避させたとしても、その親族の行為については刑を免除できるというもので、まさに『論語』における孔子の思想の制度的保障といえる条文です。昔から儒教の影響として指摘される条文でして、ケント・ギルバートさんや、それをパクった屋山太郎さんの意見が正しいならば、日本こそ「儒教の呪い」とやらにどっぷりつかった社会となってしまうでしょう。儒教の思想の根幹である「修身斉家治国平天下」にも「斉家」がありますが、社会の最小単位である家族を蔑ろにしては「修身」のみならず国も天下も定まりません。ケント本に関してはまたいずれ。後で推敲予定。今日はこの辺で。
2017.07.13
コメント(0)
-
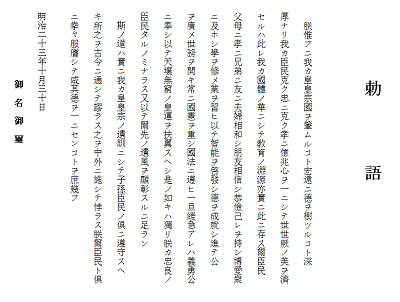
『教育勅語』と儒教。
久しぶりに更新。今日は、森友学園問題で久しぶりに話題になった『教育勅語』について。『教育勅語』は、明治23年(1890)に当時の教育の理念を説いた文書で、明治天皇の言葉(勅語)として発布されたものです。それから58年後の昭和23年(1948)に、国会の決議により廃止されました。当時は学校の奉安殿に天皇陛下のご真影と共に保管され、祝日に校長先生がうやうやしく朗読し、尋常小学校の頃には暗誦させられるというものであったそうです。この「勅語」の教育を実際に受けた方も少なくなりましたが、戦前の教育の基本であり、現在でも一部の人々から復活を叫ばれることがあります。この『教育勅語』と儒教との関係について。参照:Wikipedia 教育ニ関スル勅語https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2%E3%83%8B%E9%96%A2%E3%82%B9%E3%83%AB%E5%8B%85%E8%AA%9EWikipedia 奉安殿https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%89%E5%AE%89%E6%AE%BF『教育勅語』は、戦前において存在していた「修身」という科目の教科書に書かれていました。「修身」という言葉は、四書五経のうちの『大學』にある「格物」「致知」「正心」「誠意」「修身」「斉家」「治国」「平天下」の八つの項目のうちの「修身」がその由来です。『大學』という書物は、朱子学の最も基礎的なテキストであり、日本では二宮金次郎さんが薪を背負って歩きながら読んでいる書物として有名ですね。この『大學』には「心正而后身修。身修而后家斉。家斉而后国治。国治而后天下平。 (心が正しくなった後に、我が身が修まる。我が身が修まった後に、家の秩序が整う。家が整って後に、国が治まる。国が治まった後に、天下は平安となる。)」などとありまして、天下の安定のためには、国や家のような、より小さな社会単位だけでなく、個々人の単位での修養も必要とされ、その方法論を「修身」と呼びます。Wikipedia 修身https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E8%BA%AB 「教育勅語」や「修身」といった徳育を重視する制度が、明治の中期、23年という時期に始まったのには理由があります。それは、明治維新以降に急激に西洋化し、物質化していく「近代」への反動がきっかけでした。早い話が、明治以降に生まれた若者たちに江戸の常識が通用しなくなったんです。江戸時代の官学や基礎教育は儒教ですし、明治維新後であっても、人文学、社会学の分野での儒教の影響がまだまだ大きな時代ですから、西洋的で近代的な流れの対極に、東洋的で復古的な運動のよりどころとして儒教の思想が求められたのは自然なことでした。❝敎育ニ關スル勅語 朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン 斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ明治二十三年十月三十日御名御璽❞「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス」(上記『教育勅語』より)→朕(明治天皇)が思うには、わが皇祖皇宗が国を始めるにあたり、その版図は広く、またその打ち立てられた徳は深遠なものであった。我が臣民は忠・孝の徳に篤く、億兆の国民がこころを一つに、代々その美風を受け継いできたのは我が国の国体の精華であり、我が国の教育の原点もまたここに存している。・・・『教育勅語』はその冒頭において、臣民の在り方について「克(よ)ク忠ニ克(よ)ク孝ニ」として、基本的な儒教の徳目である「忠」「孝」について言及しています。この「克忠」「克孝」という表現は、いずれも四書五経のうち、伝説上の人物の言行録『書経(尚書)』にあります。前者は「商書(伊訓)」の「居上克明,為下克忠,與人不求備,檢身若不及,以至于有萬邦,茲惟艱哉。」、後者は「周書(微子之命)」の「恪慎克孝,肅恭神人。」です。ちなみに、「克忠」「克孝」共に『古事記』や『日本書紀』にある表現ではありませんし、そもそも『古事記』には「忠」「孝」という徳目すら記録にありません。現代の日本では『教育勅語』の内容について、「十二の徳目」などという珍妙な用語を使用して説明をすることがありますが、当ブログでは、教育勅語の徳目の主軸は、本文の中でそれぞれ二度、象徴的に使われている「忠」と「孝」であると解釈します。参照:明治神宮 教育勅語http://meijijingu.or.jp/about/3-4.html「勅語」は次にこう続きます。「爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重ジ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」(上記『教育勅語』より)→あなたたち臣民は、父母には孝行し、兄弟には仲良くし、夫婦は互いにむつまじく、友人同士はともに信じあい、常に慎み深く、誰に対しても博愛の精神を持ち、自らの学業に専念して自らの知能を啓発し、自らの徳の形成に努め、積極的に公共の利益を広めて社会のための仕事に励み、常に憲法を重視して法律を守り、何事かが起きた場合には、勇気を振り絞って、公のため、天地と共に永遠に存在する皇位の命運を扶助すべきである。ここで、孝の徳目を筆頭に、矢継ぎ早にいろいろな価値観が称揚されるわけですが、このうちの最初の部分は、『孟子』の「滕文公上」から。❝當堯之時,天下猶未平,洪水橫流,泛濫於天下;草木暢茂,禽獸繁殖;五穀不登,禽獸逼人;獸蹄鳥跡之道,交於中國。堯獨憂之,舉舜而敷治焉。舜使益掌火;益烈山澤而焚之,禽獸逃匿。禹疏九河,瀹濟、漯而注諸海;決汝、漢,排淮、泗,而注之江,然後中國可得而食也。當是時也,禹八年於外,三過其門而不入,雖欲耕,得乎?后稷教民稼穡,樹藝五穀,五穀熟而民人育。人之有道也,飽食暖衣,逸居而無教,則近於禽獸。聖人有憂之,使契為司徒,教以人倫:父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信。放勛曰:『勞之來之、匡之直之、輔之翼之,使自得之;又從而振德之。』聖人之憂民如此,而暇耕乎?❞(『孟子』滕文公上)→尭の時代には天下はまだ平らではなく、たびたび洪水が起こって天下に濁流が氾濫するようなありさまであった。草木は伸び放題で、禽獣はあふれており、五穀は足らず、禽獣が人のそばまでおびやかし、獣や鳥の足跡が中國のいたるところに踏みしめられていた。尭はひとりこれを憂い、舜にこれを治めるよう命じることとした。舜はさらに益に火を用いるよう命じた。益は山澤に火を焚いて、禽獸はその火から逃げ隠れうようになった。さらに禹は九河を渡した。瀹濟、漯を海まで通し、決汝、漢,排淮、泗は長江に注ぐようにした。この事業の後にようやく中国で食べることができるようになった。この当時、禹は八年の間戸外で働き、自宅の門を三度くぐったことはあったが宅内にまでは入らないというほどであった。それほどの境遇において、たとえ禹が耕作をしようとしても、それができたであろうか?后稷は民に農耕を教え、五穀を植えさせた。この五穀の実りが人民を育んだ。しかし、人の道というものがある。食に飽きて衣服にも不自由がなく、気ままに生活を続けても教えを受けないままでいると、人は禽獣にも似た様相を示すようになる。聖人はこれに憂いがあり、契をして司徒とし人倫を以て教化することにした。「父子には親愛があり、君臣には義理があり、夫婦には分別があり、長幼に順序があり、朋友には信義がある」と。尭曰く「民の労をいたわり、その誤りをただして直し、これを助けてこれを支え、自分自身でこれを判断できるように導き、徳の振るってこの徳に従うよう仕向けた。」聖人の憂いとは民に対してこれほどまでのものであった、自らの耕作に励む暇などあっただろうか?『孟子』の原文では、契という人物が人民に教えた人倫として、「父子有親,君臣有義,夫婦有別,長幼有序,朋友有信。」の五倫が記録されています。『教育勅語』での「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ」の部分の元ネタでして、長幼の序を引き抜くと、ほぼ同じ意味合いで語られています。また、もう少し範囲を広げて『孟子』において「五倫」の書かれた箇所を読んでみると、聖人による五倫の教化が、教育勅語の背景や動機とも共通点が多いことが読み取れます。さらに言えば『孟子』にある「人之有道也」は、『教育勅語』の最後の段落の「斯ノ道ハ」とも対応しています。・・・ちなみに、『教育勅語』において五倫類似の徳目以降の部分は、明治らしく、「博愛」であったり、「国憲」の重視等の近代的な価値観にみえる字句が並んでいますが、このうち「智能ヲ啓發」の「啓発」は『論語』からです。❝子曰、不憤不啓、不非不發、擧一隅而示之、不以三隅反、則吾不復也。❞(『論語』述而)→孔子はこうおっしゃった。「やる気の起きない者には、指導しない。口から出かかっているときには助けを出さない。四隅の一隅を示して、その三隅を推し量れないならば、私は次からその人を教えることをしないよ。」 『教育勅語』は「勅語」として、明治天皇のお言葉の形式をとっていますが、起草の中心人物として携わっていたのは当時の枢密顧問官・元田永孚(もとだ ながざね 1818~1891)と法制局長官・井上毅(いのうえ こわし 1844~1895)の二人でした。元田の方が形式的で原典の記録に忠実。井上の方が開明的で、伝統的な思想と立憲主義に基づいた西洋的価値観との両立を目指す立場という性格の違いはありましたが、当然のことながら双方ともに儒教の素養を備えた人物で、その影響は濃厚です。『教育勅語』の成立過程において両者がやり取りをしていた草案などを見ると、その経緯や意図を垣間見ることができます。❝我ガ皇祖皇宗、国ヲ肇メ民ヲ育シ、厥ノ徳宏遠、天壌窮リ無シ。我ガ臣民ノ祖先、克ク忠ニ克ク敬シ、万世易ラズ。是レ我ガ国体ニシテ、人道ノ基礎、教育ノ本原ナリ。君ハ臣民ヲ愛シテ、腹心股肱トナシ、臣民ハ君ヲ敬シテ、元首父母トナス。父慈ニ、子孝ニ、兄友ニ、弟恭ニ、夫婦和順、朋友相信ズ。之ヲ合セテ五倫ノ道トス。コノ五倫ヲ本トシテ、推テ他ニ及ボシ、己ガ欲セザル所ハ以テ人ニ施スコト無ク、親族和睦ジク、御隣相助ケ、国人相保チ、以テ億兆ヲ協和スルハ、我ガ国ノ大道ニシテ、汝臣民ノ共ニ由ル所ナリ。此ノ大道ニ由ラント欲セバ、智ヲ開キ、仁ヲ体シ、勇ヲ養ハザルベカラズ。智ハ万物ノ現を究メテ、普ニ明ラカニ義ニ精シク、進ンデ息キザルニアリ。仁ハ国家万物ヲ愛シテ、公儀私無ク、力行倦マザルニアリ。勇ハ仰イデ天ニ愧ヂズ俯シテ人ニ怍ヂズ、剛呆決断、敢為撓マザルニアリ。此ノ三ツヲ以テ人ノ大徳トシ、人性ノ固有ニシテ、我ガ国ノ善風美俗ヲ為ス所以ナリ。 斯ノ道、斯ノ徳は、則チ祖宗ノ遺訓、我ガ国臣民ヲ教育スルノ原理ニシテ、各国立教ノ異同ト風気ノ変遷トヲ問ハズ、以テ古今ニ照シテ謬ラズ、以テ中外ニ施シテ悖ラズ。汝臣民ト共ニ永久ニ率由シテ失ハザランコトヲ庶幾フ。❞(元田永孚著『教育大旨』)上記は元田の最終草案と推測されているものですが(講談社現代新書『天皇の日本の近代 下 教育勅語の思想』八木公生著等を参照)、こちらでは明確に「五倫の道」とあります。さらには智、仁、勇の三つの徳を強調しており、儒教のなかでも朱子学の影響がよく見られるつくりになっています。また、『論語』からも、最も有名な言葉の引用も見られます。❝子貢問曰。有一言而可以終身行之者乎。子曰。其恕乎。己所不欲。勿施於人。❞(『論語』衛霊公 二十三)→子貢が先生に質問した「先生、一生行うべきことを表す一言というのものがあるでしょうか?」先生はこうおっしゃった「それは恕(思いやり)だな。自分がしてほしくはないことを、他人にはしないことだよ。」最終的に発布された『教育勅語』では、井上毅の提唱により、漢文特有の言い回しや、哲学的な命題は忌避されています。元田永孚の案にある字句で削除、改定された部分も少なくありません。ただし、元田案では、現在において最も問題視される「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」というような、国家や天皇家のために奉仕べきであるというような論調はなく、仁の対象として「国家・万物」を挙げているなどを考慮すると、完成版の『教育勅語』よりも開明的な側面もあると思えます。ちなみに、『教育勅語』が発布された直後から、儒教との関連性の強さについて指摘がありました。たとえば、教育勅語が発布された明治23年(1890)11月3日の天長節に開かれた勅語の拝読会で、帝大の重野安繹(しげの やすつぐ 1827~1910)教授が、「勅語ノ大旨ハ、蓋シ忠君愛国及父子兄弟夫婦朋友ノ道ヲ履行スルニ在リテ、即チ五倫五常ノ道ナリ、五倫五常ハ儒教ノ名目ナレバ是ヲ儒教主義ト云フモ不可ナカルベシ。然ルニ斯ノ道ハ実ニ皇祖皇宗ノ遺訓ナリト宣ヒシハ深キ仔細アル事ナリ」と発言し、これが批判の的となりました。なにせ帝大の教授が公の場で「五倫五常を使っている『教育勅語』の中身は、儒教主義と言えなくもないのに、それを皇祖皇宗の遺訓と宣言してしまうのは・・」と言ってしまったわけで、この発言に対する非難の声も少なからず存在しました。重野教授は他にも、武烈天皇のように、『日本書紀』においてすら「頻りに諸悪を造し、一善も修めたまはず」と描かれている天皇についてまで皇祖皇宗に組み込んでしまうことについて否定的な見方をしたりと、率直に『教育勅語』の内容について指摘をしています。参照:Wikipedia 武烈天皇https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A6%E7%83%88%E5%A4%A9%E7%9A%87ただし、天皇陛下のお言葉として発布されて以降、『教育勅語』は年々その権威を強めていき、特に、実際の教育現場では、神聖不可侵な文書として扱われ、多くの学生がほぼ無批判の状態で暗誦を強いられました。戦後、国会の決議で廃止され、70年の歳月が経とうとしています。儒教のテキストのなかで最もポピュラーな『論語』において、孔子は弟子たちにこのように説いています。❝子曰、学而不思則罔、思而不学則殆。❞(『論語』為政第二)→先生はこうおっしゃった。「知識を学ぶだけで自分で考えないならば、見えないのと同じことである。自分で考えるだけで知識と照らし合わせることがなければ、危ういままである。」❝子曰、衆惡之必察焉、衆好之必察焉。❞(『論語』衛霊公第十五)→先生はこうおっしゃった。「皆が嫌っているものがあったとしても、必ず自ら考察しなさい。皆が好んでいるものがあったとしても、必ず自ら考察しなさい。」❝子曰、君子和而不同、小人同而不和、❞(『論語』子路第十三)→先生はこうおっしゃった。「君子は協調をしても雷同はしない。小人は雷同はしても協調はしない」後で推敲予定。今日はこの辺で。
2017.05.07
コメント(0)
-

荘子と進化論 その201。
『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』公開記念!やっと落ち着いてきたので、今日もスター・ウォーズと道教を。今回の『ローグ・ワン』では、中華圏からドニー・イェン(甄子丹)とジャン・ウェン(姜文)の二人の俳優が選ばれました。外伝とはいえ、スター・ウォーズ・シリーズにおいて主要キャラを東洋人が演じるという初めての事例です。特に、ドニー・イェンが演じるチアルート・イムウェ(Chirrut Imwe)は、アクションもさることながら、そのキャラクターそのものも世界的に好評だったようです。 今回のドニー・イェンの起用は、単に中国市場における人気取りを狙ったものだけでなく、「李小龍の名代として」もしくはその思想を体現しうる人物として選ばれたという意図はあったと思います。少なくとも『フォースの覚醒』では鳴りを潜めていた東洋思想的な要素が『ローグ・ワン』ではチアルートを中心に展開されています。参照:スターウォーズと功夫(Gongfu)。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5205/'Your eyes can deceive you, don't trust them.'(お前の目はお前自身を騙すことがある。目に見えることを信じるな。)というのは、ジェダイの訓練におけるオビ=ワンの言葉ですが、盲目であるというチアルートの設定は、フォースの本質をよく表現し得たのではないかと思います。 今回のチアルートのモデルとして座頭市の影響はもあるとは思うんですが(ベイズのデザインのモデルが赤胴鈴之助というのは確信しています)、当ブログとしては、まず金庸の武侠小説『射鵰英雄伝(1957)』『神雕侠侶(1959)』に登場する飛天蝙蝠(ひてんこうもり)・柯鎮悪(かちんあく)を挙げます。侠客集団・江南七怪の首領で、盲目です。主として伏魔杖という杖を操り、遠距離の場合には鉄菱という暗器を用います(対象が分からない場合には他の六怪が八卦で方向を知らせます)。奇しくも彼の仇である梅超風(ばいちょうふう)も作中で視力を失いますが、金庸の小説では、盲目という設定は決して珍しいものではありません。それに全真七子と江南七怪の関係が、ジェダイ評議会とローグ・ワンのメンバーとの関係に相応しています。 参照:スターウォーズと武侠。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5200/ もう一人がアメリカのテレビシリーズ『Kung Fu(燃えよ! カンフー)(1972)』の盲目の僧侶、ポー師匠です。ブルース・リーの原案によるカンフーモノの連続ドラマで、視覚に頼らずに世界を知る術を説き、禅仏教や老荘思想の基本を示すポー師匠のセリフは、マスター・ヨーダのそれと同質のものもあります。参照:The Tao of Kung Fu 1 Fear is the only darkness https://www.youtube.com/watch?v=40syAE-sRdE&list=PL-Z3T5S3xcUVJG9v1TdN0Qn6Shf89CmIw&index=1The Tao of Kung Fu 18 Disregard how others see you1 https://www.youtube.com/watch?v=qE--ckdC2-g&list=PL-Z3T5S3xcUVJG9v1TdN0Qn6Shf89CmIw&index=18❝此謂王德之人。視乎冥冥,聽乎無聲。冥冥之中,獨見曉焉;無聲之中,獨聞和焉。故深之又深,而能物焉;神之又神,而能精焉。故其與萬物接也,至無而供其求,時騁而要其宿,大小、長短、修遠。❞(『荘子』天地篇第十二)→王徳の人は、闇の中の闇を見、静寂の中の聲を聞く。闇の中の闇で一人、暁を見て、静寂の中で一人、調和のある声を聞く。故に、深層の中の深層で物を把握し、霊妙の先の霊妙で、その精を成しうる。次に、今回の『ローグ・ワン』において、チアルートのが取った最後の行動について。❝I'm one with the Force, and the Force is with me.(私はフォースと一つであり、フォースは私と共にある)❞という呪文を唱えながら、チアルートはブラスターの光線が飛び交う戦場で不思議な「弾除け」をします。まず、呪文。「フォース」と「氣」の関係のみならず、「一」の使い方が大変、荘子です。❝生也死之徒、死也生之始、孰知其紀。人之生、氣之聚也。聚則為生、散則為死。若死生為徒、吾又何患。故萬物一也。其所美者為神奇、其所惡者為臭腐。臭腐復化為神奇、神奇復化為臭腐。故曰『通天下一氣耳。』聖人故貴一。❞(『荘子』知北遊 第二十三)→ 生には死が伴い、死は生の始まりである。だれがその初めと終わりを知り得よう。人の生は【氣】が集まったもの。集まれば生となり、散じれば死となる。生と死とが一体であるとすれば、私は何を思い煩うことがあろうか? 故に万物とは一つのものなのだ。人は美しく立派なものを尊び、腐って汚いものを憎む。しかし、腐って汚いものいずれは変化して、美しく立派なものとなり、かつて尊んでいたものも、やがては腐って汚いものと変化する。故に『天下は全て一つの氣の巡り』という。聖人はそこに貴賤を設けず、その「一」を貴ぶのである。❝天下莫大於秋豪之末、而大山為小。莫壽乎殤子、而彭祖為夭。天地與我並生、而萬物與我為一。❞(『荘子』斉物論 第二)→天下において、秋の獣の毛先の先よりも巨大な存在はなく、大山よりも小さな存在はないとも言える。夭逝した者ほど長生きした者はおらず、八百年を生きた彭祖ほどの早死にをした者もいないと言える。天地は私と並び生じ、万物は私と共に「ひとつのもの」なのだ。参照:スターウォーズと道教 ~フォース(Force)と氣(Qi)~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5204/そして、本題の「弾除け」です。 こちらは、1998年のディズニー映画『Mulan(ムーラン)』のワンシーンです。左側がムーランのおばあちゃんが、往来の激しい通りを目隠しをしながら渡り切るもの。右側が兵士の訓練の際にヤオというキャラクターの功が成って、火箭の飛び交う中を走り抜けるというものです。『ローグ・ワン』におけるチアルートの行動とよく似ています。参照:Mulan - cricket scene https://www.youtube.com/watch?v=wjvHcXjAPxIMulan | I'll Make a Man Out of You | Disney Junior UK https://www.youtube.com/watch?v=vGfJeW_CcFY・・・これは道教における道術の一種として4世紀の『抱朴子』に記録があります。❝夫人在氣中,氣在人中,自天地至於萬物,無不須氣以生者也。善行氣者,內以養身,外以卻惡,然百姓日用而不知焉。吳越有禁祝之法,甚有明驗,多炁耳。知之者可以入大疫之中,與病人同床而己不染。又以群從行數十人,皆使無所畏,此是炁可以禳天災也。或有邪魅山精,侵犯人家,以瓦石擲人,以火燒人屋舍。或形見往來,或但聞其聲音言語,而善禁者以炁禁之,皆即絕,此是炁可以禁鬼神也。入山林多溪毒蝮蛇之地,凡人暫經過,無不中傷,而善禁者以炁禁之,能辟方數十里上,伴侶皆使無為害者。又能禁虎豹及蛇蜂,皆悉令伏不能起。以炁禁金瘡,血即登止。又能續骨連筋。以炁禁白刃,則可蹈之不傷,刺之不入。若人為蛇虺所中, 以炁禁之則立愈。近世左慈趙明等,以炁禁水,水為之逆流一二丈。又於茅屋上然火,煮食食之,而茅屋不焦。又以大釘釘柱,入七八寸,以炁吹之,釘即涌射而出。又以炁禁沸湯,以百許錢投中,令一人手探摝取錢,而手不灼爛。又禁水著中庭露之,大寒不冰。又能禁一里中炊者盡不得蒸熟。又禁犬令不得吠。昔吳遣賀將軍討山賊,賊中有善禁者,每當交戰,官軍刀劍皆不得拔,弓弩射矢皆還向,輒致不利。賀將軍長智有才思,乃曰,吾聞金有刃者可禁,蟲有毒者可禁,其無刃之物,無毒之蟲,則不可禁,彼能禁吾兵者,必不能禁無刃物矣。乃多作勁木白棒,選異力精卒五千人為先登,盡捉棓彼山賊,賊恃其善禁者,了不能備,於是官軍以白棒擊之,大破彼賊,禁者果不復行,所打煞者,乃有萬計。❞(『抱朴子』 至理)→そもそも人は氣の中に存在し、同時に氣は人の中にも存在する。天地から萬物に至るまで、氣によって生じないものはない。氣をよく行う者は内には身を養い、外には邪なものを退けることができる。俗人は日夜、氣に生かされながらその存在を知らずにいる。呉・越には「禁祝の法」があり甚だ霊験がある。多くは気息を操るものである。この法を知るものは疫病の流行する中に足を踏み入れて、病人と共にいても感染せずにいる。仮に数十人の同行者がいても恐れることはない。気息を調整する方術には天災を退ける効能があるからである。邪悪や魅(すだま)や山の精が人家に侵入し瓦や石を人に投げつけたり、人の屋舍に火をつけたりする場合がある。また、形を伴ったり、音や言葉だけが聞こえるというこのもある。「禁祝の法」に精通した者はこれらを絶つことができる。気息を禁じることで鬼神を禁ずることも可能だからである。毒水の流れる渓谷や蛇の出る場所では、凡人が無事で通過するのは難しいが、「禁祝の法」に精通した者であれば、数十里を歩いても無事でいられるし、その供の者もその害から免れることができる。また、虎や豹(ヒョウ)、蛇や蜂の氣を禁じることができる。それらの生き物はみな伏せたまま立ち上がることができなくなる。「禁祝の法」によって刀傷を禁じ、出血を止めることができる。また外れた骨や切れた筋を継ぐこともできる。気息によって白刃を禁じれば、刃の上に立っても傷つかず、突かれたとしても刃が入らないようにすることができる。もし人が蛇にかまれたとしても、「禁祝の法」によってすぐに回復する。近世では、左慈(さじ)・趙明(ちょうめい)らがこの術によって水を一、二丈の高さまで逆流させている。(中略)その昔、呉の賀将軍が山賊の征伐を命じられた時、賊の中に禁をよくする者がいて、交戦するたびに官軍の刀剣が抜けなくなったり、放ったはずの弓や弩がそれて味方に還ってきたりしたために、到底太刀打ちできなかった。賀将軍は理知に長けた人物であったので、「聞いたところによると、『禁祝の法』は、刃のあるものや毒のある生き物について禁じることができるのであって、もともと刃ないものや毒のない生き物を禁じることはできないそうだ。奴らが我々を禁じることができても、我々が刃を持たなければ禁じることはできまい。」というと、木を彫って棍棒を拵えて怪力の兵士に装備させ、その精鋭五千騎を先行させた。山賊たちは禁の術を頼んで、備えを怠っていた。そのため、官軍が棍棒で攻めかかると、賊たちはたちまち崩れ散った。「禁祝の法」 は全く効かず、官軍によって討ち取られた賊は万の位を数えたという。奇しくも『抱朴子』における氣の説明の後に、災厄から身を守ったり武器の殺傷力を封じる「禁祝の法」という法が書いてあります。最後の方には「弓弩射矢皆還向(弓や弩を射ても矢がみな還ってくる)」として、相手に矢が当たらないという現象も書いてあります。ちなみに「禁祝」というのは誤字ではなく、この当時書物では「呪う」という文字ではなく「祝う」の字を用いていました。後に「呪う」の字をあてて「禁呪」と呼ばれるようになります。唐の時代には咒禁博士という官職もあったようです。これが日本にも渡って、691年に「呪禁師(じゅごんし)」という公的な役職も設置されたこともあります。❝〈醫疾令〉云、呪禁生 、學呪禁解忤持禁之法、〈謂、持禁者、持杖刀讀呪文、作法禁氣爲二猛獸虎狼毒虫精魅賊盜五兵不被侵害、又以呪禁固身體、不傷湯刀刃、故曰持禁也、解忤者以呪禁法解衆邪驚忤、故曰解忤也〉❞(『政事要略 九十五至要雜事』)→ 『醫疾令』には「呪禁生が呪禁解忤持禁之法を学んだ」とある。「持禁は、杖や刀を持ったまま呪文を読み、氣を禁じることで猛獸、虎、狼、毒虫や魅(すだま)、盗賊、五兵の害を被らないようにするものである。また呪禁によって身体を固くし刀刃や火、熱湯によって傷つかないようにする。故に持禁というのである。解忤は呪禁の法によって諸々の邪な存在や怪しげな存在を解く。故に解忤という。役職名のみならば『日本書紀』にも記録がありますが、平安時代の政要の書『政事要略』では、上記のように呪禁師の説明書きがしてあります。「持杖刀讀呪文」という表現などはまさにチアルート。日本の「呪禁」も『抱朴子』の頃とあまり変化なく、様々な危険から身を護り、危険性を無効化するような方術であったことが見て取れます。ちなみにこの「呪禁師(じゅごんし)」は、典薬寮に所属していまして、呪術的な役職でありながら医療部門という区分でした。参照:『医心方』と道教 ~鏡の力~。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201411300000/❝含徳之厚、比於赤子。蜂蠆虺蛇不螫、猛獸不據、攫鳥不搏。❞(『老子』第五十五章)→ 徳が厚みを積むさまは、赤子に譬えることができるであろう。赤子は毒虫や毒蛇があえて噛み付いたりはせず、猛獣が襲ったり猛禽が捕らえようともしない。・・・この「呪禁」は、オカルト的な要素を除くと、『老子』の思想にも通じる部分がありまして、「道教」における道術の中でも象徴的な技法です。❝又能禁虎豹及蛇蜂,皆悉令伏不能起。❞(『抱朴子』 至理)→また、虎や豹(ヒョウ)、蛇や蜂の氣を禁じることができる。それらの生き物はみな伏せたまま立ち上がることができなくなる。他にも、「呪禁」のうちの一種、動物の行動を操る、調伏などは『エピソード2/クローンの攻撃』でアナキンがリークに対して使っています(Animal bond)。参照:Anakin and Padme Amidala saves Obi Wan scene part3 https://youtu.be/LsCuHnXAIUk?t=1m30s❝又按漢禁中起居註云、少君之將去也、武帝夢與之共登嵩高山、半道、有使者乘龍持節、從云中下。云太乙請少君。帝覺、以語左右曰、如我之夢、少君將舍我去矣。數日、而少君稱病死。久之、帝令人發其棺、無屍、唯衣冠在焉。按仙經云、上士舉形昇虚、謂之天仙。中士游於名山、謂之地仙。下士先死後蛻、謂之屍解仙。今少君必屍解者也、近世壺公將費長房去。及道士李意期將兩弟子去、皆託卒、死、家殯埋之。積數年、而長房來歸。又相識人見李意期將兩弟子皆在郫縣。其家各發棺視之、三棺遂有竹杖一枚、以丹書於枚、此皆屍解者也。❞(『抱朴子』 論仙)→また『按漢禁中起居註』にいう、李少君がこの世から去ろうとするとき、武帝は夢を見た。少君と共に嵩高山に登り、道の途中で、龍に乗り杖を携えた使者が雲の合間から降りてきた。彼らは太乙が少君を呼んでいるという。武帝はそこで目覚め、左右にその夢の話をした。「もし私の夢の通りであるならば、少君はもうすぐ私の元から去るだろう」と。数日後、少君は病死したという。しばらくして、帝は使者に棺を開けさせてみると、少君の屍はなく、ただ衣冠のみがあった。また、『按仙經』によると、「上士は身体をそのままに虚空へと昇る。これを天仙という。中士は名山に遊ぶ、これを地仙という。下士は一度死んで蝉の抜け殻のような状態になる。これを屍解仙という」とある。そうすると、少君はきっと屍解者であったのだろう。最近の例でも壺公は費長房を連れ去っているし、道士・李意期は二名の弟子を連れ去っている。皆何かに仮託して死に、家人が殯をしてこれを埋めている。数年経ってから、長房は帰ってきたし、李意期と二名の弟子は四川で知人に会っている。家族が棺を開けてみると、三人の棺には、それぞれ竹の杖が一本ずつ入っていて、丹沙で名前が書かれていたという。これは皆、屍解者であったのだ。他にも、オビ=ワンやヨーダにみられる身体の消失(Force ghost)。参照:尸解の世界。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5197/❝又神仙集中有召神劾鬼之法、又有使人見鬼之術。俗人聞之、皆謂虛文。或云天下無鬼神、或云有之、亦不可劾召。或云見鬼者、在男為覡、在女為巫、當須自然,非可學而得。按漢書及太史公記皆云齊人少翁,武帝以為文成將軍。武帝所幸李夫人死、少翁能令武帝見之如生人狀。又令武帝見竈神、此史籍之明文也。夫方術既令鬼見其形、又令本不見鬼者見鬼、推此而言、其餘亦何所不有也。鬼神數為人間作光怪變異、又經典所載、多鬼神之據、俗人尚不信天下之有神鬼、❞(『抱朴子』 論仙)→また、神仙の書物には神を呼び鬼を懲らしめ、人に鬼を見せる術も記録している。俗人はこれを聞くとみな「偽りだ」といいだす。あるいは「天下に鬼神など存在しない」、あるいは「鬼神を呼び出したり、調伏することなどできない」という。あるいは「男ならば覡(げき)、女ならば巫(ふ)という者が鬼を見ることができるというが、彼らは生まれつきそう見えるのであって学習すればできるというものではない」ともいう。 しかし、『漢書』『史記』には、「斉の国の少翁という人が武帝の時代に文成将軍となった。武帝の李夫人が死んだ後、少翁は、まるで生きているかのような李夫人を武帝に見せることができた。」としているし、「武帝に竈神を見せた。」ともある。これは歴とした史書の記録である。鬼神の姿を現すようにする術も、本来見えない鬼神を見せるようにする術も実在するのであって、その余は推して知るべしである。鬼神が人間のために光を放ち、形を変えるというようなことは数多くあって、経典にも記録されている。俗人はそれでも鬼神は実在すると信じようとはしない。さらには死者の魂を見る「見鬼法」など、『抱朴子』における道術は、ジェダイの神秘的なスキルを説明できるものが非常に多くあります。氣とフォースにまつわる思想のみならず、その技術的側面においても、ジェダイと道教には共通点が多いんですが、今回の『ローグ・ワン』はさらに「寄せてきた」という印象です。参照:Return Of The Jedi - Original Ending (Yub Nub, Sebastian Shaw Ghost) - HD https://youtu.be/TvXm5HuR72k?t=1m55s鬼神の実在、仙人の実在。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201409140000/ ジェダイ(Jedi)と道教(Taoism)。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5203/あとで推敲します。今日はこの辺で。
2017.02.01
コメント(0)
-
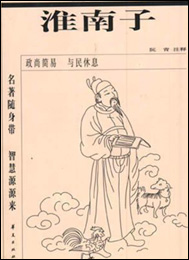
荘子と進化論 その200。
明けまして200です。今日も『淮南子』から。 ❝兩維之間,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日為一節,以生二十四時之變。斗指子,則冬至,音比黃鍾。加十五日指癸,則小寒,音比應鍾。加十五日指醜,則大寒,音比無射。加十五日指報徳之維,則越陰在地,故曰距日冬至四十六日而立春,陽氣凍解,音比南呂。加十五日指寅,則雨水,音比夷則。加十五日指甲,則雷驚蟄,音比林鍾。 (『淮南子』天文訓)❞→両維の間は、九十一度と十六分の五の角度であり、日に一度回り、十五日で一節となり、もって二十四時の変化を生ずる。北斗が子(北)を指すときがすなわち冬至であり,音程は黄鍾にあたる。十五日経過して北斗が癸を指すときがすわなち小寒であり、音程は應鍾にあたる。さらに十五日経過して北斗が醜を指すときがすなわち大寒であり、音程は無射にあたる。さらに十五日経過して北斗が報徳の維(東北)を指すときに陰が地に降りる。ゆえに「冬至から四十六日目は立春となり、陽気が氷を解く」という。音程は南呂にあたる。さらに十五日経過して北斗が寅を指すときがすなわち雨水であり、音程は夷則にあたる。さらに十五日経過して甲をさすときがすなわち雷が蟄(虫)を驚かす(驚蟄、日本でいう「啓蟄」のこと)。音程は林鍾にあたる。(以下略)前回、二十四節気について少し触れました。ちょうど11月末にユネスコの世界無形文化遺産に「二十四節気」が登録されましたので、これ記念してその続きを。参照:道家と二十四節気。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5208/ ❝太微者、太一之庭也。紫宮者、太一之居也。軒轅者、帝妃之舍也、咸池者、水魚之囿也。天阿者、群神之闕也。四宮者、所以守司賞罰。太微者、主朱雀、紫宮執斗而左旋、日行一度、以周於天、日冬至峻狼之山、日移一度、凡行百八十二度八分度之五、而夏至牛首之山、反覆三百六十五度四分度之一而成一歲。❞(『淮南子』天文訓)→太微は、太一の庭であり、紫宮は太一の住まいである。軒轅は、帝妃の舍であり、咸池は、水魚を養う園である。天阿は、群神の関である。この四宮は、賞罰を司りこれを守る門である。太微は、朱雀を主とし、紫宮は北斗を手に執って左に旋回する。一日に一巡し、天を周行して冬至の日に峻狼山に至る。日に一度移動して、おおよそ半年で182と8分の5度を巡り、夏至の日に牛首山に至る。365と4分の1度の運行により一年という歳月が経過する。『淮南子(えなんじ)』は、前漢の武帝のころ、淮南王・劉安という人物の命により紀元前二世紀に編纂された書物です。このうち「天文訓」は、『史記』の「天官書」と並んでこの当時の天文学の水準を窺い知ることができる貴重な記録なわけですが、彼らが特に注視していた天体は「北極星」や「北斗七星」といった北の星々でした。参照:荘子と太一と伊勢神宮。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005176/北極星と北斗七星というと、真北を指す「方位の基準」としての役割がありますが、同時にこの星々には「時間の基準」としての役割もあります。北の空の星々は北極を中心におおよそ一年で天を一周します。当時の人々は、同じ時刻での北斗七星の剣先の角度を計測することによって、一年のサイクルの目安としていました。二十四節気でも「斗指子(北斗が子を指す)」「指癸(北斗が癸を指す)」とあるように、北斗七星にはいわば「巨大な時計」としての機能があったわけです。また、『淮南子』は、北斗七星と同じように重要な天体についての記録があります。 ❝天神之貴者,莫貴於青龍,或曰天一,或曰太陰。太陰所居,不可背而可向,北斗所擊,不可與敵。天地以設,分而為陰陽,陽生於陰,陰生於陽。陰陽相錯,四維乃通。或死或生,萬物乃成。蚑行喙息,莫貴于人,孔竅肢體,皆通於天。天有九重,人亦有九竅;天有四時以制十二月,人亦有四肢以使十二節;天有十二月以制三百六十日,人亦有十二肢以使三百六十節。故舉事而不順天者,逆其生者也。❞ (『淮南子』天文訓)→天神のうちで青龍ほど貴いものはない。ある時は天一といい、またあるときは太陰ともいう。太陰の場所は、背を向けてはならない。北斗の撃つ場所を敵としてはならない。天地を陰陽の二気とすると、陽は陰によって生じ、陰は陽によって生じる。陰陽は互いに交わって四維が通じる。あるいは死、あるいは生、それにより萬物は生成する。足があり呼吸をする生き物の中で人より貴いものはなく、人の身体における器官や身体はみな天のはたらきに通じている。天に九重があれば、人にも九竅があり、天に四時(四季)があって十二の月があるように、人にも四肢と十二の節がある。天に十二の月と三百六十日があるように、人にもまた十二肢と三百六十の節がある。ゆえに、事あるごとに天に従わないのは、生に逆らっているのと同じことである。・・・この「青龍」が意味するものです。五行の思想でいうところの「木」を象徴する星。 ❝何謂五星?東方,木也,其帝太皞,其佐句芒,執規而治春;其神為歲星,其獸蒼龍,其音角,其日甲乙。南方,火也,其帝炎帝,其佐朱明,執衡而治夏;其神為熒惑,其獸朱鳥,其音徵,其日丙丁。中央,土也,其帝黃帝,其佐後土,執繩而制四方;其神為鎮星,其獸黃龍,其音宮,其日戊己。西方,金也,其帝少昊,其佐蓐收,執矩而治秋;其神為太白,其獸白虎,其音商,其日庚辛。北方,水也,其帝顓頊,其佐玄冥,執權而治冬;其神為辰星,其獸玄武,其音羽,其日壬癸。太陰在四仲,則歲星行三宿,太陰在四鉤,則歲星行二宿,二八十六,三四十二,故十二歲而行二十八宿。日行十二分度之一,歲行三十度十六分度之七,十二歲而周。❞(『淮南子』天文訓)→「五星」とは何を言うのだろうか? 東方は木である。その帝は太皞、その補佐は句芒、規(コンパス)を執り春を治める。その神は歲星(さいせい)となし、その獣は蒼龍、音階は角,日は甲乙である。 南方は火である。その帝は炎帝、その補佐は朱明、衡(はかり)を執り夏を治める。その神は熒惑(けいわく)となし、その獸は朱鳥、音階は徵、日は丙丁である。 中央は土である。その帝は黃帝、その補佐は後土、縄を執り四方を制する。その神は鎮星(ちんせい)となし、その獣は黃龍、音階は宮,日は戊己である。 西方は金である。その帝は少昊、その補佐は蓐收、矩(さしがね)を執り秋を治める。その神は太白(たいはく)となし、その獣は白虎、音階は商、日は庚辛である。 北方は水である。その帝は顓頊、その補佐は玄冥、權(おもり)を執り冬を治める。その神は辰星(しんせい)となし、その獣は玄武、音階は羽,日は壬癸である。 太陰が四仲にあるとき、歲星は三宿に進み、太陰が四鉤にあるとき、歲星はちょうど二宿に進む。歳星は十二年で二十八宿をめぐり、1日で十二分の一度、一年では三十度十六分の七、十二年で一周する。太陽系の惑星のうちの5つは肉眼でも観測可能です。紀元前から人類は、他の星々と異なった性格を有するそれらの惑星を注意深く見つめていました。前漢の時代には、その当時流行していた五行になぞらえて、それぞれ星の属性としました。「熒惑(けいわく)」という星は火、「鎮星(ちんせい)」という星は土、太白(たいはく)という星は金、辰星(しんせい)という星は水、という具合です。そして、その中でも最も重視されていたのが木星でした。木星は、別名を「蒼龍(青龍)」、「歳星」ともいい、11.86年で天を一周します。まさに一年という「歳」を示す星でした。木星が約十二年で一巡するという運行が十二次、十二辰という区分になり、後に十二支として活用されます。このサイクルは2000年以上使用され続け、現在ももちろん、その風習が残っています(ちなみに、十二支に動物が当てられるのは後漢のころ)。・・・ただし、木星の動きには、ある問題点があります。「時間の基準」として使うため、時計のような存在ではあるんですが、木星は反時計回り(左回り)なんです。ここは暦法だけでなく占星術にも大きく関わってくるので、南を向いて太陽や月を観測する場合の基本となる時計回り(右回り)と関連付けるのが難しくなります。そこで、術数学という学問の方法論を活用して「観念上の星」が考え出されました。丑と寅との間に鏡を立てて、そこに映る影のような星です。実際の木星の動きとは逆に、時計回りに回る「木星の影」。この星を「太歳」と言ったり「太陰」と言ったりします。Wikipedia 木星https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E6%98%9FWiukipedia 太歳https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E6%AD%B3参照:四方拝と北斗七星。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5172/・・・この反時計回りという点では北斗七星であっても同じです。『淮南子』では同様の考え方に基づいて北斗七星を「雌雄」に分けます。 ❝北斗之神有雌雄,十一月始建於子,月從一辰,雄左行,雌右行,五月合午謀刑,十一月合子謀德。太陰所居辰為厭日,厭日不可以舉百事,堪輿徐行,雄以音知雌,故為奇辰。❞(『淮南子』天文訓)→北斗の神には雌雄がある。十一月の初めに建が子を指し、一月ごとに一辰ずつ動く。雄は左行し、雌は右行する。五月に午を指して刑の位置に至り、十一月には再び徳の位置に合わさる。太陰(雌神)の場所を厭といい、厭には何事も行うべきではないという。堪輿は徐行し、雄は音によって雌を知る、ゆえにこれを奇辰という。北斗七星が反時計回りに「左行」する動きを「雄」とし、対照的に「右行」する観念上の天体を雌として、それぞれが十一月と五月に重なりあうというものです(この当時の暦では一年の始まりは11月1日)。木星の場合と同じように太陰という言葉もありますが、北斗七星の場合には雌雄が半年ごとに重なり合い、神話の時代の壁画のように二重らせんを描きます。『淮南子』では天文訓に登場する星々に「神」の字をあてていますが、この「雌雄の北斗の神」は精神訓にある「混生した二神」に対応していると思われます。❝古未有天地之時、惟像無形、窈窈冥冥、芒芠漠閔、澒蒙鴻洞、莫知其門。有二神混生,經天營地,孔乎莫知其所終極,滔乎莫知其所止息,於是乃別為陰陽,離為八極,剛柔相成,萬物乃形,煩氣為蟲,精氣為人。❞(『淮南子』精神訓)→古の天地のなかった時代、ただ無形としか形容できない、深い深い闇に包まれていたころ、ぼんやりとしてつかみようのないものが世界のいたるところにひろまりつつあった。そのとき渾然として二神が生まれて、天を経て地を営み始めた。いつどこで終わるのかわからない営みは休むことなく続き、そのうちに陰陽の別が生じ、八極が成り立ち、重合が相成り、萬物に形が生まれ、煩氣は獣や虫となり、精氣は人となった。参照:参照:太陽と月、男と女の錬金術。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5148/これと大変よく似た話が日本にあります。❝於其嶋天降坐而、見立天之御柱、見立八尋殿。於是、問其妹伊邪那美命曰「汝身者、如何成。」答曰「吾身者、成成不成合處一處在。」爾伊邪那岐命詔「我身者、成成而成餘處一處在。故以此吾身成餘處、刺塞汝身不成合處而、以爲生成國土、生奈何。」。伊邪那美命答曰「然善。」爾伊邪那岐命詔「然者、吾與汝行廻逢是天之御柱而、爲美斗能麻具波比。」如此之期、乃詔「汝者自右廻逢、我者自左廻逢。」約竟廻時、伊邪那美命、先言「阿那邇夜志愛上袁登古袁。」後伊邪那岐命言「阿那邇夜志愛上袁登賣袁。」各言竟之後、告其妹曰「女人先言、不良。」雖然、久美度邇興而生子、水蛭子、此子者入葦船而流去。次生淡嶋、是亦不入子之例。(『古事記 上』)❞→ここで諸々の天つ神はイザナキノミコトとイザナミノミコトの二柱の神に「この漂い流れている国を修めて埋め固めなさい。」と命ぜられ、天沼矛を授けて委ねられました。故に、この二柱の神は、天の浮橋に立ってその矛を下ろしてかき回されました。潮をごろごろと引き上げるときに、矛先から垂れた潮が積み重なって島となりました。これがオノゴロ島であります。 この島に二柱の神がお下りになり、そこに天の御柱を立て、八尋の御殿をお建てになられました。そこでイザナキノミコトがイザナミノミコトに「汝の身体はどうなっているのか?」と問われたので、イザナミノミコトは「我の身体は、出来上がって出来上がりきれていない場所が一つあります。」は答えられました。そして、イザナキノミコトは「我の身体は、出来上がって余っている場所が一つある。私の身体で出来上がって余っている場所を、汝の出来上がって出来上がりきれていない場所に刺して国土を作ろうと思う。生まれるのだろうか?」と言われました。イザナミノミコトは「それは善いことです。」と答えられました。そこでイザナキノミコトは「それならば、我と汝が天の御柱を回り、そこで出会って『美斗能麻具波比(ミトノマグワイ)』をしよう」と言われました。 この時、イザナキノミコトが「汝は右から回って会おう。我は左から回って会おう。」とおっしゃって約束し、その時になってイザナミノミコトがまず「ああなんてすばらしい男だろう。」とおっしゃり、後でイザナキノミコトが「ああなんてすばらしい乙女だろう。」とおっしゃられました。それぞれが言い終わった後、妹神に「女人から先に言うのはよいことでなはない。」と告げられました。とはいえその後「久美度邇興(クミドノオコリ)」をなされて、蛭子(ヒルコ)をお生みになられました。この子は葦の船に乗せて流されました。次に淡島をお生みになられましたが、これも子の数には入れられませんでした。・・・右回りと左回りは、『古事記』の冒頭のイザナギとイザナミの営みにも出てきます。『淮南子』で、北極星を中心に北斗の雌雄の神が左右に分かれて向こう側で出会う軌道と、『古事記』で、天の御柱を中心にイザナギとイザナミが左右に分かれて向こう側で出会う軌道が一致しています。さらにいえば、雄の方から声をかけるというルールも同じです。向こう側で出会ってから行う『美斗能麻具波比(ミトノマグワイ)』に、わざわざ北斗の「斗」の字をあてていることも偶然とも思えません。『夫道、有情有信、無為無形。可傳而不可受、可得而不可見。自本自根、未有天地、自古以固存。神鬼神帝、生天生地。在太極之先而不為高、在六極之下而不為深。先天地生而不為久、長於上古而不為老。豨韋氏得之、以挈天地。伏犧氏得之、以襲氣母。維斗得之、終古不忒。日月得之、終古不息。堪坏得之、以襲崑崙。馮夷得之、以遊大川。肩吾得之、以處太山。黃帝得之、以登雲天。顓頊得之、以處玄宮。禺強得之、立乎北極。西王母得之、坐乎少廣、莫知其始、莫知其終。彭祖得之、上及有虞、下及五伯。傅説得之、以相武丁、奄有天下、乘東維、騎箕尾、而比於列星。(『荘子』大宗師 第六)』→その道とは、情もあり信もあるが、無為であり、無形である。伝えることはできるが、授受をするとこはできない。会得することはできるが、見ることはできない。自ら本であり、自ら根である。未だ天地が存在しなかった古の時代から存在し、鬼を神し、帝を神し、天を生み、地を生んだ。太極の先に在りながら高いと為さず、六極の下にありながら深いと為さない。天地に先んじて存在しながら、その長さを久しいと為さず、上古より存在しながらその経過を老いを為さない。伏犧氏は之を得て、天地を一体とし、維斗は之を得て、古来より変わらぬ道しるべとなった。日月は之をて、去来より変わらぬ営みを休むことなく続ける。堪坏は之を得て、崑崙山へ入り、馮夷は之を得て、黄河を遊ぶ。肩吾は之を得て、泰山に至り、黃帝は之を得て、雲天の世界に昇り、顓頊(せんぎょく)は之を得て、玄宮に居り、禺強は之を得て、北極を守り、西王母は之を得て少廣山に座したままでいて、その始まりもその終わりも知るよしはない。彭祖(ほうそ)は之を得て、舜堯から五覇の時代までを生き延び、傅説は之を得て、武丁を助けて天下を授け、東維の星に乗り、箕の末尾の星に跨って列星に比されることとなった。荘子の時代から神話世界と天文との関連はあるんですが、古事記は特に星で読めるものが多いので、いずれ続きを。今日はこの辺で。
2017.01.01
コメント(0)
-
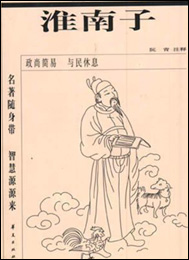
荘子と進化論 その199。
今日も『淮南子(えなんじ)』から。『淮南子』には、ある程度体系的に書かれた章もあれば、断片的な言葉が書き連ねられた章もあります。その量から「説山訓」「説林訓」と区分されているものでして、今回はそのうち「説山訓」から。❝嘗一臠肉、知一鑊之味。懸羽與炭、而知燥濕之氣。以小明大。見一葉落、而知歲之將暮。睹瓶中之冰、而知天下之寒。以近論遠。三人比肩、不能外出戸。一人相隨、可以通天下。足蹍地而為跡、暴行而為影、此易而難。莊王誅里史、孫叔敖制冠浣衣、文公棄荏席、後黴黒、咎犯辭歸、故桑葉落而長年悲也。鼎錯日用而不足貴、周鼎不爨而不可賤。物固有以不用而為有用者。地平則水不流、重鈞則衡不傾。物之尤必有所感、物固有以不用為大用者。❞(『淮南子』説山訓)→鍋の中の肉を一つ味わえば、鍋全体の味を知ることができる。羽毛と墨を天秤にかければ、周りの空気の乾湿を知ることができる。小さな事象から大きな事象を明らかにする。一枚の葉が落ちることを見れば、年が暮れに差し掛かっているこを知ることができ、水がめに氷が張っていることを見れば、天下の寒さを知ることができる。 三人肩を並べれば、戸口からでることすらかなわないが、一人ずつ従って進めば天下に通じることもできる。踏みしめれば足跡はできるものだし、動けば影もそれに従うのは当然であるが、これを思い通りにするのは難しいことである。莊王が里史を誅殺したと聞き、孫叔敖は(自分が召し出されるのを知って)冠をぬぐい衣を洗ったという、文公が蓆を捨て、浅黒い男を後列に配したとき、咎犯は(法令が改められることを知って)職を辞して帰国しようとした。故に、桑の葉が落ちることで年長者は(自らの寿命を察して)悲しむのである。日ごろ使う鼎をことさら丁寧に扱う必要はないが、祭りに使う周の鼎を粗末に扱うことはできない。もともと無用であるが故に有用である事物はあるものだ。平らな土地では水の流れようがない。重さが同じでは天秤は傾きようがない。物に均質さがないが故に使いようができる。事物には無用であるがゆえに大用にかなう場合があるものである。・・・中華圏では「一葉知秋」といい、日本では「一葉落知天下秋(一葉落ちて天下の秋を知る)」という慣用句の典拠となる部分です。厳密にいうと、元ネタの『淮南子』では、桑の葉のことを指したものですが、その後、白居易の『長恨歌』あたりから「梧桐(アオギリ)」の葉で表現されることが多くなりました。さらには、「桐(キリ)」の葉が担って、「桐一葉落ちて天下の秋を知る」または「桐一葉」という形式で使われることもあります。日本の場合には、禅語として、または季語として人口に膾炙したものだろうと思います。参照:Wikipedia アオギリhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AE%E3%83%AA我宿の淋しさおもへ桐一葉 芭蕉 春夏秋冬の「四時(四季)」は、道家の初期の段階から、この世界の構成要素として重要視されていました。「太一生水」もそうですし、『荘子』でもよく引き合いに出されます。『太一生水、水反輔太一、是以成天。天反輔太一、是以成地。天地复相輔也、是以成神明。神明复相輔也、是以成阴阳。阴阳复相輔也、是以成四时。四时复相輔也、是以成凔热。凔热复相輔也、是以成湿燥。湿燥复相輔也、成歳而止。故歳者、湿燥之所生也。湿燥者、凔热之所生也。凔热者、四时之所生也。四时者、阴阳之所生也。阴阳者、神明之所生也。神明者、天地之所生也。天地者、太一之所生也。是故、太一藏於水、行於时。周而又始、以己为万物母。(郭店楚墓竹簡『太一生水』より)』→太一が水を生じ、水は太一に反輔し、是を以て天となる。天は太一に反輔し、是を以て地となる。天地はまた相輔する。是を以て神明となる。神明また相輔して、是を以て陰陽となる。陰陽また相輔して、是を以て四季となる。四季はまた相輔する。是を以て凔熱となる。凔熱はまた相輔する。是を以て湿燥となり、湿燥はまた相輔して、歳となり止まる。故に歳は湿燥の生じるところである。凔熱は四季の生じるところである。四季は陰陽の生じるところである。陰陽は神明の生じるところである。神明は天地の生じるところである。天地は太一の生じるところである。これ故に太一は水を蔵し、時において行く。周してまた始まり、以て万物の母となる。参照:『荘子』と『淮南子』の宇宙。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005186/荘子と太一と伊勢神宮。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005176/❝天地有大美而不言。四時有明法而不議。萬物有成理而不説。聖人者、原天地之美而達萬物之理。是故至人無爲、大聖不作。觀於天地之謂也。今彼神明至精、與彼百化、物已死生方圓。莫知其根也。篇然而萬物、自古以固存。六合爲巨、未離其内。秋豪爲小、待之成體。天下莫不沈浮、終身不故。陰陽四時、運行各得其序。昏然若亡而存、油然不形而神。萬物畜而不知。此之謂本根。可以觀於天矣。❞(『荘子』知北遊 第二十三)→天地には万物を育むという素晴らしいはたらき(美)がありながら、何も言わない。四時(四季)ははっきりとした法則がありながら、それぞれが語り合うことはない。万物も存在する理由がありながら、何も説明はしない。聖人と言われる人は、天地の美に基づいて万物の理に達する。だからこそ至人は、自然に人の作為を働かせず、聖人ともなれば、自然と一体となる。今、かの神明なる「道」は、万物の変化を彼に与え、その結果、万物が百化して、生まれたり、死んだり、丸になったり四角になったりしている。何者がそうさせているかは分からない。こうして、あまねく万物は生成し、古来より存在している。。宇宙は巨大であっても「道」の法則のうちにあり、秋の日の獣の毛が細くても、それもまた「道」の法則によってそうなっている。天下は浮き沈みをしながらも形を変え続け、四時(四季)は必ず同じ順序で巡り来る。これらの存在は真っ暗で存在しないようでいて、はっきりと存在していて、形こそ見えないものの、霊妙な働きを悠然となしている。万物はその存在に養われていながら、その存在を知らない。これを「本根」と言う。これを以って初めて天を観ることもできよう。参照:大阪大学の「天地有大美而不言」の書http://www.chem.sci.osaka-u.ac.jp/catalogue/graduate/intro.html・・・『荘子』の場合には獣の毛の太さが目安です。季節にまつわる記録として、『淮南子』には「これ」もあります。❝陰陽刑徳有七舍。何謂七舍。室、堂、庭、門、巷、術、野。十二月徳居室三十日,先日至十五日,後日至十五日,而徙所居各三十日。徳在室則刑在野,徳在堂則刑在術,徳在庭則刑在巷,陰陽相徳,則刑徳合門。八月、二月,陰陽氣均,日夜分平,故曰刑徳合門。徳南則生,刑南則殺,故曰二月會而萬物生,八月會而草木死,兩維之間,九十一度十六分度之五而升,日行一度,十五日為一節,以生二十四時之變。斗指子,則冬至,音比黃鍾。加十五日指癸,則小寒,音比應鍾。加十五日指醜,則大寒,音比無射。加十五日指報徳之維,則越陰在地,故曰距日冬至四十六日而立春,陽氣凍解,音比南呂。加十五日指寅,則雨水,音比夷則。加十五日指甲,則雷驚蟄,音比林鍾。加十五日指卯中繩,故曰春分則雷行,音比蕤賓。加十五日指乙,則清明風至,音比仲呂。加十日指辰,則穀雨,音比姑洗。加十五日指常羊之維,則春分盡,故曰有四十六日而立夏,大風濟,音比夾鍾。加十五日指巳,則小滿,音比太蔟。加十五日指丙,則芒種,音比大呂。加十五日指午,則陽氣極,故曰有四十六日而夏至,音比黃鍾。加十五指丁,則小暑,音比大呂。加十五日指未,則大暑,音比太蔟。加十五日指背陽之維,則夏分盡,故曰有四十六日而立秋,涼風至,音比夾鍾。加十五日指申,則處暑,音比姑洗。加十五日指庚,則白露降,音比仲呂。加十五日指酉中繩,故曰秋分雷臧,蟄蟲北向,音比蕤賓。加十五日指辛,則寒露,音比林鍾。加十五日指戌,則霜降,音比夷則。加十五日指蹄通之維,則秋分盡,故曰有四十六日而立冬,草木畢死,音比南呂。加十五日指亥,則小雪,音比無射。加十五日指壬,則大雪,音比應鍾。加十五日指子。故曰:陽生於子,陰生於午。陽生於子,故十一月日冬至,鵲始加巢,人氣鍾首。陰生於午,故五月為小刑,薺麥亭曆枯,冬生草木必死。❞(『淮南子』天文訓)→陰陽、刑徳には七舍がある。何を七舍というのだろう?室、堂、庭、門、巷、術、野がその七舎である。十二月に徳は室に三十日間して、冬至の前の十五日と冬至の後の十五日のことである。各々三十日その舎にとどまる。徳が室にいるとき、刑は野にあり,徳が堂にいるとき、刑は術にいる。德が庭にいるとき、刑は巷にある。徳が陰陽とともにあれば、刑、徳は門にて合わさる。八月と二月は陰陽の氣が等しく、昼と夜とがともに等しい。故に刑・徳が門に合ずるという。徳が南ならば生,刑が南ならば殺。故に二月は萬物が生じるといいい、八月に草木が死するという。両維の間は、九十一度と十六分の五の角度であり、日に一度回り、十五日で一節となり、もって二十四時の変化を生ずる。北斗が子(北)を指すときがすなわち冬至であり,音程は黄鍾にあたる。十五日経過して北斗が癸を指すときがすわなち小寒であり、音程は應鍾にあたる。さらに十五日経過して北斗が醜を指すときがすなわち大寒であり、音程は無射にあたる。さらに十五日経過して北斗が報徳の維(東北)を指すときに陰が地に降りる。ゆえに「冬至から四十六日目は立春となり、陽気が氷を解く」という。音程は南呂にあたる。さらに十五日経過して北斗が寅を指すときがすなわち雨水であり、音程は夷則にあたる。さらに十五日経過して甲をさすときがすなわち雷が蟄(虫)を驚かす(驚蟄、日本でいう「啓蟄」のこと)。音程は林鍾にあたる。(以下略)前半部分の刑徳に関してはいずれ。後半部分には現代でもなじみのある「二十四節気」が書かれてあります。『淮南子』では、北斗七星の観測結果と、地上での現象とを対応させて、さらには十二の音階とも関連付けています。十二支もそうですが、現在のものとほぼ同じ「二十四節気」の記録がある最古の書物もこの『淮南子』です。参照:Wikipedia 二十四節気https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E7%AF%80%E6%B0%97参照:『荘子』と『淮南子』の宇宙。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005186/荘子と太一と伊勢神宮。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005176/❝天神之貴者,莫貴於青龍,或曰天一,或曰太陰。太陰所居,不可背而可向,北斗所擊,不可與敵。天地以設,分而為陰陽,陽生於陰,陰生於陽。陰陽相錯,四維乃通。或死或生,萬物乃成。蚑行喙息,莫貴于人,孔竅肢體,皆通於天。天有九重,人亦有九竅;天有四時以制十二月,人亦有四肢以使十二節;天有十二月以制三百六十日,人亦有十二肢以使三百六十節。故舉事而不順天者,逆其生者也。❞ (『淮南子』天文訓)→天神のうちで青龍ほど貴いものはない。ある時は天一といい、またるときは太陰ともいう。太陰の場所は、背を向けてはならない。北斗の撃つ場所を敵としてはならない。天地を陰陽の二気とすると、陽は陰によって生じ、陰は陽によって生じる。陰陽は互いに交わって四維が通じる。あるいは死、あるいは生、それにより萬物は生成する。足があり呼吸をする生き物の中で人より貴いものはなく、人の身体における器官や身体はみな天のはたらきに通じている。天に九重があれば、人にも九竅があり、天に四時(四季)があって十二の月があるように、人にも四肢と十二の節がある。天に十二の月と三百六十日があるように、人にもまた十二肢と三百六十の節がある。ゆえに、事あるごとに天に従わないのは、生に逆らっているのと同じことである。日本の『日本書紀』『古事記』には、四季についての記録がほとんど見られませんが、それに先行する紀元前の道家の書物では、宇宙観に直結する形で記録が存在します。後の道教にも通じるこの種の特徴的な考えについて、フランスの道教研究者、アンリ・マスペロは、このように説明しています。❝気の循環は、この時代(すなわち唐代以前)においては、何よりも呼吸の特殊なやり方ということにその本質がある。というのは、問題になるのは外気だからである。つまり、空気こそは人間の生命力の気なのであって、これを三つの丹田へ通さねばならないのである。 人間と宇宙とは中国人にとっては完全に同一である。それは単に全体において同一というだけではなく、おのおのの細部に至るまでも同一なのである。人間の頭は天と同様に円く、足は大地と同様に長方形である。五臓は「五つの元素(五行)」に対応し、二十四の椎骨は一年の二十四の節季に、十二の気管の輪は十二カ月に、三百六十五の骨は一年の三百六十五日に対応する。静脈とその中に入っている血液は、河川に対応する等々。実際に宇宙は巨大な身体であって、ある人たちは「太上老君」の身体だといい、また他の人たちは「盤古」--これは「元始天尊」にほかならぬ--の身体だと言っている。 老子はかれの身体を変えた。かれの左目は太陽となり、右目は月になった。頭は崑崙山となり、髪は惑星と星宿になった。その骨は竜となり、肉は四足獣に、腸は蛇に、腹は海となり、指は五岳に、毛は草木に、心臓は華蓋(の星座)になった。そして二つの腎臓は結ばれて「真の父と母」(真要父母)になった。 任昉は六世紀に、その≪述異記≫のなかで、盤古の伝説を全く同様に述べている。 むかし盤古が死んだとき、かれの頭は四岳となり、両眼は日と月になった。その脂は河と海になり、髪と鬚は草木になった。秦漢時代に世間では、盤古の頭が東岳で、腹が中岳、左腕が南岳、右腕が北岳、両足が西岳だといわれていた。古の学者は、盤古の涙は河であり、その吹く息が風、その声が雷、両眼の瞳孔が稲妻だ、と述べている。 この伝説は必ずしも道教起源のものではない。というのは、身体即宇宙という考え方そのものは。何ら道教に特有のものではないのだから。それは世界中に広く行われた信仰であり、俗界と宗教界とを問わず、ほとんどいたるところに、またあらゆる時代に存在するものである。しかし、道教徒は、身体と宇宙を同一視するこの考え方を、その同時代の人々よりもずっと極端に押し進めたのである。❞(『西暦初頭数世紀の道教に関する研究』東洋文庫刊 アンリ・マスペロ著 川勝義雄訳)今日はこの辺で。
2016.11.13
コメント(0)
-

鳩山邦夫氏の最後の訴え。
福岡6区の補選、10月11日に告示、投開票は23日です。鳩山邦夫氏の弔い合戦なんだそうなので、弔うからには、鳩山邦夫氏が最後に主張していたことを振り返える必要もあるでしょう。--------(引用はじめ)---------------------------------------------------------県農政連は自主投票に 衆院福岡6区補選 [福岡県]2016年10月07日 00時48分 衆院福岡6区補欠選挙で県農政連(林裕二委員長)は6日、自主投票を決めた。参院議員秘書の蔵内謙氏(35)と前大川市長の鳩山二郎氏(37)の無所属新人2人が推薦を求めたのに対し、6区内の5支部は3日に自主投票を決めていた。 農政連は6区内に約1万8千人の会員がいる。農政連と関係が深い自民党は公認を見送っており、保守票は蔵内氏と鳩山氏に割れることが確実だ。 6区補選には野党統一候補となった民進党新人の新井富美子氏(49)、政治団体「幸福実現党」新人の西原忠弘氏(61)も立候補を表明している。=2016/10/07付 西日本新聞朝刊=---------------------------------------------------------(引用おわり)--------参照:県農政連は自主投票に 衆院福岡6区補選 西日本新聞http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_sougou/article/280269--------(引用はじめ)---------------------------------------------------------総選挙 TPP参加反対205人 自民衆院議員7割が公約 「農業を破壊」「絶対に許すな」 安倍晋三首相(自民党総裁)が環太平洋連携協定(TPP)の交渉参加に踏み出す姿勢を強めていますが、昨年12月の総選挙で当選した自民党議員295人(選挙後復党した福岡6区の鳩山邦夫議員を含む)のうち、205人が選挙公約でTPP参加に「反対」を表明し、全体の69・5%を占めることが本紙の調査でわかりました。「これでは公約違反だ」「自民党は政権公約を守れ」の怒りの声が全国各地であがっています。 調査は、有権者に配布された300の小選挙区の選挙公報を中心に行い、選挙公報に記載のなかった議員については、メディアが選挙期間中に行った「候補者アンケート」の回答を調べました。 約7割にのぼったTPP「反対」に対し、「賛成」はわずか24人(8・1%)。66人は態度を明確にしていませんでした。 選挙公報でTPPにふれたのは108人でうち104人が「反対」を表明しています。 小野寺五典防衛相(宮城6区)は「TPP断固反対を貫く」との見出しを掲げ、「今、TPPに参加すれば、震災で甚大な被害を受けた東北地方、日本の農林水産業は厳しい状況に立たされます」と述べています。田村憲久厚生労働相(三重4区)も「例外なき関税撤廃(TPP)は絶対反対」「日本の農業や公的医療保険制度を破壊する恐れがある」との公約を掲げました。 多くの議員が、自民党が公約の一つに掲げた「『聖域なき関税撤廃』を前提にする限り、交渉参加に反対」を記載。そのなかで「TPPが掲げる全ての品目の例外なきゼロ関税化の原則は、我が国にとって受け入れられないものです」(細田健一議員・新潟2区)、「TPPだけは、絶対に、絶対に、許してはなりません」(古川禎久議員・宮崎3区)とTPPの原則まで説き、強い言葉で反対する姿勢を打ち出した公約もあります。 総選挙では、JAグループの政治団体「全国農業者農政運動組織連盟」(全国農政連)がTPP交渉参加に反対することを条件として候補者を推薦。選挙公報に「農政連推薦」と書いた議員も多くいました。当選した自民党議員のうち163人が推薦を受けました。安倍首相は「候補者アンケート」では「無回答」でしたが、全国農政連の推薦を受けていました。---------------------------------------------------------(引用おわり)--------参照:総選挙 TPP参加反対205人 しんぶん赤旗 2013年3月4日(月)http://www.jcp.or.jp/akahata/aik12/2013-03-04/2013030401_01_1.htmlぜひ、政策も引き継いでいただきたいものです。--------(引用はじめ)--------------------------------------------------------- 平成28年10月7日、安倍総理は、総理大臣官邸で第16回TPP(環太平洋パートナーシップ)に関する主要閣僚会議に出席しました。 会議では、TPPに関する国内外の情勢について議論が行われました。 総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。「今、世界の自由貿易システムは、岐路に立っています。経済成長の恩恵が広く均霑(きんてん)されていないのではないか。こんな懸念が広がれば、自由貿易に対する支持が揺らいでしまいます。保護主義の芽を、放っておいてはならない。各国が、国民の理解と支持を得て自由貿易を推進することによって、食い止めなければなりません。 日本はどうするのか。世界が注目をしています。他国に先駆け、日本の国会でTPP協定を承認し、早期発効に弾みをつける。これは、自由貿易の下で経済発展を遂げた、我が国の使命だと確信をしております。この国会で、やり遂げなければなりません。 TPPの新たなルールは、付加価値が正当に評価される、『世界の4割経済圏』を生み出します。農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。成長の起爆剤として、TPPの早期発効を期待する声が高まっています。 経済だけではありません。基本的価値を共有する国々が経済の絆を深める。これは、地域を安定させる力となります。 国会審議を通して、国民の理解と支持を得る。このために、丁寧に説明し、議論を尽くす。政府一体となって、気を引き締め、全力を尽くしていきたいと思います。」---------------------------------------------------------(引用おわり)--------参照:平成28年10月7日 TPPに関する主要閣僚会議http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201610/07tpp.html>農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。>農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。>農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。>農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。>農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。>農家や中小企業が大いに活躍できるようになります。まあ、安倍ちゃんが言っているわけですから、そうなるんでしょうよ。今日はこの辺で。
2016.10.08
コメント(2)
-
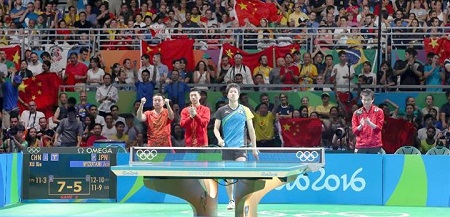
天野健作記者の跳び蹴り事件について考える。
今日もオリンピックの話を。天野健作記者の記事で、気になったことがあったのでメモ。-----(引用はじめ)-----------------------------------------跳び蹴りしてきた中国人/リオ五輪産経新聞 8月20日(土)7時55分配信 日本対中国の卓球男子団体決勝戦を観客席で取材していたときのことだ。周りは五星紅旗を振る中国人の応援でいっぱいだった。締め切りが迫っていたこともあり、時計をにらみながらパソコンを開いて原稿を書いていた。 戦況は中国側が優勢になり出し、応援団が興奮気味に。すると中国人の親子が自分たちの席を離れ、私の目の前に立ちふさがった。最初は軽く肩をたたき、横にずれてもらうよう促した。だがこれが3回も続き、さすがに堪忍袋の緒が切れて日本語で大声を出して注意した。 ところが、その母親は謝るどころか、こちらに跳び蹴りをくらわし、危うくパソコンに当たりそうになった。観戦マナーの悪さに愕然(がくぜん)とした。 中国の応援団が去った後はごみだらけで、以前に日本の観客が試合後に自主的にごみを拾って現地メディアに称賛されたのと対照的だ。盛り上がってくれるのは一向に構わない。東京五輪では、ぜひ足だけは出さないように願いたい。(天野健作)-----------------------------------------(引用おわり)-----参照:【Rio to Tokyo】 観客席で跳び蹴りしてきた中国人 2016.8.19 21:42更新 http://www.sankei.com/rio2016/news/160819/rio1608190091-n1.html穏やかな話ではないですが、順を追って読んでみます。>日本対中国の卓球男子団体決勝戦を観客席で取材していたときのことだ。周りは五星紅旗を振る中国人の応援でいっぱいだった。締め切りが迫っていたこともあり、時計をにらみながらパソコンを開いて原稿を書いていた。・・・当たり前のようにさらっと書いてありますが、不思議な書き出しです。通常の国際大会と同じく、今回のリオデジャネイロオリンピックでも各国の報道機関のために「記者席」と「観客席」の区分はありましたが、天野記者は、わざわざ「五星紅旗を振る中国人の応援でいっぱい」の観客席の方で、時計をにらみながらパソコンを開いて原稿を書いていていらしたそうです。なぜ記者席に座らなかったか事情は分かりません。> 戦況は中国側が優勢になり出し、応援団が興奮気味に。すると中国人の親子が自分たちの席を離れ、私の目の前に立ちふさがった。最初は軽く肩をたたき、横にずれてもらうよう促した。だがこれが3回も続き、さすがに堪忍袋の緒が切れて日本語で大声を出して注意した。・・・まぁ、「パソコンを開いて原稿を書いていた」ということは、世界の頂点を決める熱戦が繰り広げられ観客が総立ちとなっている中で、天野記者は一人座ったまま、「ながら観戦」していらっしゃったはずです。自分で「五星紅旗を振る中国人の応援でいっぱいだった」観客席に座っているのですから、通常は想定すべきことだと思われますが、座ったままの天野記者からでは、まったく試合が見えなくなってしまったんでしょうね。そういうことを防止するためにも前述の記者席と観客席の区別があるはずなんですが。それに、この間も日本代表の選手は日の丸を背負って戦っていますから、天野記者の「ながら観戦」は選手に対して失礼であるだけでなく、ある意味で「日の丸に対する不起立」ですね。>ところが、その母親は謝るどころか、こちらに跳び蹴りをくらわし、危うくパソコンに当たりそうになった。観戦マナーの悪さに愕然(がくぜん)とした。>ところが、その母親は謝るどころか、こちらに跳び蹴りをくらわし、危うくパソコンに当たりそうになった。観戦マナーの悪さに愕然(がくぜん)とした。>ところが、その母親は謝るどころか、こちらに跳び蹴りをくらわし、危うくパソコンに当たりそうになった。観戦マナーの悪さに愕然(がくぜん)とした。・・・ここで、核心の跳び蹴りの描写。天野記者は「こちらに跳び蹴りをくらわし、危うくパソコンに当たりそうになった。」と表現しています。「何が起きたのか」という一番肝心の事を他人に伝えるのに、この言い回しはどうなんでしょうか?前半で「跳び蹴りをくらわし」たとあるからには、天野記者がどこかを蹴られたように読むのが通常だと思われますが、どこを蹴られたとも書いてありません。逆に「危うくパソコンに当たりそうになった。」という後半の表現から、母親の蹴りは天野記者どころかパソコンにすら、かすりもしていなかったことが推測できます。その後の記述からも何の被害も見当たりませんから、記事のタイトルである『跳び蹴りしてきた中国人』というのが、何か被害があったかのように、最も大げさに表現したものであることも分かるわけです。・・・もう一つ気になるのが「跳び蹴り」という表現です。もろもろの情報から、かなり近い距離でのやりとりだったと思われますが、母親はなぜ、また、どうやって「跳び蹴り」をしたんでしょうか?わざわざ「跳び蹴り」とあるということは、天野記者の虚言であるとも思えません。天野記者が母親を叱責したとするならば、至近距離の相手に「跳び蹴り」という選択肢はないでしょう。この場合、天野記者の叱責の対象は息子の方に対してではなかったのかと思います。母親の側から見て「日中戦の真っ最中、みんなと一緒に自国の応援をしていると、後ろでパソコンをいじっていた日本人が日本語で何かをかをわめきたてはじめ、さらには息子に手をかけたので、とっさに跳び蹴りのモーションをして牽制した」というような状況でないと「跳び蹴り」はないように思います。この事例の場合、日本の法律を適用しようとしても「暴行未遂」や「器物損壊未遂」止まりで処罰のしようがないでしょう。身体的接触をしているのはむしろ天野記者の方で、母親の側は天野記者に触れていないわけです。結局のところ「私は蹴られそうになりました!」という、記者の個人的な事象を公のニュースにしているわけで、産経新聞の報道姿勢がよく表れています。-----(引用はじめ)-----------------------------------------2016.6.17 15:49更新 ピースボート災害ボランティアセンターへの回答書 一般社団法人ピースボート災害ボランティアセンターの山本隆代表理事の抗議を受け、産経新聞社は以下の回答書を送付した。 ◇回答書平成28年6月17日 6月16日に産経ニュースで報じた「TBS番組『街の声』の20代女性がピースボートスタッフに酷似していた?! 『さくらじゃないか』との声続出」の記事に関して、貴団体の抗議に回答いたします。 当該記事は6月16日にインターネット上で話題になっていた事象を記事化したものです。ご指摘通り、記事化する際、TBSおよびテレビ朝日に取材するだけでなく、貴団体にも取材すべきだったにもかかわらず、これを怠っておりました。 貴団体およびスタッフに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。 取り急ぎ、当該記事は産経ニュースおよび関連サイトから削除しました。代わって貴団体の抗議文を掲載しております。この回答文も全文を産経ニュースに掲載いたします。-----------------------------------------(引用おわり)-----少なくとも、最低限の取材や検証をしないままでも記事にするというのは、日本では産経新聞のみにできる芸当です。参照:ピースボート災害ボランティアセンターへの回答書 2016.6.17 15:49更新 http://www.sankei.com/life/news/160617/lif1606170019-n1.html【更新】産経が報じたやらせ疑惑に反論 ピースボート「取材なかった」→記事削除・謝罪https://www.buzzfeed.com/satoruishido/sankei-shinbun?utm_term=.ns5rWqa5D#.oi4gANVqw今日はこの辺で。
2016.08.21
コメント(2)
-

荘子と進化論 その198。
ひさびさに荘子です。今日は、中華圏で流行語になっている「洪荒之力(ホンホワンジーリー hóng huāng zhī lì) 」について。「洪荒之力」という言葉は、リオデジャネイロオリンピックの100メートル背泳ぎの銅メダリスト、傅園慧(フ エンケイ・Fu Yuanhui)が、競技直後のインタビューの中で使ったものです。この時の彼女の言動や、そこから垣間見える個性的なキャラクターは、中華圏のみにとどまらず、BBCも記事にするなど、周囲から好意的に受け入れられたようです。参照:Fu Yuanhui's Greatest Moments (English subs) https://www.youtube.com/watch?v=Jn0nPGfH1HI参照:Fu Yuanhui: China's disarming and expressive Olympic swimming star BBChttp://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-37031983「洪水」の「洪」に「荒野」の「荒」と書いて、「洪荒(コウコウ・hong huang)」。現代日本では、ほぼなじみのない言葉といっていいでしょう。この単語の最も古い出典は、6世紀初頭、梁の武帝の命により周興嗣が書いたとされる『千字文(せんじもん)』の冒頭「天地玄黄、宇宙洪荒」だと思われます。『千字文』は日本では『論語』とともに和仁によってもたらされた、教育用の書物、いわば教科書の元祖です。日本人が最初に触れる文字記録の入り口に、すでにこの「洪荒」という単語はありました。参照:Wikipedia 千字文https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%83%E5%AD%97%E6%96%87 『千字文』での用法を見ても分かりますが、「洪荒」は、神話の時代、天地開闢前後のこの世界(宇宙)の有様を表現する場合に使われていました。混沌としてぼんやりとした状態や人間が社会を形成する以前の時代を指したりする場合もあります。 『古天地未剖、陰陽不分、渾沌如鶏子、溟滓而含牙。及其清陽者、薄靡而爲天、重濁者、淹滯而爲地、精妙之合搏易、重濁之凝竭難。故天先成而地後定。然後、神聖生其中焉。故曰、開闢之初、洲壞浮漂、譬猶游魚之浮水上也。于時、天地之中生一物。狀如葦牙。便化爲神。號國常立尊。次國狹槌尊。次豐斟渟尊。凡三神矣。乾道獨化。所以、成此純男。』(『日本書紀』巻第一 神代上)→古の時、天と地は未だ分かれず、陰陽も分かれず、混沌として鶏の卵のようでありながら、ほのかに兆しが含まれていた。清陽なものはたなびいて天となり、重濁なものはとどまって地となった。精妙な集まりは群がりやすく、重濁な集まりは固まりにくいので、天がまず定まり、後に地が定まった。しかる後に神聖なるものがその中に生まれた。故に「開闢の始まりにおいて土地が浮かれ漂うさまは、たとえるなら、游魚が水の上を浮かんでいるようだ」と言われる。このとき天地の間に一つのものが生まれた。その様子は葦の芽が吹きだすようであり、すぐに神となられた。國常立尊(クニノトコタチノミコト)と言う。次に國狹槌尊(クニノサツチノミコト)。次に豐斟渟尊(トヨクムヌノミコト)。すべてで三柱の神、乾のみで生まれたので、純粋な男の神となられた。・・・『日本書紀』や『古事記』において最初に描かれている時代のことを「洪荒」と呼ぶわけです。参照:『荘子』と『淮南子』の宇宙。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5186/『淮南子』と『日本書紀』 ~天地開闢~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5187/「洪荒の力」という言葉は、傅園慧(フ エンケイ)の造語ではなく、去年放送された『花千骨』というテレビドラマの中でヒロインが最後に使った妖魔の力の名前からなんだそうです。この『花千骨』は、神仙世界を舞台にしたファンタジー作品で、「洪荒之力」も道教の範疇の用語から派生したものであることが見て取れます。また、『封神演義』や『西遊記』などを「洪荒小説」と呼ぶことがありますが、これは、上記の作品には「洪荒の時代」が描かれているからでして、この文脈における「洪荒之力」とは、宇宙生成論に直結する「天地開闢の力」「太古の力」「原始の力」といった意味になります。参照:《花千骨》主题曲MV 不可说-片花 霍建华丽颖动情对唱 https://www.youtube.com/watch?v=xRK5EBEXO-Q参照:Monkey Magic https://www.youtube.com/watch?v=iiqkwPJTJko↑にある❝Primal chaos❞を「洪荒」、❝Nature of monkey❞を「洪荒之力」とするとしっくりくると思います。実は『西遊記』をベースにした『ドラゴンボール』でも、「洪荒之力」というのは、何度も効果的に描かれています。老子や荘子の言葉としては直接はないものの、タオイズムにおいては大変象徴的な言葉でして、これを機会に、ということで。------(引用はじめ)-------------------------------------------------------------中国の傅園慧、愛される人柄 100背泳ぎ3位 競泳女子100メートル背泳ぎでカナダ代表のカイリー・マッセと同タイムの3着。背泳ぎで中国勢初の銅メダルを獲得して、中国のインターネットで一躍、時の人になった。 もっとも、傅園慧が愛されるのはメダルよりも、人柄によるところが大きい。8日、決勝直後にプールから上がったばかりの国営メディアとのインタビュー。 傅「メダルは取れなかったけど……」 記者「いえ、3位ですが……」 傅「ええ? 知らなかった! 腕がもうちょっと長かったら、もっといい成績だったわね。これまでの努力が無にならなくてよかったけど、足がつっちゃったわよ」 大きな口を開けて笑う傅と戸惑う記者の映像は「競泳界のコメディアン」と話題をさらい、「つまらない受け答えばかりという中国人選手のステレオタイプをよくぞ打ち破った」と彼女の中国版ツイッターには1日で400万人近いフォロワーが殺到した。 子供の時、ぜんそくだった。水泳を始めたのは、娘の体力向上にと5歳の時に父親が勧めたことがきっかけで、いまも天津市の天津医科大学で運動リハビリを学んでいる。 昨年の世界選手権の50メートル背泳ぎで優勝した背泳ぎのスペシャリストだが、50メートルの種目がない五輪は前回ロンドン大会から100メートルで出場する。 ロンドンは8位だったが、リオでは準決勝、決勝と自己ベストを更新し続け、銅メダルを手にした。それでも「両親はメダルのことなんて気にしてないわ。私に幸せであってほしいと願っているだけ。そして私は実際、幸せよ」と話し、メダル至上主義へのアレルギーをやんわりとのぞかせる。 20歳の女性らしく「もうちょっとおしとやかに」と言われることもある。それには涼しい顔でこう答える。「私には感情があるの。子供の時からこんな感じだし、自分らしくありたいと思っている。そうでなかったら、人が羨む成績を残したって意味ないわ」 私は私。五輪であろうとなかろうと、普通が一番。そう言っているように見えた。【石原聖】-------------------------------------------------------------(引用おわり)------参照:中国の傅園慧、愛される人柄 100背泳ぎ3位 毎日jphttp://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20160813/k00/00m/050/032000c『吾所謂臧者、非所謂仁義之謂也、任其性命之情而已矣。吾所謂聰者、非謂其聞彼也、自聞而已矣。吾所謂明者、非謂其見彼也、自見而已矣。夫不自見而見彼、不自得而得彼者、是得人之得而不自得其得者也、適人之適而不自適其適者也。』(『荘子』駢拇 第八)→私の言う「善」とは世間の言う仁義ではない。己が内にある自然の徳をあるがままにまかせることを善と言う。私の言う「聡」とは、外界の音がよく聞こえるということではなく、内なる声に耳を傾けることができることを言う。私が言う「明」とは、外界の色をよく見分けられることではなく、内なる私を見つめられること言う。自分の内にあるものを見つめずに、外にあるものに気を取られたり、自分の心に適うものを求めずに、他人の心に適うものを求めるのは「他人が納得することは自分も納得するものだ」と思い込んでいるのであり、それは「自分の心に適うもの」とは言えない。他人の楽しみを自分の楽しみとしているうちは、「自適」とは言わないものだ。まどろっこしい理念や理屈はさておいても、傅園慧選手は、まぎれもなく現代中国を代表するタオイストである、と私は思います。参照:The hidden meanings of yin and yang - John Bellaimey https://www.youtube.com/watch?v=ezmR9Attpyc今日はこの辺で。
2016.08.15
コメント(0)
-

タモさん逮捕さる。
今のうちに、記録。幸福実現等の広告塔、我らが空幕長、タモさんがついに逮捕されてしまいました。公務員だった頃から遵法精神が見られず、民間企業との癒着も多かったタモさんですので、あまり意外と言う印象はありません。-----(以下引用)-----------------------------------------------田母神俊雄容疑者 逮捕 14年都知事選、運動員買収 東京地検毎日新聞2016年4月14日 東京夕刊 2014年2月の東京都知事選後に、運動員に選挙運動に対する報酬を支払ったとして、東京地検特捜部は14日、知事選に立候補して落選した元航空幕僚長、田母神(たもがみ)俊雄容疑者(67)と、当時の選挙対策事務局長で会社役員の島本順光(のぶてる)容疑者(69)を公職選挙法違反(運動員買収)容疑で逮捕した。知事選後発覚した資金管理団体を巡る使途不明金問題は、元空自トップ逮捕に発展した。 田母神元空幕長の逮捕容疑は、都知事選後の14年3月中旬ごろ、東京都内の事務所で、事務を統括し選挙運動をしたことへの報酬として島本元事務局長に200万円を支払ったほか、島本元事務局長らと共謀し、同3月中旬〜5月上旬、同事務所などで運動員だった5人に対し、投票を呼びかけて練り歩いたことなどに対する報酬として、現金計280万円を供与したとしている。 島本元事務局長は田母神元空幕長から200万円を受け取った容疑でも逮捕された。 公選法は、選挙管理委員会に登録された車上運動員や事務運動員らに対する法定の範囲内での報酬支払いだけを認めている。選挙対策本部の幹部や有権者に投票を呼びかけるような選挙運動をする運動員への報酬は禁じられている。 捜査関係者によると、計280万円を受け取った5人は、東京都選管に運動員として登録されていなかった。 田母神元空幕長はこれまでの取材に対し、現金が配布されたことを認めた上で「支払いは後になって知った。私は指示も了承もしていない」と直接の関与を繰り返し否定していた。 田母神元空幕長は、都知事選で約61万票を獲得したものの得票数4位で落選した。関係者によると、選挙後に島本元事務局長が「みんなよくやってくれたので、お礼がしたい」と提案。計2000万円分の現金提供先として作成されたリストに数十人の氏名が記されていたという。 田母神元空幕長の資金管理団体「東京を守り育てる都民の会(現・田母神としおの会)」の14年の政治資金収支報告書によると、同年の収入約1億3300万円のうち、約5054万円が使途不明となっている。特捜部は先月7日、業務上横領容疑で田母神元空幕長の自宅などを家宅捜索。その後の捜査で、使途不明金の一部が知事選の運動員に報酬として支払われた疑いが強まった。【石山絵歩、飯田憲】-----------------------------------------------(引用終わり)-----われわれの先人たちは「生きて虜囚の辱めを受けず」と自決した方も多いと聞きますが、どうやらタモさんはいまのところ辱めを受けながらもお元気なようです。さて、タモさんの逮捕が平成28年4月14日ということで、タモさんのスポンサー・幸福の科学が、いつものように、熊本地震を起こした神との対話を書物にしております。-----(以下引用)-----------------------------------------------公開霊言「熊本震度7の神意と警告」2016年4月15日収録熊本県で震度7の地震が起きた。巨大地震や火山噴火を単なる自然現象ととらえるのでなく、そこに神意を読み取るのが、古来の宗教の伝統的な立場だ。 大川隆法・幸福の科学総裁は15日、地震に関わった霊的な存在を呼び、その意図を探った。「霊言現象」とは、あの世の霊存在の言葉を語り下ろす現象のこと。これは高度な悟りを開いた者に特有のものであり、「霊媒現象」(トランス状態になって意識を失い、霊が一方的にしゃべる現象)とは異なる。また、外国人の霊の霊言には、霊言現象を行う者の言語中枢から、必要な言葉を選び出し、日本語で語ることも可能である。 詳しくは⇒⇒⇒大川隆法のスーパー霊能力 「霊言」とは何か熊本の地震から一夜明けた15日、大川隆法総裁は、地震に深く関係した霊を呼び出した。 現れた神霊は、冒頭で、約1年半前に起こった阿蘇山の噴火を念頭に、「地震、噴火、津波。こういうものが来るときは、だいたい私らが、何か政治的なメッセージを出している」と語った。ただの自然現象ではなく、神意が込められたものだという。日本社会では、新聞の部数やテレビの視聴率、世論調査の結果を「民意」とする向きが強いが、この点について、神霊はこう指摘した。 「一人一票をかき集め、多数を取ったものが「正義」ということになっているが、多数になった者がやっている仕事が悪い。(中略)戦後体制で宗教や神の心を完全に排除しようとしてきた七十一年だ」 安倍談話への不快感話は安倍晋三首相に及び、5月下旬に控えている伊勢志摩サミットについて、神霊は次のように一喝した。「伊勢神宮を引き合いに出し、信仰心があるようなふりをして、日本が神々のおわす国である、と見せようとしているのだろう。しかし、心の中に“濁り"がある」また、安倍首相が靖国神社への参拝を行わないことや、昨年夏の自虐史観を踏襲する「安倍談話」、昨年末の慰安婦問題に関する「日韓合意」について、不快感を示した。 「神の正義とは何か」地震の前日にあたる14日、元航空幕僚長の田母神俊雄氏が、東京都知事選にからむ金銭問題で逮捕された。神霊はこの問題にも言及。安倍政権の狙いが、左翼に媚を売って選挙の票を確保することや、自民党内のスキャンダルをそらすことにあると指摘。「法務大臣が指揮し、逮捕している以上、総理大臣が知らないわけがない」とし、「これを北朝鮮がミサイル撃つ前の日にやった。どういう媚の売り方なんだ」「やり方が姑息。神々はこういう政治は好きではない」と憤り、本来やるべきは、 アメリカを巻き込んだ国防の強化だとした。また、神霊は約半世紀にわたって「自民党幕府」が政権を担ってきた中で、財政赤字が1000兆円超に膨らんだ責任を厳しく批判。最後に、自らの正体を「一人の考えではない。日本の意志の神、日本という国の意志なんだ」とした。 熊本では2014年11月にも阿蘇山が噴火した。それは、安倍首相が「消費増税の先送り」を表明し、衆院を解散した数日後の出来事だった。現在、自らの経済政策の失敗を棚に上げて、再び「消費増税先送り解散」を打つ動きを見せている。戦後、唯物的な価値観の中で繁栄を目指した日本人は、「神の正義とは何か」について考えることを迫られている。-----------------------------------------------(引用終わり)-----参照:Liberty Web 熊本震度7の神意と警告http://the-liberty.com/article.php?item_id=11193北朝鮮のミサイル発射の直前に元航空幕僚長を逮捕するとは何事だ!と神々も現政権にお怒りとのこと。その結果としての熊本の地震なんだそうです。そんなに政治に不満があるなら東京で地震を起こせばいいわけで、わざわざ熊本で起こしてしまう、この自称・神様の「まどろっこしさ」は、人間社会のテロリストよりも劣悪ですね。参照:熊本震度7の地震の神意を探る【CM動画】 https://www.youtube.com/watch?v=TVRrSkQV0dAこの神様のしゃべっているのは何弁?あと、たとえ神様でも人前でしゃべるときは帽子をはずしたほうが良いと思います。カルトにとって地震の直後というのは格好の稼ぎ時でもありますが、阪神淡路大震災と同じ年に起こったオウムの事件と同じように、社会的不安の暴走を引き起こすことは十分に考えられます。これに元空幕長が絡んでくるとか、もはや漫画の域ですが、産経新聞界隈では日常です。当ブログは今後ともタモさんの健康をお祈りいたします。
2016.04.18
コメント(0)
-

荘子と進化論 その197。
北東アジアの民族大移動が太陽暦と太陰暦の双方で終わりました。季節は春、ということで、今日は『荊楚歳時記(けいそさいじき)』という書物から。『荊楚歳時記』は、魏晋南北朝時代にあたる6世紀頃の、揚子江中流域の年中行事を記録したものです。著者は梁の宗懍(そうりん)という人物。彼の故郷である「荊」・「楚」と呼ばれる地域(現在の湖北省・湖南省付近、三国志では江陵と呼んでいた辺り)の風俗に焦点をあてたもので、ローカルで庶民的な生活の記録です。「歳時記(さいじき)」という表現も、この『荊楚歳時記』こそが嚆矢でして、奈良時代に伝来して以降、日本文化へ非常に大きな影響を与えました。《正月一日,是三元之日也,謂之端月。鷄鳴而起。先於庭前爆竹,以辟山臊惡鬼。帖畫雞,或斵鏤五采及土鷄于戶上。造桃板著戶,謂之仙木。繪二神貼戶左右,左神荼,右鬱壘,俗謂之門神。於是長幼悉正衣冠,以次拜賀,進椒柏酒,飲桃湯,進屠蘇酒,膠牙餳,下五辛盤,進敷于散,服却鬼丸,各進一雞子。凡飲酒次第從小起。梁有天下,不食葷,荊自此不復食雞子,以從常則。熬麻子、大豆,兼糖散之。又以錢貫繫杖脚,廻以投糞掃上,云「令如願」。正月七日為人日,以七種菜為羹,翦綵為人,或鏤金箔為人,以貼屏風,亦戴之以頭鬢,亦造華勝以相遺,登高賦詩。立春之日,悉翦綵為鷰以戴之,帖「宜春」二字。立春日,為「施鈎」之戲,以緶作篾纜相罥,綿亘數里,鳴鼓牽之。又為打毬鞦韆之戲。正月十五日,作豆糜,加油膏其上,以祠門戶。其夕,迎紫姑,以卜將來蠶桑,并占衆事。正月夜,多鬼鳥度,家家槌床打戶,捩狗耳,滅燈燭以禳之。正月未日夜,蘆苣火照井廁中,則百鬼走。》(『荊楚歳時記』より)→正月一日とは、三元の日である。いわゆる端月のこと。鶏が鳴いて目覚める。まず、庭の前で爆竹を鳴らし、山の悪鬼を退ける。画雞を貼り、あるいは五采をちらして土鷄を戸の上に置く。また桃板を造って戸に掲げる。これを仙木という。二神の絵は戸の左右に貼る。左が神荼(しんと)、右が鬱壘(うつるい)である。これが俗に言う門神のことである。ここで、老いも若きも皆衣冠を正し、順に新年の賀を拝する。椒柏酒を勧めて、桃湯を飲み、屠蘇酒を勧めて、さらに膠牙湯、五辛盤を下し、敷于散を勧めて、却鬼丸を服し、各々一つの卵を勧める。おおよそ年少の者から順に始める。梁の天下の頃には葷(にら)を食することはなく、荊州では、是から再び卵を食さず、常則に従う。麻子、大豆を煎り、糖とからめて之を散じる。また、銭を束ねたものを杖脚に繋いで回し、糞土の上に投げて「令如願(ねがうとおりになれ)」と言う。正月七日は「人日(じんじつ)」とする。七種類の野菜で羹(あつもの)を作る。彩の布を切って人形としたり、あるいは金箔を飾って人形とし、屏風に貼り付けたり、髪飾りとして頭に載せたりする。また、華勝を作って首飾りとして互いに送り合う。また、高所に登って詩を賦す。立春の日、みな彩の布をを切って燕を作って髪飾りとし、「宜春」の二字を門に貼る。立春の日には「施鈎之戲」を行う。縄を編んで篾纜(べつらん)を作り數里離れた所から太鼓を鳴らしこれを引き合う。また、「打毬(蹴鞠の一種か?)」や「鞦韆(ブランコ)」の戯を行う。正月十五日、豆糜(とうび)を作り、油膏を加えて、これで門戸を飾る。その日の夕方、紫姑を迎えてその年の蚕の成長やその他もろもろの事柄を占う。正月の夜、多くの鬼鳥が渡るため、家々では槌で床や戸を叩いたり、犬の耳をねじったり、灯火を消してこれを避ける。正月未日の夜、蘆苣(葦の束)を燃やして廁の中を照らすと、百鬼はたちまち逃げ出す。(平凡社刊 東洋文庫『荊楚歳時記』を参照)参照:維基文庫 自由的図書館 荊楚歳時記https://zh.wikisource.org/wiki/%E8%8D%8A%E6%A5%9A%E6%AD%B2%E6%99%82%E8%A8%98『荊楚歳時記』の1月の部分から抜粋しました。1500年ほど前の長江中流域の年中行事の記録の中に、現代日本においても続いている行事が見られると思います。このうち、「先於庭前爆竹,以辟山臊惡鬼(庭で爆竹を鳴らして、山の悪鬼を退ける)」という部分。現在でも大陸ではよく見られる風習ですが、この当時の「爆竹」というのは、火薬を使用しているものではなく、まさに「爆ぜる竹」。竹を火にくべて爆発させ、その音と煙で「鬼」を追い払うものだと思われます。この時代には火薬はまだ発明されていません。参照:道教と火の薬。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201504150000/また、「屠蘇(とそ)」の風習についても書かれています。これも「鬼」にまつわる記述が多いものです。参照:お屠蘇と仙薬。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201501050000/『荊楚歳時記』には、正月の風習について以下のような註釈があります。《按:莊周云︰「有掛雞于戶,懸葦索於其上,插桃符於旁,百鬼畏之。」又魏時,人問議郎董員力云︰「今正、臘旦,門前作烟火,桃神,絞索松柏,殺雞著門戶,逐疫,禮歟?」員力答曰︰「禮。十二月索室逐疫,釁門戶,磔鷄。漢火行,故作助行氣。桃,鬼所惡,畫作人首,可以有所收縛,不死之祥。」又桃者五行之精,能制百怪,謂之仙木。《括地圖》曰︰「桃都山有大桃樹,盤屈三千里,上有金雞,日照則鳴。下有二神,一名鬱,一名壘,并執葦索,以伺不祥之鬼,得則殺之。」即無神荼之名。應劭《風俗通》曰︰「《黃帝書》稱︰『上古之時,有神荼、壘鬱兄弟二人,住度朔山上桃樹下,簡百鬼。鬼妄搰人,援以葦索,執以食虎。』于是縣官以臘除夕飾桃人,垂葦索,畫虎于門,效前事也。」》(同上)→莊周にいう「戸口に鳥を掲げる家があり、その上に葦をかけ、傍らに桃符を挿すと百鬼はこれを畏れる」と。また、魏の時に議郎の董員力に人が問いて「今、年明けの朝、門前に烟火を焚き,桃神を祀り,葦縄で松柏を絞め、鶏を殺して門戸に置くのは疫を逐うのは禮によるのでしょうか?」というに、員力が答えて曰く「禮では十二月索室にて疫を逐うには,門戸を血塗り、鶏を磔にし、漢火を行うことで行氣を助ける。桃は鬼の悪むところ。人首を絵に描いて鬼を收縛する所もあるという。これは不死の祥なのだそうだ。また桃は五行の精であり、百怪を制するという仙木である。」『括地図』によると、「桃都山に大桃樹があり三千里の枝を伸ばしているという,上には金雞がおり、日に向かって鳴く。下には二神がおり、一方を鬱、一方を壘という。葦の縄を持ち、不祥の鬼をうかがい捕まえて鬼を殺す。」ともある。まだこの頃には神荼の名はない。應劭の『風俗通』には「『黃帝書』によると「上古の時、神荼、壘鬱の兄弟二人の兄弟がおり、度朔山の上の桃樹の下にて百鬼を観察している。鬼が人に悪事を働くようであれば葦の縄で捕らえて虎に食わせる。」そこで、こういった風習に倣って縣官は年の暮れに桃人を飾り、葦索を垂らし、虎を描いた画を飾る。」とある。注釈において『荘子』からの引用として、「有掛雞于戶,懸葦索於其上,插桃符於旁,百鬼畏之。(戸口に鳥を掲げる家があり、その上に葦をかけ、傍らに桃符を挿すと百鬼はこれを畏れる)」という記述があるとされていますが、これは現在の『荘子』に掲載されていません。同じく7世紀の『芸文類聚』(げいもんるいじゅう)という書物でも『荘子』の記述として「插桃枝於戶,連灰其下,童子入不畏,而鬼畏之,是鬼智不如童子也。(桃の枝を戸に差し、その下に灰を撒く。童子がこれを畏れることはないが、鬼はこれを畏れる。鬼の智が童子におよばないところである。)」とあるとしています。「桃」と「鬼」とを関連付けた記録としては最古級のものですが、現在では孫引きでしかお目にかかれない、『荘子』の逸文です。『荊楚歳時記』においても、神荼(しんと)と鬱壘(うつるい)という、鬼を召し捕らえる二神(門神)について書いてあります。他の書物では鬼門にもかかわる部分です。キーワードとして「桃」と「葦」が何度も出てきています。参照:追儺と鬼、追儺と桃。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5171/『古事記』で言うと、イザナギが黄泉国から葦原中国へと戻る途中の黄泉比良坂で「桃」を投げるシーンがあります。桃と鬼の関係はこの物語に相応しています。 註釈の中の「門前作烟火,桃神,絞索松柏,殺雞著門戶,逐疫(門前に烟火を焚き,桃神を祀り,葦縄で松柏を絞め、鶏を殺して門戸に置くのは疫を逐う)」という部分。(余談ですが、門前で行う儀式のうち、順に爆竹、桃、葦の後にある松柏は現在で言うところの「門松」を連想させます。)その後に「釁門戶,磔鷄。(門戸を血塗りして、鳥を磔にする。)」とあります。門に鶏を掲げたり、門を赤く塗る風習の名残が、いわゆる「烏頭門(うとうもん)」であろうと思われます。道観や寺院に見られる「牌坊」「牌楼」と呼んだりする門の原型です。簡易版として、門前に赤い紙を貼る風習「春聯」は、現在でもよく見られると思います。いわゆる「福は内」ってヤツです。道教の中でも「風水」の方法論も、こういった風習の中に息づいているものです。参照:維基百科 牌坊https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%89%8C%E5%9D%8A《熬麻子、大豆,兼糖散之。 按《煉化篇》云「正月旦,吞雞子、赤豆各七枚,辟瘟氣。」又《肘後方》云「旦及七日,吞麻子、小豆各十七枚,消疾疫。」張仲景《方》云︰「歲有惡氣中人,不幸便死,取大豆十七枚、雞子、白麻子并酒吞之。」然麻豆之設,當起於此。今則熬之,未知所據也。》(同上)→麻子仁(麻の実)と大豆を糖とからめて之を撒く。 註釈:『煉化篇』によると「元旦に卵と赤豆七枚を飲めば、瘟氣を退ける。」また『肘後方』には「元旦と七日には麻子仁と小豆を各十七枚飲めば、疫病は消える。」また張仲景の『方』は「毎年惡氣に当たり、運に恵まれないとすぐに死んでしまう。大豆を十七枚と卵、白い麻子と酒を合わせてこれを飲む。」とあり、麻や豆の説はまさにここから始まったのだろう。ただし、現在、なぜこれを「煎る」のかは分からない。参照:道教と神農。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201411230000/今日はこの辺で。
2016.02.20
コメント(0)
-
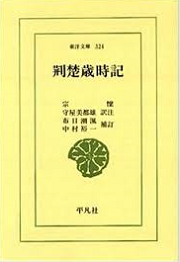
大豆の理由。
『荊楚歳時記』という魏晋南北朝時代の生活文化を記録した本によると、1500年ほど前の荊や楚といった地方では、正月に下記のような風習があったそうです。《熬麻子、大豆,兼糖散之。按《煉化篇》云「正月旦,吞雞子、赤豆各七枚,辟瘟氣。」又《肘後方》云「旦及七日,吞麻子、小豆各十七枚,消疾疫。」張仲景《方》云︰「歲有惡氣中人,不幸便死,取大豆十七枚、雞子、白麻子并酒吞之。」然麻豆之設,當起於此。今則熬之,未知所據也。》『荊楚歳時記』より→麻子仁(麻の実)と大豆を糖とからめて之を撒く。註釈:『煉化篇』によると「元旦に卵と赤豆七枚を飲めば、瘟氣を退ける。」また『肘後方』には「元旦と七日には麻子仁と小豆を各十七枚飲めば、疫病は消える。」また張仲景の『方』は「毎年惡氣に当たり、運に恵まれないとすぐに死んでしまう。大豆を十七枚と卵、白い麻子と酒を合わせてこれを飲む。」とあり、麻や豆の説はまさにここから始まったのだろう。ただし、現在、なぜこれを「煎る」のかはいまだ分からない。正月の風習の記録ではあるんですが、現在の日本の風習で言うと節分ですよね。そんな話を次回。今日はこの辺で。
2016.02.02
コメント(0)
-

荘子と進化論 その196。
今日はまず、『スター・ウォーズ エピソード1 ファントムメナス(PHANTOM MENACE 1999)』から。クワイ=ガン・ジン(Qui-Gon Jinn)が、幼き日のアナキン・スカイウォーカー(Anakin Skywalker)に教えを授けるシーン。Qui-Gon Jinn: Remember, concentrate on the moment. Feel, don't think.Use your instincts. (憶えておけ。この瞬間に集中しろ。感じろ。考えるな。自分の直感を働かせるんだ。)参照:Remember, concentrate on the moment. Feel, don't think https://www.youtube.com/watch?v=l-UHYdJ6Q8M次は、『燃えよドラゴン(Enter the Dragon 1973)』から。“Don't think! Feel! It is like a finger pointing away to the moon. Don't consentrate on the finger,or you will miss all that heavenly glory.”(考えるな!感じろ! それは月を指す指のようなものだ。 指に注意を向けるな、そんなことでは天の輝きを見失ってしまうぞ。)参照:Finger Pointing to the Moon - Bruce Leehttp://www.youtube.com/watch?v=sDW6vkuqGLg クワイ=ガンもリーも共に「集中すること」について、“Don't think(考えるな)”と“Feel (感じろ)”と同じ言葉を使っています。もちろん、映画史上に残る名作『燃えよドラゴン』の有名なセリフを『スター・ウォーズ』のスタッフが知らないわけがありません。これは明白なオマージュです。他にも『シスの復讐(REVENGE OF THE SITH 2005)』で、ヨーダが素手になったときに、左手で小さく相手を誘う仕草をするのも、ブルース・リーの影響を示唆しています。参照:Star Wars - Yoda vs. Palpatine HD qualityhttps://www.youtube.com/watch?v=9DI8kkR9G0Qスター・ウォーズ・シリーズは、エピソード1に戻った際に、殺陣も、日本の武術の動きから、中国武術のそれに移行しています。明白な例としては、ダース・モール(Darth Maul)でして、俳優のレイ・パークはブルース・リーに影響を受けて、幼い頃から中国武術を学んだ、北少林寺の棍術の使い手です。動きを見るだけでも、他の俳優との力量の差が歴然としています。(ちなみに、これまた細かいですが、オビ=ワンの動きが格段に良くなる直前の身体の上下運動は『ドラゴンへの道(The Way of the Dragon 1972)』からでしょう。)エピソード1に登場するジェダイ、クワイ=ガン・ジン(Qui-Gon Jinn)も、わざとらしいくらい東洋的なキャラクターで、戦闘の合間に瞑想をするシーンなどは、その典型といえます。 参照:Obi Wan & Qui Gon Ginn Vs Darth Maul HD 1080p https://www.youtube.com/watch?v=yHqdESArkqUブルース・リーの思想は、もともと道教(特に老荘思想)と禅仏教に軸足を置いています。スター・ウォーズ・シリーズも、同様にこれらの思想の影響がありまして、ちょっと掘り下げるだけでも、同じ泉に突き当たります。参照:ブルース・リーと東洋の思想 その1。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5180/マスター・ヨーダと老荘思想 その1。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5025/さらに言うと、クワイ=ガン・ジン(Qui-Gon Jinn)の名前の「クワイ=ガン(Qui-Gon)」の由来は「気功(Qi-gong)」ではないか、という有力な説があります。だとすると、「フォース(Force)」と「氣(Qi)」の関係や、ジェダイの思想と老荘思想や道教との類似性も、説明しやすくはなりますね。参照:ジェダイ(Jedi)と道教(Taoism)。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005203/スターウォーズと道教 ~フォースと氣~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005204/『一若志、無聽之以耳而聽之以心、無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳、心止於符。氣也者、虚而待物者也。唯道集虚。虚者、心齋也。』(『荘子』人間世 第四)→「志を一つにせよ。声を聴くのに耳ではなく心をもってせよ。そして、心ではなく【氣】をもってせよ。耳は聴くに留まり、心は知るに留まる。【氣】はすべてのものを受け入れることができる。雑念がないがゆえにすべての本質は虚にのみ集まる。無心でいるがゆえに、心斎といえるのだ。」この「氣」の性質は、セリフで説明される「フォース」のそれともよく似ています。Luke Skywalker: The Force?(「フォース」って?)Ben Kenobi: Well the Force is what gives a Jedi his power. It's an energy field created by all living things; it surrounds us, penetrates us, it binds the galaxy together.(フォースとは、ジェダイの力の源だ。それはあらゆる生き物から作り出され、われわれの周囲も包み込んでいる。そして、それは、宇宙の全てをつなぎとめているのだ。)『生也死之徒、死也生之始、孰知其紀。人之生、氣之聚也。聚則為生、散則為死。若死生為徒、吾又何患。故萬物一也。其所美者為神奇、其所惡者為臭腐。臭腐復化為神奇、神奇復化為臭腐。故曰『通天下一氣耳。』聖人故貴一。』(『荘子』知北遊 第二十三)→ 生には死が伴い、死は生の始まりである。だれがその初めと終わりを知り得よう。人の生は【氣】が集まったもの。集まれば生となり、散じれば死となる。生と死とが一体であるとすれば、私は何を思い煩うことがあろうか? 故に万物とは一つのものなのだ。人は美しく立派なものを尊び、腐って汚いものを憎む。しかし、腐って汚いものいずれは変化して、美しく立派なものとなり、かつて尊んでいたものも、やがては腐って汚いものと変化する。故に『天下は全て一つの氣の巡り』という。聖人はそこに貴賤を設けず、その「一」を貴ぶのである。後で推敲します。今日はこの辺で。
2015.12.24
コメント(0)
-

荘子と進化論 その195。
スター・ウォーズのつづき。今日は、フォース(Force)と氣(Qi)の関係について。「氣(Qi)」とは何か?この問いに対する答えは容易なものではありません。少なくとも、中国古典において紀元前に使われていた「氣」の用法は、その多くが宇宙生成論においてでして、代表的なものとしては老子の第四十二章が挙げられます。『道生一、一生二、二生三、三生萬物。萬物負陰而抱陽,沖氣以為和。』(『老子』 第四十二章)→道は一を生じ、一は二を生じ、二は三を生じ、三は万物を生じる。万物は陰を負い、陽を抱いて(並存しており)、沖氣(沖の字は本来はにすい)を以って調和している。『有物混成、先天地生。寂兮寥兮、獨立不改、周行而不殆、可以為天下母。吾不知其名、字之曰道。』(同 第二十五章)→天地に先立って、混沌とした何かがあった。静かであり、形もわからない。何にも影響されず、あまねく行き渡りながら何にも変えられない。これを天下の母となすべきだ。私はその存在の名前を知らない。あえて名づけて道(Tao)とする。参照:『荘子』と『淮南子』の宇宙。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005186/『臣安萬侶言。夫混元既凝。氣象未效。無名無爲。誰知其形。然乾坤初分。參神作造化之首。陰陽斯開。二靈爲群品之祖。(『古事記』上卷 幷序)』→臣、安万侶が申し上げます。混沌とした元素が固まり、氣のありさまが未だとらえられない頃、無名にして無為であり、誰もその形を知りませんでした。その後に乾坤(天地)が初めて分かたれ、三神が創造の魁となり、陰陽が開けて、イザナギ・イザナミの二霊が諸々の祖となりました。・・・日本で最も早くこの「氣」の記録があるのが『古事記』の上奏文です。「混元の氣→乾坤(天地)→陰陽→」という流れの片鱗がこれにも見て取れます。参照:荘子と太一と伊勢神宮。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005176/この「氣」は、フィクションの世界でも独特な変化を遂げます。特に、武術(Wushu)や気功(Qigong)の技法をさまざまな形式で展開する大衆娯楽、武侠(Wuxia)作品においては、その発展は顕著でした。 こちらは、1960年代の香港映画、『如来神掌』という作品の一場面です。火雲邪神というキャラクターと三人の道士とが、互いに氣を放出して応酬しています。この当時、基本的に目に見えない「氣」を、音や視覚効果によって直接的に描き出そうとしていました。現代人の目から見れば子供だましのような特殊効果ですが、今から半世紀以上前に「氣」を描こうという試みがあったということの実例の一つです。参照:如來神掌大戰三絕掌https://www.youtube.com/watch?v=B5Jh9nJjP7gこれは、表現としてはシスが使う「Force lightning」とよく似ています。参照:Star Wars - Yoda vs. Palpatine HD qualityhttps://www.youtube.com/watch?v=9DI8kkR9G0Q最近の例で言うと、 日本では、現在放送しているテレビシリーズ『スター・ウォーズ 反乱者たち(STAR WARS:REBELS)』(2014)の第3話「嘆きのドロイド」で、主人公のエズラが無意識にフォースを使って人を吹き飛ばすというシーンがあります。これ、金庸原作の『神雕侠侶(しんちょうきょうりょ)』(2006年度版)の中で、主人公の楊過がとっさに「蝦蟇功(がまこう)」を使うシーンとそっくりです。「剣と気功の江湖世界」で展開される武侠と『スター・ウォーズ』とはこういったところでも共通性が見られます。参照:Return of the Condor Heroes / 神雕侠侶 - 2006 - English Sub - Ep 2 https://www.youtube.com/watch?v=E8MIL4kA_Ms開始後12分くらい。ちなみに、金庸が1959年から3年間執筆した武侠小説『神雕侠侶』は、たびたび映像化されまして、去年のバージョンはこんな感じです。参照:《神雕侠侣》2014 陈晓版 主题曲MV 浩瀚 主唱:张杰 https://www.youtube.com/watch?v=kbLaMhfvm7g空気の密度というべきか、光の屈折の度合いによって氣の存在を描くのが最近の武侠モノの流行のようです。この水準でテレビドラマが製作されていることが、大陸での金庸作品の巨大さを雄弁に物語っています。金庸原作の武侠作品における「氣」も、技術が進めば進むほど透明度が増す傾向にあります。そうすると、ジェダイのフォースの表現に似てきます。参照:スターウォーズと武侠。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5200/日本でも「気」という漢字は、「天気」「気温」「二十四節気」といった外的環境を表す言葉と、「気分」「気持ち」「気づき」といった人間の意識や内面の事象を表す言葉の両方にあてられます。この「気」の用法ひとつをとっても、マクロコスモスとミクロコスモス、外的宇宙と内的宇宙の関連性が強く結び付けられる中国の思想における「氣」の思想の影響がわかると思います。これは、瞑想における「呼気」と「吸気」で説明すると分かりやすいかなと思います。自分の体内から気を吐き出し、新しい気を外から取り込む。ここにも内と外の気の関係がありますね。日本語でよく使われる「元気」という単語も、本来は、宇宙生成論における「混元の氣」のことを指すものでしたが、医療用語に転用されるなど、生命の根源的なエネルギーというような意味に使われるようになりました。参照:『黄金の華の秘密』と『夜船閑話』。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005146/『一若志,無聽之以耳而聽之以心,無聽之以心而聽之以氣。聽止於耳、心止於符。氣也者、虚而待物者也。唯道集虚。虚者、心齋也。』(『荘子』人間世 第四)→「志を一つにせよ。声を聴くのに耳ではなく心をもってせよ。そして、心ではなく【氣】をもってせよ。耳は聴くに留まり、心は知るに留まる。【氣】はすべてのものを受け入れることができる。雑念がないがゆえにすべての本質は虚にのみ集まる。無心でいるがゆえに、心斎といえるのだ。」こちらは人間の内面と「氣」の関係を記した『荘子』の言葉です。これについて、フランスの中国学者、アンリ・マスペロは、著作においてこう記しています。≪回心は神秘的生体験への入り口に過ぎない。これを終わりまで追求しようとする人は、長い浄化の段階、すなわちキリスト教徒のいう「浄めの道(ヴォア・ビュルガティヴ)」を通らなければならない。荘子はこれを「心斎」とよび、祭りによる斎戒、すなわち祭りに先立つ儀式としての物忌み、と対比させている。同じように、回教の神秘主義者は、肉体の外面的な禊の儀式に対して、魂の浄化を対立させている。シブリの言うところによると、ある日かれがモスクに行くために、いましも禊をすませたばかりのとき、かれを責める声がきこえた。「おまえは自分の外側を洗ったが、おまえの内部の清浄さはどこにあるのか」と。この心斎について荘子は次のように定義する。 おまえの注意を一つにせよ。耳で聴かずに、心で聴け。心で聴かずに「気」(霊)で聴け。きこえるものがおまえの耳を通り過ぎないように、おまえの心が専一になるようにせよ。そうすれば、「気」(霊)は「虚」となり、実在を把えるであろう。「道集」、すなわち道との合一は「虚」によってのみ得られる。この虚が、すなわち心斎である。 これは、神秘主義者における浄化ということ、すなわち外物の放棄と、それからの超脱、そして外物の影響から全く解放されて「虚」になった霊[精神・アーム]が実在を把え、絶対者と無媒介な直接の冥合に入るように、心を純化し、統一し、集中するということ、を見事に要約したものである。そして不思議なことには道家がその状態を記述しようとした「虚」という表現は、かれらに独自なものではない。スーフィ教徒は同じように、「神は人の心を空虚にして、神自身の認識を受けさせる。それゆえに、直観的なこの神の認識は、心のなかに神の純粋性を拡げてゆく」と言っている。教義的には異なった説明のなかに、同じ心理的体験が認められているのである。(東洋文庫刊 アンリ・マスペロ著『道教』より)≫「虚心坦懐」という言葉がありますが、本質と向き合う場合の精神のありかたについて、荘子は「氣で聴く」ことを諭します。STAR WARS - The DEATHSTAR BATTLE re-edited part 2 https://www.youtube.com/watch?v=aQFrl5rpXMg中華圏では「フォース(force)」は「原力(yuanli ユエンリー)」と表現されます。特に大陸の人々にとっては初めての、劇場での『スター・ウォーズ』となりますが、もし「氣」という字をあてていたら、興ざめであったはずです。たとえば、日本人にとって「フォース」は「元気」に最も近いですが、“May the force be with you(フォースと共にあらんことを)”という挨拶を「お元気で」と訳されたら、SF感が台無しですよね。今日はこの辺で。
2015.12.20
コメント(0)
-

荘子と進化論 その194。
『スターウォーズ フォースの覚醒』公開記念!今回はジェダイ(Jedi)と道教(Taoism)について。まずは『シスの復讐(Revenge of the Sith)』の最後のセリフから。Obi-Wan: I will take the child and watch over him.(私がその子を彼の元へ送り、見守りましょう。)Yoda: Until the time is right, disappear we will. [Senator Organa and Obi-Wan bow and start to leave] Master Kenobi, wait a moment. In your solitude on Tatooine, training, I have for you.(来るべき時が来るまで、我々は身を隠しておこう。マスター・ケノービ、ちと待ちなさい。タトゥイーンで一人きりのそなたに、ひとつ修練を授けよう。)Obi-Wan: Training?(修練ですか?)Yoda: An old friend has learned the path to immortality. One who has returned from the netherworld of the Force...(古い友人の中に「不死の道」について学んだ者がおる。その者はフォースの死の世界から戻ってこれたのじゃ。)ヨーダが「不死の道 "path to immortality"」と言っています。ここで対比していただきたいのが、アンリ・マスペロ(Henri Maspero / 馬伯楽 1883~1945)の『道教』という著作です。彼は20世紀前半のフランスの中国研究者で、西洋における道教研究の第一人者でした。激動の時代に積極的に現地の道士と交流し、「道蔵」所蔵の道教経典の研究に尽力した人物です。終戦間際の1945年3月に強制収容所で亡くなってしまいますが、その死後、彼の遺した資料から『中国の宗教と歴史に関する遺稿』が再編集されて1950年に発刊。この『遺稿』が、西洋における道教研究のスタンダードになります。≪古代の道教は何よりもまず信者を「永生」、あるいは中国語でいう「長生」、終わりのない「長い生命」に導くことを目指す宗教である。「永生」という言葉はほとんどキリスト教をおもわせるが、それとは全く異なった観念をひめている。実際、「不死」及び「永生」は、道教徒とキリスト教徒では、同じやり方では問題とされなかった。ギリシャ哲学につちかわれたキリスト教徒は、精神と物質とを二つの別々の実体と考える習慣がついている。すでにキリスト教以前から、死は物質におとずれずにすぎず、非物質的で、本質的に不死である精神は残存し続けるものであると認められていた。が、中国人はわわれわれのように精神と物質を決して区別しなかった。中国人にとっては、見えない、形のない状態から、見える、形のある状態へと移行するただ一つの実体があるにすぎない。人間は精神的な霊魂と物質的な肉体とからでできているのではない。それはことごとく物質的なものなのである。 (中略)あるいは道教の始祖たちは、死を圧服することによって、この不死をこの世で獲得できるという可能性を信じたのかもしれない。しかし、漢代では、道教徒はみたところそれほど奇跡的でない結果に甘んじていた。かれは生きているあいだに、不死性を賦与された一種の胚芽を自分のなかにはぐくもうと努めなければならなかった。この胚芽は形をとり、成長し、成熟すると、ちょうど蝉が殻からぬけだし、蛇が古い皮から抜け出すように、粗雑な身体を軽くて精妙な不死の身体に変える。この永生への誕生は俗世の死と全く同じであった。道教の信者は一見、死ぬようなふりをした。人々は普通の儀式に従って、かれを埋葬した。しかし死はみせかけにすぎなかった。墓の中に実際に置かれていたものは、かれが自分の肉体の姿を与えておいた剣であり、あるいは竹の杖であった。不死となった真の身体は、永生者〔仙人〕たちのあいだへ行って生きていたのである。これが身体(あるいは屍)の解放、「尸解」といわれたものであり、「尸解は擬死である」とも言われていた。 つぎの挿話はこの尸解がいかなるものであったかを示している。この話の出典は紀元後三世紀の書であって、これは武帝(B.C.140-87)とおそらくはそのほか数人の皇帝に関する一種の道教的な伝記であり、《漢禁中起居注》と題されている。 挿話の主人公、李少君は歴史上の人物で、錬金術師であり、同時代の司馬遷ものべている人物である。 李少君がたち去ろうとしたとき、武帝はかれと一しょに嵩山に登った夢をみた。中途で、竜に乗り、尊厳さのしるしを手に持った使者が、雲から下りてきて告げた。「『太一』の神は少君においでを願っています」と。皇帝は目ざめて、まわりの者に言った。『わたしがほんのいま見た夢によると、少君はまもなくわたしからはなれていくだろう」と。数日ののち、少君は病と称して死んだ。ずっとのにちなって、皇帝はその棺をあけるように命じた。ところがそのには身体はなく、衣服とかんむりしか残っていなかった。 《抱朴子》には、ほかにも同じような逸話をのせている。たとえば、ある道士とその二人の弟子が死んでから、家族がその棺を開かせた。そのいずれも朱文字のついた竹の枝がみつかった。三人ともみな身体から解放された、すなわち尸解したのである。 要するにそこには、道教の神話的創始者の一人である黄帝のように、白昼、竜に乗って昇天するという驚くべき奇蹟があったというわけではなくて、信者が死を克服することができた場合には、みせかけの死ののちに幸福な不死を享受するのだということの、信者に対する保証があったのである。≫(『道教』(東洋文庫刊 アンリ・マスペロ著 川勝義雄訳 「西暦初頭数世紀の道教に関する研究」より)これ、アンリ・マスペロの著作の導入部分からなんですが、Yoda: Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed that is.(死は生命の営みの一部なのじゃ。フォースへと変わる者を喜んで送り出せ。嘆いてはならぬ。寂しがってもならぬ。執着は嫉妬を生み、欲望の影が忍び寄るぞ。)「見えない、形のない状態から、見える、形のある状態へと移行するただ一つの実体があるにすぎない。」という表現は、「死」を「人がフォースへと変容すること」とするヨーダの言葉とも一致しますし、参照:Anakin and yodahttp://www.youtube.com/watch?v=c5xkI8uoZYE前掲の「不死の道 "path to immortality"」としての、オビ=ワン・ケノービの「尸解(剣解)」の技法、さらに、「不死となった真の身体は、永生者〔仙人〕たちのあいだへ行って生きていく」という表現も、スターウォーズでのジェダイの魂のあり方にぴったりと重なります。参照:尸解の世界。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5197/マスター・ヨーダと老荘思想 その2。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5026/『又按漢禁中起居註云、少君之將去也、武帝夢與之共登嵩高山、半道、有使者乘龍持節、從云中下。云太乙請少君。帝覺、以語左右曰、如我之夢、少君將舍我去矣。數日、而少君稱病死。久之、帝令人發其棺、無屍、唯衣冠在焉。按仙經云、上士舉形昇虚、謂之天仙。中士游於名山、謂之地仙。下士先死後蛻、謂之屍解仙。今少君必屍解者也、近世壺公將費長房去。及道士李意期將兩弟子去、皆託卒、死、家殯埋之。積數年、而長房來歸。又相識人見李意期將兩弟子皆在郫縣。其家各發棺視之、三棺遂有竹杖一枚、以丹書於枚、此皆屍解者也。』(『抱朴子』 論仙篇)→また『按漢禁中起居註』にいう。李少君がこの世から去ろうとするとき、武帝は夢を見た。少君と共に嵩高山に登り、道の途中で、龍に乗り杖を携えた使者が雲の合間から降りてきた。彼らは太乙が少君を呼んでいるという。武帝はそこで目覚め、左右にその夢の話をした。「もし私の夢の通りであるならば、少君はもうすぐ私の元から去るだろう」と。数日後、少君は病死したという。しばらくして、帝は使者に棺を開けさせてみると、少君の屍はなく、ただ衣冠のみがあった。また、『按仙經』によると、「上士は身体をそのままに虚空へと昇る。これを天仙という。中士は名山に遊ぶ、これを地仙という。下士は一度死んで蝉の抜け殻のような状態になる。これを屍解仙という」とある。そうすると、少君はきっと屍解者であったのだろう。最近の例でも壺公は費長房を連れ去っているし、道士・李意期は二名の弟子を連れ去っている。皆何かに仮託して死に、家人が殯をしてこれを埋めている。数年経ってから、長房は帰ってきたし、李意期と二名の弟子は四川で知人に会っている。家族が棺を開けてみると、三人の棺には、それぞれ竹の杖が一本ずつ入っていて、丹沙で名前が書かれていたという。これは皆、屍解者であったのだ。アンリ・マスペロの「遺稿」では、道教の説明をする場合に、他の思想、例えばギリシャ哲学の後継としてのキリスト教の思想やイスラム教との対比に重点が置かれます。身体と精神の関係や尸解について最初に触れるというのは、西洋人ならではの展開です。『抱朴子』にもあるように、「尸解仙」というのは、本来、天仙、地仙に続く下位の仙人のランクでして、映画で急に知名度が上がった「キョンシー」とかと一緒で、比較文化的論的には使いやすい素材ではあっても、道教の本質的な思想とは言い難いです。ここは、ジョージ・ルーカスがその影響を公言する、ジョゼフ・キャンベルともまた違ったアプローチであるところが興味深いです。道教研究におけるアンリ・マスペロの位置からすれば当然ではありますが、彼、もしくは彼の弟子の著作も『スターウォーズ』のネタ本のうちの一冊であろうと思います。参照:ジョゼフ・キャンベルと黄金の華の秘密。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005201/今日はこの辺で。
2015.12.06
コメント(0)
-

荘子と進化論 その193。
今日はまず、『今昔物語』での安倍晴明の記録から。≪師ニ代リテ太山府君ノ祭ノ都状ニ入リシ僧ノ語 第廿四今昔□、□ト云フ人有ケリ、□□ノ僧也、止事无キ人ニテ有ツレバ、公ケ私ニ被貴テ有ケル間、身ニ重キ病ヲ受テ惱ミ煩ケルニ、日員積テ病重ク成ヌレバ、止事无キ弟子共有テ、歎キ悲テ、旁々祈禱スト云ヘドモ、更ニ其驗无シ、而ル間、安倍晴明ト云フ陰陽師有ケリ、道ニ付テハ止事无カリケル者也、然レバ公ケ私此ヲ用タリケル、而ルニ其ノ晴明ヲ呼テ、太山府君ノ祭ト云フ事ヲ令、此ノ病ヲ助テ、命ヲ存ムト爲ルニ、晴明來テ云フ、此病ヲ占フニ、極テ重クシテ、譬ヒ太山府君ニ祈禱スト云ヘドモ、難叶カリナム、但シ此ノ病者ノ御代ニ、一人ノ僧ヲ出シ給へ、然バ其ノ人ノ名ヲ、祭ノ都状ニ註シテ、申代ヘ試ミム、不然バ更ニ力不及ヌ事也ト・・・(『今昔物語』巻第十九)≫参照:今昔物語集 巻第十九 代師入太山府君祭都状僧語 第二十四http://www.geocities.co.jp/HeartLand/1608/koten7.html・・・話をかいつまんで言うと、重い病に苦しむ僧侶がいて、病状が日に日に悪化しており、祈祷も効かない。そこで陰陽師・安倍晴明は、僧侶の病を治し、命を永らえさせるために「太山府君ノ祭」を執り行うこととした。しかし、晴明によると、僧の病があまりに重いため、たとえ「太山府君ノ祭」を行ったとしてもそれだけでは回復は難しく、弟子の一人を身代わりとして差し出し、都状にその名を書かねばならないという・・・というお話です。安倍晴明が活躍したのとほぼ同時期に書かれた医療書『医心方』もそうですが、この当時の日本は道教における呪術的な技法の影響が非常に強い時期でした。参照:『医心方』と道教 ~鏡の力~。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201411300000/ここに登場する「泰山(太山)府君(たいざんふくん)」という神様は、寿命を司る存在で、陰陽道の主祭神でもあります。日本では他にも、世阿弥の能に「泰山府君(たいざんぷくん)」という演目がありまして、こちらでも桜の寿命を伸ばす存在として演じられます。参照:能 泰山府君(たいさんぷくん) [部分] https://www.youtube.com/watch?v=ezMUUFwpFXkもちろん、「泰山」という山は日本にはなく、中国の東端、山東半島にあります。泰山(東)・衡山(南)・華山(西)・恒山(北)・嵩山(中)の五岳のうちの東岳にあたり、泰山府君も「東岳大帝(とうがくたいてい)」の異名を持ちます。泰山(東岳)は、漢の武帝の時代に本格化する「封禅(ほうぜん)」の儀式の舞台であり、天と地、生と死の狭間に位置する聖なる山です。日本で言うと富士山(不死山)に相応します。その神格化された存在が泰山府君(東岳大帝)であるわけですが、この神様は京都御所の鬼門であり、比叡山の裏鬼門に鎮座してこれを守護する赤山禅院(赤山大明神)でも祀られています。参照:Wikipedia 泰山https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%B0%E5%B1%B1次は三国志の時代のちょっと後、4世紀の『抱朴子』。『天地有司過之神、隨人所犯輕重、以奪其算、算減則人貧耗疾病、屢逢憂患、算盡則人死、諸應奪算者有數百事、不可具論。又言身中有三屍、三屍之為物、雖無形而實魂靈鬼神之屬也。欲使人早死、此屍當得作鬼、自放縱游行、享人祭酹。是以每到庚申之日、輒上天白司命、道人所為過失。又月晦之夜、竈神亦上天白人罪狀。大者奪紀。紀者、三百日也。小者奪算。算者、三日也。』(『抱朴子』 微旨 巻六)→(ある書物によると)「天地には過ちを司る神がいて、人のそばにいてその人の犯した罪の軽重によって寿命(算)を調整するという。減ずると貧しくなったり、病気になったり、悩み事が増えたりする。この「算」が尽きると人は死ぬ。」とある。 (中略)また、人の身体には三屍という虫がいる。実体があるようだが、その形はなく、「魂」や「霊」「鬼神」に属するものである。この虫は、宿主である人が死ねば自由になり、死者への供物も頂戴できるので、その人を早死にさせたいといつも考えている。庚申の日ごとに、この虫たちは天に昇り、運命を司る「司命」に、宿主である人の過失について報告をする。また、晦日(つごもり)の夜、竈神も天に人の罪狀について報告をする。罪の大なる者からは紀を奪う。紀というのは三百日のことである。小なる者からは算を奪う。算というのは三日のことである。これも日本では平安時代に始まり、現代にも脈々とつながる「庚申」の信仰についての記録ですが、天に昇った竈の神の報告を元に人間の寿命を奪う存在として「司命(しめい)」という名前が出てきます。生と死の運命を司る神で前掲の泰山府君ともよく似た神ですが、「司命」は屈原の『九歌』にも、『荘子』にも登場するため、その歴史は2500年を超えると思われます。参照:竈神と庚申(かのえさる)。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201409230000/「莊子之楚、見空髑髏。昂然有形。檄以馬捶、因而問之曰、「夫子貪生失理、而爲此乎。將子有亡國之事・斧鉞之誅、而爲此乎。將子有不善之行、愧遺父母妻子之醜、而爲此乎。將子有凍餒之患、而爲此乎。將子之春秋故及此乎。」於是語卒、援髑髏、枕而臥。夜半、髑髏見夢曰、「子之談者似弁士、視子所言、皆生人之累也。死則無此矣。子欲聞死之説乎。」莊子曰、「然。」髑髏曰、「死、無君於上、無臣於下。亦無四時之事、従然以天地為春秋。雖南面王樂、不能過也。」莊子不信曰、「吾使司命復生子形、為子骨肉肌膚、反子父母・妻子・間里知識、子欲之乎。」髑髏深顰蹙曰、「吾安能棄南面王樂而復爲人間之勞乎。」(『荘子』至楽 第十八)→荘子が楚の国に赴いたとき、空髑髏を見つけた。荘子は髑髏を打ちながら「あなたは生に執着して人の道を外したがために、こんな姿になったのか?それとも国を滅ぼして処刑されたのか?不善をなして、父母や妻子に汚名が及ばぬよう自ら命を断ったのか?衣食が足りずに飢え死にしたのか?寿命が尽きて死んだのか?」と質問を浴びせたかと思うと、おもむろに髑髏を抱き上げて、髑髏を枕に眠った。 その夜半、荘子の夢の中にくだんの髑髏が現れてこう答えた「お前の問いは、弁士と呼ばれる連中のそれに似ている。全て生きている人間だからこその悩みで、死んだ私にはすでに関わりのないことだ。死後の世界についてお前は知りたいか?」荘子「知りたいです。」髑髏「死後の世界には、上下の身分もない。四季の移り変わりもない。ゆったりと天地と時を共にするのみだ。この喜びは人の世の天子ですら味わえない至楽なのだ。」荘子は信じられないという表情で「もしあなたの骨肉や皮膚をかき集め、司命に頼んで肉体を蘇生し、魂を呼び戻し、あなたの家族やあなたの故郷へ送り届けることができるとしたら、あなたはそれを望みますか?」と尋ねると、夢の髑髏は顔をしかめてこう言った「どうしてこの至楽の世界を捨ててまで、ふたたび人の世の苦労など味わうだろうか。」『荘子』にも「司命」は登場します。夢の中で野ざらしのしゃれこうべに対し、荘子は身体の復元を司命に依頼して、蘇ることができたとしたら、という過程を示しています。これについてしゃれこうべは、明確に蘇生を拒否しています。今回例示した書物の中で、『荘子』という書物が最も古く、宗教的な権威も大きな書物です。にもかかわらず、この寓話は、宗教的迷妄から最も遠く、同時に現代にも通じる普遍的な命題が示唆されています。Supreme Chancellor: [looking a little frustrated] Did you ever hear the tragedy of Darth Plagueis "the wise"? (君は「賢者」ダース・プレイガスの悲劇を聞いたことがあるかね?)Anakin Skywalker: No. (いいえ。)Supreme Chancellor: I thought not. It's not a story the Jedi would tell you. It's a Sith legend. Darth Plagueis was a Dark Lord of the Sith who lived many years ago. He was so powerful and so wise that he could use the Force to influence the midichlorians to create life... He had such a knowledge of the dark side that he could even keep the ones he cared about from dying.(そうだろう、これはシスの伝説だ。ジェダイはこの話をしたがらないだろう。ダース・プレイガスは何年も前に実在した暗黒卿だ。彼は優れた力と智恵を備え、フォースを使ってミディクロリアンに働きかけ、生命を創造することすらできた。彼のダークサイドの知識は、目をかけた者を死から守ることすらできたという。)Anakin Skywalker: He could do that? He could actually save people from death? (そんなことができたのですか?実際に人を死から救うことが?)Supreme Chancellor: The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. (私が知る限り、フォースのダークサイドには、自然の摂理を越える多くの道がある。)Anakin Skywalker: What happened to him? (その彼に何が起きたのですか?)Supreme Chancellor: He became so powerful... the only thing he was afraid of was losing his power, which eventually, of course, he did. Unfortunately, he taught his apprentice everything he knew, and then one night, his apprentice killed him in his sleep. It's ironic that he could save others from death, but not himself. (さらに強大な力を得たダース・プレイガスは、その力を失うこと以外に恐れるものはなくなった。彼は彼の持つ全ての知識を弟子に教えたが、不幸なことに、その弟子は、師が眠っている間に師を殺してしまった。ダース・プレイガスは他人を死から救うこともできたが、彼自身の死からは避けられなかった。皮肉なことだ。)Anakin Skywalker: Is it possible to learn this power? (その力を学ぶことはできるのでしょうか?)Supreme Chancellor: Not from a Jedi. (ジェダイ側では無理だろう。)参照:Star Wars Opera Scene Dark Forces https://www.youtube.com/watch?v=HLfGh2b_me0今日はこの辺で。
2015.11.23
コメント(0)
-

田母神論文を継ぐ男。
幸福実現党の広告塔、みんなのタモさんについて。 いつの間にか、タモさんが「次世代の党」の副代表になったり、選挙に負けた後に業務上横領事件があったり、チャンネル桜の水島社長に告訴されそうになったりと、不穏な動きが見られますが、そんな中でも皆さん何かを取り戻そうとがんばっておいでのようです。しかし、もう3年も過ぎていますが具体的に「何が」戻ってきたか誰も教えてくれません。さて、今年もアパ日本再興財団主催、真の近現代史観の論文の発表の季節です!第8回の最優秀藤誠志賞は、アメリカの弁護士でタレントの、ケント・ギルバートさんに決まりました!!タイトルは、「日本人の国民性が外交・国防に及ぼす悪影響について」!今回の受賞者は他に、優秀賞(社会人部門)中村敏幸優秀賞(学生部門)小野寺崇良佳 作 青柳武彦、大石英樹、呉亮錫、杉田水脈、辻本貴一、針原崇志、松木國俊、山口富士夫、山下英次、ロバート・D・エルドリッヂというメンバーだったそうです。外国人の受賞が目立ちますね。ま、正直な話、「アメリカ国籍」で、「モルモン教徒」のケント・ギルバートさんに、歴史観で遅れを取るような日本人は、上記の受賞者も含めて、即刻!腹を切って死ぬべきだと思います♪♪参照:第8回 「真の近現代史観」受賞者発表http://ronbun.apa.co.jp/winner/index.htmlWikipedia ケント・ギルバートhttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%AE%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%88今回も、「虎ノ門ニュース 8時入り」というネット番組で、タモさんとお仕事を一緒にするケント・ギルバートさんが受賞!タモさんに身近な人が次々と300万!なんという偶然!参照:タモさんと愛人。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/20121110/ 今回の「日本人の国民性が外交・国防に及ぼす悪影響について」の前半は、この2,3年でいきなりオモシロ論壇に転向されたケント・ギルバートさんの著書そのままの主張です。サッカーの試合の終了後にごみ拾いをする青年たちや、震災直後の被災者の様子などから日本人の精神性の高さを称えたうえで、その精神性を軍事・外交面では捨てるべきであると説きます。注目すべきは、その後の展開でして、後半部分の論点は、ほぼタモさんの論文といっしょです。個人の資質なのか、国民性なのか、モルモン教の教えか何かは知りませんが、300万円も貰うわりには、注釈や出典もない不親切な「論文(笑)」なので、参考のため、タモさんの「論文(笑)」と対比しておきます。論点1.「張作霖爆殺」【田母神論文(笑)】1928 年の張作霖列車爆破事件も関東軍の仕業であると長い間言われてきたが、近年ではソ連情報機関の資料が発掘され、少なくとも日本軍がやったとは断定できなくなった。「マオ(誰も知らなかった毛沢東)(ユン・チアン、講談社)」、「黄文雄の大東亜戦争肯定論(黄文雄、ワック出版)」及び「日本よ、「歴史力」を磨け(櫻井よしこ編、文藝春秋)」などによると、最近ではコミンテルンの仕業という説が極めて有力になってきている。日中戦争の開始直前の 1937 年 7 月 7 日の廬溝橋事件についても、これまで日本の中国侵略の証みたいに言われてきた。しかし今では、東京裁判の最中に中国共産党の劉少奇が西側の記者との記者会見で「廬溝橋の仕掛け人は中国共産党で、現地指揮官はこの俺だった」と証言していたことがわかっている「大東亜解放戦争(岩間弘、岩間書店)」。【ケント・ギルバート論文(笑)】日本側で行われたソ連の謀略としては、1928年の「張作霖爆殺事件」が、実は関東軍の犯行に見せかけたソ連特務機関による犯行だったという新説が非常に興味深い。残念ながら私はロシア語の一次資料を読めないので、さらなる研究の発展に期待したい。⇒タモさんは黄文雄(笑)、櫻井よしこ(笑)などの主張からコミンテルン説。⇒ケント・ギルバートさんはロシア人、ドミトリー・プロホロフ氏の主張に興味あり。参照: APAグループ アップルタウン 特別対談| 中国牽制という共通目的のために日本とロシアは手を携えるべきだ http://smtp.apahotel.com/appletown/pdf/taidan/1003taidan.htmlアパグループの企画による、タモさんとプロホロフ氏の対談はこちら。 論点2.「ヴェノナファイル」【田母神論文(笑)】ヴェノナファイルというアメリカの公式文書がある。米国国家安全保障局(NSA)のホームページに載っている。膨大な文書であるが、月刊正論平成 18 年 5 月号に青山学院大学の福井助教授 (当時 )が内容をかいつまんで紹介してくれている。ヴェノナファイルとは、コミンテルンとアメリカにいたエージェントとの交信記録をまとめたものである。(中略)これによれば 1933 年に生まれたアメリカのフランクリン・ルーズベルト政権の中には 3 百人のコミンテルンのスパイがいたという。その中で昇りつめたのは財務省ナンバー2の財務次官ハリー・ホワイトであった。【ケント・ギルバート論文(笑)】冷戦集結後の1995年、「ベノナ」と呼ばれるソ連暗号解読プロジェクトが機密扱いを解除され、戦時中を含むソ連の暗号通信の内容が明らかになった。その結果、ソ連のスパイ行為は、マッカーシーが見積もったよりも、さらに大きな規模で行われていたことが判明した。米国だけでなく、日本政府や軍隊の中枢にも、ソ連のスパイはたくさん紛れ込んでいた。⇒ほぼいっしょ。論点3.「ハリー・ホワイト」【田母神論文(笑)】ハリー・ホワイトは日本に対する最後通牒ハル・ノートを書いた張本人であると言われている。彼はルーズベルト大統領の親友であるモーゲンソー財務長官を通じてルーズベルト大統領を動かし、我が国を日米戦争に追い込んでいく。当時ルーズベルトは共産主義の恐ろしさを認識していなかった。【ケント・ギルバート論文(笑)】さらに言えば、「ハル・ノート」の原案を書いたハリー・ホワイト財務次官補は、ソ連のコミンテルンと通じたスパイだった。戦後、その事実が判明すると、彼は身柄を拘束される前に自殺した。⇒ほぼいっしょ。論点4.「フライング・タイガース」【田母神論文(笑)】当時ルーズベルトは共産主義の恐ろしさを認識していなかった。彼はハリー・ホワイトらを通じてコミンテルンの工作を受け、戦闘機 100 機からなるフライングタイガースを派遣するなど、日本と戦う蒋介石を、陰で強力に支援していた。真珠湾攻撃に先立つ1ヶ月半も前から中国大陸においてアメリカは日本に対し、隠密に航空攻撃を開始していたのである。【ケント・ギルバート論文(笑)】真珠湾攻撃は昭和20年12月7日朝(ハワイ時間)に行われたが、米国は同年7月に日本の在米資産凍結令を出し、8月には石油の対日全面禁輸を行った。一方でルーズベルト大統領は、「援蒋ルート」を通じた中華民国への支援を継続している。加えて、「フライング・タイガーズ」と呼ばれた秘密航空部隊を承認し、退役軍人による「義勇軍」に偽装して、日米開戦以前にアジア地域へと送り込んでいる。⇒ほぼいっしょ。論点5.日米開戦の罠【田母神論文(笑)】しかしこれも今では、日本を戦争に引きずり込むために、アメリカによって慎重に仕掛けられた罠であったことが判明している。実はアメリカもコミンテルンに動かされていた。(中略)ルーズベルトは戦争をしないという公約で大統領になったため、日米戦争を開始するにはどうしても見かけ上日本に第 1 撃を引かせる必要があった。日本はルーズベルトの仕掛けた罠にはまり真珠湾攻撃を決行することになる。【ケント・ギルバート論文(笑)】ルーズベルト大統領は、日本との和平交渉を行うつもりなど最初から無かった。第二次世界大戦に参戦するために、日本に先制攻撃させることだけを考えていた。了承できるはずのない内容を含む「ハル・ノート」を突きつければ、誇り高き日本人は、和平交渉のテーブルから離れて、先制攻撃をするはずだと作戦を立てた。そして全ては、彼のシナリオ通りに運んだ。(中略)近衛文麿内閣の周辺には、たくさんの共産主義者がいたし、近衛首相自身が共産主義者だったとの説もある。結局、日米両国とも、スターリンの大規模な謀略に見事に操られて、お互いに不必要な戦争を戦った可能性が高い。⇒タモさんも、ケント・ギルバートさんも、アメリカの罠を主張しながら、本当の黒幕は共産党!というオチ。しかし、今改めて読んでも、「これも今では、日本を戦争に引きずり込むために、アメリカによって慎重に仕掛けられた罠であったことが判明している。実はアメリカもコミンテルンに動かされていた。」というのは名文です。アメリカも日本もコミンテルンにはめられてました、という驚愕の展開。先人の知性をここまで貶めた航空幕僚長は、今後もタモさんの他にはでてこないでしょう。・・・後段のケント・ギルバート論文(笑)では、近衛文麿は共産党員という趣旨の記載があります。これは、かの中川八洋先生の理論を彷彿とさせますね。気に入らないヤツは全員共産党!さすがは渡部昇一人脈!ほとばしる知性!参照:あるいは共産主義者でいっぱいの日本 ―中川八洋『近衛文麿の戦争責任』(1)―http://www.geocities.jp/yu77799/Comintern/nakagawa1.htmlタモさんブームによって一時は脚光を浴びたコミンテルンでしたが、最近では統一教会の犬ども以外、だれもその存在について語らなくなりました。しかし、輝けるタモさんの受賞から七年。ついにタモさんの志を継ぐ男が現れました!まだまだキャラが立っていませんが、これからに期待しましょう。参照:「日本は侵略国家であったのか」http://ronbun.apa.co.jp/announce/index.html#01今日はこの辺で。
2015.10.25
コメント(2)
-
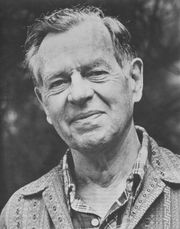
荘子と進化論 その192。
今日はジョゼフ・キャンベル(Joseph Campbell 1904~1987)について、もう少し。角川で『時を越える神話』『生きるよすがとしての神話』『野に雁の飛ぶとき』という講義録があるんですが、このうちの『時を越える神話』から。≪ブッダは地上に座っている。それは瞑想によって、自分の意識と仏性(あらゆる生物に宿っている超絶的な意識)とが合一であることを意味しています。 鈴木大拙(一八七〇 ― 一九六六)の著述のなかに、すばらしい話がありました。ある若い学僧が老師に向かって、「私にも仏性というものがございましょうか」と質問したところ、老師が「ないな」と答える。学僧は、「でも万物には仏性が宿っていると教えられました。石にも、木にも、蝶にも、蜂にも、鳥にも、けものにも。ありとあらゆる生き物に」と言う。そこで老師のいわく――「さよう、お前の言うとおり。万物には仏性が宿っておる。石にも木にも、蝶にも蜂にも、鳥にもけものにも。生きとし生けるものに。だがお前にはない」。「私にはない?いったいどうして?」「おまえがそんな問いを発するからだ。」(ジョゼフ・キャンベル著『時を越える神話(Transformations of Myth Through Time)』より 第六章 仏教-正覚への道≫ ・・・これは、『無門関』の趙州狗子という代表的な公案から。仏性を説明している部分です。『一 趙州狗子 趙州和尚、因僧問、狗子還有佛性也無。州云、無。』(『無門関』 一 趙州狗子)→ある僧が趙州和尚に「狗子にも佛性があるのでしょうか、無いのでしょうか?」と質問した。州は言った。「無」。参照:Wikipedia 仏性https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%8F%E6%80%A7ジョゼフ・キャンベルは、C・Gユングの影響が非常に大きいので、鈴木大拙の名も当然のごとく出てきます。参照:ユングと鈴木大拙。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5095/≪短い紹介を終わって、私たちも始めてみましょう。最初は瞑想です。これ(図七-1)は楽な姿勢と考えられています。背筋をまっすぐにして座らなければなりません。人間の体と宇宙の体は対等だと考えられていますから、私たちの背骨は世界の中軸ともいうべきものです。そこで私たちは世界の中軸に、中心点に、不動地に達した。そしていま瞑想に入っているのです。 人はまず呼吸のコントロールから始めます。(中略)その基礎に、感情、情緒、そして精神状態はみな呼吸に関係しているという考えがあります。あなたが休んでいるときには、呼吸は平穏なよい状態に保たれている。なにかのショックで心が動かされると、呼吸が乱れる。情念に駆られても呼吸は乱れる。逆に、呼吸を変えれば精神状態も変わる。ゆっくりと呼吸することによって、池のさざ波を静めようとするわけです。座禅僧たちの一呼吸の長さときたら驚くべきものです。修行を積んだヨーガ行者は大変な肺活量の持ち主です。 こうして私たちは波を静める。水面が静まると、分断されていたもののイメージが現れ、私たちに見えてくる。そこが肝心な点です。ここに粗野な外面的肉体があり、その手は霊妙体の象徴を支え持っています(図七-2)。この粗野な集塊(人間の体)と霊妙体とを混同してはなりません。そんなことをしたら、あなたは精神異常者となり、自分が「それ」だと信じ込んでしまします。私たちは両者を区別しなければなりません。(同上 第七章 クンダリーニ・ヨーガ(その一)--東洋人の意識と神概念)≫上記文章の下線部分を合わせて読むと、『スターウォーズ』でのヨーダのセリフに非常によく似てきます。Yoda:“For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us, and binds us. Luminous being are we, not this crude matter. You must feel the Force around you. Here, between you, me,the tree...the rock...everywhere.!!Yes...even between the land and the ship.”→ 私にはフォースという心強い味方がついておる。生命がそれを生み出し、育む。その偉大なる力は我々の周囲に満ち満ちて我々を結びつけておる。ワシらは光の存在なのじゃ、粗野な肉の塊の話ではないぞ。お主は、お主を取り巻くフォースを感じねばならぬ。ここにも、ワシとお主の間にも・・あの木々にも、岩にも・・そう、あらゆる場所にな!そして、この大地とあの戦闘機との間にも。参照:マスター・ヨーダと老荘思想 その1。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5025/『スターウォーズ』の「フォース(Force)」は、「道(tao)」か「氣(qi)」が最も親和性の高い言葉でしょうが、こう見るだけでも、ユング→ジョゼフ・キャンベル→ジョージ・ルーカスという思想の潮流がよく分かるのではないかと思います。 上記講義録において、ジョゼフ・キャンベルが「図」として例示していたのはこれです。リヒャルト・ヴィルヘルムとユングの共著『黄金の華の秘密』の挿絵。本来は道教経典で、『太乙金華宗旨』といいます。参照:『黄金の華の秘密』と『夜船閑話』。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5146/ 『凡人以意生身、身不止七尺者為身也。蓋身中有魄焉、魄附識而用、識依魄而生。魄陰也、識之體也、識不斷、則生生世世、魄之變形易質無已也。惟有魂、神之所藏也。魂晝寓於目、夜舍於肝、寓目而視、舍肝而夢、夢者神游也、九天九地、剎那歷遍。覺則冥冥焉、淵淵焉、拘於形也、即拘於魄也。故回光所以煉魂、即所以保神、即所以制魄、即所以斷識。古人出世法、煉盡陰滓、以返純乾、不過消魄全魂耳。』(『太乙金華宗旨』第二章 元神、識神)→凡そ人の身体は意を以って生じ、身体は七尺の存在にとどまらないものである。というのも、身体には「魄(はく)」があり、魄は識に従い、識もまた魄によって生じる。魄は陰であり、識が実体化したのもである。識が断たれないうちは、次々と世を経て生まれ続ける。魄はその姿形を絶えず変えてやむことがない。ただ、「魂(こん)」もまたあり、その内に精神を宿している。魂は日中には眼の中に隠れ、夜は肝臓の中に巣くう。眼の中にいるうちは魂も外界を見ており、肝臓にいるときは魂も夢を見る。夢とは精神の漂泊であり、九天九地を巡る旅も、刹那のうちにこれを夢見る。目が覚めている間でも、鬱屈してふさぎ込んでいるような者は、その形(身体)に拘っているのである。すなわち「魄(はく)」に捕らわれているのだ。故に回光とは魂を収斂する行いであり、精神を保ち魄を制し、識そのものからも解き放たれるのだ。古の人がこの世界から去る場合には、陰の滓(かす)を昇華して、純然たる陽へと還る技法であり、魄を消して魂のみの存在になることに他ならない。≪(1)「魂」Hun これは「陽」の原理に属する者であるから、私はこれをアニムスと訳した。(2)「魄」Po これは、「陰」の原理に属し、アニマと訳される。この両者はもともと、死の過程についての観察からきた表象である。したがって、両者はもともとデモン、すなわち死者(鬼)を示す共通の字形を含んでいる。(中略)アニムスは両眼の中に住み、アニマは下腹部に住む。アニムスは明るくて活動的であり、アニマは暗くて大地に結びつけられている。「魂」、アニムスに対応する文字は「鬼」と「雲」を示す文字から構成されており、「魄」、アニマに対応する文字は「鬼」と「白」からつくられている。「魄」についてのこのような概念には、中国以外のどこか他の場所でも、例えば影のたましいとか肉体のたましいというような形で、類似したとらえ方が見出せると思われる。(以上『黄金の華の秘密』ヴィルヘルムの解説 湯浅泰雄・定方昭夫訳より))≫参照:太陽と月、男と女の錬金術。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5148/この『黄金の華の秘密』に見られる、道教の「魂魄」と「陰陽」の思想は、身体が消失したり、光に似た性質のまま生者を見守ったりするジェダイの死後のあり方を、ほぼそのまま説明できます。参照:尸解の世界。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005197/『又不可墮於蘊界、所謂蘊界者、乃五陰魔用事。如一般入定、而稿木死灰之意多、大地陽春之意少。此則落於陰界、其氣冷、其息沉、且有許多寒衰景象、久之便墮木石。又不可隨於萬緣、如一入靜、而無端眾緒忽至、欲卻之不能、隨之反覺順適、此名主為奴役、久之落於色欲界。』(『太乙金華宗旨』 第五章 回光差謬)→また蘊界(うんかい)に堕ちてはならない。いわゆる蘊界とは、五陰魔の事を用いられる世界である。精神が定まったとき、木が枯れたり、冷めた灰になったような生気のない感覚となることが多く、春の大地に日が落ちるような感覚になることが少ない。そうすると、陰の世界に落ちやすい時期でもある。その氣は冷たく、その息は重苦しい。さらには数多の「寒」「衰」の景色が見え、木石のような感覚に捕らわれる。同時に外界の世界のしがらみに縛られてもならない。一度心に静かになったと思った矢先に、ありとららゆる妄想がとめどなく吹き出してしまい、どうにもならない状態に陥る場合がある。この場合には、無理に止めずに流れるに任せた方が落ち着きやすい。主客が逆転した状態が長く続くと色欲界に落ちることになる。参照:Evil Cave - Empire Strikes Back [1080p HD] https://www.youtube.com/watch?v=iwhx2gZ5fBEもちろん、ダークサイドも。今日はこの辺で。
2015.10.13
コメント(0)
-
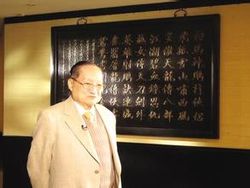
荘子と進化論 その191。
※今回は多くのネタバレを含みます。金庸の続き。参照:金庸と荘子 ~屠龍と碧血~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005199/≪周伯通(しゅうはくつう)はそういってすぐに郭靖(かくせい)に手を出してきた。二人がやっと数手合わせた時、突然周伯通の掌から力が抜け、郭靖は力の持っていきようがなく、倒れそうになったとこで左手で払われて、体は宙でもんどりをうち、左肩からどっと地に落ちた。肩に激痛が走る。周伯通はいかにもすまなそうに言った。「悪いなあ、けどただではころばせへんで。今の手を説明したるさかいよう聞きや」 郭靖は痛みをこらえて起き上がると、周伯通の方に近寄った。「ええか、『老子』という本に、こないなことが書いてあるそうや。土をこねて器を作るんは、なんもないところに器の用がある、戸や窓を穿って部屋を作るんでもなんでもないところに部屋の用がある、と言うんや。どや分かるか?」 郭靖は首を横に振った。周伯通は今しがた飯を盛ったお椀を手にもつと、こう言った。「この椀は真ん中が空やさかい飯がもれる。もし空やなかったら、どうやって飯を盛るねん?そやろ」 郭靖はうなづいた。言われてみれば簡単なことだが、そんなことを考えたことがなかった。「部屋や窓や門かて同じや。空やから人が入って住める、そやなかったら屁の役にも立たん」 そう言われてさすがの郭靖もなんとなく分かったような気になった。「全真教の最高の武功の要旨は、空と柔の二字にある。お前の師匠洪七公(こうしちこう)の武術は実と剛を旨とする外家武功の最高峰やろ、けど外家武功はあそこまで行けばもう終わりや、あれ以上はない。しかし全真教の内家武功には終わりっちゅうもんがないねん。わいみたいなんはまだ初歩やが、わいの兄貴の王真人が武功天下一になったんは運がよかったんとちがう、もし兄貴がまだ生きておったら、七日七晩闘わんでも、半日でやつらは降参してもうたやろな」(徳間文庫 金庸著・岡崎由美監修・金海南訳 『射雕英雄伝 第三巻』第十七章「両手の戦い」より)≫主人公・郭靖(かくせい)が周伯通(しゅうはくつう)という人物の教えを受けているシーン。周伯通は、老頑童の異名のとおり童顔であるだけでなく、子供のような性格でコミカルなキャラクターですが、ここでは真剣に『老子』の引用をして「空明拳」という武術の説明をしています。内容はブルース・リーと同じ、日本の武道においても相通じる思想です。参照:ブルース・リーと東洋の思想 その1。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5180/≪「そうか、おまえは知らぬのか、ほう、そうか。おまえの師匠たちが話しておらぬのならば、聞くにはおよばぬ。まあそのうち分かることだ。こうしよう。わしはおまえが気に入った。これもなにかの縁だろう。武術はだめだが、おまえに息の吸い方と眠り方、それにすわり方、立ち方を教えてやろう。」 (息の吸い方と眠り方?そんなものは赤ん坊にでもできる。そんなことを教わりに、命がけでこの崖を登ってきたのか) 郭靖はそう思ったが口には出さなかった。男は、「おまえ、あっちの石の上の雪をはらってその上に寝てみよ」 と言った。郭靖はしぶしぶ言われたとおり石の上に横たわった。「まあ、そんな寝方なら、なにもわざわざ教えるまでもあるまいな。よいか、これを覚えよ」 そう言うと、男は朗々と声をあげた。「思い定まれば、情は忘る。体虚なれば、気は運(めぐ)る。心死すれば、神(しん)は活きる。陽盛んなれば、陰は消える」 郭靖はそのとおり唱えて、しっかりと心に刻んだ。しかし意味はなんのことか分からない。「寝る前には、必ず頭の中を空っぽにして澄んだ状態にせよ、ほんの少しのことも考えてはならぬ。それから横向きに体を少し丸めて寝る、鼻でゆっくりと息をする。心の中を乱さず、外へ気が散らぬようにな」 そう言って、男は呼吸の仕方と正座して心を統一する方法を細かに説明した。郭靖がそのとおりにやってみると、はじめは体がむずむずして落ち着かなかったが、だが教わった呼吸法をやるうちに、だんだんと心が鎮まり、へその下の丹田の部分が暖かくなってきた。崖の上では肌を刺す寒風が吹いていたが、それもさして気にならない。そのまま一時もじっとよこになっていると、にわかに手足がしびれるような感覚を覚えた。郭靖の向かいにすわっていた男は、目を開けて、「よし、眠ってしまえ」と言った。郭靖はそのまま眠りにつき、目が覚めるともはや朝であった。(中略)男はなにも教えてくれなかったが、不思議なことにそれからというもの、郭靖の武術の腕はめきめきと上達した。半年も経つと、昼間の練習の時の身のこなしが軽くなり、それまでどうしてもできなかった技が簡単にできるようになったのである。江南六怪がみなよろこんだことは言うまでもない。(同上『射雕英雄伝 第一巻』第五章「白雕」より)≫ こちらは、「内功」と「軽功」の極意を伝授されているというシーンです。教えているのは、全真教の馬丹陽という人物。全真七子の最年長で形式上の全真教の教主という立場にいました。参照:金庸と荘子 ~丘処機と養生~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5198/ちょうど、ジェダイ評議会における、マスター・ヨーダと同じ位置です。技や外形を鍛える外功ではなく、精神を安定させ「氣功」の本質の体得を要する、内功を教えるというというところも同じです。上記馬丹陽、周伯通に、洪七公(こうしちこう)を加えると、ほぼ「帝国の逆襲」におけるヨーダ像ができあがります。参照:マスター・ヨーダと老荘思想 その1。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5025/全真教団は他の道教教団と比しても、内丹、いわゆる瞑想を重要視する集団でして、アクションシーンの多い「射雕三部作」においても、当然のようにその実践や理論が展開されています。「ジェダイの騎士」のモデルとして日本の武士やテンプル騎士団を挙げるのが一般的ですが、私は、金庸の武侠小説における道士こそがジェダイの、全真七子はジェダイ評議会のモデルであると思っています。ちなみに映画『スター・ウォーズ』の第一作「新たなる希望」が公開された1977年当時、金庸はすでに断筆をしています。 「気功」とフォースの用法や理論、アクションの形式のみならず、親から子へ、子から孫へと続く血統と師弟関係における縦軸が大きなテーマとなるため、武侠とスター・ウォーズにはもともと共通の構造が見られます。特に「射雕三部作(the Condor Trilogy)」と「スター・ウォーズ三部作(Star Wars trilogy )」には、物語の展開やキャラクターの設定などにも共通点が見られます。たとえば、2作目の『神雕侠侶』の主人公を「楊過(ようか)」といいます。父親が人の道を踏み外して半ば自滅して死んでしまったため、父の轍を踏まないように「過ちては則ち改むるに憚るなかれ」という『論語』の言葉から「過」の文字がとられました。彼は、父親の義兄弟であり好敵手であった「叔父さん」、郭靖の後見のもとで成長します。楊過は自分の父親がどういった人物であったかということも知らされず、知った直後に身体の一部を失ってしまいます。その後、妹と慕う女性を助け出すため、強大なモンゴル帝国と対立することになります。これ、ルーク・スカイウォーカーそっくりです。一作目の『射雕』にも父と子の物語があります。≪完顔康(わんやんこう)は床に倒れた母を抱き起した。王妃はしばらくして気をとりもどした。「母上、わたしはあなたの本当の子ですか?」完顔康は母の目を見た。「なにをやぶからぼうに言うのです」「ならばどうしてわたしに隠しごとをするのです?」王妃はだまってうつむいた。(この子に本当のことを言わなければならない。だれが本当の父親なのかを・・・。わたしはもはや汚れた体、あの人とはもういっしょになれない、でもこの子はちがう、この子は父といっしょに暮らせる・・・・)彼女の目から涙がぽとりと落ちた。完顔康は母親のただならぬ様子に息を呑んだ。「ここにおすわり、話があります。」言われるままに完顔康は椅子にすわった。手にはまだ槍を握り、目は母親を見つめたままである。「おまえ、この字を読んでごらんなさい。」包惜弱(ほうせきじゃく)は槍の柄の上の文字を示した。「子供のころもおたずねしましたが、この楊鉄心(ようてっしん)がだれなのか、おしえていただけませんでした」箪笥の中で母子の会話を聞く楊鉄心は心臓が張り裂けそうである。「この槍はもともと江南の大宋国、杭州のはずれの牛家村にあったものを、わたしがはるばる取り寄せさせたのです。あの鋤もこの椅子もすべて・・・・」「ずっと不思議でした。母上はどうしてこんな粗末なところに住んでおられるのですか?わたしが新しい家具を持ってこようとしても、いつも要らないとおっしゃっていました」「ここを粗末とお言いですか?わたしはどんな豪華な部屋よりもここが良いのです。あなたは不幸にも、父と母とともにここに住むことができませんでした」楊鉄心の頬に涙がつたった。「母上、なにをおっしゃるのです?父上がこんなところに住まわれるはずがないでしょう」そう言って完顔康は笑った。「かわいそうに、父上は十八年もの間、ここに帰りたくとも帰れなかったのです」「なんのことです!?」「おまえ、本当の父がだれか、知っていますか?」(同上『射雕英雄伝 第二巻』第九章「再会」より)≫細かくはいずれ。今日はこの辺で。
2015.09.22
コメント(0)
-
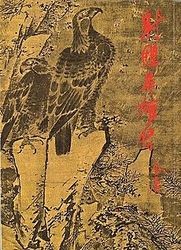
荘子と進化論 その190。
『射雕英雄伝(しゃちょうえいゆうでん))』の続き。参照:金庸と荘子 ~丘処機と養生~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005198/まずは、武侠の中で多用される用語について。●内功 いわゆる気功。意念や呼吸・血流など、身体の内部機能を修練し、体内の「気」が生み出す内力を自在に操る技。攻撃・防御・治療などに用いられる。全ての武術の基本であり、徒手・器械を問わず、各種技術の裏打ちとなる存在。一般に「○○功」と称されるのはこの内功の鍛錬法である。●外功 いわゆる武術。皮膚や筋肉を鍛え上げるほか、型や技法の修練もこれに属する。●点穴 特定の経穴(ツボ、穴道)を衝いて、内息の循環を遮断する技。経穴の位置によって、動きや各種の身体機能が封じられ、死に至ることもある。止血や毒が回るのを防ぐ作用もあるため、治療にも用いられる。機能を回復させる場合は、ふたたび経穴を衝くか、みずから内息をめぐらせて、徐々に解除することもできる。●軽功 身ごなしを軽くする技。軽身功ともいう。武侠小説では、軽功を得意とする武芸者は、常人の何倍もの速さで疾駆したり、身軽に宙を飛んだりする。(以上、徳間文庫『神雕英雄伝』(岡崎由美監修・金海南訳)「武侠小説基本用語解説」より。)西洋のファンタジーにおける「魔法」のような形で「気功」が使われています。 日本で言うと『北斗の拳(1983~1988)』や『ドラゴンボール(1984~1995)』の世界に使用されているものです。 特に『北斗の拳』の秘孔は、武侠小説の点穴から着想を得ているというのは明らかです。もともとの医療行為としての鍼灸術と武術の関係性から導き出されるものです。武侠小説における点穴は、他の作家の作品に登場しても全く問題のない、共通のツールであり、お約束事なんですが、日本では『北斗の拳』の知名度が高すぎたために独占してしまって、後続がほとんどありませんね。 『射雕英雄伝』のあらすじを「親子三代に渡る物語の二代目で、ちょっと間が抜けてはいるが、純朴な少年の成長物語。主人公は、強烈な個性を有する多くの優れた師に恵まれ、その素質も相俟って当代随一の武侠となる。」「武功天下一を決定する「華山論剣」とバラバラになった幻の経典「九陰真経」を求める旅とがパラレルに進行する。」「妻の父も有名な武侠、妻も優れた武芸者だが、結婚以降、妻の性格が豹変しファンが激減する。」ということもできますが、そうすると『ドラゴンボール』そっくりです。他にも、『北斗の拳』においてラオウとの戦いでリュウケンが見せた「北斗七星点心」という、北斗七星の陣形を描く技などは、『射雕英雄伝』で全真七子の奥義「天罡北斗陣(てんこうほくとじん)」が元ネタであると言っていいと思います。参照:百度百科 天罡北斗陣http://baike.baidu.com/view/146240.htm参照:四方拝と北斗七星。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005172/金庸の作品は、日本では1990年代に入ってようやく翻訳され始めましたが、香港では1958年には映像化が始まっていました。ブルース・リーやジャッキー・チェンの作品との関連で、「ファンタジックなカンフー」として受け入れられるようになったのだろうと思います。The Brave Archer 射雕英雄傳 (1977) **Official Trailer** by Shaw Brothershttps://www.youtube.com/watch?v=r_DbcyCVQLI本来、武侠小説は大衆小説であり、娯楽作品です。同時にこのジャンルは老荘思想、特に『荘子』の影響が強いです。たとえば、武侠の舞台となる「江湖」は荘子によく登場する地名です。金庸の作品は、武侠の中国文化における立場を強く意識していまして、多くの『荘子』の引用があります。●江湖 本来は「官」に対する隠者の隠棲する場所、また「野」つまり民間の象徴。武侠小説では、主に侠客や武芸者、盗賊などの世界をいう。(同上)『孔子曰「丘、天之戮民也。雖然、吾與汝共之。」子貢曰「敢問其方。」孔子曰「魚相造乎水、人相造乎道。相造乎水者、穿池而養給。相造乎道者、無事而生定。故曰「魚相忘乎江湖、人相忘乎道術。」子貢曰「敢問畸人。」曰「畸人者、畸於人而牟於天。故曰「天之小人、人之君子。人之君子、天之小人也。」」』(『荘子』大宗師 第六)→孔子曰く「礼を重んじる私は、礼節に縛られた天の罪人だよ。しかし、私とお前も彼らと共にできる道もある。」子貢曰「それはどの道なのですか?」孔子曰「魚は水に生き、人は道に生きる。水に生きるものは池を掘り下げると滋養にありつけ、道に生きるものは、平穏な生活に安定を取り戻す。故にこんな言葉がある「魚は江湖に水を忘れ、人は道術に道(Tao)を忘れる。」子貢曰く「敢えて畸人についてお伺いします。」曰く「畸人とは、天においてはそうでなくとも、人の世にあっては変わり者の連中だ。故にこんな言葉かある。「天の小人は人の君子、人の君子は天の小人」と。」 他にも射雕三部作の三作目『倚天屠龍記(いてんとりゅうき)』の「屠龍」、『碧血剣(へきけつけん)』の「碧血」というタイトルも、それぞれ『荘子』からです。『朱泙漫學屠龍於支離益、單千金之家、三年技成、而無所用其巧。聖人以必不必,故無兵、衆人以不必必之、故多兵。順於兵、故行有求。兵、持之則亡。』(『荘子』列禦寇 第三十二)→朱泙漫は支離益に龍を屠ふる技を学び、千金の財と三年の月日を費やしてその技を習得したが、結局、使うことはなかった。死を恐れない聖人は窮地においても、窮地としないから内に敵意がなく、死を恐れる世俗の人間は、窮地でなくても窮地にしてしまうから敵意ばかりになる。その敵意をむき出しにして、外に向うのだから、己を滅ぼすのだ。参照:『竹取物語』と道教。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005193/『外物不可必、故龍逢誅、比干戮、箕子狂、惡來死、桀、紂亡。人主莫不欲其臣之忠、而忠未必信、故伍員流於江、萇弘死於蜀、藏其血三年、化而為碧。人親莫不欲其子之孝、而孝未必愛、故孝己憂而曾參悲。』(『荘子』外物 第二十六)→外物を絶対とすべきではない。なぜならば善行を積んだ龍逢(りゅうほう)ですら誅され、比干(ひかん)も殺されているではないか。箕子(きし)は狂い、悪名高き惡來(おらい)も死に、桀、紂も結局は死んだ。臣下を持つ者は彼らの忠誠心を欲しないことはないが、忠臣の誠が主君によって必ず報われるということはない。なぜならば伍員(ごうん)の遺体は江に流され、萇弘(ちょうこう)は蜀で自らの命を断ち、その血が留まるところ三年にして、化して碧玉となったではないか。人の親であるならば子の孝行を欲しないことはないが、孝行息子が必ず愛されるということもない。なぜならば、孝己(こうき)は憂い、曾參も悲しみに暮れたではないか。 「屠龍」と「碧血」は、共に剣の名前として使われています。特に『倚天屠龍記』では殷素素というキャラクターが『荘子』の言葉を暗記しているのでよく出てきます。「碧血」」の方は日本でも戊辰戦争の慰霊碑として函館にあるので、それで知っている方はいるかもしれません。参照:Wikipedia 碧血碑https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%A7%E8%A1%80%E7%A2%91『カンフー・パンダ』の中でポーの持つ剣が不自然に緑(碧)色なのは、「碧血剣」のことを指していて、これは、『荘子』や金庸作品へのオマージュとして、あえて緑色にしています。参照:カンフーパンダと荘子。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5104/この人の剣も緑です。これは偶然かも知れません(笑)。参照:(HD 1080p) Anakin Skywalker & Obi-Wan Kenobi & Yoda vs. Count Dooku https://www.youtube.com/watch?v=BvnwLLXHabgマスター・ヨーダと老荘思想 その2。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005026/今日はこの辺で。
2015.09.09
コメント(0)
-

荘子と進化論 その189。
西暦でいうと1126年。宋王朝は女真族の金の侵攻を受け、首都開封を包囲されて、徽宗・欽宗皇帝をはじめとする皇族を拉致されてしまいます。いわゆる靖康の変です。その後、領土の北半分を失ったものの、高宗が南京で即位して南宋が興り、中国の南北に異なる民族の政治体制が成立します。この北の方の金が支配していた山東半島で、王重陽(おうちょうよう 1112-1170)という人物を中心に「全真教」という宗教団体が立ち上がります。(ちなみに、同時代には太一教、真大道教といった道教の教団も成立しています。)教義としては儒・佛・道の三教の一致を説き、禅仏教との共通点も多いのが特徴です。また、真行のような社会奉仕的な活動にも積極的な組織でした。 参照:Wikipedia 全真教https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A8%E7%9C%9F%E6%95%99教祖であった王重陽亡き後、全真教団は一人の後継者によらず、全真七子という七人の高弟たちの合議制という形式を採ります。この七人のうち、最も有名な道士を、丘処機(きゅうしょき 丘長春とも)といいます。西暦1222年、彼はチンギス・ハーンに招聘されて、二年の歳月をかけてヒンズークシ山脈の南麓(現在のアフガニスタン)の野営地を訪れています。時に丘処機は七十四歳。チンギス・ハーンに向かって養生の道を説き、モンゴルの信任と後ろ楯を得て、後の全真教団の発展の礎を築きました。 『上遣大臣喝剌播得來迎、時四月五日也。館舍定、即入見、上勞之曰「「他國徴聘皆不應、今遠踰萬里而來、朕甚嘉焉。」對曰「山野奉詔而赴者、天也。」上悦、賜坐、食次、問「真人遠來、有何長生之藥以資朕乎?」師曰「有衛生之道、而無長生之藥。」上嘉其誠實、設二帳於御幄之東以居焉。』(『長春真人西遊記』)→皇帝は喝剌播得(カラホト)に大臣を派遣して師を歓迎した。4月5日のことであった。宿舎が決まった後、すぐに謁見が始まった。皇帝は労いの言葉の後に「他国からの徴聘に応じず、はるばる万里の彼方より来る。朕はこれを嘉する。」とおっしゃった。師は「詔を奉じて赴いたのは、天の意に従ったまでのことです。」と応えられた。皇帝は喜び、その座において食事を共にした。「真人、遠方より来る。何か長生の藥をお持ちならば、朕に資してくれまいか?」師曰く「世に衛生の道はございますが、長生の藥なるものはありませぬ。」皇帝は師の誠実さを喜び、二帳の天幕を行宮(オルダ)の東に設けて居所とするよう下賜された。・・・紀行文として、また当時の中央アジアの記録としても名高い『長春真人西遊記』から。ここで丘処機は、チンギス・ハーンに「有衛生之道、而無長生之藥。(衛生の道、すなわち生を衛る道は存在するが、それは長生きのための薬ではない)」と言っています。それまでの道教では煉丹術や錬金術のような、疑似科学的な手法によって精製された薬物を服用して永遠の存在になる、というような手法が流行していたんですが、丘処機はその立場を採っていません。参照:道教と神農。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201411230000/道教と煉丹 ~霊芝と水銀~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201502250000/このことについては、日本の江戸時代のベストセラー『養生訓』でも高い評価を受けています。『丘処機が、「衛生の道ありて長生の薬なし」といへるは、養生の道はあれど、むまれ付かざるいのちを、長くする薬はなし。養生は、只むまれ付たる天年をたもつ道なり。古(いにしえ)の人も術者にたぶらかされて、長生の薬とて用ひし人、多かりしかど、そのしるしなく、かへつて薬毒にそこなはれし人あり。これ長生の薬なき也。久しく苦労して、長生の薬とて用ゆれども益なし。信ずべからず。 内慾を節にし、外邪をふせぎ、起居をつゝしみ、動静を時にせば、生れ付たる天年をたもつべし。これ養生の道あるなり。丘処機が説は、千古の迷(まよい)をやぶれり。この説信ずべし。凡そ、うたがふべきをうたがひ、信ずべきを信ずるは迷をとく道なり。』(『養生訓』)参照:荘子の養生と鬱。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5030/ 『太祖時方西征、日事攻戰、處機每言欲一天下者、必在乎不嗜殺人。及問為治之方、則對以敬天愛民為本。問長生久視之道、則告以清心寡欲為要。(『元史』巻 二百二〈釋老.丘處機〉)→太祖は当時西方への遠征の途上で日々侵攻をくりかえしていた。処機は事あるごとに「天下を欲する者は決して殺人を嗜むような者であってはなりませぬ。」と言っていた。また、統治の方法について尋ねると、「天を敬い民を愛する(敬天愛民)を基本とする」と答え、長生久視の道について尋ねると「心を清く欲を寡なく」することが肝要と答えた。正史たる『元史』の中では、丘処機はチンギス・ハーンに対して殺人を咎める発言をしたと記録されております。やはり、老子の弟子です。『夫兵者不祥之器、物或悪之、故有道者不処。君子居則貴左、用兵則貴右。兵者不之器、非君子之器。不得已而用之、恬淡爲上。勝而不美。而美之者、是楽殺人。夫楽殺人者、則不可以得志於天下矣。』(『老子』 第三一章)→兵は不祥の器である。人は普通これを嫌い、道を心得た者はこれを用いない。君子は普段左を貴ぶが、事あるときは右を貴ぶものだ。兵は不吉な器であるので、君子ならば使うべきではない。やむを得ず使うことがあろうとも、執着なく使うことが望ましい。たとえ勝っても美徳とはならない。これを徳などとする者は、殺人を享楽とする外道であろう。人殺しを楽しみとするような者が、天下を望んだところで、到底成し得るはずがない。参照:老子とトルストイ。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5072/実は、この丘処機(きゅうしょき)という人物。歴史的な評価とは比べ物にならないほど、中華圏において大変な知名度があります。彼を有名にしているのは、フィクションの世界。武侠小説『射雕英雄伝(しゃちょうえいゆうでん))』(正しくは「雕」のつくりは「鳥」))の中心人物としてです。この小説の世界において、全真教は武門の名門として、全真七子は武術の達人集団として、そして、丘処機は、短気で喧嘩っ早いところはあるのもの、実直で義理堅い「武術の達人」として描かれています。イメージと史実とのギャップからすると日本の水戸黄門に近いかな。『射雕英雄伝(しゃちょうえいゆうでん)』は、香港の『明報』の創業者にして作家の金庸(きんよう Jin Yong 1924-)の武侠小説です。作者の金庸は、1972年以降、すなわち40年以上新作の小説を発表しておりませんが、彼の作品は現在でも絶大な支持を受け映像化され続けています。連続性のある射雕三部作(the Condor Trilogy)は、特に有名です。 射雕英雄伝(しゃちょうえいゆうでん The Legend of the Condor Heroes 1957)神雕俠侶(しんちょうきょうりょ The Return of the Condor Heroes 1959)倚天屠龍記(いてんとりゅうき The Heaven Sword and Dragon Saber 1961)発表の時期も、三部作である点も、また、現在のCG技術の発達によって、「ようやく原作を忠実に映像化しても鑑賞に堪えうるようになった」点でも、J・R・R・トールキンの『指輪物語』に似ているため「西のトールキン、東の金庸」と表現される場合があります。参照:射雕片头OP《天地都在我心中》含日文翻译 https://www.youtube.com/watch?v=swBYoTEDH9Qただ、ネタバレになりますが、奇しくも、アーシュラ・K・ル=グウィンの『ゲド戦記 影との戦い(1968)』と『射雕英雄伝(1957)』のラストシーンが、双方ともに『荘子』の「影を畏れ迹を悪む」を活用していますので、武侠と西洋のファンタジーとして対比するならば、この2作がオススメです。『甚矣子之難悟也。人有畏影惡跡而去之走者、舉足愈數而跡愈多、走愈疾而影不離身、自以為尚遲、疾走不休、絶力而死。不知處陰以休影、處靜以息跡、愚亦甚矣。』(『荘子』 漁父 第三十一)→ある人が自分の影をこわがり、自分のあしあとのつくのをいやがった。影をすててしまいたい、足あとをすてたい、そこからにげたいと思って、一生懸命ににげた。足をあげて走るにしたがって足あとができてゆく。いくら走っても影は身体から離れない。そこで思うのには、まだこれでは走り方がおそいのだろうと。そこでますます急いで走った。休まずに走った。とうとう力尽きて死んでしまった。この人は馬鹿な人だ。日陰におって自分の影をなくしたらいいだろう。静かにしておれば足あともできていかないだろう。(現代語訳は湯川秀樹著『本の中の世界』「荘子」より)参照:アーシュラ・K・ル=グウィンと荘子。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5164/Wikipedia 金庸https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%BA%B8続きはいずれ。今日はこの辺で。
2015.08.16
コメント(0)
-
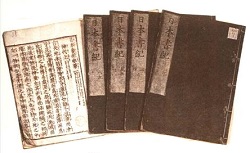
荘子と進化論 その188。
再び日本書紀。『十二月庚午朔、皇太子、遊行於片岡。時飢者臥道垂、仍問姓名、而不言。皇太子視之與飲食、卽脱衣裳、覆飢者而言、安臥也。(中略) 辛未、皇太子遣使令視飢者。使者還來之曰、飢者既死。爰皇太子大悲之、則因以葬埋於當處、墓固封也。數日之後、皇太子召近習者謂之曰「先日臥于道飢者、其非凡人、必眞人也。」遣使令視。於是、使者還來之曰「到於墓所而視之、封埋勿動。乃開以見、屍骨既空、唯衣服疊置棺上。」於是、皇太子復返使者令取其衣。如常且服矣。時人大異之曰「聖之知聖、其實哉。」逾惶。』(『日本書紀』 巻第二十二 推古天皇紀)→十二月の庚午の一日、皇太子(ひつぎのみこ)は片岡の地に行啓された。その時に飢者が道端に倒れていた。名前を尋ねても答えることはなかった。皇太子はこれを見て食べ物とのみの喪を与え、服を脱いで彼にかけて「安らかに臥しておくようおっしゃられた。(中略) 辛未の日に、皇太子(ひつぎのみこ)は飢者の様子を見て来るよう使者を遣わされた。使者は還ってきて飢者はすでに死んだと報告した。皇太子は大いにこのことを悲しまれ、その地に埋葬して、固く墓に封じられた。数日の後、皇太子は近侍の者に「先日見た行き倒れの飢者は、凡人ではなくきっと眞人であっただろう。」とおっしゃり使者にそれを確かめるよう遣いされた。使者が還ってきて「墓所にて見分たところ、土で埋め固めた場所は動いておりませんでした。これを開けてみると、死体も骨もすでになく、ただ棺の上に衣服が畳まれておりました。」と報告した。そこで皇太子は再び遣いされてその衣を持って来させ、いつものようにこれを纏われた。当時の人々はそのことに感じ入り「聖は聖を知る、とはまさにこのこと」として、ますます畏まった。この皇太子というのは聖徳太子のことです。片岡山伝説もしくは飢人伝説とも呼ばれるお話で、ここでも「真人」という言葉が使われています。途中に、棺を開けて確かめてみると、「屍骨既空、唯衣服疊置棺上。」すなわち「遺体がなくなっていて、衣服だけが棺の上に畳んで置いてあった。」と書いてあります。参照:始皇帝と道教。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410120000/天武天皇と道教。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201502010000/・・・死んだはずの人間の遺体が消失しているという現象。『日本書紀』にはもう一つ記されています。『卽詔群卿命百寮、仍葬於伊勢國能褒野陵。時、日本武尊化白鳥、從陵出之、指倭國而飛之。群臣等、因以、開其棺櫬而視之、明衣空留而屍骨無之。於是、遺使者追尋白鳥、則停於倭琴彈原、仍於其處造陵焉。白鳥更飛至河內、留舊市邑、亦其處作陵。故、時人號是三陵、曰白鳥陵。然遂高翔上天、徒葬衣冠、因欲錄功名卽定武部也。是歲也、天皇踐祚卌三年焉。』(『日本書紀』 巻第七 景行天皇)→景行天皇はすぐに群卿を召しだされ百寮に命じて、日本武尊(やまとたける)を伊勢の國の能褒野陵(のぼののみささぎ)に葬られた。時に、日本武尊は白鳥と化し、陵を飛び出して倭國の方へと飛んでいった。そこで、群臣らが日本武尊の棺を開けてこれを見てみると、明衣がむなしく残るばかりで、屍も骨も無かった。そこで、使者に遣いして白鳥を追わせたところ、白鳥は倭の琴彈原(ことひきはら)に留まったので、その地に陵を造った。白鳥はさらに河內へと至り古市邑(ふるいちのむら)に留まったので、その地にも陵を造った。時の人々は、この三つの陵を「白鳥陵」と呼んだ。その後ついに白鳥は上天へと高く飛んで行ってしまったので、日本武尊の衣冠のみを葬り、その功名を伝えんがために武部と定めた。この歳は天皇が即位されてより四十年目であった。こちらも、古代日本のスーパーヒーロー、ヤマトタケルの最期。ここでも棺を開けてみると、「明衣空留而屍骨無之」。衣服だけが残り、遺体が無かったと記されています。ここで対比していただきたいのが、紀元1世紀、後漢の時代に成立した『列仙伝』。伝説上の人物「黄帝」のお話です。『黃帝者、號曰軒轅。能劾百神、朝而使之。弱而能言、聖而預知、知物之紀。自以為雲師、有龍形。自擇亡日、與群臣辭。至於卒、還葬橋山、山崩、柩空無屍、唯劍舄在焉。仙書云「黃帝采首山之銅、鑄鼎於荊山之下、鼎成、有龍垂鬍髯下迎帝、乃昇天。群臣百僚悉持龍髯、從帝而升、攀帝弓及龍髯、拔而弓墜、群臣不得從、望帝而悲號。故後世以其處為鼎湖、名其弓為烏號焉。』(『列仙伝』黃帝)→黃帝は軒轅(けんえん)とも号した。百神をはげましては、公において彼らを使役した。幼くして言語に巧みであり、聡く、未来を知り、事物の道理に通じていた。自ら雲師となり、龍の姿をしていた。この世から去る日を告げて、多くの臣下に別れの挨拶をした。死んでから、橋山に帰って葬られた。その後山が崩れ、柩は空で屍はなくただ剣と舄(くつ)だけがあった。仙書は云う「黃帝首山の銅を採り、荊山の下にて鼎を作った。鼎ができあがった後、顎鬚をはやした龍が黄帝の迎えにやってきて、共に昇天した。群臣百僚はことごとく、龍の鬚や帝の弓につかまって共に天に昇ろうとしたが、鬚は抜けて弓も落ちてしまい、臣下たちは従うことができなくなった。彼らは帝を望んで号泣した。それゆえその場所を鼎湖とし、その弓を烏號という。黄帝の死の場合には「柩空無屍、唯劍舄在焉」、剣と靴だけが残っていたと書いてあります。というわけで『抱朴子』『又按漢禁中起居註云、少君之將去也、武帝夢與之共登嵩高山、半道、有使者乘龍持節、從云中下。云太乙請少君。帝覺、以語左右曰、如我之夢、少君將舍我去矣。數日、而少君稱病死。久之、帝令人發其棺、無屍、唯衣冠在焉。按仙經云、上士舉形昇虚、謂之天仙。中士游於名山、謂之地仙。下士先死後蛻、謂之屍解仙。今少君必屍解者也、近世壺公將費長房去。及道士李意期將兩弟子去、皆託卒、死、家殯埋之。積數年、而長房來歸。又相識人見李意期將兩弟子皆在郫縣。其家各發棺視之、三棺遂有竹杖一枚、以丹書於枚、此皆屍解者也。』(『抱朴子』 論仙篇)→また『按漢禁中起居註』にいう、李少君がこの世から去ろうとするとき、武帝は夢を見た。少君と共に嵩高山に登り、道の途中で、龍に乗り杖を携えた使者が雲の合間から降りてきた。彼らは太乙が少君を呼んでいるという。武帝はそこで目覚め、左右にその夢の話をした。「もし私の夢の通りであるならば、少君はもうすぐ私の元から去るだろう」と。数日後、少君は病死したという。しばらくして、帝は使者に棺を開けさせてみると、少君の屍はなく、ただ衣冠のみがあった。また、『按仙經』によると、「上士は身体をそのままに虚空へと昇る。これを天仙という。中士は名山に遊ぶ、これを地仙という。下士は一度死んで蝉の抜け殻のような状態になる。これを屍解仙という。」とある。そうすると、少君はきっと屍解者であったのだろう。最近の例でも壺公は費長房を連れ去っているし、道士・李意期は二名の弟子を連れ去っている。皆何かに仮託して死に、家人が殯をしてこれを埋めている。数年経ってから、長房は帰ってきたし、李意期と二名の弟子は四川で知人に会っている。家族が棺を開けてみると、三人の棺には、それぞれ竹の杖が一本ずつ入っていて、丹沙で名前が書かれていたという。これは皆、屍解者であったのだ。「(尸/屍・しかばね)を解く」と書く「尸解仙/屍解仙」。昔は「しけせん」「しげせん」とも呼んでいたようですが、現在は「しかいせん」と読む方が通りがよいです。平安末期、大江匡房の著した『本朝神仙伝』以降、「日本の仙人」としてヤマトタケル、聖徳太子が挙げられることがあるのは、『日本書紀』において神道の枠内では説明できない尸解仙の記録があるためです。 「尸解仙」のイメージとしては、『新世紀エヴァンゲリオン』で、シンクロ率が400パーセントを突破し、エントリープラグ内で肉体が消失した碇シンジや、「AIr まごころを君に」で衣服だけを残して液状化した人々のそれに近いかなと思います。あと「魂魄」をゲームのHP・MPにたとえることがあるんですが、HPゼロでMPだけの存在として活動していると仮定してみると分かりやすいかな。『抱朴子』において葛洪は『史記』にも登場する李少君の死を引き合いに出して、李少君は屍解仙であったとしています。また、仙薬の「上品・中品・下品」と同じように、1.身体をそのままに虚空へと昇る天仙。2・名山に遊ぶ地仙。3.一度死んで蝉の抜け殻のような状態になる屍解仙として、尸解仙を最低ランクに位置づけています。触媒や依代として、衣服や装飾品、剣や杖などの道具を使用して、その痕跡が残ってしまうちはまだまだ未熟という思想ですね。参照:「封禅書」と道教。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410050000/例えば、『カンフーパンダ』のマスターウーグウェイは、その最期において「杖」を依代や触媒として扱ってません。『スターウォーズ』のマスターヨーダもそうですが、公然と、衣服も残さずに消滅するならば「天仙」と言えます。参照:The Illusion of Control https://www.youtube.com/watch?v=DLpUev1FvS0なお、「尸解仙」の典型的なパターンと言えるのはオビ=ワン・ケノービです。彼の場合には、身体(死体・遺体)の消失には成功していますが、衣服と剣を残したままです。宋代の道教経典『雲笈七籤』では、この尸解を剣解と呼んでいます。参照:Obi - Wan Kenobi Vs Darth Vader - A New Hope https://www.youtube.com/watch?v=sq51w34Hg9Iマスター・ヨーダと老荘思想 その2。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5026/今日はこの辺で。
2015.08.03
コメント(0)
-
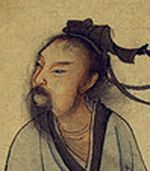
荘子と進化論 その187。
今日は列子から。『魯公扈、趙齊嬰二人有疾、同請扁鵲求治、扁鵲治之。既同愈。謂公扈、齊嬰曰「汝曩之所疾、自外而干府藏者、固藥石之所已。今有偕生之疾、與體偕長、今為汝攻之,何如?」二人曰「願先聞其驗。」扁鵲謂公扈曰「汝志彊而氣弱、故足於謀而寡於斷。齊嬰志弱而氣彊、故少於慮而傷於專。若換汝之心、則均於善矣。」扁鵲遂飲二人毒酒、迷死三日、剖胸探心、易而置之。投以神藥、既悟、如初。二人辭歸、於是公扈反齊嬰之室、而有其妻子、妻子弗識。齊嬰亦反公扈之室、有其妻子、妻子亦弗識。二室因相與訟、求辨於扁鵲。扁鵲辨其所由、訟乃已。』(『列子』湯問篇)→魯の公扈(こうこ)と趙の斉嬰(せいえい)の二人には病があり、二人とも扁鵲(へんじゃく)にその治療を求め、扁鵲は治療にあたり、二人とも快癒した。その後、扁鵲が公扈、斉嬰に「そなたらの病は外から内臓を傷めたものであったので、薬を施して治せるものであった。ところが、今、生まれたときから抱えており、身体の成長と共にひどくなっている病がある。今そなたらのためにこの病根を除こうと思うがいかがか?」と言った。二人は「まず、どのような病なのか、先生のお見立てをお聞かせください。」という、扁鵲は公扈に「そなたの志は固いが、氣が弱い。考え事が多い割りに、ここぞというときの決断ができない。齊嬰は志はもろいが、氣は強い。考え事は少ないが、向こう見ずなのじゃ。そなたらの心を取り換えるならば、二人の心がよくつりあうこととなろう。」と言った。扁鵲は二人に毒酒を飲ませ、生死の境を彷徨わせること三日目、ついに胸を探り出し、心を取り換えてしまいこみ、神藥を投じて、二人を目覚めさせた。二人とも、数日前と変わる様子もなかった。二人は辞去して帰宅した。公扈は齊嬰の家に戻ったが、妻子にしてみれば彼は見知らぬ他人であった。齊嬰は公扈の家に戻ったが、妻子にしてみれば彼は見知らぬ他人であった。両家の者たちは共に訴え、扁鵲に説明を求めたが、扁鵲の説明を聞くと、訴えを取り下げた。扁鵲(へんじゃく)という人物は、紀元前から多くの逸話を残す「伝説の名医」でして、日本の『万葉集』の「沈痾自哀文(ちんあじあいぶん)」にもその名が登場します。参照:憶良の病と『抱朴子』。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410260000/ 『華佗字元化、沛國譙人也、一名旉。遊學徐土、兼通數經。曉養性之術、年且百歲而猶有壯容、時人以為仙。沛相陳珪舉孝廉、太尉黃琬辟、皆不就。精於方藥、處齊不過數種、心識分銖、不假稱量。針灸不過數處。若疾發結於內、針藥所不能及者、乃令先以酒服麻沸散、既醉無所覺、因刳破腹背、抽割積聚。若在腸胃、則斷截湔洗、除去疾穢、既而縫合、傅以神膏、四五日創愈、一月之間皆平復。』(『後漢書』方術列伝 )→華佗(かだ)、字(あざな)は元化、沛国・譙(しょう)の人である。またの名を「旉(ふ)」という。徐州にて遊学し、数々の経典に通じていた。養性の術に明るく、百歳に近づいていても容姿は壮年の頃と変わらなかったため、時の人々は彼が仙人となったと思っていた。沛国の相、陳珪(ちんけい)は、華侘を孝廉に推挙し、太尉の黃琬(こうえん)も彼を招いたものの、固辞された。方藥に精通しているが、処方するのは数種のみ。分量は心で識り、秤を用いることもない。針灸を施す場合も数か所のみ。もし、病が人の内から発して、針でも薬でも通じない場合には、まず酒で麻沸散を飲ませ、酔って知覚が無くなってから、腹または背を切り開き、病の集まったところを取り出す。もし病が胃腸にあるならば、切り取ってから洗い、穢れを除き去って縫合し、神膏を塗りこむ。四、五日で治り、一ヶ月で全快する。漢代末期、三国志の時代の名医・華侘が酒と麻沸散による外科手術の記録が『後漢書』にありますが、『列子』の寓話でも、現在で言う麻酔と同じように酒を飲ませてから手術をしている設定です。『列子』の寓話の中では、「扁鵲遂飲二人毒酒、迷死三日、剖胸探心、易而置之。投以神藥、既悟、如初。(扁鵲は二人に毒酒を飲ませ、生死の境を彷徨わせること三日目、ついに胸を探り出し、心を取り換えてしまいこみ、神藥を投じて、二人を目覚めさせた。二人とも、数日前と変わる様子もなかった。)」とあります。これって心臓移植ですよね。後半部分は、「細胞記憶(Body memory)」や「記憶転移」ですよね。参照:華侘と『後漢書』。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410190000/Wikipedia 細胞記憶https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%A8%98%E6%86%B6Wikipedia 記憶転移https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%98%E6%86%B6%E8%BB%A2%E7%A7%BB『列子』という書物は、『老子』『荘子』に比べれば成立は遅くて、唐の時代『沖虚真経』と呼ばれ始めたころのものが、現在のものとほぼ同じといえる、という程度です。しかし、たとえ千五百年程度の歴史でしかないとしても、『列子』の一部は現代で言うSFです。参照:列子の人造人間は蝶の夢をみるか?http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5088/荘子の夢、蕉鹿の夢。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5160/次は『荘子』。『少知問於大公調曰「何謂丘里之言?」大公調曰「丘里者、合十姓百名而以為風俗也。合異以為同、散同以為異。今指馬之百體而不得馬、而馬係於前者、立其百體而謂之馬也。是故丘山積卑而為高、江河合水而為大、大人合并而為公。是以自外入者、有主而不執。由中出者、有正而不距。四時殊氣、天不賜、故歲成。五官殊職、君不私、故國治。文武大人不賜、故徳備。萬物殊理、道不私、故無名。無名故無為、無為而無不為。時有終始、世有變化、禍福淳淳、至有所拂者而有所宜。自殉殊面、有所正者有所差。比於大澤、百材皆度。觀於大山、木石同壇。此之謂丘里之言。」(『荘子』則陽 第二十五)→少知が大公調に尋ねて曰わく「丘里の言とは何でしょう?」大公調曰わく「丘里の言というのは、十の姓と百人の人間で構成された人々の風俗によって構成されている。つまり、本来はそれぞれ異なったものを一つのものとして集めてできたものであるのだから、またバラバラの一つともなりうる。今、馬の身体を百にまでバラバラにしてしまうとすると、その一つの部品を馬とは呼ばないが、その部品の全てを繋げて立たせたものは馬と呼べるというようなものだ。これ故に丘山は背の低い石が積み重なって高さを保ち、江河は小さな流れが合わさってその大きさを保っているといえる。大はそういった事柄をあわせて公の仕事を為す。このようであるから、外から入ってきた者に対しても、自らが主であるかのような態度を取らず、内から出た者に対しても、自らに正しさがあるとして遠ざけるような態度を取らない。春夏秋冬の季節は氣を異にするが、天はそのうちの一つに私しないから、一年という歳月が成り立つ。五官はその職分を異にするが、それを統括する君に私しないから、国は治まる。文武について大人は私しないから、君に徳が備わる。萬物は理を異にするが、道は私しないから、道に名は無い。無名であるが故に無為であり、無為でありながら為さないことはない。時には始まりと終わりがあり、世界は絶えず変化を続け、幸福と不幸は常に降りかかり、都合がよいかどうかは定まらない。一つの事柄からも、正しいとできるものも、正しくないとできるものもある。百種の多様な材木が、一つの河を流れているかのようであり、大山を眺めてみると、小さな木石の積み重ねでできているかのようなもの。このようなものを丘里の言という。」「丘里の言」を「輿論」と読む書物もあるようです。「小異を捨てて大道に就く」が『荘子』からであることがよく分かる文章ですが、途中で、全体と一部を説明する場合に、馬をバラバラにしてその部品と、再び組み合わせたものとの対比をしています。アプローチに違いはあれど、『荘子』にも『列子』にも見られる一貫した思想があります。後に道教は、東アジアの医術や武術にも大きな影響を及ぼすこととなりますが、それは、彼らでしか有し得なかった独特の宇宙観の賜物でもあります。インドの思想や技法で購うことのできない「身体という宇宙」の観法および思想が、書物としての『荘子』にも『列子』にも見られます。参照:身体技法と老荘思想 ~技と道~。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5127/『百骸、九竅、六藏,賅而存焉,吾誰與為親?汝皆說之乎?其有私焉?如是皆有,為臣妾乎,其臣妾不足以相治乎。其遞相為君臣乎,其有真君存焉。如求得其情與不得,無益損乎其真。』(『荘子』斉物論 第二)→ 人の身体には百の関節、九つの穴、六つの臓器があるが、我々はそれをえこひいきするだろうか?あなたは差別なく扱うだろうか?差別を設けるであろうか?その主従によって制御するのであろうか?交互に主従となるのであろうか?この場合、主宰者がいて統率していると考えることができる。ただし、たとえば、真君の存在と知っているかいないかは、真君の働きには関係が無いのだ。今日はこの辺で。
2015.07.27
コメント(0)
-

荘子と進化論 その186。
「プーさん」のつづき。参照:プーさんと老荘思想。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005194/今回はディズニー作品『アナと雪の女王(原題Frozen)』のテーマ曲「Let it go」を。アカデミー賞の主題歌賞を受賞し、世界的にヒットした楽曲です。日本では、「Let It Go〜ありのままで〜」として、去年、さんざん聴かされました。ここで、「Let it go」と対比していただきたいのが、『Mulan(1998)』の「Reflection」です。 『アナと雪の女王』は、『リトルマーメイド』以降の、『美女と野獣』『アラジン』(かつては「ネオクラッシックス」と呼んでいた!)といった作品群を意識して製作されていますが、これは脚本や演出だけでなく、楽曲においてもそうだったようでして、「Let it go」と「Reflection」は大変よく似ています。 まず、周囲の期待に応えられない主人公の苦悩という主題が一致しています。エルサのいう「perfect girl」と、ムーランのいう「perfect bride/ perfect daughter」も同じ用法です。曲中で髪をほどくという動作も同じ。参照:FROZEN - Let It Go Sing-along | Official Disney HD https://www.youtube.com/watch?v=L0MK7qz13bUMulan - Reflections [HQ] https://www.youtube.com/watch?v=1_BtlAw4trg・・・ちなみに、「Reflection」の日本語版でも「ありのままの自分」という表現を使っていまして、「ありのまま」という言葉の用法も、『ムーラン』の方が先です。Mulan - Reflection (Japanese Version) https://www.youtube.com/watch?v=fGTSMCorc4g「ありのまま」「あるがまま」といった言葉は、前掲の『タオのプーさん』でもそうですが、老荘思想や禅、浄土といった中国由来の思想を日本語で説明する場合に、よく使われる言葉です。参照:道元禅師 映画『禅ZEN』予告編 https://www.youtube.com/watch?v=fnWXt-3I1U4実は、この歌詞は、西洋人が見る老荘思想や禅の思想の特徴的な見方をなぞっている形跡があります。日本語版よりも英語版の方が一致点が多いのでその辺を(以後、歌詞はコテコテの直訳を付記します)。"Let it go, let it goCan't hold it back anymore(もう隠し続けられない)""I'm never going back, the past is in the past(これからは振り返らない、過去は過去のこと)"『體盡無窮、而遊無朕、盡其所受於天、而無見得、亦而虚已。至人之用心若鏡、不將不迎、應而不藏、故能勝物而不傷。』(『荘子』応帝王第七)→無限の世界に飛び出して、形なき世界を遊ぶ。天により受けたままの恩恵をことごとく受け入れ、それ以外を求めない。ひたすらに虚心になるのだ。至人の心は曇りなき鏡のようであり、過去の事象に囚われず、未来を思い悩むこともない。全ての変化に応じて、引きとめることもない。故に、曇りなき鏡を、何者も傷つけることはできない。「将(おく)らず、迎えず、応じて、蔵せず」。過去を悔やまず、未来を悩まず、応じることはあっても、それを溜めおくこともない。今を生きる「ヒア・ナウ」の思想です。「Let it go」というのは、『荘子』に最も近いです。"I don't care what they're going to say(他人がどう言ったって気にはしないわ)""No right, no wrong, no rules for me, I'm free!(正しいも、間違いも、ルールもない。今こそが自由!)"『吾所謂臧者、非所謂仁義之謂也、任其性命之情而已矣。吾所謂聰者、非謂其聞彼也、自聞而已矣。吾所謂明者、非謂其見彼也、自見而已矣。夫不自見而見彼、不自得而得彼者、是得人之得而不自得其得者也、適人之適而不自適其適者也。』(『荘子』駢拇 第八)→私の言う「善」とは世間の言う仁義ではない。己が内にある自然の徳をあるがままにまかせることを善と言う。私の言う「聡」とは、外界の音がよく聞こえるということではなく、内なる声を聴けることを言う。私が言う「明」とは、外界の色をよく見分けられることではなく、内なる私を見つめられること言う。自分の内にあるものを見つめずに、外にあるものに気を取られたり、自分の心に適うものを求めずに、他人の心に適うものを求めるのは「他人が納得することは自分も納得するものだ」と思い込んでいるからであり、それは「自分の心に適うもの」とは言えない。他人の楽しみを自分の楽しみとしているうちは、「自適」とは言わないものだ。「Let it go」というのは、エルサが雪山に篭るときに歌われるので、ちょうどマッチするんですが、悠々自適の自適というのは、後の世では隠者の教えの手本となる、荘子の特徴的な思想です。参照:スティーブ・ジョブズと禅と荘子 その5。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5177/"A kingdom of isolation, and it looks like I'm the Queen(孤独な王国にたたずむ、私は女王に見られているのね)"『澤雉十歩一啄、百歩一飲、不?畜乎樊中。神雖王、不善也。』(『荘子』養生主 第三)→沢のキジは十歩に一度エサをついばみ、百歩に一度水を飲む。そんなキジでも籠の中に閉じ込められる事を望まない。人間で言えば王様のようにエサや水にありつけても、心がそれを善しとしないからだ。・・・王侯のような暮らしでも、自適であるとは限りません。他にも、"Don't let them in, don't let them seeBe the good girl you always have to beConceal, don't feel, don't let them know"ここであらわれている、エルサに求められる圧力ついても、『子曰「民可使由之,不可使知之。」』(『論語』泰伯)→先生はおっしゃった「民衆には、由らしめるべきであり、知らしめてはならない。」日本人が大く曲解する『論語』の「知らしむべからず、由らしむべし」にそっくりでして、ステレオタイプな儒家と道家の対立軸とも一致点が見られます。あと二つ、特徴的な歌詞。“Let the storm rage on(嵐よ吹きすさぶままに)”“Let the storm rage on”。これは、ユングのタオイズムの捉え方に非常に近い、内と外の自然の関係を象徴していまして、ユングの影響ではないかと思います。参照:ユングと雨乞い、ユングと無為自然。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5191/「有漏路より無漏路へ帰る一休み 雨降らば降れ 風吹かば吹け」一休宗純“The cold never bothered me anyway!(もう冷さに煩うことはないわ)”『且有真人、而後有真知。何謂真人?古之真人、不逆寡、不雄成、不謨士。若然者、過而弗悔、當而不自得也。若然者、登高不慄、入水不濡、入火不熱。是知之能登假於道也若此。』(『荘子』大宗師 第六)→真人ありて、しかる後に真知あり。どのような人を真人というのだろうか?(中略)高所にあっても物怖じせず、水に入っても濡れず、火に入っても熱さを感じない。知が至り道に到達したものはこのようなものだ。参照:始皇帝と道教。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410120000/・・・「Let it go」の歌詞は、『荘子』に描かれている至人、真人といった人々や、代表的な禅者が到達した「境涯」の言葉にぴったり符合するんです。私は偶然だとは思っていません。「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて 冷しかりけり」 永平道元今日はこの辺で。
2015.07.06
コメント(0)
-

荘子と進化論 その185。
前回の続き。参照:『竹取物語』と荘子。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5193/日本の物語文学の黎明期にも影響が見られる『荘子』ですが、今回はちょっと変り種を。老荘思想の関連書になぜかついてくる「くまのプーさん」について。たとえば、 PHPから『くまのプーさん 心がふっとラクになる言葉 』『くまのプーさん 小さなしあわせに気づく言葉』という本が出ていまして、それぞれ、『老子』『荘子』、明の時代に洪自誠が著した『菜根譚』の言葉を、プーさんの挿絵と共に載せています。さらに最近では、『くまのプーさん心を見つめる言葉 くまのプーさんと読む「論語」』なる、プーさんと論語の本まで登場しておりまして(ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 監修!)、中国古典といえばプーさんというような不思議な流れがあります。「プーさん」と中国古典の抱き合わせ。源流に遡ると、1982年に刊行された“The Tao of Pooh ”という書物に突き当たります。著者はアメリカ人、ベンジャミン・ホフ(Benjamin Hoff 1946~)という人物です。『クマのプーさん』と老荘思想の紹介本として、80年代には世界的なベストセラーであったそうです。日本語版は1989年に発刊されています。・・・そもそも、プーさんと老荘思想に関係はあるのか?『タオのプーさん』によると、一つはプーさんの人格、もう一つは名前です。紀元前の書物にもあり、現在も使われている言葉の中に「素朴(素樸)」という言葉があります。日中ともに使用されて意味もほぼ同じ、なんですが、これは老荘思想の言葉でして、中国語では「sùpǔ」と発音します。素朴の朴(樸)の字の読みが「プー」なんです。・・・「樸(あらき)」とは、人為の加わる前の原木のことです。≪ <樸>(あらき)の原理で肝心な点は、本来の素朴さを備えているものには生来の力がある、ということだ。素朴さに変化が起こると、その力はたちまち損なわれ、失われてしまう。代表的な中国の辞書で樸(プー)という漢字を見ると「自然な、単純な、飾り気のない、正直な」という定義が出ている。樸(プー)は二つの文字でできている。まず、基本的な意味である「偏」は、樹木や木材という字。そして、音をあらわす「旁」はうっそうと茂るものとか、茂みという漢字。それで「茂みのなかの木」ないし「切られていない木」というあたりから「自然の状態にあるもの」という意味が出てくる---一般にタオイストの著書の英語版では「彫られていない木(アンカーヴド・ブロック)という言い方をする。 このタオイストの原理の基本は、自然のままの美しさと機能を持つものだけでなく、人間にもあてはまる。それからクマにも。(平河出版社刊 ベンジャミン・ホフ著 吉福伸逸、松下みさを訳 『タオのプーさん』より)≫Wikipedia The Tao of Poohhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Tao_of_Pooh『絕聖棄智、民利百倍。絕仁棄義、民復孝慈。絕巧棄利、盜賊無有。此三者以為文不足。故令有所屬。見素抱樸、少私寡欲。』(『老子道徳経』第十九章)→聖を絶ち、智を棄てれば、民の利は百倍する。仁を絶ち、義を棄てれば、民は孝慈に立ち返る。巧を絶ち、利を棄てれば、盗賊はいなくなる。この三つの言葉では足りないので、それにつないでこう言おう。「素を見せて樸(あらき)を抱き、私を小さく、欲を少なくせよ」と。『故至徳之世、其行填填、其視顛顛。当是時也、山無蹊隧、澤無舟梁。萬物群生、連属其郷。禽獣成群、草木遂長。是故禽獣可係羈而遊、烏鵲之巣可攀援而閲。夫至徳之世、同與禽獣居、族與萬物並、悪乎知君子小人哉。同乎無知、其徳不離。同乎無欲、是謂素樸。素樸而民性得矣。』(『荘子』 馬蹄 第九)→ゆえに、至徳の世というのは、束縛もなく人の行いは穏やかで、人々の瞳は明るかった。かつての至徳の世では、山には道も拓かれず、川には舟も無かった。万物は群生して、棲み分けをする必要もなかった。動物たちは群れを成し、草木は伸びやかに成長した。ゆえに、動物を紐に繋いで共に遊ぶことが出来たし、木によじ登って、カササギの巣をのぞいてみることができた。その至徳の世においては、動物たちと同じ場所に住み、万物と並んで暮らしていた。そこに君子や小人なんているはずがない。人々はさもしい知識も持たず、徳が心から離れず、無欲でいた。これを「素樸(そぼく)」という。素樸だからこそこそ民はあるがままでいられる。『荘子』の場合には、道具の使用や、社会性、広い意味での人為、すなわち「文明」を「獲得」する以前の人の姿を描写する場合に「素樸」という表現をしています。↑の英語版Wikipediaのページでもわかるように、この本は、『三聖吸酸図』の解説もやっています。世界遺産・日光東照宮の陽明門の彫刻でも有名なモチーフです。≪三人の男が、大きな酢桶をかこんで立っている。それぞれの指に酢を浸して、味見をしたばかりだ。ひとりひとりの表情に、三人三様の反応があらわれている。絵は寓話的なものだから、このひとたちがただの酢の味ききではなく、中国の「三教」の代表だということ、そして味を見ているその酢が人生の本質(エッセンス)を象徴していることを心得ておくほうがいいだろう。三人の導師(マスター)とは、孔子、仏陀、そして現存する最も古いタオイズムの著者、老子だ。一人目はすっぱそうな表情を浮かべ、二人目は苦い顔、なのに三人目はほほえんでいる。 孔子にとって、人生は、どちらかというとすっぱいものだった。現在は過去と足なみをそろえていないし、地上の人間のまつりごとは、宇宙のまつりごとである<天の道>と調和していないと考えていたのだ。だから彼は<先祖>をうやまうことを、皇帝が<天子>として無限の天と地を仲立ちする、古来の典礼や儀式と同じくらい重視した。儒教のもとでは、整然とした宮廷音楽、定められた立居振舞と言いまわしを用いる非常に複雑な儀式制度がつくりあげられ、それぞれ特定の目的で特定の時に使われていた。孔子について、こんな言葉が記されている。「敷物がまっすぐでなければ、師はお座りになろうとしなかった」。これで、儒教のもとで諸事がどのように行われたかおわかりだろう。 絵の中の第二の人物、仏陀にとってこの世の生活は苦しみを招く執着や欲望に満ちあふれた苦々しいものだった。この世は罠をしかけ、妄想を生みだし、あらゆる生き物をを苦しめる際限のない輪廻であるとみなされた。心の平安を見出すには、この「塵界」を超え、サンスクリット語で文字通り「無風」状態を意味するニルヴァーナ(涅槃)に達するしかない、と仏教徒は考えた。発祥の地インドから中国に渡ったのち、仏教は本来楽天的な中国人のおかげでずいぶん変わったけれど、それでも敬虔な仏教徒は、日常生活の苦い風にニルヴァーナの道をさまたげられる感じることがしばしばだった。 老子にとって、そもそものはじめから天地のあいだにあった自然の調和は、だれもがいつでも見出しうるものだった。といっても、儒教のきまりにしたがっていては無理だ。『道徳経』にもあるように、地は、その本質において天を映しだしており、おなじ法則によって営まれている----人間の法則によってではない。これらの法則は、遠い惑星の回転ばかりでなく、森の鳥や海の魚の活動にも影響をおよぼしている。老子によれば、宇宙の法則によってつくりだされ、支配されている自然のバランスに人間が介入すればするほど、その調和は遠のいてしまう。無理をすればするほど、問題が大きくなる。軽重、乾湿、遅速にかかわらず、万物はその内に独自の性質をもっており、それを無視すると面倒が起こらずにはすまない。観念的で一方的な規則が外から押しつけられれば、どうしても軋轢が生じる。人生がすっぱくなるのはそのときだけだ。 (中略)それから何世紀ものあいだに、老子の古典的な教えは、哲学的、求道的、民間宗教的な諸形態にわかれて発展していった。これからすべて大きくひとまとめにして、道教(タオイズム)と呼ぶことができる。けれど、ここでとりあげているタオイズムの基本は、あらゆる日々の営みの真価を充分に認め、それから学びとり、それとつきあっていく、ひとつの特別なやり方にすぎない。タオイストの見方では、この調和のとれた生き方がおのずから幸福をもたらす。明るい落ちつきこそ、タオイストの人格のいちばん目立つ特徴といっていい。それに微妙なユーモアのセンス。これなどは、たとえば二千五百年前の『道徳経』のような、もっとも深遠なタオイストの書物にさえ見られる。老子と並び称される道教の第二の大家、荘子の著したものを読むと、泉からわきでる水さながら静かな笑いがこみあげてくるようだ。 「でも、それがお酢となんの関係があるの?」と、プーがきいた。 「それは説明したと思ったよ」と、ぼくはいった。 「ぼくはそう思わないな」 「それなら、いま説明しよう」 「それがいい」 例の絵で、老子はなぜほほえんでいんだろう?ほかのふたりの表情からもわかるように、人生を象徴するその酢はたしかにイタダケナイ味だったにちがいない。けれども、人生で起こるさまざまなことと仲良くつきあっていくことで、タオイストは、ほかのひとなら否定的にとらえるかもしれないことを、肯定的なものに変えてしまう。タオイストにいわせれば、酸いも苦いも、ありのままを受け容れようとしないおせっかいな心から出ているのだ。あるがままに理解して役立てれば、人生そのものは甘い。それが『酢を味わう者』のメッセージだ。(同上)≫今日はこの辺で。
2015.05.25
コメント(0)
-

荘子と進化論 その184。
前回の続き。参照:『今昔物語』『宇治拾遺物語』と荘子。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/5192/今回は日本最古の物語文学作品『竹取物語』で。いわずと知れた歴史的作品ですが、神仙思想を含めた、道教のエッセンスは濃厚です。例えば、ラストシーンでかぐや姫が月に帰るときに「不死の薬」が出てきます。“「この國に生れぬるとならば、歎かせ奉らぬ程まで侍るべきを、侍らで過ぎ別れぬること、返す返す意なくこそ覺え侍れ。脱ぎおく衣(きぬ)をかたみと見給へ。月の出でたらん夜は見おこせ給へ。見すて奉りてまかる空よりもおちぬべき心ちす。」と、かきおく。天人(あまびと)の中にもたせたる箱あり。天(あま)の羽衣入れり。又あるは不死の藥入れり。ひとりの天人いふ、「壺なる御(み)藥たてまつれ。きたなき所のもの食(きこ)しめしたれば、御心地あしからんものぞ。」とて、持てよりたれば、聊甞め給ひて、少しかたみとて、脱ぎおく衣に包まんとすれば、ある天人つゝませず、御衣(みぞ)をとり出でてきせんとす。(『竹取物語』より)”参照:Wikipedia 竹取物語http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B9%E5%8F%96%E7%89%A9%E8%AA%9Eかぐや姫は、旧暦の八月十五日(大陸では中秋節)に月へと帰ります。現在の中秋の名月でもなじみのある、不死の薬を飲んで月へと帰る「嫦娥奔月(じょうがほんげつ)」のお話も竹取物語の基盤となっています。嫦娥奔月の最も古い記録は、『日本書紀』の元ネタでもある紀元前2世紀の『淮南子』でして、この『淮南子』の編者である淮南王・劉安自身にも不死の薬を服用した伝説があります。羽化登仙とも言いますが、かぐや姫もその典型的なパターンを踏襲する形で、月へと旅立っています。参照:嫦娥と兎とひきがえる。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/005188/物語の中で、かぐや姫は五人の有力な求婚者に対して、結婚と引き換えに珍しい品々を要求しています。一部は五行に対応しています。石作の皇子(いしづくりのみこ) → 「仏の御石の鉢」車持皇子(くらもちのみこ) → 「蓬莱の玉の枝」右大臣 阿倍御主人(あべのみうし) → 「火鼠の皮衣(ひねずみのかわごろも)」大納言 大伴御行(おおとものみゆき) → 「龍の首の玉」中納言 石上麿足(いそのかみのまろたり) → 「燕の子安貝(つばくらめのこやすがい)」。このうち「(東の海の蓬莱に生えているという)白銀を根とし、黄金を茎とし、白玉を実としてたてる木」の枝、「蓬莱の玉の枝」は『史記』「秦始皇本紀」でも有名な蓬莱伝説。参照:始皇帝と道教。http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201410120000/実は「蓬莱の玉の枝(蓬莱)」と「火鼠の皮衣(唐土)」の二品は、よく似た話が『列子』の湯問篇にあります。『革曰「渤海之東不知幾億萬里、有大壑焉、實惟无底之谷、其下无底、名曰歸墟。八絃九野之水、天漢之流、莫不注之、而无増无減焉。其中有五山焉。一曰岱輿、二曰員嶠、三曰方壺、四曰瀛洲、五曰蓬萊。其山高下周旋三萬里、其頂平處九千里。山之中聞相去七萬里、以為鄰居焉。其上臺觀皆金玉、其上禽獸皆純縞。珠玕之樹皆叢生、華實皆有滋味、食之皆不老不死。所居之人皆仙聖之種。一日一夕飛相往來者、不可數焉。」』(『列子』湯問篇)→湯王は再び質問した。「物には大きいと小さいという区別があるのだろうか?長いと短いという区別があるのだろうか?同じと違うという区別があるのだろうか?」夏革は答えて言った。「渤海の東、幾億萬里とも言えない場所に巨大な谷があるそうです。この谷は底なしでどこまでも深く、名を歸墟と申します。八絃九野の水、天漢の流れ、あらゆる水がその場所に流れ落ちながらも、その水かさは増えることも減ることもないそうです。その谷に五山があり、一に岱輿(たいよ)、二に員嶠(えんきょう)、三も方壺(ほうこ)、四に瀛洲(えいしゅう)、五に蓬萊(ほうらい)と申します。その山の周囲は三萬里あり、頂上の平らな場所は九千里、山はお互いに七萬里ほどの距離を経て隣り合っています。その頂上には、金銀で彩られた建物があって、その山の禽獸は皆純白であり、宝珠の木が群生し、花も実も美味であると同時に、食すれば不老不死となります。その山に住む者は神仙の類いで朝な夕なに山々を飛翔して巡り、数え上げることもかないません。」『周穆王大征西戎、西戎獻錕吾之劍、火浣之布。其劍長尺有咫、練鋼赤刃、用之切玉如切泥焉。火浣之布、浣之必投於火。布則火色、垢則布色。出火而振之、皓然疑乎雪。皇子以為无此物、傳之者妄。蕭叔曰「皇子果於自信、果於誣理哉。」』(『列子』湯問篇)→周の穆王は西戎を大いに征伐し、西戎は錕吾の剣と、火で洗う布を献上した。剣の長さは一尺八寸、よく鍛えられた赤刃で玉を泥のようにたやすく斬る。火で洗う布(火浣之布)は汚れを落とすのに火を使う布で、最初は火の色に染まり、汚れはそのままの色でいる。火から離して振るうと汚れは落ち、布の方は雪のように真っ白に戻る。この話を聞いたある皇子は「そんなものは存在しない。誰かが撒いた妄言だ」と言った。蕭叔は「皇子は自ら信をもって判断したが、存在するものですらないと断定することになってしまった。」と言っている。この「火浣の布」は現在で言うと石綿のことでしょう。『抱朴子』では、魏文帝・曹丕のエピソードとして語られています。『魏文帝窮覽洽聞,自呼於物無所不經,謂天下無切玉之刀,火浣之布,及著典論,嘗據言此事。其間未期,二物畢至。帝乃嘆息,遽毀斯論。事無固必,殆為此也。陳思王著釋疑論云,初謂道術,直呼愚民詐僞空言定矣。』(『抱朴子』論仙)→魏文帝・曹丕 は博覧で、自分に知らぬことなどないと豪語していた。天下に玉を斬る刀はなく、火浣之布なども『典論』という著作の中で存在しないものとして主張した。しかし、時を経ずしてこの二物が文帝に送られてきた。文帝は嘆息して、すぐさま今までの主張を捨てた。「物事に固執しすぎてはならない、これはこうだと決め付けてはならない。」という教えはこういう場合のことを言うのだろう。」・・・前述の『列子』も後述の『抱朴子』の論仙篇もそうですが、もともと「実在するかどうか」について道家の中でも議論のある部分です。『竹取物語』でも「得難きもの」として扱われたのでしょう。参照:鬼神の実在、仙人の実在。 http://plaza.rakuten.co.jp/poetarin/diary/201409140000/もう一つ。巨万の富を費やして海を捜索した「龍の首の玉」。これは『荘子』から。“「我弓の力は、龍あらばふと射殺して首の玉はとりてん。遲く來るやつばらを待たじ。」との給ひて、船に乘りて、海ごとにありき給ふに、いと遠くて、筑紫の方の海に漕ぎいで給ひぬ。いかゞしけん、はやき風吹きて、世界くらがりて、船を吹きもてありく。(中略)楫取答へてまをす、「神ならねば何業をか仕(つかうまつ)らん。風吹き浪はげしけれども、神さへいたゞきに落ちかゝるやうなるは、龍を殺さんと求め給ひさぶらへばかくあンなり。はやても龍の吹かするなり。はや神に祈り給へ。」といへば、「よきことなり。」とて、「楫取の御(おん)神聞しめせ。をぢなく心幼く龍を殺さんと思ひけり。今より後は毛一筋をだに動し奉らじ。」と、祝詞(よごと)をはなちて、立居なく呼ばひ給ふこと、千度(ちたび)ばかり申し給ふけにやあらん、やうやう神なりやみぬ。少しあかりて、風はなほはやく吹く。 楫取のいはく、「これは龍のしわざにこそありけれ。この吹く風はよき方の風なり。あしき方の風にはあらず。よき方に赴きて吹くなり。」といへども、大納言は是を聞き入れ給はず、三四日(みかよか)ありて吹き返しよせたり。濱を見れば、播磨の明石の濱なりけり。大納言「南海の濱に吹き寄せられたるにやあらん。」と思ひて、息つき伏し給へり。(『竹取物語』より)”『朱泙漫學屠龍於支離益、單千金之家、三年技成、而無所用其巧。聖人以必不必,故無兵、衆人以不必必之、故多兵。順於兵、故行有求。兵、持之則亡。』(『荘子』列禦寇 第三十二)→朱泙漫は支離益に龍を屠ふる技を学び、千金の財と三年の月日を費やしてその技を習得したが、結局、使うことはなかった。死を恐れない聖人は窮地においても、窮地としないから内に敵意がなく、死を恐れる世俗の人間は、窮地でなくても窮地にしてしまうから敵意ばかりになる。その敵意をむき出しにして、外に向うのだから、己を滅ぼすのだ。『莊子曰「河上有家貧恃緯蕭而食者、其子沒於淵、得千金之珠。其父謂其子曰『取石來鍛之。夫千金之珠、必在九重之淵而驪龍頷下、子能得珠者、必遭其睡也。使驪龍而寤、子尚奚微之有哉』今宋國之深、非直九重之淵也。宋王之猛、非直驪龍也。子能得車者、必遭其睡也。使宋王而寤、子為齏粉夫!」』(『荘子』列禦寇 第三十二)→荘子曰く「河上に葦ですだれを織って食いつなぐ貧しい家があったそうだ。その家の子供が、淵を潜って遊んでいるときに、川底で千金の珠を拾った。父親はその子に言った『こんな珠、石でも取ってきて砕いてしまえ。その千金の珠は九重の淵に棲むという黒龍(驪龍)の顎の下にある珠だ。お前が得たというのは、黒龍がちょうど眠っていた時だったからに違いない。もし黒龍が起きていたら、お前は髪の毛一本残さずに食われていたことだろう。』」(『荘子』列御寇 第三十二)ドラゴンボールを求める、ドラゴンスレイヤーによるドラゴンクエストのお話です(笑)。それぞれ「屠龍の技」、「 驪竜頷下の珠(りりょうがんかのたま)」と言いまして、『竹取物語』の大伴御行は、『荘子』の寓話と同じように龍に会うことすらできませんでした。列子について多く書かれた「列禦寇篇」からでして、『竹取物語』は列子の影響の方が最も強いです。ただし、日本の物語文学の歴史の中で、『荘子』の影響がはっきりと読める作品であることに変わりはありませんので、今のうちに。今日はこの辺で。
2015.05.06
コメント(0)
全1723件 (1723件中 1-50件目)