テーマ: 好きなクラシック(2399)
カテゴリ: クラシック音楽
『 今日のクラシック音楽
存命中からすでに伝説の指揮者と言われた謎の多いカルロス・クライバー(1930-2004)については、多くの人たちがそれぞれのブログなどに、彼への様々な想いを込めて書いておられます。 何も私がここにあらためて書き記すことはないのですが、私なりに彼の演奏などについての思い出を書いてみようと思います。

クライバーは1930年に20世紀の偉大な指揮者エーリッヒ・クライバーとアメリカ女性ルース・グッドリッチとの間に生れています。 父エーリッヒはナチスの政策の反対してアルゼンチンに移住しています。
父が著名な世界的名指揮者であったのに、カルロス・クライバーは音楽を勉強することを許されなかったそうです。 それでチューリッチの工科大学で化学を専攻する学生でしたが、音楽への道を進むことを諦めきれずに結局指揮者生活の道へと入っていき、いわば叩き上げの職人のように音楽を勉強したようです。 幼い時から両親の期待を一心に受けて音楽の英才教育によって、薔薇のごとく華やかな音楽生活をおくる演奏家とはまったく違う境遇での勉強だったのかもしれません。 まあ、その時には父エーリッヒ・クライバーからの指導もあったのかも知れません(これは憶測ですが)。
カルロス・クライバーは演奏するレパートリーが非常に少なく、そこへ録音嫌いもあってスタジオでのセッション録音はほとんどなくて、演奏会のライブ録音がほとんどです。
彼のレパートリーは、交響曲なら
ベートーベン 第4・第5・第6・第7
ハイドン 「驚愕」
シューベルト 第3・「未完成」
ブラームス 第2・第4
ボロディン 第2番
くらいでしょう。
オペラなら、
ヴェルディ 「椿姫」・「オテロ」、
プッチーニ 「ラ・ボエーム」、
ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」、
R.シュトラウス「ばらの騎士」、
ウエーバー 「魔弾の射手」、
J.シュトラウス「こうもり」
くらいでしょうか。 これらは残されているディスクからですが実際の舞台での他の曲の演奏はわかりませんが。
故朝比奈 隆先生もレパートリーが極端に少ない指揮者で、繰り返しベートーベン・ブラームス・ブルックナーを基軸にシューベルト、シューマン、チャイコフスキー、マーラーを振るのみでしたが(晩年は3Bに限られていたようですが)、それでもクライバーに比べると多いですね。
カルロス・クライバーの演奏の特徴は、非常に豊かな音楽的生命力に富んでいることだと思います。 それに驚異的とも言えるクライバー特有の弾力性のあるリズムと、テンポが迅速とも言えるほどの速いテンポ。 テンポは速くてもとてもしなやかさのある旋律の描き方。 強い意志を感じさせながらも強靭さだけで終わらないダイナミックな軽やかさ。
私は一度だけカルロス・クライバーの演奏会を客席で聴いたことがあります。 オーケストラはアムステルダム・コンセルトへボー管弦楽団。 プログラムはベートーベンの交響曲第4番と第7番。 場所はオランダ・アムステルダム・コンセルトへボーで1983年10月20日でした。
しなやかな棒さばきに酔い、彼自身が音楽であるかのような身の動きに楽章が終わるごとにため息をついていました。 そう、カルロス・クライバーの指揮姿そのものが芸術を感じさせる稀有な指揮者と言えるでしょう。
これは現在DVDとしても記録されてリリースされています。
おそらくこれほどまでに音楽の持つ魅力を外に向かって爆発させるような表現をする指揮者は、過去でも現在でもいないのではないでしょうか? わずかに似た演奏をする人にバーンスタインがいますが、彼のテンポは逆に非常に遅いので、比較にはなりません。
クライバーの演奏を聴いていますと、音楽に感じた本能をそのままに、純粋無垢に表現しているのかも知れません。 感情などは皆無と言えるほどに高い音楽性が生命力を持って迫ってくるような表現なのです。 他の伝説的指揮者(フルトヴェングラー、ワルター、カラヤン、トスカニーニ、バーンスタインなど)が音そのものに血と感情を通わせて表現しているのとは対極にあるクライバーの表現と言えるでしょう。
音楽をこのように表現できるのは、もう天才としか言いようのない指揮者ではないでしょうか。 こういう指揮者はもう二度と現れないかもしれません。
しかし、「しかし」なんです。 確かに彼の演奏を客席で聴いて上述のように感じ、まるで非の打ち所のない出来栄えに感動を味わいましたが、それは多分に外面的なものとして心に残ってしまい、いい例ではありませんが最高のスポーツカーで快適そのものの感触を味わっているのですが、下りてみればそれまでといった感じが私には残ります。 これはいつディスクを聴いても同じなんです。
上に書きましたように他の名指揮者のように血と感情を音として表現することが絶対である人たちとの温度差かもしれません。 誤解のないように言いますが、決してクライバーの演奏は感情がないと言っているのではありません。 速いテンポで見事に旋律の美しさ、リズムの素晴らしさを表現しているのですが、ホームを駆け抜けていく「のぞみ号」のような快適さだけが残ってしまいます。
そこが私をクライバーファンにしない理由かもしれません。
それに比べるとオペラは違います。 歌手の歌によって楽しめるオペラは絶対音楽とは違う感動をもたらしてくれます。 劇としての表現を楽しめて、音楽が湧き起こってくるかのようで、リズムは沸立って生命力に燃えており、緊張感とニュアンスが素晴らしく、聴いたあとでもいつまでも心に残ります。 私が最も好きなクライバーの振ったオペラでは「椿姫」で、ここに書きました全てを味わえる素晴らしい演奏・録音です。
2004年の今日(7月13日)、カルロス・クライバーは伝説のまま74歳の生涯を閉じています。
愛聴盤 ベートーベン交響曲第4番・第7番 コンセルトヘボー管弦楽団
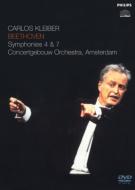
(Philips Classic 0701009 1983年10月19日ー20日 海外盤DVD)
ヴェルディ オペラ「椿姫」
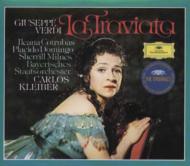
(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30149 1976-77年録音)
バイエルン国立歌劇場管弦楽団・合唱団 イレアナ・コトルバス、プラシド・ドミンゴ、シェリル・ミルンズ他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『 今日の音楽カレンダー 』
1915年 没 アルノルト・シェーンベルグ(作曲家)
1924年 誕生 カルロ・ベルゴンツィ(テノール)
2004年 没 カルロス・クライバー(指揮者)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ともの『 今日の一花 』 ネコジャラシ


撮影地 大阪府和泉市 2006年7月06日
存命中からすでに伝説の指揮者と言われた謎の多いカルロス・クライバー(1930-2004)については、多くの人たちがそれぞれのブログなどに、彼への様々な想いを込めて書いておられます。 何も私がここにあらためて書き記すことはないのですが、私なりに彼の演奏などについての思い出を書いてみようと思います。

クライバーは1930年に20世紀の偉大な指揮者エーリッヒ・クライバーとアメリカ女性ルース・グッドリッチとの間に生れています。 父エーリッヒはナチスの政策の反対してアルゼンチンに移住しています。
父が著名な世界的名指揮者であったのに、カルロス・クライバーは音楽を勉強することを許されなかったそうです。 それでチューリッチの工科大学で化学を専攻する学生でしたが、音楽への道を進むことを諦めきれずに結局指揮者生活の道へと入っていき、いわば叩き上げの職人のように音楽を勉強したようです。 幼い時から両親の期待を一心に受けて音楽の英才教育によって、薔薇のごとく華やかな音楽生活をおくる演奏家とはまったく違う境遇での勉強だったのかもしれません。 まあ、その時には父エーリッヒ・クライバーからの指導もあったのかも知れません(これは憶測ですが)。
カルロス・クライバーは演奏するレパートリーが非常に少なく、そこへ録音嫌いもあってスタジオでのセッション録音はほとんどなくて、演奏会のライブ録音がほとんどです。
彼のレパートリーは、交響曲なら
ベートーベン 第4・第5・第6・第7
ハイドン 「驚愕」
シューベルト 第3・「未完成」
ブラームス 第2・第4
ボロディン 第2番
くらいでしょう。
オペラなら、
ヴェルディ 「椿姫」・「オテロ」、
プッチーニ 「ラ・ボエーム」、
ワーグナー 「トリスタンとイゾルデ」、
R.シュトラウス「ばらの騎士」、
ウエーバー 「魔弾の射手」、
J.シュトラウス「こうもり」
くらいでしょうか。 これらは残されているディスクからですが実際の舞台での他の曲の演奏はわかりませんが。
故朝比奈 隆先生もレパートリーが極端に少ない指揮者で、繰り返しベートーベン・ブラームス・ブルックナーを基軸にシューベルト、シューマン、チャイコフスキー、マーラーを振るのみでしたが(晩年は3Bに限られていたようですが)、それでもクライバーに比べると多いですね。
カルロス・クライバーの演奏の特徴は、非常に豊かな音楽的生命力に富んでいることだと思います。 それに驚異的とも言えるクライバー特有の弾力性のあるリズムと、テンポが迅速とも言えるほどの速いテンポ。 テンポは速くてもとてもしなやかさのある旋律の描き方。 強い意志を感じさせながらも強靭さだけで終わらないダイナミックな軽やかさ。
私は一度だけカルロス・クライバーの演奏会を客席で聴いたことがあります。 オーケストラはアムステルダム・コンセルトへボー管弦楽団。 プログラムはベートーベンの交響曲第4番と第7番。 場所はオランダ・アムステルダム・コンセルトへボーで1983年10月20日でした。
しなやかな棒さばきに酔い、彼自身が音楽であるかのような身の動きに楽章が終わるごとにため息をついていました。 そう、カルロス・クライバーの指揮姿そのものが芸術を感じさせる稀有な指揮者と言えるでしょう。
これは現在DVDとしても記録されてリリースされています。
おそらくこれほどまでに音楽の持つ魅力を外に向かって爆発させるような表現をする指揮者は、過去でも現在でもいないのではないでしょうか? わずかに似た演奏をする人にバーンスタインがいますが、彼のテンポは逆に非常に遅いので、比較にはなりません。
クライバーの演奏を聴いていますと、音楽に感じた本能をそのままに、純粋無垢に表現しているのかも知れません。 感情などは皆無と言えるほどに高い音楽性が生命力を持って迫ってくるような表現なのです。 他の伝説的指揮者(フルトヴェングラー、ワルター、カラヤン、トスカニーニ、バーンスタインなど)が音そのものに血と感情を通わせて表現しているのとは対極にあるクライバーの表現と言えるでしょう。
音楽をこのように表現できるのは、もう天才としか言いようのない指揮者ではないでしょうか。 こういう指揮者はもう二度と現れないかもしれません。
しかし、「しかし」なんです。 確かに彼の演奏を客席で聴いて上述のように感じ、まるで非の打ち所のない出来栄えに感動を味わいましたが、それは多分に外面的なものとして心に残ってしまい、いい例ではありませんが最高のスポーツカーで快適そのものの感触を味わっているのですが、下りてみればそれまでといった感じが私には残ります。 これはいつディスクを聴いても同じなんです。
上に書きましたように他の名指揮者のように血と感情を音として表現することが絶対である人たちとの温度差かもしれません。 誤解のないように言いますが、決してクライバーの演奏は感情がないと言っているのではありません。 速いテンポで見事に旋律の美しさ、リズムの素晴らしさを表現しているのですが、ホームを駆け抜けていく「のぞみ号」のような快適さだけが残ってしまいます。
そこが私をクライバーファンにしない理由かもしれません。
それに比べるとオペラは違います。 歌手の歌によって楽しめるオペラは絶対音楽とは違う感動をもたらしてくれます。 劇としての表現を楽しめて、音楽が湧き起こってくるかのようで、リズムは沸立って生命力に燃えており、緊張感とニュアンスが素晴らしく、聴いたあとでもいつまでも心に残ります。 私が最も好きなクライバーの振ったオペラでは「椿姫」で、ここに書きました全てを味わえる素晴らしい演奏・録音です。
2004年の今日(7月13日)、カルロス・クライバーは伝説のまま74歳の生涯を閉じています。
愛聴盤 ベートーベン交響曲第4番・第7番 コンセルトヘボー管弦楽団
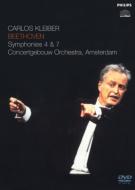
(Philips Classic 0701009 1983年10月19日ー20日 海外盤DVD)
ヴェルディ オペラ「椿姫」
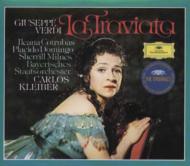
(ドイツグラモフォン原盤 ユニヴァーサル・ミュージック POCG30149 1976-77年録音)
バイエルン国立歌劇場管弦楽団・合唱団 イレアナ・コトルバス、プラシド・ドミンゴ、シェリル・ミルンズ他
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
『 今日の音楽カレンダー 』
1915年 没 アルノルト・シェーンベルグ(作曲家)
1924年 誕生 カルロ・ベルゴンツィ(テノール)
2004年 没 カルロス・クライバー(指揮者)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ともの『 今日の一花 』 ネコジャラシ


撮影地 大阪府和泉市 2006年7月06日
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[クラシック音楽] カテゴリの最新記事
-
「ニーベルングの指輪」の魅力 2009年02月04日
-
ワーグナー 指輪物語/山茶花 2009年01月19日 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
コメント新着
ifJU8X Really enjoyed this blog article.Much thank@ ifJU8X Really enjoyed this blog article.Much thanks again. Great.
ifJU8X Really enjoyed this blog article…
ONY72s I cannot thank you enough for the post. Wil@ ONY72s I cannot thank you enough for the post. Will read on...
ONY72s I cannot thank you enough for th…
フリーページ
© Rakuten Group, Inc.











