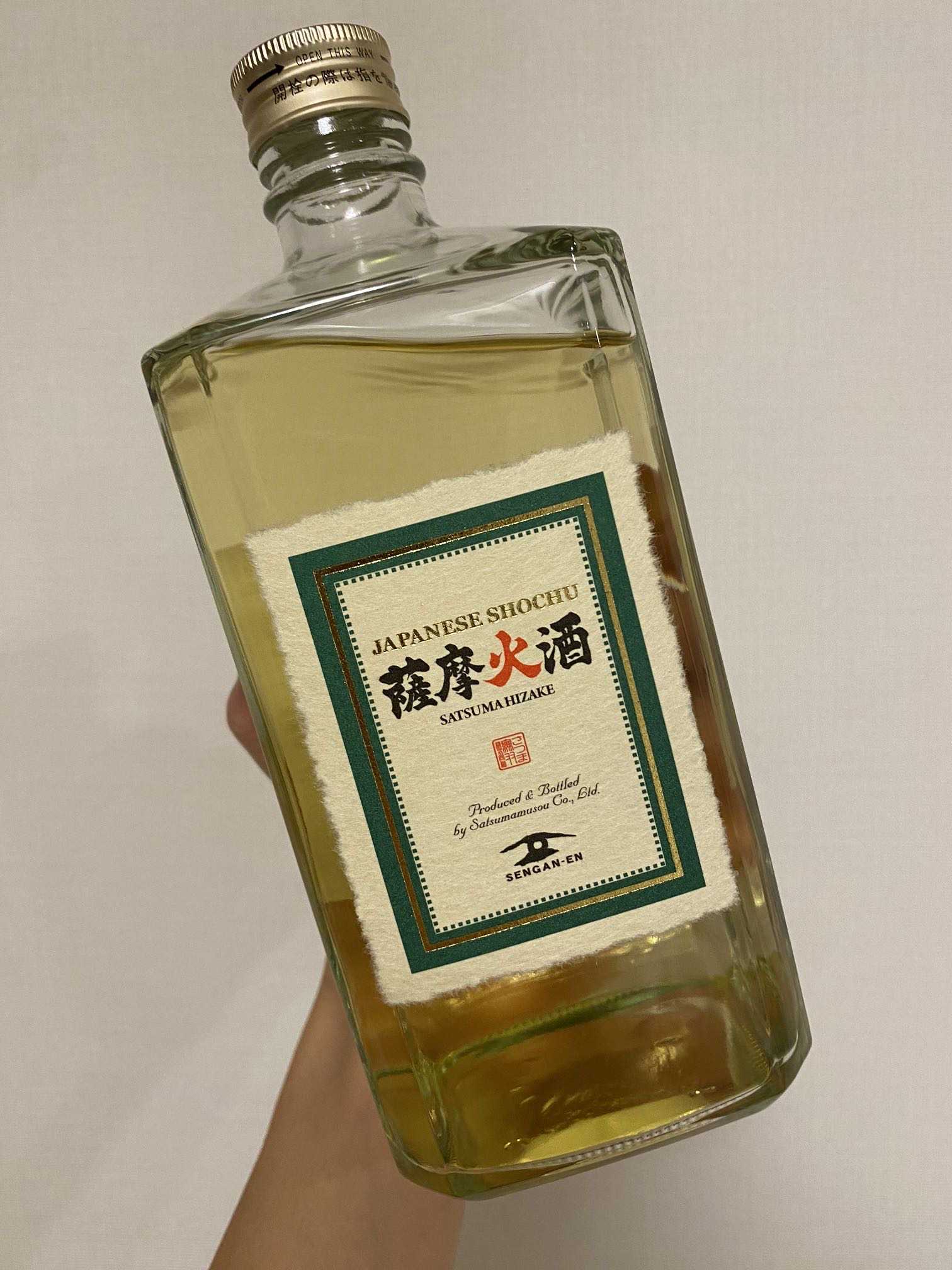2007年01月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

トライアスロンを浜離宮恩賜庭園で
日経新聞によれば、東京都は、東京湾近辺の水質浄化等により、2016年の夏期五輪で、浜離宮恩賜庭園付近の隅田川河口でトライアスロンを開催する計画であるという。このため人が安心して泳げる水準まで浄化する必要があるという。都は同時に水辺空間を観光に活用し海外客を呼び込む計画だという。しかしながら、浜離宮恩賜公園からみた景観は、池に浮かぶ茶室の背景に汐留シオサイトの超高層群がそびえ立っている。浜離宮をおとずれたときに、不思議なことに日本人は何も感じていないようであったが、フランス人と思しき外国人たちは、驚きの声をあげて、写真をとっていた。歴史的景観の中に、現代の超高層ビルがそびえると言う構図は、フランスのパリに、1970年頃に、モンパルナスタワーを建てて失敗して以降、パリ市民により拒絶されてきた歴史がある。こんな景観のところに、海外客をよびこもうとしても果たして思惑通りになるのだろうか。それにしても、1)カキや水生植物による水質浄化実験2)生物が生息できる海岸や護岸整備3)河川の汚泥除去の三事業による浄化作戦はオリンピックや観光のためばかりでなく、日本の国民にとって重要な課題であろう。
Jan 31, 2007
コメント(0)
-
イスラムが13億人の新経済圏に
日経新聞によれば、アラビア語で帰依、服従を意味するイスラムを信じる国家=国民が、北アフリカから中東を経て東南アジアに至る一帯に展開し、その数が十三億人にのぼるという。今後二十年で、世界人口の三分の一がイスラム教徒になるとの予測もある。イスラム教徒は、7世紀以来、西洋世界をしのぐ繁栄を謳歌したこともあったが、一部の王侯貴族を除いては、自然との対話の中に生きる、素朴な生活をおくる人々の集合であった。西洋社会の産業革命とは縁のない生活で、第1次産業と第3次産業の交易で生活をつづけてきた。イスラム教徒の中にも、経験なイスラム教徒と、そうでない、アルコールを飲みお祈りをしないイスラム教徒が居るのは事実であるが、長い歴史の中で、西洋社会に比べると、信仰により、心が満たされれば幸せであるという心的福祉の信仰が普及していて、西洋社会の様に、物が満たされれば幸せであるという物的福祉の考え方とは、かけ離れた生活をしてきた多くの国民がいた。従って、国民一人当たりの地球環境に与える負荷のようなものは、西洋諸国に比べ物にならない程低く、大きな人口を持っても、西洋諸国の地球環境汚染に比べれば、たいしたことがないはずであった。しかるに、イスラム諸国は石油の生産国であるところが大きく、昨今の石油収入の増大で、地球環境問題対策の新エネルギー技術の発展の前に、石油マネーで、膨大な開発行為を行い、生活水準をあげ、観光などで、自立できるようにしようとしているようである。これは、イスラム教徒が、心的福祉から物的福祉に変化しつつあることをしめしており、地球環境問題への環境負荷の原因とはあまり考えられていなかった人々が、物欲の固まりとなり、物質を変化させ、正のエントロピーを地球環境システムの中で急激に増大しようとしているという恐ろしい構造である。中国やインドにしたって、かつては、自然との対話の中に生活してきた人々が多かったが、昨今の、経済発展の中で、心的福祉ではがまんできず、物的福祉を追い求める国民を急激に増大している。地球温暖化問題で、先進国がCO2削減を要求されてきたが、これからは、中国、インド、イスラムなどの、心的福祉がくずれて、物的福祉を追い求める様になった国々に対しても、現実に差し迫った問題として、環境問題を配慮した持続可能な発展を目指す様に、心がけてもらう必要が、緊急の事態となっている。日本やヨーロッパは環境技術に秀でているというが、こうした旧発展途上国の変身に対して、最先端の技術をもって、環境調整を先に立って進めてゆく必要がある。イスラムの人々には、豊かな生活というものが、本当は、物的福祉により得られる物ではなく、心的福祉により得られる物であることをイスラムの原点に遡って、理解してもらわなければ、地球が水の星でなくなる日も急激に早くなる危険性が極めて大であろう。
Jan 30, 2007
コメント(0)
-
教育改革には都市計画や建築計画の改善が必要
近頃、教育改革が叫ばれているが、学科の内容はともかく、子供達のしつけや道徳の改善には、学校の内部だけの問題だけではなく、親子関係や子供達の環境の改善が必要である。都市計画的には、子供の通学環境や遊びの環境が昭和の中頃から激変し、草野球や鬼ごっこや川遊びなどのできる広場とか神社仏閣の境内や、小川とか、森とか、路地だとかがどんどん失われている。子供達はそうした空間関係を通じて、子供達の間での人間関係を学習し、また、ヒバリやスズメ、カブトムシ、クワガタ、メダカ、ザリガニ、コオロギ、バッタ、デンデンムシなどを通じて、生命の神秘や大事さを学習してきた。そうした環境を、都市への人口集中や人口減少社会を迎えても止むことないマンションの建設を通じて、破壊され、子供達は、同世代間の人間関係や生命の大事さを学習することが出来なくなっている。建築計画的には、伝統的な日本の住居が主として機能的理由から壊され、それにかわって、いわゆるnLDK(2LDKとか3LDKなど)型の一戸建て住宅やマンションへの居住に変わっている。これは、伝統的な住居が、部屋と部屋が縁側で結ばれたり、襖や障子で仕切られていて、ハレの時などには、一体化した空間として使われ、ケ(普段)の時には、個々の空間として使われていたことにより、家族間の関係を、完全なプライベートの関係ではなく、ゆるやかな、プライバシーとゆるやかな、密接関係とに関係づけるに役立っていたと言える。それに対し、nLDK型では、子供たちはひとりひとつずつ個室を持ち、親も主寝室に就寝し、親子が顔をあわせることができるのは、空間的にはLDだけになって、必要以上の家庭内プライバシーを強制するようになっている。空間関係が人間関係に投影されているのである。世代間で監視や見守るという意識を空間が奪っているのである。さらに、父親などの労働環境から、日本人は夕方5時の終業時間になっても帰宅しないし、職住接近の都市計画にもなっていない。従って、特に父親が子供と顔を合わせる時間が住宅の空間的特徴とあわせて、ほとんど無くなり、父親の存在が希薄になっている。さらに、給料が銀行振込で支払われることにより、ますます、父親の権威が喪失してくることになった。子供と向き合うことが出来るのが、母親だけとなり、家庭内の教育が母親の重荷となり、母親にもストレスがたまるようになった。伝統的日本の住居では、親の親世代、すなわち、お爺さんやお婆さんと一つ屋根の下の空間を共有していたため、家族関係も、そのように構造化されていたが、孫の存在を緩やかに見守り、家庭内環境を緩やかに制御していたお年寄りがいないため、母親の子供の教育に関する負担はますます増えていると考えられる。都市の内部では、高層住宅がどんどん建てられているが、小さい子供は、高層住宅の外の世界に一人で出て行くことが少なくなり、外の世界で以前は自然に養われていた、同世代間の人間関係や生命の大事さを経験するのが、学校などにいる時間に限定されるようになった。しかも、学校から帰っても、nLDK型の住居の中の子供の個室にひきこもり、インターネットなどだけが、外の世界との交流となる世の中になっている。このように、最近問題になっている教育改革ではあるが、学校の内部に起因する現象よりも、都市の中やまちづくりや、建築計画特に住宅の空間関係や環境に起因する現象の方が重大であると考えられる。従って、戦後培われてきた都市計画や建築計画は人間の空間として見直しが必要な時期が来ていると考えられる。
Jan 29, 2007
コメント(0)
-
地球を冷やす
地球温暖化問題は、太陽エネルギーに対し不透明な温暖化ガスの濃度が産業革命以前の自然状態に近い地球環境に比べて絶対的に高くなっていることによる。従って、根本的解決には、温暖化ガスの濃度を下げる方策を創案する必要がある。その一つが、温暖化の影響力が多いCH4をメタンハイドレイトとして海底に埋蔵する方法であろう。同様に、CO2をドライアイスとして固定化する方法があろうか。しかし、いずれにせよ、メタンハイドレイトやドライアイスを生成する時のイニシャル=エネルギー=コストがどの程度であるかが問題となるし、安全性があるかどうかが問題になる。安全性と言えば、緑色植物利用によるCO2吸収があるが、これについては、各方面で既に試みられつつある。地球の歴史を紐解くと、地球の温度が低下するきっかけとなった状況として、隕石の衝突などにより、地球の内部の物質が大量に大気圏内に放出されたり、火山の大噴火により同様なことが生じた場合がある。これに類する方法で、宇宙から大気圏内に降り注ぐ太陽エネルギーを調節する方法がないかと言えば、雲による日影が定常状態より多い状態が或程度続く場合が想定されるだろう。すなわち、雲が多くなって、外から来る負のエントロピーである太陽エネルギー(特に赤外線)を反射することができるならば、地球温暖化を軽減できるのではないかと考えることもあり得るのではないかと期待する。また、雲と雨はつきものであるから、同時に、淡水資源を乾燥地などに降り注ぐことも出来、ついでに緑色植物を増やせるのではないかと期待することも出来るかもしれない。地球の水と大気の循環システムを操作するのは、ある意味で非常に危険なことであり、地球温暖化問題とは、個別の問題解決というよりはシステムの問題であるから、その道の専門家達に十分なシミュレーションを行った上で、検討していただければ、思わぬ結果に繋がることもあるかもしれないと期待する次第である。
Jan 28, 2007
コメント(0)
-
本物の逸品を作れ
情報社会に入ったためかもしれないが、消費者の希望に従ったオン=デマンドな商品を作るというのが、時代の流れだと宣伝する御用学者などがいたりする昨今であったが、本当にそれでいいのであろうか?結果として、工業製品などは、オン=デマンドとはいかないまでも、消費者の消費動向にこびへつらったもののオンパレードとなり、ニューヨーク近代美術館などに展示されるようなレベルの高い製品が相対的に減っているのではないかと感ぜられる今日この頃である。レベルの高さの視点にはいろいろとあると思われるが、たとえば、長く使っても飽きのこないデザインというのがあるであろう。かつてインダストリアル=デザインの大学の講義で、ちょっと見た目に良くて、使っているとすぐに飽きがくるものが、インダストリアル=デザインの商品として経済性が高いようなことを教えていたが、資源=エネルギー=環境問題の最中の現在ではそんなデザインでは環境に良くないことは明らかである。省エネ技術や環境技術によりランニング=コストが減るからと言って、新しい工業製品などにどんどん転換することを推進するような方向に経済が動いているようであるが、新しい工業製品へ、長く使い込んだ逸品から変更するときにかかるランニングコストや廃棄コストは計算に入っているのであろうか。また、次から次へと新製品に変えてくなかで、商品にたいする愛着というものが本当にうまれてくるのであろうか。そうした、様々な点をかんがえると、工業製品や商品のデザインは、長く使い込んでよさが分かるようなもの、長く使い込んでもよさが損なわれないものすなわち、ほんものの逸品をめざすことが必要であり、消費者に単純に媚びないそうしたデザインのあり方こそが、21世紀のものづくりのあり方であるのではないだろうか。本当にいいものにものづくりを限定すること、インダストリアル=デザイナーやグラフィック=デザイナーのマスターベーションにおつきあいするのではなく、安くても、本物の逸品を生み出していく必要がある。そうすることで、工場等の生産ラインが単純化され、よけいな部材を大量に作ることなく、化石燃料資源の消費を最小限にすませ、ものづくりのイニシャル=コストを最低限にすることができ、資源=エネルギー=環境問題に良い結果をもたらす他、人々の、ものに対する愛着を生み出す力となるのではないだろうか?また、本物の逸品であっても、少品種大量生産でえられるならば、相対的に価値のあるものが、安い値段で手に入ることになる。21世紀の資源=エネルギー=環境問題は、デザイナーや生産者のマスターベーションや、みかけの、経済の回転性に左右される時代はもう終わりであることを暗示しているのではないかとおもわれる今日この頃である。製品の種類を作らなくていいから、ほんとうに人の心を和ませる本物の逸品をリーズナブルな価格で提供することが、サステナブル=デベロップメントにつながることを、考え直す必要があろう。
Jan 27, 2007
コメント(0)
-
ホリエモン、法廷で涙ぐむ
ライブドア騒動も一区切りを迎え、3月16日には、判決がでるという。今日で、検察と容疑者ホリエモンの最終弁論は終了したもようである。ホリエモンが逮捕されて1ヶ月くらいしたところでこのブログに書いた次のような記事を思い出した。Mar 1, 2006努力をしても報われない国 「つ ぶ や き(274)」 TBSのNEWS23で、日本の子供達の勉学における向上心がなくなりつつあると言う統計を発表した。そして、今の日本が子供達の心に「努力をしても報われない国」と映っていると評していた。一方、テレビ朝日の報道ステーションでは、ホリエモン・ショックを取り上げ、若い企業家たちに、努力をしても報われない印象を与えていることが論じられていた。マスコミも、ホリエモン・ショックで、今まで、マスコミで祭り上げてきたホリエモンを今回の逮捕で、手のひらを返したように報道しすぎたことに、異論が生じはじめていることを伺わせた。一部の専門家によれば、ホリエモンの一連の投資行為は、資本取引にあたり、それまで、タブーとされてきたことにあたるという。しかし、そんなに簡単に言い切ることができるのであろうか。人類の歴史は、常に、新しい概念を生み出してきており、もしかすると、ホリエモンらにより開発された虚業による資本取引は、資本取引されたとたんに、市場価値を認められ、ある種の実業になるのではないかという議論もあるようである。これにより、開発された投資行為がリファインされれば、日本がかかえている770兆円とも言われる、債務を減少させることができるテクニックが開発される可能性をも潜めているのではないかと、期待することはいけないことなのであろうか。そもそも、ITや、特にソフトウェア産業は、ホリエモンの虚業ほどでないにしろ、ものづくり等のいわゆる実業に比べて、自分で負荷価値を作り出してしまう、虚業的体質をもっているものであり、そういうものの積み重ねのなかで、新しい価値や思想が生み出されているのではないだろうかという疑問に誰か答えてほしい。第二次産業から第三次産業が生れたとき、第二次産業は実業としても、新しい第三次産業は、虚業的性格にみられていたことはなかったのだろうか。一方で、地球環境問題を背景として、20世紀の科学やものづくりやハードウェア産業は、物的福祉の方法として、地球環境に負の影響をあたえるものとして、変換をもとめられているか、消滅することが求められているようなものではないのだろうか。それに対して、これから、生み出されてくる当初は虚業と思われるような、ソフトウェア産業こそが、物的福祉の方法を減少させて、地球環境に与える人間一人あたりの負のエントロピー等の影響をあたえるものとして、評価されるべきなのではないか。教えてほしい。その究極の形として、物的福祉から心的福祉への移行こそが、これからの時代に求められているものなのではないのだろうか。文字通り心的福祉を追求すれば物的福祉のような物的実業によるCO2やエントロピーの増大を最小限に食い止めることができるようなものではないのだろうか。物事に、物的情報の取引を超えて、価値や意味を見出すことが、今後の情報社会であり、また、シャロンの情報理論に欠けているところであり、多くの人々のコンセンサスを得て、価値や意味を創造したのであれば、ホリエモンのやったことは、物を動かさず、価値や意味を、他の企業の債権や株式との関係により生み出していた、新しい遣りかたの兆しであったのではなかったのか。そのままの方法で、日本国民の770兆円の負債を解消できるような方法になるとはおもわれないが、より、エラボレートすることで、その手助けになるような理論的裏づけをえることにならないのか。そして、既得権者の国日本で、若者達に、既得権を乗り越えて、環境にやさしく、経済を持続させ、場合によっては、物的福祉の社会を最小限にし、心的福祉とのバランスのとれた社会を実現するきっかけとなる手法をうみだすことはできないのであろうか。世の中は、新しい価値や意味を生み出す情報にもっと寛容になるべきではないだろうか。地球環境問題を持続的に解決するやりかたを本当に生み出しうるのは、そうした、元虚業で、新しい実業に移行してゆく産業なのではないだろうか。
Jan 26, 2007
コメント(0)
-
道州制とからめて省庁再々編
日経新聞によれば、安倍首相は、「道州制とのかかわりもある。あるべき省庁の姿を検討してほしい」と具体案の検討を進める様に自民党の中馬弘毅行政改革推進本部長に指示したという。道州制では、日本の国家を代表する中央政府には、国家統合を担う憲法の下に、外交と防衛を担ってもらう必要があるが、道州の固有の文化と持続的発展を進めるためには、道州固有の自治と、人口誘致と、産業誘致と環境=都市=農業政策が必要であろう。そのためには、法律は基本的に道州のものとし、公務員や免許、資格などは基本的に道州のものとし、地域性に合った税制が必要であり、それにより、産業誘致と人材誘致が道州の文化的な創造力を喚起するようにしなければならない。美しい国を作るには、地域に合った多様性ある文化と伝統をもった市民を育てなければならない。教育も地域独自の文化と伝統を育て上げるものとしなければならない。現在の中央官庁主導による中央集権的な官僚機構は、画一的な行政指導に陥りやすい欠点をもっていたが、一方で、優秀な人材も集めるだけの魅力をもっていたのだろう。従って、道州に解き放ち分散してゆくことになっても、道州の新しい活力を生み出すだけのポテンシャルを有していることであろう。地方に埋もれた人材との融合を計ることにより、他の道州との間で、自由競争原理が働くことにより、独自性と、協調性と、競争力を養うことが出来るだろう。21世紀の環境行政などは、地域に合った創案が必要であるとともに、日本共同体、あるいは、東アジア共同体としての連携した行動が必要である。それは、外交や防衛と類似点を有しているだろう。総じて、宇宙船地球号の市民として、日本人が参加しアイデンティティを持たさせるための、グローバルな対話と協力を担う部門は、日本の中央政府が担い、個々の市民の生活や生命を活性化させるためのローカルな奉仕(サービス)とコミュニティーを担うのが道州以下の地方公共団体となるのではないだろうか。
Jan 24, 2007
コメント(0)
-
21世紀環境立国戦略策定へ
日経新聞夕刊によれば、1月23日午前、安倍首相は、若林環境相に対し、環境問題への取り組みとして、「21世紀環境立国戦略」を3月末までに策定するように指示したという。地球温暖化対策や環境面での途上国支援などを盛り込む見通しであるという。「世界の環境問題で日本がリーダーシップを発揮し、貢献すべきだと考えている。」と表明したという。環境問題のリーダーシップをとることが、今後の日本の持続的発展にとって重要であると言う認識が出来た模様である。一方で、日経新聞によれば、中東経済、の成長に陰りがでており、原油下落や、国際的な脱石油資源の流れがでていることが原因であろう。これに関連し、以前のブログで、以下のような記事を書いて、安倍内閣の目安箱にも投稿していたことを思い出した。Dec 6, 2006サウジアラビアでメガ経済都市 「つ ぶ や き(274)」 [ 建築・都市・建築家 ] 日経新聞によれば、世界最大の産油国サウジアラビアは、産業多角化による長期的な安定成長を実現するため、国内6箇所にメガ経済としを新設し、人口増による厳しい雇用環境を解消し、若年層によるサウジ王室批判を緩和するねらいという。事業費は今後10-15年で約14兆円を見込んでいるという。一方で、大量の化石燃料資源の消費(正のエントロピーの発生)に対し、今後先進各国の技術力向上により、バイオ系の燃料や資源の活用による、化石燃料の消費の最小減化が始まると予想される。それに対して、石油生産各国が、石油に依存しない経済体制をできるだけはやく構築することを考えていることと予想される。サウジやアラブ首長国連邦などのメガ経済都市建設は、こうした将来展望によるものとも考えられよう。バブルの直前頃、仕事でサウジアラビアに行くことが何回かあったが、首都のリヤド空港に飛行機が近づいたのがわかるだいぶ前から、何にもない砂漠地帯に向けて、飛行機が下降をはじめるのが記憶に残っている。そして、何にもない砂漠の中に、リヤド空港がポツンと見えるか見えないかのうちに着陸してしまうくらい、サウジアラビアには、広大な砂漠地帯が広がっている。仕事は、サウジアラビアの中の、地下水を利用した、ピボットシステムによる円形の農場の展開する農業地帯、アルカシムに、総合大学を計画設計することであった。その大学は、その後、20年くらい経つが、農学部だけができてホームページがあり、他の部分はどうなっているのかわからない。当時も、サウジ王室に反対する勢力のいる地方の懐柔政策ということで、計画されていたのであるが、計画だおれで、ほとんど実現していない。今回の計画も、全ての計画が実現されるかは、国内情勢と、石油情勢などを天秤にかけての話となることであろう。先進各国で、バイオマスを利用したエネルギー改革の進展が早くすすめば、できるだけ、早く、石油価格が下がらないうちに、石油資源により回収できる資産を獲得する努力をすることになろう。
Jan 23, 2007
コメント(0)
-
界面活性剤も植物系で量産に
1月18日付の日経新聞によれば、ライオンは、衣料用洗剤の洗浄成分となる植物系原料(界面活性剤MES(メチルエステルスルフォネート))を2008年から量産をするという。マレーシアに工場建設し、自社以外にも欧米の洗剤メーカーなどに提供する。1991年にライオンが世界で初めて商業生産に成功し既に一部の洗剤で使われている。パーム油やヤシ油から生産する。バイオ燃料や、プラスチッックになるポリ乳酸だけではなく、界面活性剤にも植物系の石油代替資源が量産されつつあり、CO2発生が抑制された、地球環境に優しい工業生産が、バイオ系で実現しつつあるようである。
Jan 22, 2007
コメント(0)
-
法隆寺の伽藍が赤かった時 NO.2
東京都にもホームページに目安箱があることが分かったので、以下の記事を、そちらにも投稿してみた。東京都のは、首相官邸のホームページと違って、匿名(名前を書かないこともできるが)でないが、投稿者の名前を調べて、どうするつもりなのだろうか?Dec 20, 2006法隆寺の伽藍が赤かった時 「つ ぶ や き(274)」 [ 建築・都市・建築家 ] 12月14日の日経新聞によれば、東京都は景観規制で、2007年4月に施行する都の改正景観条例で都内全域で高層建築物の外観色を一定範囲内に抑えるという。外観色の規制では23区内が60m以上、多摩など23区以外の市町村では45m以上の高さの建物が対象となる見通しである。色の選別では、人間の視覚を基に客観的な尺度として使われているマンセル記号により、色相、明度、彩度を用い都では明度と再度を「落ち着いた色彩」の数値内におさめる考えという。要するに、汚い既存の街並にあわせて汚れた色の建物としろと言っているようなものである。美しい街並を造るのであるならば、原色の彩度や明度の高い色の建物であっても美しくなるような形態の建築を配置しなければおかしいのではないか、と建築家仲間で議論となっている。法隆寺のような美しい建築は、現在では時間が経ち、古色に彩られているが、もともとは赤い朱のようなものが塗られていたことは実物をみればだれにでもわかる。イタリアの街並を形成している伝統的建築も、時間の経過とともに汚れているが、もともとは彩色豊かであったものが多いし、豊かな色彩であるが故に世界遺産になったものもある。ギリシアのパルテノン神殿の妻側などは、原色でぬられていたことが分かっている。日光の東照宮のカラフルな色彩の境内の彩度や明度を落とせという人はいないだろう。これらの例にみるまでもなく、黄金比などで美しい形態に整えられたプロポーションの良い建築は、原色でぬりわけても美しい絵画や彫刻のように美しいのである。美しくなる可能性のある建築を汚れたきたない街の色に統一しろというのは、汚れたきたない建築にしろと言っているのと同じである。現在の日本の戦後建築は美しく無いものが多い。それにあわせて、美しく無い街並を形成するというのはまちがっている。50年もたたないうちに、現在の美しく無い建物は、機能的に消えてなくなる運命にある。本当に美しい街並をつくろうというのであるならば、原色に塗り分けても美しいプロポーションの建築を建ててゆき、50年後や100年後に現在の汚い建物がなくなっていったときに美しい街並になるようにしなければならない。そもそも、デザインが出来るかどうか分からない人や美しい建物を造る自信のない人たちが、審査会などで幅を利かしているのではないかと考えたくなる消極的な考え方である。普通の建築をつくる建築士には、月並みな建物しかつくらないから、冴えない色のめだたない建物にしてもらう方がよいということもあるかもしれないが、一律に色彩制限をして、21世紀を代表する大建築となる可能性のある建築を平凡な建物としてしまう失敗をしないようにしなければならない。建築意匠や建築史の大家、あるいは、活躍している建築家などデザインの分かる人を集めて委員会を構成し、審査に合格した建物だけでもよいから、美しい色彩の美しいプロポーションの建築で21世紀の街並を構成するように頭を切り替える必要があるのではないか?
Jan 21, 2007
コメント(0)
-
道州制導入なら、内政は地方に
今日は、イタリア料理を、連れ合いに合わせて、アルコール抜きで食べた。素材の生々しい味わいがダイレクトに感じられた。それはともかく、日経新聞によれば、全国知事会は、2007年1月18日、都内で総会を開き、道州制に対する基本方針をまとめたという。それによれば、道州制を将来導入する場合には、「(外交=防衛などを除く)内政に関する事務は基本的に地方が担う」と明記されたという。国と地方の役割を見直すため、中央省庁の解体=再編が必要だと指摘したという。そういえば、かつて、道州制に関連した環境問題の方向性について、以下の様に、ブログに書き、安倍内閣のホームページの目安箱に投稿していたのを思い出した。Jan 12, 2007首都圏のヒート=アイランドは道州制で解消 「つ ぶ や き(274)」 [ 建築・都市・建築家 ] 日経新聞によれば、昨年度は首都圏へ移り住んだ人口が転出した人の数を13万人強上回り、バブル期なみの多さになった模様であるという。2002年から5年間の転入超過数の合計は58万人と、バブル期の累積51万人を上回るという。東京都では、小学校校庭の芝生化や建物屋上緑化や、壁面緑化などでヒート=アイランドを解消しようと目論んでいるが、ヒート=アイランドの原因を考えるとき、そうした小手先の対処ではすまないと考えられる。そもそも首都圏のヒート=アイランドの原因は、人口集中による冷暖房負荷の上昇が最大の要因であり、首都圏の人口集中を根本的に解消しない限り、いたちごっこである。現在の東京一極集中の中央集権的行政システムでは、東京に、官僚機構があり、そのため、東京に銀行の本店があり、その相乗効果で、東京に企業の本社があつまり、東京に、企業や行政の中枢があることで、東京に来なければ何も決定できないような社会構造にある。これを防ぐには、防衛と外交は東京の中央政府でするとしても、それ以外の政府機関を分割分散し、かつ、機能的にする必要がある。それが道州制の実現であり、多極中心の地域に対応した、行政サービスの実現である。道州制により、道州の決定事項は、道州都にいかなければ実現できなくなれば、自ずと、民族大移動がおき、人口の東京への一極集中は解除されるであろう。当然、首都圏のヒート=アイランド現象も緩和されることになろう。
Jan 19, 2007
コメント(0)
-
日本人も子供をふやせるか
日経新聞によれば、フランスでは1990年代前半まで長くて以下基調の続いた出生率の低下を脱して、2006年には、一人の女性が一生の間に産む子供の数である合計特殊出生率が、2.005に上昇したという。イタリア、ドイツなど隣国の出生率伸び悩みとは対照的に「欧州一の多産国」の地位を獲得したという。これには、政府や自治体による○ 出産費用のほか出産休暇中の所得補償 (休業=復職にかかわる各種手当の拡充)、○ 育児支出が所得控除の対象になる(税制優遇)、○ 第二子以降の子供の家族手当(N分N乗方式)などの育児支援政策のほか、労働時間の短さ○ 法定労働時間が週35時間、や社会的意識の高さ○ 出産=育児で退職するという発想がない、○ 出産→職場復帰は当然との考え方が一般的、など、複数の要因が関連しているという。私がフランスに長期滞在していたのは、フランスの出生率が停滞していた1980年代末期であるが、それでも、フランス社会は日本と異なっていた。フランス人は、残業など殆どせず、定刻の5時になると、ケンケンガクガクであった会議をパタっと終了し、ニコニコ握手して、自宅へと帰っていった。そして、夕方から夜の時間帯は、職住接近しているパリの街であるから、家族との十分充実した生活時間に費やしていた。家族でオペラや演劇を見たり、パリのレストランで食事をしたりすることもあるだろうが、それ以上に、自分の家で家族と過ごす時間が十分に権利として獲得されていたようである。当然、家庭が重視され、子供が出来る確率が高くなる。子供の世話は、母親だけではなく、父親も携わることになる。そうした社会環境の充実が、その後の出生率の回復の基底にあると考えられる。日本人は、会社人間が多く、不必要な残業手当稼ぎのための残業は最近ではなくなってきたかもしれないが、以前、父親などの帰宅時間は遅い場合が多く、家族が家庭に揃う時間が少なく、家庭問題や教育問題の温床になっているばかりか、子供が出来る確率が減少することになる。現在日本で起きている社会問題の多くが、家族がバラバラになっている日本社会と労働環境を背景としていることが考えられる。政府も、このような事態に気づいていると見え、労働環境の転換を意図しているようであるが、その趣旨が明瞭に示されないため、労働組合等の反対にあっているものと思われる。また、最低限の生活をするのに必要な食事や居住のための社会的経費が、日本では高すぎると言うこともあると考えられる。国民が、何のために生き、何のために家族をつくり、何のために労働し、何のためにお金を稼ぐのか、と言った、基本的な人権にかかわることを考え理解するように、マスコミや政府がうまく誘導してほしいものである。
Jan 18, 2007
コメント(0)
-
建築廃材で商業生産のバイオエタノール
日経新聞によれば、バイオエタノール=ジャパンは、2007年1月16日、建築廃木材を使って、ガソリン代替燃料であるバイオエタノールの商用生産を開始した。原料が、安定調達できる建築廃材であり、サトウキビの様に食糧としての需要に影響されない利点があるという。しかし、最も注目すべきは、サトウキビやトウモロコシの糖やデンプンを発酵させてつくるバイオエタノールではないことである。これまで、技術的にむずかしかった、木や草に含まれる糖を発酵させることを特殊な微生物を使い量産化を実現したことである。食糧に使われる糖やデンプンでなく、草や木の光合成による一般的成分を、生態系のバクテリアにより分解して植物系の燃料資源を実現することができることを実証したことである。太陽エネルギーから来る負のエントロピーを直接的に光合成した緑色植物の生成する有機物をこれもまた生態系のバクテリアで分解してバイオエタノールを獲得したこと。そして、太陽エネルギーの負のエントロピーにより駆動される、水と大気の大循環により大気圏外の宇宙に放出しやすい形にバクテリアで加工しているわけである。地球システムにおけるエントロピー収支の実現が産業革命以降の工業活動とはひと味ちがう、生態系を利用したそれ以前の江戸時代などの自然エネルギー利用技術に近い形で実現することができることに意義があるであろう。
Jan 17, 2007
コメント(0)
-
東アジアサミット 統合検討へ前進
日経新聞によれば、アジア太平洋16カ国による東アジア首脳会議(サミット)は、2007年1月15日、省エネやバイオ燃料の利用推進を盛り込んだ「エネルギー安全保障に関するセブ宣言」を採択して閉幕した。エネルギー効率化と省エネルギー計画を強化し、水力発電、再生エネルギーシステム、バイオ燃料を拡大する。温暖化ガスの排出を削減し、地球規模の気候変動の緩和に貢献する。化石燃料の利用の継続や大気汚染と温暖化ガス排出の問題に対処するため、クリーンで低排出の技術を促進する。バイオ燃料の利用を促進し、バイオ燃料の自由な貿易や原動機や自動車に使用するバイオ燃料の基準を設定する。エネルギー効率改善に向けた目標と行動計画を各国が自主的に策定する。東南アジア諸国連合(ASEAN)電力網やASEAN縦断ガスパイプラインなど地域のエネルギーインフラへの投資を通じて安定したエネルギー供給を確保する資源=エネルギー=環境問題対策に対し一歩前進したとともに、経済成長を前提とした施策が見え隠れしているようである。一方で、東アジア首脳会議の役割が、日中関係の改善で大幅に前進し、サミット参加16カ国での経済連携協定(EPA)研究など、日本の提案に中国は反対せず、サミットが対話の場から具体的な経済協力を検討する枠組みへと深化した。問題点がない訳ではないが、今回、日中間の関係改善が東アジアの経済統合を、「東アジア環境共同体」的な意識をもつことで、良い雰囲気をもたらしたという。
Jan 16, 2007
コメント(0)
-
「水づくり」日本企業世界で拡大
日経新聞によれば、日本企業が海外で飲料=工業用水をつくりだす水資源事業を拡大するという。旭化成は中国や米国で、浄化膜受注、東レは地中海沿岸地域で、淡水化受注、浄水場や海水の淡水化に使う水処理膜を相次ぎ受注している。三菱商事などは水道事業への投資や運営を進める。人口増や工業化を背景に世界の淡水不足は深刻さが増しつつある。環境技術で蓄積がある日本企業には海外から引き合いが急増しており、水資源分野を成長市場と位置づけて開拓するという。汚水を浄化するのにつかう精密ろ過膜や海水から淡水をつくりだす逆浸透膜などの技術がある。水資源事業のうち上下水道の建設?運営は欧州企業がノウハウをもち、仏スエズなどが中国市場で先行する。日本勢は超微細技術を武器に水処理膜の高性能化などで攻勢をかけ、インフラ整備を通じて産油国などとの関係強化も狙うと言う。淡水資源の重要さと確保については、このブログの下記の記事で述べてきたし、安倍内閣の目安箱にも投書してきた。穀物、10年ぶり高値 2006/11/30http://plaza.rakuten.co.jp/spaceplanners/diary/200611300000/日本の技術で淡水を作れ 2006/12/01http://plaza.rakuten.co.jp/spaceplanners/diary/200612010000/食糧よりもバイオ燃料確保、と淡水資源 2006/12/24http://plaza.rakuten.co.jp/spaceplanners/diary/200612240000/植物原料素材温暖化ガス削減に期待と淡水資源の確保 2006/12/25http://plaza.rakuten.co.jp/spaceplanners/diary/200612250000/クロマグロ、水温上昇で産卵場所縮小 2006/12/26http://plaza.rakuten.co.jp/spaceplanners/diary/200612260000/
Jan 14, 2007
コメント(0)
-
首都圏のヒート=アイランドは道州制で解消
日経新聞によれば、昨年度は首都圏へ移り住んだ人口が転出した人の数を13万人強上回り、バブル期なみの多さになった模様であるという。2002年から5年間の転入超過数の合計は58万人と、バブル期の累積51万人を上回るという。東京都では、小学校校庭の芝生化や建物屋上緑化や、壁面緑化などでヒート=アイランドを解消しようと目論んでいるが、ヒート=アイランドの原因を考えるとき、そうした小手先の対処ではすまないと考えられる。そもそも首都圏のヒート=アイランドの原因は、人口集中による冷暖房負荷の上昇が最大の要因であり、首都圏の人口集中を根本的に解消しない限り、いたちごっこである。現在の東京一極集中の中央集権的行政システムでは、東京に、官僚機構があり、そのため、東京に銀行の本店があり、その相乗効果で、東京に企業の本社があつまり、東京に、企業や行政の中枢があることで、東京に来なければ何も決定できないような社会構造にある。これを防ぐには、防衛と外交は東京の中央政府でするとしても、それ以外の政府機関を分割分散し、かつ、機能的にする必要がある。それが道州制の実現であり、多極中心の地域に対応した、行政サービスの実現である。道州制により、道州の決定事項は、道州都にいかなければ実現できなくなれば、自ずと、民族大移動がおき、人口の東京への一極集中は解除されるであろう。当然、首都圏のヒート=アイランド現象も緩和されることになろう。
Jan 12, 2007
コメント(0)
-
アメリカ エタノール生産倍増
日経新聞によれば、アメリカで、トウモロコシから作るエタノールの生産が急増している。どうように、ブラジルもサトウキビから作るエタノールの増産を急ピッチで進めており、7年後には倍増を計画している。CO2ノ削減条約(京都議定書)の消極的なアメリカが、石油エネルギーからバイオ系の燃料にかえてきているということは、原油価に煮比べて、バイオ系の燃料の価格が比肩しうる段階にきていることによるとかんがえられる。昨今のベラルーシのロシア-ヨーロッパ間のパイプライン閉鎖も、原油の欠乏からくる原油価格の引き下げ要因である。アメリカはもともと石油生産大国であったが、中近東その他の石油を輸入して、自国の石油資源の温存化を将来の世代のためにはかっているようであるが、地球環境にやさしいと見なされる、バイオ系の燃料の生産の流れは、これからの主流であることは間違いなさそうである。
Jan 11, 2007
コメント(0)
-
植民地が内部にできる日本の近未来像
日経新聞によれば、東京大学の吉川洋教授によれば、過去200年間の先進国の経済成長を例に上げ、日本が人口減少社会になっても、夢を実現しようとする原動力によるイノベーションにより、経済成長が可能であるという。しかしながら、過去の日本を含めた先進国の経済成長は対立する、発展途上国が、原始状態に近い状態であったという現実があり、先進国と発展途上国の相対的経済格差により発展の実態と実感が得られていたということに着目すべきではないのだろうか。これからの日本の人口減社会で起こることが現在の日本などで現実に起きていることの延長であるとするならば、かつて対立構造として存在していた、発展途上国が、中国やインドのように先進国の仲間入り一歩手前にきており、その一方で、日本の国内に、イノベーションの結果として発展途上にいる国民と、先進的国民とが存在するようになり、日本国民総「中の上」状態であった過去から、国内に先進的国民の搾取する植民地が出来上がった状態であると考えられる。すなわち、国民の多くが実感しているのは、建築家が典型的にそうであるように、過去よりあるいは同じだけ仕事をしても、絶対的収入が減少していることであり、あるいは、過去に比べて、移転可能な同類業種全体の収入が絶対的に減少していることではないだろうか。一国の中に、経済的植民地ができるようでは、もはや、一国の体裁をなしていないとも考えられる。経済発展構造が、世界の先進的国民 対 発展途上的国民に入れ替わるだけでないかというのが実感である。そして、発展途上的国民の約20年前の状態を原始状態とすれば、発展途上的国民にとって現在は、原始状態以前となっていることを当局や、関係者は理解しているのであろうか。当事者に問うてみたいものである。
Jan 10, 2007
コメント(0)
-
環境規制が経済を動かす、急げ東アジア環境共同体
欧州連合(EC)の化学物質規制RoHS指令の影響を受け、ECに輸出をしている日本企業の先行開発が進んでいる。これは、特定地域の環境規制をクリアしないとその地域に輸出ができなくなり、クリアしたとしても、地域内企業と同水準では競争力が劣る可能性が高いことを暗示している。環境規制をかける特定地域では、自らの経済にとり、最も都合の良い環境規制を選択できるため、開発コストなどの点で有利となる。環境規制をかけることで、地域内の環境がよくなり、環境技術開発が進み他地域での競争力が増し、地域内外の経済が回転するというトリプルメリットが生じることになる。後追い型の日本政府の場合には、日本企業の企業努力により、解決することはできても、環境規制をコントロールできないため、日本企業にとってはハンディキャップ=レースとなる。日本の弱点は、一緒に、環境経済政策を立案する地域共同体をもっていないことである。当面、東アジア環境共同体の早期実現をめざす必要があるであろう。環境共同体は大きい程競争力が強くなるので、それこそ、大東亜環境共栄共同体ができるものなら、かつての汚名も同時にそぎ落とすことができるかもしれないが、反感や誤解が生じる可能性が大であるので、まずは、東アジアでの環境共同体をめざすべきであろう。
Jan 8, 2007
コメント(0)
-
種の絶滅
昨日の日経新聞によれば、1月4日までにまとめられ、今年半ばに正式発表されることになっている、国連環境計画(UNEP)による地球環境白書案によれば、過去20年間に地球環境が大幅に損なわれ、自然状態(多分、その前の20年より遥か昔との比較)の推計で100倍の速度で生物が絶滅し続け、野生生物の総個体数も20年間で40%減ったとの報告があり、大気汚染が再び(先進国で一時減っていた硫黄酸化物の排出量が、アジアの排出増によって1995年頃から増加に転じ)悪化に転じていることなどが観測され、砂漠化や土壌劣化が進み、過剰な灌漑で起こる塩害の影響を受ける土地が拡大傾向にあり、農地や牧草地の拡大により、日本列島3つ分以上の森林が失われたという。このままでは、改善も望み薄だという。環境対策を意思決定の根幹におくよう各国に政策の転換を求めている。有識者委員会が「持続可能な開発(Sustainable Development)」の重要性を指摘してから20年を機に今回の白書がまとめられたが、政治的な意思の欠如や資金不足、経済や開発政策で環境問題が重視されないことなどが障害となり、持続可能な開発が実現していないと分析している。以前からここで述べているように、現代物理学が絶対的な真理として唯一認めているという熱力学第二法則は、「閉じた系(孤立していて、その外界と物質およびエネルギーの交換をすることができず、そのため、熱力学的平衡の状態に到達する事が出来るような系)においては、そのエントロピーが常に増加する方向にのみ変化が進行する。」ことを主張している。これを別のいい方をすれば、東洋思想における「覆水盆に返らず」である。すなわち、ひとたび、(閉じた系の中で)拡散化したものは、開いた系として、エネルギーや負のエントロピーを供給しないかぎりは、元に戻らないということである。これを参照すれば、開いた系として、太陽エネルギーのフロー(負のエントロピー)を最大限利用し、太陽エネルギーのストッックである化石燃料資源等を可能な限り利用しないようにし、太陽エネルギーのフローの一部によって引き起こされる水と大気の大循環により、正のエントロピーが大気圏外に放出できるようなシステムを生物生態系、かつ、科学技術的に開発しないかぎりは、元に戻ることはないということになる。そのために必要な政策と予算をたてる強い意志が、各国政府に要求され、特に、日本国政府には資源小国輸入大国、農産物輸入大国としての淡水資源間接輸入大国として、確固たる態度を示していただきたいものである。また、すでに、拡散したり、汚染したりしてしまった資源は、負のエントロピーを注入して復元するしかないが、そもそも、拡散したり、汚染したりしていなければ、よけいな負のエントロピーを地球環境内に放出する必要がない訳である。根源的な環境問題の解決には、科学技術的には、化石燃料資源の拡散を最小限にすますようにすることであることであり、一方、生物生態系の力を有効に維持、使用すべきことを熱力学第二法則は、教えてくれるのである。
Jan 6, 2007
コメント(0)
-
初詣
昨日、久しぶりに初詣で明治神宮に参拝してきた。たぶん23年ぶりである。明治神宮の参道や境内は、鬱蒼とした杜でかこまれている。これが、約100年前に造られた人口の森である事に気がつく人は少ない。伝統的な神社のような建築は、四半世紀たってもかわらず、落ち着いたたたずまいをしていた。今後も、何百年か、この神宮の杜と社はその姿をそこに残すことであろう。それに比べて、戦後の現代建築はどうだろうか。百年は愚か、十数年たつと、うっすらと汚れがめだち、くずぶっているものが多い。しかも、機能的に使いにくくなったと言う理由で、3~40年経つと、取り壊されてしまうものが多い。大地震がおきて倒れても、伝統的日本建築は、起こして簡単に補修されて保存されるが、現代建築は、50年に1度クラスの地震でこわれなくても、100年や200年に1度クラスの地震で倒壊のおそれがあるというだけで、壊されて建て替えられてしまう。そもそも、機能的に使いにくくなったというだけで、3~40年で建て替えてしまうというのに、50年に1度くらいの地震で倒壊のおそれがあるということで、建て替えてしまうのでは、人々の原風景を形成する都市や街並を維持することなどできないし、美しい景観を都市に求めることなど無理な事かもしれない。今日の日経新聞でも、ある有名な都市計画学者が、「しかし、せっかくの欧米での教訓や感動が少しも生かされることなく、美しくない街づくりに身をゆだねてきた。」また、「多くの仕事をしてきたつもりだが、結果として美しくない景観を許してしまった。」と反省している記事がのせられている。建築家 丹下健三先生は、若かりし頃から、「美しいからと言って機能的であるとはかぎらないが、美しいもののみ機能的である。」と主張して、美しい建物をいくつも残してきた。こうした考え方が、やっと定着しつつある今日この頃であろうか。
Jan 4, 2007
コメント(1)
-
平成の廃藩置県としての道州制
日経新聞によれば、日本経団連は、1月1日付けで2015年度までに実現すべき目標や今後5年の政策のあり方を示した提言「希望の国、日本」(御手洗ビジョン)を公表したという。その中で、国から地方へ権限を移譲する地方分権についてふれ、「平成の廃藩置県」と位置づけ、2015年をめどに道州制を導入し、1800強ある市町村も半数程度に減らすべきであると唱えているという。経済圏を広域にし、競争力を高めるという。現在の中央集権型行政は120年以上前につくられたものであり、その後の交通網の進歩や最近のIT化などを反映していないと考え、都道府県が47もあり、細分化で無駄も生じているので、集中化により合理化したいという。御手洗ビジョンに、資源=エネルギー=環境問題に対するビジョンや、道州制導入との関係が示されている様子がないのが大きな問題点ではあるが、財界としても、道州制を前提として、経済活動を進めてゆく事の宣言であると考えられる。
Jan 1, 2007
コメント(0)
全22件 (22件中 1-22件目)
1