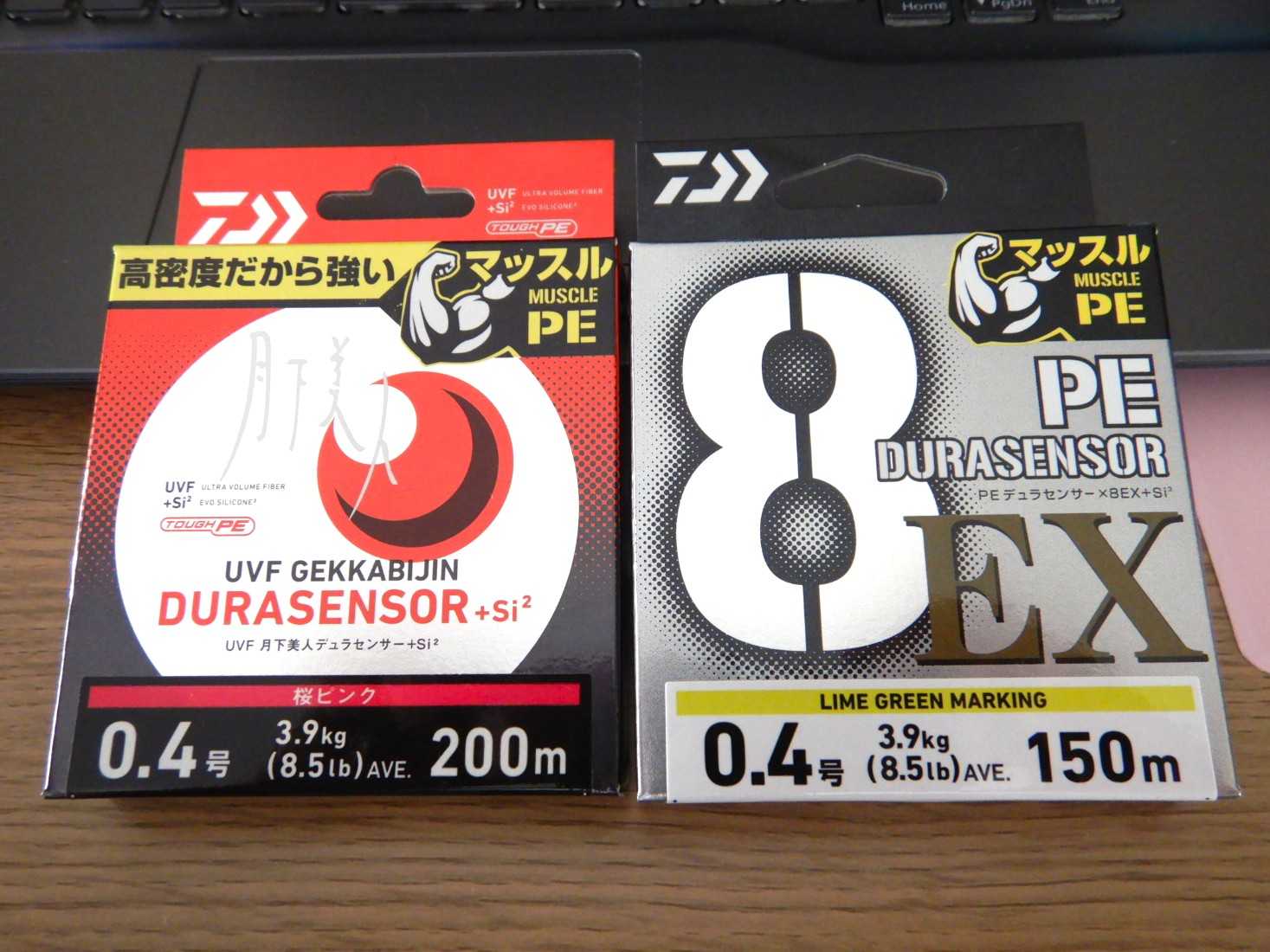全575件 (575件中 1-50件目)
-

早めの春の味覚
暦のみならず、実態も春へと一歩ずつ近づきつつある今日この頃ですが、土曜は午前中の晴れ間も早々に消えて午後は雲が多く、日曜も朝から雨模様。春もまだ二の足を踏んでいそうです。そのような中、土曜日に春の足音探しに散策してきました。マルバタチツボスミレ posted by (C)sasama_teaたった一輪でしたが、スミレの花が咲いていました。周囲を軽く見渡しましたがこちらのみ。少しだけ得をしたような気分です。(全体の様子から交雑種のマルバタチツボスミレとしました)タンポポも外来種が幅を利かせて季節感もあったものでもないのですが、生粋の国産タンポポの旬はやはり春、ですね。日当たりの良い場所ではすでに数株が花を咲かせていました。カントウタンポポの蕾 posted by (C)sasama_teaタンポポの花は黄色、と決めてかかると、このような色合いも新鮮に映りませんか。舌状花の裏側に赤い色が乗っているのは在来種のタンポポだけです。花は立派に開いてナンボ・・・かもしれませんけれど、未熟な姿もまた乙なものです。いかがですか?他、カラスノエンドウやオオイヌノフグリなどの雑草さんたちが花をつけていましたが、まだまだ野原は春に程遠い姿でした。それでも本格的に暖かくなる前にも、準備だけは着々と進んでいます。ノカンゾウ芽出し posted by (C)sasama_tea昨年訪れた時には随分と多くなりすぎていたノカンゾウの芽です。一帯を埋め尽くすほどのおびただしい芽、芽、芽。。。美味しいのですよ、これ。土の中にナイフを差し込み、根元の柔らかくて白い部分から切り取ります。さっと湯通しする程度で食べられます。甘くてクセがなく、いつもはぬたにして食べるのですが、今回は初めてポン酢で食べてみました。こちらもイケます。美味。そしてこちらも。手前がひとつだけ見つけられたふきのとう。その後ろが、道端の雑草としては有名すぎるヨモギの天ぷらです。枯れ草ばかりの草地で何をしてるのか奇妙な行動に映るやも知れないのですが、ただ(無料)の食材も結構美味いものだったりするのです。『ビンボウクサイ』ほっといてください! なんて吠えたりしませんが、目先を変えてみるのもまた面白いのです、とは申し上げてみたいと思いますよさ、次は何を食べられるのかな?
2009.03.01
コメント(4)
-

スゴイダイズ ヨーグルトタイプ
先日、とある新商品を発売前に体験することが出来るということでそのモニターに応募したところ見事に当選しました。その新商品というのがこの大塚食品の豆乳から作られた『スゴイダイズ ヨーグルトタイプ』でした。当初はヨーグルトの新商品としか知らせてもらえず、どのようなものが試せるのかわくわくしながら待っていましたが、届いた箱を開けてびっくり、1ダース入りの上記商品でした。太っ腹ですね。豆乳製のヨーグルトは他社さんのものを試したことがありますが、乳製品のものより軽めの口当たりと感じました。スゴイダイズ ヨーグルトタイプの特長はこんな感じです。成人病予備群の方々には良さげな内容です。ふたを開けるとこのような感じです。豆乳由来の色がついていました。味に関しては、豆乳自体は豆臭さがあって飲みづらく感じることもありますが、こちらはそのような匂いや味のきつさは強く感じず、あっさりした出来上がりになっていました。あえて例えてみると、レアチーズケーキのような食感でした(雰囲気がお分かりいただけますかな)。素材表示を見ると野菜が使われていて、それらで豆乳のくせを消したのかな? などと想像しました。ただ個人的には、粘り気を出すための増粘多糖類が多すぎるように感じました。もう少しさらっとした舌触りのほうが飽きずに食べられるようには思います。全体的な評価としては、毎日食べ続けるにはちょっと重いので、他のヨーグルトと組み合わせながら、間に挟んで食べたい、というところでした。また、栄養面が体に与える影響は、期間が短くて、あるいは普段からヨーグルトを常用しているためこの豆乳ヨーグルトを食べたことによる違いがはっきりとは分かりませんでした。普段ヨーグルトを食べない方には、常用することで腸内環境を改善することが出来るとは思います。いかがなものでしょう。ちなみに、発売日は3月16日だそうです。 以上、サンプルテストに関する報告でした。 (復帰前の腕慣らしにしてみました。次回は通常どおりの内容に戻したいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。ちなみに私のお気に入りヨーグルトはチチヤスヨーグルトです)(直前にもうひとつ日記を書きました)
2009.02.25
コメント(8)
-

ありがとうございます
まず、率直に『ありがとうごさいます』と言わせていただきます。何がきっかけか、つまづいて気づくと肉体的というより、精神的な部分にわだかまりが残ってしまいました。そのついでに眠気も増大、ヤル気を置き去りに日々パソコンを目の前にしながら次の瞬間には突っ伏して居眠りしている自分の姿がありました。ある種のわだかまりが片付いて、さてブログを再開しようとするも一度急停止してしまうとなかなか動き出せなくなりフラストレーションを溜めたまま動き出せない・・・そのような馬鹿みたいな日々、でした。ただその分、やりたいことはあり過ぎの状態でしたので空いた穴を無理矢理埋めるようにいろいろと挑戦していました。今もそれらは進行中ですので、ご覧いただけるような状況になりましたらご披露できるかもしれないです。(ほとんど『食』に関係する内容ですが実際には大した内容でもないと思います)写真に関しては、じつは冬の間はほとんど撮れませんでした。遠出するほど体力が残らなかった状況が多く家の近辺をうろつく程度で収穫があまりありませんでした。上の写真は日曜日に撮影したものです。今年の冬は寒さも厳しく、枯れ草の中にもセイヨウタンポポの花もまだ疎らです。徐々に暖かくなりそうですから春遠からじ、ということでしょうけれど。では申し訳ありませんがこの記事を以て励ましのコメントに対するレスとさせていただきます。温かい言葉の数々、本当にありがとうございました。
2009.02.24
コメント(0)
-
。。。
何の前触れもなく、長期に渡って更新を滞らせてしまいまして失礼しました。派遣切りなどの景気の悪い話ばかりの昨今ですが私の場合はそれらが上記の理由となっているわけではありません。当ブログへ訪問し、少しでも楽しんでいただくことが目的で始めたわけですからつまらない私の愚痴を書き込みそうになって我に返り自粛しなければと決めたまま不意にブログが書けなくなってしまいました。少々お間抜けな話です。そうして居留守を重ねているうちに季節がそっくりひとつ分過ぎてしまいました。休日の天候不順に加えて体力的な問題もあって冬季にやるべきことと決めていた内容もほぼ手付かずです。去年の記録と見比べると、梅の開花も1週間以上早いですね。桜も例年より早いようで、関東が先陣を切るようです。先々週あたりにはカエルの声も聞けましたし今日はシジュウカラが美しいさえずりを聞かせてくれました。冬眠からやっと目覚めた獣のように春の息吹を身近に感じながら私も活動を再開しようかと。。。申し訳ありません少しだけ穴の中から外の様子を窺わせてください。勝手な事ばかりする馬鹿に興味が失せているかもしれませんし。。。(ここまでご覧いただきありがとうございます。感謝)
2009.02.20
コメント(5)
-

高野山の箒
まずお詫び。サボリの期間が長すぎて、全てを回りきることが出来ませんでした。順次全てに目を通していきます。失礼ながら、どうかお許しを。では、「ぼちぼち」再開します。この土日は天候が優れず、時折雨が降り出し散策には良くない状況でした。土曜は雨でこもりきり、日曜は午後から雨模様。それでもどこへも出かけないのもシャクですから日曜は雨の中出かけてきました。ただ収穫はほぼなしで、ヤマイモのムカゴを少量採取しただけでした。仕方がないのでその1週間前のことです。11月1日、曇りがちでも時々陽が顔を覗かせるような中途な日でした。風も少し強く、被写体は右へ左へと容赦なく動いてしまい、写真撮影には困難な条件下でもありました。そんな中、初めて図鑑で見てから幾歳、実物を自分の目で見ることを願い続けていた花を確認するためにある場所を訪れたのですが、探すとなるとなかなか見つからないもので、場所は合っているはずだと確信しながらも、今年もまたダメかと諦めかけていたのでした。コウヤボウキ posted by (C)sasama_tea昨年も記事にしましたが、そのときには花も終わりかけで、ちょっと残念な思いが残されたのでした。今年は悲願がようやく叶い、8分咲き程度の状態でコウヤボウキの花を見ることができました。近くにタイアザミの花がありましたので、比較のために一緒に撮影してみました。どちらもキク科植物ですが、随分と様子が異なりますね。コウヤボウキは木本(もくほん、つまり草ではなく木)で、日本のキク科の植物では異色の存在でしょう。地面からたくさんの細い枝を出し、ある意味目立たない植物ではないはずなのですが、秋に花を確認しに出かけると、藪の中では見つけられないことが多いのです。今回初めて花がたくさん咲いた状態で観察することが叶ったのですが、ここでさらに気づいたことがあります。それはこの花に香りがあるということです。キク科特有の酸味のある香りですが、甘みのある独特の香りはお気に入りのひとつなりました。爪楊枝よりも細い枝に、メルヘンチックな花、そして繊細な香り。高野山で箒に使われていたというその由来とはかけ離れた花でした。ついでに同じ日に撮影した写真です。リュウノウギク posted by (C)sasama_tea基本的に白い花のリュウノウギクも、花の終わりごろには周囲がピンク色に染まります。そろそろ秋も終わりかな、と思い始める頃に咲く野菊で、私はこの花も大好きです。ただ今年は草刈りで刈られてしまったものも多く、白く目立つはずの花が少ないのが残念です。昨年は暖冬の影響で年越しまでこの花が咲いていましたが、今年はどうなのでしょう。(別件ですが、いくつかおかしな狂い咲きが見つかっています。やはり人以外の生き物は地球上の異常に敏感なのか?)ブログランキングに参加しています
2008.11.09
コメント(5)
-

ツマグロヒョウモンに癒される
いろいろありまして、ブログ更新ができない状態でした。少しずつ状況も好転してきましたので、ぼちぼち元に戻していくことにします。先日のキノコの話はとっとと終わらせるはずでしたが、状況も見ながら別の機会に書きます。(キノコの季節ももう終わりかなぁ・・・)行き詰っているときに楽しいことを見つけるのはかなり労力を要しますが、もともと好きなことでうっぷんを晴らすのがいちばんですね、やはり。ツマグロヒョウモン posted by (C)sasama_tea初めて実物を見ました。ヒメアカタテハかと思いましたが、よく見るとツマグロヒョウモンのようで、自分の周囲を逃げまくる姿を追い回して撮影してきました。吸蜜中には接写できるほど近づけましたので、夢中になって追い回していると憂さも少しは晴れました。ありがとう、そんな感じです。そのときに撮影した全ての写真をつなぎ合わせてスライドショーを作成してみました。物好きな方はこちら(フォト蔵)でご覧ください。(結構重い動画です↑)それでは、今後もよしなに。。。
2008.11.08
コメント(6)
-

きのこのこ
例のキノコは食べました。ブログのネタになるはずでしたが、私的な理由で少々延期します。他に少しだけ用ができてしまいまして、その用事を済ませるだけで精一杯になってしまいました。ごめんなさい。そこで場つなぎにこのようなものを用意しました。分解途中の落ち葉に生えた、柄の長さが1ミリ程度の微小なキノコの一種です。彼らも頑張っています。・・・・・ごめんなさい、気の利いた台詞も浮かびません。眠ります。。。
2008.10.26
コメント(4)
-

眠いです。
少しブログを留守にしてしまいました。皆さん、お加減いかがでしょう。私は風邪を引いたとかそのような理由はありませんけれど、とにかく眠くて更新にたどり着けませんでした。土曜日の(現時点では)昨日、晴れマークのついていたはずのお天気は見事に外れて曇り。滞っていた部屋の掃除も手間取り、家を出たのは午後1時過ぎで、空は重く、今にも雨が降りそうでしたが、傘を用意していざ出発したのでした。まずは気になっていたキノコの場所へ訪れると、出ていました、やっと出ました。今年は寒暖が波のようにやって来る、なかなか寒くならない秋でしたのでキノコもあまり積極的には現れてくれない年でした。ただ雨は多めに降っていますので、キノコの発生条件だけは整っています。そのキノコの発生を確認しましたので、この日は急きょキノコ探しへと変更しまして、普段見ない場所も探してきました。あまり寒くならない影響かもしれませんが、キノコ自体の種類はさほど多くはないのですが、あるキノコが大発生していました。先ほどのキノコは雨の影響で土を被り、洗わないと食べられない状況にあり、後者は虫食い状態で虫出しが完了しないとこれまた食べたくないわけで、実際に口にするのは今日のことになります。料理した時点でブログに載せることにしましたが、勿体ぶるほどのものでもないのです、実際には。上の話とは関係ないのですが、とりあえず季節的な写真を1枚載せておきます。(画像編集するだけの体力が残っていなくてキノコの話題を後回しにしたのは内緒にしてください)ツチイナゴ幼虫 posted by (C)sasama_tea冬を成虫で過ごすツチイナゴの幼虫は、成虫が茶系統の体に対して違和感があるほど緑の体色です。冬の枯れた草に紛れるための成虫の茶、逆に秋の頃を過ごす緑の幼虫。環境に馴染み、うまくできていますね。ちなみに、こちらが以前使用したツチイナゴの成虫です。撮影は6月で、成虫で冬越しした後、このくらいの時期までそのまま生きているそうです。眼下の黒い「涙線」が特徴のツチイナゴの紹介でした。では、一度休んでから皆様のところへお邪魔いたします。ブログランキングに参加しています
2008.10.25
コメント(6)
-

蝶の災難
秋の深まりとともにこのような光景が多く見られるようになった気がします。(10月13日撮影)すでに翅と体の一部を残すのみとなってしまったヒメジャノメでしょうか、この時点でもしゃぶられ続けていました。最近まで蜘蛛を毛嫌いしていましたが、観察してみると興味深い点も数多いと感じるようになりました。ただ一般的には嫌われ者ですよね?接写で撮影した蜘蛛の画像が多いのですが、あまり多用しないほうが良いかもしれませんね?さて18日の土曜日、笹の葉の近くを舞うシジミチョウの仲間を見つけて、確か笹の周辺で生活するその仲間がいたな、と思い出し、卵でも産みつけに来たのかとカメラを構えて近づいてみました。すると舞っていた個体とは別にもう一頭、笹の葉の裏に見えました。そこには白地に黒い斑点の特徴的なシジミチョウ、初めてお目にかかるゴイシジミがいたのです。・・・?哀れゴイシジミ posted by (C)sasama_teaなんと、すでにハナグモに捕らえられた状態でした!私が最初に目撃したもう一頭は、この写真の個体に対して求愛行動を取っていたようです。しかも、捕らえられた個体のすぐ脇にはアブラムシの群れがあり、産卵のためにやって来たところをハナグモに捕らえられたという構図が考えられます。初見の蝶がこのような事態に巻き込まれていて少なからず衝撃を受けてしまいましたが、冷静に考えてみると、ハナグモの能力の凄さも感じてしまいました。哀れゴイシジミ posted by (C)sasama_teaハナグモは花の咲いている場所で獲物を待ち構えていることが多く、花の咲いてる状態を察知してその場にやって来る凄い蜘蛛だと考えるだけでした。ただ、少し考えてみてください。写真の状況では花などどこにもありませんが、ハナグモはその場所で待ち伏せていたと考えるのが適当のような気がします。笹の葉にアブラムシがいるとゴイシジミが来る、と理解してハナグモは待ち伏せていたのでしょうか?不思議ですねぇ。ハナグモの頭脳、かなり明晰です。ハナグモはかなり気になる存在でしたが、これから先も目が離せないですよ。ブログランキングに参加していますさて、蝶の受難ということで、蜘蛛とは無関係ですが、こちらも併せて掲載しておきます。ルリタテハ幼虫 posted by (C)sasama_tea10月7日撮影のこの写真、ルリタテハの幼虫の状態がどのようになっていて、蛹でも見つからないかと探しているときにこのような場面に出くわしました。頭の部分はすでに潰れているようで、そのあたりからは黒い液体が流れて出ていて、この段階では固まっていたようでした。他に外傷も見当たらないようでしたから、病死したことを示す痕跡ということなのでしょうか。越冬する成虫が発生することばかりを思い描いていた私にとってはかなり衝撃的でしたが、周囲にあれほど見られたルリタテハの幼虫の姿もほとんど見えなくなってしまっていたようですし、鳥の餌となってしまっていたり、どこかで病死していたりと、露のごとく消え去ってしまった幼虫もいるのだと改めて知ることになりました。きれい事ばかりではない、自然の摂理というものを何となく理解するに至りました。人もそのうち何かに食われる??
2008.10.20
コメント(8)
-

カマキリも強いだけではない
カマキリが多いように感じるとは昨日に述べましたが、そのお陰で興味深い出会いも体験させてもらえました。画像はトリミングしてありますので本当は小さい体のコカマキリです。(9月23日撮影)コカマキリといえば茶系の体色しか存在しないと思い込んでいましたが、ネットで検索すると希少ながらも写真のような緑型のコカマキリも存在することが判明しました。発見の瞬間には今まで見たことのない新手のカマキリの登場かと色めきたってしまいましたが、カマの内側の黒い模様はまさにコカマキリの特徴そのものでした。臆病な性格のコカマキリは、私から徐々に遠ざかるように移動し、それを追いかけては撮影していました。葉の陰に隠れてしまうため撮影もままならず、捕らえて場所を整えて撮影、また逃げられ、捕まえ・・・とアホみたいに繰り返すこと、何度?やっとのことでまともな写真が数枚撮れました。大変な作業ではありましたが、じつは楽しかったです。(コカマキリにとっては迷惑千万)そして、このような場面も。。。(以下は10月13日撮影)オオカマキリ絶命1 posted by (C)sasama_tea遠くから見つけたときには「モズのはやにえ」かとワクワクしましたが、実際に近くで観察してみると、尖った場所に突き刺されているわけではなく、何かの原因で病死したような雰囲気でした。オオカマキリ絶命2 posted by (C)sasama_tea少し角度を変えてみると、左目に陥没したような損傷が見つかりましたが、それが致命傷かは定かではありません。撮影した反対側がすぐ水田で、それを目当てにしたハリガネムシの影響かも私には判断がつきかねますので、死に至った原因については皆目検討がつかないです。お腹はパンパンに膨れているため、産卵間近のメスです。次世代に結びつかなかったのは残念ですが、これも定めということなのですね。蟻が周囲で歩き回っていましたから、余すことなく活用されるのでしょう。そういえば、すでにオオカマキリの卵鞘がひとつ見つかりました。明日への布石は打たれています。心配には及ばない・・・自然の摂理がそこに存在するのでした。ブログランキングに参加しています
2008.10.18
コメント(6)
-

カマキリのかくれんぼ
今年はカマキリと大型の蜘蛛が多いように感じますが、気のせいでしょうか。昨年は探してもあまり姿を見つけられなかったのでしたが、今年は目を向けた先にカマキリが潜んでいることがかなり多いです。オオカマキリ posted by (C)sasama_teaカナムグラの葉に隠れていたオオカマキリ。状景を写し出せるように少し遠目から狙いましたが、例によって視線はカメラのほうです。動きを止めてじっと待つ。獲物がやって来るまでじっと待ち続けるのでしょうか、効率が良さそうには見えなくても、この方法がいちばんなのでしょう。。。オオカマキリ posted by (C)sasama_tea1枚目と格好はよく似ていますが別個体です。今度はカラスウリの葉に隠れて、体をまっすぐ伸ばした状態で待ち続けていました。カメラ目線はまたもイタダキです。オオカマキリ posted by (C)sasama_teaこちらもカラスウリの葉の上。両のカマを揃えて、ボクサーのファイティングポーズのような状態でゆっくりと移動していました。上に示しました3枚の写真は、ともに9月13日に撮影したもので、3個体の発見場所は数mのごく狭い範囲でした。私が「カマキリ多いなぁ」と感じる所以です。その割にはトンボが少なく感じたりしますが、均衡が崩れない程度にうまく成り立っているのですかね。何かが起きていたとしても、実際に分かるのはずっと後のことだったりもしますから、本当に見たままを受け入れていいのかはよく分かりません。(恐怖を煽るつもりではありませんが、どうなのでしょうね)ところで、昨年ジョロウグモとカマキリの一触即発の現場を目撃したのですが、当時は私が手を出したために勝負はおあずけとなりました。蜘蛛とカマキリ posted by (C)sasama_teaカマキリの種類は特定できませんでしたが、もう1回の脱皮で成虫になれるはずの個体がコガネグモに捕らえられてグルグル巻きにされていました。すでに動きません。絶対無敵に見えるカマを装備したカマキリも、コガネグモナガコカネグモには抵抗し切れなかったようです。(黒鯛ちゃんからの指摘で訂正しました)勝ち負けの結果が今回のようになるとは限らないのがまた面白いところで、カマキリが勝てないまでも蜘蛛に一泡吹かせることもきっとあるはず。カマキリの肩を持ってしまっていますけれど、戦闘メカに通ずるようなカマキリには強くあって欲しいと願ってしまうのでした。ブログランキングに参加しています
2008.10.17
コメント(10)
-

セセリチョウの背中
街路樹のイチョウはまだ緑色ですが、少し山のほうへ移動しますと、そちらのイチョウの葉は少しだけ黄色味を帯び始めていました。早い時期に赤くなるウルシ科の木の葉も今はまだ緑色で、植物の化粧で秋を感じるにはちょっとだけ早いみたいです。フォト蔵に障害が発生しているようで、いろいろと構成を考えていましたが簡略化してしまいました。少しずつ気温が変化していることと、曇り空で陽光による体温上昇が望めないためでしょうか、いつもは敏捷に動き回る蝶がじっと動かない状況が多くなってきたように感じます。写真のイチモンジセセリも葉の上に止まったまま、翅を開閉する動作だけで近づくのが容易でした。いつもでしたら横目に見ながら通り過ぎるのが常なのですが、何となくその場の雰囲気でレンズを向けてしまいました。そして、数枚パシャパシャと撮影しているときに、あることに気づきました。翅を開閉している動作を眺めていると、通常は閉じた翅に隠れて見えない背の部分が確認できたのですが、茶色の体には似つかわしくないような、鮮やかな青色が隠れていたのです。今まで全く気づいていませんでした。撮影したその日に急いでセセリチョウの仲間のネット検索を行ない、ブログなどに掲載されたその画像の数々を確認すると、背の部分に青い色が乗っている種類がいくつか存在することに気づいたのでした。こういうものは「見えないおしゃれ」というものなのでしょうかね。外見は地味な色のスーツなのに、パンツだけは派手柄・・・みたいな。先日のホシヒメホウジャクの後翅のオレンジ色同様、何かのアピールに使用されているとは思いますから、人がいちいち驚くほどのことではないとは思うのですが、その場ではガキみたいにひとりではしゃいでしまいました。ブログランキングに参加していますフォト蔵のコメントに対するレスができない状態でしたため、レスはまた後ほど改めてさせていただきますね、るるさん。
2008.10.15
コメント(8)
-

紫の野菊
秋の深まりを感じる変化のひとつ、野菊の開花が散歩を楽しませてくれています。この周辺では、紫色の野菊は主に3種類あるようで、ユウガギク、カントウヨメナ、ノコンギクがそれに当たります。ぱっと見はどれも似ていて「同じじゃん(関東弁)」というところなのですが、よく観察してみると確かに違いはあるみたいです。ユウガギク posted by (C)sasama_tea葉を揉むと柚子に似た香りがあるとの理由からユウガギク(柚香菊)と呼ばれるということですが、実際にはそれほどでもないですね。他の2種に比べると花の色が薄く、白っぽい色の花も多いです。葉の幅も狭く、茎の上部の葉はかなり小さくなっています。花の数は他の2種に比べて多いような気もします。(気のせいかもしれませんけれど)カントウヨメナ posted by (C)sasama_teaもうひとつがカントウヨメナで、関西で見られるヨメナに似て関東地方に多く自生するためにそのように呼ばれています。3種の中では個体による花色の変化が最も少なく、大体全ての個体で青紫色の花が咲き、それが見分けるひとつの条件でもあります。(写真では色がはっきり再現されていないのが残念です)ノコンギク posted by (C)sasama_teaそして最後はノコンギク(野紺菊)。青紫から赤紫まで花色に幅がありますが、大体紫色の花が咲いています。前述の2種に比べると、頭花の中央の筒状花(黄色の部分)が少なく、舌状花の幅も細い個体が多いため何となく優しい雰囲気の野菊と私は感じます。開花時期も前2種よりも若干遅めです。見た目だけで見分けるのはかなり困難ですが、花の後のタネについた冠毛、いわゆる綿毛の長さで種を見分ける方法がありますので、併用すると確実性が増すと思います。ユウガギクとカントウヨメナはヨメナ属で、見ても生えているのが分からないくらい冠毛が短く、逆にシオン属のノコンギクは冠毛が2種に比べ長いため簡単に見分けられます。私の認識している限りではこの周辺に似た種類は無いように感じますので、それほど悩まされずに済んでいますが、野菊を見分けるのはかなり大変ですね。中間の性質を持っている個体には困りますもの。皆さんも苦労されていることでしょう。頭から湯気出しながら頑張ってください。ミゾソバとオオカマキリ posted by (C)sasama_tea天気が良いとは言えない空でしたが、雨が降らなければ、まぁ良しとします。道端にはミゾソバの花も満開になっていて、畦も随分と華やかでした。そしてそこにはいろいろなドラマもあり、冬を目前に虫たちは精一杯に生を紡いでいるのでした。カマキリさん、カメラ目線ご馳走さまです。ブログランキングに参加しています
2008.10.13
コメント(6)
-

雨 夕に止む
休日の土曜日、前日の天気予報が外れないかと期待するも、予定通りに午後2時まできっちり雨が降り続きました。雨に降られながら遠出をするのも避けたかったものですから、出発の準備だけ整えながら悶々と過ごしていました。そして雲が切れて日が差すとすでに光は赤みを帯び始めていましたが、構わず買い物がてら散策へと出かけてきました。直前まで雨が降っていて、気温も若干低めであったからでしょうが、虫の姿もあまり見かけない状況でした。ちょっと寂しいですね。ノシメトンボ posted by (C)sasama_teaこの時期、いつもはノシメトンボで溢れかえる枯れ木にもその姿は疎らでした。トンボは今年少ないですか?モンキチョウ posted by (C)sasama_tea露のついた草をかき分けながら前進する都度靴が少しずつ濡れてしまいます。観察対象も少ないのに濡れてばかりで割に合わず、陽も傾いていますので諦めて帰路につきましたが、その道すがらにモンキチョウが多く見られました。ただその多くは体温の低下で活動意欲が低下しているのでしょうか、イネ科の花穂に掴まってお休みモードに移行中の状態でした。そこでこれ幸いとばかりに、濡れた草をかき分けモンキチョウのいる場所まで近づいたのですが、まだお休みには早いようで、カメラを構えるたびに逃げられてしまい、結局さらに靴を濡らすだけの結果と相成りましたとさ。上の写真は、じつはトリミングして編集してあります(しかもピントも甘いです)。いつ逃げられてもおかしくない状況では、構図を気にしながら撮影するのは難しいですね。経験不足です。明日は朝から全国的に寒そうです。そして、早朝から仕事。おやすみなさい。。。ブログランキングに参加しています
2008.10.11
コメント(4)
-

止まった姿
秋の花の中では少し地味めなバラ科のワレモコウ。夏の終わりか秋の初めの草刈りで一旦消えるも、花を咲かせようと急ぎ再びこの季節に向けて茎を伸ばし、赤い集合花を咲かせます。草姿が細長くピントを合わせづらいので花のアップにしてしまいました。10月4日のこの日はあいにくの曇り空。体がガタガタでやる気も削がれた状態でしたが、何もせずに過ごすのもしゃくでしたので、その身に鞭を振るって出かけてきました。ただ体が重く、グダグダの状態で歩き回る中、短い時間でも収穫はありました。キタキチョウ posted by (C)sasama_teaワンパターン気味ですが、今回もキタキチョウです。シソ科のヤマハッカの花に夢中になっているところをカメラで覗き見です。うまくピントが合った画像をパソコン上で拡大して初めて気づきましたが、普段はくるくると巻いた状態の口吻は、意外と自由な方向に曲げながら花の中に差し入れられているようです。ちなみに上の写真の状態では、口吻がS字状に曲がっています。そしてこの撮影場所のすぐ近くに、じっと動かずに休んでいる蛾も見つけました。ホシヒメホウジャク posted by (C)sasama_tea花も終わってしまったタデ科ミズヒキに掴まったまま微動だにしない興味をそそる蛾。あまりにも動かないものですから、指で触ったり突いたりしてしまいました。命が尽きているのかと錯覚させるほど動きがなかったのですが、実際にはちゃんと生きていましたよ。翅に触れてみると、前翅に隠れた後翅には鮮やかなオレンジ色の配色が見つかり、ただの地味な蛾ではないことも分かりました。正体が分からない蛾ではありましたが、近くのヤマハッカの花を飛び回るホウジャクの翅に同様の色が見えたことから、双方が同一種であることに気づけました。ホバリングしながら忙しく飛び回るホウジャクが止まっていると、写真のように地味で目立たない姿だとは露ほども思いませんでしたのでかなり驚いてしまいました。ホシヒメホウジャク posted by (C)sasama_teaこちらは横からの姿です。意外にきれいにピントが合っていたものですから、少し大きめにトリミングして、原版のままフォト蔵に入れておきました。ご興味がありましたら、画像をクリックしてフォト蔵にてご鑑賞ください。飛び回る姿とのギャップが楽しめるかもしれませんよ。ブログランキングに参加していますちなみに、ホウジャクの飛ぶ姿は捉えられませんでした。負けでした。。。
2008.10.09
コメント(6)
-

ちょう、疲れた
前回から1週間ぶりの更新となります。体力の衰えでしょうか、ままならないです。10月2日の朝、歩道の隅で休むちょうちょ。朝日を受けるヒメアカタテハ posted by (C)sasama_tea気温が低かった影響でしょう、朝日に背を向けるヒメアカタテハはじっと動かず、表面積をいっぱいに広げて体温上昇を待っているようでした。しばらくは近づいても動くことはなく、私が満足するまで撮影させてもらえました。とりあえず撮影を済ませてその場所を移動しますと、弾かれたように突然飛び去っていってしまいました。充電完了! といったところだったのでしょうかね。私はといえば、地獄の仕事が待ち構えていましたので、憂鬱な気持ちを少しはその蝶に慰めてもらえました。その日の仕事中に見つけた、初見のきれいな蛾を暇を見つけて撮影しました。少し暗い場所で、上手くきれいに撮れませんでしたので、雰囲気だけでも伝わるように大きくトリミングしました。翅を広げた幅は2cmほどの小さな蛾ですが、緑色の翅がきれいな蛾でした。名前を調べてみるとシャクガの仲間で、翅にある4つの白い紋などの特徴からヨツモンマエジロアオシャクという長ったらしい名前がつけられていました。(ちなみに、他にもシャクガには緑色のものが数種類存在しているようです)翌日も同じ現場での作業があり、体力の無さが露呈し、それ以来疲れ果ててブログにはたどり着けませんでした。ダメですねぇ。傷だらけのオオミズアオ posted by (C)sasama_teaこちらはまた別の日ですが、以前に撮影しておいた写真です。寒さを感じられるような季節になると、多くの虫たちにとっては生を全うする季節でもあるわけで、傷ついた姿を多く見かけるようになりますね。(先ほどのヒメアカタテハも背の毛が抜け落ちていました)こちらはオオミズアオという大型の蛾。捨てられたうちわのように、翅は筋だけを残してボロボロの状態になっていて、すでに飛ぶための役割は果たせないようでした。ただただ、翅をバタつかせて地面を歩き回るだけです。傷ついている虫を見ていると、少し切ない気もしてきますが、次世代には確実にバトンが渡されているはずですから、そっとそのままを受け入れるのが「自然」なのでしょうね。キンモクセイの香りが風に吹かれてどこからともなくやって来て、ヒヨドリが騒がしくなり、モズの声もよく聞こえます。今年は秋を堪能したいですね。ブログランキングに参加しています毎度挑戦しつつも、全く成功しなかったセセリチョウの正面顔写真。ようやく捉えることが叶いましたので記念に掲載。オオチャバネセセリ? posted by (C)sasama_teaもっと楽しい写真が撮れるように頑張ろう!
2008.10.07
コメント(6)
-

異色のデュオ
ユウガギク posted by (C)sasama_tea日曜日の出来事です。夏の間に刈られて勢いをなくしていた草たちも、秋の深まりとともに回復し、彩りを添えるように秋らしい花が少しずつ増えてきました。写真の花はユウガギクで、野菊のひとつとして扱われているごくふつうの植物です。ノコンギクやカントウヨメナに比べると花の色が白っぽくて地味な印象もありますが、その分花をいっぱいつけますので見劣りはしないでしょう。キクのような、蜜を出す小花をたくさん咲かせる花は虫に好まれるようで、種類に偏りなくいろいろな虫を見つけることができますね。ただ、写真のような組み合わせで見るのはおそらくこのときが初めてかもしれません。片や明るい黄色のキタキチョウ、一方は暗い黒のシロシタホタルガ。仲が良さそうではありませんけれど、並んでそれぞれ夢中に蜜を堪能している様子でした。あまり近くに近寄らせてくれない蝶も、食事に夢中なら無防備な状態を晒してくれます。光源が弱く、風で揺れる状況の中、必死に撮影してきました。シャッタースピードが遅いのでISO感度を200まで上げましたところ、後で見直してみると若干ノイズが乗ってしまったことに気づかされました。やはりコンデジでは限界が浅いですね。シロシタホタルガ posted by (C)sasama_tea少し脱線しましたが、こちらはもう一方のシロシタホタルガを横から捉えたものです。口吻を伸ばして蜜を吸っている様が窺えます。黒い体で地味な印象を受けますが、背の白く目立つ帯が昼間行動する蛾の証なのでしょうか、蝶とともに活発に行動していました。実りの秋と表現されるのは植物に限ったことではなくて、その実りを興じる虫たちも冬越しを目前にせっせと次世代を生み出すため、その身を太らせているようですね。(幼虫から成虫に変態した虫も多いのでしょうか、虫の種類も秋になって増えた気がします。)ゆえにやぶ蚊はしつこいです。嫌というほど刺されています。ほんと、刺された後もしばらくかゆいので迷惑ですね。変な病気を媒介していないことを祈ります。ブログランキングに参加しています
2008.10.01
コメント(8)
-

サルトリイバラのゆりかご
時は9月20日のこと、キノコを探して歩いていると、サルトリイバラの葉の裏側にオレンジ色のとげとげした存在に気づきました。5月17日付の日記で、初めて出会ったルリタテハの幼虫のことを書きましたが、その後幼虫も成虫にも出会う機会がないまま、ようやくカメラが故障した8月あたりに別の場所でルリタテハの成虫を見る機会に恵まれました。逢瀬はごくごく短いものの、その感動はひとしおでした。そして時は流れて先ほどの9月20日。ルリタテハの成虫に出会えた場所から少し離れた場所で幼虫に出会えたわけなのですが、その場所から少し移動し、ルリタテハを目撃した場所のすぐ近くにあるサルトリイバラを調べてみると、葉が何かの虫にかじられたようなものが多数見つかり、さらに丁寧に調べてみると、案の定、葉の裏にルリタテハの幼虫数個体を見つけることができました。しかも、段階的に成長度合いが分かるように、3種類の幼虫が近場に集まっていました。以下、写真を並べてみますので見比べてくださいませ。ルリタテハ幼虫1 posted by (C)sasama_teaルリタテハ幼虫2 posted by (C)sasama_teaルリタテハ終齢幼虫 posted by (C)sasama_tea成長とともに色合いも変化していくさまが興味深いです。初めは黒かったトゲの色も徐々に退色して、最後は先端に少し黒を残すだけの白いトゲになるのですね。このトゲは、毒を持つ蛾の毛虫を想像させ、触ると毒で酷い目に会わされそうな印象を抱かせるかもしれませんけれど、じつは全くの誤解で毒など無く、触れてもとりあえず害はありませんのでご心配無用です。どのような感触か気になって今回実際にそのトゲに触れてみましたが、尖端が鋭くて、かなり硬いトゲでした。ただし、硬く鋭くても触れたくらいでは皮膚に刺さることもなく、本当に何の害もないつんつんしただけの存在でした。この幼虫、餌を食べる以外のときと、葉を揺らしたりしたときには、写真の状態のように体を丸めて過ごしているようです。私の想像ですが、鳥がこの硬いトゲを持つ幼虫を丸呑みしようとしたとき、トゲが喉に引っかかって、痛みで吐き出してしまうのではないかと思うのです。そのため、体を丸めて「トゲの団子」のような格好になっているのではないでしょうか。そしてこの日、ルリタテハの幼虫に別れを告げ、さらに別の場所へ向かい、雨雲を気にしながら散策を続けました。すると偶然とは面白いもので、そこでは成虫のルリタテハに出会えました。ただ、クヌギの樹液を吸うルリタテハの横にはスズメバチの姿が・・・。そのスズメバチに警戒しつつ、それでもルリタテハを狙ってカメラを構えました。ただのアホ?ルリタテハと樹液 posted by (C)sasama_tea中央にルリタテハ、そのすぐ下方にスズメバチ。さらに下方と、画面外に多数のタテハチョウの仲間がいました。スズメバチは1匹でしたが、蝶をときどき蹴散らし、樹液を独占しようと躍起になっていましたが、追われて逃げた蝶はすぐにまた舞い戻って、何事も無かったかのように樹液を吸っていました。ところが、あるときスズメバチはタテハチョウの翅に食らいつき、絡み合いながら地面に向かって落ちていきましたが、タテハチョウは命からがら逃げていくことができたようです。さて、この写真のルリタテハ。スズメバチに追われて逃げたのを見計らって、私はその後を追いかけました。見失いそうになりながら必死で追いかけると、とりあえず何かの葉に止まって休んでいるようでした。近づき撮影をば、と考えるもさすがに近寄らせてもらえず、気配を感じてすっと逃げてしまいました。が。逃げたはずのルリタテハが私の近くを飛び回ります。何故だろう? と思いつつもストーカーを続けていると、近くへやって来たルリタテハが、私の背負っていたバッグの肩紐にかけていた青いシャツへ不意に止まりました。そのことを確認すべく振り返ると、見えた途端に逃げられてしまいました。さらにその後にもう一度同様のことがあり、写真に収めようとする努力も空しく、あざ笑うかのように再び飛び去ってしまいました。青いシャツに何かルリタテハを惹きつける魅力があるのかと、ルリタテハに向かって差し出してみたものの、その後は興味を示す気配すら感じられず、スズメバチの待つ写真の場所へ戻って樹液を吸っているだけでした。小雨が降り始め、ルリタテハにもフラレて意気消沈気味の私は(ウソです)、本降りになる前に戻ることに決めたわけなのですが、先のルリタテハ、やってくれました。自転車に乗ろうかとしていた瞬間、頭の近くに黒い影がやって来て、すぐにルリタテハと気づきましたが、何を思ったのか、そのルリタテハが私の頭に止まりました。。。「何を!?」驚いている私を置き去りに、そのまま例の樹液の場所に向かってルリタテハは一直線に飛んでいきました。完全に嫌がらせです。。。小さな、いたずらっぽい笑い声も聞こえたような、聞こえなかったような・・・。蝶のように見えただけで、じつは妖精だったのかも。・・・などと世迷いごとを口にしている間に病院のお世話になってきます。長々とお付き合いいただきありがとうございました。(ルリタテハの行動は実話です。ただ、何に興味を示していたのかは結局不明でした。)ブログランキングに参加していますははっ、アホですが、精神状態は正常です・・・そのつもりです(笑)
2008.09.30
コメント(4)
-

自らを守る盾
上空に寒気が入ってきているそうで、一気に秋らしい雰囲気になってきました。部屋のどこかで鳴くカネタタキの声を聞きながら、ただ今ブログを書いています。日曜日は一日を通して曇り空、気温も20度程度で肌寒く、風も幾分強めに吹いていました。草刈りから回復しつつある植物はようやく秋の花を咲かせ始めましたが、気温の低下に陽光も届かないため虫の動きはかなり緩慢でした。逆にその緩慢さを突いて、普段はちょこまかと動き回る虫を撮影しました。コセンダングサで蜜を吸うキタキチョウ。なかなか近くで写真を撮らせてくれないこの蝶も、このときばかりはゆっくり近づけば逃げられずに撮影も可能でした。ウラナミシジミ posted by (C)sasama_tea体が温まらないせいか、ツバメシジミはウラナミシジミは葉の上に乗ったまま動きを止め、真横にカメラを寄せても彫像のように静止したままでした。そのお陰で翅の模様もくっきり。美しいですね。最近読んだ本には、蝶の翅の眼状紋の役割について書かれていました。翅の内側の眼状紋は脅して追い払うためにあり、逆に外側のものは誘い込んでその眼状紋を攻撃している隙に逃げる役割を持っているそうです。バタバタと上下に揺れる独特の飛び方は、容易に狙いを定めることができず、とりあえず飛んでしまえば生存できる可能性も増えるということのようです。ゆえに。。。こちらの写真のように、橙の模様がついた箇所だけを犠牲にして、逃げて生き延びることもできるみたいなのです。こちらの個体の場合、すでに切り札は使用済みですから、崖っぷちに立たされているということなのでしょうかね。最後まで逃げ切れ!そして、このような虫も見ることができましたが、翅の模様にはどのような意味が込められているのでしょう?シロシタホタルガとツルドクダミ posted by (C)sasama_teaほぼ全身が黒に覆われる中、翅の一部にくっきりと白い線が目立っています。この模様は人間の目には目立ちすぎるように感じられますけれど、生存に関して何らかの意味が込められているものと想像できます。それにしても、不思議な姿です。ちなみに、白い小さな花を咲かせる植物はツルドクダミという中国原産の帰化植物です。江戸時代に薬用の目的で栽培していたものが逃げ出したのだそうです。これまであまり気にしていなかった植物でしたが、元を辿れば中国渡来の植物だったとは少々驚かされてしまいました。現在は人の手から園芸植物が逃げ出す。。。と表現するより、人が望んで自然環境をかく乱していると思うしかないような状況が続いています。先日はアロエが雑木林の中に捨てられていて、見事に根付いていたのです。「自然に還れ」ということで、不要になった自宅の鉢物を山に捨てているのだと思いますが、環境破壊を自らの手で行なうような愚行は止めていただけないものでしょうか。本来あるべきものが虐げられている現実を、理解していただける日が戻ることはありますか?寂しい限りです。ブログランキングに参加しています
2008.09.28
コメント(6)
-

腹の虫
スズメバチのような凶暴な生き物を除き、とりあえず一度は接写で撮影したいとカメラを手に自然の生き物たちと対峙していますが、多くの生き物はその命を守らんと必死で、ちょっとの振動でもすぐに逃げてしまいます。蝶なんかはその代表格で、花に夢中にでもなっていないと、初めの一歩で逃げてしまいますね。自分の影がかぶさっただけでもダメだったりしますし。。。イチモンジセセリ posted by (C)sasama_teaこちらは、花に夢中になっているイチモンジセセリにじわじわと近づき、腕だけ伸ばして撮影したものです。運が良ければ上手くいきますが、このセセリもちょっとした振動であっという間にいなくなってしまいました。こちらも頑張って接近して、何とか近くで撮影することができました。キタテハは比較的おっとり型の性格なのでしょうか、何かに夢中になっていると近づくのはそれほど難しくないみたいです。ちなみに、白い花はヒヨドリバナで、この花が咲く頃に何故かヒヨドリが人里に帰ってきます。ギョエーギョエーと騒々しい声が聞こえていますよ。うつろなヒメジャノメ posted by (C)sasama_teaそして、前回の話題のオニヤンマの産卵に気づく直前、この蝶をしげしげと眺めていました。前述のように、近づいただけでも警戒して逃げてしまうはずの蝶が、このときばかりは微動だにしませんでした。何かがおかしい、と感じて1枚撮影したのですが、後ろで聞こえるバタバタとうるさい羽音のほうが気になりましたのでそちらへ向かい、この蝶のことは後回しにしたのです。じつはこの時点で何となく分かっていたので放置したのですが、散々楽しんで戻ってきても微動だにしていません。よく見ていただきますと、触角の向きが変なのですね。ふつうは前方に突き出しているはずですが、後ろ向きにうな垂れています。戻ってきて、その場に動かずにいる蝶に手をかざしてみましたが反応はなし。そのまま翅に触れてみましたが全く反応がなく、絶命していることに確信を抱いて翅を動かしてみて初めて、「黒い染み」と思っていたものの正体を知りました。黒い染みは翅についていたものではなく、翅と腹部にうがたれた大きな「穴」でした。カラスウリの葉をしっかりと掴んだ足は、触れたくらいでは離れることがないほど強固なもので、亡くなっているとは俄かに信じられないほど堂々とした姿です。寄生虫が無事安定した場所にたどり着けるように蝶の思考を操っていたのでしょうか?想像すると何だか怖いですね。自然界には寄生型の生活をする種も少なくないようですから、実態を認識していないだけで、身近にはもっと同様の事象も発生しているものと想像できます。願わくば、人に寄生するような生物が近くにいませんように。ブログランキングに参加しています
2008.09.26
コメント(4)
-

オニヤンマ!
なかなか思うように更新が叶わず、忘れ去られてしまいそうな、そのような不安もちらほら・・・ヘクソカズラという気の毒な名前の植物ですが、その花については珍しいものではありませんのでご存知かと思います。昨年見つけたその変わり花を当ブログでどこかに載せたましたが、行方不明になってしまいました。ヘクソカズラには、時折図鑑にある一般的な様子の花とは異なる花も見ることができます。上の写真の花もそのようなもので、よーく観察するとその違いに気づいていただけるかもしれません。どこが?ひと目で見分けられる特徴は、中央の赤い色のついた箇所です。通常よりも範囲が広くなっていて、子供がいたずらして母親の口紅を塗ったような・・・要は、赤い色が目立つということです。本来は中心部分だけが赤い程度ですが、日の丸くらいに大きくなっていますね。そしてもう一点。それは、ひとまわり花自体が大きいということなのですが、写真からは分かりませんね。実物を目にしていただければ、「あれっ?」と気づくことができる程度の違いはありました。意外にヘクソカズラの花には個体変異が多く生じるようです。地味な花ですが、探してみますか?話題は一変して、こちらは赤トンボの代表格のノシメトンボです。近くにやって来たのを眺めてみると、翅の一部が見事に欠けていました。4枚あるうちの1枚だけですが、3分の2程度が失われていたものの、全く飛ぶことには支障がないようでした。健気な姿に、頑張れ、と応援したくなります。ところで、トンボの話題で少々面白い動画を撮影しましたので、そちらを紹介したいと思います。ただし容量が大きくてこちらに直接貼り付けることができませんので、フォト蔵へジャンプしてそちらでご覧ください。フォト蔵『オニヤンマの産卵』バタバタと聞こえる豪快な羽音の主を探してみると、大型のトンボが産卵している光景に出会えました。そこは杉植林の足元が湧き水で湿地化してしまった場所で、サワガニも見られるほど水がきれいなので、オニヤンマが産卵するには良い条件なのでしょうか。湿地の上に固い倒木がありましたのでそちらを足場にして、産卵場所から1メートル程度の距離で撮影することができました。初めは写真撮影に挑戦したのですが、日陰でトンボの動きに対応しきれず残像写真になってしまいましたので動画撮影に切り替えました。このカメラの最高画質で撮影したために容量はかなりのものになってしまいましたが、映像自体はそれなりに見られるものになりました。ただ、カメラワークが酷いのはお許しいただけると有り難いです。ちなみに、オニヤンマとは20センチあたりまで近づいたというか、向こうから接近してきて威嚇のような行動を受けたわけですが、それでも気にせず産卵を続けるほど堂々とした態度でした。こちらに向かってくるオニヤンマと目が合ったときには、一瞬噛みつかれるかと冷や冷やさせるほど、威厳のある虫ですね、オニヤンマは。。。人がほとんど踏み入らないようなこの場所、これから先もずっと、人に汚されないでいて欲しいと願います。(ゆえに、質問にはお答えいたしかねます、悪しからず)ブログランキングに参加しています
2008.09.25
コメント(6)
-

焦げ臭いACアダプタ
またも1週間ほどステルス状態に陥ってしまいました。その原因はパソコンのトラブルです。パソコンの電源を入れた途端にACアダプタ付近から「パチパチパチ・・・」と異常音が聞こえてきましたので慌ててスイッチをオフにしましたが、完全に電源が落ちる前にプツっと切れてしまいました。その後パソコンに再び電源が入ることはなく、アダプタからは何となくプラスチックが焦げたような匂いが感じられたのでした。こうして、どうにもこうにも行かなくなってしまいましたので、半ば捨て鉢にアダプタを分解してみれば、案の定素子の一部が基盤から外れていて、その近くが熱で黒く焦げ、かつ軽く溶けていたのでした。あのとき、無理矢理起動し続けていたとしたら、もしかするとアダプタが発火していたのかもしれなかったのでしょうか。危険でした。その後は仕事で代替品を手に入れる暇がなく、ようやく金曜日にネットで探してみると楽天市場に偶然ひとつだけ中古品が見つかり、安いものを探すことを諦めてそちらを購入することにし、そして現在に至ります。(ちなみに、Yを頭文字に持つところのオークションにもっと安いものも見つかりましたが、パソコンが起動しないため売買成立後のやり取りができないことが分かっていたものですから、今回は泣く泣く諦めました)今回のアダプタの故障の原因について思い当たることは、おそらく、コネクタ近辺の断線が引き起こした接触不良です。そちらがアダプタ自体に不要な負荷をかけ、とどのつまりは燃える寸前までに至ったのでしょう。もともと気にはしていたのですが、ともすれば火災を引き起こしかねない状況にまで発展するとは想像だにしていませんでした。皆さんも電源コードの取り扱いには注意しましょう。注意一秒、怪我一生!ところで、台風の影響で不順な天候続きですが、自然観察と写真撮影は続けておりました。雨の影響で遠出は避けてきましたが、近場でも自然の営みを見つけるのにそれほど苦労せずに済みました。ブログ更新ができずに素材だけが集まった状態で何をして良いのか、考えがまとまらない状況に陥っています。(種の同定ができない虫も多数。難しいですねぇ)アカネ posted by (C)sasama_teaとりあえず選択してみたのがこちら。染物、夕焼けの別名、赤トンボにもつけられているアカネというつる性の多年草です。とにかくたくさん咲くだけで、特に何という特徴もない花ですね。人の価値観ではその見た目にさほどの価値が感じられなくても、そこにはしっかりとハナグモが待ち構えていました。そこは、虫たちが腹を満たすための、ある種の戦場みたいなものなのかもしれませんね。アカネと蜘蛛の子 posted by (C)sasama_tea上の写真では分かりづらいとは思いますが、こちらは食事場というよりは、保育園のような場所なのでしょうか。「怖いもの見たさ」がおありでしたら、上の画像をクリックしてもう少し大きな状態でご覧ください。なかなか気持ち悪い状況であります。話は変わりますが、今回の大雨も、度が過ぎていなければ恵みの雨になるはずで、私自身はキノコの収穫を期待しているところです。夜の気温が下がりさえすれば、来週末はキノコ尽くしになりますかな?ブログランキングに参加しています
2008.09.21
コメント(4)
-

秋咲きネジバナ
ネジバナの話題で何度か記事を書いてきましたが、ネジバナは基本的に初夏の花で、その生活環の中では真夏に休眠するために地上から一旦姿が消えてしまいます。北海道のるる555さんの記事を見せていただいたことで、寒地のネジバナの開花期が8月の真夏であることを知ることができたのは新たな発見になりました。寒地の事例は例外ではありますが、暖地のネジバナの中には通常の初夏の開花期以外に9月に開花する個体も存在します。私も今までに数個体の秋咲きネジバナを確認してきましたが、まとめて秋咲きの個体を確認できたことはありませんでしたので、ただ花が咲いているのを確認するだけに留まっていました。昨年秋咲き個体からタネを採取して実生を試みましたが、通常種の実生と混ざってしまったようで、その生活環を知る作業はご破算となってしまいました。ところが、先週の日曜日の9日、秋咲きネジバナの小群落に出会うことになり、「秋咲き」という性質がどうやら遺伝しているらしいことが分かりました。残念なことにその時点でカメラが修理中で手元にあったのが旧式カメラ。20個体くらいの小群落をうまく再現できる写真にはなりそうもなかったものですから撮影はしませんでした。改めて修理後のカメラを手に1週間後の土曜日の13日に再び訪れると、開花個体も随分と減ってしまい、ネジバナを写しただけの写真となってしまいました。背景に秋らしさでも写しこめれば良かったのですが、写せる範囲にはそのようなものが存在しませんでした。ちなみに、背景の緑色のものはビニール製のネットで、削り取った斜面の土が流失しないように貼り付けたものです。じつは3年前、この場所は工事でかく乱にあった場所でして、一度無理矢理リセットされた大地がその歳月を経る中で、逞しい生命力のネジバナはいち早くその版図を広げられたようです。奇しくも、そのネジバナが秋咲きの性質を有していたわけで、通常ではあまりまとまって見られない秋咲きネジバナが同じ地域で多数見ることができたようなのです。そこでもっけの幸いと勝手に判断し、ひと株だけ頂戴してしまいました。自然のままでは通常種のネジバナと区別がつかず、秋咲きネジバナの生活環を観察するのが難しいため、鉢植えにして観察させてもらうことにしました。以前からその生活環について興味がありましたので、大事に育てながらネジバナの性質について調べてみたいと思います。(休眠期に当たる8月中に、秋咲きネジバナがどのように過ごしているのかは謎のまま。少なくとも現在得られる情報の中には無いようです)ところで、秋咲きネジバナが開花する時期には花の姿がよく似た植物も開花期にあり、ネジバナ探しを困難にさせる嫌な要因にもなっています。ツルボ posted by (C)sasama_teaその花はユリ科のツルボ。この花自体は秋を感じさせる好きな花なのですが、秋咲きネジバナを探すときには大きな障害になります。その姿が似ているため、百本のツルボの中に1本のネジバナが咲いていても探すのはかなり困難な作業になります・・・というより、探したくないですね。あまりにもツルボが密集して咲いているため、踏み潰しながらネジバナだけを探す作業は続けられませんし。。。ツルボとミツバチ posted by (C)sasama_tea一斉に花が咲くため、ツルボには蝶や蜂、その他いろいろな虫がやって来ますので、虫を探すには格好の待ち伏せ場所かもしれませんね。この日、私は他の場所にも向かう予定がありましたので、少し写真撮影をしただけでその場を後にし、別の場所で様々な虫との出会いを満喫することになったのでありました。。。そのときの話はまた別の機会にて。ブログランキングに参加していますなお余談ですが、人のかく乱した場所や新たに整備した公園などでネジバナが花を目立たせるようになるまでに要する期間はおよそ3年程度。そのことについては以前に書いたことがありますが、覚えていらっしゃいますか?この考え自体は私の推論に過ぎないのですが、今回の秋咲きネジバナの一件からもその考え方が間違っていないと確信できました。その考え方の詳細については、そのうちどこかで書くかもしれませんし、暇がなくて勝手な妄想で終わるかもしれません(笑)
2008.09.14
コメント(5)
-

農業とその周辺の事情
すっかりご無沙汰してしまいました。最近眠くて仕方がなくて、全くブログに手が回りませんでした。カメラは無事手元に戻り、持ち歩いて写真を撮り始めました。思うように言うことを聞かない旧式のカメラと比べるまでもなく、反応が速く、設定をいろいろといじれるこのカメラは最高です。(ただ、ニコンのサービス部の対応には疑問の残ることも多々ありましたが、ここでは面倒なので割愛しましょう)夏日を記録して昼間は暑いままですが、空は高くなり、ようやく秋らしさも感じられるようになりました。食欲の秋ということで、米の収穫も随分と進んでいます。安心な農業 posted by (C)sasama_tea先日の事故米の一件、ただ単に今まで表面化していなかっただけで、じつは根の深い問題のようです。毎日のように新たな「被害」情報がもたらされ、じつは既に口にしてしまっているのではないか、と不安にさせるほど誰にも身近な問題になりつつあるのではないでしょうか。上の写真は、JA千葉が行なう減農薬の米作りを告知する看板のようです。日本の農業は基本的に安心・安全を提供するもので、海外でも高値で買ってくれる場合もあるようなのですが、最近は度々外国から輸入した食品を国内産と偽装して、危ない食品を高値で売りさばくような悪徳業者が跋扈する酷い国と成り下がっています。結局は、表側を見ただけでは本物かニセモノかを区別するのは難しく、生産者や中間業者の良心を信じるしかないわけでして、産地が明記されているから安心とか、生産者の顔写真が載っているから信用していいとか、頼りにすべき判断基準があるはずなのですが、実際にはそれを利用して騙しているだけなのかもしれないと考えてしまうようになると、あまりにも世知辛いですね。虫や鳥などの自然の生き物も近寄らない作物を、私は絶対に食べたいとは思いません。少しくらい虫にかじられているくらいのもののほうが、実際には安全で、安心して口に運べる作物なのかもしれませんよ。知らず知らずのうちに、体内で農薬が蓄積されていくなんて考えたくもないです。ブログランキングに参加しています眠気もないこのようなときに限って、翌日は早出の仕事だったりします。皆様へのご訪問はまた後日にさせていただきます。ごめんなさい。
2008.09.13
コメント(2)
-

季節は秋でも飽きない虫のこと
今日は午前中に仕事があり、家へ戻ってから出かけようと思いながら、季節を無視したような入道雲を睨みつつ出かける機会を逸してしまいました。結局、買い物の予定がありましたので夕方に出たついでにキノコを探してきました。先日の長雨の影響でしょうか、目を疑うほどの毒キノコの群れに出会い、雨後のタケノコならぬ雨後のキノコの光景にびっくり!丹念に探してみると、数種類のキノコの中にヤマドリタケモドキという食用キノコも見つかりました。このキノコは、欧州で珍重されるセップ(仏)、ポルチーニ(伊)などと呼ばれるヤマドリタケの近縁種で美味しいキノコです。その採取から1週間後の今日、もう少し採れないかと立ち寄ってみると、そのときから雨らしい雨が降らなかったため、水分量が少ない絶妙の状態で1本だけ採れました。(雨続きなどで水分を吸ったキノコは美味しくないです。その意味では、栽培もののキノコも水で洗うのは厳禁です)しかも傘の大きさが20cmくらいのかなりの大物で、虫もほぼついていない素晴らしい獲物となりました。カメラがなく写真による実況中継ができないのが残念ですが、とっても美味しいキノコでした。前回食べたのが何年も・・・何年かな、かなり前のことになりますから、調べて調べて、少しだけおっかなびっくり食べたのですが・・・ところで、前日の土曜日も散策に出ましたが、昨晩は疲れて寝てしまいました。撮影データが取り出せないカメラを持参しましたが、観察して楽しい出来事はたっぷりでも、裏腹に画素数の低い写真しか撮れず、データも即座に取り出せないと、気分の盛りあがらないことこの上ない状況です。イチモンジチョウに飛び掛るオオカマキリ、顔中粉だらけのムギワラトンボ、オニヤンマのドッグファイト。。。どの場面も事件現場の前後の静止画像でしか撮影できませんでしたが、3時間程度の短い散策でも充実した楽しいひとときでした。要は時機のみが大切で、自然に対する気持ちがどうとかということはどうでも良くて、深い洞察力があるとか、たまたまその場に居合わせただけとか、そういうことで全てが決定されるのです、きっと。こちらは今回の記事とは関係のない写真ではありますが、文字だけでは寂しいので載せておきます。(2枚とも撮影日は7月13日)ゴマダラカミキリ posted by (C)sasama_tea ゴマダラカミキリ posted by (C)sasama_tea味覚の秋、こちらでは稲刈り作業の半分くらいが終了しつつある様子でした。小麦粉の価格が高騰する中で米の価値を見直そうとする動きが活発化しているようですが、水田を潰して大規模な商業施設を建設する動きが見られたり、人の食べられないような汚染米が食料米として出回っている報道があったりします。結局のところ行政や自治体はどのようにしたいのか、市民は実際には何を食べたいのか、そのような問題がそっちのけのまま、儲け話だけがひとり歩きをしているようにも見えてしまいますね。私はといえば、米が大好きです。白米もいいし、せんべいも、もちも、きりたんぽ、すし、栗ご飯・・・・・・ブログランキングに参加しています
2008.09.07
コメント(6)
-

かなづち、かんな、のみ・・・のこぎり!
ご無沙汰しております。。。日々更新を心がけて用意はしているのですが、結局居眠りしたりで・・・今回のこの記事は完成まで5日もかかってしまいました。そのようなわけで、当初は2回に分けて書く予定の画像を一度に使用したために、少々しつこくなってしまったかもしれません。文章を読むのが面倒でしたら、とりあえず写真だけでもご覧ください。時はモンキチョウの集団羽化らしき場面に立ち会うことになりました8月23日の土曜日。モンキチョウの羽化直後の個体、あるいは蛹が見つからないかと足許を眺めながらあるいていたところに、黒い甲虫がとことこ歩いているのを見つけました。初めはシデムシくらいかと思ったのですが、よく観察するとクワガタのように見えてきたのでした。ノコギリクワガタ♀ posted by (C)sasama_teaカメラを地面に置いて撮影した写真がこちらです。自信はありませんが、おそらくノコギリクワガタのメスでしょう。普段クワガタはあまり動き回る虫ではないはずですが、やけに動き回っていたので気になって観察すれば、何と数匹の蟻がたかっていました。ノコギリクワガタ♀ posted by (C)sasama_tea蟻が噛みついているくらいですから弱っているのかと想像してみるものの、どうやらその気配はないようでした。ただ単純に、クワガタが地面の上で余裕をかましているところに、動きの速い蟻に捕まって泡を食って逃げ回っていたということだったのでしょうか。足の先や体節の継ぎ目、果ては触覚まで計5匹くらいの蟻が取りついていましたので、気の毒にも思い、そのクワガタを捕まえて蟻を取り除き、助けてあげたつもりでしたが・・・ノコギリクワガタ♀ posted by (C)sasama_tea凄い剣幕で睨みつけられましたクワガタにとっては、蟻よりも人間のほうが疎ましいようです。ごめんなさい。。。そして、そのようなことがあった翌日のこと。雨を気にしながら午後遅く散歩に出ました。前日の場所から1km程度離れた場所ですが、こちらも草刈り直後で見るものも乏しく、とりあえず何か見つからないかと雑木林の縁伝いに探していました。すると、近くの木からぽとりと黒い物体が地面に落ちてきたのですが、何かと眺めてみれば、この地を10年以上歩き回って初めて見るオスのノコギリクワガタでした。ノコギリクワガタ♂ posted by (C)sasama_tea私が近くを通ったときにびっくりして落ちてきたのかもしれません。調べてみると、ノコギリクワガタは昼間土に潜って休んでいるのではなく、木の上などにいることが多いということですので、夕方といえどもまだ日が出ていましたし、ノコ君は寝ていたのかもしれませんね。捕まえてみるとその動きは鈍く、擬死(死んだふり)というよりは、もしかすると寝ぼけていたのかも?ちなみにこちらはノコ君が潜んでいたと考えられるコナラの樹液の出ていた場所です。うまくキヅタの葉に隠されていて、よく探さないと分からない場所でした。ただし、寝ぼけていたのではその潜伏効果も薄まってしまったようですが。最後に、こちらのノコ君の自慢の大アゴのアップで締めくくりとさせていただきます。ノコギリクワガタ♂ posted by (C)sasama_tea「文章少なめ」を目指すつもりでしたが、凝り性でダメですね。長々とお付き合いいただきありがとうございます。ブログランキングに参加しています修理に出したカメラの納期予定は5日でしたが、予定が過ぎてもカメラは一向に届かず、メールでの断りも何もなしです。「7日までには返送して欲しい」と但し書きをしておきましたが、顧客の意向に添えない旨を伝えて欲しいと願うのは望みすぎでしょうかね。対応部署は土日休みということで、全く以て打つ手なしです。か、かめらぁ。。。
2008.09.05
コメント(4)
-
さえない天気
日曜日で休みでしたが、雨が降りそうな雲とにらめっこしつつ外出の機会を窺っていました。結局ひきこもりのまま一日は過ぎてしまい、無為に過ごしたような一日でした。カメラは修理に出して手元にはなく、意気込みもどこかに置き忘れたような状態です。ただ、時折見せた晴れ間はありがたく、雨で溜まっていた洗濯物は随分と片付きましたので、生活面では良いこともあった訳です。溜まっていた疲れもありましたし、ぐうたら過ごすのも良いのですかね。正直なところ、心残りもあるのですけれど。。。雨が降り続き、夜の気温も下がったためにキノコがぽつぽつ生えていました。よく分からないキノコなので、食べませんよ。かつてはアミタケやチチアワタケなんてキノコがよく採れましたが、最近は林の乾燥化でさっぱり採れませんでしたが、適度に潤った千葉ではキノコも出てくるのかな。ここ数年ハツタケも食べていないですから、今年は秋の味覚を楽しみたいです。カメラもなく動機づけも弱くなってしまい、今日は文字だけで終わりにします。写真はもう少しありますから、次回はそちらを使用して書いてみます。では、おやすみなさい。。。
2008.08.31
コメント(4)
-

ハネを伸ばしたいとき
好事魔多し。再びデジカメが故障しました。ナナナナ、ナナナナ、液晶、故障・・・(ジョイマン調)撮影した直後に背面の液晶が眩しいほどに明るくなりまして、おまけに画像が横にズレて二重に表示されて訳が分からなくなってしまいました。 orzとりあえずこの状態で撮影を試みて、パソコン上で確認してみると画像データ自体は壊れていないようでした。ただし、設定変更などのデータは液晶画面に表示されるような仕組みですから、このままでは思い通りの写真を撮るのは困難です。仕方がないので再び里帰りしてもらうことにしました。幸い、雨が激しく散策どころではありませんので、手元にカメラが無くなっても手持ち豚さん・・・いえ、手持ち無沙汰にはならない、のかなぁ。早く戻ってきてね、と祈るばかりです泣き言はここまで。雷でメインメモリを壊してから、雷が近づいてくるとパソコンを起動しているのが怖くなってしまい、ここ数日更新がおろそかになっていました。そのため先日のモンキチョウの話から随分と日が空いてしまいましたが、そのときの続きの話となります。先々週の土曜日となりますが、草刈りから回復しつつある草場を歩いていると、なぜかモンキチョウの姿が目立つことに気づきました。突然足許の草陰から飛び出すモンキチョウもいて、お互い驚いている状況だったと思います。ただ、飛び出してきた蝶は力なく近くの植物の葉に降り立って動かなくなることも多く、そのことが少し引っかかることでもありました。モンキチョウ羽化 posted by (C)sasama_teaこの写真の蝶、じつは発見時には地面の上でジタバタと暴れていました。何をしているのか疑問に思いましたが、すぐ近くで見つかった黄色のサナギの殻で状況が飲み込めました。翅も完全に開ききっていないようですし、何かの拍子にどこかから落ちてしまい、飛び立ちたくてもまだ飛び立てず、状況が好転しないまま空回りし続けていたのでしょうね。状況証拠も兼ねて、ジタバタ逃げ回るこの子を掬い上げ、脱出殻の見える場所に乗せてあげると落ち着いたのか、あれほど暴れていたのが嘘のように静かになりました。いい子だ、そのままもう少し待てば飛べるようになるのだよね?状況が飲み込めれば、他にも同様な状況が見つからないかと探してみましたが、意図的に探すと見つからないものですね。ムラサキツメクサの枯れた黄色い葉がモンキチョウの翅に見えてしまって紛らわしく感じましたので、結果が得られないまますぐに止めてしまいました。それから近辺を散策しているうちに雲行きがみるみる怪しくなってきましたので、雨が降り出す前に帰らなくちゃ、と自転車まで戻るとこちらのような光景が待ち構えていました。灯台下暗しとは、まさにこのことです。モンキチョウ羽化 posted by (C)sasama_tea条件はばっちり、教科書的な状況でしょうか。そろそろ飛び立てるのではないかという状態のモンキチョウに出会うことができました。全ての状況を加味した訳ではありませんが、この日はモンキチョウが羽化するのに適した日だったのでしょうか。草刈りの災難を受け、草もろともモンキチョウの幼虫の大半も被害を受けたと想像するのは難くない事実でしょう。その際無事に生き残った幼虫の多くが、何とかして生き残ろうとサナギに変態し、そこから同時期に羽化した成体がちょうどこの日に多く見られたということだったかもしれません。想像通りだとすると、虫が被った災難はいかほどのものだったのでしょう?一網打尽の危機だったのかもしれませんね。人の無知な行動の怖さ、改めて思い知らされたような気がします。突然ある種の生き物が消えてしまったと感じる背景には、人の愚かな行動が関係しているのかもしれないと考えると、何かやる瀬無い気持ちになってしまいます。何か私にできることがあるとすれば、とても小さなことではありますけれど、今回のように自然界で起きていることを写真で紹介していくことでしょうか。意図するままに伝わるかは疑問も残るところではありますが、新たな発見や、建設的な行動につながれば・・・そのように思います。上の画像はトリミングしたもので、本日3枚目の写真と同じ個体のものです。蝶を正面から眺めるとおかしな顔ですが、ピンクの足といい、間近で観察してみるのも楽しいですよ。人の記憶力なんてあまり当てになりませんし、一瞬を永遠にしてくれるカメラは偉大ですね。カメラも虫も、ますます好きになってしまいますよ。ブログランキングに参加しています
2008.08.30
コメント(6)
-

目がかゆい?
前回のトンボの話のときと同じ日の土曜日、やけにモンキチョウが多くなったと感じたそのときに撮影した写真が下のものです。モンキチョウ、眼をコシコシ posted by (C)sasama_tea何の変哲もないモンキチョウの写真です。ただ、写真をクリックした後に見られるもう少し大きな状態では、前足が複眼の前にかざされていることがよくお分かりになると思います。その前足、実際にはかなり速く複眼の前を動かされていて、まるでかゆくなった目をこすっているような光景でした。この写真は接写5cmで撮影しましたが、普段のモンキチョウは近づくとすぐに逃げてしまうほど警戒心が強いようです。このときばかりは私が見えていないのか、全くの無警戒状態のようでした。それはまるで、私を構っていられない状態にあったようにも見えました。珍しいようでしたので、動画撮影に切り替えようとモード設定を変えている隙に、お掃除されてすっきりした視力で見つけた私から逃げるためでしょうか、この子はすっと飛び立ってしまいました。もう是非皆さんにも見ていただきたかったので実に残念です。とにかく可愛らしい仕草でしたよ。・・・と、モンキチョウの話はもう少し続くのですが、時間の問題で次回に繰越しになってしまいました。ではでは。。。ブログランキングに参加しています
2008.08.27
コメント(4)
-

DRAGONFLYは火を吹かない
以前このブログで『トンボがトンボを襲うとき』と題して記事を書いたことがあります。その当時、トンボが同類のトンボを襲う現場に偶然にも立ち会わせ、その状景を観察しつつ、現場カメラマンさながら無我夢中に撮影してしまったことを今でもはっきりと憶えています。こんな偶然に度々出会えることもないだろうと諦めていましたが、ま、何の悪戯か、出会えるものですね、またも目撃することになりました。土曜日当日、雲行きは怪しく、雨がいつ降り出してもおかしくない状態でしたが、カメラが修理から戻って来たこともありまして、折りたたみの傘を持参で散策へと出かけました。ただ、時間も遅く、遠くへ行けそうもない状況で、どこへ向かうか決まっていたわけでもなく、「そうだ、あそこへ行こう」と何となくその場で決め・・・というよりは、実際のところ誰かにでも呼ばれるような感覚、そう、『何かが起きる際のいつもの前兆』とは大げさですが、人知の及ばない超感覚みたいなもので、その場へ引き寄せられるように感じることがときどきあります。とりあえず何か当てがあるでもなく、草刈りから回復しつつある草地をふらふら歩いていましたが、自然の中のドラマはいくつも見つかりました。(そちらはまた別の機会に。)そのようなとき、足許のアシの葉にトンボの姿が見えたのですが、初めに見えたときから何かの違和感がありました。(・・・とその前に、映像自体が衝撃的でもありますので、グロいものが平気な方だけこのさらに下の写真をご覧くださいませ。) シオカラトンボ posted by (C)sasama_teaこちらの写真は先ほどの話とは無関係ですが、下のグロい写真を隠す意味を持たせています。緑色の複眼がきれいなシオカラトンボの♂、争いもなく和んでいるようにも見えますね。肉食の闘争心など微塵も感じられないかもしれないです。さて、心の準備ができましたら、下へスクロールしてください。このまま本題へと参ります。。。その違和感とは、例えば、蜘蛛に捕まえられたトンボを見ているような、トンボの生体がそこにあるようには感じられないような状況。とにかく、立った状態から見ると何かが変でした。シオカラトンボの狩り posted by (C)sasama_tea腰を下ろして真正面で眺めれば、全てが解決しました。シオカラトンボが、他の種類のトンボを捕らえて食事の真っ最中だったのです。しかも頭からガブリ!!モグモグと動き続けるシオカラトンボの口の動き、かなり生々しいものでした。ちなみに、設定のことを気にせず急いでいたために酷い画像ですが、その様子の動画をフォト蔵で見られるようにしました。その様子は下のリンクからご覧いただけますので、ご興味のある方はどうぞ。動画『シオカラトンボがトンボをかじる』いかがでした?共食いと称される方もおられるようですが、同じトンボのなりをしていても、種が異なれば敵も同然。肉食のトンボにとっては餌との認識しかないのかもしれないです。自然を眺める上で忘れてはいけないことは、人の頭の中で考える知識はあまり役に立たないことも多い、ということでしょう。フィルターをかけて見てしまうと、真実から遠ざかってしまうかもしれないのですね。そこにあるものをありのままに捉えること、つまりそれはまさに子供の視点。大人の目には映らないものもあったり・・・ということは、私は未だにただのガキだということを証明しただけのようです。世間的には変人扱いされる立場ということなのかもしれませんけれど、とりあえず私自身は楽しいので問題なしでありますブログランキングに参加しています
2008.08.26
コメント(6)
-

ブライダルベールのごとく
ようやくカメラが修理から戻ってきました。22日が納品予定でしたが、それよりも1日早く21日には手元に届きました。再び手にすると、撮りたい気持ちがふつふつと沸き起こってきます。・・・というわけで、22日の夕方、気になっている花の撮影へと出かけてきました。ガガイモ posted by (C)sasama_teaつる植物のガガイモは、民家近くで雑草として見られることもありますが、その花をじっくりと見られることもあまり多くはないのかもしれませんね。花はそれほど大きくはないため、観賞価値を見い出してもらえることも少ないでしょうが、じっくりと観察してみると面白い花です。毛深いし。。。そして近くまで寄ってみますと、独特の酸味のある香りにも気づいていただけるかも。人によってはお好みに合わないかもしれませんが、一度は試してみませんか?この時期にいちばん気になる花が今回の目的です。足が速いので、花が散ってしまっていると楽しみのひとつを失ってしょげてしまいます。(半分は嘘です。)センニンソウ満開 posted by (C)sasama_teaセンニンソウの白い花。つる植物ですから、条件さえ整えばかくのごとく美しい姿で花を咲かせてくれます。下地になっているのはムラサキシキブの木で、紫色の実が熟す前の前座的な役割を担い、この白い豪華な花を見せつけてくれます。白い花の姿のみならず、甘い香りも大好きです。上のほうから白い花で覆われた姿は、花嫁を飾るブライダルベールのようでもありますね。満開の純白の花をしばし堪能しました。ちなみに、クレマチスとはセンニンソウ属の総称で、まさにこちらが代表種となっています。そしてキンポウゲ科である本種、樹液が皮膚に触れるとかぶれることがあるそうですから、花を採取するときにはご留意ください。(葉に触れたくらいでは大丈夫だと思います)あぁ、花はやっぱりいいですね。久しぶりに心が癒されました。ここ数日は気温が低下して、秋を感じさせるような雰囲気になりました。遠くからはカネタタキの声も聞こえてきましたし。秋の七草であるクズの花もちらほら目立ち始めましたので、何となく秋が実感できます。このまま暑さを忘れさせて欲しいものですね。ブログランキングに参加していますネタだけ握り締めて、ブログを更新する格好のまま眠気と戦い、そして負け続けています。新鮮なネタだけは持っていますが、握った手の温もりでそのまま腐ってしまいそうです。以上、ひとりごとでした。
2008.08.23
コメント(4)
-

蜂とて生き物
昼間の暑さは相変わらずですが、夜になると気温は下がりやすくなってきたようです。関東でも大雨や竜巻の注意報がよく出ていますから、大気はかなり不安定なのでしょうね。そのからみか、先ほど突風が吹いて部屋の中が冷たい空気で満たされました。暑さを和らげてくれるのは大歓迎ですが、突然の大雨なんかは最悪です。ゆるゆると過ごせる秋がやって来ることを祈りましょう。さて、前回はアブでしたが、今回はハチの写真です。ハラナガツチバチ posted by (C)sasama_tea以前ご紹介しました青紫のムラサキツメクサの花を再度確認のために訪れたときに撮影した写真です。小さな花から一所懸命に蜜を吸うのはハラナガツチバチというごく普通の、どこででも見られる中型のハチです。正確は非常に大人しく、人が近づくとどんどんと逃げていってしまいます。あまりしつこくカメラを近づけるとうるさそうに牽制してきますが、さっと身を引けば、刺されることはないと思います。このハチに限らず、蝶でも、体の長い虫がその体に見合わないような小さな花から蜜を吸おうとしているとき、写真のように体を「くの字」に曲げていることに最近気づきました。その姿がいかにも一所懸命で、一途な感じで可愛く思えてしまいました。そしてもう1枚。本来なら組写真でお見せするはずでしたが、とりあえず1枚だけの公開になります。スズバチ posted by (C)sasama_teaセメントがむき出しでざらざらした感触が気に入ったのでしょうか、蜂の巣が作られていることに気づきました。巣の大きさは気づいた当初はかなり小さく、この種のハチが作る標準的なものでした。そのハチの種類は想像できましたが、いかんせん巣の主は現れませんでした。そして、主の姿が見えないまま巣は徐々に大きさを増し、肥大し続けました。しかも、どこから運んできたのか巣材は黒い土。さらに進むと茶色の土も織り交ぜられ、芸術的な雰囲気が漂い始めてきました。ハチの巣の作り始めに気づいてから5日後、とうとうその巣の主に出会えたときに撮影したものが先ほどの写真です。正体が分からないままビビり気味に撮影したためにピントが甘くなってしまっています。ただ、近づいても攻撃してくるほど好戦的なハチではありませんでしたが、近づきすぎたためにホバリングしながら「近づくな」という意味の警告は受けましたそれからネット検索で調べると、程なくスズバチと判明しました。鈴型の巣を作ることから名づけられたそうですが、写真の巣から想像することは難しいですね。複数の本来鈴型の巣を複数組み合わせたことで、肥大した異様に大きい泥製の巣となってしまったようです。検索でも分かりましたとおり、スズバチの性格は大人しく、滅多に人を刺すことはないとのこと。ただし、その毒は強いらしいです。単純に、人が余計なちょっかいを出さない限りは敵とはならず、むしろ一般に嫌がられるイモムシを餌としていることから、益虫と考えて良いのだと思います。言うなれば、人が積極的に守るべき虫のひとつなのではないでしょうか。スズバチの巣ということが分かり、私はこの巣を守るべきと考えました。ただ、泥で作られた割に硬くしっかりしているために、壁からはがすことは容易ではなさそうです。管理会社の定期清掃で壊されると危惧したのですが、油断している隙に完膚なきまで破壊し尽くされました。後に残された残骸にはアリがたかり、数個の巣の欠片が見つかるだけの悲しい結果となってしまいました。『蜂が怖い』というのは、ある種の先入観からもたらされる誤解で、人を襲うほど好戦的なハチはそれほどいないのではないでしょうか。虫だって生き物ですし、人の都合のいいように拡大解釈すれば、人が安定して暮らせる基盤を作り上げているのは、人が「虫けら」と蔑んでいるちっぽけな存在。『虫のいない快適な暮らし』をお望みになれば、虫を退治した人間も同時に存在が危ぶまれるのでしょうかね。ミツバチが消えただけで、養蜂のみならず、農業にも深刻な影響が及ぶわけですから、「嫌いなものだから消えてしまってもいい」というような傲慢な考えは捨てたほうが良いのかもしれませんね。先日、地面に転がるゴキブリの死骸がアリによってバラバラにされ、巣に持ち込まれて数日のうちに消えてしまったのを見て改めて思いました。「小さな虫は凄い!」と。。。ブログランキングに参加していますようやくカメラの修理完了メールが届きました。納期予定が22日でしたから、予定通りに手許に届きそうです。
2008.08.20
コメント(6)
-

おっきいアブ
カメラが手許に有っても無いような状況ですので、故障以前に撮り貯めた写真も底を突いてしまうかもしれないと焦り始めています。次の週末には帰って来ない・・・でしょう。何とかなる。。。かなぁ。そして、今日も花がありません。おそらく、見た目だけで嫌われそうな虫の2態です。一瞬ハチか? と勘違いしてしまいそうですが、こちらは大型のアブで、ゴツゴツした印象にぴったりのオオイシアブという名前でした。全体に黒っぽいのがオスということですから、この写真の個体もオスみたいです。→寝ぼけていましたので、訂正します。胸の部分にオレンジ色の毛が生えているのが♂、全体が黒いのが♀でした。ゆえに、写真の個体は♂です。このアブが乗っている葉はヤマフジのもので、想像するとアブの大きさもご理解していただけるかと思います。撮影時点では名前すら知らない虫でしたので、恐る恐る近づき、風で揺れる葉の上のアブを接写で撮影しました。ただ、なかなかピントの合う写真を撮れず、失敗しながら何度もしつこく撮り続けてしまいました。その間、大きなアブは動かず協力してくれていましたが、不意にうるさそうに顔をかすめて飛び去ってしまいました。そのとき、少しだけビビってしまったのはいうまでもありませんただ、このオオイシアブは特に人を襲ってくるわけでもないですから、手出ししなければ大きいだけの虫みたいです。そして、先日私の足にやって来たシオヤアブをご紹介しましたが、またも近くまでやって来たシオヤアブを見てしまいました。大きく撮影しているようですが、じつは元の写真からトリミングしました。出窓の外の枠にやって来たシオヤアブに気づいて、室内からその様子を撮影してみましたが、彼もまた小さな虫を捕らえていました。うーん、捕らえられている虫の正体は分かりませんねぇ。赤い触角・・・甲虫ですが何でしょう。その状況が、捕らえた獲物を見せびらかしに来ているようにも感じられますが、ま、私の妄想です。トンボも獲物を捕らえているときは、枝先にとまってあまり動き回らずムシャムシャ食べることに専念したがっているように見えます。そのようなときは絶好の被写体になってくれますので、こちらのアブも似たような状態のようですね。食事ぐらいはゆっくりと過ごしたい、というところなのでしょうかね。その証拠にしばらくこの場所に居座り続け、しばらくして気づいたときにはいなくなっていました。見た目は獰猛で、スズメバチのように人でも平気で襲ってきそうな気もしますが、今回の大型のアブ2種はどちらも特に人へ危害を加える虫ではないようです。毛むくじゃらで、大きな眼を持つ大きなアブも、見ようによっては愛嬌のある顔にも見えてしまう・・・見えませんか?危険な虫も多いのですが、そうではない、見た目だけで損している虫も多いことでしょう。とりあえず「怖そう」という理由だけで退治するのは止めましょう。彼らにだって存在理由はあるし、どこかで人の為になっているはずですから。。。(益虫は守り、害虫は殺せと述べているわけではないので、念のため)ブログランキングに参加しています
2008.08.18
コメント(4)
-

うるしとマンゴー
カラカラの大地にようやくまとまった雨が降りました。気温も幾分下がり、ちょっとだけ過ごしやすいです。上の写真は、とあるお宅での撮影です(ケータイで撮影)。「反省」のポーズでも取るように、花も何もない場所で休むナミアゲハの後翅の突起は傷ついていて、近くに寄っても逃げることがなく、どことなく元気がない様子でした。もう少し近づいてみるとびっくりしたように飛び立ち、弱々しく低空飛行するものの、数メートル向こうの地面に降りてしまいました。追いかけてみると逃げようとするのですが、勢いがなくてすぐに降りてしまいます。人の世はお盆でしたから、どなたかの魂を乗せて家主の元へやって来たのかと話しましたが、赤トンボのみならず、アゲハチョウなどにも故人の魂の面影に思いを寄せることもいかがなものでしょう。ここまでは近況ですが、ここから後の話はひと月前くらいことです。山には人体に危険を及ぼす虫や植物が相当数用意されているわけなのですが、その中でも代表格のウルシ、弱い方は大変みたいですね。私は幸いなことにウルシかぶれには耐性が備わっているようで、その症状は拡がったりせずに、軽症で気がつくと完治していることがふつうでした。ちなみに調べてみると、ウルシによるかぶれはアレルギー性接触性皮膚炎と呼ばれるもので、その樹液に触れたり、木の傍を通ることで引き起こされるそうです。その原因物質はウルシオールと呼ばれるもので、ウルシ科ウルシ属に含まれることが多い、とのこと。意外なことにその他にも、食品では馴染みの深いと思われるマンゴー、カシューナッツ、ピスタチオなどにも少なからず含まれるそうです。さて、ひと月程度前のことです。里山付近での散策では必ず軍手着用で事に当たるようにしているのですが、運悪く忘れてしまい、素手で行動をしたことがありました。きっとそれが原因で、気がつけば手の指にウルシかぶれのような症状が表れていました。ただし私の場合は、水疱のように見えても1mm程度の大きさしかなく、決して破れることもありません。いつものこと、とそのまま放置していたのですが、ある私の行動とともに状況は一変しました。メロン、リンゴ、マンゴーの入ったドライフルーツをそのとき食べました。かぶれが気になっていたまさにそのときに食べたわけで、小さく書いた部分でお分かりのように、ウルシオールを体内から摂取したためにウルシかぶれを助長してしまったようです。もともと生じていたかぶれは左手の指のみでしたが、ドライフルーツを食べた翌日には右手にも症状が表れ、皮膚の表面が赤く腫れる部分が表れ始めました。それほど酷くはないのですが、段々とかゆみが増し、気がつくと一部の足の指にも飛び火していました。マンゴーの件を調べてから、口の中も少し腫れていることにも気づきました。ただ幸いなことに、症状が表れたのは手足の指と口内の粘膜のみのようです。小さく記した中に「アレルギー性」とありますが、あくまでもウルシオールという物質はかぶれの原因を作るだけで、体の中を駆け巡って各所で症状をまき散らすわけではないようです。アレルギーが原因ですから、たとえ触れた部分が手だけであっても、体が過剰に反応すると全身に症状が表れてしまうのでしょうね。(原因物質に触れたとしても、しっかりと石鹸などで洗っておけば他人にうつす心配は無いようです。)ドライマンゴーを口にした翌日に左右の手指が赤く腫れてかゆくなっても、さらに翌日も余った残りのドライマンゴーを食べ続けました。そもそもその時点では原因がマンゴーにあるとは露ほども知りませんでしたから、原因を追求できても後の祭りです。食べた後の数日間は腫れが酷かったものの、指以外には拡大の兆候はなく、状況を冷静に判断し、「待てば治る」と訳の分からない自信を根拠に1週間を過ごすと、赤い腫れはほぼ沈静化しました。ふぅーっ、とひと安心でした。その後はほぼ気にすることなく過ごし、ひと月程度経過した現在では、ぷっくり膨らんでいた場所が体の内側から再生を始めて、症状を生じた皮膚の表面が剥がれています。(かさぶたが取れたような状況です)危ない橋を渡ったようにも感じますが、とりあえず何事もなくやり過ごせました。つくづく悪運が強いです。アレルギー反応で有名なのが、スズメバチの引き起こすアナフィキラシーショックです。ごくごく簡単に申せば、スズメバチに2度刺されると命に危険が及ぶこともあるということです。そのアナフィキラシーショックという異常なアレルギー反応は、ときとして食品からももたらされることもあり、全く関係のない食品の食べ合わせが原因で症状が引き起こされることもあるそうですから、何かを口にした後に体調が急変した場合には気をつけるようにしましょう。自分だけでなく、アレルギーを持つ方が近くに居られる場合は特に気をつけたほうが良いかもしれませんよ。では、美味しいものが多くなる秋、不意のアレルギー反応にはご注意あれ。ブログランキングに参加していますウルシには耐性を有する私ですが、ウルシ同様の症状を表すというノウルシ(トウダイグサ科)の仲間のナツトウダイ(じつは不確定。原因は他にあるかもしれません)にかぶれ、全身が真っ赤に腫れて散々な思いをしたことがあります。とにかくかゆくて、おまけに全身が熱を持って耐えがたい状況でした。教訓としては、素手でむやみやたらに自然のものに触れたりしないということと(帰宅後や食事前には手洗いを奨励)、症状が軽いうちに手を打っておくほうがつらい思いをしなくて済むかもしれないということです。前述の状況でも、注射1本でほぼ数日のうちに大体収まりました。くれぐれも轍を踏まないように。。。
2008.08.17
コメント(6)
-

葉っぱかじっても 大目に見てね
「残暑厳しい・・・」などとよく表現されていますが、昨今はどこまでも夏が続いているように感じてしまいます。秋を感じる暇もなく、気づくと冬? となってしまわないことを今のうちから祈っておきたい気分です。体が重く感じます。。。えい、やっ! と気温を下げる魔法をかけたいですねぇ。はい、ここまでは独りごと。里山まで出かければ探し物もいろいろ見つかるものですが、人里近くでは「これでもか!」とばかりに夏の草刈りが行なわれています。クローバーが繁茂してうっそうとしかけた場所も今はスポーツ刈りの頭のような状態で、花もなければ虫もどこかへ行ってしまいました。花のほうは刈られてしまって、写真向きの被写体を探すのが困難になっています。今年は特に・・・ですね。これも良い機会と、今年は虫を探しています。おそらく虫を見るにしても、きれいとかカッコいいとか、ひいきしている虫を見るときと、地味でどうでもいいと感じる虫を見るときとの扱いはかなり違うのでしょう。マメコガネ posted by (C)sasama_tea小さなマメコガネも、きっとそのような虫のひとつ。樹液に群がるカナブンの輝きに囚われても、マメコガネを美しいと感じる人も少ないでしょうね。写真ではヤマノイモの葉をかじっている様子が窺えますが、農業では害虫として嫌われており、遠く北アメリカ大陸でも害虫として日本から帰化し、Japanese beetleと呼ばれているそうです。小さいといえども侮れない存在です。シロコブゾウムシ posted by (C)sasama_tea普段はあまり気にしないゾウムシの仲間でも、花が見つからなければカメラもそちらへ向くことに。。。ゾウムシとしては少し大きめのシロコブゾウムシという種類のようです。粉を吹く体と、後ろ側のふたつの突起が特徴とのこと。食草はマメ科植物ということで、縁がかじられたクズの葉の上で動きもせず休んでいました。名前はゾウムシですが、見た目はバク(獏)のようでもあります。この写真を撮影しているときにクズの花の香が漂ってきていたのですが、探せどもその花の姿は見つからず。ああ花がないねぇ、と地味めな虫を撮るばかりです。ところで、ゾウムシにもいろいろいるもので、撮影はほぼ1年前になりますが、このようなゾウムシを部屋の窓際で見つけました。「象の鼻」に当たる口吻が著しく長く、国内のゾウムシの中では最も長いそうです。名前はツバキシギゾウムシで、口吻が鳥のシギの嘴に似ていて、ツバキの実に卵を産み付けることに由来しています。メスの場合は体長よりも口吻のほうが長いそうですから、写真の個体はメスのようですね。まったく、生き残るために何かひとつに特化した生物はどこか滑稽に思えても、その狡猾なほどに美しい形態には見惚れてしまいます。人間にもそのような要素が多く備わっていると思いますが、うまく生かされているのでしょうかね?随分と無駄になっているようにも感じますが・・・。ブログランキングに参加しています
2008.08.14
コメント(6)
-

すももももももあんずもうめも
暑さでそろそろバテ気味になりつつあります。ここ数日は少し涼しくなってきたようでひと息ついていますが、体がすこーし重く感じるようになってしまいました。とにかく食べて乗り切ります!カメラから写真のデータが取り出せないため、最新の状況報告ができなくなってしまいましたので、さかのぼって春まで時を戻してしまいます。梅が咲き、次いで桜が咲くその中間あたりに、生まれて初めて見る花がありました。それは桜の花に似て桜にあらず、どことなく梅の花にも似ているも梅ともまた異なる。バラ科の花には違いないと確信するものの、図鑑で調べても分からないままの花がこちらでした。スモモ posted by (C)sasama_tea遠くまで香るほどではありませんが、近くで嗅ぐと桜や梅とは格段の差、とにかく甘い芳香がその花にはありました。そのせいで完全にひと目惚れです。スモモ posted by (C)sasama_tea木の高さは4mくらいで、幹も枝もかなり細め。根元から数本の幹が立ち上がるのは野生の桜と同様の性質。桜の花に比べるとふたまわりくらいは小さめでも、たくさんの花が咲くためにかなり豪華な木でした。花の季節が終わり、甘い香りが気になってしつこく調べるものの全く手がかりがつかめず、ようやくしっぽをつかみかけたときに、下のような実を見つけたのでした。表面には毛が生えていなくて、白いブルームと呼ばれる粉が吹いています。(撮影は6月14日)見た目は、梅のような実です。このあたりで確信が持てました。バラ科のスモモだろう、という結論です。おそらく間違いないでしょう。スモモはもともと中国から渡ってきた植物で、広く日本でも栽培されたり、庭木として植えられてきたようです。私も子供の頃に、祖父の家に植えられていた巴旦杏(はたんきょう)と呼ばれるスモモの実のお裾分けに預かっていました。先ほどの写真からおよそ1か月後の7月19日。まだまだ硬いままでしたが、外側は赤く色づいていました。周囲には同様の木は1本も見当たらないようで、誰かが植えたとしか考えられないこのスモモらしき木ですが、ついていた実は見つけられただけでこのひとつだけです。もともとスモモは、単独では実をつけることが難しいらしく、傍に桜や桃などの同時期に花を咲かせるバラ科の木を近くに植えると実つきを良くすることができるそうです。この木の傍にはソメイヨシノとヤマザクラはありますが、双方を行き来する虫や鳥はほとんどいなかったのでしょうね。たったひとつだけの実を観察し、野生のものだから甘くないかも・・・などと食べることを前提にしていましたが、上の赤くなり始めた実を撮影した1週間後。。。見事に無くなっていました。落果したのかと直下を探してみるも見つからず。ある種の喪失感とともに、言葉が見つかりませんでした。・・・来年は、私自ら受粉を行なうことにします。きっと、いっぱいつくよ。。。ブログランキングに参加していますなお余談ですが、中国には『君子は瓜田に履を納れず、李下に冠を正さず』(くんしはかでんにくつをいれず、りかにかんむりをたださず)という格言があるほど、李(すもも)は桃に並んで人気のある木だそうです。ちなみに、前述の格言を要約すると、「誰かが見ているかもしれないので、紛らわしいことをするでない」という意味になります。気をつけましょう。
2008.08.11
コメント(6)
-

つなぎのカメラ。。。
故障してしまったデジカメは、木曜日に里帰り。帰宅予定は22日以降になりそうです。夏季休業とも重なってしまい、少しだけ遅くなるようです。そこで、知り合いから古いデジカメを借りることになり、とりあえず今となっては信じがたいほど分厚いデジカメ持参で散策へと出かけました。目の前のオニヤンマを逃したりしつつも、使いづらい旧式デジカメを駆使して数枚撮影して帰宅し、さてパソコンに取り込もうかとUSBケーブルを繋ごうと・・・繋がらないよ・・・旧式ゆえ、『専用USB』ですって。(ちなみに、FinepixA210という機種です)おまけにxDピクチャーカード使用で、私の環境ではパソコンに取り込めません。ははは。。。四苦八苦しながら撮影した写真は、とりあえずお預けとなってしまいました。お間抜けなことをしてしまいました。ま、取り込もうとして、コネクタが合わなかったときの私の気持ちを写真で表すとこのような感じで。ありっ?ちなみに、上の画像はトリミングしてあります。巣の入口で、蟻が頭だけ出して警戒している状態を写真に撮ってみたのですが、小さくても大写しにすると迫力がありますね。噛まれると、悶絶するほど痛くしてくれる蟻もいますし、侮れない存在です。ただし、私は旧式デジカメの能力を侮ってしまいました。ここまで使えないのかぁ!明日は早出ですので、おやすみなさい。それにしても、くやしい・・・ブログランキングに参加しています残暑が厳しいですね。体温より高い気温って、どういうことでしょう。皆さんも、お体大事に。
2008.08.09
コメント(6)
-

バッタ三様
これからの季節、虫の声が徐々に大きくなり、野原を行けばキチキチ音を鳴らしながら飛ぶバッタに出会う機会も多くなるでしょう。現時点ではまだ幼虫の段階のバッタも多いようですが、すでに成虫になっているバッタも見られました。(私の知識も経験も少ないために、気づかずに成虫になっているバッタも多いのかもしれませんが)ミカドフキバッタ posted by (C)sasama_teaこれまで気づいていなかったようで、後ろ足が青いきれいなバッタを見ることになり、思わずカメラを向けてしまいました。(7月20日撮影)フキバッタという種類のようで、主にフキの葉を食べているからその名になったとのこと。地方ごとにフキバッタの種類が違うそうで、東北から関東に生息する種はミカドフキバッタと呼ばれるそうです。あまり体が大きくなく、成虫でも羽が退化して羽ばたくことはできないそうで、おそらく写真の個体もこの状態で大人です。しかも、近づいても逃げず大人しかったですよ。そして、こちらも同日撮影。カメラを向けると・・・ヤブキリ posted by (C)sasama_tea頭を突き出して威嚇されてしまいました。左右にめいっぱい開かれた丈夫そうなアゴ、足に生えた鋭く長いトゲトゲ、そして大きな体。まるでエイリアンのよう。後々調べて知ることになりましたが、こちらはヤブキリという名前で、じつは肉食、ときにセミを捕らえて食べてしまうこともあるそうです。固定観念でバッタは草をはむ生き物と勝手に解釈してましたが、これほどまでに攻撃的で獰猛なバッタがいるとは思いませんでした。実際に飛び掛って来ることはありませんでしたが、体を大きく見せようと上下に体を揺らしたり、前後に飛び掛るような素振りを見せたり、今にも噛みついてきそうな勢いは感じました。虫の嫌いな方はのけぞって身を引いてしまうかもしれませんね。正体の分からないまま近づいた私も、ちょこっとだけ怖かったです最後は少し日付が戻りまして、今年の6月1日の写真からです。眼の下の涙線と呼ばれる黒い線が特徴のツチイナゴです。冬季を成虫で過ごすバッタでは唯一のこちら、7月くらいまでは成虫が見られるそうですが、さすがに現在はいなくなってしまったでしょう。再び地上に姿を現すのは10月のことだそうで、暑い夏を避けるサイクルは快適なのでしょうか。逆に寒い冬を成虫で過ごしている姿は、無駄に動かずじっとしているみたいです。実際に冬に見つけたツチイナゴの動きは緩慢で、敵が少なくて快適・・・とは見えませんでした。ま、人の感覚で眺めれば、理解のできない事象も多々ありますが、きっと大きなお世話ですね。子供みたいに自然相手に遊んでいる大人たちにとっては、そのような理不尽に感じられる虫などの生活様式が面白いわけで、どこを見てもつまらないことなんて無いのですよね?ブログランキングに参加しています
2008.08.07
コメント(4)
-

殻を脱ぎ捨てる
首都圏の各所で局地的な豪雨が最近目立ちますね。テレビでその豪雨を『ゲリラ豪雨』というような呼び方をしていたような気がしますが、幸い、未だ私はそのようなものに出会ったことはありません。雨が降れば、熱せられた大地も幾分冷やされて過ごしやすくもなりそうですけれど、突然の雷や鉄砲水など、暑くて耐えられないほうがまだましなのでしょうか。最近の天気予報を見るたび思うことでした。さて、自然観察のお話です。前回のカマキリくんに出会ったその日に、バッタの姿もたくさん見ました。草刈りから回復しつつある丈の短い草むらに足を踏み入れるたび、バッタが右往左往逃げ回ります。ときに、私の体にぶつかって、きびすを返して即座に逃げていく粗こつものもいたりします。そのような中、逃げもせず、草にしっかりとしがみついたショウリョウバッタの幼虫がいました。離すものかとがっしり長い葉を抱え込む姿は、何となく滑稽な姿にも見えてしまいます。ただその眼は真剣そのもので、カマキリの眼がカメラを睨みつけているように見えるのと同様、弱者であるバッタの眼にも迫力が感じられました。初めて見る光景で、いったい何をしているのか想像もできませんでしたが、すぐ後に見ることになった場面で、簡単に理解することができました。ショウリョウバッタ抜け殻 posted by (C)sasama_tea見た目はまるでミイラのようですが、先ほどの様子とほぼ同じで葉をしっかりと抱きかかえています。つまり、先ほどの様子は脱皮前のもので、小さくなった殻を脱ぎ捨てるために踏ん張っている姿だったようです。まるで出産に臨む妊婦さんのようです。相当な体力が必要で、近づいた私に構っていられる余裕はなかったのでしょうね。そのことを裏付けるように、1週間後に再度同じ場所に訪れると似たような光景があちこちで観察できました。風が強く、ケータイでの撮影ということできれいに撮れませんでしたが、雰囲気は伝わりますね?周囲を見て回ると、笑ってしまいたくなるほど同様の抜け殻だらけでした。未だ翅の長くないショウリョウバッタがうろうろしていましたから、成虫になるための脱皮が観察できるでしょう。必死に殻を脱ぎ捨てている様子を見てみたいです。バッタを話題にしましたので、こちらの写真も載せておきます。赤いバッタ posted by (C)sasama_tea突然現れた赤いバッタを逃げられる前に撮影しなければいけないと、慌てながら1枚だけ撮れました。(ピントが少し甘かったため、輪郭にシャープ処理を施しました)原版に若干色の補正をかけてありますが、実物も赤みを帯びた妙なバッタでしたよ。ネット上でも「ピンク色のバッタ」の画像が確認できますが、それらのバッタに比べるとかなり感動は薄くなるものの、緑や茶色以外の体色の変異体を見られたのは幸運そのものでしょう。捕らえて標本にしたいなどとは思いませんので、そのまま姿が見送りました。今後このバッタがどのように成長して、さらにどのような子孫を残すのか気になるところですが、植物と異なり虫の扱いに慣れていない私は「とりあえずまた会えればいいか」と見るだけにしました。赤いバッタならV3(ぶいすりー)か。。。などとほざき、また次回もバッタになるかもしれないと、予告しながら今回は終了です。ブログランキングに参加していますお分かりにならなければ、最後の部分は無視していただいて構いませんので。。。
2008.08.06
コメント(5)
-

弱者と強者
もう毎日のように「○○!」と書いていると、それだけで汗が出てきて気分が滅入ってきそうですので止めておきます。それでも、どこまで気温が上昇するのか、嫌になってしまうというよりも気がかりです。それでは最初は日曜日の話です。ケータイ片手にヤマユリの花を撮影する傍らで、少々飛び方のおかしな蝶に出会いました。状況からして傷を負っているように感じます。羽ばたくも飛び立てず、地面近くを右往左往していたのはヒメアカタテハ。観察すると、右の上翅の付け根に損傷を負っているらしく、羽ばたいても平衡が取れずに飛び続けられないようでした。逃げられないので被写体としては最適ですが、それでは事件現場で写真を撮り続ける輩とあまり変わりありませんので、数枚撮影してそれ以上追い回すのは止めました。弱ったこの蝶はいずれ捕食者に捕らわれてしまうはずで、あとは自然の摂理に任せる外ないのでしょう。その捕食者の一員、カマキリも随分と大きくなりました。オオカマキリ posted by (C)sasama_teaこちらは同じ公園内で1週間前に撮影しました。まだデジカメの画像です。地面をとことこと歩くカマキリを見つけると、スルスルと斜面を登り、木の上まで素早く移動していました。捕食者であるカマキリでも、遮蔽物の少ない場所では安心できないのでしょうね。これほどまで素早く移動するカマキリの姿は初めて見ました。移動が緩やかになったところでレンズを向けると、いつものようにカメラ目線となります。憎めない存在です。そしてもう少し歩いてみると、もう1匹のカマキリに出会いました。オオカマキリ posted by (C)sasama_teaこちらはセイタカアワダチソウの上に鎮座し、獲物でも待っているのでしょうか、風が吹くたびそれに合わせるよう左右に体をゆっくりと動かしていました。風に揺れる草の葉にでもなりきっているのでしょうね。ただし、レンズを差し向けるとこちらもカメラ目線。急いで写真を撮ります。何か気になるから動くもの、つまりカメラや人のほうを睨みつけるように眺めるのですが、危険がないと認識するとすぐに、興味がなくなったようにこちらを見てくれなくなってしまいます。捕食される虫にとっては最悪の相手かもしれませんが、私にとっては最高の虫ですね、カマキリは。しつこく追い回すと人にさえ反撃する気性を持ちながら、素直に手に乗ってくることもあるほど無頓着だったり、被写体としては申し分なしです。ところで、『自然調べ2008 夏休みカマキリを探せ』というイベントをご存知ですか?日本で初めてのカマキリの全国一斉調査を行なうそうで、全国からカマキリの成虫の写真を集め、その分布地図を作成するのが目的だということです。私も参加してみようかと思いますが、皆さんもいかがですか?童心に返って、カマキリと戯れてみましょう!ブログランキングに参加しています
2008.08.04
コメント(4)
-

芳しき山百合の花
カメラが故障してしまいましたが、ヤマユリの花が咲いているはずですから見ない訳には参りません。記録もとりあえず残しておきたいですから、使い勝手は悪いのですが、ケータイのカメラで我慢することにしました。ヤマユリ posted by (C)sasama_tea撮影した画像をケータイ画面で確認するのは難しいので、とりあえず枚数を多く撮影してきました。満足できる出来上がりではありませんが、ケータイでもそこそこの写真は撮れますね。先週はまだ蕾だけのこの小群落も、8割方の蕾は開いた状態になっていましたので、辺りはその花の甘い香りに包まれていて、いい気分にさせてもらえました。こうして日記を打ち込んでいるこの時点でも、ときどきその甘い香りの記憶が脳神経を刺激して、ありもしない香りを嗅いでいるように脳が錯覚しているようです。幸せな頭です。ヤマユリ posted by (C)sasama_teaまだ開いていない蕾もありましたので、この周辺ではあと10日くらいはヤマユリの姿と香りを楽しめます。ちなみに、場所は明かしませんが、このヤマユリは公園内に咲いているものなのですが、ひと月くらい前に草刈りされたときにこの場所だけ刈られずに残され、一部の人に見守られながら花を咲かせられる状況下にあるようです。多くの人がこの場所に訪れるようですが、ヤマユリに興味を抱く人も少ないみたいです。このときには近くには誰もおらず、盗掘されることもないようでもあります。無関心というのは少し問題ですので、注目しつつ見守れることのできる環境が必要ですね。ヤマユリ posted by (C)sasama_tea狭い範囲の個体群ですが、花の形質の個体差はかなり大きく、上の写真のような赤みの強い個体も幾つか見られました。写真では分かりづらいのですが、赤と黄色のグラデーションがきれいでしたよ。シロテンハナムグリ posted by (C)sasama_teaこちらは少し小振りの花。花弁の長さも、周囲の大型の花のおよそ半分程度で、反り返る性質も弱いようです。その小さい花を撮影しようと近づいてみると、そこにはハナムグリの姿がありました。ヤマユリの花には「よだれ」と表現しても良いくらいに蜜が出ています。その蜜を一心不乱に吸い続けるハナムグリの貪欲なこと。後ろから撮影されていることなど気づいていないのでしょうね。他にも小さな蜂やハエの仲間が花にいましたが、期待していたアゲハチョウの仲間の訪問には出会えませんでした。見栄えがするのでしょうが、残念です。庭の豪華な栽培ユリも美しいです。ただ、山に自生するユリは紛れもなくその園芸種に血を与えた原種ですから、絶やさないような環境作りと、見守ることのできる心構えを伝えてゆけたら、と思っています。甘く儚く夢の如き香りの山百合の姿が辛く切ない幻の花となりませんように・・・ブログランキングに参加しています
2008.08.02
コメント(8)
-

蝶の愛情表現?
前回の記事と同日のことです。ちょうどヒメウラナミジャノメとイチモンジチョウを見た間くらいの出来事になります。その日、周辺でタテハチョウの仲間が右に左に飛び回っていたのを見ていたのですが、近づこうとする逃げられ、無視すると近くにやって来るということを何度も繰り返していました。すると、ひらひらと舞っていたタテハチョウが降りてきて地面近くの葉の上にとまりました。観察すると、その翅の色と同じような枯れ葉の上にいるように見えましたが、しばらくの間そこから移動せずにいました。動かないなら、と意を決して少しずつ近づいてみると、あちらさん、熱心に何かを行なっているようで逃げません。それならもっと近づいて・・・と実行する前にとりあえず1枚。。。キタテハ posted by (C)sasama_tea1メートル程度の距離まで近づくとはっきりしました。枯れ葉と思っていたものは、同族の蝶のようです。途中、翅の開閉も行なっていましたので、撮影した写真からトリミングしたものがこちらです。帰宅後に調べましたが、よく似た種類との相違点は、後翅の表の模様の中の黒い斑紋、その中に青い模様があるとキタテハだそうです。表側の翅の色から、上に位置している個体はオスのようですが、未熟者ゆえ、下側の個体がメスかは定かではありません。そして話を元に戻します。近づいても逃げないようですので、カメラの設定をマクロ側にしてさらに近づきました。ほふく前進のように、半袖でむき出しの腕を地面に押し付け、体勢を低くしての撮影でした。(草刈り直後で尖ったものが多く、撮影後は擦り傷だらけになりました)キタテハ posted by (C)sasama_tea上側の個体がもう一方の横腹に頭を押し付け、熱心に何かを行なっているようでした。当初は、力尽きた仲間から体液を吸い取っているとも考えていましたが、この後上側の個体は飛び去り、一方の個体は横たわったまま残されました。残された個体がどのような状態なのかと調べようとした瞬間、その個体は勢いよく飛び去ってしまいました。しばし呆然です。キタテハをじっくり観察したのは初めてですし、このような状況に出会ったのも初めてです。愛情表現に決まりなどはないでしょうし、この光景もじつは何らかの愛情表現のひとつだったのでしょうか。謎ですねぇ。でも面白いですブログランキングに参加していますさて、ここからは余談になります。じつは、新しいカメラが故障しました。購入から4か月。ポケットに入れて持ち歩くことが多いのですが、たまに知らないうちに電源スイッチに当たって起動してしまうことがあります。レンズが出ていてびっくり、という状況です。今回、そのような状況でレンズが飛び出していたのですが、レンズが中途半端な位置で止まっていて、「レンズエラー」が出て何もできない状態になってしまいました。運悪くサポートも土日で休みのようで、無償修理をしてもらうとしても週明けからの対応になりそうです。あぁ、なんてことでしょう。がっくりです。
2008.08.01
コメント(6)
-

蒸し蒸し 虫虫
雲が多くて日差しが緩和されるかと戸外へ出ると、湿度が異様に高くて、晴れの日よりもじつは暑くて余計に疲れているのではないかと思うこの頃です。自転車で走っているときには、自分の汗がいい具合に気化熱を奪って涼しく感じさせてくれるのですが、止まった瞬間にその恩恵も無くなり、暑さを再認識した体が汗を噴き出させてくれます。こまめな水分補給が不可欠ですね。散策に出てみたものの、遠くまで自転車を走らせる気力も直ぐにそぎ落とされ、近場でとりあえず我慢するしかありません。目立つ花の種類も少なく、現時点では虫の姿を追いかけています。ただ、疲れているので逃げられるばかり。接写を臨めばまた逃げられるばかり、です。そのような中、ヤマユリの大きな蕾が目立つようになり、いつ咲くのかと楽しみにしている傍で甘い香りが漂ってきます。どこだろうと探してみると、笹薮の奥のほうにヤマユリの花が見えました。4、5メートルは離れているとは思いますが、さすがはヤマユリ、いい香りを堪能させてもらいました。近くには蝶の姿が多く見えますが、ほとんどはあっという間にどこかへと飛び去ってしまい、写真を撮る云々の以前に、未だに種類すら判別できないでいます。ヒメウラナミジャノメ posted by (C)sasama_teaふらふら~と現れたヒメウラナミジャノメのカップルを、ゆ~っくりと近づき激写。いわゆる、ピーピング。「お子様は何人おつくりになられます?」『今、忙しいから後にして!』「はぁ、ごもっともで」馬に蹴られて・・・退散します。イチモンジチョウの翅の表裏 posted by (C)sasama_tea生まれて初めて、まともにこの手の蝶の同定が行なえたかもしれません。黒地に白い模様の入った蝶が目の前を通り過ぎるのを何度も確認していましたが、写真にも収められず、ゆっくりと眺めることもできずでどの種類が生息しているのかも分からずじまいでした。ようやく近くで観察できる機会に恵まれ、2メートル弱程度の距離から光学3倍で狙ってみました。一定間隔で翅を開いたり閉じたりを繰り返し、表裏の模様の違いもばっちり撮影できました。ちょうど図書館で借りてきた蝶の図鑑がありましたので調べてみると、どうやらイチモンジチョウで良いようです。あぁ、いろいろな意味ですっきりしました。もう一種の蝶も同日に撮影できましたが、写真の加工が間に合わず、次回に繰り越します。それは妙な光景でしたので、是非ご覧いただきたいと思います。ブログランキングに参加しています余談ですが、愛用のノートパソコン以外でこのブログを見る機会がありまして、そこで愛機のモニターの発色がおかしいことに気づかされました。ゆえに、これまでの当ブログで扱ってきた写真の色使いが「変」だったということも分かりました。パソコンのモニターの色設定を、少しカメラのモニターの色使いに合わせて調整してみましたので、ズレが解消されて、今回からまともな画像になっていると良いのですが・・・いかがでしょう?
2008.07.30
コメント(4)
-

実りの秋のその手前
曇り空の土日、暑さだけはしっかりと健在で、自転車で移動の都度汗だくになり、行動がかなり制限させられています。おまけに日曜は予報どおりに今にも雨が降りそうで、遠出を阻む嫌な圧力をかけらてしまいました。ぽつりと数滴の雨に出会うものの結局は降らずじまいでしたが、日差しが雲に遮られているはずが逆に暑いのなんの。休み休み移動していましたが、帰宅後に撮影した写真を見返してみると、ほとんど写真を撮っていませんでした。さて、暑いさなか、秋は未だ遠く、想像することもはばかられそうですが、実りの秋は着々と近づいてきているようでもありました。山栗 posted by (C)sasama_tea山栗のイガはゴルフボール程度の大きさまでに生長しています。マナーの悪い人との競争ですが、お口汚し程度でも食べられるとうれしいです。そして、こちらは水田の様子です。花といってもピンと来ないかもしれませんが、こちらもれっきとしたイネの花です。稲穂 posted by (C)sasama_tea台風などを経験しながら、これから秋に向けて美味しいお米へと生長していくことでしょう。食欲の秋が待ち遠しいです最後は少し毛色が異なりますが、食欲が抑えられない者の様子を撮影した写真です。クサギ posted by (C)sasama_tea葉をすり潰すとニオイが酷いということでついたクサギ(臭木)の花は、その名に反して良い香りで好きな花のひとつです。その花の蕾がそろそろ咲きそうな状態を確認してきましたが、その蕾の脇にはハナグモの幼体がすでに陣取っていました。気が早いというか何というか、花が咲く前なのにすでに匂いを嗅ぎつけて来たのでしょうかね。いつも感心させられますが、蜘蛛たちは何に惹かれて花へとやって来るのでしょう?ふしぎですよねぇ。ブログランキングに参加しています暑くてへとへとになって帰ってきても食欲が無くならないのが幸いです。本日はカレーでした。暑いときはあっさり食べたいと思うことが多いものの、やっぱりカレーも外せませんね。
2008.07.27
コメント(4)
-

青いムラサキツメクサ
間が1日空いてしまいましたが、先日の写真の話の続きです。ムラサキツメクサの花は、その名の示すとおりに紫色・・・実際には赤みを帯びた紫色の花がふつうですが、その花色は濃淡様々で、個々の花を並べてグラデーションを作ってみるのも面白いかもしれません。ときに、その紫の花には白花品も現れまして、その白さから『セッカツメクサ(雪花詰草)』という特別な名で呼ばれることもあります。セッカツメクサ posted by (C)sasama_tea白いですねシロツメクサの花に似ていますが、花の直下に葉がついていることで直ぐに見分けられます。さて、前回の画像をもう一度載せます。画質を落としていますので少々荒れていますが、私の意図している内容はよく表されていると思います。(ちなみに、花瓶は使い終えたオイスターソースのビンです。)上の画像は、個体ごとのムラサキツメクサの花の色の違いを確認するために、個体それぞれからひとつずつ花を採取して花瓶に生けてみたものです。自転車を走らせながらある個体の花を見たとき、「ん?!」とその花の色に目が釘付けにさせれてしまいました。その個体がこちらです。青紫花のムラサキツメクサ posted by (C)sasama_tea夕暮れ時の赤い光が当たって色が変化しているかもしれませんが、何となく色におかしな感覚が見られませんでしょうか。ムラサキツメクサの花に色の濃淡があることは周知の事実ですが、「青い」花って、ご覧になったことがありますか?上の写真の花は、明らかに周囲の花色の系統とは異質な色で、赤みが後退した青紫色の花を咲かせる変異のように感じました。写真では分かりやすくするためと、補正などを行なっていないことを示すために、近くにあった通常の赤紫の花を並べてみました。青くないですか?これを踏まえて花瓶の花を眺めてみると、赤くない系統の花がお分かりになるのではないでしょうか?面白いですね。鉢で簡単に栽培できれば、完全に青い花になるまで栽培し続けても面白そうですが、すでに栽培できるスペースがありませんので眺めるだけにしておきます。自然はきまぐれです。見ないフリをしていないと、「ふしぎ」を教えてくれない意地悪な一面があるようです。見ないフリ、見ないフリ。。。妙な個体がまた見つかるかも・・・ブログランキングに参加しています
2008.07.25
コメント(6)
-

ネジバナの未熟果
つい先ほど、細かい振動を伴う揺れを感じました。Yahoo!の災害情報によると、東北地方で再び震度6強の地震が起きたようです。酷い被害が生じていないことをお祈りします。ネジバナの栽培にいそしんでいることを何度かこのブログで取り上げていますが、皆さんの参考になるかと写真を用意したまま放置されていたものがありますのでご紹介しておきます。ネジバナの実は、熟した途端にあっさりタネをまき散らしてしまいますので、タネを採るのが難しいかもしれませんね。上の写真の株は、何度か紹介しました斑入りのネジバナで、今回はこちらの株で人工交配を行ないました。ネジバナは虫がやって来ない限りは受粉も確実にはされないようで、室内で外界から隔絶して栽培している環境ではほぼ結実は起こらないようです。写真では、花茎の下側から2番目と3番目の花に人工授粉を行なっています。特に3番目の実は他と違ってかなり膨らんでいますので、容易に見分けがつくと思います。いかがでしょう?なお、受粉は6月21日で、写真の状態が7月6日になります。少し茶色を帯びたこの程度ですでにタネは出来上がっていて、もう少し手前の緑色の状態でもタネを採るのに支障はありません。受粉から実が熟すまでの期間はわずか2週間程度。超特急です。写真の状態から2日も放置するとタネは飛び散ってなくなってしまいますので、この段階で実ごと採ってしまい、実を乾燥させると粉のようなタネが実の外側に現れてきます。あとは、タネをまく場所を用意するだけです。基本的に湿り気を確保できる場所であれば良いようですが、高確率で発芽させるにはシュンランやネジバナなどのラン類を植えた鉢にまくのが最適です。(その理由は、発芽に必要なラン菌を確保するため)そして、運が良ければタネをまいてからひと月も経つと発芽が見られます。発芽からの成長記録はこちらからご覧いただけますので、ネジバナの栽培に挑戦される方は参考にしてみてください。(ただ、記事を書くのが遅すぎましたか。タネを確保できないかもしれませんね。)ちなみに私の予定では、3通りの組み合わせで交配させたネジバナ実生苗を栽培することになっています。ただし予定は未定で、上手く発芽・成長が管理できない場合はご破算ですから、最終的には成り行き次第です。昨年分は上手く開花までこぎつけましたが、さて今回はどのような結末となるのでしょう。早くても結果が出るのは1年後ですから、気長に付き合うことになります。ところで、本日の内容が予定と少しズレてしまいましたので、予告の画像だけ載せておきます。自転車に乗りながら眺めていたムラサキツメクサの花に妙な違和感を感じて、じっくり観察したことで気づいたことがあります。その点を実際に検証すべく、花瓶にそれぞれの花をまとめて生けてみた光景が上の写真の状態です。何かお気づきになれましたか?その内容についてはまた次回ということで。。。ブログランキングに参加しています
2008.07.23
コメント(4)
-

ウラギンシジミの好む食べ物は?
日曜日、汗を掻き掻き、必死こいて散策して来た訳なのですが、今年も昨年同様ある蝶に追いかけ回されました。蝶と相性が良さそうなのはきれいな花と相場が決まっていそうなものですが、水辺や、ある種のミネラルを含む対象から養分を補給することもふつうのようですね。私を追いかけ回していた蝶も、汗に含まれるミネラル分を目当てにしているようです。決して、匂いフェチの蝶ではないのでしょう。その蝶、ひたすら私の回りを飛び続けていましたが、ある瞬間に突然いなくなってしまいました。すると近くには、先ほどの蝶と同種の蝶が地面に群れていて、その様子が下の写真になります。ウラギンシジミとカエル posted by (C)sasama_tea蝶の正体はウラギンシジミで、この辺りでは夏の暑い盛りに成虫が多く見られ、汗を掻いた状態を待ち望んでいるかのように人の後をついて飛び回っています。写真の状況に戻りますが、近づくまではそれがカエルの死骸だとは気づきませんでした。かなりグロいですね。ただ、ウラギンシジミにとっては燐(リン)などのミネラルが補給できる格好の対象のようです。あまりにも夢中になっているため、触れない限りはどこまでも近づくことができます。ウラギンシジミとカエル posted by (C)sasama_teaマクロで、どアップです。蟻やハエと一緒になってむさぼっていました。白い無垢な印象とは裏腹に、かなり残酷で無常な印象を受けてしまいますが、これも自然の営みの一端を示しているだけで、さして驚くことでもないのだと思います。それからもう少し移動すると、別の場所にもウラギンシジミが群れていて、地面に落ちた何かから栄養を補給しているようでした。ウラギンシジミとう○こ posted by (C)sasama_tea未舗装の道のど真ん中、少々臭うイチモツに群がるウラギンシジミの中には、不自然な格好の個体が見えましたが、じつはそれらはすでに絶命していました。(同様の光景についての過去記事がこちらにあります)道の先には1台の車が見えましたので、夢中になっていたウラギンシジミが車に轢かれたと想像するのはそれほど難しいことではないですね。人が近づけば逃げ出すのが蝶の用心深さと考えたいところですが、ウラギンシジミにはそのような考えは通用しないようですね。うん○相手にそこまで執着するとは、ある種の尊敬の意を表したいところですが、その体で人に近づいてくる訳で、1歩とは言わず2歩3歩と身を引いてしまいそうな・・・。・・・などとのたまいながら、やって来たウラギンシジミにも寛容に振る舞っていますこの子は、ひたすら私の回りを飛び回っては、体に直接取り付いたり、あるいは自転車についた体液を舐め回したり、天真爛漫に振る舞っていました。 汚いかもしれないが、好きにするがいいさ。口吻が触れるたびに妙なくすぐったい感触に見舞われても、特段害がある訳でもないようですし、しばし成り行きに身を任せましょう。最近流行りの角質を食べてくれる魚のように、ウラギンシジミにも何かの効用があれば・・・というところですが、何もないのでしょうね。皆さんも、とりあえず一度はいかがですか?ちなみに、昨年は撮影できませんでしたが、こちらが白い翅の内側の模様です。ミネラル分の色か? ・・・と考えるのは野暮ですね。ウラギンシジミでここまで遊べるとは思いませんでした。ブログランキングに参加しています
2008.07.22
コメント(6)
-

ムシ来る
シオヤアブ posted by (C)sasama_tea日曜日のこと。帰路も長いし、そろそろ戻ろうかと歩いていると、視線の向こう側からアブが真っ直ぐに私のほうへやって来ました。そして、何の躊躇もないように私の足許へ。じっと動かないのでカメラを向けて1枚。よく見ると、口には獲物を捕らえています。獲物を仕留めた足でわざわざ私の許へやって来たのはどのような理由があったのでしょう?意味不明です。特徴を残そうと横からの写真を撮ろうとすると、不意にどこかへ飛んで行ってしまいました。とりあえず調べてみると、写真には写っていない尾端の白い毛の特徴からシオヤアブのオスと判明しました。シオヤアブは肉食のアブのようですが、人には無害なのかな。攻撃を受けたことがありませんので平気なのでしょう。ブログランキングに参加しています居眠り、こっくり。予定とは異なる内容になりました。
2008.07.21
コメント(4)
-

風に舞う甘い香り
暑さが日に日に増してくるようで、暑いのが苦手な私としては辛い夏の毎日です。それでも動かないことには見たいものも見られない訳ですから、麦茶持参で、チャリをえっちら漕ぎつつ、体力と相談しながら散策へと出かけています。夜まで持ち堪えられないのは、どうかお許しください。倒れそうになりつつ土日と散策してきました。収穫があったのか無かったのか、自分でもよく分からないのですが、ブログのネタになるようなものはいろいろとありました。体と相談しながら書いてみようと思います。とりあえず日曜日のことになります。水分補給をしながら、やっとのことで目的地にたどり着くと、花はあまり見られないものの、虫の姿はよく目につきました。ただ、疲れているので虫を追う気力は減退気味です。ハグロトンボを追い、名前の分からない蝶を追い、それから・・・ああ、やめよう、はしゃぐと帰れなくなってしまう。そのような中、ふと甘い香りに気づきました。毎年夏になると香る花、そう、あれに違いない。周囲をぐるりと探しても、見つからない。いや、すぐ近くにあるはず。一度先に進んでから戻ってみると。。。甘い香りの出処 posted by (C)sasama_tea想像どおり、ヤマユリの花が隠れていました。農道の脇の雑木林の縁、上から垂れたアケビのつると葉にすっぽりと覆われていたため、外から見ただけではその存在には気づかないみたいでした。花を見ると採りたくなってしまう方たちが多い昨今、これくらいの防備は必要かもしれません。ヤマユリ posted by (C)sasama_tea今年初のヤマユリでしたので、記念にアップで1枚をパシャっと。大きな花です。世界に誇れる、日本の野生の花。大切にしたいですね。ブログランキングに参加しています花の写真は少ないのですが、虫との出会いは多かったです。そのほとんどは写真に収められませんでしたが、妙な面々の写真も撮ることができましたので、頑張って記事にしてみます。
2008.07.20
コメント(6)
-

トンボの顔
時期が合わないのか、それとも刈り取られてしまったのか、きれいに咲く花の被写体があまり見つからず、仕方なしに横切る虫などを片っ端から追いかけています。ただ写真に収めるのは想像以上に難しく、汗だくで追いかけた虫たちは藪や田んぼの真ん中へと消えてしまいます。その点ではトンボの中には優しい方たちも少なくなくて、マクロのぎりぎりまで近づいても逃げないのは有り難いです。マユタテアカネ posted by (C)sasama_tea名前の由来どおりでは「眉」ですが、誰の目にも「鼻の穴」にしか見えないマユタテアカネのメス、でいいですかね。理解したつもりでも、1年が経過すると見分けがつかなくなってしまいました。ノシメトンボ posted by (C)sasama_tea1枚目のトンボと似たような色合いですが、顔には「鼻の穴」模様がなく、翅の先に黒い色が乗っています。住宅地にもやって来るノシメトンボは人を恐れず、手に留まらせることも簡単ですね。近づいて撮影していると、ふと首を傾げる動作を繰り返していましたので、タイミングを見計らって撮影すると、まるで彼と会話でもしているような写真になりました。ノシメトンボはいいですねぇ。遊ぶ相手としては不足なしです。ところで、以前「神様トンボ」という話題をこのブログで書いたのですが、そのときに載せたハグロトンボは静止画でした。今回新しく買い換えたデジカメの動画機能の試し撮りも兼ねて、ハグロトンボが翅を広げる動作を動画撮影してみましたので、身体験の方はご覧くださいませ。 ハグロトンボの翅の開閉行動 byフォト蔵この翅を開閉する動作が、手を合わせて拝む姿に通じるものがあるという訳で、「神様トンボ」「仏トンボ」「精霊トンボ」などと表現されるのだろう、ということです。さて、これからトンボの数も増えてくることでしょうから、頑張ってトンボに近づいて写真を撮ってみたいです。思わぬ発見があるかも・・・?ブログランキングに参加しています
2008.07.16
コメント(8)
全575件 (575件中 1-50件目)