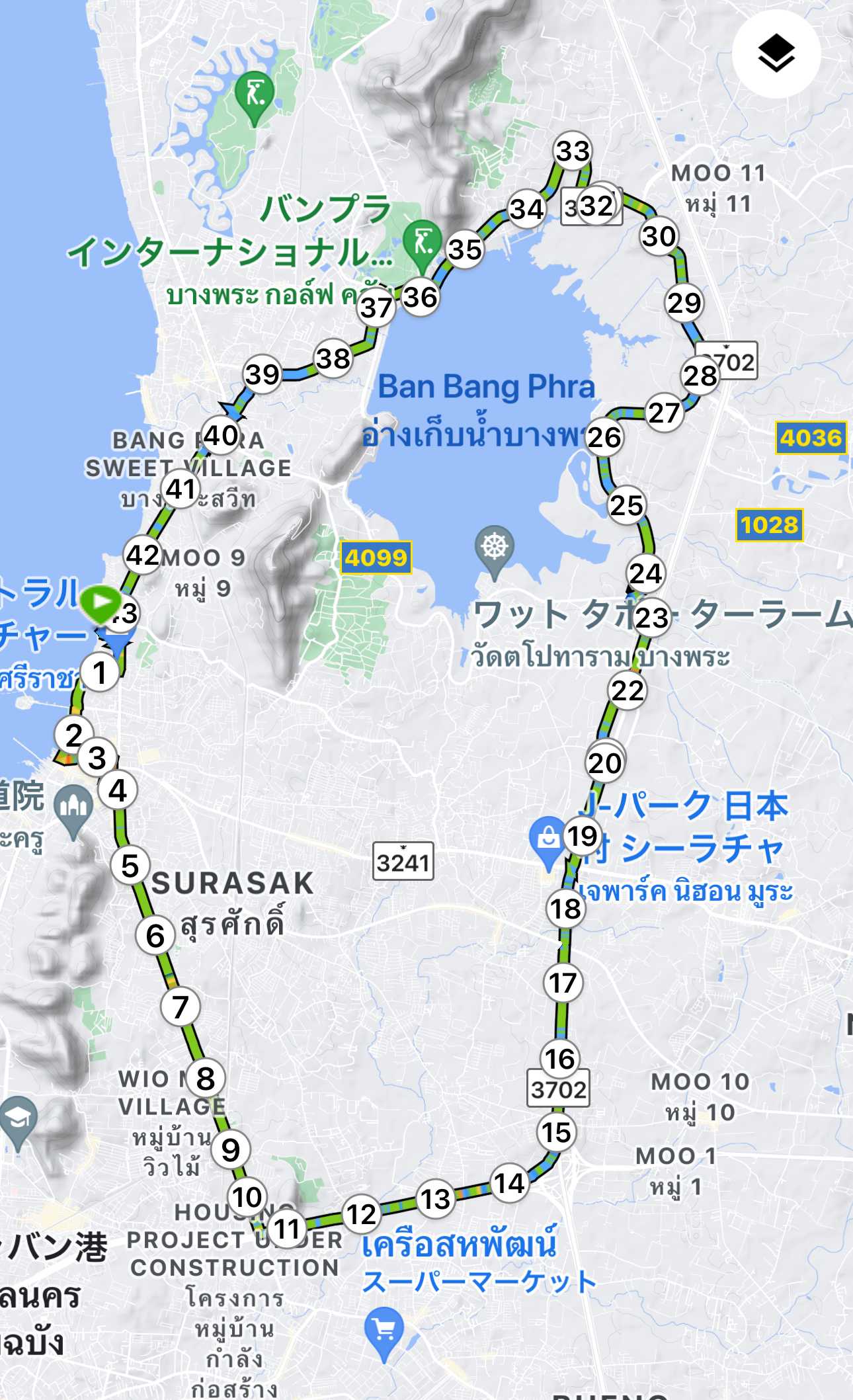-
1

会津壱番館(会津若松市)
会津若松の「会津壱番館」で珈琲タイム。 Memorial House of Dr. Hideyo Noguchi とコーヒーカップに書いてありました。 若き野口英世博士が勉学に明け暮れた旧医院の1階が喫茶店になっていて、2階が資料館になっているこの建物は「野口英世青春館」と名付けられていました。 太平洋から遠く離れた会津盆地にあるこの街も、エリア的には福島県に属しているため、東日本大震災以降、風評被害に見舞われて観光客の足も遠退いていたように思います。 2011年に来たときは夏休み中だというのに七日町通りに人の気配もなく、悲しい気持ちになりました。 だけど今回はわりとたくさんの観光客とすれ違って、少しホッとしました。 会津は良いところです。 私は大好き。
July 14, 2019
閲覧総数 329
-
2

新函館北斗駅で乗り換え
東北新幹線から、札幌へ向かう特急北斗に、新函館北斗駅で乗り換えた。新幹線到着から特急出発までの乗換時間は12分。乗り換えてみての感想は…現役世代ならゆっくり歩いても余裕で乗り換えられる。子供連れやお年寄りでも普通に歩けば大丈夫。とはいえ、新幹線から全員降りるので、混んでいると結構時間がかかる。できるだけ早く新幹線を降りた方がより安心、と思いました。乗り換えの流れは…①新幹線を降りる。②エスカレーターに乗って2階へ上る。③2階に着いたら、札幌方面に行く人も、函館方面に行く人も、次に乗る列車の切符を持っている人は全員「のりかえ」のサインのある改札に向かう。④乗ってきた新幹線のチケット、これから乗る特急のチケットと乗車券を一緒に改札に入れる。⑤特急のチケットと乗車券が手元に戻る。⑥特急北斗が停車しているホームに階段またはエレベーターで降りる。⑦特急北斗に乗車。注意点は…・10両編成の新幹線から降りた乗客が一斉にエスカレーターに向かうので、新幹線をゆっくり降りると、長い列の後ろに並ぶことになる。今回、新幹線を降りるのが遅かったので、ホームに降りてからエスカレーターに乗るまで、本来30秒もかからないところ、数分かかった気がする。10分程度の乗換時間でこの数分は結構焦る。・エスカレーターで2階に上ると、「出口」と「のりかえ口」が見える。大半の人が「のりかえ口」に向かうので、流れに乗って進む。・改札を抜けてホームに向かう階段に着くと、大半の人は函館方面のホームに降りていく。札幌方面のホームに行く人は少ないので間違わないように進む。・特急北斗は函館始発なので、新函館北斗駅の停車時間は短い。今回は、のりかえ口を過ぎたあたりから発車のベルと乗車を促すアナウンスが聞こえてきて、焦った。高齢の親には「急がなくて大丈夫」とか言いながらもできるだけ急いで階段を降り、列車に乗り込んだ。・とは言っても、乗り遅れが出ないように駅員さんが人の流れを後ろの方まで確認していた様子。あまり慌てる必要はなかったかもしれない。と特急に乗ってから思った。新幹線は満席。乗り換えた特急は、密にならないように指定席が割り当てられていて快適でした。
July 22, 2022
閲覧総数 13157
-
3

出国の流れ@ロサンゼルス国際空港(LAX)
ロサンゼルス国際空港(LAX)では、アメリカの航空会社以外はほぼターミナルB(トム・ブラッドリー国際ターミナル)から発着している。そのうえ、発着便が集中する時間帯もあるようなので、余裕をみて早めに滞在先を出発し、空港に向かった。幸いフリーウェイの渋滞はほとんどなく、搭乗時間の4時間くらい前に空港に着いた。ターミナルBに入り、まずはスーツケースを預けてしまおうと、航空会社(ANA)のカウンターに行ってみると「出発の3時間前に窓口は開きます」との表示があって、スタッフの姿はなかった。「あと1時間か…」と、つぶやきながら少しぶらついてみたが、搭乗手続きのフロアには飲食する場所やトラベルグッズのお店くらいしかない。ここで何もせずに時間を潰すのももったいないので、帰国便もスーツケースを機内に持ち込むことにした。小さなスーツケースでの旅は、こういう時に楽だ。だけど、預けるつもりだったスーツケースにペットボトルの水を入れていたことを忘れていたので手荷物検査で引っ掛かり、ペットボトルは未開封のまま没収された。反省…。出国手続きを終えて搭乗口のあるフロアに入ると、ブランドショップやお土産のお店などが並んでいた。とはいえ、どのお店も品揃えは豊富とは言えない。気の利いたお土産が買いたいなら、空港に来る前に買うのが正解だと思った。ここで僕は、免税店でお土産のチョコレートをいくつか買った。それから搭乗口に向かう途中で、蒸しパンのような大きなパンと、野菜ジュースのようなソフトドリンクも買った。搭乗口の近くに座って、パンを食べたり荷物の入れ替えをしながら搭乗までの時間を過ごした。不慣れなアメリカひとり旅も、あとは飛行機に乗るだけ。しかも飛行機は日本のANA。そう思うと、僕の心は一気にゆるゆるになり、至福の時間になった。意外なことに、アメリカからの出国に際して、LAX空港に着いてから飛行機に搭乗するまでパスポートを一度も使わなかった。特に搭乗口では、チケットも使わず、顔認証でゲートが開いた。(念のためパスポートとチケットを手に持っているようには促されたものの、使うことはなかった。)こんなに簡素化しても乗客の誤進入や悪意のある侵入を防げているのだからすごい、とひたすら感心しながら機内に向かった。
April 27, 2024
閲覧総数 5019
-
4

秋のトマム(北海道占冠村)
札幌から日帰りで行けるところ…今回は夕張とトマムに行くことにした。初めに夕張、そしてトマムへ。高速道路が片側一車線だったせいか、夕張からトマムまでは地図で感じていたより遠く、北海道の広さを実感した。長いトンネルが連続する高速道路をトマムICで降りた。その途端、リゾートの雰囲気が一気に漂い始めた。さすがは星野リゾート、というのが第一印象。10月下旬。紅葉が見ごろを迎えていて、ハロウィンのデコレーションがあちこちにあるホテル内には、家族連れの姿を多く見かけた。ホテルから続く通路を「ホタルストリート」まで上り、「GARAKU」でスープカレーを食べて、チャイを飲んだ。とても美味しかった。ホテルの隣には広大な草原が広がり、乗馬を楽しむ姿などが見えた。千歳空港からも札幌からも決して近くないトマム。廃墟のようになったスキーリゾートを各地で見かける中、これだけ活気のあるリゾートがここにあることが嬉しくて、今度はゆっくり泊まりで来たい、と思った。
November 27, 2025
閲覧総数 8
-
5

支笏湖(北海道千歳市)
札幌を朝8時に出て、洞爺湖と昭和新山、そして支笏湖を周り、夕方、札幌に戻った。5月上旬、北海道は本格的な観光シーズンにはまだ少し早く、車で走っていて渋滞に出会うことはなかった。赤信号で止められることも、と言うより信号を見かけることも余りなく、車の流れに乗ってひたすら走り続けた結果、カーナビが予想する到着時間よりも前に目的地に着くことができた。この日3カ所目の目的地が支笏湖。着いた時、静かな湖面に向かって雲間からの陽の光が放射状に注いでいた。もしも眠りから覚めた時にこの風景が目に入ったら、言い方は変だけど、自分は今ちゃんと生きてるか?もしかするとここは天国か?などと思いかねないくらい、息を呑むような美しさだった。車を停めたところは支笏湖ビジターセンター近くの有料駐車場。料金は500円。駐車場から湖の間には飲食店がいくつもあり、その中の一軒、碧水というお店で「いももち」を買って食べた。もっちりと温かくて、気持ちがほっこりした。
July 10, 2025
閲覧総数 67