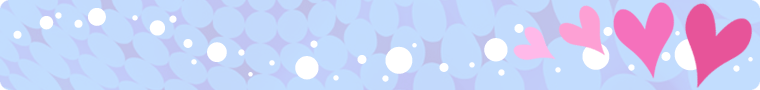出産に関わる手続き
●出生届出期間
生まれた日を含めて14日以内
●届出地
出生地または父母の住民登録地、本籍地のいずれかの市区町村役場
●届出人
生まれた子の父または母
●必要なもの
○出生届
(届書は右半分が出生証明書になっていますので、医師か助産師に証明をもらってください。)
↑
用紙は通常、各病院にあるそうです。
○届出人の印鑑(朱肉を使うもの)
○母子健康手帳
○国民健康保険被保険者証
●注意事項
○お子さんの名は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。
○出生届を出した後、住民登録地で次の手続き等が必要な場合があります。
・国民健康保険に関すること
・児童手当の申請
・乳児医療証の申請
<国民健康保険に加入する場合>
●子どもが生まれたとき
被保険者証,母子健康手帳
<児童手当>
未就学の児童を養育している人に支給されます。
ただし、所得制限があります。
第1子分 支給月額:5,000円
出生届を提出時に説明があります。
<新生児の届>
母子健康手帳別冊についている「新生児の届」を居住地の健康福祉センターに提出してください。
<小児医療費助成(0歳のお子さん)>
健康保険に加入しているお子さんが、病気やケガで医療機関に受診したときに
保険診療の自己負担額(一部負担金)を助成します。
ただし、健康診断、予防注射等保険外診療については助成できません。
(入院時の食事代も対象外です。)
☆対象となるお子さん
届け出をした市町村内に住所があること
健康保険に加入していること
※次のような場合は対象になりません。
1生活保護を受けている場合
2児童福祉施設などに入所している場合
3他の医療費助成事業により医療費の助成を受けている場合
(例:重度心身障害医療費助成事業、ひとり親家庭等医療費助成事業等)
<申請方法と助成内容>
保護者の所得制限はありません。
★申請方法
お子さんが生まれましたら 乳 医療証交付申請書に必要事項を記入の上、
出生届担当または行政センターに提出して下さい。
※所得制限はありませんが、事務処理の都合上、所得確認をしています。
対象となる年の保護者の所得が転入や所得の未申告などで確認できない方には、役所から『交付申請書』と『所得証明書』を提出するよう指示があります。
★助成内容
入院・通院医療費の自己負担分(保険対象外は除く)が助成されます。
★対象期間
生まれた日または本市に転入した日から満1歳に達した月の月末までです。
(ただし、1日生まれは誕生月の前月末日まで)
★医療証の使い方
県内の保険医療機関で医療証と健康保険証を提出すれば医療費の自己負担分(保険診療外は除きます)を支払わずに受診できます。
医療証の発行前に受診した場合や県外の保険医療機関で受診した場合は、
一度自己負担をして頂き、後日払い戻しの手続きをして下さい。(<払い戻しの手続き>へ)
<払い戻しの手続き>
★申請に必要なもの
医療証(0歳~3歳)
健康保険証
保護者名義の金融機関の通帳(郵便局は不可)
領収書(医療機関発行、お子さんの名前、保険診療点数が入っているもの)
印鑑
<こんな時は忘れず届け出を>
1医療証を紛失または汚損してしまった。
2住所、氏名などに変更が出た。
3死亡した時、生活保護を受ける時、他の医療費助成制度を受ける時、転出した時、有効期限がきれた時などは医療証をお返し下さい。
<出産育児一時金>
国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主に出産育児一時金として30万円を支給します。
<申請に必要なもの>
・被保険者証
・印鑑(朱肉を使うもの)
・世帯主名義の通帳(郵便局以外)
<申請先>
健康保険課または行政センターで申請してください。
<分娩費の支払が困難な方は>
通常、出産後に支給される30万円を市から医療機関に支払い、
その分医療機関への支払が 減額される受領委任払いの制度があります。
ご希望の方は健康保険課へご相談ください。
ただし受診医療機関によっては利用できない場合があります。
<会社を退職後6ヵ月以内に出産した方は>
以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、
国民健康保険からは支給されません。
ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります。
※出産後2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
会社の健康保険に加入している方は、詳しい手続きの方法は必ず加入している健康保険にお問い合わせください。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
-
-

- クリスマス
- 栗ヶ沢バプテスト教会水曜祈祷会2025…
- (2025-12-04 12:16:27)
-
-
-

- ●購入物品お披露目~~●
- 楽天✕ダイソー◎ストレス減った朝ルー…
- (2025-12-04 14:43:27)
-
© Rakuten Group, Inc.