全て
| カテゴリ未分類
| 怨念の湿地帯
| ギョウム連絡
| ホーリーエルフの祝福
| 天使の施し
| 葡萄酒(ブドウシュ)=ドーピング
| 誘惑のシャドウ
| 奈落の落とし穴
| ローの祈り
| 停戦協定
| 雷神の怒り
カテゴリ: 奈落の落とし穴
現行のユニットでこのフォーマットで
完全な形のDB型をつくるのは何となくムリがあるような気がする。
と言う事で自作スピーカーでは名門中の名門、
FOSTEXのユニットを使って
DB型スピーカーを設計してみようと思う。
まずはウーファーだがサブロクの定尺板をフルに使おうとすると
ウーファー口径の上限値はやはり20cmだろう。
となるとウーファーはFW208HSに限られる。
まずはこのウーファーを活かして他の設計を詰めていこう。
FW208HSの周波数特性図をみると、
オフィシャルな周波数特性図では書かれていないが
分割振動域は600Hzから800Hz辺りから始まっている様に思える。
この帯域を外してネットワーク並びにスコーカーを
考えていこう。
スコーカーは小型フルレンジのトーンゾイレ式と決まっている。
使用するとなればコストを鑑みてかんすぴシリーズの
P650K,P800K,P1000Kの3種類から選ぶことになる。
因みに高価なFEシリーズだと音圧レベルの関係からFE126NVが候補になるが
大きさが12cmとなってしまい、これでは20cmとの視覚的バランスが悪い。
FE103NVだと音圧レベル的にもう少し欲しい。
FFシリーズは全体的に効率が悪いので合う機種が無い。
話を戻そう。
ウーファーのクロスオーバー周波数を600~800Hzとすれば
周蓮特性図を見ると86dB、スコーカーをトーンゾイレで使用すると
86dBより2.5dB程度低いと丁度良い。
600~800Hz以上の帯域でかんすぴシリーズから選ぶとすると
効率の点ではP800Kが丁度良い事になる。
ツィーターは価格と帯域でFT17Hでキマリだ。
音圧レベルの点から行けばFT28Dも候補になる。
FT28Dの音を実は聞いたことが無いのだが
周波数特性図を見ると2Way用な気がして仕方がない。
価格もFT17Hのほうが若干安いのでこちらを使おう。
それぞれのクロスオーバー周波数を
600Hzと6KHzとして、以下のような設計となった。
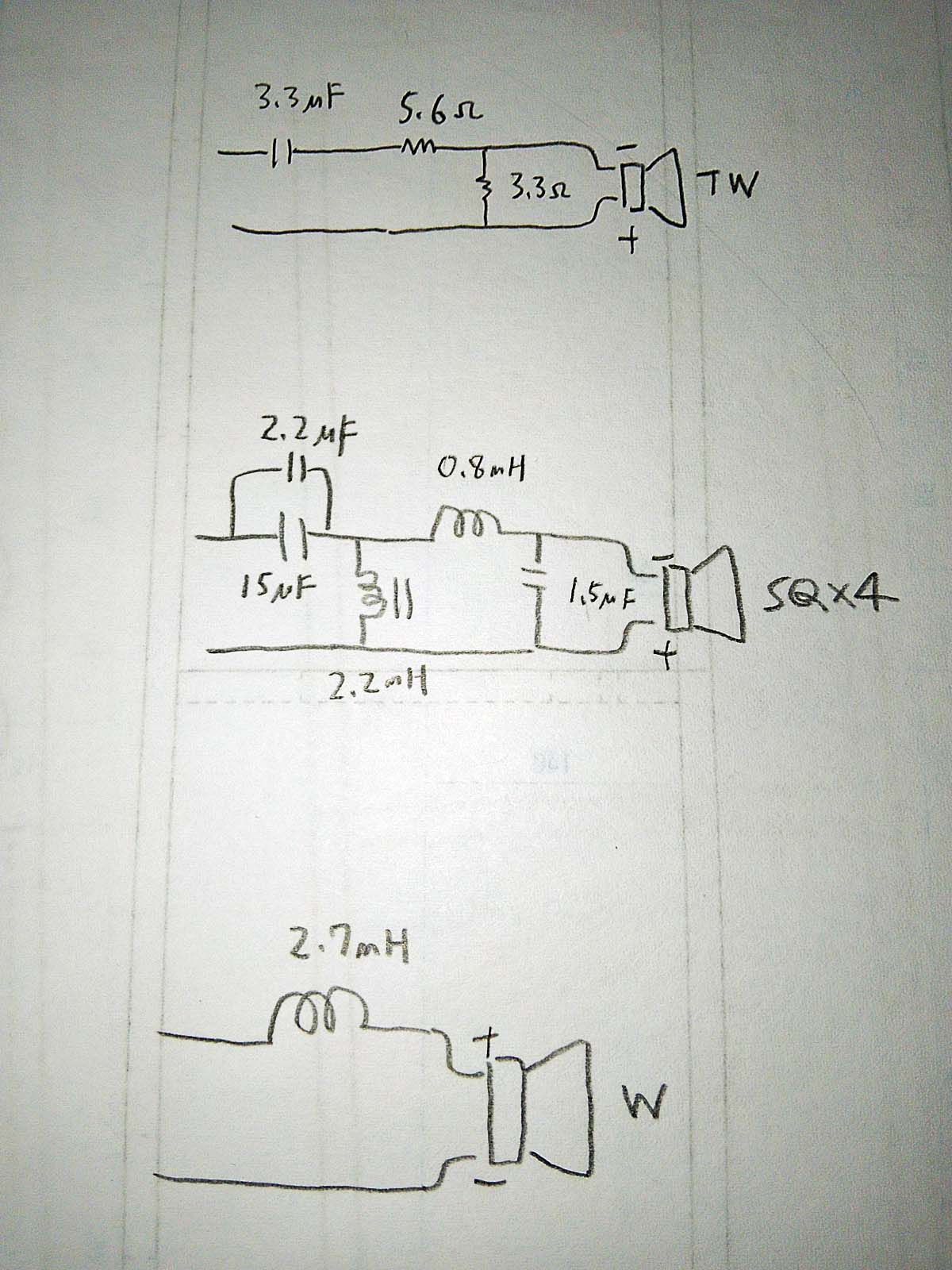
-6dB型と-12dB型とが混在しているが、
これは単純にコストを抑える為。
特にコイルは値が張るので、コイルの容量を
極力小さくする工夫をしている。
ツィーターの減衰については可変式アッテネーターの方が
後々楽なのだが、個人的には固定式のほうが好きなので
このようにしてある。
ヒヤリングをして不満が出る可能性があるのであれば
近似値の抵抗を事前に購入しておくというのも
一つの手だろう。
どのみち可変式アッテネーターを買って組み込むより
格段に安価に組めること請け合いだ。
ネットワークを組むにあたって重要なのは
ユニットにシリーズに接続されるパーツ類の質だ。
特にコンデンサーの質には注意を払いたい。
パラレルに入るパーツは正直どうでも良いので
その分シリーズに接続されるパーツに奢る事を勧めたい。
次回は外形図の設計に入りたいと思う。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[奈落の落とし穴] カテゴリの最新記事
-
11/1の日記 選挙なんか行っても無駄だとい… 2021.11.02
-
10/20の日記 シャープ/京セラ/富士通のス… 2020.10.20
-
7/26の日記 ダブルバスレフ型スピーカーを… 2020.07.26
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.









