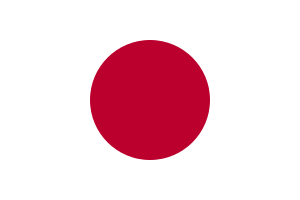「日本の使う資源エネルギーは、世界を牛耳っている石油メジャー経由に依存しすぎない。日本独自ルートの開発は当たり前」
腹の底にはそれがあった。さらに、世界を支配している巨大メジャーの存在も分かっていた。そこで、アメリカの我が侭にも応じて、聞けることは聞いていたのだった。・・・・・下記。

ハワイでのニクソンとの首脳会談で濃縮ウランの思い切った量の買い取りを決めた。
「メジャーの世界支配、崩す」(田中角栄のふろしき)
小長秘書官の証言(11)
コラム(経済・政治) (1/2ページ)2018/2/26 6:30日本経済新聞 電子版
俺が首相として前面に立ちトップダウンでやる。そうでなければ資源メジャーの世界支配は突き崩せない」——。田中角栄の迫力に小長啓一は気押されそうになった。1973年9月の資源外交前夜のことである。
角栄は決して単なる外交好きではなかった。表面的に外国の要人とスタイリッシュに渡り合い自分をアピールするようなことはなかった。73年からの外交も、ただのセレモニーではなく日本の首相として「実」をとりに行く外交だった。
だからこそ問題だった。日本の資源立国という「実」にこだわった外交は、そのまま米国のエネルギー支配から抜けだすことを意味した。それが米国を怒らせ、後に「米国の虎の尾を踏んだ」と言われる結果を引き寄せることになる。
実際、73年の資源外交までは米国との関係がギクシャクすることはあったが、決定的に怒らせるまでには至らなかった。72年の中国との国交正常化についても「中国と話し合うことは米国には話を通していたし了承済みのこと。その後、周恩来、毛沢東と角栄が一気に国交正常化にまで持っていけたのは、両国トップの力量の成せる技で何もおかしいことではない」(官邸)はずだった。
そもそも最初から角栄と米国の関係は悪かったわけではない。むしろ、逆だったかもしれない。首相となった角栄が米国と本格的に最初の接点を持ったのは首相就任から2カ月たった1972年8月31日からの日米首脳会談。この時、米国側は異例の厚遇をみせた。
何しろ会談場所がハワイなのだ。米大統領のニクソンとの首脳会談を申し入れたのは角栄のほうだったが、その後、事務方で具体的な日程や場所を詰めていくうちに「それならハワイで」ということになったのだった。
角栄が首相に就任して初めての日米首脳会談だ。会談場所はワシントンというのが当時の常識だった。ところが米国側は日本に配慮して日本と米国の真ん中のハワイまで出てきてくれるという。米国にしてみれば、日本に輸入拡大を迫るという負い目があったことは事実だ。しかし、それだけではなかった。角栄への感謝があった。71年10月、2000億円の予算措置を断行することで日米繊維交渉を決着させた角栄の手腕に対する敬意の表れだった。
ハワイに到着した角栄たち一行をニクソンはわざわざ空港のタラップの下まで足を運び出迎えるという、これもまた異例の気遣いを見せた。快晴ハワイ。日本航空の特別機でハワイのオアフ島にあるヒッカム空軍基地に到着した角栄をニクソンは満面の笑みで迎えた。
この時、ある「事件」が起きる。ユニークで印象的な事件だ。飛行機のタラップを下りてきた角栄が、まだ完全に地上にまで下りきらないのに、ニクソンが「やあ」と手を差し伸べたのだ。
タラップの階段はまだ2段ほど残っていたが、ここで角栄がニクソンの手を握り握手、2人で写真に納まった。写った写真をみて納得。角栄とニクソンの頭の高さはちょうど同じだった。身長164センチの角栄を、長身のニクソンが気遣った「面白い光景」だったと竹下登の回顧録『政治とは何か』にある。
ただ、角栄とニクソンが握手を交わしたこの瞬間、2人のすれ違いは始まっていたのかもしれない。角栄はこのハワイでの日米首脳会談の目的を20日後の訪中を米国に認めさせることに比重を置いていた。これに対し、ニクソンの頭のかなりの部分を占領していたのは日米貿易不均衡の是正だった。
確かにニクソンを悩ませた日米の貿易不均衡は深刻さの度合いを増していた。1968年、日本の国民総生産(GNP)は西ドイツを抜き世界第2位、その有力な輸出先が米国であり、71年の米国が抱える対日貿易赤字額は過去最大の30億ドルに達していた。米国は日本に対し輸入を拡大することでこの貿易不均衡を是正することを求めていたのだった。
対応はさすがに角栄だ。ハワイでの日米首脳会談で角栄は米国の要求にスバリ応えた。「3年のうちに貿易不均衡を是正する」とニクソンに明言、日本は米国から11億ドル分の特別輸入を約束したのだった。
後のロッキード事件の火ダネとなる民間航空機の輸入はこの時決まった。日本側は3億2千万ドルの米国製民間航空機の買い取りを決める。そして同時に決まったのが米国産濃縮ウランの買い取りだった。
この時、通産省の想定を超えたのは民間航空機よりも濃縮ウランのほうだった。その量は1万トンSWU。当時、日本で運転していた原子力発電機はわずか5基、そこからすれば1万トンSWUの濃縮ウランは当時の日本にとっては途方もない量だといえた。仮に原発の基数が増えない前提なら10年分程度の燃料を契約してしまったことになる。
さすがに電力業界も驚いた。ハワイの日米首脳会談の後、訪中が控えていたため米国に日本も持ち込む「手土産」が必要なことは心得ていた。濃縮ウランの購入はその1つだったが、せいぜいすでに電力業界が購入契約を済ませていた「5年分程度にプラスα」が日本側の想定だった。
もちろん角栄も事務方の事前レクチャーでその落としどころは聞かされていた。「コンピューター付きブルドーザー」と呼ばれた角栄である。数字が頭に入っていないわけはなかった。
しかし角栄は米国側の風を読んだ。小長は「相当の圧力だった」と証言するが、そこは角栄も同じ。同じ圧力を感じていた。プラスα程度では米国は到底、収まらないとみて一気に1万トンSWUの数字を掲げた。「日本は無資源国。いずれ原子力は日本の基幹エネルギーとなる」。角栄の勘だった。
角栄の決断でハワイの日米首脳会談はとりあえず成功裏に終わった。しかし、あくまでも「とりあえず」だった。1年後、角栄が展開する資源外交が米国の逆鱗(げきりん)に触れる。舞台はフランスだった。=敬称略
タグ: 田中角栄
【このカテゴリーの最新記事】