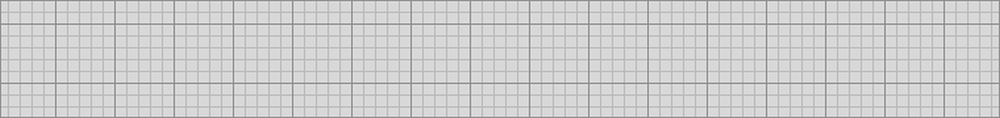-
1

源氏物語〔12帖 須磨 2〕
源氏物語〔12帖 須磨 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。源氏は須磨への出立を前に、別れの悲しみに満たされていた。妻や情人たちは、共に行きたいと願うも、須磨のような人里離れた地に連れ立つことは、源氏自身にも彼女らにも耐えがたいものになると考え、一緒に連れて行くことはやめた。源氏のことを支え守られていた人々は、その決断に寂しさを抱いていた。左大臣も源氏の去りゆく運命を嘆き、「昔、院に愛されていた頃が嘘のようだ。何もかもが末世の中で、あなたの失脚は私にとっても悲嘆に耐えない」と述べ、源氏に寄り添った。源氏は己の運命を悟り、過去の愛憎や宮廷の複雑な事情を振り返りながらも、遠い地でその罰を引き受ける覚悟を示した。三位中将が加わり夜も更けると、源氏はかつての恋人である中納言の君に別れを告げた。翌朝、源氏は都を出発し、花々の咲き残る庭を眺めながら、女房たちとの別れに心を痛めた。彼の息子の若君や、左大臣家の人々の涙を見て、源氏はその離別の哀しみを深く噛みしめた。左大臣夫人からも惜別の言葉が届き、源氏は彼らへ歌を詠んで別れを惜しんだ。宮もまた悲しみの中で歌を返し、左大臣家は彼らの別れの歌が余韻を残し、女房たちの涙で満ちていた。源氏が二条の院へ帰って見ると、ここでも女房は宵からずっと歎き明かしたふうで、所々に かたまって世の成り行きを悲しんでいた。家職の詰め所を見ると、親しい侍臣は源氏について 行くはずで、その用意と、家族たちとの別れを惜しむために各自が家のほうへ行っていてだれ もいない。家職以外の者も始終集まって来ていたものであるが、訪ねて来ることは官辺の目が 恐ろしくてだれもできないのである。これまで門前に多かった馬や車はもとより影もないので ある。人生とはこんなに寂しいものであったのだと源氏は思った。食堂の大食卓なども使用す る人数が少なくて、半分ほどは塵を積もらせていた。畳は所々裏向けにしてあった。自分がいるうちにすでにこうである、まして去ってしまったあとの家はどんなに荒涼たるものになるだろうと源氏は思った。
2024.11.22
閲覧総数 86
-
2

源氏物語〔12帖 須磨 1〕
源氏物語〔12帖 須磨 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。源氏物語の12帖「須磨」では、源氏が藤壺の女御や朧月夜との関係を知る人々からの嫉妬や誹謗中傷に苦しみ、ついには朝廷からの圧力によって都を追われ、須磨に隠棲することになる。須磨での源氏は、都での華やかな生活から一転し、荒々しい自然の中で孤独と向き合う。夜の嵐や海の波の音に囲まれ、心細さと寂しさに苛まれながらも、現世を離れたような静寂の中で自身の運命や人生について思索するようになり、やがて源氏は須磨での生活を通して、都での浮ついた生活や人間関係を振り返り、新たな覚悟を抱き始める。当帝の外戚の大臣一派が極端な圧迫をして源氏に不愉快な目を見せることが多くなって行く。 つとめて冷静にはしていても、このままで置けば今以上な禍いが起こって来るかもしれぬと源 氏は思うようになった。源氏が隠栖の地に擬している須磨という所は、昔は相当に家などもあ ったが、近ごろはさびれて人口も稀薄になり、漁夫の住んでいる数もわずかであると源氏は聞いていたが、田舎といっても人の多い所で、引き締まりのない隠栖になってしまってはいやであるし、そうかといって、京にあまり遠くては、人には言えぬことではあるが夫人のことが気がかりでならぬであろうしと、煩悶した結果須磨へ行こうと決心した。この際は源氏の心に上 ってくる過去も未来も皆悲しかった。いとわしく思った都も、いよいよ遠くへ離れて行こうとする時になっては、捨て去りがたい気のするものの多いことを源氏は感じていた。その中でも若い夫人が、近づく別れを日々に悲しんでいる様子の哀れさは何にもまさっていたましかった。 この人とはどんなことがあっても再会を遂げようという覚悟はあっても、考えてみれば、一日 二日の外泊をしていても恋しさに堪えられなかったし、女王もその間は同じように心細がって いたそんな間柄であるから、幾年と期間の定まった別居でもなし、無常の人世では、仮の別れが永久の別れになるやも計られないのである。
2024.11.21
閲覧総数 60
-
3

紫式部日記 池の底まで照らす篝火の眩しさ
「紫式部日記」 「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「紫式部日記」の研鑽を公開してます。これに対して、紫式部の歌は、澄める池の 底まで照らす かがり火に まばゆきまでも うきわが身かな澄み切った池の底まで照らす篝火のまぶしさまで 憂いに満ちた暗いわが身が 引き比べられて辛いことだ。 藤原道長邸の栄光を見るにつけても、紫式部はそれを単純に「めでたい」などとは思えない。篝火(かがりび)の光の中に闇を見てしまう。まばゆきまでも うきわが身かなと嘆くのは、紫式部独自の人生観である。和泉式部の歌は恋を情熱的に歌い上げ、紫式部の文学は華やかである。また紫式部は輝きの中に不幸な闇を見てしまう。歌人と物語作家の歌は、交換不能の秀歌といえる。
2022.08.23
閲覧総数 294
-
4

南京大虐殺記念館3
「南京事件3」 「中国写真ライフ」では、江蘇省南京「南京大虐殺記念館」の写真を公開しています。南京大虐殺記念館は旧日本軍の非道行為を内外にアピールする為に建てられたのが南京大虐殺記念館だが実際とは異なる。 中国国民すら知らなかった南京事件は1971年日中国交樹立前に朝日新聞紙上に掲載された本多勝一の「中国の旅」という連載記事から始まる。私が中国へ居住した1993年当時は南京事件で気が重く中国人から攻め立てられる度に謝罪ばかりしていた。それは大虐殺は本当にあったと信じていたからだった。今回で3回目となる南京への旅だが初めて来た時の事を記念館を歩きながらも思い出していた。2000年11月雨の降りしきる南京空港へ降り迎えの車で南京大虐殺記念館へと走らせたがまだ地理に疎い私は南京大虐殺記念館の距離が結構遠かったように記憶している。12年前は南京大虐殺記念館へ入った時に入口の「300000」の数字に驚きながらも説明を受けながら、中へ中へと進んでいった。
2012.03.16
閲覧総数 1271
-
5

源氏物語〔11帖 花散里 3 完〕
源氏物語〔11帖 花散里 3 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語11帖 花散里 の研鑽」を公開してます。これを聞いた女御も、もとから孤独の悲しみに浸っていたが、今さらまたその寂しさが身にしみてくる様子が見え、彼女の人柄が、ますます源氏の心を惹きつける優しさを感じさせた。女御は、「人目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒のつまとなりけれ(人の目もなく、荒れ果ててしまった宿では、橘の花が軒先の飾りとなっているのだろう)」と詠み、人に忘れられて荒れた宿に、誰の手も加えられず自然のままに咲く橘の花が、まるで宿の装飾のように咲き誇っている様子が詠まれている。ここでの「橘の花」は、かつての栄華や人の温もりを象徴する一方、今はただひっそりと咲き続けるその姿が、寂寥感や無常観を際立たせている。橘の香りや姿が、過ぎ去った時の流れや失われたものへの哀愁を感じさせ、美しくも切ない情景を表現し、少しの言葉に彼女らしさがにじんでいたので、源氏はこの女御こそ本当に気高い女性だと感じた。先ほどの家の女をはじめ、幾人かの女性を思い出していたが、その中で自然と女御の品位が際立った。源氏はさらに、西の座敷へ静かに、親しげに歩み寄り、恋しい思いを訴えた。長い時を経ても変わらぬ愛情を、率直な言葉で告げたのである。彼の恋人たちは、特別な身分や魅力を備えた女性たちが多く、長く関係を保つことに同意しない人々は去ってゆくが、それも仕方がないと源氏は考えていた。町の家の女性もその一人であり、今は他に愛人がいる身であった。(完)明日より(第12帖須磨)を公開予定。
2024.11.20
閲覧総数 75
-
6

源氏物語〔10帖 賢木 12〕
源氏物語〔10帖 賢木 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。源氏にあまりに似ているため中宮は世間を恐れて悩むこともあった。源氏は中宮への恋心を抱きつつも、自らの冷淡さを反省し隠棲を決め、秋の野の草花を眺めるために雲林院へと出かけた。源氏は母の兄である律師のいる寺で経を読み仏勤めに励もうと、数日滞在することにしたが、その間にも色づき始めた木々や秋草の花の哀れな様子に心を奪われていた。学僧たちを集めて論議を聞いたりもしたが、場所が場所だけに無常観が増し、なおも中宮への未練を強く感じる自分を見つめることとなった。月光のもと、僧たちが菊や紅葉の花を仏に捧げる様子を見て、僧にはこうした務めがあり未来への希望を持てることが羨ましいと感じた一方、自分はこの世への未練を断ち切れないでいた。律師が「念仏衆生摂取不捨」と唱える声を聞くと、ますます出家への思いと紫の女王への気がかりが募るばかりである。しばらく滞在しようと決めた源氏は恋妻である紫夫人に手紙を送った。「出家の真似事をしていますが、寺の生活は寂しく心細いばかりです。もう少し留まって法師たちから教えを受けようと思いますが、あなたはどう過ごしていますか」と書かれた檀紙は飾り気がなく美しかった。「浅茅生(あさじふ)の露の宿りに君を置きて四方の嵐ぞ静心なし」という歌も情が込められたもので、紫夫人はこれを読んで泣いた。返事は白い式紙に「風吹けば先づぞ乱るる色変はる浅茅が露にかかるささがに」と一言書かれてあった。源氏は「字がますます上達している」と独り言を言いながら微笑んだ。紫夫人の字は源氏に似つつも、わずかに艶やかな女性らしさが加わっていた。源氏は斎院がいる加茂が近いこともあり、女房の中将宛に「物思いが募って家を離れ、こんな所に泊まっていますが、それが誰のためかはお分かりでしょうか」と恨みを綴った手紙を送った。斎院には「かけまくも畏けれどもそのかみの秋思ほゆる木綿襷かな」と昔の想いを忘れがたく感じつつも、浅緑色の手紙を神々しい枝にかけて送った。中将からの返事には、長く続く日々の退屈さから昔を思い返すことがあり、あなたを思い出すこともあるが、ここでは何も現在に続くものはない、別世界だという思いが綴られていた。
2024.11.11
閲覧総数 44