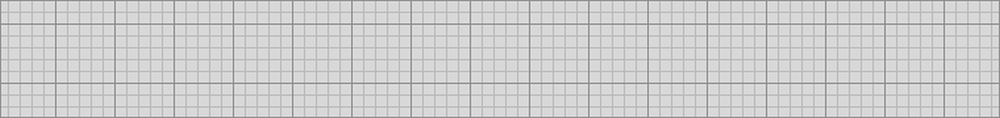全4937件 (4937件中 1-50件目)
-

源氏物語〔12帖 須磨 7〕
源氏物語〔12帖 須磨 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。二条の院では夏の衣類を作って須磨へ送る準備が進められ、かつては想像もできなかった孤独な生活を実感し、夫人は源氏の面影を忘れられずにいた。源氏がよく使っていた戸口や寄りかかっていた柱を見るたびに、かつて共に過ごした日々の尊さと寂しさが募り、胸が締めつけられるようであった。入道の宮もまた、東宮のために尽力していた源氏が逆境にあることを悲しんでいた。源氏の恋情に対しては冷淡を装い、世間の噂を避けるため努力していた宮だったが、今や尼僧として世俗を離れた境地にあり、源氏に対する感情も素直に哀惜の情が混じっていた。宮は、源氏の旅路に祈りを込めた歌を手紙に添えて送った。尚侍からの返信は、短くも苦しい想いがこもっていた。中納言の君からは、尚侍が源氏の不在を嘆く様子が伝えられ、源氏はその報告に涙した。紫の女王もまた心を込めて手紙を返し、彼女から送られた夜着や衣類には洗練された美意識が表れていた。それを見た源氏は、運命を恨めしく感じ、紫の女王と共に静かな生活を送る未来が奪われたことに無念さを覚えた。左大臣からは、若君の成長を知らせる便りも届き、源氏は我が子に対する親の情を新たにした。しかし、祖父母に守られている安心感があり、源氏は心を落ち着けることができた。なお、須磨へ移る際に筆者が触れなかったが、源氏は伊勢の御息所にも使者を送り、熱情的で典雅な手紙を受け取っていた。伊勢の御息所は源氏の消息を知ると、心の奥底から動かされ、現実であると信じ難い源氏の隠棲に想いを馳せた。その運命が長く続かないことを望む一方、暗い心の中で、この現実が夢の続きであるかのような感覚を抱く。御息所は伊勢の浜辺から須磨の浦にまで想いを送るように、悲しみや嘆きを込めた歌をいくつも綴り、長い手紙を書き続けた。御息所との恋が破れた経緯を思い出し、源氏は彼女に対する負い目と深い後悔を感じた。そんな御息所からの愛情がこもった手紙に源氏は強く心を動かされ、しばらくその使者を留めて伊勢の話を聞いたり、侍臣たちと語り合った。侍もまた源氏の優雅な風貌に触れ、喜びの涙を流したのである。
2024.11.27
コメント(1)
-

源氏物語〔12帖 須磨 6〕
源氏物語〔12帖 須磨 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。道中でも夫人の面影が消えず、源氏は胸を痛めたまま船に乗り込んだ。時期は日が長く、風にも恵まれて午後には須磨に着いた。生まれて初めての旅に心細さと新鮮さが入り交じる源氏は、荒れ果てた大江殿の松を見て、自分が遠い唐国に名を残した平安朝の歌人のように、将来が見えないと感じる。波が寄せては返す姿を見ながら、ふるさとへの恋しさを詠んだ歌が口をつき、人々もその歌に心打たれた。遠く霞む山々を見ると、千里の旅路を詠み、涙を浮かべた中国詩人の心境が重なり、寂しさが募る。須磨の居所は、都の屋敷とは異なり、茅葺きの風情ある山荘で、垣根や珍しい建材が見慣れぬ趣を醸していた。見晴らしも美しく、ただの旅ならば面白く感じただろうが、源氏は仕方なくここでの日々を過ごす。領地の人々を呼び、家の整備を進めさせ、都に仕えるような生活とはほど遠い状況にもどかしさを覚えたが、山荘は次第に落ち着きある居所に整っていった。そうして迎えた五月雨の季節、源氏は京に残した愛しい人々を思い、孤独と悲しみに沈んだ。夫人、東宮、そして無邪気に遊ぶ若君のことを考えると京のことが恋しくてたまらない。源氏は京へ手紙を送ることを決め、夫人に対し、「松島の漁師もどんな気持ちで須磨の海に涙を流しているのか」と哀しみをこめて書いた。尚侍には中納言を通して「昔を懐かしむにつけ、会いたい気持ちが募る」と伝え、二条院、入道の宮、若君の乳母にもそれぞれ思いを託し、源氏の心は京へ向かった。京では、須磨からの使いが源氏の手紙を届けると、多くの人々が動揺に駆られた。二条の院の女王はその知らせに心を乱し、体調を崩して起き上がることもできず、泣き続ける彼女を女房たちはなだめるのに苦労していた。源氏の愛用していた品々や衣服の香りは、まるで亡き人の後を思うかのように女王の心を乱し、身近な存在を失った悲しみが彼女を襲った。その様子を見かねた少納言は、北山の僧都に祈祷を頼み、源氏と女王の幸福を仏に祈願した。
2024.11.26
コメント(28)
-

源氏物語〔12帖 須磨 5〕
源氏物語〔12帖 須磨 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。源氏は出発の前、上から下までの女房たちを西の対に集め、生活に必要な絹布類を豊富に分け与えた。また、左大臣家にいる若君の乳母たちや花散里にも実用的な物品を贈った。そして、人目を避けながら尚侍にも別れの手紙を送った。源氏は京を去ることに悲しみを感じ、彼女に対する未練の歌を詠んだ。尚侍も涙を流しながら別れの歌を返したが、源氏は彼女との再会を断念し、手紙だけで別れることにした。出発前夜、源氏は院の墓参りのため北山へ向かい、その前に入道の宮へも挨拶に行った。宮は別れを悲しみながらも、東宮の未来に対して不安を抱いていた。源氏も東宮が無事即位する事を願うと述べ、別離の悲しみを交えながら話した。源氏は供の数を減らし、少人数で院の墓へ向かった。途中、右近衛将曹がかつての華やかな時代を思い出し、加茂の社に拝礼した。源氏も悲しみに浸り、歌を詠んで別れを告げた。墓に着いた源氏は、かつての皇帝との思い出に涙を流しながら祈った。月が雲に隠れる中、森の暗闇の中で、源氏は皇帝の幻影を見たかのような不思議な体験をした。その後、二条の院に戻り、東宮にも別れの挨拶をし、中宮へも最後の手紙を託した。源氏が出発の日、桜が散りかけた枝に手紙を添え、別れの思いを東宮に伝える。東宮は幼いながらも手紙を真剣に読み、「しばらく会えないだけでも恋しいのに、遠くに行ったらもっとつらくなる」と返事を書かせた。命婦は源氏の若い頃の恋を思い出し、過去の苦労を思い、自分に責任を感じて胸が痛む。返事には「何も言うことができない。寂しそうな様子を見て自分も悲しい」と書き、その後、「咲いてすぐ散るのはつらいが、再び春の都を訪れ、桜の花を楽しめることもあるだろう」と添えた。女房たちは東宮の殿で泣き交わし、源氏が不運な旅に出ることを皆が惜しんだ。源氏を慕う者は多いが、政府の圧力に恐れ、表立って同情を示す者はいなかった。みな源氏への感謝と無念を抱え、陰で政府を批判していたが、誰も動かず、源氏もその無力さに悲しみを覚えていた。当日、夜遅くまで夫人と語り合い、簡単な旅装で出発しようとしていた。
2024.11.25
コメント(25)
-

源氏物語〔12帖 須磨 4〕
源氏物語〔12帖 須磨 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。源氏は鏡に映る自分の痩せた顔を見て「随分衰えたものだ」と嘆き、夫人もそれを見て涙を浮かべた。親王と中将が帰った後、源氏は花散里の寂しさを察し、彼女に会わねば恨まれるかもしれないと思い、夜遅くになって訪れた。花散里が「別れの際にここを訪れてくれたことが嬉しい」と喜ぶ様子に、源氏は彼女の生活が今後どうなるかを案じた。薄曇りの月が差し込み、広い池や築山が寂しげに見え、須磨の浦の孤独さを思い浮かべた。出発二日前、姫君は源氏がもう訪れないのではと落ち込んでいたが、月明かりの中を歩く源氏に気づき、二人は月を眺めながら語らった。「夜が短いですね。もうこうして一緒にいることもないでしょう。なぜもっと早く、あなたといられる時間を作らなかったのか」と源氏が悔やみ、恋の始まりからの思い出を語った。鶏が鳴き、源氏も世間体を気にして早朝に去らねばならなかった。月が沈むような気分で、花散里の袖に月影が差し、「宿る月さえ濡るる顔なる」という歌のような哀愁が漂っていた。花散里の寂しさがあまりに痛ましく、源氏は「行きめぐり、ついには住むべき月影の、しばし曇らん空を眺めるなかれ」と慰めを歌ったが、別れが儚く涙を誘った。旅支度が整い、源氏は現在の権勢に媚びない忠実な者たちを家司として残し、少人数の誠実な随行者を選んだ。持っていくのは日々必要な物だけで、飾り気のない品々と詩集、琴一つを選んだ。華美な装飾品は持たず、質素な生活を決意している。西の対に家の管理を任せ、所有地や財産の証書も夫人に託し、信頼する少納言の乳母を中心に倉庫や財産の管理を任せる手配を整えた。これまで東の対の女房として源氏に直接使われていた中の、中務、中将などという源氏の愛人らは、源氏の冷淡さに恨めしいところはあっても、接近して暮らすことに幸福を認めて満足 していた人たちで、今後は何を楽しみに女房勤めができようと思ったのであるが、長生きができてまた京へ帰るかもしれない私の所にいたいと思う人は西の対で勤めているがいいと源氏は言う。
2024.11.24
コメント(25)
-

源氏物語〔12帖 須磨 3〕
源氏物語〔12帖 須磨 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。西の対へ行くと、格子が宵のまま下ろされておらず、夫人は夜通し物思いにふけっていたため、縁側のあちこちで寝ていた童女たちがようやく起き出し、夜着のまま往来している様子が趣深かった。気弱になっている源氏は、何年も留守にしている間に皆が散り散りに他所へ移ってしまうのではないかとありえないことまで想像し、心細さを感じた。源氏は夫人に昨晩、左大臣家を訪ねて夜が更けて一泊したことを告げ、「他のことを疑い悔しがってはいないか。京にいる間、せめてあなたと一緒にいたいと思っているが、いよいよ遠くへ行くことになり、どこにも挨拶を済ませておかなければならない家が多くある」と話した。夫人は「あなたの失脚以外に悔しいことなどない」と応じ、その様子には他人にはない深い悲しみが見られた。父の親王は初めから夫人に対し、手元で育てた姫君ほどの愛情を持たず、今は皇太后派を憚ってよそよそしい態度をとり、源氏の不幸も見舞いに来なかったため、夫人は人聞きも恥ずかしいと思いつつ、かえって存在を知られないほうがよかったと悔やんでいた。継母である宮の夫人が「あの人が幸福な女に見えたと思うと、その夢はすぐ消え去る。母も祖母も、今度は良人にさえ短い縁しかないのか」と嘆いたことを聞いた夫人は、人知れず恨めしく思い、親子の縁を絶ち、頼れる人もいない孤独な女王であった。源氏は夫人に「いつまでもこの状態に置かれるのなら、どんな佗びしい住まいでも迎えたい。しかし今それをするのは人聞きが悪いから控えているだけだ。勅勘を受けた人間は明るい場所へ出ることも許されない。のんきにしていると罪を重ねることになり、罪を犯していないことは自負しているが、前世の因縁か何かでこのようになっているため、愛する妻と共に流刑地に行くことは常識では考えられないことで、政府にまた迫害の口実を与えるようなものだ」と語った。昼頃まで寝室にいた源氏は帥の宮や三位中将の訪問を受け、着替えに無地の直衣を選び、かえって艶やかに見えた。
2024.11.23
コメント(28)
-

源氏物語〔12帖 須磨 2〕
源氏物語〔12帖 須磨 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語 12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。源氏は須磨への出立を前に、別れの悲しみに満たされていた。妻や情人たちは、共に行きたいと願うも、須磨のような人里離れた地に連れ立つことは、源氏自身にも彼女らにも耐えがたいものになると考え、一緒に連れて行くことはやめた。源氏のことを支え守られていた人々は、その決断に寂しさを抱いていた。左大臣も源氏の去りゆく運命を嘆き、「昔、院に愛されていた頃が嘘のようだ。何もかもが末世の中で、あなたの失脚は私にとっても悲嘆に耐えない」と述べ、源氏に寄り添った。源氏は己の運命を悟り、過去の愛憎や宮廷の複雑な事情を振り返りながらも、遠い地でその罰を引き受ける覚悟を示した。三位中将が加わり夜も更けると、源氏はかつての恋人である中納言の君に別れを告げた。翌朝、源氏は都を出発し、花々の咲き残る庭を眺めながら、女房たちとの別れに心を痛めた。彼の息子の若君や、左大臣家の人々の涙を見て、源氏はその離別の哀しみを深く噛みしめた。左大臣夫人からも惜別の言葉が届き、源氏は彼らへ歌を詠んで別れを惜しんだ。宮もまた悲しみの中で歌を返し、左大臣家は彼らの別れの歌が余韻を残し、女房たちの涙で満ちていた。源氏が二条の院へ帰って見ると、ここでも女房は宵からずっと歎き明かしたふうで、所々に かたまって世の成り行きを悲しんでいた。家職の詰め所を見ると、親しい侍臣は源氏について 行くはずで、その用意と、家族たちとの別れを惜しむために各自が家のほうへ行っていてだれ もいない。家職以外の者も始終集まって来ていたものであるが、訪ねて来ることは官辺の目が 恐ろしくてだれもできないのである。これまで門前に多かった馬や車はもとより影もないので ある。人生とはこんなに寂しいものであったのだと源氏は思った。食堂の大食卓なども使用す る人数が少なくて、半分ほどは塵を積もらせていた。畳は所々裏向けにしてあった。自分がいるうちにすでにこうである、まして去ってしまったあとの家はどんなに荒涼たるものになるだろうと源氏は思った。
2024.11.22
コメント(23)
-

源氏物語〔12帖 須磨 1〕
源氏物語〔12帖 須磨 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語12帖 須磨 の研鑽」を公開してます。源氏物語の12帖「須磨」では、源氏が藤壺の女御や朧月夜との関係を知る人々からの嫉妬や誹謗中傷に苦しみ、ついには朝廷からの圧力によって都を追われ、須磨に隠棲することになる。須磨での源氏は、都での華やかな生活から一転し、荒々しい自然の中で孤独と向き合う。夜の嵐や海の波の音に囲まれ、心細さと寂しさに苛まれながらも、現世を離れたような静寂の中で自身の運命や人生について思索するようになり、やがて源氏は須磨での生活を通して、都での浮ついた生活や人間関係を振り返り、新たな覚悟を抱き始める。当帝の外戚の大臣一派が極端な圧迫をして源氏に不愉快な目を見せることが多くなって行く。 つとめて冷静にはしていても、このままで置けば今以上な禍いが起こって来るかもしれぬと源 氏は思うようになった。源氏が隠栖の地に擬している須磨という所は、昔は相当に家などもあ ったが、近ごろはさびれて人口も稀薄になり、漁夫の住んでいる数もわずかであると源氏は聞いていたが、田舎といっても人の多い所で、引き締まりのない隠栖になってしまってはいやであるし、そうかといって、京にあまり遠くては、人には言えぬことではあるが夫人のことが気がかりでならぬであろうしと、煩悶した結果須磨へ行こうと決心した。この際は源氏の心に上 ってくる過去も未来も皆悲しかった。いとわしく思った都も、いよいよ遠くへ離れて行こうとする時になっては、捨て去りがたい気のするものの多いことを源氏は感じていた。その中でも若い夫人が、近づく別れを日々に悲しんでいる様子の哀れさは何にもまさっていたましかった。 この人とはどんなことがあっても再会を遂げようという覚悟はあっても、考えてみれば、一日 二日の外泊をしていても恋しさに堪えられなかったし、女王もその間は同じように心細がって いたそんな間柄であるから、幾年と期間の定まった別居でもなし、無常の人世では、仮の別れが永久の別れになるやも計られないのである。
2024.11.21
コメント(23)
-

源氏物語〔11帖 花散里 3 完〕
源氏物語〔11帖 花散里 3 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語11帖 花散里 の研鑽」を公開してます。これを聞いた女御も、もとから孤独の悲しみに浸っていたが、今さらまたその寂しさが身にしみてくる様子が見え、彼女の人柄が、ますます源氏の心を惹きつける優しさを感じさせた。女御は、「人目なく荒れたる宿は橘の花こそ軒のつまとなりけれ(人の目もなく、荒れ果ててしまった宿では、橘の花が軒先の飾りとなっているのだろう)」と詠み、人に忘れられて荒れた宿に、誰の手も加えられず自然のままに咲く橘の花が、まるで宿の装飾のように咲き誇っている様子が詠まれている。ここでの「橘の花」は、かつての栄華や人の温もりを象徴する一方、今はただひっそりと咲き続けるその姿が、寂寥感や無常観を際立たせている。橘の香りや姿が、過ぎ去った時の流れや失われたものへの哀愁を感じさせ、美しくも切ない情景を表現し、少しの言葉に彼女らしさがにじんでいたので、源氏はこの女御こそ本当に気高い女性だと感じた。先ほどの家の女をはじめ、幾人かの女性を思い出していたが、その中で自然と女御の品位が際立った。源氏はさらに、西の座敷へ静かに、親しげに歩み寄り、恋しい思いを訴えた。長い時を経ても変わらぬ愛情を、率直な言葉で告げたのである。彼の恋人たちは、特別な身分や魅力を備えた女性たちが多く、長く関係を保つことに同意しない人々は去ってゆくが、それも仕方がないと源氏は考えていた。町の家の女性もその一人であり、今は他に愛人がいる身であった。(完)明日より(第12帖須磨)を公開予定。
2024.11.20
コメント(27)
-

源氏物語〔11帖 花散里 2〕
源氏物語〔11帖 花散里 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語11帖 花散里 の研鑽」を公開してます。惟光が屋敷に入ると、寝殿の西端に女房たちが集まって話をしていた。惟光の声に気づいた女房たちは、源氏の歌を受け取りながらも、訪問者が誰かわからないふうを装い、「ほととぎす語らふ声はそれながらあなおぼつかな五月雨の空」という返歌を返した。彼女はわざとわからないふりをしているらしく、惟光は「門違いでしょうか」と言って退出し、彼女はそれを見送って心中で寂しさを感じ、悔しく思った。源氏も「知らぬふりをするのも当然だ」と理解しつつも物足りなさを覚え、彼女と同じほどの身分の五節が九州に行っていることを思い出した。彼の心はどこへ行っても女性たちに惹かれ、それが彼に相応の悩みをもたらしていた。長い時が過ぎても同じように愛し愛されたいと願い、多くの女性たちが源氏のせいで物思いに沈んでいた。源氏が目的として訪ねた家は、予想通りひっそりと静まり返り、寂しさが身に染み入るような佇まいであった。まず女御の居間を訪れ、彼女と話すうちに夜が更け、二十日月が上ると、大木が茂る庭はさらに暗く、軒近くの橘の木が懐かしい香りを漂わせていた。女御はすでに年を重ねていたが、柔和な上品さが漂い、かつて大いに寵愛を受けたわけではないものの、院が愛すべき人と見ていたことを源氏は思い出し、懐かしい昔の宮廷や思い出に涙を流した。そこへ杜鵑(ほととぎす)が啼き、先ほど町で聞いた声の同じ鳥が追ってきたようで、源氏はおかしくなり、「いにしへのこと語らへば杜鵑いかに知りてか」という古歌を小声で歌った。源氏は、「橘の香をなつかしみほととぎす花散る里を訪ねてぞとふ(橘の香りが懐かしくて、ほととぎすが花が散るこの里を訪ねて尋ねている)」と詠み、昔の御代が恋しくなるときにはここへ来るのが最もふさわしいと感じたと伝え、「非常に慰められる一方で、また悲しみも覚えます。時代に順応しようとする人々ばかりですから、昔を語り合う相手が減ってゆきます。しかし、あなたのほうが私以上に寂しいでしょう」と話しかけた。
2024.11.19
コメント(20)
-

源氏物語〔11帖 花散里 1〕
源氏物語〔11帖 花散里 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語11帖 花散里 の研鑽」を公開してます。源氏が「花散里」という女性に対して抱く気持ちや、花散里との関係が描かれている。花散里は、派手さや華やかさはないものの、源氏にとって心が安らぐ存在で、花散里は源氏の大勢いる女性たちの中でも特別な感情を抱かせ、安定した関係を築いている。花散里の落ち着いた性格と控えめな魅力が描かれ、源氏が心の拠り所と感じている様子が伝わってくる。「花散里」は、源氏が心の安らぎを求める場であり、他の女性とは違う特別な位置にいる人物を表している。源氏は、恋愛における苦しみは昔も今も変わらない思いであるが、近ごろは他からの耐えがたい圧迫が増し、心細くなっている。このため、世の中から離れたいという思いも浮かんでくるが、簡単に断ち切れない縁も数多くあった。麗景殿の女御は、皇子もおらず院が崩御した後は頼りない境遇となっていたが、源氏の援助で生活していた。この女御の妹である三の君とは、源氏が若いころに恋仲になり、その関係を絶つこともなく、かといって正妻として扱うこともせず、まれに訪れるのみだった。彼女は女として心痛することの多い立場である。物悲しい心境にある源氏は、急に彼女に会いたい気持ちが高まり、五月雨の晴れ間に出かけることにし、あえて簡素な身なりで少人数を従え、中川辺りを通ると、庭木が繁る小さな屋敷から琴の音が和琴に合わせて響いていた。源氏はその音に心惹かれ、往来に近い建物でもあるため車から少し体を出して眺めると、風に乗って大木の桂の葉の香りが漂い、加茂の祭りを思い出させた。源氏はその家に興味を抱き、よくよく考えると一度だけ訪れたことのある女性の家であった。久しく訪ねていない自分のことを彼女は忘れているかもしれないと思いつつも、どうしても通り過ぎることができず、じっと見つめていると杜鵑(ほととぎす)が鳴き、源氏に何かを促すようだった。そこで、車を引き返させ、惟光を使いに出して「をちかへりえぞ忍ばれぬ杜鵑ほの語らひし宿の垣根に(戻っては来たけれど、どうしても懐かしさを抑えられず、ほととぎすが昔語りをするように鳴いている)」という歌を伝えさせた。
2024.11.18
コメント(27)
-

源氏物語〔10帖 賢木 18 完〕
源氏物語〔10帖 賢木 18 完〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。大臣は尚侍(女御)に、顔色が良くないのはしつこい物怪(もののけ)の影響だと言い、「もっと修法をさせておけばよかった」と話していると、ふと見慣れない帯が尚侍の着物に絡みついているのを発見し、不思議に思う。その後、几帳の前には見慣れない男の字で書かれた紙が散らかっているのも目に入り、大臣は驚きと恐れを感じる。「この紙は誰が書いたものか、不審だ。誰の字であるか確認したい」と言って尚侍に紙を求めるが、彼女は答えられず、狼狽している。状況が明らかになると尚侍は失神するように動揺し、大臣も「娘の恥をこれ以上晒すべきではない」と思うのが常であろうに、怒りのままに紙を拾い、ついに几帳の隙間から源氏が横になっている姿を見つける。源氏は驚いて顔を夜着で隠し、大臣はその無礼さに激しく怒りをあらわに。だが、直接怒りをぶつけることはせず、怒りと無念を胸に紙を持って寝殿へ去っていく。尚侍も深く恐れて気が遠くなり、源氏も彼女のために心を痛めながら彼女を慰めようとする。大臣は堪えきれず太后に源氏と尚侍の不品行を訴え、目撃した事実を述べる。「この字は源氏のものです。彼女は源氏に誘惑されて恋人同士になっていたが、敬意を表して黙って結婚を認めようとした。だが拒まれてしまい、宮中に入れましたが、あの関係があったせいで女御にはなれず寂しい思いをしていたのに、再びこのような罪を犯すとは残念でなりません。世間で源氏が斎院に恋文を送っているという噂があったが、私は信じなかった。あのようなことをしては神罰を受けるのは明白で、自分も無事では済まないと理解しているはずだと思っていたからです」これを聞いた太后は怒りを顔に表し、源氏への憎しみを募らせる。彼女は、「陛下も軽んじられている。兄の方である太子に娘を嫁がせようとはしなかったが、年若い源氏に嫁がせるために取っておいたのです。それを彼は誘惑し、父母も誰も非難せず結婚させた。私は妹を哀れに思い、他の女御たちに引けを取らせないために努力したが、今は源氏が好きなようにしているのがよいようだ」と憤る。大臣は後悔し、「この件は秘密にしていただきたい。陛下にも伝えないでください。もし源氏が改めないならば、自分が責任を負います」と懇願するが、太后の怒りは収まらず、源氏への憎悪が増すばかりで、彼を排除することを考え始める。(完)明日より(第11帖花散里)を公開予定。
2024.11.17
コメント(25)
-

源氏物語〔10帖 賢木 17〕
源氏物語〔10帖 賢木 17〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。修法などもさせて尚侍の病の全快したこ とで家族は皆喜んでいた。こんなころである、得がたい機会であると恋人たちはしめし合わせ て、無理な方法を講じて毎夜源氏は逢いに行った。若い盛りのはなやかな容貌を持った人の病 で少し痩せたあとの顔は非常に美しいものであった。皇太后も同じ邸に住んでおいでになるこ ろであったから恐ろしいことなのであるが、こんなことのあればあるほどその恋がおもしろく なる源氏は忍んで行く夜を多く重ねることになったのである。こんなにまでなっては気がつく 人もあったであろうが、太后に訴えようとはだれもしなかった。大臣もむろん知らなかった。雨がにわかに大降りになって、雷鳴が急にはげしく起こってきたある夜明けに、公子たちや 太后付きの役人などが騒いであなたこなたと走り歩きもするし、そのほか平生この時間に出ていない人もその辺に出ている様子がうかがわれたし、また女房たちも恐ろしがって帳台の近くへ寄って来て、源氏は帰って行くにも行かれぬことになって、どうすればよいかと惑っ た。秘密に携わっている二人ほどの女房が困りきっていた。雷鳴がやんで、雨が少し小降りに なったころに、大巨が出て来て、最初に太后の御殿のほうへ見舞いに行ったのを、ちょうどま た雨がさっと音を立てて降り出していたので、源氏も尚侍も気がつかなかった。大臣は軽輩がするように突然座敷の御簾を上げて顔を出した。「どうだね、とてもこわい晩だったから、こちらのことを心配していたが出て来られなかった。中将や宮の亮は来ていたか」などという様子が、早口で大臣らしい落ち着きも何もない。源氏は発見されたくないということに気をつかいながらも、この大臣を左大臣に比べて思ってみるとおかしくてならなかった。 せめて座敷の中へはいってからものを言えばよかったのである。尚侍は困りながらいざり出て 来たが、顔の赤くなっているのを大臣はまだ病気がまったく快くはなっていないのかと思った。 熱があるのであろうと心配したのである。
2024.11.16
コメント(28)
-

源氏物語〔10帖 賢木 16〕
源氏物語〔10帖 賢木 16〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。彼が人間としてさらに成熟していることを感慨深く見つめている。この場面全体を通じて、源氏と中宮の深い心の交錯と運命の悲哀が描かれ、彼らが世俗を離れ、それぞれの道を歩む様子が切なくも美しく描かれている。春の官吏の任命において、中宮に仕えていた人々は本来得られるはずの官職がもらえず、推薦された人々の位階もそのままにされ、悲嘆に暮れる者が多かった。中宮が出家したことで后の地位は消え、それに伴い財産も失うと解釈されたため、政府の待遇も冷たくなった。中宮はそれを予測して執着を持っていなかったが、仕える人々が不安な様子を見せると、心中に動揺が生じることもあった。それでも、中宮は自分の犠牲を覚悟し、息子である東宮の即位に障害がないように祈り、信仰に励んで不安を和らげていた。源氏も中宮のこの心情を理解し、共感していた。一方で、源氏に仕える役人たちも不遇で、左大臣は失意のうちに引退の願いを出したが、帝は彼を重んじて何度も辞表を返却した。それでも左大臣は出仕を拒み、結果として太政大臣一族だけが栄える状況となり、帝も世間も嘆いていた。左大臣の息子たちも以前は順調に昇進していたが、今やその栄光は過去のものとなり、三位中将も時勢に意気消沈していた。ある日、三位中将は詩集を持って二条の院へ訪れ、源氏も貴重な詩集を取り出し、韻を競う遊びを行った。学者たちも参加し、源氏の深い知識に感嘆し、右の組が敗北した。数日後、再戦の宴が開かれ、席上で詩が詠まれ、庭の花や自然の景色が盛り上げ役となった。源氏が特に可愛がっていた幼い少年が「高砂」を歌い、源氏はその愛らしさに服を与えた。その姿は席の者たちの心を打ち、源氏の美しさが際立っていた。宴が進む中、三位中将は源氏に杯を勧め、詩を詠み交わした。詩や歌の多くは源氏を称賛するもので、源氏もその場に満足し、周公の伝承を引用し口にした。兵部卿の宮もこの宴に参加し、音楽を楽しむなどして、二条の院での和やかなひとときを共に過ごした。その時分に尚侍が御所から自邸へ退出した。前から瘧病にかかっていたので、禁厭などの宮中でできない療法も実家で試みようとしてであった。
2024.11.15
コメント(29)
-

源氏物語〔10帖 賢木 15〕
源氏物語〔10帖 賢木 15〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。中宮の父帝の一周忌を機に、彼女は法華経の八講を盛大に催した。十一月の初めには雪の中で亡き父を偲び、源氏もその場に参加して深く悲しみに浸っていた。十二月にはさらに崇厳な仏事が続き、その場で中宮は思い立って出家を表明した。出家の儀式が始まり、人々は涙に暮れ、特に源氏は驚きと悲しみに心を乱す。中宮が自身の出家を決意したことを「昨年の悲しみがあった時から考えていた」と伝えられると、源氏は深い悲しみと共に、御簾の奥の様子や薫香が立ち込める香りに極楽世界を思い浮かべ、哀切の想いに沈みこむ。中宮が出家を決意し、源氏が彼女の変化に心を揺さぶられる様子が描かれている。源氏は、中宮が出家することによって中宮が自分の手の届かない存在になることを理解し、愛慕と敬意の入り混じった複雑な感情を抱いた。中宮に対する源氏の思いは、もはや単なる恋愛感情を超えた崇高な敬意となっており、彼女が仏門に入ることでその感情がさらに強く、切なくなっている。中宮は出家を通じて世俗を離れ、信仰に生きる覚悟を固めたが、源氏が訪れると過去の思いが蘇り、涙を抑えきれなくなる。また、彼女は東宮(息子)への責任を果たすべく仏道に励んでおり、その背後には母としての深い愛情と心の苦悩がある。源氏もまた、二条の院に戻った後も中宮への思いが消えることはなかった。仏道に生きる決意をした中宮を見守る形でその愛慕を昇華させようと試みる。春が訪れると、華やかな宮中行事が続く中、中宮は自身の人生の無常を感じ、仏道への思いを強める。その寂しさと清らかさは、彼女の住まいの様子にも表れている。中宮邸に訪れた源氏は、彼女の身の回りの変化や、仏門に入った中宮の落ち着いた様子を見て、かつての華やかな宮廷生活を懐かしみ、失われた日々を痛ましく思う。仏道に入った中宮の姿は、源氏にとっても手の届かない存在へと変わり、彼は彼女の前で涙を流さずにはいられない。老いた女房たちは、出家を決意し、信仰に生きる中宮を称賛しつつ、かつての源氏の栄光や幸福に満ちた姿を思い起こしていた。
2024.11.14
コメント(26)
-

源氏物語〔10帖 賢木 14〕
源氏物語〔10帖 賢木 14〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。中宮は、東宮に関することで信頼を寄せつつも感情を表に出さない理知的な態度を示し続け、源氏はそれに不満を感じていた。東宮の世話は源氏が行っており、今度ばかりは冷淡に振る舞えば怪しまれるだろうと考えた源氏は、ある日中宮が御所を出る日に帝を訪問した。帝は懐かしむように源氏と昔の話、今の話を交わし、院の面影を重ねるようであり、その会話の中で尚侍との関係についても理解を示しつつ、詩や歌の話に話題が移った。帝は斎宮の美しさやその下向の日の出来事を回想し、源氏も野の宮での曙の別れに心打たれたことを語り合った。その夜、二十日の月が夜空に輝き始め、夜の趣が増す中、帝は「音楽を聞きたい夜だ」と言われたが、源氏は「中宮が退出されると聞きましたので訪問しようと思っています」と述べた。院の遺言通りに親身に東宮の世話をしていることを帝に伝えた。帝は、「院は東宮を我が子のように愛するようにと命じたので、自分も兄弟以上に大切に思っているが、控えめに接するようにしている」と話された。その後、源氏が退出する際に藤大納言の息子である頭の弁が皮肉交じりに口ずさむも、源氏は何もとがめずにその場を去った。その後、源氏は「ただ今まで御前におりましたので、遅くなりました」と中宮に挨拶し、月明かりが照らす御所の庭を見渡して、院が御位におられた頃の懐かしい音楽遊びを思い出していた。源氏が中宮の悲しい別れと彼女の出家という深い転機を迎える場面である。まず、「九重に霧や隔つる雲の上の月をはるかに思ひやるかな」というのは、高貴な身分である中宮への思いを遠くから募らせる源氏の心情を示している。これは命婦が源氏に伝えた言葉であり、中宮の気配を微かに感じ、抑えきれぬ恋しさと哀れみを誘っている。この状況で源氏は、中宮への届かぬ想いを詠んだ「月影は見し世の秋に変はらねど隔つる霧のつらくもあるかな」という歌を口にします。この歌は、変わらない月影(彼女への想い)は以前と同じ秋を照らすが、今は隔てられる霧(隔離された現実)がその想いを苦しくさせているという意味です。中宮がその悲しい別れを経ての出家に至る過程では、彼女が東宮へ未来を託し、成長を促しながらも、思いが深く届いていないことに失望や哀れみを抱く描写があります。中宮の心情や、源氏を誘い出そうとする他の女性たちからの手紙が、彼の心を動かしつつも軽く流されている様子が描かれ、源氏がなおも中宮に特別な情を注ぐことが示されている。
2024.11.13
コメント(26)
-

源氏物語〔10帖 賢木 13〕
源氏物語〔10帖 賢木 13〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。斎院からは木綿の片に「そのかみやいかがはありし木綿襷心にかけて忍ぶらんゆゑ」とだけ書かれていた。斎院の文字には細やかな味わいはないが、高雅で、漢字の崩し方はますます巧みになっており、成長した美しさが想像され胸を高鳴らせていたが、神罰を恐れないようにと自戒した。源氏は去年、野の宮での別れがちょうどこの頃であったことを思い出し、自分の恋愛がうまくいかないのは神々の加護によるものだと考えたが、恋愛に障害があるとより一層情熱が高まる自分の性格を知らなかったのである。もしそれを望んでいたのなら、加茂の女王との結婚も難しくはなかったはずだが、当時は無頓着であり、今となって後悔の念に駆られて涙を流すばかりであった。一方、斎院も普通の恋愛感情を込めた手紙を受け取るのではなく、これまで源氏から多くの文を受け取り、それに対して少し返事をすることもあったが、神聖な職に就いているにもかかわらず少しばかりの謹慎を欠いた行為でもあった。天台の経典六十巻を読み、難解な箇所を僧たちに尋ねるなどしながら寺に滞在する源氏を見て、僧たちは彼が仏の力によって寺に引き寄せられたと考え、皆が喜んでいた。静かな寺で朝夕に人生の儚さを感じながらも、紫の女王に対する深い愛情が源氏の帰宅を促し、彼は寺を後にすることを決める。出発前には盛大な法要を行い、僧たちや周囲の下層民にも多くの施しを行った。帰る際には寺の広場に集まった人々が涙ながらに彼を見送っており、喪服姿で黒い車に乗った源氏の美しい姿は人々の心を魅了した。夫人は幾日かのうちにさらに美しさを増したようであり、高雅な中にも源氏の愛に対する不安が見え隠れし、彼は一層愛おしさを感じた。紅葉の美しさが増す山から枝を折ってきた源氏は、長い間手紙も出さず寂しさを感じていたので、それを何気なく中宮への贈り物として届けさせ、命婦宛に手紙を添えた。そこには、近頃は宗教的な勉学に励んでいるため不在が続いた旨と紅葉の美しさを分かち合いたいという意が記されていた。珍しいほど美しい紅葉に喜ぶ中宮であったが、枝に添えられた手紙に気づくと、源氏の矛盾した行動に反感を覚え、瓶に挿した枝を庇の間の柱の前に出してしまった。
2024.11.12
コメント(29)
-

源氏物語〔10帖 賢木 12〕
源氏物語〔10帖 賢木 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。源氏にあまりに似ているため中宮は世間を恐れて悩むこともあった。源氏は中宮への恋心を抱きつつも、自らの冷淡さを反省し隠棲を決め、秋の野の草花を眺めるために雲林院へと出かけた。源氏は母の兄である律師のいる寺で経を読み仏勤めに励もうと、数日滞在することにしたが、その間にも色づき始めた木々や秋草の花の哀れな様子に心を奪われていた。学僧たちを集めて論議を聞いたりもしたが、場所が場所だけに無常観が増し、なおも中宮への未練を強く感じる自分を見つめることとなった。月光のもと、僧たちが菊や紅葉の花を仏に捧げる様子を見て、僧にはこうした務めがあり未来への希望を持てることが羨ましいと感じた一方、自分はこの世への未練を断ち切れないでいた。律師が「念仏衆生摂取不捨」と唱える声を聞くと、ますます出家への思いと紫の女王への気がかりが募るばかりである。しばらく滞在しようと決めた源氏は恋妻である紫夫人に手紙を送った。「出家の真似事をしていますが、寺の生活は寂しく心細いばかりです。もう少し留まって法師たちから教えを受けようと思いますが、あなたはどう過ごしていますか」と書かれた檀紙は飾り気がなく美しかった。「浅茅生(あさじふ)の露の宿りに君を置きて四方の嵐ぞ静心なし」という歌も情が込められたもので、紫夫人はこれを読んで泣いた。返事は白い式紙に「風吹けば先づぞ乱るる色変はる浅茅が露にかかるささがに」と一言書かれてあった。源氏は「字がますます上達している」と独り言を言いながら微笑んだ。紫夫人の字は源氏に似つつも、わずかに艶やかな女性らしさが加わっていた。源氏は斎院がいる加茂が近いこともあり、女房の中将宛に「物思いが募って家を離れ、こんな所に泊まっていますが、それが誰のためかはお分かりでしょうか」と恨みを綴った手紙を送った。斎院には「かけまくも畏けれどもそのかみの秋思ほゆる木綿襷かな」と昔の想いを忘れがたく感じつつも、浅緑色の手紙を神々しい枝にかけて送った。中将からの返事には、長く続く日々の退屈さから昔を思い返すことがあり、あなたを思い出すこともあるが、ここでは何も現在に続くものはない、別世界だという思いが綴られていた。
2024.11.11
コメント(25)
-

源氏物語〔10帖 賢木 11〕
源氏物語〔10帖 賢木 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。宮自身も東宮のためには源氏の好意を保っておく必要があると感じていた。源氏が人生を悲観して僧になってしまうことは避けねばならないと考えたが、同時に、頻繁にこのような出来事が続けば、世間の人々がどんな噂を立てるかは容易に想像できる。宮は、自分が尼になり、皇太后の不興を買って后の位を退くことが最良ではないかと考え始めた。そして、自分が院の遺言にどれだけ重く縛られているかを思うと、漢の戚夫人のように苛まれることはないにしても、世間の嘲笑を受ける運命にあると感じるようになっていた。これを機に尼の生活に入ることが最善だと宮は考えたが、東宮に会わずに姿を変えるのは申し訳ないと思い、目立たぬ形で御所に参内した。源氏は、病気を理由に宮に従うことはなく、普段は好意を表していたが、贈り物などの関係は変わらないまま、宮に会いに行こうとはしなかった。そのため、事情を知っている人たちは、源氏が深く悲観しているのだろうと同情していた。東宮は短い間に美しく成長され、久しぶりに母宮と会うことができた喜びに夢中になり、甘えたりする姿が非常に愛らしいものであるが、母宮もこの子を離れて信仰の道に入ることができるのかと自問していた。その上、宮中の空気は時の移り変わりに伴い、人の心も変わりゆくことを痛感させ、人生の無常を教えてくれるものだった。特に太后が復讐心に燃え、宮中に出入りする者たちが冷たい視線を投げかけることもあった。東宮を守る立場にいること自体がかえって東宮を危うくするのではないかと悩むのであった。中宮は「長くお目にかからなければ私の顔が変わってしまうかもしれません」と仰せになると、東宮は「式部のようにですか。そんなことはありませんよ」と笑った。中宮は「私が髪を短くして、黒い着物を着て夜居のお坊様のようになろうと思っていますので、次にお会いするのはずっと先になるかもしれません」と涙ながらに告げると、東宮は真剣な顔になり「長くおいでにならないと、私はあなたにお会いしたくてたまらなくなります」と涙を流した。東宮の美しい髪や愛らしい顔立ちは成長するに従ってますます源氏とそっくりであり、見間違える事もあるほどだった。
2024.11.10
コメント(24)
-

源氏物語〔10帖 賢木 10〕
源氏物語〔10帖 賢木 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。宮は上着を源氏に押しつけ、逃げようとしたが、髪と衣が源氏の手に引かれていた。宮は自分の運命を悲しく思いながらも、非常に清らかな気高さを保ち、源氏に対して強く抵抗した。源氏は泣きながら愛を訴えたが、宮はあくまで冷静で、ただ「体調が良くなったら改めて話をしましょう」とだけ答えた。源氏は千言万語を尽くして自分の苦しい思いを伝えたが、宮は優しく受け止めつつも、二度と罪を犯すことはできないと心を固めた。夜が明けても源氏は宮のそばを離れたくなかったが、王命婦や弁が説得して、やっと源氏は退去することに同意した。宮は半ば死んだような状態で、何も言わず、ただ朝を迎えた。源氏は宮に対して、自分はもうすぐ死ぬだろうと告げた。それでも死後もこの世に執着することで罰を受けるのだろうと言い、宮への強い思いを表していた。彼は逢うことの難しさに苦しんでおり、今生きている間に宮に会えなければ、何世代にも渡って嘆き続けるだろうと言い、どんな状況になっても宮に執着し続けると告白した。宮はそれに対して嘆息をつき、長い生涯の恨みを人に残しても、自分の心を敵にしないでほしいという詩を詠んで、源氏の言葉を軽く受け流すような態度を見せた。その優美さに源氏は心を惹かれながらも、軽蔑されるのは辛く、これ以上自分を押し進めるのは控えなければならないと感じて、その場を去った。それ以来、源氏は宮に対して手紙を送ることをやめ、顔を見せることも避けるようになった。彼は自分が冷たく扱われたことに傷つき、宮から同情を感じるまで沈黙を守ろうと決めていた。彼は御所や東宮にも顔を出さず、引きこもってしまった。日々、冷たい態度への恨みが募る一方で、恋しさもますます強まり、まるで魂が抜けたように感じ、自分が病気にでもなったかのような状態に陥っていた。源氏は、この世での生活がますます虚しく感じられ、僧になろうかと思い詰めることが多くなっていたが、いつもその決意を揺るがすのは若い妻の存在であった。彼は、自分だけを頼りに生きている優しい妻を見捨てることができず、僧になる決心はつかないでいた。一方で、宮も心が大きく揺れていた。源氏が手紙も送らず、引きこもってしまったことに対して、命婦たちは彼を気の毒に思っていた。
2024.11.09
コメント(27)
-

源氏物語〔10帖 賢木 9〕
源氏物語〔10帖 賢木 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。慎重に計画された行動で、宮にとっては夢のような出来事だった。源氏は誠実な言葉で宮の心を動かそうとしたが、宮は冷静さを失わず、それに応じなかった。次第に宮は胸の痛みを感じ始め、苦しむようになった。命婦や弁など、秘密を共有している女房たちが驚き、様々な手助けをした。源氏は宮が恨めしくてたまらない上に、この世が真っ暗になったように感じ、呆然としたまま朝まで寝室に留まっていた。宮の病状を聞きつけ、女房たちが頻繁に往来するようになり、源氏は無意識に塗籠に押し込まれてしまった。女房が源氏の上着をそっと持ってきたものの、彼女も恐れていた。宮は未来に対する悲観と、現在の状況に対する苦しみから体調を崩した。翌朝になっても回復せず、兄の兵部卿宮や中宮大夫が参殿し、祈りの僧を迎えるような話が進んでいた。源氏はこれを苦しく聞いていたが、夕方になってようやく宮の病状が少し収まった。源氏が一日を塗籠で過ごしていたことを中宮は知らず、命婦や弁も心配をかけないように黙っていた。宮は昼の座に出て静かに座っていた。病状が回復したらしいと兵部卿宮も帰り、居間には少数の人々しか残らなかった。普段から宮に仕えている親しい者だけが、几帳の後ろや襖子の陰などに控えていた。命婦は源氏をそっと外に出して帰す方法を考え、再び宮に近づかないようにしないと、また病状が悪化すると宮が気の毒だと囁いていた。源氏は塗籠の戸に手をかけ、そっと開けて屏風と壁の間を伝い、宮の近くまで進んだ。宮の横顔を影から眺める喜びに胸を躍らせ、涙まで流していた。宮は「まだ私は苦しい。死ぬのではないか」と言いながら外を眺めていたが、その横顔は非常に美しかった。髪の質や形、頭の輪郭は西の対の姫君とそっくりで、源氏は改めて二人がよく似ていることに驚いた。初恋の宮は他の誰よりも優れて見え、源氏は過去も未来も忘れて宮に近づき、そっと衣の褄を引いた。源氏の香の香りが立ち込め、宮は気づいて驚き、前に伏してしまった。源氏は、せめて一度でも振り返ってほしいと願ったが、宮は冷たく対応し、源氏は物足りなさと恨めしさを感じた。
2024.11.08
コメント(21)
-

源氏物語〔10帖 賢木 8〕
源氏物語〔10帖 賢木 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。御修法のために御所に出入りする人が多い時期であり、このような密会が自分の手で行われることを中納言の君は恐れていた。朝夕に見飽きることがない源氏と稀に会えた尚侍の喜びは想像に難くない。尚侍も今が青春の盛りの姿で、美しく艶やかで若々しく、男性の心を強く惹きつける魅力を持っていた。やがて夜が明ける頃、下の庭から「宿直をいたしております」と高い声で近衛の下士が言った。これは中少将の誰かが女房の局に来て寝ているのを知り、意地悪な者が告げ口をしてわざわざ挨拶をさせにやったのだろうと源氏は考えた。御所の庭でのこうした挨拶回りは趣があるものの、源氏にとってはやや煩わしかった。さらに庭のあちこちで「寅一つ」(午前四時)と報告する声も聞こえてきた。尚侍は「心から袖を濡らすこともあるでしょう。明けたと知らせる声につけて」と詠い、その様子はどこかはかなげであった。源氏も「嘆きつつ我が世はこうして過ぎていくのだろうか、胸が晴れる時もなく」と詠い、落ち着かないまま別れを告げて出て行った。まだ朝には遠い暁の月夜で、霧が一面に広がる中、簡素な狩衣姿で歩く源氏は美しかった。この時、承香殿の女御の兄である頭中将が、藤壺の御殿から出て、月明かりに影を落とす立蔀の前に立っていたのだが、源氏はそのことを知らずに近づいてしまった。この出来事が後に批難の声を招くことになるだろう。源氏は尚侍との新たな関係ができたことに喜びを感じていた。中宮が一切隙を見せないご立派な方であることを認めながらも、その恋心がかなわぬことに対して、恨めしく悲しい思いを抱くことが多かった。源氏は御所へ参内することに気が進まなかったが、それでも東宮に会えないのは寂しいと感じていた。東宮には他に後援者がいなく、ただ源氏だけが中宮にとって頼りだったが、源氏は時折東宮に迷惑をかけるような行動をしていた。院が亡くなるまで、その秘密を全く知られずにいたことでも、東宮は大きな罪だと感じており、今また悪評が立てば、東宮には必ず大きな不幸が訪れると心配し、源氏の情熱を断ち切ろうと仏に祈っていた。宮は祈祷を頼み、できる限りの手段で源氏の恋心から身を守ろうとしていたが、ある時、思いもよらず源氏が寝所に近づいてきた。
2024.11.07
コメント(28)
-

源氏物語〔10帖 賢木 7〕
源氏物語〔10帖 賢木 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。源氏は昔と変わらず、左大臣家を訪れては故夫人の女房たちを大切にしていた。大臣家の人々も、源氏が非常に若君を愛していることに感激し、若君は一層大切にされた。かつての源氏はあまりにも社会的に恵まれ過ぎていて、周囲の目が回るほどの華やかさだったが、最近ではかつての恋人たちとの関係も自然と途絶えがちになり、軽い関係だった女性たちの家に訪れることさえ、源氏には居心地の悪さを感じさせるようになっていた。そのため、余裕が生まれ、家庭の主人として落ち着いて暮らしていた。兵部卿宮の王女が幸福であることを皆が祝福した。少納言は、姫君の幸運は祖母の尼君が仏に祈った結果だと思っていた。父である親王も朗らかに二条の院を訪れ、夫人の生んだ他の王女たちは特に大きな幸運に恵まれていなかったが、ただ一人、姫君だけがその運命を負ったかのように見えたため、継母にあたる夫人は嫉妬を感じていた。紫の上は、小説にあるような継娘の幸運を現実に得たのだった。加茂の斎院は父帝の喪のために引退されたため、代わりに式部卿宮の朝顔の姫君がその職を継ぐこととなった。伊勢に女王が斎宮として行かれたことはあったが、加茂の斎院には内親王が就くことが多く、今回は適当な女御腹の宮様がいなかったか、そうした決まりがあったのである。源氏はこの女王に今も恋心を抱いていたが、結婚が不可能な神聖な職に就くことになったことを残念に思っていた。彼の側近である女房の中将は依然として源氏の用事をよくこなしており、手紙なども頻繁にやりとりしていた。源氏は当代の自身の不遇な立場には何も気にせず、斎院と尚侍に対する恋心を嘆いていた。帝は院の遺言通りに源氏を愛していたが、若くしてきわめて心の弱い方であり、母后や祖父の大臣の意向に従うしかなく、朝政に対して多くの不満があった。源氏は昔よりもさらに恋の自由がない境遇にいたが、それでも尚侍と文を通じて絶えず恋をささやくことで、少なからず幸福感を得ていた。宮中で五壇の御修法が行われ、帝が謹慎されていた頃、源氏は夢のようにして尚侍に近づいた。中納言の君が、かつての弘徽殿の細殿の小部屋に源氏を導いたのである。
2024.11.06
コメント(25)
-

源氏物語〔10帖 賢木 6〕
源氏物語〔10帖 賢木 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。中宮の供奉を務める多くの高官たちは、院の生前と変わらぬ様子であったが、心の中では寂しさを抱えており、実家に帰ることがかえって無縁の地に思える中宮は、近年ほとんど実家に帰る機会がなかったことをしみじみと感じていた。年が変わっても、諒闇(喪に服す期間)の春は非常に寂しかった。源氏は特に寂しさを感じ、家に閉じこもって過ごしていた。例年なら一月の官吏の交代時期には、院の時代もそうだったしその後も二条の院の門は訪問客の馬や車で賑わっていたが、今年は明らかにその数が減っていた。宿直に来る人の夜具を入れた袋もあまり見かけなくなり、近しい家司たちだけが気楽に事務を行っているのを見て、源氏は自分の家の勢力が衰え、それに応じて人々の信頼も薄れていることを感じ、面白くなかった。右大臣家の六の君が二月に尚侍(ないしのかみ)になったのは、院の崩御によって前任の尚侍が尼となったためだ。大臣家が全力で後援し、六の君自身も美貌と品格を備えていたため、後宮の中でも際立った存在となった。皇太后は実家にいることが多く、稀に参内する際には梅壺の御殿を宿所としたため、弘徽殿が尚侍の曹司となり、隣の登花殿は長く放置されていたが、今では再び使われて賑やかになっていた。女房たちも多く侍り、華やかな後宮生活を送りつつも、尚侍は密かに源氏を想い続けていた。源氏から手紙が忍んで届くことも以前と変わらなかったが、六の君が後宮に入ってから源氏の情熱はさらに燃え上がっていた。院が生きていたころは遠慮があったが、皇太后は源氏に対する積年の恨みを晴らす時が来たと考え、彼に対する圧力が増していくのを見た源氏は、不快感を抱きながらも、予想していたとはいえ、その苦しみを常に味わうことに耐えられなくなっていた。左大臣も不快感を抱き、あまり御所に顔を出さなかった。亡くなった令嬢に対して東宮の話があったにもかかわらず、源氏に妻として迎えさせたことで、皇太后は不満を抱いていた。右大臣とはもともと仲が悪く、左大臣は前代である院の時代に政治を専横的に動かしたこともあったため、当代で右大臣が外戚として権力を握っているのを快く思わないのは当然だった。
2024.11.05
コメント(26)
-

源氏物語〔10帖 賢木 5〕
源氏物語〔10帖 賢木 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。桐壺院は東宮を支えるように何度も言い聞かせていた。夜遅くになって東宮が帰り、その際に供奉した多くの公卿たちの姿はまるで行幸に匹敵するほどの盛大さだった。東宮が帰った後、桐壺院は最も深く悲しんだ。皇太后は来る予定だったが、中宮が院にずっと寄り添っていたことに不満を抱いて躊躇している間に院は崩御してしまった。慈悲深い桐壺院との別れに、多くの人々がどれほど悲しんだか計り知れない。院が天皇の位を退いた後も、政治はすべて順調に進んでいたが、今の天皇はまだ若く、外戚の大臣も人格者ではなかったため、将来的にその大臣が権力を握ることを恐れて官僚たちは不安を感じていた。院が最も愛した中宮や源氏も、特に深い悲しみの中にあった。院が亡くなった後の仏事では、多くの遺子の中で源氏が目立って誠実な弔いをしており、周囲の人々もそれを当然としつつも源氏の孝心に共感した。喪服姿の源氏は限りなく美しく、去年と今年と不幸が続いたことで彼の心は世を厭うようになり、出家を考えるほどだったが、彼には多くの絆があり、それは実現しなかった。四十九日までは女御や更衣たちが院の御所にこもっていたが、その日が過ぎると皆散り散りに実家へ帰って行った。十月二十日、空は寂しげで、誰もが世の終わりを感じるような心細い季節だった。中宮は最も悲しんでいたが、皇太后の性格をよく知っていたため、今後どのような扱いを受けるかという不安よりも、院の愛情に包まれていた日々を思い出す悲しみが大きかった。永久に院の御所に留まることはできず、皆が去らなければならないことも中宮にとって寂しさを感じさせた。中宮は三条の宮へ帰ることになり、兄である兵部卿の宮が迎えに来た。激しい風の中に雪が混じる日で、かつての賑やかだった御所も今や静まり返っていた。源氏は中宮の御殿を訪れ、院の在世中の話をしていたが、庭の松が雪に打たれて枯れ落ちる様子を見た中宮が詠んだ歌に源氏は深く心を動かされ、涙を流した。凍りついた池を眺めながら源氏もまた、自らの感情を和歌に託し、かつての院の影を見られないことに悲しみを覚えたが、その歌は源氏としてはまだ未熟なものだった。その後、王命婦もまた和歌を詠み、そのほかの女房たちもそれに続いた。
2024.11.04
コメント(22)
-

源氏物語〔10帖 賢木 4〕
源氏物語〔10帖 賢木 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。「振り捨てて今日は行くとも鈴鹿川八十瀬の波に袖は濡れまい」すでに夜も更け、慌ただしい中で、翌日逢坂山の向こうから御息所の返事が届いた。「全てを振り捨てて今日は出発するけれども、鈴鹿川のいくつもの浅瀬に立つ波のような困難や障害があっても、自分の袖は涙で濡れることはないだろう」と簡素に書かれていたが、貴人らしさを感じさせる巧みな筆遣いであった。源氏はもう少し優しさがあれば、最上の文字となるだろうと思った。秋の夜明け、濃い霧がかかり、身にしみる空を眺めながら源氏は「行く先を眺めることもできない。この秋は逢坂山に霧が立ちはだかっている」と口ずさみ、一日中物思いにふけりながら過ごした。旅立った御息所は、さらに堪えがたい悲しみに包まれていただろう。院の病状は十月に入ってから重篤となり、この君を惜しむ者は誰一人としていなかった。帝も心配のあまり行幸されたが、衰弱した院は東宮のことを何度も帝に頼んだ。さらに源氏にまで話が及び、「私が生きている時と同じように、重要なことも些細なこともすべて彼に相談するように。年は若いが、国を治めるのに十分な資格を持っていると私は認めている。彼には一国を支配する才能が備わっているからこそ、私は彼がそのことで誤解を受けることがないよう、親王にはせず、人臣の列に加えたのだ。将来、大臣として国務を任せるつもりでいた。私が亡くなった後でも、この言葉を尊重してほしい」と遺言を残した。院は多くの希望を述べたが、それを全て書き写すことはできなかった。帝はこれが最後の会見であると感じ、院の言葉を悲しげに聞きながら、遺言を違えることはしないと何度も誓った。帝は以前にも増して美しく、その風采に院は満足し、頼もしく感じた。高貴な身分であるため、感情のままに父帝の元に留まることはできず、その日のうちに還幸されたが、二人の心には会見の後も長く悲しみが残った。東宮も同時に見舞いに行くはずだったが、大げさになることを懸念して別の日に見舞った。幼いながらも大人びた愛らしい様子に、久しぶりの再会に喜びが勝り、今の状況を深く理解せず、無邪気に笑顔で院の前に現れた。その横で中宮が泣いているため、院の心には様々な悲しみが押し寄せていた。
2024.11.03
コメント(28)
-

源氏物語〔10帖 賢木 3〕
源氏物語〔10帖 賢木 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。長奉送使や官庁から参列した高官も名のある人々ばかりで、院が後援者として存在しているからである。出立の日に、源氏から別離の悲しみを綴った手紙が届いた。さらに、斎宮宛のものとして、斎布に添えられたものもあった。手紙には「いかずちの神ですら恋人の仲を裂くことはないと言います。八洲を守る国つ御神も心あるなら、飽きぬ別れの中を断たないでほしい。どう考えても神の意図が理解できず、私は納得できない」と書かれていた。斎宮はそれを受け取り、返事をした。宮の歌を女別当が代筆し、「国つ神が空に分け隔てをするというなら、まずはないがしろにされることをただしなければならない」と詠んだ。源氏は、宮中での式を見たいと思いながらも、去る者が見送りに出るのは気が引けると感じて家にとどまった。斎宮からの大人びた返歌を見て、源氏は微笑み、彼女が年齢以上にしっかりとした人物に成長していることに胸が高鳴った。恋をすべきではない相手に対して好奇心が湧くのは源氏の癖であり、顔を見る機会があった幼少期の斎宮のままで終わってしまったことを残念に思った。しかし、運命は予測できないものであり、再び彼女を見る機会があるかもしれないと源氏は考えた。見識高い美しい女性として名高い御息所に付き添われた斎宮の出発の列を一目見ようと物見車が多く出ていた日、斎宮は午後四時に宮中へ入った。御息所は、父の大臣が未来の后と見なして東宮の後宮に入れた自分をかつてどれほど華やかに扱ってくれたか、不幸な運命の末、后の輿ではなく、わずかに付き従う立場で自分が宮廷を目にする今となっては、感慨深いものがあった。十六歳で皇太子の妃となり、二十歳で未亡人となり、三十歳で再び内裏に入った御息所の歌は「その時のことを今日は思い出すまいと思えども、心の中で何かが悲しんでいる」と詠んだ。斎宮は十四歳であったが、美しさに包まれ、この世の女性とは思えぬほどの美貌であった。斎王の美しさに心を打たれながら、帝が別れの御櫛を髪に挿して渡される時、帝は悲しみに堪えかねて悄然としていた。式の終わりを待つ斎宮の女房たちの乗った車から見える袖の美しさは、特に人目を引いた。若い殿上役人たちはそれぞれ個人的に別れを惜しみ、行列は暗くなってから動き出し、二条から洞院の大路を折れる場所にある二条院の辺りで源氏は物思いに沈みながら榊に歌を添えて送った。
2024.11.02
コメント(26)
-

源氏物語〔10帖 賢木 2〕
源氏物語〔10帖 賢木 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。九月七日、斎宮の出発が迫っていた。御息所も忙しく、会う余裕がないと言っていたが、手紙を何度も送ったため、最後の会見について躊躇しつつも、少なくとも物越し(直接顔を合わせない方法)でなら会おうと決めた。心の中では、昔の恋人との再会を待ち望んでいた。町を離れて広々とした野原に出ると、源氏は秋の深まりを感じた。草花は衰え、虫の声と松風の音が混じり合い、遠く野の宮からかすかに楽の音が聞こえてきた。その風情は非常に艶やかであった。源氏は、身分を隠し、控えめな行列を伴って野の宮に向かっていたが、あえて美しく装って来た。供の若者たちはその風流さを面白がっていた。源氏は心の中で、これまでこの野原を訪れなかったことを後悔していた。源氏が六条御息所を訪ねて、彼女が住んでいる野の宮に到着する。そこは質素な構えだが、丸木の鳥居などが神聖な雰囲気を醸し出していて、源氏は何となく神々の領域にいるような感覚を持つ。周囲には神官らしき男たちが集まり、独特の雰囲気が漂っている。源氏は、恋人である御息所がこんな場所で何ヶ月も過ごしていることに胸を痛める。源氏が訪問を知らせると、音楽の音がやみ、御簾(みす)の中から衣擦れの音が聞こえる。源氏は御息所と直接会いたいと伝えるが、彼女はなかなか出てこない。源氏は、「昔のように素直に会ってくれても良いのに」と感じ、御簾越しに榊の枝を差し入れて、自分の心情を伝える。彼は「私の心は常に変わらないのに、なぜ冷たくされるのか」と問いかける。それに対して、御息所も心の中では迷いながらも、「自分の気持ちはまだ残っているが、過去の出来事を思うと、会うのが辛い」と応じる。二人は昔の恋を思い出し、源氏は涙を流す。御息所も感情を抑えきれず、涙を流すが、彼女は伊勢行きを止めることはできないと感じている。夜が明け、秋の冷たい風が吹く中で、二人はつらい別れを迎える。源氏は涙ながらに宮を去り、二条の院に戻るまで涙を止められなかった。御息所も心乱れて、源氏との別れを悲しむ。彼女の出発が近づいているが、源氏からの手紙や贈り物に心が揺れる一方で、もはや恋は終わったと感じていた。源氏と御息所が再び会い、過去の恋に心を乱される様子が描かれ、二人の感情の揺れ動きが、別れの寂しさと重なり合い、切ない情景となっている。十六日、桂川で斎宮の御禊の式では、例年以上に華やかに行われた。
2024.11.01
コメント(25)
-

源氏物語〔10帖 賢木 1〕
源氏物語〔10帖 賢木 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語10帖 賢木(さかき) の研鑽」を公開してます。10帖 賢木(さかき)の中では源氏と六条御息所との関係が冷え切っていく様子や、源氏の家族関係に大きな変化が起こる事。まず、源氏と御息所の関係が悪化する。御息所は娘の斎宮(伊勢神宮に仕える巫女)のために伊勢へ行くことを決め、源氏との別れを決意するが、源氏も未練を感じながら、冷淡な態度をとるようになる。一方で、源氏の父である桐壺院が病に倒れ、ついに崩御(亡くなる)。これによって、源氏は政治的にも孤立し、権力を持つ左大臣や弘徽殿女御(こうきでんのにょうご)らと対立することになる。さらに、源氏の正妻である葵の上が妊娠し、出産するが、その後に亡くなってしまう。源氏は深い悲しみに沈むが、周囲の人々の関係もますます複雑になり、物語は波乱含みの展開を迎える。「賢木(さかき)」は、源氏の人生における大きな転換点を描いており、源氏の感情や人間関係の変化が大きく進む巻で、六条御息所は、斎宮(さいぐう)の伊勢への出発が近づくにつれて、ますます心細くなる。世間では、左大臣家の夫人が亡くなった後、源氏と御息所が夫婦になるだろうという噂が広まっていた。御息所の家でも、そうなるだろうと期待していたが、実際には源氏は冷淡な態度を取り始めた。夫人が病気の間に、御息所が源氏に嫌われるような出来事があったことも、彼女の中では確信に変わっていた。苦しみながらも、御息所は伊勢行きを決意する。母親が斎宮に同行するのは珍しいが、娘がまだ若いという理由をつけて、御息所は源氏への恋から完全に離れようとする。源氏もさすがに冷静ではいられず、御息所が去ってしまうことに未練があったが、手紙だけは愛情を込めて送っていた。しかし、御息所はもう源氏と恋人として会うつもりはなく、源氏も彼女に対する冷たい記憶が消えていないため、冷静に別れられるだろうと思っていた。しかし、御息所自身は源氏への愛情が強いため、会うことで心が乱れ、苦しみが増すと考え、冷たい態度を取っている。御息所は時折、野の宮から六条の邸にこっそり帰ることがあったが、源氏はそれを知らなかった。野の宮は恋人が通う場所ではないため、二人は長い間会うことがなかった。源氏は、父である院が病気で苦しんでいたこともあり、ますます余裕がなくなっていたが、御息所を恨んだままでは彼女に気の毒だし、世間の評判を考えて、ついに彼女を訪れることにした。
2024.10.31
コメント(30)
-

源氏物語〔9帖 葵 22 完〕
源氏物語〔9帖 葵 22〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。宮からの挨拶を女房が取り次ぐ場面が描かれ、女房が伝えたのは、「今日だけは昔の事を忘れようとしていましたが、あなたの御訪問でその努力が無駄になってしまった」という内容で、さらに宮は、「昔からこちらで作らせていたお召し物も、あれ以来私の涙で視力が曇り、出来栄えが悪くなりましたが、今日だけはこんなものでもお着替えください」と言い、掛けてあった衣服のほかに、とても手の込んだ美しい衣装一揃いを贈りました。これらは今日のために特別に作らせたもので、色も織り方も特別なものだった。源氏はすぐにその衣装の下襲に着替えたが、もし自分が訪れていなければ、宮が失望してしまっただろうと心苦しく感じていた。源氏は、「春の訪れのしるしとして、当然あなたにお会いすべき私が参上しましたが、様々な思いが蘇り、涙がこぼれて、お話を伺うことができません。今日のために新しい色衣を着ても、涙が降り落ちる気がします」これに対して宮は返歌を詠み、「新しい年が来たと言わずとも、降るものは涙、つまり降り注いでいるのは涙だけです」と返した。このやりとりから、宮がどれほど深く悲しんでいたかが感じられる。葵の巻で源氏は、六条御息所という高貴な女性とも関係を持っていて、彼女は源氏に対する独占欲や嫉妬で心を痛め、賀茂祭で、葵の上と六条御息所は、共にこの祭りに参加し、二人の間に緊張が走ります。御息所は、源氏が正妻である葵の上を大切にすることに不満を感じていた。葵の上に対して激しい嫉妬を抱いて、この嫉妬心が高まるあまり、御息所の生霊(いきりょう)が無意識のうちに葵の上に取り憑き、彼女を苦しめることになる。葵の上は、その後急激に体調を崩し、結局、出産後間もなく亡くなってしまう。源氏は彼女が亡くなる直前にようやく彼女に心を寄せるが、その時にはもう遅く、彼は深い悲しみと後悔に苛まれることになる。この章では、源氏の女性たちとの関係の複雑さや、嫉妬と愛情のもつれが大きなテーマとなっていて、六条御息所の感情の揺れと、葵の上の悲劇的な最期が印象的に描かれていた。(完)明日より(第10帖賢木さかき)を公開予定。
2024.10.30
コメント(28)
-

源氏物語〔9帖 葵 21〕
源氏物語〔9帖 葵 21〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。大臣は涙を拭いながらそれを手に取り、若い女房たちがそれを見ておかしがる。紙には詩歌がたくさん書かれており、字も上手だったと大臣はため息をつきながら語り、その後、空間をじっと見つめて物思いにふける。大臣は、源氏が婿でなくなったことを惜しんでおり、詩の中に「亡き魂ぞいとど悲しき寝し床のあくがれがたき心ならひに」と書かれた部分を読み、また別の詩の一節「君なくて塵積もりぬる床なつの露うち払ひいく夜寝ぬらん」には、撫子の花が挟まれていた。それを見て大臣は宮に見せ、娘との縁が短かったことを嘆き、日に日に恋しさが募ることに困っていると語り、また源氏が他人になってしまうことが悲しいと泣いた。若い女房たちは集まり、自分たちの別れについても悲しみを共有していた。一方、院では源氏が痩せたことを心配され、食事を勧められたりする。中宮に伺った際にも、源氏は過去の打撃から悲しみが消えないことを語り、中宮からの励ましに感謝しつつ、厭世的な気持ちになったことを述べた。喪中の服をまとい、いつもよりも寂しさを漂わせた源氏の姿は人々の同情を引き、彼の姿には艶やかさが見えた。源氏は二条の院に戻り、きれいに整えられた御殿で待ち受けていた男女を見て、左大臣家を出た際の女房たちの姿を思い出し、彼女たちを哀れに感じた。その後、冬の装飾に変えた西の対に行き、少納言の計らいで美しく整えられた若い女房や童女たちの姿を目にし、紫の女王が美しく座っているのを見ていた。源氏が長く会っていなかった若紫に再会する場面が描かれており、源氏は久しぶりに彼女に会った。成長した姿を目の当たりにして彼女の美しさに心を打たれ、恥ずかしそうに振る舞う様子や初恋の頃から変わらない顔立ちに感銘を受けて心を躍らせ、今後は彼女と一緒に過ごすことができる喜びを語りながらも、これまで喪に服していたことを理由にその場を去り、再び訪れることを約束したが、少納言は源氏が多くの愛人を持つことを知っていたために紫の上に新たな困難が訪れるのではないかと不安に思い、源氏はその後、他の女房たちと過ごしながら乳母からの哀れな手紙に心を痛め、しばらくは恋人たちの元にも足を運ばず一人で過ごす日々が続き、紫の上も一人前の女性となり結婚する時期が来たと感じながらも、源氏の軽口が通じないことに退屈を感じ、彼女の知性や芸術的才能に喜びを見出しつつも愛が募るたびに悩みが深まった。
2024.10.29
コメント(30)
-

源氏物語〔9帖 葵 20〕
源氏物語〔9帖 葵 20〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。源氏の軽口が通じないことに退屈を感じ、それに苦しむようになり、ある朝、源氏が目覚めると紫の上はまだ寝床に伏しており、女房たちは彼女の様子を心配し、源氏はそっと硯箱を置いて紫の上がそれに気づき手紙を開くと「あやなくも隔てけるかな夜を重ねさすがに馴れし中の衣を」という歌が書かれていたが、彼女は源氏の真意を理解できず、これまで信頼してきた源氏に対して疑念と悲しみを抱き、源氏が様子を伺いに来た際にも彼女は体調不良を理由に彼を避け、源氏がどれだけ機嫌を取ろうとしても言葉を発さず、源氏は「もうあなたのところへは来ない、こんなにも私を恥ずかしい目に遭わせるのだから」と嘆きつつも、彼女の無邪気な少女らしさに愛おしさを感じ、その日も彼女のそばに付き添って慰めようとした。だが、彼女の態度は変わらず、源氏はますます彼女を愛おしく感じ、その晩は亥の子の餅を食べる日であったが源氏は自身の喪中を理由に派手な祝宴を控え、控えめに準備された西の対で餅を見ながら南側の座敷に移り、従者の惟光を呼んで餅を翌日の夕方に持ってくるよう指示し、微笑む源氏の様子から惟光はすべてを察した。惟光が源氏に「そうでございますとも、おめでたい初めのお式は吉日を選びませんでは。それにいたしましても、今晩の亥の子ではなく、明晩の子の子餅はどれほど作ってまいったものでございましょう」とまじめな顔で尋ねる場面で、源氏は「今夜の三分の一くらいだ」と答え、それを聞いた惟光は心得た様子で立ち去り、世慣れた態度で行動することに源氏は感心していた。惟光は誰にも言わず、自分でほぼ全て手配して主人の結婚式の三日目の餅を準備した。源氏は新夫人の機嫌を直すために、これまで盗み出してきた女性を扱うのと同じくらい苦労していると感じ、そんな困難の中にも興味を覚えた。そして、源氏はもう一夜だって彼女と離れていられないと感じ始めていた。惟光は、命じられた餅を夜が更けるのを待って持ってきた。源氏が少納言のような年配の女房に頼むのは気が引けると考え、少納言の娘の弁という若い女房に頼んだ。惟光は弁に「これは間違いなく御寝室のお枕元へ差し上げなければならない物なのですよ。お頼みします。たしかに」と頼み、弁は少し不思議に思いながらも受け取り、「私はこれまで誰ともいい加減なごまかしの必要な交渉をしたことがありません」と言った。
2024.10.28
コメント(26)
-

源氏物語〔9帖 葵 19〕
源氏物語〔9帖 葵 19〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。孤児の少女が心細そうにしているのを見て、源氏はその子を哀れに思い、「これからは私だけが君を可愛がる人だね」と慰める。その子は源氏の言葉に泣き出し、黒い喪服を身にまとった姿が哀れで可憐に見える。源氏は、葵の上を失ったことによって女房たちが散り散りになってしまうことを悲しみ、皆に一緒にいてほしいと願う。また、葵の上の身近な品々が女房たちに分け与えられ、源氏はこれ以上籠居するわけにはいかず、院の御所へ出向く準備をする。別れの時が近づき、邸内には別れを惜しむ者たちの涙と、木の葉を散らす風が吹き、しぐれが降り注ぐ。源氏は二条の院に戻る予定であり、女房たちはその別れを悲しみ、源氏は涙を流しながらも、葵の上の死によって改めて人生の無常を感じた。源氏自身もいつ死に取られるか分からないという不安を口にする。彼の姿は、深い悲しみの中にあってもなお美しく、女房たちや大臣も彼の言葉に共感し、涙を流す。大臣もまた、葵の上を失った悲しみを抱え、源氏に対して、自分が余命いくばくもないこと、そして子供に先立たれた悲しみを語り、涙をこぼす。大臣は、自分の弱さを人に見せたくないため、院に伺わず、源氏にそのことを取り計らってもらうよう頼む。源氏は女房たちが心細そうにしている姿を哀れに思い、彼女たちに対しても、今後もこの邸に立ち寄ることがあるだろうと慰める。女房たちはそれを信じつつも、源氏が本当にもうこの家を訪れることはないのではないかという不安を抱え、別れを悲しむ。この場面は、源氏が葵の上を失った悲しみを乗り越えようとする中で、女房たちとの別れがさらに寂しさを深め、彼の心に大きな影響を与えていることが描かれている。人生の無常と別れの哀しみが強調され、源氏もまた、その運命に直面している様子が伝わってくる。女房たちは源氏が去ることを悲しんでいるが、源氏は自分のことを信頼してくれる妻がもういないため、以前のようにのんきに外を出歩くこともできなくなったと語り、すぐにまた訪れると言って出て行った。大臣は、源氏がかつて住んでいた座敷に入り、部屋の様子や装飾は以前と変わらないものの、そこにある空虚さを強く感じた。帳台の前には硯や無駄書きの紙があった。
2024.10.27
コメント(28)
-

源氏物語〔9帖 葵 18〕
源氏物語〔9帖 葵 18〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。源氏はこの手紙を受け取ったとき、普段よりも見事な筆跡に心を惹かれるが、内容が慰問状として素知らぬふりをしていることに複雑な感情を抱く。過去の出来事を考えれば、彼女と完全に縁を切るのは残酷であり、名誉を傷つけることにもなると感じた。源氏はまた、六条御息所の生霊を見たという出来事に心を悩ませていた。彼の恋はもう戻ることができないと感じ、彼女に返事を書くことを決意する。返事の中で、心から常に彼女を思っていること、そして「露のようなはかない命」の象徴を用いて、恨みを忘れて欲しいと伝えた。六条御息所は、源氏の手紙を読んで、そこに込められた感情を悟るが、それが自分の薄命のせいだと悲しむ。彼女は自分が源氏と恋に落ち、最終的に悪名を取ることになる運命を重苦しく感じていた。その後、源氏は独り身の生活を送る中、三位中将などの訪問を受けながら、さまざまな話をしたが、彼の心には常に人生の寂しさが漂っていた。彼の喪服姿は艶やかであり、その中で故人を偲ぶ詩を詠んでいる。また、宮に花を贈り、故人を思う感情を表現する一方で、源氏の心は依然として複雑な感情に揺れている。この全体を通じて、源氏は死者や過去の恋愛に対する深い哀感を抱きつつも、新しい関係や未来を考えざるを得ない状態にあった。また、彼の心に秘めた後悔や未練が、彼の行動や思考に強く影響を与えていることが描かれている。源氏が亡き葵の上を悼み、彼女の死後の生活や女房たちとの別れについて語られている。夜になり、光源氏は灯りを近くに置いて、信頼する女房たちを呼び集めて話をしている。中納言の君(源氏の情人だった女性)もいたが、葵の上の忌中では源氏は彼女を情人として扱わず、主従として接していた。それを中納言の君は、源氏が葵の上への愛情を示していると感じ、嬉しく思っていた。源氏は女房たちと話しながら、葵の上を失った寂しさや人生の無常を語り、女房たちも皆涙を流す。源氏は、これから先、女房たちと離れることを寂しく思っている。源氏は、葵の上を失ったことを話しながらも、未来への不安や自身の命についても触れ、女房たちに対して、これまでのように一緒にいることはできないかもしれないと告げる。源氏の言葉に女房たちはさらに涙を流し、源氏もまた涙を浮かべる。特に葵の上が可愛がっていた孤児の少女が心細そうにしている。
2024.10.26
コメント(29)
-

源氏物語〔9帖 葵 17〕
源氏物語〔9帖 葵 17〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。その唯一の姫君を失ったことは、袖に置いた玉が砕ける以上に惜しく、残念なことであったに違いない。源氏は二条院にすら行かず、仏勤めに専念して過ごしていた。恋人たちには手紙を送っていたが、六条御息所だけには一切の消息を伝えなかった。人生を早くから悲観的に見ていた源氏は、情人たちがいなければ僧になってしまうかもしれないと考えることもあった。しかし、その時彼の目に最初に浮かぶのは、西の対に住む姫君の寂しそうな面影であった。夜は一人で帳台に寝た。多くの侍女が周囲に座っていても、夫人のそばにいないことは限りなく寂しいことだった。「秋の別れの時期に、恋しい人がいなくなってしまうのは辛い」と思いながら、源氏は眠れず、声の良い僧侶を選んで念仏を唱えさせ、そのような夜明けの心持ちは耐えがたいものだった。秋が深まり、ある夜明け、白菊が色づき始めた枝に青がかった灰色の紙に書かれた手紙が置かれていた。源氏がその手紙を開くと、それは六条御息所からのものだった。「これまで遠慮してお尋ねしなかった私の気持ちはおわかりでしょうか」と書かれていた。葵の上の死を巡る源氏と関係者たちの感情や動きが描かれています。特に源氏と六条御息所の関係が焦点となっており、また源氏の喪中の心境が重く描写されています。まず、六条御息所は源氏に手紙を送りますが、その中で「人の世の無常を露にたとえ、短い命の儚さ」を表現しています。人の世が哀れだと聞いても、それ以上に心に染みることは、露が露を送るように、はかない命を思い、その無常を感じることである。まさにこの朝の空の色を見て、深く感傷を覚えたので、つい筆を取って書いてしまった。この句があまりにも心にしみたためだ。書かれた文字も普段以上に美しく、源氏はこれを見て感嘆しながらも、その手紙が表面上は素知らぬふりをした慰問状であることに、少し恨めしく思った。源氏は、たとえ過去にあのような出来事があったとしても、完全に関係を断つことは残酷であり、自分の名誉を傷つけることにもなると感じていた。彼は、死んだ人の運命は定められていたのだと自分に言い聞かせながら、あの夜に御息所の生霊を見たことに疑念を抱いていた。彼の恋心がもう二度と戻ることがないことがうかがわれる。そのために手紙を無視することはあまりに冷酷だと思い、返事を書く決心をする。彼女は源氏に対して今朝の空の色が哀愁を帯びていることを述べ、手紙を書かずにはいられなかった心境を伝えている。
2024.10.25
コメント(19)
-

源氏物語〔9帖 葵 16〕
源氏物語〔9帖 葵 16〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。左大臣の娘であり源氏の正妻であった葵の上の葬儀には、多くの人が参列した。寺々から集められた僧侶たちも念仏を唱えるために集まり、鳥辺野は人々でいっぱいだった。天皇をはじめとして皇后や皇太子から使者が次々に到着し、葬場で弔辞を読んだ。左大臣は悲しみに打ちひしがれ、立ち上がる力も失っていた。彼は「こんな老いぼれになってから、若い娘を失って無力に泣いている自分がいる」と嘆いた。恥ずかしさを感じつつ泣いている左大臣を悲しんで見ない者はいなかった。葬儀は夜を通して行われ、終わりには遺体を広い野に置き、火葬されるという寂しい結末を迎え、皆は早朝に帰って行った。死はこのようなものであり、源氏も以前愛した人を一人失ったことはあったが、今回の葵の上の死によって一層深い悲しみを感じた。八月の終わりの有明月が空に浮かび、その空の色が源氏の心に染みた。左大臣の悲しみを同情しつつも、源氏は耐えられず、車の中から空ばかりを見つめていた。「昇りゆく煙はそれと分からなくても、雲に漂うその哀しみは感じられるものだ」と思い、家に帰っても眠れなかった。源氏は葵の上との長い夫婦生活を振り返り、なぜ自分が彼女に十分な愛情を示さなかったのか、なぜ一時的な衝動に駆られて彼女を傷つけるようなことをしてしまったのかを悔やんだ。彼女は生涯、心から自分に打ち解けることはなかったと感じるが、今となっては何の意味もない。喪服を着ていることさえ夢のように感じ、もし自分が先に死んでいたら、葵の上はもっと深い喪服を着て悲しんでいただろうと思うと、また悲しみが押し寄せてくる。源氏は「限りがあるなら薄墨の喪服は浅い色だが、涙は袖を深い淵にしてしまう」と詠んだ後、念仏を唱え、その姿は限りなく艶やかだった。経を小声で読み、「法界三昧普賢大士」と唱える源氏は、仏勤めに慣れた僧侶よりも尊く感じられた。若君を見ても、「形見の子さえもいなかったなら、どうして耐えられただろう」と古歌を思い出し、さらに悲しくなったが、この形見の子が残されただけでも慰められるべきだと考えた。左大臣の妻も悲しみに沈んで寝込み、命が危うい様子で家の人々は慌てて祈祷を行わせた。寂しい日々が過ぎ、四十九日の法要の準備をするにも、宮は予期していなかったため悲しみに打ちひしがれていた。娘に欠点があったとしても、親が死を嘆く気持ちは深いものであり、ましてや貴女としてほぼ完全であった姫君の死を母親が嘆くのは至極当然である。
2024.10.24
コメント(24)
-

源氏物語〔9帖 葵 15〕
源氏物語〔9帖 葵 15〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。病気の妻を気遣う源氏の姿に、女房たちは同情を覚えた。葵の上は美人であるにもかかわらず、衰弱してほとんど存在感がなくなり、寝ている様子は痛ましく見えた。それでも、少しも乱れることなく枕にかかっている彼女の髪の美しさには、男の魂を奪うほどの魅力を感じた。源氏は、自分が長い間この美しい妻に満足できなかったことが不思議に思い、彼女をじっと見つめます。この場面は、源氏が葵の上に対して感じる複雑な感情と、彼女の美しさに改めて惹かれる様子を描いています。源氏は、御所に出かける前に葵の上に話しかけ、自分がいない間も早く元気になってほしいと願います。彼は、いつもお母様(葵の上の母)に甘えているので、もっと早く自立して回復し、一緒にいられるようになってほしいと言い残して出かけます。葵の上は病床から源氏の装束姿をこれまでよりも熱心に見送ります。その日、秋の官吏の昇任が決まる日であり、大臣も参内していました。息子たちもそれぞれ希望する昇進を得るため、大臣のそばを離れないようにしていました。屋敷の中が静かになった頃、突然、葵の上は激しい胸の痛みに襲われ、息絶えてしまいます。迎えの使いを出す間もなく、彼女はそのまま命を落としました。左大臣と光源氏は、彼女の死を聞いて急いで屋敷に戻りますが、葵の上は既に亡くなっていました。葵の上の突然の死は、左大臣の邸を混乱させます。夜中の出来事であり、叡山の座主や他の僧侶を招く余裕もなく、葵の上の死はだれにとっても予期せぬものだったため、皆が呆然とするばかりでした。慰問使たちが訪れるものの、取り次ぎを行う者もおらず、邸内には泣き声が響き渡る。左大臣夫妻と光源氏の嘆きは非常に深く、特に源氏は妻の死に対して深い悲しみと人生の無常を感じていた。物怪のせいで一時的に仮死状態になったこともあるため、二、三日はそのまま病夫人として寝かせて蘇生を待ったが、やがて彼女が完全に亡くなったことを認めざるを得なくなる。どれほど祈っても蘇生することはなく、死が確実なものとなり、鳥辺野の火葬場へ葵の上を送ることになる。この場面では、葵の上の死に対する源氏の深い悲しみと、左大臣夫妻の悲痛な感情が強調されている。また、彼らの感情を超えて、死という避けられない現実が静かに忍び寄り、人生の無常感が漂う場面となっている。
2024.10.23
コメント(25)
-

源氏物語〔9帖 葵 14〕
源氏物語〔9帖 葵 14〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。一方の光源氏は、少し心が落ち着いたものの、以前に生霊となった六条御息所が現れたことや、その時の彼女の言葉を思い出し、彼女の元に訪ねていかないことに対して罪悪感を感じた。しかし、その記憶がある限り、以前のように彼女に愛情を抱くことができるかどうか自信が持てず、苦悩していた。源氏は、御息所の名誉を守るためにも手紙だけを送るにとどめ、直接会いにはいかなかった。御息所の体調はまだ回復しておらず、両親もその状態を心配して見守っているため、源氏も浮ついた行動は控えていた。葵の上の容体もまだ優れず、源氏と同じ部屋で過ごすことはなく、源氏は生まれたばかりの若君の可愛さに心を奪われている状況だった。この場面は、六条御息所の嫉妬と苦しみ、そして源氏の心の葛藤を鮮明に描き、彼らの複雑な人間関係と感情の動きが表現されている。源氏の長子である若君が生まれたことに対して、葵の上の父である大臣は非常に喜んでおり、すべてが理想的に進んでいるように感じている。しかし、葵の上の体調が回復するのが非常に遅いことが唯一の心配事であり、大臣もその点を気にかけていた。それでも、これまでの重体を考えると、現在の状態は普通だと受け入れつつも、大きな幸福感は減少していない。一方で、源氏は若君の美しさが東宮に似ていることを見て、幼い皇太弟を恋しく思い、御所に長く上がっていないことに耐えられなくなっていた。そこで、葵の上に対して、そろそろ御所に行かなくてはならないが、せめて近くで少し話をしたいと伝えた。それに対して、女房は葵の上に忠告し、あなた方の間柄は体裁を気にするようなものではないので、物越しにでも話をすればよいと助言した所、これを受けて、源氏は病室に入り、葵の上と会話を交わした。葵の上は非常に弱っており、返事も時折しかできないが、それでも絶望的だった以前の状態と比べると、源氏は今が夢のように幸せだと感じた。かつて彼女の命が危ぶまれた時期を思い出しながら話をしているうちに、葵の上が突然様々なことを口にした場面が蘇り、源氏は不快感を覚えて会話を打ち切ろうとした。源氏は、長話はやめようと言い、女房に、お湯を差し上げよと命じた。
2024.10.22
コメント(25)
-

源氏物語〔9帖 葵 13〕
源氏物語〔9帖 葵 13〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。「そんなことを言っても、あなたが誰であるか私は知らない。確かに名を言ってみなさい」と源氏が言うと、その人物はますます御息所そっくりに見えた。驚きを通り越して、不気味さに寒気を覚えた。女房たちが近づく気配にも、源氏はそれを見破られるのではないかと胸が高鳴った。病苦にもだえる声が少し静まったのは、少し楽になったのかもしれないと、宮様が飲み物を持たせて寄こした時だった。その女房に抱き起こされて間もなく、子が生まれた。源氏は非常に嬉しく思ったが、物怪が他の者に移って騒ぎ立った。それに加えて、まだ後産も終わっていなかったので、不安は続いていた。夫と両親が神仏に大願を立てたのはこの時だった。そのおかげか、すべてが無事に済んだので、叡山の座主をはじめ高僧たちは、誇らしげに汗を拭きながら帰っていった。これまで心配し続けていた人々はほっとして、危険が去ったという安心感に包まれ、回復の兆しが見えたと誰もが思った。修法なども改めて行われていたが、今、目前に新しい命が誕生したことに対する喜びが大きく、左大臣家は昨日とは打って変わって幸福に満たされた様子だった。院をはじめ、親王方や高官たちからは派手な産養の祝いの宴が毎晩開かれた。生まれたのは男子だったので、これらの儀式は特に華やかだった。六条御息所が自分が生霊となってしまったことに深い苦悩を感じている様子が描かれています。六条御息所は、光源氏が正妻・葵の上との間に子供が生まれたという話を聞き、それに対して非常に不快に感じていました。彼女は、葵の上が危険な状況にあったにもかかわらず、なぜ無事に子供を出産できたのかと、嫉妬と驚きを抱きます。その一方で、彼女自身は過去に失神するほど心身が不調になっていた日々を思い返します。その時、彼女の衣服には祈りの僧が焚いた護摩の香りが染み込んでいましたが、何をしてもその異変は改まらず、自分が生霊として人々に影響を与えているという説を否定できなくなり、それに対して強い悲しみを感じます。自分の心の中にある苦しみを誰にも打ち明けられず、一人で悩み続ける御息所は、ついに源氏との関係を清算しなければならないと決意する。
2024.10.21
コメント(24)
-

源氏物語〔9帖 葵 12〕
源氏物語〔9帖 葵 12〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。父母たちは、席を外したが、この時、加持を行う僧が声を低くして法華経を読み始めたのが、非常にありがたいと感じられた。几帳の垂れ絹を引き上げて源氏が中を覗くと、夫人は美しい顔をしており、腹部だけが大きく盛り上がった形で横たわっていた。ほかの誰が見ても涙を禁じ得ない姿であり、まして夫である源氏が見て、惜しさと悲しさを覚えるのは当然のことであった。白い着物を着ていて、顔色は病熱で華やかになっている。たくさんの長い髪は中ほどで束ねられて、枕に添えてあった。こんなふうに美女が横たわっている姿は、最も魅惑的に見えた。源氏は妻の手を取って、「悲しいじゃありませんか。私にこんな苦しい思いをさせてしまうなんて」と言うものの、多くは言えず、ただ泣くばかりであった。普段は源氏にまっすぐ見られると恥ずかしそうにして目をそらしていたその目で、今はじっと夫を見上げているうちに、涙がそこから流れ出ていた。それを見て、源氏が深い哀れみを感じたのは言うまでもない。あまりにも泣いているのを見て、夫人は別れを惜しんで親たちのことを考えたり、また自分を見て、別れの耐え難い悲しみを感じているのだろうと源氏は思った。「そんなに悲しまないで。私はそれほど危険な状態ではないと思う。また、たとえどうなっても、夫婦は来世でも逢えるのだから。御両親も、親子の縁というのは特別な縁だから、来世で再会できると信じていなさい」と源氏が慰めると、そうじゃないのです。私は苦しくてたまりませんから、しばらく法力をゆるめてもらいたいとお願いしようとしたのです。私は、こんなふうにしてこちらに出てくるつもりはなかったのですが、物思いをする人の魂というものは本当に自分から離れていってしまうものなのですと懐かしそうに言ったあとで、「嘆きわび、空に乱れるわが魂を、結びとめてよ、下界のすみかに」という声も様子も、夫人ではなくなっていた。全く変わってしまったのである。怪しいと思って考えてみると、夫人は完全に六条の御息所になっていた。源氏は驚き、愕然とした。人々がいろいろと噂をしていたことも、くだらない人々が言い出したことだとこれまで源氏は否定してきたが、それが今、現実となって目の前に現れているのだった。こんなことがこの世にあるのだと思うと、人生が嫌になってきた。魂の嘆きや苦しみが空にまで広がり、それを現世に引き留めてほしいという願いを表現している。
2024.10.20
コメント(28)
-

源氏物語〔9帖 葵 11〕
源氏物語〔9帖 葵 11〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。御息所は、現実の自分にはそんな事ができる筈もないのに、夢の中では荒々しい力が働いた。情けないことだが、魂が身体を離れていっているのではないかと思われた。時折、御息所は失神状態になっていた。何もないことを悪く言うのが世間であり、まして今の自分は彼らのみだりに相手をののしる格好の人物だろうと考えると、御息所は名誉が傷つけられることが苦しくてならなかった。死後にこの世に恨みを残して霊が現れることはよくあることだが、それすらも罪深いことだと思うべきであるのに、生きている自分がそのような悪名を負うのは悲しいことである。すべて源氏を愛してしまった罪だと御息所は考えた。その人への愛を捨てなければならないと努めたが、それは実現不可能なほど難しいことであった。斎宮(伊勢神宮に奉仕した斎王の御所)は去年すでに御所の中へ移られるはずだったが、さまざまな障りがあり、この秋ようやく断食生活の第一歩を踏み出すことになった。そしてもう九月からは嵯峨の野の宮へ入ることになっている。それに加えて、二度ある御禊の日の準備に邸の人々は忙殺されている。しかし、御息所は頭がぼんやりとして、寝て過ごすことが多かった。邸の男女たちは、このことを心配して祈祷を頼んだりしていた。何か特定の病気というわけでもなく、ただぶらぶらと病んでいる状態だった。源氏からも常に見舞いの手紙は届いていたが、愛する妻の容態の悪さが、源氏自身がこの人を訪ねることをできなくしているようであった。まだ産期には早いと思い一家の者たちが油断しているうちに、葵の君は急に産みの苦しみを感じ始めた。病気の祈祷に加えて、安産の祈祷も数多く行われたが、御息所の執念深い物怪だけはどうしても夫人から離れなかった。名高い僧たちも、これほどの物怪に出会った経験がないと言って困っていた。しかし、さすがに法力で抑えられ、物怪は哀れに泣き始めた。法力を少し緩めてくださいな、大将さんに話したいことがありますと、そう夫人の口から言うのであった。あんなこと、訳があるのですよ。私たちの想像が当たりますよと、女房たちは言って、病床に立てられた几帳の前に源氏を導いた。父母たちは、娘が良人に何か言い残すことがあるのかもしれないと思い、席を外した。
2024.10.19
コメント(22)
-

源氏物語〔9帖 葵 10〕
源氏物語〔9帖 葵 10〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。源氏は、理想通りにはいかないものだと思い、性質、容貌、教養など、さまざまな長所があるのに、一人の女性に愛を集中することができないことが苦しかった。そしてまた返事を書いた。「袖が濡れると言っているのは、深い恋をしてくれない方への恨みで、「あさみにや人は下り立つわが方は身もそぼつまで深きこひぢを」「あさみ」は、「浅い場所」を指し、恋路(こいぢ、恋の道のり)の浅い場所で、まだ深くない恋の初期段階を示し、「人は下り立つ」は、誰かがその浅い恋の道のりに踏み入れるという意味になり、恋愛の始まりを暗示している。「私の方では、身体がそぼつまで」とは、涙や雨で衣が濡れるということで、恋のために苦しんでいることを意味し、「深きこひぢを」深く思い悩んでいる恋の道を表している。「あさみにや人は下り立つわが方は身もそぼつまで深きこひぢを」の意味は、語り手(恋する者)が、相手はまだ浅い恋の道に立っているだけだが、私の方はもう身も心も恋に深く染まってしまい、涙や苦悩で身が濡れるほどだという心境を表している。つまり、相手との恋の進み具合に差があり、語り手はすでに恋に深く悩んでいることを嘆いている。この表現は、源氏物語の繊細な恋愛感情の描写が特徴的な一場面の一つで、この返事を自分の口からではなく筆を借りて書くことがどれほど苦痛なことかと書いていた。葵の君の容体はますます悪化していた。六条の御息所の生霊であるとか、彼女の父であった故人の大臣の亡霊が憑いているという噂が聞こえてきた。御息所は自分の薄命を嘆く以外に、人を呪う気持ちはないが、物思いがつのれば魂が身体を離れていくということがあるなら、もしかするとその魂が源氏の正妻である葵の君の病床に現れて恨みを告げているのかもしれないと考えた。そんなふうに悟られることもあり、物思いに満ちた自分の生涯の中で、今回ほど苦しいと思ったことはなかった。御禊の日の屈辱感から生まれた恨みは、自分でも抑えきれないほど強いものになってしまった。御息所は、少しでも眠ると夢の中で美しい姫君の前に立ち、自分が乱暴にふるまい、武者ぶりついて撲ったりする夢を何度も見た。現実の自分にはそんな事ができる筈もないのに、夢の中では荒々しい力が働いた。
2024.10.18
コメント(26)
-

源氏物語〔9帖 葵 9〕
源氏物語〔9帖 葵 9〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。「袖が濡れる恋路と知りながら、それでも降り立つ田子のように辛い」「袖が濡れる恋路」とは、涙や感情のあふれから袖が濡れる、つまり辛い恋の道のりを意味し、恋愛が思い通りにならず、涙が流れるような状況を暗示している。「それでも降り立つ田子のように辛い」という部分は、古典的な「田子の浦」に関連する表現で、田子の浦の風景や自然の厳しさを象徴的に使っている。ここでは、困難が予測されているにもかかわらず、それに向かって進んでいくという強い意志や、避けられない運命に立ち向かう辛さを表現している。全体として、この表現表現は「辛い恋の道のりを知りながらも、それでもその恋愛に進んでいく苦しさ」を描いており、恋愛における感情の複雑さや、避けられない運命に対する切なさが込められている。「悔しくぞ汲みそめてける浅ければ袖のみ濡るる山の井の水」この和歌は、恋愛の切なさや未熟な感情を水にたとえて表現している。各部分を細かく見てみると、「悔しくぞ」は「悔しくて」という意味で、何かをしてしまったことを後悔している気持ちを表し、「汲みそめてける」は、「汲む」というのは水を汲むことで、ここでは「始めて汲んだ」という意味。つまり、恋の感情を初めて始めてしまったことを悔やんでいる。「浅ければ」は、比喩的に使われ、恋の深さがまだ浅いことを示している。そのため、感情がそこまで深くはなく、「袖のみ濡るる」、つまりは袖が少しだけ濡れる程度だということだ。ここでの「袖が濡れる」は涙を表すことが多く、深い恋であれば全身が水に浸かるような深い悲しみがある。深い恋に対し、浅い恋ではまだ涙が袖を少しだけ濡らす程度の悲しみだという意味になるのだろう。「山の井の水」とは山中にある井戸の水で、恋心や感情を象徴することが多い。この場合、井戸の水が浅いため、深い感情には至らず、袖が少し濡れる程度にしかならないというたとえで、全体の意味を考えると、「恋の始まりに対する悔いを感じているが、感情がまだ浅いため、袖が少し濡れる程度で深い悲しみには至らない」という内容だろう。恋がまだ十分に深まっていない未熟さを、水の浅さや袖が濡れる程度にたとえた美しい表現だろう。つまり、恋愛における浅さと未熟さを後悔している心情が込められている。幾人かの恋人の中でも特に字が美しいと源氏は思いながらも、理想通りにはいかないものだと思った。
2024.10.17
コメント(24)
-

源氏物語〔9帖 葵 8〕
源氏物語〔9帖 葵 8〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。葵の上は泣いてばかりおり、時折、胸がせき上がるように苦しんでいた。御所からも頻繁に見舞いの使いが訪れ、祈祷までも別に行わせていた。こんなに光栄な夫人に万一のことがあってはならないと、誰もが心配していた。世間全体が惜しんだり歎いたりしているこの噂も、御息所にとっては不快だった。それまでは決してこうではなかった。競争心を刺激したのは車争いという小さな出来事に過ぎなかったが、それが御息所にとってどれほど大きな恨みになっていたのか左大臣家の人々は想像もしていなかった。この部分では、六条御息所が源氏に対する複雑な感情と、葵の上が物の怪に苦しめられる様子が描かれています。また、源氏と葵の上の間には冷えた関係がある一方で、源氏が彼女を心から気遣う姿も強調されている。物思いはますます御息所の病を悪化させていた。斎宮を気にかけて、他の家へ行って修法などを行わせていた。源氏はそれを聞いて、どんな具合が悪いのかと気の毒に思い、彼女を訪ねた。自宅ではない人の家であったため、人目を避けて二人は会った。長く会いに来なかったことを申し訳なく思い、源氏はこまごまと説明していた。妻の病状を心配して話していた。「私はそれほど心配していないのですが、親たちが大変な騒ぎをしているので、気の毒で、少し容体が良くなるまでは謹慎を表したいと思っているだけなのです。あなたが心を広く持って見守ってくれたら、私は幸せです」と語った。女は、いつもよりも弱々しく見えるのを、もっともなことだと思って源氏は同情していた。疑いや恨みが消えたわけではなく、源氏が朝帰りする美しい姿を見て、御息所は自分がこの人から離れられるはずがないと思った。正夫人としての立場があり、さらに子供が生まれるとなれば、他の女性への愛は冷めていき、今のように毎日待ち続けることは命を縮めることであろうと感じた。それでも源氏を思い続け、物思いが癒えない御息所に、次の日はただ手紙だけが届いた。この間、少し癒えていた病人が、また急に悪くなり、苦しんでいるので、出られないと書かれていた。それを見て、御息所は例の上手な言い訳だと思いながらも返事を書いた。「袖が濡れる恋路と知りながら、それでも降り立つ田子のように辛い」古い歌に「悔しくぞ汲みそめてける浅ければ袖のみ濡るる山の井の水」とあるように、と返事を送った。
2024.10.16
コメント(27)
-

源氏物語〔9帖 葵 7〕
源氏物語〔9帖 葵 7〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。御息所は捨てられた女と世間に見られたくないという世間体も気になった。しかし、安心して京に留まることもできなかった。車争いの日に全く無視された記憶がある限り、心の平静を保つことができなかった。自身の心を定めることができず、寝ても覚めても煩悶し続けるせいか、次第に心が身体から離れていくように感じ、空虚な感覚に苛まれ、病気のようになっていた。源氏は最初から伊勢へ行くことに断然反対するわけでもなく、「私のようなつまらない男を愛してくださったあなたが、私を嫌になり、遠くへ行ってしまうのはもっともなことですが、寛大な心を持って変わらぬ愛情を続けていただき、前世の因縁を全うしたいと私は願っています」と言って彼女を引き留めようとしていた。だが、そんな思いを慰めようと出かけた御禊の川で、不幸な出来事を目にすることになる。葵の上は物の怪に取り憑かれたような状態で非常に苦しんでいた。両親が心配していたので、源氏も他所へ行くことを遠慮せざるを得ず、二条の院などにもほんの時々帰るだけであった。夫婦仲は親密ではなかったが、源氏は妻として葵の上を他のどの女性よりも尊重しており、彼女が妊娠して苦しんでいるため、憐みの情も強く、修法や祈祷も左大臣家だけでなく、さまざまな場所で行わせていた。物の怪や生霊といったものがたくさん現れ、いろいろな名乗りをする者もいたが、どれも葵の上に移ることはなく、病む彼女にじっと取り憑いたままで、激しく悩ませるわけでもなく、片時も離れない物の怪が一つあった。どんな修験僧の技術でも自由にすることができないほどの執念があるもので、これはただの物の怪ではないと誰もが思った。左大臣家の人々は、源氏の愛人の中で誰かが葵の上を恨んでいるのではないかと考え、六条御息所や二条の院の女など、源氏に愛されている女性たちを疑った。しかし、物の怪に言わせた言葉からその主を知ろうとしても、何の手がかりも得ることはできなかった。物の怪が、姫君を育てた乳母のような者や、代々この家に敵対してきた亡霊などが葵の上に取り憑いたのではないとわかった。葵の上は泣いてばかりおり、時折、胸がせき上がるように苦しんでいた。どうなるのか、誰もが不安でならなかった。
2024.10.15
コメント(24)
-

源氏物語〔9帖 葵 6〕
源氏物語〔9帖 葵 6〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。源氏は車を進めるでもなく、停めるでもなく、躊躇している時に、満員の女車から扇を出して源氏の従者を呼ぶ者があった。「こちらへおいでになりませんか。この場所をお譲りしてもよろしいですよ」という挨拶である。どこの風流な女がそんなことをしているのだろうと思いながらも、そこは実際に良い場所だったため、源氏はその車のそばに車を並べて停めさせた。「どうしてこんなに良い場所を取ったのか、羨ましく思っていました」と言うと、品の良い扇の端を折り、それに書いて差し出してきた。「はかなしや人のかざせるあふひ故神のしるしの今日を待ちける」と書かれていた。注連縄を張っているのだから。源氏はこれが源典侍の字だとすぐに思い出した。どこまで若返ろうとするのかと醜く思った源氏は、皮肉を込めて「かざしける心ぞ仇に思ほゆる八十氏人になべてあふひを」と書いてやると、恥ずかしそうにまた歌が来た。「くやしくも挿しけるかな名のみして人だのめなる草葉ばかりを」と書かれていた。その日、源氏が女の同乗者を伴い、簾さえ上げずに町へ出ていることを妬ましく思う人が多かった。御禊の日には端麗だった源氏も、今日はくつろいだ雰囲気で物見車に乗っているのだから、並んで乗っている女も普通の者ではないだろうと皆が思い巡らしていた。源典侍のような者では、競争者として名乗りを上げられても問題にはならないだろうと思っていた。源氏は少し物足りなさを感じたが、それでも愛人がいるということで晴れがましい気持ちになり、源典侍のような厚かましい老女でも、さすがに困らせるような戯言をあまり言い出すことはできなかった。源氏が祭りの見物に出かける際の様子を描き、源氏の優雅で洗練された振る舞いと、それに対する周囲の女性たちの反応、特に源典侍との皮肉の応酬がおもしろい。御息所の煩悶は、これまでの数年間の物思いとは比較にならないほどのものになっていた。源氏に対して完全に信頼できるほどの愛情を持たないと決めつけながらも、断然別れて斎宮に従い伊勢へ行くというのは心細いことに思われ、捨てられた女と世間に見られたくないという世間体も気になった。
2024.10.14
コメント(20)
-

源氏物語〔9帖 葵 5〕
源氏物語〔9帖 葵 5〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。「女王さんの髪は私が切ってあげよう」と言った源氏も、「あまりたくさんいるから困るね。大人になったら、いったいどんな髪になるのだろう」と困っていた。「長い髪の人でも、前の髪は少し短いものだけど、あまりに揃いすぎるのもかえって良くないかもしれない」とも言いながら、源氏の仕事は終わった。「千尋」と言った。これは髪そぎの祝いの言葉であり、「千尋(ちひろ)」という言葉が使われている。これは髪の長さを表す表現で、千尋とは非常に長い髪のことを意味している。平安時代の貴族女性は、髪を長く伸ばすことが美徳とされ、特に高貴な身分の女性は非常に長い髪を持っていた。髪そぎは、通常結婚や出家など重要な節目で行われる儀式の一部である。したがって、「千尋」の言葉は、葵の巻での髪そぎの祝いにおいて、長く伸びた髪がもたらす美しさや吉兆を讃え、さらにその髪が末永く幸せに続くようにという願いを表すものと解釈できる。少納言は感激して、源氏が「はかりなき千尋の底の海松房の生ひ行く末はわれのみぞ見ん//海の底に生えている海松房(海藻)が成長し続けるように、未来や愛情がどう発展していくのか、その行く末を見届けるのは自分だけだという気持ちを詠んでいる。深くて計り知れない未来や感情の動き、そしてその成長を自分が一人で見守るという覚悟が込められている」と告げた時、女王は「千尋ともいかでか知らん定めなく満ち干る潮ののどけからぬに//深さが計り知れない「千尋の海」のように、変わりやすく不安定な状況に対して心が穏やかでない様子を詠んでいる。「千尋の海」の深さや潮の満ち引きが一定しないことを、人生や感情の不確実性に重ねている。つまり、「その深さがどれほどか知ることはできないが、一定しない潮のように、状況は変わりやすく心穏やかではいられない」といった意味を持ち、未来への不安や人間関係の複雑さ、特に愛情や心情の不安定さを象徴している」と書いていた。貴女らしく、しかも若々しく美しい人に、源氏は満足を感じていた。その日も町には車が隙間なく出ていた。馬場殿のあたりで祭りの行列を見ようとしたが、都合の良い場所が見つからなかった。「大官連がこの辺りにたくさん来ていて、面倒なところだ」と源氏は言い、車を進めるでもなく、停めるでもなく、躊躇している時に、満員の女車から扇を出して源氏の従者を呼ぶ者があった。
2024.10.13
コメント(25)
-

源氏物語〔9帖 葵 4〕
源氏物語〔9帖 葵 4〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。式部卿の宮は桟敷で見物していたが、源氏の美しさを見て、自分の娘の朝顔の姫君が求愛を受けていることを思い、娘も源氏に対して並々ならぬ誠実さを感じているのだと改めて感心した。しかし、それは結婚を考えるほどの気持ちではなかった。宮の若い女房たちは源氏を褒め称え、翌日の加茂祭の日には左大臣家の人々は見物に出なかった。京都の賀茂祭(葵祭)での「御禊(みそぎ)」の日に、貴族たちが観覧のために自分の牛車を並べ、よい場所をめぐって争いが起こった。有名なのは、光源氏の正妻である葵の上と、彼の愛人六条御息所の車争いで、六条御息所の牛車が、葵の上の牛車に押されて移動させられてしまう場面が描かれており、このことで六条御息所は屈辱を感じ、その後、彼女の嫉妬や恨みが「生霊(いきりょう)」となって葵の上に影響を及ぼすことになる。この車争いの場面は、単なる物理的な争い以上に、女性たちの社会的地位や嫉妬、感情の葛藤が表れた象徴的な場面で、源氏は、御禊の日の車争いについて聞き、御息所に同情し、葵夫人の態度に満足できずにいた。夫人としての立場は十分にあるものの、その強い性格から情味に欠け、結果的に御息所を侮辱してしまったことを源氏は悔やみ、すぐに御息所を訪ねた。しかし、斎宮がまだ邸にいたため、神への配慮を理由に会うことはできなかった。源氏は、御息所と自分の心の行き違いを嘆き、なぜお互いにもっと柔軟な心を持てなかったのだろうかと思い悩んだ。源氏が御息所に対して抱く同情や後悔の念、そして葵夫人との間にある複雑な感情が描かれている。祭りの日に源氏は左大臣家へは行かず、二条の院にいた。そして源氏は、町に出て見物しようという気持ちになっていた。西の対に行き、惟光に車の準備を命じた。女たちも見物に出かけるのですかと言いながら、源氏は美しく装った紫の姫君を笑顔で見つめていた。「あなたはぜひお出かけなさい。私が一緒に連れて行きましょうね」と言って、平生よりも美しく見える少女の髪を手で撫でながら、「ずいぶん長い間、髪を切っていないね。今日は髪をそぐのに良い日だろう」と言って、陰陽道の調べ役を呼んで良い時間を聞いたりしながら、「女房たちは先に出かけるといい」と言った。そして、きれいに装った童女たちの姿を点検したが、少女らしく可愛らしくそろえられた髪の裾が、華やかな紋織の袴にかかっているのが特に目を引いた。
2024.10.12
コメント(24)
-

源氏物語〔9帖 葵 3〕
源氏物語〔9帖 葵 3〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。御息所は見物をやめて帰ろうとしたが、車が混み合っていて出ることができなかった。行列が見えてきたという声が上がり、御息所は恋しい人(源氏)の姿を待つ気持ちを抑えられなかった。源氏は御息所が来ていることに気づかず、振り返ることもなかった。御息所は自分が無視されていることを感じ、さらに傷ついた。行列を見て、源氏の従者たちが左大臣家の車には敬意を表して通ったことも、御息所には侮辱と感じられた。「影をのみみたらし川のつれなさに身のうきほどぞいとど知らるる//自分の影だけが映るみたらし川の冷たさを無情に感じ、それによって自分が抱えている苦しさや孤独感が一層強く感じられる」「影をのみ」という表現は、川に自分の姿が映ることを指し、「みたらし川のつれなさ」は、川の冷たさや無情さが、心のつらさや孤独感に重ね合わされている。御息所は、涙がこぼれるのを同じ車に乗っている人々に見られるのを恥ずかしく思いながらも、源氏が馬上でいつもよりもさらに美しく見えたことを見ずに済んだならよかったという思いもあった。行列に参加している人々はみなそれぞれの身分に応じて美しい装いをしていたが、高官の中でも源氏ほど見栄えのする者はいなかった。大将の臨時の随身を近衛の尉が務めるのは珍しく、何か特別な行事の際にのみ許されるものであったが、今日は蔵人を兼ねた右近衛の尉が源氏に従っていた。その他の随身たちも、容姿ともに優れた者が選ばれていて、源氏が世の中で重んじられていることは、こうした時にも明らかであった。この世で源氏に惹かれない者などいなかった。髪の上から上着をまとった、身分の高い女性や尼なども、群衆の中に倒れかかるようになって見物していた。普段は尼がこのような場にいると、俗世を捨てた者がそんなことをしているのは醜いと思われるのだが、今日は源氏を見ようとしているのだから仕方がないと皆が同情した。背中を髪で膨らませた卑しい女たちや、労働者階級の者までもが、手を額に当てて源氏を仰ぎ見て、喜んでいた。また、源氏の注意を引くこともない地方官の娘なども、精一杯の装いをして牛車に乗り、気取って見物していた。こうして一条の大路は人で溢れていた。源氏の情人たちは、恋人の美しさを目の前にして、自分の価値を反省させられる気持ちになった。
2024.10.11
コメント(24)
-

源氏物語〔9帖 葵 2〕
源氏物語〔9帖 葵 2〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。斎宮も姪ではなく、自分の娘のように思っているから、どちらの立場から見ても御息所を大切にすべきだと情熱的な心で熱くなったり冷めたりするのは、世間から批判されるだろうと源氏に注意を促した。源氏自身もそれは尤もだと思い、ただ恐縮するばかりであった。院の忠告を受け入れながらも、中宮への恋心が万が一耳に入ったらどうしようと恐れ、慎みながら院を退出した。院までもが御息所との関係を認めて注意してくるほどになっているため、御息所の名誉のためにも、自分の名誉のためにも軽率な行動は取れないと思い、以前よりも一層彼女を尊重するようになったが、それでも源氏は彼女を公然と妻として扱うことはしなかった。御息所も年長であることを気にして、無理に正妻の立場を求めることはなかった。源氏はそのことに甘んじている様子であったが、院もそれを知っており、世間でも知らない者はおらず、それにもかかわらず源氏が誠意を見せないことに御息所は深く恨んでいた。この噂が世間に広まると、式部卿宮の朝顔の姫君は、源氏の甘い言葉に惑わされて後悔することになる愚かさを学ぶまいと心に決め、時折短い返事を書くことも以前はあったが、今ではほとんど返事をしなくなった。しかし、露骨に反感を示したり、軽蔑的な態度を取ったりすることがなかったため、源氏はその点を喜んでいた。こうした態度ゆえに、源氏は彼女を長年にわたって忘れられない、愛しい存在だと思っていた。一方で、左大臣家にいる葵の上(この人物が中心となって描かれた帖隠そうともしない源氏に対して、恨みを言っても仕方がないと思っていた。彼女は妊娠していて体調が悪く、心細い気持ちになっていた。源氏は、自分の子の母となろうとする葵の上に対して、新たな愛情を感じ始めていた。そして、これを喜ぶ一方で、葵の上の両親ともに不安を感じており、妊婦の無事を祈るために神仏へ祈りを捧げていた。このような状況の中で、源氏も心に余裕がなく、愛しているにもかかわらず、訪れることができない恋人の家が多かったと思われる。その頃、前代の加茂の斎院が退き、皇太后の娘である女三の宮が新しい斎院に選ばれた。
2024.10.10
コメント(27)
-

源氏物語〔9帖 葵 1〕
源氏物語〔9帖 葵 1〕「Dog photography and Essay」では、「愛犬もも」と「源氏物語9帖 葵(あおい) の研鑽」を公開してます。「葵(あおい)」の文面を読んでいく内に「葵(あおい)」と「葵の上」は、全く別物であると気付く。「葵の上」は光源氏の正妻であり、「葵の巻」に登場する主要な人物で「葵の上」として知られている。「葵の上」は貴族の高貴な家柄の女性で、光源氏との関係に苦しむ場面が描かれている。特に「葵の上」と「六条御息所」との霊的な対立が「葵の巻」でクライマックスを迎えている。「葵」という単語自体を検索しても「葵」は植物の名前でもあり、葵の上という人物とは区別される。源氏物語の中では植物や自然が象徴的に使われることが多く、葵は特定の人物ではなく、植物としての象徴性を持っている。そのため、物語の中で「葵の上」と呼ばれる人物と、「葵」という植物やその象徴性は異なるものということが理解できた。本文に入りたい。天皇が新しく即位し、時代の雰囲気が変わってから、源氏は何に対しても関心が持てなくなっていた。官位が上がったことで生活が窮屈になり、自由に動くこともできなくなっていた。そして、あちらこちらに待ちわびている恋人たちを苦しませる結果になっていた。そうした不満の報いなのか、源氏自身は中宮からの冷淡さに嘆き、涙を流してばかりいた。位を退いた院(前天皇)と中宮は、まるで普通の夫婦のように暮らしていたが、前の弘徽殿(こきでん/皇后・中宮・女御などの住居)の女御であった新しい皇太后は嫉妬しているようで、院へには行かず、当時の天皇の御所にしか行かなかった。そのため、競争相手もおらず、中宮は気楽に見えた。時々、派手な音楽会を開いて、その様子は世間でも評判になり、院の生活は非常に幸福そうであった。ただ唯一、恋しく思っていたのは、内裏にいる東宮(皇太子)だけであり、東宮に後見役がいないことを心配して、源氏にその役目を任せた。源氏は自分の立場に悩みながらも、その任命をうれしく思った。六条御息所が産んだ前皇太子の忘れ形見の女王が斎宮に選ばれた。源氏の愛が不安定だと感じていた御息所は、若い斎宮に託して、自分も伊勢へ下ろうかとその時から思っていた。この噂を院が聞きつけ、私の弟である東宮が非常に愛していた人を、お前が冷たく扱うのを見ると、私はとても悲しく思っていた。
2024.10.09
コメント(25)
全4937件 (4937件中 1-50件目)