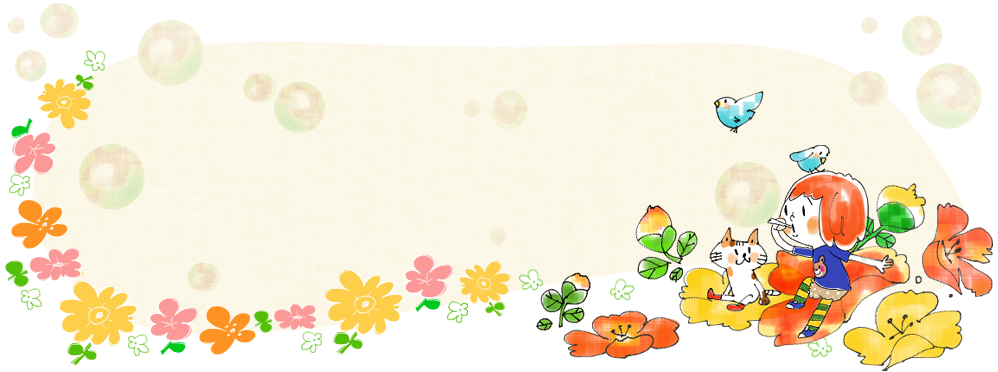5月18日(土)
近藤芳美「土屋文明」より(72)
岩波書店近藤芳美集第七巻「土屋文明 … 鑑賞篇」よりの転載です。
第八歌集『山下水(やましたみず)』より(3)
この者もかく言ふ術(すべ)を知れりしか憤るにあらず蔑(さげすむ)むにあらず
(昭和二十一年)
この男も、このような物言いをする事を知っていたのか。それを今の自分は憤るのでもなく、またさげすもうとするのでもない。
敗戦の虚脱の中からデモクラシーの声が湧き起こって行く。赤旗にかこまれて、徳田球一らの共産主義者らが釈放され刑務所の鉄門を出る。新しい時代が始まろうとする。だが、その時代の中に、昨日までファシズムをたたえ、民衆を叱咤しつづけていたものが、いちはやく口をぬぐったような物言いを始め出す。
恬然として彼らは自由を説き、亡国の苦渋にうなだれるものを眼下に見下す。この国の学者たち、指導者たちである。それをつめたい目で歌い、片隅の一人の憤怒に堪えている。二十一年のはじめの歌。その前に文明は戦争中の首相近衛文麿の自殺の事を歌っている。激しい変転をつづけて行く歴史の中で、彼は老リベラリストとしての自分の姿勢を守りつづけている。
走井に小石を並べ流れ道を移すことなども一日(いちにち)のうち
(昭和二十一年)
走井は山の泉の流れなのだろう。その清らかな水に小石を並べ、流れ道を変えようと作者はひとりうずくまって働いている。はかない、孤独な一日の労働である。そういう気持の歌われた作品なのであろう。語り合うものとていない、流離の老歌人の感慨が独語のように呟かれている。
「霜いくらか少なき朝目に見えて増さるる泉よ春待ち得たり」「尾長一群去りたる後に起きいでて昨日より温かしと思ふ楽しも」「こひねがひ向へば今朝は緑ある土に靄のごとく降る雨」「枯草の中の一こゑを蛙かと思ふ午すぎ出でつつ採めり」などの歌がある。山深い疎開地にもおそい春の来ようとする季節である事が知られる。「春待ち得たり」ということばにも、敗戦の年の苦しい冬をようやくに生き得た思いが深くこめられているのであろう。その実感の背後にある作品である。
(つづく)
-
近藤芳美『短歌と人生」語録』 (28)… 2024.06.20
-
歌集「未知の時間」(前田鐵江第一歌集)… 2024.06.20
-
近藤芳美「土屋文明:土屋文明論」より 2024.06.20