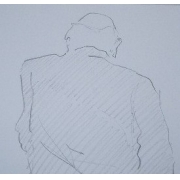テーマ: ★つ・ぶ・や・き★(541407)
カテゴリ: エッセイ
敬老の日が近づいた。
我が地区の長寿会ではこの日に古希、喜寿、傘寿、米寿などの会員にお祝い金を贈ることになっている。先日、今年の該当者の名簿が会長から届いた。該当者は15名。名簿の欄外に「数え年による」と添え書きがあった。
そうか、「数え年ねえ……」、不思議なものに出会った気分である。なんとなく気になるので、制度上はどうなっているのかを、ウィキペディアで調べた。
◆1873年(明治6年)2月5日の「太政官布告第36号(年齡計算方ヲ定ム)」で「幾年幾月と数える」という表現で満年齢による年齢計算が規定された。
というから満年齢の始まりは150年も前のことになる。ただしこの布告では、満年齢を原則としながらも旧暦では数え年を使用するという、双方を併用するような表現になっていた。続いて29年後
◆1902年12月22日施行の「年齢計算ニ関スル法律(明治35年12月2日 法律第50号)」で明治6年太政官布告第36号が廃止され、「出生日を起算日として民法に定める期間計算で年齢を計算する」と規定された。これは結果的に満年齢での年齢計算を規定していることになる。
1873年の規定では双方の併用が認められていたのを、ここで初めて満年齢を使うように定められたのだ。それでも一般の市民生活では法的制度を無視する形で数え年が使われ続けた。それから更に73年
◆1950年1月1日施行の「年齢のとなえ方に関する法律(昭和24年5月24日 法律第96号)」により、国民には満年齢によって年齢を表すことを改めて推奨し、国・地方公共団体の機関に対しては満年齢の使用を義務付け、数え年を用いる場合は明示することを義務付けた。
現在では満年齢が定着したとはいえ、厄年とか七五三、あるいは先述の古希などの昔からの祝い事では、数え年が生き残っている。ここまでの経緯を見ても、数え年から満年齢への切り替えがいかに難しいかがよくわかる。
人はもともと保守的なのであろう。だから現状を変えることに強い抵抗感を持つ。それは身の回りの多くの事例でいやというほど体験済みである。「昔からやってることだから」と言われると、議論の余地がない。
我が日常は合理主義中心、数え年とか和暦には全く無縁である。また前例を変えることにもそれほど抵抗感はない。むしろ積極的である。
そんな私は当然、神仏やその信心にも無関心である。なのに毎朝、神棚の榊と仏花の水替えをやっている、世の中、合理主義だけでは済まないらしい。(2023年8月)
*
エッセイサークルの例会
上記は本日提出作品です
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[エッセイ] カテゴリの最新記事
-
今月のエッセイ『親子で滝巡り』 2024/05/22 コメント(3)
-
今月のエッセイ「孫の結婚式」 2024/04/24 コメント(5)
-
今月のエッセイ「三月の花」 2024/03/27 コメント(6)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
© Rakuten Group, Inc.