PR
X
Free Space
免責事項 : 当ブログは私が少しでも成長し、「より良い投資家」 になるための私的な勉強の場として運営しています。記事内容は一般的に入手可能な公開情報に基づいて作成していますが、同時に諸々のバイアスのかかったあくまでも個人的な見解であり、特定銘柄の売買の推奨を目的としたものでは全くありません。また市場の未来がどうなるかは誰にも分からないため記事内容の正確性は保証しません。そのため当ブログの記事に基づいて投資を行い損失が発生した場合にも当方は一切の責任を負いません。投資はくれぐれも100%ご自身の判断と責任の元で行って頂きます様、伏してお願い申し上げます。
Calendar
G-7ホールディング…
 New!
征野三朗さん
New!
征野三朗さん
メモ2 New! 4畳半2間さん
米は「世界中の国を… New! Condor3333さん
【人気】スポンサー… New!
わくわく303さん
New!
わくわく303さん
ワインの五段階 New!
slowlysheepさん
New!
slowlysheepさん
6/16(日)メンテナ… 楽天ブログスタッフさん
5月末運用成績&PF mk4274さん
運用成績・ポートフ… lodestar2006さん
lodestar2006さん
【5月運用成績】+11… かぶ1000さん
2024年5月のパフォー… らすかる0555さん
 New!
征野三朗さん
New!
征野三朗さんメモ2 New! 4畳半2間さん
米は「世界中の国を… New! Condor3333さん
【人気】スポンサー…
 New!
わくわく303さん
New!
わくわく303さんワインの五段階
 New!
slowlysheepさん
New!
slowlysheepさん6/16(日)メンテナ… 楽天ブログスタッフさん
5月末運用成績&PF mk4274さん
運用成績・ポートフ…
 lodestar2006さん
lodestar2006さん【5月運用成績】+11… かぶ1000さん
2024年5月のパフォー… らすかる0555さん
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 株式投資全般
ロシアによるウクライナへの本格的な軍事侵攻が始まりました。この記事を書いている2022年2月25日現在、ロシア軍はウクライナの首都キエフに既に到達しているという情報もあり、今後どうなっていくのか全く分からない状況です。
そして、「なんだ、このくらいで済むのか、じゃあ、ウチらも遠慮なく台湾と日本をやっちゃおう。核を持ってないからちょろいし。」と中国は間違いなく思うでしょうし、我々日本人にとっても全く他人事では無いと思います。そのため個人的には今回のロシアの行動は「第3次世界大戦」の引き金になる可能性もあるのではないか?とも感じています。
さて、投資家としては「大きな戦争が起こると株式市場にどういう影響があるのか?」について、ここで改めて学びなおす必要があると考えています。。。。
、、、ということで、今日は株式投資本オールタイムベスト116位
アノマリー投資(ジェフリー・A・ハーシュ著、パンローリング 2013年)
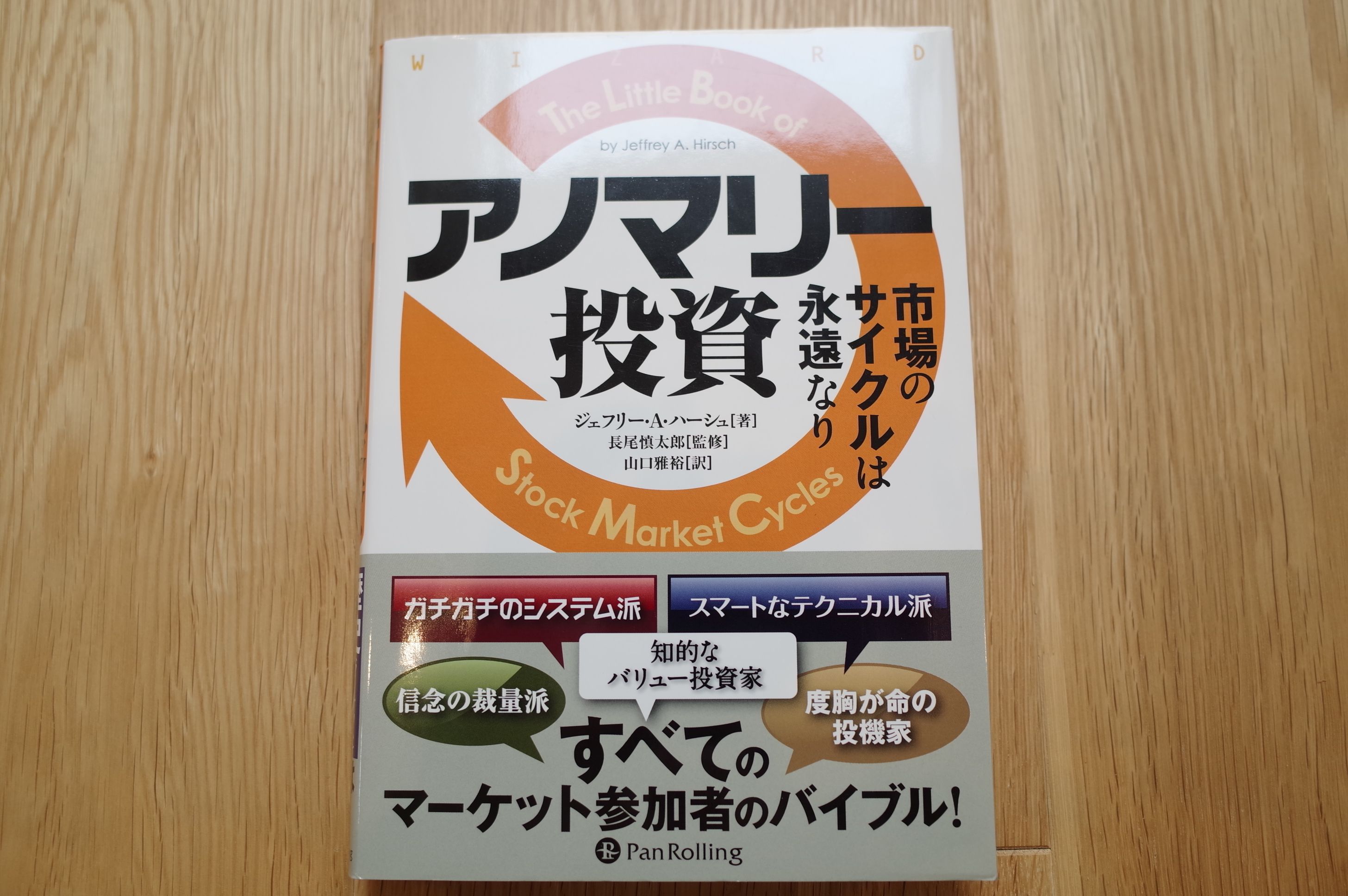
のまさかの第9弾です。
今日は、素晴らしい出来である 第2章 戦争と平和 から。


確かに今のロシアの指導者であるプーチン大統領が国内経済に焦点を当てているとはとても思えません。経済合理性からすれば、致命的な経済制裁を受けることになるウクライナへの全面侵攻に利があるとはとても考えられないですからね。


うーん、ロシアが世界平和を大きく揺るがしている今、本当に勉強になる言葉がならんでいますね。続きを見ていきましょう。


図2.1 インフレ後に続く500%以上の上昇

うぉお、この図は滅茶苦茶勉強になります。しっかりと目に焼き付けたいですね。

つまり、大きな戦争はインフレを引き起こし、「インフレに追随する」特質を持っている株式市場は自動追尾して同じく上昇するということですね。
今回のロシアによるウクライナ侵攻でも早速、原油や小麦などの商品価格が急騰しています。これらは間違いなくインフレに直結するでしょう。果たして世界はまたもや「ハーシュの予言」通りに動くことになるのでしょうか?
そして、「なんだ、このくらいで済むのか、じゃあ、ウチらも遠慮なく台湾と日本をやっちゃおう。核を持ってないからちょろいし。」と中国は間違いなく思うでしょうし、我々日本人にとっても全く他人事では無いと思います。そのため個人的には今回のロシアの行動は「第3次世界大戦」の引き金になる可能性もあるのではないか?とも感じています。
さて、投資家としては「大きな戦争が起こると株式市場にどういう影響があるのか?」について、ここで改めて学びなおす必要があると考えています。。。。
、、、ということで、今日は株式投資本オールタイムベスト116位
アノマリー投資(ジェフリー・A・ハーシュ著、パンローリング 2013年)
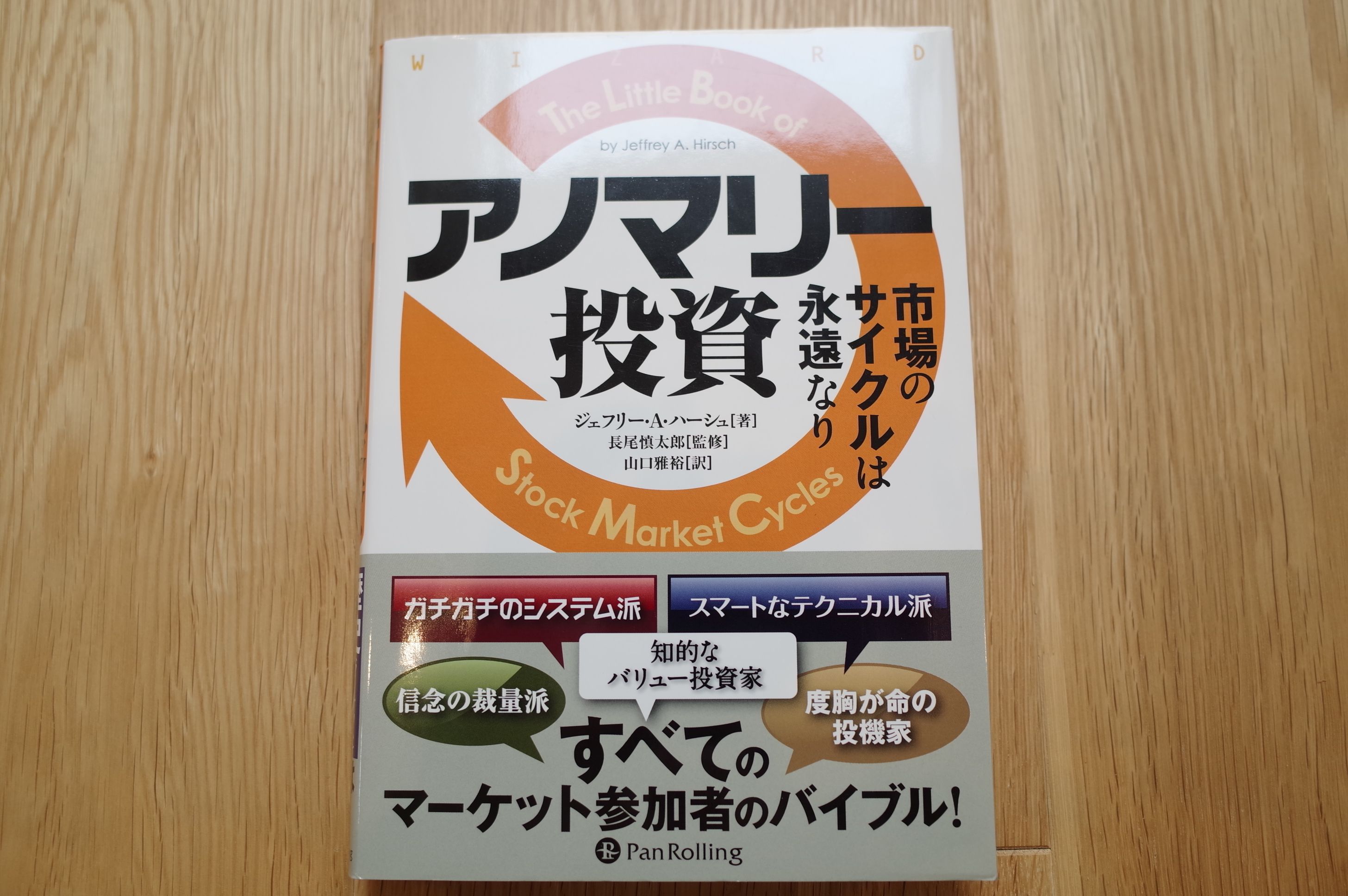
のまさかの第9弾です。
今日は、素晴らしい出来である 第2章 戦争と平和 から。

株式市場で唯一、最も永続的な影響を及ぼすものは、間違いなく戦争である。
戦争と平和やインフレの影響は、過去2世紀の間、活況と低迷の循環を生み出す原動力だった。戦時にはレンジ相場を生み、平時には相場を上げる要素は何だろうか?
答えは、インフレだ。政府は戦争中に国庫を空にする。また、国内の心配事や経済よりも、外国や戦争にかかわる問題に焦点を合わせる。結果として物価の持続的上昇、すなわちインフレが起きる。
経済が落ち着きを取り戻して、政府が国内問題に再び焦点を合わせたときに、初めて株式市場は新高値まで急上昇するのだ。

確かに今のロシアの指導者であるプーチン大統領が国内経済に焦点を当てているとはとても思えません。経済合理性からすれば、致命的な経済制裁を受けることになるウクライナへの全面侵攻に利があるとはとても考えられないですからね。
戦争ーそれは何の役に立つのか?
アメリカが戦争にかかわっているときに、ダウ平均が高値を維持したことは1回もなかった。相場が大きく上放れしないのは、投資家の熱意が高まらないせいだと考えられる。

相場は良いニュースが続けば上昇するし、悪いニュースが続けば下落する。また、戦争初期のほうが反応しやすい。長い戦闘が終わるころには、投資家はニュースに反応しなくなるようになる。また、相場は戦争の終わりを予測して、高値を付ける。

うーん、ロシアが世界平和を大きく揺るがしている今、本当に勉強になる言葉がならんでいますね。続きを見ていきましょう。
図2.1は大局を示している。このグラフはダウ平均とCPI(消費者物価指数)を示したもので、第1次世界大戦、第2次世界大戦、ベトナム戦争を含み長期のレンジ相場の時期にはアミを掛けている。長期の素晴らしい好況と強気相場はカッコでくくり、ダウ平均のパフォーマンスを表示している。
戦争とインフレとその後の相場の追い上げには無視できない相関関係がある。戦時を含むボックス圏はどれも、おおよそ同じ比率のレンジ幅である。これらは500%の上昇への発射台に見える。インフレと相場の追い上げには明らかに相関関係がある。
第1次世界大戦時のインフレ(110%の上昇)に続く1920年代には、株価が504%上昇した。第2次世界大戦時のインフレ(74%の上昇)は、その後のダウ平均の523%の上昇に先行していた。最後に、ベトナム戦争と、石油禁輸と1970年代の悪名高いスタグフレーションによる200%以上のインフレとそれ以降の超大型の強気相場は、すべての投資家への警告であると同時に、希望を思い起こさせる。


図2.1 インフレ後に続く500%以上の上昇

うぉお、この図は滅茶苦茶勉強になります。しっかりと目に焼き付けたいですね。
まとめ
戦争が続く間、相場は一定レンジにとらえられて、新高値も維持できない。戦争が終わってインフレが安定するとき、平和と技術革新をきっかけに景気が上向く。相場はインフレを追いかけて、500%以上も急上昇することがよくある。

つまり、大きな戦争はインフレを引き起こし、「インフレに追随する」特質を持っている株式市場は自動追尾して同じく上昇するということですね。
今回のロシアによるウクライナ侵攻でも早速、原油や小麦などの商品価格が急騰しています。これらは間違いなくインフレに直結するでしょう。果たして世界はまたもや「ハーシュの予言」通りに動くことになるのでしょうか?
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Feb 25, 2022 10:43:35 PM
[株式投資全般] カテゴリの最新記事
-
2024年6月の抱負。 Jun 1, 2024
-
2024年5月のまとめ。 May 31, 2024
-
ついに。 May 19, 2024
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










