PR
X
カレンダー
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)読書案内「日本語・教育」
(21)週刊マンガ便「コミック」
(88)演劇「ナショナルシアターライブ」でお昼寝
(33)徘徊日記「日帰りでお出かけ」
(58)演劇「劇場」でお昼寝
(2)映画「元町映画館」でお昼寝
(98)映画「ちょっと遠くの映画館」でお昼寝
(14)映画「シネリーブル神戸」でお昼寝
(107)読書案内「映画館で出会った本」
(16)読書案内「翻訳小説・詩・他」
(49)読書案内「漱石・鴎外・露伴・龍之介・百閒・その他」
(19)徘徊日記「垂水・舞子・明石」あたり
(51)読書案内 「医者や科学者の仕事、まあ科学一般」
(25)読書案内「現代の作家」
(106)徘徊日記「お泊りでお出かけ」
(63)徘徊日記「神戸・元町・三宮」あたり
(84)読書案内「絵本・児童文学」=チビラ君たちへ
(46)読書案内「社会・歴史・哲学・思想」
(67)読書案内 「芸術:音楽・美術・写真・装幀 他」
(31)読書案内「近・現代詩歌」
(50)徘徊「港めぐり」
(4)バカ猫 百態
(21)読書案内「橋本治・加藤典洋・内田樹・高橋源一郎・他」
(17)読書案内「水俣・沖縄・アフガニスタン 石牟礼道子・渡辺京二・中村哲 他」
(20)読書案内「鶴見俊輔・黒川創・岡部伊都子・小田実 べ平連・思想の科学あたり」
(15)映画「OSミント・ハーバーランド」でお昼寝
(3)映画「こたつシネマ」でお昼寝
(14)映画「パルシネマ」でお昼寝
(41)読書案内「昭和の文学」
(23)読書案内「BookCoverChallenge」2020・05
(16)読書案内「くいしんぼう」
(9)映画「Cinema Kobe」でお昼寝
(6)週刊マンガ便「ちばてつや・ちばあきお」
(8)週刊マンガ便「石塚真一・浦沢直樹・ハロルド作石」
(33)週刊マンガ便「原泰久・鈴ノ木ユウ・野田サトル」
(32)ベランダだより
(131)徘徊日記 団地界隈
(108)徘徊日記 兵庫区・長田区あたり
(24)徘徊日記 須磨区あたり
(26)徘徊日記 西区・北区あたり
(8)徘徊日記 灘区・東灘区あたり
(37)徘徊日記 美術館・博物館・Etc
(4)週刊マンガ便「吉田秋生・高野文子・やまだ紫」
(7)徘徊日記 芦屋・西宮あたり
(7)読書案内「大江健三郎・井上ひさし・開高健 他」
(12)読書案内「古井由吉・後藤明生・他 内向の世代あたり」
(3)読書案内「谷川俊太郎・茨木のり子・大岡信 あたり」
(19)読書案内「啄木・白秋・晶子 あたり」
(4)読書案内「丸谷才一・和田誠・池澤夏樹」
(9)読書案内「吉本隆明・鮎川信夫・黒田三郎・荒地あたり」
(13)週刊マンガ便 「松本大洋」・「山川直人」
(13)読書案内「リービ英雄・多和田葉子・カズオイシグロ」国境を越えて
(5)読書案内「村上春樹・川上未映子」
(13)映画 パレスチナ・中東の監督
(6)読書案内「近代詩 賢治・中也・光太郎 あたり」
(7)映画 韓国の監督
(22)映画 香港・中国・台湾の監督
(35)映画 アニメーション
(13)映画 日本の監督 ア行・カ行・サ行 是枝・黒沢
(48)映画 日本の監督 タ行・ナ行・ハ行 鄭
(25)映画 日本の監督 マ行・ヤ行・ラ行・ワ行
(14)映画 イギリス・アイルランド・アイスランドの監督
(36)映画 イタリアの監督
(18)映画 ドイツ・ポーランド他の監督
(14)映画 ソビエト・ロシアの監督
(6)映画 アメリカの監督
(79)震災をめぐって 東北・神戸・原発
(5)読書案内「旅行・冒険」
(3)読書案内「本・読書・書評・図書館・古本屋」
(11)映画 オーストラリア・ニュージーランドの監督
(4)映画 フランスの監督
(42)映画 スペイン・ポルトガルの監督
(10)映画 カナダの監督
(3)映画 グルジア(ジョージア)の監督
(9)映画 ウクライナ・リトアニアの監督
(6)映画 イスラエルの監督
(3)映画 マケドニア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、クロアチア、スロベニアの監督
(3)映画 オランダ・デンマーク・ベルギーの監督
(7)映画 フィンランド・スウェーデン・ノルウェイの監督
(5)映画 トルコ・イランの映画監督
(8)映画 ギリシアの監督
(2)映画 アルゼンチン・ブラジル・ペルーの監督
(2)映画 ハンガリーの監督
(4)映画 セネガルの監督
(1)映画 スイス・オーストリアの監督
(3)読書案内 戯曲 シナリオ 劇作家
(1)読書案内 ジブリの本とマンガ
(5) ジョージ・ミラー「マッドマックス フュリオサ」109ハットno44
ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」
佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247
週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)
佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246
週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)
週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)
徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり
徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」
週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)
ベランダだより 2024年6月5日(水) 「( ̄∇ ̄;)ハッハッハ、古稀だそうです!」
佐藤真「まひるのほし」シネリーブル神戸no247
週刊 読書案内 養老孟司×名越康文「二ホンという病」(日刊現代・講談社)
佐藤真「エドワード・サイード OUT OF PLACE」シネリーブル神戸no246
週刊 読書案内 吉本隆明「ちひさな群への挨拶」(思潮社)
週刊 読書案内 吉本隆明「廃人の歌」(「吉本隆明全詩集」思潮社)
徘徊日記 2024年5月30日(木)「三日で出所(笑)!」舞子あたり
徘徊日記 2024年5月29日(水)「目覚めたら、目の前に明石大橋!」
週刊 読書案内 岡田暁生「音楽の聴き方」(中公新書)
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ: 読書案内「現代の作家」
100days100bookcovers no70
色川武大「狂人日記」(福武文庫・講談社文芸文庫) 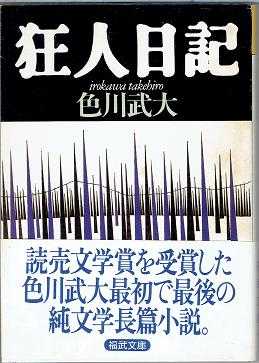 KOBAYASI君
の 星野博美『のりたまと煙突』
から、 「内省」
をバトンにして、 DEGUTIさん
が差し出してくれたのは 庄野潤三
の 『夕べの雲』
でした。
KOBAYASI君
の 星野博美『のりたまと煙突』
から、 「内省」
をバトンにして、 DEGUTIさん
が差し出してくれたのは 庄野潤三
の 『夕べの雲』
でした。
作品名を見ながら、ふと、浮かんできたのは
ぼくがこの作家の名前に出会ったのは高3の時でした。私淑していた世界史の先生の下宿の棚から借り出した 江藤淳 の 「成熟と喪失」 (今では 講談社文芸文庫 、当時は、たぶん、 河出書房 の単行本)という 「第三の新人」 を論じた評論の中でのことです。変なことを詳しく覚えているようですが、今思えばそれがぼくの 「文学オタク」 の始まりだったからなのかもしれませんね。
「オタク少年」 は、翌年の一年間、午前中しか学校がない浪人生活をいいことに、 「成熟と喪失」 で論じられた作家たちを読みふけったわけですが、その中で、その後も読み続けたのが、 遠藤周作 や 吉行淳之介 ではなくて、 庄野潤三 と 安岡章太郎 、そして 小島信夫 だったというところに、まあ、 「性根」の好み があらわれているようでおもしろいですね。
庄野潤三 が 『プールサイド小景』 で芥川賞を取ったのが 1955年 で、ぼくが生まれた翌年です。昭和30年。以後、一年間だったかのアメリカ留学の生活をつづった 『ガンビア滞在記』 、初期の代表作とも言うべき、釣りをする父と息子の話を書いた 『静物』 、で、 『夕べの雲』 が 1965年 です。
作風は、 DEGUTIさん のおっしゃるように 「平和な家庭の風景」 の 「おだやか」 で 「ユーモラス」 な描写ということなのですが、うまく言えませんが、どこかに 「喪われたもの」 と 「壊れそうなもの」 の 「不安定」 を感じさせるところのある 「おだやかさ」 に惹かれたのでしょうね。たとえば、 DEGUTIさん が引いていらっしゃる、こんな描写がぼくは好きです。
なんだ、それなら、さっさとそっちに行けばいいじゃないかと言われそうですが、 庄野潤三 は読み直したい人でもあって、語りたかったのでしょうね。
『夕べの雲』 が 読売文学賞 を取ったのは 1966年 ですが、23年後、 1989年 の受賞作が 色川武大「狂人日記」(福武文庫、今は講談社文芸文庫) でした。
「麻雀放浪記」 の 直木賞作家 、 阿佐田哲也 という方が通りがいいのかもしれませんが、ぼくにとっては 「百」、「狂人日記」 の 色川武大 です。彼はこの作品で 読売文学賞 を受賞しますが、受賞を知らないまま心臓破裂で世を去ったそうです。 60歳の生涯 だったそうです。
作品は 「自分」 と自称する 「元飾り職人」 の 「狂気」 と 「正気」 の間を行き来する日々の暮らし、「目」に見える外側の世界と内側の世界を描いた一人称の小説です。
主人公は病院で暮らしているのですが、彼が生きているのは、まあ、こんな世界です。
とはいえ、この作品が 1988年 に上辞されたことに絡めていえば、戦後社会という経済成長はあれども、確たる支柱の 「喪失」 の中で生きることを余儀なくされた 「個人」 を描いて、 「自我」 を描き続けてきたといわれる 「近代文学」 と、「 社会的人間」 を描こうとした 「戦後文学」 の終焉を鮮やかに描き切った傑作だというのが、ぼくの思い込みです。
「平成」 や 「令和」 の文学が、 色川武大 の荒涼とした
なんだか、老人の繰り言になりましたが、 YAMAMOTOさん 、お次をよろしくお願いします。 T・SIMAKUA・2021・06・07







色川武大「狂人日記」(福武文庫・講談社文芸文庫)
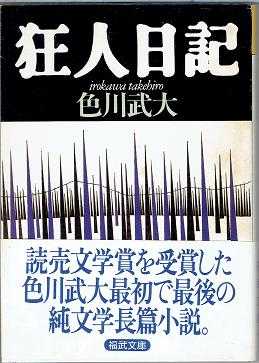
作品名を見ながら、ふと、浮かんできたのは
「ああ、いよいよ、出発点かあ・・・」 という感慨でした。
ぼくがこの作家の名前に出会ったのは高3の時でした。私淑していた世界史の先生の下宿の棚から借り出した 江藤淳 の 「成熟と喪失」 (今では 講談社文芸文庫 、当時は、たぶん、 河出書房 の単行本)という 「第三の新人」 を論じた評論の中でのことです。変なことを詳しく覚えているようですが、今思えばそれがぼくの 「文学オタク」 の始まりだったからなのかもしれませんね。
「オタク少年」 は、翌年の一年間、午前中しか学校がない浪人生活をいいことに、 「成熟と喪失」 で論じられた作家たちを読みふけったわけですが、その中で、その後も読み続けたのが、 遠藤周作 や 吉行淳之介 ではなくて、 庄野潤三 と 安岡章太郎 、そして 小島信夫 だったというところに、まあ、 「性根」の好み があらわれているようでおもしろいですね。
庄野潤三 が 『プールサイド小景』 で芥川賞を取ったのが 1955年 で、ぼくが生まれた翌年です。昭和30年。以後、一年間だったかのアメリカ留学の生活をつづった 『ガンビア滞在記』 、初期の代表作とも言うべき、釣りをする父と息子の話を書いた 『静物』 、で、 『夕べの雲』 が 1965年 です。
作風は、 DEGUTIさん のおっしゃるように 「平和な家庭の風景」 の 「おだやか」 で 「ユーモラス」 な描写ということなのですが、うまく言えませんが、どこかに 「喪われたもの」 と 「壊れそうなもの」 の 「不安定」 を感じさせるところのある 「おだやかさ」 に惹かれたのでしょうね。たとえば、 DEGUTIさん が引いていらっしゃる、こんな描写がぼくは好きです。
家ごと空に舞い上がって、その中には寝間着をきた彼と細君と子供がいて、 長々と思い出話をしてきましたが、バトンは
「やられた!」
と叫んでいる。
そういう場面を空想するのなら大風の方がよく似合う。台風では、そうはゆかない。
「読売文学賞」 です(笑)。
なんだ、それなら、さっさとそっちに行けばいいじゃないかと言われそうですが、 庄野潤三 は読み直したい人でもあって、語りたかったのでしょうね。
『夕べの雲』 が 読売文学賞 を取ったのは 1966年 ですが、23年後、 1989年 の受賞作が 色川武大「狂人日記」(福武文庫、今は講談社文芸文庫) でした。
「麻雀放浪記」 の 直木賞作家 、 阿佐田哲也 という方が通りがいいのかもしれませんが、ぼくにとっては 「百」、「狂人日記」 の 色川武大 です。彼はこの作品で 読売文学賞 を受賞しますが、受賞を知らないまま心臓破裂で世を去ったそうです。 60歳の生涯 だったそうです。
作品は 「自分」 と自称する 「元飾り職人」 の 「狂気」 と 「正気」 の間を行き来する日々の暮らし、「目」に見える外側の世界と内側の世界を描いた一人称の小説です。
主人公は病院で暮らしているのですが、彼が生きているのは、まあ、こんな世界です。
「一番怖いものは、何ですか」
と医者が上機嫌でいう。
自分が黙っているので、さらにうちとけた調子で、
「誰にもあるでしょう、怖いものが。蛇とか、蛙とか、虫とか」
「そういうことなら、べつにないようですねえ―」自分はにべもなくいった。「ただ、怖くなりだすと、なんでも怖いです。」
如何に生くべきか。そいうことを考える年齢では早くもなくなった。もう五十を越した、一生は短きもの也。このまま転げるように生き終えてしまいたいものだ。
一人では、やっぱり生きていかれない。他者が居ない分だけ、幻像が繁殖してくる。自分の病気はここから発していると思う。他者に心を開け。簡単に思う人も居るだろうが、自分がやろうとすると、卑屈になったり、圧迫してしまったりしてしまう。そればかりでなく、どの場合も不通の個所がこつんと残る。
死んでやろうと思う。ずいぶんよそよそしい言葉で、人に告げても信じるまい。自分にも、まだ嘘くさくきこえる。 引用していて、ちょっとヤバい気分になりますが、こういうのをひと様に紹介していいのかどうか、不安になりますね。
死んでやろうじゃない。死ぬよりほかに道はなしということだ。それで、自然史がよろしい。今日から、喰わぬ。
とはいえ、この作品が 1988年 に上辞されたことに絡めていえば、戦後社会という経済成長はあれども、確たる支柱の 「喪失」 の中で生きることを余儀なくされた 「個人」 を描いて、 「自我」 を描き続けてきたといわれる 「近代文学」 と、「 社会的人間」 を描こうとした 「戦後文学」 の終焉を鮮やかに描き切った傑作だというのが、ぼくの思い込みです。
「平成」 や 「令和」 の文学が、 色川武大 の荒涼とした
「崩壊」の世界 を、どう受け止めているのか、興味深いのですが、どうも、だれも論じないまま忘れられて行く雰囲気ですね。
なんだか、老人の繰り言になりましたが、 YAMAMOTOさん 、お次をよろしくお願いします。 T・SIMAKUA・2021・06・07
追記2024・05・11
投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目) (61日目~70日目) (71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめています。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと 備忘録 が開きます。
投稿記事を 100days 100bookcovers Challenge備忘録 (1日目~10日目) (11日目~20日目) (21日目~30日目) (31日目~40日目) (41日目~50日目) (51日目~60日目) (61日目~70日目) (71日目~80日目) (81日目~90日目) というかたちまとめています。日付にリンク先を貼りましたのでクリックしていただくと 備忘録 が開きます。



追記
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[読書案内「現代の作家」] カテゴリの最新記事
-
週刊 読書案内 滝口悠生「水平線」(新… 2024.05.11
-
週刊 読書案内 乗代雄介「掠れうる星た… 2024.05.09
-
週刊 読書案内 井戸川射子「この世の喜… 2024.04.15
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










