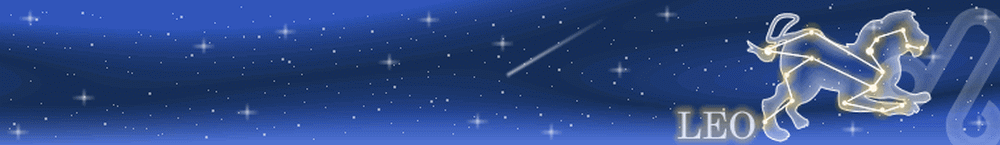PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
Gibson USA / Les Pa…
 New!
Mot_tenさん
New!
Mot_tenさん
ANAのタイムセールで… hiro-p88さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
ひとりゴト dmasterさん
シュタイナー関連書… カタリナnoteさん
 New!
Mot_tenさん
New!
Mot_tenさんANAのタイムセールで… hiro-p88さん
不法滞在は即刻強制… シャルドネ。さん
ひとりゴト dmasterさん
シュタイナー関連書… カタリナnoteさん
Comments
カテゴリ: 突発性難聴体験記
今回の突発性難聴体験で最も悔いが残るのは、高圧酸素治療を発症初期から受けられなかったことだ。
今も調べれば調べるほど、発症初期の高圧酸素治療の有効性を支持する論文がたくさん見つかるのである。
もちろん初期から受けられたとしても治っていたかどうかはわからない。しかし初期治療で全てが決まってしまう病気なのだから、例え治らなかったにしても「初期から充分にあらゆる治療を受けることができた。これで治らなかったのなら致し方ない」と納得できるのと、「あのときあの治療を受けていれば治っていたかもしれない」と悔いを残すのとでは気持ちの上で雲泥の差がある。
前にも述べたように当地では高圧酸素治療の設備があるのはN病院と県立病院のみだが、前者には耳鼻科が無く、後者では耳鼻科では使われていない。県立病院で使われていない理由はわからないが、診療点数の高い緊急疾患のみに絞っているためか、県立の耳鼻科医が高圧酸素治療の効果を認めていないかのどちらかだろう。
従って「耳鼻科に入院してしまうと高圧酸素治療が初期に受けられなくなる」というバカげた矛盾が発生する。この矛盾について少し説明しておこうと思う。
医師は意外と健康保険上のルールに無頓着なところがあるが、病院の事務方はいい意味でも悪い意味でも医師にルールを守らせて病院に経済的不利益が発生しないようちゃんと監視している。大学病院のような公的病院であってもというか、むしろ公的病院の方が厳しいかもしれない。
厚労省が決める保険のルールは、多くの場合医療費の抑制が目的であって患者の利益のためでは無い。
自分が患者になって初めてわかったが、私が入院した大学病院はDPC対象病院である。
DPC対象病院とは入院中にどんな治療や検査を行っても、病名によって診療報酬が一律に決められている病院である。いわゆる「まるめ=包括」のことである。手の込んだ治療や検査をするほど病院としては損することになる。逆に無駄な検査せず不要な薬は使わないようにして、早めに退院させれば病院は得をする。要はこれも医療費抑制を目的とした制度である。
入院中の回診時にこんなやりとりがあった。
講師「この聴力の落ち方(1000ヘルツに限局している)はめずらしいね。聴神経腫瘍による圧迫も疑った方がいいんじゃないかな。頭部MRIを撮るべきだね。」
私「じゃあ入院中ですし時間はありますから撮ってもらえませんか?」
講師「いや、入院中の患者には緊急でも無い限りMRIは撮れないんですよ。」
私「ハア?」
講師「入院中だと何をやっても一定金額しか診療報酬が入ってこないから、MRIのような高額な検査は原則入院患者にはやらないんです。もしやるんだったら、退院した後に外来でやるといいよ。」
なんのこっちゃ?重症でしっかり治療しようということで入院しているのに、MRIひとつ撮れないなんてあまりにも矛盾しているじゃないか!?撮れないわけじゃない。病院が少しでも損しないように撮らないよう指導されているのだ。
高圧酸素治療についても同じ矛盾が立ちはだかっていた。
もし私が大学病院入院中にN病院に出向いて高圧酸素治療を受けたとしたら(本当はそうしたかったのだが)、それにかかる費用をN病院は保険請求できないことになっている。入院先である大学病院から保険請求して、支払われた金額を大学からN病院に支払うことになる。
ところが包括の別枠として大学病院から保険請求できるのは発症後1週間以内の高圧酸素治療のみで、それ以後の高圧酸素治療の費用を大学病院は保険請求することができない。包括の中での治療と見なされるのである。
もちろんN病院としては無料で高圧酸素治療を行うわけにはいかないので、大学病院は一定の診療報酬の中から発症7日以後の高圧酸素治療の費用をN病院に支払わなければならない。これはかなりの金額になるので、大学病院の収益はガタッと減ってしまうことになる。通常突発性難聴に対する高圧酸素治療は10〜15回あるいはそれ以上行われるので、大学病院はかなりの金額を持ち出すことになる。ヘタすると赤字である。
これが大学病院入院中の患者が他院で高圧酸素治療を受けられない(大学病院が受けさせない)理由である。
これも医療費抑制のために厚労省が決めたルールである。
結果として私の場合発症後17日目というあまり効果の期待できない時期からの開始となってしまった。
しかしこんなことは、突然耳が聴こえなくなってとにかく治療をと焦っている時期に冷静に調べられることではない。この矛盾に満ちたシステムがわかった今なら、開業医でもどこでもいいから耳鼻科にお願いしてステロイドとデフィブラーゼを強引に外来通院で点滴してもらい、N病院で高圧酸素治療を受けるよう紹介状を書いてもらえば全ての治療を発症後7日以内受けることができただろうにと思う。ヘタに入院してしまったのが失敗だったのだ。
都市部にいけば、ステロイド+デフィブラーゼ+高圧酸素治療、もしくはステロイド+星状神経節ブロック+高圧酸素治療を入院当日から同時に行える病院がある。東京なら荏原病院などが有名だし、大阪なら大阪労災病院、滋賀県なら草津総合病院などがある。探せば他にもあるだろう。しかしそんな情報がわかってきたのは、すでに大学病院に入院してしばらく経ってからだ。時既に遅しだった。
今このブログを読んで下さっている方は既に突発性難聴になってしまった方が多いのかもしれない。幸いにしてまだなっていない方は、もしなってしまった場合速やかに全ての治療が同時に行える病院に行くことを強くお勧めする。ステロイドやデフィブラーゼ点滴などどこでもできる。要するにポイントは高圧酸素治療設備があるか否かである。できれば星状神経節ブロックも選べる病院の方がいい(デフィブラーゼ点滴と同時には行えないが)。これは腕のいい麻酔科医がいることが条件となる。
最初は開業の耳鼻科で診てもらったとしても、よほど軽症で無い限り全ての治療が行える病院に紹介状を書いてもらうよう頼み込むことだ。治すチャンスは2週間しか無い。2週間などあっという間に経ってしまう。例え遠い病院での入院になったとしても、その後の人生で片耳の聴力を失うか否かを考えれば迷うことは無いはずだ。
今も調べれば調べるほど、発症初期の高圧酸素治療の有効性を支持する論文がたくさん見つかるのである。
もちろん初期から受けられたとしても治っていたかどうかはわからない。しかし初期治療で全てが決まってしまう病気なのだから、例え治らなかったにしても「初期から充分にあらゆる治療を受けることができた。これで治らなかったのなら致し方ない」と納得できるのと、「あのときあの治療を受けていれば治っていたかもしれない」と悔いを残すのとでは気持ちの上で雲泥の差がある。
前にも述べたように当地では高圧酸素治療の設備があるのはN病院と県立病院のみだが、前者には耳鼻科が無く、後者では耳鼻科では使われていない。県立病院で使われていない理由はわからないが、診療点数の高い緊急疾患のみに絞っているためか、県立の耳鼻科医が高圧酸素治療の効果を認めていないかのどちらかだろう。
従って「耳鼻科に入院してしまうと高圧酸素治療が初期に受けられなくなる」というバカげた矛盾が発生する。この矛盾について少し説明しておこうと思う。
医師は意外と健康保険上のルールに無頓着なところがあるが、病院の事務方はいい意味でも悪い意味でも医師にルールを守らせて病院に経済的不利益が発生しないようちゃんと監視している。大学病院のような公的病院であってもというか、むしろ公的病院の方が厳しいかもしれない。
厚労省が決める保険のルールは、多くの場合医療費の抑制が目的であって患者の利益のためでは無い。
自分が患者になって初めてわかったが、私が入院した大学病院はDPC対象病院である。
DPC対象病院とは入院中にどんな治療や検査を行っても、病名によって診療報酬が一律に決められている病院である。いわゆる「まるめ=包括」のことである。手の込んだ治療や検査をするほど病院としては損することになる。逆に無駄な検査せず不要な薬は使わないようにして、早めに退院させれば病院は得をする。要はこれも医療費抑制を目的とした制度である。
入院中の回診時にこんなやりとりがあった。
講師「この聴力の落ち方(1000ヘルツに限局している)はめずらしいね。聴神経腫瘍による圧迫も疑った方がいいんじゃないかな。頭部MRIを撮るべきだね。」
私「じゃあ入院中ですし時間はありますから撮ってもらえませんか?」
講師「いや、入院中の患者には緊急でも無い限りMRIは撮れないんですよ。」
私「ハア?」
講師「入院中だと何をやっても一定金額しか診療報酬が入ってこないから、MRIのような高額な検査は原則入院患者にはやらないんです。もしやるんだったら、退院した後に外来でやるといいよ。」
なんのこっちゃ?重症でしっかり治療しようということで入院しているのに、MRIひとつ撮れないなんてあまりにも矛盾しているじゃないか!?撮れないわけじゃない。病院が少しでも損しないように撮らないよう指導されているのだ。
高圧酸素治療についても同じ矛盾が立ちはだかっていた。
もし私が大学病院入院中にN病院に出向いて高圧酸素治療を受けたとしたら(本当はそうしたかったのだが)、それにかかる費用をN病院は保険請求できないことになっている。入院先である大学病院から保険請求して、支払われた金額を大学からN病院に支払うことになる。
ところが包括の別枠として大学病院から保険請求できるのは発症後1週間以内の高圧酸素治療のみで、それ以後の高圧酸素治療の費用を大学病院は保険請求することができない。包括の中での治療と見なされるのである。
もちろんN病院としては無料で高圧酸素治療を行うわけにはいかないので、大学病院は一定の診療報酬の中から発症7日以後の高圧酸素治療の費用をN病院に支払わなければならない。これはかなりの金額になるので、大学病院の収益はガタッと減ってしまうことになる。通常突発性難聴に対する高圧酸素治療は10〜15回あるいはそれ以上行われるので、大学病院はかなりの金額を持ち出すことになる。ヘタすると赤字である。
これが大学病院入院中の患者が他院で高圧酸素治療を受けられない(大学病院が受けさせない)理由である。
これも医療費抑制のために厚労省が決めたルールである。
結果として私の場合発症後17日目というあまり効果の期待できない時期からの開始となってしまった。
しかしこんなことは、突然耳が聴こえなくなってとにかく治療をと焦っている時期に冷静に調べられることではない。この矛盾に満ちたシステムがわかった今なら、開業医でもどこでもいいから耳鼻科にお願いしてステロイドとデフィブラーゼを強引に外来通院で点滴してもらい、N病院で高圧酸素治療を受けるよう紹介状を書いてもらえば全ての治療を発症後7日以内受けることができただろうにと思う。ヘタに入院してしまったのが失敗だったのだ。
都市部にいけば、ステロイド+デフィブラーゼ+高圧酸素治療、もしくはステロイド+星状神経節ブロック+高圧酸素治療を入院当日から同時に行える病院がある。東京なら荏原病院などが有名だし、大阪なら大阪労災病院、滋賀県なら草津総合病院などがある。探せば他にもあるだろう。しかしそんな情報がわかってきたのは、すでに大学病院に入院してしばらく経ってからだ。時既に遅しだった。
今このブログを読んで下さっている方は既に突発性難聴になってしまった方が多いのかもしれない。幸いにしてまだなっていない方は、もしなってしまった場合速やかに全ての治療が同時に行える病院に行くことを強くお勧めする。ステロイドやデフィブラーゼ点滴などどこでもできる。要するにポイントは高圧酸素治療設備があるか否かである。できれば星状神経節ブロックも選べる病院の方がいい(デフィブラーゼ点滴と同時には行えないが)。これは腕のいい麻酔科医がいることが条件となる。
最初は開業の耳鼻科で診てもらったとしても、よほど軽症で無い限り全ての治療が行える病院に紹介状を書いてもらうよう頼み込むことだ。治すチャンスは2週間しか無い。2週間などあっという間に経ってしまう。例え遠い病院での入院になったとしても、その後の人生で片耳の聴力を失うか否かを考えれば迷うことは無いはずだ。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[突発性難聴体験記] カテゴリの最新記事
-
聴覚補充現象とBGM 2016.10.26 コメント(5)
-
突発性難聴発症1年半後 その4 2016.10.08 コメント(1)
-
突発性難聴発症1年半後 その3 2016.10.02 コメント(4)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.