第三話 反乱前夜(2)

【 第三話 反乱前夜(2) 】
トゥパク・アマルはそのまま一晩馬を駆り、夜明け頃、再びティンタ郡の集落に戻ってきた。
一晩雨の中を走り続けて体は冷え、疲れてはいたが、心は雨に洗われたためか、幾分平常心を取り戻しつつあった。
そろそろ、夜が明けていく。
見上げると、徐々に白みゆく空に、明けの明星が清らかな光を放っていた。
雨上がりの早朝の空は晴れ渡り、天頂は吸いこまれるような群青色だ。
空気もとても澄んでいる。
トゥパク・アマルは自らの館に戻る前に、集落から少し道をそれ、ビラコチャの神殿まで馬を走らせた。
スペイン征服以降、時の止まったようなこの神殿は、今となっては平素から人影を見ることは稀である。
今もしんと静まり返り、誰かがいるとしても、せいぜいインカ時代の亡霊くらいだろう。
トゥパク・アマルは馬を下り、ゆっくりと神殿に向かった。
朝露が、山の端からこぼれはじめた朝日を受けて、きらきらと繊細な輝きを放ちはじめる。
かつてのインカ帝国の創造神が祭られたこの神殿に、あの栄華を誇ったインカ時代の頃と同じ夜明けの時刻が、今日も変わらず訪れつつあるのだった。
彼は神殿の先端に立った。
そこからは、日の出に染まりゆくコルディエラ山脈の雄大なパノラマが一望に見渡せる。
トゥパク・アマルが見守るなか、まるで彼に導かれるかのように、輝く太陽が山の端をくっきりと朱色に染め上げながら昇ってきた。
太陽は透明なオレンジ色の光を放ちつつ、徐々に速度を速め、天に向かって確実に昇っていく。
それと共に、視界いっぱいに連なるコルディエラ山脈の山々が、まばゆい陽光と共鳴するかのように鮮烈な赤い光を放ち、煌々と輝きはじめた。
まるで見渡す限りの山と空が、清冽な濃いオレンジ色の炎を上げながら燃え立っていくようだ。
その情景は、まるで、太陽が、山々が、尽きることのない生命力をこの父祖の地に解き放っていくかのようだった。
トゥパク・アマルは心を奪われたように、その光景に見入っていた。
それから、彼は我にかえり、そして、大地を踏みしめる足の裏の感触を確かめた。
この大地、ここは古来からアンデスの神々とその民の息づく地。
そして、この大地も山脈も太陽も、確かに、今も、変わらずそこにあるではないか。
トゥパク・アマルは再び陽光に燃え立つ長大な山脈をみつめた。
彼はいまや、再び冷静さを取り戻した頭で考えた。
これまでの制圧者による無数の非道、それへの数知れぬ訴えと抗議行動、しかし、繰り返される非道、そして、挙句はブラスの暗殺…。
(正攻法では、やはり現状は打開できぬのか…!)
この時、トゥパク・アマルの中に、一つの決意が生まれつつあった。
だが、流血をみる前にすべきことはすべてしてからだ、とも考えていた。
事を起こすのは、その後だ。
最終手段を決行するとしても、十分な計画と準備が必要だ。
そして、その暁には、この地の民の中に眠れるインカの魂を再び呼び覚ますのだ…――!
トゥパク・アマルは天空を見つめた。
そこには、天頂さして留まることなく昇りゆく、輝ける太陽の姿があった。
その晩、早速、トゥパク・アマルはディエゴ、ベルムデス、ビルカパサ、フランシスコなど、主だった者を館に呼んだ。
さすがに当地のカシーケ(領主)だけあって、館の敷地は広大で、その中央に西洋風の格調高い堅固な建造物がある。
館の周囲には、選りすぐりのインカ族の豪腕の男たちが随所に配備されており、昼夜を問わず厳しい警護の目を光らせていた。
また、敷地内の広大な牧場には、数百頭のラバが飼われていた。
トゥパク・アマルはこの地のカシーケであると共に以前から大規模な商売も行っており、商隊を指揮して数百頭のラバに荷を乗せ、首府リマや、はるかブエノス・アイレスまで旅することもあった。
その夜の会合に際して、トゥパク・アマルはベルムデスの進言通り、スペイン本国へ渡ることのリスクの大きさについて考えた。
そして、スペイン行きを見合わせる旨を告げた後、集まった者たち一人一人を改めて見渡した。
いずれも、このインカの地を深く愛し、インカの民の解放を心の底から願い、これまでも心と力を合わせてきた者たちばかりだ。
互いに宗教的とも言えるほどの深い絆で結ばれている同志でもあった。
そして、今、自らの決断を告げる時がきたのだ。
「反乱の準備を進めようと考えている。」
あの地底から湧き上がるような声で、トゥパク・アマルは言った。
テーブルの中央に置かれたランプの火が、放射線状に光を放ち、それぞれの男たちの姿を浮き上がらせていた。
異議を唱える者など、誰もいなかった。
むしろ、ここにいる多数の者が、恐らく、何年も前からトゥパク・アマルのその決断を待っていたのだ。
緊迫の色と共に、高揚感が部屋の空気に滲みはじめる。
「だが…――。」
トゥパク・アマルは、全く情を挟まぬ声で続けた。
「反乱を確実に成功させるためには、隙の無い計画と準備が必要だ。
そして、もちろん、それは最終手段だ。
事を起こせば、インカの民にも多くの犠牲者を出すことは免れまい。
流血を見る前に、できることはすべてやらねばならない。」
一同も深く頷く。
その瞬間、ランプの炎はその放射状の光をひときわ強め、男たちの決意を秘めた横顔をくっきりと照ら出した。
こうして、インカの民の復権に向けた反乱準備が、極秘裏に進み始めたのだった。
限られた地域だけで武力蜂起するだけでは、単なる焼け石に水である。
火器がなく、武装面で著しく劣るインカ側にとって、この国を揺るがす反乱に発展させるためには、何よりも心を一つにし、あらゆる地域での一斉蜂起が不可欠だ。
この時のために、これまでトゥパク・アマルは商売という名目で多数のラバを飼い、大規模な商隊を組んできたのだった。
今、そのことが真の意味で役立つ時がきたのだ。
反乱準備を極秘裏に進める上で、商隊を装えたことは、スペイン側からの嫌疑を免れるためには非常に好都合であった。
そして、その慎重な反乱準備のためには、ここからさらに数年間の期間を要することになるのである。
トゥパク・アマルは、これまで通り商隊を率いてラバと共に荷を輸送しながら、ティンタ郡からはるかに離れた地域まで自ら足を運んだ。
そして、志を同じくするインカ族の者たちに直に会い、自らの胸の内を語り、相手の思いを熱心に聴き、固く手を結んでいった。
それは決して反乱に巻き込むための策略ではなかった。
そのような単なる巻き込み作戦では、何年先になるかわからぬ反乱に向けての意志を維持させることなど不可能であったろうし、早晩、裏切り者の出現によってトゥパク・アマルはスペインの役人に売られてしまっていたであろう。
しかし、そのようなことのなかったことは、歴史が証明している。
彼らは「その日」に向けて、真の意味で心を一つにしていったのである。

今、トゥパク・アマルの眼前には、広大な美しい湖が広がっていた。
標高3800メートルという世界で一番高所にある湖、ティティカカ湖である。
世界にも数少ない古代湖のひとつでもある。
湖には、葦でできたウロス島をはじめとして、太陽の島、月の島など41の大小の島々が点在し、かつて太陽の島には黄金で飾られた神殿がそびえ輝いていた。
言うまでも無く、それらの黄金はずいぶん昔にスペイン人によってすべて持ち去られていたのだが。
トゥパク・アマルは号令をかけ、商隊に休息を命じた。
空気の薄い高所を進んできたため、商隊員たちにも、ラバたちにも、十分な休息が必要だった。
トゥパク・アマルは湖岸に降り立ち、午後の陽光に輝く紺碧の湖面を眺めた。
この湖には、インカ帝国の創始者マンコカパクが降り立ったという伝説が伝えられている。
確かに、広大な湖面に青い空が鏡のように映り、その様子は神秘と幻想に満ちている。
トゥパク・アマルは、その神秘的な美しさに心を奪われた。
空気が非常に澄んでいるため湖や空の青さがいっそう増し、その自然美はとうてい言葉では言い尽くせぬものだった。
まるで湖に吸いこまれそうな錯覚にとらわれる。
高所にある湖面を吹き渡る風は身を切るように冷たかったが、彼にはむしろその冷たさが心地よかった。
長い黒髪が風の中に舞っている。
光を受け、風を切り、神秘の湖岸に立つその姿を、商隊員たちは、正確には商隊員を装った護衛官たちだが、息を詰めて見守った。
彼らの目に、そのトゥパク・アマルの姿はインカ皇帝の降臨さながらに見えていたことだろう。
父祖発祥の地とされるその伝説の湖に心を奪われたようなトゥパク・アマルの傍に、いつもの側近ビルカパサがゆっくり近づいた。
「トゥパク・アマル様、そろそろ出立いたしましょう。
この辺りの道は、日が落ちると危険です。」
トゥパク・アマルも我に返って、同意した。
今回の旅路は長く、危険を伴うものだった。
このティティカカ湖の周辺は、トゥパク・アマルの領地があるペルー副王領のはずれであり、むしろ、隣接するラ・プラタ副王領に属する地域であった。
この18世紀の時代、あまりに広大なかつてのインカ帝国は、スペイン人によって幾つかの副王領に分割統治されていた。
トゥパク・アマルらのいる「ペルー副王領(首府リマ)」のほか、「ラ・プラタ副王領(首府ブエノス・アイレス)」、「新グラナダ副王領(首府ボゴター)」があった。
スペイン人の圧制に苦しんでいたのは、トゥパク・アマルらのいるペルー副王領のインカ族の人々だけではなかったのだ。
他の副王領でも、無数のインカ族の人々が、そして、混血児や黒人たちが、あるいは、当地生まれの白人が、スペイン渡来の白人たちによって苦しめられていた。
トゥパク・アマルはそれらの地域の人々にも、当然ながら目を向けていた。
それ故、今回の旅は、ラ・プラタ副王領のインカ族に対して影響力をもつ猛将フリアン・アパサに会うことが目的だった。
アパサも表向きはトゥパク・アマルと同様に商売を行っており、コカや服地などを商って遠方までしばしば旅をし、インカ族の間で顔も広かった。
この時、トゥパク・アマルはこのアパサなる人物との面識はまだなかったが、彼のこの地域での影響力を考慮すると、手を携えるべき重要な人物には違いなかった。
アパサの協力を得られれば、このラ・プラタ副王領で苦しむ人々を救済するための大きな要となるはずだ。
それにしても、アパサに関する噂は、その評価が非常にまちまちであった。
アパサの右に出る将はいないと絶賛する者もいれば、卑しく、ずるく、獰猛な人間であるという悪評判もあった。
フリアン・アパサ…――果たして、いかなる人物なのか。
トゥパク・アマルは、間もなく会えるであろうその人物に思いを馳せた。
アパサは、この神秘のティティカカ湖周辺の部落に住んでいた。
トゥパク・アマル率いる商隊はティティカカ湖を出立し、アパサの屋敷のあるシカシカの部落への道を進み始めた。
実は、この地域界隈は、かつてのインカ帝国に征服された地域でもあった。
この辺りは、もともとインカ以前(プレインカ)の巨石建築や多数の土器で有名なティアワナコ文明を築いた誇り高い民族の地であり、実際、この時代に至っても、彼らにとってはかつての征服者であったインカの人間を好意的に思わぬ者も少なくはなかった。
そういう意味では、トゥパク・アマルにとって、この地域の民は、スペイン人とはまた別の次元で難しい相手でもあった。
ティティカカ湖からシカシカへの道は、さきほどの神々しい雰囲気とはうって変わって、うら寂しい様相に変わっていた。
人気の無い荒涼たる高原を一本の乾いた道が貫き、やや低くなった土地に稀に耕地が見えるほかは、トーラという木本の植物か、イチュという固い草本の植物が生えているくらいで、実に淋しい。
しかも、プレインカ時代に作られたとおぼしき、土のチュルパ(家形の墳墓)が所々に林立しているのが見え、商隊員の心をいっそう、うら悲しい気持ちにさせていた。
次第に夕闇が迫ってくる。
人気のない道を、100頭ほどのラバと50人ほどの商隊員は整然と列を成し、悄然と進んでいった。

トゥパク・アマルは予測できない奇襲に備えて警護の目を光らせるよう指示をし、実際、ビルカパサをはじめ隊員たちの眼光は険しくなっていた。
トゥパク・アマルは馬を降り、懐からオンダ(投石器)を出して肩にかけた。
その時だった。
ふいに草陰から黒い影が幾つも飛び出してきたかと見えた途端、トゥパク・アマルらの商隊を50~60人の褐色の男たちが取り囲んだ。
ビルカパサが素早くトゥパク・アマルの前に身を投げ出し、敵襲に構える。
商隊員を装っていた護衛官たちも、トゥパク・アマルを守るように円陣を組み、オンダの紐に手をかけて敵の動きに眼を光らせた。
両集団の間に強い緊張感が走り、無言の睨みあいの瞬間が流れた。
トゥパク・アマルは鋭い視線で、相手方の一団をざっと眺めた。
褐色の兵ばかり、いずれも、インカ族と思われた。
先方もトゥパク・アマルの動きに、まんじりともせず、険しい視線を投げている。
自分のいかなる能動的な動きも、相手を刺激することになるだろう。
トゥパク・アマルはその身を動かさぬよう慎重に肩だけ動かし、オンダを地面に捨てた。
ゴトリと鈍い音がして、彼のオンダが地面に落ちる。
敵方のみならず、味方の護衛も息を呑んだ。
しかし、確かに、その瞬間、場の空気が微かに緩んだ。
その機を逃さず、トゥパク・アマルは平常通りの口調で名乗った。
「私は、ペルー副王領ティンタ郡のカシーケ、トゥパク・アマルだ。
シカシカの集落へ商用で向かっている。」
トゥパク・アマルが言い終わるか否かという間に、突如、彼の前に戦斧が投げこまれた。
それは、インカ族が武器として用いる、厳(いか)つい戦用の斧であった。
即座にビルカパサが身を翻し、斧が投げられてきた方向に向かって右手にオンダの石を掲げ、左手で紐の端を握り締めた。
いつでも振り切る姿勢である。
ビルカパサの目が、鷲のように険しく光った。
「待て。」
トゥパク・アマルはビルカパサを片手で制し、戦斧を投げた主の方向を鋭い目で見据えた。
彼は警戒しつつも、冷静な頭で状況を分析していた。
相手は戦斧で切りかかってきたのではなく、投げてよこしてきたのだ。
その意味は?
恐らく、挑発か…――。
少なくとも、即座に命を奪おうという意図ではないらしい。
トゥパク・アマルはビルカパサを制した手でさらに彼を横にどかせ、自分の正面を敵の前に開いた。
そして、身構えながらも慎重に身を屈め、戦斧を手に取った。
ずっしりとした重量感が手に伝わってくる。
斧はインカ族にとってオンダと並ぶ代表的な武器の一つである。
アンデス一帯はその地形柄、山岳戦が多く、接近戦に有効な戦斧や棍棒の類が発達してきた。
戦斧は一般の斧よりも刃が鋭く、重く、片手で扱える代物ではない。
が、敵方の集団の中から一人の男が、戦斧を軽々と片手で握りながら一歩前に進み出た。
身長は中位で、筋骨隆々たる、20代半ばと見えるインカ族の男である。
服装はいかにも原住民的で頓着ない薄汚れた伝統的な貫頭衣を着ているが、その目は小さいながらも深く窪み、活動性と意志の強さが漲っていた。
一方で、その相貌には、復讐心に憑かれたような獰猛さがうかがえ、危険な野獣をも連想させる。
その男は不遜な態度で、トゥパク・アマルを見据えた。
そして、不気味に笑った。
「あんたが、トゥパク・アマルか。」
トゥパク・アマルを呼び捨てにされたことで、再びビルカパサが肩をいからせ、身を乗り出した。
トゥパク・アマルは再度ビルカパサを制し、「そうだ。」と、やや目を細めながら応えた。
「俺は、フリアン・アパサ。
今夜の客人をお迎えにあがった。」
そして、再び不遜に笑う。
トゥパク・アマルも、やや冷ややかな眼差しに変わった。
「これはこれは、アパサ殿でしたか。」
難しい相手だと予想はしていたがここまでとは、と内心苦笑した。
「トゥパク・アマル、お前の腕が知りたい!
他の話はそれからだ。」
アパサは単刀直入に言い放った。
それは、いきなりの戦斧での果し合いの申し出だった。
しかも、アパサはインカ族の中でも名の知れた猛将である。
さすがのトゥパク・アマルも不意をつかれた思いがしたが、断って事がすみそうな状況ではなかった。
「何を申されるか、アパサ殿、このお方は…!」と目を血走らせ、アパサの方に猛全と挑みかからんばかりのビルカパサをまた制して、トゥパク・アマルは戦斧をゆっくり構えた。
30代にさしかかったとはいえ、トゥパク・アマル自身も腕に覚えのある武者である。
アパサの眼差しは不遜ではあったが、ひどく真剣でもあることを、トゥパク・アマルは見逃さなかった。
この先、命運を共にする相手として足る人物か、見極めんとの考えであろう。
このようなやり方が、人を見定める際のアパサ流なのに違いあるまい。
ここは受けて立つのが筋であろう。
しかも、上手く事を運べれば、かつての征服者インカへの復讐心に燃えるアパサの心を開くことにもつながるかもしれない。
トゥパク・アマルは横目で地形を確認した。
幸い、トーラの密集する林が近くにある。
彼は今にも噛み付いてきそうなアパサを見た。
猛将ときこえの高いその男の腕を、自ら見定めてみたい衝動も湧いてくる。
「わかった。
申し出に応じよう。」
トゥパク・アマルの答えに、ビルカパサは驚愕してトゥパク・アマルに向き直った。
普段冷静なビルカパサでも、さすがに動揺を隠せないらしかった。
「トゥパク・アマル様!
このようなところでお命を危険に晒すなど、あなた様らしくありませぬ!
あのような者の挑発に乗られては…――。」
周りの護衛兵もビルカパサに同意し、トゥパク・アマルを口々に制した。
トゥパク・アマルは「大丈夫だ。」と言って上着を脱ぎ捨て、ビルカパサや兵が止めるのをかきわけアパサの前に歩み出た。
アパサはニヤリと笑って、トゥパク・アマルを見た。
その目はやはり不遜ではあったが、先ほどとは少し色が変わり、無謀な申し出を受け入れた眼前の男、トゥパク・アマルへの肯定的な色合いが多少なりとも混ざっていた。
トゥパク・アマルは、その目の色の変化に応えるように、彼自身もアパサへの礼を目で送った。
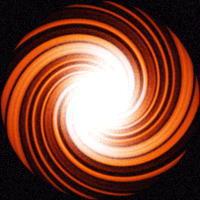
「誰も手出しをするな!!」
アパサは言い放つと、いきなり片手で握った戦斧を振り下ろしてきた。
トゥパク・アマルは素早く背後に飛んだ。
アパサの振り下ろした斧から生じた衝撃波は、まるで地面をえぐるような激しさでトゥパク・アマルの足元を揺るがした。
トゥパク・アマルは敏捷にアパサの右後方に走った。
それは、先ほど確認したトーラの林のある方向だった。
「逃げる気か!」
アパサが再びトゥパク・アマルめがけて斧を振り下ろす。
地面の岩が激しい音を立てて粉砕された。
トゥパク・アマルは再び俊敏に斧をかわし、トーラ林の方向へとさらに移動した。
アパサは繰り返しトゥパク・アマルめがけて鈍器を振り下ろす。
トゥパク・アマルは敢えて、ぎりぎりまでアパサの斧をひきつけた。
それ故、アパサの斧には必要以上に力が入り、空を切って、地面へのめりこんだ。
アパサの斧をかわしながら、トゥパク・アマルは敵の斧使いの特性を冷静に分析した。
斧は重い鈍器である。
斧は一撃の破壊力は大きいが、攻撃が遅いこと、及び、体力を消耗しやすいという欠点がある。
鈍器であるが故に凶悪なのだが、空振りの時間的ロスもかなり大きい。
アパサは片手で戦斧を振るうほどの怪力だった。
しかし、それ故、力に頼っていた。
速さと機動性の面では、トゥパク・アマルの方が勝っていた。
トゥパク・アマルはアパサの攻撃を俊敏にかわし、消耗戦に出た。
しかし、アパサの体力は並大抵ではなく、しかも、トゥパク・アマルほどでないにしろ、並外れたスピードももっていた。
野獣のごとく獰猛に挑みかかってくるにもにもかかわらず、アパサのその身のこなしは、どこか華麗で美しくさえある。
しかも、アパサはその怪力ゆえ、斧の連打を軽々と行えた。
否、単なる怪力なのではない。
心身共に極限まで鍛え上げられているからこそ、成し得る技なのだ。
トゥパク・アマルはアパサの刃をかわしながらも、その男の腕に感服していた。
これだけの腕をもっている者は、そうはいまい。
この男が「猛将」と謳われるのは、誇張や偽りではないらしい。
そのままトゥパク・アマルはトーラの林の中に走り込んだ。
斧は強力だが、障害物が密集した状況では使えない。
トーラの木をなぎ倒し、斧を縦横無尽に振るいながら、アパサはトゥパク・アマルを繰り返し襲った。
が、もはや木々が邪魔をして、その威力は落ちていた。
アパサは、林に至るまでにトゥパク・アマルを仕留められなかったことを悔やんだ。
トゥパク・アマルは、とにかく身のこなしも足も不気味に速かった。
肩で息をしながら、アパサは苦笑した。
額から頬を汗が伝う。
その時だった。
アパサの斧をかわし、トーラの中を走るトゥパク・アマルがピタリと動きを止めた。
もともと長身のトゥパク・アマルの姿が、アパサの目には己に覆いかぶさる黒い影のごとくに見えた次の瞬間、トゥパク・アマルはそのまま斧を両手で右に振り上げ、アパサの首めがけて雷(いかずち)のごとく振り下ろしてきた。
あまりにも瞬間的な出来事だったが、さすがにアパサは俊敏に身をこなし、振り下ろされる斧を自らの斧で受け留めた…――。
そのはずだった。
が、トゥパク・アマルは、アパサの首めがけて右上から振り下ろすかと見えたその戦斧を瞬時に左に振りきり、そのままゆっくりとアパサの左足めがけて振り下ろした。
アパサの宙空に構えた腕は虚しく空を切り、トゥパク・アマルの振り下ろした斧は、しかし、振り下ろすというよりも、ゆっくりとアパサの左足に当たった。
斧が「入る」というより「当たった」という程度だったが、互いに譲らぬ攻防戦の中で、それはトゥパク・アマルにとって有利なものだった。
恐らく、トゥパク・アマルは敢えてゆっくりと当てた程度に留めたのだが、アパサの体はそのまま地に沈んでいった。

「あんたったら、なんてことを!!」
部下たちに肩を抱かれ、足を引きずりながら自分の館に戻ってきた夫に、アパサの妻バルトリーナは金切り声を上げた。
そして、夫を鬼のような眼差しで睨みつけた。
さすがのアパサも妻の剣幕に気圧されて、足の痛みも忘れたように館の奥に逃げ込んでしまった。
アパサの妻は、すっかり日も落ちた頃、やっと夫と共に館に到着したトゥパク・アマルらの商隊の方にすっ飛んで行った。
それから、商隊員の誰かれ構わず、殆ど泣きそうな顔で頭を下げて回り始めた。
「すいませんねえ。
本当に、うちのあの人が、またとんでもないことをしちまって。
本当に、もう、なんとお詫びしたらいいものか…!
ああ~~、なんてことだろう。
皇帝様に、こんなことしちゃって…!!」
そして、頭を抱えて、しまいには地面にひれ伏すようにうずくまってしまった。
やや大袈裟にも見えかねない態度だったが、その様子には本当に必死さがうかがえた。
しかし、先ほどの一件以来、さすがに常時は冷静なビルカパサも機嫌を損ねていて、アパサの妻の様子にも冷ややかな視線を投げていた。
トゥパク・アマルはビルカパサの肩を軽く叩き、「気にするなと言っておあげ。」と促した。
ビルカパサはちらりとトゥパク・アマルを見た。
その顔は、いつになく、恨めしそうな表情である。
「トゥパク・アマル様、先ほどのようなこと、もうニ度となさらないでください。
あのような挑発に乗っていては、お命が幾つあっても足りませぬ。
あなた様に何かあったら…。」
ビルカパサは厳しい目を向けた。
トゥパク・アマルは頷き、「あれは必要なことだったのだよ。だが、お前の言葉もよく覚えておこう。さあ、行っておあげ。」と、ビルカパサの背中を押した。
ビルカパサはトゥパク・アマルにもう一度視線を投げてから、地面に泣き崩れるようにうずくまっているアパサの妻、バルトリーナの方に向かった。
ビルカパサは、もう終わってしまったことだし、幸いトゥパク・アマル様も無事だから、と彼女に話し、それよりもトゥパク・アマル様を早く館に通してほしいと伝えた。
バルトリーナは深い安堵の表情になり、本来は気丈な女性なのですぐに元気を取り戻し、改めてトゥパク・アマルに恭しく礼をして館へと招き入れた。
その晩遅く、トゥパク・アマルは、ようやくアパサと二人で話す時間をもつことができた。
アパサは薬草を塗って布でくるんだ左足をひきずりながら、部屋の一隅に置かれた巨大な木樽の方に進んでいくと、荒々しく栓をひねった。
樽の口から、勢いよくチチャ酒がほとばしり出た。
彼は、その酒を間口の広い木のカップに波々と入れて、その一つをトゥパク・アマルの前のテーブルに無造作に置いた。
チチャ酒は古来からアンデス地帯で愛飲されている伝統的なトウモロコシを原料とする酒である。
カップの上面から、ビールのような泡が滴っている。
アパサはぐいと自分のチチャ酒をあおった。
「おまえ、本気なのか。」
泡のついた口を腕で拭きながら、アパサはトゥパク・アマルを探るように見た。
「本気だ。」
トゥパク・アマルもアパサを見返した。
アパサはフンッと鼻息を吐くと、トゥパク・アマルから視線をずらし、深夜の夜闇しか見えぬ窓の方を見やった。
それから、再びチチャ酒をすすりながら、カップの陰からトゥパク・アマルを覗くように見る。
そして、カップを口から離して、低い声で言った。
「俺とて、スペイン人のやり口には、腸(はらわた)が煮えている。だが…。」
彼のトゥパク・アマルに向ける目は、鋭くなった。
「おまえがインカの皇族か何か知らんが、そんなことは俺には関係ねえ。
もともとインカは虫が好かねえんだ。
おまえの指図を受ける気はない。」
トゥパク・アマルもチチャ酒を口に運んだ。
そして、アパサが先にしたように夜闇が広がる窓を見やってから、視線を眼前の男に戻した。
「もとより承知している。
この国で苦しんでいる人々を救う、そのことが一致しているならば、我々は同志になれる。」
アパサの瞳の色が、かすかに変わる。
トゥパク・アマルは、その意味を読み取りかねた。
が、敵意だけではない何かを感じた。
「トゥパク・アマル、忘れるなよ。
この国には、既にスペイン人に取り込まれちまっているインカ族も多い。
俺たちのように、古くっからの因縁でかつてのインカ帝国の奴らに恨みを持つ者もいる。
へたな反乱は、かえって同族同士で血を流すことになるのだ。」
アパサの言葉に、トゥパク・アマルは深く頷いた。
そして、この一見虚勢を張っている男の胸の内に、熱い正義心と、真理を見抜く鋭い洞察力を見て取った。
その思いをこめて、トゥパク・アマルは噛み締めるようにアパサに言った。
「だからこそ、そなたの力が必要なのだ。
この国で苦しんでいる者が、種族を超えて心を合わせるために。」
それはトゥパク・アマルの真実の思いであった。
そして、やや自分より低いアパサの目線に合わせるように、トゥパク・アマルは少し身を沈めるような格好で、真正面から眼前の男を見据えた。
その切れ長の目元に、熱を帯びた光を宿しながら。
「アパサ殿。
そなたに、わたしの指図を受けさせようなどという気は、もとより持ってはいない。
そなたの考え、判断は、己(おのれ)自身で信頼するに値するであろう。
わたしもそなたを信じよう。
だから、そなたの思うようにすればよい。
ただ、いずれそなたも事を起こすつもりであるならば、共に時を合わせた方が効果的であろうと思うまでだ。」
アパサは微妙に目元をぴくつかせながら、「うまいことを言っても、結局は、おまえが音頭(おんど)取りをするのだろうが。」と、相変わらず憎々しげに言う。
だが、その後、不意に少々面白そうに笑った。
「トゥパク・アマル。
おまえも因果な奴だ。
余計なことなぞ考えなければ、一生、何の苦労もなく、安穏と豪遊できるだけの地位も金もあるくせに。」
「それは、アパサ殿、そなたも同じであろう。」
そして、互いに顔を見合わせ、フッと笑って肩をすくめた。
アパサはチチャ酒を飲み干すと、トゥパク・アマルにも飲めと勧め、二人分の酒を改めてついできた。
そして、カップを軽く掲げ、トゥパク・アマルのカップに当てた。
「おまえの今後の動き次第だが、まあ少しは心積もりをしておこう。」
そして、相変わらず不遜な、しかし、熱い眼差しで笑った。
トゥパク・アマルも笑みを返し、自分のカップを相手のそれに当て、酒を飲み干した。
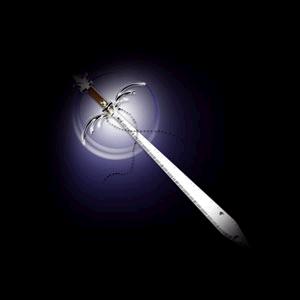
二人分の3杯目のチチャ酒をつぎに立って戻ってきたアパサからカップを受け取りながら、トゥパク・アマルは今までとは少し趣きの違う笑顔をつくって言った。
「どうだろうか、アパサ殿。
わたしの甥をそなたの元にあずけることは、かなわぬだろうか。」
突然の申し出に、アパサは目を丸くした。
「なんの話だ?」
「わたしの甥は、今、クスコの神学校で学んでいるのだが、卒業したら、そなたの元で武芸を学ばせてやりたいのだが。」
アパサは全く取り合わぬ風情で、手をひらひらと振った。
「なんで俺がおまえの甥っ子の面倒なんか見なきゃならねえんだ。
冗談はよしてくれ。」
「冗談ではない。
そなたの腕、この身で知ることかない、可愛い甥の師としてこれに勝る者はないと感じたのだ。
是非、お願いしたい。」
そして、やや大袈裟な、しかし真剣な口調でトゥパク・アマルはつけ加えた。
「この国の存亡に関ることかもしれないのだよ。」
トゥパク・アマルの引き下がらぬ様子に、アパサはやや閉口気味に言った。
「なんでまた、甥っ子なんだ。
おまえには、息子だっているんだろう。」
トゥパク・アマルは「受けてくれるね。」と言わんばかりに少し身を乗り出しながら、静かな声で答えた。
「わたしの息子はまだ幼い。
それに、息子ではスペイン人の役人たちにも目立ってしまう。」
トゥパク・アマルは窓の方をみやりながら、「それに…。」と、遠くを見る眼差しで呟くように言った。
「あれを見ていると、自分の若かった頃を思い出すのだよ。」
そして、改めて、礼をこめた目でアパサを見た。
「アンドレスをそなたにあずけたい。
神学校を卒業したら、武将としてのそなたの腕を授けてやってはくれまいか。」
「ずいぶん、その甥っ子を買っているんだな。」
トゥパク・アマルは瞳で笑い、それから、まっすぐアパサを見た。
「この後、わたしには何が起こるか分からぬからな。」
アパサは、その意味を察した。
「命を粗末にするなよ。」
「先刻は戦斧を振るってきたくせに、そなたに言われるのは妙な気分だな。」
「フンッ…!」
と、再び鼻息を荒げてそっぽを向きながらも、まるで案じるのを悟られまいとするかのように、アパサは横目でトゥパク・アマルの方にちらりと視線を投げた。
命を粗末にするな…――そのアパサの言葉に、トゥパク・アマルは頷くとも頷かぬともつかぬ表情のまま、ただ静かな笑みを返していた。
◆◇◆◇ここまでお読みくださり、誠にありがとうございました。続きは、フリーページ 第三話 反乱前夜(3) をご覧ください。◆◇◆◇
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- お勧めの本
- お友だちからお願いします: 三浦しを…
- (2024-11-27 20:47:01)
-
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(リチャード・C・ホーグラン…
- (2024-11-20 20:31:59)
-
-
-

- 最近、読んだ本を教えて!
- 皮はぐ者 ミシェル・ペイヴァ―
- (2024-11-29 16:38:21)
-
© Rakuten Group, Inc.


