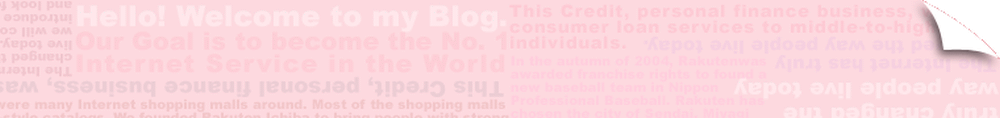全て
| カテゴリ未分類
| 競馬
| 時事ネタ?
| 2006年11月読書
| 2006年12月読書
| 身辺雑記
| 映画鑑賞記
| 2007年01月読書
| グイン・サーガ
| DVD視聴記
| 2007年02月読書
| 2007年03月読書
| 2007年04月読書
| 2007年05月読書
| 競馬MEMO
| 2007年06月読書
| 2007年07月読書
| 2007年08月読書
| 2007年09月読書
| 2007年10~12月読書
| ベストセラー
| 2008年01~03月読書
| ブックオフ105円本を読む。
| 2008年04~07月読書
| 劇も観る。
| 2008年08~12月読書
| 2009年以降の読書
カテゴリ: 2008年04~07月読書
[1] 読書日記
< 今われわれが享受している「ふつう」は、何のかのといいながら、親世代がふつう
以上に努力してくれた蓄積のおかげなのであり、決してふつうに過ごしていて天から
降ってくるようなものではない。そして今、日本はそんなかっての貯金を使い果たし
つつある。というか、国庫をみれば、実は「豊かさ」なんてなくて、すべては借金の
上に成り立っていたのである。
この状況下で「努力しない」というのは、「淘汰して下さい」と言っているようなも
のだ。 >
長山靖生 「不勉強が身にしみる」(光文社新書)

を読了。
例えば、ゆとり教育。
< 学校の週休二日制は、生徒にゆとりを持たせるためではなく、公立学校の教職員
という「公務員」の勤務時間短縮のための制度改革だった >
< 学習内容が減ったからといって、教育時間もいっしょに減らす必要性(必然性)は、
どこにあったのだろう。これでは結局のところ、学校における一時間当たりの学習
濃度は変わらないではないか >
道徳教育、人格教育ならば、
< 「学級崩壊」をきたすのは、躾よりも勉強を優先した結果ではない。躾も教育も
ないがしろにされているから、見事にそのどちらも身につかないだけなのでは
あるまいか >
< だいたい自分の子供もろくに監督できない人間に、どうして学校の監視、監督、
助言ができようか。それが出来るくらいのしっかりした親、社会的な発言力もある
ほどの人物なら、そもそも今時の公立学校に子供を通わせてはいない >
何かを信じるという行為は、
< 信じるというのは、善良な行為ではなく、思考の停止である。考えるのをやめに
して、あとは他人の意見に身を委ねる。それが「信じる」ということだ。そして
しばしば、安易に信ずる者は、被害者になるばかりではなく、加害者にもなって
しまう >
< 「分かる」を諦めて「信じる」に移行するラインが、すべての人間に存在する。
誰でもすべて「分かる」ことができない以上、理解力の限界の先は、他人の説明
なり、何らかの世界観なりを「信じて」納得するより仕方ない >
当たり前といえば、当たり前のなことでもあるけれど、勉強になりました。
< 今われわれが享受している「ふつう」は、何のかのといいながら、親世代がふつう
以上に努力してくれた蓄積のおかげなのであり、決してふつうに過ごしていて天から
降ってくるようなものではない。そして今、日本はそんなかっての貯金を使い果たし
つつある。というか、国庫をみれば、実は「豊かさ」なんてなくて、すべては借金の
上に成り立っていたのである。
この状況下で「努力しない」というのは、「淘汰して下さい」と言っているようなも
のだ。 >
長山靖生 「不勉強が身にしみる」(光文社新書)

を読了。
例えば、ゆとり教育。
< 学校の週休二日制は、生徒にゆとりを持たせるためではなく、公立学校の教職員
という「公務員」の勤務時間短縮のための制度改革だった >
< 学習内容が減ったからといって、教育時間もいっしょに減らす必要性(必然性)は、
どこにあったのだろう。これでは結局のところ、学校における一時間当たりの学習
濃度は変わらないではないか >
道徳教育、人格教育ならば、
< 「学級崩壊」をきたすのは、躾よりも勉強を優先した結果ではない。躾も教育も
ないがしろにされているから、見事にそのどちらも身につかないだけなのでは
あるまいか >
< だいたい自分の子供もろくに監督できない人間に、どうして学校の監視、監督、
助言ができようか。それが出来るくらいのしっかりした親、社会的な発言力もある
ほどの人物なら、そもそも今時の公立学校に子供を通わせてはいない >
何かを信じるという行為は、
< 信じるというのは、善良な行為ではなく、思考の停止である。考えるのをやめに
して、あとは他人の意見に身を委ねる。それが「信じる」ということだ。そして
しばしば、安易に信ずる者は、被害者になるばかりではなく、加害者にもなって
しまう >
< 「分かる」を諦めて「信じる」に移行するラインが、すべての人間に存在する。
誰でもすべて「分かる」ことができない以上、理解力の限界の先は、他人の説明
なり、何らかの世界観なりを「信じて」納得するより仕方ない >
当たり前といえば、当たり前のなことでもあるけれど、勉強になりました。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[2008年04~07月読書] カテゴリの最新記事
-
長山靖生 「謎解き 少年少女世界の名作」 2008年06月04日
-
鹿島茂 「SとM」 2008年06月02日
-
岡嶋裕史 「数式を使わないデータマイニ… 2008年05月29日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.