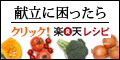震災関連死:福島県内で直接死上回る 避難生活疲れで
東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の被災者の死亡例のうち、福島県内自治体が「震災関連死」と認定した死者数が8月末現在で1539人に上り、地震や津波による直接死者数1599人(県災害対策本部調べ)に迫っていることが、毎日新聞の調査で分かった。少なくとも109人について申請中であることも判明。近く直接死を上回るのは確実だ。
関連死の審査会を設置しているか、今年3月末までに関連死を認定したケースがある福島県内25市町村を調べた。復興庁が公表した3月末の関連死者1383人から5カ月で156人が新たに増えたことになる。宮城県では今年8月末現在で869人、岩手県は413人だった。
長引く避難生活で体調が悪化したり、自殺に追い込まれたりするケースがあり、原発事故被害の深刻さが裏付けられた。関連死申請の相談を受けた経験がある馬奈木厳太郎弁護士は「原発事故による避難者数が多い上、将来の見通しも立たずにストレスがたまっている。今後も増える可能性がある」と指摘している。
(毎日新聞 2013/09/08 より抜粋、編集)
↓記事を読んで浮かんだうp主の疑問を中心に「震災関連死の現状」について簡単に纏めました ↓
まず、用語や仕組みについて調べてみると。
震災関連死 とは、「東日本大震災による直接的な被害などではなく、負傷の悪化や避難生活での過労など間接的な原因により死亡し、災害弔慰金の支給対象となったケース」と定義される。(by復興庁)
災害弔慰金 とは、「異常な自然現象により被害を受け死亡した住民の遺族に対して支給する。被災後三か月間生死不明の者は、該当者と推定する。主たる生計維持者は500万円、それ以外は250万円である。」(by災害弔慰金の支給等に関する法律)
ということでした。震災関連死を認定するのは、被災した市町村または都道府県に設置された審査会で、その費用は都道府県と国が併せて四分の三ほど負担する、と。 てことは残りは被災した市町村???
<東日本大震災における震災関連死データ>
認定数:全国 2688人(2013年3月)
県別認定数:福島761人 宮城636人 岩手193人 茨城32人 その他10人(2012年3月)
認定率:福島75% 宮城66% 岩手39%(県別。2013年2月) ←福島、宮城70%岩手60%という説も。
認定者年齢:~20歳4人 21~65歳168人 66歳以上1460人
認定者死亡時期: 被災から1週間以内355人 1ヶ月以内511人 3ヶ月以内458人 6ヶ月以内235人 1年以内73人 1年6ヶ月以内156人
<東日本における震災関連死の特徴>
●認定者の死因の9割は既往症や医療不足によるもの。自殺は現時点で13人のみ。
●認定者の9割は高齢者。70歳代80歳代と年代が上がるほど多くなる。
●現在も避難区域の高齢化が進んでいる。若年世代や子どもの転出が背景か。また、震災関連死も増加している。
●岩手県の認定率が低いのは、岩手県審査会に委ねている市町村がいくつかあるから。現地にいなければ、被災の実態が理解されにくく、認定が厳しくなっている。 →市町村単位の設置は困難でも、せめて沿岸の広域振興局に置くべきとの意見も。
●阪神淡路大震災における震災関連死は、921人。東日本大震災の震災関連死は、戦後最大となる。
東日本大震災から2年半を経て。この震災はいまも終わりが見えていません。7年後のオリンピックを日本中で楽しめるように、これからの日本のありかた、政治を選択していかなくてはならないと強く思いました。
以下、参考にしたサイト様_(._.)_
- 復興庁 日牛日本大震災における震災関連死に関する報告 http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat2/sub-cat2-2/ ←震災関連死を数値で捉えることができます。最初と最後の頁がおすすめ。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S48/S48HO082.html
- コトバンク 震災関連死 http://kotobank.jp/word/%E9%9C%87%E7%81%BD%E9%96%A2%E9%80%A3%E6%AD%BB
- 福島民報 避難区域の高齢化加速 http://www.minpo.jp/news/detail/2013091610904
- 岩手日報 震災関連死認定、本県は39% 被災3県で最低 http://www.iwate-np.co.jp/cgi-bin/topnews.cgi?20130919_9
- 日経メディカル 「震災関連死」の定義が決定 http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/all/hotnews/int/201205/524916.html
- 毎日新聞 日弁連、震災関連死で意見書 http://mainichi.jp/area/iwate/news/20130919ddlk03040006000c.html
PR
キーワードサーチ
カレンダー
January , 2025
December , 2024
October , 2024