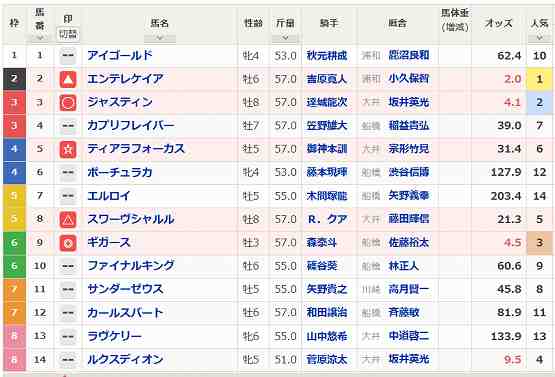25話 【捲土重来】
25話 (柾) 【捲土重来】―ケンドチョウライ―
16時台のコスメ売り場には学校帰りの女子高生の姿が目立つ。
一風変わったデザインは、名の知れた有名な進学高の制服だ。二三人の友達連れが何組か、売り場を行き来する。
「これカワイイ」「あれも欲しい」「でもお金が足りない」と一喜一憂する彼女たち。
もう化粧をする年頃なのかと驚いたのは、この売り場を任された昔のことだ。いまではすっかりそんな光景にも慣れていた。
商品の新規陳列レポートを確認しながら売り場を廻っていると、1人の女子高生が商品を手に取っているのが目に入った。
彼女は躊躇いもなく、それを制服の上に羽織ったグレーのカーディガンポケットに忍ばせる。
(――ちっ。万引きとは、またイヤな場面に出くわしたものだ)
やれやれと思いつつも、≪万引きに関するマニュアル≫に則り、しばらく様子を見ることにする。
ひとつ腑に落ちない点は、彼女の態度だ。どことなく目がぼんやりしていて、切羽詰まった様子は見受けられない。
ひとの気配や監視カメラを警戒しながら盗るのが定石なのに、彼女は周囲などものともせず、堂々と盗みを働いた。
(常習犯か?)
そんな考えも一瞬頭をかすめたのだが、長年の勘が『彼女は常習犯ではない』とシグナルを発している。
何にせよ、見張り続ける必要があった。
やや離れた位置から彼女を尾行する。歩く速度は早くもなければ遅くもなく、恐ろしいぐらいに普通だ。
僕以外の者がいまの彼女を見たところで、こんな有名進学校生が万引き犯(仮)だとは、誰も夢にも思うまい。
例えポケットに入れてしまったとしても、あとで商品を戻せば見逃せるのだが、一歩でも外に出れば万引きの成立だ。
(さて、彼女はどうするのか)
呆気なく店から出た。こうなるともう、彼女を庇う理由はない。
PHSで容赦なく保安係の投入を要請し、万引きの現行犯として、保安室まで連行してもらった。
***
「どうなった?」
件の少女を任せた保安員に経過を尋ねると、およそ保安員には見えないミニスカートを穿いた女性は軽い溜息をついた。
「大人しいもんよ。素直に犯行を認めたわ。初犯だから警察も呼ばなかった。学校にも連絡はしない。
ただ、母親には連絡したわ。母子家庭だそうで、勤め先からこちらに向かってる最中よ。厳重注意で終わりそうね」
「注意だけで済みそうなのか?」
「反抗も、抵抗もしないし、反省してる。
母親が来たら、管理職立ち合いのもと、盗んだ商品を買い取って貰って、誓約書にサインして貰うことになるわ」
「彼女、まだ隣りの部屋に?」
「えぇ、いるわ。母親が来るまであと50分はかかるそうよ。それまでここでモニタの監視してるしかないわ」
「商品のことで彼女と話がしたいんだが、可能か?」
「構わないわ」
保安員はどうぞとばかりに手の平を保安室のドアに向け、僕の入室許可を出した。
***
18時。時間を確認してから保安室に入る。狭くて殺風景で、簡素なものしかこの部屋にはない。
彼女は椅子に座ったまま微動だにしなかった。
誰が出入りしようが自分には関係ないとでもいうような心の断絶を感じた。
机の上には、彼女が盗った口紅が置いてあった。はっきり言って、全く人気のないシリーズだ。
「やぁ」
さっきまで保安官が座っていたであろう椅子に腰掛けると彼女に話しかけたが、反応はない。
(こんな調子で本当に会話が成り立ったのか?)
名前や年齢を尋ねても、彼女は返事を寄越すどころか視線すら動かさなかった。取り付く島もないとはこのことか。
机に置かれていたファイルに目を通す。要注意人物リストの一番上には既に彼女の名前と写真がファイリングされていた。
『神木彩/カミキアヤ/17歳/名古屋市×××高校在学』云々。
前髪が邪魔をして表情は見えないが、染めていない髪、短くないスカートなどは、生徒手帳に記載された規定そのものだ。
「神木さんとやら。なぜこれにしたんだ?」
その問いに、神木さんは微かに顔をあげた。僕を見る目にはマスカラも無塗布で、僅かに震える唇はグロスも注していない。
「キミが盗んだこの商品は、僕が言うのもなんだけど、何で置いてるんだろうっていうぐらい全く売れないものなんだ。
どうせ盗むなら、高価なものや、人気の高いものの方がいいに決まってる。だからそれを選んだキミが不思議でならなくてね」
ようやく彼女は、蚊の鳴くような小さな声で「知らない」とだけ告げた。
「知らない? 何を知らない?」
「他の商品なんて知らない。メイクの仕方なんて、分からない」
ちらりと視線を動かせば、机の上にはファイルとは別に、高価そうな参考書や問題集が累々と積み上げられていた。
どうやら保安員は身体検査に加え、鞄の持ち物検査もしたらしいが、それがそのままの状態になってしまっている。
(しかしこの量とは……。さすが、県内でも優秀な進学校なだけあるな)
ファイルの犯行動機の項目には『なんとなく』や『よく覚えていない』という曖昧なことばしか並んでいない。
こうなると邪推するしかないのだが、学業に励むあまり、参考書を買い続けてコスメを買うお金がなかった口だろうか。
あるいは有名な進学校の生徒だ、成績のことでムシャクシャしていたのかもしれない。
勉強ばかりでオシャレのおの字も知らず、今回たまたま魔が差した――。そんなところだろうか?
(ふむ)
「ここで待っていてくれないか」
僕の問いかけに、神木さんは不安げな顔で小さく頷いた。
ドアを開けると、隣りの部屋で監視モニタを凝視していた保安員が尋ねてきた。
「あら、柾さん。話は終わった?」
「悪いが、もう少しだけ話がしたいんだ。いいかな?」
「変なことさえしなければね」
「恩にきる」
保安員はなおもモニタに視線を送り、店内に異常がないか、全神経を研ぎ澄ませている。
その横を突っ切ると、コスメ売り場に向かった。
***
机の上に、新品のコスメ類を並べていく。
いまやメーカーの顧客争奪戦は苛烈の一途をたどり、いかに一瞬にして目を引くかを意識して作られている。
結果、凝ったデザインの容器が多いわけだが、彼女も例外ではなかった。
彼女は僕の予期せぬ行動に唖然としていたものの、目の前に散乱する見慣れない『宝石』の美しさに目を瞠った。
中でもペン状のようなものを見つけ、不思議そうにしている。
彼女にとってはさながら参考書にラインを引くためのマーカーペンにしか見えないのだろう。
「蓋を開ければ違いに気付くと思うが、パッと見ただけではまず分からないデザインだろう? それはアイラインだ」
「……名前は聞いたことがあります。アイラインってこんな形をしてるんですね」
やっと感嘆めいたことばを引き出すことに成功した。
「顔をあげて」
「?」
「十分綺麗な目だ。左目を閉じて」
驚いた彼女は、身をよじろうとした。
「動くな。じっとして」
「!」
そんなつもりはなかったのだが、彼女には鋭い声として響いたかもしれない。彼女は怖々と椅子に座りなおした。
じっとしていることを確認してから左目にラインを施す。続いて右目も同じように。
「鏡はあるか?」
キャップを閉めながら聞くと、彼女は首を振った。化粧とはとことん無縁なのだろう。綺麗な肌をしているだけに意外だった。
「じゃあこの手鏡を持って。これがキミだ」
手鏡を渡すとおずおずと自分の顔の前に近付けた彼女は、己の姿を確認するなり「これが?」と驚き、何度も目を瞬かせた。
まるで固い意志を持ったようだろう? と聞くと、首肯する。
「鏡を置いて、顔をこっちに向けて」
一瞬逡巡した彼女だったが、言われた通り鏡を机の上に置くと、身体をこちらに向けた。
「次はアイブロウ。エキゾチックな顔立ちだし、オレンジゴールドが映えるかもな。単に僕の好みだが。
今度は口を少し開けて」
恥ずかしそうにしつつも微かに開いた唇に、スパチュラで切り取った口紅をリップブラシに付けながらなぞっていく。
「ティッシュを軽く噛んで」
きゅっとティッシュを噛ませ、はみ出た箇所は拭ってやる。下唇の中央にだけグロスを施し、これで唇は完成だ。
「さて、アイシャドウはどれにする? 選んでみるか?」
戸惑っている彼女は、ふるふると顔を横に振った。降参のポーズのつもりなのだろう。
「神木さんはイエローベースだからな。ここはカーキにしてみようか」
パウダーアイシャドウを瞼に乗せ、グラデーションを作っていく。多少時間はかかったが、その分綺麗に塗れたと思う。
「ほら、どうだ?」
手鏡を彼女に向けてやる。
普段の自分とかけ離れた姿を見て戸惑ってはいるものの、瞳の奥に宿った喜びの光は隠し切れていない。
(あぁ――そうだった、僕はこの瞬間が好きなんだ)
生かし切れていない魅力を引き出し、自分は綺麗なのだと気付かせてあげる手助けをしたくてコスメ売り場を希望した。
初心に戻れた気がして、胸に熱いものが込み上げてくる。これはしばらく味わっていなかったもの――『手応え』だ。
(まさかこんな感情が再び芽生えるなんて)
チーフになってからは統括業務に忙しく、美容部員の仕事から完全に手を引いていただけに、純粋に楽しく思える。
(今度、最新の知識を吸収しに、化粧品会社のメイク勉強会に参加するか)
最近はまんねりなルーチンワークが祟り、勤務意欲の乏しさにどうしたものかと危機感を抱いていたところだった。
だから今回、目標ができたことが嬉しくもあり、まだまだ向上心を失っていなかった自分が誇らしくもあった。
「これが……私?」
「キミだよ。間違いなくね」
「嘘みたい。だってこんなの……いつもの自分じゃない……! まるで雑誌に載ってる子みたい……」
「綺麗だ」
「お、お世辞は結構です……」
急に顔が真っ赤になり、慌てた様子で伏せるように手鏡を机に置く。
「お世辞じゃない。勉強もお洒落ももっと楽しめばいい。誰も止めやしない。綺麗な子が増えれば世の男が喜ぶ。それだけさ」
「でも……! お母さんが……お母さんが、勉強を疎かにしてはいけないって。
私、お金を使うたびにお小遣い帳の記入をしなくちゃいけないんです。でもメイク道具なんて買ったら絶対怒られる。だから……」
しゅんと項垂れるところを見るに、それが動機の根幹に繋がっているのかもしれないと僕は思った。
おしゃれに憧れる一方で、母への期待を裏切るわけにはいかないジレンマ。
『うつつを抜かしている場合ではない』と己を叱咤するも、煌びやかな売り場は年頃の少女にはいささか刺激が強すぎた。
心に閉じ込めていた羨望が溢れ出し、今回万引きという手段に手を染めることになってしまったのだろう。
「お洒落をすると、勉強が疎かになるのか? 院まで行ったが、そんなおかしな方程式は知らないな」
彼女がハッとした顔で僕を見返した。そんな考え方もあるのかと、初めて気付いた様子で。
「逆にその発想がよろしくない。そんなに堅く考えてしまうと、ますます自分を追い込むことになるぞ。さっきのキミみたいに」
「……ごめんなさい」
深く反省しているようだ。決して涙は見せず、歯を食いしばって、自分がしたことの罪の重さを認識しているようだった。
きっと彼女は大丈夫だろう。そんな根拠のない自信が、なぜか僕の胸を満たした。
(今回は警察に通報しないケースだったな。その場合だと、学校に報告するかしないかは生徒の任意次第、だっけか)
「……あぁ、そうだ」
危うく忘れるところだった。一緒に持って来たクレンジングシートを手渡す。
「これでメイクを落とすんだ」
「え……でも……」
せっかくの変身が解けてしまうことを残念がっていることは、手に取るように分かった。
だが彼女の場合、それではいけないのだ。僕は懇々と説き伏せる。
「じきにお母さんが見える。その時にそんなメイクをしていたら、心からの謝罪も嘘臭く聴こえてしまうぞ。
名残惜しいだろうが、いますぐそのシートでメイクを全部落とすんだ」
「で、でも……せっかく……貴方が……褒め……褒めてくれたのに」
(なんてことだ。ここで泣くのか?)
万引きの説教時には涙すら見せなかったというのに。
彼女に女性としての片鱗を見たような気がした。蝶は羽化したことで羽根を広げ、羽ばたきたがっている。
ならば僕はその手助けをするより他に道はない。
「2週間後の土曜日、午後15時、コスメ売り場だ。どうだ、来れそうか?」
彩はきょとんとしていたが、次の瞬間、こくんと頷いた。
「よし、いい子だ。しばらく辛い日々が続くだろうが、2週間後にまたメイクをしてあげるから。頑張れるね?」
「……はい!」
「もし売り場に僕の姿がなかったら、近くのスタッフに『柾を訪ねてきた、アポ済みだ』と言えばいいから」
「分かりました。柾さんですね。……柾さん、今日は本当にごめんなさい。でも……ありがとうございました」
「あぁ。じゃあな。2週間後に会おう」
この約束が彼女にとっていい方向へ向かえばいいと願わずにいられない。
僕はコンコンとドアを叩き、隣りの部屋を開ける。
「あら。もう用は済んだ?」
「あぁ、済んだよ。ありがとう」
まだ仕事が残っているし、これ以上ここに留まるわけにはいかない。保安員にお礼を言い、退室した。
***
2週間があっという間に過ぎ、約束の土曜日午後15時になった。
そろそろ来る頃かと思い、売り場で陳列の作業をしていると、彩は時間通りに現れた。
今日は私服姿だ。白いワンピースに、黄色のカーディガンを羽織っている。
「あの……柾さん、こんにちは。その節は、本当に申し訳ありませんでした」
まっすぐに僕の目を見、頭を下げる。
「神木さん、髪切ったんだな」
指摘すると、頭を上げた彩は照れくさそうにボブカットの毛先に触れた。
「はい。あれから親にこっぴどく叱られて、私が悪かったこと、ちゃんと反省していることを伝えました。
学校にも報告して、……優秀な君が? って驚かれちゃったけど……もう期待を裏切る真似はしないと誓いました。
謹慎処分や退学処分を覚悟してたんですけど、ずるいことに反省文5枚の提出だけで済んでしまいました。
髪を切ったのは、私なりのけじめです。できれば、学校にはもっと重く罰して欲しかった……」
「誠意が伝わったんだ。上辺だけじゃなく、心の底から深く反省していることが。ありがたいことじゃないか」
「はい。もう私、二度とぐれたりしません。親も学校も私を気にかけて、心配してくれていることも分かりましたし。
それもこれも、柾さんのお陰です」
「僕の?」
「そうです。柾さんが私の気持ちを肯定してくれたこと、本当に嬉しかったんです。
勉強の大切さも否定せず、その上でおしゃれすることもこれから頑張れって仰ってくださいましたよね。
必死に机に齧りついてきた今までの私の行為は決して無駄なんかじゃなかった、そう思ったら報われたような気がしました。
柾さんの言葉が、ストンと胸に落ちてきたんです」
「そう言って貰えて、僕こそ嬉しい」
彼女の目は既に前を向いていて、きらきらと眩しかった。
これなら本当に大丈夫だろう。
「今日キミに来て貰ったのは他でもない。キミさえ良ければ、メイクをしていかないか?
今日は、特に腕のいい美容部員が出勤してるんだ。彼女はあらゆる賞を総なめにしているほどの実力者でね。
普段は指名客によって予約が埋まってるんだが、15時から16時まではスケジュールを空けて貰った。
キミがメイク体験を望むなら、いますぐ彼女を呼び出すよ」
店内用のPHSを取り出し、短縮番号を押せるようにスタンバイする。
「あの……それは……、メイク体験はとても魅力的で……ぜひお願いしたいです。でも……」
「うん?」
「あの……せっかくですけど……その女性じゃなくて……あの……出来れば柾さんがいいです。……駄目ですか?」
「僕?」
「私、出来れば柾さんにもう一度お願いしたいです……!」
顔を真っ赤にしながら彩は訴えた。まさかそんな提案をされるとは思わず、僕は虚を突かれる。
「いや、だが僕はそんなに巧いわけでは……。多忙を理由にメイク講座の受講もさぼっていたし……」
「でも、この間の柾さんのメイク、私、とても好きだって思いました。だ、だから……」
たどたどしく自分の想いを綴る少女に対し、これ以上ノーと抗い続けることは、僕の美学に反した。
「――光栄だ。分かった、僕で良ければ」
「はい! 柾さんがいいです」
ホッとしたように、くしゃりと笑う。笑顔は満開のひまわりを彷彿させるほど明るい。
「きっと、もっと綺麗になるんだろうなぁ」
「え?」
「いや、何でもない。じゃあこっちに来て」
いやはや、恐れ入った。本当に、女性が花を咲かすのは早い。あっという間だ。
彩はこれからどんどん綺麗になっていくことだろう。
***
彩の帰り際、重いけど持てる? と、コスメケースを渡した。
「こっちの勉強も、後々必要になってくるから」
「これは……?」
「僕からのプレゼント。自分で研究してみるんだ。こればかりは、実践あるのみだから」
中を開けると、彩の口から感嘆の声が零れた。
ケースの中には化粧水から乳液、クレンジングオイルに始まり、メイク道具が一式詰め込んである。どれも新品だ。
実は千早歴が好きなブランドのラインで揃えてみたのだが、それは僕だけの秘密だ。
「でも、こんなに沢山……! とても素敵だと思います。めちゃくちゃ嬉しいですし。でも、何だか申し訳なくて……」
「キミを数時間拘束してしまったお詫びと、勝手に女の子の肌に触ってしまったお詫びだ。もう無茶はするなよ」
「ありがとう……ございますっ……! 本当に……本当に、ありがとう、柾さん!
せめてもの罪滅ぼしというか、お礼に、私、これからは柾さんがいるところで化粧品を買いますね。
こんなに良くして頂いたのに、それぐらいのお礼しか出来なくてごめんなさい。また相談に乗っていただけると嬉しいです」
「いつでも歓迎するよ」
僕のことばに、彩は二度目の笑みを見せた。心強くも未来を信じている顔だ。
おめでとう、新たなる彩り豊かな女性の誕生だ。
改稿2018.04.19
© Rakuten Group, Inc.