全177件 (177件中 1-50件目)
-
07月29日 ■ 伊神十御
07月29日 ■ 伊神十御(1)朝目が覚めて枕元に置いてあるスマホで時間を確認すると、メールアプリの通知数が異様に多いことに気付いた。今日が自分の誕生日だと気付いたのは、そこ宛てに届けられたお祝いメッセージの数々だった。幸せを噛みしめるように1件ずつ読んでいく。ほとんどがユナイソンの社員からで、この後すぐ会えるのにこうして送ってくれるなんて、とてもありがたい話である。とは言え、お礼を返している時間はあるだろうか。今日は早番。そろそろ準備をしなくては――。そうこうしている内に未読メッセージが最後の1件になった。中国の『万里の長城』をアイコンにしているアカウントからだ。けれども見覚えはない。「……誰かがアイコンを変えたのかな……?」不思議に思いながらもタップすると、見知った名前が視界に入った。万里。「な……、まさか……」ここ数年、ずっと連絡を取りたかった相手だ。自分の耳に届く、どくんどくんと早鐘のように鳴り響く心臓。思わぬ展開に胸がざわめき出し、変な汗が溢れ出してきた。文章は一切なくて、どこかへ誘導するURLのリンクだけが貼られている。一瞬、これはフィッシング詐欺ではないのか、とも疑った。果たして連絡を取りたいと願っていた相手から、こうも都合よく接触してくるものだろうか?だが間違いなくメッセージの送り主は『万里』になっていて、だとすれば本人に違いない。震える指がURLの上を彷徨っていると、突然スマホがアラーム音を発した。オレの心臓はさらに高飛びし、「うわっ」と声を漏らしてしまった。よくよく見ればなんのことはない、出社5分前を知らせるタイマーだ。「やばい!」すっかり気を取られていて、準備のことなど完全に失念していた。スマホを閉じると通勤バッグの中に突っ込み、慌てて身支度を整え始めた。朝食は抜くしかない。(2)何とか遅刻は免れたものの、仕事中はつい注意力散漫になってしまい、各方面から「どうしたの?」と心配されてしまった。気を引き締めねばと己に言い聞かせても、浮ついた心は消えてはくれない。それどころか早く昼休憩になってくれないだろうかと願う始末で、完全に上の空状態になってしまっていた。やっとその時間を迎えると、弁当箱とスマホを持って一目散に社員食堂へと向かった。早速目についた空席に座り、弁当はテーブルの脇へ。目下、重要度を占めているのはスマホの方だ。アプリを起動させて件のアイコンをタップ、再びURLのところまで進める。深呼吸をして、とうとう押してしまった。すると、『♪Happy birthday to you.』「……!!??」まさか動画サイトに繋がり、勝手に流れ始めるとは夢にも思わず、完全に度肝を抜かれた。公衆の面前だ、早く止めないと!『♪Happy birthday to you,Happy birthday, dear Togo,Happy birthday to you.』音量は大。テノール歌手が歌っているかのような張りのあるバースデーソングが社員食堂内に響き渡り、慌てて停止ボタンを押した。今朝味わったものに劣らない、ばくんばくんと鳴り打つ心臓。もう何がなんだか理解が追いつかない。それでも顔を上げれば、しんと静まり返ってはいるものの、従業員たちの視線は全てオレに注がれていた。そんな中、「……っふふ、あはははははっ」と爆笑し始めたのが、少し離れた席にいた八女さんだった。(3)「笑い過ぎッスよ」八女さんの対座にいた杣庄くんが嗜めてくれたお陰もあったのだろう。八女さんは首を竦めると、「ごめんごめん」と謝りながらオレの方に小さく手を合わせてくれた。でもオレにしてみれば、場の空気が白けるよりも、誰かが笑ってくれた方が救われるし、ありがたい。首を横に振って『気にしてないよ』と伝えると、八女さんは杣庄くんを連れてオレの席へとやって来た。「伊神、改めて誕生日おめでとう」「おめでとうございます、伊神さん」「2人とも、ありがとう」「ところで、何を観てたの?」やすが八女さん、耳聡い。バースデーソングの『十御』部分を聞き逃さなかったようだ。「あぁ、うん……。実は、とても珍しい子からメッセージが届いてたんだ。でも文章はなくて、URLだけでさ。タップしてみたら急に動画が流れ出したものだから、ビックリしたよ」「そうだったんスね」紙コップに注がれたコーラを飲みながら相槌を打ったのは杣庄くんだった。「貴方宛てにバースデーソングを歌ってくれるなんて嬉しい話じゃない。しかもオペラ歌手並みに巧かったし」「あぁ、それは……声楽を習っていたからね、彼は」「へぇ。道理で巧いはずだわ。ねぇ、動画もう1回見せて!」八女さんにせがまれる形ではあったけれど、オレもちゃんと観ておきたかった。今度はボリュームに気を付け、このテーブルだけに聴こえる音量に調整する。再びURLをタップすると、動画が流れた。『♪Happy birthday to you,Happy birthday to you,Happy birthday, dear Togo,Happy birthday to you.』「……これだけ? しかも本人登場せず?」八女さんたちが物言いたげにオレを見つめるのも当然だ。背景はどこかの部屋の壁が映っているだけなのだから。「いや、まだ続きがあるみたいだぜ」杣庄くんの指摘を受けて動画の下部分を見てみると、再生時間は計3分になっていて、まだ折り返し地点のようだ。「ほんとだ」でも歌声の主が現れる気配はない。ただの編集ミスかと思った矢先、ひょっこり画面の横からのぞき込むように男の顔が現れた。こちらに手を振っている。『ハーイ、兄貴! 元気かい?』「……アルッシュ!」こちらの声が届くわけないのに、咄嗟に呼び掛けてしまう。オレに似た癖毛で、褐色肌。母譲りのくっきり二重で、切れ目の眼差しが面白そうに笑っている。のりの利いた白いシャツにはアイロンがかけられていて、相変わらず身だしなみに気を遣っている気配が窺えた。『俺と連絡を取りたがってるって、マーンから聞いてね。今日は動画を送ってみたよ。どうだっただろう? 驚いてくれたかな?』あぁ、ほんとに驚いたよ! 思えばいつも神出鬼没なんだから!『兄貴、誕生日おめでとう。最近はどう? アマヤから近況は聞いてる方だけど、タイムラグがあるからね。今も日本住まいかな?』ここで軽い咳払いが入る。『俺は見ての通り、元気そのものだ。だから心配しないで。ここは日本から何マイルと離れているけど、心はいつも兄貴を想ってるよ』その割に、今の滞在先を教えないじゃないか。『じゃあ、またね。バイバイ! ♪Happy birthday to you.』バースデーソングの最後のワンフレーズで締め括られ、動画は終わった。「……はぁ~、びっくりした」「じゃないわよ。訳しなさいよ。さっきのヒンドゥー語だったじゃない」隣りから八女さんの突っ込みが入り、言われてはたと気付く。もう1度動画を流しながら訳していくと、『マーン』とは何かと訊かれたので、お母さんという意味だよと教えてあげた。「本当に今のが貴方の弟さんなの?」「そうだけど……どうして?」「いえ、顔立ちは似てると思うんだけど、やけに陽キャだから……」「なるほど。でも名は体を表すって言うじゃない? 彼の名前はアルッシュ。伊神・アルッシュ・万里(ばんり)。アルッシュって言うのは『勝者、太陽からの日差し』という意味なんだ。因みに、双子の妹がいるんだけど――」「えっっっ、そうなの!!??」何故だか前のめりに食いつかれ、「う、うん」と頷く。「妹の名前が、さっき出た『アマヤ』だよ。伊神・アマヤ・千里(せんり)。アマヤは『夜の雨』という意味なんだ」「綺麗ッスね。王様に、太陽の日差しに、夜の雨か……。しかも日本名の方は、十、千、万って単位で統一してるんスね。面白いなぁ」「伊神のラジュ(王様)って言うのが未だにピンとこないんだけどね。性格が優しすぎて」それにはオレも苦笑いするしかない。「でもま、優しい王様って素敵だと思うわ」笑みを向けられ、オレとしてもホッとする。そう言って貰えるとありがたい。「ところで弟くんの……万里くんが言ってた、『連絡を取りたがってる』ってどういうこと?」八女さんとしてはアレッシュ呼びよりも万里と呼ぶ方がしっくりくるのだろう。オレは、その逆だった。「それがさ、どうやらアレッシュはオレに居場所を知られたくないみたいで、どこにいるのか教えてくれないんだよ」「居場所を知られたくない?」「オレも本人から聞いたわけではないんだ。妹が言うには『アレッシュは兄貴越えするまでは連絡を取りたくないって言ってる』そうでさ」「あらら。万里くんにとって、お兄ちゃんは越えるべき存在なのね」「オレからしたら、とっくの昔に越えてるよ、って思うんだけどなぁ」「俺、伊神さんの器は相当デカいと思いますもん。さすが王様ってだけあって、そう易々とは抜けれないんじゃないッスかね」「杣庄の言う通りかもね」「……2人とも、これ見てて」そう言ってスマホを2人に見せる。2人が身を乗り出し、画面を覗き込んだのを確認すると、アレッシュが送ってきた宛先に対し「Thank you.」と入力し、送信ボタンを押した。ところがエラー表示が出て『送信不可』という文字が表れる。「え? 送信不可?」「早速アレッシュがアドレスを代えたんだよ」「……はぁ!?」「うわ……。まさか連絡を取りたくないって……そういう意味ッスか! えぐいなぁ~」「どういうことよ、杣庄」「つまり、伊神さんは弟さんにメッセージを送ることが出来ないってこと。常に一方通行なんスよ!向こうは伊神さんのアドレスを知っているから――伊神さんがアドレスを変更しないって分かってるから――いつでも送ることが出来るけれども」「な……。えっ……?」杣庄くんの推理内容が思いもよらないものだったのか、八女さんは軽く絶句した。「ご明察だよ、杣庄くん」「斜め上を行ってるわね~。そこまでして兄貴越えがしたいの? さては筋金入りのブラコンね?」「決してブラコンではないと思うけど……。だからまぁ、この動画はオレにとって、何よりも大切なプレゼントなんだよね」オレが苦笑すると、八女さんはわしゃわしゃと頭を撫でてきた。それはまるで『よかったわね』とも『頑張りなさいよ』とも受け取れるボディーランゲージで。オレとしては、またひとつ、素敵なプレゼントを貰ったような気がしたのだった。2021.07.29
2021.07.29
コメント(0)
-

本を作りました!
最大の目標は、『Gentleman』を1冊の本にすることです。これがずっと昔からの夢でした。自費出版とかぼんやり考えていて、でも半分諦めかけていたのですが、今年はその夢が叶うよう、情報などを集めて、実現に向けて何とか理想の形に近づけるよう頑張ってみたいです。この大きな夢をいきなり叶えるのは難しそうだったので、まずは段階を踏んでいこうと、短編で本を作ることにしました。文字数にして約1万字。見事、36頁の本が出来上がりました!本日完成品が手元に届いたのですが、きちんとしたカバーもあり、憧れのくるみ綴じ処理が施してあり、ちゃんと『本』の形になっています。パラパラ中をめくった瞬間、こう……何て言うんだろうな?「すごい! ヤバい!」と語彙力喪失気味の感想しか出て来なくて。めちゃくちゃテンション上がっちゃいました。誤字脱字があるといけないので、1冊のみ刷りました。でもこれ……いざこうして本にしてみると、周囲に「見て見てー! ちょっと作ってみたのー!」と触れ回りたい気分になっちゃいますね😊――と言いつつ、私が趣味で小説書いてることは、片手ほどの人数しか知らないのですが……(汗)それにしても、楽しい作業だったなぁ♪久し振りに校正して、文章整えて、写真の配置とか考えたり、表紙の色を決めたり……。(表紙、赤にして大正解でした🍎)1万字くらいが、ちょうど私に合ってるのかもしれません。大きな夢に、一歩近付けた気がします♡2021.03.09 花夜(かや)
2021.03.09
コメント(0)
-
2021年、正月記す
明けましておめでとうございます。まさかこちらを更新する日が来ようとは……いやはや、自分でも驚きです。昨年、1つ前のエントリで、『いまはブログも一切やっていないですし、ツイッターも呟かなくなったので、(中略)ひと段落したら、またなにか自分の想いを発信する場所を確保しようかな』と記しましたが、夏からブログを、秋から別アカでtwitterを始めておりました。「やっぱり作ってたのね」という声が、どこからか聞こえてきそうです。すみません。常に何かしら、こそこそ運営してます……。自分にはスクラップアンドビルドを繰り返す悪癖があり、『公表してもすぐに壊すようでは、ひとさまにご連絡を差し上げたところで申し訳ないな』と思い、一定期間続けてこられた暁には告知をしよう! と、そんな腹積もりでいました(事実、夏から始めたブログ、既に1回壊してます)。ただいま、いつ告知させていただこうかと考えている最中です。えぇと、ここを更新しようと思った理由ですが――。今年は執筆活動をしたいなと思いまして、その決意表明をしに参りました。ちっとも動かない自分を追い込みたかったという気持ちもあります。具体的に『何を』とまでは決めていないのですが、・『Gentleman』の各キャラ誕生日話の完成・『Gentleman5』を新たに書き始めたい・『Liar Wolf(※旧タイトル『ENSLAVE』から変更しました)』・以前から書いてみたいと思っていた『民俗ミステリ物』以上の4つです(他の書き掛け小説も書けたらよいのですが……)最大の目標は、『Gentleman』を1冊の本にすることです。これがずっと昔からの夢でした。自費出版とかぼんやり考えていて、でも半分諦めかけていたのですが、今年はその夢が叶うよう、情報などを集めて、実現に向けて何とか理想の形に近づけるよう頑張ってみたいです。ではでは、言った割にあまり表に出て来ないかもしれませんが、本年もよろしくお願いいたします。2021.01.04 花夜(かや)
2021.01.04
コメント(2)
-
完了しました!
はい! これを以て【Gentleman】の改稿作業を終了いたします!あー、長かった! 丁度2年掛かりました! ビックリ!!あとは、設定関連の修正を終わらせるぐらい……かな。がんばった! よくがんばったよ、私! うん! 明日はケーキ食べような!こうやって日記めいたものを書くのも、ここでは数年振りですね。いまはブログも一切やっていないですし、ツイッターも呟かなくなったので、こうして『自分のことば』を書くのも随分と久しい行為です。なんだかどきどきするなぁ……!ひと段落したら、またなにか自分の想いを発信する場所を確保しようかな。この物語を読んでくださっている方がいらっしゃるのかどうか分からないのですが、取り敢えず、少しは読みやすくなった……と思います。いや、そう思いたい……!ではでは。また水面下に潜って作業を続けますが、以上、業務連絡でした。北摂かや
2020.02.22
コメント(0)
-
06月02日 ■ 児玉菫
06月02日 ■ 児玉菫カーテン生地で一切の光を遮った、ホコリ臭い実験棟。私はそこで、3日に及ぶ観察実験を行っていた。助手たちが黙々と器材やシミュレーションレポート、コンビニ弁当や栄養ドリンクを運んで来たりしてくれる。実験中は、形振り構っていられない。束ねていた髪はいつの間にかほつれ、顕微鏡を覗き込みすぎて、目元周辺はパンダ目になってしまっている。そんな私の唯一綺麗な部位と言ったら、気分を変えるためと眠気覚ましのため数時間置きに磨く、歯ぐらいなものだ。「スミレさん、荷物が届いてますよ」「ごめん、今寄らないで。匂いに自信がないの」「俺が代わります。一番近いスーパー銭湯で、湯浴みでもしてきて下さい」「もうちょっとしたらね」「強情だなぁ」背後からにゅっと手が伸びてきたかと思えば、パソコンに打ち込んでいたデータを保存してしまった挙句、ソフトを閉じてしまった。「何するの、岩代クン!」強引な手口に、反論してやらねばと振り向いた。思った以上の至近距離に、助手の岩代甲斐はいた。切れ長の目が合う。淡々と彼は言った。「そこは、『甲斐』でお願いしますと何度も……」はぁやれやれと、呆れたように。「まだプライベートの時間じゃないのよ、岩代クン」「続きは俺が。だから休んで下さい。もう限界でしょう」「イケるわよ。全然余裕よ。なにを言われたって、一段落つくまでは休みませんから」マウスを握り直し、ソフトを再起動。すると突然、髪を掻き分けるように、頭をわしと掴まれた。細くて長い指、それなのに力強いそれは、岩代クンのものだった。「何するのっ」耳に近付いてくる、彼の顔、息、唇。「俺、匂いフェチって……言いましたっけ。スミレさんの香り、堪能しちゃいますよ?」「変態ッ! やめなさい! 言ったでしょ、近寄らないでって……! こら!」彼の髪は少しだけ長くて、肩位置まである。それを結んでいるものだから、抵抗している内に髪留めのゴムを外してしまったようだ。私の腕に、彼の柔らかい黒髪がパサリと落ちる。その感触に、私は徐々に総毛立つ。恐ろしい。誰よりも淫靡で、有能で、高飛車な相手。Sを自覚していた私だけど、上には上がいる。彼は私を遥かに上回るドSだ。ここで従わなければ、岩代甲斐という人物は強硬手段に訴え出るだろう。他の助手にそんな場面を見られるわけにはいかない。「わ、分かった! 分かりましたから! 行きます、行って来ます! だから観察お願い……っ」「よく出来ました」耳たぶを舐められたかと思うと、次の瞬間には軽く噛まれていた。彼には私が怒ることが予想できたはずだ。当然、私は叱りつけようとした。けれども彼の唇は、開きかけた私の口を塞いでしまい――。「んー! んむ、むんうーぅぅ!?(なにするのよ!)」「スミレさん、続きは家で。今日は帰れるでしょう?」ちら、とデータを観て、さらりと言う。このまま何事もなければ実験が終わることを把握したらしい。「帰らない」「なんで……どうして」主導権を奪い返せた嬉しさで、私はほほほっと笑ってやった。「今日は絹ちゃんと玄クンがお祝いしてくれるの」「玄……」ピク、と岩代クンのこめかみが痙攣する。「じゃあ、今日は帰って来ないんですか?」「さぁ、どうかしら」――直パパも誘ったんだけど、来れるのかしら……。ハラハラしていた絹の姿が脳裏をかすめる。べつに直近と会ったところで昔の関係に戻る気はないのだけど。向こうも同じ気持ちでしょうし。それでも目の前の助手には思うところがあったらしく、ぎゅ、と抱き締められた。「行かないで下さい」「1年に1回の記念日よ? 子供たちと過ごさせて」「柾さんには会うんですか?」「きっと来ないわよ」「焼けぼっくいに火が」「つかないわよ」「愛してます」「光栄だわ」「好きだ」「私も」「ハッピーバースデー」「ありがと」「いただきます」「それは駄目」2013.05.272020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
06月01日 ■ レオナ・イップ
06月01日 ■ レオナ・イップ『キミには失望したよ、レオナ』満たされない。満たされない。あぁ、足りない。ダメよ、貴方では、貴方なんかでは、てんで話にならない――!“荒ければ良いだろう”。貴方、それって勢いだけよね? 私には分かるのよ、そういうの。興醒めよ。どきなさい。そして早くここから出て行って。イ尓給我走!『恨むなら、キミの情報を売った加納を恨むんだな』次。貴方はどうかしら。私を悦ばせてくれるわよね?……なによ、結局、貴方もなの? どいつもこいつも、下手、下手、下手くそね……っ!虫酸が走るわ。消えなさい! あぁ、男なんて、目障りな存在よ!『キミを失うのは悲しいよ。まぁ、キミならばこの先、その美貌でなんとかなるだろう』許せない……。許さないわ。この地位から引きずり落とした上層部、人を道連れにした加納、私を虚仮にした伊神。そう、私を破滅に導いたのは、いつだって男だった。責任を取って貰うわよ。贖いなさい、償いなさい。香港支部の王座から退陣させられた私は、今や薬漬け、アルコール浸り、性依存症。そもそものきっかけをくれたのは、伊神だったわよね?今でも覚えてるわ。私を前に、ほんの一瞬、脅えた顔を覗かせた。狂おしいほど、私の嗜虐心を煽ったわよ。ダビデ像も真っ青な、綺麗な彫刻のような肢体。最高の貢物を捧げてきた都築を、初めて偉いと思ったわ。嫌よ嫌よも好きの内。伊神が抵抗するたび、私の身体中に火が灯っていった。そんな私に貴方は何をした?最低な仕打ちをしたわよね。覚えてる?貴方、切れ切れの声でこう言ったわ。「とうこちゃん」嫉妬って、こういうことかしら?身体だけで十分だと思っていたのに、初めてよ。心まで手に入れたいなんて思ったのは。貴方は唖然とした私の隙をついて私を押しのけ、とても綺麗な声と発音で、ドインジューと謝ったのよ。そして部屋から出て行った。私とカッターシャツ、ネクタイを残して。ねぇ、今でも覚えてるかしら? 私は覚えてる。誰と寝ても、いつだって、私の脳裏には貴方がチラつくの。許せないわ。許せないわ。涙が止まらない。そんな貴方から、エアメールが届いた。よく私の居場所が分かったわね。もう香港にはいないのよ。地位を剥奪され、かれこれ半年以上落ちぶれた生活を送っている私を、よく見付けたわね。誰から訊いたの。というより、よく私に連絡を取ろうと思ったわね。2枚に渡る便せんには、丁寧な英文。あんなに綺麗な発音をしていたのに、『広東語は苦手だから』と文書の始めで断わって。あれからどんな生活を送っていますか? 無事ですか? 不便はないですか?馬鹿じゃないの。正真正銘、愚か者よね? 私が貴方なら、そもそも絶対に連絡なんて取らないし、ましてやフェイドアウトするのが当たり前でしょう。接触するなんて、信じられない。返事? するわけないでしょう。貴方はこんなことをして、何がしたいって言うの。何が目的よ? お友達になりましょう? 馬鹿言わないで。絆を深める意思もないクセに、こんな手紙を送ったって、しょうがないのよ。更生でもさせたいのかしら。そんなワケないわよね。私がこんな隠遁生活を謳歌してるって、知っているならともかく。……いえ、でも。私の居場所を突き止めたのなら、私の現状を知っていたって、おかしくはない……。……!! 許せない、知ったわね? 私のザマを、零落れた私を……!見るな、見るな、見るな! (見ないで! 貴方には知られたくなかった)貴方には、貴方だけには。(違うの、私、本当はこんな女じゃなかった――)信じて貰えない。どうせ、もう、何を、言ったって、無駄な、……。便せんの最後の言葉は、広東語で締め括られていた。生日快楽。――誕生日、おめでとう。このまま恨みを抱えて生きて行くのか、レオナ・イップよ。違う。私は気高き女。香港支店長まで登り詰めた女よ。このままでは終われない……!誓うわ。返信は広東語じゃない。英語でもなければヒンドゥー語でもない。日本語で、直接会って返事をしてあげる。素晴らしい生活を送っているわ。平穏無事にね。お陰さまで、生き易くてよ?2013.05.252020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
03月22日 ■ 麻生環
03月22日 ■ 麻生環出勤時刻が近付き、忘れ物はないだろうかと手荷物を確認する。戸締りにも注意して、最終確認のために玄関のドアに鍵をかけていると「お兄ちゃん」と呼ばれた。「おっはー。誕生日おめっとー。遠路遥々ケーキのデリバリー」デニムのダメージジーンズに、プーマのスポーティーな運動靴。色違いのタンクトップを重ね着し、その上からフード付きのパーカーを着た妹が近付いて来る。背中にこれまたスポーティーなバッグパックを背負い、両手に大きな紙袋。その中にケーキが入っているのだろう。がさつな性格に似合わず邑は料理が得意で、お菓子作りは小学生の頃からハマっていた。以来、イベントごとに欠かさず手作りのスイーツを作っては、こうして届けてくれる。「おー、やった! わざわざありがとな」「今回はそれだけのためだけじゃなくて」と言って、俺に手渡した方とは別の箱を指し示した。それは? と尋ねれば、歴ちゃんにね、と返って来た。「お兄ちゃんにはアップルパイと野菜たっぷりのスフレね。歴ちゃんには桃のケーキを作ったんだ」「さんきゅ」せっかくのケーキが痛まないよう、早々に冷蔵庫へ入れておかねばなるまい。「俺、今から仕事なんだが。ち……」ちぃ、と言い掛けた言葉が止まる。そう呼んでいることが急に気恥かしくなった。妹には知られたくない。「千早さんはどうだったかな。仕事かもしれないし、休みかもしれない」「あ、サプライズで作ったから、歴ちゃんには何の連絡もしてないんだ。歴ちゃんのケーキ、預かっててよ。でもナマモノだから今日中に渡してね。今から名古屋で友達と落ち合って遊ぶ予定でさ。もう行くね」「お前さ、俺が仕事終わってから予定入れてたらどうするつもりだったんだ?」「どうせ予定なんてないんでしょ? あったらシフト自体、休みにしてただろうし」ニヤニヤと意地の悪い笑みを浮かべる邑に、俺はどう切り返すべきか考えていると、じゃあね~と言って回れ右。駆け足で去って行った。全く、逃げ足の速いやつ。*ちぃと職場で会えればよかったんだが、今日はPOSルームに用事もなかったし、店内を移動しても彼女の姿を見ることはなかった。だが事務所に設置されている回転板は出勤になっていたので、間違いなく出社しているのだろう。持ち場所である家電売り場のレジに立っていると、潮透子嬢が前を横切った。すかさず俺は「潮さん」と呼び止める。反射的に「はい?」と答えた彼女は俺を見て、仕事を頼まれると思ったのだろう、制服のスカートポケットから小さなメモ帳を取り出した。「あぁ、悪い。仕事の依頼じゃないんだ。今日の千早さんのシフトはどうなってる?」「千早さんは早番ですよ。今日は16時半上がり」「そう。ありがとう」「いえ。失礼します」目礼をして再び歩き出した潮さんを見送り、腕時計に視線を落とす。時刻は15時半。上手い具合に接触を計れればいいのだが。*結論から言うと、ちぃとは会えなかったし連絡も取れなかった。家電製品について尋ねられ、客対応をしている内に時間はあっという間に過ぎていった。結局俺の業務が終わったのが19時で、この時間からケーキを持参したところで果たして受け取って貰えるだろうか。一抹の不安を抱え、急いで帰宅する。ちぃ用の箱を冷蔵庫から取り出すと、彼女の部屋へと向かった。ドアチャイムを鳴らす。ややしてから、ちぃがドアを開けた。ロングワンピースの上に、長袖のニットを羽織っている。珍しいことに、長い髪を左右で分けるような、両結びの束ね方だ。「麻生さん?」「アポなし突撃、すまんね。今朝邑が来てさ。ちぃの分のケーキを作ったからって。これなんだけど」「えっ、私に?」「どうもホールらしくてさ。食べ切れなさそうなら誰かと分けた方がいいかもな。でもナマモノだから早めに」「明日、兄にもお裾分けします。丁度明日来る予定になってるんです」「そりゃ丁度いいや。そういうきっかけって大切だよな。そうじゃないと疎遠になりがちだからな。俺たちみたいに」俺としては、何気なしに言った言葉だった。だからちぃが豆鉄砲を食らったような顔になったのが解せなかった。まるで理解不能のような、戸惑っているような表情だ。困惑した顔を俺に向け、「どういう意味ですか? 仲が悪い? でも、仲いいですよね……?」「よくないって。今も絶交状態だぜ?」「ぜ……。……え?」「……?」話が噛み合わなくて、俺達2人は眉根を寄せる。やがて1つの結論に辿り着いた。あぁそっか。「……悪い。言ってなかったかも。うち、兄がいるんだ」その言葉の意味を咀嚼しているらしい。ちぃはマジマジと俺を見つめると、「え……えぇー!?」彼女らしからぬ大声で叫び、慌てて口を両手で押さえた。そしてきょろきょろと渡り廊下の反応を窺う。「ごっ、ごめんなさい。夜なのに騒いだりして。……あの、立ち話もなんですから……」そう言って、ちぃは身体の位置を僅かにずらした。「もしお時間があるなら、上がって下さい。部屋、汚いですけど……」*社宅なんだから間取りは全く一緒なのだが、インテリアは丸っきり違った。俺とは到底似付くわけもなく、ましてや妹の邑とも遠くかけ離れた、いわゆる『女性』の部屋だった。白を基調にした、淡いブルーとピンクが混じる部屋。所々にさり気ないレースが施してある物を選ぶ趣味らしい。ちぃの部屋に上がるのはこれで4度目になるが、付き添いもなく1人で入ったのはこれが初めて。ある程度家具の位置は把握しているので、ベッドの方向は視界に入れないようにした。……いや、別に俺はそんなやましい目的で来たわけじゃなくて、そもそもこうなる展開すら予想にしていなくてだな……。「麻生さん」「! あぁ、何?」「どこでもお好きなところに座ってくれて構いませんから」リビングに2人掛けのソファーがある。テーブルを隔てた正面にはテレビが置いてあって、まぁ普通はそこに座るだろうな。そこに腰を落ち着けると、ぽつんと置いてあった、リボンが縫い込んであるクッションを抱きかかえた。意外に心地いい。「夕食はもうお済みですか、麻生さん」「いや、19時に終わって速攻でここに来た」「じゃあ、まだなんですね。あの……えっと」「どした?」「……今から食事を摂ろうと思ってたところで……。私の手料理なんかでよければ、その……食べて行かれます?」おいおいおいおい、なんなんだ、この展開は?お宅訪問がお部屋訪問で夕飯一緒にだと? このままだとお風呂まで一緒になんて展開に……なるわけねーだろ。俺の馬鹿野郎。「あー……、すっげ嬉しいんだけどさ、図々しくも食べたりして大丈夫か?」「大丈夫です。さっきも言いましたけど、明日兄が来る予定だから多めにお米を炊いたんです。寧ろ今日平らげて貰えた方が、兄としては炊き直した新鮮なお米にありつける分、幸せかも」そう言って、くすっと笑う。「ちなみに今日は洋風です。おろしハンバーグに、ポトフ、サラダ……。私はこれでお腹がいっぱいになってしまうんですけど、麻生さんはもう1品2品欲しいですよね?」「いや、問題ないよ。それどころかバランスの取れた料理にあり付けて嬉しいぜ。あぁ、そう言えば部屋に邑の手土産もあるしな」「そうでした。私もすっかり忘れちゃって。……わぁ、美味しそうな桃のタルト!」箱を開けたちぃは、うっとりした目でタルトを取り出した。「でも、その前にまずは夕食ですよね」てきぱきと準備をこなし、リビングのテーブルの上いっぱいに2人分の食器が並んだ。ちぃは2人掛けのソファーには座らず、俺とL字になるような位置で正座した。俺も何となくその方がいいような気がして、ソファーから立ち上がり、カーペットの上で胡坐をかいた。「麻生さん?」「いや、俺だけソファーって何か申し訳なくて」「お客様ですもの。気にしないで下さい」「でもいいんだ。こっちのが慣れてるし。おぉ、すげぇ。どれも美味そうだ」「はい、召し上がれ」照れ臭そうに笑うちぃ。 「いただきます」真っ先に食欲をくすぐるハンバーグを頬張る。大根おろしと肉汁が絶妙で病み付きになりそうだった。「デミグラスも好きだけど、おろしも最高だな。ちぃ天才」「そんな……」はにかむちぃを余所に、俺の箸は止まることを知らず、あれもこれもと平らげてしまった。「やっぱり男性は食べ終わるのが早いですね。兄も早くて」片付けをしながら、ちぃはしみじみと言った。「そう言えば……。さっきのお話」「あぁ、それを言わないと、部屋に上げた貰っただけでなく、食事までご馳走になっちまった意味がなくなっちまうな」ちぃはコーヒーと桃のタルトを切り分けた皿をテーブルの上に置いてくれた。「さんきゅ。んーと、どこから話すべきかな……。それじゃあ、思い付いたままな」「はい」「俺は次男なんだ。兄貴がいる。と言っても兄貴は既婚者だから、戸籍は抜いてるんだ」「何もかも初耳です……」「まぁなぁ……」敢えて話題にしなかった。それは成り行きの結果でもあるのだが、こうして打ち明けることもまた、成り行きなのだろう。*「麻生摂(セツ)。俺の4個上で、融通の利かない長男坊だ。成績優秀で、俺はよく「環もお兄ちゃんを見習いなさい」って口を酸っぱくして言われたもんだ。今は美容師をしてて、雑誌が言うには『時代のカリスマ』なんだと。笑っちまうよな」「そんなに腕のよい方なんですか?」「さぁねぇ……。俺に言わせれば、腕のいい美容師より、経営のプロ、いや……鬼だな」「鬼?」「こんなエピソードがあるんだ。うちが床屋を営んでるのは知ってるよな?」「はい」「跡取り息子の長男がうちの店を継ぐ・継がないって話が当然昔からあってさ。兄貴も当初、独立なんて考えてなかった。とにかくまずは自分の腕を磨くのが先で、敢えてそういう問題を考えないようにしてたのもあったと思う。ある時親父が入院することになって、両親共々休業せざるを得なくなった。代わりに店で本格的に修行を積むようになった床屋歴3年の兄貴が店を開けたんだ。床屋だからさ、来るのは馴染み客ばかりだろ? 兄貴が普通に振る舞っていれば、それで済むはずだった」「何があったんです?」「兄貴は客単価が高くなるよう、巧妙な手口で運営するようになった。頭皮ケアも必要ですなんて、言葉巧みにその気にさせて。それは親とは正反対の営業だからさ、次第に馴染み客は離れていく。客層がずれていったんだ。両親が復帰した頃には若い子たちの名前で予約リストが埋まってた。両親はカンカン。そんなに自分の経営がしたいなら自分の店を持てと言って兄貴を勘当したんだ。俺は美容師になろうとは思ってなかったから、目の前で起こってた変化もスルーしてて……親に負い目と罪悪感があってさ。様変わりしちまった店を見て、両親は打ちひしがれてさ。そんな姿を見たら兄貴が許せなくなった」「お兄さんはよかれと思ってた部分もあるんじゃないですか?」「まぁそうなんだろうな。兄貴は兄貴なりに家のことを考えてたんだと思う。『美容室の数は、全国に存在する信号機の数より多く、毎日5件は潰れる激戦職。両親のように甘っちょろいオモテナシでは火の車になって当然だ。俺は違う。客単価アップを図っている』って。両親と兄貴とでは、ただ目指すものが違ったんだ」「それで、お兄さんは……?」「今では何店舗か構える経営者。最近ではエステ業界にも進出したって噂だ。ま、元気にやってんだろ」「そうだったんですか……」「兄貴ってのは、先へ行く生き物だよな。追い付いたと思っても追い越せない。常に先を行きやがる。陰でこそこそ何してるんだか」「本当にそうですよね……。分かります、私も。いつかまた一緒に笑える日が来るといいですね。ご自慢のお兄さん、なんでしょう?」「ははっ。ちぃにはお見通しか。確かに俺には出来過ぎた兄貴で、でも自慢の兄貴だったよ。何回か連絡も取ろうとしたしな。勇気出なくて頓挫したけど」「焦らなくても大丈夫です。絶対に。いつか時が解決してくれます」「……最近は、見かねた邑が、俺と兄貴の仲を取り持とうと必死なんだ。と言うより家族愛に目覚めたっつーか。今日もこうしてわざわざ誕生日に託けて名古屋まで来てくれたし。あいつも結構寂しがりなところがあるから、こういう機会を利用して……」「誕生日?」「え? あ、いや……」「誕生日って仰いましたよね? 麻生さんのお誕生日なんですか?」「いや、だからその……」「麻生さん!」「……実は」「そんな! どうして仰って下さらなかったんです!? 私ったら、こんな御持て成ししか出来なくて……」「いや、十分だから。十分過ぎるくらい十分だから」ちぃには頑固な部分もある。こっちが折れるまで押し切ってしまう、意外な一面が備わっているのだ。始めは面食らったもんだが、付き合いも長くなると、次第に『ここで折れておくべきなんだろうな』というタイミングも分かるようになってきた。「ほんと、美味かったよ。女性の手料理って最高だな」「麻生さん……」「さてと、そろそろ帰るわ。長居しても申し訳ないしな。何せ社宅だし。あらぬ噂を立てられたら、マジであんたが不憫だ」「私は……」「こら。間違っても『構わない』なんて言うなよ? 帰宅する気でいる男を引き留めたりしたら、痛い目見るぞ」「……」「じゃあな。ご馳走様。近年にない、最高の誕生日だったよ」腰を上げ、玄関へ移動する。するとちぃは俺を押しのけるように靴を履いて、玄関からひょっこり外の気配を窺った。「……今なら誰もいません」「さんきゅ」ちぃの頭をぽんぽんと叩き、渡り廊下へ出た。「お休み」「お休みなさい。邑さんに、ご馳走様でしたって伝えて貰えますか?」「あぁ、伝えとく」「あと、」「ん?」「誕生日、おめでとうございます。麻生さん」「……。さんきゅ」もうここで帰らなければ。去らなければ、いつまで経ってもここから動けなくなるような気がした。1歩2歩と歩いて、5歩6歩と歩みを強める。曲がり角で振り返ると、ちぃはドアの前にまだ立っていて、笑いながら手を振った。俺も手を挙げる。角を曲がり、俺の姿が見えなくなったのを目途に、ドアを閉める音がした。「参ったな……。ちぃに言った言葉、全部が全部本音だわ……」俺も随分素直になったもんだ。こんなに自分を曝け出したのは、随分久しい気がする。それがいいことなのか悪いことなのか分からない。思い返せば恥ずかしいことも口走ったと思う。だが、不思議と悪い気はしなかった。スマホを取り出す。邑にケーキの御礼メールを送り、次に兄貴の携帯番号を表示させた。今まで何度もかけるのを躊躇い、結局はやめた。でも今日は指が通話ボタンを押していた。コール音を3回4回と重ね、電話口に兄貴が出た。「……環か?」訝しげな声。そして懐かしい声。何も変わっていない。兄貴の声がした。「そう、俺」やべぇ。この先何も考えてなかった。何を話すだとか、そんなの、ちっとも。――『大丈夫です。絶対に』ちぃの言葉が蘇る。大丈夫。だって相手は兄貴だから。「元気か、兄貴?」「あぁ、元気だが……。お前はどうなんだ?」「俺? 俺も元気だよ」2012.05.122020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
03月14日 ■ 不破犬君
03月14日 ■ 不破犬君3月中旬にしてホワイトデー。暦上、春ではあるものの、吹く風は未だに冷たく、朝晩は5度以下にまで冷え込む。下手をすれば冬より体調管理に気を配らなければならない日が続く中、なんとか快晴を迎えた今日。僕はライトオンのジーンズにマウジーのTシャツと薄手ニットという比較的ラフな出で立ちを選んだ。向かうはユナイソンの社宅マンション共同駐車場。手に工具を携え、腰にはバイクのキー。今から何をするかと言えば、バイクのメンテナンスだ。やるからにはとことん綺麗にしようと思っていた。だから休みである今日を狙っていたし、晴れ晴れとした天気なのは僥倖としか言いようがない。空いたスペースを陣取って、愛車のYAMAHAボディを丹念に磨きあげる。空気圧や溝に関しては、給油の時こまめにチェックするようにしているから問題ない。2時間ほど掛け、仕上げの段階へ。パーツや傷の具合を見ていると、「おはよう、不破」と声を掛けられた。振り向くと、私服姿の柾さんが立っていた。アスペジのブラックパンツ、バナナリパブリックの白灰2枚重ねタンクトップ、ポールスミスのネイビーカーデ。それらは思わず溜息が漏れそうになるくらい柾さんに似合っている。うっとりしかけて、危うく挨拶を忘れるところだった。思わぬ人物の登場に、僕はすっくと立ち上がる。「おはようございます、柾さん」するとさらにその背後から、「よぉ。おはよ、不破」と、これまた私服姿の麻生さん。リーバイスホワイトデニムをスリムストレートで穿きこなし、グレイカラーのユニクロ七分袖シャツを着ている。羽織り物はGAPのサファリジャケット・コットンニットモデルだ。柾さんもだけど、麻生さんの休日スタイルも真似たくなる。麻生さんだからこそ似合うスタイルなのだろうが。「麻生さん! おはようございます。お2人とも、今日はお休みですか?」「あぁ、休み。お前さんもみたいだな」「えぇ。今日はバイクのメンテをしようと思いまして」「奇遇だな。俺らも車イジろうと思ってさ」「……麻生。やはり店へ持って行く」柾さんは気乗りしないのか、苦い顔をして麻生さんに溜息をついた。「またお前はそういうことをー。俺に任せろって。絶対大丈夫だから」「その根拠のない自信が怖いんだ」「お前の車、モノがモノだからそういうのも高いんだよ。俺ならロハだぜ」「ロハって大正時代の言い方だろう……。いや、僕は別に構わない。今まで通りで結構だ」やり取りからして、混み入った話なのかな。駄目もとで麻生さんに訊いてみる。「今から何をするんです?」「スタッドレスからノーマルに履き替えるんだ。もう雪も降らないと見た」「タイヤ交換ですか」「こいつさー、工賃払ってまで正規タイヤメーカー店でやって貰うって言い張るんだぜ」「うわ、毎年そんなことしてたんですか? 勿体ない! タイヤ交換ぐらい僕も手伝いますよ」「ほら柾、不破もいてくれたら安心だろ? それと悪ぃんだけどさ、不破。柾の後、俺のも手伝ってくれないか?」「お安い御用です」1台4本なんて15分もあれば余裕だ。2台に増えたところで30分と掛からない。というか、別に3人も要らないわけで。始めから柾さんは頭数に含まれていないのだろう。麻生さんは早速作業に取り掛かる。柾さんの愛車、BMWのトランクを開けると道具一式を取り出した。レンチの平坦な部分を使ってタイヤカバーを外す。次は1つのタイヤに付いている4つのネジを取る番だが、簡単には取れない。それは予想済みだ。十字レンチをネジに差し込み、その上から足を掛け、乗ったと同時に一気に体重を掛ける。柾さんとしては、心中穏やかではないだろう。きっとこんな場面はお目にかかったことなどないだろうから。「……タイヤ交換とは、いつもこんなに荒々しいものなのか?」「あのな。F1のピットストップとはわけが違うんだぜ?」大方、タイヤ交換中は「珈琲でも飲んでお待ち下さい」と言われて優雅に寛いでいたんだろ。そう指摘した麻生さんの言葉通りに違いない。柾さんは否定も肯定もしなかった。*「タイヤの摩耗をなくすためにフロントタイヤとリアタイヤの入れ替えもしておく。ローテは鉄板だぞ」そんな麻生さんの蘊蓄を、柾さんは右から左へと聞き流しているのだった。結局、麻生さんのホワイトデニムを一切汚すことなく、作業はあっさり終了した。「楽勝楽勝♪」満足気にレンチをバトンよろしくクルクル回す麻生さんは機嫌がいい。麻生さんの愛車、プリウスαの履き替えも無事に終了したからだろう。その気持ちはよく分かる。手入れされた車体は、そのホワイトパールを目映く光らせていた。その麻生さんは、道具を片付け始めた途中で、こっちに近付いてくる人影に気付いた。「よッス、青柳!」「あれ、麻生さんに不破? 柾さんも? どうしたんですか?」質問は敬語。ゆえにこの疑問文は麻生さんに投げ掛けられたものだろうと推理する。「タイヤ交換してたんだ」「あぁ、そろそろそんな時期ですね。俺もやっておいた方がいいかな……?」「タイヤがあるならやってやるぜ。どこか出掛ける用事があるなら無理強いはしないが」「暇だったんで、バッティングにでも行こうかなって。でもタイヤ交換したいです」その様子を眺めていた柾さんが言う。「こうなったら、他の社員にも声を掛けてみたらどうだ、麻生」柾さんは車留めに腰掛けていた。その手にはいつの間にかBOSS缶が握られている。よく見たらコンビニの袋があり、その中にコーヒーやお茶のペットボトルが10本ほど入っていた。いつの間にコンビニへ……? ちっとも気付かなかった。柾さんと目が合う。柾さんは笑みを浮かべ「お疲れさん」と労い、ペットボトルを僕の方へ放り投げた。ペプシネックス。これ、大好きなんだ。「ありがとうございます。いただきます」柾さんの意見を取り入れた麻生さんはスマホをイジり始める。誰に連絡しているのかまでは分からない。打ち終えた頃には青柳チーフのシルバーメタリック、『カムリハイブリッド』が横付けされていた。*かくしてタイヤ交換祭りと相成った。「俺も俺も」と参加者が集い、共同駐車場は賑やかだった。気付けば男ばかり集まり、どこからともなくボールが出現すると、簡易サッカーが始まった。かと思えば違うコミュニティも出来上がっており、会話に花が咲いていた。「どこの支店だったかな? アーユラ製薬のマネキンが可愛いって言ってたぜ」「呼んでくれよ、日雑売り場ー」「いいですねー。じゃあ第4週の日曜日に来て貰いましょうか」「だめだめ。俺第4日曜休みだもん。次の週になんね?」「我儘だなー」「だって見たいじゃん」やんややんやと浮かれている内に日が暮れ始めた。小集団ごとに夕飯を食べに行ったり遊びに行ったり部屋へ戻ったりと、三々五々に散り始める。その頃には早番出勤だった社員も勤務を終え、この騒ぎに合流していた。「あー、腹減ったー! なぁ、飯食いに行こうぜ。杣庄、美味しい店教えてくれー」麻生さんの提案に応じたのは、柾さん、青柳チーフ、五十嵐さん、平塚、ソマさん、そして僕。計7人でソマさんオススメの飲み屋へと移動することになった。「そう言えば、お犬様の誕生日だよな、今日」平塚がにやりと笑う。「えっ、そうなのか?」と諸先輩方。「不破には1日たくさん働いて貰ったし、今日は奢り決定だな!」麻生さんがくしゃくしゃと僕の髪を掻き乱す。「2次会はどこに行くつもりなんだい? ボーリングでもしたいけどね、俺は」「よぉし、嵐、言ったな? 今度は負けないからな」柾さんは何故か、揺るぎない声音で宣言する。ソマさんが「五十嵐さんってボーリング強いんですか?」と尋ねれば、麻生さん曰く「嵐ってば鬼強」とのこと。「あ、碩人と十御もいま仕事終わったって、メールが」「マジか、青柳! よしよし、呼びな呼びな! 伊神と一廼穂には訊きたいことがあるんだ」麻生さんは浮かれ気分だが、僕は萎える一方だ。「青柳チーフ、やめて下さいよ、メンテ2人組呼ぶの……」「嫉妬は見苦しいぞ、不破」青柳チーフに窘められ、ソマさんからもそうだそうだと頷かれる。くそ、なんだこの布陣。「楽しい誕生日の夜になりそうだなぁ、お犬様」慣れ慣れしく肩を組んで来た平塚の横っ腹にエルボーを食らわせ、速攻で黙らせる。ふと尋ねたいことがあったのを思い出して、僕は歩幅を落とし、最後尾にいた麻生さんの横に並んだ。「麻生さん」「んー? どした?」そう尋ねる麻生さんの声は柔らかくて。だからこそ余計に尋ねるのに躊躇われた。「凪さん……千早さんって、来ます……?」僕の質問に、麻生さんは目を僅かに見開いた。次の瞬間、屈託ない笑い声とともに肩をガシと組まれる。「ホント、不破は千早兄貴が好きなんだな。柾にとっては天敵だが」そ、そうだよな。わざわざ友達の苦手な人物に呼び掛けるわけないよな……。少しがっかりしている僕の隣りで、麻生さんはスマホを操る。「ほら。見てみ」そう言って差し出された麻生さんのスマホの画面には、今日のメールのやり取りが並んでいた。タイヤ祭りの呼び掛けメールに呼応した何人かの中に、『千早凪』の名前もある。開くと、「『今日は遅番なので、間に合えば参加します』。あ……」「よかったな」麻生さんは肩を組んでいた腕をほどくと、僕の背中をポンと叩く。麻生さんは凪さんを呼んでくれたんだ。その事実が嬉しくて、でも気恥かしくて。「……つーか10人の野郎集団って。どんなんですか、本当に」照れ隠しに僕が一人ごちれば、そのすぐ横で。「本当だ。暑苦しくて敵わん」苦虫を噛み潰したような顔で、柾さんはしみじみと賛同したのだった。2012.04.122023.02.13 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
02月13日 ■ 姫丸二季
02月13日 ■ 姫丸二季雪。雪だった。音もなく、未明から降り始めたであろう白のそれは、灰色のコンクリートの上にうっすら、層として重なろうとしていた。道理で寒いわけだと苦笑を漏らす。袷の着物に長羽織を纏う。それだけでも随分と違った。【春夏冬中】と書かれた札を店の入り口にかける。黒か焦げ茶かで迷うような色で出来た木の札は、以前友人の千早凪がこしらえてくれたものだ。秋が無いので【商い中】という意味だが、果たしてこの寒空の下、早朝から呉服屋を訪ねる客があるとは我ながら思えない。それでも7時の目覚めと共に店を開けることが日課となっていたし、飛び込みで着付けを希望する客も、いないわけではない。この店はおれ1人で切り盛りしている。店を開けつつ、店先から「御免下さい」と声が掛からない限り、ゆっくりと身支度を整えていられるのは、気楽だし、都合もよかった。改めて木札を見やる。友人の手によるそれは、一種の守り札のようで、なんとも心強い。墨汁で認められた毛筆の字の上を、おれは右手でなぞった。おれが千早凪と知り合ったのは、今から7年も前のこと。業界第一位のスーパー『horizon』の名古屋店にテナントとして入店していた呉服屋チェーン『ゑび寿(えびす)』に勤めていた時だった。―7年前―社員食堂には暗黙のルールがあった。直営の従業員が5列中窓寄り3列分を陣取るように座り、テナントに籍を置く者は隅の方で肩身狭く食べるのが常だった。逆らうのもばかばかしく思え、『右に倣え』でおれも隅の、部屋からすれば暗い位置で毎日食事を取っていた。着物にコンビニ弁当という組み合わせが不釣り合いのような気がして、なるべく弁当を持参するようにしていた。今日は細かく刻んだ生姜入りの稲荷寿司を握り、唐揚げをふんだんに詰めて来た。バランスより、好物重視。それがおれのポリシーだ。「あーっ、姫丸クンだ。や~ん、やっぱり着物すっごく似合うー! カッコイーなぁ」思わず稲荷寿司を落としそうになった。食堂中に響く、甲高い声で人の名前を呼ばれたら、誰だって困惑するだろう。しかも、ただでさえ悪目立ちする着物だから。実際ちらちらと数人がこちらを振り向き始めていた。おれは目の前の彼女を恨めしく思った。「……長瀬さん……でしたっけ?」一体、何の用なんだろう。「あっ。覚えててくれたんだ~? 結衣、嬉しいな~!」屈託なく笑う彼女のことを、おれは名前と所属ぐらいしか知らない。女性に人気のインナーショップ店員だったと思う。記憶に自信がないのは、彼女との出会いが今日で3度目だからだ。「覚えて貰ったついでに、あたしとメアド交換して欲しいな~。SNSでもLINEでもいいよ~?」「は……?」「姫丸クンって鈍いのかな? それともウブ? だって姫丸クンかっこいーんだもん。彼女いなかったらあたしが立候補する! なんちゃってー」そういうことか。合点がいったと同時に、再び困惑してしまう。この手の問題には厄介さを覚えるのだ。特別な女性などいないし、好意を寄せている女性もいないのだが、将来を考えると軽々しく付き合えないのが現状だ。 ゆくゆくは実家の呉服屋を手伝って貰わなければならない。相手選びは慎重にならざるを得ないのだ。この時点で彼女を判断するのも気がひけるが、凡そ呉服問屋に嫁ぎ、脈々と受け継がれてきた『しきたり』を守ってくれるとは到底思えなかった。肩からずり落ちたニットのトップス、ちらりと見えるブラらしきものの紐、冬だと言うのにお尻さえ見えかねない短すぎるジーンズのパンツ。和装女性の真逆に位置するであろう魅惑の生足がにゅっと伸び、10cmはある厚底靴を履いている彼女に、果たして女将の座が務まるだろうか。人を見た目で判断するな? 確かにそうだ。だが彼女は伝統文化である着物を前に、「丈もっと短くしたいな~! 裾をレースにしちゃおうか!」と言い出しかねない危うさを孕んでいた。駄目だ、この子を彼女にするわけにはいかない。「申し訳ないけど、あなたと連絡を取るつもりはないんだ」言った途端、相手の顔が豹変した。ぞくっとするほど冷たい目になり、全身から『断るなんてナニサマのつもり?』と刺すような空気が迸っている。「割り込み失礼――。すまないが、彼は婚約中の身なんだ。婚約者に操を立ててる。悪いが他を当たってくれないか」突然、背後から声がした。おれと長瀬さんは同時に彼を見た。スーツを着こなしたその男は、まるでオーシャンズやレオンなどと言ったメンズ雑誌から抜け出したような、目を見張る美形だった。誰だ……? おれは知らない。見たこともないし。それは長瀬さんの方も同じだったようで、得体の知れないイケメンを前に戸惑っているようだった。「これが姫丸さんの婚約者。2人が並んだらお似合いだろう?」そう言って1枚の写真を長瀬さんの顔面に近付けた。おれには写真が見えなかったが、彼女はやがて唇を噛み締めると、おれと男性を睨み付けてから踵を返し、食堂から出て行った。その背を安堵の気持ちで見送りながら、お礼を言う。「有難う御座います。その……助かりました」そして彼に向き直る。彼は一番近くにあった椅子に腰掛けた。おれが弁当を食べていた席の隣りに。「いや。次第に雲行きが怪しくなってきたのが分かったからさ。彼女と付き合えない理由があったんだろ?」「何故そう思うんです?」「なんとなく。強いて言うなら、きみの立ち居振る舞いが、老舗の呉服問屋然としてることに違和感を覚えたからかな。今はテナントの『ゑび寿』で働いてるみたいだけど、実際はどこかの呉服問屋の若旦那かと思って」おれは面食らった。一体何者なんだ、このひとは。「凄いな……。当たりです。確かに実家は創業119年の呉服問屋を営んでいます。勉強と修行を兼ねて『ゑび寿』に入社しましたけど、ゆくゆくは家業を継ぐつもりで」「やはりそうか。まぁ俺も似たようなもんだから。『家』に縛られてる。だからピンと来たんだ」しれっと言ってのけるが、それはそんな簡単に言えるセリフではないのでは……?それだけ幼少期より、重責を担うことを運命付けられてきたのだろうか。だから彼は若干諦めに似た境地で吐き捨てるように言ったに違いない。「機転に感謝します。そう言えば、何の写真を長瀬さんに見せたんです?」彼の手には、2階の写真屋店のロゴが入った紙袋があった。長瀬さんに見せたのは、その中から引き抜いた1枚だったのだろう。「写っているのは俺の大切な子でね。言っておくが、やらないぞ」写真の女性に吸い寄せられた。どこかの公園だろうか? 銀杏並木の中、名前を呼ばれ、振り向いた瞬間の画(え)のようだった。肩より若干長い黒髪を揺らし、白のボウタイブラウスに紺のフレアスカートを穿いた清楚で可憐な女性が、レンズに向かって微笑んでいた。いや、笑っているのはレンズにではない。撮影した相手……彼を見て、か?「とても素敵な女性ですね」「そ、そうか? いや、そう言って貰えると、兄として鼻が高いが……」……なんだって?「兄として? ……つまり、この写真の女性は、あなたの妹さん?」「そうだが」「あなたの彼女では?」「……? おかしなことを言うな? 実の妹と付き合うわけないだろう」「え、でもさっき『俺の大切な子』って……」「そうだが、何か?」……あぁそうか、これが世間で言うところのシスコン、というやつなんだな。本当にいるんだ、自分の妹を溺愛する兄というのは。「秋に家族旅行で岡崎に行った時の写真でね。出来を眺めていたんだが、絶妙なタイミングだったな。レキのお陰で助かった」そう言って、再び写真の中の妹に魅入る変人……いやいや、おれにとっての恩人。千早凪とは、こうして出逢ったのだった。―現在―「結城紬とは渋いな」昔を懐古していたからだろうか。実際に凪の声がしたような気がして、一瞬自分の頭がこんがらがった。だがやはり本人のものだった。凪だ。あの時はスーツ姿だったが、今はカジュアルな出で立ちでおれの前に立っていた。「凪! どうしたんだ、こんな朝早く?」「今日は休みなんだ。なんとなくふらりとこっちに足が向いて、それで。それと、誕生日おめでとう」手に何か持ってるなと思ったら、おれへの土産だったらしい。差し出されたそれを有り難く受け取った。「凪はいつも神出鬼没で、思いがけないサプライズを仕掛けてくるんだな」やれやれと苦笑しつつも、凪の優しさが嬉しかった。「ここは寒いから、店に入りなよ。さっき朝食用にポタージュを作ったんだ。飲むだろう?」「あぁ。ありがとう」「……さっき、【春夏冬中】の札を見て、昔のことを思い出してたんだ」「昔のこと?」「おれと凪が初めて出会った日のこと」「あぁ、あれか」凪は目を細め、口元に笑みを浮かべた。カップに注いだポタージュに視線を落とすも、その目は優しげだ。「俺も覚えてる。いつかヒメに紹介するよ。妹を」妹……。『千早歴』の話題が出たのは、実に3ヶ月振りになる。凪が起こした『事件』のあらましを11月に聞き、その時に知ったのだ。凪が後ろめたさゆえに歴さんと距離を置いていたことを。horizonにいた頃は、毎日耳にタコが出来るくらい聞かされていた。「レキが」「レキは」と。ところが凪がユナイソンに転職してからは一切歴さんのことを口にしなくなった。きっとそれは良心が疼いていたからだろう。極力妹のことを考えないようにしていたに違いない。そうでもしなければ凪のことだ、精神をとことん病んだだろうから――。「久し振りだな。凪の口から歴さんの名前を聞くのは。……大切な妹だろ。いいのか、おれに紹介して」「お前ならな。ヒメならいい」「そうか」しゅわしゅわ、とストーブの上のやかんが音を立てる。おれはひとりごちた。「温泉に行きたいな」「温泉か。いいな。いつか行こう」「あぁ」おれが何気なく漏らした言葉を、凪は覚えていた。おれが下呂温泉で歴さんに出逢うことになるのは、今日から4ヶ月後のこと。だが今は当然、そんな未来の話など知る由もない。「なぁ、ヒメ」「ん?」「……積もりそうだな」「そうだな」窓から見えるは雪。そう、雪だ。深々と降り続く雪は、灰色の地面を白銀へと塗り替えてゆく。凪を見やる。おれはふと、凪が抱えている仄暗い闇、痣のような過去を、雪のように上書き出来る存在になれたら、と思った。不器用で、まっすぐな男。それが千早凪だ。見ていて危なかしい。けれどおれには大切な、見放せない親友。2012.09.032020.03.15 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
02月05日 ■ 児玉玄
02月05日 ■ 児玉玄普段通りと言っても過言ではない絹と2人きりのバースデーディナーに、喜ばしい来訪者があった。千早歴さんである。アルコールが入ってほんのり頬を染めた歴さんはかなり色っぽい。和の艶に弱い俺である。じろじろ見続けるような非礼はしたくなかったから盗み見る形になってしまい、不審者めいていたかも。とは言え、歴さんといえば柾さんの想い人。幾ら歴さんが魅力的な女性でも、柾さんを敵に回すような極太魂は生憎持ち合わせていない。俺的には、思春期男子が通過するであろう儀式『近所の憧れのお姉さん』という位置付けに相当する。22時になり、歴さんがお暇する旨を告げると、絹は「えぇ~っ」と無念そうな声をあげた。こういう甘え方は柾さんにしかしないから、よほど歴さんを気に入ったに違いない。「もう帰っちゃうなんて……。泊まってくれても構わないのよ!?」絹の無茶な提案に、歴さんは困り顔だった。「絹、歴さんは明日も仕事なんだから」「そうよね……。じゃあ歴さん。マンションまで送るわ」「え? そんな、大丈夫よ!」申し出をしきりに辞退する歴さんに、2人がかりで「せめて1人では帰らないように」と説き伏せる。何かあっては柾さんに会わせる顔がないし、そもそも夜道は本当に危険だから。結局歴さんはタクシーの代わりに兄を呼ぶと誓ってくれた。電話口で兄は快諾。かくして異様な早さで迎えが来て、歴さんは無事、帰宅の途についたのだった。*空になった皿やグラスを満足気に見た絹は「晩餐はこれにてお開き」と笑い、片付けを始めた。手分けをすれば、その分早く終わる。そこは長年培ってきた阿吽の呼吸が物を言う。あっという間にシンクはピカピカ、拭いた食器は棚に収まり、空の瓶は死角スペースへ追いやり片付け終了。「絹。お風呂沸いたから入れるよ」「ありがとう。じゃあ先に入る――」そこで絹の言葉が途切れた。明らかに様子がおかしかったので絹を見ると、なぜか玄関の方を凝視している。「……お風呂は後にするわ」「絹?」「彼は要るのかしら……。ううん、要らないのかも……。どっちかな? 分からない……」今度は小声でぶつぶつと独り言。一体どうしたって言うんだ?「なぁ、絹?」「玄くんにお客様よ。出てあげてね」「客? こんな時間に?」絹はそう言ったきり、ふいっと自分の部屋に戻ってしまった。内心戸惑っていると、チャイムの音が鳴った。どうして来訪者があると分かったんだろう。異端の力が成せる業なのか?走りにくいスリッパで駆け付け、ドアを開けた。そこには思い掛けない人物がいた。「杣庄さん!?」以前悪友に誘われて立ち寄った大須にある古着屋店の臨時店員であり、ユナイソンの社員である杣庄さんだ。彼とは(絹の言葉を借りるならば)出会うべくして出会った。それほど奇妙な縁を持っている。などと一方的に解釈していのだが実際に会うのはこれで2回目だし、何故彼がここにいるのだろう?「よぉ、こんばんは。千早さん、来なかったか?」「さっきまでいました。さっき帰られたばかりです」「入れ違いか。だろうな。あー、えっと、今日誕生日なんだってな? 柾さんから聞いた。ここの場所も。で、こんな時間になっちまって悪ィんだが、よかったらこれ、貰ってやってくれないか?」言うなり、肩に掛けていたクーラーボックスを差し出した。50cm四方はある、大きな箱だ。「な、なんですかこれ?」「ははっ。閉店間際に捌いて来た。刺身と、漬けマグロと、海老の甲羅グラタン。あぁ、あと甘エビ。今日はもう遅いからアレだが、このままクーラーボックスに入れておけばまぁ冬だし、鮮度も大丈夫だから」「そんな高価なモノ貰えませんよ……!」「気にすんな、俺の好意だから。その代わり、これが美味かったら今度からはウチで魚を買ってくれ」ニッと笑う杣庄さん。ふと、根本的な商魂の逞しさが柾さんと似ているような気がした。横たわる大きな違いはただ1つ。杣庄さんは職人気質、柾さんは商人気質だという点だ。売り方や考え方に差異はあれ、目指す所は一緒なんだろうと思う。2人を思うと身体が震えた。凄い人達だ。「じゃあな」杣庄さん的には用が済んだことになるのだろう。身が軽くなってフットワークもよくなり、帰ろうとする。「あ、待って下さい!」思わず口から制止の声が出て、引き留めたところでどうしたいのかと必死に考える。ただ御礼が言いたかったからだけなのか、もっと時間を共有していたからかったのか俺にも分からない。悩んでいると、「こんばんは」と背後から絹の声がした。挨拶は初対面の杣庄さんに向けてのものだった。双子の姉の存在も知っているようで、杣庄さんは「どうも」と言って軽く頭を下げた。「夜分に申し訳ない」「絹、杣庄さんから高価な魚を頂いたんだ」「杣庄さん、ありがとうございます」俺や柾さんに向けられるトーンとは違う、≪迷える人たち≫向けに作った、大人びた女性の口調・表情。ここで絹が姿を現したということは……つまり、そういうことなのだろうか。彼もまた、≪迷える人≫?こうなると俺の出る幕ではない。絹の出方を待つ。だが意外にも、絹はそれ以上何も言わなかった。傍目には通り掛かりの客人に挨拶と御礼を述べた家人として映ったことだろう。絹も俺も引き留めておく言葉が無いなら、杣庄さんを帰さないといけない。「杣庄さん、途中まで送りますよ」杣庄さんはお前がそうしたいならといった様子で頷いた。絹は「行ってらっしゃい」と微笑む。「またお会い出来る日を楽しみにしてます」と告げて。*杣庄さんを駅の改札口まで見送ると、俺は一目散にマンションへ戻った。絹には聞きたいことがある。さっきの不可解なやり取りを説明して貰いたかった。俺のことなどお見通しだったようで、絹は紅茶を注いで待っていた。その目には憂いがある。「絹……?」「玄くんが杣庄さんと出逢ったのは、きっとそうなる運命だったからなのね」「どういうこと? さっき、どうしてわざわざ対面したんだ? 何かアンテナに引っ掛かったのか? でも普段のように、押しつけがましく石を渡したりしなかったな。どうして?」「どうすべきか迷ったから、実際に対峙してみたの。お陰で色々と分かったわ。彼は私の木霊を拒否してた。でも彼には救いが必要みたい。私では駄目。今の私では。ゆくゆくは玄くんが踏み込むしかない。彼の心に」「杣庄さんが大きな救いを必要としてるだって?」「大きな穴よ。本当に大きな。本人はそれほど自覚していないみたいだけど、実際はとても深くて根強いの。今の私には選べない。彼に適切な石を……。今、土足で踏み込めば拒まれる。それがハッキリと分かった」「キーワードは? ユナイソン絡みなのか?」「ううん。それは全く問題ない。寧ろ、ユナイソンでの生活があるから彼は正気を保っていられるんだわ。問題は私生活の方。とてもイヤな感じがするの」「私生活? 兄弟仲はいいって言ってたけど……」妹の唄ちゃんは美少女。恋愛体質だけど店番を快く引き受けるし、家族想いのいい子だって聞いてる。杣庄さんだっていい人だ。彼には姉がいるらしく、粗暴な割に面倒見がよいと言っていた。彼曰く、3人で力を併せて祖母と暮らしている。……そうじゃなかったっけ?「御両親は?」「え? いや、何も言ってなかった。というか、何も聞いてない」「問題は御両親よ。暗くて深い闇だわ。油断してるとこっちまで引きずり込まれる」「そんな大袈裟な」「玄くんには分からない? いいえ、分かりたくないんだわ。きっと本能では感じ取ってる。肌にぴりぴり来てる感じ、しない? ついスミレさんの助けを借りたくならない?恐怖が大き過ぎて、ハッキリ言って今回ばかりは目を背けたいわ。……勿論立ち向かうけど」「絹……」「杣庄さんの連絡先、知ってる?」「あぁ、さっき聞いた。送ってく時にそんな流れになって交換し合った」「玄くんに杣庄さんが必要なように、杣庄さんにも玄くんが必要なんだわ。大丈夫。長期戦になるけど、きっと……ううん、絶対幸せに向かって歩き出せる」漠然とした不安。忍び寄る影。何かが始まろうとしている。掘り起こさなくてはならない何か。視界に入ったクーラーボックスを見て思う。杣庄さんが今、暗い何かを抱えているのなら是が非でも救いたいと。決意を新たにする。同時に、力が生まれた日でもあった。2012.03.22 2020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
02月05日 ■ 児玉絹
02月05日 ■ 児玉絹「あんな事、言うんじゃなかったわ」朝の早い内から、絹は猛省していた。内容は柾への一方的な非難に対して。今日、2月5日は絹と玄の誕生日。夜には仕事を終えた柾がマンションに立ち寄り、3人で祝杯をあげる予定だった。指折り数えて待ち侘びていた誕生日だったのに、柾は当日の朝になって「行けなくなった」と言う。「急遽ピンチヒッターとして部会に出なければならなくなった。今日は無理かもしれない」当然、絹は駄々を捏ねた。仕事が一番なのは分かる。でもよりにもよって今日だなんて――。拗ねたことが仇になった。部会に行かなければならないので柾は急いでいたのだ。資料も用意しなければならないし、頭に詰め込まなければならない情報だってあるだろう。一分一秒を争う朝の忙しい時分に、絹との押し問答をしている余裕などなかったはずだ。だから柾が絹に対して苛立ったのも仕方がなかったし、当然だった。「切るからな」と冷たく宣言されて遮断された通話。絹はとことん落ち込んだ。ごみ捨てに行く足取りも重い。いつもなら階段を利用するが、気力も湧かずエレベータで移動する。「あなた、新婚さん?」たまたま居合わせた主婦に声を掛けられた。「旦那さんとよく並んで歩いてるのを見掛けるわ。なんだか見ていると微笑ましくてねぇ……」エレベータには絹と、声を掛けてきた主婦しかいない。だからその言葉は明らかに絹に向けられている。恐らく、玄を旦那だと勘違いしているのだろう。苗字も同じで、年もさほど変わらない。見る人が見ればそんな間違いも起こすのかもしれない。いちいち「双子です」と訂正するのも面倒だ。根掘り葉掘り訊かれるのは性分に合わない。身内には違いないのだし、と心の中で言い訳をして、絹は微笑みを返した。*ユナイソンの社員食堂で、杣庄は柾を捕まえた。何気ない会話を楽しんでいると、歴も姿を現した。席を見付けるために右往左往していたので、杣庄は歴に声を掛けた。知り合いがいてホッとした様子の歴は、杣庄の横に座る。彼女のトレイには和食が並んでいた。「カボチャの金平! 美味しいよな、それ」そういう杣庄も同じものをチョイスしていた。しかも山盛りだ。思わずクスリと歴は笑った。「何の話をしていたんです?」歴が尋ねると、柾はフォークでレモンバジルのウインナーを刺した手を止めた。どことなく眉根が寄っている気がして、もしかして不機嫌なのかしらと考える。「いや……絹と朝、少し口論をね」「珍しいですね。柾さんが口論だなんて。しかも絹さんに?」「今日は子供たちの誕生日で祝う予定だったんだがドタキャンしてしまってね。絹に散々怒鳴られた」「え? 今日、絹さんのお誕生日なんですか?」「え? 今日って玄の誕生日なんですか?」歴と杣庄の声が綺麗にハモった。柾はあぁと頷き、ほうじ茶が入った湯のみを啜る。歴と杣庄は思わず顔を見合わせる。恐らく考えていることは同じだ。歴は絹を、杣庄は玄を想ってる。「15時から部会でね。多分その後は飲みに行くことになるんじゃないかな。だから絹たちの方を断わった」「そんな……。何とかなりませんか? 絹さん、とても残念がるんじゃないかしら……」「行ってやりたいのは山々だが、部会そのものが何時に終わるか分からない。守れない約束など始めからしない方がいい」「でも……。……そうですか」しゅん、と項垂れる歴。絹がどれだけ柾を義父として、人として愛しているかを知っている。だからこそ、絹が不憫でならない。一方で、柾が社内でどんなポジションにいるのかも熟知している。彼は出世頭の1人で、今だって重要なポストにいる。部会は大切だし、その繋がりはもっと大切だろう。寂しさが伝播する。どちらも歴にとって大切な人。――だから彼らが寂しいと、私も寂しい。*「今日ね、エレベータで乗り合わせた人に、お似合いの夫婦ねって言われたわ」「は? 夫婦? なんのこと?」突拍子もない話題に玄は付いて行けなくて、絹を見返した。トントンと野菜に包丁を入れる音がする中、だからねと絹は言い添えた。「きっと誤解してるのよ。私と玄クンのこと。双子だとは思いもよらないんだわ」「うーん、顔だって似てると思うんだけどなぁ」「そうね。でも……」急に口を噤んだ絹に、玄はどうしたんだ? と尋ねる。「ううん。何でもない」「絹、明らかに何か隠してる。絹と俺の付き合いって、生まれた頃から一緒なんだからさ、ちょっとした機微で分かっちまうっての」「玄クンは誤魔化せないなぁ。ごめん、玄クン、お父さんに似て来たなって思ったの」「お父さんって――」「……ん、産みの親の方ね」「……。そういう絹こそさ、スミレさんに似て来た気がする」「……ごめんね。変な話しちゃったね。ほら、作り終えた料理、そっちのテーブルに移動させて」「あぁ」どことなくぎこちない空気が流れる。それもこれも、柾がいないからだ。たった2人きりの食事は味気ない。しかも2人とも主役なのに。お互い祝え合えて嬉しい気もするけど、穴は確かに存在する。心に大きく、ぽっかりと。「さ、食べようか。いただきます」「いただきます」洋食メインのディナー。絹の腕は確かで、凝った料理もお手の物。だけど今日は腕の揮い甲斐がなかった。無言の食卓。美味しいねという短い言葉だけがぽつりと漏れる。はぁ、何て寂しい晩餐。くすんと絹が嘆いていると、来訪を告げるチャイムの音が鳴った。「宅配便かしら。玄クン、何か頼んだ?」「頼んだ。アメシストの原石が欲しかったからさ。大丈夫、もう代金は払ってあるから」「分かった」スッと立ち上がると、絹は印鑑を持って玄関へ向かう。やがてキャーッと甲高い悲鳴があがった。*「絹? どうしたの?」玄が慌てて玄関へ駆けつけると、そこには見知らぬ女性が立っていた。長いストレートの黒髪を垂らし、白いロングコートを羽織ったその女性は玄を見ると優しく微笑み、丁寧にお辞儀をする。「初めまして。千早歴と申します」「ちは……!」知ってる。その名前は柾の恋の相手。ユナイソンの大和撫子。「えっと、柾さんは今日、いないんだけど……?」「あ、いえ、違うんです。柾さんに会いに来たわけじゃないんです。私、柾さんから今日がお2人の誕生日だと伺って。いてもたってもいられなくて、これを……」差し出した歴の手には、バラの花束と有名ケーキ店の箱があった。もう1種類の紙袋にはスパークリングワイン。「ごめんなさい。急に押し掛けてしまって。もうお暇しますから――」「歴さん! 是非上がって行って! ケーキ、一緒に食べましょうっ! ねっ?」「わー、これはまさかのサプライズギフト! 千早さん、ありがとうございます」「柾さんから住所を聞き出しただけでも後ろめたいのに、そんな……」恐縮しきる歴をよそに、絹は早速、歴の腕をとってダイニングへ引っ張り込む。あれよあれよという間にバラの花が活けられ、歴の前にはワインと絹お手製の料理が用意された。「これ、絹さんが?」「えぇ。昔から料理が好きで、得意なの。でも歴さんのお口に合うか心配だわ」「絹の手料理は、専ら俺と柾さんにしか振る舞われないから。いざ第三者に食べさせるとなると怖いよね」見守る絹と玄。頬張る歴。わ、と歴は呻いた。「お……美味しい……! 凄い、絹さん!」「本当? よかったー」大袈裟なほど胸を撫で下ろす絹は、それだけどきどきしていたのだろう。歴の言葉はお世辞ではなく本心からのものだったから、あっという間に料理を平らげてしまった。「嬉しい食べっぷりだわ。よければお持ち帰りする? タッパーに詰めてもいい?」魅力的なお誘いだった。頂いては図々しいかしらと思いながらも歴は頬を染めてお裾分けを貰うことにした。「こんなことまでして貰って、寧ろ申し訳ないわ」「あのね、歴さん。私も玄も、今日は寂しい誕生日だったの。直パパは不在だしね。でも、歴さんがこうして駆け付けてくれた。本当に嬉しかったの、私」そう呟く絹の横顔はとても綺麗で。歴は改めて来てよかったと思う。「直パパに祝って貰うだけが幸せじゃないのね。そのことに、今更ながら気が付いたわ。ねぇ玄クン。私たち、視野が狭かったのね。人に心を許していなかったのもしれないわ」「しかも絹は、≪依頼者≫との連絡を一切取らない主義だしな」「今日はね、実はちょっと反省した。直パパがいなくても大丈夫なようにならなきゃいけないわね。巣立ってみようかしら。無理かもしれないけど」「そう気付けただけでも進歩じゃないか?」「そうね」絹は笑う。玄も笑う。歴も笑った。「それじゃあ、乾杯★」「乾杯」「乾杯!」酌み交わす美酒に酔い痴れる。友と呼べる人と過ごせる一夕は、掛け替えのない、甘くて温かい誕生日。2012.02.182020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
01月04日 ■ 平塚鷲
01月04日 ■ 平塚鷲「なぁなぁ、不破く~ん」その甘ったるい声に、不破犬君は背筋を凍らせた。思わずロッカーを爪で引っ掻いてしまい、この世で最も嫌いな音を立ててしまった犬君は、そのやるせなさを平塚鷲にぶつけた。「……消え失せろ」ストレートなセリフに平塚は「うっ」と呻き、「不破、キツ……」と口を尖らせた。「何だ。さっきから人のことをじろじろと。そんなに僕の着替えが見たいのか、変態」犬君の言葉は間違っていない。出社時間が同じで、2人が男子ロッカーに入ったのは数分違いだった。コートを脱ぐだけで準備を終えてしまった平塚は、ネクタイを結ぶ犬君の傍へ行き、声を掛けたそうにしていた。鬱陶しく思っていた犬君は敢えて無視をしていたのだが、そこに突然の「不破く~ん」である。平塚には、被害がロッカーだけで済んでよかったと感謝して欲しいぐらいだ。蹴りを入れようかと思ったのを、すんでの所で堪えてやったのだから。「その冗談は笑えないわー。お前の身体って、俺が目指しているモノとは真逆だしー」「いちいち癪に障る言い方だな。何なんだ、一体」姿見に全身を映し、ネクタイの曲がり具合を調整していると、平塚も隣りで同じことをしていた。犬君としては真似るなと言ってやりたかったが、明らかにネクタイが曲がっていたので今回は目を瞑ることにした。「今日さー、俺ってば誕生日」「……。へぇ。あっそう。おめでとー。……で?」「で、じゃねぇよ」鏡の中で、平塚は膨れ面をしている。犬君には理由が分からない。誕生日おめでとう。それの何がいけないんだ?「何かさー、ほら、こう……なんかねぇのかよー。祝ってくれよー。俺、今ロンリーなんだからさー」「うわ、ツラ。キツ。まさか自分からねだるのか……」「いーぬーきーくーーーーん」「やめろよ変態。話し掛けるな。お前なんか知るか」そこをたまたま杣庄が通りかかる。午後からの遅番である平塚や犬君と違い、杣庄は早番で、昼休憩中だったのだろう。ピリピリとした空気が漂い、犬君と杣庄の冷やかな目が交差したかと思うと、杣庄は白けた様子で更衣室から出て行った。(馬鹿にされた……っ)犬君はこの憤懣やるかたない感情を、やはり平塚にぶつけるしかなかった。*「あのー、すいません。そこのジュースの自販機にお金入れたんだけど、商品出てこないんだよねー」制服を着崩した2人の女子高校生が、奇跡的に担当者である青柳チーフと犬君を捕まえたのは17時のことだった。こういう苦情はまず手近な従業員に届けられ、そこからPHSを経由してドライの社員に回って来ることが多いため、青柳は感動すら覚えた。「しかもお誂え向きに自販機の鍵を持っている俺。今日はツイてるな」女子高校生には聞こえないように、青柳は犬君に小声で告げる。「チーフ、そのツキを僕に恵んで下さい。昼頃からツイてないんです」「え、今日のお前、疫病神なのか? ダークフォースお断り。あまり近寄るな」「『スターウォーズごっこ』ついでに、一緒にダークサイドに落ちましょうよ、ブルーウィロー卿」「お前それ、単に俺の苗字を英語で言っただけだろう。適当に訳したのはいいが、ブルーウィローっていう立派な皿があるんだよ」「……恥の上塗りをしてしまった……。今日は三隣亡だ……」「博識だと思うなら、これからはジェダイ・マスターと呼んでくれ」「了解です、ジェダイ・マスター」そんなふざけたやり取りが行われているとも知らずに、件の女子高校生たちは自販機の前に立つなり「これ」と紅茶のパネルを指差す。「叩くと直るって、よく言うよねー」「言う言う。まぁそんなお子様チックなこと、うちらはやらないけどねー……って、ん?」言葉遣いの割に、随分と高尚な心根の持ち主である女子高校生たちをよそに、青柳はどん、と自販機を叩いた。「……うわ。叩いたし……」「しかも、出て来たし……」購入予定だった紅茶のペットボトルが音を立てながら取り出し口へと滑り落ちて来た。「あはは! イケメンのおにーさん、ありがとー」「お店の人なのに、荒っぽくて無茶苦茶。でも、ありがとーございましたっ」「どう致しまして」彼女たちが去った後、中の様子を調べるために青柳は鍵で解錠し、扉を開けてみた。青柳の顔が曇る。「あー……」「どうしました?」「さっきの彼女たちの前に、買い損ねた客がいたみたいだ。お金を投入したものの、商品が出てこなくて諦めたのか」そう推理する青柳の手には、在庫過多となったお茶のペットボトル1本。「僕ならさっきの彼女たちみたいに言いますけどね」「人それぞれなんだろうな。それにな、面白いとは思わないか?あと数百歩も歩けば、店の中で更に安く、全く同じモノが買えるんだ。なのに、より高い自動販売機で買い求めてしまう。つまりここで買い求める客と言うのは、時間と歩く労力が惜しいんだな。そう考えると、苦情を言わずに立ち去る人の心中も分かるというものだ」「さすがジェダイ・マスター。何かのビジネス書に書かれたような御高説、胸に沁み入ります」「相変わらず慇懃無礼だな。そんなジェダイ・パダワンのお前にやるよ、ほら」帳尻合わせの為、青柳はお茶のペットボトルを犬君に渡す。犬君は思いきり不服そうな顔をした。「パダワンはないでしょ……。せめてジェダイ・ナイトにして下さい」*時刻は21時を回り、男子更衣室は帰宅準備をする従業員で溢れていた。犬君がネクタイを緩めていると、「お疲れー」と、平塚が本当に疲れた顔で自分のロッカーにやって来る。「忙しかったみたいだな」「お陰様でね。あー、くたくただー。ケーキ食いたかったのに、買えなかったぜちくしょー」上着を羽織るだけで平塚の準備は済んでしまう。早々にパタンと閉めると、「じゃあな」と言って出口に向かった。「平塚」「あん?」振り向きざま、犬君はお茶のペットボトルを放り投げる。あたふたと受け取ろうとするが取り損ねてしまい、床へと落下したペットボトルの角がべこんと凹んでしまった。「悪ィ」「いや、いいんだけど、なにこれ」「何ってプレゼントだよ。誕生日なんだろ? おめでと」犬君はそっけなく言い、ハンガーにかかっていたコートに手を伸ばす。「ふ……ふわぁ……。お前ってやつは……何ていいヤツなんだ」「暑苦しい。やめろよマジで。ちなみにそれ、在庫過多でタダの商品」「わざわざそんなこと言うなよ。それでも嬉しいから。サンキュ。じゃあな」くるりと向きを変え、ドアノブに手を掛けた平塚だったが。後ろからダウンジャケットを、しかも首部分を強く引っ張られ、ぐえっと息を詰まらせる。「て、てめぇ、どういうつもりだ、不破! 死ぬかと思ったぞ!?」「死んだらこれも食べられないぞ」着替え終わった犬君の手には小さな紙袋が提げられ、それを平塚の顔面に突き出したのだった。それを怪訝そうに見つめる平塚。「……なんだ?」「やるよ。さすがにペットボトル1本、しかも在庫過多による進呈なんてあり得ないだろう」ハテナマークが飛び交う平塚を置いて、さっさと犬君は歩き出す。紙袋の中身を確認した平塚は暫く無言だったが、やがてダッシュで犬君を追い、後ろから羽交い締めにした。「お犬様~! 大好きだワン!」「うざ……」紙袋の中にはキッシュと抹茶ケーキ、ミルクレープ、びわタルトが入っていた。閉店間際に犬君がケーキ屋で買い求めた商品だから、選ぶ余地はなかった。そもそも平塚の好みなど全く知らないのだが。「よし、これから俺の部屋に行って、一緒に食おうぜ」「嫌だ。帰って寝る方が、よっぽど有意義だ」憎まれ口を叩いてはいるものの、なんだかんだと人に甘い犬君である。結局は平塚に付き合いケーキを分け合ったのだが、そんな過ごし方をしたとは誰にも言えない秘密なのだった。2012.01.13 2020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
01月01日 ■ 柾直近
01月01日 ■ 柾直近正月=仕事という公式で成り立っている小売店。そこに連なる関係者各位は、碌に休息と安寧と年末年始の気分と酒を味わうこともなく、早朝よりあくせく働く。――今日も今日とて。「動かない」手元を見下ろし、ぎこちない動きしか出来ない五指の状態にやれやれと溜息をつく。息は白いわ鼻がツンと痛むわで、『身体がシバる』とはこういうことを言うのかと、妙なところで腑に落ちるのだった。そもそも場所はユナイソン従業員出入り口の検収所。荷物の搬入があるため、大きな扉が口を開けた状態だ。朝一番に動き出すのがこの部署だ。今、検収の人間は三々五々に散り、業者のトラックから積み下ろされる荷台と伝票を照らし合わせている。そんな彼らをよそに、僕は麻生と2人で机を借り切っていた。机があるのは部屋の中だが、部屋が暖まっていないため、どうしても隙間風が身に沁みる。「麻生、手が動かないから伝票がめくれないんだが」己の身に起きた不幸を嘆くと、L字型机の『_』の位置で作業をしていた麻生は無情な言葉を浴びせかけた。「そんな言い訳が通用すると思ったら大間違いだからな」麻生は怒っている。そのゲージは、彼の担当部署である家電の伝票を探しあてることでしか下がりはしないだろう。先日、書類の上に書類を重ね、誤って家電の伝票まで束ねてしまった。誰が悪いかと言えば、僕……らしい。「お前と作業をしてたんだから、犯人はお前だろ」というのが麻生の弁だ。――御尤も。「だがこう寒くてはな。時間を改めて、また来る」「そう言って、自分ンとこの開店準備に戻るつもりだろう。そうは問屋が卸さねぇぞ、柾」「当たり前だろう。こっちは売り場の回転率が早いんだから」元旦は福袋目当ての客で賑わう。コスメの袋は買い得だと知られており、事前予約の電話もよく鳴ったものだ。「へぇー……」どうやら僕の言葉は麻生の不興を買ったようで、ヤツは切り口を変えて反撃してきた。「回転率は早くても、売上で言えば家電が上なんだよなぁ~」「値段の桁が違うんだから当たり前だろう。難癖をつけるな」「ったく、11時までには見付けろよ」「3時間しかくれないのか? 鬼だな」そうやって憎まれ口の応酬をしていると、検収の前を1人の女性が横切った。白いコートがふわりとなびき、その人物が誰か気付いた瞬間、検収の窓をがらりと開けていた。「おはよう、千早」「えっ……。あっ、おはようございます、柾さん! お誕生日、おめでとうございます」あけましておめでとうじゃなくて、お誕生日おめでとうと言う。千早歴とはそういう子だ。公の祭事より、個の祝事を祝ってくれるような、そんな優しい面はとても魅力的で好ましい。「ありがとう。新年おめでとう」「あけましておめでとうございます。……あっ、麻生さん! おはようございます」千早の位置からは奥になるため、麻生の姿を認めたのは、まぁ当然僕より後になってしまうだろう。麻生は椅子ごと身体を千早の方に向けると、「おはよ、おめでとさん」と笑う。「はい、おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします」深々と礼をする千早だったが、顔をあげるとハテと首を傾げ、「何をなさってるんです?」と疑問文。「麻生の伝票を捜してる」「行方不明なんですか? 私もお手伝いします」着替えてきますから、少し待っていて下さいねと言い残し、走り去る千早。「お前、売り場へ戻るんだろう?」にやにやと意地の悪い笑みを浮かべる麻生に「気が変わった」と短く告げ、椅子に座り直した。10分と経たずにやって来た千早は、部屋に入るなり「この部屋寒いですね」と臆した声で言う。「お二人とも、大丈夫ですか?」「ちぃ、そこで飲み物買って来てくれると嬉しいんだが」出入り口付近に自動販売機が並んでいるので、それが恋しくなったのだろう。依頼主の麻生は財布から千円を抜き取ると千早に渡した。行儀よく、両手で紙幣を受け取る千早は可愛い。「温かいやつなら何でもいいや。3人分な」「はい。分かりました」小走りに駆ける千早を見送っていると、麻生から「伝票」と急かされ、やむなく視線を机に戻した。ほどなくして、缶飲料を大事そうに胸に抱えた千早が帰って来た。羨ましい缶どもめ。「お待たせしました。どうぞ」と言って手渡されたのは、コーンポタージュ。3つともそれだった。「千早にしては……珍しいな?」いつもなら僕にはブラック、麻生にはホットレモンやお茶、千早自身にはカフェオレや紅茶なのだが……。どういった風の吹き回しだ?「あ……苦手でしたか?」「いや、むしろ俺は好きだけど」「僕も好きだが……」その言葉に、千早は「よかった!」と顔を綻ばせる。極寒の地に春の女神が舞い降りたような気がする。「どれにしようか悩んでいたら、外で作業をなさっていた方が御丁寧にも教えて下さったんです。『普通にコーヒーやお茶を買うより、コーンポタージュの方が温かさが持続するからいいよ』って。『振ればさらに温かくなる』って仰るんですけど、本当かしら……。あ、ホントですね」「……千早。誰から訊いたって?」「え? ですから、いま外で運搬作業中の……確か、≪ロセ・パン≫の方です」「男性? 若いの?」「? はい、男性です。杣庄さんぐらいの年齢かしら……?」うかうかしていたら取られてしまう。最近、本気でそう思う。「あのぅ、それが何か……?」新年早々、恋愛バトルのゴングが鳴り響く。やれやれと再び溜息。「取り敢えず、千早は僕と一緒に伝票を捜そう。そのあと一緒に仕事をして、一緒に昼飯を食べて、一緒に店を出て、一緒に初詣に出掛けよう。一緒に帰宅して、一緒に夕飯を食べて、一緒にケーキを食べて、一緒に風呂に入って、一緒に寝よう」「……バカか、お前」結局自分の力で伝票を掘り出してみせた麻生は、綴じ直した分厚いファイルで僕の頭を叩く。「一緒にケーキを食べて、まででしたら喜んで。麻生さんも御一緒に……」「は? 俺も? いや、ちぃ、空気を読め。お願いだから」「空気?」「……分かった。麻生も一緒に」「……。悪いね、柾……」「謝るな。余計胸が疼く」本当に、うかうかしていられない。決意も新たに、今年は何とかしようと思う。――かなり本気で。2012.01.012020.02.22 改稿
2020.02.22
コメント(0)
-
誕生日編【目次】
01月01日 ■ 柾直近 01月04日 ■ 平塚鷲 02月05日 ■ 児玉絹 02月05日 ■ 児玉玄 02月13日 ■ 姫丸二季03月14日 ■ 不破犬君 03月22日 ■ 麻生環06月01日 ■ レオナ・イップ06月02日 ■ 児玉菫07月29日 ■ 伊神十御07月31日 ■ 潮透子08月06日 ■ 八女芙蓉08月18日 ■ 志貴迦琳09月01日 ■ 千早歴09月07日 ■ 鬼無里因香11月19日 ■ 五十嵐資11月30日 ■ 青柳幹久12月09日 ■ 杣庄進12月11日 ■ 鬼無里火香12月26日 ■ 千早凪01月 …… 01┃柾 04┃平塚02月 …… 05┃絹 05┃玄 13┃姫丸03月 …… 03┃邑 05┃小春 14┃犬君 22┃麻生04月 …… 17┃そよ香 27┃奈和子05月 …… 05┃唄06月 …… 01┃レオナ 02┃菫 10┃後藤田 26┃碩人07月 …… 02┃涙無 0┃3加納 06┃馬渕 16┃佐和子 17┃恭子 27┃那漣 29┃伊神 31┃透子08月 …… 04┃茨 06┃芙蓉 09┃迦琳 27┃有賀 29┃間宮09月 …… 01┃歴 04┃黛 07┃因香 10┃為葉 17┃三原10月 …… 09┃香椎 29┃都築11月 …… 19┃五十嵐 30┃青柳12月 …… 09┃杣庄 11┃火香 26┃凪
2020.02.21
コメント(0)
-
G4 (迦) 【計画的な、犯行ね】
日常編 (迦) 【計画的な、犯行ね】声が聴きたい。一言でいい。どんな言葉でもいいから。この耳で、貴方の声を捕らえたい。*ひと月目はどうってこともなく、淡々と時が過ぎていった。あと2ヶ月も経てば出張から帰ってくるんだし、この調子なら平気。そう思ってた。それは強がりでしかなかったことを、42日目にして悟る羽目になる。今や放り出された砂漠の中で、オアシス目指してまだかしらと挫けそうになる寸前。忘れてないよ。今だって鮮明に思い出せる。脳裏にきちんと焼き付いて、こびり付いたままだもの。でも私が欲しいのは、記憶より実体。*「不破君、寂しいよ」スルリと口から漏れた私の言葉に、後輩はひどく動揺した。その証拠に、彼の疑惑の目は私の感情を読み取ってやらんとばかりに固定されている。「志貴さん……。嘘でしょう? 今なんて言いました?」恐る恐るのていで、不破君は尋ねた。「寂しいって言ったの。チーフがいなくて寂しい。つらい」どうやっても気持ちは誤魔化せない。本音を吐かなければ、不安に押し潰されそうで怖かった。こうして受け止めてくれる人がいる。それだけでも私は恵まれていると知る。「今頃なにしてるんだろ。向こうに素敵な女性がいたらどうしよう」「志貴さん、電話してないんですか? メールは?」「してない」私の回答に不破君は目を丸くした。「ちょっと……。天邪鬼になるところが違うでしょ。そこは変な意地張ってちゃ駄目ですよ」「歯止めがきかなくなってしつこく連絡したら嫌われちゃうでしょ。私は自分を律することに不得手なの」「寂しいなら寂しいって素直に伝えるべきです」「無理よ、私は不破君じゃないもの。……いい、我慢する」我慢は慣れてる。今までだって、ずっとそうしてきた。隠すのは得意だったじゃない。私なら楽勝よ。「またそんな無理をする……」「ごめん不破君。私から切り出したのに。忘れて」両手を合わせて詫びる私を見下ろしながら、不破君は納得のいかない顔のまま無言を貫くのだった。*控え目なノック音がして、私は「はい」と応じた。「どうぞ」ドアを開けて入ってきたのはPOSオペレータの千早歴ちゃんだった。「おはようございます、志貴さん」鈴の音を彷彿させる澄んだ声、綺麗に着こなした制服姿、それらに見惚れながら、「どうしたの?」と尋ねる。頬に添えられた指、小首をちょこんと傾げた仕草から窺うに、千早ちゃんは困った様子だった。「志貴さん、分からないことがあるんです」そう言ってすいと差し出されたファイルには、【POS/EOS】と打たれたテプラが貼ってある。販売時点情報管理のPOS、そのPOSを活用した補充発注システムのEOS。どちらもマーケティング用語ではメジャーだ。中を開けばマニュアルがページ順に綴ってあった。POSルームで管理されている手引き書なのだろう。「実はこのマニュアル、祖本なんです。改訂版の存在を知り、本部に送って貰うよう手配したんですけど……」今日の便で送るため、到着は早くても明日になると言う。「でも、明日じゃ間に合わない作業があるんです」聞けば千早ちゃんには青柳チーフから『出張期間中だけ頼む』と割り振られた仕事があるのだとか。それは1週間に1度、決められた日に行う作業で、ここ数週間は順調に作業出来ていた。「でも、今回はイレギュラーな作業がありまして。マニュアルを見ても古いから載っていないし、先輩方はお休みですし……」女傑四人衆は温泉旅行中で、潮透子ちゃんは本日休みだった。なるほど、それで私のところに来たのね。「どんな作業?」「マーチャンダイジングの情報をPOSの機械へ送るんです。その際、不要なデータなどの取捨選択を――」「ごめん、分かんないや」完全に青柳チーフの仕事だ。でもチーフ、それを私ではなく千早ちゃんに振るなんて……。「志貴さん?」悶々としているところを呼び掛けられ、ハッと顔を上げる。心配気な顔が私を覗き込んでいた。「あっ、ごめんね。それは私だと分からないし、不破君も……知らないだろうなぁ。他群番はどうかな?」「発注の仕方が違うみたいです。でも今日までに行わなければいけなくて」「それは困ったわね」私はと言えば、「うーん」と唸るばかりの脳無しである。「志貴さん。申し訳ないんですけど……」「なぁに?」「青柳チーフと連絡を取ることって出来ませんか?」「えっ!?」「あのっ……お願いします!」90度のお辞儀をして、そのまま顔を上げようとしない千早ちゃんをおろおろと見下ろし、「やめてやめて千早ちゃん」と私。「お願いしますぅ……」「きゃー! ちょっと、そのお願いの仕方は反則よぉぉぉ。わ、分かった! 分かったから」要求を受け入れると、千早ちゃんはコロッと笑顔になり、「本当ですか!? ありがとうございます!」と早変わり。「ちょ、ちょっと待ってね」ごそごそとスカートからスマホを取り出す。奇しくもア行の一番上に、かの人の名前はあった。逡巡しつつも、千早ちゃんのためと言い聞かせ、発信ボタンを押した。2回のコール音がしたのち、「青柳です」息が詰まったのは、一瞬のことだった。胸が高鳴り、心臓がどくどくと脈打つ。「あ、あの、おつかれさまですチーフ。今宜しいでしょうか」「志貴か。どうした?」あとにしてくれ、とは言われなかった。このまま話し続けても平気なのだろう。私は千早ちゃんがチーフと連絡を取りたがっている旨を伝え、彼女に代わる。3分程度のやり取りがあり、お忙しい中ありがとうございましたと締め括った彼女は私にスマホを寄越した。千早ちゃんの悩みは無事解決したようだ。「あ……チーフ、有難うございました。ではこれで失礼します」惜しみつつ、電話を切ろうとした。すると、「志貴、元気か?」この声は――聴き覚えがある。きっと受話器の向こうで、微笑している。ありありと、まざまざと、思い出すことが出来る。「はい、元気です」正確には、「元気になりました」。「そうか、それはなにより。あぁそうだ。3ヶ月の予定だったが、つい今しがた、お達しがあってな。俺の後任が決まったらしい。引き継ぎ終了次第、そっちに戻る」“お待ちしております”。出掛かった本音を抑え、代わりに「えぇ~」という不満を電話口へ漏らす。「俺がいないからって、羽根を伸ばせるのも今の内だ。束の間の平穏を、精々楽しんでおくんだな」この声も思い出せる。不敵に笑っているに違いない。会いたい――早く会いたいな。「帰って来るなとは申しません。ただ、東京土産をたくさんご用意しておいて下さいね。私も不破君も千早ちゃんも大変なんですから」「東京でしか買えないヤツな」「約束ですよ」「あぁ」「嘘付いたらハリセンボンですから。美味しいディナーご馳走して貰います」「志貴と行くのか? 面白い。これはわざと買い忘れるのも一興だな」「なっ……。う、嘘です今の嘘! 今のナシ! 失礼します!」勢いよく電話を切り、またやってしまったと大後悔。でも……でも。「嬉しそうですね。よっぽどイイコトがあったんでしょうね」すぐ真横からしれっとした声が聴こえてきて、思わず身を引いた。いったいいつの間に不破君がここに!?「お陰で助かりました、志貴さん。ありがとうございました!」さらにその横で、にこにこと微笑む千早ちゃん。「ダラしないなぁ。ニヤけ過ぎですよ、志貴さん」呆れた口調で指摘され、「ち、違うわよ。ニヤけてなんかいないわよ、失礼ね!」と反論する私の声は、わずかながら上擦っていた。「それより、よくも2人して私を担いだわね?」「何のことでしょうか」「しらばっくれないで、不破君。千早さんに、青柳チーフに電話するようお願いしたでしょっ」「えぇー。そんな面倒なことしませんよー」「千早ちゃん、彼から依頼されたのよね?」「……いいえ? 私は本当に困ってました」にこにこにこと千早ちゃん。「そ、そう? それならいいの。そういうことにしておいてあげるっ」照れ隠しでソッポを向くと、ぷ、と無礼にも不破君は小さく吹き出した。私は敢えて、気付かない振りをする。顔を真っ赤にしたままで。2013.07.042023.02.13 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G4 (迦) 【たまには、甘える】
日常編 (迦) 【たまには、甘える】6時。これが私、志貴迦琳という人間の稼働開始時間だ。染み付いた慣れは他にもあり、例えば家事は朝方済ませるようにしている。洗濯物干し、各部屋の掃除、食事の仕込み等。すべては仕事後の私を楽にするため。安息を欲するであろう夜の自分のために、朝の内にギアを入れておくのだ。*今日も今日とて6時に起き、To Do LISTに何本かの完了線を引いた頃には3時間が経っていた。休日は細かい部分にも目を光らすことが出来る。窓の桟だとか、排水溝の掃除だとか。そこに手を付けてしまうと懲りだしてしまい、早く起きた割には遅めの時間に朝食を摂ることになる。朝食メニューは、その時の気分次第。今日はなんとなく洋食が食べたかったから、サラダスパゲッティを大目に作り、クロワッサンと併せた。飲み物はコーヒー。インスタントの日もあれば、豆を挽いて本格的に淹れることもある。大抵前者は平日で、後者は休日。キリマンジャロを豆から挽けば、香ばしい匂いだけで眠気やストレスを吹き飛ばしてくれそうだ。ミルを片付けていると、ふとインスタントのコーヒー粉を切らしていた事に気付いた。そう言えば昨日仕事が終わったその足で買うつもりだったのに、うっかり買い忘れてしまったんだっけ……。どうせ買い物に行く予定だ。でもその前に、スマホを使って近所のスーパーのWebチラシをザッピング。鳩屋にてインスタントコーヒー日替わり奉仕価格398円。お1人様2点限り。しめた。鳩屋は比較的近いスーパーだ。自転車で3分という好立地条件にある地方スーパーは心強い。裏を返せば、鳩屋はユナイソンの好敵手でもある。だけど今日の私は給料前。半値以下の値段を見せられたら、黙って買いに行くしかない。スーパーの一社員である前に、一消費者でもあるのだ。*鳩屋の開店時間は朝10時。開店5分前の段階で、自転車を利用する地元付近の主婦たちが、ドアが開くのを今か今かと待っていた。10時になりドアが開くと、欲しい物目掛け、彼女たちは奮闘する。かくいう私も、大きな声では言えないが、歩を強めて今日の目玉であるインスタントコーヒーを求めた。1人2点なので、在庫にはまだ余裕があった。でもきっとこの調子では10分ないし15分で完売するだろう。……などと冷静に見積もる悪いクセを、つい、してしまったり。いけないいけない。ここにはもう用もないのだし、買い物客の邪魔になるだけなので撤退しなければ。ふと、去り掛けて思う。擦れ違う人の中には老人も多い。欲しい商品を無事に手に取るまでの、なんと不利なことか。ほら、今だって。おばあさんが杖をついてゆっくりフロアを歩いてる。その間に何人のお客が彼女を追い越して行った?1回目の清算を終えた心無い客が引き返し、再度同じ商品に手を伸ばしたかと思うと今度は違うレジを通って2個目を手に入れようとしている。これが10分後ならば、おばあさんの手にはもう行き届かなかったかも知れない。それはなんて見るに忍びない、切ない光景だろう。願わくば、どうか在庫が多くありますように。バックヤードから補充されますように。ちくりと胸に小さなトゲ。あーあ、なんだかな……と思っていたから、油断していたんだと思う。「インスタントコーヒー、どこにありました?」擦れ違った人に声を掛けられ、思わずこう口走ってしまった。「はい、いらっしゃいませ! 日替わり奉仕品のインスタントコーヒーでございますね? こちらでございます。ご案内いたします」って、しまった! つい条件反射で普段の客対応! なまじ、売り場を知っていただけに!スマイルに加え、親指を折り曲げた手で堂々と売り場を指し示した私なんて、私服を着た鳩屋の店員にしか見えないだろう。案の定お客は、『えぇ……? この子、店員でもないのに、一体なんなの……?』と不信そうな顔で私を見ている。鳩屋の店員だと勘違いされたに違いなく、とは言えユナイソンの店員がライバル店で買い物に来たと思われるのも、それはそれで後ろめたい。何にせよ、この人を案内しなければ。「どうぞ、こちらです」普段の要領で案内をし終えると、ドッと伝う汗を背中に感じながら、そそくさと逃げるようにレジへ向かった。*翌日の昼食時、その出来事を杣庄君に話したら、彼は真面目な顔で応じてくれた。「一種の職業病ですよね。分かりますよ、俺も頻繁にやらかすんだよな」「杣庄君が?」彼は眉を寄せると、思い出したくないような口振りになる。「例えば、よそのお店の鮮魚コーナーに行ったとするじゃないですか。で、刺身が視界に入る。身の切り方が、なってない。『こんなの商品になるか! 撤去してやり直せ!』と口走りかけて気付く。あぁ、ここ俺の戦場じゃなかったわ……って」「あるある! 商品の陳列が汚いと、つい直したり」「あ~、出ますよね、手が勝手に。それとか、賞味期限の日付をチェックしてた自分に気付いたり」「するする! 『え、これまだ見切らないの?』って心の中で大きな世話なんか焼いたりして」あるある談義で盛り上がっていると、社員に割り振られているPHSが鳴った。青柳チーフからだ。 「はい、志貴です」「休憩中に悪い。店が混んで来た。戻って来れるか?」「分かりました。今行きます」通話を終えると、向かいに座っていた杣庄君が「店、混んでるんスか?」と腰を浮かせかけた。「そうみたい。ちょっと行って来るね」「俺も行きます」食堂備え付きの湯呑みだけ返却口へ戻すと、持参したお弁当箱を掴んで社員食堂を後にした。*食料品売り場のレジが異様に混んでいた。青柳チーフと不破君は、2人ともレジの応援に入ったようだ。売場を見れば商品が欠品していたりして、棚ががさがさの状態だった。早速アルバイトを2人集め、商品補充の指示を出す。自分も出来る範囲で品出しをしようとバックヤードへ商品を取りに行きかけると、「すみません」と声を掛けられた。「はい、いらっしゃいませ!」スマイル0円で振り向くと、何故か違和感を覚えた。一瞬デジャヴュ。あれ……?「このお菓子パックなんですけどね。子供会で配りたいので3箱注文したくって。……あら、あなた確か昨日の……」昨日の……? そうだ、思い出した! 昨日私がドヤ顔でコーヒー売り場を案内しようとしたお客様だーっ!!バレてしまった。ユナイソンの店員だということも、失態をおかした変人だということも。うろたえていると、「志貴」と青柳チーフの声がした。どうしてよりによってチーフが!? さっきまでレジにいたじゃない!?「お客様。部下が失礼を働きましたでしょうか」「いえいえ、そうじゃないの。昨日はありがとう。とても素敵な笑顔で分かり易い案内だったわ。こちらの従業員だったのね。道理で丁寧に答えて下さったわけだわ。あなたは、この方の上司? 教育が行き届いてるのね。この子のお陰で、昨日は気持ちのいい買い物が出来たのよ」「!」ほ、誉められた……。お客様から、じかに……!「ありがとうございます。またの御利用をお待ちしております」隣りでそつなく微笑む青柳チーフ。私は夢心地のまま、ポーっとなる。「じゃあ、あなたに頼もうかしら。子供会の……」「は、はい! お菓子パックを3箱ですね。畏まりました。いつ頃の御入り用でしょうか?」「来週末の土曜までには欲しいのだけど」「在庫を確認次第、折り返しお電話させていただきますので、こちらにお客様の氏名と電話番号をお願いします」*注文のやり取りを終え、商品の発注を掛ける。後は商品が到着次第、お客様に連絡が行けば無事完了だ。ドライの控室にて仕入れ先に発注の電話をし終えると、青柳チーフが部屋に入って来た。「休憩中だったのに呼び出して悪かった。残りの30分、行っていいぞ」「はい」許可が出たので胸元に再び休憩バッジを付ける。腕時計で戻って来る時間を確認しながら退室しかけると、「志貴」と名前を呼ばれた。「はい」「よくやった」自分だけに向けられる、青柳チーフのその微笑が嬉しくて。口元が緩むのを必死に堪えながら、私は頷いた。そしてその顔がバレないようにスッと移動する。今日は自分へ御褒美をあげたい気分だ。買ったばかりのインスタントコーヒーで、甘い甘いカフェオレを作ろう。マシュマロだって入れてしまえ。スライスしたチョコだってトッピングするんだ。ホイップを添えてもいいかも。とにかく、今日の夜はとびきり自分に優しく、おめでとうと祝杯をあげたい気分なのだった。2012.03.082020.02.13 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G4 (―) 【遊びじゃ、ないの】
日常編 (―) 【遊びじゃ、ないの】【1】「よぉ青柳。シケたツラしてやがんな」つなぎ服を着た男2人のうちの1人が、青柳と擦れ違いざま声を掛ける。青柳は、ありがたみに欠ける悪友の登場にやれやれと溜息を吐いた。そんな反応すら楽しむように、一廼穂碩人は笑う。「こんな雨じゃ、客足も少ねぇよな」がらんどう。そんな言葉が相応しいほど店内は静かだった。開店してから3時間は経過している。つまり、もう正午過ぎだ。なのに朝から客数より従業員の方が多い。碩人の言うように、降り続く大雨が原因だった。従業員でさえ通勤の途中で引き返したくなるほど、風雨の強さには辟易していたのだ。なおさら客は来たがらない。それに、この大雨は数日前から決定していた。それを裏付けるように、前日午後の売り上げは異常に高かった。『その代わり、明日は絶対出掛けないから!』とでも言うかのように。「あーあ、見切りの量も半端ねぇな。このパン、いつまで保つんだ?」碩人は、青柳がさっきまでシールを貼っていた商品に手を伸ばす。昨日の昼過ぎに品切れを起こしそうになり、慌てて業者に連絡して追加発注した分だ。ある程度の数はさばけたものの、種類によっては見事に在庫が残ってしまっていた。ネイビーのつなぎ服を着たもう1人の男も、同じように商品を手に取る。アーミーグリーンの碩人よりは、清潔な作業着だ。「賞味期限は明日の日付だね。オレ、今日のお昼これにするよ」「伊神、お前の優しさにはマジで敬意を評するわ。チョココルネなんて見るからに甘そうなもの、よく選ぶな」「辛いのも買えば、プラマイゼロじゃない?」「まぁな……」と碩人。「そうか?」と青柳。伊神は悩むことなく、ひょいひょいとパンを3つ取り上げる。チョココルネ、あらびきソーセージ、黒胡椒バジル。これだけで総カロリーは千を超える。その事実を伝えたものの、伊神は大して気にもせず買い求めた。よく3つも食えるなと呆れた碩人も、何だかんだ言いながら在庫過多で苦しんでいる青柳を助ける形で2個購入。「助かる」心の底から礼を述べた青柳も、自ら責任を取る形で3つ買い求めた。【2】結局、1日を通して客は少なかった。早番だった青柳と碩人、伊神の3人は定時で上がり、そのままテナントで夕食を済ませることにした。3階の『ソナタ』には外国のお酒が種類豊富に置かれているので、満場一致でそこに決まった。お馴染みの定位置を確保する。まるで今日は従業員のために開けていますとばかりに見知った顔がちらほら。意外にも、ソナタには同じく早番だった志貴迦琳がいた。同期の社員と一緒だ。向こうは会話に夢中のようで、3人が入って来たことに気付いてすらいない。青柳には、寧ろ好都合のように思えた。料理と酒を味わいながら友人と親交を深め、しばらく静かな時の流れを堪能する。贅沢なひとときだった。気付けば志貴たちの姿がなかった。いつ会計を済ませたのかは分からないが、時計を見れば自分たちも2時間の滞在を超えようとしていた。腕時計を見下ろす青柳に「そろそろ出るか」と碩人が声を掛け、伊神も頷く。阿吽の呼吸のように3人の意見が一致した。会計を済ませると、店を出たところで志貴が立っていた。「バイバーイ」と言いながら一緒にいた社員に手を振っていたところを見ると、2人は店先で別れたようだ。「志貴」「あ。青柳チーフ……」目が合う。そして、お互い無言。青柳の背後から碩人が顔を出し、「おー、志貴じゃん」と声を掛ける。「こんばんは、志貴さん」「こんばんは、伊神さん」「ん? 志貴よ、なぜ伊神にだけ挨拶を?」腑に落ちないながらもにこにこ笑う碩人を丸々無視し、志貴は青柳をじっと見つめた。「な、なんだよ」落ち着かない青柳に対し、志貴は小さく呟く。「……『青柳会』」青柳は絶句した。次の言葉を絞り出すのに、十分長いと思わせるほどの間が空く。「お前……どうしてその名前を……一体どこから……」「おぉ……感激。久々に聞いたな、その名前」からかうように碩人が言うものだから、青柳は「黙ってろ」と牽制せざるを得ない。「志貴さん、急にどうしたの?」「八女さんから聞きました。昔そんな会があったって。竜平会とか、そういう類のものですよね?」「え? いや、別にお笑いは目指してなかった……よね?」伊神は目を丸くして青柳を振り返った。わななく青柳の肢体、一方でツボにハマったのか、碩人は腹を抱えて笑っている。「なんて日だよ、今日は。あーおもしろ。志貴、青柳会ってのは、女傑四人衆が作った青柳ファンクラブだ」「碩人!」「会の存在を知られちまったんだ。内容を掴まれるのも時間の問題だろ? だったら正確に教えた方がいいんじゃねぇか」「そういう問題じゃない」「おー照れてる照れてる」「照れてない」囃したてる碩人の背中をドンと押す。相変わらずカカと笑う碩人は頭の後ろで手を組み、先へ。伊神もその後に続く。「まったく……」やれやれと呆れる青柳だったが、――かくん、と身体がほんの少しだけ傾く感じがした。振り返れば、歩きかけた青柳のシャツの裾を、志貴が掴んでいた。「おい?」見下ろせば、志貴は顔を背けている。それなのに、手は青柳の服を放そうとしない。「……私も加入したかった……」ぽそりと呟かれたその言葉に、青柳はまたも絶句する。碩人とトオゴには聞かれてないよな、今の――?前方を見れば碩人と伊神は和気藹藹と喋っていて、こっちのやり取りには気付いていない様子。青柳は胸を撫で下ろした。「……会は既に解散しちまってるよ。それにお前が加入したところでメンバーがたった1人なんて、そんな会、どう考えてもおかしいだろ」「……青柳チーフの良さを知っているのは私1人で十分です……」そう告げる顔は、誤魔化しがきかないほど真っ赤で。「……お前さ、何で今そゆこと言うかな……。時と場合を考えろよ……」なんて残酷な女なんだろう。いつもは可愛げのない暴言ばかり吐くくせに、稀に砂糖蜜のように甘い甘い言葉を紡ぎ出す。だからこそギュッと抱き締めたい。その衝動はいつも突然で、しかも今日のようにタイミングが悪い日が多いのだ。でも今日は。今日こそは。……くそ、碩人や十御に、なんと言って一抜けすればいい?どうせ何を言っても冷やかされるのがオチだ。特に碩人からは。ならばいっそ、ハッキリ『志貴と一緒に帰る』と言ってみるか?「……嘘です。それじゃあ」パッと手を放し、くるりと方向転換。呆気に取られる青柳をその場に残し、志貴はすたすたと歩き出した。「あのアマ……やっぱり可愛くねぇ……!」悪態をつき、2人のもとへ歩く青柳は、もう後ろを振り返らない。顔を赤く染め、泣きそうなまでに切ない表情を浮かべた志貴が、青柳の姿が見えなくなるまで見送り続けていた。2014.08.182020.02.21 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G4 (迦) 【過去から、未来へ】
日常編 (迦) 【過去から、未来へ】たった今、私は聞き慣れない言葉を八女さんの口から聞かされた。その中に私が好意を寄せている人の名前が入っていたから、私はつい、おうむ返し。「『青柳会』? なんですか、それ」「その名が示す通り、青柳に恋した女たちによって発足された会よ」聞き捨てならなかった。だとしたら私も入会しなければならないではないか。入会金、年会費、入会特典はなんだろう。そんな事に思いを巡らせながら、先を促していた。「入会するにはどうすればいいんですか?」真剣に尋ねた私を見て、八女さんは呆気にとられていた顔を、ものの5秒と経たないうちに崩し、小さく噴き出した。「いやぁね、昔の話だってば。そんな会、今はもうないわよ」「いったい何を目的として設立されたんです?」困惑気味に尋ねると、八女さんは、ついと顔を窓の外へと向けた。ここは3階だし、窓際というわけでもない。少し離れている。広がる景色は澄んだ青空、ただそれだけだ。「発足人は元カノ。周りは全員フレネミー。青柳に恋した女4人による、小さな会だった」どきりと心臓が跳ねた。何かの協定……だったのだろうか。「以前、話したことがあったわよね。昔、青柳が好きだったって」記憶を手繰りよせるまでもない。そんな情報はすぐに引き出せた。だって、あの告白はあまりにも意味深だったから。今でこそ八女さんには杣庄クンという恋人がいるけれど、魅力的な八女さんだから、どうしてもそわそわしてしまうのだ。「入社してまもなく配置された岡崎店でね、私たちは出会ったの。香椎、黛、馬渕、伊神、青柳、そして私。青柳はモテたわ。例えばそうね、今でも覚えてるエピソードは……。事務所で作業をしていた時のことよ。たまたま私が電話を取ったのだけど、お客様からでね、おもちゃ売り場宛ての問い合わせだったの。私はその売り場に内線を繋げた。でも、社員は休みで、従業員はレジ対応中なのか、ちっとも捕まえられなかった。私もパニックでね。外部からの電話を取ったのなんてまだ数回だったし、早くしなきゃという焦りで、ただおろおろしてた。そんな時、休日出勤してた青柳が『俺に回せ』と言ってくれて、ことなきを得たの。とても頼もしかったわ。電話を切った青柳に御礼を言おうと思ったけど、彼、店長に叱られてる最中だったの。だから言いそびれてしまって」「え? 青柳チーフ、叱られてたんですか?」「休日出勤が店長にバレて、事務所で叱られてたところだったのよ。でも、そのお陰で私は救われた。周りにいた女性陣も目がハートよ。頼りになる人大好き! ってね。それが香椎たち」「うわ、友達全員がライバルですか?」「そうよ。しかも、友達の皮をかぶった、友を装う敵、つまりフレネミーになったってわけ」女傑四人衆がフレネミー? 頭がくらっとした。あんなクセのある女性たちが腹に一物抱えていた状態でいるなんて、考えるだに恐ろしい!「しかも肉食系女子ばかりだから、みんな押しが強くて。結果的に誰も青柳を射止められず、それどころか彼にトラウマを植え付けてしまったのよね。『アンチ社内恋愛主義』にまで発展してしまうとは思わなかったわよ」「えぇ!? ひょっとして青柳チーフが頑なに社内恋愛を拒否していたのは、つまり」「私たちの所為ね、恐らくは」なんて人騒がせな人たち……。あ、でも。女傑四人衆がいてくれたからこそ、青柳チーフは社内で恋人を作らなかった。私に機会が回ってきたのは、そのお陰なのかも……。「そうね、志貴には感謝して貰わないと」どうやら八女さんに、たるんだ頬を見られてしまったようだ。えへへ、とはにかんだ私を見て、八女さんはふっと柔らかい笑みを浮かべた。そして、ティーカップに注がれた紅茶を飲み干す。「行きましょうか」「はい」午後2時。休憩時間終了。席を立つと、私は大きく背を伸ばした。「午後も頑張るぞ~」活を入れるために。2013.10.032020.02.13 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G4 (青) 【社交的な、紳士然】
日常編 (青) 【社交的な、紳士然】「これ、どなたかここに置き忘れてますね。名刺入れだ。……物凄い量だな」「……俺はこれよりもっとすごい名刺入れを持っている奴を知ってる」「これよりも!? すごい人脈ですね」「人脈、ね。まぁ、あながち間違っちゃいないかな……」数日前、事務所での出来事。麻生さんと俺の、何気ないやりとりが、縁起悪く表現すれば『走馬灯のように』頭の片隅をよぎる中。焦っている俺は千手観音を羨ましく思いながら腕を動かし、ドライの詰め所中の書類や封筒を掻き集めては移動させ、あちこちに紙の山を作り続けていた。「ないですねー、どこにも」「馬鹿野郎、もっと手を動かせ。俺の半分以下の動作で動きやがって」気弱になってしまっていたから、やる気のない不破犬君を怒鳴らずにはいられなかった。とは言え今回の件。不破には全く関係もなければ落ち度もない。とある1枚の名刺を捜しているのは俺で、必要としているのも俺だ。そして紛失させてしまったのも俺。つまりすべて自分の所為なのだから不破に当たるのは八つ当たりというもので、それは重々承知なのだが、猫の手も借りたい時だ。『借りてきた猫』はちっとも動きやしなかったので、悪態の1つもつきたくなってしまうのだった。――許せ、不破。「くそ、どこへ行ったんだ? これだけ捜しても見付からないなんて、そんな馬鹿な……」隣りで不破は、くぁと大きな欠伸。すかさず俺は、その後頭部をはたく。「痛いじゃないですか、チーフ」「ハエがいたんだ、感謝しろ」「あれ、青柳? お前、私服で何やってんだ」背後から声を掛けられ振り返れば、カッターシャツ姿の麻生さんが立っていた。「あ、急用で、ちょっと」ふぅんと短い返答をした麻生さんは、特に急いでいるようでもない。ふと、彼が小脇に抱えたユナイソンのロゴ入り黒封筒が視界に入った。本部専用のブラックレター。そう言えば、事務所に掲げられている出勤ボードの麻生さんの欄。日付までは覚えていないが、今週のどこかで『本部』と書かれていた気もする。とすると、本部から帰って来たところかもしれない。「お帰りなさい、麻生チーフ。鬼無里三姉妹には会いました?」「あぁ、三女にな。お茶を淹れて貰った」どうやら本当に本部帰りだったようだ。その麻生さんが、俺を見つめる。「……なんだか忙しそうだな」「青柳チーフが名刺を失くしてしまったみたいで、てんやわんやなんです」やれやれと大仰に溜息をついてみせる不肖の部下の頭に、俺はもう1度軽い鉄槌を食らわせる。「痛いですってば」「ハチが止まってた」「なぁ青柳、分からないなら代表番号に電話すれば?」「急を要するので、できれば担当者本人の方が……」不破ばかりにちょっかいをかけるわけにもいかず、引き続き手を動かしながら俺は答えた。「担当者? 誰なんだ」「新見さんです」『新見』と教えたところで、麻生さんからすれば「誰だそれ?」とハテナに違いない。俺は「美日(びび)の」、と付け加えた。コーヒーをメインに事業展開を図った『美日カンパニー(BBC)』は食事の時間帯にCMを打つことが多いため、国民の認知度は高い。当然麻生さんもご存知で、「BBCか」と呟いた。「新見さんは苦手です」滅多に人の評価など口にしない不破が、珍しくポソリと呟いた。麻生さんもそんな不破が意外だったようで、「へぇ?」と目を丸くした。「強引なんですよ」取引の手腕が、と不破は嘆いた。不破には何度か新見さんとやり取りをして貰っている。不破にはやりにくい相手だったのだろう。まぁ、新見さんに苦手意識を持っているのは不破だけじゃない。かくいう俺も同じだった。必死に名刺を捜しているのは、新見さんがBBC経由の連絡を嫌がるタイプだからだ。「用があれば自分宛てにかけてください」。過去にそんなお達しがあったので、同じ轍を踏むまいと誓い、いま現在足掻いている最中の俺である。「それは大変だな」と麻生さんは同情してくれているが、同時に尻ポケットからスマートフォンを取り出して操作を始めてしまった。そうだ、麻生さんにだって勿論仕事がある。ここで引き留めてしまっては申し訳ない。スマートフォンの画面に視線を落とし、さっさと指を動かす麻生さんをそっとしておく。相変わらず俺の半分以下の動作で動く不破と、二人三脚で再び名刺を捜していると、「麻生、なんの用だ」柾さんが部屋に入って来た。どうやら麻生さんが柾さんを呼んだらしい。さきほどのスマートフォン操作がそれだったのかと思い至ったが、呼び寄せた理由までは分かりかねた。「おー、入れよ、柾」こっちこっちと手招き。「今日は休みなのか、青柳」俺の私服姿を見て不思議に思ったのだろう。柾さんに向かって「はい」と答えた。「青柳はさ、BBCの新見さんと連絡を取りたいのに、肝心の名刺を失くしちまったんだと」麻生さんが簡潔にまとめ、柾さんに説明してくれていた。俺は心の中で、尊敬する2人の先輩に己の失態を晒すなど、これほど恥ずかしい失態は金輪際しないと誓う。「新見さんか……厄介だな」と柾さんが腕を組み、ひとこと。俺は「そうなんですよ」と力の抜けた生返事。……ん……? この様子。柾さん、新見さんを知ってる……のか?「柾さん……?」これも麻生さんの指示だったのだろうか。柾さんは無印良品の名刺フォルダを持っていた。その中から1枚の名刺を取り出してみせる。さながら、意地悪く堰き止めていた8や6を、“今だ!”とばかりに差し出す『七並べ』のように。「美日カンパニー営業部営業三課・新見清子……って、これ!」「な? 前に言ったろ? 『もっとすごい名刺入れを持っている奴を知ってる』って」と、完全に呆れ返った声で麻生さん。「あの時青柳は『すごい人脈ですね』なんて言ったけどさ、果たして人脈なのかね、これは」「失敬だな、麻生。人脈以外のなにものでもないだろう」失敬だと言いつつも、柾さんはふふんと笑っている。不破は柾さんの分厚い名刺入れを“失敬”して、順繰りに捲っていた。「……うわー、僕も初めて見ます。なんですか、この女性だらけの名刺」「『女性だらけ』じゃなく、『女性専用ホルダー』な、不破」「これ全部女性の名刺ですか!? はぁ!? 180枚用って書いてありますよ!? しかも全部埋まってるじゃないですか!」「ちなみにそれ、Vol.1だからな」「麻生、お前それ以上は何も言うな」「柾チーフ、これは完全に僕の興味からくる質問ですけど、男性版はどれくらいですか?」「Vol.1だけだ」「……ひょっとして、貰っても捨ててます?」不破の推理に柾さんは無言を押し通す。これはグレイのままの方がいい。世の中には、知らなくていい事もある。男性の名刺は捨てているのか? とか、女性の名刺ホルダーは現在Vol.いくつまであるのか? ――なんてことは。かくして柾さんのお陰で掴まえることが出来た新見さんは、しかし俺からの連絡を不思議がっていた。「前回の商談の時に紙類がなくてさ、青柳くんが持ってた私の名刺しかなくて、裏側に仕入れ価格とか色々とメモしちゃったじゃない?その名刺さ、ほら、そのまま私が持って帰ってしまったから、連絡先分かんなかったでしょ。それなのに、よく分かったねぇ」そう……だったか? しくった、完全に失念していた。 名刺は彼女の手に戻されていたのか。道理でどこをどれだけ捜しても見付からなかったわけだ。「実は、柾さんに伺った次第で……」「そういえば彼もいまネオナゴヤなんだっけ。なるほど、納得だわ」……怖くてどちらにも訊けやしない。片やコーヒーをメインに扱う会社の新見さん。もう片方はコスメ売場の柾さん。接点などないではないか。いったい、いつ、どんな経緯で彼女の名刺を、柾さんは得たのだろう?いやしかし、それもグレイのままの方がいいのだろう。世の中には、知らなくていい事もある。かなり気になる点ではあるが、新見さんの気分を損なわずに済み、ホッと胸を撫で下ろす俺であった。2013.10.232020.02.13 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G3 (―) 【Come On!】
日常編 (―) 【Come On!】「ご……ごめんなさい。ごめんなさい……っ」謝罪の言葉は涙ながらに。真っ赤になりながらも青褪めた歴を見下ろし、柾は深い深い溜息をついた。誰も悪くない。歴が謝る必要など皆無だし、そもそも誰かに責任を取ってもらうなどという問題でもない。しいて言うなら自分が悪いのだ。心底そう思いながら、柾は溜息を繰り返す。*「明日は、いとこの結婚式なんです。多分私ひとりでは捌き切れないほどの手土産をいただくことになると思うので、お裾分けをお届けしてもいいですか?」前日にそう言い残した歴は、宣言通り自分ひとりで抱えるのがやっとの手荷物を持って柾が住むマンションの一室を訪れたのだった。時刻は20時を回っていた。式は午前中からだったにもかかわらず、めでたさと親戚一同による久し振りの逢瀬も相まって、宴は盛り上がり続けたと歴は言う。「ですので、こんな時間になってしまいました」「僕も7時に帰って来たばかりだし、構わない。むしろこんなに頂いてしまっていいのか?」「えぇ。私1人では使い切れないと思いますし。あ、でも無理しないでくださいね。どなたかに差し上げてもらって結構ですので」石鹸やら、お菓子やら、砂糖やら――。袋の中には綺麗なラッピングが施された品々が隙間なく納められていた。「ありがとう。色々と助かるよ」ちょうど石鹸が切れかけていたことを思い出し、柾はタイミングのよさに感謝した。お礼の意味も込めて歴の頭を撫でると、彼女はふふっと笑った。「いいえ。どういたしまして」「それにしても――歴」柾の声が、ワントーンだけ低くなる。その変化に気付かない歴ではなかった。それはまるで、蝶を拿捕せんと虎視眈々狙い定める蜘蛛のよう。無意識に肩がびくっと跳ねるも、柾はその脅えすらも愉しむかのようにうっすらと笑った。「――素敵だね。とても綺麗だ」柾に手首を捕まえられ、ぐいっと力任せに引っ張られる。歴の肢体は柾の腕のなかにすっぽりと収まり、そのまま抱きすくめられる。「あの……あのっ、直近さん……」「シー。黙って」柾の唇が、戸惑う歴の下唇を優しく食む。(これは……まずい。直近さん、エンジンかかってる……!)歴の背中に回されていた腕は腰へと位置を変えられており、心なしか下半身同士が密着を始めたように思うのは気のせいではないはずだ。「っ……直近さんっ、だめ……、おね、おねがい」もしかして、と歴は思った。結婚式に出るため、今日は着物を着ている。呉服問屋の若き店主、姫丸二季と何度も打ち合わせをして作った、歴のための一張羅。歴の魅力を最大限引き出してあげると請け負ってくれた姫丸は、宣言通り、それはそれは見事な訪問着をこしらえてくれた。燃えるような、赤の、色を。(直近さん、私がいつもと違う出で立ちだから、とか、そういうこと……?)だとしたら、姫丸の願いはある意味叶ったことになる。魅力を最大限引き出しすぎて……歴にぞっこんの柾には効果覿面すぎるほどの効き目だ。欲情させるために作ったわけではなかったのに。こんなはずではなかったのに。(さしもの姫丸さんも、『まさか』だろうな……。って、こんな展開になってしまったことは絶対に言わないけど! 言えないし!)色々と考えているうちに、柾は背後の帯をほどきにかかっていた。「あ、やっ、」気付いた歴は身じろぎ、手をどけようとしたが、相も変わらず柾の胸のなかにいる彼女は男の力に勝てずにいる。このまま一気に脱がされ、ことが進むのかと思いきや、どうも様子がおかしい。柾の手はもぞもぞと動いているものの、帯がほどける気配はなくて。(直近さん……?)柾の顔を見れば、少し拗ねた様子だった。どうやってほどくんだ、これ? と言っているかのような。(あ……ひょっとして……)着物は姫丸の母親が着付けてくれた。しっかりした帯結びは、さすがプロによる手法。きつく、かたく結ばれ、しかもその折り方は複雑で難解だ。素人がササッと剥ぎ取れるものではない。(『こうするんですよ』って、私が手伝うべき? でも、でも、……それって恥ずかしい……!)真っ赤になった歴は、柾の胸に顔を埋めた。その衝動で柾の身体はグラつき、衝動と相まって帯にかけていた指が結び目をほどき終える。柾にしてみれば怪我の功名。歴にとっては次のステップ突入の予感。その後は時代劇に出てくる濡れ場のワンシーンのようにグルグルと帯を剥ぎ取られ、着物だけになった歴は後ずさる。「な、直近さん。落ち着いて……ね?」帯だけで時間がかかったことにプライドが傷付いたのか、柾は新たに立ちはだかった試練に早速取り掛かる。今度は着物だ。伊達締めをあっさり外すと、今度は腰紐へと手を伸ばす。(あ、でも、これって実は次の試練だったり……)腰紐は、着物の裾が落ちてこないよう、しっかりときつく結ぶのが常識だ。姫丸の母は容赦なく、まるで絞め殺すように強く結んでいた。しかも腰紐は着物で2本、さらに襦袢で2本の、計4本。それらを取るのは柾を困らせることになりそうだ。案の定、柾の指は歴の上半身に食い込んだ紐を取るのに苦労していた。何せ指一本の隙間すら許さないのが腰紐の正しい在り方。歴の細い指ならともかく、柾の指はそれよりも太いのだから、なかなか取れないのは当然だ。(ど、どうしよう……。殿方に恥をかかせてしまうなんて……私の馬鹿……っ!)服を脱がすのに時間を掛け過ぎ。そんな男の姿は滑稽だ――。もし柾がそう思っているのなら、歴としては心底申し訳なく思う。「ご、ごめんなさい」「……何が?」外せない焦りを悟られまいとしているのか、しかし内心ではイラついているようで、柾の返事は少しだけ素っ気ない。(あぁ、やっぱり気にしてるんだ、直近さん……!)だってこれが洋服だったら既に全てを剥ぎ取って愛撫を始めている頃合いだもの、と思い。そう思ったことに対してもボボッと顔を赤らめる。歴としては、もう色々といっぱいいっぱいだ。柾に恥をかかせたこと。その柾とこれから行為を行おうとしていること。歴のなかで芽生えた罪悪感が、謝罪となって口から漏れる。「っ……ごめんなさい。ごめんなさいぃ、直近さん……」この子は一体何を急に謝り出すんだ、と柾は呆気に取られ、手を止める。あれやこれやとしているうちに2人はベッドの上へと移動していたわけだが、押し倒した歴を見下ろせば、潤んだ瞳に見つめ返された。恥ずかしさで顔を赤く染めるのは毎度のことで、でも今回は青褪めてもいた。その理由は柾が着物を脱がすのに手間取っているからだろう。恥をかかせてしまってごめんなさいと言っているのが、歴の態度から読み取れた。「……いや、僕の方こそすまない……」寧ろ歴に恥をかかせてしまったような気がして。柾は、はぁ、と溜息をついた。「衝動を抑えられなくて……」着物姿の歴を目の当たりにした瞬間、美しさに目も心も奪われた。はっきり言ってしまえば、その時から既に彼女を抱くことしか考えていなかった。(オスのサガだと言ってしまえばそれまでだが……)ところが、だ。昔から憧れていた『帯回しプレイ』は意外に難しいし、着物にいたっては紐すら外すことが困難で、ちっとも脱がせられない。幻想と現実の違いに打ちのめされた形だ。ふと、今日はもう諦めるか、と思った。腰紐は一向にほどけそうにないし、無理強いした感も否めない。半泣き状態の歴の瞼のうえに軽くキスをして、「ごめんよ」と謝る。「さぁ、起きて。歴」手首を掴み、立ち上がらせようとした、その時。歴が自らの腰に手をやり、腰紐を外し始めた。1本。そしてさらにもう1本。着物がはだけ、桃色の襦袢が姿を現した。驚きのあまり目を瞠る柾に、小さな声で歴は言った。「あの……襦袢のほうの紐は……着物より、きつく結ばないことになっているんです。……だから……」だから――外して。直近さんが。言外に匂わせた、なけなしの勇気を振り絞って告げられた“おねだり”。「分かった」柾の手は、再び腰紐へと近付く。2015.08.242020.02.21 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G3 (麻) 【Unrequited Love!】
日常編 (麻) 【Unrequited Love!】――困ったな。一度だけ口をつけた紙コップ。中にはなみなみと注がれたままの温かいコーヒー。俺はどうしてもそれをテーブルの上に置くことが出来ない。置けば多少なりとも音が生じ、俺がこの場に居ることがバレてしまう。それは避けねばならないだろう。「俺、あなたのことが、す……好き、でした!」5メートルと離れていない位置で、後輩の平塚が勇気を振り絞って女性に告白している場面なのだから。*片さねばならない仕事を抱えていた俺は、出勤時間の1時間前に入店していた。常に出入り自由の社員食堂。その一角を借りて、コーヒーを啜りながら作業を進めるつもりでいたのだ。食堂のスタッフが来るのは1時間半後。それまでは気ままに過ごせると高をくくっていた。予想通り、だだっ広い空間には誰1人としておらず、好ましい発進に心が浮き立った。これなら仕事も捗るだろう。自動販売機はドアから一番離れた場所、奥まったところにあるため、まずそこへ向かう。自販機に一番近いテーブルに鞄を置き、目覚めのための一杯、コロンビア産を謳い文句にしたコーヒーを買い求め、さぁいざ席に着かんとした所で、「ね、ねぇ。急にどうしたの、平塚くん」「いいから、早くこっちに――」いや、よくねぇ。ちっともよくねぇよ、馬鹿。何かから逃げているのか、こっちに近付いて来る足音が2つ。片方の声は平塚のものだ。女の方には聴き覚えがないが、社員の1人に違いない。「ここなら誰もいない……よな?」慎重気味の平塚に対し、仕事の邪魔すんな、と一言声を掛けようとした時だった。「あのさ、俺」やけに神妙な口調で話し始める平塚に、俺は「ん?」と首を傾げた。ちょっと待て。このパターンはひょっとして……。このまま出て行くべきではないと、直感が告げる。俺の足は踏みとどまることに成功した。「俺……俺さ」「平塚くん?」……あぁ、おい、マジかよ平塚。今から告白するってのか? しかも社員食堂で?いや、恐らくあいつなりにシミュレーションしていたんだろうよ。現に「ここなら誰もいない」って言ってたし、本命だった場所に人が居たもんだから、告白出来なかったんだろう。だからって第二候補が社員食堂って、どうなんだそれ。しかし、こうなってしまっては出るに出られないし、カップは置くに置けないし、くそ、タイミング悪いな……。平塚のメールアドレスなら知ってる。送って教えるべきだろうか。壁のL字で見えないだろうが、実はお前の後ろに居るんだ。告白の返事を俺に聴かれたくなければ速やかに立ち去れ、とでも。だが、第三候補地を探すとなると、平塚の不甲斐なさに女だって引くだろう。さすがにそれは忍びない。となると、俺はこのままじっとしてるしかないんだな。あぁ、ったく。「俺、あなたのことが、す……好き、でした! 付き合ってください!」おー、偉いぞ。よく言えたな。と感心していると、「ごめんなさい」間髪入れずに断った!? うわぁ……マジか。「え、っと……。もしかして、彼氏いた?」片想い相手の彼氏の有無に関しては、平塚は事前にリサーチする方だが。下調べが甘かったのか?「そうじゃない。私、好きな人がいるの。だから……」「俺が入り込む余地はない?」返事がないところをみると、彼女は声には出さず、頷くなどのジェスチャーをしたのだろう。平塚が「そっか」と呟いた。「俺、応援するよ。その恋、実るといいね」平塚ー、いいヤツだな、お前。俺には分かるぞ、お前のよさが。見えない位置でうんうん頷いていると、「平塚くんには本当に申し訳ないと思う。私の気持ちを酌んでくれてありがとね。応援も心強いな。でも、実るかな……? 正直、自信なくて」「ソノちゃん、綺麗だし、仕事も頑張ってるもん。きっと通じるよ。相手、誰か訊いてもいい?」始めは「え、えー……?」と恥ずかしがっていたソノちゃんとやらは、観念したのか「えっとね」と勇気を振り絞った。「麻生さん……なの」「そっか、麻生さんか。うん、頑張ってね。応援してるよ」……。平塚の声に覇気がないのは仕方がないとして、取り敢えず俺は俺で絶体絶命だ。2人がこっちに来ることはないとは思うが、見付かったら万事休す――。ところが、だった。「な、何か……緊張したからか、咽喉カラカラ! 自販機で飲み物買おうかな」その場を取り繕うかのように平塚が言い出し、「あ、私も」とソノちゃんとやらも右に倣えをしだした。おい……ッ!俺は咄嗟にスマホを操作する。壁のL字で見えないだろうが、実はお前の後ろにいる。さっき冗談で打った文章が生き残っていた奇跡に感謝しつつ、俺は『届け!』と念を込めながら送信した。2秒程度のブランクのあと、♪チャララ~と平塚のスマホがメロディーを奏で始めた。「鳴ってるよ?」とソノちゃんが告げたことで、平塚は出ても構わないと判断したのだろう。「じゃあちょっとだけ。不作法、ごめんね」と断ってから操作する平塚はしかし、数秒と経たない内に意見を翻した。「ソノちゃん、1階の自販機のラインナップがリニューアルしてたって知ってた? そっちの方にしない?」「うん、いいよ」すぐに立ち去る音がして、俺はホッと胸を撫で下ろしたのだった。*昼休みを迎え、従業員通路の階段を降りていると、平塚がスッと横切るのが見えた。俺は小走りして平塚の肩に腕を乗せる。「よぅ」「……酷いですよ。麻生さんがあの場にいたなんて」「言っておくが、俺が先にいたんだからな? 後から入って来て勝手に告白をし始めたのはそっちだ」「それはそうですけど」ぶー、とぶーたれた平塚は頬を膨らませ、つんとソッポを向いてしまう。「お前、俺がソノちゃんとやらを振るって分かってても応援しようとしてんだな」「……やっぱり振るつもりなんですね」それには答えない。そして答えないことこそが肯定の返事であると、平塚はとっくの昔に理解している。「教えてください。麻生さんは歴さんを諦めたんですか?」「諦めたぜ。だって柾がいるからな。安心して任せられる」「じゃあ、どうして誰とも付き合おうとしないんです?」「付き合わなきゃいけないのか?」「……いいえ」何を言ったところで俺の意思を寸分たりとも変えられないことを知っている平塚は、不服そうに「別にいいと思います」と付け足す。「お前さ、俺以外の名前が出たならともかく、俺の名前が出た時点でソノちゃんとやらに『応援する』なんて言わなきゃよかったのに」「『その恋は絶対実らないよ、だから付き合おう』って? 無茶言わんでくださいよ……」「押しが足りないんだよ。あそこで一歩引いちまったからソノちゃんは……」「あんたに……あんたに何が分かるんだよッ!」「ん?」肩に回したままだった俺の腕を、平塚はピシッと払いのけた。怒ってる? 平塚が俺に噛み付いてきたことなんて、一度でもあっただろうか。いや、ない。これにはさすがの俺も驚いて、まじまじと平塚の顔を穴が開くほど見つめたのだった。鳩が豆鉄砲をくらったようにポカンとしている俺を余所に、ぎゃんぎゃんとヤツは言い募った。「麻生さんはさ、好きなヒトを友達に託して納得してるんだろ!? それであんたの恋にはケリがついたんだろ!?俺だってそうだ。好きなヒトには好きなヒトがいたけど、応援したいと思った!最初からあんたが断るって分かってるのに、それでも応援しようと思った! それが俺なりのケリのつけ方だ! 俺は満足してる。自分で導きだした答えに、何の不満もないよ。だから押しが足りないだの、駄目出しだの……勝手にすんなよなッ!」キッと見据えた平塚の目尻には、涙が溜まっていた。あぁ、そうか。こいつはソノちゃんとやらに、心底惚れていたんだな……。彼女のために、ここまで怒れるのか。彼女の想いを尊重したくて。いいヤツだなぁ、ほんとに。「……俺な、誰に寂しいって言えばいいのか、分からなかった」「……?」急に脈絡のないことを言われた平塚は困惑顔になっていたが、黙って俺を見返しているところを見ると、話は聞いて貰えるようだ。「千早さんと柾、一気に両方失った気がしてな。ほんと言うと、心細かったりしたんだ」「麻生さんが?」「そ。笑っちまうよな。柄にもなくさ」「いや……それは……」「一度でも寂しいって言葉にしちまったら、さらに苦しむことになってしまうんじゃないかって本気で思ったんだ。寂しさを認めることになる。だから、感情を押し殺すしかなかった。……今のお前のように、素直に泣けたらよかったんだがな」「麻生さん……」本来ならば、俺は慰めなければならない立場のはずだ。それがどうして、たった数時間前に玉砕した男に向かって、俺自身が弱音をぽろぽろと吐き出しているのだろう。情けない話だ。平塚も呆れていることだろう。大人として、みっともなかったな。「……悪ィ、平塚。お互い、この手の話は今度酒でも飲みながら――」「麻生さん! 俺でよければ胸を貸します!」平塚は胸を反らし、カモン! と腕を広げている。女子社員たちが風変わりなポーズを取っている平塚を見て、「なにしてるんだろね」「可愛いー」と言いながら通り掛かる。そんな好奇な眼差しや、やんややんや囃し立てる外野を一切合財無視して、平塚は真剣な目で俺を見ていた。「お前……馬鹿だろ」「よく言われます」呆れた俺の馬鹿だろ発言にめげることもなく、平塚は二カッと笑ってみせる。俺にはその強さが嬉しくて。眩しくて。「……ちょっと借りるな」ぽすん、と頭を平塚の胸に預けた。平塚が「わっ」と小さな声をあげる。まさか本当に俺が胸を借りるとは思わなかったのだろう。「両方失ったなんて寂しいこと、言わんでください。今日も明日も明後日も、歴さんと柾さんは麻生さんの味方ですよ」「……だな」何度もそう自分に言い聞かせてた。でも、欲しかったのは『確信』。誰かにそう言って貰わなければ、自信が持てなかったのが正直な話で。いつの間にこんなに弱くなったのだろうと思う。人は、時を重ねれば自然と強くなる生き物だと、勝手に思い込んでいた。遅まきながら、そうじゃないことを痛感させられた格好だ。ぽんぽんと頭を優しめに叩く平塚のそれは、安心しろというサインなのだろう。不思議と落ち着く感じがした。「――何……してるんだ?」「わぁっ、柾さん!」「……柾?」普段の声に、若干『恐る恐る尋ねる』気配が混じっていた。大方柾のことだ、男同士でよくもまぁ堂々とバックヤードで抱き合えるな、とでも思っているに違いない。「いえその、麻生さんが意気消沈してるんで、そのー……」たじたじになって答える平塚に、「ふむ」と応じながら俺を見る。「麻生」今度は柾が腕を広げた。「まさか! ウソでしょ!?」と平塚が驚くのも無理はない。俺だって驚いているし、突拍子もない出来事に困惑してもいる。しかし柾の表情はいたって真面目で、決してふざけているようにはみえない。『男に触れる趣味はない』。普段からそう豪語している柾だからこそ、広げられた腕に意図を見い出すのは容易いことだった。平塚から離れ、サンキュな、と告げる。こくこくと頷く平塚は、これから迎える展開を前に、固唾を飲んでもいた。柾の正面に立つ。目と目が合うが、特に目で会話をするということもなく、俺は平塚の時と同様、頭を柾の胸に宛がった。暫くは、何の感情も湧いてこなかった。柾が背中に手を回し、摩ったところで、こいつが俺の孤独を融解させようとしていることを知った。言葉にしなくても、気付いてたんだ、柾は。3人でいた頃とは違う、微妙な立ち位置によって抱えることになってしまった、俺の疎外感に。「柾……。ごめん。ありがとう」心配かけて悪い。でも、今もなお俺を必要としてくれてるんだな。サンキュ。「ありがとう、麻生。……すまない」いいんだ。ちぃが選んだのはお前だ。別に俺が彼女を譲ったわけじゃねぇよ。だから謝るなよな。ちぃの目は確かだぜ。俺は柾の胸を押し返す。目と目が合う。柾は笑っていた。だから俺も笑い返す。「麻生、昼ご飯食べに行かないか?」「おぅ、行こうぜ。平塚も、ほら」「はい!」溝から外れてしまった車輪が元の位置に戻り、仕切り直す準備が整ったのを、今の俺にはきちんと感じ取ることが出来ていた。2014.09.152020.02.21 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G3 (―) 【Show Me!】
日常編 (―) 【Show Me!】__芙蓉sideソマと休日が重なった、ある日のこと。彼の自宅にお邪魔して、料理を作りがてら、一緒にお昼ご飯を食べる約束をしていた。至極和やかなランチタイムだったと思う。とあるニュースを観るまでは。「次のニュースです。本日9時頃、愛知県名古屋市××区2丁目の××さん宅から出火していると、近所から通報がありました。火は40分後に消し止められましたが、木造2階建ては損傷が激しく全焼。1階から1人の遺体が発見されました。家主の××さんとは連絡が取れておらず、現在遺体の身元の確認を行っています。××区では先月より不審火が3件相次いでおり、警察では一連の事件との関係を詳しく調べています」「××区ですって。近いわね」私が呟いた、その時だった。キンッ! と耳障りな金属音がして、反射的に視線を向けた。食べかけ途中のハンバーグに、まるで墓標のように突き刺さったそれは、ソマが使っていたフォーク。普段なら絶対にしない行儀の悪さに違和感を覚え、ソマを見る。「……!」ぞっとするような暗い表情に、私は息をのんだ。陰鬱のなかに見え隠れするのは、激しい怒りだろうか。「……クソがっ……!」ひやりとした。心臓を鷲掴まれた感覚だった。ソマをイラつかせたのは私だろうか? だとしたら、何がいけなかった?テーブルの上に両肘をつき、両手で自らの顔を覆ってしまったソマに、声を掛けるのは躊躇われた。問い掛けたところで、果たして彼は反応してくれるだろうか? 「……ソマ?」反応はなかった。荒げた呼気を落ち着かせようと、息を整えている。自我を取り戻そうするかのように。私もこの時間を使い、落ち付け、落ち着け、と心に言い聞かせる。「…………悪ィ、……八女さん」意外にも、ソマのリカバリは早かった。なんのこと? ととぼけるのも白々しいし、それに、いまソマから逃げるのは得策ではない気がした。謝罪を述べたということは、本人に『悪いことをした』という自覚があるのだろう。「いいえ、大丈夫よ。どうしたの?」なるべく詮索の嵐になってしまわないよう注意しながら尋ねる。うながしたものの、ソマは何も言わない。再び口をかたく閉ざしてしまった。「料理、口に合わなかった? せっかく台所を貸してくれたのに、悪かったわ」「……そうじゃない。でも……ごめん、食欲ないから……」「無理しないで。ラップに包んで冷蔵庫に入れておくわね。食べれそうになったら食べてくれればいいわ」ハンバーグはソマの大好物だった。作っているときも「早く食べたい」なんて楽しみにしていたぐらいだ。前回は和風おろしだったから、今回はデミグラスソース。市販のものに手を加えただけだから、極端にまずいわけでもない。作り方だって以前と同じ手順を踏んだ。サラダもお米もコーンポタージュも、失敗してないと断言できる。だから多分、ソマの機嫌が悪くなったのは私のせいではないだろう。……と思う。痴態の穴埋めをするかのように、ソマは私の背後に回ると、ギュッと抱き締めてきた。私の肩に顔をうずめ、しばらくその姿勢のままのソマ。その頭を、優しく撫でてあげる。こんなことしか出来ない自分を歯痒く思いながら。何を落ち込んでいるのだろう? 彼は何を抱えているのだろう? なぜ、急に憤りを感じたのか。すべてを理解した上で、救ってあげたいけれど……。ソマは顔を上げると、ぎこちなく笑った。その顔が、ごめんと謝っていた。彼の唇が、私のひたいに触れる。「八女さん、今日は……ごめん」帰ってくれ、と彼は言った。*いつもは治安がよくないからと言って大須駅まで送ってくれていたソマだけど、今日は勝手が違った。玄関先で分かれた時、ソマは本当に元気がなくて、このまま付き添わなくていいのだろうかと心が揺さぶられた。それでもソマは私に帰って欲しそうだった。望まぬ長居をして、神経を逆撫でするようなことはしたくない。だから私は岐路に着くことにした。ソマの家は表屋造りになっているから、数歩も歩けばソマのおばあさまが切り盛りしている古着屋に寄ることができた。挨拶だけでもしていこうと思い、暖簾をくぐる。店の番台にいたのは、ソマの妹の唄ちゃんだった。彼女は私を見るなり顔をパァッと輝かせ、「芙蓉おねーさま!」と駆け寄ってきてくれた。杣庄唄ちゃんは、とんでもないほど容姿が整った子で、大須でも有名な看板娘である。直接本人から聞いたことはないけれど、ソマ曰く、色んな業種のスカウトマンから声を掛けられることもあるんだそう。今日の唄ちゃんは白色ワンピースを着ていた。それがまたとてもよく似合っている。胸の位置まである髪を、“耳隠し”という古風な技で纏めていた。「こんにちは、唄ちゃん」「こんにちは! 今日は、お兄ちゃんとデート?」「そうなんだけど……」女の勘は鋭い。特に唄ちゃんは、ひとの感情の変化を察知する能力に秀でていた。「はは~ん。さてはお兄ちゃん、醜態を曝しちゃったのね」そうだ、唄ちゃんなら何か知ってるかもしれない。私は安易な考えで、さきほどのやり取りを語って聞かせた。「いつもと様子がおかしいなと思って。でも料理は問題なかったはずだし、火事のニュースも大須ではなかったし……」そこまで言って、気付いた。そこまで言わなければ、気付かなかった。唄ちゃんの様子が、おかしい。「……て……」『許して』? 聞き間違いかと思ったけれど、耳を澄ませばやはり同じ呟きが彼女の口から吐き出されている。身体はがたがたと小刻みに揺れ、激しく動揺しているようだ。涙を流しながら「ごめんなさい、ウタを許して、いい子にしてるから」と繰り返す唄ちゃんを見て、私は愕然とする。同じだ。これはソマと同じ症状だ――! どうしよう、どうしよう!?「唄ちゃん!?」ひたすら誰かに謝り続ける唄ちゃんを救う術を、私は持たなかった。そもそもソマも同じような状態にしたまま、ここに来てしまったのだ。己の浅はかな判断ミスを呪うしかなかった。「ごめんね、唄ちゃん」細い身体を抱き締め、頭を撫でる。やがて落ち着いてきたのか、啜り泣く声に変わった。「芙蓉……おねーさま……ごめん……な、さい……」「あなたは何も悪くないわ。……ごめんね」一体、この子たちは……。なにと闘っているの? どんな闇を抱えているの?このまま放っておくわけにもいかないけれど、二進も三進もいかなくなってしまったのもまた、事実だった。__歴side出勤した時からずっと思っていた。「大丈夫ですか? 元気がありませんね、芙蓉先輩」見るからに覇気のない上司に声を掛けると、「……千早ぁ」と半べその状態で抱き付く芙蓉先輩だった。「どっ、どうなさったんです……か?」心なしか頬で胸をスリスリされてるような気がしたものの、気の所為だと言い聞かせて。すると、「ちょっとね……自己嫌悪。自信喪失」芙蓉先輩ともあろうお方が自己嫌悪!? しかも自信喪失……!?よほど酷い目にあったのだろうか。訊かずにはいられなかった。「一体何があったんです? 昨日は杣庄さんとデートでしたよね。杣庄さんとトラブルでも……?」「分からない……分からないの」「なにしてるんですかー。いつからここはレズの巣窟に?」「透子先輩!」気だるげに入室してきたのは、遅番の透子先輩だった。「潮! 潮ぉぉ」透子先輩を見るなり、芙蓉先輩は今度、そちらへと駆け付けギュッと抱擁。「……あーん。もれなく私もレズの道ー。千早さん、なにこれー」「わ、私にもよく……。何がなんだか……」やれやれと溜息を漏らす透子先輩。その格好のまま、パソコンの電源を入れるという器用な行動をやってのけた。「仕事は?」「明後日入る折り込みチラシの本刷り待ちです」「それなら丁度来たとこ。さっき事務所で貰って来たの。いいわ、私がやる」「ありがとうございます」「さぁ、八女先輩。邪魔ですからどいて下さい」芙蓉先輩相手でも容赦ない言葉を発する透子先輩である。「潮ったら、なんて冷たい子なの」「仕事させてください」「私と仕事、どっちが大事なの?」「仕事です。仕事は私にお給金をくれます。一方、この抱擁は私に怖気(おぞけ)しかくれません」「潮ぉ」透子先輩、言い方が不破さんっぽいですよ! という言葉を、すんでのところで飲み込む私。「本当になんなんですか? 分かりましたよ。話、聞きますから」「ソマの様子が突然おかしくなって……」そう切り出すと、八女先輩は順を追って説明し始めた。唄さんのくだりまで話し終えると、八女先輩は透子先輩に「心当たりある?」とすがるように尋ねた。眉根を寄せながら、首を横に振る透子先輩。そんな、と絶望に叩きつけられた芙蓉先輩の声。透子先輩が一縷の望みだったに違いない。「杣庄はそれほど短気というわけでもないし、憤りを感じたらその場で解決するようなタイプです。今の話を聞く限り、杣庄の心の中に燻っているものがあって、それが何かの拍子で噴火してしまったと考えるしか……」「そう……よね。どうしたものかしら。潮も知らないということは、伊神も知らないでしょうし」「本人に聞くしかないと思いますけどね」「そうは言うけど潮、あの雰囲気は尋常じゃなかったわ。しばらくは無理よ」妹の唄さんを泣かせてしまって引け目を感じているのだろう。芙蓉先輩は慎重だった。「秘密主義ですからねー、杣庄は。言いたくないことは言わないし、踏み込ませない。線引きがハッキリしてる分、難しいかも」「駄目よ。このまま放ってはおけないわ。どうも根が深そうな気がするの。根本的に解決しないとまた繰り返しかねない」芙蓉先輩の言い分は、尤もだった。とはいえ、昨日今日蓄積した『浅い闇』などではないだろう。恐らく長い月日が経っているはず。深さも暗さも嵩増しされているであろう強力な闇に、どう立ち向かえというのか――。「……あ」1つだけ、方法を思い付いた。「千早、どうしたの?」「私、特殊カウンセラーの知り合いがいるのですけど……」「特殊……カウンセラー?」「はい。でも本当に特殊な方向からのアプローチになるので、治療の保証はできませんけど……」私の頭のなかには児玉絹さんが浮かんでいた。彼女の力を100%信じている。信じてはいるが、今回のケースにうまく作用するかまでは断言できなくて、私のプレゼンは尻すぼみになっていった。「お願い、千早。その方を紹介してもらえない? お金なら払うから」切羽詰まった表情で両手を握られ、私も腹をくくるしかなかった。そうだ、賭けてみよう。何もしないより、動いてみた方がいいに違いない。「分かりました。連絡してみますね」果たして児玉絹さんは応じてくれるだろうか。そんな心配も杞憂に終わった。早速絹さんにコンタクトを取ってみると、二つ返事でOKしてくれたのだ。驚くことに、簡易的説明だったにも関わらず、「ひょっとして、杣庄さんかしら」と、向こうから名前があがった。その凄さに、舌を巻くやら、唖然とするやら。「杣庄さんなら、私より玄クンの方が打ってつけよ」「玄さんですか?」「杣庄さんと友達なの。いま家にいないから、私から連絡しておくわね」「宜しくお願いします!」電話越しだということも忘れて、私は勢いよく礼をした。日取りは杣庄さんの休みである、2日後の朝10時。大須観音駅2番出入口で落ち合うことになった。そのやり取りを聞いていた透子先輩は勤務計画表へと視線を向ける。つられて私もそちらを見た。八女先輩が休み、透子先輩が早番、私が遅番となっていた。これは、杣庄さんが抱え続けてきた『闇』だ。恋人の芙蓉先輩をはじめ、仲のいい透子先輩や伊神さんにも語らなかった、大きな問題。だから私は行くべきではない。私に出来るのは、玄さんと芙蓉先輩を引き合わせ、問題解決への糸口を見付けること。芙蓉先輩は、私と透子先輩についてきて欲しいと零しつつも、ことがことだけに1人で臨んでみせるわと力強く英断した。透子先輩は、杣庄が話したくなった時に耳を傾けることにするわ、と優しく微笑んだ。__玄side絹の「お帰りなさい」という労いの挨拶にはまったく覇気がなくて、状況を考えればそれも仕方ないかと思った。「玄クンの胸騒ぎ、当たってしまったわね」と旅行かばんを受け取りながら、絹は寂しそうに呟いた。「どうも近い内に進展があるんじゃないかって、嫌な予感がしてならなかったんだ」4日前から妙な胸騒ぎがして、次の日から熊野古道入りした。大自然に身を預け、木と水、土、空気など、あらゆる自然界のものたちから力を貰った。なにに備えてだったのか、今なら分かる。杣庄さんを救う日が来たのだ。同時にそれは、負けられない戦いでもある。脱衣場で服を脱ぎ、浴室に向かう。ペットボトルに入った真水を2リットル分、頭から注いだ。そしてパン、と柏手1つ。「清め給え。木、気、祈、器、満ち、溢れ、加護せよ。木霊、小玉、木魂、我は児玉なり」短く精神統一して、ついでに旅の疲れと汗を流すため、身を清める。脱衣場へ戻ると、絹が洗濯済みの服を用意してくれていた。リビングに行けば、今度は絹が慣れた口調で祓詞を紡ぐ。「『諸々の禍事/罪/穢/有らむをば/祓へ給ひ清め給へと/白すことを聞こし召せと/恐み恐みも白す』」「……行って来る」「行ってらっしゃい」4日前に俺を見送ってくれた時のように、絹は「信じてるわ」と結び、俺を送り出してくれた。__芙蓉side当日はいてもたってもいられず、9時半には待ち合わせ場所で初対面となる児玉玄君を待ち侘びていた。千早に「どんな子?」と訊ねたら「ハンサムな方ですよ」と返された私は、男性の美醜に疎い面があるので内心困っていた。9時45分に「あの」と声を掛けられた。相手はどう見ても私と同じ年代ぐらいだ。「お1人ですか? もし宜しければ一緒にお茶でも」ナンパだったのか。紛らわしいわね。私は何も言わず、にっこり笑う。男は失礼しましたと頭を掻いていずこかへと去って行った。「すみません」今度は黒髪が特徴的な、長身でスラリとした大学生ぐらいの男子だった。さらりとした髪質に、白のカッターシャツに黒のパンツという出で立ち。全身から清潔感が漂っている。「児玉玄と言います。八女さんですか?」誰かに似ていると思ったら、雰囲気が柾さんにそっくりだった。容姿がではない。落ち着いた話し方が、だ。「えぇ。今日は来てくれてありがとう!」「とんでもないです。俺も、杣庄さんには恩があって。それにしても、杣庄さんの関係者って、美しい方ばかりですね」「あら、お上手」「本心です」前述の通り、私は美醜に疎いので、「千早が貴方をハンサムだと褒めてたわ」と伝えると、顔を赤らめた。「歴さんが? 嬉しいです。……ところで、今日はこのまま杣庄さんの家へ向かうんですか?」「えぇ、そのつもりよ。とは言え、アポなし突撃なの。もし居なかったら空振りになるかも。その時はごめんなさいね」「いえ。寧ろ、アポなし突撃の方が良いと俺も思ってました。警戒されて、逃げられても困りますし」ありがたいことに、玄君とは気が合うみたいだ。このまま調子よく物事が進めばいいのだけど。たびたび覗かせる弱気を、ヒールのかかとをカツンと鳴らすことで蹴散らしてみせる。大須観音を通過し、私たちは観音通へと踏み込む。大須2丁目から3丁目が、大須商店街と称される区域だ。4つの主要な通りがあり、1,200店もの商い場を誇る。その中で、ソマの店兼住居があるのは大須本通。玄君は友達と一緒に、ソマのお婆様が営んでいる店へ訪れたことがあるらしい。お陰で私たちは迷わず目的地へと辿り着くことができた。ビルと家屋、店舗が混じり合い、独特のアンダーグラウンドを展開している界隈を突き抜けた先に、ソマの家はあった。店は開いているようだった。店先には商い中の札が下がっていたし、誰かまでは判り兼ねたけれどガラス越しに人影が動くのを確認した。玄君とのアイコンタクトで、訪問するのは自宅の方と決めた。ブザーを押して応答を待つ。現れたのはソマ本人だった。彼が着ている草木染めのTシャツは、店で買い取った時点で一目惚れしたため自ら購入したという、松葉色のオーガニックコットンだ。麻生さんと七分袖同盟を結んでいるらしく、袖を通した時に写メを送ったという話がある。つまりはお気に入りの一着。ジーンズも古着屋を通じて手に入れた品だった。ビンテージ物だから値が張ったのだと彼は言っていた。この服装から考えるに、さては出掛ける用事でもあったのだろうか。挨拶も忘れ考察を組み立てていると、当の本人は突然の訪問に虚をつかれたようで、困惑気味な表情を浮かべる。同時に警戒心を抱いたようだった。「珍しい組み合わせだな」「突然ごめんなさい」あんな別れ方をしたのだから、神妙な顔つきになってしまうのも仕方ないかなと思う。屈託なく笑うなんて私には出来ない。きっとソマにも。「いや。この間は悪かったと思ってる。それで、どうしたんだ? 玄と一緒に来たのか、玄とは偶然一緒になったのか」「一緒に来ました」と玄君。尋ねられた質問には誠実かつ素直に答えようという姿勢が見受けられ、私はなかなか好青年だと思った。「へぇ、一緒に。これまたどうして」口の端はにやりと笑っているかのよう。でも目は嘘をつけない。彼の双眸から窺えるそれ。ソマは笑ってなどいない。正面から向かい合うと決めてきたのだ。こっちだって退かないんだからね、ソマ。「貴方の様子がおかしかったから、心配で見に来たの。玄君の力を知ってるわよね? 千早から教えて貰ったのよ」「千早さんか。なるほど……。すまねぇけど、帰ってくれ」にべもない言葉だった。ほんのついさっきまでの決意が挫けてしまいそうになる。「どうして……」「カウンセリングのつもりだろうが、俺は一切話さないと過去に誓ったんだ。その方針を曲げるつもりはねぇ」ドスの利いた声だった。玄君はそんな口調のソマを知らないのだろう。どうしましょうと不安げに私を見つめる。「過去に誓った? 未来を信じる気はないの?」「悪夢から解放してくれるのか、八女サン? 出来もしねぇことは口にしちゃいけねぇよ」「貴方がどんな過去を生きてきたのか知りようがないんじゃ、私だってどうしたらいいのか分からないわ」「放っといてくれ! あんたには関係ないだろ!」「杣庄さん、さすがに言い過ぎじゃ……」「いいのよ玄君。あのね、覚えておいて。『あんたには関係ない』。これってね、S.O.Sサインなの」「S.O.S?」玄君が怪訝な表情で私を見た。にこりと微笑む私。「そう。心の奥底ではこう思ってる。『俺を助けてくれ』」「あんたなぁっ……!」カッと頬を赤く染めたソマが1歩前に出る。私はひるまないし、退かない。動じないと決めたもの。と、何者かが廊下の奥からどかどかと大きな足音が近付いてきたかと思うと、ソマの背中を蹴りつけた。「玄関先でなに喚いてんだ、てめぇ!」とソマをなじっている。ゆるく巻かれた黒髪のポニーテール。敷居の高さを差っ引いても明らかに長身だ。濃いグレイのパンツスーツを見事に穿きこなしている。唄ちゃんに似ているけれど、どちらかと言えばソマに似た造形だ。そして口調からは想像もつかないけれど、間違いなく女性だった。「いってぇ……」床の上で四つん這いになり、痛みに耐えているソマに対し、迫力美女はヤンキー座りをしてソマの顎をクイッと右手人差指で持ち上げる。「お客様がお見えなら、応接間にご案内するのが常識だろ。土間で門前払いしやがって。ふざけてんのかてめぇ」「そのお客様の前で乱暴狼藉を働いてるのは誰なんだっつー話だよ」「よぉ。あんたら、進のダチ?」言いながらこの女性、なんとソマの背中にそのまま座ってしまった。「ばっ……ふざけんな、すぐ降りろ、その尻どかせ!」ソマの訴えに耳を貸す気もないらしく、にやにやと薄ら笑いを浮かべている彼女は、恐らくソマの親近者だ。思うに――杣庄茨。「お邪魔しております。同僚の八女芙蓉と申します」「こんにちは。児玉玄と言います。大学生です」「杣庄茨だ。よろしく」案の定だった。それにしても、苛烈な女性だわ。「お噂はかねがね……」「どんな噂だろ? ま、こいつのことだから碌なものじゃないだろうが」完全にソマを椅子扱いしている。足を組んだその姿勢は完全にリラックスモードだ。「先ほどはこの馬鹿が失礼した。代わって謝るよ。すまなかった」「く……っの、どきやがれ!」渾身の力で起き上がったソマ。椅子を失った茨さんはそのまま立ち上がると今度は壁に寄り掛かる。「さっき帰ってきたばかりだろ!? 寝てろよ、茨!」「ノビの容疑者にバンカケしたらあっさり歌ったんでな~。今日は気分がいいんだ」専門用語の羅列に首を捻っていると、茨さんがこっちを見て言い直した。「住居不法侵入の容疑者に職務質問をしたら、あっさり自白したんだ」茨さんの職業を思い出す。詳しい所属先までは分からないけれど、刑事だった。「そのご機嫌麗しい最中に、だ。ヤサでぎゃんぎゃん吠えられちゃ構わねぇんだよ、このタコ」言葉遣いは悪いけれど、言っている内容は至極尤もな話だった。夜勤明けでお疲れのところに訪問してしまったのは、完全にこちら側の落ち度だ。常識を優先しなければならなかった。アポを入れるべきだったのだ。「ごめんなさい、私ったら……」「あぁ、あたしはあなたに怒ったわけではなくて、一方的に大声を張り上げた進を叱ってるだけだから、気にすんな。それと、別に出直さなくてもいい。つか、なに揉めてたんだ?」「茨には関係ない」「進には訊いてねぇんだよ。それに、関係あるかないのかはあたしが判断する! さ、どーぞ?」促された私は言葉につまる。話してしまった方がいい。それは分かってる。でも、もし訊ねて、ソマや唄ちゃんのように取り乱すようなことがあったら?肝の据わった人に見えるけれど、私にはその『万が一』の展開になるのが恐ろしい。「構わねぇから言ってみ? あ、ちょい待ち。上がんな」この人……。私が――それこそ――『歌う』ことを確信してるんだわ。「……分かりました」あぁ。この人の前では、黙秘し通せるわけがない。*案内された応接間であらましを告げている間、茨さんは口を挟むことなく静聴していた。ソマは黙って茨さんの横に座っている。こちらもまた、正座を崩す格好で。私が唄ちゃんにも迷惑を掛けたことを詫びると、茨さんは「ふぅん」とだけ呟いた。しばらく無言の間が続く。その静寂を打ち破ったのは、顔をひょっこり覗かせた唄ちゃんだった。「お兄ちゃん、店番交替してくれるんじゃなかったの? もう30分も超過して……あっ、ごめんなさい。来客中?」相手が私と玄君だと気付いた唄ちゃんは、驚いた顔をする。その顔に悲観的なものは浮かんでいなかったけれど、私はどうしても謝りたい衝動に駆られた。「唄ちゃん! 先日はごめんなさい」「芙蓉おねーさま、そんな……。寧ろ、あんなに取り乱したりして、私こそ謝らないといけないなって思ってて……」「ありがとう、唄ちゃん」その気配りにじんときてお礼を言うと、唄ちゃんはふるふると首を振り、微笑んだ。「唄、シンを連れて来な。あんたたちにも同席して貰うよ」「お店は、お婆ちゃんに任せていい?」「どうせ誰も来やしねぇよ」茨さんの言葉に唄ちゃんは肩をすくめ、パタパタとスリッパ音を鳴らしながらいずこかへと去って行った。『シン』とは、恐らく少し前に逮捕された万引き犯の1人息子のことだろう。見受け人が正式に決定するまで、杣庄家で預かっているという話は聞いていたけれど、どうして呼ぶ必要があるのかは疑問だ。先にシン君が現れた。見ず知らずの大人がいたことで臆したのか、入り口で止まってしまったのを、茨さんが入室するよう手招きする。白のTシャツにベージュのカーゴパンツという出で立ちのシン君は、年の離れたソマの実弟に見えなくもない。「適当に座んな」じゃあ、とソマの隣りにちょこんと座る。丁寧にも正座をして。やがて唄ちゃんが、急須とお茶受けを載せたお盆を持って入って来た。お茶受けは北海道の名産、三方六。「お土産に頂いたの。どうぞ、召し上がって下さい」そう言うと、慣れた手つきで6等分に切り分けて配膳してくれた。唄ちゃんも正座したのを確認すると、茨さんは言った。「昔話をしよう」*「20年前、あたしらと両親の5人は県内某所に住んでた。子供会の集会の時だったかな。同級生の親がこんな会話をしてきたんだ。『杣庄さん家も大変ね。越してきたばかりなのに』」「大変?」「隣家がゴミ屋敷だったんだ。町内会なんかで常に問題視されててさ。特集を組む為にテレビクルーが撮影しに来たこともあった。老婆が1人で暮らしていたんだが、まぁ、これが気の強い御仁でね。どれだけ苦情を入れても物集めをやめようとしなかった。だがある日、とうとう年貢を納める時がきた。強制執行だ。住民の訴えに、行政がやっと腰をあげて立ち入り調査が入ったんだ。『どいつが先導者だい!?』『俺だ、ババァ!』なんて具合に、当日は相当、揉めに揉めたよ。トラック数台分に乗せられた品々を見て、ゴミ屋敷の主は打ちひしがれていった。やれやれ、これでやっと問題が片付いたと思いきや、主は懲りずにゴミを溜めだしてなぁ。またもやお宝の山を築き上げていったんだ。ちなみに町内会に訴えた男っつーのは、ゴミ屋敷の斜向かいに家を構えててな?車庫から車を出す際に、ゴミ屋敷から溢れ出た『壊れた洗濯機』が原因で、愛車のボディをガガガッと削っちまったんだと。それで腹の虫が治まらなくて発起人になったわけだが、こいつがまぁ、再び累々と積み上げられたゴミを見て、怒る怒る!行政が介入しても改善しないどころか、悪夢の再来。怒りは沸点に達して、ある日、男はゴミ屋敷に火を点けた」「……!!」「昼間だったが、生憎と風が強かった。火は瞬く間にゴミ屋敷のありとあらゆる物体を舐めるように溶かし、やがて杣庄家にも飛び火――。我が家は類焼した」「そんな!!」「命辛々逃げ出した老婆は生きてた。だがもう家にはいられない。何せ全焼だからな。老婆と杣庄家の5人は公民館を借りて寝泊まりすることになった。『こんな事件を起こしてしまって申し訳ない。もう品物は集めない』。今更謝罪されたって、耳には入ってこねぇよな。心にも響かねぇ。突然の出来事に、我が家全員茫然自失だったんだから。事件があったのは、その夜だった。公民館に、くだんの男が入って来た。『ババァ、まだ生きてやがったのか! もう1度火を点けてやる!』と言い出したそいつを、老婆は『この放火犯め!』と罵った。しばらく罵り合いが続いて――逆上した男は、持参した刃渡り20cmの包丁を使って、老婆を刺殺した」「……うそ……」衝撃の告白を聞いて二の句が出ない私に、茨さんはサラッと続ける。「この辺の描写はしないから安心しな。話してるこっちも、いい気分じゃないしな」ここで一端口を閉じると、茨さんはソマや唄ちゃんへと視線を向ける。2人は項垂れていた。先日のようにうわ言を呟いたりはしなかったけれど、畳には既に涙の海が広がっていた。再び、茨さんの回想が始まった。「切っ先は今度、母に突き付けられた。男の目は完全にイッちまってたよ。恐怖に駆られた母は――」「『お願い、やめて、やめて下さい。どうか……! 私じゃなくて、子供たちを……!』」私は二重の意味で驚いた。母親が恐怖の中で口走った一言がもし本当にその言葉だったのなら、子供を犠牲にしてまで命乞いをしたのと同じだからだ。そしてその言葉を紡いだのが杣庄家の誰でもなく、玄君だったから、余計に混乱せざるを得なかった。茨さんが目を剥いて呆然としている。「なぜそれを知っている……?」とうめいたことで、玄君の言葉が事実なのだと判明した。「急に……女性の声が、頭の中に流れ込んで来たんだ」玄君も玄君で、衝撃を食らったみたいだった。よろめきながら立ち上がった玄君は、ソマに近付くなり、手首を掴んだ。「そう、これだ! これが教えてくれたんだ」「な、なんだ……!?」戸惑いの色を隠せないソマは、玄君の視線が自分の手首にあることに気付く。パワーストーンと数珠が連なった革のブレスレットに。「この家に来てから、石が呼んでる気配を感じてたんだ。これだったのか……」千早が言っていたのは、この風変わりな能力のことね。私とソマは事前に知っていたから話についていけたけど、茨さんや唄ちゃん、シン君はぽかんと口を開け、呆けていた。「3人にお話しがあります。あなた方の母親は、決してあなた達を見捨てたわけじゃない」「な……なに言ってんだ、玄?」「玄くん、ウタに気を遣わなくていいよ……?」戸惑うソマと唄ちゃん。一方で、茨さんは目尻を上げた。「やいやい、どういう意味でぇ!? あいつは『どうか私じゃなくて子供を』って、こう言ったんだ! 何が、どう違う!?」玄君は既に、柾さん譲りの冷静さを取り戻していた。私にはそれが、頼もしく思えた。「本当はこうです。『お願い、やめて、やめて下さい。どうか……! 〝あなた、私じゃなくて、子供たちを先に逃がしてあげて”」「あなた、私じゃなくて子供を先に逃がしてあげて……?」思いもよらなかったのだろう。ソマは呆然としている。「呼び掛けてる『あなた』ってのは……俺らの親父のことか?」「そうです」「そんな……馬鹿な! あた……あたしはてっきり……子供たちを狙えって言ったのだとばかり……。……嘘だろ?」「本当です。信じて下さい。お父様は、御存命ですよね?」「あぁ……。だが……。実は、犯人と格闘したとき、揉み合いになって殺しちまったんだ。男が持っていた包丁でな。勿論正当防衛さ! とはいえ、もうそこには住めなかった。逃げるようにして出て行ったよ。親父は今、県外で1人暮らししてる。あたしたちは祖母に預けられて育ったんだ……」何から何まで驚くことだらけだった。これだけのものを、3人はずっと、こっそり抱え続けてきたと言うの?先日放火のニュースを聞いて取り乱したのも、事件を思い出してしまったから?「迎えに行きましょう」私の口からは、自然とそんな言葉が漏れていた。「……八女サン?」「ソマのお父さん、身を挺して庇ってくれたのよね? 近い内に……呼び寄せて……家族と一緒に暮らせたらいいなと思って」ソマは無言だった。正当防衛とは言え、人を殺めた経験を持つ父親と、1つ屋根の下で暮らそうなどとは到底思えないのかもしれない。或いは、今まで信じて疑わなかった母親の痛烈な言葉が、真実と真逆だったことを受け入れるだけで精一杯なのか。「ふえぇぇ。玄くんありがとう。ほんとに、ほんとに、ほんとに、ありがとうっ!」唄ちゃんはお礼のハグを玄君にしたまま、感極まってそのまま泣き出してしまった。茨さんが深い溜息をつく。場は、少しずつ正常さを取り戻しているように思えた。「おい、シンはどうした?」と、茨さんが気付くまでは。皆が一斉に部屋を見渡した。本当だ、シン君がいない。まずは茨さんが駆け出し、次にソマ、玄君。私と唄ちゃんも後を追う。「シン!」呼び止める声がしたのは外だった。じたばたと暴れるシン君の襟首を背後から掴んだ茨さんは、大人しくしろと一喝して、なぜ急に出て行ったのかと問う。途端、シン君の顔がへにゃっと崩れ、泣き顔になった。「嘘付き! 茨さんは嘘付きだっ! 僕と同じだと思ってたのに! 母親が実は味方だったとか、なんだよそれっ、ふざけるな!」「シンっ」「どうせ僕だけボッチだよ! 母親から見捨てられたのは、僕ぐらいなもんだっ。なんだよ、なんであんな話聞かせたんだよっ。自慢か!?」「あたしはあんたを裏切ってもいない。自慢してもいない。そもそも、こうなるなんて思ってもみなかった。こんな展開が待ってるなんて……。あたしはね、シン。あんたにも真実を知って貰おうと思ったんだ。それだけだ」うぅ~とうめくように泣く。孤独に耐えられず、不安が押し寄せたに違いない。「シン君。つまり、茨さんはね、こう言いたかったんだ。『何でも一緒に』って」「シン君も、1人じゃないのよ」私も言葉を添える。瞳を潤ませた少年は、茨さんの胸に飛び込んだ。*帰り道、私と玄君は名古屋駅の地下街にあるスターバックスで休憩した。テーブルいっぱいに何種類ものスイーツを並べたのは、無性に食べたくなったからだ。それほどへとへとだった。一番甘そうなチョコレートのデザートを食べる私も、ソイラテを飲む玄君も、しばらくは無言だった。やがて、どちらともなくほぼ同時に、「はぁ~~~~~~」という深くて長い溜息をついた。「……お疲れさまでした、八女さん」「玄君も。お疲れさま」私たちはお互い持ち上げたコップをコツンと鳴らし合う形で、祝杯をあげた。改めて目の前の人物に御礼を言う。「玄君、本当にありがとう。玄君のお陰よ」「お礼を言うのは俺の方です。冬の頃から杣庄さんが助けを求めてるんだって気付いてたのに、俺なんかが力になれるのかなって不安で、何も出来なかった……。八女さんが声を掛けてくれたお陰です。歴さんにも感謝しないといけないですね」弱々しく笑みを浮かべる玄君は、己の不甲斐なさを嘆いているかのようだった。「ものごとにはタイミングというものがあるのよ。それが丁度いま重なっただけ。玄君が深く考えることないわ」「……気を遣ってくださって、ありがとうございます」「あら、本当よ? それに、結果オーライだったじゃないの。ね!」はい、終わり! とばかりにピーチタルトをフォークで一口サイズに切ると、玄君の口の前へ運ぶ。「はい、あーん」え、と一瞬固まるのが分かった。でもそこは私に恥をかかせてはいけないと思ったのか、素直に食べてくれた。「美味しいです」「よしよし」「……惨劇の発端となったのは放火です。包丁は、目の前で老婆と母親を刺した忌むべき媒体ではありますけど、その包丁のお陰で彼らは助かってもいるんです」「父親が正当防衛を成功させていなかったら、一家皆殺しという結末もあり得たものね」その光景を考えるだに恐ろしい。「そもそも包丁が苦手ならば、杣庄さんはユナイソンで鮮魚売り場を希望したりはしなかったはずです」「そうよね、言われてみれば確かに」「『火事』と『放火』は全くの別物です。八女さんの話を聞くに、杣庄さんたちが反応を示したのは、後者でした」これにて一件落着、とばかりに私たちは「ふぅ」と息を吐いた。心なし、タルトはいつもより甘くて、いつもより優しい味がした。2013.08.012020.02.21 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G3 (―) 【Canicular Days!】
日常編 (―) 【Canicular Days!】[1]文月、土用の丑の日――。灼熱地獄の中、5名の男衆が、客から決して見えない位置に設けられた特設プレハブ内で作業をしていた。そこはユナイソン・ネオナゴヤ店、鮮魚売り場の裏手側。鮮魚専用搬入口と作業場を兼ね備えた通路の、更に奥の奥。プレハブの広さは10畳ほど。簡易とはいえ、それを手掛けたメンテナンス部には「よくやった」と労いたくなるような出来栄えだ。朝8時の時点で、小屋の中は白煙と独特な匂いで充満していた。巨大な扇風機が小屋を取り囲むように4台稼働しているが、それでも霧消には至らない。煙がもうもうと立ち込める中、忙しなく動いているのはネオナゴヤ店の鮮魚社員3人に、本部鮮魚部から今日の為に応援に来ている2人の計5人。ユナイソン・ネオナゴヤ店は――というより、殆どのユナイソンでは――、土用の丑の日は焼き立ての炭火焼き鰻を提供するのをウリとしている。ただ、そうなるといつもの作業場だけでは場所も設備も足りないので、こうして毎年特設プレハブを作っては売り場へ運んでいる。活気もだが、熱気も凄い。職人魂に火が付いたように、5人は鰻を捌いては炭火で丹念に焼き、特製のたれに潜らせていく。「ソマ、こっち出来たぞ。持って行け」「はい!」「炭が足りねぇな」「この鰻を店に出した後、俺が取って来ます!」「頼む」いつもは書類整理に追われている本部陣だが、かつては杣庄のように『現場』を30年勤め上げた、魚売り場の大ベテラン。腕は衰えているどころか、僅か数時間で昔の感覚を取り戻しており、すっかり現役然。そんな2人の巧みな技に舌を巻きつつ、杣庄は言われた通り、出来たての蒲焼を台に乗せ、売り場へと急ぐ。既に開店時間を迎えていたらしい。鮮魚コーナーには出来たての鰻が並ぶのを今か今かと待ち望む人で賑わい、杣庄と鰻を見るなりワッと詰め駆けた。「ちょ、待っ……」心の準備が出来ていなかった。狼狽する杣庄を補佐したのは、これまたベテランの女性パート。毎年恒例の事だけに、裁き方を心得ている。「さきほどお配りした番号表通り、1番から順番にお渡ししますからね! ちゃんと渡しますから、大丈夫ですよ!」慌てなくてもちゃんと数を用意出来る。なくなっても、裏で沢山作っているから、少し待って貰えれば渡せる。そんな言葉が客たちに安心感を与え、場の混乱は収まっていった。「さんきゅ。助かったよ、和瀬さん」「こんなの朝飯前。ここは私に任せて、ソマ君は裏で作って作って!」「あぁ」額に浮かんだ玉の汗を、首に掛けた手拭いで拭うと、杣庄は駆け足でプレハブへと戻った。途中、炭の束を掴むことも忘れずに。(懐かしいわねぇ)芙蓉は、売り場とプレハブを忙しなく行き来する杣庄の姿を見て、昔を思い出す。あれは、杣庄が本部で行われていた新人教育を終え、岐阜店へ入ったばかりの頃だった――。[2]「お帰りなさい、芙蓉」2ヶ月の出張を終えた芙蓉が岐阜店へ戻ると、悪友の馬渕が労いの声を掛けてきた。「ただいま。私がいない間、何か面白いことはあった?」「そうねぇ。新入社員が入ったぐらいかしら~」「へぇ? 今年の新入社員って? 何人だっけ」「貴女の部下になる子が1人。潮さんって言う子。本来ならFTである貴女が教えるべきなのに、可哀想に、未だ本部で研修を受けてるわ」「本部に電話しないといけないわね。私が面倒を見るから、引き渡して貰うよう言わなくちゃ」「先週、鮮魚に1人来たわよん。男の子が! 目がギラッギラしててね、なんかもう、いかにもヤル気に溢れた新人君って感じなの。初々しいわ~」「鮮魚だけに、イキがいいのが来たってわけね」「それも、とびっきりの、ね」うふふと馬渕が眉尻を下げる。恍惚としたその表情は、女である芙蓉すらドキッとしてしまう魅惑的なものだった。[3]馬渕にそそのかされたわけではないが、芙蓉は何となく鮮魚に入った新人が気になり、仕事に託けて売り場を覗きに行った。鮮魚売り場は独特の臭いを放っているが、芙蓉はそういう香りが嫌いではなかった。そこには色んな人が汗水流して頑張った結晶――商品――があるから。市場から仕入れたばかりの真サバやトビウオといった旬の魚を横目に、芙蓉は件の人物を探す。すると見慣れない男が1人、芙蓉の横を通り過ぎる。擦れ違いざまに目が合った。時間にして数秒。相手は芙蓉を見て瞠目したように見えたのだが――単なる気の所為だろうか。声を掛けようとしたが、肝心の『言葉』を用意していなかった。結局、彼がそうなのね、と納得するだけの形で、芙蓉はその場を後にした。[4]例の新人がPOSルームを訪ねて来た。入荷したばかりの商品を登録して欲しいとのことだった。出迎えた芙蓉は、新人の格好を見て顔色をサッと変える。その変化に気付いたのか、若干戸惑った様子で彼は訊ねた。「あ……俺、何か不味かったですか?」馬渕に『ギラッギラとして』と言わせしめた目には、今や狼狽の色が浮かんでいる。芙蓉は努めて冷静に言った。「あのね、ルーキー君。キミの足元を見てごらんなさい」芙蓉の言葉に、彼は素直に従った。己の足を見下ろし、これが何か? と尋ね返す。「靴よ靴。それ、鮮魚用の長靴でしょ? 売り場から離れる時は、ちゃんと履き替えなさい。上司から教わらなかったの?」「あ……。すみません……。そうですよね、不衛生でした」(あら、素直な子じゃない)「分かればいいの。これは登録しておくから、持ち場へ戻っていいわ」「お願いします」軽く礼をして、踵を返す。その背中を見送りながら、芙蓉は首を傾げる。どうにも馬渕の言っていたような、『ヤル気に溢れた』感が伝わってこない。(でも、鮮魚に配属された新入社員って、彼のコトなのよね?)さっき名札を見た。そこには『杣庄』の名。(杣庄君ねぇ……)配属されてから今日までの間に、やる気を削がれるような出来事でもあったのだろうか。自分の時はどうだったかしらと懐古し、配属されたのは今とは違う部署だったと気付く。もれなく余計な思い出――それも思い出したくもない、最低な――までオマケで付いてきて、芙蓉は慌てて記憶を頭から追い出した。指は自然と、杣庄から依頼された商品を登録していた。今ではすっかりPOSオペレータねと苦笑を漏らす。[5]岐阜店の閉店時間は21時だが、それはレジを閉める時間であって、従業員が帰れるのは21時15分以降。その日、芙蓉は16分に退室の旨をIDカードにて記録していた。更衣室で服を着替え、帰る準備を済ませた彼女は、消したはずのPOSルームに灯りが点っていることを不思議に思い、ガラス窓から部屋を覗いた。(……誰?)見ない顔だった。明らかに自分より年下の男が、芙蓉の席に座っている。ドアノブに手を掛けると、スムーズに開いた。パスワードが解除されている。パスワードはチーフ職の人間に聞けば答えられるような簡単な4桁の数字で、確かにあってないようなものに思えるが――。それでも、POSルームは特殊な部屋に違いない。そんな部屋で、こそこそと何をしているのか、この男は。「何してるの?」突然の芙蓉の声に、男がハッと顔を上げる。バツが悪そうな表情だった。「あ……すみません。俺、売価変更の依頼をしたかったんですけど、POSオペレータさんの姿が見えなかったから……」「あなた、誰?」「俺――じゃない、僕は杣庄です。鮮魚に配属された新入社員です」(昼間のルーキー君か。帽子と作業着を脱いでるから分からなかったわ)「POSオペレータ以外の人間が勝手にシステムを操作するのは感心しないわね。新人なら尚更よ。不正だとかセキュリティだとか、そういう面を考慮すると」「すみません」これで、杣庄から聞いた謝罪の言葉は何回になっただろう?1度注意すれば素直に聞くタイプのようだし、お小言を食らわせるのはそこで勘弁することにした。「代わるわ。紙を見せて。……あぁ、本部からの緊急FAXね。どこまで入力――」杣庄を立ち上がらせ、いざ自分の席に座り直すも、それら全てが無駄な行動だった。FAX用紙にびっしりと書かれた訂正箇所は、既に杣庄の手によってレ点が打たれている。芙蓉が21時に離席してから約20分。その間に杣庄はパソコンを立ち上げ、これらを入力し終えたと言うのか。「あなたが入力したの?」「すみません」「違うわ。責めてるわけじゃないの。完璧に入力してるから、『凄い』って言いたかっただけよ」若干興奮気味の芙蓉に、杣庄は僅かに顔を赤らめる。その反応が初々しくて、芙蓉はその顔を見詰めた。「いや、あの……本部研修で教えて貰いましたし……。それに俺、じゃない僕、パソコン操作には慣れてるから」「俺でいいわよ。一人称」いちいち言い直すところが可愛くて、芙蓉はくすくすと笑う。杣庄の顔は、更に赤みを増した。(よく見ると……顔が整ってるわねぇ。帽子・作業着の時の印象とは、大分違うわ)さらさらの髪は柔らかそうだ。決して染めたりはしない、硬派な黒艶。仕事柄なのか、目にかからないその髪は、清潔感を与えている。半袖から覗いた腕はバランスのいい肉付きで、スレンダーに見えるが、スポーツを難なくこなす風にも見える。それなのに、理系にも文系にも見える。(不思議な子ねぇ……)でも、芙蓉的にはイケメンの部類に入る。とは言え、同期の伊神を皆が『イケメン』と評す中、芙蓉だけが首を縦に振らないので、自分の審美眼についてはイマイチ自信が持てないのだが。(まぁいいわ! 私が好ましいと思えば、それでいいのだし。うん、ジャニーズっぽいわねぇ、ルーキー君♪)己の顔を観賞されていることに気付いたのか、杣庄の顔には困惑の色が浮かんでいる。「ねぇ、困ったことでもあった?」「は……?」唐突に尋ねられ、杣庄は答えに窮した。「馬渕があなたのことを、『目がギラッギラしてて、いかにもヤル気に溢れた新人君』って評していたの。でも私が見た限り、そんな風には見えなかったから……。困ってることがあるなら、相談に乗るわよ?」「あ……いえ……」ふい、と顔を背ける杣庄。芙蓉は「それならいいけど」と言い、その件についてはそれ以上言及しなかった。「期待してるわよ、ルーキー君。じゃあね」パソコンの電源を再度落とし、芙蓉は手荷物を持って部屋を出る。慌てて杣庄が廊下まで出ると、その背後に「お疲れ様でした!」と声を掛けた。「お疲れ様。明日も頑張ってね。お休みなさい、ルーキー君」「……ルーキーなんて呼ぶなよな……。ちぇ、完全に部下扱いだ。こっちは一目惚れして、八女さん相手に緊張しまくりだってのに……」そんな呟き声が杣庄の口から漏れたことなんて、一切知るよしもなく。芙蓉は一つ大きな背伸びをして、岐路に着く。[6](あの頃は初々しかったわよねぇ、杣庄も)今ではすっかり凛々しくなった。年下だけれど、誰よりも頼りになる、立派なジェントルマン。彼は今、暑さと闘いながら手の甲で汗を拭い、やっと日陰での15分休息に漕ぎ着いたところだった。「ソマ」呼び掛けた芙蓉の声に気付くと、杣庄はふっと柔らかい笑みを浮かべた。日に照らされて赤くなってしまった肌を、汗が伝っている。アスファルトの地面にぽたりぽたりと落ちていく雫たち。「はい、これ」水に潜らせた冷たいタオル。芙蓉の差し入れを受け取ると、杣庄は顔を拭き、首に掛けた。「うわー、極楽! 気持ちいい……」「お疲れさま」「これしき平気だよ。あ、八女サン」「ん?」「今日の夕飯は、俺が焼いたうなぎ食べて」「ソマ、それ、最高の口説き文句」「ははっ。楽しみにしてな! 美味しいの焼くから」そして笑う。芙蓉だけに向けられた笑顔。立ち上がった杣庄は芙蓉の頭をぽんぽんと叩き、駆け足でプレハブ小屋へと戻って行った。その背中を、芙蓉は誇らしく思う。文月、土用の丑の日。蜃気楼に揺らめくアスファルト。灼熱地獄の中に見る、今となっては誰よりも愛おしい人。2011.07.212020.02.21 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G3 (―) 【Come Across!】
日常編 (―) 【Come Across!】[1]そうなんスよ。最近、ちょっと立ち寄り辛いですよね。若干怖い女の子がいるかなって。触らぬ神に祟りなしですけど。正直、困ったと言えば困ってるんです。 「――ってコトを、平塚クンから聞いたの」「それが俺の家に来られない理由? マジっすか?」「治安が悪いんでしょう?」「たまたま平塚が柄の悪い学生を見掛けただけですよ」「十分怖いわよ」「大丈夫だって。俺が迎えに行くから」「そう? じゃあ明日。午前中は美容院に予約を入れちゃったの。14時にバス亭に来てくれる?」「分かった。じゃあ明日な。お休み」「お休みなさい」会話を終わらせ、携帯電話の通話を遮断。古着屋店への冷やかしショッピングを兼ねた恋人の初家庭訪問に漕ぎ着き、やれやれと言ったところか。ふぅーと息を吐いていると、「『大丈夫だって。俺が迎えに行くから。お休み』……だって! きゃーっ」黄色い歓声にギョッとして振り返れば、店番を終えて住居スペースに戻って来た妹の唄が柱の影からひょこっと現れる。「唄」「今の! 今の絶対彼女よね!? お兄ちゃんにも春が来たのね! ねぇ、どんな人!? どんな人なの、教えてよー!」唄と恋は切り離せない。いつでもどんな時でも恋に生き、恋愛を中心に人生を謳歌してる唄にとって、俺のスキャンダルは砂漠のオアシス並に魅力があるらしい。「お前には関係ない」存在を認めてしまえば、根掘り葉掘り質問攻めに遭うのがオチだ。ここは黙秘権を行使するに限る。「いいわよ、大体分かるから」「……は?」分かる?「分かるって、何が?」「お兄ちゃん、意外にも堅物で硬派なトコあるしー、大和撫子タイプと思いきや、意外に元気な子に惹かれたりするんだよね。黒髪サラリより、茶髪ふんわりが好きでしょー? ねっねっ、どう? ウタの推理! 鋭いトコ突いてる?」どういう心眼をしてやがるんだろうな、コイツは。一応合ってはいる。だがここで認めるわけにはいかない。「彼女なんていねぇよ」「ふふっ、付き合いだしてまだ間もないんだねー」……生活しにくいこと、この上ない。[2]杣庄唄の≪庭≫移動には、たいてい地下鉄とバスが使われる。 今日は地下鉄伏見駅から東山線に乗り込み、星ヶ丘に出た。デートは高級住宅街が広がる静寂と気品の街の中にある『星が丘テラス』に決定だ。 基本、唄はデートに時間を掛けない。デートは3~4時間で終わらせる。それがいつものスタンスだった。だらだら一緒に居続けると刺激や緊張がどうしても薄れてしまうし、これからという時分で別れ、次の逢瀬に繋げるのが彼女のデートの仕方だ。今日も待ち合わせはランチを兼ねたこともあり11時にセッティングしてあるが、相手には14時で帰る旨を、前もって告げてある。「店番忙しいのに今日は付き合ってくれてありがとね、唄ちゃん」「ウタも、少しでも一緒に過ごせて嬉しいよ」「3時間しかないから、色々考えてきたんだけど」「本当? ケヴィン、ありがとー!」限られた時間内で唄を喜ばせようと、相手は有意義なデートプランを用意してくれる。やはり、時間はハッキリ区切ってしまうに限る。[3]デートの相手とは星ヶ丘で別れ、唄は単独岐路に着く。他にも寄りたい店があったため、唄は最寄りの市営バス停からバスに乗り込んだ。学校が多い地区でもあるが、幸い、この時間帯は下校時刻とは重ならないようだ。それでも3人の女子大生たちが乗車した。バスの乗車率は低いので簡単に席にはあり着けるのだが、何を思ってか3人の女子大生はバスの乗車口付近に塊っている。次の停車場で乗り込んできた人の邪魔になりかねない。それを承知の上なのか、あるいは我関せずなのか……。 バスの揺れに心地よくなってきた唄は、うとうとと目を閉じる。目的地まで寝てしまわない程度に休んでいようと身体を沈めるが、女子大生たちの話し声は大きく、前の方に席を取った唄にまで聞こえてきた。 「こないだ合コンした医大生。何度も電話掛かってきて迷惑なんですけど」 「でもこの御時世、医大生は貴重かもよー? キープしとけってー」 (他の乗車客も困ってるだろうな……)休息を邪魔され目を開けた唄は、問題の集団をコソコソと見やる乗客が点在していることに気付いた。早く降りてはくれないものかと舌打ちするサラリーマンの男性もいたが、その音は彼女たちにバッチリ聞こえていたようだ。 「聞いた今の? 胸糞悪いわ、あのオヤジ。うちらのコト邪険にした」 「聞いた。何アレ。超ムカツク」 「ナニサマのつもり? オヤジ死ねよ」 非難轟轟の嵐に、サラリーマンは俯いてしまった。 あわよくば彼女たちの暴走を止めて貰おうと思っていたのだが彼には荷が重かったらしい。 女子大生らは再び会話に花を咲かせていた。全く降りる気配も見せない。一体彼女たちはどこで降りるつもりなのか。唄は意を決して席を立つ。近付く静かな気配に、3人は唄を見やった。 「なにあんた」 「えっとー……、ごめんなさい、少し会話のボリュームを落として貰えませんか? それにそこは入り口だし、もう少しその長い脚を引っ込めてくれないと、他の方が乗る時に引っ掛けたりして危険かなー、なんて」 唄が笑みを浮かべながら告げると、相手は鼻で笑う。 「なにこのヒト」「あれだ、お説教ってヤツ」 完全に馬鹿にした目が、面白そうに唄を嘗め回す。上着、スカート丈、身に着けている装飾類の品定め――まるで唄のスタイルを推し量っているかのようでもある。 「オネーサン、雑誌モデルみたいな格好してるー。必死だねー。心優しい美咲が、オトコ紹介してあげようか。医学生なんだけどー」 「医学生?」「うわ、オネーサン必死? ちょっと心揺れてるし!」 「ううん、そうじゃなくて。いま付き合ってるひと、お医者様なの……」 素で反応する唄。それがあまりにも自然だったので、その言葉に嘘偽りがないことを悟ったらしい。唄が気に食わなかったのか、美咲が拳を突き出してきた。条件反射でよける唄。呆れると同時に身の危険を感じ、唄は外の景色をチラリと見た。次のバス停までは僅かな距離だが、問題はそこから乗車する客がいるかどうかだ。機転を利かして運転手が止まってくれればいいのだが――。 「素直に殴られなさいよ!」 今度は別の女子大生が殴りかかってきた。(しまった、裁ききれない)息を止め、覚悟を決めた唄だが、急なブレーキのお陰で救われた。「……なによ、赤信号?」「違う、バス停だって」と舌打つ美咲。 『名古屋駅前ー名古屋駅前ー』のアナウンスと共に、すぐ横の入り口が音を立てて開いた。主要停留所なだけあり、乗る客は多い。「邪魔よ」とステップを登りかけた女性の声がした。その人物を見て、唄は目を丸くする。 乗車してきたのはとんでもない迫力美人だ。女性は3人を押しのけると仁王立ちに腕組みをする。その迫力に度肝を抜かれ、全員声も出ない。 「公共の施設で一体なんなの、アンタたち? というか、何の騒ぎ? 乗客が全員降りちゃったわよ」「おばさんこそなんなのよ!」「……ねぇ、このひと……どっかで見たことある気がする」 1人が呟けば、「はぁ?」「誰なの?」と他の2人も女性を見つめる。 「あ……あー! この人『芙蓉の君』だ! 2年連続ミス政嵐の!」「なに? うちらのセンパイってこと?」「そこ!」 急に鋭い声を発した女性に、唄を含めた4人はびくりと身体を強張らせた。 「はぁ? 何?」 「構図的に考えて、3対1の喧嘩かしら。見苦しいわね」「なっ……」「しかも、原因が手に取るように分かるわ」女性は唄をチラリと見てから、鋭い視線を3人に向かって投げ掛ける。「しかも私を知っているなんて、世間は狭いわね。――御機嫌よう、私の可愛い後輩たち?」「……ヤバイ、逃げよう。名古屋駅で騒ぎ起こしたら後々面倒だし!」 青褪めた女子大生は発車寸前にも関わらず運転手に扉を開けるよう脅し気味に言いつけ、一斉に降りる。 歩行者専用道路を走り抜ける彼女らの背を見送っていた唄は我に返ると、目を輝かせて女性に声を掛けた。「あの……! 有り難う御座いましたっ」「別に、御礼を言われることなんてしてないわ」苦笑をする女性。名古屋駅からの出発だというのに、異例の少人数になってしまった、空席が目立つバス。女性が適当な席に座り直すと、唄はおずおずとその隣りに腰を落とす。「あの……隣りに座っても構いませんか?」「あら。もう座ってるじゃない」くすくすと笑うその笑顔に、唄は顔を火照らせる。「ところで、さっきの騒ぎは何だったの?」尋ねられたので、唄は事の経緯をざっと話す。話し終えると、「なるほどね」と彼女は言った。「可愛いだけじゃなく、勇敢なのね。きっと素敵な教育を受けてきたのね」女性の言葉に唄は顔を少しだけ曇らせた。それでも笑顔を貼り付かせながら、明るく答えてみせた。「実は、両親がいなくて。祖母と姉たちに育てて貰ったんです」「そう。じゃあ、その方たちがたくさん愛情を注いでくれたのね。私も母がいないから、父にはかなり苦労をかけてしまったわ」「おねえさんには、兄弟がいないんですか?」「兄弟はいないわ。一人っ子なの。あ、今、私を可哀想とか思ったでしょ? それは違うわよ。父の愛情を独り占め出来たもの。ふふっ、いいでしょ」「……はい!」そんな話をしながら、唄は『おねえさん』との会話をこのまま楽しみたいと思う。(初対面なのに、それも図々しい話かしら? でも素敵な人だし……!)出逢ってまだ数分。なのにどんどん惹き込まれていく。目が離せない。心が近寄りたがっている。「おねえさんは、政嵐学院の卒業生なんですか?」「どうして?」「さっきの女子大生、ミス政嵐がどうとかって……」「過去の栄光ねー。私にもそんな華やかな時代があったという話よ」「そんな。今だって華やかですよ!」「あら。ありがと」だが、無情にも別れは近付いてくる。見慣れた風景は確かに地元のもので、バスの運転士は『大須ー大須ー』とアナウンス。唄は断腸の思いで降車ボタンに手を伸ばしかける。だが、女性の方が窓際に座っていた分、押すのが早かった。「あ……おねえさんも大須で下りるんですか?」「えぇ。彼氏と待ち合わせしてるの」「デートですか! いいですねっ。……あーぁ、私のお兄ちゃんの彼女が、おねえさんのような女性だったらよかったのにー」「ありがとう。私もあなたのように、可愛くて素直な妹が欲しいわ」(言うのよ、ウタ! おねえさんに連絡先を聞いて、アドレスを交換し合って――! さぁ早く!)「あ、あの……」【大須ー大須ー。降りる際は足元に御注意下さい】アナウンスに急かされ、降りざるを得ない。こうなったら地上で接触するしかない。唄は先に降りると、彼女が降りて来るのを待った。だが女性は待ち人を見付けたようだ。片手を挙げ、「待たせてごめんなさい」と嬉しそうに微笑む。「……え!?」唄は目を疑った。『おねえさん』が話しかけているのは紛れもない、実の兄だったから。お兄ちゃん、と言いかけた言葉を遮るように、女性は「ソマ!」と呼び掛ける。「ちゃんと迎えに行くって言ったろ? ……って……どうしてお前まで一緒なんだ、唄」「お兄ちゃん……それは……こっちのセリフ……」「え? ソマ? ……お兄ちゃん?」「……えーと、お互い名前は知らないワケだ? 分かった、紹介する。八女サン、こいつは俺の妹の唄。唄、この人は職場の先輩で、八女芙蓉さん」「ひどい!」その紹介文に怒りの声をあげたのは唄だった。あまりの剣幕に、杣庄も芙蓉もビックリしている。「おねえさんはお兄ちゃんのこと『彼氏』だって私に言ってくれたのに、お兄ちゃんはおねえさんのこと、職場の先輩だなんて言うんだ!? どうしてちゃんと『彼女』だって言わないの!? お兄ちゃん、最ッッ低!!!!」「な……っ、馬鹿、こんな往来で……!」「男なら堂々と『俺の彼女だ』って言いなさいよね、お兄ちゃんの馬鹿ー!」「だから唄! 黙れ、お願いだから!」感情が昂ってきたのか、唄の目にはうっすらと涙が浮かんでいる。芙蓉にはそれが嬉しくて仕方ない。自分の気持ちを察してくれただけではなく、見事に代弁してくれた。「唄ちゃん、ありがとう」芙蓉はぎゅ、と唄を抱き締める。いい子だ。こんなにいい子だったなんて。祖母と姉たちに育てて貰ったんです――。その言葉は、どこまでも本当だった。「唄ちゃん、今から私と一緒に遊ぼうか」「芙蓉さん……! あの……『おねえさま』って呼んでもいいですか……?」「こらー。ちょっと待てー。どこへ向かおうとしてるんだお前はー。つーか、八女サンは俺とデートだっつーの!」「お兄ちゃんに芙蓉さんは勿体ないと思う!」「いや、それは確かにそうなんだが……。こら、待てよ唄!」「お兄ちゃんなんて大嫌いーっだ! 行きましょ、芙蓉さん。大須、ウタが案内してあげる!」「本当? 嬉しい」「唄!」ほら、だって。陽はまだあんなに高い。だから、まだまだ一緒にいられる。2011.03.102020.02.21 改稿
2020.02.21
コメント(0)
-
G3 (―) 【Happy Valentine!】
日常編 (―) 【Happy Valentine!】「……なんでここにいるんです」「それはこっちのセリフだ」*2月14日、午後12時半。昼休憩にありついた犬君が回転寿司店に入ると、店員からテーブル席での相席を請われた。平日だが、チラシ広告が打たれた日とあって、ユナイソンネオナゴヤ店内は休日並みに賑わっている。さらにこのお店自体が1皿85円のキャンペーンを行っていることも相まって、店からはみ出るほどの長蛇の列が出来ていた。回転寿司といえば客の回転率は早い方だが、それでも昼時とあって席の確保は追い付かないらしく、犬君は二つ返事で了承したのだが。「げ」「うわ」あろう事か、通された先には杣庄がいた。「……店員さん、チェンジで」「行っちまったぞ、馬鹿」空の皿が2枚に、しょうが、湯呑み。杣庄も席に着いて間もないようだった。となると、しばらくは顔を向き合わせて食べるしかないだろう。大人しく黙って食べればいいものを、テーブルに設置された注文用のタブレット端末を奪い合い、そのたびに言い争う格好となる。口喧嘩の論点は次第にずれていき、今日がバレンタインデーということもあり、チョコレートの話題へと発展した。「チョコの数だ? そりゃ減るだろ。彼女ができたんだから。誰も八女さん相手にしようなんて思わねーよ」「ざまーみろです。僕は増えましたけどね、ふふん」「透子とお前が結ばれるお伽噺なんざ、誰からも想定されていないからだろ。たくさん貰えてよかったな、モテ男」杣庄は洒落た黒い紙袋を手繰り寄せた。中身を取り出すと、犬君に見せびらかすように、ひらひらと上下に動かしてみせた。大きくはないが、小さくもない。手をパーに広げた程度の大きさだ。幅は5cmほど。その漆黒の箱は厳かに見え、決して安価には見えない。「義理すら貰えないんじゃ俺の相手じゃねぇよな」「まさかそれ、透子さんからとか言いませんよね」「透子からだっつの。さっき貰った」今日、透子とは2度ほど会話のやり取りをしている。プライドが邪魔をして、自分から催促はしていない。その実、淡い期待はしていた。二人きりのタイミングを狙っての接触だったのに、チョコのチの字もなければ、何かを渡そうとする素振りも見受けられなかった。――それなのに、ソマ先輩には既に渡しているだって? 義理なのに、あんなに立派そうなものを?敗北感を抱かずにはいられなかった。己が惨めで仕方ない。これまで何度も尋ねてきた。ソマ先輩を意識してるのではないのかと。そのたびに透子は怒り、「杣庄とはそんなんじゃない」と言い切った。しかしである。待遇が明らかに違い過ぎやしませんか、透子さん。なんですか、あの黒い箱。あれ結構高そうですよ?あぁ、太刀打ち出来ない――。本命とはいかないまでも、せめて義理だけでも。欲しかった。透子さんから。「凹み過ぎだろ、お前」お茶をすする杣庄が呆れ顔で犬君を見やる。その犬君からは、ずもももも……と黒い影のようなものを背負っているような気配すら感じられる。児玉玄が見たら「祓いましょう」と言い出しかねない、ダーク極まりない落胆振りだった。「きっと伊神さんも貰ってますよね……」「あぁ、渡してた。俺より立派なものを」――ちょっと。ちょっと待って下さいよ。一体何本刺してくるんですか。僕のライフもうゼロですから。あんたが貰ったって言った時点で既に。「はぁ……」「ご愁傷さん」「……これが現実ですよね。奇跡が起きて、仕事終わった後にツンデレ口調で『ほら、早く受け取りなさいよ』なんて展開、ないですよね」「透子ならあり得なくはないが、お前相手にそれをやるかと訊かれたら、答えはさて、どうだろうな?」会話はそこで途切れた。二人からは、ただひたすら平らげ、空になった皿を積み重ねる音だけ。お互い無言のまま皿の積み上がる高さを競っていたものの、杣庄が先におりた。あぁ大人だな、と思う。ムキになって喧嘩をしかけてみたところで、相手は飄々とこなしてみせ、かつ綺麗に身を引いてみせる。自分にはそれが出来ない。したいけれど。そんなオトナになりたいと憧れるけれども。ふいにハッとする。いけすかない杣庄相手に憧れの念や嫉妬心を抱くなんて、どうかしてる――。杣庄が店員を呼び、先に会計を済ませた。自分も既に満腹だし、同じタイミングで店を出ても構わなかったのだが、やめておく。最後の一皿を取ろうと手が伸びる。掴んだそれは、サイドメニューのチョコレートケーキだった。――甘いのは得意じゃないけど、やっぱり欲しいもんは欲しいよな。ぱくりと頬張る。これが透子さんから貰えたチョコだったらよかったのに。*休憩時間は残すところ20分。バックヤードへ戻る途中、バレンタインの特設コーナーが視界に入った。レジには青柳と柾が入っていた。当日に買い求める客は列をなし、忙しそうだった。あの2人も沢山貰ってそうだが実際のところはどうなのだろうと考え、いや、バレンタインは個数ではないと思い直す。それに、そういう考えは、自分にくれた人に対して失礼に当たるのではないか。チョコに込めた想いをもう少し大切に扱わねば、と思った。――そうだ、チョコは想いなんだ。透子さんが抱く、伊神さんへの想い。透子さんが抱く、ソマ先輩への想い。そこに込められた想いの形というのは、感謝であったり、愛情であったり、友情であったり。さまざまなれど、どれも尊き感情だ。――『チョコが貰えない理由』というのもあるんだ。透子さんが抱く、僕への想い。想いが何もなければ、渡す理由もない。実に単純明快だ。貰えなかったというのは、つまりそういうことなのだろう……。トドメを自分で刺し、切なくなりながらもバックヤードへ戻る。ドライの詰め所へ行き、エプロンを着けていると、ノック音がした。「はーい」後ろ手にリボンを結び、廊下にいるであろう人物を出迎える。立っていたのは透子だった。「とーこさん!?」「な、何よ。何でそんなに険しい顔してんの?」犬君の形相を目にした透子は半歩ほど後ずさる。思わず期待してしまう。でも、既に二度も打ち砕かれている。これは三度目の正直? いや、そんな馬鹿な。「え……と、青柳チーフに用とか?」「青柳チーフ? 私が用あるのはあんただけど」「よ、用って……」「こないだ入力頼んできたアレ。拡大コピーしてって言ったのに通常コピーして千早さんに渡したでしょ。数字が小さくて見辛いのよ。私がやり直すから原本渡してくれない?」「はぁ……」「ちょっと。人の話聞いてる?」「聞いてます。聞いてますよ、はいはい」言われた通り、入力に必要な書類一式を渡す。受け取った透子が中身を確認する。犬君はいても立ってもいられず、「透子さん」と名を呼ぶ。「なに?」「今日はバレンタインですけど」「そうね」「僕にはないんですか?」ページを繰っていた透子の手がぴたりと止まる。「ないって、チョコのこと? 欲しいの?」マジマジと見つめる透子に対し、犬君はプライドをかなぐり捨て、真剣な面持ちできっぱりと言う。「透子さんの本命チョコが欲しいです」「本命って……。職場でそんなことさらっと言えるの、あんたや柾チーフぐらいでしょうね」「僕まだ休憩中ですから」「いや、そういう問題じゃなくてね……。あ、休憩中なの?」「えぇ。1時半まで」「ふぅん」よくよく見ると、透子の胸にも休憩バッジが付いていた。傍らにバッグが置いてあるところをみると、ここへは食堂へ向かうついでに寄ったのだろう。透子はそのバッグに書類を収め、左右を見渡し人がいないのを確認すると、小さな袋を取り出した。「ハッピーバレンタイン、不破犬君」「え……」いつものツンデレ口調じゃない。透子が伊神に話し掛けている時のような、優しく、元気な笑顔だ。こんな表情で、こんな仕草で話しかけてくれること自体、稀である。しかも今日はバレンタインデー。これは夢だろうかとさえ思ってしまう。犬君の動揺を知ってか知らずか――否、完全に知り得ないだろう。透子は自然な笑みを浮かべながら先を続ける。「私のチョコ欲しいって言ってくれて嬉しかった。ありがと」「……っ……!」「私、これから休憩だから。じゃあね。あ、原本はコピーが終わり次第返すわ」本命ですか? 義理ですか? このチョコには透子さんの、どんな想いが込められてるんです?訊きたい。でも今は幸せで胸がいっぱいで、何も言葉が出て来ない。でもせめて。そう、そうだ、お礼だけでも。「あのっ! 透子さん、ありがとうございますっ!」「ホワイトデー期待してるから。3倍ね、3倍」「3倍でいいんですか? 5倍にも10倍にもしますよ」「重いわよ、馬鹿」言いながら、くすくすと笑う透子を見送ったあと、紙袋を見た。そして中身を取り出す。杣庄に渡したものとは全く別物のようだ。漆黒の紙袋でもなければ、漆黒の箱でもない。自分に渡されたのは、真っ赤な紙袋に、真っ赤な箱。大きさは手の平ぐらい。だが、高さは10cmほど。渡す相手によって、買う店を変えているとしか思えない。それはつまり、1人1人の相手を想い浮かべながら、その人物に合った品を選び、贈っているということに他ならないではないか。透子から真意は聞き出せなかったものの、犬君にはなんとなく、透子の想いが伝わってきたような気がした。2013.02.132020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Double Happy!】
日常編 (―) 【Double Happy!】「つ」それはきちんと発音したものではなく、たんに歯の隙間、口から零れ落ちただけの「つ」だった。その「つ」という音が出てから4秒ないし5秒後に、麻生の唇からその続きとなる言葉が吐き出された。「かれた~……」机に突っ伏す麻生だが、スタミナはある方だ。その麻生を疲れさせるほどの激務だった。1月1日、新年早々の初売りである。「……お疲れ様です、麻生さん」労いながら真横に座ったのは、同じ時間に上がった歴だ。とは言え歴の生気も麻生同様抜け切っている。束ねた髪は所々ほつれており、芙蓉が見たら卒倒するか悲鳴をあげるかのどちらかだろう。それを直すのも今は億劫な状態だ。「元旦って、こんなに激務でしたっけ」誰に尋ねたわけでもないその質問に答えたのは、質問者である歴の正面に座った柾だ。配膳された水を煽り、疲れた声で「いや」と前置きしてから続ける。「慣れないイベントをこなした所為だろうな。通常業務の他に違うことをしたから疲弊したんだと思う」……ですよね、と歴は頷いた。「やっぱり、そうですよね。それが大きな原因ですよね」「明らかに人員配分間違ってるぞ。本部からの応援はどうしたんだ? 俺はそれが気になって仕方がなかった」「開始5分の時点で気付くべきだったな。応援者などいないということに」「開始直後に悟ってたさ。だがな、希望というものがあるだろ? パンドラの箱的な」「麻生の口からギリシャ神話が出て来るとは思わなかった」2人が軽口の応酬を繰り広げている間にカフェの店員が注文を取りに来て、歴は3人分の料理を頼む。早番出勤に加え、元旦ということでいつもより2時間ほど閉店時間が早い。そのため歴たち3人も16時に上がれたのだが、何せ麻生がボヤきたくなる程度には身体を酷使してしまっている。それでも柾と麻生のやり取りは、どこか漫才めいていて、歴としては耳に心地いい。2人の会話に耳を傾けていた歴だったが、ふと視界に入った場面が目を惹いた。それはいま3人がいるカフェの真正面、絵画を売っているテナント。店の一等地には『風水』『金運上昇』と書かれたPOPカードの傍に、やたらと黄色が目立つ絵が額縁に入れられ並んでいた。値段は小さいもので2千円、大きいもので5千円から1万円だ。「どうした、ちぃ」その店に注がれていた歴の視線に気付いた麻生は、何がそんなに気になるのかと店を注視した。そこには黄色い花の絵があるだけで他に目立った特徴はなく、だからこそ解せずにいる。「さきほど1万円の絵を買われたお客様がいたんです。風水の絵の購入者はクジが引けるらしく、その方は見事に缶ビールのケースを当てました」「ふぅん?」尚更解せない麻生である。缶ビールのケースがどうしたと言うのだろう。まさか欲しいわけではあるまい。その心を読んだかのように、歴は言った。「その次のお客様は2千円の絵を買ったんです。またも当選し、2kgのお米を持って行かれました」「ビールと米が欲しいのか、ちぃ」「千早さんが言いたいのはそういうことではないと思うが」切れ長の目を画廊に向けながら柾。柾には既にある程度の予測がついたのか、新たに訪れた客と、接客している店員を注目し、答え合わせの段階に入っているようだ。「駄目だ、頭が働かねぇ……」疲労が呼んだのか、眠気が襲いかかる。そんな厳しい状況で柾ばりの推理など出来ようはずもない。「凄い話術だな。ものの数分で1万円をお買い上げ、だ。正月は羽振りがいいとは言え、これは見事」「あ、クジを引きます」「当たるぞ」柾の予想は的中した。老夫婦が引き当てたのは味噌汁の詰め合わせだった。「何かしら当たるんだな」くぁ、と欠伸をした麻生の何気ない感想に、柾と歴は顔を見合わせた。「頭が働いていない割には綺麗な解を出してみせたな」「凄いです、麻生さん!」「……あ?」「やっぱりそういう手口だったんですね」「……おい、ちょっと待て。解だの手口だの何の話だ?」もう少しで引っ付きそうな瞼をむりやり開け、麻生は2人に説明を求めた。「何だ、全部お見通しだと思ったのにちっとも気付いてないじゃないか」「だから何の話だ」「『黄色いアイテムで金運上昇間違いなし』という謳い文句を、店側があの場で実践してるんだ」そこでやっと気付いた。2人が何を訝しんでいたか……に。ポスターには各当選アイテムの他に数も記載されていた。当然『外れ』も存在しており、本数的には外れが1番多い。それなのに絵を買い求めた者がクジを引くと、誰しもが何かしら当選する仕組みになっている。まるで外れなど始めから存在しないかのように。「当選者数を水増しして裁判沙汰になった事件があったが……この場合はどうなるんだ?」首を傾げた麻生に、「正月だ。野暮なことは言いっこなしだ」きっと金額の中に当選アイテム代も含まれているんだろう、だの、それに何の罪に問えるというのか、だの。挙句の果てに、そもそも外れがないというのも予測の域を出ない、などと、自らの推理を真っ向から否定する言葉さえ生まれる始末。来たれ平穏、お疲れ自分。もう何も考えたくはない。とにかく疲れた……。3人は目の前で繰り広げられている珍事を都合良く解釈するに留めた。「あ、飲み物が来ました」「ちぃが頼んだいちじくタルトも来たぜ」「それ、私ではなく柾さん用なんです。お誕生日おめでとうございます、柾さん」「ありがとう」「おめっと、柾。んじゃ、紅茶とコーヒーだが……乾杯」「乾杯」「今日も1日お疲れ様でした。今年も1年、宜しくお願いしますっ」2014.01.012020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Help Me!】
日常編 (―) 【Help Me!】ドライ食品を担当している社員たちは焦っていた。「千早ちゃん! お願いしますっ! どうかこの通り!」手を合わせて必死に懇願しているのは、ユナイソンネオナゴヤ店ドライ売場の女性社員、志貴迦琳。遠目から見た様子では、従業員通路を往来する者たちに片っ端から声を掛けていたようだった。歴もその対象者のようで、目が合うなり擦り寄って来たかと思えば、深々と頭を下げられた。「志貴先輩、分かりましたから顔を上げて下さい」勤続年数は迦琳の方が上なのに、後輩相手にお辞儀をさせてしまっているのが後ろめたくて、歴はおろおろと迦琳の肩に手を回す。「歴、どうしたんだ?」背後から声を掛けてきたのは彼女の兄の凪。歴は自然と安堵の面持ちになる。「兄さんも知ってるでしょう? 今年のクリスマスケーキの販売数が伸び悩んでいるのを。従業員販売で数を稼ぎたいらしくて」予約開始直後に2個予約していた。これ以上買っても食べきれないだろう。でも……。歴が訴える目で見ると、凪は微笑んだ。そんな兄の決断が好ましくて……嬉しくて、釣られて笑顔になる。「いいよ、買おう。ホテルのケーキは残ってる?」「あ、残ってます! 2番と4番、9番と……17番のケーキでしたら」「フルーツタルトが美味しそうだ。9番と――どうする?」「私は4番の、食用花入りのケーキ」「2個もいいんですか? 私が言うのも変ですけど、千早さんには既に2個予約を入れて貰ってるし、追加分は1つで十分ですよ?」心配げに尋ねる迦琳に、凪は「平気平気」と軽い返事。「歴、鬼無里三姉妹に持って行こうな」「ひどいわ兄さん。ついこの間、因香さんが決意したばかりじゃない。『ダイエットを始めた』って」「クリスマスなんだから無礼講さ。今から愉しみだなぁ。ヒステリックに叫ぶ因香さんの顔」「私はてっきり、困っている志貴先輩を助けたいがために追加を申し出たとばかり……。まさか、そんなよこしまな思惑を抱いていたなんて」「どんな理由だろうと、数が捌けて志貴さんは大助かり。俺は鬼無里三姉妹に積もり積もった長年の鬱憤が晴らせてラッキー。誰も困らない」「因香さんたちが可哀想です」「それとも、お前が全部食べるか?」「それは……。出来れば私もケーキの過剰摂取は避けたいけれど……」「じゃあ決まりだな」「! や、やっぱりやめましょうよ、兄さん! あとが怖いわ。私達だけで食べましょう!?」千早兄妹が言い争う中、迦琳は注文書に数を記した。『4番・9番、業務課千早様』。「ほんとにありがとっ」スッと差し出されるお客様控えの紙。歴は複雑な思いでそれを受け取るのだった。*杣庄の機嫌は悪い。買いたくもないケーキを、これまた買いたくもない犬君から買うことになってしまったからだ。「八女先輩に『受取日に関しては杣庄に訊いて頂戴』って言われたから来たのに、思いっきり敬遠ムードですね。それで、いつにします?」犬君の手には、芙蓉からオーダーされた分の注文書があった。杣庄は魚を裁いていた手を休めると、手袋を取り、その紙を奪い取る。「1番? おいおい、八女サンは何考えてンだ? 何でこんな高いケーキを買う必要があるんだよ」「あ。1番を勧めたのは僕です」「てめ……! ナニ勝手に吹き込んでやがる!」「いまさら変更なんてしないですよねー? ソマ先輩の度量が試されますもんねー?」にこにこと笑顔を浮かべながらも、その言葉には毒がたっぷり仕込まれていた。杣庄は舌打ちすると、「変更はしねぇよ」と吐き捨てる。「受取日はどうします? デートは何日ですか?」「……ほぅ、いい度胸だなぁ? 何日から受け取れるんだ?」「23日から25日です。24日のイブにしておきましょうか。僕って優しい上に気が利くなぁ」「そうだと思ったぜ……! いいか、耳の穴かっぽじってよ~く聴けよ?」前置きをすると、他の者ならビクつきかねない大声を杣庄はあげた。「くそ忙しい書き入れ時に、デートなんざ出来るかー!」その一部始終を、書類を届けに来ていた透子が見ていた。「どこまでも杣庄を怒らせるのが得意よね」そんな透子に向かい、犬君は言う。「とても残念です」「は? いきなり何の話?」「24日が休めないのは僕もなんです。透子さん、25日は休みを入れておいて下さいね。24日は仕事が終わり次第迎えに行きますから」「……ニジューゴニチもシゴトしてろォ!」透子と杣庄の声が重なる中、犬君はお客様控えの紙にペンを走らせるのだった。*「十御、頼む! この通り!」「あんたも懲りないわねー。伊神はケーキなんて要らないって言ってるじゃない」「芙蓉は黙ってて欲しい。俺は十御に言ってるんだ」当事者が無言のままでは忍びない――。伊神は言い合う同期たちの会話を遮った。「幹久、八女さんはオレを心配してくれてるんだから、そんな言い方しないで。それと、オレが断われないばかりに迷惑かけてゴメン、八女さん。ケーキ屋のを既に頼んでるからもう注文出来ないんだ。ごめん。でもサイズが小さければ……」「いや、売れ残ってるのはどれもホールケーキなんだ。悪いな」青柳と伊神は申し訳なさそうに詫び合う。そんな2人を、芙蓉は冷めた目で見つめた。「そういう青柳はいくつ買ったの? 他人に買わせて自分は買わないなんて言ったら、かなりの顰蹙モノよ?」「3個買わせて頂いたよ。幸いにも妹がいるからな。でも、これが限界だ。因みに、志貴と不破は2個ずつ」「わんちゃんから聞いたわ。それにしても、あなたたちも大変ねぇ……。そうだ、柾さんと麻生さんに声を掛けたら?」名案とばかりにはしゃぐ芙蓉をよそに、青柳は渋い顔を作った。「俺が、あのお2人に質問出来ると思うか? 恋人と一流ホテルで食事をしつつ、パティシエ特製のケーキを食べてそうなのに」「読みが浅いわね。それは絶対にナイと思うわ」――だって、千早歴にそんな予定は入っていないんだもの。その芙蓉の読みは、見事に当たっていた。*「一流ホテルで食事をしつつ、パティシエ特製のケーキを頬張る? そんな過ごし方をしたのは何年前の話だったかな」溜息混じりに現状を嘆く柾に対し、即答したのは麻生だった。「ちぃに本気になる前まで、だろ? お前のことだから、相手は毎年違ったんだろうな」「もう覚えてない」棘棘しい麻生にげんなりした様子の柾。話題を逸らすため、犬君に向き直る。「麻生はケーキにトラウマがあるからパスするそうだ」「悪いなー、不破」「いいえ。……妹さんのケーキバイキングの時の後遺症ですよね?」「あぁ、まぁな……」「不破。千早は何個買ってる?」「4個です」麻生はその数に目を見張り、柾もきょとんとした。すかさず補足を入れた。「凪さんが、従姉妹である鬼無里三姉妹に差し入れするんだそうです」「なるほど」「……僕と彼女でせいぜいホール1個……いや、多いか」「ってお前、ちぃと過ごす気かよ?」「何を言ってる? 僕には『彼女と過ごす』という一択しかないんだが?」「はははーおめでたいなー。一体どんな脳の構造をしてるんだろうなー」「僕も柾さんを見習うべきですね。透子さんと過ごす。選択肢はコレ1本」――残念だったわね。クリスマスは千早さんたちと女子会よ。つい先ほど突き付けられた現実――透子の予定――など、忘れることにしよう。「……こうなったら、強引に捻じ込んでやる」思わず漏れた呟きに、「何が?」と麻生。「何を?」と柾。「いえ、こちらの話です。ご協力、ありがとうございました!」甘い甘いクリスマスケーキ。果たして甘いクリスマスを過ごせるのは……。一体、何人?2010.12.25 2020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (邑) 【Brother Complex!】
日常編 (邑) 【Brother Complex!】「大体あんたは理想が高すぎるのよ」一切の遠慮なし。思いっきり苦々しい顔で、悪友の千鳥はシェーク片手に私を睨んだ。「そんなことない」「大アリ。あんたにはイケメンな兄貴がいるから、他の男性と無意識の内に比較してしちゃってるのよ」「そんなこと……ない」2度目の否定は、心なしか声のボリュームが下がっていた。「そんなんじゃ彼氏なんて到底ムリだねムリ。クリスマスが近いからって、嘆くのはおやめ。そういうのは、ブラコンから卒業してから言うもんだ」ズズーっと、みっともない音を出しながらシェークを飲み干す千鳥。態度も口も悪い。でも彼女の言うことだけは正しいから、私は「むぅ……」とむくれるしかない。「そうだ、最近彼女と別れてロンリーな男友達が1人いるのよ。邑、会ってみない?」「えー?」「ほらそれ。そういう態度。それがダメなんだってば。どうしてそこで可能性を生もうとしないかなー?」「だって……」「そりゃ、あんたは中高と女子校に通ってたから、男に対して免疫がないっていうか、苦手なんだろうけど。いつまでもお兄ちゃんに守って貰ってちゃ不味いって」「……。やっぱりやだ。乗り気になれない」「でもさっき、店から出てったカップルを見て、羨んでたじゃんよー?」「それはそれ、これはこれ」「これじゃあ先が思いやられるわねー。いっそ、お兄さんからいい人紹介して貰ったら?」「お兄ちゃんから?」「交友関係が幅広そうじゃん。それに、お兄さんのお墨付きだったら、邑だって安心でしょ?」「……どうかなー」「今日の課題。『お兄ちゃん、誰かいい友達いない?』って聞くこと。いい?」「よくない。何言ってんのよ千鳥」「……今年も一緒に過ごすか、ロンリークリスマス」「その言い方やめてよー。私は千鳥と過ごせて嬉しいんだからさー」「ハイハイ。じゃあ、邑に美味しいケーキを作って貰おうかね。私はワイン用意するからさ」「承った」「うし、じゃあ帰ろうか。明日から憂鬱な月曜が始まるし」「だね」立ち上がりかけた時、スマホがメロディーを奏でた。「お兄ちゃんからだ……」「なんだって?」「今度遊園地行かないかって」「……ダメだ。あんた絶対、結婚出来ないわ……」「私もそんな気がしてきた……」「お兄さんに恋人がいないのも原因の1つかもね。私、立候補しようかな」「千鳥が私の義姉になるの? 冗談やめてよー」「え? 普通にいい案だと思うんだけどなー」そんな他愛ない会話で、今日も1日が終わる。マフラーを巻いて外に出れば、今年最初の雪がちらついていた。2020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (潮) 【Don't Apologize!】
日常編 (潮) 【Don't Apologize!】「お姉ちゃん、これあげるよ」たった1つの気紛れから起こった、小さな事件。*「それ……」八女先輩が、目敏く私の小指を捕える。「見せて」咄嗟に隠そうとしたのに、逆に引っ張られてしまい、白日のもとに曝されることになってしまった左手の小指。そこに光る銀の輪を、八女先輩はしげしげと注視する。「ピンキーリングね。シンプルなデザインで、素敵じゃない」会社の服装規定では、指輪は『幅が細いもの、石が付いていないもの』ならば1つだけ身につけてもいいことになっていた。はめる指に関しては特に書かれていないため、小指でも大丈夫だと勝手な解釈をする従業員は少なくない。かくいう私も、会社では、今日がピンキーリングデビュー。先日、なんの気紛れか、妹の那漣が私の分も買って来てくれたのだ。普段はそんな片鱗を見せないため、柄にもなく胸を打たれてしまった。とは言え「まぁ、安かったからね」。その一言は、余分だったわよ。「でもこれサイズが少し大きくて。気を付けなきゃいつか落としそうで困……」右手で素っぽ抜いた瞬間、「あっ!?」と叫んでしまった。やばい。咄嗟にそう悟って青ざめる。飛ばした。私、どこかへ指輪を飛ばしてしまった!「潮、不用心よ? 全く……」呆れた八女先輩がきょろきょろと床を見渡す。私もそれに倣う。先輩より腰をかがめ、照明によって輝きを放っていて欲しいと願いながら。「どこへ行ったのかしら。大丈夫よ。この部屋にあることだけは確かなんだから」確かにそれは心強かった。POSルームの中にある。それだけは確実で、隈なく探せばいつか見付かる。単に時間の問題だけのはずだった。「失礼します」入って来たのは不破犬君だった。仕事の依頼だったに違いない。でも、私と八女先輩が床下を見ているので、自分で操作した方が早いと判断したようだ。特に声を掛けることもなく、パソコンを操作し始めた。八女先輩は来訪者にはお構いなしに、プリンタの棚下に潜り始めていた。「おかしいわね。左から右へ飛ばしたんだから、絶対こっちの方にあるはずよね?」私の立ち位置から、そう判断したのだろう。「あの指輪、伊神からの贈り物?」血の気が引くとはこのことか。不破犬君にバッチリ聴こえてしまった。指輪、伊神、贈り物。この3つの単語と私たちの体勢が、全てを物語っていると言っても過言ではない。彼には全て把握出来たことだろう。「違います」の言葉より、不破犬君の退室の方が早かった。結局最初から最後まで何も言わず、素っ気なさを通り越し、無視を決め込む形で。いいもん。別に私、弁解がしたいわけじゃない。どう誤解されようと、別に。社内旅行以来、不破犬君は私を避けるようになった。それは勤務時間に如実となって表れていた。わざとかと思えるぐらい擦れ違う。私が休めば出勤し、私が出勤すれば休む。1週間の内に2日は休みを確保しなければならないので、そうなると出勤日が重なる日は週に3日なのだが。私が早朝出勤だと遅出出勤、私が遅出出勤だと早出出勤などと、笑えるぐらい真逆なのだった。あれは絶対、私の勤務計画表を見てるに違いない。そうでなければここまで重ならないなんておかしいではないか。誰かに言えば、「気の所為だ」とか「気にし過ぎだ」などと切り返されかねないので黙っているが、心の中ではそんな疑念が燻り続けていた。そもそもそんな瑣末なことが気に掛かるなんて、私こそどうかしてる。めちゃくちゃ気になってるっぽいじゃない。そんなの絶対ありえない!「潮?」八女先輩が不審そうに私を見ていた。あぁ、なんだっけ? 何か問われていたような気がする。えぇと……。「あぁ……違いますよ! あの指輪は、妹から貰ったんです。一応お揃いってことで」てっきり薄い反応になるものだと思っていた。なぁんだ、伊神じゃないの、と落胆でもするかのような。けれど、八女先輩は言ったのだ。「なら、なおさら見付けないと!」と。「えぇ? でも、妹からですし……」「だからこそ大切なんじゃない! 私は素直に羨ましいわよ」八女先輩は一人っ子。兄弟姉妹への憧れは、人一倍強いのかもしれないと合点がいった。ところが仕事の合間を見付けて探したものの、結局その日は見付からなかった。帰り際、「明日になれば清掃員が見付けてくれるかもしれないわ」と八女先輩が励ますように言ってくれた。帰宅の途につき、エントランスに設置されたポストを開けると、空の空間を予想していたのに、小さな包みだけが入っていた。新手のダイレクトメールだろうかと思いつつ手に取るも、見覚えのある包装紙はユナイソンのもの。簡素なラッピングを解くと、中から出て来たのはなんと、私が失くしたピンキーリングだった。指にはめてみると、ややぶかぶかな具合も、デザインも、紛れもない私のものである。慌てて包装紙を引っ繰り返したりしたけれど、特に何も記されてはいない。それでも差出人にはピンと来た。不破犬君しかいないではないか!一体いつの間に見付けたんだろう? そもそもどこに落ちていたのか……。あの場で教えてくれなかったのは、私を避けていたからだろうかと思うと、微かに心がざわめいた。このままでは、弁解もさせて貰えない。お礼すら言わせて貰えない。指輪の送り主が伊神さんからだと誤解されたままだし、借りだけが残ってしまう形になってしまう。私はその場で考えあぐね――やがて包装紙を綺麗に広げると、『ありがとう! 妹からのプレゼントだったから、助かりました』と書き記した。それを不破犬君のポストに投函する。明日になれば気付いて貰えるだろう。……一体なにをやっているんだろう、私は。どうしてこんな、まだるっこしいやり取りをしているのか。とはいえ、自分が蒔いた種なのだから、この事実をきちんと受け止めなければと言い聞かせ、私は天井のライトに指をかざした。指輪は一切の曇りもなく、光沢を放っている。それを見たら、なんとなく心が軽くなった気がした。2014.08.182020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Lovey-dovey Couple!】
日常編 (―) 【Lovey-dovey Couple!】折り込みチラシが入る日、開店前は修羅場と化す。POPの付け替えや値段確認を迫られ、ひとりひとりが与えられた任務をさばいていく。「ダメ! それまだ入力してないからPOP付け替えちゃダメよ」芙蓉の鋭い静止声を耳にした隣りの席の透子は、依頼人の手にある玉子パックに視線を巡らせると素早く報告した。「それなら私が昨日入力済みです。でも、カートに入ってるカニの缶詰、あれはまだ未入力」「では私が入れますね」歴が席を立ち、カニの缶詰を受け取ると着席した。パソコンのUSBに繋がっているバーコードスキャナでバーコードを読み取り、素早く値段を打ち込む。「はい、どうぞ」「ありがとう千早さん」これで無事、依頼人は次の作業であるテスト用レジの列に並ぶことが出来る。「ごめーん、これ値段抜いてくれない? 今日は300円で売りたいのー」「分かりました」新たな依頼を受け、再び席を立ったのは歴だ。しかし今度は着席したりせず、立ったまま入力する。室内が混んできたため、少しでも時間短縮をしたい。「ねぇ、パンってどうなってる?」芙蓉が尋ねる。「分からなかったJANコードが2つほど」そう答えた透子はいま、花の値段入力をしている。芙蓉は果物の入力、歴は野菜の入力。パソコンは3台ともフルに稼働しており、他の売り場のことまで気が配れないのが現状だ。「あと1分」と透子。「あと4分」と芙蓉。「あと2分です」と歴。つまり、いま抱えている作業が終わる時間の目安だ。「じゃあ私が行きます」透子が名乗りをあげ、宣言通り1分後にはPOSルームを退室していた。バックヤードを足早に抜け、観音式の扉を開ける。すぐ目の前のパンコーナーには、天井に届かん限りの高さまで積み上げられていたケース。品出し専用のパートが、累々と積み上げられたパンを必死に売台へ並べている最中だ。「新製品が未入力なので、パンを貸してもらえますか?」透子の問い掛けに、素早く品が集められた。2品ならばわざわざPOSルームに持って行かなくてもいいだろう。必要なJANコードを書き留めるためメモ帳を広げるが、「……そうだった」普段使っている小さなポケットサイズのメモ帳は、尽きそうになっていた。(昨日仕事帰りに文具売り場に寄るつもりが、すっかり忘れてたわ)それでも何とか隙間を確保し、書き付ける。(やっぱり無いと不便ね。今日こそ買って帰らないと)帰宅前にメモ帳を買うこと、と頭に叩き込み、踵を返す。その時、「透子さん!」と背後で声がした。振り返ると、犬君がこっちに来いとばかりに手招きしている。近付き、「なに?」と尋ねる。「これを108円で。こっちが238円、で、えーっと、あれを218円でお願いします」「108、238、218ね」もうメモ帳の隙間はない。商品が入ったカゴごと受け取ると、透子は身を翻そうとした。「不破君。これ、賞味期限が近いんだけど、どうする?」志貴が駆けて来た。「380円にしましょう。そっちは258円でいいですよね」「分かった」志貴は素直に頷くが、透子は溜息をつくしかない。覚えるものが増えてしまったではないか。「108、238、218、380、258ね」「そうです。頑張りますねー、透子さん」「じゃあね。今度こそ戻るわよ、私。これ以上構ってられない――」「潮さん、いいところに。これも追加してくれ」なんてことだ! 今度は青柳チーフの声がかぶさってしまった。「あぁ。それ、698円まで下げたんですけど、結局売れなかったんですよね」「アカでも良いからさっさと売ってしまえ。半額でもいい」「この際もっと下げちゃいましょうか。328円は?」「構わん。やっちまえ」「というわけで透子さん、328円でお願いします」「えーと。ということは、108、238、218、380、258、328ね。お願いだからこれ以上増やさないでよ?」釘をさしながら、そういえば、と透子は忌々しい事実を思い出していた。(仕事中に不破犬君の近くに寄ると、今日みたいに次々と容赦なく売価変更の依頼を頼まれてしまうんだっけ)ふと手に温かい感触を覚え、なにごと? と見やる。犬君が透子の手首をグイッと掴んでいた。「な、なに?」眉根を寄せる透子を余所に、犬君は透子の手のひらにペンを滑らせた。「あ、ちょっと! 勝手に何するの……ちょ、くすぐったい!」「動かないでくださいよ」「やだやだ、ちょ……もう! くすぐったいって言ってるでしょ!?」笑みを消し、本気で怒るも、犬君は飄々と受け流してしまう。「ははっ、これで大丈夫でしょう?」「あーっ! 油性ペンで書いたわね!?」「108、と……。よし」値段を書き込みながら、生命線が長いですねと余計な感想を呟いた犬君の頭を小突きたかったが、手が塞がっているため断念した。念入りに手入れした手に望まぬ書き込みをされ、透子は完全に不貞腐れていた。「デリカシーなさ過ぎ」そのひとことに、ペンが止まる。「そこまで書いたらどれだけ書いたって一緒よ。全部書いて」ヤケクソとばかりにてのひらを広げる。心なしか、犬君の数字が小さくなったのは気のせいだろうか。書き終え、ペンが離れ、かと思えばもう一度何かを書き足した。『ごめんなさい』(仕方ないわね)ペチ、と軽く犬君の頬を叩いた。「クッキー生地のシュークリームで手を打ってあげる」「了解です!」素直に頷いた犬君を見て満足したのか、透子はもう笑顔に戻っていた。2017.06.232020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (凪) 【Meow Meow!】
日常編 (凪) 【Meow Meow!】凪、黒猫、警報機、早朝の出来事。4:47am暗い、深い、淵。前方にチカリと光るものがあった。そこまで進み、何だろうと足を止め、しゃがみ込む。鈴。「にゃあ」どこかで猫が鳴いている。泣いている。4:48amちか、ちか、ちか。まだ光り続けている。今度は瞼の裏が、やけに眩しい。明滅するLEDライト――スマホ――着信?手を伸ばし、応答する。「もしもし」「アルゴス・セキュリティからの入電です。こちらは千早凪さんのお電話でしょうか」「……あぁ」警備会社からの電話? ネオナゴヤ店に何か遭ったのか。「4時43分、警報機が作動しました」「! すぐ行く」役職柄、夜中に不法侵入があった場合はただちに店まで駆け付けることになっていた。「店長にも連絡を入れたのですが、酒盛り後でアルコールが抜けず、タクシーで駆け付けるとのことでした」「店長はお嬢さんの結婚式に出席するため、昨日から神戸入りのはず」「えぇ。今からとんぼ返りで、こちらへ向かうと」「分かった」数分のやり取りをしたのち、今度は俺から店長に連絡を入れる。警備会社から連絡を受けたことで覚醒なさったようだが、眠たげな気配は電話越しに伝わってきていた。「今からこちらへ戻ると伺いましたが」「あぁ、3時間ぐらい掛かるかな。こんな時分では、始発もまだでね」「いえ、店長はそちらで待機を」「しかし、何かあってからでは遅いぞ」「一番早く到着できるのは私です。のちほど報告します。では」結婚式を誰よりも楽しみにしていたのは店長で、今日がその晴れ舞台なのだ。父不在の式では、娘さんが悲しむだろう。責任は俺が取る。どうせ、これ以上は下がりようのない地位だ。5:23amまだ明けてもいない時刻。建物の一番高いところから降り注ぐ、頼りなさげなサーチライトのシャワー。従業員入り口に向かうと、2人の警備員が待ち構えていた。俺とそんなに変わらない年齢に見える。「お疲れ様です。どこが作動したんですか?」「4階東側、犬走りです」「そんな細いところを? 侵入者はピーター・パーカーか?」「スパイダーマンかどうかはともかく、既に1人の警備員が現場へ向かっています」と警備員。入り口で1人待機せねばならず、もう1人は2階を廻ると言う。俺は現場急行組というわけか。警備員から警棒を借り、事務所内から該当する鍵をもぎ取った。先に駆け付けている警備員は、大方、立体駐車場から進んだ口だろう。俺は店内からだ。最短距離を割り出し、いざ目的地へ。とは言え、店内は暗い。状況が状況なだけに不気味な店内を、全速力で突っ切る。未稼働のエスカレータを上り、4階東側へ到着。店内と、立体駐車場の境目の出入り口だった。「警備員さん」懐中電灯の光を頼りに駆け寄ると、こちらも俺と同じぐらいの年代の男性が振り返った。「あぁ、お疲れ様です。どうやら誤作動のようですよ」「誤作動ですか」「えぇ。猫のようです。さきほど鳴き声が聴こえました」「誰かが猫を連れて侵入した可能性は? 猫を囮にして、こっちを油断させるという」「100%ないとは言い切れませんが、それだと4階まで上る意味はあまりないんじゃないですか」彼の言い分には一理あった。東側に関しては3階も4階と同じ構造になっている。地上に近ければ近いほど、逃げるのは楽だろう。わざわざ4階を選ぶ必要などない……か。「ともかく、猫を捕獲しないとな」「猫なら、そこにいますよ。見て下さい」警備員が懐中電灯を僅かに移動させる。しかし、そこには何もない。「スポットライトの、もう少し先です。犬走りがね、途中で切れてるんですよ。行き止まりで。で、あいつ帰って来ないんです」なるほど。じかに猫を照らしては、脅えた拍子に逃げ出しかねない。30cmしか幅はないのだから、下手をすれば落下してしまう。その時、にゃあと猫が鳴いた。デジャ・ヴュ?その鳴き声は、夢の中で聴いた声に似ていた。まぁ、猫だしな。声なんて似たようなものか。「犬走りの長さは約20メートル。やれやれ、1階の売り場からキャットフードを持って来るべきか?」「警備員さん。俺の足元を照らしてくれないか」「え? この細いの、行くんですか?」「1階までなんて悠長なこと、してられないだろう。サポート頼む」どうせ暗いから分からないのだが、なるべく下は見ないように、1歩1歩を壁側に沿ってゆっくり歩く。にゃあ、と鳴いていた猫は、俺が近付いてきたのが不満なのか、威嚇するような鳴き声へと変わった。「あー、駄目駄目。動くなよ。落ちちまうぞ。ほら、おいで」猫はふーふーと低い呻き声。明らかに怖がっている。参ったな……。「ちちちー、ちちちー」舌を打ちながら、ゆっくり手を差し伸べる。鋭い痛みが走った。前足で引っ掻かれたようだ。手を引っ込めたのがいけなかった。バランスを崩し、尻餅をつく。危ない。下手をすれば落ちるのは自分の方だ。動悸を抑えつつ、再度手を伸ばす。またもや鋭い爪で手の甲を引っ掻かれたが、今度は耐え忍ぶ。「こっちだ、ほら。おいで」ふぎゃーと一段大きな声で鳴く。思わず近所迷惑になるのではとヒヤリとしたものの、地上から大分離れている。多分大丈夫だろう。「参ったな。猫の扱いなんて、したことないしな……」ペットショップへ行けば、いつも歴が瞳を輝かせてガラスにへばり付くように犬や猫を覗いていたっけ。もしかしたら歴なら扱いも巧いのかもな。「お前は歴に似てるな。俺を疎ましく思ってるんだろ。俺は、単に心配なんだよ」長期戦を覚悟して、だらんと腕を垂らす。すると、温もりが手に当たった。……擦り寄って来たのか!「よし、確保」そのまま抱えるが、抱き方がまずかったかもしれない。再びイヤイヤをするように暴れ出した。危ないから、じっとしてろ。慎重に元来た道を引き返す。「やりましたね!」「あぁ、なんとか」頬を伝う汗を手の甲で拭う。空はほんの少しだけ、明るくなっていた。6:22am警備員と一緒に店内を見回り、猫以外の侵入がなかったことを確認すると、俺は店長に連絡を入れた。猫による誤作動だと伝えると店長は安堵したようで、俺に何度も礼を言い、予定通り式に向かう手筈となった。猫の行く末は考えないようにした。可愛いからというだけで飼える代物ではない。しかるべき手順を踏む事になるだろう。取り敢えず、保健所が開くまでは警備員が預かるという話になった。時刻は6時をまわり、俺にとってはとても微妙な時間になってしまっていた。今日は早番で、出勤時刻は8時。あと1時間半ほどしかないが、このまま店に居続けても仕方がないし、何より身支度を整え直したかった。かと言って、マンションへの往復時間を考えると超過しかねない。スラックスからスマホを取り出し、歴に電話を掛ける。彼女はすぐに捕まった。「おはよう、歴」「おはよう。……どうしたの? こんな朝早く」「いや、ちょっと。それより、今からそっちへ行ってもいいか?」「今から? えぇ、構わないけれど……」「10分後に着く」歴の返事は待たず、着信を切る。電話口の向こうでしかめっ面をした歴の顔が浮かんだ。6:35amさすが社宅マンション。10分もあれば余裕で着いてしまう。呼び鈴を鳴らすと、ガチャリとドアが開き、歴が顔を覗かせた。「おはよう、兄さん。……どうしたの、その顔!?」「顔?」「その赤いの、血なの?」「血? いや、顔は引っ掛かれなかったはずだが」そう言えば、猫との格闘後に傷口で顔の汗を拭ってしまった。あの時に付いてしまったのだろう。手の甲をまじまじと見ると、歴が「それ……!」と慌てふためいた。「傷なの? ねぇ、どうしたの? 駄目よ、早く処置しないと!」手首を掴むなり、ぐいと室内に連れ込まれる。朝食の準備中だったのか、芳しい味噌汁の匂いが充満していた。「猫が店内に侵入して、警報機が誤作動を起こしたんだ。見付けたはいいが、これがなかなかの強敵でね」「事務所に救急箱があったでしょうに。どうして早急に処置しなかったの? 危険よ?」「幾つか手配している内に、つい疎かに……」そんな会話をやり取りしつつも、歴はてきぱきと脱脂綿やピンセット、消毒液などを用意している。「沁みるけど、我慢してね」申し訳なさそうに詫びる歴に「平気だ」と告げる。が、それは虚勢でしかなかった。患部に容赦なく消毒液が行き渡り、悶絶寸前の痛みが襲う。「悪いことは言わないわ。後で病院に行って、診て貰った方がいいと思う。傷が残ったら目もあてられないもの」「大袈裟だ」「兄さん! お願いだから、言うことを聞いて」拗ねた口調で咎めてはいるが、歴なりに心配してくれているのだろう。俺にはその言葉だけで十二分に嬉しいのだが。「分かったよ。どうせガーゼ諸々買い揃えなくてはいけないし、病院で出して貰えるなら有り難い」素直に折れたのが功を奏したのか、歴はホッと胸を撫で下ろして微笑んだ。「朝食まだでしょう? 待っててね、今用意するから」そうか、傷は利き手につけられてしまったか……。何重にも巻かれた仰々しい包帯に視線を落とす。やがて配膳された食器たちを見て、ある事実に気付いた。「食べられない」歴の巻き方では、箸はおろか、スプーンやフォークだって握れない。慣れない左手で格闘していると、歴が「兄さん……」と小さく天を仰ぐ真似をした。「しょうがないわね。はい、あーん」「…………」「た、食べてくれないと……困るんだけど……!」顔を真っ赤にして、スプーンをぷるぷると震わせている歴。……病院には、朝一番に行くことにしよう。早期完治させなければ。2013.05.272020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (凪) 【Jerk Around!】
日常編 (凪) 【Jerk Around!】「凪さんの恋愛失敗談を聞かせてください」その顔に無邪気な笑みを浮かべ、不破犬君は言った。「人の恥ずかしい過去をほじくるのか? いい趣味とは言えないな」「じゃあ、これは時効だなってヤツを1つ。それで手を打ちます」呆れた男だ。複数のネタを仕入れるつもりだったのか。「時効か……。よし、良いだろう。では1つだけ。もし君が一千万円を手に入れたらどうする?」突然突拍子のない質問を投げ掛けられた不破君は、怪訝にしながらも忠実に返事を寄越す。「貯金、保険、株、旅行、親孝行、募金、趣味、身の回りの物を揃え直す、透子さんとのデート資金。……ぐらいですか。内訳は考えてませんけど、まぁ半分以上は貯蓄の方向で」財形の見直しを1番に持ってくるあたり、実に彼らしい受け答えだと思った。そしてデートの相手を潮透子さんと決めているところも。「同じ質問を、昔されてね。『もし凪が一千万手に入れたらどうする?』って」「あぁ、訊ねた相手は元カノですか。それで、何て答えたんです?」「パーセンテージで答えてしまったんだ」「パーセントで? え、例えば貯金を50%とか、投資に20%とか?」「あぁ」「うわ、それを瞬時に答える凪さんがすごいですよ。相手の方、ビックリなさったでしょう」「面食ってたよ。でも、頭のいい子だった。気を取り直して耳を傾けてくれたんだ」「でも、それがどうして失敗しちゃったんですか?」「残の存在に気付いたんだ」「ザン? あぁ、残りですか。全て足しても100%にならなかったんですね」不破君の頭の回転もなかなかのものだ。俺は頷く。「あぁ、1%残ってた。彼女はミュウミュウの財布をおねだりしてきたよ。だけど、『妹にサマンサタバサのバッグを買うに決まっている』と言ってしまってね」今でも覚えてる。まずは呆けた顔をしていた。理解した瞬間、「はぁァ!?」と素っ頓狂な声をあげた彼女。お嬢様学校に通ってるという話だったけど、つい、本当かな? と疑ったのは、別れる数分前の話だ。久し振りに思い出して、なんだか笑えてきた。不破君も呆れた顔をしている。そしてこう言った。「凪さん、それは振られます」2013.05.052020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Russian Roulette!】
日常編 (―) 【Russian Roulette!】__歴side「やぁ、千早さん」柾さんの甘い声に、胃がきゅっと縮こまった感覚を覚える。心臓の音が自分でもハッキリと分かるぐらい大きく聴こえ始めた。どっくんどっくんと脈打つさま。耳まで赤くなっているに違いない。――神様、私、柾さんの声を聴いただけなのですがっ!最近気付いたことがある。柾さんは私を呼ぶ時、『さん』と『君』を使い分けているようなのだ。さん、の時は要注意。甘い罠が待っていることが多かった。まさか、今も私をからかいに?でも、でも、でも!今はお昼休みで食堂内とは言え、ここは職場です、柾さん!__柾side「は、はい」僕が呼び掛けると、ただ呼び掛けただけなのに警戒するような目つきで僕に視線を合わせてきた。お誂え向きに、隣りの席は空いていた。許可を乞うわけでもなく自然に陣取り、僕たちは見つめ合った。相変わらず、向こうの怯えっぷりは酷かったが。無言の応酬に耐えかねた彼女は、耳まで真っ赤にしながら弱音を上げた。「……柾さん、どうされたんですか?」第一ラウンド、あっさり勝利。ほんの少しの優越感。オイルが入った小瓶を取り出すと、千早さんの前に置いた。怪訝そうな瞳は今度、その青い瓶へと移動する。これは何? とその目が問うていた。「いい物を手にいれた。今度発売される、マッサージオイルのサンプルだ」「マッサージオイル、ですか。あまり使わないので、よく分からないのですけど……」「全身に使えるんだ。毎日パソコンに向かっての作業だし、疲れているだろう」すかさず彼女の左手を握った。一瞬、その手を引っ込める感覚があった。そうはさせまいと、僕は再び彼女の手を強く握りしめる。__歴side青い小瓶に吸い寄せられていた。柾さんはサンプルだと言ったけれど、その割にはラベルも可愛らしいデザインで、インテリアとしても充分通用したからだ。でもこういうの、どうやって使えばいいんだろう?芙蓉先輩が愛用していることは知ってる。先輩にこそお似合いの品じゃないかしら……。そうぼんやり考えていると、急に左手を柾さんの手が覆ってきた。私はビックリして手を引っ込めようとしたけれど、柾さんはより一層力を込めて、離そうとはしてくれない。「ま、柾さんっ」「してあげるよ」――やばいです! 何かするつもりです、この人っ!真っ赤になったばかりなのに、今度は血の気が引いたように真っ青になる私。うろたえ続ける私の横で、柾さんは器用に右手だけで小瓶の蓋を開けると、小瓶を逆さまにした。柾さんの手から私の手に向かって、黄金色のオイルがとろ~りと滴り落ちてくる。“する”って、もしかしてハンドマッサージ……?「……っ」オイルの冷たさと、柾さんの手の温もり。両極端な温度差は、次第に熱を帯びていく。柾さんの手の大きさと、男性特有の硬さに意識を持っていかれる。ついには右手も加わり、私の指の隙間や付け根、節々を揉みほぐし、引っ張り、掌のツボを押してくる。絶妙なテクニック。これって、これって、ううう、なんだかエッチなんですけど、柾さん~っ!__柾sideマッサージの行為に紛れ、恋人繋ぎをしたりして遊んでいるのは内緒の話だ。見ると、余裕がないのか、レキは空いている方の右手を口元に持っていき、声を漏らすまいと我慢していた。――いや、ちょっと待て。待ってくれ。その表情と仕草を、ここでするのか? ……反則だろう!これ以上は、僕の方の歯止めが利かなくなる。なんてことだ。僕は単に彼女の、恥じらう顔と態度が見たかった。それだけだった。恍惚めいた表情を導き出そうなんて、思ってもいなかった。そもそもガチガチにガードされた千早歴からそんな反応を引き出せるとは、想定外だったぐらいだ。それなのに。指で感応するのか?――くそ、やめてくれ。他にも試したくなる衝動を抑えるのに、こっちはこれから努力しなければいけないんだぞ。第2ラウンドは僕の負けだ。心の中で、はぁ、と溜息をつく。そもそも勝負していることすら、彼女は露ほどにも思っていないのだろう。それも癪なので、仕返ししてやりたくなった。彼女の耳に、顔を寄せる。「その反応。すごくセクシーだよ、千早さん」__歴sideマッサージの最中、ずっとずっと、心臓が破裂しそうだった。顔を背けるだけで精一杯。早く終わってと願うばかり。それなのに、柾さんはいつの間にか私の耳に顔を寄せて、こう囁いてきた。「その反応。すごくセクシーだよ、千早さん」開いた口が塞がらない。頭が真っ白で、何も言い返せない。柾さんは固まってしまった私に微笑むと、温かいお手拭きで丁寧に私の左手のオイルを拭い取ってくれた。「これでは、右手も差し出して、なんていうのは、土台ムリな注文かな?」意地悪く、クスリと笑われる。あぁ、今の私に、「そんなことないです!」と言って、右手を差し出す余裕があったら。そうすればもう、子供扱いされることもなくなるのに。いつもそう。柾さんには、何だか敗北感を抱いてばかり。「や……やめて下さい。右手もこんなことをされてしまったら、私、もう……どうにかなっちゃいそうです……!」千早歴、完全な白旗宣言だった。__柾side悔し紛れに囁いたものの、僕的にあれは殺し文句だった。『右手は無理だろう』とからかったのも、仕返しの内だった。これで少しは気が紛れた。そう思ったのに、またもや大きく覆された。「や……やめて下さい。右手もこんなことをされてしまったら、私、もう……どうにかなっちゃいそうです……!」「……」――超天然のファム・ファタル。僕の気持ちも知らないで。つくづく、ここが職場じゃなければよかったのにと思う。これ以上、悶々とした感情を抱かせないでくれ……。勝負は1勝2敗。柾直近、ここは素直に白旗をあげておくべきだろう。2013.03.142020.02.20 改稿※このあと凪に見付かり、柾がしこたま怒られたのは、また別のお話。
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Sunny Tower!】
日常編 (―) 【Sunny Tower!】時針が11を、分針が30を示したのを自らの腕時計で確認した柾は、顔をすいと上げた。眼前では部下であるコスメ&ビューティ部門のメンバーたちが、スタッフミーティングが始まるのを待っていた。前もって告知してあった時刻を迎えた。遅刻は認めない。柾は一番左に立つ者から順に、人数を数えていった。「一二三四五六七八九十百千卍(ひふみよいつむゆななやここのたりももちよろず)」「1人足りませんね」ネオナゴヤ店における柾の懐刀、三原江が、赤縁眼鏡のフレームをくい、と上げながら眉根を寄せる。「……ま、抜けた穴の正体は一目瞭然だがな。あいつには後で罰則を与えておく」そんな台詞を捨て置いてから、柾は「ミーティングを始める!」と宣言し、全員に向き直る。「制汗剤の売り上げが伸びて来ている。先月比102.4%。『コトポップ』次第で更に売り上げが見込めそうだ。今日明日中に着手するように。次、薬局関連。『スイッチOTC薬』新規入荷に伴い、在庫を気にしておくように。今年は昨年の異常気象によって、虫関連の……」「わあああん、柾さあああん」突然、粛々と進行していたミーティングをぶち壊す、なんとも間の抜けた声がバックヤードに木霊した。まるで子供がべそをかくような、思わず脱力を誘う大人のそれ。「どうしたー由利ちゃん」『由利』こそスタッフミーティングに遅刻した不届き者であり、後で柾によってお灸を据えられる事が決定している人物である。可愛らしい名前だが、『由利』というのは先祖代々、脈々と受け継がれてきた苗字であり、由利主税(ゆりちから)は、歴とした男だった。由利は言う。「お客様から『陽だまりの匂いとはどんな感じなのか』と尋ねられた由利は、上手く答える事が出来ませんでしたあああ」嘆きと共に、塔を模したオレンジの瓶が柾に差し出される。『Sunny Tower』とラベルに記載されているそれは、発売して間もない新作の香水だった。「由利主税、一生の不覚。つーか知るかよ陽だまりの匂いなんてさ。『それでも社員なの?』って、何で僕が馬鹿にされないといけないのさ。大体僕はコスメ担当の社員じゃなく、薬局勤務の薬剤師だし! 畑が違うんだよー。この白衣が見えないっての?」「売り場が近いから、その手の質問が多いのは分かるが――」ユナイソン規則。“尋ねられた質問には懇切丁寧に笑顔にて対応すべし”。だが由利の言う通り、陽だまりの匂いを言葉にするのはなかなか難しい。「テスターはなかったのか?」「そんなのなかったよー。あれば速攻渡したってー。メーカーもさ、箱に『陽だまりの匂い』なんて書くなよなー。表現が曖昧なんだよ全く」やれやれ、これではミーティングどころではないな。柾は逡巡したのち、解散を告げ、社員達を持ち場へ帰らせた。「由利、他にも曖昧な表記の香水はなかったか?」「5種類ぐらいあったかな。柾さん、できれば全部テスター作ってよ。僕もうあんな思いするのイヤだよ」由利は口こそ悪いものの、医学知識が豊富なので、自分を頼ってくれる患者の質問には『須く正当に答えるべし』をモットーにしている。そんな由利だからこそ、答えに窮するなど以ての外。主義に反するのだ。かくして同僚のSOSを聞き届けた柾の次の仕事が決まった。午後は香水のテスター作りに取り掛かる。調べた結果、テスターのない香水は10種類にも満たなかったが、中には匂いが断たれてしまったものもあったため、1から作り直すことにした。部下と手分けしてコットンに香水を滲み込ませていく。テスターが完成するたびに、由利は満足そうに頷くのだった。「『月の雫』。……そうかなぁ? まぁでも、そう言い切られちゃ仕方ないか。『星舞(ほしまい)』。……うへ、あんまり好きじゃないな」「由利、手が空いてるならテスターを並べて来てくれ」「はいはーい。……おっと」時刻は15時過ぎ。店内には小学生低学年の子供を連れた主婦の姿がちらほら目立ち始めていた。由利にぶつかったのは正にその小学生の1人で、後ろ歩きだった所を由利に気付かず(由利自身も視界に入っていなかった)つんのめってしまったようだ。「大丈夫かい?」少し目を丸くした由利は、2~3年生ぐらいの男子児童に尋ねる。「あ……ごめんなさい」男子はバツの悪そうな顔をし、隣りにいた母親も「何やってるの、だから危ないって言ったでしょ」と子供に叱りつつ、由利に頭を下げた。客とのトラブルには発展しなかったが、子供とぶつかった拍子に、由利の肘が柾の腕に当たったらしく、香水の瓶が手元を離れ、床に転げ落ちてしまった。テスター作りの最中だった為、蓋をしていなかったそれは、とっくとっくと小さな音を立てながら床に池を作っていく……。「わー! ごめんよ柾さん!」「いや、こんなのは別に、拭けばいいだけのことで……」気を利かせた三原が雑巾で床を拭き始めるが、不幸とは重なるもので、7センチのヒールがつるんと滑った。三原は尻餅をつき、その足が作業台にぶつかる。可動式の作業台は呆気なく揺れ、上に乗っていた香水が1つ、また1つと落下した。それは三原同様、床を拭き始めていた柾の背中に降り注ぐ。「あーあ……」痛ましいものを見るかのように、由利の顔が歪む。今度は柾の背中の上で香水が混じり合い、ぽたぽたと雫を垂らして行った。2つの香水を浴びてしまった柾は、仕事にならないので早退届を提出した。一時帰宅が望ましかったが、浴びた量は半端ない。例え風呂に入ったとしても、そう易々と匂いは落ちてなどくれないだろう。夕方4時。社宅マンションには人気がない。いつもの癖でエレベータの▲を押したが、今の状態で狭い箱になど入ろうものなら、匂いが染み付いてしまい、迷惑千万だと気付く。仕方なく階段を利用しようとした時だった。エレベータが1階に到着したらしく、中から麻生が出て来た。そう言えば、今日は休みだったか……。「柾。お前、今日は遅番だったよな? 何やってンだ?」最悪なタイミングに、思わず溜息が出てしまう。「うわ、くさっ!」案の定、近付いた麻生に嫌な顔をされてしまった。「なんなんだこれ? 何やらかしたんだよ、お前!」腕で鼻全体を覆う麻生に、柾は「仕事中に香水の瓶が割れた」と短く説明する。「金木犀テイストの『女神の微笑み』と、鈴蘭テイストの『堕天使の温情』だそうだ」「どんな綺麗な言葉を並べたって、ヘドロと一緒だ」割れた3本の香水。被害総額は15,120円。それなのに、言うに事欠いてヘドロとは。「どんな語彙も、お前には形無しだな、麻生」聞いたか? ヘドロだとさ。明日の朝になっても匂いが落ちてなかったら、由利のヤツ、覚えてろよ。「ミーティングに遅れた罰と併せて、とっちめてやる」2011.04.222020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Who Cares?】
日常編 (―) 【Who Cares?】__犬君side出勤途中。僕の前を歩く、透子さんの姿。高鳴る胸。同時に嬉しさと切なさが込み上げてくる。勇み足になってしまうのは、早く追い付きたいから。最終的には、小走りになっていたかもしれない。透子さんの肩を叩く。軽く、弾むように。「おはようございます、透子さん」「おはよう」僕とは全く逆のロー・テンションで、素っ気なく告げる透子さん。どうすれば彼女から笑顔の挨拶を引き出せるだろう?それとも、僕には到底ムリな願い?軽いショックを受けたけれど、隣りに並べた僥倖については素直に喜びたい。何も言わない透子さん。僕も敢えて、話題を生むつもりはなかった。居心地悪くさせてしまっているかな……? でも、それならそれで、彼女はこう言うハズに違いない。「この沈黙には耐えられないわ」って。__透子side挨拶を寄越したきり、不破犬君は何も言わない。なんなのよ……と思いながらも、朝から言い争うのも疲れそうだから、ただ黙々と歩いた。無言の2人。無言の登社。そんな沈黙の中で、自分の隣りから発せられる男物の靴音が気になって仕方ない。歩幅は、明らかに向こうの方が広い。今にも追い抜きかねないのに、横のラインは依然保たれたままだ。周りの人たちからは、私たちが仲睦まじく歩いているように見えているのだろうか?それにしたって、歪曲された事実ほど不本意なものはない。__犬君side透子さんと一緒だった所を平塚は見ていたらしく、冷やかし半分・やっかみ半分の言葉を僕に浴びせてきた。「別に会話はなかった」と言えば、「倦怠期の夫婦かよ!」と痛いものを見る目で労わられた。__透子side「わんちゃんと一緒に来たみたいね」私の隣りでナイスバディの下着姿を晒す八女先輩が、ハンガーから制服のスカートを外しながら言った。「まぁ……一緒は一緒でしたけど」「含みのある言い方ねぇ。つまり、一緒だったという事実のみを強調したいわけね」ワイン色で統一されたインナーたちが、制服によって覆われていく。勿体ないなぁと思っていたら、「じろじろ見ないで」と怒られた。はいはい、すみませんね。「早く着替えなさいよ? 今日は忙しい火曜日なんだから」そうだった。今日は開店直後の時間帯が二番目に混む、魔の火曜日。八女先輩が早番なのも、不破犬君が早番なのも、ひとえに今日が特売日だから。慌てて制服に袖を通す私。そして、髪を結い直す。朝からボーっとし過ぎてしまったことを嘆くのも、毎度のこと。低血圧だから仕方ない。……そんな根拠のない言い訳を心の中で呟き、いざ出勤。__犬君side誰にとっても、開店前の1時間は、店内とPOSルームを幾度となく往来する。この時ばかりは、さしもの僕も透子さんに見惚れているわけにはいかない。心を奪われれば、それが命取りにもなり得る。――というのは大袈裟か。ともかく、異常な繁盛を見せるだけに、売価ミスなどもってのほか。致命的で許されないのが火曜日の常である。それなのに――。「あれ……?」必死にパソコンを操作する透子さんの後ろ姿を見て、首を傾げた。それは、朝と雰囲気が違っていることに気付いたから。どこがどう変わってしまったんだろうと首を捻る。そうか、髪だ。私服の時は、細かいレースが特徴的な白の……なんて言うんだ? えーと、シュシュ?そう、シュシュで髪を結んでいた。でも今は、目立ちにくいタイプの黒ゴムでまとめられている。「透子さん、朝と髪留めが違うんですね」さり気なく言えば、「規定を守ってるだけよ」多忙な時に関係ない話をしないでと睨まれた。__犬君side「私、透子先輩ほど女性らしい方って、いないと思うんです」食堂の窓際。小さなテーブルを挟んだ2つの椅子。歴さんは食べ終えたサンドウィッチの折り畳み式小箱を片付けながら、優しい口調で言った。「……確かに僕は透子さんが好きです。好きですけど、どう考えても歴さんの方が断トツに女性らしいと思いますよ」僕の真正面で微笑み続ける歴さんは、有り難う御座いますと頬を染め、小さなお辞儀を返してくれた。素直で可愛くて、その上優しさに長けた後輩だ。「挨拶の件にしたって、無愛想じゃないですか。これが他の男なら、「何だこの女」って呆れてますよ」「でも不破さんは、そんな透子先輩しか見えていないじゃありませんか」「……それは……まぁ……」「ふふっ」楽しそうにニコニコと笑う歴さんは、自販機で買った紅茶を飲みながら、おもむろに自分の頭を指した。注目せよと言わんばかりに。長い髪を後ろで1つに束ねていた歴さんは、その髪留めをスッと解く。男子社員の間で『烏の濡羽色』と大評判の黒髪が、肩から背中にかけて散らばった。僕でさえ目を奪われたのだから、彼女に想いを馳せる男性が見たら、この場で抱き締めてしまいたい衝動に駆られてしまうかもしれない。それほどまでに今の仕草はヘアケアCMに採用されてもおかしくない名シーンだった。現に、後ろの席に座っていた男子社員は、髪を解いた瞬間に漂ったシャンプーの香りに気が付き、振り返ったほどである。「今から髪を結びます。何秒掛かると思いますか?」何を言い出すかと思えば……。見当もつかないが、1つに纏めて結ぶだけだから、20秒ぐらいだろうか。数字を告げると、歴さんは腕時計で確認するように言い、ポーチに入っていた柘植櫛で髪を梳き始めた。丁寧に櫛を入れ、左手に束を集めながら、器用に後れ毛の処理をする。「終わりました」と両手をスカートの上に戻した歴さんの髪は、先ほどと同じように綺麗に結ばれていた。「単純な結び方をした私でさえ、1分掛かりました」まるで種明かしをするかのように言い含める歴さん。「透子先輩は私より短いですけど、結構凝った髪型をしているんです。今日は裏編み込みをしつつ、片結びをしていました。これって3分は掛かると思うんですよ。1~2分で出来なくはないですけど、あそこまで綺麗に纏めるためには3分必要でしょうね」「……それで?」歴さんは、ここが重要だといわんばかりに身を乗り出した。「プライベートと仕事。シュシュと黒ゴムを付け替えるために1度解いている……。これって、意外と面倒で、手間だったりするんです。私なんか、本音を言えばそんな時間も惜しいぐらい。故に、『服装に合わせて髪留めを変えつつも面倒な髪型を繰り返す透子先輩は、誰よりも女性らしい』、と言いたいんです。まぁ、髪留めのゴムを変える際に、手でしっかりと髪の束を押さえていれば、結び直す手間も省けますけどね。透子先輩がそうやって手直ししている所は見たことがないので、やっぱり逐一始めから結び直してるんだと思いますよ」「それは……つまり、透子さんの女性らしい部分に惚れ直すべきだと?」「私が言わなくても、十分過ぎるぐらい心を動かされてしまったんじゃありませんか?」彼女の推理は正しい。事実、今すぐにでも透子さんに会いたくなってしまった僕である。「透子先輩を冷たい人だと誤解なさらないで下さいね。私、それだけが心配です」「大丈夫。ちゃんと知ってるから」本当に迷惑だったら、はっきり言うだろう。横に並んだ時も、本当にイヤだったらそう告げていただろうし、走り出すなどのアクションを起こしていたに違いないのだ。それは、僕の都合のいい解釈だろうか?でも、何年も見てきたんだ。ずっと。透子さんだけを。だから僕には分かる。好かれているかはギリギリのラインだとしても、少なくとも嫌われてはいないかな、って……ね。2010.12.202020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (―) 【Fallin' Love!】
日常編 (―) 【Fallin' Love!】1 : 犬君視点 社員食堂 PM1:09平塚鷲が恋をした。――らしい。「少女時代のメンバーにいてもおかしくない美脚の持ち主なんだぜ。美人だしさ、ある日突然紛れ込んでも違和感がないだろうって言う」言うに事欠いて少女時代を引き合いに出すとは。ファンをも恐れぬ、ゆゆしき所業だ。「どこで知り合ったって?」「お前全然人の話聞いてねーだろ。まだ知り合ってねーんだって。単なる俺の片想いなの。だからこうして相談してるのに、不破犬の馬鹿野郎ー!」「フワケン? また新しいあだ名が増えたなぁ、不破」「そこは別に感心して欲しい部分じゃないですからね、麻生さん!? 俺の恋バナ聴いてくださいよっ」「八女先輩やこいつが勝手に増やすんですよ」「不破も麻生さんも、俺の話ちゃんと聞いてくださいよー!」「だからさっきから何回も言ってるだろ? 俺は陰ながらの応援はするが動・か・な・い。つーか俺を巻・き・込・む・な」麻生さんは始終この調子で、平塚の恋バナから一線を画していた。読み広げていたビジネス誌『週刊ダイヤモンド』を顔の前に掲げ、我関せずの姿勢を貫く徹底ぶりだ。表紙にでかでかと記載された、『流通大激変! 「選ばれる店」の秘密』の文字が目に入る。何だか面白そうだ。あとで麻生さんから借りよう。他にも累々とビジネス誌が積み上げられていて、『解明! 安さプラスαで「売れる店」』や『労働組合の腐敗』などのバックナンバーもあった。それは分かるけど、『今年こそ取り戻したい! 男の健康』や『寺・墓・葬儀にかかるカネ』は何だろう。聞いちゃいけないような気もするが。平塚は平塚で、出社前に立ち寄ったコンビニで買って来た男性向け雑誌をパラパラと繰っている。そうしつつ、まだボヤいているのだ。器用なヤツ。「五十嵐さんに言ったら笑顔で『頑張れ』だし。何をどう頑張れって言うんだよ……。おっ、このグラビアアイドル、すっげ」ほらほら見てみーと僕にページを突き付ける。ベッドに横たわる、ガーターベルト着用の艶めかしい女性1人。「パス。透子さんに1票」「そーかよ。そりゃあ悪かったな」懲りもせず、平塚は今度、麻生さんにそのページを向けた。大先輩に向かって、何ともチャレンジャーな男だ。グラビアを見せる度胸があるなら、さっさと片想いの女性に告白でもなんでもすればいいだろうに。一方麻生さんはというと、その雑誌を受け取ると、平塚が提示した写真を眺めたのち、ページを捲った。そこにはあられもない女性の姿、姿、姿。やがて、とあるページで麻生さんの手が止まった。平塚のもとへ雑誌を滑らせる。「こっちの方が好みだ」「!」平塚は鼻を押さえる。まるで出掛かった鼻血が垂れてこないようにするためのジェスチャー。勿論血など流れていない。単なるポーズだ。そこには薄ピンク色のコルセットを纏った美少女がにっこりと微笑んでいた。胸の盛り上がり方が妙にエロい。腰のくびれ、太股に結んである黒のリボン。「素晴らしいチョイスです、麻生さん」と僕。「褒められても嬉しかねぇよ」再びビジネス誌を読み耽る麻生さんに、「この子、どことなく千早歴嬢に似てやしませんか?」と呟く平塚の声が聴こえたかどうかは定かではない。2 : 犬君視点 1階花屋専門店≪aurora rouge.≫ PM5:44「ほら、あの子あの子!」平塚は背を向けたまま、花屋の女性店員を指し示した。彼女の身体が“くの字”に曲げられているのは、鉢の陳列をし直しているからだ。「近付かないとよく分からないな」「客のフリして行って来てくれよ。ついでに名前と出勤時間、宜しく頼む!」前半の提案は魅力的。後半の提案は却下。女々しく隠れたがる平塚をその場に残すと、客として入店した。「いらっしゃいませ!」零れる笑顔、というのは言い過ぎかもしれないが、接客対応としては満点の挨拶だと思う。なるほど、平塚が好みそうなタイプだ。ゆるかわ、という表現でいいだろう。鎖骨まで伸びた髪をふんわりと巻いて、片結びしている。スカートが似合いそうなのにジーンズを穿いているのは、しゃがむ作業が多いためか。僕が花ではなく、彼女の顔をじっと見ていたからだろう。自分に質問したがっていると思われたようで、「お客様、もし宜しければ私が花を選ばせて頂きますが……?」と控え目に尋ねられる。「あぁ、じゃあ……お願いします。花は選び慣れていなくて」「分かりました。お手伝いさせて頂きます。プレゼント用ですか?」「えぇ。大好きで大好きで仕方ない女性に」真面目に答えたら、まじまじと見つめられ、ふふっと笑われた。「凄い! そんなに情熱的に想われているその人が羨ましい」「その人、僕を袖にするんです」またしても真面目に答えたら、今度は「あははっ」と笑われた。「あらまぁ! 小悪魔みたいな方ですねぇ。よーし、その人に振り向いて貰えるような花束、作っちゃうぞー」女性店員はくるりと方向転換すると、10分の時間を費やして3,000円の花束を作ってくれた。「紫で妖艶に纏めるよりも、女性の心をくすぐる色彩で勝負しました。黄色と迷ったんですけど……でもやっぱり赤やピンクですよね」自身は青系の服を着ているにも拘わらず、赤を褒めちぎる。女性の心は複雑怪奇だと思いつつ、僕は店を後にした。赤系統の色で纏められた、ガーベラ・バラ・ダリアたち。彼女の傑作品に羨望の眼差しを送りながら、平塚はもどかしげに言う。「彼女、なんていう名前だった!? 彼氏はいるのか!? 連絡先は!? シフトはどんな具合だって!?」あ。「悪い。素で忘れてた」3 : 杣庄視点 男子更衣室 AM8:58不破犬君は当てにならなかった――。不貞腐れた平塚は、ぶつぶつと不平不満を漏らす。それで、俺にどうしろって? 恋のアドバイス?「知ったこっちゃねぇな」「1秒と経たずに拒絶って!」「その手の質問をするからだ」「ソマ先輩しか頼れる人はいないんですよー!」「なんでだよ……」「実際に恋愛が上手く行ってる人に訊くのが一番だから!」その答えは聞き捨てならない。俺と八女サンがどういうバランスの上で恋愛を続けているのか、コイツは何も分かっちゃいないからだ。「俺は俺でお前はお前。俺の意見なんざ参考になりゃしねぇよ」「そんなことないッスよー! 八女芙蓉と言えば、ユナイソン高嶺の花の1人。その彼氏が、他ならぬソマ先輩なんですもんー」そりゃあまぁ、“芙蓉”は花の一種だけども。加えて霊峰富士の異称は“芙蓉の高嶺”と言うけども。「取り敢えず、顔見知りになりたいんですよねー。気さくに話せる仲になりたいんです」「花屋に通い詰めりゃいいだろ」「でも俺、今まで花に何の興味もなかったし。無知な俺が通う頻度だけ上げたって、そりゃ無謀ってもんでしょ!?」「適当に用事拵えりゃいい話じゃねぇか。誰かの見舞い用に、小さな花束こさえてくれだのなんだのってよ」「ソマ先輩!」「何だよ、うるせぇな」「結局頼りになってるじゃないですか! 俺、だからソマ先輩って大好き!」そこで気付く。いつしかアドバイスめいたやり取りをしていたことに。しくった腹いせに舌打ちが付いて出る。八つ当たりとばかりに荒々しくロッカーを閉めた。4 : 杣庄視点 1階花屋専門店≪aurora rouge.≫ PM0:17午前中にそんなやり取りがあったにも拘わらず、俺が平塚の想い人がいる花屋にいるにはわけがあった。11時半から取るはずだった昼休憩が若干ずれ込み、食堂に入ったのが11時50分。そこで俺の運命は狂った。平塚も食堂にいたのだ。俺を見付けるなりそそくさと擦り寄ると、俺がきつねうどんをつつく傍らで、ヤツはたぬきうどんを啜った。俺が箸を置くなり平塚はあっという間に2人分のトレーを返却口へ戻しに行き、次の瞬間には唖然としている俺の腕を掴み、ここへ連れて来た。言うなれば拉致である。「俺がいても仕方ねぇだろ? なに考えてんだ、お前は」予測不可能な行動を起こす平塚に振り回された俺は、ガシガシと己の髪を掻き乱す。どこまでも七面倒な奴め。「2人で入りましょうよ~」「馬鹿かお前は」耳を疑い、目を疑い、頭を疑った。だが確かに平塚は俺を誘ったのだ。懇願する目で訴えて。つまり、正気の沙汰なのだ。「大の男が2人で一緒に『お花屋さん』? ふざけんのも大概にしろ」「俺……しくじりたくないんですよー!」ついに俺は脱力し、掌で両目を覆った。出るのは深い溜息ばかり。一体なんなんだ、コイツは? こんな軟弱な男に恋をする資格があるのか?よくよく見れば、平塚は女が好みそうな顔をしている。実際、女性社員から可愛がられている場面にも遭遇したりする。確か数ヶ月前までは彼女だっていたはずだし、軟派な部分もあったりして、いわゆる肉食系の部類に入ると思っていたのだ。それが蓋を開けてみれば、この体たらく。草食系? いや、それにしては女性を求める気持ちが大きい気もするが……。「……あのな、平塚。無理に恋愛する必要はねぇんだ。不用意に傷を作る必要もねぇ。分かるか、俺の言ってること?」「無理にって何ですか? 俺、あの子を見てるとドキドキするんですよ。それって恋でしょ? だから別に、無理してるわけじゃないし!」「何をそんなに恐れてるんだ? そもそも、一気に距離を縮め過ぎようとしてる。果てしなく無謀だ」「そんなことないですよ!」「ある。現にお前は一気に彼女から情報を引き出そうとした。不破の野郎を使ってな。名前、連絡先、勤務時間、彼氏の有無。――違うだろ? 普通は「こんにちは」っつー挨拶からだろ。よっぽどのことがない限り、それら全ての情報を得るなんてムリな話だっつーの。何度か通った後で、1つ1つ訊いていけよな」俺の意見は平塚のお気には召さなかったらしい。今やヤツの口元は拗ねたようにへの字型に曲がっているし、目線だってそっぽを向いている。これ以上、俺の戯言は聴いていたくないという思いがありありと表れていた。「それに、俺がお前と一緒に中に入っていけない理由がもう1つある」声を若干落とした俺に、平塚は「何スか、理由って」とぶっきら棒に尋ねた。「今気付いたが、花屋に八女サンがいる。俺が中に入っても身動き1つ取れねぇよ。八女サンの前で他の女性のご機嫌窺いなんざありえねぇ」え? と花屋に視線を送る平塚。ユナイソンの制服姿のまま、冷ケースの中で切り花を探すのに夢中になっている、客としての八女芙蓉を確認したのだろう。悪事に手を染めようとしているわけでもないのに、後ろめたい意識があるのか、平塚はまたしても俺の腕を強靭な握力で掴むとその場から駆け出した。5 : 杣庄視点 バックヤード PM0:35平塚と俺はバックヤードへ戻った。残りの休憩時間はあと15分。どうやら今日は食後の珈琲にはありつけないらしい。「……俺だって恋がしたいんだ」「お前……」きっと、コイツにはコイツなりの事情があるんだろう。でなければ、ここまで追い詰められたりはしないんじゃないか。色んな“何か”が重なった揚句、今の暴走平塚を生んでしまった。俺が説得したところで、コイツは耳を傾けてくれるだろうか? いや、そんな保証はどこにもない。そもそも平塚が本当に俺を頼っているのか、それすらも怪しいというもんだ。俺は俺なりに考える。もし俺が平塚なら――本来の平塚だったなら――誰に相談するか、を。いた。いるじゃないか。打って付けの人物が。平塚の鼻を、ピンと指で弾き飛ばす。いてっと呻く平塚。「人選を誤んな、糞餓鬼その2」今度は俺がヤツの腕を掴み、引き摺り回す番だった。確か、探している人物も早番出勤のはずで、だとしたら何ヶ所か適当に走り回れば会えるに違いない。近い場所からあたろう。バックヤードをこのまま直進すれば第一候補のPOSルームを通過する。案の定と言うべきか、運がよかったと言うべきか。早速探し人を発見した。部屋に入るなり、俺は件の人の名前を呼んだ。「柾さん、すいません。ちょっと話があるんです」6 : 柾視点 POSルーム PM0:45POSルームには潮さんがいたので、彼女に商品の価格訂正を依頼したところだった。仕事に託けて千早歴との逢瀬を楽しみにしていたのだが、生憎と彼女は休みを取っていた。部屋には潮さんが操るマウスのクリック音と、緩やかなメロディーラインの店内BGMが流れていたが、その静かな空間に異音が混じった。武骨な手によって、ドアが乱暴に開け放たれる。「柾さん、すいません。ちょっと話があるんです」「柾さんは駄目ッスよ! 柾さんだけは!」「何が駄目なんだよ? どう考えたって柾さんしかいないだろ!?」「俺だって真っ先に考えましたよ! でも、かえって逆効果なんです、柾さんじゃ――」鮮魚担当の杣庄とバッグ売場担当の平塚だった。言い募る2人。柾、柾、柾。きっと僕のことなのだろう。だがハテ、2人は僕に何の用なのか――。「うっさい!」噛み付かんばかりの勢いで牙を剥いたのは誰あろう、潮透子嬢だった。八女芙蓉女総帥の元で4年も指導を受けていれば、男性社員を清々しく一喝することだって可能だということか。さて困った。同じように千早歴も感化されてしまったらどうしよう? 変な影響を受けなければいいのだが。潮透子嬢を頼もしく思いながらも、心の中にはそんな複雑な戸惑いも芽生え始めてしまっている。一方、たった4文字で黙らざるを得なくなった杣庄と平塚は、彼女の豹変ぶりに顔を引き攣らせている。2人にとって未知の体験だったに違いない。「と、透子……。落ち付けよ。な?」「落ち着く必要があるのは杣庄の方! そっちは昼休憩中かもしれないけど、私と柾さんは仕事中なの。邪魔しないで!」「邪魔って何だよ?」「明らかに妨害してるじゃないの」正論を述べているのは潮さん。やれやれ、今は潮さんと杣庄を引き離すのが得策か。言い争っている内に仕事のことなどすっかり・うっかり失念してしまったらしく、このままでは、まぁ、僕の分の依頼など放置決定だ。仕方がないのでその後を引き継ぐ。勝手に入力を済ませると、商品と杣庄どもの首根っこを押さえ、退散した。7 : 杣庄視点 喫煙室 PM0:473人で喫煙室に入る。俺は設置してあった自販機で缶コーヒーを買い、一気に煽った。平塚からぼそぼそと、断片的にだが説明を受けた柾さんは、「花屋の店員?」と鸚鵡返した。「名前だけは、さっきネームプレートが僅かに見えて分かったんです。白井さんって」「白井さんね。で、僕にどうして欲しいって?」「いえ、別に俺は何も」「名前、勤務時間、彼氏の有無、連絡先」言い淀む平塚をよそに、俺は一気に言った。「なるほど」柾さんは吸い納めとばかりに大きく煙草を吸い、煙を吐く。吸殻を容器に捨てると、「午後8時、睡蓮で」と、ユナイソン2階にあるバイキングの場所を指定してから出て行った。俺は平塚に柾さんを頼らなかった理由を訊こうとしたが、明らかに時間不足だったので止めておく。またの機会にすればいいか……。それでもって。柾さんがどんな意図で待ち合わせを決めたのかは分からないが、来るなとは言われなかった。多分、俺も参加していいのだろう。「平塚、8時に睡蓮な」空になった缶コーヒーが音を立てて沈んだ数秒後、平塚は弱々しく頷いた。8 :2階飲食店≪バイキング「睡蓮」≫ PM8:12結論から言えば、柾は平塚が所望していたデータの全てをもぎ取って来ていた。「俺、柾さんにだけは絶対に頼りたくなかったんです。彼女が柾さんになびいたらと思ったら、それだけでもう胃がキリキリして。不破は潮さんにぞっこん惚れまくってるし、ソマ先輩には彼女がいるから安全牌だろうって。麻生さんは……言わずもがな」「うるせぇよ……」「その心配は僕にもない」と前置きする柾。「ネームプレート読み間違えたな、平塚。白井じゃなく、臼井だったぞ。臼井みどりさん、25歳。彼氏はいないが、旦那がいる。花屋の店長だそうだ。住所は市内。勤務形態はランダム。以上」相手のデータを諳んじる柾に、麻生は「警察官になれば、さぞかし重宝したろうに」と、彼の才能を嘆いた。「へぇ……。あの人、既婚者だったのか。見る目はあったが、時既に遅しだったな」ウインナーを頬張りながら犬君、次いで杣庄が茶碗蒸しの中に入った銀杏をすくい上げながら、口角を上げて言う。「花屋だから結婚指輪は外していた。なるほどな」花屋に土と水は付き物。勤務中にそんな大切なものは身に付けないだろう。ふいに柾の手が止まった。平塚が目の前の皿に視線を落したまま、ジッとしていたから。「睡蓮を指定したのは、最近食が細かったお前に、たらふく食って貰うためだったんだがな」それなのに、よりによってラーメンなんか持って来やがって――。食べかけていたグラタン皿を追いやると、平塚のノビかけたラーメンを救出するかのごとく食べ始めた。「あーもー! なんでこうも上手くいかないかなー!」ラーメンの器が消えたことで、平塚の周りには若干のスペースが空いたわけだ。彼はそこに突っ伏すと、大仰に吐き捨てる。思わず顔を見合わせる麻生、柾、杣庄、犬君。「さー、どうしてだろうなー。俺には分かりかねる。そうそう、次も俺を巻き込むなよ」「気弱なくせに、がっつき過ぎだ」「お前に、男としての魅力がないんだろうな」同時に述べたにもかかわらず、平塚には誰がどのセリフを放ったのかちゃんと分かっていた。がば、と身を起こすと犬君を睨む。「俺に魅力がナイだとぉ? 犬め……殴らせろ、1発」「イヌ……。また新しいあだ名が増えたな、不破」「これはあだ名とは言いませんよ、麻生さん」「だから! そこは別に感心して欲しい部分じゃないですからねー、麻生さん!」「ところで、どうして急に独り身だなんだと焦りだしたんだ? 今の時期、特にカップルイベントなんてないだろ?」彼女いない歴がいよいよ二桁の年数に届いてしまった麻生の発言に、柾はやれやれとばかりに露骨な溜息。「なんだよ……悪かったな、疎くて……」さすがに傷付いたらしく、ムッとしながらもバツ悪そうに小さく呟く麻生である。助け舟とばかりに「夜桜・イルミネーション」と犬君が言えば、「ドライブ・潮干狩り」と杣庄が続き、柾が「公園デート・いちご狩り」と締め括る。「あぁ、そういうことか」納得の麻生だったが、当の平塚にはまだ足りなかったらしい。「アウトドア・別荘」と付け足した。「えっ。お前んち、別荘持ってるのか?」「姉貴の旦那が軽井沢出身なんですよ。両親がログハウスの経営をしてたんですけど、年を理由に最近、経営権を義兄に譲ったとかで。せっかく遊びに行きやすくなった事だし、だから彼女が欲しいなって。そんな矢先に臼井さんを見掛けるようになって一目惚れしたんスけど……」「水臭いなぁ。軽井沢の別荘なら俺も一緒に行ってやるって」「誰が好き好んで男と別荘!? 確かに麻生さんは上司として好きですけど、絶対イヤだ……!」「俺だってお前と2人きりなんてのは想定外だ。俺が言いたかったのは、皆でわいわい集うっつー雰囲気でだな……」「うわー。それ絶対、キャンプのイメージだー。The・男の合宿って感じ。飯盒炊爨・カレー・テントのノリでしょー、麻生さん」「お前、どこまで俺を虚仮にするつもりだ?」言い合う平塚と麻生をよそに、「所詮、振られてもこんなもんですよね、平塚なんて」「心配するだけムダってもんだろ。糞餓鬼その2に振り回されたのが今日1日限りでよかったぜ」「麻生もなぁ……。『俺を巻き込むな』という割には、傷心の平塚のアフターケア対策をしっかりしてるじゃないか」結局何だかんだ言いつつも、『友情』だったワケだ。――なんて、誰も口にはしない。そんな小っ恥ずかしいこと、口が裂けても言わない。認めもしない。至極ささやかな出来事。平塚鷲は恋をした。でも、恋に落ちたわけじゃない。「いつか現れるさ。お前にも、素敵な女性が」犬君の言葉に、それぞれが苦笑いをしながらも首肯する。「……そう願うよ」平塚を労う宴は、制限時間120分もの間続いたのだった。■ 後日談という名の補完 ■犬君 「そう言えば、麻生さんが食堂で読んでらっしゃった商業誌って……」麻生 「あぁ。あれは俺の。柾に貸してくれって言われて、色々持って来たんだ」犬君 「僕も読みたいんですけど」麻生 「じゃあ、読み終わったらお前に渡すよう、柾に言っておく」犬君 「有り難う御座います」麻生 「なぁ不破。臼井さんに作って貰った花束、結局どうしたんだ?」犬君 「花でしたら、その日の夜、透子さんに渡しました。マンションの部屋に行って」麻生 「この積極性が平塚にあればなぁ……」犬君 「花束貰うだけ貰って、速攻でドア閉められて、施錠されましたけどね」麻生 「……潮さん、どこまで逞しくなるんだろうな……」お後がよろしいようで\(^o^)/2010.12.202020.02.20 改稿
2020.02.20
コメント(0)
-
G3 (潮) 【I Gotcha!】
日常編 (潮) 【I Gotcha!】「愛してるよ、ヴェロニカ」「私もよ、ファウスト。あぁ……ならばいっそ、この国から出てしまいたい……!」「故郷を捨てるというのかい?」「ここで追っ手に捕まって息絶えるよりも、生き延びてあなたと過ごす道を、私は選ぶわ」「君の決意は固いんだね。分かった、今すぐにでも荷造りをしよう」「彼らが来ない内に」「スペインを出よう」手を取り合う、スクリーンの中の美男美女。私はその画面を、単に風景の一部として眺めていた。咀嚼によって、ばりん、とおにぎりせんべいが割れる。香ばしい醤油の匂いがたまらない。しゅわしゅわという蒸気の音が聴こえてくる。そろそろ薬缶が沸騰する頃合いだ。緑茶を淹れるため、私は立ち上がった。「……駄作だわ。不破犬君に文句を言ってやらなくちゃ」休日の暇潰しにDVD観賞がしたい。そう漏らした言葉を、彼はちゃんと聞いていた。翌日手渡されたのは4年前に公開された、『西へ』という欧州映画。殺人現場を目撃してしまったヒロインのヴェロニカが、幼馴染のファウストと愛の逃避行を計る、そんな物語だ。以上、50字あらすじ終了。彼はなぜこんな陳腐なDVDをセレクトしたのだろう。まだ前回借りた極道物の方が、スカッとした気分になれた分、評価に値するというものだ。とは言え『ティファニーで朝食を』や『ローマの休日』『ロッキー』など、映画史を代表するタイトルを好む不破犬君のこと。「それ以外の映画にして」というオーダーを出した私が間違っていたのだろう――多分。「あぁ……ファウスト……そんな……ファウスト! 嘘よ、あなたが死んでしまうなんて。これは夢だわ。そう、悪夢なのよ」……ほらー。目を離した隙に死んじゃったじゃん、ファウスト。緑茶を淹れ終え、リビングに戻る。エンドクレジットに差し掛かり、DVDレコーダーに手を伸ばしかけたところで、ざぁぁという音が外から聴こえて来た。雨だ。慌ててDVDとTVの電源を切り、湯呑みをテーブルに置くと、南の窓へ一目散に走った。カーテンを開ける。午前にも関わらず、いつの間にか空はどんよりと分厚い層の雲が覆っていた。気象庁は予報を外した。スリッパを履き替え、社宅マンションに備え付けられている、お粗末ながらも重宝しているベランダへ出る。干してから3時間しか経っていない洗濯物。こんな天気では乾こうはずもない。ハンガーごと外していると、視界に、私と同じように急な雨に降られ、洗濯物を避難させている人影が飛び込んできた。斜め下の階だ。その人物も私の存在に気が付いたようだった。私の姿を認めた彼は、困った顔で笑い、「やぁ」と話しかけてくる。「参っちまうよな、潮さん」「本当ですね、麻生さん」*まさか、後輩の想い人(その1? それとも、その2?)と、休日にこんな会話を交わすことになろうとは。「許してね、千早さん」リビングに戻るなり、十字を切る私。それにしても雨だなんて。今日は買い物に行くつもりだったのに。そうでなければ明日の朝食の食卓が危うい。何せパンすらないのだから。コンビニに行くより、ユナイソンの方が近いので、やはり買い物は外せない。「でもその前に……明日の朝より今日の昼が問題よね……。はは、見事にないわ」冷蔵庫の中はすっからかん。それと言うのも、妹の那漣が昨晩遊びに来ていたので。あれは予想外の来訪だった。結局、ユナイソンのテナントで昼食を摂り、その後ゆっくりと買い物をするコースに決める。荷物のことを考えると自転車で行くのが好ましかったが、傘差し運転は禁止されているので、徒歩で行くことにした。*準備を整え、エレベーターで降下する。マンションの出入り口で、またもや麻生さんと鉢合わせた。シンプルな白の六分袖カットソーに黒の美脚ジーンズという出で立ち。さりげないお洒落加減に、つい魅入ってしまう。いけないいけない。慌てて視線を引き剥がす。「出掛けるのか?」傘を持った私を見て、麻生さんは私に訊ねて来た。「はい。ネオナゴヤで食事を済ませてから買い物をするつもりです」出入り口にいるというのに、麻生さんは傘を持っていなかった。ポストに用があったわけではないだろう。このマンションへの配達は常に夕方なのだから。「店に行くのか」「えぇ。それじゃあ行って来ます。徒歩なんで、小雨の内に行っておかないと」踵を返すと、背後から「待った」と声が掛けられた。振り向くと、麻生さんは車のキーを見せながら言い添える。「俺もネオナゴヤで食事と買い物をするつもりだったんだ。よければ一緒に行かないか?」*麻生さんの運転する車に乗り込む私。聞けばこの新車、妹以外に女性を乗せたことがないのだとか――。(千早さん、ほんとにゴメン)本日2回目の懺悔。しかも、「帰りは荷物があるから大変だろう」と言うことで、車で送ってくれると言う。昼食と買い物、どちらもお互いに必要なため、面倒だから一緒に行動しよう、ということになった。「じゃあ、今日は麻生さんとデートですね」「そうなるな」「宜しくお願いします」「こちらこそ」うーん、麻生さんか。はっきり言って、どんな人物なのかよく知らない。浮いた話は聞かないが、彼を狙っている女性社員は少なくはないようだ。有能社員が集められたという噂が実しやかに囁かれているネオナゴヤでこそ人気は分散化してしまっているが、麻生さんだって負けてはいない。というより、寧ろ麻生さんは勝ち組か……?ちらりと横顔を盗み見る。あー、納得。確かにイケメンだ、この人。チーフ職に就いているから優秀なのだろうし、フェミニストな節も見受けられる。駄目出しのしようがない。車はネオナゴヤの駐車場へと滑りこむ。バック駐車を一発で決める麻生さんの格好よさを、認めないわけにはいかない。「どうして麻生さんに恋人がいないんでしょう」「藪から棒に何を言い出すんだ、潮さん」「いえ、本当に不思議なんです」「そう言われても困るんだが」「ですよね。すみません」「なんか潮さんって、不破に似てるな」「……はぁ!? どこがですか!? 似てませんよ」声を荒げて反論すると、麻生さんは笑いながら詫びる。「ごめんごめん。淡々と話すところが似てるなーと思って。一緒に働いていると、どこか似てきたりするもんなのかな」「だから似てませんって。じゃあ、麻生さんは千早さんに似て来たと思います?」「は? 俺がち――千早さんに?」「えぇ」「いや、似てない似てない。似るはずがない」麻生さんは真っ先に否定する。でも、私は知っている。千早さんが男の人に慣れてきているのと同様、麻生さんも女の人に慣れてきていることを。そんなことは口が裂けても言えないから、私は別の方向から切り返すことにした。私だって千早さんと同じ職場にいるのだ。彼女の口調を真似ることなんて造作もない。なるべく彼女の声音・話すスピードに似せながら、私は言葉の矢を放った。「麻生さん」「ん?」潮透子一世一代の晴れ舞台、開幕だ。「『この後私は麻生さんと一緒に過ごすので……夜になった時にはもう、私は麻生さん色に染まっちゃうかも、ですよ?』」麻生さんは一瞬の間ののち、降参の白旗を揚げた。「マジか! 似てる! 雰囲気激似だぜ、すげぇよ潮さん! それに男も真っ青の殺し文句だな。参った、俺の負けだよ」してやったり。満足した私は思わず笑顔になる。そんな私を見て、麻生さんは笑った。よかった、今日は楽しい1日になりそうだ。2010.10.152020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (―) 【Find Out!】
日常編 (―) 【Find Out!】[ネオナゴヤ店 バックヤード AM9:37]「麻生、読んだか?」素っ気ない言葉に麻生環が振り返れば、そこには1枚の紙を渡そうとしている柾の姿があった。「見て分からないか? 生憎、両手が塞がっていてね」吐き捨てるように麻生は応じる。柾だって知っているはずなのだ。なぜならば、麻生はかなり大きな荷物を抱えているのだから。店頭にディスプレイするための見本品。最新の空気清浄機だ。それほど重くはないのだが、なにせ嵩張る代物だった。だから何だとばかりに柾は視線を麻生に向け、平然と続ける。「口がある」「……あと数歩で売り場なんだがな? 俺は空気清浄機を両手で持って、なおかつ口で紙を咥えにゃならんのか? どんな絵面だ、阿呆。いいから、概要を話せ。そこまで言うからには、緊急連絡網なんだろ?」「あぁ。ここ最近の店内トラブル一覧表だ。万引き・カツアゲ・暴行、等々」「何も今に始まったことでもないだろうに。俺のポケットにでも捻じ込んでくれ。後で読む」柾の瞳が一瞬光ったのは気のせいだろうか――麻生の口元を狙っている気がする。結局はそれも杞憂だったようで、柾は麻生のスラックスに手を伸ばし、ポケットに手を掛けたところで……。「あーそーぉさんっ!」麻生の背中に平手打ち。力任せの暴挙は稀代のトラブルメイカー、平塚鷲によるものだった。「平塚っ! 痛ぇよ馬鹿!」「あれー? 柾さん、何スかその紙?」「緊急連絡網だ」「え? 俺、まだ見てない」驚くべき速さで柾の手から紙を抜くと、平塚は文章を斜め読みする。ふーん、と短い感想を漏らすと、にっこり微笑む。麻生の眉根が寄る。平塚の笑顔など、悪魔の頬笑み以外のなにものでもないからだ。「おい平塚、」「ほいっ、麻生さん☆」嫌な予感が的中した。麻生の口に差し込まれる1枚の紙。「「ハイ・ファイブ!」」柾と平塚が、お互いの手を叩き合わせた。こういう時だけ示し合わせたかのように息がぴったり合う2人のコントに、麻生は膝の部分を使って平塚の背中を軽く蹴り入れた。*[ネオナゴヤ店 AM10:54]千早歴の困った顔を見て、麻生は『何が彼女を困らせているのだろう?』と考えた。自分がPOSルームに来るまで、彼女は穏やかな笑みを湛えていた。とすれば、原因は自分側にあるとしか思えない。しかし、自分は「オーディオプレイヤーの1週間の売り上げデータを教えて欲しい」と頼んだだけである。いつもなら30秒もあれば、歴が微笑みながら個数を教えてくれるはずだった。だが今日に限ってその表情は険しい。「どうしたんだ? ちぃ」歴は解せない顔で麻生を見、椅子を回転させて再びパソコンの画面に向き合った。「これ……おかしくないですか?」「おかしい?」どういう説明をすれば伝わるだろうかと、歴の目が訴えていた。麻生は、歴の隣りの空席――今日は休みである、潮透子の席だ――の椅子を引くと、背もたれ部分を前に持ってくるように腰かけた。「売り上げ金額が合わないような……」そう言うと、キーボードを操って画面を切り替えた。麻生に見えるように、歴はパソコン自体を斜めに向ける。「ここを見て下さい。本来ならば、この商品は16,000円で……4つ売れたんですから、ここの数値は64,000円にならなければなりません」「あぁ。それは分かる」「でも59,200円になってます」「……ほんとだ」「この1週間の内に、特売でも掛けました?」「いや? そんな指示、俺は出してないぞ。……おかしいな?」またもや画面を切り替え、歴は値段の推移を確認する。「そうですね……おかしいです。POSオペレータの誰1人として、その商品の値段を変えた形跡はありません」ネオナゴヤ店のPOSオペレータは3人。千早歴に、彼女の数年先輩である潮透子、そして指導者の地位にいる八女芙蓉だ。歴はまだ新参者とは言え、芙蓉直々の指導を受けている。ネオナゴヤという新店に来られたのも、その能力が買われた結果だろう。「単純に割るとどうなる? 1台14,800円で売れた計算だな」「でも、そんな値段の入力はしていないと、パソコン自身が言っていますし……」「うーん……?」結局、歴の笑顔は見られないまま、麻生はPOSルームを後にした。*[ネオナゴヤ店 AM11:04]POSルームを出た麻生は、犬君とぶつかりそうになった。慌てて回避する。「……っと、悪ィ!」「こちらこそすみません、麻生さん」「おー、凄い量だなー。どうしたんだ?」犬君は、台車に溢れんばかりの商品を運んでいる最中だった。味噌、醤油、飲料など多岐に渡る。「他の支店で新商品フェアをやったんですけど、見事にドボン。とてもさばき切れないから、ネオナゴヤでも売ってくれ! と頼まれました。確かに売れないんですよ。10%OFFにしていたけど、40%OFFにしてしまおうかと思って。どうせうちの店の懐は痛まないですし」「見切り品にするのか。シールを貼るのだけでも一苦労だな」「本当ですよ。シール代だって馬鹿にならないし。寧ろ、シール代で売り上げ消えますからね。笑えませんよ」犬君はひらひらと『40%引き』と書かれたシールの束を麻生に見せる。瞬間、麻生に閃くものがあった。「……そうか……!」「?」「今度お前にメシ奢ってやるよ! 感謝な!」「……僕、何かしましたっけ?」「したんだよ。そうそう、あの緊急連絡網見たか?」「万引きや悪質な手口での犯行が増えてるという通達書のことですか? 見ましたけど」「うちも被害出てるんだよな?」「どうでしょうね? 確かに近隣店舗での報告例は多かった気がしますけど」「どうやらこの店も狙われつつあるらしい」*[ネオナゴヤ店 PM1:12]ネオナゴヤ店の食堂。麻生はフライドポテトを1本掴むと、それを振りながら言った。「答えは単純な計算で出た」「単純な計算?」サラダをすくいあげた手を止め、歴は首を傾げて麻生をキョトンと見る。「あぁ。3台は普通に売れたんだ。16,000円で。すると48,000円になる」「えぇ」「実際の売上金額は59,200円。残りは10,200円だ。これは定価の三割値に相当する」「なるほど。犯人は『30%引き』のシールを商品にこっそり貼ってレジを通ったというわけか」柾はスマホの電卓機能を使って試算していた。柾の前には相変わらずBOSS缶のブラックが置いてある。「よくもまぁ、そんなことを考えるもんだ」「万引きに匹敵する、かなり悪質な手口ですね」「シール以外にも、紙で『30%引き』と書かれたものもあるからな。それだと、紙の上部分をセロハンテープでくっ付けるだけで出来ちまう」「どこかの別の見切り商品に貼られたソレを、単に貼りかえるだけの手口なんて……。凄いことを考えますね」「幾つか対処法が思いつかないでもない。早速、本部に報告しておくよ」「これで、犯行が減るといいですね」「だな。これにて一件落着」「凄いです、麻生さん! もしかしたら、金一封が出るんじゃないですか?」「はは、出ない出ない。もし出たとしても、不破に奢ることになってるけどな」「じゃあ、私がそこのジュース1本奢っちゃいます!」「千早、僕には?」「柾さんは既に珈琲を飲んでらっしゃるじゃないですか」その答えに、柾は自分の缶コーヒーを麻生の手に握らせた。「麻生なら、これで十分だ。僕に飲み物をくれないかな、千早?」「……もぅっ! 分かりました、柾さんと麻生さんの分、ちゃんと用意しますから」「お前、どれだけ大人げないんだ……」「なんとでも言え」立ち上がった歴は、食堂の端に置いてある自動販売機へと向かった。やがて、その腕に3本の紙パックジュースを抱えた彼女が帰って来る。「はい、麻生さんっ」手渡す歴の笑顔を見て、麻生の口端が上がる。(金一封だって? 馬鹿な。俺には、これで十分だ)「ありがとさん」紙パックを受け取ると、大事そうに懐へとしまう。これは今日1日のご褒美として、帰宅してから飲もう。取り敢えずは柾がくれたBOSS缶を飲み干し、麻生は煙草のフィルターに火を付け、美味しそうに煙を燻らせた。2009.09.022020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (潮) 【Impudent Talk!】
日常編 (潮) 【Impudent Talk!】「潮さん、ちょっといいかな」そう言って私に声を掛けてきたのは、業務部として事務所に詰めている1つ年上の先輩、常盤さんだった。常盤さんは千早凪氏のもとで忠実に働く勤労社員。気さくな性格が万人受けするらしく、事務所に頼みごとがある時は『常盤さんだと頼みやすい』と評判だ。ゆえに、上は上司から下は部下にいたるまで重宝がられている。そんな事務方の人間が、微妙に畑違いな同部署POSルームを訪ねてくるなど珍事に等しい。だからこそナニゴト!? と身構えてしまった。それが杞憂だと分かったのは、常盤さんが低姿勢を貫いたからだ。常盤さんは言う。「八女さんも千早さんも休みで、潮さん1人のところ申し訳ない。今しがた、本部からとある売り上げデータを集計したいという要請があってね。今日は凪さんが公外でいないから、俺には出力方法が分からなくて……。悪いが助けてくれないか?」その言葉と共に差し出された1枚の用紙を見やる。売り上げ個数と金額の欄が空白になっていた。(つまり、ここを埋めればいいわけね)私は自分の席に常盤さんを座らせる。彼の正面に、パソコンが鎮座している形だ。私の案内に従った常盤さんは、おっかなびっくりの手付きでマウスを動かしていたものの、1分後には空欄箇所を埋めるのに成功していた。「……なんだ。思いのほか簡単に出力できるものだったんだね。それなのにいつも凪さんに任せっ放しで……申し訳なかったなぁ」常盤さんは心の底から詫びるような声を出し、重ねて私にも御礼の意を述べるのだった。最後に再度「ありがとう」と言って退室した常盤さんを見送りながら私は椅子に座り直し、いち方向へと回転させた。「あなたと同じことを、同じ方法で教えたのに、あちらさんは一度こっきりで覚えてくだすったわよ? どこかの誰かさんとは大違いね」首をすくめ、毒を吐くようにせせら笑う私。POSルームの奥で一人寡黙に書類整理に励んでいた不遜な男、不破犬君は、動かしていた手をピタリと止めるとその身体を私に向け、にっこり笑った。「ふぅん……? 常盤さんにはかからなかったのかな? 透子さんのテンプテーション。僕にはかかりっ放しで、今でさえ2人きりというシチュエーションに、何をしでかすか分からない状態ですけど」「な……っ!」くっ……。このバカ犬。やり込めたつもりが逆にやり込められ、挙句、千早さんや八女先輩、杣庄という名の助け船は出そうにない。だからといって、勢いに任せて部屋から出るなんてのはイヤだ。だって、なんだか癪だから。結局、生まれたての羞恥心を抱えたまま無言で机に向き直った。反論しない私がおかしかったのか、不破犬君はくくくと忍び笑い。(……うぅっ、覚えてらっしゃい。絶対近い内に逆襲してやるんだから)それまで精々歯の浮く寒々しいセリフを、湯水のように垂れ流すがいいわ!まるで決意表明するかのごとくキーボードのエンターキーを人差し指で叩きつけると、中断していた仕事を再開させる私なのだった。2011.09.192020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (犬) 【One Day!】
日常編 (犬) 【One Day!】「いや、だがこれだとアカだぞ?」「売れば売るほど赤字です。いっそロスリーダーで行きますか、青柳チーフ」「待って! 不破君、丼勘定じゃなくて、そこの計算機を使って正しい数字を出してよ」「そういう計算は、志貴さんの方が早いですからお任せします」「全くもう……!」「志貴、計算機取ってくれないか。――200でギリギリ利益範囲内か……。不破、お前の意見は?」「僕なら、その倍取ります」「400か。魅力的で無難な数字だが。――志貴?」「……私も不破君と同じ意見です。400ないし500と言ったところですか」「そんなもんだな、やっぱり。よし、400ケースで行こう。不破、発注頼む」「了解です」*そんな仕事のやり取りがあって、僕は商品発注のために、とある書類を探している。そこに注文したい個数を記入し、今日中に問屋へFAXを流さなければいけないのだが。「ない……よな?」どこを探しても、その紙が見当たらない。確かに昨日、この部屋で見たのに。ドライ部門に宛がわれた、この小部屋で。「……っかしぃな……?」お世辞にも綺麗とは言えない机上の書類山だが、間違っても捨てる、なんてミスはしない。何故ならば皆が皆、書類を捨てないからだ(おい、と自分で突っ込んでおく)。左手でPHSを持ち、「志貴さーん、用紙が見当たりませんけど」とヘルプを送りながら、僕の右手は至るところを引っ繰り返す。「あの紙ならPOSルームじゃないかな。ほら、JANコードも付いてたから。チーフが値段の入力を頼んでたはずよ」「どうしてそんな重要事項をさっきの時点で教えてくれなかったんですか」「知ってると思って」「知りませんよ、今日僕、遅番でしたし」志貴さんに愚痴っても仕方がない。早々に電話を切り上げると、今度はPOSルームにかけ直す。2コール後、電話に出たのは透子さんだった。「はい、POS潮です」「透子さん!」明らかに僕の声は弾んでいた。対する透子さんは声のトーンを下げる。「……何の用?」いやいや、テンションも低くなってるじゃないですか。凹みたくなる気分を押さえつつ、件の用紙についての心当たりを訊ねてみたところ、やはりPOSルームにあるとのことだった。「それ、今から持って来てくれませんか?」「取りに来なさいよ。こっちは忙しいの」「僕も忙しいんですけど」「全く……しょうがないわね」不機嫌なセリフで締め括られた電話。でもこれで透子さんに会える。そう思うと、この機会を崇めたくもなるというものだ。*「私に書類を持って来させるなんて、いい度胸してるわね」……。おかしい。何かがおかしい。確かに『POSオペレータ』は僕の欲しかったFAX用紙を携えていた。でも、どうしてそれが、「……八女さん……」なんですか、神様。「今、舌打ちしたでしょ」「しました」「ホントにいい度胸ね……。潮は本当に手が離せないのよ」そう。ここは仕事場で。僕は恋愛ではなく、仕事をしに来ている。だからガッカリするのはお門違い……。なんだろうけど、やっぱり釈然としないのは何故だろう?「恋に障害はつきものよ、わんちゃん」不敵な笑みを浮かべる八女さんに言われるまでもない。そんなものは――「……百も承知です」2011.06.172020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (―) 【Various Men!】
日常編 (―) 【Various Men!】(1)桜前線が日本を横断し始めた3月下旬。ユナイソンネオナゴヤ店に足を運ぶ女性客らは、こぞって重たいダウンコートを脱ぎ、淡い色のスプリングコートに袖を通していた。春めいた装い、豊かに加わる色彩。私が先に満喫するのよと言わんばかりのトレンドファッションの先駆者たち。冬物最終処分品は店頭には出ていない。もしあったとしても、それらは2階バックヤードの隅へと追いやられている。今、婦人服売り場にはパステルカラーやホワイト、明るい原色を基調とした布地たちが一面に広がり、人々の目を眩ませている。女性は晴れ晴れとした気分になっているし、男性は薄手の生地を手に今にも涎を垂らさんばかり。僅かだが水着コーナーも設けられており、ハート型の目をするか、もしくは目尻を下げていた。客の目当ては新しさや安さ、加えて個性的だったり、実用性があったりするもの。ニーズは増え、店側もあの手この手で販売戦略を練る。奇しくも今日から新たな戦が始まろうとしていた。その名もインナーバーゲン。春物の下着がどれも30%OFFになるという触れ込みは人気を博し、インナーコーナーはミスからミセスまでの幅広い年齢層の女性客でごった返していた。「客注分のキャミソールが届いたそうです」「このストッキングはセンター発注? それともメーカー発注でしたっけ」婦人服売場の責任者である五十嵐を呼ぶ従業員。そしてレジには会計を待つ長蛇の列。オープン1ヶ月を祝して作った目玉が、まさかここまで好評だとは。(三割引の集客率は大きいな。この多忙さでは、昼休憩は断念せざるを得ないだろう)五十嵐はレジを打ちながら、頭の中で午後のローテーションを組み換え始めた。効率のいい最善策を見繕わなければ。(2)「こんなことしてる場合じゃないのよ!」突然喚きはじめた八女芙蓉の声に、すぐ近くで作業をしていた伊神十御が目をぱちくりさせて彼女を振り返る。ここはバックヤード内にあるPOSルーム。伊神は故障したエアコンを直すために派遣された。作業している内に暑くなったのだろう。黒のつなぎの作業服は、上半身部分を肩から外すように脱いでおり、腰にだらしなく垂らしてある状態だ。下に着ていた白の七分袖はストレッチVネックのTシャツで、ヒューゴ・ボスのロゴがさり気なく縫い付けてある。汗を拭う伊神の姿にタオルとスポーツドリンクを差し入れしたくなるであろう、この部屋のもう1人の住人、潮透子の姿はない。優しげな表情や口調から、穏やかで知的なインドア派と思われがちな伊神だが、日々運動を欠かさないため、健康的で程よく筋肉もついている。背も高いのでスーツだって馴染むように着こなせてしまえるし、どんなTシャツでも見栄えよく映る。本人に自覚が一切ない、モデル張りの男。それが伊神だった。そしてそんな男性を前にしても一切なびかない女性が芙蓉である。「どうしたの、八女さん」2人は同期。知り合ってから9年目に突入しようとしているが、「伊神」「八女さん」という呼び方は変わらない。その仲も然り。芙蓉はすらりと伸びた足を組み換え、伊神を睨む。彼が何かしたわけでもないのに、とばっちりを受ける損な役割を引き受けるのも昔のままだ。「買い物に行きたくても行けないのよ」「どうして?」「1つ、潮も千早も休みだから。2つ、昼休憩まで後10分もあるから。3つ、今にも商品が売り切れてしまいそうだから」「オレが買って来ようか? もう修理も終わるし、いつ休憩に入っても構わないから動けるよ?」いつもの芙蓉なら、「あら本当? 助かるわ」と伊神を見送ったことだろう。伊神の方も、それに似た返事が返ってくるものだと思っていた。だからこその進言だった。だが今回は違った。なぜか芙蓉は顔を紅潮させ、口をぱくぱくさせている。言いたいのに何と言えばいいのか分からない……そんな反応だ。「いい。遠慮しておくわ」と絞り出すのが関の山。頼って貰えなかったことが寂しくて、おずおずと尋ね返す。「何が欲しかったの? 遠慮しないで言ってごらんよ」「言えないのよ」「あぁ、サプライズギフトってやつ? 杣庄君に贈るのかな? 大丈夫、ちゃんと黙ってるから。これでも口は堅い方だよ」にこにこと無邪気に笑みをたたえる伊神は何も悪くない。それどころか善人そのものだ。だから芙蓉の心は申し訳ない気持ちでいっぱいになった。反して、実際口から出てきた言葉は辛辣で、人を傷つけかねないものだった。「行かなくていいって言ってるでしょう!?」元をただせば、大声を張り上げ、会話を開始させたのは芙蓉ではなかったか? 自分の責任を棚に上げたこの言い草はあんまりである。だが伊神は責めない。そもそも芙蓉の言動に目くじらを立てたことすらない。傍若無人な振る舞いだろうと、伊神ならば絶対に許してくれる。この世で唯一甘えさせてくれる男性だということを、芙蓉はよく知っていた。そこにつけ込む自分の卑怯さも、身に沁みて理解している。老若男女問わず、困っている人を見掛けるたびに、すかさず手を差し伸べて来た伊神。だが今度ばかりは少し黙っていて欲しい。度を越したボランティアは、煩わしいお節介と同義語だ。「ごめん、八女さん」しゃしゃり出たことに気付いたのだろう。伊神は参ったな、と弱々しい苦笑いを浮かべた。「……何度も言うようだけどね、伊神は何も悪くないの。謝る必要ないわ」(こんなフォローも、毎度のことね)成長しない自分に辟易する芙蓉。伊神は時計を見て微笑んだ。「八女さん、休憩の時間だよ。買い物に行って来なよ」(3)昼休憩から戻った芙蓉は不機嫌だった。不貞腐れているのは誰の目にも明らかだったし、そうと知りながら声を掛ける者はいない。女傑四人衆の三人、それに伊神を除けば。伊神は芙蓉の後ろ姿を見掛けると、その後を追った。本日2度目のPOSルーム。室内には衣料品売場の五十嵐とコスメ売場の柾がおり、芙蓉を見るなり安堵した顔付きになった。お互い、修正を要する商品を小脇に抱えていた。「戻って来てくれて助かった。入力を頼むよ」オペレータ不在の際はパソコンにパスワードをかけてあるから勝手には触れないようになっている。芙蓉の入力が終わった時点で伊神は声を掛ける。「欲しかったものは買えたかい?」「……売り切れてた」芙蓉は渋々答える。「そう、残念だったね」心底残念そうに同情するものだから、沈んでいた気持ちを半分以上霧消させた。嫌な気分を分かち合ってくれたことが芙蓉には嬉しかった。伊神はどこまでも優しい。「仕方ないわ。元々そのサイズ、どこのお店でも少量ずつしか置いていないの」たったそれだけの言葉で五十嵐は希望商品を悟ってしまった。横にいた柾も同様に。売場担当者だからこそ気付けた五十嵐に対し、柾は豊富な女性遍歴によって答えを導き出したまでなのだが。「ブラジャーが欲しかったのか?」五十嵐が芙蓉に尋ねる。入社以来ずっと婦人服売場に身を投じてきた五十嵐にとって、下着関連の単語はすっかり耳馴染みである。うら若き女性が頬を染めたとしてもセクハラと結びつけて貰っては困るし、それでは仕事が遅々として進まないから五十嵐の場合は臆さず言う癖がついていた。「……まさか、そこまで明け透けに仰られるとは思いませんでした」言いにくそうに芙蓉は認める。不自然なほどの自然さで、視線を芙蓉の全身に巡らせた柾は、「ふむ、失礼」と言ってメモ用紙を1枚手に取った。そこにさらさらと書かれたアルファベットと数字を見て、芙蓉は戦慄する。「どうしてそれを……」E65と書かれたそれは芙蓉のブラジャーサイズだった。「見れば分かる」(千早の想い人ったら、随分とそっけなく言ってくれるわね)芙蓉は思わず口を尖らせた。柾はどこ吹く風である。「嵐」嵐。柾は五十嵐をそう呼ぶ。「なんだ?」「これはつまり、こうだろ?」メモ用紙に付け足される数値に、五十嵐は「よく知ってるな」と呆れたような感嘆を漏らした。「八女さんはこれも買える」しれっと言いながら突き出した柾手製のメモには、こう書き足されていた。AA90=A85=B80=C75=D70=E65。「C75、D70なら、在庫数も多いと思うんだが」「柾の言う通りだ。が、俺としてはそんな知識を披露して欲しくはなかったな」「麻生みたいなことを言うなよ」表情はそのままで、拗ねたことを言う柾。芙蓉は呆然としたまま紙を受け取り、くらくらする頭に手を置いた。「……そうか、八女さんが欲しかったのは……ランジェリーだったんだね」免疫がない伊神は居心地が悪いのか、ただただ恐縮しきっている。(ランジェリーという単語さえ、やっとのことで口にしているんでしょうね)芙蓉はやれやれと伊神の顔を見つめた。やはり伊神は純朴すぎる。(それに引きかえ、柾さんときたら)「一番多く補えるのはAA115=A110=B105=C100=D95=E90=F85=G80=H75=I70=J65か」「逆に少ないのはAA65で、一種類しかない」新たなメモ紙に表を作り数字を埋めて行く柾と、それを確認する五十嵐を眺めながら、千早には見せられない光景だわね、と芙蓉は苦笑した。2010.04.012020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (柾) 【Forbidden Fruit!】
日常編 (柾) 【Forbidden Fruit!】理系脳の人間が、超常現象をも愛していると言ったら、世間はどんな反応を示すだろう。その事実が暴かれるたび、児玉菫の心は深く傷付いていった。最先端の科学とオカルトは真逆の位置にある。スキャンダルの所為で、築き上げた信頼が一気に崩れることも、ままあった。彼女が神秘的事象を素直に受け入れているのには、その出自によるところが大きい。彼女の先祖は鎌倉時代まで遡ることが可能で、歴史を紐解けば『武蔵七党』が一つ、児玉党の血筋という話だ。それが分家筋である児玉岳(がく/祖父)の誇りであり、未来永劫に渡り、決して絶やさぬようにと望んだ血脈だった。武士団として名を馳せた児玉家がなぜ精霊信仰に目覚めたのか。それは、ある先祖が気紛れを起こしたためと伝えられている。治癒能力に長けた先祖が木の珠を使って祈祷したところ、土地の流行り病を救ったというのだ。街人たちは児玉のお陰だと持て囃し、すっかり気をよくした先祖は刀を捨て、呪いの世界に身を投じたという。『児玉は木霊(木魂)の長であり、古玉、小玉、子玉、木珠を用いて人を癒やす』――そう記された巻物も、家宝の一つとして存在している。拙い行書、という点がいまいち信憑性に欠けるが……。かくして。武士であった家系が、気紛れな祖先の、奇妙な能力開花に伴い、摩訶不思議な道を歩んだのが児玉家だった。彼女はそんな家で育ったものだから、オカルトを信じる信じないというレベルの話ではなく、それは日常生活に溶け込んでいた。科学者がオカルトを信仰しているのではない。オカルトに慣れ親しんだ者が、科学をも選んだのだ。彼女が愛したのは自然だけでなく、科学もだった。ただそれだけのことである。菫は本格的に科学の道を歩もうとしていた。児玉としての役割を果たすことが減ったのも、理由の1つだった。*菫とは、親同士が知り合いだった。僕の姉の恭子と菫は同級生でもあり、友人でもあった。そして科学者を目指す同志でもあった。僕が中学2年の頃、成績が落ちたことにショックを受けた母は、夏休みだけでも息子を見てくれないかと菫に家庭教師の話をもちかけた。当時、菫は社会人1年目。中学の理科教師だった。そもそも立場が立場だった。公務員がアルバイト代を受け取ることは出来ない。菫は拒んでいたものの、久し振りに見る僕を見て気が変わったようだった。「お金は要りません。ボランティアでいいですよ」結婚4年弱。旦那と子供もありながら、彼女は『公務員のアルバイト』以上に悪質かつ倫理に背いた行動に出た。あろうことか僕を誘惑し、関係を持ったのだ。精神的に幼かった僕は、菫に懸想せざるを得なかった。禁じられた恋だったからこそ、その熱は下がりにくく、また、終わらせ辛くもあった。*中3の冬休み。そして誕生日。「あれ? 直近はいないのか?」「あれなら自分の部屋で缶詰めしてる。模試が近いんだ」「なにも正月に勉強なんざしなくたって」「あら、駄目よ。直には公立に入って貰わないといけないんだから」親戚が集まるリビング、その上の階で、実際には家庭教師である菫と姫初め――。そもそも、菫から勉強を教わったことなど殆どなかった。会っている時は、常に保健体育の実践をしていたのだから。それでも菫と別れたくない一心で、僕は独学で勉強をしたり、授業を真面目に受け、成績を維持していた。そういう意味では、菫はとんだ策士だった。*やがて菫が離婚した。それは彼女が正式に児玉を継ぐ日でもあった。離婚の理由を尋ねると、菫はすらすらと諳んじてみせた。一、実父が逝き児玉家を守らねばならないが、今のところ後継者は自分しかいない一、旦那は科学の権威。彼曰く婿養子という条件だけでも破格の待遇だったのに、これ以上怪しげな世界に身を置くことは出来ない一、その事で生じた旦那との不和「一、直が好きだから」「どうせ僕じゃなく、僕の身体だろ」「そうね。だから貴方を手に入れたいの。『柾』を全部頂戴。貴方の全てを」そして理由の一つに『児玉家再興のため、柾姓を確保』と追加した。どうやら彼女には『柾』という苗字が大層魅力的に映ったらしい。木への信仰がそうさせるのだろう。当時、僕には婚約者がいた。三木奈和子という同期の女性だ。折しも半年前にイニシャルを彫った指輪を贈ったばかり。菫の世迷言など真に受けようはずもない。が。何を思ったのか、『児玉』の生業を知っていた僕の両親は、菫にすっかり肩入れしていた。あろうことか、「うちの直を貰ってやって」と、本人を抜きに縁談を進めていたのだ――。奈和子に別れを告げ、僕は菫を選んだ。思うに、菫は初恋の相手だ。天秤にかければどちらに傾くか、それは言わずもがな。やがて僕と菫、そして菫の連れ子である双生児、絹と玄との4人生活が始まった。*その菫との結婚生活も長くは続かなかった。菫の浮気が発覚したのだ。相手は学生で、助手だという。僕は流石に落ち込んだ。少し考えれば分かりそうなものだった。彼女には、彼女の恋愛観がある。僕とだって、そうだったじゃないか。いつかこんな日が来ると予測し、覚悟しておくべきだった。腹いせのつもりで、見よう見まね、僕も浮気を始めた。始めの内こそ背徳感があったものの、慣れるのは時間の問題だった。それでも満たされない毎日だった。浮気をしても埋まらない溝がある。自分は何をしているのか?そんな時に、千早歴と出逢った。児玉菫や三木姉妹以来となる、難攻不落のファム・ファタル。強引に関係を持とうと思えば持てた。彼女はどの女性よりもひ弱で、流されやすそうなタイプだったから。『男』の力で、『上司』という権力で、『話術』という嘘で。組み敷こうと思えば、出会ったその日にでも落とせただろう。それでも出来なかったのは、彼女に翻弄されたかったからだ。面白そうだ、などと値踏み違いを起こしてしまったからだ。なにがなにが。それこそとんでもない間違いだった。大事にし過ぎてしまった。自ら彼女との間に垣根を作ってしまった。己の手そのものが届かないようにと。気高い存在だと認めてしまったから、僕は彼女に触れられないままでいる。「柾さん」彼女の声は毒のような蜜の味。僕の心をいとも容易く絡げとってしまう。「柾……? そうじゃなくて。言ってごらん。ナオチカだ」「……」顔を赤らめ、いやいやと首を横に振る。翻弄したいのに、ちっとも屈服しやしない。そのスリルがまた、たまらない。2013.07.172020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (柾) 【Dark Past!】
日常編 (柾) 【Dark Past!】「僕の友人の友人の話なんですけどね。なんでもその男、幸せな新婚ライフを謳歌しているかと思いきや、とある女性に浮気の愉しさを教え込まれてしまったんですって。それからは、人が変わったみたいに浮気三昧。二股、三股、ある時はそれ以上の女性と情事を興じているそうで」「……ひどい話だな。天罰でも下ればいいのに」「柾さん、浮気の証拠を掴む方法って知ってます?」「どうするんだ?」「現場を押さえればいいんです」「単純明快だが、身も蓋もない」*額。頬。首筋。鎖骨。手先。背中。太股。愛撫の場所を増やし、唇を這わす位置を変えるたび、彼女は肢体を丸め、「くすぐったいよ」と笑う。「くすぐらせたいわけじゃないんだが」「だって、くすぐったいんだもん」ごめんね柾さん、と微笑む。「ココはくすぐったくないから。柾さんの期待に応えてあげられるよ?」そう言うと、顔を近付け唇を重ねた。始めは僕が彼女を組み敷いていたのに、気付けば彼女の方が馬乗りになっていた。いつの間に?「……逆」「え……?」体の位置を入れ替える。それだけでイニシアチブが取れてしまうのだから不思議だ。僕を見上げる瞳孔が見開かれていく。余裕をなくしつつあるのか、顔を強張らせて。『大丈夫だから』。心の中で呟く。そんなに怖がらなくても大丈夫だから。優しくするから。だから委ねて欲しい。でも僕には気紛れなところもあるから。口先では違うことを言って、翻弄してしまうかもしれない。例えばほら、こんな風に。「覚悟してね」僕は片方の掌で彼女の視界を遮るように両目を覆い、耳元で囁く。キミの身に振りかかるであろう、これからの未来。快楽の度合い。覚悟してね。*「直ー。直ー? いないのー?」朝陽が昇り始めたばかりの時刻。ぺたん、ぺたんと素足で廊下と部屋を行き来する足音が聴こえて来る。それは遠ざかったり、近付いたりしている。やがて、「直ー。……あぁ、やっぱり寝室だったのね」と、独り言めいた小声。覚醒し切れていない頭で整理する。今日は世間で言うところの祝日。それが珍しく自分の休みと重なった。時刻は7時を過ぎたばかり。見慣れた景色は自分のマンションのもので、僕はベッドに横たわっている。隣りには部下。彼女は裸。それは自分も同じ。当然ながら事後。そして、こんな非常識な時間に訪ねて来た上、無断侵入を試みた人物は姉の涙無だった。祝日? 呪日の間違いじゃないか? 「……ありゃ。ごめんねー」ベッドを上から覗き込んできた涙無は苦笑い。せめて、この子は起こさないようにしないと。そう思っていると、気配で違和を感じたのだろう。一夜を共にした彼女が上半身を起こした。寝ぼけ眼を手でごしごしと擦り、あふ……と小さな欠伸。「ん……柾さん?」と小首を傾げるも、視界には見慣れぬ女性が「やっほー」と手を振っている姿が入ったのだろう。「誰!?」と警戒心を剥き出した。七面倒臭い展開だ。これが女性同士の修羅場なら、まだよかったかもしれない。今のように、親族に見られることほど厄介なものはない。「ごめんなさいねぇ、野暮なことしちゃって。ちょっと弟に挨拶をと思って立ち寄ったんだけどー」目の前にいるのが僕の姉と知った彼女の行動は早かった。あんぐりと口を開けると、ベッドから這い出し――その途中で「わきゃ!」と躓き――床に散らばった服を掻き集める。それらを素早く身に着けると、「あの、えーっと、また後で。って言うかえぇっと、……さよなら!」。玄関から退場した。「……ありゃりゃ。テンパらせちゃった。悪いことしちゃったなー」「確信犯だろ」「あんた結婚したばかりなのに何してんの? 結婚後即別居?」「単身赴任と言って欲しい」「奥方と同じ市内に住んでおきながら単身赴任って説得力ないわよ」「別にいいだろ……。それより1年半振りに顔を見せたな。何の用だ?」「ぶらりと気ままに一時帰国。小春姉にあんたの住所聞いて、合鍵借りたの」「帰ってくれ」「驚かせようと思って極秘帰国した私を邪険に扱うつもり? 直ってば冷たいわ」「今日は用事があるんだ」「さっきの子とデート?」「あの子は……。……いいだろ、別に」「よくない。こんなのいいワケない。でも、あんたに何言っても無駄だって事は幼少期からとくと知ってるから諭すのはやめたの。それよりお腹空いちゃった。何か作ってよ」「嫌だ。何で僕が……」「勝手に台所借りるのは申し訳ないしー」「勝手に鍵を借りるのは申し訳なくないのか?」「あははー、これはお姉様1本取られたわー。ま、いいから作ってよ」「……部屋から出てってくれ」「ちょっとー。この期に及んで追い出す気ー? フライト8時間だったのよー?」「……下着」「にゃ?」「……だから、せめて下着ぐらい穿かせてくれ」「あっははー。これはこれは! 気付いてあげらんなくて、メンゴ・メンゴ!」涙無はカラカラと笑うと部屋から出て行く。その途中で……見られた。床に落ちていたものを。「いやん。直ってば、ポールスミスのローライズの黒ボクサー?」「出てけ、変態」*「直ってば本当に用事があったのね。てっきり、その場凌ぎの嘘だと思ってたわ」『私も行きたい』という我儘を許したのは、どうせ断わっても僕の後を付いて来ることが安易に予想できたからだった。社宅マンションの隣りにある喫茶店が待ち合わせ場所だった。10時に来る予定だった2人は、聞けば予定より早く席に案内されていたと言う。照れ臭そうに笑む少年に対し、少女の方は天真爛漫な笑顔を振りまいていた。「直パパ、会いたかったー!」「……援交?」僕の隣りで呟いた涙無のその言葉に、周囲にいた客たちの視線が僕目掛けて一斉に突き刺さる。「人を勝手に犯罪者に仕立てるな。僕と絹の関係を知っているくせに」戸籍上は僕の子供である2人。姉の絹に、弟の玄。彼らは僕の隣りに座る涙無をきょとんと見やる。「えっと……直パパ。こちらの方は、新しい彼女さん?」娘公認の浮気というのも情けない話だ。改めて、僕の行動が常軌を逸脱していると気付かされる。 ところで、僕の結婚話が持ち上がり、籍を入れてから今日までの間、涙無は日本を離れ、遠く欧州にいた。だから子供たちと涙無は互いに今回が初めての対面となるわけで、絹が涙無を知らないのも無理からぬこと。それにしたって、涙無が僕の『彼女』に見えるのには納得がいかない。「こんな女と付き合う男がいたら教えて欲しいもんだ」「これは早いトコ自己紹介しなきゃね。初めましてー。直の実姉の涙無よ」恐らくは面識済みの長女恭子、次女小春と比べてしまったのだろう。三女の軽さ加減に絹は目を丸くしたようだった。「あなたが涙無さんなんですね……! 初めまして。児玉絹と申します」「絹ちゃんか。ってことはそっちが弟くんね。えっと、木綿くん?」「……いいえ?」にこりと笑って冗談を軽くいなす玄には同情する。「いくらスミレでも、自分の腹を痛めて産んだ双子の名前を豆腐の種類にするわけないだろう」「聞いてみなけりゃ分かんないじゃん?」分からいでか。馬鹿め。「初めまして。児玉玄です」「シズカ君かー。イケメンだー。お姉さんの恋人になって欲しいなー。私、募集中なんだけど、どう?」「涙無さんと俺は身内関係にあるわけですよね? 再婚相手の姉と付き合っていいものなのかな……? 倫理とか面倒なんで辞退しておきますね」「振られちゃった。絹ちゃんは?」「私?」「絹ちゃんのような美人さんが私は大好物」「あら、光栄ですわ。そうですね、ご縁があれば……そんな関係になるかも知れませんわね?」「絹ちゃん、気に入ったわー! 大丈夫、玄君も好きよ」光栄です、と玄は苦笑する。それにしても、末恐ろしいのは絹の懐の深さだ。博愛主義な性格が恋愛に発展しかねない危うさを含んでいる。これは釘を刺しておくべきだろう。「絹のその言葉は社交辞令だって、父さんは信じているからな」「なっ……直パパー! シズカ君、聞いた!? 『父さん』だって! 直パパが自分のこと『父さん』って言ったの、初めて聞いたー!」「……ははぁ~。なんとなく分かったわ、絹ちゃんの性格」「えぇ、分かりやすいでしょう? 絹は、柾さん至上主義なんです」玄の補足に、涙無は深く頷いた。「なるほどね。それで、今日はどんな集まりなの?」「絹が僕に伝えたいことがあるそうだ。……だろ? 絹」絹に発言を促すと、さっきまでの上機嫌はどこに行ったのかと疑いたくなるほど眉尻を下げた。「絹?」「私、直パパと別れるのは嫌なの」「……絹。僕には何を言っているのか」さっぱり分からない。だから再度、問おうとした。だが僕が口を開くより、涙無によるポロシャツ胸倉掴みの方が早かった。「あんたさー、どこまで手広く浮気してんの? よりにもよって奥さんの娘とデキてるって、ハ! そこまで性根が腐ってたなんてね。殴っていい?」「誤解だ。確かに女子高生は守備範囲だが、付き合えるわけないだろう。戸籍上では僕の娘なんだぞ」「絹ちゃんはただの『女子高生』じゃないわ! 美人女子高生よ! なのに付き合えないだとー!?」「待て。その反論もおかしくないか? それにだ、もし他人同士で、こんな出逢いじゃなければ、僕だってこんな綺麗な子は放っておかない」「ほらみなさい! あんたは天性のスケベなのよ!」「あの……趣旨が、ずれてやいませんか?」困惑気味に仲裁に入る玄の言葉に、僕と涙無は黙り込む。絹も複雑そうな顔で僕を見ていた。「……大丈夫だ、絹。異性として見てはいないから」我ながら最低レベルのフォローだと認識しつつ、これからも絹と親子関係を築いていくならば、その点だけははっきりさせておく必要があった。 「その点については私も大丈夫です。親子フィルターが存在していますし。それに『柾直近の娘』って、レア度では恋人より上よね、直パパ?」レア度発言には苦笑せざるを得ない。なるほど、そんな考え方もあるのか。「それじゃあ」と涙無が尋ねる。「さっきの『別れたくない』っていうのは、一体何の話?」「直パパに離婚の相がハッキリ見えたんです。それで、思い留まるように進言したくて」「待ってくれ。僕が離婚?」「どういうこと? 直の浮気が奥さんにバレて、怒髪天ってコト?」「直パパの素行を、母は既に知ってます。寧ろ、浮気を始めたのは母が先なので、直パパは被害者側なのですが……」「えぇっ? そんな修羅場状態だったの? でも、離婚の相って? 『相』ってつまり、占いのことでしょ?」「絹と玄は占い師顔負けの予言者だ」「あー、そういえば電話で聞いた気がする。あんたの縁談にはそんな奇怪な話が付き纏ってたっけね。奥さんがあんたを手に入れたがってた理由は『柾』の血筋云々が……だっけ?」「はい。木霊遣いを生業としている児玉家には、柾姓がとても魅力的だったのです。柾という漢字には木が入っていますでしょう? 正しく木を制するのは、児玉にとって……」「ストップ。説明されても分かんないからいいや。ごめんね。こういう言い方は酷かもしれないけど、要するに児玉菫さんは直の苗字が柾だったから結婚したがったのよね?その我儘を押し通して直をゲットしたものの、愛があって籍を入れたわけではないから浮気を始めたってのはエゴよね?」「直パパが離婚を考えても仕方ないと思います。でも私は、直パパには『パパ』のままでいて欲しい……」「絹ちゃんの気持ちは分かるけどね……」涙無は溜息。僕としても絹を悲しませたくなかったから、「離婚は考えてないよ。せめて、君たちが成人するまではね」言ってから気付く。失言に。どう見繕っても、最後の言葉は余計だった。「そんな……期限付きだなんて」「初婚の柾さんが、母さんの究極の我儘に付き合ってくれたんだ。それだけでも感謝しきれないのに、これ以上束縛なんてできないよ」項垂れる絹に、隣りの玄が言い聞かせるようにゆっくりと話す。僕へのフォローのつもりなのだろう。その心遣いが有り難かった。「そんなの、私だって勿論分かってるわ、玄くん。でも感情が追い付かないの」「俺と絹が成人するまでに柾さんが心変わりして、居続けてくれているかもよ?」「私の予言的中率を知っているでしょう? やけに楽観的ね、玄くん」「俺だって、そんな予言が当たって欲しくないさ」絹の的中率が高いからこそ、玄もそこで口を噤んでしまったのだろう。後を継いだのは涙無だった。「2人が成人するまでは大丈夫だって直本人も言ってるし、玄君の言う通り、直だって考え直すかもよー?」「……だといいのですけど」「絹ちゃん、視た未来を捻じ曲げる能力ってないのかな? 回避能力みたいな。今からそういうのを養えばどうかな?」オカルトめいたことなど何も知らないくせに、涙無は一丁前にぺらぺらと喋るが、どうせ思い付いた順に垂れ流しているだけのことだろう。一方、絹は目から鱗だとばかりに、見る見る頬を上気させた。「ただ視るだけではなく、回避できるように……? それなら直パパとの未来も安泰かも……!」『大丈夫なのか?』と目で玄に問えば、『このまま黙って様子を見ましょう』とアイコンタクトが返ってきたので、黙秘を貫くことにした。「絹ちゃんの未来も変わるかもねー」「……え?」「ん? え? 私、変なこと言った? 深い意味はなかったんだけど」お前はいつも風変わりな発言しかしないだろう。何を今更のたまうか。「まぁ何が一番望ましいかって、直が浮気をやめることなんだけどねー」いきなり矛先が僕へと向き、その切っ先が胸に突き刺さる。「直パパには、無理矢理スミレ……母が結婚を迫った経緯もあるので、浮気に走っても仕方ない部分もあると思うんですけれどね」「そんな風に直を甘やかしたら駄目よ、玄君」「浮気をやめたからと言って、僕の気持ちが菫に向くとは思えないが」「……あんたね……、じゃあ何で結婚したのよ……」「秘密」言って、そっぽを向く。すると斜め前のテーブル通路側に座っていた他の客と目が合った。友達と会話を楽しんでいたところ、ふと何気なく視線を動かしたら、そこには僕がいて、お互いに目が克ち合った――そんな何気ないタイミングだった。年の頃は25前後。ショートボブの黒髪、揺れる両耳のピアス。微笑んでみた。彼女は周囲を見回して、それが自分に向けられたものだと気付き、はにかむ。「ちょっと。聞いてるの、直?」「浮気をやめろ、だろ。善処するよ」話は終わったとばかりに僕は財布を取り出す。それが解散の合図だった。絹と玄は席を立ち、出口へ向かう。涙無もその後に続く。請求書を掴むと、2枚の野口英世紙幣と1枚のカードを財布から引き抜いた。ショートボブの彼女の横を通り過ぎる時、さり気なくテーブルの上にカードのみ滑らせる。彼女が慌ててそのカードを掴むのを目の端で捕らえつつ、僕は歩く速度を落とすことなくレジへ向かう。彼女の手に渡ったカード――僕の携帯番号が書かれた名刺――を彼女がどうするか、それは近い未来に分かるだろう。僕の浮気癖が治るかどうかに関しては、遠い未来に委ねようと思う。僕には気紛れなところもあるから。口先では違うことを言って、翻弄してしまうかもしれない。例えばほら、こんな風に。「もしもし、柾です。君は……けさ喫茶店で会った子か。電話をくれて嬉しいよ」僕の身に振りかかるであろう、これからの未来。覚悟なんて、まだ必要ないだろ?2011.08.202020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G3 (―) 【New Year!】
日常編 (―) 【New Year!】1月1日。それは柾の誕生日。「だからこれ、祝い酒。あと花束」柾の嫌がる顔が予想通りの仏頂面だったため、送り主である麻生環は吹き出さずにいられない。「不服か?」「この顔を見ろ。僕が喜んでいるように見えるのか?」「いや、見えないな」「……まぁいい。ありがたく頂くよ」幻の大吟醸とまで呼ばれているお酒をチラつかされれば、邪険に扱う気も失せるというものだ。「仕事が終わったら店の外で待っててくれって言うから、何事かと思った」「こういうのはサプライズが基本だからな」「せっかく閉店時間が2時間早いから、初詣に行こうと思ってたのに……」「柾でも初詣に行くのか。あ、じゃあ俺も付き合うぜ」「……」「おっと。まるで、野郎2人と行くぐらいなら1人の方がいいって言いた気だな」「その通りだ。だから『誘わない』という選択肢も用意しておいてくれ」「あー無理。きっと忘れる」麻生はニッと片方の唇を上げ、車のカギのチェーンをぐるぐると指で回す。「待て麻生。お前、どこの神社に行こうとしてる?」「は? 柾こそ、どこに行くつもりなんだ」「裏の神社」店の裏側に、人気のない社が建っていることは麻生も知ってはいた。だが……。「少し足を伸ばせば熱田神宮だぜ?」「こういうのは、氏神様から参るのが基本だ」「お前がそう言うなら素直に従うさ」麻生は両手を小さく挙げて、早くも降参のポーズ。柾ともそろそろ永い付き合いなので、その辺りの折り合いは弁えているつもりだ。駐車場まで行き、車内にお酒と花束を置くと、2人は寒空の下、神社へ向かう。普段は寂しい御社も、年末年始は人の往来が少なくない。燈籠に灯る火を頼りに参道を奥へ奥へと進み、手水舎、拝殿、本殿を巡った。「やけに長かったな」麻生が指摘したのは、柾が祈念に費やした時間のことである。投じた御賽銭に見合わないだけの祈念をこめた麻生だったが、柾は麻生が参拝を終えてもまだ祈りを続けていた。「頑張れるだけ頑張って――。最後には、神頼みな部分もあるからな」意味深な……それでいて、弱々しく微笑む柾に、麻生は目を見張った。「そんなに深刻に悩んでるのか?」「悩み? いや、どっちかと言えば、願いだな」「願い……ねぇ」「色々ある。本当に、いろいろ」「例えば?」「……子供たちが、ありがたいことに懐いてくれてて。この前離婚の話題を出したら2人に泣かれた。あれには参ったよ。離れたくないって大騒ぎで。離婚手続きに手間取っているのは、子供たちが大反対している部分も大きくてね。血は繋がっていないが、あの子たちには幸せになって欲しいから、……少し辛い」「泣かれただって? ……でも確かその2人ってさ……」「凄く仲のいい双子の姉弟だ。名前も知っているだろう? 姉は、」「いや、俺が言いたいのはそういうことじゃなくてだな……」そこまで言い掛けていた麻生だったが、口を噤んだ。子供たちが柾との別れを純粋に惜しんでいる。その事実が重要なのだ。「……お前には幸せになって欲しいと思ってるよ」「? 麻生、今……何か言ったか?」――柾、お前にも幸せになる権利があるんだ。……そんなこと、「阿呆。口が裂けても言わねーよ」2010.01.012020.02.19 改稿
2020.02.19
コメント(0)
-
G2 (―) 【澳門於】
日常編 (―) 【澳門於】―マカオニオイテ―[01]地上25階の部屋に入るなり、備え付けのデスクの上に荷物を置いた。肩への負担がなくなったことで、因香はほっと溜息をつく。自分ではそこまで詰め込んだ覚えはないのだが、余計なものまで持ち込んでしまったかもしれない。例えばヘアドライヤー。各部屋に用意されていることは知っていたが、実際に使えるか分からないため、変圧器とプラグも持参した。石橋を叩いて渡る性格ではないと自負している。だが海外だからという理由で、いざという時のための保険をかけてしまうほどには慎重になっているようだ。「えーと。マカオのホテルチップは手配ごとにMOP10ずつ渡せばよかったんだっけ」財布を開け、紙幣を渡しやすいように整理しておく。その後は非常口の場所を確認し、モーニングコールの手配も済ませる。どんな時も備えあれ、だ。ふと、やけに部屋が暗いことに気付き、窓へと歩み寄った。雨の音がする。カーテンを開けると、横殴りの雨が窓に叩き付けるように降っていた。「早速スコールに見舞われたか。大歓迎されてるわね」やれやれと首を竦めたものの、自分には関係ないことに思い至った。そもそも香港経由でマカオに訪れたのは、カジノで遊ぶことが目的である。夏季ボーナスを使って豪遊よ、と恋人に告げたのはつい先日のこと。彼女は呆れたとばかりに「せいぜい気を付けることね」と因香を見送った。そのカジノは雨に降られない場所にある。そう、宿泊するホテルに直接カジノ場が設けられているのだ。因香は早速階下へ向かった。ドレスコードは不要で、ふらりと立ち寄ることが出来るのがマカオカジノの利点でもある。「ベガスカジノでは換金したらとんとんだったからな~。不完全燃焼ではあったのよね。やっぱり勝つか負けるかはっきりさせないと」仕事柄、戦略を立てるのは得意だ。引き際さえ見誤なければギャンブルは怖くない。ただ、今回は使う金額が決まっているため、『引き際=すっからかんになった時』と言えないのがたまにきずだ。「まぁ、やめどきに関しては、その時の気分で決めちゃうのもいいかもね」物欲はさほどない。その容姿からブランドが好きそうだというレッテルを貼られがちな因香だが、意外にも堅実で、姉妹のお下がりを愛用することも多かった。家族と同居なので居住費に関しては家に入れるお金だけで済むし、プチプラコスメで済んでしまう、大変ありがたい肌質だ。ランニングが趣味のため健康に一役買っているし、自炊も得意だ。公共交通機関が発達した都市部在住のため、車を持っていなくても生活に困らない。たまには自分の欲望を満たさないといけない。やっと仕事でも山を乗り越えたのだし、今回の旅行は御褒美も兼ねているのだ。足取りも軽く、因香はドアを開ける。入口にガードマンはいない。日本で言うところのゲームセンターみたいなもので、わりかし緩い雰囲気だ。とは言え、これは店の規模にもよる。監視の強弱は、賭場場の大小に比例するといっても過言ではない。因香が利用しようとしているここ、サングラシアホテルは、こじんまりしたカジノ場。出入りは自由だし、プレイしている様子を眺めるだけでも構わない。敢えてそういうラフに過ごせる場所を選んだのだ。(さてさて、まずは台のチェック、と)ドリンクを飲めるコーナーに立ち寄り、炭酸飲料を注いで貰う。チップを渡すと、若い女性店員がス……と人差し指である一角を示した。「?」「あそこには行かない方がいいわ」「ほほぅ」開口一番に否定形Don'tを聞かされて、興味を引かれないはずがない。面白そうに口角を上げた因香はチップを上乗せする。すぐ退散するつもりだったが気が変わった。ここで飲みながら情報収集するのも悪くない。倍のお小遣いを受け取った店員は笑みこそ浮かべなかったものの、気を良くしたのは確かで、因香に追加のネタを提供した。「昨晩からブラックジャックのディーラーが熱を出して休んでてね。今日はピンチヒッターなんだけど、あの人には近付かない方がいい」視線を辿った先のブラックジャックエリアはそれなりに賑わっていた。カードゲームはカジノの代名詞。一度は挑戦してみたいと思う人気ゲームなのだが……。「あのドヤ顔男、相当強いの?」「強い、の意味にもよるわ。とにかく相手にしないで。特にあなたみたいな美人は。近寄っちゃ駄目よ、絶対に」さらにチップを弾む。眼前に現れたMOP10を見た店員の目がキラリと光るやいなや、近くに誰もいないことを確認すると、因香に耳を近付け囁いた。「あいつ、とんでもないセクハラ野郎なの。底辺ディーラーのくせして、ギャンブルに縁がないドリンクガールにだけは威張れるからって、そりゃもう酷いのよ」「あっ、そーゆー……」(差別野郎ってわけか)「辞めていった子なんて、片手の指じゃ数え切れなくなってる。でも上っ面はいいの。ピット・ボスにへこへこ媚び諂うから、彼のお気に入りみたいで」"Pit Boss"? と疑問を抱いたが、直訳すればいいだけかと思い直す。要するにカジノ場において、権限を持った責任者のことを指しているのだろう。カジノの支配人とは違うのかと新たな疑問が生じたが、そこは後から調べればいいことだ。「教えてくれてありがとう。ブラックジャックで遊びたくなったら、別のディーラーのテーブルにするわ。でも、どこが穴場かな……」その方がいいと相手は頷いた。そして、結局どれも同じよ、とも。「ブラックジャック担当なのだから、相当腕っ節の強いディーラーが据えられると思うでしょ? あれはブラフよ。だからどの台に行っても大丈夫」「へぇ、そうなの? 初めて聞いたわ。でもよく言うわよね? 『あいつは凄腕ディーラーだ!』とか……」「そう勘違いしてるひとも多いけど、実は違うのよ。ルール上、彼らには限られた行動しか出来ない。だから必要以上に臆さなくてもいいの」そのアドバイスのお陰で、取っ付きにくかったブラックジャックへのイメージが払拭された。(そっか……。相手が無敵とは限らないのか。アウェーの空間だったから少しビビってたけど、ちゃんとプレイヤー側にも配慮されてるのね)「ドリンクガール一同の願いはね、あいつを再起不能なまでに叩きのめしてくれる猛者が現れてくれることなの」グラスを磨く手が止まった。自分は何を言ってしまったのだろうと後悔していることがありありと分かる間だった。「ごめんなさい。私が言ったことは気にしないで。そもそも何で遊ぶかの選択はあなたが決めることなのにね。それもギャンブルの内なのだから」因香は最後の一口を煽り、グラスを返した。受け取った店員の手が僅かに震えていることに気付く。(あー……。なるほど。そういうことか)毒牙は彼女にも向いている。今日辺り、誘いがあるのだろう。いや、既にあったのかも知れない。このまま夜を迎えるのが怖くて仕方ないのだろう。(でもこれさー、もし私が勝っちゃったら? プライドずたずたにされて逆上したりしてさ? その鬱憤をこの子にぶつけるってこともあり得るんじゃない?)諸刃だな、と思う。危険極まりない。(さて、どうしたもんか……)出来ない約束はしない方がいい。いくら底辺ディーラーと揶揄されていようが、雇われるからにはプレイヤー以上の力はあるのだろうから。「……美味しかったわ。ご馳走さま」取り敢えず様子見だ。力量を見定めてから決めてもいいだろう。因香は敢えて店員に何も言わず、その場を離れることにした。[02]あんな話を聞かされてはどうにかしてあげたいと思うのが人情というものだろう。仮にあのセクハラ云々が作り話だったとしても、因香が「儲けにきた」気持ちは正当なものだから、勝っても後ろめたくはないのだ。本当は自分のペースで遊べるスロット台に向かうつもりでいたが、予定変更、ブラックジャック台へと足を向けた。さて、問題の台に到着すると、3人のプレイヤーがいた。どの人物も寡黙で表情が乏しく、お世辞にも楽しんでいる気配はない。ただの時間潰しとも取れる一方、真剣勝負においてわざと表情を消している可能性もある。初心者は避けた方がいいとされるサードスペース(左端)には誰もいない。そんな中、一番目を引いたのは右端に座った黒髪の女性だった。背中までのゆるふわヘアで、丸眼鏡をかけている。服装はジーンズに黒のTシャツ。野暮ったく、ありふれた格好なのに、何故か惹き付けられてしまう。年齢は不詳だ。外国人の年を当てるのは難しい。国籍はインド人だろうか。或いはバングラデシュ人か。綺麗な顔立ちをしている。ふと視線を感じ、気配を追うと、ディーラーと目が合った。ボディラインが際立つものを好んで着る因香のことを、上から下へと眺めているではないか。(こいつ……ドリンクガール以外にプレイヤーまで食っちゃうのかしら。どの部屋に泊まっているのか調べられたら不味いわね)視線には気付かなかった振りをして、因香は傍観者のていを装って流れを観察することにした。ボソボソと単語だけで喋る者もいるが、ジェスチャーで進行していくプレイヤーもいる。(あ、負けたみたい)右端の女性が大損をしたようだ。それでもマキシマムベットに拘っているようで、賭け金は変えてこない。(ブラックジャックは還元率が高いし、むきになって取り戻そうという気持ちは分かる。よく分かる)それでもやっぱり、(負けてるし)居ても立ってもいられず、因香は「スプリット」と女性にだけ伝わるように小声で囁いた。一瞬びくりと固まった女性は、少し逡巡したのち、因香の助言通りスプリットを選ぶ。その後も因香は何度か口を挟み、女性は勝つことが出来た。「ありがとう」「どういたしまして」「ミズ。あなたも遊びませんか?」ディーラーに声を掛けられ、因香は女性の隣りに着席した。彼女は負けた分を取り戻したい一心なのか、全額をベットしてきた。その度胸に大丈夫かしらとハラハラせずにいられない。蓋を開けてみれば因香の圧勝だった。ディーラーは悔しそうな顔を一瞬だけ覗かせたが、「おめでとうございます」と形ばかりの賛辞を送られ、悪い気はしない。(ほら! 一矢報いてやったわよ!)因香のような初心者に『再起不能に叩きのめしてあげる』ことは出来なかったが、当初の目的より稼げたのだから、これでよしとしよう。一方、隣りの女性は利益を得て納得したのか、席を離れようとしていた。慌てて因香も席を離れ、女性を追った。「あの」「……え?」声を掛けられたことが意外だったのか、女性は振り返るなり足を止めた。きょとんとした顔で因香を見ている。「えー……と。もしよろしければ、一緒にカフェでもどうかなー……なんて」「……ごめんなさい。この後、約束があるの」ナンパは見事に失敗した。因香としては、「ソウデスカ」と頭をかきながら退散するしかない。「では、失礼します」頭を下げ、女性はカジノ場を後にした。「あ、名前を聞くのすら忘れた……」意気消沈したものの、恋人女性のマークが頭に浮かび、頭をふるふると振る。「いかんいかん、私にはマークがいるんだってば。でも……不思議なひとだったわね」今はもう見えない姿なのに、因香の視線は入り口のドアから離れようとはしなかった。[03]アムヤがサングラシアホテルのカジノ場を選んだのには理由がある。それはここから徒歩1分の場所に世界的に有名なマカオカジノがあり、サングラシアの方が客数として少ないからだった。ドレスコードも必要なく、自分のペースで遊べるため、アムヤはいつもここを選んでは毎回率先して負け続けていた。加えて、もう1分歩けば駅に着くのも強みだった。駅にはカフェが数軒あり、待ち合わせの場所に事欠かない。慌てて約束の店に入ると、早速甘い匂いが鼻孔をくすぐった。エッグタルトだ。大好物に目がくらみ、慌ててショーケースから視線を剥がす。奥では既に待ち合わせの人物が紅茶を嗜んでいた。「トオゴ! お待たせ!」男性に近付くなり、その両頬にキスを落とす。相手もそれに倣った。「そんなに慌てなくても良かったのに」息を切らしたアムヤを見て、相手はくすりと笑った。ふんわりとした髪質や色は、アムヤのそれと似ていた。「だって……早く会いたかったし……」「久し振りだね」「ほんと! 1年半よ。長かったわ。でもどうしたの? 急にマカオで落ち合おうだなんて」「アムヤに伝えたいことがあったんだ。オレ、日本に帰国することになった。だからその前に逢いたくて連絡したんだ」「えっ、帰国するの? いつ?」「実はそんなに日がないんだ。明日の便で発つことになってる。父さんがセントレア国際空港まで迎えに来てくれるんだ」「トオゴとまた離れちゃうのね」「ごめんよ。急な異動だったんだ。アムヤは? いつインドに戻るの?」「決めてないけど、今週中には帰るつもり」「そうか。またしばらく会えなくなるね。いくらSNSが普及したからと言っても、こうして直接顔を見れないのはつらいよ」男性の手がアムヤの頬に伸び、優しく撫でる。アムヤはその手の上から自分の手を重ねた。「トオゴの声、聴いてて落ち着くから私もすっごく残念。でもまた会えるわ。だって家族じゃない」寂しさをむりやり捩じ伏せ、気丈に微笑んでみせる健気な実妹の姿に、兄は自分も見習わなければと反省する。「その家族は、今や世界中に散り散りになってしまっているけどね」「ほんとね! 会う場所が毎回違う国だから大変よ。面白いからいいけど」「そう言えば、いま弟はどこにいるんだい? オレが連絡しても繋がらないんだ。アムヤは知ってる?」「知ってるけど、言えないのよ。ごめんなさい。『兄貴離れしたいから、兄貴から尋ねられても絶対に教えないでくれ』って念を押されてるの」「なんだい、それ……。1年3ヶ月前まで中東にいたことは確かなんだ。お願いだアムヤ、せめてどの大陸かだけでも……この通り」両手を合わせて拝む兄を見て、すっかり日本がホームベースになってしまってるんだなぁと痛感した。こうしてヒンディー語で話していても、仕草は日本寄りなのだから驚いてしまう。「渡航中止勧告が出たから、もう中東にはいないわ。南アメリカ大陸よ」「今度は南アメリカか……。やれやれ」「幸い言語学には不自由していないから無茶が可能なのよね。どこの国に行ってもしぶとく生きていけるもの」「だからこそ心配なんだ」分かるだろう? と優しい兄は目で訴える。兄離れしていない弟――アムヤにとってはそちらも兄だが――のことを棚に置いて、よく言ったものだ。自分の方こそ弟離れ出来ていないではないか。最も、誰が相手であろうとトオゴは心を寄せて思い遣ることに長けているのだが。「ところでアムヤ、今日はもうツキを手放してきたのかい?」トオゴに尋ねられ、ハッと顔を上げたアムヤは、「失敗しちゃったのよ!」と今にも泣きそうな顔で報告した。彼女のルーティンワークが崩れるなんて珍しいことで、トオゴとしては仰天のできごとである。「どういうこと?」「それがね」カジノ場ではクールに振る舞っていたアムヤは一転、急にそわそわと落ち着かなくなってしまったように自分の二の腕を摩る。「オリエンタルな風貌の美人な女性が近付いてきて、私に進言してきたの」「進言って……アドバイス? なんでまた……」「彼女、私がわざと負けているなんて思いもよらなかったんだわ。ことを荒立てて、印象に残りたくなかったから、アドバイスを受け入れるしかなくて」「それで勝ってしまったのか……」「あまり勝ちたくなかったから、ほんの少しプラスになった時点で早々に降りたわ。あぁどうしよう。もう一度負けてこなくっちゃ……」「そうだね、その方がいい」真剣な顔つきでトオゴは頷いた。このままでは大切な妹が悲運に見舞われてしまう。高確率で。元々アムヤは運が強かった。どの国の、どの占い師も、『伊神アムヤは強運の星の下に産まれた』という占い結果を弾き出していた。だが運はバランスだということを、インド人の血を引く彼女はよく理解していた。強運が凶運に化けることだって在り得るし、ふたつは紙一重でもある。ツキを手放すためにわざとカジノで負けていた。その恒例儀式を、因香が関わってしまったことで、計画が狂ってしまった……。「だからと言って、彼女を責めるのはお門違いだわ。だって、わざと負けようとする物好きなんて、世界中を見回したってそうそういないでしょうしね」「そうだね。優しいこころの持ち主だったんだろうな」「きっともう彼女もいないだろうから、もう一度サングラシアに寄って、今度こそ負けてくるわ」「分かった。じゃあ早速ホテルまで送るよ」「そんな、大丈夫よ。ホテルまでは目と鼻の先だし、それに……ほら、雨も上がったわ」窓越しに外を見やれば、本日2度目のスコールはやんでいたようで、日が落ちた空には星が輝いていた。「トオゴも香港に戻らなくちゃ。でしょ?」カフェで過ごしてから一度も時計を見ていなかったことに気付き、自分の左腕を見やったトオゴは珍しく「うわ」と狼狽した。「もうこんな時間だったのか……!」「え? そこまで差し迫ってたの? 大丈夫?」「走れば何とか……」「行って、トオゴ! ここのお勘定は私がしておくから」「ごめん、アムヤ。送ってあげられなくて」「ううん。またね、トオゴ」「うん、また。愛してる」「私もよ」来たときと同じように妹の両頬にキスを落とすと、トオゴは店から出て行った。そして外に出るなり、小走りで駅へと向かう。見えなくなるかならないかギリギリのところで、トオゴが振り返った。さすがに手は振らず、挙げただけだったが、アムヤとしては気が気ではない。「もう……っ。何してるのよ、早く行きなさいったら……!」どこまでも優しい兄の姿が完全に見えなくなるまで、アムヤも右手を挙げ続けた。[04]ひとりマカオの夕暮れを楽しんでいた因香は、夕方のドリンクガールがどうなったのかが気になり、部屋には戻らずカジノ場へと足を運んだ。出会った場所には別のドリンクガールがいた。そもそも名前を訊いていなかったので、特徴を伝えた上で、彼女がいまどこにいるのか尋ねてみる。すると意外なことばが返ってきた。「それならルーシーね。あの子なら、さっき病院へ行ったわ」思い掛けない場所を告げられ、因香は自分のヒアリングが正しかったのかいまいち自信が持てず、相手の単語を鸚鵡返すしかなかった。「"the hospital"?」「クソ男に暴力を振るわれたのよ! 可哀想に顔を殴られて、よろめいちゃったの。その時受け身を取ろうとしたけど、失敗して手首を捻ったみたいで」暴力、と聞いて因香の背筋がぞわりと冷えた。それはあれか、例の底辺ディーラーの仕業なのか。「それって、底辺ディーラーにやられたの?」「そう! フランクよ! あいつ、絶対に許せないわ。ルーシーに付き添ってあげたかったけど、私、学校代を払うためにお金を稼がなきゃいけなくて……」唇を噛み締めるドリンクガールは目に涙を浮かべていた。許せないと憤りつつも、身動きが取れない己のことも同じように憎んでいるようで、やるせなくなる。「自分を責めちゃ駄目よ。ね? 学費を稼いでるあなたは立派で偉いと思う。本当よ。それに友人想いだわ。大丈夫、ルーシーも分かってくれてるわよ」因香の真摯な目に説得力を見出したのか、ドリンクガールは少し躊躇ったのちに、こくんと頷く。「フランクがルーシーを追って行ったという可能性はどう? あるかしら?」「ううん。それはないわ。だって支配人がルーシーを病院に連れて行ってくれたもの。フランクは支配人が苦手なの。一緒に行くはずないわ!」因香は確信した。ピット・ボスと支配人は別だ。ピット・ボスと底辺ディーラーのフランクは懇意の関係にあるが、支配人はそうではないらしい。ならばルーシーは安全だ。今のところは、という条件つきではあるが。「そのフランクはどこへ行ったの?」「分からないのよ。ルーシーを殴って、そのままどこかへ行ってしまったから」途方に暮れた2人は「はぁ」と同じタイミングで溜息をつくしかなかった。「よぉカレン」常連客の男性が因香の横に割って話しかけてきた。「あら、いらっしゃい」「なぁ、ここへ来る時に女性をナンパしてる男がいたんだけどさぁ」「あのね、申し訳ないんだけど、いま取り込んでるの」「待って。えぇと、カレンさん? ちょっと待って。どうもその話引っ掛かるわ。その男、どこでナンパしてたの?」ドリンクガールより先に、見知らぬ女性客から質問されるとは思ってもみなかったのだろう。一瞬気圧されたものの、すぐに方角を提示した。「ホテル入り口を右に曲がって、2ブロック行ったとこだよ」「近いわね」「男の顔、どっかで見たことあるなぁと思ってたんだけど、いま思い出したよ。あれ、ブラックジャックのディーラーじゃないかな」反射的に因香はドリンクガールのカレンと顔を見合わせる。間違いない、フランクだ。「ありがと!」因香は礼を言って身を翻すとカジノ場から姿を消した。カレンも追いたかったが、仕事を放棄するわけにはいかない。改めて情報提供者を見つめ返す。「ありがとう、助かったわ」「あのディーラーを探してたのか?」「うん。そんなとこ」カレンの口から、それ以上語られることはなかった。男性客は想い人が心ここにあらずだと気付くとスツールから下り、スロットマシンの方へと向かって行った。「……ルーシーも、さっきの女性も、フランクに目を付けらてしまった女性も……どうか無事でありますように」敬虔なカトリックの信者らしく素早く十字を切ると、強く女性たちの身の安全を願う。どうか神の加護があらんことを、と。[05]「くそったれ!」吐き出された粗暴なことばと共に、フランクは足元に転がっていたアルミ缶を力強く蹴り飛ばした。それは放物線を描いてどこかへと飛んでいく。見えなくなった缶が、さきほど自分の前から逃げて行ったドリンクガールの姿と重なり、さらに苛立ち度が増す。あの女め、返す返すも憎らしい。今日は仕事が終わったら待ってろよ。そう前もって言い含めておいたのに、こそこそと帰る支度をしていた。おいと声を掛けるとノー! と睨みつけてきた。あまつさえ逃げようとした。だから分からせてやったのだ。逆えばどうなるかを。女運もツイてなければ、勝負運の方もからっきしだった。オリエント美女の客の所為で、フランクの今日の売り上げはマイナスになってしまった。「むかつくぜ。ったく」どこかで女でも引っ掛けるか。フランクが下卑た笑みを浮かべながら周囲を見回すと、暗闇の中、足早に近付いて来る軽やかな靴の音とシルエットが視界に入った。顔は見えないが、細身で、髪をふわふわとなびかせている。足さばきから察するに、若い女に違いない。「よぉ、ミズ」女の行く手を阻むように、フランクは自身の身体を滑り込ませた。突然の障害物の登場に、女性は驚いて足を止めた。だがそれが間違いだった。本来なら、押しのけるようにすり抜けなければならなかったのだ。隙を見せてしまった女性はフランクの格好の的になり果ててしまい、ただでさえ不快な距離感がさらに狭まってしまう。「な、なんですか……?」返ってきたのは英語だった。やったぜ、とフランクはほくそ笑む。自分好みの声だったからだ。さぞかし艶めいた感嘆の声を紡いでくれることだろう。「一緒に酒でも飲まないか? いい店知ってんだ」馴れ馴れしく肩を抱き、歩かせようとする。けれども女の方は逆らうように抵抗した。『てこでも動くものですか』とばかりに地面から足を上げようとしない。そう、動いてしまったら負けなのだ。ただでさえカッカしていたフランクは、思い通りにならない女の態度に今度こそ激昂した。腰に腕を回すと、ほら行くぞと力任せの行動に出たのだ。恐怖で声を上げることも出来ない女性を助けようとする通行人もいなかった。「トオゴ……トオゴぉ……」落胆した女が未知の言葉を呟いていたが、トーゴという単語に心当たりがないフランクは耳も貸さなかった。一番近いホテルはどこだろうと、キョロキョロするのに忙しかったせいでもある。[07]――ツキを手放さなかったせいだ。アムヤは半ばパニックになりながらも己を責め続けていた。(あの時、彼女のアドバイスを断っておけば良かったんだわ。さっさと運を捨てておけば、こんなことにはならなかった――)後悔してもし切れない。悪い出来事は現在進行形で振りかかっている。問題は、その悪運がどこまで及ぶのか、だ。最悪のケースはホテルに連れ込まれてしまうことだ。腕力では勝てない。それをいま、身をもって痛感中だ。自分に残された危機脱出方法はただひとつ。まだ塞がれていない口だ。誰かに届けと祈りながら、アムヤは助けを呼んだ。結果は無残なものだった。数ヶ国語を駆使して助けを呼んでいるのに誰からの反応もない。ひとけはあるはずなのに。「ヘルプ! バチャーオー! ジィウ・ミン・ア! ソコーホ! オ・スクール! イムダート……!」「黙って歩けよ」「ナジュダ……。ヒルフェ……。ヘルプ……ヘルプ・ミー。バチャーオー……バチャーオ、トオゴぉ……」(でも彼は行ってしまった。日本に。もう助けて貰えない。彼はもう、日本に……)「助けて……助けて……」日本語で呼び掛けても来ないことは分かっていた。それでもあの笑顔に逢いたい。あの声に救われるから、もう一度逢いたいのに。「待ってて。いま助けるからね」聴き間違いかと思った。日本語で助けを求めて、日本語がすぐに返ってくるはずがないのだ。脳が勝手に翻訳してしまったに違いないと思い直し、それでも藁に縋るように声のした方を見る。するとこちらに近付いて来る影があった。(トオゴ?)ではない、とすぐに分かった。靴の音はハイヒールだ。相手は女性だった。「ねぇ、その子を離してくんない?」彼女は確かに日本語を話していたはず。それなのに、解放しろと告げた文章は英語だった。そうか、フランクに向けて言っているのかとアムヤは気付く。「お前は? あぁ、さっきカジノにいた女か。俺はいま猛烈にむしゃくしゃしてるんだよ。こいつを離せだ? 何言ってやがる。寧ろお前も一緒に来い」沸々と苛立っているのが分かり、アムヤはぞっとする。いけない、これ以上彼を刺激しては。そんなアムヤの胸中など露知らず、相対する因香は「あ、そう」とだけ呟いた。対話不可の判断を下したように見える。ツカツカと近寄る因香は、一体何を考えているのか。策でもあるのか。相手は自分より大分図体が大きいというのに。とうとうゼロ距離まで詰め寄ってきてしまった。因香は相手を上目に見やる。「お願いです。どうかその子を離してください」「やだね。断る」「……私、お願いはしたわよ」はぁ、と吐息をつくと、やおら右膝を上げ、フランクの靴を踏みつけた。声にならない悲鳴がフランクから漏れる。何をそんなにもんどり打っているのかと身を捩って見たアムヤは唖然とした。因香の履いていた靴はハイヒールと言えども凶器のような類で、踏まれれば相当痛そうな鋭利系ピンヒールだった。太い釘が刺さったのと同じではないだろうか。よくこんな高いヒールを履いて歩けるものだと感心すらしてしまう。「今よ!」アムヤの腕を掴んだ因香は引っ張られるがまま足を動かす。最初の数歩こそ因香に引き摺られていたものの、思考を切り替え、体勢を立て直している数秒を経ると、自らの意志で逃走することができた。「灯台もと暗し。ホテルに戻りましょう。事情を説明すれば、匿って貰えるわ」アムヤがそう言うと、因香もその答えに達していたようで、2人はサングラシアまで全速力で走り切った。[08]とにかく時間との勝負だった。サングラシアのホテルに入るなり因香とアムヤはフロント係に事情を説明し、自分たちが被害者であることを訴えた。ありがたいことに、事の重大さがフロント係に伝わったようで、すぐさまホテルの支配人を呼んでくれた。ホテル側も、カジノ従業員であるフランクの話は耳にしたことがあったのだろう。その証拠に因香たちが疑われることはなく、丁寧な詫びが告げられた。詫びよりも、2人が欲しいのは安寧だった。支配人は姉妹店での滞在を提案し、2人は承諾した。姉妹店まではホテルの車で送ってくれるという。結局姉妹店に到着するまで1時間が慌ただしく過ぎてしまったが、その甲斐あってかフランクもここまでは来れまいと確信できる。くたくたの体に活を入れ、2人はホテル内の天津料理店で食事をすることにした。「まずはお疲れさま」「お疲れさま……」お互い労り合うも、その言葉に覇気はない。疲労感が勝り、食べ物も胃の調子を優遇する粥と養命酒を選ぶ始末だった。それでも味の方は抜群で、ぺろりと平らげてしまったが。「不思議だわ。どうしてあなたがあそこに現れたのか」アムヤは店員に我儘を言って淹れて貰った白湯を飲みながら因香に尋ねる。「それはさっきホテルの支配人にも説明したじゃない。カジノのドリンクガールと話してる最中に、あの男の情報を掴んだからで……」ノー、とはっきり遮る声には、少しばかり苛立ちが含まれているように思えた。どうもアムヤは機嫌が悪いようだ。仕方ないか、と因香は思う。あれだけ散々な目に遭えば、気持ちが腐るのも頷けるというものだ。「それは『流れ』でしょう。私が知りたいのは、『あなたが私を助けた理由』」「あー……そこ」つまり、こういうことか? 因香にとってアムヤは赤の他人だ。カジノ場で一度アドバイスをしたが、ただそれだけの関係である。それなのに、自分の危険を顧みず、なぜ大男と対峙するに至ったのか――。そこを聞きたいのだろう。「あなたが『助けて』って言ったから」「……そうね」言った。確かに言った。英語に始まりヒンドゥー語、フランス語、ドイツ語、……記憶が定かではないがトルコ語でも口走った気がする。「あの時、あなたが日本語で『助けて』って言うものだから、心底驚いちゃった。日本語が話せるのね」「日本に住んでこともあったから」「へぇ。マルチリンガルなのね。凄い、初めて会ったわ。……あ、そうでもないか。日本にもいたっけ。でも彼の場合はトリリンガルだったのかな」「あなたは日本人なの?」アムヤからの質問に、因香はギョッと目を大きく見開いた。「どっからどう見ても日本人の顔立ち、立ち居振る舞いでしょ? 見て分かんない? めっちゃ大和撫子じゃない!?」本気で訴える因香の迫力に、アムヤは一拍置いて「ふふっ」と笑う。心の底から面白かった。「大和撫子って、しおらしくて、はにかみ屋さんみたいな女性を言うんじゃなかったかしら? どう見てもあなたはグラディエーターだったわ」「グラディエーターって……! せめてララ・クロフトとかさぁ……」「ごめんごめん。何もラッセル・クロウ張りだって言ってるわけじゃないのよ。戦士のようだったと言いたかっただけで」ちゃんとアンジーっぽかったわ、とフォローを入れてから、アムヤは続ける。「オリエンタルな雰囲気を纏っていたし、正直に言うと日本人だとは思わなかったわ」「それは良く言われる」うん、と深く頷く因香である。「ほんと言うとね、私、カジノ場でわざと負けていたのよ」アムヤの告白に驚いた因香は、案の定何故かと問い掛けてきた。「ツキを手放すための儀式だったの」そう聞いても、いまいちピンとこない。ツキを手放したら勿体無いじゃないか、というのが因香の率直な感想だったからだ。「陰と陽、とでも言えば分かりやすいかしら」「あー、なんとなく分かるかも。要はあれでしょ。何事もバランスってやつ」「正解。私は運が強過ぎるの。昔から、善いことだけが立て続けに起こるラッキーガールだった。でもそんなの不公平じゃない?」「自分だけ無尽蔵に幸せが訪れるのは他の人からしたら申し訳ないことだ、って? だからわざとギャンブルで負けて悪い出来事を被ってた?」「そう」「でもそれってさ……。前提が違う気がする」「前提が……違う?」「自分からわざわざ不幸を取りに行くって、『遠慮しい』だなって思う」「え……」ズバズバと切り込む物の言い方に、アムヤは戸惑いを覚えた。ここまで本音で感想を述べられたのは初めてのことで、理解が追い付かない。「善いことだけが起こる? いやいや、そんなわけないから。そこは個人の解釈の問題だよ。あなたがそう思い込んでるだけ」「……」「例えばあなたに悪いことが起きたとする。でもあなたの場合、そこから何かを得ようとしてるんじゃない? だから結果的に損した気分にならない」「損した気分にならない?」「うん。不運な出来事だったはずなのに、『良い経験をさせて貰った』とか『今後の為に活かそう』とか、最終的にそうやって前向きになってない?」「あ……」思い至る節があったのか、アムヤは口元に手を当てた。「何かを学んだら、ひとって『勉強になったわー』とか思うわけよ。つまり成長よね。それをあなたは難なく繰り返してきた。それが『幸運スパイラル』」「つまり私の強運の正体は……私の捉え方によるものだと言いたいのね?」「そう。本人は一切気付いていないポジティブシンキングが、あなたの幸運体質の正体!」「……」「だからー、私が言いたいのはね? わざとギャンブルで負けなくてもいいってこと! 自ら不運を引き寄せに行かなくてもいいんだってことよ」アムヤの鼻をちょんと人差し指でつついてウインクを寄越す因香だったが、アムヤとしてはそんな軽いジェスチャーを受け止められないのが現状だ。「……私の負けギャンブルは無駄な行為だった?」「いや、無駄にしてたのは行為っていうよりお金じゃない?」「……そうね。お金……えぇ、そうね。無駄にしてたわね……」湯呑みを煽るが、とっくに中身は空っぽだった。アムヤは早鐘のように脈打つ鼓動を静めようと深呼吸を何度も繰り返す。「……ごめんなさい。あなたの言葉が衝撃的で……。でも、そうかもしれない。この世は陰陽で出来ているのだと思ってきたけど……」「あ、すみませーん。チャイナドレスのおねーさーん、白湯をもう一杯くださーい」「陽に溢れてても……陰を避けて通っても良かったの……?」「あと、杏露酒くださーい。……ん? うん、そうそう、そんな感じ」一瞬『ひとの話を聞いていないだろう』とも思ったが、よくよく考えれば白湯はアムヤの為に注文してくれたのだ。随分と世話焼きではないか。「……前言撤回するわ。あなたは正真正銘、大和撫子だと思う」「え? 急にどうしたの」「別に。とにかく、新しい物の見方というか、物は考えようだなということを、あなたから教わったわ。ありがとう」「それそれ。早速幸運スパイラル実演中。ギャンブルに負けてツキを手放せなかったーって悔しがってた割に、最後にはこうやって気付きを得ちゃってる」「……参ったわ。降参よ。本当ね」「もう二度とギャンブルで負けようとしないでよ? あと、自分から不幸になりに行くのも禁止だからね!」「はいはい、分かりました」肩を竦めて頷くと、丁度店員が白湯と杏露酒を持って来てくれた。2人は全く異なるコップ同士を合わせる。「2人の出逢いに」「乾杯」かちん、と澄んだ音が鳴り響いた。[09]翌日、ふかふかの高級ベッドで目覚めた因香は、ベッドを椅子代わりにして腰掛けると大きな溜息を吐いた。「しまった……」不覚も不覚だった。『2人の出逢いに乾杯』までしたというのに、相手の名前や国籍を一切聞いていないことに気付いたのだ。加えて自分も名乗らなかった。世界は広い。二度と彼女と会うことはないだろう。だからこそ、聞いておかなかったことが悔やまれて仕方ない。どの部屋を取ったかは知っている。だが因香は思うのだ。きっと彼女は既にチェックアウトした後だろうと。例えいっとき意気投合したとしても、彼女からは風来坊のような気質を感じた。彼女は渡り鳥に似ている。世界中を渡り行く探求者だ。「せめて名前だけでも聞いておけばよかった……」そうすれば、彼女が幻だったかもしれないなんて思わなくて済むのに。因香は部屋を見渡した。昨日の出来事が本当にあったのだと証明できるものは、宛がわれたこの部屋――サングラシア姉妹店である、このスイートルームにいることだけだった。決して忘れないように、因香は机上に置かれたホテルの刻印入り絵葉書を1枚だけ失敬すると、自分の手帳に挟み込んだ。これがあれば、彼女を忘れることはないだろう。そうだ、決して忘れない。そう思ったら、元気が出てきた。因香の口元が自然と弧を描く。「……さーて! シャワーでも浴びますか!」ぐんと腕を天上に向かって伸ばし、因香は浴室へと向かった。[10]惹かれなかったと言えば嘘になる。誰に? 助けて貰った恩人にだ。アムヤは明けて間もない時間から既にマカオを出国していた。向かうはインド、ニューデリー。アムヤにしてみれば大きな――本当に大きな、転換点とも言える出来事に遭遇した。自分の根本を見直さなければならない事象に。たった数分でマカオが完全に見えなくなる。それは少し寂しいような気もした。(不思議だわ。今までは、次に行く国に想いを馳せてわくわくしていたのに……。今回だけは、後ろ髪を引かれてる)それは彼女の存在が影響しているのだろうか。(彼女、日本人だって言ってた。日本……日本か)かつて住んでいた故郷。そして何の因果か、愛する兄が向かった国。(私が向かう先は、本当にインドで良いの?)たった1日で、日本に行きたい欲が生じてしまった。いま南アメリカにいる、もうひとりの兄のように、自分も軽やかに行き先を決められたなら……。(私がインドでしたいことって……?)このまま戻ったところで特にない気がする。未来が見い出せない。渡航前と同じ毎日がまた始まり、繰り返されるだけだ。(『言語学とパッションがあればどうにでもなる』が兄の持論だった。そうよね、そうかもしれない)よく考えよう。幸いにもフライト時間は12時間。時間だけはたっぷりあるのだから。そうは思いつつも、熟考よりも勘の方が、時には正しい判断が下せることを、アムヤはよく知っていた。2019.10.05
2020.02.16
コメント(0)
-
G2 (―) 【橋頭堡】
日常編 (―) 【橋頭堡】―キョウトウホ―自宅の玄関を開け、最初に視界に入るのは、1本の南天の木だった。40年前、南雲の妻が苗を買い、そこから育てた代物だ。≪難を転ずる≫ことから、『縁起のよい木とされている』という話を聞いた妻は、新居の庭にそれを置いた。南天は大木にならないので、南雲は始め、それほどこの木を好きになれなかった。松のように、どっしりと構えたものを好んだ彼は、南天の大きさに物足りなさを感じ、弱々しい木と捉えていたのだ。けれども、雪を被った南天の姿に虜となった今では、毎年のように赤い実がつくのを誰よりも待ち侘びている。今は11月。急に冷え込んだ天気の影響で、紅葉した南天の葉は、霜で縁取られていた。*2年前に定年を迎えた南雲は、62歳になった今、知人の紹介で警備員をしている。徒歩5分という、通勤に便利な近距離。警備員仲間は南雲と同じ境遇の人物が集まっているため人間関係も良好だ。勤務計画さえ上手く立ててしまえば、数日休んで連泊旅行することも出来る。何の憂いもない南雲の日常。けれどもここ最近、南雲を困らせているものがある。それは……。「おはようございます、南雲さん」伊神はロングコートのポケットから社員証を取り出し、従業員入り口から数メートルほど進んだ所で人の出入りをチェックしている南雲に呼び掛けた。ユナイソンの従業員を始め、荷積み業者やメーカーの営業が必ず通らなければならない、関所の役目を果たしている区域。そこに2点ほど恵まれないことがあった。問題は、入り口にある。*≪従業員専用≫というからには、客には見せてはならない部分を預っているという意味に他ならない。品物の在庫倉庫、生肉や鮮魚の加工場……つまり≪バックヤード≫を兼ねているため、人物以外にも、商品すら全て、ここを通らなければならない。≪警備員≫が人物をチェックし、品物をチェックする≪検収≫へと流れていく仕組みだ。様々な物品を通さなければならない為、入り口はとても広い。開店前に品物が出入りする、いわゆる≪第一便(イチビン)≫が、トラックから続々と運び込まれる時間だが、今日などは霜が降りた、特に寒い日。入り口が北側に位置するため、寒さが尚更堪える。仕事の内容には、遣り甲斐がある。けれども木製の簡易作業台の前に立つその姿は、お世辞にもサマにはなっているとは言えない。椅子などない。完全な立ち仕事だ。それが最近、特にきつくなってきている。ストーブはあるにはあるが、四面中一面が壁なし状態では、とても追いつかない。警備服の上にコートを羽織った南雲は、提示された社員証を確認してから伊神に答えた。「おはよう。今日は一段と寒いね」「本当、寒いですね。南雲さん、風邪なんてひかないで下さいね」「ありがとう」「そうだ。これ、使い掛けで申し訳ないですけど、どうぞ」伊神がもう片方のポケットから取り出したのは、携帯用のカイロだった。「マンション出た頃に封を開けたので、夕方まで大丈夫ですよ」「だが、それだとキミが……」「オレなら大丈夫。これでも一応、毎日走って抵抗力つけてるし」辞退する南雲の手に、半ば強引にカイロを押し付けると、伊神は男子ロッカーへと足を進めて行った。「……あたたかいなぁ……」それは人の心だったり、画期的な携帯保温器具だったり。南雲はシワが目立ち始めた両手で、カイロを包み込んだ。*あらかた荷物が収容された、開店時間の午前10時。一面開いていたシャッターがゆっくりと下り始める。次にこのシャッターが開くのは、≪第二便(ニビン)≫が運び込まれる午後1時だ。今では人間が出入りするためのドアが、たまに開けられるぐらいの頻度に落ち着いた。先に出勤していた同僚たちは既に仕事に取り掛かっていた。事務所の壊れた電話を直したり、ごみが車輪に絡まって動かなくなった買い物カートを直したりと、さまざまだ。繋ぎの服に着替えた伊神だったが、今のところ出番はないようだ。社内用携帯をポケットに収めると、メンテナンス室を後にした。伊神の控え室でもある≪メンテナンス室≫も、≪警備≫や≪検収≫の近くにある。その為、伊神は南雲たち警備員とも仲がいい。メンテナンス室を出た伊神は、一段落ついた南雲の名を呼んだ。「あぁ、伊神クンか」伊神の姿を認めた南雲の手には、カイロが握り締められていた。その様子を見た伊神は、呼気の白さに気付く。「シャッターが下りても、寒さは変わりませんね」「そうだねぇ。でもさっきキミに貰ったカイロのお陰で、手先が温かいよ」「本当? それはよかった」笑顔を湛えた伊神だったが、ふとその顔が引き締まる。「どうしたんだい、伊神クン?」伊神の変化に気付き、声を掛けるものの、呼ばれた本人は意に介さない。「せめて風だけでも、どうにか出来ないかな……?」そう呟くのである。「伊神クン?」「え? あぁ、すみません。えっと……何の話でしたっけ?」「いや、話と言うか……。あぁ、そうだ。今日はね、南天の木に霜が降ってたんだよ。葉の先にね、ビッシリと、こう……」「ナンテン……?」「あぁ、南天だよ」「太い幹のナンテンは、確か……材木になりますよね……?」「そうなのかい? いや、すまない。そこまでは知らないなぁ……」「箸なんかに使われていますね。オレの母は宗教上、箸を持ってはいませんでしたけど。祖母がオレにプレゼントしてくれて……」「キミの流暢な日本語を聞いていると、本当にインド人とのハーフなのかと驚いてしまうよ」「箸……箸か……。……端?」「ハシ?」伊神の視線が南雲を定める。考え事をしている伊神の癖だった。色男に真っ向からジッと見詰められ、南雲は若干落ち着かない。「ハシが、どうしたんだい、伊神クン?」「そうか、机の両端を囲ってしまえばいいんだ! それだけでも風は防げる」「な、なんの話だい?」「その机です。少し手を加えてもいいですか?」「手を加える?」「えぇ。この机の両端に、頭の高さまでのベニヤ板、もしくは透明ガラスをこしらえるんです。それで多少なりとも風除けになります。色を塗り直せば見栄えもよくなるかも。逆に夏はそれがあると暑いので、取り外し出来るように工夫して」「直に風が当たらなくなるのかい? それは皆、喜ぶよ!」「許可とか……いるのかな? 店長に伺ってみればいいかな……? 許可が下りたら、早速作業を始めます」「もし許可が下りなかったとしても、伊神クンのその気持ちだけで十分だよ」「許可が下りることを願いましょう」伊神が微笑む。彼が言葉にすると、本当に実現出来そうに思えるから不思議だ。つられる様に、南雲も微笑んだ。*伊神と南雲の祈りは通じ、あっさりと許可が下りた。寧ろ店長は気付かなかった落ち度を詫びるほどである。早速伊神は作業に取り掛かり、次の日の昼には塗装作業すら終えてしまっていた。他のメンテナンスの仕事が入って来なかったのも、順調な作業に拍車をかけた要因だった。かくしてヴァージョンアップした警備の作業台は警備員全員から重宝がられ、伊神には大賛辞が送られた。南雲の憂いの1つはこうして解消された。立ち仕事という悩みはまだ残っているものの、妻の勧めで始めた登山のお陰で、それほどめげない足腰にはなってきている。今日もまた1日が始まる。玄関を開けるのだ。そして、南天の木を見よう。本格的な冬の訪れとともに、その赤い実が弾けんばかりにたわわに実る姿を見守ろう。きっと今年も、白い雪が赤い実を覆い、新聞を取りに行った妻が「あなた!」と息せき切って呼びに来るだろうから。2008.09.152020.02.16 改稿
2020.02.16
コメント(0)
-
G2 (杣) 【茶飯事】
日常編 (杣) 【茶飯事】―サハンジ―「ん……」枕元付近で鳴るスマホの音で目を覚ます。音の方向に手を伸ばし、まどろみの中、当てずっぽうで電話に出た。「……ぁい、杣庄ですが……」「ソマ!」朝から喚く知り合いの女性は限られている。ヒステリーのあまり、般若の形相になっていなければいいのだが。「どうせ起こすなら、おはよう進クンぐらい言えないんスか、八女サン」「何が進クンよ! ご飯しか進まないわよ!」「耳元で喚かないで下さいよ……っていうか懐かしいですね、そのCM。味の素でしたっけ……」「そんなことはどうでもいいの。会社のPHSどうしたの?」「ピッチ? ……あぁ、すんません。昨日そのまま持って帰って来ちまった……」「しかも、鮮魚のじゃなくて、あれはワンちゃんのPHSでしょう!」「あーそう言えばそうでしたねー……」「今すぐ持って来なさい」「……はぁ?」「反論は許さないわよ! ついでに手伝えって、あなたの上司が言ってるわよ」嘘みたいな展開に、一気に頭が覚醒した。「待て待て待て待て。今日は休みなんだけど? どんな無茶振りッスか」「チラシの駅弁が間違って緑店に配送されたらしいの。回収しがてらPHSも持って来なさい」「……人遣い荒……」「祝日がどれだけ忙しいか知らないワケじゃないでしょう? 1人休みを謳歌してるなんて許さないわ」「……どんなイチャモンだよ……。わかりましたよー、行きゃいいんでしょ……」YESが聞ければそれで満足なのか、電話は一方的に切られた。特に予定はなかったものの、何が悲しくて職場まで行かなければならないんだと挫けそうになりながらも喝を入れ、掛け布団を剥ぎ取った。*ドアの向こうに八女サンの頭が見えた。俺に気付いてドアを開けて迎え入れてくれた。「開店10分前。上出来よ、ソマ!」「段ボール2箱分って伝票にあったけど、それでよかったのか? 俺、今回の駅弁発注にはノータッチだから、言われるがまま持って来た」「バッチリよ!」「あとこれ、不破の野郎のピッチな」八女サンに預けようとジーンズのポケットから年季の入った社内用PHSを取り出す。するとタイミングよく不破犬君が廊下を通りかかった。そうだ、透子がいるPOSルームを、あいつが見ないはずがない。案の定室内に視線を走らせたかと思うと、目聡く透子を見付け、手を振った。「おい、透子」「分かってる。呼んであげるわ」俺が手招きしたところであいつは従わないだろう。……いや、透子が近くにいるなら話は別か。だがとにもかくにも透子自ら勝手出てくれた。透子が不破に向かって手招きすると、尻尾を振った犬のように一目散に入室してきた。「潮さん、何かご用ですか?」「はいこれ。あんたのピッチ」「あぁ、ソマ先輩が間違って持って返ったやつですね」「人聞き悪いこと言うな。鮮魚のが壊れて修理に出したから、数日ドライのを借りることになっただけだろうが」「あぁ、ソマ先輩。いたんですか。朝からご苦労様です」いま気付きましたと言わんばかりの投げやりな挨拶を食らう。「そこは『お疲れ様です』だろ、糞餓鬼」「ちゃんと相手を選んで使い分けているので、ご指導は不要です」営業スマイルで牽制しやがる。「てめぇ……」引きつった顔で臨戦態勢に入る俺の背中を後ろから突くのは透子だった。「まぁまぁ。ソマ、ありがとね。ほんとに助かったよ」「お前だけだぜ、俺のことを労わってくれるのは。ざまーみろ糞餓鬼、悔しかったらお前も透子の役に立ってみやがれ」「……どこまで子供なんですか、貴方って人は……」どちらが年上か分からない、冷たい目を向ける不破犬君。そこで店内中に開店3分前を告げるチャイムが鳴り響く。「さぁ、イラッシャイマセの挨拶に行くわよー」ユナイソン名物、従業員によるお客様の一斉お出迎えだ。俺が「頑張れよ」と背中を叩く。透子は親指を突き立て、POSルームを飛び出した。今日もユナイソンの1日が始まる。2009.01.172020.02.16 改稿
2020.02.16
コメント(0)
-
G2 (―) 【青写真】
日常編 (―) 【青写真】―アオジャシン―「駄目だ駄目だ駄目だ駄目だ、なんだそのへなちょこな切り方は! てめぇに切らせる魚なんざ、もうねぇよっ。出てけー!」怒号によって新入社員の杣庄を鮮魚の作業所から追い出したのは来栖勝喜(くるすしょうき)。38歳、鮮魚チーフである。今にも出刃包丁で襲いかからんとする鬼の形相を目の当たりにして、杣庄は口元をひくつかせ、命辛々逃げ出した。「くっそ、これで何回目だよ!」後ろ手に引き戸を閉め、息を整えながら扉にもたれかかる。「なんだァ、ソマ。まーたショウキの野郎を怒らせたのかよ。飽きもせず、毎度毎度よくやるなァ」その姿を見て呵呵大笑したのは青果売り場のチーフ、壬生恒彦(みぶつねひこ)、44歳。売り場が隣りなので接触率はどうしたって高い。壬生の隣りには、ユナイソン岐阜店きっての高嶺の花と揶揄される八女芙蓉がいた。杣庄を見つめたまま、今のやり取りを見て唖然としている。連日鮮魚売り場で繰り広げられる『来栖・杣庄の戦い』を知らないのだろう。無理もない。彼女が受け持つPOSルームからこの戦場は離れている。杣庄は、心の中でチッと舌を打った。片想いの相手の前で、なんとも情けない姿を曝け出してしまったものだ。「別に、怒らせたいわけじゃ……ないッス……」杣庄が顔をぷいと背け、もごもごと言い訳をしていると、壬生はボールペンの蓋を口に咥え、紙にさらさらと書き付けながら「ま、アイツが勝手に怒ってンだから仕方ねぇわな」と、慰めになっているようで、なっていないことを言う。「ほら。出来たぞ、フヨウ」「ありがとうございます」杣庄は芙蓉を盗み見た。壬生から受け取った紙をバインダに挟むと、小脇に抱え、青果の作業場から出て行くところだった。己の手から漂う血生臭い魚の臭いとは違って、その残り香は、夏の草原を彷彿とさせる。あまりにも住む世界が違いすぎて、気が滅入った。このまま片想いを続けても、この恋は実らないだろう。そう思うと落胆せざるを得ない。なにせたった今、仕事が出来ない場面をバッチリ見られたばかりだ。ユナイソンに入社して鮮魚に配属されたものの、料理学校を出たわけでもなく、畑違いの商学部出身。私生活では幼い頃から家事をしてきたつもりだったが、いざ仕事となると、これがちっとも使えない。メジャーどころはともかく、マイナーな魚の名前は覚えづらく、見分けもつきにくい。さらに季節や出世魚など、知識も蓄えなければならない。魚のさばき方も三枚おろしと刺身を造るのがやっとだったのに、その上迅速さと丁寧さが求められ、挙句「切り方がなってない」と部屋から追い出される始末。そもそも魚によってさばき方は違うのだから、次から次へと魚を寄越されても、切り方に関する記憶を引き出す時間くらいは与えて欲しいものだ。「いつまでしみったれた顔してやがる。とっとと中入ってショウキに詫び入れて来い、詫び」来栖といい、壬生といい、どうにも自分の周りには体育会系思考回路の持ち主が多くて困る。血気盛ん過ぎるのも考えものだ。やれやれと思いつつ、壬生の言うことは理にかなっていたので、杣庄は壬生に目礼をしてから大きく深呼吸をし、再び作業場へと戻って行った。*「お兄ちゃん……またなの……?」泣きべそに近い悲鳴は、唄の口から出た。食卓に並べられた大量のまぐろの切り落としを見て眉尻を下げた唄は、床にへたり込みかねない雰囲気でもある。「唄、滅多なことを言うもんじゃねぇよ。立派な高級魚だ。そんなこと言ってるとバチが当たるぞ」唄のあとから入って来た長女の茨が、いつものぞんざいな口調で妹を窘めた。茨の髪はシャワーを浴びたばかりで濡れている。犯人を確保した際、泥の中で格闘した彼女は帰宅早々湯船に浸かった。空腹と疲労で体力は限界寸前。肉だろうが魚だろうが、血・肉・骨になってくれるものは何であろうと大歓迎だ。「でもでも。これで18日間ぶっ通しでまぐろだよ? たまにぶりだったりマスだったり。でも結局は魚でしょ? さすがにお肉食べたいよ。栄養偏るよぉ」「ファーストフードでハンバーガー食べりゃ良いじゃねぇか」「駄目よ、お姉ちゃん。栄養過多だからそれは避けたい乙女心なの」唄の言い分は『食事の有無』からすれば食にあり付けるだけ贅沢であり我儘なのだが、『献立の観点』からすれば杣庄自身、申し訳ないと思わずにはいられない。「ウタから見たら綺麗に切れてるよ? これでもまだ汚い切り口なの? 駄目出ししてくる来栖さんって人の刺身とお兄ちゃんのとでは、どこがどう違うの?」一番始めに切った魚に比べれば、杣庄の腕はかなり上がった方だ。それでも20年の職人歴を誇るチーフとでは、比べるべくもない。そもそも杣庄が毎日切り続けているのは、客から「切り方が下手だから」と、返品を食らった手痛い出来事がきっかけだ。あの現実にはさすがに深く傷付き、帰宅途中に涙を零した。その時に誓ったのだ。毎日出来る限り、家でも練習しようと。弊害がなかったわけではない。唄が言うように連日魚料理になってしまっているし、さばき方の練習をするには1尾丸ごと買って自腹を切るしかない。今月は出費がかさむが、これも勉強代だ。「悪ィな、唄。付き合わせちまって」「……んーん。ウタこそ、ひどいこと言っちゃった。ごめんなさい、お兄ちゃん」贅沢のできない環境下なのに我儘を漏らしてしまった己の発言を恥じて、唄は素直に謝った。茨は唄の頭をポンポンと軽く叩き、フッと笑う。「……ほら、唄。いただきます。な?」「はぁーい。いただきますっ」協力を惜しまない姉と妹に心の中で感謝をして、杣庄も箸を取り、「いただきます」と手を合わせた。*近道などない。結局は実践の積み重ね、経験でしか能力は培われない。そのことに気付いた杣庄は信念を貫くかのように魚をさばき続け、杣庄家の食卓に魚が登場しなくなったのは、ひと月半が経った頃だった。上司である来栖からは相変わらず激しい叱責が飛ぶ。それでもこの頃になると、新入社員の分際では全部が全部、即応えられない難題であることも、杣庄は勘付いていた。応えられる範囲で全力を尽くし、無理だと思った部分は力不足と把握した上で切り捨てる。出来なかったオーダーに関しては、「課せられた宿題」としてメモ書きしておく。そうしておけば、後から復習することが可能だからだ。自ら取捨選択をするようになってからは、もともと備わっていた勘の鋭さも相まって、めきめきと上達し、吸収していった。更なる知識を求め、競りや市場への買い付け、寿司巡りなどへ赴く頻度が増えると、来栖の怒鳴り声は反比例するかのように激減した。それでも稀に大きなミスをしてしまい……、「ソマぁぁぁぁ、てめぇぇぇ」「す、すんません」「馬鹿タレ、1時間戻って来ンなぁ!」11時の段階で放逐され、昼食には早いが社員食堂へと避難する。さっき間違えたのはなぜだろう、どこの時点で誤ってしまったのだろう。トレーを脇にやり、メモ帳に思い付く限りの問題点を論(あげつら)っていると、「杣庄君」と自分を呼ぶ声があり、スッと紙コップが目の前に置かれた。並々と注がれているのはホットのコーヒーで、食堂内に設置されている自動販売機のそれに違いなかった。視線を上げればそこには思わぬ人物が立っていた。杣庄の想い人。心臓は早鐘を打ち始め、「え、あの、これは?」と問い返すだけで精一杯。芙蓉は杣庄が腰かけているテーブルの後ろに、彼とは背中合わせの形で着席する。自分の分も買い求めていたらしく、ことん、と紙コップを置く音が響いた。「もうお昼ご飯食べてるんだ? 早いのね」早いのは部屋を追い出されたからだ。来栖の命令には“頭を冷やして来い”、という意味合いもあった。だから仕方なく食べていただけ――。1時間の休憩が終わったら、気持ちを切り替えて仕事に臨む所存だ。けれどもそんな恥ずかしい姿、そう何度も晒せるはずもない。曖昧に言葉を濁すと、芙蓉は杣庄の心の内を読んだかのようにふふっと笑った。「さてはミスでもしちゃったのかしら、ルーキー君。来栖チーフは例えそれが褒め言葉だとしても叱ってるような言い方に聞こえちゃうから、余計大変よね」「あぁ、いや、でも俺の場合はミスの所為だから……」結局本当のことを告げる羽目になってしまった。きっと、背中合わせだからなのだ。目を見なくて済んでいる分、素直に吐き出せたのだろう。これが対面だったら、絶対本当のことなど言えなかった。「ミス……ミスかぁ。でも杣庄君は頑張ってるじゃない。毎日お魚買って、お家でさばいてるんでしょ? 偉いわね」なぜ芙蓉がそれを知っているのか、杣庄には分からない。同期の潮透子にも話していないし、芙蓉と仲が良く、杣庄自身とも仲の良い伊神十御にだって教えていない情報だ。杣庄が首を傾げていると、芙蓉はあっさりネタバレをした。「レジの子が教えてくれたの。杣庄君が毎日終業後に一尾まるごと買ってる……って」それでか、と腑に落ちた。じつは、従業員が通って良いレジは決まっている。何度も利用している内に、レジの子とも懇意になった。その子にだけは教えていた。自分でさばく為に購入しているのだと。「偉くなんかないッス。ただ、早く上手になりたいんで。それだけです」「立派な理由じゃない。充分偉いわよ。私は職務を全う出来なかったの。だからね、杣庄君を見てると、つい、「頑張って!」って、応援に力が入っちゃう」芙蓉の言葉には驚くことだらけだ。いち新入社員の自分に目を掛けてくれている。そうと知っただけで舞い踊りたくなる。その一方で、尋ねたくなる点もいくつかあった。「ありがとうございます。でもあの……職務を全う出来なかったって、どういう意味ですか?」「あー……」その「あー……」を言い換えると、こうだ。『ルーキー君、そこ、訊いちゃう?』。訊いたら嫌われる? でも知りたい。好きな人の過去。見たことのない一面。どうしたって知りたいし、どうしたって聴いてみたい。杣庄は「やっぱり聞くの、やめます」とは言わなかった。質問を取り下げなかった。芙蓉にしたって、『内緒』と言ってはぐらかすことも出来たのに、そうはしなかった。杣庄に真摯であろうとした。「私は、もともとサービスカウンターだったの」八女さんの制服姿を見てみたかった、と杣庄は思った。サービスカウンターは制服が可愛いことで有名だ。容姿端麗で成績が優秀な人物でないと就けない。憧れの女性が花形ポストに居たとは、思わぬ収穫だ。「異動したんですか」「したんじゃない。させられたの」芙蓉にしては珍しく、ムッとした口調で言い返した。「ここで働いていれば、いつか噂話で耳にすると思う。私のコト。けど、他人からの伝聞なんて尾ひれが付く。だったら自分から正しく説明した方がマシよね。だから話すんだけど……」聞きたかったのに、急に口を噤んでしまった。「……八女さん?」「ルーキー君は入社半年よね。こんなこと、言っても良いのかしらと思って」「いまさら何を……」「そうよね、ごめんなさい。実は、枕営業を拒んだからなの」「枕……。え?」頭が働いてくれない。処理しきれない。そりゃ確かに八女さんは綺麗なひとだ。だからそういう誘いもあるだろう。でも……。「うちの会社が、ですか? そういう手段を持ち掛けた?」「ルーキー君、先輩からの有り難い助言、ちゃんと聞いておきなさい。いつ何時役に立つか分からないから。大切なのは、鑑識眼を磨くこと」芙蓉と茨がダブる。鑑識眼を養えとは、刑事である姉自身も口を酸っぱくして何度も言っていた。世の中を渡る上で、五感が頼りになるのだと。そして第六感も働かすようにと。そうすれば、何が正しくて何が間違っているのか分かるから。自分がどのように動けば良いか、瞬間的に閃くから。「昼間から変なこと言ってごめんなさいね。私が言いたかったのは、私は序盤から挫けてしまったけど、一所懸命頑張ってる杣庄君には、その努力が認められるといいなってこと」芙蓉的には杣庄を励ましたつもりだろうが、彼女に惚れている立場からすれば、枕営業を指示した者を懲らしめてやりたいと誓うきっかけになったに過ぎない。訊けば芙蓉は教えてくれるだろうか? 『仇を取りたいので、八女さんにそんな馬鹿げた命令を下したヤツの名前を今ここで教えて下さい』と。そんな衝動に駆られつつ、しかしルーキー君と呼ばれているようではまだまだだな、とも思う。それこそ鑑識眼を磨いて、自分で突き止めてみせればいいのではないか? メモに加えよう。コミュニティの強化、と。岐阜店だけではなく、他店にも、本部にも顔が利くようにしておく。そうすれば自ずと情報は入ってくるだろう。そして、芙蓉は自身の失脚について“失敗”という言葉で一括りにしたが、それには異論を唱える杣庄だった。「あの、俺、頑張ります。でも八女さん。八女さんだって、今与えられた職務で頑張ってみえるじゃないですか。挫けてなんかいないですよ。そりゃ確かに枝は一度折れてしまったかもしれないけど、そこからまだ芽吹きます。きっと」そこで再び無言の芙蓉。かなりくさい発言だっただろうかと後悔し始める杣庄に、芙蓉の笑い声が重なった。「ふふっ……。ちょっと待って。ね、これ、始めは何の話しだったっけ?」「え、始めですか? 始めは俺が慰められてて……」「よね? なのに、何で今は形勢逆転してるの!? あっはは、おっかしい……!」「あ……」それは、俺が元気付けたかったからです。八女さんのことを。そんな本音など言えるはずもなく、もどかしく飲み込む。「あなたの未来が楽しみだわ。何か、しでかしてくれそうだもの」俺が積極的に何かを仕掛ける――?「……八女さん。実は俺、今ちょうど目標が出来たところです」「へぇ……!? どんな?」「今は言えないっす。ごめんなさい」「いいわ。見てるから」芙蓉には何気ない言葉だったに違いない。それでも杣庄には力強いエールになった。単なる後輩という位置付け。それでも想い人は将来に期待してくれている。「あの、八女さんって彼氏いるんですか?」「いないわよ」「いないんですか……。意外です」情報ゲット。しかも嬉しい答えだ。「そういうルーキー君こそ。彼女はいるの? あ、潮とか?」「透子? ありえないっす」「あら、どうして? ツンデレは苦手?」「確かにガミガミ系は苦手かも。姉貴がそういうタイプなんで」「じゃあ、ふんわりお嬢様系とか」「それも身内にいるんで、別に……」「ん……? あとはどんなタイプが残ってるっけ?」あなたです、とも言えず。「八女さん。アドバイス、ありがとうございます」心を込めて礼を述べるだけに留めておく。今は。「あと、コーヒーご馳走様っす」「どういたしまして」芙蓉がくれたコーヒーだ。しっかり味わおう。腕時計に目をやれば、休憩時間が終わろうとしていた。杣庄は席を立つ。「じゃあ、俺はこれで」「行ってらっしゃい」その時だけは、芙蓉の顔を見た。綺麗だよな、と思う。つくづく思い知らされる。高嶺の花だってこと。それでもいつか振り向かしたい。それはさっき掲げた目標のひとつ。あとは、八女芙蓉に枕営業を指示した人間を見付けだし、お灸を据える。そうそう、鮮魚のチーフになり、ゆくゆくは本部のバイヤーになることだって夢だ。そのためにはまず、来栖をぎゃふんと言わせないといけない。「道のりは長いな」やれやれと首を竦めつつも、階段を駆け下りる杣庄の足取りはどことなく軽やかだった。2014.01.172020.02.15 改稿
2020.02.15
コメント(0)
-
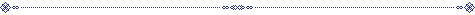
日常編【目次】
≪ Gentleman ≫(歴)歴視点 (柾)柾視点 (環)環視点 (邑)邑視点 (潮)潮視点 (犬)犬君視点 (芙)芙蓉視点 (杣)杣庄視点(迦)迦琳視点 (青)青柳視点 (―)複数視点or三人称 Gentleman2日常編 (―) 【青写真】―アオジャシン― 未来はきっと、この手の中に。日常編 (―) 【茶飯事】―サハンジ― この日常、依存の恐れあり。日常編 (伊) 【橋頭堡】―キョウトウホ― 大切な人には、生きやすい世界で笑っていて欲しいから。日常編 (―) 【澳門於】―マカオニオイテ― 偶然だろうが運命だろうが、重要なのは貴女に出逢った事実だけ。Gentleman3日常編 (―) 【New Year!】 お前が知らないだけで、俺は意外とお前を見てるぞ。日常編 (柾) 【Dark Past!】 それはまだ、運命の女に出逢ってなかった頃の話。日常編 (柾) 【Forbidden Fruit!】 手が届きそうな位置に、甘くて美味しそうな実があるの。日常編 (―) 【Various Men!】 紳士のままでいて欲しいの。日常編 (犬) 【One Day!】 いつもこんなんばっかですよ[犬君談]日常編 (潮) 【Impudent Talk!】 どうしたら小気味よく出し抜けるのかしら?日常編 (―) 【Find Out!】 看破はした。チェックメイトは任せるよ。日常編 (潮) 【I Gotcha!】 たまには、女優気分も良いかもね。日常編 (―) 【Fallin' Love!】 誰もが望む。これが最後の片想いになりますようにと。日常編 (―) 【Who Cares?】 誰が構うものか。日常編 (―) 【Sunny Tower!】 ねぇ、そのフレイバーを教えて!日常編 (―) 【Russian Roulette!】 アナタには、一生勝てないのかも?日常編 (凪) 【Jerk Around!】 一千万と恋の行方。日常編 (凪) 【Meow Meow!】 凪、黒猫、警報機、早朝の出来事。日常編 (―) 【Lovey-dovey Couple!】 なぜか憎めなくて。日常編 (潮) 【Don't Apologize!】 言い訳はなしよ。日常編 (邑) 【Brother Complex!】 ずっとあの頃のままだと思っていたのに。日常編 (―) 【Help Me!】 こちとら商人(あきんど)や! 売ったもん勝ちやでぇ!☆(ゝω・`)日常編 (歴) 【Christmas Eve!】 その感情を決めるのは、自分。日常編 (―) 【Double Happy!】 今年も祝える幸せ。日常編 (―) 【Happy Valentine!】 心を込めて。日常編 (―) 【Come Across!】 縁は、どこで繋がっているか分からない。だから手繰り寄せよう、引き延ばそう。日常編 (―) 【Canicular Days!】 恋いて焦がれて目を細む。蜃気楼に浮かぶ貴方の姿。日常編 (―) 【Show Me!】 あなたの傷を見せて。 日常編 (環) 【Unrequited Love!】 君への恋は、『過去の出来事』にしたはずだった。日常編 (―) 【Come On!】 こんな気持ちになるのは、決してあなただけではなくて。Gentleman4日常編 (青) 【社交的な、紳士然】 どこまで真似て良いものか?日常編 (迦) 【過去から、未来へ】 繋がると信じているから。 日常編 (―) 【遊びじゃ、ないの】 遊び? 本心? 見えない。貴方の本心が見えないの。日常編 (迦) 【たまには、甘える】 だって、稀にしかないのだから。 日常編 (迦) 【計画的な、犯行ね】 でも実は、感謝してるんだ。
2020.02.15
コメント(0)
-
09話 【愛し抜く、と誓う】
←08話┃ ● ┃日常編→09話 (―) 【愛し抜く、と誓う】_志貴side[1]欠勤は4日目を迎え、何をするでもなく日がな一日不貞寝をして過ごした。ありがたいことに熱はすっかり下がっていた。会社を辞めたりはしない。でも行きたくない。そんな堕落下にいた私のもとを一昨日、不破君が訪ねて来た。私の心配をしてのことだと思うと追い返すこともできず面会はしたが、私から負のオーラを嗅ぎ取ったのだろう、そそくさと帰ってしまった。きっと呆れ、幻滅したに違いない。こんな腑抜けた女が先輩風を吹かしているなんて、世の中間違っているよね。いっそ勤続年数を返上したいぐらいだ。青柳チーフに告白した件についても、丸ごとなかったことにしたい。執拗に食い下がり、醜態を曝してしまった。それだけならまだしも、あの場面を誰かに見られていたらしく、攻撃ならぬ口撃を受けた。『高望みよ、釣り合いが取れないわ』。そんな言葉ならまだ耐えられた。青柳チーフと私を並べたら、ちぐはぐで滑稽なカップルの出来上がり。それは私も認めてる。でも、『勤務中も頭の中を色欲で満たしている志貴さんの指示なんか受けたくないです』という恨み混じりの一言には深く傷付いた。アルバイトとパートタイマーの諍いを中途半端に掻き乱してしまい、結局どちらの力にもなれず、八方美人な性格が高じてどちらも敵に回してしまった。私を扱き下ろす言葉の数々は、そんな彼女たちから発せられたものであり、他部門の者からは苦笑いで頑張れよと励まされたのだけれど、心が疲れてしまった。だからこうして泣きモードで布団にくるまっている。これ以上自分の殻が破れないように。繭から出られないように。全ては自分を守るためだった。籠城という手段を、自ら選んだのだ。この我儘な態度は減給に匹敵するだろう。いや、それでは甘い。数日間の出勤停止命令が下るかもしれない。枕元で携帯電話が着信音が鳴った。とうとうお咎めがきたと思った。事務方からの通達に違いない。もぞもぞと這い出て画面を確認する。着信1件、留守電再生。流れて来たメッセージは青柳チーフの『志貴、俺だ。復帰した。今度はお前がダウンしたと不破から聞いた。養生するように』という文言だった。……そうか、復帰したんだ青柳チーフ。治ったんだ、肺炎。よかった。かなり辛そうだったから。そんな大変な時に4日も穴を空けたりして、不破君や平塚君、パートさんたちには悪いことをしてしまったな……。……。駄目だ、ここままじゃ。よくない、絶対よくない!居ても立ってもいられず、私は速攻着替え、出掛ける準備をした。11時42分。今から行けば、ラストまで働ける。働かせて貰えればの話だけれど。[2]叱責を受ける覚悟でいたものの、擦れ違う人たちが向けるのは好奇の眼差しだった。それは失恋した者を面白おかしく見るような見世物めいてはおらず、さながらゴシップの渦中にいるような印象だった。腹を据えて店長や食品副店長に謝罪に行けば、「話は青柳から聞いている」と先回りで言われ、狐につままれるしかない。一体私の処遇はどうなっているのか。処罰されこそすれ、なんのお咎めもなしプラス野放し放逐されるなんて、なにごと?注意されなかったことが腑に落ちず、私は事務所の奥へと突き進んだ。デスクに総勘定元帳を広げ、2画面仕様のデュアルモニタパソコンには株価関連のグラフやチャート。それらを操る主に声を掛ける。「千早チーフ。お話しがあります」首を上げ、私を見上げた。そしてぎぃ、と椅子にもたれた千早チーフ。青色光を遮断するブルーカット仕様の眼鏡越しに、視線が克ち合う。「志貴さんか。体調はもう大丈夫なのかい?」「はい、お陰様で、もう大丈夫です」「よかった。それで、話というのは?」「休んだ4日分ですけれど……」「あぁ。有給休暇にするように昨日青柳君から言われたから、そのように処理した」「青柳チーフからですか?」「彼を看病している内に菌がうつったと聞いたんだが。彼はマイコプラズマ肺炎の診断書を提出したが、君もそうなのか?」 どうなっているの? 私が青柳チーフを看病? なんの話? 青柳チーフの部屋に行ったこともなければ、接触した覚えもないのに。「看病疲れでダウンしたのか。交際開始早々大変なようだが、志貴さんなら公私ともども頑張れそうだな。応援してるよ」ふっと笑う千早チーフが見れて役得! いつもならそう思っただろう。でも今はそれどころじゃない。聞き逃せないフレーズを耳にした。交際開始?疑問符だらけで答えが知りたい。これ以上ボロが出ないように、私は事務所を退室した。[3]事務所、バックヤード、どちらにも青柳チーフはいない。普段なら昼休憩に行く時間だと、探し終えてから自分の落ち度に気が付いた。私が休んだことで3人体制になってしまっているから、時間をずらしているに違いない。チーフか不破くんのどちらかは売場にいるのだろう。丁度階段から不破くんが降りて来た。入れ替わる時間なのか、青柳チーフもバックヤードへ戻って来た。私はそれとなく近付くが、踏み出せなかったばかりに気付かれず、2人の会話が始まってしまった。「赤ん坊をカートのカゴに入れていたのを見て、他のお客さまから『汚いからやめさせろ』と苦情が来たんだが」「そんなことがあったんですか?」「あぁ。だが直接伝えられるわけもなく、言い回しを考えるのに苦労した」「『その商品プライスレス』なんて最低な冗談、言えませんもんね」「『赤ん坊が汚いからやめて貰えませんか』とも言えないしな」「結局、何て言ったんです?」「『赤ちゃんに値段はつけられないと思うので、カゴからお出し下さい』」「苦しいですね……」「俺がオブラートに包んで言えるのは、せいぜいこれぐらいだ」……これも日常茶飯事内におけるカウントされるべき珍事なのだろう……多分。今度は不破くんが報告した。「柾さんやソマさんと一緒にフードコートでご飯を食べていたんですけど、離れた位置に迷子がいたみたいで。居合わせた女性社員がサービスカウンターに連れていったんですって。偶然居合わせた本部の人間が「彼女は誰だ?」なんて言い出して、シンデレラ探しですよ。紳士陣は戦々恐々で。柾さんは『千早じゃありませんように』、僕は『透子さんじゃありませんように』、ソマさんは『八女サンじゃありませんように』って」「誰だったんだ?」「馬渕さんです」「嘘だろう?」「それが本当なんですよ。ビックリですよね」……駄目だ、やり取りが終わるのを待っていたら日が暮れてしまう。意を決して進み出た。影と靴音に気付いた2人の男性が顔をあげ、私を見やる。「わ、ビックリした。志貴さん!」驚いた不破くんに対し、青柳チーフは面白いものを見たかのように口角をあげた。「体調は治ったみたいだな。安心したよ。俺を看病した所為でダウンしたとあっては彼氏失格だからな」「……なんの冗談ですか、チーフ。相当悪質なデマが流れているみたいですけど」「デマ?」「……私が、青柳チーフと付き合ってるという噂です。何がどうなってるんですか? ご存知なんでしょう?」「事実だろう?」「事実? 事実ですって?」「俺と志貴は付き合ってる。なぜなら俺はお前にベタ惚れで、何度断わられてもめげずに交際を申し込んだから。……だろ?」「……楽しいですか? 人の恋心を土足で踏みにじって。馬鹿にしてるんですか?」押し殺した声を遮ったのは不破くんだった。「志貴さん、ちょっとこっちへ」と断わると、私を一番端まで連れていく。そこは細長い倉庫の隅で、スイッチを付けなければどこに何があるのか分からないほど暗く、人気もないような、密談するには打って付けの場所。それでも不破君は念を入れるように周囲に気を配り、本当に人がいないかどうかを確認した。私もそれにならい、ぐるりと首を動かす。チーフからも距離を取っている。感情的にならなければ、決して漏れ聴こえやしないと保証できた。「青柳チーフは過度な中傷から志貴さんを守るために、あの噂を流したんです。そうでなければ今だってまだ志貴さんは振られたショックで寝込んでいると思われていたはずです」『はずです』ではなく、それはまごうことなき事実だ。のこのこと姿を現わせば、その時点でまだ「やーい、フラれた」と後ろ指をさされていたことだろう。「あのね不破君。何がツラいか分かる? たとえこれが嘘の恋愛ごっこでも、嬉しいって思ってしまっている自分がいるの。馬鹿だよね、本当」上から目線で宣告された、偽物の恋人。主導権を握っているのは青柳チーフ。惚れた弱みだから仕方ない。「志貴さん……」不破くんはそれ以上何も言わなかった。私たちが戻ると、チーフの姿はなかった。昼休憩に行ったんでしょうね、と不破くんが呟いた。[4]「志貴、ご飯食べに行かない?」ドライの詰め所に八女さんが顔を出し、手招きすると出し抜けにそう言った。青柳チーフに関する何かを伝えたがっているのだとすぐに分かった。八女さんとプライベートで外食をするなんて、今まで一度としてなかったからだ。「私、今日は最終までなんです。シフト」上がるのは21時になるだろう。かなり八女さんを待たせなければならなくなってしまう。すると八女さんは部屋へずいっと入り、壁に留めてあった勤務計画表を確認しだした。「あなた、明日は遅番なのね」「えぇ、そうですけど……」「仕事が終わったら、マンションの私の部屋に来て。ご飯作って待ってるわ。今夜はうちに泊って行けばいい。必要なものは私が用意しておくから」「え!?」「話したい気分でしょ? 顔がそう言ってる」指摘されても「そうかな?」と首を捻らざるをえない。八女さんはお節介だと突っ撥ねることもできた。それが出来なかったのは、私を見る目が寂しそうだったからだ。私を憐れんでいるのだろうか。同情しているのだろうか。もしそうだったとしても、『志貴に声を掛けなければ』という衝動に駆られたのだけは間違いない。それはきっとありがたいことなんだろう。見て見ぬフリだって出来るのに。出来たのに。八女さんは、そうしないんだな。人を放っておけないんだ。「分かりました。終わったら、直行します」約束を取り付けたあとは、再び我武者羅に働いた。出来得る限り欠勤をした3日分を取り戻したい。[5]「青柳は社内恋愛を心底イヤがっていたの。彼の言い回しは捻くれているけれど……少しでも気持ちを汲んでもらえたらって思う」「分かってます。ずっと見てきましたから。でも偽りの演技はいつかバレます。メッキが剥がれてしまうのと同じで」「青柳は筋書きを用意しているみたい。ほとぼりが冷めたらこう言うんですって。『志貴に振られたから別れたよ』って」「どうしてそういうことを本人の口から直接聴かせて貰えないんでしょう? 八女さんも不破君も、私からしたら、立ちはだかる壁に見えてしまう」「そうかもしれないわね。あなたからしたら私は青柳の近くにいる女という認識になってしまうんでしょうね。でも彼とは同期で友達というだけよ」「チーフが守りたがっているのは部下としての志貴迦琳で、女としての志貴迦琳なんかじゃない。……居た堪れません」「それでも青柳はあなたを守ろうとしているわ」「……」「青柳が上から目線なのはあなたに嫌われようとしているからなのだし、きっと青柳はね、今頃気付いてる。志貴が健気だってこと。本当に自分を好いてくれているんだってこと。誰よりも情熱的で、女性らしいってこと。朴念仁だからねー、青柳は。鈍いし、認めたがらない。でも大丈夫よ。『恋愛ゲームだ』なんて馬鹿みたいに格好付けてるけど、私には、翻弄されて本気にさせられてる青柳の姿が今から目に浮かぶの。ふふっ。滑稽だけど新鮮で、そんな青柳を見るのも悪くないわ。今から言っちゃう。おめでとう、志貴」「……呑気ですね、八女さん」「あら、何言ってるのよ。これはチャンスよ。怖気付いちゃだめ。恋人のフリだけど、世間的には正真正銘『恋人』なんだから、何をしようが志貴の勝手よ? 自由なの。既成事実だって作りたい放題」こそっと囁く八女さんは魅惑的で、しかもその内容にもどきっとした。押しの一手ってこと?「今は青柳が主導権を握っているけど、志貴にだって手綱を取る道はあるのよね。青柳ったら、そこんとこ分かってるのかしら?いいえ、絶対気付いてないわね。あー、愉快!」マッコリの缶を片手に、けたけたと笑う八女さんである。でもふと真顔になって、静かに言った。「私は志貴を尊敬してる。真正面から青柳にぶつかったでしょう? 自分の気持ちを偽らずに最後まで言い切ったでしょう? 凄く偉いと思うの」「自分のワガママを押し通しただけだとも言えますけど」ふふっと八女さんは笑った。「……幸せになれるといいわよね、志貴。ううん、志貴だけじゃない。千早も潮も私も。香椎も黛も馬渕も。……世の中の女性、全員!恋に生きて、仕事に生きて、試練をくぐり抜けて……タフなんかじゃないのにね、女なんて。脆くて、危うくて、寂しがりやで弱いのに、みんなみんな頑張ってる。歯を食い縛ってる。でも水面下で一所懸命足を動かしている白鳥のように、その必死なサマは億尾にも出さない。だってそれって美しくないでしょう? 時には見苦しいとさえ判断されてしまう。やるせないわよね、強くないのに無茶ばかりさせられて。だから男性には守って貰わないといけないの。愛されないと寂しくて死んじゃう。そういう、儚くて美しいものだから」「八女さん……」「幸運を祈ってるわ。大丈夫、青柳とあなた、とてもお似合いよ? 自信を持って。もっと素直になればいいのよ。好きって何回言ってもいい。減らないわ。何も減らない。プライドを捨てることにもならない。言い続けていいの。攻撃的じゃなく、無償の愛なら。だってね、人を愛するって素敵なことだから。これからも包んであげてね、青柳のこと」八女さんのセリフは青柳チーフの気持ちを丸っきり無視している。でもなぜだろう? するりと「はい」、なんて言葉が滑り落ちたのは。頷いてみせたのは。私でも頑張れる? これ以上の勇気を持てる? 自分を信じてもいいのだろうか。だとしたら賭けてみる価値は充分だ。 無理かもしれない、不釣り合いかもしれない、不相応かもしれない。そんなマイナスのイメージが、いつの間にか取っ払われてる。恐れない。もう逃げない。足音を耳にしただけで踵を返していたあの日の私とはもう違うから。受け入れようと思う。自然体であろう。だって、愛にはきっと、見せかけの装飾、取り繕った見栄なんて似合わないだろうから。「憑き物が落ちたみたい、っていうのは変かもしれないけど、好きって、こういうことなのかな……」たどたどしい文を繋ぎ合わせてなんとか八女さんに説明すると、「そうよ!」と満面の笑みで応じてくれた。大丈夫だ、と思った。どんな結末になっても、もう大丈夫。天邪鬼には戻らない。心に根差した蕾は開花したがってる。_青柳side[6]穏やかな顔付きになった志貴は物腰も柔らかくなり、陰でまことしやかに「これは恋が為せる業だ」と囁かれているのを俺は知っていた。人の噂は75日というが、実際には2週間ほどで落ち着いた。順調な恋愛は、周囲を白けさせるらしい。つまり、これで作戦は成功したことになる。それから3週間が経ち、4週間が経ち、1ヶ月が経った。その頃にはもう、疑う者もいなくなっていた。だがこれは俺にとっては番狂わせな出来事でもあった。仲違いをして別れなければならなかったのだ。それも、俺が嫌われる形で。志貴が俺を振る方法で。それなのに志貴は、俺を見る眼差しをすっかり変えていた。以前は脅え、震えていた瞳も、今では慈しみが宿っている。足音を聴きつけるなり逃げていたくせに、今では振り返って笑みを零す。――憎しみ合えない。喧嘩など起こりようがない。けしかけたこともあった。わざと喧嘩が起きるように仕向けて、怒り任せに別れの言葉を切り出させようとした。だがそれも無駄だった。志貴は歩み寄ろうとした。分かり合える道を選ぼうと、真剣に思案しだした。本当に変わったのだ。そうなると俺も変わらざるを得なくなった。だってそうだろう? 敵愾心のない女性を、頭ごなしに叱れるわけがない。叱る回数が減る。怒鳴る回数が減る。猜疑心は霧消し、穏やかな時間が生まれる。他愛のない会話が増え、相槌が増える。理解しあった先に友情が育まれ、尊敬しあう内に、それは愛情へと変わった。自覚した俺は、志貴に言った『ウソ』を撤回した。もはや俺の意固地など、生まれてしまった恋心にとっては邪魔なものでしかなかったから。志貴は素直に受け入れた。「さようならですね」。彼女はそう言った。さようならだって? 俺にはそんなつもりはさらさらない。「俺はウソを撤回しただけであって、お前と別れるつもりはない」「どういう意味ですか?」「『俺と志貴は付き合ってる。なぜなら俺はお前にベタ惚れで、何度断わられてもめげずに交際を申し込んだから』」「その言葉は……」「――ウソではなくなったという話だ」「ウソじゃなくなった……?」「どの口がそれを言うんだと思うかもしれないが……」志貴の髪に触れ、それを一房、耳に掛けてやる。思えば、これが彼女を女性として意識して触れた初めての行為。今度は志貴の手が俺の手首を掴んだ。そのまま己の頬へと導く。彼女の赤い頬は武骨な手の平で撫でられ、それでも心地よさそうに目を瞑った。「……続けて下さい」彼女はゆっくりと目を開いた。その一言を告げる俺の顔を、一瞬でも見逃さないとでも言うように。「俺はお前を大切に想う。何よりも、誰よりも愛おしいんだ。志貴」「……ありがとうございます!」ふふっと笑った目尻から、つっと涙が伝った。こうして、志貴迦琳は公私ともに俺のパートナーになった。_志貴side[8]近付いて来る。一定のリズムで、足音が。「誰か、志貴を見掛けなかったか?」「いいえ、見てません」行かなければ、早く。「お前は?」「いえ、チーフ」「どこへ行ったんだ……? おい、志貴を知らないか?」貴方が呼ぶ。だから私はそれに応える。「お呼びですか、青柳チーフ」「志貴」チーフは私を振り返った。顔には微笑が浮かんでいる。優しげな薄鈍(うすにび)色の双眸が私を捕えた。「来月ドライの会合に出席することになった。このリストに載っている資料を揃えてくれ」A4用紙3枚に渡る内容を頭に叩き込み、青柳チーフに返却する。「売上レポート関連については早速明日から集計できるようPOSオペレータに依頼しておきます。レポートは私が毎日ファイルに綴って保管します」「頼む」「はい! 任せてください」チーフの信頼を得るようになってから、ユナイソンネオナゴヤ店ドライ売り場は円滑にコミュニケーションが取れている。チーム内の不和は取り除かれ、元の鞘に納まった。今にして思えば、歯車を狂わせていたのは私のひん曲がった性格が大きな原因だった。上司には天邪鬼な態度だったし、部下にはどっちつかずで頼りない姿を曝し続けていたもの。頼られないのは当たり前の話で、それでもそんな私を見捨てずにいてくれたチーフや八女さん、不破君たちユナイソンの仲間――。それは掛け替えのない、私の宝物だ。交際は順調で、私たちは婚約を交わした。薬指の指輪が婚約指輪から結婚指輪になり、やがて身籠った私はユナイソンを退社した。「振られたから辞めます、だっけ? あの時辞めていたら、今のお前はいなかったな」幹久さんは、たまに過去の話を蒸し返しては私の頬を膨らませるようなことをわざと言う。「いざとなったら女性は強いんです!」こちらもわざと拗ねてみせる。「そうだな、迦琳は強い。でも俺を置いて行かないでくれ。立つ瀬がなくなっちまう」豊かになった腹部を優しく撫でる、未来のパパ。なんだかくすぐったい。自然と笑みが零れ、胸が切ない気持ちでいっぱいになった。「勿論です、旦那さま」道はいつだって正せられるし、自分だって変えられる。未来は変幻自在なんだと。そのことを教えてくれたのは、ねぇ、八女さん。あなたでした。ありがとう。そして不破くんにもたくさん救って貰った。彼にも心から感謝を。ありがとう。私の両腕は、愛しいものを抱き締めるためにあるの。私の目は、愛するものを最期まで見届けるためにあるの。私の心、身体、魂、全てを使って愛し抜くわ。だってほら、世界はこんなにも儚くて、でも逞しくて、美しいものだから。貴方と歩む。どこまでも、行けるところまで。――それが、志貴迦琳の一生よ!END.2012.07.182023.02.13 改稿←08話┃ ● ┃日常編→
2020.02.14
コメント(0)
全177件 (177件中 1-50件目)
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- バンダイ イタジャガ HUNTER×HUNTER …
- (2024-11-27 20:25:22)
-
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- ブルーインパルス
- (2024-11-28 06:30:11)
-
-
-

- GUNの世界
- 昭和回想1982年5月号のGUN広告
- (2024-11-27 13:31:34)
-








