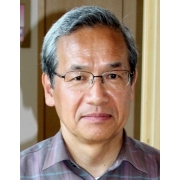PR
X
Category
Calendar
Comments
しろうと自然科学者@ Re[1]:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:キツネノカミソリの花が咲き始めました。ヒガンバナは、地温が20℃になると花芽が分化して発達し開花するそうですが、キツネノカミソリはどのようにして季節を感じるのでしょうか。7月下旬のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(07/31)
猛暑続きですが 狐のカミソリの花が 咲…
しろうと自然科学者@ Re[1]:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
蕗さん8256さんへ コメントありがとうござ…
蕗さん8256
@ Re:ニホンズイセンの花、ソシンロウバイの花、たわわに実っているクロガネモチの果実。1月のウォーキングコース(玉川上水緑道)。(01/30)
日本水仙 ソシンロウバイの花が 奇麗に…
モラタメ・シャンプ…
New!
だいちゃん0204さん
都内公園・カワセミ♂… New!
★黒鯛ちゃんさん
New!
★黒鯛ちゃんさん
日本の野生蘭 オオ… New!
himekyonさん
New!
himekyonさん
50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
都内公園・カワセミ♂…
 New!
★黒鯛ちゃんさん
New!
★黒鯛ちゃんさん日本の野生蘭 オオ…
 New!
himekyonさん
New!
himekyonさん50日ぶりの小さな庭 hiromomoさん
M.KEIZOの「花のある… M.KEIZOさん
Keyword Search
▼キーワード検索
カテゴリ: 山野草と樹木と野鳥たち
ウォーキングの途中で、民家の庭にマンサクの花が咲いていました。毎年のように何度見ても、花弁(花びら)が変わった形の花です。


マンサク(満作、万作、金縷梅)
1.マンサク科マンサク属マンサク。
2.和名の「満作」は、黄色い花を枝いっぱいにつけるので「豊年満作」から来た説、早春の花の少ない時期に他の花に先駆けまず咲くことから「まず咲く」「まんずさく」が訛ったとの説もある。
3.日本各地の山林に自生するが、庭木としても栽培される。
フキノトウは、だいぶ大きくなり、花が見えてきました。

ヒヨドリが木の枝にとまっていました。木の枝の上では、丸々としているように見えます。

公園・広場として整備されたところの一画に、コナラの幼木が植えられています。

コナラ(小楢)
1.ブナ科コナラ属コナラ。
2.和名の「小楢」は、ミズナラの別名の大楢と比較してつけられた。「ナラ」については、葉が平たい様子の「ならす」から来た説、枝に残っている葉を冬風が吹き鳴らすから来た説、若葉が軟らかい様子の「なよらか」から来た説などがあるという。
3.武蔵野の雑木林を構成する主な木の一つ。公園の樹木、建築・家具材、薪炭、シイタケの「ほだ木」として利用される。実はドングリ。
このサイズから大きな木に成長するためには、一体何年かかるのでしょうか。
武蔵野の雑木林では、萌芽更新(伐採された切り株から「ひこばえ(萌芽)」を出して再生すること)のしやすいコナラやクヌギを薪炭林の主要樹木として維持してきました。萌芽更新を利用することによって、幼木から育てるよりも成長が速かったようです。近くの雑木林で、試験的な萌芽更新作業をしているのを見ましたが、伐採後わずか数年で大きな木になっていました。
ウォーキングコース沿いには、根元が直径1メートルから1.5メートルもあるコナラ・クヌギがたくさんあります。江戸時代(1653年~1654年)に作られた林ですので、その頃から炭焼き材として利用されていたのでしょうか。358年の歴史がありますが、直径2メートルにもなる欅は、この歴史のいつごろ植えられたものでしょうか。
ベランダ側のあちこちに、カマキリの卵鞘(らんしょう)があります。毎年、庭の木の枝に作るのに、今回は、水仙の葉、鉄製園芸用品収納棚、アルミサッシと壁に作っています。春先から初夏、温かくなると、1センチメートル位の小さなカマキリが、卵鞘の下から次々と出てきます。
水仙の葉の卵鞘(2011年11月20日撮影)。先日の雪で見えなくなってしまいました。

園芸用品収納棚の卵鞘。

アルミサッシと壁に作られた卵鞘。網戸を開けることができなくなりましたが、春までの辛抱です。

カマキリ(螳螂、蟷螂)
1.昆虫綱カマキリ目に属する昆虫の総称。日本では、カマキリ科とヒメカマキリ科に属する2科9種。
2. 和名の「螳螂」は、鎌状の前脚で獲物を捕えて大顎でかじって食べることから「鎌切り」という説、鎌状の前脚の特徴から「鎌錐」という説など。
3.メスは、数百個前後の卵を卵鞘の中に産み付ける。卵鞘は、卵と同時に分泌される粘液で作られる。卵は、卵鞘内で多数の気泡に包まれ、外部の衝撃や気温から守られている。


マンサク(満作、万作、金縷梅)
1.マンサク科マンサク属マンサク。
2.和名の「満作」は、黄色い花を枝いっぱいにつけるので「豊年満作」から来た説、早春の花の少ない時期に他の花に先駆けまず咲くことから「まず咲く」「まんずさく」が訛ったとの説もある。
3.日本各地の山林に自生するが、庭木としても栽培される。
フキノトウは、だいぶ大きくなり、花が見えてきました。

ヒヨドリが木の枝にとまっていました。木の枝の上では、丸々としているように見えます。

公園・広場として整備されたところの一画に、コナラの幼木が植えられています。

コナラ(小楢)
1.ブナ科コナラ属コナラ。
2.和名の「小楢」は、ミズナラの別名の大楢と比較してつけられた。「ナラ」については、葉が平たい様子の「ならす」から来た説、枝に残っている葉を冬風が吹き鳴らすから来た説、若葉が軟らかい様子の「なよらか」から来た説などがあるという。
3.武蔵野の雑木林を構成する主な木の一つ。公園の樹木、建築・家具材、薪炭、シイタケの「ほだ木」として利用される。実はドングリ。
このサイズから大きな木に成長するためには、一体何年かかるのでしょうか。
武蔵野の雑木林では、萌芽更新(伐採された切り株から「ひこばえ(萌芽)」を出して再生すること)のしやすいコナラやクヌギを薪炭林の主要樹木として維持してきました。萌芽更新を利用することによって、幼木から育てるよりも成長が速かったようです。近くの雑木林で、試験的な萌芽更新作業をしているのを見ましたが、伐採後わずか数年で大きな木になっていました。
ウォーキングコース沿いには、根元が直径1メートルから1.5メートルもあるコナラ・クヌギがたくさんあります。江戸時代(1653年~1654年)に作られた林ですので、その頃から炭焼き材として利用されていたのでしょうか。358年の歴史がありますが、直径2メートルにもなる欅は、この歴史のいつごろ植えられたものでしょうか。
ベランダ側のあちこちに、カマキリの卵鞘(らんしょう)があります。毎年、庭の木の枝に作るのに、今回は、水仙の葉、鉄製園芸用品収納棚、アルミサッシと壁に作っています。春先から初夏、温かくなると、1センチメートル位の小さなカマキリが、卵鞘の下から次々と出てきます。
水仙の葉の卵鞘(2011年11月20日撮影)。先日の雪で見えなくなってしまいました。

園芸用品収納棚の卵鞘。

アルミサッシと壁に作られた卵鞘。網戸を開けることができなくなりましたが、春までの辛抱です。

カマキリ(螳螂、蟷螂)
1.昆虫綱カマキリ目に属する昆虫の総称。日本では、カマキリ科とヒメカマキリ科に属する2科9種。
2. 和名の「螳螂」は、鎌状の前脚で獲物を捕えて大顎でかじって食べることから「鎌切り」という説、鎌状の前脚の特徴から「鎌錐」という説など。
3.メスは、数百個前後の卵を卵鞘の中に産み付ける。卵鞘は、卵と同時に分泌される粘液で作られる。卵は、卵鞘内で多数の気泡に包まれ、外部の衝撃や気温から守られている。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[山野草と樹木と野鳥たち] カテゴリの最新記事
-
「アオ」の名がつくアオキ、アオゲラ、ア… 2015.01.28 コメント(2)
-
「タカ」と「クマ」の名がつくオオタカ、… 2015.01.06
-
昨年10月に種を蒔いて育ててきたパンジー… 2014.02.05
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.