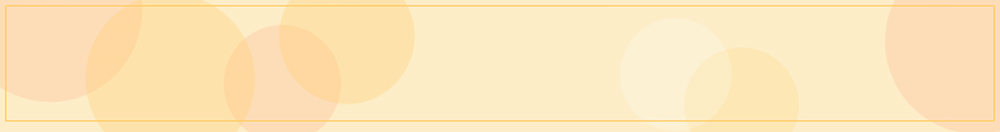[ちょっとなつかしのファンタジー] カテゴリの記事
全112件 (112件中 1-50件目)
-

昔からあった異世界転生ラノベ『白馬の王子』タニス・リー
タニス・リーというとちょっとダークで絢爛豪華なファンタジー作家さんでしたが、彼女が自分の作風のパロディとして書いたような、「なろう系」的で軽~い異世界転生ファンタジーが、『白馬の王子』です。 タイトルからしておちょくっています。オーソドックスなロマンチック・ヒーロー大好きの友人は、むかし、タイトルと中山星香の表紙絵に惹かれてこの本を読み、「だまされたっ」と怒っておりました。 冒頭から、主人公は、白馬で荒野を旅する自分の名前も目的もわからず、 「・・・いっさいがっさい忘れちまうというのは――ええと記憶ソーヒツだっけ?」 「記憶喪失ですよ」馬がしゃべった。 「やっ、おまえは口がきけるのか!」・・・ 「そんなこと、できるわけないでしょう」と馬。「馬が口をきくなんて話が、どこにあります?」 「そうだな」 ――タニス・リー『白馬の王子』井辻朱美訳と、やりとりもまるで漫才なのです。 気乗りしないまま彼は姫から剣をもらい、陳腐な怪物から逃げ回り、いやいやながら真鍮のドラゴンを倒し、文句を言いつつクエストを続けていきます。その間に、ハート型の月が昇ったり、ドーナツ型の太陽が出たりします。作者、ふざけ放題って感じ。 しかし、彼の旅が進むにつれ、荒野だけだった世界にはさまざまな彩りの風景や生き物が出てきて、あたかも空白な彼の記憶を新たな事物で満たしていくよう。そして彼は自分が<待たれていた救い主>だと知らされます。 世界を救うため外から召喚されたヒーロー。これこそ異世界ものの王道であり真髄ですね。児童文学の古典では、ナルニア国ものがたりの『ライオンと魔女』も、『はてしない物語』もそうです。硬直した社会の改革には、外部からの刺激が必要、ということでしょうか。 鍛冶師が魔剣をくれるし、老賢者は主人公自身の失われた記憶=魂が入っている卵をくれる。気のふれた魔女がそれを奪う。トリックスター的な木の精の少年は、究極の敵「ヌルグレイヴ」がやって来ると言う。・・・というふうに、だんだん彼のやるべきことが見えてきました。しかし、 ふつうこうした異世界へのまきこまれ型主人公は、はじめこそおたおたしていますが、とちゅうからはけっこうその気になってノリ出してしまうことが多いのに、彼はあくまでシラけています。 ――訳者あとがきという具合です。けれど、実はそれが肝心で(→以下ネタバレ)、記憶喪失の部外者だからこそ「ヌルグレイヴ」(じつは「絶望」の実体化だった)に取りつかれず、「歓喜」を生みだすことができたのです。 とはいえ、このオチはちょっとチート(いかさま)、最近のなろう系っぽい。 と思っていると卵は無事にもどり、孵化して、彼は記憶を取り戻します。 「・・・ぼくはとても貧乏で、とても年をとっていて、無一物でひとりぼっちだった。・・・」 ――『白馬の王子』 つまり、主人公は現実世界で野垂れ死に、この異世界に来たらしいのです。 考えようによっては、異世界は彼の内なる世界(魂)そのもので、それは荒野だったり月が三つあったりハチャメチャです。彼は主人公(=ヒーロー、つまり白馬の王子)として自分で自分の人生の<救い主>となってやり直し、現実人生で打ち勝てなかった孤独や荒廃や無秩序、特に「絶望」を克服しなければならなかったのでしょう。 事故死したり、過労死したり、自死したりして始まることも多い最近の転生ものの、これはプロトタイプといえそうです。
August 3, 2023
コメント(0)
-

『常世の森の魔女』舞台神聖祝典劇を呪われた魔女の視点から
インディ・ジョーンズのシリーズ最終作がいよいよ上映! とのことで、過去作品もテレビ放映されていましたが、私は3番目「最後の聖戦」が好きです。西洋のファンタジーで一大勢力を誇る「アーサー王もの」の重要アイテム「聖杯(グラール)」をめぐる物語ですから。 「最後の聖戦」の聖杯は飲むと永遠の命が授かるという設定でしたが、今回とりあげる『常世の森の魔女(原題だと「心の聖杯」)』では、イエス・キリストの磔刑を笑った女クンドリーが、呪われて千年も生き続け魔女となっています。 クンドリーはもともと、ワグナーのオペラ「パルジファル」の登場人物です。聖杯守護者アムフォルタス(傷ついた漁夫王)に薬を持ってくる(第一幕)のに、悪の魔術師クリングゾル(=クリンゾール)にあやつられパルジファル(=パーシヴァル)を誘惑する(第二幕)、善悪両面を持つとされるそうです。そもそもアムフォルタスが負傷したのも、クンドリーが誘惑したからなのです。 魔術師に支配されたせいでクンドリーはこの物語のすべての悪を引き起こし、呪われ錯乱し、最後には魂の救済を得るけれどそれはすなわち死ぬことでした。善でありたいと願いながら悪に染まり、苦悩と献身のはてに死して救われる、つまり多くの人間の一生を象徴しているとも言えそうですが、・・・普通に考えるとなんだか、どうしようもなく気の毒な役回りですよね。 『常世の森の魔女』では、このクンドリーの生涯が語られます。悪の手先になったいきさつ、なぜキリストを笑ったのか、どのようにアムフォルタスを誘惑し後悔し、苦しんだか、など。 作者の創造のかなめは、クンドリーがアムフォルタスをたらしこんだ時に、千年来で初めて恋心を抱いたので、必死に彼を救おうとするところ。アムフォルタスも、陥れられて、傷と恥辱と後悔しかなくなったというのに、クンドリーが最後に見せた苦痛と後悔の表情を信じて、彼女への愛と赦しを心に確認する・・・つまり純愛ものなんですね。 ところが、このロマンチックな設定、私にはどうもピンと来なかったです。 まず、キリストの時代から千年も高級娼婦をしてきたクンドリーが、なぜいまになって初恋みたいにアムフォルタスへの愛にめざめるのか、その実感がわきません・・・確かにアムフォルタスは彼女を貴婦人として大切にしましたが、千年の経験のうちには同様に彼女にいれこんだ男性も一人や二人いたでしょう。何が彼女の琴線に触れたのか、・・・まあ恋愛ですから理屈抜きの運命的な出会いだったんでしょうか。それならもうちょっとそれらしく、特別な何かが描かれてほしかったですね。 アムフォルタスも、彼女に会う前から、聖杯守護者としての人生に息苦しさを感じて十字軍従軍時代の生活を懐かしむばかりで、どうも魅力に乏しい感じ。 ともあれ、クンドリーは魔術師クリンゾールによって過去につき返され、呪われた千年の生涯をくり返す羽目に陥ります。そこで、彼女は、自分の行動によって過去を改変してキリストの受難を阻み、ひいてはアムフォルタスの恥辱というのちの歴史を起こりえないようにしよう、と努力します。遠大で無謀な、神をも恐れぬ計画ですが、彼女は必死です。そして案の定、普通の人間と同じに見えながら彼女より器の大きいキリストを前にして、彼女はその運命を変えるために動くことは結局できませんでした。絶望するクンドリー; その瞬間、傷口から毒が噴き出すように哄笑が湧き上がった ーースーザン・シュウォーツ『常世の森の魔女』嶋田洋一訳 この場面はなかなか説得力があります。小手先だけで運命を変えようしても、無理だとさとった時の無力感が絶望の笑いとなってしまったのですね。 でもつまり、クンドリーの個人的な愛の心だけでは、呪いは解けなかったということです。 そして「憐れみにより賢者となった愚者」パルジファル(=パーシヴァル)の登場となります。 オペラの筋書きを言えば、クンドリーが彼を誘惑しようと語りかけキスをしたことで、彼はおのれの役割に目ざめて聖杯の奇蹟を起こし、アムフォルタスやクンドリーの魂を救うのです。物語の方でも、救い主はパーシヴァル。原話のテーマである宗教的救済が踏襲され、二人の純愛は、無力でした。 というわけで、宗教劇にロマンスを持ちこんだ物語としては、ちょっと中途半端なんじゃないかなー、と思ったHANNAでした。
June 30, 2023
コメント(0)
-

孤軍奮闘する子供たち――「オレンジ党」シリーズ続
前回、このシリーズのダークな部分ばかり挙げましたが、一番恐ろしいのは、“体制”側が邪悪な《黒い魔法》側であるということです。大人はたいていその手先になったり惑わされたりして、敵に回ってしまいます。 そうでない大人(ルミの父や担任の先生、鳥博士)は無力で少数派。 唯一、第1巻『オレンジ党と黒い釜』では《時の魔法》の樹木の精霊「とき老人」が主人公たちを導きますが、最後は「黒い釜」を破壊するため自らを犠牲にします。――また衝撃の“死”が出てきました。(ところでこれは、ウェールズの伝説『マビノギオン』に出てくる、死者を再生させる大釜を破壊するエヴニシエンの物語と同じ結末です。) おまけに、第三の勢力であるはずの土着の《古い魔法》は、弱体化しています。この魔法を司る家系の源先生は、やることなすこと大時代的で滑稽な役回り。土地の精霊「土神」も、『魔の沼』では黒い沼の王に体をのっとられてしまったり、あまり頼りになりません。 このように、善なる《時の魔法》を信奉するオレンジ党の子供たちの闘いは味方も少なく、困難に満ちています。 「オレンジ党」の名の由来を語る短編「闇の中のオレンジ」には、《古い魔法》の「物言う泉」の水面に、オレンジの実のような盃が浮かんでいる、というくだりがあります。 孤立無援でクエストをする主人公たちの命の輝きを表すかのような、あるいは、宇宙の闇の中で輝く太陽(《黒い太陽》とは対極の、真実の太陽)のようなイメージです。 オレンジ党のメンバーは盃の形の光るバッジをつけていますが、盃というと、やはりイギリスやフランスの中世、聖杯伝説が思い起こされます。フランス文学者の作者は前作『光車よ、まわれ』で、闇に輝く光車の探索について「まるで聖杯をさがすアーサー王の騎士みたい」と使命感を表現しましたが、オレンジ党でも同様ですね。 第3巻『オレンジ党、海へ』では、《鳥の王の宝》が光車に匹敵する重要アイテム。これはもとは李エルザの祖父母に属する魔法石で、その中心は、やはり生命を象徴するような赤い玉です。 エルザは朝鮮の血をひき、また物語中にも朝鮮由来の登場人物や朝鮮語がたくさん出てきます。 そこで私は、アカル姫伝説を思いだしました。朝鮮の乙女と太陽神の娘で、赤い玉の化身です。それからまた、橘の伝説もありますね。日本神話で不老不死の妙薬として求められた、タチバナの丸い実は「ときじくのかくのみ」(常世の国の、光/かぐわしい果実)と呼ばれ、太陽のシンボルだそうです。 李エルザがこの宝玉/果実を使って、邪悪な《黒い太陽》をうちやぶり、時と海を越えて常世へゆくキム船長の帆船「金龍丸」へとみんなを導く、というのが、『海へ』のラストなのだと私には思えました; そしてあたしたち、あそこで最後にもう一度、死んだお父さん、お母さんに会えるのよ! ーー天沢退二郎『オレンジ党、海へ』 ただし、朝鮮に由来する人の中でも、吉田四郎は微妙な立場に立たされ、救われませんでした。祖父が宝玉を奪ってご神体にまつったという、大鳥神社の跡取りである彼は、鳥の王に使われたり、カモメや泉をおがむ老婆に変身したりしながら何とか誠実であろうとしますが、最初は夢の中とはいえ血まみれのケガを負い、最後はほんとうに失明してしまいました。 死とまではいかないものの、あまりにも厳しい結末が胸に残ります。
November 15, 2022
コメント(0)
-

子供たちの無気味な冒険――『三つの魔法』(オレンジ党)シリーズ
近ごろは電子版でも読める、1970~80年代の「オレンジ党」の冒険3部作と、関連する短編集『闇の中のオレンジ』をご紹介。(2011年に4作目『オレンジ党最後の歌』が出ているらしいのですが、私は未読です) 小学6年生(いつも注目! 子供時代の終わり、最強の子供たち)が主人公で、シリーズ名通り3種類の魔法がせめぎあう設定。ただし、ダークです! 単に暴力的、悲劇的というより、不穏で後味の微妙な、忘れがたい印象を残すお話ばかり。 まず、個人的な感想ですが、見知らぬ荒々しい異界のようでありながら現実の日本と思われる舞台背景が、無気味。 モデルは千葉県らしく(作者は、物語とは無関係と断っていますが)、ああ、だから土地が広々として沼地や泉、落花生畑や牧場があるのですね。関西人の私にはなじみのない、原野、寄せ集めの森、荒れ地を開墾した畑、その中に忽然と現れる新興住宅地、広漠とした丘陵地帯。そこで次々ときみわるい出来事が起こるので、ちょっと悪夢じみています。 第1作『オレンジ党と黒い釜』では、転校してきた主人公ルミの日常を、黒泥や黒いナメクジのような怪異が浸食します。《グーン》の《黒い魔法》が残した穢れだというのですが、先日観たアマプラドラマ「力の指輪」にも、オークに穢された土地の牝牛が、黒い乳を出すシーンがありましたっけ。 穢れは5つの「黒い釜」として地中に封じられたのに、漏れ出て復活したのです。『闇の中のオレンジ』中の短編「《グーン》の黒い釜」では、土と水が汚染され作物が育たないと説明されています。植物の精霊たちは五郎と妹を連れ、ノアの方舟を思わせる古代船で時を超えて脱出しますが、おかあさんは、 もうだめ。畑はみんなだめ。黒いもの。子どもたちも行ってしまう。あたしにはもう何もできない。もう生きてけない。と書き残して首をつります。日常に突然現れる衝撃的な“死”。 2作め『魔の沼』では広がる黒い沼の怪異がメインです。行方不明の妹を探す中学生キヨシ(京志)が登場しますが、その妹は沼の王の養女にされ、黄泉の国のような異界にとらわれているのです。赤い目隠しをして下の妹を抱いた、巫女のようなチサは、最後まで兄と巡り会うことができません。 おまけに、黒い沼の出現と呼応して主人公ルミの体内で「黒い汁のつまった部分」が発動、命が危険になります。必死に解毒薬を煎じるルミ。善の側の純粋な主人公の内部に「黒い汁」が巣くっていたというのが、かなり無気味です。 思春期前の子供の物語には“死”の恐怖が出てくる、と以前も書きましたが、このシリーズは特に“死”に満ちていると言えます。ルミをはじめオレンジ党の仲間たちは全員、母親を亡くしています。それも、《黒い魔法》を封じた時に手を貸した《古い魔法》の犠牲(いけにえ)となった、というから恐ろしい。 邪悪な《黒い魔法》は、第3作『オレンジ党、海へ』でさらに強大な、「空飛ぶ黒い影」や「黒い太陽」となって猛威をふるいます。要らない大人の知識で読むと、飛行機や原発が連想されてしまいます。 じつはこのシリーズの舞台と時代は成田闘争(空港建設反対運動)と重なっていて、「農民ゲリラ」を名乗る大人たちが出てきたり、「緑衣隊」(機動隊?)が官憲をふりかざして踏みこんできたり。 邪悪の源ともいえる「黒い太陽」の力に惹かれて、白衣の研究者はマッド・サイエンティストと化し、「空飛ぶ黒い影」の被害者だったはずの「鳥の王」すら、その力を欲して悪に堕ちます。 40年前悪さをしたという《グーン》は“軍”、旧日本軍でしょうか。戦後、軍から払い下げられた土地を懸命に開拓した農民たちが、空港建設によって再び土地を失い、反対闘争、暴力、利権争い、仲間割れなど混迷するありさまを念頭に、作者はこの物語をつむいでいったようです。 ところで、私は昔、成田闘争で過激派と呼ばれた島寛征という人の、 棲家を奪われた野槌(土地の精霊)たちがひそかに逆襲の相談をしている というような文をどこかで読んだ記憶があるのですが、『海へ』を読んだとき、この文が恐ろしいイメージとして何度もよみがえりました。 今度は、そんなダークで敵味方錯綜する大人たちに対する、オレンジ党の“光”について……次回。
November 3, 2022
コメント(0)
-

異世界丸ごと謎解き(ミステリー)『イルスの竪琴』3部作
やや難解な作品の多いマキリップの初期の長編。むかし山岸凉子が表紙や挿絵を描いてました(再版の表紙は違う人→)。訳者の脇明子さんが『指輪物語』と比較しているので、当時、意気ごんで読みましたが、いやいや洞察力と推理力、構成力がすごく必要で、しかも鋭く細やかな感性がないと楽しめないという、なかなかハードな作品です。 今回、再読してみて、異世界の舞台が南の方はなんとなくケルトの「マビノギオン」的な舞台だな、物言う豚とか死者の軍勢とか、「変身術者」はアイルランドの古い神々そっくりだとか。中央の古代遺跡はストーンヘンジのたぐいみたいだし、北の方はゲルマンや北欧系(鉱山とか雪原とか)だな、などと楽しむ余裕ができました。 全体を貫くテーマは“謎解き“。舞台となる異世界では、すべて物事の理解は謎解きという形で成されます。主人公モルゴンは大学で謎解きを学ぶ。いくつかある国々の歴史や成り立ちも謎で構成されている。領主や魔法使いは謎解きの試合をする。そして、否応なく探索の旅をするモルゴンの使命も最後の最後まで謎! トールキンは異世界の解説を大量に提示してくれますが、マキリップの作品は予備知識なしで放り込まれる系なので、読者は、登場人物たち以上に頭の中が謎だらけのまま読み進めねばなりません。 けれど、荒俣宏の『別世界通信』によると、ファンタジーのルーツである神話には、世界や人間を理解するのに謎解きが重要な要素として出てくるのです(スフィンクスの謎とか)。だから、『イルスの竪琴』の世界や登場人物、ストーリーを理解するには、読者も謎ときに参加するしかありません! 幻想文学が宇宙の本質に迫ろうとするとき、それは必然的に神話じみた謎かけへとすがたを変え…[中略]…入社式(イニシアシオン[成人式])のための謎ときを読むものに挑みかけるとき、それは試練への愛にまで昇華する。 ――荒俣宏『別世界通信』[旧版にも新版にもあり] こうして、わけがわかんないなあと不満をもらしつつも、謎解きにはまって読み進むことは、モルゴンが故郷の素朴な暮らしに戻りたいと何度も願いつつも、結局は自分の出自や世界の謎を解くために危険な探索へと突き進むのと、同じなんですね。 ファンタジーの効用は、主人公の冒険を読むことによって、読者も異世界体験をして成長したり癒やされたりすることにある!というわけです。 そして、突然襲ってくる得体の知れない「変身術者」たちや、そもそもこの異世界の秩序の主として名だけが何度も出てくる「偉大なる者」って何なの? なんで戦ってるの? モルゴンはそれとどう関係があるの? それがちっとも分からないまま、何百ページも物語が進んでいきます。もちろん最後には次々わかってきますけど、正解は次々予想外。いや、後から思えばなぜ予想できなかったんだろうと思うのですが、うまく作者に手玉にとられてしまうんですね。 探偵小説なら理屈や証拠の品が伏線になるのだけど、マキリップは感性の作家なので、感情や感覚が伏線といったらいいのでしょうか。とにかく、異世界丸ごとを解き明かすミステリー。 もちろん魅力的な登場人物たちや、魔法のたぐいもたっぷりです。
August 1, 2022
コメント(0)
-

黄金の子ども時代を瓶詰めにーー『たんぽぽのお酒』
今日は夏至。夏が近づいてきました。レイ・ブラッドベリの夏の名作『たんぽぽのお酒』、でも私は長いこと敬遠していました。 主人公ダグラス少年のひと夏の出来事を、12歳という年齢の持つするどい感覚でつむいでいます。が、子ども“向け”に説明のゆきとどいた作品ではないので、米国イリノイ州(ブラッドベリの故郷)の古き良き田舎町の風情がよくわかっていないと、とっつきにくいと思われます。 ようやく真剣に読もうとしたのは、長野まゆみ『夜間飛行』を読んだあとで、この物語にはおそらくブラッドベリへのオマージュとして、たんぽぽのお酒が出てきます。 主人公の少年たちは夏至の頃ミステリーツアーに参加するのですが、ホテルの部屋にたんぽぽの花を浮かべたリキュールが置いてあり、それを飲みながらすばらしい時間を満喫するのです。 本家ブラッドベリのたんぽぽのお酒(ダンデライアン・ワイン)も、そのたんぽぽを摘んでおじいさんと一緒に瓶詰めした記憶に象徴される、楽しい夏の日々が、あとになって見たり味わったり、いやその名を口にするだけで豊かによみがえるというのです; たんぽぽのお酒。 この言葉を口にすると舌に夏の味がする。夏をつかまえてびんに詰めたのがこのお酒だ。 ――レイ・ブラッドベリ『たんぽぽのお酒』北山克彦訳 その記憶というのは、“12歳という年齢の持つするどい感覚”の産物で、この年齢のころは、ほかの日記でも書きましたが、幼年時代の終わりとかプレ思春期とかいう、一大転換期なのです(河合隼雄の受け売り)。男の子の声変わり・女の子の初潮の、直前の時期。子どもとしての完成形かつ大人への第一歩で、すごいパワーと可能性、新鮮な感動に満ちた時期。 児童文学でいうと、この年齢の主人公たちは、親や大人の庇護を離れてまっさらな心で世界に乗りだします。スティーブン・キング『スタンド・バイ・ミー』なんかがそうですね(この映画のように情景も一緒に触れることができれば、『たんぽぽのお酒』もなじみやすいのかなあと思います)。 『たんぽぽのお酒』は遠くへ冒険に行く話ではありませんが、町には野性味のある危険地帯「峡谷」や、死の象徴としての恐ろしい〈孤独の人〉の噂があります。 面白いのは、主人公ダグラス(12歳)は夜に友人たちと峡谷へ遊びに行ってしまうのですが、彼のよき相棒である弟トム(10歳)は母のそばにとどまり、母の心配を感じて自分も恐怖にとらえられるのです。2歳の年齢差がよく現れていますね! 世界を知り始める時期のうちでもトムはまだ本当に初心者で、歯磨きだの野球だの、いろんなものの数を数えて統計を取っています。それに触発されたダグラスは、夏の出来事を「慣例と儀式」と「発見と啓示」に分類してメモに記録します。つまり、彼はすでに、世界に不変(に見える)ものと、変化するものとを感じとり、考察しているのですね。 不変なものには、「慣例と儀式」であるたんぽぽのお酒づくりや、新しいテニスシューズを買うことなどのほかに、近所の老人たちの存在も分類されそうです。 老未亡人ベントレー夫人のエピソードで、少女たちは、夫人もかつては少女だったという事実を頑として信じません。それは、幼年時代の子供にとって時間は円環で、昨日と今日と明日は基本的に同じ(「慣例と儀式」)、何か冒険に出かけても必ず帰宅してベッドにもぐりこみ何の変化もないからです。いつまでも連載が続く「サザエさん」や「ドラえもん」の楽しい世界。 そんな幼年少女たちと一緒にいるのは、トムです。トムにその発見を聞いた兄ダグラスは、 「みごとだ! あたってるよ。老人は過去に決して子供ではなかった!」 ――――『たんぽぽのお酒』と納得しますが、じつはそれは彼らの理解できる世界がまだ不変(幼年時代)のみだという、証拠ですね。 次に(トムではなく)ダグラスが、老フリーリー大佐のエピソードに登場します。 フリーリー大佐は昔の出来事をいきいきと語るので、ダグラスたちに「〈タイム・マシン〉」と名付けられます。大佐の話を聞くのも、新しく世界を知ることのひとつで、ワクワク感あふれています。ところが大佐はむかし暮らしたメキシコシティーに長距離電話して受話器から街の喧騒を聞き、若返った気持ちになったまま昇天しているところを、ダグラスたちに発見されます。 (余談ですが長野まゆみによく出てくる、電話の受話器の向こうの海の音を聞く場面は、きっとこのエピソードがもとになっているのでしょうね。) つまり、老人は不変に見えるが不変ではないこと、去ってしまうことをダグラスは目の当たりにする(「発見と啓示」)のです。不変に思っていた人や物事の死や変化は、物語のいたるところに出てきます。大佐だけでなく老ルーミスもおおおばさんも死に、殺人事件もあります。毎日遊んだ親友は引っ越し、市街電車はなくなってバスになり、1セントで動く占い人形は壊れてしまいます。 これも、この時期の子供をテーマにした児童文学にはよくあることで、プレ思春期の子供たちは、自分自身の生の存在を意識するだけでなく、幼かった自分が“死んで”、黄金の幼年時代が終わりを告げ、未知で自由でおそろしい大人の世界へ向かってゆかねばならないことを、察知するからです。 だから、幼年時代の終わりは死の意識をはらんでいます。いとうせいこう『ノーライフキング』と同じように、ダグラスとトムの兄弟も死の危険を乗りこえるイニシエーションのまっただ中なのです。夏の終わりにダグラスが高熱で寝こむあたりが、死の危険の集大成ですね。 それはまた、夏という季節にもぴったり来ます。夏は動植物が生を謳歌しますが、生の頂点とはすなわち、折り返し地点、凋落と死の始まりでもあるのですから。 幼年時代の自分の“死”を回避しようとしても不可能ですが、たとえばたんぽぽのお酒や思い出アルバムのような何かの形にしたり、ダグラスのメモ帳のように記録したりすれば、黄金の幼年時代を永遠化して保存することができるかもしれません。 季節がちがうので蛇足ですが、私は小学生の頃、キンモクセイの花をビーズ用の小さい空き瓶につめて保存しようとしたことがあります(みごと失敗しましたが)。今でもキンモクセイを見たりかいだりするたびに、ランドセルをゆすって花を集めながら帰った日々の思い出がよみがえります。
June 21, 2022
コメント(0)
-
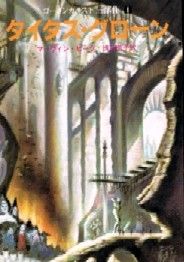
キャラ立ちがすごい『タイタス・グローン』(ゴーメンガースト三部作)
三部作の最初の『タイタス・グローン』しか読んでいないのですが、それというのも文庫本ながら超分厚く、表紙もおどろおどろしいうえに、ファンタジー的感動要素があまりないと思われた(3冊読めばあるのかもしれないけど)からなのでした(画像は現在の表紙とは違います。が、現在の表紙も負けず劣らずです)。 舞台となるゴシック調のゴーメンガースト城とその周囲地域は、架空ですが異世界というほどではなく、中世ヨーロッパのどこかにありそうな感じ。城は何世代にもわたって増築されて石造りの迷宮のようになり、それだけで一つの閉じた世界をかたちづくっています。 物質的に閉鎖世界であるだけでなく、住人たちの営みも、古来不変の伝統的ルーティンにがんじがらめにされています。 城内では、個性のキツすぎる人々が、決まったエリアでそれぞれのキャラにふさわしい不変の日々を送っています。彼らには意味深な名前がついていて、城の当主はグローン(「うめく」)伯爵セパルクレイヴ(「墓の墓」)、料理長はスウェルター(「汗だく」)、書庫長はサワダスト(饐えた埃)などなど。そもそも城の名ゴーメンガーストも「大食で陰惨」で、ゴシックすぎて滑稽ささえ感じられます。 巻頭の序文その他で、このような登場人物は、ディケンズ(19世紀)の小説に出てくる、特徴的な性格を強調した典型的なキャラクターと比されています。つまり今風に言うと、"キャラが立ってる"ということ。ほんとに、本の厚みのほとんどが、キャラの描写(描写のしかたまで個性的!)にあてられている感じがします。 どこまで読んでも、人々は徹頭徹尾おのれのキャラ全開でーーセパルクレイヴは内省的で鬱屈し、スウェルターは醜悪な肥満体で弟子をいじめ、90歳のサワダストは古文書通り一分の狂いも許さず儀式を執行します。強烈な個性ゆえにほぼ全員が自己完結しており、他人が何を考えているかなど興味がない。対立することはあっても心の交流はほとんどありません。 世継ぎの男子(タイタス)が誕生してさえ、キャラクターたちの日常は揺るぎません。母である奥方はすぐにも床上げして、ペットの無数の猫や鳥相手の生活に戻ってしまいます。老乳母はきりなく愚痴りながらタイタスの姉フューシャ(もう15歳)を甘やかして世話をやいていたのが、今度はタイタスの世話をやくことになるだけです。 とはいえ、赤ん坊のタイタスのために、若い乳母が城外の村から連れてこられます。初めて出てきた外の世界の住人(しかも若い女)が、城の雰囲気を変えたりするのだろうか?と淡い期待をしても、…さっぱりです。 城内のキャラとは対照的に、城の周囲の村人たちは一様に泥小屋に住み、誰も彼も同じようで、 肉体が成熟しきると美しさが崩れ去って、わずかな時間生き生きと栄華を誇った花の如く萎びてしまうのだ。 ーーマーヴィン・ピーク『タイタス・グローン』浅羽莢子訳 という具合。新しい乳母のケダも若さの最後の一瞬を生きているだけで、数ヶ月タイタスに乳をやったあとは村に帰り、若い村の男2人と生命を燃やし、あっという間に燃えつきていきます。 城の内も外も、もはや変化しないという意味で、老人ばかりが目立ちます。 ・・・異世界のはずなのに、何だか、思い当たりますね。日々不変の狭い日常。閉塞し老いた社会。形式的で心のふれあいのない人々。我々の世界も案外似ているかも、なのです。 ただ、奇妙な救いになっているのは、ゴーメンガスト世界を取り巻く山や空や気象などの荒々しい自然です。ぶきみな「ねじれの森」でさえ、鮮烈で息がつける気がします。 主人公タイタスはこの巻ではまだ赤ん坊で、閉鎖社会を打ち破るのは続巻以降なのですが、この巻にも変化をもたらす登場人物がいないわけではありません。 一人は、料理人見習いから下剋上していく若者スティアパイク(「矛を操る」)。彼は脱走し屋根にのぼり(開放感のある眺望の描写があります)、陰謀をたくらんで結果的に城主セパルクレイヴを狂死においやります。しかし、終始一貫そういうキャラであり、彼自身は不変といえるでしょう。 私が注目したのは、唯一変化を遂げる登場人物、タイタスの姉フューシャです。見晴らしのある屋根裏部屋を子どもらしい秘密基地にして自己充足していた彼女は、最初、弟の誕生を嫌がって、 …だめよ! 許さない! 許さない! そんなこと、あっちゃいけない、… ーー『タイタス・グローン』と泣きじゃくっていました。他の人々同様、不変を望んでいたのです。 ところが、屋根裏部屋には窓からスティアパイクが乱入し、それから彼女の生活が変わり始めます。スティアパイクを自分なりに観察することから始まって、眺めるだけだった外へ実際に出かけ、森を探索します。次に火事と父の狂気に直面すると、それまで交流のなかった父への愛と気遣いに目ざめ、彼を救おうと心を痛めます。 ところで、父グローン伯爵は唯一の生きがいである蔵書が焼けたのがきっかけでメンタルのバランスを失い、フクロウになってしまいます。体にせよ心にせよ本当に変身すればファンタジー(センス・オブ・ワンダー(驚異)をともなう)ですが、グローン伯爵セパルクレイヴの場合は、フクロウになってしまう自分を意識し続ける心の病のようです。 細かく描かれる彼の心情を読んでいくと、何だかセパルクレイヴは最初からフクロウだったと思えてきます。つまり、読書によって正常な精神をつなぎとめていただけで、物語の最初から、廃墟のような城のあるじとしてのフクロウ性こそが彼の本質だったのでしょう。 いずれにせよ、粛々と城のしきたりをこなしていた父が、フクロウのようなポーズで炉棚にあがりこんで大真面目にホーホー言うのを見て、フューシャはショックを受けます; …この長い数秒のうちに少女は多くの男女の理解を越えた年齢までいっぺんに年を取ってしまう。 ーー『タイタス・グローン』 気の毒なフューシャではありますが、このあと彼女は医者を呼び、乳母を気遣ったり弟タイタスの世話をするようになります。硬直化しとりつく島もないキャラクターたちの中で、生き生きとしているのは、彼女だけという気がします。 こうして長大な第1巻は、2歳のタイタスが父の死後当主となり、冒頭に出てくる、城で最も孤立不変な最上階広間の管理人ロットコッド(「腐ったタラ」)でさえ「変化」を感じる、という記述で終わります。 こんなにも個性派揃いのキャラを紹介することで、主人公登場前の「不変」さと、いよいよ始まった「変化」の重要性がきわだっています。
July 3, 2019
コメント(0)
-

謝肉祭の終わり--「ろうそくを持っていない者は…」
今年の謝肉祭(カーニバル)はきのうで終わって、今日は聖灰水曜日だそうです。以前このブログでもとりあげたホフマンの『ブランビラ王女』を再読しました。これは、ローマの謝肉祭を舞台にした幻想物語です。 あとがきによると、作者ホフマンは実はローマどころかイタリアに行ったことなどなかったのに、イタリア喜劇の仮装が描かれた版画に着想を得て、この物語を書いたそうです。また、謝肉祭の様子はゲーテを参考にしたとのこと。 なるほど、ホフマンもドイツの人ですから、明るい古代文明の地イタリアに憧れをいだいていたのですね。 そして、ローマの謝肉祭最終日(マルディグラ)の夜に叫ばれるという、 <蝋燭ヲ持ッテナイ奴ハ殺シチマエ!> --E・T・A・ホフマン『ブランビラ王女』種村季弘訳 も、ゲーテの引用だそうです。若いとき読んだ岩波文庫のゲーテ『イタリア紀行』(相良守峯訳)をさがしてみると、ありました、「蝋燭の燃えさし(モッコリ)を持っていないものは、殺されてしまえ!」と言いながらろうそくを消し合う大騒ぎをして楽しむと。 そして、何だかこれに似たセリフに覚えがあると思ったら。 そう、エンデ『鏡の中の鏡』の第7話に、 「明かりをかかげている者どもを、殺せ!」 ーーミヒャエル・エンデ『鏡の中の鏡』丘沢静也訳というのがありました。おお、エンデもドイツ人でしたっけ。こういうふうに発見がつながってくると、面白いですねえ、ブック・サーフィン。 もっともエンデのは文の意味が逆になっていて、このあと本当に虐殺が起こるという血なまぐさい場面。羽目を外して楽しむ祭のかけ声とは正反対の裏返しですね。 謝肉祭の無礼講は、聖/俗、男/女、貧/富、生/死など既存の価値観をひっくり返すカタルシスだそうですが、エンデはそれをさらに逆手に取っているというわけです。 さらに連想すると、明かりをかかげるというのは、ユング心理学で言うところの、理性の象徴です。明かりをかかげて暗闇を照らし、真実を見極めるという行為は、たとえば「美女と野獣」などのおとぎ話で、男の正体を見極めようとする女性なんかに表されているそうです。 すると、ろうそくを持つ者を殺せというエンデの恐ろしいセリフは、理性が圧殺され狂気が支配する感じがしますね。そしてどうしても、前世紀のあの大戦中のドイツ(そしてイタリアや日本などでも)の悪夢ーー全体主義によって個人の理性が圧殺された悲劇を思い起こさずにはいられません。 お祭の狂騒とほんとうの狂気とは紙一重。そんな気のする、聖灰水曜日でした。 木曜日からは、四旬節(レント)の断食です。中山星香の古~い短編「魔法使いたちの休日」を思い出しました。
March 6, 2019
コメント(0)
-

異世界のリアルな手触り--『赤い月と黒の山』
ジョイ・チャント『赤い月と黒の山』は、異世界ファンタジーのある種の典型でして、①主人公が異世界に投げ込まれる、②そこでの大事件に重要な役割を果たし、③また現実世界に帰ってくる、というもの。 有名どころでは、「ナルニア国ものがたり」の『ライオンと魔女』(C・S・ルイス)や『はてしない物語』(ミヒャエル・エンデ)なんかがそうですね。 読者の興味をそそるのは、①まず異世界の様相への驚きと好奇心。それから、②主人公が果たす、異邦人ならではの役割とは? さらに、③どのように現実に帰還するか。 (お恥ずかしながら拙作『海鳴りの石』でもその辺を一生懸命追求しております。) 『赤い月と黒の山』では、そのどれもが緻密ですばらしいのです。 まず、異世界に転移した主人公の驚きととまどい、どのようになじんでいったかが、細やかに描かれます。ああ異世界に来たんだなあ、で終わったりしません! しかも、主人公が3きょうだいなので、それぞれが年齢と性格に応じた反応を見せますが、はっきり言って「ナルニア」の4きょうだいよりずっと深くて真に迫っています。 異邦人ならではの役割についても、3人3様の役割があるのですが、最初から分かっていてそれ目指して進むのではなく、あとになって判明するように仕組まれています。 それから現実への帰還も、予想どおりの帰り方をする弟妹と、予想外のなかなかたいへんな帰り方をする兄とが描かれ、迫力・魅力満点です。 さきに挙げたルイスやエンデを初め、精巧に創り上げた異世界を披露する作家は多くいますが、ジョイ・チャントの異世界は精巧というよりリアルです。これは私がルイスよりエンデより、トールキンが好きである理由でもあるのですが、異世界の手触りがリアルなのです。 道は突然、生きもののように見え、ただの固く踏み固められた土とずんぐりした草の帯ではなく、精神と意志を備えたもののように感じられた。自分を見限った人間どもの浮気さなどおかまいなしで、無視されようが気にもとめず、どこまでいっても終わりのない忍耐強い蛇のように、道標の脇を走り、昔ながらの終点へと続く。 --ジョイ・チャント『赤い月と黒の山』浅羽莢子訳 これは主人公の一人ニコラスが古い街道あとに来た場面の一部です。ニコラスは兄や妹よりも客観的に異世界を観察し、考え深く味わいます。物語の本筋とは無関係な古い道の、このような描写を読むと、まるで作者が本当に異世界に旅して得た感慨をニコラスに語らせているかのようです。 この本のまえがきによると、実際その通りなのです。作者は子供のころ自分が異世界の女王であると空想し、以来ずっと自分の世界を持ち続け探検しつづけてきたというのです。作者の成長につれ異世界は住民を増やし変貌し、歴史を持ち、豊かになっていき、大人になってその一端を、物語の形で他の人に紹介した・・・それがこの本というわけです。 様々な異世界を次々と量産する作家も多いなかで、ほんとうに自分の心の拠り所である一つの世界にこだわりつづけたこの作者のやり方は、素人っぽいと言えるでしょう。しかし、その世界は濃密で細部までリアルで、空気の味や石ころの手触りまで、作者が愛でた通りに伝わってくるのです。 トールキンも生涯、同じ「中つ国」の言語と歴史とを追求した人で、実在の世界の歴史や文化を研究するかのように、ああでもないこうでもないと、自分の創った異世界を探求しつづけました。 だからこそ、年長の主人公オリヴァは最後に、異世界を忘れる飲み物を辞退して、現実に戻ってきます。 「兄さん--あれ、みんな本当にあったの?」 ・・・ 「そうとも」・・・「そうだとも、ペニー。全部本当に起きたんだよ」 --『赤い月と黒の山』 このリアルが、すばらしいです。 作者は続編、というか、自分の異世界の他の物語をさらにいくつか出版していますが、未訳のようで残念です。
October 11, 2018
コメント(0)
-
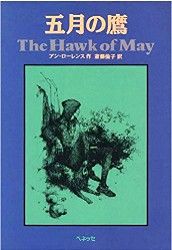
『五月の鷹』--地味でもアーサー王もの、純英国産のファンタズニックが素敵
タイトルの「五月の鷹」とはグワルヒメイ、つまりガウェインのことです。アーサー王の甥で、円卓の騎士の中でもかなりメジャーな人物。 伝説ではアーサー王自身の探索(クエスト)が、この物語ではガウェインの探索として描かれていますが、よくある怪物や悪漢を退治するとか姫君の救出ではなく、「すべての女が最も望んでいることとはなにか?」という問いの答えを探すこと。なんとも地味なクエストです(結局は姫君の救出につながるのですが)。 ガウェインの性格もこの物語では生真面目で控えめなため、それほど魅力的ではありません。 けれど、私がこの物語で気に入っているところは、地味なガウェインが地味な探索で、ごく自然に何の呪文も仕掛けもなく、ふっと不思議な世界へ入りこむところなのです。 たとえば、 わだちがあるところを見ると、ふだん人々が使っている道なのだろうが、いったん、まだ淡い色の若葉の下に入ると、人間のたてる物音は一切きこえなかった。 --アン・ローレンス『五月の鷹』斎藤倫子訳と、普通の道をたどっているはずが、いつの間にか果樹園の廃墟になり、わだちには昨年の落ち葉が積もっている。静けさの中に花の香りが充満し、そよとの風もなく、ガウェインは現実感が薄れ、空腹も感じず、…やがてかそけき声に気づくと、それは魔術師マーリンが自分を呼ぶ声だった… 現実世界とつながっている幻想世界。そこへ至るのに、特別な儀式は要らない。人里のすぐ隣にある大自然という異界。五月祭の前日には乙女たちが草地で輪になって踊ります。さすらうガウェインにとって、その音楽や歌は、まるで呪文のよう、すばやく消え去る姿はまるで幻のよう。 こういう感覚は、一昔前の日本人には結構おなじみだったりして、たとえば『となりのトトロ』はタイトルのとおり、自宅の庭から行けてしまうところにトトロが住んでいます。異界との境界はあいまい、というより、異界は現実世界に自然に混じりあっている。 急に話がとびますが、先ごろ『英国幻視の少年たち』の2巻目(ミッドサマー・イヴ)を読んでみたのですが、やっぱり私には英国っぽさも幻視っぽさもあまり感じられなかったです。妖精の輪が出てきたり、夏至に妖精界との通路が開いたりするのに、そこにとってつけたように--まるでゲームの画面にあらかじめ設定してあるアイコンのように--出てくるキノコの輪や坑道が、なんとなくわざとらしく感じられたりして。 ロウソクに反時計回りに火をつける、とか、いろいろ手順を踏むこと自体は面白いのですが、呪文をとなえるとスイッチを切り替えたように異界が現れるのでは、どうも雰囲気が・・・、「幻想」性がなさすぎる気がするのです。 トトロやネコバスが、一定の呪文や儀式で必ず現れたら、なんだかがっかりしませんか。 イギリスや日本の異界は地続きであってほしい、という私の理想は、『五月の鷹』に出てくるような、実際に隣にある異界のかもしだすかそけき気配を描いた作品を多く読んだり観たりしてきたせいだと思うのです。 もってまわった言い方になりましたが、つまりそういう異界を感じたい時に、おすすめの一冊『五月の鷹』なのでした。
August 12, 2018
コメント(0)
-
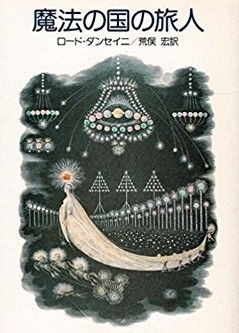
ダンセイニ卿のほら話『魔法の国の旅人』
ロンドンの紳士の集うクラブで、常連ジョーキンズ氏が語る“トラベラーズ・テイル(ほら話)”。ちょっと前に『ウイスキー&ジョーキンズ』という本が出ましたが(未読!そのうち買わねば)、これも同じシリーズ。ただし私が持っているのは30年以上前の早川FT文庫です。このころ、荒俣宏訳のダンセイニ作品が次々出版されたのでした。 英国の伝統的文化“クラブ”の雰囲気を味わえるほか、文学的だけどあくまで軽い語り口や、20世紀前半の古風なSF、英国やアイルランドらしい幻想趣味、自然描写の精妙さ、などが、情報過多で多忙すぎる現代にはレトロで心地よい感じ。 大好きな「ドリトル先生」シリーズの“ネズミ・クラブ”についてでも書いたことがありますが、この種の読み物はクラブという一つの枠の中にさまざまなジャンルの物語が詰まっていて、そのバラエティを味わったり、気分によって好きな物語をチョイスして再読したり、そんな楽しみ方ができます。 でもダンセイニですから、すべてに幻想四次元的な奥深さが漂っているのも嬉しい! 以下、いくつかご紹介と感想。 ジョーキンズが人魚に恋をした思い出、「ジョーキンズの奥方」。ホテルで見せ物にされていた人魚は、神秘的な海の瞳をしているけれど、ホテルの噂話が好き。かみ合わない二人がおもしろい。人魚姫の野性の美に恋をしたジョーキンズは野性のゆえに失恋する。 「妖精の黄金」は、アイルランドの有名な妖精レプラホーンの民話どおり。予想できる結末だけど、ちょっとだけSFのタイムトラベル的な味付けが最後に。 ツングース大爆発にまつわるほら話「大きなダイヤモンド」。トラベラーズ・テイルの真骨頂! 「最後の野牛」は期待しているとジョーキンズに煙に巻かれ、「クラヴリッツ」は「時と神々」調の小話で、ジョーキンズ氏はしばし不在。と思ったら「ラメセスの姫君」で古代エジプトの恋物語を紹介してくれる。ところでこの話、井辻朱美の「ファラオの娘」とイメージが重なってしまいました(ストーリーは全然違いますが、クレオパトラを始めエジプト美女というのは独特のイメージがありますね)。 「ジャートン病」もちょっとごまかされた感じがするけれど、次の「電気王」は読み応え十分、語りはくどいけれど大変おもしろかった。この話の主人公がジョーキング氏(ミスター冗談)ではなくメイキング氏(ミスター発明家、実業家)という名前なのが、まんまで人を食っている。エジソンなんかがモデルかしら。 メイキング氏は自分のあふれるアイデアやその実用化の思考に終われまくってノイローゼになり、救済を求めてインドへ行く。インドの魅力たっぷり。特に、最後に救済を得るヒマラヤのラマ教寺院は、ペガーナの世界をどこか彷彿とさせる。この話や、神坂智子のシルクロードなコミックス、さらにいつぞや読んだ藤枝静男『田紳有楽』なんかによると、やはりラダックとかあの辺は悟りを開くには最適な所みたいですね。そして、オチが最高! 「われらが遠いいとこたち」「ビリヤード・クラブの戦略討議」はちょっとひねくれたSFです。前者はいかにもどこかで読んだような展開(語り尽くされた感あり)ですがレトロな宇宙旅行を楽しめます。後者は、ちょっと笑えないオチですね、核兵器の存在が当たり前になってしまっている現代、しかもわが国では…
September 22, 2017
コメント(0)
-
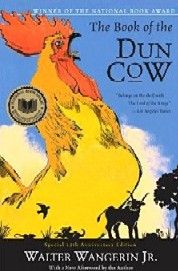
ニワトリの出てくる物語ーー『ダン・カウの書』
お正月も過ぎましたが、酉年ということでニワトリの出てくるお話を紹介。 今はなきサンリオ文庫の『ダン・カウの書』(ウォルター・ワンジェリンJr.)です。 主人公がションティクリア(=高らかに歌う、つまりコケコッコー)という名の雄鶏で、彼と配下の動物たちが、悪の化身と戦う勧善懲悪なストーリーが、もったいぶったコミカルな調子で進んでいきます。 中世ヨーロッパ文学に狐のルナール(ライネッケ狐)の物語群がありますが、ちくま文庫の「狐物語」を見ると、荘重な叙事詩をまねてユーモラスに語られており、そこに雄鶏シャントクレールやその妻パントが、動物たちの一員として出てきます。 どうも『ダン・カウの書』の主人公ションティクリアと妻パーティロット(または他の雌鶏たち、登場する田園の小動物たち)は、この中世パロディ叙事詩を念頭に描き出されたのではないかと思うのです。 ちなみに「ダン・カウの書」というのもアイルランドの古い神話伝説を集めた書物の名でして、私はむかしこの本と勘違いして雄鶏の物語を買ってしまったのでした。中味がアイルランドとは全然ちがう動物寓話で最初がっかりしましたが、読んでみるとそれなりに面白いものでした。 それなりに、というのは、寓話とは作者が伝えたいことを細部まで意図して物語に仕立てたもので、イソップ寓話とか、ジョージ・オーウェルの『動物農場』のように、表面の物語よりも、それにくるまれた教訓などの方が存在を主張しがちなのです。作者の意図抜きには読めないお話、とでもいいましょうか。 けれど私は物語自体が主体的に展開していくファンタジー(分類の基準に曖昧なところはありますが)が好みなのです。作者が何より物語を好きで語っていくうちに、おのずと主張がにじみ出たり、普遍的な何かが現れ出てきたりする、そういうのが好きです。 この本の作者はルーテル教会の牧師さんだそうで、上から目線で物語る語り口といい、宗教性が強く感じられるストーリーといい、やはり「キリスト教の寓話」なのだと思います。が、私としては物語そのものを楽しく味わうことにしています。 で、半ば滑稽でドン・キホーテ的に描かれる領主ションティクリア氏ですが、オンドリというのはその姿や仕草から、どうもこんなふうに自意識過剰な権威のカタマリに描かれることが多いようです。でも、笑い者にしてばかりでは済みません。彼には悪の番人、そして目覚めた悪との戦いの司令官としての神に与えられた使命があるのです。 物語の後半は悪との決死の戦いが生々しく繰り広げられ、ションティクリアや動物たちの心の中の葛藤なども織り込まれて、目が離せません。ひねくれ者のイタチ、自己憐憫のカタマリの犬など個性豊かなキャラクターたちのそれぞれの心情の変化も、真に迫っています。 そして、滑稽に思えたションティクリアの時を告げる鳴き声(彼の「聖務日課」だそうです)が、皆の心を結びつけ、秩序を保ち、悪をおしかえします。 ちょうど先日、NHKの動物番組「ダーウィンが来た」お正月特集で、「原始時代、野生のニワトリは、闇の終わりと朝の到来を告げる鳴き声ゆえに、人間に価値を見いだされ家畜化された」と解説していましたが、まさにその通り。コケコッコーは闇をはらい光をもたらす呪術的な声なのです。 舟崎克彦『ぽっぺん先生と泥の王子』でぽっぺん先生こと鳥飼の埴輪が抱えていたニワトリは、ときをつくって闇の世界に夜明けをもたらし埴輪たちを目覚めさせます。また、ホープ・マーリーズ『霧のラッド』(主人公はチャンティクリア判事/市長)にも、 Before the cry of Chanticleer, (チャンティクリアの叫びの前に) Gibbers away Endymion Leer (エンディミオン・リアはぶつくさ逃げる)などとあり、訳者は「妖精はオンドリの鳴き声を聞くと逃げ出す」という伝説を紹介しています。 夜明けを告げ、闇や悪や迷妄をはらうコケコッコー。ニワトリって実はファンタジックな生き物だったのです!
January 13, 2017
コメント(2)
-

力を封じられた王様--『夏の王』『光をはこぶ娘』
この夏は、各地で猛暑日も多いですが、豪雨もほんとうに多いですね。 災害が心配なほどめちゃくちゃに降る夕立を見ていると、ほんとに天の神さまか誰かが癇癪を起こしたかと思ってしまいます。 ということで、O.R.メリングのアイルランド・ファンタジーの中で、まだこのブログにとりあげていなかった『光をはこぶ娘』を思い出したのですが、お話の中に、妖精王のひとりルーフが妃の失踪を嘆くあまり、荒れ狂って天を裂き嵐を起こすというくだりがあるのです。 メリングの描く妖精はシチュエーションによって体の大きさが変わり、ルーフも人間並みの大きさのときもありますが、主人公の少女ダーナが初めて見たときは、山中の湿原に横たわる巨人でした。 手足を広げ、背に大石をのせて横たわる王の姿が見えたと思ったつぎの瞬間には、石のケルンのそばに浸食された泥炭の堆積が広がっているようにしか見えなくなる。 --O.R.メリング『光をはこぶ娘』井辻朱美訳 王の民である小さな妖精たちは何とか王をなだめて眠らせようと子守歌を歌い、大きな石で押さえつけて動かないようにしていました。しかし怪力の王は悲しみに狂って暴れつづけ、それに呼応して嵐はひどくなり、とうとう湿原は「爆発」し、泥流が洪水のようにあたりを破壊します。 荒ぶる自然神をなだめるのに、よくある生け贄とかでなく、子守歌を歌うというのが印象に残ります。 日本やほかの多神教の神話伝説に似たような例があったかしら、とずいぶん頭をひねりましたが、ありそうで実は無いのか、単に私が知らないだけなのか、どうも思い当たりません。 悪さをする神を、他の神がこらしめたり追放したりする例(日本のスサノオとか)はあるのですが。役小角の使い魔にされた一言主とか、弱くなってしまった神さまとも、ちょっと違うし。 一方また、メリングのこのシリーズの別の巻『夏の王』では、タイトルにもなっている荒ぶる妖精王は、鳥族の女王である牝ワシを殺すなどの乱暴をしたため、他の妖精たちによって捕らえられ、岩山の中に幽閉されています。 「・・・じつを言えば、<王>の眷属のなかにも、その捕縛に手を貸したものがあるとやら。(中略)彼を二、三世紀幽閉しとくべきだっていう意見が、大勢を占めていた。」 --O.R.メリング『夏の王』井辻朱美訳 こんどはなだめられるのではなく、力づくで閉じこめられている神性を持つ王。それもやはり臣下の手で。 こういう存在って、もしかしてアイルランドやケルト特有なのでしょうか。 それにしても、メリングは妖精王の狂気もそれを救う力も、すべての原動力を「愛」であるというところに持っていくのですが、各所にちりばめられた聖書の引用とあいまって、ああキリスト教文化だなあ、とニッポン人読者である私は感じるのでした。 (豪雨から、ずいぶん話がズレてしまいました)
August 14, 2015
コメント(0)
-

ハラハラ宝探し--『コーンウォールの聖杯』
「闇の戦い」シリーズのスーザン・クーパーの最も初期の作品の一つ、『コーンウォールの聖杯』は、今では「闇の戦い」シリーズの第1作とされていますが、雰囲気は『闇の戦い』以降の4作とだいぶ違います。 4作の主人公、11歳にして「古老」に選ばれたウィルがまだ登場せず、シリーズを貫く善悪の歴史的戦いもまだ表に現れてきません。物語のメインは3人兄弟の夏休みのお宝探しで、「悪」はお宝を狙う悪者にすぎないため、いろいろ背景に疑問は残りますが、とりあえず子供たちの冒険を楽しむことができます。 泊まった別荘の屋根裏探検、古地図と古文書の発見。なぞめいた立石、月光が示すお宝の隠し場所。村のお祭。子供たちだけで海辺の洞窟探検。ついにお宝「コーンウォールの聖杯」発見。 並行して悪者がせまってきます。悪者の正体も、味方となるメリー大伯父さんの持つ不思議な雰囲気も、子供たちにはなぞめいたまま。読者としては少し気になりますが、神秘的な雰囲気を残しておくのも、活劇的な宝探しの奥行きとしては、成功していると思います。 というのも、子供の目線から語られているので、背景が重すぎるとどうしても全体がむずかしくなってしまいます。あとの4作がまさにそんな感じで、子供でありながら歴史的戦いの善の側の重要人物「古老」となったウィルは、重い使命に、ともすれば子供らしさを失いがち。 歴史ファンタジーとしての世界の構築は、4作のほうがしっかり説明されていて、完成度は高い。しかし、それゆえのハードさが全編を覆っていて、読む方にもかなり「覚悟」が要ると思います。 それはちょうど、子供向けのお話として書かれた『ホビットの冒険』が、背景の善悪の争いを追求した結果、重厚でときには悲壮感すらただよう続編『指輪物語』三部作へと続いていったのと、同じような経緯ではないでしょうか。 ともあれ、1作目の『コーンウォールの聖杯』は、重厚長大な「闇の戦い」以降4作の前座として、より親しみやすく楽しめる作品だと思います。 全体に、さほどファンタジーじみてはいなくて、日常の範囲内でのマジカルな体験がいくつかあるばかりです。が、その中でも、イギリス人にはきっと魔法のようなオーラを放つ「アーサー王」が、子供たち、とくに年少のバーニーに与える影響力が、わたし的にはすばらしいと思いました。
March 5, 2015
コメント(0)
-

古い魔力に満ちた春の夜--スーザン・クーパー『みどりの妖婆』
『みどりの妖婆』は、冬至からクリスマス(一年の変わりめ)にかけての雪の恐怖や魔法の対決を描いた『光の六つのしるし』の続編で、「闇の戦い」シリーズの第2巻。こんどは、海辺に舞台を移し、復活祭(冬から春への変わりめ)に起こる百鬼夜行が出てきます。 ヨーロッパに「緑の男Greenman」と呼ばれる精霊のモチーフがあり、ウェールズではこの精霊が冬の精霊に勝利して春を招くというグリーンマン・フェスティバルが開催されるそうです。日本でも節分で鬼を追い払ったりするのと、似ていますね。 この物語では男manではなく、緑の魔女(原題Greenwitch)の像なのですが、復活祭のころ、セイヨウサンザシ、ナナカマド、ハシバミなど魔法と関係の深い植物でつくられ、村の女性たちが願掛けをした後、海へ投げこまれ(奉納され)ます。捧げものを受け取るのは太古の海の女神ティーシス(ギリシャ神話のテテュス)。 いろいろな神話や物語で、海あるいは水は、一般の魔術が効かない領域、それらより古い原初的・野性的な力を持つ領域とされるようですが、このお話でも海の力は「荒魔術」と呼ばれます。有史以前、善悪という観念もまだないころの人類が大自然に感じていた畏怖そのもの。それは主人公の現代の子供たちにも、根源的な恐怖となって伝わってきます。 その憑かれた一夜のもろもろの幻影や物の怪や亡霊が、小さな海村が経てきたもろもろの世紀から抜け出して来たトリウィシックの過去の民が、時間の中の暗黒の一点に集中したのだった。 --スーザン・クーパー『みどりの妖婆』浅羽莢子訳 もともと「闇の戦い」シリーズは、アーサー王周辺を中心に歴史の中の善悪の戦いを軸に展開していくのですが、その中にこのような、「世の始まりより前からのもっと古い魔法」(C・S・ルイス「ナルニア」シリーズの言葉)が出てくるのは、興味深いです。 ストーリー的には、子供たちの視点からの善悪の対立や謎解きなども魅力的ですが、作者の描く本能的・根源的な恐怖感は、1作めにもおとらず真に迫ってすごいです。 ついでに、新装版でない古い方の表紙絵も、なかなかすごい迫力です。
February 23, 2015
コメント(2)
-

古い本を読み直すと
このところずっと、手持ちの古いファンタジーを読み返しています。 すでにこのブログで取り上げたことのある本もありますが、それでもまた読み返すと忘れていたあれこれ、新たに気づくあれこれがあって、おもしろいものです。 まずロイド・アリグザンダー「プリデイン物語」シリーズ。アメリカ人作ですが、ウェールズ伝説ほか古いファンタジーの要素がいっぱいつまっています。 「忘れていたあれこれ」の一つは、以前ジョージ・マクドナルド「巨人の心臓」について書いた時、巨人が自分の心臓を取り出して鳥の巣に隠しておくというモチーフ。「どこかで聞いたような話」と表現したのですが、見つかりました。プリデイン物語第4巻『旅人タラン』に出てくる悪い魔法使いモルダのエピソードです。 モルダは自分の命そのものを、安全なように、小指の骨に宿らせて、木のうろに隠しました。主人公タランは、仲間のいたずらカラスやけだものガーギとともに、偶然その骨を見つけます。そして後に、それを使って悪い魔法使いをほろぼすことができました。 大切な指の骨。このモチーフからは、また別に、タニス・リー「冬物語」に出てくる聖遺物である巫女の人差し指の骨のことも思い起こされます。 それはそれとして、命をよそに隠す原型がもしかしたらあるかしらと、ウェールズ伝説『マビノギオン』を読み返してみましたが、残念ながら見つかりませんでした。 その代わりに、プリデイン物語にもよく出てくる「マソイヌイの息子マース王」という名を、スーザン・クーパー「闇の戦い」シリーズ第1巻『光の六つのしるし』で見かけたぞ!と、不意に思い出しました。ちょうど今冬は寒くて雪がたくさん降ったりするので、冬至からクリスマスの十二夜にかけて大雪が降るこの物語のことが気になっていたのです。 そこで、この本も読み返して改めてその重厚さを味わいました。 そうしたら、クリスマス翌日にミソサザイを集める場面が出てきたではありませんか。以前はすっかり読み飛ばしていましたが、今回は、一昨年入手した『マン島の妖精物語』に鳥の王様ミソサザイを狩る風習が紹介されていたのを思い出しました。『光の六つのしるし』では、ひつぎに載せられたこの鳥たちが、不思議な力を持つ仙女に変身したように描かれ、印象的でした。 ところで、いまこれを書くために検索していて、この物語が映画化されていたのを発見しました。2008年「ザ・シーカー」というタイトルで、DVDも発売されています。レビューを少し読むと、イギリスの田園など舞台背景は美しいが、どうも原作とかなり違うしあまり評価がよくないようです。私は、映画化されるとき原作がどのように変えられるかには、興味があるのですが、うーん、ここまで酷評されると、観るのをためらいます。 一定の評価のある原作を映像化するのって、むずかしいのですね。 などと、興味があちこちへ飛びながらも、そういうブックサーフィンが楽しいHANNAでした。
January 12, 2015
コメント(0)
-

最低の主人公が変わる・・・ジェフリー・フォード『白い果実』
1997年世界幻想文学大賞受賞作。のわりには、表紙やタイトルが地味な感じ。 表紙はバベルの塔みたいな絵で、これはこれで良いのだけど、「部分」と書いてあるせいか、いま一歩。それに、たぶん物語とは無関係に描かれた絵を持ってきたようで、なかみと「風合い」が合っていない感じがします。 邦題は、原題“The Psysiognomy”(人相学、骨相学。本文中では観相学)だと地味なので、物語で探求されるお宝である「白い果実」にしたのでしょうけど、やっぱり地味かも。このところファンタジー系の派手な本がどんどん出版されているので・・・、しかし、この地味だけれど上品なセンスの良さが、国書刊行会らしいところでしょうか。 物語の方は、一人称で語る主人公が、品もなくセンスも最低です。観相学の権威ということですが、ヒトラーを思わせる狂気の独裁者の右腕。権柄ずくでえらそうで、インテリのくせに暴力的で、とにかく鼻持ちならない悪党。あまりに最低なのでその言動、独白すべてが滑稽なほど。もちろん、作者はこれでもかと誇張して悪人を描き出しているのです。 舞台は、独裁者の脳から生まれた水晶とサンゴの都市。独裁者が命じて造らせたというだけでなく、後半で彼の頭痛に連動して建物が爆発したりしています。 あるいは砂丘の中の硫黄採掘鉱、これも見張りの兵士の頭の内部とつながりがあるようです。 そのほか、美薬という名の麻薬、青い鉱石になってしまう鉱夫、〈旅人〉と呼ばれるミイラ。楽園、魔物、キメラ的な人造人間たち・・・、そのようなアイテムにいろどられた異世界で、最悪な主人公は、恋をし、すべてがそこから変わっていきます。 物語の後半は、改心した主人公の贖罪の道のりという感じで、読んでいる方はホッとする一方、前半の毒気がなくなって物足りない気もします。独裁者も、改心した主人公の視点で描かれると、一種のあわれさが目立ちはじめます。最後に都市が崩壊し自分もよれよれになっても、独裁者は生き方を変えることができません; 「・・・やらなくてはならないことがたくさんある。ゆうべまた夢を見て、素晴らしいビジョンを得たのだ」 ――ジェフリー・フォード『白い果実』山尾篤子ほか訳、独裁者ビロウのせりふ とりあえず悪夢のような独裁都市はなくなり、主人公もまともな性格の持ち主となって出直していますから、めでたしめでたしの結末です。しかし白い果実とはいったい何だったのか、頭脳と連動する空間にはどういう仕掛けがあるのか、謎がいっぱいです。 三部作の1冊目なので、まだまだ主人公の旅は続き、異世界は充実していきそうです。悪者のインパクトがなくなった主人公がちょっと魅力減な気もしますが、続きも読んでみたいです。
March 4, 2014
コメント(0)
-

京都の古書店「レティシア書房」にて
冊子「本と本屋とわたしの話5」のご縁で、京都の古書店「レティシア書房」に行ってきました。この冊子も置かれているほか、現在開催中の「古本市」に、うれしはずかし、拙作も並べていただいています。 「本と本屋と…5」には、このブログでも何度か熱く語ったことのある斎藤惇夫『グリックの冒険』『冒険者たち』との出会いについて、書かせていただいたのですが、レティシア書房の店主さんが『冒険者たち』をお好きだったことから、いろいろお話することができました! 中でも、『冒険者たち』をあのクロサワ映画の傑作「七人の侍」のようだとのご指摘が、新鮮でした。私は日本映画にはとんと疎いので、でもさすがにスピルバーグやルーカスがお手本にした映画ですから、あらすじは知っていました。 いま改めてWikiで調べてみると、「七人の侍」の影響を受けた作品の中に、アニメ「ガンバの冒険」が挙げられているんですね。なるほど、だからアニメは7匹なのか。 ところで、この古書店には児童書も置いてあります。それも、古書とは思えないほどきれいなものが多く、きちんと棚にスペースを割り当てられていました。 子供の本は読み古されぼろぼろになったものが無造作に売られていることはよくありますが、一人前の本として並んでいると、嬉しいものです。 そして、さらに嬉しいことは、“むかし見かけてぜひ欲しいと思って、でも買えなかったまま忘れかけていたあの本”に2冊も出会いました。 どちらも、平成元年に話題となった本、ニコライ・A・バイコフ『偉大なる王(ワン)』と、リチャード・フォード『銀の森の少年』(Quest For The Faradawn)です。もちろん即、買い!です。帰りの電車の中でホクホクと眺めるうち、思い出しました。平成元年の春、私は就職し、新しい環境の中で余裕のない毎日を送っていたため、これらの本を手に入れることができなかったのでした。 バイコフの方は、野生の虎の物語で、ずっと後になって絵本『ウェン王子とトラ』に出会ったとき、そういえば!と思い出したものの、すでに絶版になっていました。 『銀の森の少年』はやはり動物モノで、こちらはイギリスの現代版ジャングル・ブックみたいな紹介をどこかで見かけて本屋さんで手に取った覚えがあります。そのとき、原題のファラドーン(とおい夜明け)という言葉がなんとも魔法のように魅力的に思えたのでした。 今日あらためて見ると、訳者は詩人の北村太郎でした。 運命の再会にすっかり気が大きくなって、もう一冊買いました。ドイツのファンタジー、コルネーリア・フンケ『魔法の声』です。これは2003年の本です。 就職したての年は一時的に新規の読書から遠ざかっただけでしたが、子供が生まれてから数年間はかなり長きにわたって新しい本を買っていません。やはり新刊本などチェックする余裕がなく、読み慣れた手持ちの本ばかり手にとっていたのです(そのぶん、子供に絵本を買って自分でも楽しんでいましたけれど)。 この本は、ちょうどそんな時期の本なのでした。 これで、しばらく楽しめそうです。収穫の多い一日でした。
January 30, 2014
コメント(0)
-

少しブラックなメルヘン集『ぬすまれた夢』
脚の静脈瘤治療のため3泊4日入院していましたが、無事復帰しました。その間に病院の図書室から借りて読んだ本が、ジョーン・エイキン『ぬすまれた夢』です。 絵が緻密でうつくしく、井辻朱美訳ということで手に取りましたが、作者は『ウィロビーチェイスのおおかみ』など長編でも有名な人(ただし私は未読)。 メルヘンチックな短編がいくつか収録されていますが、どのお話もところどころ、「えっ!」というような要素がさしはさまれていて非常にスパイシーです。 たとえば、男の子がテニスラケットでチョウチョをたたいていじめていると、精霊が現れて怒ります。すると、男の子の片脚が勝手に胴体をはなれ、ぴょんぴょんとんだあげく、バスに乗って行ってしまうのです。男の子が抗議すると、もう片脚も! つまり脚の家出です。 挿絵には、シュガーバターのように甘く繊細なタッチで、脚のない少年が逆立ちして歩くところや、家出してパブで踊っている脚が描かれています。なんだか、ぞーっとします。 昔話にある残酷な側面、というのがよく指摘されますが、このお話はそれを意図的にメルヘンにはさみこみ、童謡の中に現代音楽的不協和音を響かせる、みたいなことをやっているようです。 結末もひねりのきいたものが多く、私が気に入ったのは、スコットランド特有の水怪ケルピーが出てくる話: 居心地の良い部屋の絵を得意とする画家の作品に、いたずらなケルピーが侵入。画廊に飾ろうとするとどの絵の部屋にも、おぞましい姿のケルピーが知らぬ間に描きこまれています。画家はあわてふためいて故郷の海辺に行き、姿を見せないケルピーに向かって絵から出て行ってくれるよう懇願します。ケルピーいわく、画家が少年のころ初めて描きたいと願ったこの海辺の光景を描いてくれ。・・・世に出て成功した画家の原点を突いてくるあたり、なかなかあっぱれなケルピーです。 画家はふるさとの物寂しい海辺の風景を描き、その作品を海に(=ケルピーに)献じます。これでケルピーは満足して絵から消え去り、一件落着したでしょうか? いいえ、皮肉なことに、彼が海辺にいる間に、町の画廊では彼の「ケルピーのいる部屋の絵」がすばらしい着想だと大評判になっていました。ところがほどなく、すべての絵からケルピーは消えてしまうのです。 町へ戻った画家はしかし、いまさら自力ではケルピーの姿を描けません。ほんもののケルピーは彼の前には一度も姿を見せなかったのですから。 ・・・ケルピーって何だろうと考えさせられるお話でした。心地よい絵に突如侵入していたケルピー、それはちょうど、この本の心地よいメルヘンに突如侵入してくるぶきみにブラックでシュールなイメージのようです。脚は胴体から逃げだし、お姫様の髪の毛は悪口雑言を吐き、お風呂に現れた蜘蛛はみるみる巨大化し、増殖します。 思うに、キレイな絵空事的ファンタジーは心をなごませるけれど、それのみでは存在し得ないのです。エデンの園にヘビ(サタン)が出たように、フェアリーランドには危険な竜や不気味な洞窟が必ずあるように。 画家の絵はキレイだったけれど、画竜点睛を欠いていたのでしょう。そこには、この世の不条理の化身たるケルピーが加えられる必要があったのです。不条理の化身というと印象が悪いですが、実はそれは理屈ではとらえきれない、真の芸術的インスピレーションなのかもしれません。 画家が初めてケルピーに話しかけられ、世界一の画家になりたいという願望をもらすのは、少年の頃でした。彼は、見たことこそないけれど、じつは少年時代からケルピーを知っていたのです。ぐんぐん重くなる亀の甲羅(ケルピーが中にいたようだが、気づいたときにはからっぽだった)を運ぶ少年の彼は、すでにケルピーという不条理/天与の才能をかかえて人生を歩み始めていたのでした。 ・・・なんてことを考えながら何度か読むと、挿絵に描かれたケルピーの姿(頭が馬で下半身が魚。最近、いろんなゲームにかわいい姿で登場したりしているようですが、本来は人外魔境的不気味な妖怪)もなんだか親しみ深く感じられました。
June 6, 2013
コメント(2)
-

『たのしい川べ』続編の続編、『川べに恋風』
以前、ケネス・グレーアムの名作『たのしい川べ』の続編ウイリアム・ホーウッド作『川べにこがらし』を読んだのですが、先日これのさらに続編『川べに恋風』を発見し、さっそく楽しみました。 原題は「Toad Triumphant」(勝利を得たヒキガエル)といいますが、この「勝利」とは『たのしい川べ』の終章でヒキガエルが、イタチどもから屋敷を取り返すくだりで使われていた言葉でもあります。続編の作者は、『こがらし』同様、グレーアムの原典に呼応するような筋書きや言葉使いをきっちりと用いているらしいのです。 では、今回はどんな「勝利」なのでしょうか。 表紙絵を見ると、原典『たのしい川べ』の画家E・H・シェパードと画風の似たパトリック・ベンソンの描く、生きた銅像と化したヒキガエル氏の姿があります。そう、『川べに恋風』では、ついにヒキガエル氏の銅像が(ローマの皇帝風なのですが、彼自身は「凱旋(triumphant)将軍風」と言っています)、建ってしまうのです! 邦題から推測できるとおり、今回はヒキガエル氏に恋という冒険(熱病)がふりかかります。自動車よりも飛行機よりも熱狂的なものと言っては、この時代(20世紀初頭ぐらいの設定)にはもう恋しかありますまい。しかし、それでは彼はついに恋の勝者にもなったのか? といえば、実はそうではないのです。 『たのしい川べ』は男性だけの世界です。イギリス文学には独特の「独身男性=bachelor」像や彼らの社会があるような気がしますが、モグラ、ミズネズミ、アナグマ、ヒキガエルたちはまさに独身貴族を謳歌している古典的・理想的な男性たちです(カワウソには息子がいるが父子家庭)。色恋沙汰にかまけて友情や趣味豊かな日々の落ち着いた暮らしを乱すことはありません。迷惑をこうむる家族がいないからこそ、ヒキガエルも羽目をはずすことができるのでしょう。 一方、この手の物語は常に一つの課題をかかえていて、それは黄金時代の永遠化ということです。以前『くまのプーさん』や『長くつしたのピッピ』のラスト・シーンで幼年時代が永遠化されることに触れましたが、川べの世界は「幼年」ではないにしろ、女性が排除されている点で永遠の独身時代といえそうです。『たのしい川べ』でも、モグラの登場以来、次々にエピソードが語られ、一見、たのしい川べ世界がいつまでも変わらず続きそうに思えます。そこではヒキガエルは性懲りもなく羽目をはずしては、またもとの川べ仲間のところへ戻って来る・・・ しかしグレーアムは、イタチどもから屋敷を奪還した後、ヒキガエルは性格が変わり、落ち着いて精神的に大人になったと述べて、物語をしめくくっています。そこには、一抹の抵抗感・さびしさが漂います。 ホーウッドは続編『川べにこがらし』で、原典の結末、つまり「大人になること」に抵抗を示しています。大勢の読者の気持ちを代弁して、そんなに簡単にヒキガエル氏が落ち着いてしまうはずがない!というわけです。そして、ヒキガエル氏は飛行機に乗り出します。結末ではとうとう屋敷が火事で燃えてしまいますが、保険金がおりるからすぐにも新しい屋敷を建て直すとヒキガエルは断言しています。モグラとミズネズミもボートに戻っていき、また楽しい独身世界が繰り返すだろうと思われます。 けれど、ホーウッドはここでも原典にならって、あるいはグレーアムよりもっとはっきりと、「永遠化」の問題に取り組む姿勢を見せています。それは最後の場面にカワウソの息子ポートリと、モグラの甥をもってきたところ――最初はモグラにとって厄介者だった甥が、やがてはモグラの後を継ぐだろうということが暗示されているのです。 そもそも、読み返してみると『こがらし』には、川べ世界をおびやかす影、永遠の黄金時代とは相容れない“死”や「あの世(beyond)」の描写がたくさん出てきます。しょっぱなから、とても現実的な内容のモグラの「遺書」があり、ついで飛行機から放り出されたミズネズミが墜落していく短い時間に「あの世」を見る体験をします(実際には川上の景色だったのですが)。これらは、時の流れや世界の変化を感じさせ、物語がもう永遠の楽しいくり返しでは済まなくなる(幼年=黄金時代の終わり)兆しと思われます。 前置きが長くなりましたが、今回の『恋風』ではそれがいっそう具体的に問題になってくるのです。そのため、幼年文学ならでは楽園的楽しさはかなり損なわれ、ヤングアダルトというか、大人向きの話になっています。 まず、いつも物語の発端であるモグラは、漠然とした不安にとりつかれていますが、これこそ黄金時代の終焉の予感、時の流れの自覚で、彼は「新しい世代」にゆずることを考え、自分には甥、カワウソには息子がいるが、アナグマやヒキガエルたちには財産を受け継ぐ後継者がおらず、川べの世界は自分たちの世代で終わってしまうんじゃないかと心配し始めたのです。 ついで、ヒキガエル氏の例の突発的熱狂で、彼は新しい屋敷の庭の真ん中に自分の銅像を建てようと計画します。銅像こそ、黄金時代の永遠化にほかなりません。彼も無意識に、自分の黄金時代の終わりを感じとり、今のうちにメモリアル(「永遠の不滅」と彼は言っています)をつくって永遠化しようとしているのです。 さらに、降ってわいたような、夫を亡くしたヒキガエルのマダムの登場で、もちろんヒキガエル氏は恋に恋して熱狂し、気楽なバチェラー仲間の平穏は危機に陥ります。少なくとも、アナグマはそう感じているようです。 ところが、当のアナグマ自身にも変化がありました。封印してきた過去(実は妻子持ちで、妻は病死し、息子は出て行った)が明らかになり、モグラとネズミは出て行った息子の足跡をたどって、「あの世」へ探検に出かけます。 あの世といっても、実際には地続きの、川をさかのぼった土地なのですが、モグラたち小動物にとっては滝だの恐ろしいカワカマスだの、誰も帰って来ないだの、畏怖と伝説と魅力?に満ちた別世界です。 彼らがさかのぼる川は岸に廃墟などが見え、まるでレテ川やアケロン川(三途の川)のよう、あの世のとば口の酒場に集っているのはなんだか亡者のようでもあります。しかし、モグラとネズミはついにアナグマの息子そして孫を見いだすことができました。さらに、ヒキガエルが、自分そっくりの少年ヒキガエル(マダムの連れ子)を従えて乗りこんでくると、陰気な酒場はたちまち彼の熱狂と勝利にわきかえり、読者を生き返ったような気分にさせてくれます。 物語にはさらに、英国ならではの(これも独身)プロフェッショナルな執事プレンダガーストが、トリックスターのように表に裏に大活躍して、結局マダムは排除され、ヒキガエルは申し分のない後継者である少年を得ました。これこそが、生命のない銅像よりもすばらしい「永遠化」つまり、生命の譲り渡しという、すべての生き物が時の流れに対抗して得ることのできる勝利でした。 恋をしてこそ一人前、ようやくヒキガエルは大人になったようです。とはいえ、作者はまだ完全に満足はしていないようで、このあと「The Willows and Beyond(柳とあの世)」という完結編があるそうです(ただし邦訳はありません)。そこでは黄金の川べ世界にほんとうの終焉がおとずれるのかもしれません。
March 7, 2013
コメント(2)
-

2~3月の読書メモ
更新できなかった日々の読書メモです 3月にいちど読書感想を書きかけたのに、眠かったせいかうっかり保存前にブラウザを閉じてしまい、全部消えてしまいました。 そのとき書こうとしていた内容が、今あんまり思い出せない・・・パトリシア・マキリップ版タムレイン伝説;『冬の薔薇』 はやく春が来てほしい気持ちになるので、今年の冬にはある意味よく合ったお話。妖精界から現れた不思議な男性を、彼に惹かれる少女が人間界に連れ戻すという大枠では、なるほどスコットランドの伝説と同じです。バラを摘むとか、緑のマントとか、細部も伝説から借りているようです。でも登場人物も舞台設定もだいぶ趣が違うので、もとの伝説は気になりません。 この世と異界が重なり合う幻惑的な描写は、マキリップお得意のすばらしさがあります。主人公の少女の住む古い農家は、 夜、窓によその炎や別人の顔が映ることもあった。蜘蛛が天上の片隅の暗がりにかけた巣は、年々複雑なものになっていく。まるで、空中の宮殿を受け継いで、代替わりのたびに建て増していくようだ。 --マキリップ『冬の薔薇』原島文世訳 などと描写され、何となく(私の大好きな)『影のオンブリア』みたい。 そしてまた、幻想の迷宮のように話が進む割には、終わり方はあっさりしているところも、マキリップの特徴なんでしょうね。わけのわからない長い夢からふと覚めたような気分で読み終わります。読んでも物語がまとめられなかったパトリシア・マキリップ;『女魔法使いと白鳥のひな』 こちらの幻想譚は難解でした。星座たちの争いとか、すごく興味深いモチーフがいっぱいなのに、作者にケムにまかれた感じで、よく分からないまま、結末へ引きずられていきました。 前半の「道の民」(ジプシーとか、ロマニーとかいった人々がモデルのようです)の主人公が沼地の魔女のところへ行く話と、後半の宮廷モノとが私の中でかみあわず、もっと説明して!と思ってしまいます。しかしたぶん、説明などせずになぞめかしたまま不思議な情景を描きつらねていくのがマキリップの表現法なのでしょう。 とにかく、初読ではついていけなかったで、続編『白鳥のひなと火の鳥』へは進めそうにない私でした。そのほか、CRALAさんお薦めの『銀の船と青い海』を堪能しました。最近はCGぽい線や色の塗り方のコミックスやアニメが多いですが、萩尾望都さんの昔の絵にはいかにも手間暇書けた手書きの美しさがあって、味わい深いです。スーザン・クーパーの『影の王』は、作者が正当派英国調・重々しいジュブナイル・歴史ファンタジー(『影との戦い』シリーズ)の人なので、おそるおそる手に取りましたが、これは歴史ものでもまったく別種の、わりと単純なタイムスリップ物語でした。シェイクスピアやエリザベス1世がリアルな描写で出てくるのが興味深いですが、ちょっとリアルすぎてファンタジー味はないですね。
March 15, 2012
コメント(0)
-

タニス・リーの小品2つ『冬物語』
しんしんと冷える夜に外の風音など聞きながら読むとよいかも、の本を、棚の隅から探し出しました。80年代の早川FT文庫、冬景色に展開するタニス・リーのおとぎ話2つをおさめた『冬物語』です。 タイトルにもなっている一つ目の「冬物語」(原題The Winter Players)は、荒涼たる冬の海辺に立つ、小さな神殿からお話が始まります。神殿が代々守ってきた聖なる骨を、よそ者の男が盗んで逃げたので、責任者である若い巫女は必死に後を追いかけます。 大人の読者には、彼女がなぜ神殿を放置してまで、ひたすら盗人を追いかけるのか、何となく想像がつきます。聖域に強引に侵入した男が奪ったのは、彼女の“女心”なのですから。 ♪わたしの胸の鍵を/壊して逃げていった あいつは何処にいるのか/盗んだ心かえせという歌(ピンクレディー「ウォンテッド」)というのがありましたが、まさにそんな感じですね。 ところが追いついた男は彼女に わたしたちは不思議なゲームの競技者(プレイヤー)なんだ。あんたと、そしてこのわたしは。 ――『冬物語』室生信子訳と言い、さらに読み進むと、彼に聖骨を盗ませた悪い魔術師の存在が明らかになります。しかし、すべてはその悪者の仕組んだたくらみだったのかと思うと、実はさらに大がかりな、時の流れをさかのぼってくり返す、物語の枠組みが見えてきます。 原因が結果に、その結果が時を戻って最初の出来事の原因につながる、円環的ストーリー。そこには始まりも終わりもなく、同じことが永遠に繰り返されます。タイムワープを会得した主人公にとっては、以前書きました村上春樹『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』の博士の言う一種の“永遠の生命”なのかもしれません。 またそれは、カート・ヴォネガット・ジュニアの『スローターハウス5』(これもかなり古い作品ですね)によると、 ・・・あらゆる瞬間は、過去、現在、未来を問わず、常に存在してきたのだし、常に存在しつづけるのである。・・・いったん過ぎ去った瞬間は二度ともどってこないという、われわれ地球人の現実認識は錯覚にすぎない。 ――伊藤典夫訳 人生をそんなふうに四次元的にとらえてしまうと、そこから抜け出せなくなってしまいます。 しかし、「冬物語」のヒロインは勇気を持って、自分の意志で別の人生を選び取るのです。運命だとあきらめずに、ただ一点でも自力で変えることができれば、堂々巡りの呪縛は解けます。そして、物語のラストでは、うってかわって夏の青く明るい海の情景が描かれます。冬物語を繰り返していたプレイヤーは、別の物語を自らつむいだのです。 さて、二つめの物語「アヴィリスの妖杯」は、うってかわってホラーです。原題はCompanions on the Roadで、後書きによるとトールキンの『指輪物語』第一部「旅の仲間(The Fellowship of the Ring)」を意識しているのではないかとのこと。なるほど、すばらしいが恐ろしい呪いをもたらす宝物をたずさえての旅、という点では共通しています。 しかし、趣きがかなり違って、こちらはちょっと怖いです。心理的にじわじわ恐怖に追いつめられていく天涯孤独な主人公の運命を思って、ハラハラします。次々に呪いの餌食になって死んでいく道連れ二人は、それほど凶悪なキャラクターではなく、ただ心の弱さに負けて命を落とすので、よけい怖いのです。 ネタバレしますと、それほど善人でない主人公ですが、ふと見せた素朴な思いやりの心のおかげで助かります。因果応報、小さな親切があなたを救う、といった感じです。そういえば彼だけは助かるような伏線があちこちにあったなと後から思うのですが、結末に至るまでは恐ろしい前兆現象にばかり気をとられるので、良きしるしにはあまり注意を払うことができません。 タニス・リーってほんとにストーリー・テラーだなあと、巧みな技を感じさせるお話でした。
February 21, 2012
コメント(2)
-
『黒龍とお茶を』――シブかっこいい中国紳士
辰年なので、ファンタジーを標榜するこのブログでもやっぱりドラゴンで始めなくては!と思いましたが、洋風のドラゴンの物語は掃いて捨てるほどあるので、ここは一つ「龍」の字を使っているマカヴォイの『黒龍とお茶を』で始めようと思います。 マカヴォイはそのむかし、「魔法の歌3部作」の表紙絵を中山星香が描いたので買い求めたのですが、それがまあまあ面白かったので、『黒龍とお茶を』も買ってみたのです。 しかし、物語に出てくる勝ち気な新進エンジニアのリズよりもまだ少し、私の方が年下だった当時、リズの母親(50歳)と初老の中国紳士(もっと年上、じつははかりしれないほど)との、上品なラブストーリーは、どうもピンと来なかったというのが本音です。 それに、早川FT文庫の割には、なかみはコンピューター犯罪のからんだ誘拐劇で、壮麗に天を舞う龍の姿なんてものはまったく出てこないのです。 しかし、今やヒロインのマーサの年齢も近づいてきたせいでしょうか、読み返してみると、なかなか小粋でエキゾチックな、味わい深いロマンスなのでした。 コンピューターの話題は四半世紀も前なので何だか古くさく、事件のどたばたも軽いですが、そのレトロな軽さが心地よく感じられる・・・のは、やっぱり歳のせいでしょうか。 ともあれ、なんと言っても中国紳士メイランド・ロング氏が、ものすごくステキなんです。アラフィフ女性向けの白馬の王子様とでも言えそう。 ロング氏は椅子にすわったまま背を伸ばし、それによって蔭の中に消えてしまう。両手を触れ合わせ、それから開くので、まるで空中に鳥を放つかのよう・・・(後略) ロング氏は、まだ腰かけたままだ。口の前で両手の指先を合わせて、教会の尖塔のようにしているので、顔の一部が隠れている。(中略)・・・しなやかに立ち上がった。椅子の肘掛けには触れもしない。 --R.A.マカヴォイ『黒龍とお茶を』黒丸尚訳などという描写で、裕福で上品な彼がただの金持ちの有閑老人ではなくて、神秘的な、内に力を秘めた魅力的なおじさまに仕上がっています。 サンフランシスコのホテルのスイートに滞在し、絹のスーツを着こなし、真っ白なシャツに浅黒い肌、西洋的な微笑と中国風の微笑を巧みに使い分け、コンピューターのことも理解してしまう、スーパー紳士。会話の途中でチョーサーなど古典を不意に引用し、禅やタオイズムについて語り、達磨大師を個人的に知っているなどと話しても、この人なら鼻につかず、嫌みもありません。 それもそのはず、彼の正体はブラック・ドラゴン・・・人間になったドラゴンなのでした。 ドラゴンだから超人的パワーを持っているとか、魔法を使うとかではないので、物語が佳境に入ってもいわゆるファンタジー的なミラクルはありません。しかしそれでも、圧倒的なロング氏の存在感と、おばさんながら芸術家でそれゆえにかシンプルに本質を突くマーサとが、お似合いのカップルになっていく過程はちょっとマジカルな感じもします。 年を重ねた教養の深さと威厳、ノーブルでお金持ち、しかも寝姿の描写はパワフルでセクシーという、非の打ち所のないロング氏の魅力は、極上の烏龍茶のシブかっこよさに似ています。そう、彼は烏龍(ほんとはお茶の名前にすぎず、こういうドラゴンはいないそうですが)の化身なんですね。
January 7, 2012
コメント(2)
-

『ハロウィーンがやってきた』レイ・ブラッドベリ
レイ・ブラッドベリが少年少女向けに、ハロウィンの由来について語ります。世界各地をめぐりながら、理屈っぽい“由来”ではなく、その原初的な雰囲気について。 ケルト・フリークの私は、ソーイン(ケルトのハロウィン)についてはちょっと知っていたのですが、メキシコの「死者の祭」、こわくて楽しい、骸骨だらけの夜中のお墓参りなんかは知りませんでした! そんなふうに、とってもお勉強になる本『ハロウィーンがやってきた』。 私は古い版(晶文社の文学のおくりもの全集)を借りて読みましたが、新版も出ているのですね。 案内役の、幽霊屋敷の主の名はマウントシュラウド(mount「墓」shroud「きょうかたびら」)だなんて、とってつけたようにあやしいんですが、引率される子どもの気持ちになってどんどんついてゆくと、最後にはおどろおどろしくも美しいクリスマスツリーのようなハロウィンの木(原題Halloween Tree)が印象的です。(右画像はマウントシュラウドの屋敷とハロウィン・ツリーの挿絵) ジュヴナイル小説なので、ちょっとお説教くさいのと、ハロウィンの晩に連れ去られ危機に陥った少年が、実は急性盲腸炎だった・・・という、えらく現実的なオチが気になりますが、幻想世界旅行のあいだはそんなことはちっとも気になりませんでした。 さすが、ブラッドベリです。
October 27, 2011
コメント(4)
-
G・マクドナルド「巨人の心臓」
前回に付け足す感じで、『黄金の鍵』(吉田新一訳、ちくま文庫)に収録されているおとぎ話「巨人の心臓」について。 これも、どこかで聞いたようなお話。作者も「ケルトに伝わる巨人国伝説」について言及しています。しかし実際はヨーロッパ各地に似たような話があるようです。 この手の巨人は、大事な心臓を体の外のどこか(じつは鳥の巣の中)に隠しておいて、だから自分は無事だと思いこんでいるのです。主人公の子供が巨人の家で隠れているあいだに、巨人の妻が心臓のありかを聞き出し、それを盗み聞きした主人公が心臓を探しあてて巨人を倒すのです。 小さな主人公が大きな巨人(鬼)を退治するのはよしとして、不思議なのは「体の外に心臓を隠す」というモチーフ。どんなふうにするのか、ちょっと想像もつかない気がします。 しかし、「心臓」というのを「他人に奪われたら困る、いちばん大事な物」と考えると、たとえばこれは「お財布またはお金」のことかな? と置き換えてみてはどうでしょう。 すると、巨人とその妻のこんな会話も、なるほどありそうだなと思われます; 「いまどこにおいてあるか知らんだろう。一か月前に動かしたよ」 「まあ、・・・自分の妻を信用できないなんて」 そして妻は夫に、心臓を家の中のどこかにしまっておくようにと言いますが、夫の本音は「それでは妻を有利にしてしまう」。 「自分の心臓の世話ぐらい面倒でいやなことはないなあ。まして責任なんか背負いきれたもんじゃない・・・」 「ですからあたしにあずけたらいいと言っているでしょう・・・」 「そりゃわかっているよ、おまえ。だけど、それじゃあおまえに責任をかぶせすぎる」 --「巨人の心臓」吉田新一訳『黄金の鍵』より 心臓をお金に置き換えると、とてもわかりやすい、でも卑近なやりとりになってしまいますね。 本当の心臓だと思ってみたり、財産の詰まった財布だと思ってみたりすると、おとぎ話は二度三度楽しめます。
June 6, 2011
コメント(2)
-
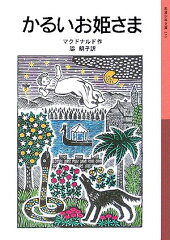
G・マクドナルド「かるい姫」--人間的ドラマに昇華するおとぎ話
王さまとおきさきが、長らく望んでやっと授かった美しいお姫さま。しかし命名式に招かれなかった魔女が姫を呪って・・・。グリム童話の「いばら姫」(「眠り姫」)でおなじみの始まり方です。が、イギリスの古典的妖精物語作家ジョージ・マクドナルドの「かるい姫」も同じなんです。 ところがこちらの呪いは即効で、赤ちゃんの姫に「重さ」がなくなってしまいます。ちょっと触れただけでもふわふわ空へ飛んで行ってしまううえ、心まで軽すぎて、何事もケラケラと笑うばかりのお姫さま。王と王妃は嘆き悲しみます。 しかし、姫が幼いうちは、いつも機嫌良く笑っているし、召使いたちは姫をボールのように投げあって楽しめるし、軽いというのもなかなか良いなと思えます。実際、われわれ皆を地上に縛りつけている“重力”から自由なお姫さまは、地上のさまざまな悩み事とも無縁な風情で、うらやましいくらいです。 しかし、成長するにつれ、誰しも笑っているばかりではすみません。そういう意味では、この物語でも、呪いが本当にに効力を表してくるのは姫が十七歳になった時(「いばら姫」では十六歳)です。 たぶん姫にとって一番よいのは恋に落ちることであったろう。だが、そもそも重さのまったくない姫が何かに落ちるにはどうしたらいいかがまず問題、というより難題であった。 --「かるい姫」吉田新一訳『黄金の鍵』 そして、お定まりの王子さまが登場。湖で泳ぐ姫を見初めます。じつは、水中にいる時だけは姫も一般人と同じように重さがあり、精神的にもあまり軽々しくなく、美しさはいっそうきわだつのです。 といっても、一般に水中では浮力がはたらいて重さをさほど感じなくなるので、姫が水中で重さを持つといっても、それは一般人が水中で感じるほどの、浮力を差し引いた重みということになりますが。 ともかく、お城の前にある湖こそ、姫の本来の“心”そのものであり、呪いの効かない領域でした。それでも姫から積極的に“恋する”わけではなく、ただ王子と仲良くなるだけ。しかしそれを知って怒った魔女が蛇に湖水を飲み干させるまじないをかけたので、湖は底にあいた穴から水が漏れ、日一日と干上がっていき、それにつれて姫は衰弱し始めます。 興味深いのは、国じゅうの泉や流れが干上がり、国じゅうの赤ん坊が笑わなくなってしまうところ。笑ってばかりのかるい姫+豊かな湖水(=姫の心)は、豊かな国土の象徴なのですね。 物語は、水が湖底の穴から漏れていくのを止めるために王子が身を犠牲にして“穴をふさぐ”という場面で、コミカルなおとぎ話から悲劇的クライマックスへ急展開。よみがえる湖の中で王子はおぼれて息絶えます! おとぎ話はハッピーエンドだと思って気軽に読んでいると、とても切なくなってしまいます。 かるい姫が重さを(=心を)獲得して一人前の大人になるのは、王子の死が必要なほどたいへんなことなのです。 王子の死をもたらす湖水とともに、姫の内部でも心があふれ、彼女はとつぜん王子を救おうと必死になります。絶望的な状況の中で、蘇生の努力を続ける姫。親である王も王妃も知らないあいだに、姫はあきらめずがんばるのです。 結果、ファンタジーらしく奇蹟が起こって王子は蘇生し、姫は涙(=水)を流して床に倒れ、王国には恵みの雨が降り注ぎます。王子の死によってあがなわれた姫の重さ(心)のパワーが、王子の死そのものをくつがえす。そして、国じゅうが救われてハッピーエンドが訪れます。 マクドナルドの作品は、不思議なイメージや幻想的なシンボルに満ちていて、起承転結があまり感じられないものも多いのですが、「かるい姫」は、このように波瀾万丈の末、なかなか感動的な結末を迎えます。 画像は岩波少年文庫版。私の読んだのは吉田新一訳『黄金の鍵』(ちくま文庫。もとは妖精文庫)に収録されたものですが、こちらは絶版のようです。
June 1, 2011
コメント(0)
-

わたりむつこ『はなはなみんみ物語』のかげりの部分
1980年の作品で、当時はファンタジーは日本ではまだ珍しいジャンルでした。が、なぜか日本でも小人のファンタジーは、さとうさとるとかいぬいとみこが、もっと以前から書いていますね。 この『はなはなみんみ物語』シリーズも小人の家族の、ほのぼのと暖かい、けれどニッポン的なかげりもあるお話です。“ニッポン的なかげり”とは、私の勝手な言葉ですが、子供時代、いぬいとみこ『木かげの家の小人たち』を読んだとき感じたもので、つまり私たちより前の世代の人たちが必ずと言っていいほどひきずっている戦争の痛みのことです。 おさな心に、私は、この手の“かげり”が出てくる話は怖くて読むのがイヤでした。 ・・・小人のふたごの兄妹「はなはな」と「みんみ」が、おじいさんのひきうすの歌にこめられていた魔法の呪文に気づき、空を飛ぶ。同族の小人たちが遠くにいるという話を聞いて、彼らをさがしに一家で旅に出る。おそろしい「羊びと」につかまってしまう・・・というような、魔法と冒険旅行のお話だけの方が、私には安心して楽しめるんですね。 でも、そこに小人一族の繁栄と没落の歴史、同族で殺し合った過去というのがからんできます。食べ物を作るかわりに武器となる「いかり草」ばかりを育て、戦いのために魔法を使ってついにはほろびた小人たちの国。その生き残りであった白ひげじいさん。 そういった底流があってこそ、物語はより深く、広く、長くなったのでしょう。 けれども、作者の心があまりにも強くそこにこめられているために、私は逆に“かげり”の部分が出てくるたびにファンタジー世界から現実へどん!と突き返されるように感じます。 白ひげじいさんは、戦争の時、いかり草から作った爆弾「いかり玉」を体にくくりつけて空を飛び、敵に体当たりする「空中隊員」でした。その有様は、先の大戦時の特攻隊そのままなのです。 生き残ってしまった彼は、空を飛ぶ魔法を二度と使うまいと誰にも教えず、そのくせ忘れきってしまうこともできずに、粉挽き歌にこめて何度も何度も歌い続けていたのです。 白ひげじいさんの罪の意識の重さは、北国の美しい自然の描写や、りすやうさぎとのメルヘンチックで暖かいふれあい、悪とはいえ自然の精霊であった「羊びと」との戦いなどの中で、かなり異質なのです。 この異質な重さを気にしながら読み進んでいくうち、おじいさんは「羊びと」にとらわれた家族を救うために、封印していた魔法を使い、爆弾をかかえて“特攻”して、死んでしまうのです。 ほろびた小人族ぜんぶの罪を白ひげじいさんに背負わせて死なすのが、作者の意図だったのでしょうか。もう一人の戦争体験者、爆弾づくりの研究者だったもえびじいさんは、髪をふり乱して苦しむのです; 「罪深いわしが、こうして救われるとは……この死にふさわしいのは、このわしだったのに……」 ――わたりむつこ『はなはなみんみ物語』 単に年老いた者が先に逝くとか、罪を犯した者が犠牲になるとかではなく、くいあらためて贖罪に余生をささげてきた者が、このような死に方や生き残り方をする、というのは、一筋縄ではいかない運命観や死生観で、ノンフィクションならともかく、ファンタジーというジャンルのかなめのエピソードにこれが表れる。それが“ニッポン的なかげり”。 私は大人になって読み返しても、なぜ白ひげじいさんが最後の最後に自己犠牲的“特攻”をしなければならなかったのか、分かりません。 ともあれ、仲間は見つかったものの非常に重い過去を引き継いだ小人一家たちは、ほろびたふるさへ新たな旅を始めることになり、第1巻は終わります。 実は続巻は手元にないのです。昔の読後感があまりに重かったので・・・。 近年また復刊されたようなので、再読しようかなとも思うのですが。
March 10, 2011
コメント(0)
-

女騎士アランナ『冒険のはじまりしとき』――少女の成長物語
アメリカのティーンズに人気のシリーズだそうで、全4巻の1巻目『冒険のはじまりしとき』を読んでみました。 辺境育ちの少年が、旅をしたり武者修行をしたりして成長していく、というのは異世界ファンタジーのもっともありがちなパターンですが、このお話は主人公を女の子にもってきたのですね。 ヒロインのアランナは男装して性別を隠しているうえ、心も体もそろそろ女性として成長し始める時期なので、いろいろ苦労やハプニングがいっぱい。それを一途にがんばって乗り越える。周りにはいじめっ子あり、友だちあり、きびしい先生にやさしい先生、王位を狙う悪者、と典型的な役者が勢揃い。 アランナは血の気が多いけれどとてもいい子で、好感が持てます。周りのお定まりな登場人物たちは、それに比べるとちょっと魅力が足りないですが、もしかしたらアランナ自身がまだ子供(1巻では10歳~13歳)なので、自分を取り巻く人々をつかみきれていないのかもしれません。この年頃は自分のことで精いっぱいになってしまう子も多いと思いますから。 わたし的には、こういうヒロインのこういう物語って、何度も出会っているような気がします。特にコミックスの世界で・・・『ベルばら』のオスカルはもちろん、木原敏江の「とりかえばや異聞」(確か『夢の碑』に収録)に出てくる、双子の兄の身代わりに戦国時代の殿様をつとめる紫子とか、やはり双子の兄とよく入れかわりを演じる『妖精国の騎士』ローゼリイとか。 思うに、男性と同じように強くありたい、活躍したいというのは少女(いや大人の女性でも?)に共通する願望なのでしょう。 私は男女雇用機会均等法という法律ができたてのころ社会人になりましたが、周りにはいわゆるキャリアウーマン(死語?)志望の乙女たちがたくさんいました。男性と同じように残業でも転勤でも頑張って、男性社会での地位を獲得しようとするあまり、何だか時々女性であることを捨ててるんじゃない?と思える人々がいたものです。 アランナが、ふくらみ始めた胸に包帯を(日本式に言うとさらしを)巻いて、重い剣の稽古に打ちこむ姿は、熱血だけれどどこか無理していて痛々しい。でも本人は同情されるのは負けることだと思っているから、ひたすらつっぱっている。そうやっているうちは、周りの人間のほんとうの優しさ(ベルばらでいうと、アンドレの優しさですね)に気づくことができないのです。 この物語はアランナの視点しか詳しくえがかれていないので、今の段階では、魅力的なはずの双子の兄トムとか、ジョナサン王子、盗賊王ジョージ(この人物はまったく描き足りていない)が、まだまだ薄っぺらいです。 とりあえず2巻以降でアランナは、周りにも女性であることを公表する予定のようですし、精神的にも自分の中の女性に目覚めていきそうなので、そこで個性的な魅力が出てくるかどうか、がこのシリーズが面白いかどうかの決め手なんじゃないかと思います。 ところで、タイトルが1巻だけ文語体なのはなぜなんでしょう。なかみの文体と合っていなくてヘンです。2巻以降はとても普通のタイトルなんですけど。なかみも、会話文とか特に、訳がちょっとこなれていない感があります。原文は読んだことないので何とも言えませんが・・・
February 8, 2011
コメント(0)
-

円環的に思える『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』
村上春樹に関してはシロウトなんですが、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』は設定がとってもファンタジーなので、なかなか興味深いです。ちなみに、私が初めて読んだ村上春樹で、そのあと『ノルウェイの森』『国境の南、太陽の西』を読んで、それっきりです。 この物語は「世界の終り」という話と「ハードボイルド・ワンダーランド」という話が交互に1章ずつ語られて進んでいきます。 読んだ方はご存じのように、「世界の終り」では主人公が壁に囲まれ一角獣の居るさびしい町に来て住むことになりますが、これは実は主人公の脳の中にあるイメージであり、つまりファンタジー世界。一方、「ハードボイルド・ワンダーランド」は主人公が実際に生活している現実社会。それが交互に出てきて互いに微妙な影響を及ぼしながら同時進行していきます。 この手法は、ファンタジー的第二世界と現実とを行き来するミヒャエル・エンデの『はてしない物語』を思い起こさせます。じつは、ファンタジー小説では珍しくもない構成。というより、ファンタジーを読むという行為じたいが、こんなふうに第二世界と現実を行きつ戻りつしているのです。 「世界の終り」の方は、本に囲まれた町の地図がついているうえ、一角獣とか夢を読むとか、ファンタジー的アイテムがいっぱい。特に、主人公が自分の影と引き離され、その「影」が一個の人格を持つあたりは、河合隼雄の『影の現象学』にたくさん紹介されている、古今東西の影をテーマにした物語と共通点がありそう。 たとえば、主人公は影を失ったために、「心」を次第に失う危険にさらされます。壁に囲まれた町にはそうやって心を失った人ばかりが住んでいるのですが、心がないといっても彼らは一見、ふつうに物事を感じたり考えたりはします。ここでいう「心」とは、河合隼雄が「たましい」と表現したもののようです。 さて「ハードボイルド・ワンダーランド」の方も、主人公にとっての現実世界とはいえ、なんだかのっけからあやしい展開です。 この舞台設定を「近未来社会」だと解説しているのをネットのどこかで見かけたのですが、通り過ぎる車からデュランデュラン(80年代のポップスグループ)の歌が聞こえるのですから、これはその当時の「現在の現実社会」の一種なのだと思います。「一種」と言いたいのは、この世界が主人公から見たものすごく主観的な世界で、しかもあとになるほど微妙にゆがんできているので、実はこれもまたファンタジー世界だったのではないかと思われるからです。 じつは私自身は、このような架空世界に、現実の固有名詞を持ちこむのはキライなんですけど、しかもそれが私の好きだったデュランデュランで、そのうえ主人公(村上春樹氏)がそれを思い切りけなしていたりするので、ますますムッときちゃうのですが・・・ 閑話休題。「ハードボイルド・ワンダーランド」は、そのタイトルがすでに『不思議の国のアリス』(アリス・イン・ワンダーランド)を示唆しており、物語冒頭に出てくるエレベーターは、アリスがうさぎ穴を地下へとゆっくり落ちていくシーンを暗示しています。『アリス』の原題は「アリス・イン・アンダーグラウンド」ですが、村上春樹の主人公もさらに地下の不思議の国へと下降していきます。 その地下への入り口がクロゼット(衣装だんす)の奥に隠されているというのも、『ライオンと魔女』(ナルニア国ものがたり)の設定を彷彿とさせます。 つまり、「ハードボイルド・ワンダーランド」の世界もファンタジー(架空)であるというしるしが、あちこちに散らばっているのです。 途中をとばしますけれど、結局「世界の終り」の主人公は「影」と一緒に町からの脱出を計画しますが、土壇場で思いとどまり、「影」だけが深い淵にとびこんで、地下水路を使って外界へ脱出することになります。そのとき、「鳥」(ユング心理学ではたましいの象徴)が壁を越えていくのが見えることからも、「影」はやはり「たましい」なのですね。 一方、「ハードボイルド・ワンダーランド」の方では、主人公は知らぬうちに組みこまれた脳内回路「世界の終り」に意識が閉じこめられる羽目に陥って終わります。それは「死」に似ていますが、彼の脳を手術した老博士はそれを「永遠の生命」であると言います。 そこで私は思ったのですが、「ハードボイルド・ワンダーランド」の最後で「現実世界」の意識を失った主人公は、その後「世界の終り」の町に行き着く、つまり物語冒頭につながっていくのではないでしょうか。 そして、「世界の終り」の最後で町を脱出した「影」こそが、「ハードボイルド・ワンダーランド」の現実世界の主人公だったような気もします。 つまり、2つの物語は最後と最初がつながって、ウロボロスの蛇の輪のように永遠にぐるぐるめぐり続ける、一種の「はてしない物語(ネバーエンディング・ストーリー)」に思えます。これもまた、ファンタジーではよくとりあげられるテーマであり、深く掘り下げるとまだまだいろんなことが言えそうです。
January 14, 2011
コメント(6)
-

記念復刊でゲット!『ささやき貝の秘密』
私の敬愛してやまないドリトル先生の生みの親、ヒュー・ロフティングの「幻の名作」『ささやき貝の秘密』が、岩波少年文庫60年記念で復刊されたというので、さっそく買いました。原書は1931年、『ドリトル先生月へゆく』と『月から帰る』の間に書かれたということです。 もともとロフティングは、ドリトル先生シリーズを『月へゆく』で終わらせるつもりだったそうです。動物語を話す風変わりな獣医ドリトル先生の最終的な落ち着き場所は月だ、と思ったのでしょうね。しかし、「ドリトル先生を月に置き去りにしたのはけしからん」という読者のお便りがたくさん届き、しばらくして『月から帰る』が書かれました。 ・・・で、その空白の間に、こんな素敵な中世風物語が創られていたとは! びっくりです。 ロフティングはもともと建築技師で、息子あての手紙に書かれた物語が偶然日の目を見たのがきっかけで、ドリトル先生シリーズが世に出ました。新聞連載などの形でつぎつぎと続きを書いたものの、ドリトル・ワールド以外に何か書こうという気持ちが彼にあった、なんてとっても意外です。 『ささやき貝の秘密』の前半は、幼い兄妹が、魔女と噂される謎の老女から「ささやき貝」という魔法のアイテムをもらい、それを父の借金返済に何とか役立てようとするお話。 ドリトル先生シリーズと同じように、社会的弱者に独特の価値を見いだす作者の視点が特徴的です。父の借金をどうすればなくせるか分かるのは、魔女と言われるリンゴ売りのおばあさんしかいない、と兄妹は確信しています。また、彼らが魔女の居所を聞く相手は盲目の老人や足の悪い少年。 物語の後半は、ささやき貝を若い王様に献上して自分も騎士になった兄ジャイルズの青年時代です。王との友情、恋の苦しみなどロマンス風の展開ですが、最後に瀕死の王を救いに現れたのは、物語の発端となったりんご売りの老女でした。彼女はしかし、王を助けると褒美をもらうでもなく、去っていきます。 ドリトル先生シリーズの訳者井伏鱒二が、ドリトル先生のことを「巷間の聖者」と呼んでいますが、このりんご売りの老女もまさにそんな感じですね。 最後に、主人公の名前、ジャイルズについて。 物語中に王のセリフとして 「ジャイルズ…(中略)…由緒ある名前だ。…あの方は、からだの不自由な人たちの守護聖人であった。」とあります。いまどき、ジャイルズという名前はそれほどポピュラーには思えませんが、中世には人気のある名前だったそうです。調べると、確かに中世の隠者で身体障害者の聖人(聖アエギディウス)でした。 実はトールキンに中世を舞台にした物語『農夫ジャイルズの冒険』というのがありまして、主人公が出世するところなどが共通しているので、気になってしまいました。 日本語でも昔風の名前や現代風の名前があるのと同じように、英語圏の名前にも時代によるはやりすたりがあるのでしょう。 惜しむらくは、復刻版なので、90年代に出回っていた本の表紙絵が見られないということです。挿絵と同じ中世風の趣のある線画でリンゴ売りのおばあさんを描いているらしいので、表紙に使わないとしても、ぜひ収録して欲しかったです。
November 8, 2010
コメント(4)
-

「ウィラン・サーガ」つづき『水の誘い』『風の勇士』
少し日があいてしまいましたが、パトリシア・ライトソンのオーストラリアン・ファンタジー『氷の覇者』の続刊『水の誘い』『風の勇士』のご紹介です。「大地人」(アボリジニ)の若者ウィランを主人公とする三部作ですが、『氷の覇者』が氷の精による大地奪還の挑戦という大陸規模のお話であるのに対し、続く2冊で起こる出来事はそれほど壮大ではありません。 2巻め『水の誘い』(原題The Dark Bright Water くらくきらめく水)では、迷子になった水の精ユンガムラの引き起こす騒動をしずめるため、英雄ウィランが呼ばれます。1巻では壮大な時空のストーリーに圧倒されて、目立たず地味だったウィラン。しかし今回は、美しい魔性の精霊ユンガムラに最初から惹きつけられ、そこへ同じ大地人の友人ウララ(男です)との友情がからみ、物語は彼の個人的な事情で展開していきます。もちろん、色々な土着の精霊たちが生々しく登場するのは1巻にひけを取らないですけれど。 結局ウィランはユンガムラを火と煙でいぶして“人間”のようにしてしまい、彼女を恋人にする決意をしてこの巻は終わります。 オーストラリアの精霊たちは、自立して野性的で、人間にとってはかなり危険な存在でもあるようです。ユンガムラは魔法の歌で若い男をさそって水死させてしまう、ギリシャ神話のセイレーンのような水精ですが、決して“悪”なのではなく、本質的にそういう存在である、というふうに描かれます。 だから、ウィランとユンガムラの恋物語もうまくいくわけはなく、3巻ではユンガムラの姉妹である水の精たちが彼女を取り戻しに来て、二人は引き裂かれてしまいます。 そのうえ今度は、人間に作られた「死」の精霊が現れ、ウィランと敵対します。ウルガルというこの精霊は、大地から生まれた今までの精霊たちとは違って、なかなか手強いのですが、読みかえると、これは一人の人間ウィランが、人間であるがゆえに避けられない「死」への恐怖や嫌悪感とどのように向き合っていくか、という問題のように思えます。重大な問題ではありますが、内面的に克服すべき試練であり、やはり1巻に比べると個人的なレベルの物語です。 今回ウィランは、肉体を離れた魂だけで、ですが、ウルガルと組んずほぐれつの格闘をします。今までの地味な脇役みたいなヒーローではなく、堂々と戦うのです。しかし、華々しい勝利はありません。魂は「死」を乗り越えて自由になりますが、人間の肉体は、「死」には勝てないのです。 ネタバレを承知で書きますと、ウィランの肉体は石になってしまいます。しかし、彼の魂は死を克服し、大地から解き放たれて、「風のうしろで behind the Wind」、永遠のヒーローとなるのです。この言葉が3巻の原題となっていますが、私はイギリスの古典的ファンタジー『北風のうしろの国』(ジョージ・マクドナルド、原題 At the Back of the North Wind)を思い出しました。内容は全然ちがいますが、どちらも現世を超えた永遠の国を「風のうしろ、風の裏側」と表現しています。 ウィランが人間としての肉体を手放してしまうラスト・シーンは、しかし、解脱した明るさに満ちています。彼は永遠に生きる存在として、精霊の仲間入りをしたようなわけで、今度はユンガムラの妻を取り戻し永遠に一緒にいられるのですから、ハッピー・エンドなのでしょうね。 エピローグ的に記されているのは、七人のユンガムラ姉妹とは、夜空のプレアデス星団(すばる)の七つ星の伝説であるということ。なるほど『オーストラリア・アボリジニの伝説 ドリームタイム』にも、七人姉妹の星の伝説が載っています。
October 17, 2010
コメント(2)
-
夏に氷が攻めてくる――『氷の覇者』P・ライトソン
残暑厳しき折から・・・ 灼熱の砂漠を内にかかえ、外側を青い海にあらわれる旧き大地、オーストラリアのファンタジーを再読しました。私は若い頃シドニーなど東海岸を旅行したことがあります。お正月休みを利用した旅でしたが、むろんオーストラリアは真夏で、ブリスベーンでは40度近い猛暑でした。動物園のカンガルーやエミューはみんな木陰で寝ていましたっけ。 旅の記念に、先住民族アボリジニのアートを模したという、魚の絵のついた大きなイヤリングを買ったのですが、それというのも、私はこの本を読んでから、ほんとうは海岸部ではなくエアーズロックやカカドゥに行ってアボリジニの壁画などを見てみたかったのです。 それはさておき。 年老いた南の大地は、海のかなたに、指をひろげ、手のひらを少しすぼめた手のような形で横たわっている。上空では風が鳴り、まわりをとりまく海辺には、波が打ち寄せる。・・・(中略)・・・風と水にもまれるなかで、大地は、巨大な手を休めるかのように、ひっそりと横たわる。そのすべての力を秘めたままで。 ――パトリシア・ライトソン『氷の覇者』渡辺南都子訳 オーストラリア大陸をこんなふうに描いて語り起こすこの物語は、アボリジニの若者(ふだんは都会に住んでいる)ウィランを主人公にした三部作の第1作です。この最初の数行を読んだだけで、広大な大地と海、そこを吹きすさぶ風、といった、圧倒的な大自然のゆるぎないエネルギーがつたわってきます。 次に作者は、その赤い旧い大地の上で暮らす者たちを3種類(+1)に分けて教えてくれます。 「幸福人(ハッピー・フォーク)」は海岸の都市部に住む現代的白人たち。幸福を追求して商売に精を出す。 「内陸人(インランダーズ)」は長年にわたって内陸部を開拓してきた白人たち。 「大地人(ピープル)」は昔からこの大陸に住んできたアボリジニたち。原語では何の説明もつかないただ「人々(ピープル)」と呼ばれているのが興味深いです。この人たちこそオーストラリアの本来の住人なのですね。 さらに、オーストラリア本来の住人として、作者は大地そのものから生まれた精霊たちを挙げています。私たちが昔話やファンタジーでよくお目にかかるヨーロッパや東洋の精霊とはちがう、ずっと野性的で根源的な趣のある多くの精霊たち。 そんな精霊の一種族、洞窟の奥底にいる氷作りのニンヤ族が、おそらくは氷河期の再来を願って、活動を開始するのが物語の発端です。夏を目前にして霜がおり、エアーズロック付近でキャンプしていた主人公ウィランは氷による蜃気楼を見ます。 ニンヤ族は、かつて(氷期の終わりに)彼らを地下に封じ込めた溶岩の精霊ナルガンをかたきとし、ナルガンを求めて大陸を移動します。 それを阻止すべく、大地人の英雄として選ばれたウィランは、岩の精霊ミミ(カカドゥの洞窟壁画にあるような、細長い手足の女の精霊)と一緒に、魔法の石をたずさえ、ニンヤ族を追う・・・精霊の始祖ナルガンを目覚めさせ、氷を再び封じこめるために。 と、あらすじを書いてみるととても派手なお話のように聞こえます。確かに、舞台となるオーストラリア大陸の広大さ、自然の豊かさ、苛酷さがたっぷりと描かれ、また太古から生き続ける精霊たちを生き生きと登場させている点では、空間的にも時間的にも壮大なスケールです。 そう、壮大すぎて、悠久すぎて、もう人間の活動なんて、小さい、小さい。 主人公ウィランは真面目で寡黙な青年で、つまりちっともヒーローらしくありません。はっきりいって、地味です。しまいには「氷の覇者」という称号を得るのですが、いわゆる冒険・探索ファンタジーにありがちなすばらしい大活躍を、しません。それどころか、自分なんかがなぜ選ばれたのかと悩み、卑下し、それでもこつこつがんばります。 何とも、現実的なヒーローです。 氷の精霊vs溶岩の精霊、という壮大な対立の構図も、物語の最後には、あれっ、そうなの・・・という感じで終息します。ネタバレさせますと、溶岩の精霊の最長老、始祖ナルガンというのが、海と戦う長い長い年月を経て、今となっては小さな石になってしまっているのです。それを知った時のウィランの落胆は、そのまま読者の落胆でもあります。 確かに、精霊ミミの言うとおり、 「人間っていうのは! いったい、大きさというのがどういうものかわかっているの? あんたより大きければ偉大で、小さいと小物だって、それしかわからないのね。」 しかし、実際には始祖ナルガンは氷の精霊と戦うことはできませんでした。だから物語のクライマックスにスペクタクルな精霊大戦争なんかは、ありません。実際にニンヤ族を鎮めたのは大地人の呪歌、つまり人間の力でした。大地人の古老こそが、ニンヤを再び封じ込めたのです。それは、精霊大戦争よりも、ずっとリアリティのある結末ではありました。 こんなわけで、遠大な時空を背景にした精霊たちの出てくるファンタジーとはいえ、この物語はかなり異色です。しかし、夢幻の軽々しさのかわりに、今もどっしりと息づいている大陸の底力のようなものをリアルに感じさせます。 日本とはまるで違った風土、オーストラリアへの憧れを生む一冊です。 画像は今は絶版のハヤカワ文庫FTの表紙でめるへんめーかーさんの絵。洋書(ペーパーバック)の表紙(リアルなアボリジニが描かれている)とはだいぶ趣が違いますが、私はなかなか好きです。
September 6, 2010
コメント(0)
-
『妖精ディックのたたかい』――英国妖精学の権威の作品
作者のキャサリン・M・ブリッグズはイギリスのフォークロア(民俗学)学会の会長だった妖精研究家です。私の本棚には『妖精の国の住民』(井村君江訳、研究社)がありますが、妖精の出てくる民話や伝説の紹介や「妖精小辞典」が収録されていて、W・B・イエイツの『ケルト幻想物語』(ちくま文庫)とともに、西洋ファンタジーの基礎知識、みたいに思って愛読しています。 彼女は研究書だけでなく創作物語も出していて、それが『妖精ディックのたたかい』なのです。 舞台は17世紀のイギリス・コッツウォルズ地方。でも有名な観光地のストラトフォード・アポン・エイボンやバースではなく、東の方のバーフォードあたり。表紙の裏にある地図には、当時の村々のほか、有史前の土塁や古墳、ウィッチウッド(「魔女の森」)、「しばり首の丘」などという場所がしるしてあり、見ているだけでわくわくします。 主人公のホバディ・ディックは、農場の手伝いを知らない間にしてくれる、ぼろをまとった“家つき妖精”で、ホブとかロブ、ブラウニーなどという種類だそうです。日本で言うと座敷わらしなんかが近いイメージでしょうか。 物語では、清教徒革命後、空き家になってしまったある旧家の農場を守るホバディ・ディックが、引っ越してきた新しい住民を迎えて、何とか農場の伝統的な暮らしをとりもどそうと奮闘する様子が描かれます。 イギリスの風俗や歴史になじみのない日本人が読むにはちょっとわかりにくいところもありますが、訳者の注釈がきちんと入っているし、わからないなりに読み進んでいくと、だんだんその時その場所の雰囲気が読めてきて、いつしかぐいぐいストーリーにひっぱられていきます。 復活祭や五月祭、クリスマスなど季節ごとの行事の描写がすばらしく、そのような古き良きイギリスでは、妖精たち、幽霊、魔女、呪文、宝探しなどのファンタジックなアイテムが、身近でごく自然な登場人物であり出来事であったのがわかります。 最後に妖精ホバディ・ディックが善行によって宗教的に“解放”されるのが、ちょっとキリスト教的でやはり日本的にはなじみにくいけれど、これはやはり西洋の宗教的伝統なのでしょうね。日本の座敷わらしはほとけ様になったりしないでしょうけど・・・ ただこれもあからさまには書かずに、暗示的に示されているので、説教臭さはありません。 一つだけ私が気に入らなかったのは、「妖精ディックのたたかい」という邦題(原題はHOBBERDY DICK)で、だってどう読んでもディックは戦ってはいないのです。もちろん具体的な戦闘行為でないことを示すためにたぶん「たたかい」とひらがなになっているのでしょうが、だとしてもこれは何のたたかいなのでしょうか。 妖精であるディックには、生存競争的な「たたかい」は似合わないし、“解放”を勝ち取るために日々スローガンを叫んで努力しているわけでもない。妖精はもっと自然体で本能や古い習慣のままにひっそりと生きているのであって、時々がんばる場面はあるけれど、「たたかい」という言葉の持つ雰囲気とはちがうのに・・・ と、私は思うのでした。 ともあれ、妖精の権威のえがいた、まちがいのない妖精譚ですから、イギリスの田園や妖精の好きな人にはお薦めの作品だと思います。
July 20, 2010
コメント(2)
-
ダンセイニ『魔法使いの弟子』――黄金のスペイン
創作をちょっと中断して、久しぶりに読書日記です。 以前とりあげた『影の谷の物語』の姉妹編『魔法使いの弟子』。邦題は訳者の荒俣宏がデュカス作曲の「魔法使いの弟子」(ディズニーが「ファンタジア」で映像化したのでも有名!)から借りてきたのだそうです。 『影の谷』と同様、作者の賛美する「黄金時代のスペイン」が舞台です。歴史的に言うと、スペインが世界に植民地を広げた16~17世紀をそう呼ぶらしいですが、ダンセイニの物語ではどうももっと前、騎士道精神や魔法があふれる中世のスペインのことのようです。 で、私的にはこの物語のBGMはデュカスよりも、甘くけだるいアルベニスの「タンゴ」なんかがいいと思うのですが、それはともかく、今度もまっさらな青年ラモン・アロンソが主人公です。 彼は妹の結婚持参金を得るため、父の命令で魔法使いのもとへ錬金術を学びに行きます。この魔法使いは『影の谷』に出てきた大魔術師よりは劣るものの、魔法使いならではの俗世を超越した人物で、不老不死の薬を定期的に飲んだり、人間からとりあげた「影」をあやしい宇宙探査?に遣わしたりしています。 物語はラモン・アロンソが不用意に手放してしまった自分の「影」を取り戻し、それから魔法使いの下働きとなっている老女の影をも取り返すというのがおもなストーリー。 「影」が本体である人間から離れてしまうという話は古今東西いろいろあるそうで、私は河合隼雄の『影の現象学』でその深い意味をいろいろ知りましたが、長くなるので今日は省略します。 ただ、ラモン・アロンソ自身の影の奪還よりも、下働きの老女に影が戻ったとき、彼女の長い影無しの年月が消え失せて、うら若い乙女に戻るという奇蹟が感動的でした。 (ところで、この話でも、デュカスの「魔法使いの弟子」でも、あるいは『ハウルの動く城』や井辻朱美『トヴィウスの森の物語』などでも、魔法使いや魔王の住みかには掃除人がつきもののようです。なぜなんでしょう? 魔女には箒がつきものだし) さてそんな影奪回のストーリーの一方で、ラモン・アロンソの妹は、隣の強欲男に嫁がされるところを、偶然訪れた「影の谷の公爵」に兄の作った「惚れ薬」を飲ませ、しまいには二人はめでたく結ばれることになります。このサイド・ストーリーに出てくる公爵が、『影の谷物語』の主人公ロドリゲスの息子なのでした。 結局、持参金など無くても妹がすばらしい結婚をしたので、ラモン・アロンソのやったことは魔法使いのもとから「影」を解放した、ということになります。「影」を奪われた魔法使いは激怒して追いかけてきたでしょうか? あるいは恐ろしい報復をしかけたでしょうか? いいえ、このあたりがダンセイニらしい筋書きだなと思うのですが、魔法使いの精神はそのような俗な言動を超越しているのです。彼は弟子も掃除女も影も失って、 「そろそろ歳月も終わりに近づいた」と言うと、すべての魔性のものたち――妖精や小鬼や牧神など――を従えて、葦笛を吹きながら異世界へと去っていきます。 それが、スペインの黄金時代の終わりであった、とダンセイニは話をしめくくっています。 ラモン・アロンソと妹の、二組の幸福な人間のカップルが誕生し、魔法はこの世を離れていく・・・それは『指輪物語』のラストにも似て、人間以外の物を言う種族が去り、この世が人間の手に託された瞬間。まさに、時代の変わり目というわけです。 そして、ハーメルンの笛吹男よろしく去ってゆく魔法使いと、あとに続く魔性の者たちの行列は、一種のフェアリー・ライド(精霊たちの騎行)なのでした。
April 20, 2010
コメント(2)
-

『アブダラと空飛ぶ絨毯』――アラビアンナイト風美辞麗句
宮崎アニメの原作『ハウルの動く城』の姉妹編、アラビアンナイト風。 ダイアナ・ウィン・ジョーンズは軽妙洒脱な文章で、テンポもよく、とても面白いのですが、テンポが良すぎて、読んでいて私はちょっともたもたしてしまいます。 それでもこの物語の場合、最初は主人公である絨毯商アブダラが、謎の旅人から空飛ぶ絨毯を手に入れて王女に恋するという、アラビアンナイトそのもののようなストーリーなので、まだゆっくりと楽しめます。 ところが、アブダラが国を逃げ出した後は大忙し。盗賊が出た、と思ったらそれは謎の旅人だった、そして正体はジン(精霊)だった・・・というふうに、次々出てくる登場人物のほとんどが別の顔を持っていて、その「見あらわし」の連続に少し疲れます。 特に最後の方は『動く城』と同様、それまでのオールスターキャストがいっせいに現れ、次から次へと種明かしが続き、ひたすら賑やかでめまぐるしい。まさしく大団円!という感じなのですが、持ち時間があとちょっととでもいうように、やや強引にまとめあげているような気がしてしまうのですね。 ところでこの物語は、舞台設定や奇想天外な筋書きのほか、美辞麗句を連ねた仰々しいセリフがいかにもアラビアンナイト風で、その長いセリフが出てくるとめまぐるしい展開もちょっと一休みするので、私は気に入りました。 「おお、ご立派な絨毯殿。色あざやかにして、精巧をきわめ、魔法をいと巧みによりあわせたる絨毯殿・・・」 「ああ、優美な魅惑のつづれ織り殿・・・愛すべき高貴なるあなた様」 「工芸品の貴族殿、あなた様は絨毯の帝王ともいうべきお方」 ――ダイアナ・ウィン・ジョーンズ『アブダラと空飛ぶ絨毯』西村醇子訳 こんなごてごてしたお世辞を言われた絨毯が、気をよくして一生懸命飛んだりするので、いっそう面白いです。最後の種明かしの場面で、この絨毯の性格が、『動く城』に出てきたカルシファーの性格と一緒だったなあ、と気づくのは愉快でした。
March 9, 2010
コメント(0)
-

『ふしぎをのせたアリエル号』――人形たちの航海
『ふしぎをのせたアリエル号』は、作者はアメリカ人ですが、とてもイギリス風な海洋-冒険-少女-ファンタジー。まず本の分厚さがすごいです。ストーリー自体も盛りだくさんだし、ユーモラスで意味深なセリフがいっぱいあって、それをていねいな文体(私は訳本しか読んでないんですけど、たぶん原文も)でしっかり語っていくので、この長さになったのでしょう。 各章の冒頭にはマザーグースの童謡が一つずつ掲げられています。物語全体が、マザーグースに着想を得てできあがったのではないかと思わされます。 邦題に「ふしぎをのせた」とあるのはなかなか適切な説明で、このお話ではモノ(人形)から人間へ、人間から人形へという変身が、いとも自然に行われます。 主人公の孤児エイミイは、生まれたときから一緒だった船長(キャプテン)姿のお人形を大切にし、語りかけ、マザーグースを歌って聞かせます。するとその人形は、人間になり、エイミイを「妹」と呼びます。 人間になったキャプテンは、海へ行って本当の船長になり、孤児院にいるエイミイを迎えに来ますが、彼を待つ間、いろいろと悪意や誤解のせいでエイミイはキャプテンが死んだと思いこみ、自分も生きる気力を失ったようにベッドに横たわってしまいます。そして、彼女は何と人形になってしまうのです。 人間になったキャプテンは、人形になったエイミイを大切に抱いて船(アリエル号)に乗りこみ、海賊の宝を探しに出かけます。 捨て子や海賊の宝、戦いや裏切りなど、オーソドックスな冒険物語の要素がたくさんあるにもかかわらず、この写実的なまでの変身のために、物語はおとぎ話よりもリアルな感じがする一方、なにか浮世離れした雰囲気も持っています。 おまけに、帆船アリエル号の乗組員たちの多くも、マザーグースと聖書によって命を得た動物!や人形なのです。それから厚化粧の魔女風の女「オニババ」もいます。普通なのは「クラウド一等航海士」だけといえるでしょう。 エイミイの父は彼女を孤児院に捨てて船乗りになりました。孤児院にいる善玉・悪玉2人の女性教師「エクレア先生」「ニガウリ先生」も、若いころ船乗りの恋人に去られてしまった過去があるようです。そしてキャプテンも船乗り・・・ こうしたことを全部考え合わせてみると、このふしぎな物語は、少女エイミイの心の旅のお話ということができるかもしれません。キャプテンはエイミイの分身、ユングの心理学風に言うなら、彼女の心にある男性的な人格なのでしょう。エイミイが4歳でものごころつく頃、人形のキャプテンは箱から出されてエイミイの相棒となります。 そして、彼女に自我が芽生える思春期前の10歳の時、キャプテンは人間の男性になります。孤児院の先生がいろいろと干渉したせいで、キャプテンが海へ去ると、エイミイは彼(魂の半身)を失って、 ・・・エイミイはほとんどごはんを食べなくなり、まったくあそばなくなりました。 ・・・エイミイは一日中、ベッドにねたきりで、ほとんどぴくりともせずに、天井ばかりをじっと見ていました。 ――リチャード・ケネディ『ふしぎをのせたアリエル号』中川千尋訳と、自分を閉ざしてゆき、ついに人形になってしまいます。キャプテンが生きて活動するかわりに、エイミイは死んだも同然の状態になるわけです。 しかし、人形になったエイミイは、キャプテンに連れられて海へ行き、アリエル号に乗りこみ、すべてのできごと――冒険、危険、悲しいこと、嬉しいことをみんな見聞きして体験していきます。 見方を変えると、アリエル号の旅はエイミイの心的体験なのだと言えないでしょうか。外的には活動を停止して、内界にひきこもってしまった彼女のの心の中で、キャプテンやぬいぐるみたちが命を得ていきいきと動きだし、海へ行き、冒険とそれから何かもっと運命的なできごとを求めて、旅をしているのです。 マザーグースや聖書が繰り返し出てくるのも、エイミイの心にその二つの本がしっかりと根づいていたからでしょうし、乗組員の言動がユーモラスなのに起こる事件が結構血なまぐさいのも、彼女の心の状態を表しているかのようです。 そして、生ける屍(人形)となってしまった少女のかわりに、分身であるキャプテンは精一杯の大活躍をし、ついに生き別れた父に感動の再会をします。孤児院の少女には追えなかったけれど、キャプテンは海へ追いかけていって見事に父を見つけるのです。 ここで、エイミイと同じように置き去りにされたらしい、昔の2人の少女、つまり孤児院のエクレア先生とニガウリ先生のことが気になります。あまりに対照的で、表裏一体なのではと思わせる両先生もまた、実はアリエル号で海に出ていたのです。とすると、これはエイミイ一人の心の旅ではなく、エクレア/ニガウリ先生の心の旅でもあるのかもしれません・・・ 戦いに勝利し、黄金を手に入れ、父を見つけ、こうして自分の役割を果たしたキャプテンは去ってしまいます。人形に戻るのでもなく、どこかへ行ってしまうのでもなく、彼自身の人生をまっとうしてアリエル号のこの世から去ってしまうのです。リアルな死の場面は衝撃的ですが、その少し前から人形のエイミイは息を吹き返し始めています。生と死の入れ替わり。今度のそれは旅の終わりを暗示しています。 もちろん、最初はこんなあれこれを考えずに、どんどんストーリーを読み進んで行くことができます! ハラハラドキドキ、途中でやめられません。最後の場面でアリエル号は故郷の港へ向かってまっしぐらに進み、読者はおさまるべきところにすべてがおさまって、大団円を迎える心地よさに浸ることができます。
February 19, 2010
コメント(4)
-

梨木香歩『裏庭』――和洋折衷ファンタジー
図書館でハードカバーを借りて読んだ後、文庫本を購入したら、こちらには河合隼雄(心理学者)の解説がついていて、「ラッキー!」と思いました。 河合隼雄は「すべての少女は心の中に「庭」を持っている」(『子どもの宇宙』)と述べていますので、13歳の少女「照美」が「裏庭」という異世界を旅するこの物語は、彼が解説するにはもってこいの作品だったのでしょう。 それにしても、『裏庭』というタイトルは、何とも暗くて地味です。このタイトルは児童文学ファンタジー大賞をとった時に知りましたが、どうも読みたいという気にならなくて、同じ作者の『西の魔女が死んだ』の方を先に手に取りました。 表紙を見ると「GARDEN」と英語のタイトルもついていて、こちらには「裏」という意味が含まれていません。主人公は日本人ですが、洋館やイギリス人が出てくるこの物語は、和風なところと西洋風なところが奇妙に混じり合っています。 そして、和風なところは、日本の風土独特の暗さ・・・怪談じみた怖さとものがなしさがにじみ出ています。まさに「裏庭」という言葉がぴったり。 ところが、対照的に、裏庭のある洋館の持ち主であるイギリスの老婦人が登場すると、からりとした明るい力強さが感じられます。無人の古い洋館にある、異世界への出入り口である古い大きな鏡も、アンティークな魅力たっぷりでそれほど怖くない。そして、 そもそも、裏庭(バックヤード)という言葉自体がマーサには気に入らなかった。打ち捨てられた、とるに足りないものを思わせる、庭を侮った言葉だというのだ。 ――梨木香歩『裏庭』 と作者自身が書いています。だからこそ英語のタイトルはBACKYARDでなくてGARDENなんでしょうね。 このような和風な雰囲気と西洋風な雰囲気の混在やせめぎあいは、主人公が旅する異世界にどっさり詰めこまれていて、独特の世界をつくりあげています。が、私にはちょっと詰めこみすぎのように感じられました。主人公が現代少女だからかもしれませんが、登場人物やエピソードが和洋あちこちからの“借り物”のようで、それらをつぎはぎして世界がつくられているみたいに思えてしまうのです。 たとえば、異世界に入りこんで最初に出会う人物は、ムーミンのスナフキンに似ているというのです。帽子や釣りといった共通点のほかに、ちょっと変わり者で集団に属さないところや、得体の知れないところ、少し怖いようなあんな目つきをしているらしい、そして彼自身も「スナッフ・キンだ」と名乗ったり・・・ かと思うと「根の国」だの「ハシヒメ」「餓鬼」だの古風でおどろおどろしい和風のイメージ、「ドラゴングラス」「クォーツァス」「タム・リン」など洋ものファンタジーっぽいキラキラした言葉。双子の「カラダ・メナーンダ」(“だからだめなんだ”のアナグラム)「ソレデ・モイーンダ」はキャロルの『鏡の国のアリス』に出てくるトイードルダム・トイードルディ兄弟を彷彿とさせますし、地中から気味の悪い「黒ミミズ」や「地イタチ」が出てくるくだりは、まるでシュールな悪夢。 また、この作者は香りについての描写が印象的なのですが、異世界で「クレゾール」や「プラスティック」などの今風な匂いがしたりします。 現実世界と異世界の符合やからみあいは面白いし、心に残るイメージもたくさんあるのですが、私には最後までこのごちゃまぜ感がぬぐえなくて、ちょっと居心地の悪い異世界体験でした。それも作者の意図するところなのかもしれませんが。 ストーリーはきちんとしていて、心に傷を負った主人公やその家族、周囲の人々もだいたいみんなおさまるべきところにおさまって、物語は終わります。 「日本ではねえ、マーサ。家庭〔ホーム〕って、家の庭って書くんだよ。〔中略〕・・・日本の家庭はそれぞれ、その名の中に庭を持っている。」 ――『裏庭』なんていうせりふが、前の「裏庭」「バックヤード」についての発言と対をなしているようで、なかなか考えさせられます。
November 9, 2009
コメント(2)
-

荻原規子『薄紅天女』――女性の欠如
画像は、少女漫画風の新書版を載せてみました。タイトルになっている天女のほか、主人公の少年阿高と、ヒロイン苑上(そのえ)が描かれています。私は抽象的な表紙のハードカバーを持っているのですが、これだけ分厚い本だとやはり表紙でぐぐっと惹きつけられなければなかなか手に取るきっかけがないかもしれません。 荻原規子の古代日本を舞台とする「勾玉三部作」最終巻です。といってもそれぞれ独立した物語で、さらに中世を舞台に同軸の『風神秘抄』もあります。私は神話が好きなのでもっとも古い時代の『空色勾玉』がいちばんのお気に入り、この『薄紅天女』は、ちょっと「うーん」なのです。 その理由の一つは、作中にも説明されるとおり、この物語が平安遷都の頃(792年)に設定されており、神代の勾玉が神秘的なパワーをいかんなく発揮するにはもう時代が下りすぎているためです。 タイトルの「天女」は、征服欲と同族殺しに自家中毒してしまった天皇家を救うため、勾玉をたずさえて現れるべき女性でしたが、実際には病んだ皇太子の夢にしか登場しないのです。 『空色勾玉』『白鳥異伝』で勾玉を持っていたのが少女(巫女)であったのと違い、『薄紅天女』では、表紙左の野性的な少年阿高が勾玉の主でした。そしてその勾玉の来歴はついに分からずじまい。阿高の母である蝦夷族(アイヌの人々)の巫女姫も、天皇が期待したように勾玉の主(=天女)とは、なりませんでした。 さらに、天皇の座す都(長岡京)では物の怪が跋扈し、狙われた皇太子を守ろうとして皇太后も皇后も命を落としたので、ヒロインの皇女苑上は、父帝に、伊勢へ避難しろと命じられます。 (父上は苑上のことなどいらないのだ……) (わたくしが男にさえ生まれていたら、こんなふうにないがしろにされることはなかっただろうに……) ――荻原規子『薄紅天女』 そこで苑上は男装して御所を抜け出します。表紙の中央下にいる貴族の装束の男の子は、実は苑上の変装姿です。その手助けをするのは、これまた男装の麗人、藤原仲成こと薬子(史実では仲成と薬子は兄妹なのですが、このお話では同一人物となっています)。 つまり、宮中には“女性”がいないのです。脇役である苑上の乳母さえ、去ってしまいます。権力争いと支配欲でいっぱいの男性社会。生命をはぐくんだり、いやしたりする象徴としての女性が生きていけない、不毛地帯。そして夢に見た天女が来るどころか、母ゆずりの破壊的な力を持つ少年阿高がやって来るに及んで、御所は地獄絵のようになってしまいます。 阿高の父方の故郷である坂東(関東)の風土や人々が対照的に明るく力強いので、物語のバランスが保たれているのですが、それにしてもクライマックスへ向かって、とても重苦しい感じがしました。男装した苑上も藤原薬子も、がんばってはいるけれど、かなり無理をしていていたいたしい。 むかし、トールキンの『指輪物語』に女性キャラクターがとても少ない、というテーマで小論を書いたことがありますが、『薄紅天女』でも同じことが言えます。ニッポンの中心である都と天皇家に、生命の守り手である女性の生きる余地がない。それほど悪環境である、ということです。 結局、阿高が天皇に勾玉を手渡すことで物の怪は消え、皇太子の病も快方に向かいます。しかし、宮中に戻った苑上は死んだように無気力になってしまう。阿高が大胆にも彼女をさらって坂東へ連れて行って初めて、苑上は本当の人生を歩み始めるのです。 残された兄の皇太子は嘆きます; 「皇(すめらぎ=天皇家)は妹を犠牲にして長らえたのだ」 「わたしは、近親の女性を最後の一人まで失ってしまった。」 ――『薄紅天女』 そうではない、最後に残った“女性”藤原薬子はこのあと女に戻って皇太子の側にいる、というところで宮中の話は幕をとじるのですが、やはり閉塞感はぬぐえません。歴史をひもとけば、このあと何が起こるかがわかっているからです――平安遷都のあと、皇太子は平城天皇となりますが、4年で退位して弟嵯峨天皇が立ちます。しかし、平城太上天皇は弟と争い、それがもとで薬子の乱が起こるのです。またもや同族争い、そしてただ一人残った“女性”薬子は謀反の首謀者として自害。・・・なんだか、元の木阿弥です。 そんなふうに天皇家をつきはなした作者は、坂東に希望をつないでいるようです。なるほど、やがて坂東の武士たちが活躍する時代がやってくるのですから、歴史の大きな流れをきちんとふまえています。続編『風神秘抄』にもつながります。 しかし『空色勾玉』の千早矢(天皇家の祖とされる)が好きな私としては、阿高と苑上のハッピーエンドの一方で、天皇家の重苦しい結末に「うーん」とため息をつくのです。
October 28, 2009
コメント(0)
-

ロンドンのキキとジジ?『黒ねこの王子カーボネル』
岩浪少年文庫の表紙を見たら、「これって『魔女の宅急便』?」と思ってしまいそうな、『黒ねこの王子カーボネル』。黒猫を連れ、ほうきにまたがって空を飛ぶ魔女は、今も昔も、洋の東西を問わず、女の子のあこがれなんでしょうか。 原書は1955年出版ですが、最近、新版が出て、新聞等にも紹介されました。私のところへも某復刊ドットコムから宣伝のメールが届いたので、とりあえず図書館で借りてみました。 角田栄子の魔女キキは、魔女にしてはほのぼのとした、性格の良い女の子でしたが(ジブリの映画のキキはちょっと違う)、『カーボネル』の主人公ロージーも、特に変人ではなく、家はちょっと貧しいけれど、明るく気だての良い少女です。キキと違って、偶然、魔女からほうきと黒猫を買ってしまっただけで、本来ごく普通の女の子だったのです。 普通でなかったのは、黒猫の方でした。名前はカーボネル(カーボン=炭のように真っ黒という意味でしょう)、ロンドン界隈の猫王国の「王子」の生まれですが、子猫の時に魔女にさらわれ、呪文をかけられて魔女の奴隷にされていたというのです。 とらわれの王子は、実に堂々として、賢くて、気まぐれで、ぷいっと行ってしまうかと思うとすり寄ってきたり、謎めいているかと思うと素直な優しさを見せたり、つまりは猫好きな人にはたまらない、猫特有の魅力にあふれています。 で、普通でない黒猫に、普通の女の子ロージーは振り回されてしまいます。 「ときどき、カーボネルったら、まるで、あたしに買われたんじゃなくて、あたしを買ったみたいなふりをするわ」 ――バーバラ・スレイ『黒ねこの王子カーボネル』山本まつよ訳 けれどもきっと、猫好きの人は、魔女のように猫を思い通りに扱うよりも、ロージーのようにすてきな猫の気まぐれに振り回される方が楽しいと感じるに違いありません。気のいいロージーは、結局カーボネルに同情し、彼の味方となり、彼を縛っている魔法を解くために、あれこれ冒険をすることになります。 呪文が出てきたり、ほうきで空を飛んだりしますが、ロージーの冒険は格別おそろしいめにも逢わず、別世界に行ってしまうこともなく、楽しく進行します。彼女の相棒となる男の子ジョンも、ごく普通の子。出会う大人たちも、癖はあっても善い人ばかりです。最後の方で魔女と対決するのですが、この魔女もすでに年を取って廃業寸前なのです。ロージーたちはわりと簡単に、魔法の書を奪うことができます。 刺激的ではないけれど、安心して読める、そんなファンタジー。でも、カーボネルが猫の王位を奪還するところだけは、かなりハラハラします。人間たちの世界はほのぼのでも、猫の世界は、力が支配しており、カーボネルと赤猫の一騎打ちは、流血の暴力沙汰となります。それまでのお行儀の善い冒険とはきっちり区別して描かれているところが、良いですね。 結局、たちの悪い赤猫はジョンの手で飼い主のもとへ(人間世界へ)帰され、読者も安心な人間世界に立ち戻ってほっとします。一件落着とともに、呪文もほうきも、魔法も、おしまいになってしまいました。 しかし、ロージーにとっては、確かに別世界は存在したのです。アパートの上階の窓から見晴らすロンドンの町並みの屋根屋根がネコの国だというカーボネルの解説を聞くとき、ロージーには、見慣れた人間の町にオーバーラップして、ネコの王国という別世界が見えてきたのですから。日常の光景のなかに自然に見えてくるファンタジーの世界・・・、ロージーの澄んだ子供の目だからこそ、見ることができたというべきでしょうか。
September 24, 2009
コメント(2)
-

皆既日食に幻の島をめざせ――『ぽっぺん先生と笑うカモメ号』
今日の日食、曇り空でしたけど、買い物に出かけた大阪・梅田のビルの谷間で、三日月の形のお日様(の輪郭)を見ることが出来ました。遠くまで見に出かけて雨に降られた人とかもおられる中、私ってラッキー いちばん欠けた時間帯だったので、あたりは雨でも降りそうなぐらい薄暗くなりました。これが皆既日食だったらもっと暗くなって、異常な雰囲気なんでしょうね。 で、日食に非日常的世界へ脱出を試みるお話を思い出しました。児童書なんですが、大人向きか?と思われるところもあり、なかなか奥の深いお話です。 生物学者であるぽっぺん先生が、太陽や磁気をたよりに旅をすると言われる渡り鳥が、日食の時はどんな様子を見せるかを研究しようとするところから始まります。ところがそこは『ぽっぺん先生』シリーズのオハコで、先生はいつしかヨットにただ一人乗りこんで、鳥たちの伝説の楽園アルカナイカ島をめざすはめに。 「ごらんなさい。太陽がすっかりかくれたわ」 ・・・そこには、昼の月にべったりと目かくしをされた皆既食のどす黒い空が、舟のゆくてへ流れる一条の帯に切りさかれてひろがっています。が、よく見れば、その帯は舟を追いぬいて飛行してゆくおびただしい渡り鳥たちの影だったのです。 ・・・ということは、カモメのいうとおり、いまこの舟は海図にない海流を、地図にない場所めざして進んでいるということなのでしょうか。 ――舟崎克彦『ぽっぺん先生と笑うカモメ号』 前作『ぽっぺん先生の日曜日』『ぽっぺん先生と帰らずの沼』と違うのは、日常的現実世界へ帰ろうとする先生の試みが物語り中ほどで失敗し、先生はこの世を捨て去る決心をして、水先案内のカモメとともにこの世ならぬ楽園島を本気でめざす気になるところ。 ところが、前向きな決意をしたというのに、舟が進むこの世ならぬ海域は、何やらおどろおどろしい様相を呈してくるのです。入道雲は巨大なイモムシに、夕焼け雲は水平線からわき出てだまし絵のように空へ駆け上るイモリたちに変幻し、夜になるときらびやかな満艦飾の亡霊船が出現。魔王ルシフェルや魔界の怪物たちのパーティ、美少女の姿でいけにえにされそうになるカモメ・・・など、さながら地獄絵巻。 そして、魔物をうちやぶって、(日食の終わっていつものように)のぼる朝日とともに、めざす島が見えてくる、その時・・・。魔法はとけ、楽園は消え、夢は霧散してしまいます。何ともいえない切ないエンディング。 ぽっぺん先生シリーズのうちで、ひそかに私のいちばん好きな1冊です。
July 22, 2009
コメント(2)
-
『ムーミン谷の仲間たち』――冒険家ムーミンパパ
『ムーミン谷の仲間たち』さらにつづきです。 ムーミンの世界では、孤独とさすらいを愛するのはスナフキンだけではなくて、むしろ原点は、若いころ冒険家だったムーミンパパだろうと思われます。 画像はムーミン公式サイトで見つけた、新発売のマグです。 『ムーミンパパの思い出』に語られるように、ムーミントロールのルーツ(つまりムーミンパパとムーミンママの出会い)や、スナフキンやミイの出自には、ムーミンパパの若き日の冒険(さすらい)が大きく関係しています。日常を離れた自由気ままな冒険こそが、のちのムーミン屋敷での自由気ままな日常生活の土台にあった、というべきでしょうか。 しかもムーミンパパは、『ムーミン谷の仲間たち』の「ニョロニョロのひみつ」では、自分が築いたムーミン屋敷と家族の日常から出奔して、ニョロニョロとともに海へ乗り出してしまいます。 家族に「ひとことの説明もなしに」、突然家出てしまうお父さん。現実だったらかなりヒドイです。 しかし、作者は弁解しています; たぶん、パパ自身も、なぜ自分がとびださなくてはならないか、わからなかったでしょうね。 ・・・ ムーミンママはいいました。 「そのうちにはかえってきますわ。・・・きっとこんども、かえってくるでしょうよ」 だから、だれも心配しませんでしたが、それはたいへんいいことでした。・・・ ――『ムーミン谷の仲間たち』 冒険家だったムーミンパパを知っているからこそ、いやもっと言うと、ムーミンパパが冒険していたからこそ自分たちが出会ったという事実があるからこそ、ムーミンママは、パパの帰還を頭から信じて、日常にとどまっていられるのでしょう。 いっぽうムーミンパパは、出会ったニョロニョロに困惑しつつも、限りない自由を感じながら船旅を続けるうち、守るべき家族や穏やかな谷の日常を忘れ、大海原やさびしい月、そのただ中の自分の存在を感じながら、次第に“ニョロニョロ化”していきます。 スナフキンが“ひとり”と“友情”の間を揺れ動くように、ムーミンパパの意識も“自由”と“家族”の間で揺れているのです。時には、“自由”の方に振り子が大きく振れて、こうしてニョロニョロと一緒にあてどのない旅をする。 そしてとうとう、大勢のニョロニョロの集まる島へ着きます。 ニョロニョロが孤島に大集合する不可思議なできごとについては、もっと前に書かれた『楽しいムーミン一家』にも出てきて、こちらでは一家みんなが一緒に船に乗りこんで、ニョロニョロの島へ行きます。 パパの船旅は、たぶん、これより以前のできごとという設定なのでしょうが、書かれたのは『楽しいムーミン一家』より後です。きっと作者は家族みんなでのニョロニョロの島体験を書いた後、その旅を、もっともっと孤独で自由で非日常な体験としてムーミンパパ一人に担わせたくなったのではないでしょうか。 ともあれ、ニョロニョロの大集会を見、すさまじい雷と大風にあって、突然ムーミンパパは我に返ります。ニョロニョロとはどんな者たちなのかについて、“見るべきほどのものは見つ”みたいな気持ちになったのかもしれません。 「ぼく、家に帰るよ! すぐに出発するよ!」――『ムーミン谷の仲間たち』 自分は家にいて(=日常で)も、じゅうぶん冒険ずきでいられる、というのがムーミンパパの結論でした。彼は非常にスッキリした気分で家に帰り、いつもムーミントロールが知っているような、落ち着いた良いお父さんにおさまったのだと思います。 翻訳者山室静の巻末解説には、この短編にかぎってはまとまりが悪く、失敗作ではないか、というコメントがあります。確かに、ムーミンパパの突発的な家出衝動とか、わけのわからない船旅とか、得体の知れないニョロニョロとかの断片的な、まとまりのわるい冒険談かもしれません。普通の冒険物語にあるような、力強い前向きな明るさや、起承転結のメリハリや、最後の達成感など、どれもはっきりしません。 しかし、ふと、こういうのが、人生の中年期の“冒険”なのかなと思います。突発的な感情の高まりがあったかと思うと、すぐまた気がふさぐ。戦闘的な気分になる瞬間のすぐ後に、友好的な気分になる。ニョロニョロとは意思疎通ができぬままなので、言葉は常にムーミンパパの独白や一方通行のセリフばかり。それでも、“冒険”はなしとげられ、彼は心落ち着いて日常に帰ります。中年期には、自分の日常を納得するために、このような形で“冒険”をする必要があるのかもしれません。
June 15, 2009
コメント(4)
-
『ムーミン谷の仲間たち』――フィリフヨンカ
『ムーミン谷の仲間たち』つづきです。 この短編集には、スナフキンの章以外にも、日常の社会生活を離れた“孤独”“さすらい”“大自然”への憧れや共感があちこちに出てきます。とても子供向けに書かれた童話だとは思えないものもありますが、作者の心のほとばしりが現れているのだと思います。 「この世のおわりにおびえるフィリフヨンカ」は、神経質で義理堅く几帳面なオールドミス(「おくさま」と呼ばれていますが家族はいないようです)が主人公です。 フィリフヨンカのつねとして、彼女もこちゃこちゃしたしなものをどっさりもっています。小さいかがみだの、赤いビロードのわくにいれた写真だの、小さい貝がらとか、せともののねこやヘムルが、かぎあみのレースの上にすわっているのだの・・・ ――ヤンソン『ムーミン谷の仲間たち』山室静訳 つまり彼女は、よこぶえとパイプの他ほとんど持ち物を持たないスナフキンの、対極なのです。 祖母の住んでいた海辺の古い寂しい家に住み、誰それからもらったり譲られたりした、細々した家財道具を守り、シマシマのじゅうたんをシマ模様の一つずつごしごし洗うフィリフヨンカ。本質的には大事とも思えないしがらみにしばられた、こせこせした日常。その中で、彼女は何か大きな破局がやってくるという根拠のない予感にいつもおびえています。 しかも、誰とも分かち合うことのできないその予感は、嵐の訪れとともに的中するのです。 たまたま今日、私の住むあたりは梅雨入りだということですが、単なる雨でさえそれなりのムードを持っています。まして大自然のパワーをあらわす嵐とか雷、竜巻などの天候は、私たちの気分に強く働きかけるようです。 フィリフヨンカが家の中でこちゃこちゃした財産とともに在った時には、嵐は暗くやかましく、恐ろしいものでした。中でも、割れた鏡のかけらにうつった青ざめた自分の姿が、彼女には最も恐ろしいものだったのでしょう。彼女はそれを見たとたん、たまらず外へ逃げ出します。 しかし、広々した大自然の中へ出てみると、そこは家の中よりあかるく、静かで、そして、 ふしぎなことに、彼女は、きゅうに自分がまったく安全なのを、感じたのです。・・・しかも、なんともいえず気持ちがいいのです。なにをくよくよすることがあるでしょうか。とうとう、大きなさいなんがきてしまったのです。――『ムーミン谷の仲間たち』 彼女の恐れていた破局とは、日常のしがらみを捨て去ることだったのです。大嵐のあとの、まっしろなたつまき。朝日にばら色に染まる、そのたつまきに、彼女の家と財産はすっかり持ち去られてしまいます。 「もうわたし、二度とびくびくしなくてもいいんだわ。いまこそ、自由になったのよ」――『ムーミン谷の仲間たち』 高らかに勝利宣言をしたフィリフヨンカは、孤独に、自由に、嵐に洗われたじゅうたんでサーフィンをします。何と野性的で、爽快な場面でしょう。日常に追われる私たちも、心のどこかで彼女と同じような危機感を感じ、また、彼女と同じように檻を破って自由になりたいと願っているのではないでしょうか。 まだ次回へつづきます。
June 9, 2009
コメント(0)
-

『ムーミン谷の仲間たち』――さすらいのスナフキン
弁解から始めますと、近頃パソコンが不調です。とっても反応が「重く」なってしまって・・・もしかして買い換え時? 買ってからまだ(もう)7,8年なんですけど・・・ で、ムーミンの話題は、だいぶ前“春の旅立ち”にからめた日記をいくつか書いた、その続きのつもりでした(季節がずれちゃいましたが)。 ムーミンの一党で“旅”をするひとといえば、やはりスナフキン。短編集『ムーミン谷の仲間たち』の最初のお話「春のしらべ」は、孤独なさすらいびとスナフキンの本質にせまる?お話です。 スナフキンはさすらいの詩人で作曲家でもありますが、彼が新しい「春のしらべ」を作るまでのあれこれ――せっかく歌の着想がわいたのに、偶然出会ったちいさな「はい虫」のおしゃべりや何やかやに気持ちを乱され、旅の足取りまで乱されて、でも結局はちゃんと、歌はできる――、それは、芸術家の“産みの苦しみ”の実例をわかりやすく語っていると思われます。 スナフキンが歌を作るには世間一般のしがらみから離れて、自由に、独りでいなければなりません。もともと彼は“独り”をそれはそれは愛しているのですが、でも、だからといって、誰とも全くつきあわないわけではないのです。ゆきずりのはい虫の悩みや願いも聞いてやるし、旅に出ても必ずムーミン谷には戻ってきて、ムーミントロールの「親友」であり続けるスナフキンは、“独り”と“友情”との微妙なバランスをどのようにとっているのか。 これは、芸術家でなくても、人間関係や社会的立場にしばられる(あるいはそこに適応しにくい)現代人にとって、興味深い問題だと思います。 スナフキンが、ムーミン谷には仲間として居られるのは、 ムーミンたちはおたがいに、人のことは心配しないことにしているのです。こうすれば、だれだって良心が発達するし、ありったけの自由がえられますからね。――ヤンソン『ムーミン谷の仲間たち』山室静訳という、ムーミンたちのおおらかな気質のおかげでしょう。 だからと言って、気配りをしないわけではありません。「世界でいちばんさいごのりゅう」では、竜がスナフキンだけになついたことにしょげ返るムーミントロールの気持ちを、スナフキンはちゃんと察知して、そっと竜を遠くへやり、なにげなくふるまいながらムーミンを元気づけます。 けれど、自分のことしか頭にない、自分の気持ちで精一杯なはい虫に対しては、邪魔されたスナフキンはイライラして“切れそう”になります。でも、やっぱり見捨ててはおけない。“独り”と“友情”の葛藤。こういう気持ちって、あるなあ、と思います。 大丈夫。自分の気持ちに素直であり続けることで、最後に「春のしらべ」の霊感はちゃんとスナフキンのもとへやってきます; ――第一部はあこがれ、第二部と第三部は春のかなしみ、それから、そうです、たったひとりでいることの、大きな大きなよころびでした。――『ムーミン谷の仲間たち』 はい虫につきあってやり、彼に名前をつけてやり、彼のために戻ってきてやったことで、スナフキンの孤独の喜びはいっそう増し、音楽はいっそう豊かになったのだろうと思います。
June 7, 2009
コメント(4)
-
魔法の丘――『吟遊詩人トーマス』ほか
「エイルドンEiledonの丘」は、昔のイングランド-スコットランドの国境地帯にあります。私の“行ってみたい土地”リストを作ったとしたら、多分No.1でしょう。 私が初めてこの丘に出会った?のは、サトクリフの古代英国史小説『第九軍団のワシ』でした。イングランドがローマ領だった頃、その辺りは最果ての属州で、トリノモンティウム(三つの丘の土地)という砦がありました。主人公たちが、うち捨てられ廃墟となった砦で野宿していると、荒涼として亡霊の出そうな静けさの中、ふいにどこからかローマ兵の歌が口笛で流れてくる・・・ そんな雰囲気を記憶していたら、数年後ウォルター・スコットの叙事詩「最後の吟遊詩人の歌」The Lay of the Last Minstrel の一節に、大魔術師マイケル・スコットがその魔力で「エイルドンの丘を三つに裂き」というくだりがあるのに出くわしました。 実際、スコットはエイルドンの丘の見える家に住んでいたことがあったそうです。 さらに、素敵なエイルドンに遭遇したのは、ビッグ・カントリーという80年代英国ロック・バンドの歌でした。ケルト風のメロディーを使ったり、ギターでバグパイプの音色を真似るなど、私の趣味にぴったりのバンドでしたが、3rdアルバム「The Seer」(予言者、千里眼)の中に、ゆったりとしたバラード調べの「Eiledon」という一曲があったのです; Eiledon, I will be there / Eiledon, my dream is there 彼らの歌を聴くと、発音は「エィーリドン」のように聞こえます。 さて、この丘で妖精の女王に会い、彼女にキスをして妖精の国の楽師になったというのが、「正直者」トーマスの伝説です。彼が7年間、妖精の女王に仕え、嘘をつけなくなったのでそう呼ばれるのだとか。7年後人間界に戻ってきたトーマスは予言者としても有名になり、年老いてまた妖精の国に行ってしまったといいます。 妖精の美女に連れられて異界に行ってしまう男の話は、浦島太郎からアイルランドのオシアンまで、いくつか似た伝説があるようですが、帰ってきてからも大活躍をするのはトーマスだけではないでしょうか。そう考えると、妖精界と人間界と両方で成功をおさめたトーマスって、すごいですね。 その魅力的なトーマス伝説を小説化した『吟遊詩人トーマス』では、井辻朱美がEiledenを「イールドン」と訳しています。幻想文学大賞受賞作だそうです。 ところが、読んでみると、魔法の雰囲気に満ちていて、味のある登場人物が出てき、語り口もなめらかなのに、いま一歩物足りないようなお話でした。 スコットランドの自然や風物、人々の生活はていねいに描かれているし、妖精世界の描き方も不可思議で美しく、また残酷で興味深い。だのに、肝心のトーマスに期待したほどの魅力が感じられないのです。 美形で腕もよく、モテモテの吟遊詩人であるトーマスは、普通の人間くさいところもあって、イールドンの百姓娘とごく普通の恋もしました。それなのに、妖精女王と一緒に行ってしまうのは、なぜなのか・・・そのあたりをもっと突っこんで書いてくれれば・・・と思います。 神隠しにあったトーマスを親身になって心配する老夫婦や、百姓娘エスペルスが、人間として親しみ深く描かれているのに対し、トーマス自身は結局どんな人物なのかつかみどころがないままなのです。人間も妖精も、トーマスのどこにそんなに惚れこんだのか? というあたりが、最後まで読んでもよく分かりませんでした。 ただ、訳者井辻朱美の解説を読むと、はっきりとした人物像をあえて描ききらずに、わざとぼやかしてあるのだとのことです。それこそが、トーマス伝説の神秘さ、不思議さをあらわしているのだと・・・ それはともかく、「イールドンの丘」の描写は素敵です。ますます行ってみたくなります; そこ〔=イールドンの峰〕からなら、世界が宝石ずくめの地図のように眼下に広がっているのが見え、きこえるのは風がエニシダの茂みを鳴らす音ばかりだという。 ――エレン・カシュナー『吟遊詩人トーマス』井辻朱美訳 これは、『ウォーターシップダウンのうさぎたち』で、やっと丘の頂上に着いたうさぎたちが、「来て、見てごらんよ! 世界中が見える」と感動するくだりを思い出させました。 ファンタジーの本質の一つに、現実世界から離れた視点から現実世界を見つめ直すということがあります。妖精女王の鈴の音は聞けずとも、下界を見はらせる丘の上は、ファンタジーにぴったりの聖域なのだと思います。
August 15, 2008
コメント(0)
-
精霊たちの行進――『小人たちの黄金』ほか
むかし手放してしまった大好きな本を、先日ふと古本で買い戻しました。1912年、アイルランドの独立運動の高まりの中で書かれた民族的?ファンタジー、スティーヴンスの『小人たちの黄金』です。 古代アイルランドやケルトが大好きな私ですが、近代のアイルランドは、飢饉やイギリス支配下の圧政、血なまぐさい独立運動など、どうも暗くて重いので、敬遠してしまいます。だいたい、政治的なニオイのする詩や小説って、なかなかおおらかな気持ちでは楽しめません。 ところが、この本は読めるんです。アイルランドの民衆(いや、あたたかでまっとうな人間性を求めるすべての現代人)を鼓舞する意図が見え見えなんですが、登場する賢者・魔女・子供たち・小人・乙女、そして神さままでもが、素朴で神秘的、しかもユーモラス。 ストーリーのあらすじを書いても、このお話の人を食った面白さは伝えることができません。けれどあえて紹介しますと、頭でっかちで偏屈で頑固な賢者が、牧神やアンガス・オグの神、彼らに愛された乙女とかかわることで、生き生きとした人間性に目覚めます。啓示にうたれ信仰に目覚めた人のように、賢者は出会う人々の心を目覚めさせてゆく。 ところがこの神話的なストーリーに、突然現れた警察が、誤解から賢者を逮捕してしまう。このあたり、賢者はちょっとイエス・キリスト的です。処刑されるのかなと心配になります。 しかし、賢者の無邪気な子供たちと、妻である魔女が、アイルランドじゅうの眠れる神々や小人、妖精たちに呼びかけて、彼らは立ち上がります。そして生命の讃歌を歌い、踊りながら進み、イギリスの支配にあえぐダブリンを解放し、賢者を救い出すのです。 この神がかり的な解放と行進は、いくつかのファンタジーに見られる共通のパターンで、もとはというと、ヨーロッパ各地にある“眠れる英雄の伝説”じゃないかと思います。アーサー王(またはフィッツジェラルド伯、オールダリーの洞窟の騎士、バルバロッサ王などなど)は人知れず眠り続けているが、来るべき祖国の危難の時には目覚めて、彼の名をあがめるすべての人々とともに祖国を救う・・・というものです。 映画「ナルニア第2章カスピアン王子の角笛」を観て、バッカスやシレノスたちの祝祭的な行進の場面がなかったのが残念、と書きましたが、人間性を抑圧するくびきを断ち切るこの行進も、同類だと思います。 それからやはりアイルランド作家の“幻の名作”『霧のラッド』のラストにも、妖精たちの大行進が、現実主義の町を解放するというクライマックスがあります。 現実のアイルランドの独立解放運動は悲劇的で血なまぐさいもののようですが、その一方で、祖国愛や人間愛を(照れ隠しと冷静さのアイロニーをほどよくブレンドしながら)神話的なファンタジーでうたいあげようとした人々がいたということは、それ自体一種の“救い”であるように思えます。
July 20, 2008
コメント(2)
-
レアもの!? ソビエトのファンタジー『自然の教室』
ここ数日の暑さに我が家の庭はすっかり夏!で、カマキリの子やバッタの子、毛虫イモムシ、チョウチョにアブ、とにかく虫がいっぱいです。きのうなんか、クヌギの近くのトレリス(春にスイトピーをからませていたのを、そのまま放置していた)に、セミのぬけがらがついていました。 それで思い出したのが、ソ連の昆虫物語、『自然の教室』。子供の頃、福音館日曜日文庫というシリーズから出ていまして、『ファーブル昆虫記』で虫好きになった私が、とても楽しんで読みふけった本です。 後書きによると、ソ連ではロングセラー児童書だったそうで、当時(今も?)おとぎ話以外のソ連(ロシア)の児童書なんて、ほんとに珍しいものでした。しかも、学者先生と2人の子供がミクロサイズになって、昆虫の世界を冒険するという、SFみたいな大長編です。 表紙絵からして、リアルな虫で、苦手な人は退いてしまいそう。挿絵は日本の画家さんですが、主人公の子供は出さずに、図鑑なみにリアルな虫や植物のみを描いていて、これが虫好きにはたまらない。ヘタに原作のイメージを壊さず、かえって読者の想像力をふくらませてくれます。 ただ、タイトルが地味ですよね。自然の教室、なんてなんかお勉強くさい。現題は「カリークとワーリャの異常な冒険」で、この方がいいのに、と思います。 主人公の兄妹カリークとワーリャは、学者先生の新薬をいたずらで飲んで、体がミニサイズになってしまうんです。そして、トンボの背中に乗って池へ、さらにその周囲の丘へと連れてゆかれます。そこは、いろいろな昆虫たちがなまなましい生存競争を繰り広げる、ドラマチックなミクロワールドでした。 と書くと、夢のようなファンタジーみたいなんですが、いわゆるおとぎ話調のファンタジーとは違って、虫の世界に行ったからとて、この物語では虫がしゃべったりはしません。虫はあくまで虫らしく、餌をとったり巣をつくったりしています。それを小さな兄妹の視点からとことんリアルに描写しているところが、すごいです。 太陽の光を浴びると、トンボの胴体は、ふくれて強そうになり、つやつやしてきた。が、雲の冷たい陰がさすとすぐに、ちぢまってしわがより、古いいすの座席のようにゆるんできた。 ――ヤン・ラリー『自然の教室』八住利雄訳 これなんて、ほんとにトンボの背中に乗ったことがあるのかと思わせるような表現ですよね。 二人はトンボから落ちて池にはまり、アメンボに狙われ、ミズグモにつかまります。一方、学者先生も、子供たちを探し出して助けるために、自ら小さくなる薬を飲んで、ミクロワールドに乗りこんでいきます。タンポポの綿毛につかまって空を飛んだり、アリマキの蜜を飲んだり、マツヨイグサの花の中に閉じこめられたり、本当に想像を絶する大冒険が続きます。 二人は学者先生とめぐりあえるのか? そして三人はミクロワールドを乗り切って、先生が草地に置いた「元のサイズにもどる薬」のもとへたどりつけるのか? とにかく、ハラハラドキドキの連続です。 旅の間、学者先生は自然に関する知識でいろいろな困難を乗り切って行きます。最後の方ではナラの葉の船体に、ハエの羽の帆を張ったヨット「オサムシ号」を作ったりして、ちょっと船乗り気分です。図鑑か写真のような絵ばかりだった挿絵が、ここだけ、マニアックな船の図になっているのも嬉しい。 そして、470ページに及ぶ奇想天外な旅の末、彼らはめでたく家に帰ります。冒険の醍醐味と結末をしっかりおさえ、知的な驚きとユーモアと、学者先生と兄妹の人間味あふれた、これはなかなかの傑作だと思うのですが、今となっては絶版です。 やっぱり邦題が悪いんじゃないかしら。誰か、再評価してほしいです。ピクサーが映画化してくれたら、楽しいかも。
July 8, 2008
コメント(2)
-

『マリアンヌの夢』――少女の夢の中の少年
今日は今年度初の読書ボランティアの会合があり、まずはお勉強会ということで、『ぼくはおこった』(ハーウィン・オラム)という絵本が紹介されました。主人公の男の子が、「早く寝なさい」としかられたことをきっかけに、家をこわし、町をこわし、地球をこわし、宇宙もめちゃくちゃにして、とうとう自分がなぜ怒っていたのか忘れてしまって、ベッドで眠るというお話。 講師の先生が、ふんわり心のあたたまるいい話ばかりでなく、子供の内面の嵐を描写したような、こんな絵本もありますよとおっしゃいました。 で、最近読んだ本を連想したんですが、キャサリン・ストー『マリアンヌの夢』。これは、主人公マリアンヌの将来の夢は・・・、という話ではなく、10歳の彼女が長わずらいをして病床で見た夢、それもちょっと不可解で無気味なところもある夢と、そこからの脱出のお話です。 病気や夢、その中の恐怖や不安といった体験は、子供にもふりかかってくるものだし、重要な意味を持っているということ。 そんなテーマを持つこの本は、(冒険やスペクタクルものが好きな)私は、自発的にはまず読まないだろうなという物語。 それを手に取るきっかけは、この本が河井隼雄『ファンタジーを読む』で絶賛されていて、病気という外的にはマイナスな状態が、 マリアンヌの成長のために必要なことであった。 病いは内面の仕事(成長)の充実のためにおとずれてくることが多い。などという解説がとっても“目からウロコ”だったことです。 そして、実際に読んでみて私の心に残ったのは、夢に現れる内面の不安や恐ろしさよりも、マリアンヌがそれを乗り越えられたのはマークという男の子の存在だったということ、彼女にとってそれほど重要な価値を持つ“夢の中の少年”そのものでした。 物語の構成は分かりやすくて、マリアンヌがひいおばあちゃんの裁縫箱にあったある特別な鉛筆で絵を描くと、眠ったとき、その絵の通りのものが夢に現れるのです。 最初マリアンヌはなにげなく草原と岩と家を描き、次に夢の中で自分がその家の中に入れるように、窓に男の子を描き足します。すると夢の中にも男の子が出てくる。 ところがそれは、起きているとき病床の彼女を教えに来る家庭教師の先生の、もう一人の生徒である、やはり病気の男の子マークらしいのです。 思春期にかかる女の子が、夢の中や空想で一人の男の子を思い描くというのは、よくあることだと思います(反対に、男性にも心に描く女性像というのがあるんでしょうけど)。 それは実際に見たことがなかったり、見たことはあってもほとんど知らないような男の子で、それなのにとても印象的で気になってしまう。 私も若い頃は時々、男の子の出てくる印象的な夢を見ました。目が覚めてみるとそれはその当時好きだった誰それ君や、憧れていた先輩のような気がします。でも、よく思い出してみると、全然ちがっていて、なぜ「憧れの彼」だと思ったのかさえ分からない。それなのに「夢の彼」は忘れがたく、時には私の心の中での重みが現実の「彼」をしのいでしまうほど鮮烈なイメージとして残り続ける・・・そんな体験を、私はこの本を読んで思い出しました。 現実の生活では、男の子よりも、女友達の方がずっと親しくしているのに、なぜ女の子の夢は見ない(見てもあまり覚えていない)のだろうと思いました。この物語でも、マリアンヌは夢の中のマークとけんかして彼の顔をぬりつぶし、かわりに友達になれそうな女の子を描こうとするのに、うまくいきません。 マークはマリアンヌの夢(=心)の家に住み続け、やがて彼女は足のたたない彼を励まし、手助けし、ついに歩けるようになった彼と、自転車に乗って家から出て行くのです。 家は、避難所ではあるのですが、彼女が自分で描いた周囲の岩に見張られています。岩は悪意を持ち、マリアンヌとマークに迫ってきます。このあたり、とても無気味で怖い悪夢です。 マリアンヌとマークが助け合いながら二人で家を脱出し、灯台(とその向こうの海)をめざすところは、やがて大人になっていく少女の旅立ちを象徴しています。 ただ、最後の場面で、マリアンヌは魔法の鉛筆をマークにあげてしまいます。灯台からさらに海へ行くのに、マークがヘリコプターを描いてそれを夢の世界に登場させるためです。 もともとはマリアンヌの夢を創っていくアイテムだった鉛筆を、夢の中のマークに与えるとは、どういう意味なのでしょう。次に夢を見たとき、マークはマリアンヌに置き手紙を残して、先にヘリコプターに乗って海へ飛んでいっていました。マリアンヌは迎えに来るよという手紙を読んで、灯台で彼を待つところで、物語は終わります。 最初はマークが家の中でマリアンヌを待つ風情だったのに、最後には逆にマリアンヌが灯台の中でマークが外に連れ出してくれるのを待つことになります。二人には信頼関係があるのでマリアンヌに不安はないようですが、私は何だかせつない気がします。 男の子というものは、そうやって、行ってしまうのです。行ってしまうのこそが男の子だと言うべきかもしれません。そして、少女はそれが分かっていても彼を前進させるために、魔法の鉛筆(それはマリアンヌのひいおばあさんの形見であるので、女性に代々伝えられてきた魔法の宝物と思われます)を与えてしまわねばならないのです。 そんなことを感じたとき思い出されたのが、やはり思春期に入る少女が夢?の世界で少年と出会い冒険をする物語の、最後の方の場面; その時あたしは、ジェットサムはきっとこのあとも、冒険をつづけて行くだろう、と思ったの。・・・ ・・・ 「あなたに上げるものがあるの。」・・・ そう言ってあたしはポケットからマンティッドのおくりものを出しました。これをジェットサムにやりたいという気持ちが、あたしの心のどこかからわいて来たの。・・・ 「マンティッドのおくりものよ。あなたに上げるわ。きっと、いることがあってよ」 ・・・ ・・・あたしは手をふらず・・・じっと見送り、その人を待っているもののところへ行かせてあげたの。 ――シーラ・ムーン『ふしぎな虫たちの国』山本俊子訳 マリアンヌの方はマークの迎えを待つのですが、全然あせらず、それよりも鉛筆を与えたことに満足し、ゆったりと平和な気持ちになっています。現実世界ではこのときマリアンヌもマークも病が癒え、二人ともリハビリ?のため海へ行く予定が語られるので、たぶん夢としての結末は、これでいいのでしょうね。 夢が終わり、今度はほんとうにマリアンヌとマークが出会う物語(『マリアンヌとマーク』)もあるようです。でもたぶん現実のマークは夢のマーク=彼女の心の家に住んでいたマークとは違うでしょう。私は、訪れてそして去っていった“夢の少年”の思い出こそ、貴重なマリアンヌだけの宝物になるだろうなあ、などとセンチメンタルな思いに浸るのでした。
May 14, 2008
コメント(0)
-

寒くても心あったか――『ふうたのゆきまつり』
子ギツネのふうたを主人公にした四季のお話のうち、“冬”の巻です。 子ギツネって、かわいいし賢そうだからか、よく童話の主人公になっていますね。『てぶくろを買いに』『ごんぎつね』(新美南吉)が有名ですが、私が小学校の時の教科書には、松谷みよ子の「きつねの子のひろったていきけん」というのが載っていました。 「ふうた」も、けなげでかわいい子ギツネです。車のヘッドライトにびっくりして立ち往生したところを、運転手(タクシー運転手のまついさん)に助けられ、 「ぼく、しんだんだな。まっくらで、なんにも わからないや。」 「あしおとが するよ。とうとう、かみさまが ぼくを むかえに きたんだな。」 ――あまんきみこ『ふうたのゆきまつり』などと、ひとりごとを言うのです。この無邪気なセリフが、とても自然で、いいですねえ。 ヘッドライトのあまりのまぶしさに野生動物の敏感な目はくらんでしまって、立ちすくみ、気が遠くなって・・・、などと説明されるよりも、こんなセリフでこそ子供の心にすんなり理解されるんでしょうねえ。でも、大人になってから読み返すと、物語のしょっぱなから、無邪気なふうたが「死」を意識しているのだなあと気づかされて、何だかドキッとします。 で、まついさんの手助けで、子ギツネふうたはうまく人間の男の子に化けて、雪で作ったかまくらに初めて行くことができました。暗い空、白いかまくら、その中の火鉢や女の子の赤い着物などの、シンプルで美しい景色の描写や、雪祭りの歌などが、幻想的な雰囲気をかもしだしていて、宮沢賢治の『雪渡り』なども思い出させます。 雪の真っ白な、星の輝く寒い晩は、キツネと人間が心を通わせる雰囲気に、ぴったりなのでしょうか。 「ねえ。おじちゃん。おじちゃんも ほんとうは、きつねでしょう?」という、眠りかけたふうたの最後のセリフが、これまた無邪気で、あったかい。そんなふうに慕われるタクシーのまついさん、今では何だかなつかしいような優しさを持ったキャラクターですね。
January 27, 2008
コメント(2)
-

S・キング『シャイニング』――恐怖の冬ごもり
先日、ロマンティックな冬ごもりということで『トッペンカムデンへようこそ』をご紹介したのですが、反対にとってもコワイ冬ごもりといえば、やはりこれですね。『シャイニング』。素敵な題名なのに、そしてファンタジー的要素や表現がいっぱいあるのに、とにかく怖すぎて読めない・・・映画も観たくないっ いや、もちろん読み通したことはあります。ずっと昔に一度だけ。その時は眠れなくなってしまいました。寝室の外の廊下を近づいてくる音が聞こえるような気がして・・・ そういえば、『クリスマス・キャロル』の亡霊も鎖をひきずって廊下を近づいて来るのでしたっけ。 主人公の少年、5歳のダニーは、心に「かがやき(シャイニング)」つまり予知・幻視・テレバシーなどの超能力を持っており、それがファンタジーによく出てくる魔法使いとか、予言者とか、そういった能力者と通じるところがあって、とても興味深いのです。 そして、自分の能力や予知した恐怖におびえとまどうダニーの前に、よき理解者ハローラン(60歳の黒人。いわゆる老賢者タイプ。キングのファンタジー小説『タリスマン』に出てくる黒人の音楽家スピーディと似ている)が現れて、彼をなぐさめ導きます。 「ダニー、おまえさんの頭のなかには大きななにかが詰まってる。それがわかるようになるまでは、うんと大きくならなきゃならん。それについて勇気を持たなきゃならん」 ――スティーブン・キイング『シャイニング』深町眞理子訳 老人が超能力「かがやき」について説明し、少年と仲間になるくだりが、私はとても好きなので、ときどき読み返します。でも、その先は・・・、特に物語後半は、とにかく怖いので二度と読みません! ホラーが苦手な私には、S・キングの話はどれも怖いのですが、特に幼い子供やその家族が登場する話は、やはり自分の子供のことなどつい考えてしまうので、ますますいただけません。 怖いところは全部とばして、最後の決戦に進みます。古いホテルに積もり積もった過去の邪悪な亡霊たちがよみがえり、怪物と化してダニーを殺そうと追ってきます。たった5歳のダニーが身の内の「かがやき」を発揮してこの父の姿をした怪物と真っ向から対決する場面は、やはりファンタジーやおとぎ話によくある“象徴的父殺し”の試練を思い起こさせ、感動的です。 そしてホテルの爆発というスペクタクルを経て、ダニーは“悲しみを超えて賢くなった一人前の人間”へと成長していくだろうという希望を示し、そこに寄り添うハローラン、見守る母、などを描きながら、物語はきっちりと終わります。 同じく家族もののホラー『ペットセマタリー』(これも二度と読めない)なんかにくらべると、最後が「かがやいて」いるのてホッとします。
December 27, 2007
コメント(2)
-
『タマスターラー』――タニス・リーの語るインド夜話
先日の日記でちらっと書きました、インド神話を下敷きにした物語。 タニス・リーというと、幻想的でお色気たっぷりな物語を、おとぎ話風にどこかさめた視点から語る、80年代「ファンタジイ界の女王」。 「平たい地球」シリーズ(『闇の公子』『死の王』『惑乱の公子』etc)が有名かと思いますが、この『タマスターラー』は、インドを舞台としていることと、彼女には珍しく?現代に近い時代をリアルに扱っていることが、異色です。 だから、異世界ファンタジーに縁のない読者や、他のタニス・リー作品はちょっと濃すぎていただけないという読者でも、楽しめるかもしれません。 第一夜から第七夜まで、七つのお話が語られますが、少し過去(植民地時代のインド)の話もあれば、近未来(それも、少し過去の人々が思い描いたノスタルジックな近未来)の話もあります。イギリス人から見たインドが描かれるかと思うと、インドの人々だけが出てくる寓話のような話が語られ、また、レイ・ブラッドベリの描く未来の火星のように哲学めいたSFもあります。 そしてここでも、熱くて濃い大気、土やジャングルのにおい、ナーガ(龍)やマングース、虎、蒼い首を持つ鳥などの、あやしい魅力を持つ獣、「輪廻(サンサーラ)」「業(カルマ)」「定め(ダルマ)」などの神秘的で象徴的な言葉――それらがスパイスのように物語にインドの香りを効かせています。
November 26, 2007
コメント(2)
全112件 (112件中 1-50件目)