PR
X
フリーページ
九星暦

平成四年度 九星カレンダー

令和4年10月~令和6年1月 九星暦 (暦日大鑑と照合済み)

令和5年神社暦ほか 皇紀2683年 西暦2023年

令和6(西暦2024)年九星暦 (『暦日大鑑』と照合済み)

令和6 (皇紀2684、西暦2024) 年年報文面 甲辰 三碧木星 暦
64卦表
姓名科学ポータル

画数検索

数意解説

人生グラフ検索

人生グラフ No.1 ~ No.80

人生グラフ No.81 ~ No.160

人生グラフ No.161 ~ No.240

人生グラフ No.241 ~ No.320

人生グラフ No.321 ~ No.400

人生グラフ No.401 ~ No.480

人生グラフ No.481 ~ No.560

人生グラフ No.561 ~ No.640
最も効果をあらわす画数一覧 23分野

1 政治家として成功する画数

2 実業家として大成する画数

3 外交官として国際舞台で活躍する画数

4 大学教授や研究者として名を成す画数

5 科学者・技術者として新開発に成功する画数

6 医者に多い画数

7 弁護士に多い画数

8 商売人(小売業)として販路を広げ繁栄を招く画数

9 水商売で成功する画数

10 作家や評論家など文筆業で成功する画数

11 芸術家として名を成す画数

12 デザイナーとして時代を先取りしていく画数

13 スポーツマンとして成功する画数

14 芸能界でスターになれる画数

15 男性顔負けの女傑、才女として活躍する画数

16 良妻賢母として平和な家庭を築く画数

17 チャーミングな美人に多い画数

18 相手に見染められ、玉の輿に乗る画数

19 結婚入籍の改名後、幸福な新生活を送れる画数

20 マスコミの社会で成功する画数

21 アイディアマンに多い画数

22 手芸職人として特殊な才能を発揮する画数

23 経済的に恵まれた一生を送れる画数
結婚姓名占術 数表 目次

結婚姓名占術 数表① 1字名 内面性格と情熱運

結婚姓名占術 数表② 2字名 内面性格と情熱運

3字名(内面性格のタイプと情熱運)or対人性格のタイプと対人運

1字姓(結婚好適期)

2字姓(結婚好適期)

3字姓(結婚好適期)

7つの相性タイプの読み方

相性分析 ブランク表 婚前・婚後
続・日本人が知ってはならない歴史

序章 注1 エージェント(agent)

序章 注2 海軍陸戦隊は五千人余の兵力……

第一章 注1 金日生

第一章 注2 修身齋家治国平天下

第二章 注 つまり伊藤博文は上から撃たれたのです。

第六章 (注)帷蝙(いあく)上奏権

第八章 (注1)一九二八(昭和三)年六月の張作揉の爆殺

第八章 注(2)……中からそして上から知力と権力で 革命はやるのだ………

第八章 資料1 『諸君』平成十六年一月号・二三七頁 一九五一年証言
●UT版日本国紀 目次● 20220820改 小笠原諸島を日本領に

日本国紀 目次 発表順
動画の文字起こし 品質は良くありません

武田邦彦「ホント話」114・20220729「海洋酸性化「パン食は胃腸に良くない
小山内彰先生の四柱推命の活用法より

五行(十干)について

「四柱推命学入門」小山内彰著(希林館) 目次

小山内彰先生の四柱八字計算サイト
シオンの議定書 目次

シオンの議定書の読み方をガイドするパンフレット
高神覚昇「般若心経講義」(角川ソフィア文庫)目次
100年数秘の本 目次
『「リサイクル」汚染列島』武田邦彦著 青春出版社 インデックス
『「正しい」とは何か?』武田邦彦著 小学館 目次
『姓名(なまえ)』牧正人史著 青春出版社 目次
64卦
目次 『「気候変動・脱炭素」14のウソ』渡辺正著(丸善出版株式会社)
著作権の切れた書籍の書庫 焚書図書館 R050823更新

GHQ焚書図書『皇室と日本精神』
竹田恒泰の幕末・孝明天皇論 再生リストV0.5

教育勅語
便利機能メモ

エクセルデータ入力規則1

パワポの技1

エクセルで棒グラフを作る

エクセルで 様 をつける方法

☑をセルに入れる

ワードで一ページに収めたい

ワードのフォント変更に伴う行間設定の変更
聞いていたい、踊りたい

タップ BeatIt

Clean Bandit - Stronger
コメント新着
サイド自由欄
カテゴリ: カテゴリ未分類
こうした姿勢は、自然に対しても貰かれていました。
アイヌ人は、川に上ってくるサケや川魚を食料にしていました。川に生かされているということを自覚していて、川を非常に大切にしました。具体的に言うと、アイヌ人は、川の上流に村を作らなかったのです。上流に進出していけば、住む地域は広がりますが、川の恵みは枯渇していきます。それがわかっていた。だからある一定の地域にしか住もうとしませんでした。
自然と人間の活動を調和させていたのです。
住む地域も食料も限られるわけですから、ある一定数以上、人口は増加しません。増加しないから、自然環境がこれ以上、損なわれることがないのです。上手に、自然と自分たちの生活のバランスを取っていたというわけです。狩りの仕方もそうでした。アイヌの人々は、狩りに行くときに占いをするのです。今日、狩りに行ったほうがいいかどうか占うのです。で、「今日は行っても獲物が捕れない」という宣託が出ると、狩りを休みました。
これはしかし、非常に非効率的です。毎日、狩りに行ったほうが、獲物は多いに決まっているのですから。どこで狩りをしたらいいか占うならまだしも、行くか行かないかを占うのは、現代人から見るとナンセンスです。
アイヌ人の「正しさ」に照らし合わせれば、これが正解でした。占いをすることで獲物の絶対量が減るということは、自分たちの食料になる獲物の量が減りすぎることがない、ということです。占いは、狩りに行く頻度を下げるために行なわれていたのです。力の強い人間という種が思うように狩りをしますと、動物がいなくなってしまうわけですね。
例えば、西洋人が北アメリカに入植した当時、アメリカの空には何十億羽というリョコウバトが飛んでいました。鳥類史上もっとも多くの数がいたとも言われている鳥です。なにせ数が多いものですから、鉄砲で撃てばすぐに取れた。簡単に食料を確保できたのです。
ところがあるときふと気づくと、空にはたった一羽のリョコウバトも、飛んではいませんでした。すべてを撃ち殺してしまったのです。入植が始まってから約300年後の1914年、動物園で飼育されていた一羽が死に、アイヌ人は、こうしたことが起こりうることを知っていました。狩り(生活)を永続的に続けるためには、狩りに行く日数を制限しなければなりません。それが占いだったのです。
ついにリョコウバトは絶滅してしまったのです。
これは草原のライオンなどもそうです。テレビでライオンの様子を見ると、集団でごろごろしているようにしか見えません。でもそれでいいのです。毎日全力で狩りをしていたら、自分たちの食料である草食動物がいなくなってしまいますから。必要な分だけ狩ったら、あとは寝て過ごす。それが自分たちを生きながらえる方法だと、ライオンたちはわかっているのですね。
アイヌという民族は、こう考えると、非常に判断力が高く、全体のバランスを考えることができる能力を持っていると言えます。平和を好み、穏やか。生活の知恵もたくさん持っている。
現代人のわれわれから見ても、アイヌの生き方は「正しい」と映ります。
しかし、いくら正しい人でも、力がなければ、生き残っていくことはできないのも世の常です。それはアイヌはじめ、いろいろな民族の歴史が証明しています。
倭人との戦いでは、和睦交渉の場で酒宴がもうけられ、酔ったところで斬り殺されるということもありました。こうしてアイヌの長――戦士たちは、常に悲惨な最期を遂げるわけです。
それはアイヌに暴力と邪悪さがなかったということですね。「正しさ」は、一方で力などの後ろ盾がなければ貫くことができないという場合もあるのです。その段階をまだ現代人は、抜け出せていない。そのことをアイヌの歴史は、私たちに教えてくれているのです。
私はアイヌの人たちの生き方に多くのことを学びました。学び始めた頃は、衝撃さえ受けました。通常、「戦争は人間にとって避けられないものだ」、あるいは「剣を取って自由を守れ」という言葉には私たちは正義を感じます。しかしその正義は、アイヌと比較してみると、「私たちが歴史で学ぶ血腥い時代と地域だけ」のこととわかったのです。
高等学校の歴史の時間を思い出してください。
日本では、源平の戦い、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、関ヶ原の戦い、日露戦争……と教わることは戦争のことばかりでした。もちろん歴史的には戦争によって政権が代わったりしますから、どうしても戦争が主になってしまうのでしょうが、それはつまり国の上層「政権」、部だけのことです。
平清盛が病死して平家が滅亡し、源氏の鎌倉幕府ができても、庶民の生活にほとんど変化はありませんでした。変化と言えば、荘園を管理している貴族が武家に代わったぐらいで、庶民に比べればデラックスな家に住み、威張っている人が、変わらず上にいるだけのことです。
1192年(最近では1185年ということに変更されてます) に鎌倉幕府が開かれたということをイヤというほど習い、年号を覚えさせられましたが、私は「歴史学上の錯覚」か「権威主義」だと思っています。
もっと大切なのは「およそ1200年頃に武家政治になったが、庶民の生活や農業で生計を立てることにはなんの影響もなかった」ということだと思います。
そう考えると、いったい、日本の戦争というのは何だったのでしょうか?
外国では戦争が起こると、負けた国の人たちは奴隷として戦勝国に連れていかれ、奴隷になって生産を担当しました。ギリシャでも人口の2%が支配層で、98%が奴隷だったとも言われて
います。しかし、日本は四面を海に囲まれ、天皇陛下をいただくほぼ単一民族と言ってよい状態だったので、奴隷は存在しませんでした。戦争をするのは単なる武士同士のメンツみたいなもので、平家も源氏も、足利(室町幕府)、徳川(江戸幕府) でもまったく同じなのです。
つまり、戦争はやむを得ない、もしくは正義であると言うのは権力争いをしている上層部だけであり、庶民には無関係とも考えられます。
戦争の正義、領土の正義の結論を出す前に、もう少し視野を広げてみましょう。
『「正しい」とは何か?』武田邦彦著 小学館より
アイヌ人は、川に上ってくるサケや川魚を食料にしていました。川に生かされているということを自覚していて、川を非常に大切にしました。具体的に言うと、アイヌ人は、川の上流に村を作らなかったのです。上流に進出していけば、住む地域は広がりますが、川の恵みは枯渇していきます。それがわかっていた。だからある一定の地域にしか住もうとしませんでした。
自然と人間の活動を調和させていたのです。
住む地域も食料も限られるわけですから、ある一定数以上、人口は増加しません。増加しないから、自然環境がこれ以上、損なわれることがないのです。上手に、自然と自分たちの生活のバランスを取っていたというわけです。狩りの仕方もそうでした。アイヌの人々は、狩りに行くときに占いをするのです。今日、狩りに行ったほうがいいかどうか占うのです。で、「今日は行っても獲物が捕れない」という宣託が出ると、狩りを休みました。
これはしかし、非常に非効率的です。毎日、狩りに行ったほうが、獲物は多いに決まっているのですから。どこで狩りをしたらいいか占うならまだしも、行くか行かないかを占うのは、現代人から見るとナンセンスです。
アイヌ人の「正しさ」に照らし合わせれば、これが正解でした。占いをすることで獲物の絶対量が減るということは、自分たちの食料になる獲物の量が減りすぎることがない、ということです。占いは、狩りに行く頻度を下げるために行なわれていたのです。力の強い人間という種が思うように狩りをしますと、動物がいなくなってしまうわけですね。
例えば、西洋人が北アメリカに入植した当時、アメリカの空には何十億羽というリョコウバトが飛んでいました。鳥類史上もっとも多くの数がいたとも言われている鳥です。なにせ数が多いものですから、鉄砲で撃てばすぐに取れた。簡単に食料を確保できたのです。
ところがあるときふと気づくと、空にはたった一羽のリョコウバトも、飛んではいませんでした。すべてを撃ち殺してしまったのです。入植が始まってから約300年後の1914年、動物園で飼育されていた一羽が死に、アイヌ人は、こうしたことが起こりうることを知っていました。狩り(生活)を永続的に続けるためには、狩りに行く日数を制限しなければなりません。それが占いだったのです。
ついにリョコウバトは絶滅してしまったのです。
これは草原のライオンなどもそうです。テレビでライオンの様子を見ると、集団でごろごろしているようにしか見えません。でもそれでいいのです。毎日全力で狩りをしていたら、自分たちの食料である草食動物がいなくなってしまいますから。必要な分だけ狩ったら、あとは寝て過ごす。それが自分たちを生きながらえる方法だと、ライオンたちはわかっているのですね。
アイヌという民族は、こう考えると、非常に判断力が高く、全体のバランスを考えることができる能力を持っていると言えます。平和を好み、穏やか。生活の知恵もたくさん持っている。
現代人のわれわれから見ても、アイヌの生き方は「正しい」と映ります。
しかし、いくら正しい人でも、力がなければ、生き残っていくことはできないのも世の常です。それはアイヌはじめ、いろいろな民族の歴史が証明しています。
倭人との戦いでは、和睦交渉の場で酒宴がもうけられ、酔ったところで斬り殺されるということもありました。こうしてアイヌの長――戦士たちは、常に悲惨な最期を遂げるわけです。
それはアイヌに暴力と邪悪さがなかったということですね。「正しさ」は、一方で力などの後ろ盾がなければ貫くことができないという場合もあるのです。その段階をまだ現代人は、抜け出せていない。そのことをアイヌの歴史は、私たちに教えてくれているのです。
私はアイヌの人たちの生き方に多くのことを学びました。学び始めた頃は、衝撃さえ受けました。通常、「戦争は人間にとって避けられないものだ」、あるいは「剣を取って自由を守れ」という言葉には私たちは正義を感じます。しかしその正義は、アイヌと比較してみると、「私たちが歴史で学ぶ血腥い時代と地域だけ」のこととわかったのです。
高等学校の歴史の時間を思い出してください。
日本では、源平の戦い、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、関ヶ原の戦い、日露戦争……と教わることは戦争のことばかりでした。もちろん歴史的には戦争によって政権が代わったりしますから、どうしても戦争が主になってしまうのでしょうが、それはつまり国の上層「政権」、部だけのことです。
平清盛が病死して平家が滅亡し、源氏の鎌倉幕府ができても、庶民の生活にほとんど変化はありませんでした。変化と言えば、荘園を管理している貴族が武家に代わったぐらいで、庶民に比べればデラックスな家に住み、威張っている人が、変わらず上にいるだけのことです。
1192年(最近では1185年ということに変更されてます) に鎌倉幕府が開かれたということをイヤというほど習い、年号を覚えさせられましたが、私は「歴史学上の錯覚」か「権威主義」だと思っています。
もっと大切なのは「およそ1200年頃に武家政治になったが、庶民の生活や農業で生計を立てることにはなんの影響もなかった」ということだと思います。
そう考えると、いったい、日本の戦争というのは何だったのでしょうか?
外国では戦争が起こると、負けた国の人たちは奴隷として戦勝国に連れていかれ、奴隷になって生産を担当しました。ギリシャでも人口の2%が支配層で、98%が奴隷だったとも言われて
います。しかし、日本は四面を海に囲まれ、天皇陛下をいただくほぼ単一民族と言ってよい状態だったので、奴隷は存在しませんでした。戦争をするのは単なる武士同士のメンツみたいなもので、平家も源氏も、足利(室町幕府)、徳川(江戸幕府) でもまったく同じなのです。
つまり、戦争はやむを得ない、もしくは正義であると言うのは権力争いをしている上層部だけであり、庶民には無関係とも考えられます。
戦争の正義、領土の正義の結論を出す前に、もう少し視野を広げてみましょう。
『「正しい」とは何か?』武田邦彦著 小学館より
「正しい」とは何か? 武田教授の眠れない講義【電子書籍】[ 武田邦彦 ]
価格:858円
(2022/8/6時点)
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.


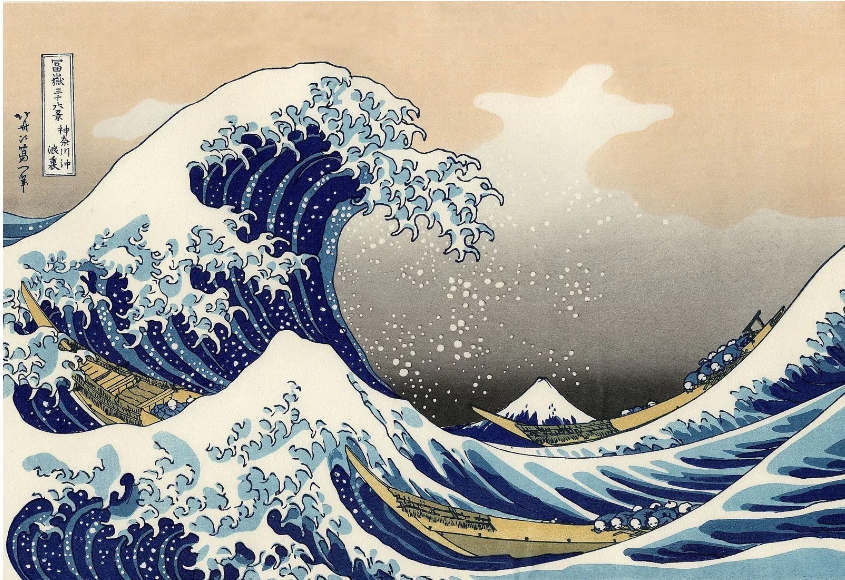

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/24abaf01.7511450e.24abaf02.41158075/?me_id=1319013&item_id=10000434&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_gold%2Fkoreshika-oisizu%2Fcabinet%2Fchikusen%2Fkuro1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1780d17d.c9cb47b0.1780d17e.825e3bdd/?me_id=1278256&item_id=11560678&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F1642%2F2000000131642.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)







