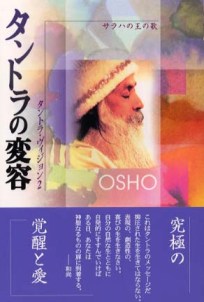
「タントラの変容」
タントラ・ヴィジョン2 サラハ王の歌 Osho 2000/12 市民出版社 原書1979 原講話1977/5
「タントラ・ヴィジョン1」
続刊。上下巻2冊、1と2で出版社が変わり翻訳者も変わった。だが、その差異は、Oshoの流れにはあまり影響はない。むしろ多様性に彩りを添えている。
タントラは異なる洞察を与える。革命ではなく、反逆だ。反逆は個人的なものだ。ひとりきりでも反逆はできる。そのためにに仲間を組織する必要はない。ひとりでも反逆はできる。あなただけで。それは社会に対する闘いではない。
覚えておきなさい。それはただ、社会を超えて行く。反社会的なものではなく、非社交的なものだ。社会とはまったく関係ない。タントラは隷属に抗うものではなく、自由に従う---在るという自由に。
p15
「超シャンバラ」
などのチャネリングものには、いくばくかの聞くべき価値があるが、最後は彼らの体系や価値観を押し売りしてくる。
タントラ曰く、用心しなさい---耽溺に用心しなさい。放棄に用心しなさい。どちらにも用心しなさい。どちらも罠だ。どちらもマインドの罠にかかることだ。
それなら、その方法はどこにあるのだろう? タントラ曰く、気づきがその方法だ。耽溺は機械的だ。抑圧は機械的だ。どちらも機械的だ。機械的なものごとから逃れる唯一の方法は、気づいていること、油断なく覚めていることだ。ヒマラヤに行ってはならない。ヒマラヤの沈黙を内側にもたらしなさい。逃避してはならない。もっと気づいていなさい。恐れずに深くものごとを見つめてごらん---恐れずに。恐れずに深く物事を見つめてごらん。いわゆる宗教的な人々が教え続けていることに耳を傾けてはならない。彼らは恐がらせる。セックスを見つめることを、あなたに許さない。死を見つめることを許さない。彼らはあなたの恐れを利用し、途方もなく搾取してきた。
p108
700年前のチベットでOshoの前世は、タントリックなコミューンを率いていた。当ブログでも
みてきた
ように、1203年にインド仏教=ヴィクラマシラー大僧院がイスラーム軍団に襲撃され、仏教の正統はヒマラヤのかなたの高原に受け継がれた。そして、チベットタントラの野生的な花々は、ツォンカパ(1357~1419)の登場によって「剪定」されてしまった。
ブッタ、サラハ、シャーキャシュリーパドラ、の系譜で伝えられ、チベット高地に根付いたタントラ思想が、まだ、ツォンカパによって体系化、組織化されるまえの生々しいオリジナリティを携えていた時代にOshoは生きていた。あるいは、仏教の流れというよりは、チベットに以前より存在していた土着的なマニ教の流れにいながら、チベット・マニ教とインド・タントラが合流するダイナミズムの中に生息していた。
700年間、転生してこなかったことを考えると、Oshoの魂は、その後のチベット・タントラの流れを必ずしも肯定ばかりはしていなかったのではないだろうか 。
「彼らだけが、ヒマラヤの偉大な高み、純粋さを知っている」「チベットは、世界中で宗教にもっとも近づいた唯一の国だ」
といいつつ、「ヒマラヤに行ってはならない」ともいう。この現代にチベットならぬインドに最後の転生をしてきたOshoの真意は「ヒマラヤの沈黙を内側にもたらしなさい。逃避してはならない。もっと気づいていなさい。恐れずに深くものごとを見つめてごらん---恐れずに。恐れずに深く物事を見つめてごらん。」というところにあるのだろう。まさにMeditation in the Marketplaceということになる。
Oshoは
「チベット人は眠れる脳の様々な力を知り、体験した---だが霊的な修行に関するかぎり、チベットは偉大な国になれなかった。驚くことに、チベットは多くのことを成し遂げたにもかかわらず、ひとりの覚者(ブッタ)も生み出せなかった。チベットは様々な力を開発し、多くの珍しい事柄を知り得たが、それをつまらないことに使ってしまった。」
とも言っている。この「チベットは一人のブッタも生み出せなかった」という言葉を、チベット宗教関係者は、どう読むだろうか。たしかに仏教の命脈を正統的に継続はしてきた。しかし、あらたなるブッタを生み出すことは出来なかった、とOshoは言っている。もちろん、Oshoは仏教徒になることを説いてはいない。ブッタになることを説いている。だから「運動」として
アートベンガル
や
佐々井秀嶺
の新仏教徒運動は、同じインド国内の同時代に起こったことだけれども、Oshoは特に過大に評価したことはなかった。
ちっぽけな知識を信頼しないことだ。自分が辿り着いたとは思わないように。少し覚えては、人々はときおり非常に満足してしまう・・・そうして、そこで彼らは止めてしまう。進むのを止めてしまう。それは壮大な旅だ。終わりのない旅だ。覚えるほど、覚えられる。覚えれば覚えるほど、覚えることは、ますますあると意識する。知れば知るほど、その神秘は強烈になる。知れば知るほど、自分が知っているという感覚がなくなる。知ることで新たな扉が開く。知ることで新たな神秘が明かされる。
だから、ちっぽけな知識で満足してはならない。神が彼自身を明かすまで、けっして甘んじてはならない。霊的な、大いなる不満をあらしめなさい。
この神聖な不満を自らのうちに持つ、充分な幸運たちだけが---神をおいて他をみたされない者たち---彼らだけが辿り着く。他の誰でもない。
p145
う~~む、ここまで聞いちゃうと、ますます旅をしたくなるなぁ。いつまでも続くここへの旅。
二人の恋人たちは、寺院の二本の柱のようだ。それこそが、カリール・ジブランの言うところだ。ひとつの屋根を支えているが離れている。くっついていない。寺院の二本の柱が近くなりすぎれば寺院は倒れてしまう。屋根は支えられない。チャン・ツー・オーディトリアムの柱を見なさい。離れて立っている---ひとつの屋根を支えている。恋人たちはそうあるべきだ---離れて、個として、それでも共有のものを支えている。
p159
この部分は、レクチャーが終わった数ヶ月後に英文のニューズレターになった。1977年当時プーナに行って、この部分を読んでとても感動した記憶がある。
あなたがすべてになるとき、すべてとひとつになるとき、この宇宙と同じくらい広大であるとき、すべてを包含するとき、星々はあなたの内側で動き始め、この世のものがあなたの中で生れては消えるとき、あなたが広大無辺の広がりを持ちとき、働きかける(ワーク)は終わる。
あなたは家に帰り着いている。これがタントラのゴールだ。
p240
このブログでもいろいろタントラについて読んできた。だけどOshoが語るタントラがいちばん美しい。
タントラの洞察は直接、神に、真理に、存在するものに向かう。タントラに仲介者はいない。中間商人(ブローカー)はいない。タントラに司祭はいない。タントラ曰く、聖職者が介入する瞬間、主教が腐敗する。宗教を腐敗させるのは、悪魔ではなく聖職者だ。聖職者は悪魔に仕える。
神は直接にしか向かえない。媒介はない。他人を介することはできない。神は直(じか)に接するものだからだ。神は今ここにいて、すでにあなたを取り巻いている。内側に外側に、神だけがいる。
p286
ここは、もうタントラの世界なのか、Oshoの世界なのかわからない。すべてのOshoの道はここに辿り着く。
セックスのオーガズムは、タントラの道では途方もなく重要になった。それはあなたに究極の真理を与えはしないが、少なくともマインドを超えて、かいま見る機会を与える。それは小さな窓を与えてくれる---ほんの束の間。長くはとどまれないが、それでもあなたにとって、それは真理との接触を持つ唯一の可能性だ。さもないと、あなたは常に自分の思考に取り囲まれて、その思考は何も明白にしない。釈明はすべてたわごとにすぎない。
p377
タントラは、あなたに両方の世界を与える。タントラはいずれか一方という見方ではなく、あれもこれも両方という見方だ。タントラはとても包括的だ。どの宗教もその意味においては貧しく見える。なぜなら、それは世間を取り払って不必要な選択を強いるからだ。それらは言う。世間か神かどちらかを選べと。宗教は、神を世間の向こうに回す。タントラは唯一の全一の宗教だ---ただひとつの全一な宗教だ。これほど全一な洞察を持った宗教は、地上に生れたことがなかった。
p402
タントラは、物事の真にあるがままに対する卓越した洞察だ。けれども最後に覚えておきなさい。それは哲学ではない。洞察だ。それに入って生きたければ、マインドからではなく、マインドぬきで向かわなくてはならないだろう。
無心(ノーマインド)がタントラの扉だ。無思考がタントラの道だ。体験こそがタントラの道だ。
p418
サラハは、ブッタの200年後に起こったことをみたはずだ。誤った解釈、そして人々はほとんどセックスにとり憑かれていた。仏教僧も尼僧の妄執ゆえに、タントラは反逆として生れた---仏教への反逆であって、ブッダへの反逆ではない。その反逆をもって、サラハはブッダの魂を取り戻した。そうだ、人はセックスを超えなくてはならないが、その超越からは理解が起こる。
タントラは理解を信じる。物事を全一に理解しなさい。すると、その魔手から自由になる。適切に理解されない物事はのしかかったままだ。
だからあなたは正しい。あなたは尋ねている。「どうしてタントラは仏教から成長したのでしょう? 私の知るかぎりでは、セックスは瞑想の障害という感じがします」。まさにその通り、そのためだ。タントラは仏教への反逆であり、ブッダに従うものだ。それは追従者に逆らっても、マスターに逆らうものではない。追従者は文字を持ち運んでいて、サラハは魂を取り戻した。
サラハはブッタが在ったのと同じ、光明の化身だ。サラハはブッダだ。
p435
-
GATI チベット文化圏 2007.05.13
-
西蔵回廊 カイラス巡礼 2007.05.13
-
チベットの民話 2007.05.12
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




