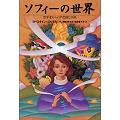
「ソフィーの世界」
哲学者からの不思議な手紙 <2>
ヨースタイン・ゴルデル /池田香代子
あ
ちこちに読みかけの本を置いたまま、興味をばらばらに拡散したままになっているようでもあり、雑然とした中でもなにか方向性がでてきたようでもあり、当ブログでの1024冊目に向けて、大小さまざまなエントリーが続いている。なにはともあれ、読みかけになっている本は、その前に駆け込みで読了しておきたい。
「ソフィーの世界」は、読者対象を14歳の少女に仮定していることもあり、文体や運びとしては読みやすいのだが、そのテーマは、西洋哲学史なので、そのテーマの難渋さとともに範囲も広いので、私にははっきり言って一辺に読み込めるような内容ではない。
それでも、すこしづつ読み進めている。古代ギリシャにおけるソクラテス、そしてその以前と以後の哲学者たちの動き。そして、キリスト教の出現。プラトンとアリストテレス。そして、アウグスティヌスとトマス・アクィナス。
ソフィーは小さくうなずいた。僧服のアルベルトは話を続けた。
「中世まっさかりの時代のもっとも偉大な、もっとも重要な哲学者は、1225年に生まれて1274年に死んだトマス・アクィナスだ。ローマとナポリのあいだのアクィノという小さな町の出身なのでそう呼ばれるんだが、ぱりの大学で教えていたこともある。ぼくはさっきトマス・アクィナスのことを哲学者と言ったけど、それと同じくらい、トマス・アクィナスは神学者だった。その頃は哲学と神学ははっきりと分かれていなかった。つまりだね、トマス・アクィナスはアリストテレスを独自のやり方で『キリスト教徒にしてしまった』んだな。中世の初めにアウグスティヌスがプラトンをキリスト教徒にしたように。」
Oshoも
「私の愛した本」
でアウグスティヌスには触れている。しかし、この本のリストを見る限り、Oshoは
トマス・アクィナス
の本「神学大全」に触れているところはどうやらないようだ。「盛期スコラ学の代表的神学者であり、トマスが大成したスコラ学は長きに渡ってカトリック教会の公式神学となった」とされる。Oshoはこの辺から、バチカンについてはよく思っていないようだ。もっともプラトンやアリストテレスについても点はめちゃくちゃ辛い。
「でも、ちょっとおかしくない? この哲学者たちをキリスト教徒にしてしまうなんて、だって、この人たちはキリストよりも何百年も前に生きていたんでしょう?」
「それはもっともだ。つまり、この二人の偉大な哲学者たちを「キリスト教徒」にしてしまう」っていうのは、二人がとことん読み込まれ、理解されたために、もうキリスト教の教義をおびやかすものと見なさなくてもいいと思われたってことだ。トマス・アクィナスは、『雄牛の角を素手でとらえた』と言われているよ」
「哲学が闘牛とどんな関係があるの? ちっともわからない」
「すごくむずかしいことをやってのけたってことだよ。トマス・アクィナスはアリストテレスの哲学をキリスト教を合体させようとした一人だ。信仰と知識を統合させようとした、と言ってもいい。トマス・アクィナスはそれをなしとげた。それは、彼がアリストテレスの哲学に踏み込んで、そのことば質(じち)をとらえたからなんだ」
p233
ここに来てふと思う。「真理」の探究には、統合化の道と、オールリセットの道がありそうだな、ということ。どちらかというとソクラテスやキリストはオールリセットの道だろうか。それに対するトマス・アクィナスは統合派だ。この動きを拡大解釈すると、ケン・ウィルバー(最新刊 「インテグラル・スピリチュアリティ
」がでたようだ)は、その名の通り、統合派だろうが、かたや「ニューエイジ」の旗手とも評価される フィンドホーン
のひとびとは、どちらかといえばオールリセット派に分類されるだろうか。
ちょうどこの本も スピノザ
のところまで読み込んできたところだが、思えばスピノザも、どちらかと言えばオールリセット派だろう。キリスト教、とくにトマス・アクィナスに見られるキリスト教は、この時点では統合派の最たるものであろうが、時代は前後するが、ボーディ・ダルマは、オールリセット派に分類してもいいだろう。
はて、それでは、Oshoは統合派か、オールリセット派か、という新たな疑問が湧いてくる。Oshoが特段のマスターを持たずにエンライトメントしたとするなら、それはオールリセット派と見なしてもいいだろうが、その自らの力で創ったプラットホームに、地球上のすべて(とは言えずとも多岐にわたる)の精神的探求のメソッドを統合した(かにみえる)。そういった意味では、統合派とも言える。
はてさて。
-
悟りへの階梯 2008.10.27
-
ツォンカパ チベットの密教ヨーガ 2008.10.26
-
聖ツォンカパ伝<2> 2008.10.25
PR
Freepage List
Category
目次
(6)22番目のカテゴリー
(49)バック・ヤード
(108)osho@spiritual.earth
(108)mandala-integral
(108)agarta-david
(108)スピノザ
(108)環境心理学
(108)アンソロポロジー
(108)スピリット・オブ・エクスタシー
(108)マーケットプレイス
(108)OSHOmmp/gnu/agarta0.0.2
(108)チェロキー
(108)シンギュラリタリアン
(108)レムリア
(108)2nd ライフ
(108)ブッダ達の心理学1.0
(108)マルチチュード
(108)シンギュラリティ
(108)アガルタ
(108)ネットワーク社会と未来
(108)地球人スピリット
(108)ブログ・ジャーナリズム
(108)Comments




