2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年08月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

2009 トンガ ザトウクジラ ホエールスイム 1日目 再会
海は濁りがちで、天候も低い雲に覆われ続けた初日だったが、幸い母子のクジラに遭遇。何とか撮影も出来た。しかし、一点気になることがあった。特徴的な、母クジラの尾びれのことだ。両端が大きく欠落している母クジラ尾びれ、昨年遭遇した母クジラのものと(記憶の中では)そっくりだったのだ。しかし、同じ母クジラだったとしても、子クジラはその大きさからも、1年間まったく成長していないことになる。このことは、どう説明すればよいのか?帰港後夕食時に、別のボートのガイドをしていたプロカメラマンのトニーウー氏から、昨年撮影した写真と比較して、今日の母クジラは、尾びれの特徴・模様が一致するので同じ個体だが、子クジラは別だったとの話があった。ザトウクジラの繁殖・出産・子育ての海域は同じで、通常母クジラは2-3年周期で出産するのだが、おそらく昨年出産した子どもは、この海域で何らかの理由で死んでしまい、その後、新たに繁殖活動を行った結果が今年の子どもなのだろう。子どもが亡くなったのは、病気や鮫等に襲われたためか、ヒートランに巻き込まれたためなど種々考えられる。バンドウイルカやネズミイルカ、コビトイルカの観察事例では、新たな繁殖を行いがために、子イルカを殺すオスイルカの存在が確認されている。育児中の母イルカは新たな繁殖よりも育児に熱心であるため、オスイルカにとっては子イルカは邪魔な存在でしかないのだ。クジラとイルカは同じ鯨類。ザトウクジラにも同様なことがあってもおかしくない。いづれにせよ、昨年の母子・今年の母子にどのような出来事があったのかは推量の域を出ないのだが、2年続けて新たな出産を行ったクジラの確認は非常に稀なことになる。そしてトンガのババウ諸島という限定された海域であったにせよこの広い大海で2年続けて同じ母クジラとの再会ができたことに感慨深い思いをした。できることなら、今年は無事に子育てをまっとうしてほしいと強く願った。帰宅後、私も昨年撮影した写真との比較を行った。やはり、母クジラはひれの形・傷の付き方など一致したが、子クジラは明らかに別の個体だった。こちらは、今年撮影した母子。こちらは、昨年撮影した母子。
2009/08/31
コメント(4)
-

2009 トンガ ザトウクジラ ホエールスイム 1日目 母子
トンガでのザトウクジラの水中撮影初日、天候はあいにくの曇天、それほど暗くはないが、低い雲が空一面を覆っている。朝食を摂っていると、突然の突風ともにバケツをひっくり返したような雨。2年前のいやな記憶がよみがえる。風が強いと時化るため、船を海に出すことができなくなり、一昨年は1日キャンセルとなったのだ。しかし、風上の空を見ると明るくなってきている。短いスコールで収まりそうだ。嵐は1時間足らずで遠ざかり、水中カメラマン越智隆治氏のガイドで他のゲスト2名と海に出る。ボートのスキッパーはノア、トンガのホエールウォッチング船のスキッパーでは第一人者であろうオンゴの息子さんだそうだ。船は西のリーフ方面に向かう。先週から風の強い状況の影響のためか、うねりと波が残っている。これでは外洋に出ることは厳しいだろう。越智さんが、2つのブロー(しおふき)を発見する。一つは小さい。どうやら母子のようだ。幸い、動きはゆっくりしている。タイミングを計って船を少し遠めに寄せ、静かに海に入る。残念ながら相当濁っている。これではたとえクジラが見えても撮影にはむかない状況だ。クジラがいるであろう方向を目指して飛沫を上げないようゆっくりと静かにフィンをあおる。(母子のクジラと泳ぐ場合、子クジラにストレスを与えないように、 フィンで飛沫を立てない。 急なアプローチを避け慎重に接近する。 潜水せずに水面上での観察にとどめる。 などのルールが決められている。)やがて、母クジラの白い胸鰭がおぼろげに見えてくる。大きい。でっぷりと太っているクジラだ。尾鰭が見える、なにやら見覚えのある特徴的な形をしている。 昨年観察した母クジラの尾鰭によく似ているのだが、通常ザトウクジラは2-3年周期で出産を行うため、昨年出産したであろう同じ母クジラの可能性はないはずなのだが・・・。クジラが母親の影から姿を見せた。やはり小さい。数日前に生まれたばかりの赤ちゃんクジラのようだ。大きな母親の頭ほどの大きさしかない。ゆっくりと、母子に向けてアプローチを行うが、少し母親が警戒しているのかしばらくすると移動してしまう。いったん船に戻り、越智さんから「こちらに慣れさせる為に、しばらくはもっと慎重にアプローチしてクジラを追いかけないようにしましょう。」との指示が出る。クジラの移動が収まったのを確認して再度エントリー、慎重に慎重にアプローチを行う。何度かこのようなことを繰り返しているうちに、ほとんどこちらを気にすることがなくなってきた。相変わらず濁りのある海況だったため満足いく撮影はなかなか出来なかったが、初日にしては上々のスタートとなった。
2009/08/29
コメント(4)
-

セボシウミタケハゼの卵保護
クジラはまだ現像してませんので、過去に撮った魚の写真を・・・。バリ島トランベンで撮影したセボシウミタケハゼです。トランベンでは写真のようにホヤに産み付けられた卵を保護するハゼを見かけることが多くあります。
2009/08/27
コメント(4)
-

帰ってきました。 2009 トンガ ザトウクジラ 水中撮影
日曜日深夜、トンガでのザトウクジラの水中撮影から帰宅しました。現地4日、往復の移動に5日と、いつもながらとんでもない行程でしたが、何とか水中撮影ができました。写真は、RAWデータからの現像作業をほとんど行っていないので、とりあえず1枚のみUPします。浅い砂地でうたた寝している?お母さんクジラと、寄り添う子クジラの「JAWS」君です。(「JAWS」君のことはまた後日)あいにく濁りがちな海でしたが、2頭の影が海底の砂に映るぐらいの晴天でした。
2009/08/25
コメント(4)
-

ザトウクジラ 水中写真
3年連続となる南太平洋トンガ王国でのザトウクジラの水中撮影に出発する。現地からの情報では、風が強く、芳しくない海況が続いているようだが、今年は、クジラたちとどんな出会いが待っているのか?写真は、以前HOMEに載せていた物。画像を入れ替えたためブログでは見れなくなっていたので再登場となった。
2009/08/15
コメント(4)
-

クロスズメダイ幼魚
ここ数回エビカニなど甲殻類が続きましたが、久々に魚の写真を。クロスズメダイの幼魚です。ごらんのように非常に美しい魚ですが、名前の通り成魚は黒一色であまり目立ちません。
2009/08/13
コメント(4)
-

ユキンコボウシガニ
前回はチャツボホヤの一種の中に住むエビをご紹介しましたが、今日は、チャツボホヤの一種を背負っているカニ、以前もブログに掲載したした通称「ユキンコボウシガニ」です。通常見られるユキンコは白い体色にオレンジ色の目の標準和名オガサワラカムリとのことですが、今日の写真のユキンコはちょっと違います。緑色の体色に白いゴルフボールのような目、「抹茶ユキンコ」なんて呼びたくなるようなカニですが、こちらのブログによるとシカクイソカムリという種のようです。うわ目づかいが、なんともいえません。超カワイイ!こちらはお食事中です。別のカメラで青抜きも撮ってみたんですが、なぜか書き込みエラーが発生したようで、この1枚しか救出できませんでした。
2009/08/12
コメント(4)
-

カイメンカクレエビの一種
ひき続きカイメンカクレエビの一種です。前回のネズミカイメン君とは姿形は同じような感じですが、こちらは鮮やかな黄色の体色で、住処も違います。どんなところに住んでいるかというと、このような大型のチャツボホヤの一種の中に暮らしています。腹部に卵を抱えていますね。卵からは眼が透けているのが見えます。こちらは、同じ個体を上から撮ったもの。背中には次の繁殖に備えて順番待ちの卵が、その手前の頭部には次の次の繁殖に備えた卵が見えます。このエビを紹介してくださったお店では、ダニみたいで可愛くないといわれてましたが、個人的にはかなりツボでした。
2009/08/10
コメント(0)
-

カイメンカクレエビの一種
カイメンカクレエビの一種です。名前はカイメンですが、イタボヤの中で見つかることが多いようです。ネズミみたいに見えなくもないですが、結構好きなエビです。
2009/08/08
コメント(4)
-

アカシマシラヒゲエビ
ウツボの口元をクリーニング中のアカシマシラヒゲエビです。ありがちな写真ですね。
2009/08/05
コメント(2)
-

カタボシニシキベニハゼ
海の日の連休に、沖縄本島で潜ってきました。この時期の本島は、比較的安定した海況の日が多く、ビーチエントリーでは海の穏やかなときでないと入りづらい、ホーシューなどのポイントに行けるチャンスが多いのです。ホーシューは、エントリー後リーフの棚をしばらく進むと、-50m過ぎまで垂直に落ちるドロップオフが特徴的なポイントです。昨年、ホーシューで潜ったときは、アカオビサンゴアマダイやアケボノハゼなどを撮影しましたが、今回の狙いは、深場のベニハゼ2種。ただこのポイントで見られるということ以外まったく情報もない中でギャンブル的なダイビングとなることを覚悟の上での潜水となりましたが、何とか1種は発見・撮影することができました。カタボシニシキベニハゼです。以前、バリで近似種と思われるハゼを撮ったことがありましたが、カタボシ自身は初見でした。やはりこの2種、やはり明確に尾びれの模様が異なりますね。
2009/08/03
コメント(6)
-

フタイロハナゴイ
フタイロハナゴイの幼魚。めっちゃ男前なやつでした。
2009/08/01
コメント(6)
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-
-

- 釣り好きの人集まれー
- GW その3 下巻には必須ですね 逆…
- (2025-05-03 22:19:54)
-
-
-
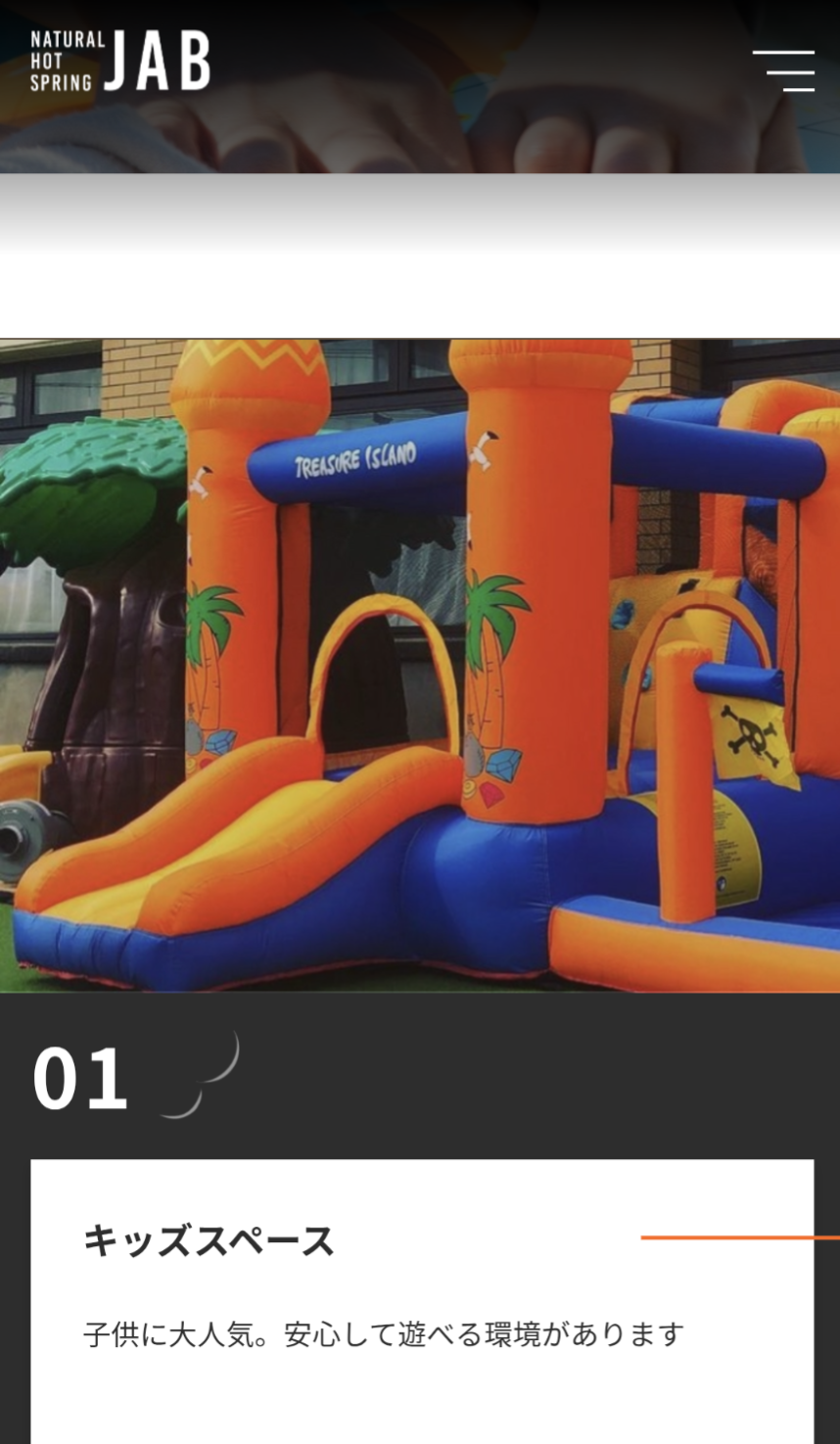
- 日帰り温泉あれこれ
- 【三重県♨️日帰り温泉】四日市駅から…
- (2025-05-01 12:26:33)
-
-
-

- バス釣りのホームページ
- アベンタクローラーバゼル 入荷
- (2025-05-02 06:13:17)
-







