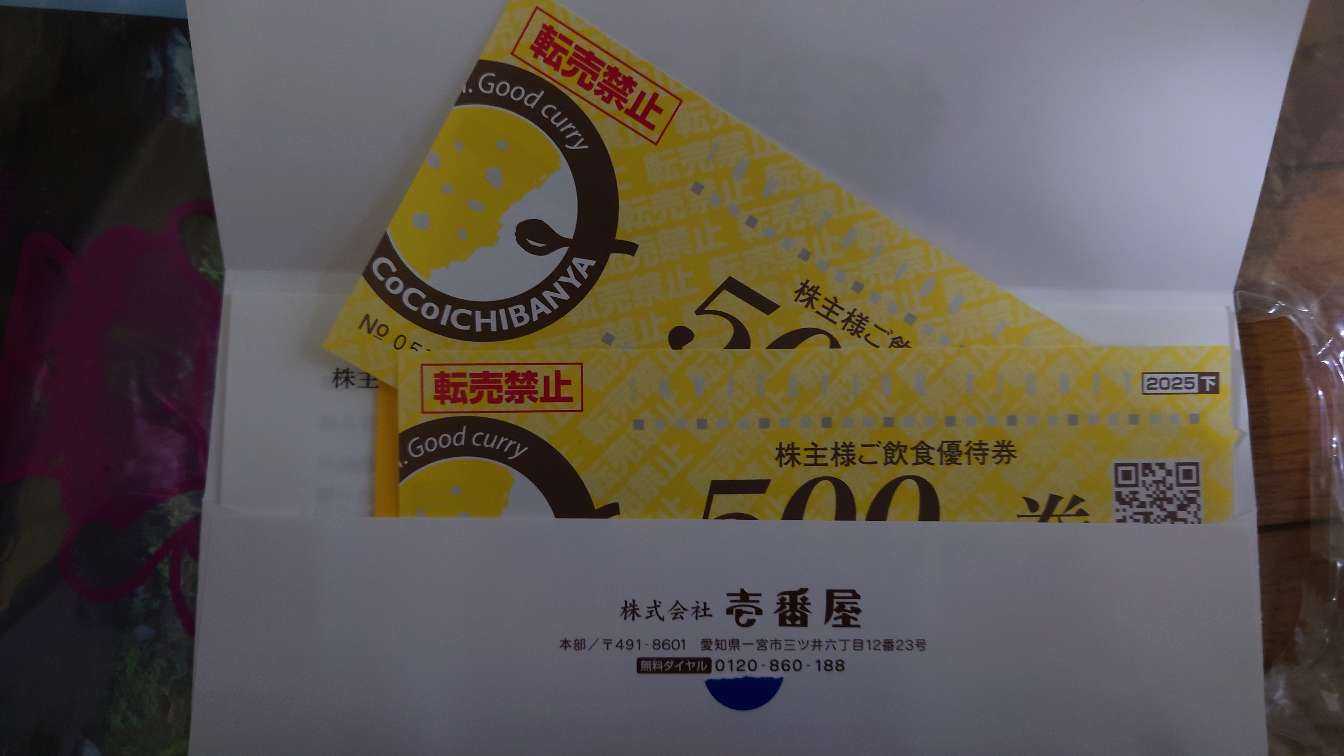全127件 (127件中 1-50件目)
-
働けなくなるぞ
会社の先輩にも出版社のビジネスについて話をしてみました。「へー、そんなことがあるんだ」先輩も驚いていました。「ね、すごいでしょ!このビジネス! そりゃどこの馬の骨かわからん新人の本を出したって売れるわけない。 そんなことするより、本を出したい小金も持ちを安定的に確保した方が ビジネスとしては安泰です。」「そりゃ、そうだな」「それもそうだけど、お前の本の内容も気になるな・・・」「え?この本の題って「日本の会社はこんなところ」だろ? しかも全部実話ってことは、うちの会社の恥部を世間に晒すってことだろ? 読めばわかるとなると、こりゃ問題になるぜ」「一応、誰かわからないように書いてますよ。A課長とかB所長とかにね。 しかし、面白い出来事というか、自分たちが受けた 理不尽なことを記録しながら書いたものだから 当人あるいは周りの人が読めばわかりますね。」「ほら、それがやばいんだよ。」 理不尽なことをいう人やおかしなことを言う人たちは 自分の無能さや無責任さは認めたくないもの。 それを指摘するようなものには敏感に反応するぞ。」「それもいいんじゃないですか。 周りから言われなきゃ気が付かないってことは それだけでも今の現状をよく表してるし おもしろいじゃないですか?」「だから、それが気に障るとここで働けなくなるぞ。」「そうなるとそれはネタになりますね!!」「だから、そうじゃなくって、 お前が本を出した、 しかも会社ネタで現実にあった管理者層のバカ話が書店に並ぶ。 そうなったら、ここで働けるわけないだろ。」「いやー、そうなったら、うれしいですね。 気持ちよく辞めますよ! だって自分の本が並んで、内容を評価されて、 会社の人たちもそれを読んでくれて となると、思い残すことはないですわ。ハハハハ・・・」「こらこら、お前は・・・・」
July 12, 2006
コメント(0)
-
その額で一生の思い出が出来ると考えたら安い??
音楽をやっている友人と話をする機会がありました。「本を出したいと思ってたんだけど、ひどい目に遭ったわ。 喜んで出版社に行ったら、すぐ金の話だもんな。 内容云々より、ローンも組めますよみたいな話だから、 ますます怪しいって感じだったよ。ハハハ・・・。 でもビジネスとしては間違ってないよな。 あれがあの出版社のドル箱なら あの手法で生計を立てているってことだもんな。」「あ~それって、CDの世界でも似たようなことあるよ。 自分の曲を世に出したいって奴はたくさんいるんだよ。 その気持ちは良くわかるだろ? そういう連中を相手にCDを出さないかって いってくる会社があるんだよな。 一生懸命お金を捻出して、まったく売れないCDを出すんだよな。 そりゃ、音楽やってる奴らはみんな出してみたいもん。」「それってまったく同じ構図やね。媒体が本かCDかって違いだけやん。 本を出したい奴と曲を出したい奴に対し、 それをターゲットに商売しようって会社があるってこと。 そういう意味ではバランスとれてんのかな・・・・。」「しかしなあ・・・・。 これまた払えない額じゃないんだよな。」「そこなんだよ。 その額で一生の思い出が出来ると考えたら安いってところの額なんだよ」「まあ、矯正下着もそうやってムチャクチャ売ったらしいで!」「ハハハハハハ・・・・・」こんな会話をやり取りしました。
July 11, 2006
コメント(0)
-
ターゲット層に選択と集中
本を売ることで出版社のビジネスが成り立っていると誰もが思います。これは読者が顧客層です。出版社である以上、どの出版社もそのとおりです。しかし、本を出したい人を顧客層としている出版社も存在するのです。どんなビジネスにも顧客となるターゲット層を絞ることは重要です。ターゲット層に選択と集中を行うのは当然といえば当然でしょう。利益体系から考えると、「売れる本を出す」より、「本を出したい人」の方が安定はしています。おそらく次から次に「本を出したい」という人達がたくさんいるでしょう。その人たちをたくさん募っていけば、ビジネスとして充分成り立ちます。「経営判断としては正しいんだろうな・・・・」そんなことを思いました。ただ「読者の視点」と「書き手の心情」は無視されています。金さえ積めば本を出せるという構図は必然的に中身が薄くなるでしょう。またビジネスだけで出版される本は「書き手の心情」を無視する。うれしいのは出版社だけ・・・。本が出たということでうれしい書き手もいるにはいますけど・・・。
July 10, 2006
コメント(0)
-
誕生日の日に・・・・
とほほ・・・・その日は自分の誕生日でした。喜び勇んで出版社に行きました・・・。うれしく友人に「行ってきますメール」を何通も打ちました。帰りの足取りは自然と重くなりました。ああ、そういうことなのか。こういうビジネスモデルなんだな・・・・。確かに自分の原稿がそんなに出来がいい訳はない。冷静に考えればおかしな話です。読む人の視点で書き溜めたものではありません。修正しなきゃいけないところも沢山ありました。それが明らかな理由として出版社の方の話は原稿の内容より支払いをどうするかの話に終始されていました。この本が売れようが売れまいが出版社としては本を出したい人がいればビジネスとしては終了です。ううう・・・・。続く
June 20, 2006
コメント(0)
-
それで印税ですが・・・・
それで印税ですが、増刷分×7%です。そうなんですか・・・。えっ、増刷分となると、増刷にならなかったら終わりということですね。そういうことになります。でも当社としても広告をかけますし、ご自分で売られる方もいます。増刷になるかならないかは期間があるんですか?1年間で初版が売れるかどうかです。・・・・・。支払い方法は、一括と三分割とクレジットがあります。まあ、まだどうするかわからないのでそのような話は待って下さい。私としてはこのような額を提示されるとは考えてなかったものですから・・・御社ではこの協同出版という形しかないのですか?ええ、うちでは協同出版というのが基本です。そうですか・・・・まあ、車一台を買うよりは本を出すことの方が価値があると思うのでやってみたい気持ちはありますが、すぐにハイと言える値段ではないですね。よくわかりましたので考えてきます。この本は今しかないですからタイミングを逃したら遅いということもありますからね。わかりました・・・。続く
June 19, 2006
コメント(0)
-
協同出版って??
いいですねー。このような着眼点で書いた本は今のところないし、出すのであれば今ですよ。えっ、ほんとですか!!面白いとは思いましたが、そうですかね・・・。ところで、今回見積もりを作らせていただきました。当社は協同出版という形をとらせてもらっており、冊数は500部でこのようになります。本人が50部買取で150万円ですね。えーーーー! 協同出版????原稿が良かったから出してもらえるのではないのですか?しかし、こんなに掛かるもんなんでしょうか?はい、原稿を読ませていただいてこれなら本に出来るというものを選んでいます。当然、修正しなきゃいけない部分、編集しなきゃいけない部分はありますのでこれから一緒に作っていきましょう。しかし、この値段はすごいですね。はっきりいって、このような値段を自己負担することなどまったく考えてなかったので驚いています。先ほど協同出版っていわれてましたけど、自費出版ってことですか?いいえ、自費出版とは違います。まず大きく違うのがこのISBNコードなんですよ。これがなかったら書店で売れないんですよ。自費出版の場合はこれがないんです。協同出版の場合は出版社が編集や販売をやりますのでISBNコードが付きますし、全国の書店に並ぶことになります。当然、広告等の営業も当社がやるのでその辺が自費出版とは違いますね。はぁ・・・・。それで、印税なんですが、続く
June 18, 2006
コメント(2)
-
このような本を書こうと思われたきっかけは?
読ませてもらいましたけど、良く書けていますね!今までに何か書かれた事はおありですか?いいえ、ありません。ただ仕事で業界向けの冊子を作ったりするので硬い文章は良く書いてます。このような本を書こうと思われたきっかけは?そうですね・・・、団塊の世代ジュニアって、とても優秀なんですよね。生まれた人の絶対数が多いでしょ。厳しい競争を勝ち抜いて高校・大学、就職するんですよ。でもね、会社に入るでしょ、すると上司はね、みんな彼らのようなプロセスを経て就職した訳じゃなく、何もしなくても翌年の給料が2倍になったような時代に入社しているんですよ。上司といわないまでも先輩だって、いわゆるバブリアンなんですよ。仕方ない、お前の会社に入社してやるよ!って感じで就職したんですよね。それは大きな世代間ギャップなんですよね。だって、努力して努力して厳しい戦いを勝ち抜いてきて団塊の世代ジュニアの到達点が「あれれ、努力してきてないやつらばっかじゃん!!」ということなんですよ。そりゃ、悩みますよね・・・。俺はこんな人たちに遣われるためにいろんな努力してきたのか・・・。寿司職人に例えると老舗で厳しい修行した後にとんでもない回転すしに入れられて「寿司は機械が握るんだ。お前はメンテナンスやれ!」っていわれるようなものだもの・・・。そんな彼ら彼女らによく相談を持ちかけられたんです。「○○部長って、××理論知らないんですよ。あれってこの業界の常識でしょ?? あれ知らないで偉そうに命令するんだけど、おいおいって感じですよあああ、もう辞めたいな・・・。」実際、優秀な人ほど辞めていきましたよ。そんなんをみると残念でね・・・。彼ら彼女たちと一緒に仕事をしたらきっと良い仕事が出来たのにな。といつも思ってました。だから、そんな彼ら彼女らが日頃の理不尽さを苛立ちを ぷっ、と笑ってくれるようなものを出してみたいと思ったんですよ。だって、それを嘆いて辞めていっても進歩はないし、理不尽さを皆で共有して、それを笑って後の世代にそのようにならないことを考えたほうが前向きでしょ?そう思ったんですよ。続く
June 17, 2006
コメント(0)
-
本を出したい!
生涯に1度は、本を出してみたいと思っています。実は数年前からその思いは強くて、少しずつ文章を書き溜めていました。思いつくままに書き溜めていくと、いつのまにか、会社で起きた理不尽な出来事集ができあがりました。上司から言われて頭をかしげたこと、これは絶対おかしいよ!という話がたくさん溜まっていきました。この2月の中旬頃、「あなたの本ができます!」という広告を見つけました。「よし、これを試しにこの出版社に出してみよう」と思いました。書き溜めた原稿をプリントアウトし、簡単な企画書と一緒に送ってみたところ、数日後、その出版社の担当の方から電話が入りました。「原稿を読ませてもらいました。非常に面白いですね!本を出版されたいんですよね?一度、こちらにお話に来ませんか?」このとき、本当に舞い上がってしまいました。(笑)「自分の本が出版されて本屋に並ぶんだ!!」とってもうれしかったのを思い出します。当日は朝から気合入れてその出版社に足を運びました。期待半分、不安半分、どうなるかな?と思いながら何も知らない私はテーブルに着いたのでありました。続く
June 16, 2006
コメント(0)
-
「何か新しいことをしようとするとき」
新しいことをしようとするとき、様々なタイプに出会う。こういう仕事をしていて最も多くて嫌いなタイプ・・・・それは、「私は何をしたらいいですか?」というタイプである。今日もまたそんな輩に出会った。会社勤めのサラリーマンだから、仕方ないといえばこの話は終わってしまうが、「あ~情けない」と思うのは自分だけだろうか・・・・。何がこんなに情けないかというと、わかりやすく例えるとこういうことだ。いまここに真っ白いキャンバスがある。絵の具もある。お金もある。時間もある。ある日、オーナーに絵を描いて欲しいといわれた。そのためのメンバーが10人選ばれた。オーナーから与えられた課題はただひとつ、「お客様が喜ぶ絵を描いて欲しい」たったそれだけである。自分ならこう考える。1.何を書こうかな。2.これを書こう。(書きたい)3.どうやって書こう・・・・・新しいことをやるときに一番面白いのは、この1~3だと思う。何故なら、自分の頭で考えをめぐらせることができるからだ。しかも、自由に表現できるチャンスを与えられているのである。どんな絵を描こう、あれもいい、これもいい、これも描きたい、あれも描きたいと考える楽しさがある。もし、これらがすべて決まっていて、「はーい、僕ちゃんは、こことここに、この色の絵の具を塗ってくださいね」といわれたら、「バイトでも雇ってやってもらったらどうだろう」というだろう。それがまさしく「私は何をしたらいいですか?」なのである。今日の打ち合わせで最も情けなく思った一言。「帰って上司に報告するとき、何を話したらいいかわからない」・・・・・・・・(絶句)・・・・・・・そりゃそうやろ、だって今日は1.何を書こう。2.これを書きたい3.どうやって書こうという会議(いわゆるブレーンストーミング)をしたのであって「はーい、僕ちゃんは、こことここに、この色の絵の具を塗ってくださいね」という指示待ち族用の会議をしなかったんだから・・・・。
February 27, 2006
コメント(0)
-

甲子園への遺言―伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯
久しぶりに骨のある本に出会った。読み始めると吸い込まれていくような感じだった。夜中に読み始めると眠れなくなった。一気に最後まで読み通した。その本の題名は「甲子園への遺言―伝説の打撃コーチ高畠導宏の生涯」甲子園への遺言30年間に渡りプロ野球という厳しい世界で有能なコーチとして生きて来た方のお話である。ご存知のようにプロ野球は毎年毎年の契約更改をして初めて次の1年が保証される世界。力がなければ、あるいは必要とされなければ、次の年はないのである。育てた選手は多く、のべ30人のタイトルフォルダーがいる。イチロー、田口をはじめ、最近の選手では、サブロー、福浦、小久保、アリアス少し古い世代だと、落合、高沢、西村、水上、袴田、藤原・・・・コーチとしての基盤は当時の南海ホークスで培った知識と経験に基づく。どんなピッチャーにも癖がある。その癖を誰よりも早く察知しストレートやカーブなどの球種を見極める。独自の打撃理論はシンプルで理に適っており非常にわかりやすい。インサイドアウトのバット軌道、玉の内側を最短距離で上から叩く、球の下側を叩きスピンをかける、へその前がミートポイント、フォロースルーは大きく。また彼の指導は決して強制するものではなく選手を尊重する提案型。欠点は治るものではない、長所を伸ばす。そうすると自然に欠点が治る。また、選手が成長する上で必要なものを気力、精神力などメンタル面に着目したところである。驚くことにプロ野球コーチの傍らで通信教育で心理学を学び、教職を取った。福岡の高校へ赴任し甲子園制覇を目指す。赴任2年目に病に倒れ不帰の人となる。しかし、彼の生き方や残した言葉が多くの若者の心を捉え、今も行き続けている。この本では卓越した打撃理論に加え彼の生き様に感動を覚える。また、生半可な経験論ではなく厳しい世界を真剣に生きてきた一野球人の真実のメッセージを感じる。ほんとにいい本を読んだ。
January 4, 2006
コメント(0)
-
新年明けましておめでとうございます。
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今日から仕事始め、電車はガラガラ。うちは年末年始が1日ずつ少ないので、正月休みはただの連休のようにあっという間だった。そんなことは置いといて、2006年も始まった。休み中にいろいろと考える時間があったのは、とても有意義だった。2005年は「アウトプット元年」としたスタートした。年初はインターネットを使い自分なりに新しいことにチャレンジした。しかし、春ぐらいからは野球や音楽、仕事・・・・etc従来からやってきたことが忙しくなった。そんなこともあり小休止。自分がやろうとしたことの弱点を認識したのでよく考えてみたくなったからだ。しかし、この5日間で考え直したこと、やっぱり新しいことをやりたいということ。新しいことをやろうとするとトライアンドエラーは仕方ない。そのステップも楽しめばいい。結果云々より面白さを求めてみたい。問題は時間配分だろうな。従来からやってきたこと、これからもやり続けたいこと、新しくやってみたいこと、本当にたくさんある。選択と集中というよりどれも集中したい・・・・(笑)自分をうまくマネージメントするしかないな。
January 4, 2006
コメント(2)
-
宅ふぁいる便
大容量ファイルやデータを仕事や友人に送ろうとしたとき皆さんはどうされてますか?自分がよくやっていたのは、Yahoo eグループ内のブリーフケースへの保存。でもこれは友人にしか活用できない。仕事関係ではCDをメール便で送ったりしていた。それが、今日、優れた無料サービスを発見した!『宅ふぁいる便』 http://www.filesend.to いやー、これはすごい!最大50MB、無料の大容量ファイル受け渡しサービスである。仕事関係の大容量の受け渡しに最適である。使い方は至って簡単。送り主は簡単なメールを書いてアップロードするだけ。受け取り主は宅ふぁいる便から届いたメールにURLが貼り付けてある。そこをクリックしてパソコンにダウンロードするだけ。これで大容量のデジタルデータの受け取りは完了する。ほんと便利だね、こりゃ。友達同士で「CD(DVD)貸してよ!」っていうのが、これからは「CD(DVD)データを送ってよ!」になるわな。
December 21, 2005
コメント(2)
-
cookpad、BlogRanger・・・・・・浅田真央
ブログでの評判やクチコミを検索をサイトがある。テクノラティという検索サイトで、今、最も検索されている話題をピックアップしている。本日(12/20)のランキングである。 1.cookpad 2.BlogRanger 3.CMS 4.W-ZERO3 5.上川隆也 6.浅田真央 7.フクダユウイチ 8.ほぼ日手帳 9.あらしのよるに10.XBOX360・・・・この中でわかるのは、浅田真央ちゃんくらいやないか(笑)調べてみると、ランキング1位のcookpadは、料理のレシピを互いに公開するコミュニケーションブログだそうだ。食は誰も共通の話題。今晩、何の料理にしようか、この素材があるんだけど、どう料理したらいいのか、これおいしかったから、是非、他の人にも教えてあげたい・・・。理に適っている!!さすが人気サイト。2位のBlogRangerは、検索キーワードを登録することにより効率的に情報収集できるサイトらしい。(違っていたら修正してください)情報過多の時代、効率的に的確な情報を収集したい。ニーズというよりウォンツだ。すみませんが、3番以降はわかりません(笑)上川隆也は確かバレー???
December 20, 2005
コメント(0)
-
昨日は野球の納会だった。
この時期は忘年会シーズンである。各方面からもお誘いを受けるので、スケジュールが合わないときは欠席しているが昨日は野球の納会だった。中年の野球好きが集まって今シーズン1年を振り返りながら来年に向けて各自の野球談義を披露する。それぞれ高校野球や大学野球等で活躍した選手、それなりに持論を持っている。それぞれが指摘することは各ポジションから見る客観的評価でありそれなりに当たっていて面白い。自分が言われたことは初回から3回まではいいピッチングをする。4回に崩れるケースが多い。パターンが悪くなると玉が甘くなる。これは自分の課題でもある。「熱い気持ちは必要だが、冷静でなければいけない」憧れの選手からも教えてもらった言葉でもある。年一度の納会、野球好きの中年が少年のような顔をして楽しんでいるのは本当にいい瞬間である。おかげさまで今年もチームの最優秀選手賞をいただいた。何年やっても課題もあり、弱点に気付くことがある。完成することはない。来年はボールも変わる。ユニフォームを新調されることになった。背番号も「1」をもらえることになった。もちろん大好きな1番を希望した。ほんと楽しいね!
December 19, 2005
コメント(0)
-
こんな不思議なこともあるんだな。
仕事で元プロ野球選手に会った。自分が中学生、高校生の時に大活躍されていた憧れの選手である。実は1年半ほど前に羽田空港でお見かけしたことがある。不思議なことにその日の前日、ふっと「明日、(その方に)あったら何をしゃべろうか?」と思った。「同郷なのでその話をしよう!」と・・・・考えた。まさかそんなことがある訳がない。すっかり忘れて翌日の朝、羽田の待合室で呆然とした。「おおお!!!」同じ便の搭乗ゲートにまさしくその方がいるではないか!!何の面識もないので、声をお掛けすることはなかったが、本当に驚いた。伊丹空港に着いたとき、会えれば話かけようと思ったがそのような瞬間は来なかった。しかし、その時、何故か、また会えるのではないかと思っていた。先月末、同僚が「次回の取材は○○さんですよ」と行って来た。「おおおおお!!ついに来た。是非、その取材に行かせてくれ!!!」こんな不思議なこともあるんだな。ほんとに驚いた。もちろん、お会いした最初に「わたしも同郷です。」という話から始めさせてもらった。印象はTVや雑誌で見るそのまま。一本気な性格は周りの人を魅了する。会ってみて元気が出る人。同行した関係者曰く「ちょい悪オヤジってはやっているけど、俺はこんなオヤジになりたいな!」ほんと何か一つを極めた人は違うね。願いがかなったことに感謝しつつ、いろいろ思い返した。実感が湧くのはこれからやろうな(笑)以下、語録の一部です↓・「自分のことは、自分が主役。自分が精一杯やらないといけない」・「自分がどうありたいか」「目標を持て」 エースであるためには何をしたら良いのか? 足らないところは何なのか? それを修正するためには何をすべきか?・「負けたくないという気持ちは必要であるが、常に冷静でなければならない」・「ひとつのことを48時間続けてやることはできるか?」 限界を知ることで、自分の今の力が客観的に分かる・「知ろうとしなければ出会えない」 いい食べ物も、いい飲み物、友人も自分から求めなければ出会えない 日本のいろんなところの知人を通じて、食物は取り寄せている。 どんなことも常に研究をし、考える・「子供達に本物を教えるために決して手を抜かない」 スピードボールを全力で投げる いろんなところにもっともっと力がある奴がいることを知らせる
December 14, 2005
コメント(2)
-
すっかりファンになってしまった。
ある女性歌手の方とお話しする機会があった。先日も日曜朝の人気番組で取り上げられた人気歌手である。テレビのイメージと大差なく、ユーモアもあり気さくな感じ。話してみて本当に魅力ある人だった。すっかりファンになってしまった。最も印象に残った話は、『力のある歌は残る』という話。長く歌い継がれる歌というのは、それだけ人々の心に強く残っている。歌を聴くと誰もがそのときそのときに何をしていたかをぱっと思い出す。童謡にはそんな力があるという話だった。そういえば沖縄民謡の歌手も同じことをいていた。今までに何百何千という島唄ができた。その唄が何百年にもわたり歌い継がれる歌がある。そんな歌は力がある歌であると。まったく同感である。最近はターミナルケアで歌われたり、いろんなボランティア活動もされているそうだ。確かに幼少期に歌った歌を認知症の患者に聴かせるとわすかながら歌いだしたり、驚くべき反応があるそうだ。自分も晩年は老人ホームやターミナルケアの病院をギター1本抱えて回ろうか、そんな気がした。
November 30, 2005
コメント(4)
-
だって、この話って
朝礼の話は多少インパクトがあったようだ。「人間味があるのがいい業種は寿司屋さんと蕎麦屋さん以外は何があるんですか?」と質問が来た。「医者、薬局なんかはそうじゃないですかね。あと散髪屋、エステなんかもそうでしょう」と答えておいた。まあ、ハートフルなところを残しておかなければいけない職業を考えればわかりやすいと思う。すると「お客様によって求めるものが違いますからね」と帰ってきた。そりゃ、そうなんだけど、それを言ってしまえば、朝礼の話は何やったんやってことになる。(笑)例えば、ピッチングの配球は人間心理と確率論のゲームでありそこに面白さがある。こんな感じのバッターはこういう風にする(考える)確率が高いと考える(感じる)から「ピッチャーとしての攻め方」が出てくる。それを、「うん、バッターによってそれぞれ違うから」っていうともう、この話は終わるよ(笑)だって、この話って、違いの中にどれだけの確率の高い共通項があるかそれを見つけ出して、いかにこちらが優位に攻める話だからね(笑)
November 4, 2005
コメント(0)
-
便利さの追求はバランスが必要
この前書いた「最近の回転寿司で・・・」というコラムを題材に便利さの追求はバランスが必要と訴えた。要するに「追求していいもの」と「しない方がいいもの」がある。という話をした。していいものは、SUICAとか、混雑したレジとか、みどりの窓口などしていけないのは、寿司屋とか、蕎麦屋とかであると。医者や薬屋などもその類と言っておいた。自動販売機に症状を入れて病気の可能性がわかるのはよくない。そこには人間味が要るといった。回転寿司の皿計算で「ピュッ」というセンサーで計算するんだという話は知らない人も多いし、受けた。面白かったのが、ある支店長さんに「回転寿司で人間味は求めないでしょう」といわれた。「回転寿司に人間味を求めているのではなく寿司屋という枠に求めている」と答えた。わかってない、やれやれ・・・。しかし、こういう風に捉えた人ってけっこう多いかもしれない。
November 3, 2005
コメント(0)
-
毛髪に関する川柳コンテスト
ツムラのモウガという毛髪剤の商品webで毛髪に関する川柳コンテストをやってた。私もグローリーというペンネームで投稿してみた。結果は、惜しくも次点。しかも、2点も次点に並んでる・・・・。「君の髪 今は昔 僕の髪」「そらしても 頭にあるよ あなたの目」http://www.mouga.jp/contest/tousen.html3点出して2点が次点なのでポイントは押さえていた。しかし、惜しいね・・・・。(笑)ちなみに落選したのが「寄せてみる 乗せてみるけど わかるよな」けっこういい線だと思うけどなぁ・・・。
October 25, 2005
コメント(2)
-
ランチにいったとき・・・
いつものようにランチを取るために会社近くのお店に入った。お昼時は、どのお店も大変忙しくしている。この店もそんなお店だった。同僚とふたり、空いてたカウンター席へ腰掛けた。隣の一番左の席には中年女性が一人座っていた。注文を終わり、座って待っているとお隣の中年女性より先に我々の前にハンバーグが来た。注文したものによって多少の誤差があるのは仕方ない。そんなことだろうと思っていた矢先、お隣の中年女性、「あと、どのくらいかかりますか!」怖い口調だった。確認のため、女性店員さんが、「お客様、ご注文は○○ハンバーグですよね?」とやってきた。すると、その女性、「さっき、言いました!!」と、さっきより強い口調でお答えになる。それを聞いていた別の女性店員さんが来られて、「お待たせして申し訳ありません。再度、ご注文を確認させていただきます。お客様のご注文は○○ハンバーグですよね?ソースはデミグラスソースですよね?」再度、その女性、「だから、さっき、あの人に言いました!!!!」ともっと強い口調・・・・。見るからにお忙しそうな店内、次から次にハンバーグを焼いている。誰が見ても分かること。早く食べたいのなら、早く自分の注文とソースを伝えればいい(笑)そこでごねればごねるほど、自分の前に商品が出てくるのが遅くなる。それがわからんかなぁ・・・・。(笑)何をそんなにイライラしているのかわからないが、感情的になっているのは見て取れた。しかし、何が満たされないのだろうかね・・・・。この女性をみて思い出したのが、3つのベストセラー本。「オニババ化する女達」「下流社会」「女たちはなぜクチコミに弱いのか」この出来事を思い出しながら是非読んでみてくださいませ。
October 24, 2005
コメント(2)
-
考える野球
昨日の試合は、久しぶりに勝った。得点は4-2だったが、格下チーム相手に苦戦した。試合内容としては良いとはいえない。ただ、昨日は試してみたいことがあった。これまではアウトコース一辺倒で投げてきた。これを見直し、投球幅を広げるためにインコースの使い方を考えてみた。内側にシュート気味のボールを投げておいてアウトローのストレートあるいはスライダー系統のボールで引っ掛けさせる。もうひとつはこれに加えて落ちるボールを組み合わせてみようと思った。インコースのボールは早い回に効果があった。しかし2順目からは甘く入ったように思う。落ちるボールは投げ方と落差がイマイチ。もう少し練習が必要であろう。しかし、新しいことにチャレンジをしていかないと進歩もないし楽しくもない。また、「考えない野球」はやってても無意味である。ただ遊んで帰ればいいというのではいけない。次回対戦相手は強豪である。今回のトライアルがどう生きるか?試してみる。
October 24, 2005
コメント(0)
-
幻のソース
昨夜食べた串揚げは旨かった。その上、安かった。その中でもソースは気になった。関東圏で食するソースはどうも合わない。おそらく関西圏のソースなのだろう。幻のソースというのがある。生野区工場で親子代々受け継がれた類稀なソースらしい。基本的には業務用らしく、一般には販売されていないそうだ。ただ、関西の旨いお好み焼き屋に行くと置いてあるらしい。お好み焼きフリークは知らず知らずのうちにこのソースを掛けて食べているに違いない。しかし、このソース、家内工業でやっているらしく大量生産されていない。秘伝の香辛料レシピで安定した品質を保つには少量サイズが限界だからだ。この中でも数が少ないのがタンクに溜まったオリを含んだソース。辛口らしいが、特別なソースらしい。そう聞くとどうしても味わってみたくなった。おそらくどこかで口にはしているだろう。でも食べてみたい。インターネットで検索してみたところネットでは、素人も購入できる。ところが売り切れと表示されているところが多数。しかし、探してみると残数は少ないものの売っている店舗を発見。早速、代引きで3本発注。これで幻のソース入手。さて、どんな味だろう?
October 4, 2005
コメント(0)
-
オヤジ、串揚げを食べる!
隔週である法律の講習会へ行っている。難しい内容なので講座を終えるとふっと息抜きがしたくなる。会場を出て最寄り駅を超え、新橋界隈を歩く。毎回、通る道を変え食事をする店を探す。新しい店を見つけて中を覗くと、どこへいってもオヤジばかりである。しかし、そこには興味深いお店がたくさんある。こんなお店散策がひとつの楽しみだ。昨日はそんな中に穴場の串揚げ屋を見つけた。入り組んだ道なので、知らなきゃいけそうにない。味はどうか心配ではあったが、どうみても関西風、「大丈夫だろう、ゴー。」そう判断し暖簾をくぐる。店内には「ソース2度付け禁止」と書いてある。関西の串揚げルール通りに食べればいい。揚げたての串揚げを1度だけソースにつける。熱々の串揚げにこれが良く合う。冷たいビールやホッピーを飲みながら自らの1日の労をねぎらう。どこからみても正真正銘のオヤジである。
October 4, 2005
コメント(2)
-
エウリアンをご存知でしょうか?
エウリアンをご存知でしょうか?高額な絵画を売りつける人たちを指すらしい。日曜日の報道特集で放送されていた。昔、渋谷でこの手の悪質商法に引っ張られそうになったことがある。「無料で絵画展をやってますからお立ち寄りください」という若い女性に誘われ、お店の中に入ってしまった。そこからは延々「この絵に出会ったのは運命だ。今買わなきゃ、もう出会えない。」とか「真面目に聞いて欲しい。真剣に話しているから真剣に考えて欲しい。」とか・・・(笑)70万円から100万円くらいの値段だった。「1ヶ月にするとこれくらいだから安いでしょ?」「月々どれくらいだったら払える?」というような強烈なセールストークだった。詳細状況が分かってきたので、途中で話をさえぎり「まったく興味がないから!」といって店を出た。幸い、高額な絵画を買うようなことはなかったがあの強引なやり方なら引っ掛かる若者が多いのは頷ける。報道特集でやるくらいだから被害総額もすごいのだろう。最近は特定商取引法の改正等により、クーリングオフや解約をやりやすくなった。報道特集でも言っていたが、特定商取引法では、「販売目的」を言わねばならないらしい。絵画の場合だと「展示即売会をやっています!」といわないといけないらしい。そんなことは確かにいってなかった。昨日、銀行へ行くついでに会社近くのエウリアンを観察してみた。やはり報道特集の翌日だ。「こんにちは!展示即売会をやっています!」とエウリアンが言っていた。「昨日、TVみたで!がんばりや!」と言いそうになった(笑)
October 3, 2005
コメント(2)
-
不甲斐ない試合
悪いピッチングをした後はどうもモヤモヤが晴れない。今回の結果は1-5。プレイボール前のピッチング練習から難題勃発・・・・。「今日もやったるで!」という感じで球を投げていると、球審が近寄ってきた。「(君の)このグローブは違反だ。他にグローブはないのか?」「は???何がいけないんですか?」「ここの色とここの色が違う。連盟の規程に書いてある。グローブを変えないならピッチャーを代わってもらうことになる。」「今までそんなんいわれたことないですよ。」「書いてあるんだ」野球の古い体質、審判の絶対性は知っているので、こういうケースは絶対ひっくり返らない。グローブは左手の使い方と関係があるので大きな問題である。そうはいっても、試合をするためには代用グラブを使うしかない。泣く泣くグローブを交換・・・・。試合は、4イニング目に自滅した。1アウトからの1塁ゴロが飛んだ。明らかなミスジャッジ・・・・。しかし、これも野球。次打者を抑えることを考えたが、カッカッ来ている自分をコントロールできなかった。結果、投げ急ぎ、ストライクを甘いコースへ・・・連打を浴び、4失点。あとで考えれば、投げ急ぐ必要はまったくなし。意識的にボールをもう数球投げてもどうということはなかった。取られるべくして点を取られている。たくさんの反省が残った。東京に来て一番悪い試合だった。あ~、くそ!!
October 2, 2005
コメント(2)
-
ご健康を切に願う・・・
仕事の関係で、ある女性歌手にお会いする機会があった。業界業界のルールというか、しきたりがわからないので、事前確認は怠らなかった。同行者に詳細な情報収集をして、細かいケースまでチェック・・・・。インターネット検索はもちろん最近の話題は勉強しておいた。業界のしきたりはわからないのは仕方ないが、自分に出来ることはこの方のことを知っておくことだと考えたからだ。当然、ところどころで役に立った。同行者には驚かれたがこのような仕事をする上では当然なんじゃないかなと逆に驚いた。幸い、お話をする上では失礼はなかったようで今回の仕事はうまくいった。最初はお互い硬かったが、話をするうちに顔が和み、か細い声で話される姿はTVの対談番組と同じ。永い間、トップ歌手として活躍されているので、その方の気遣いはさすが。大物ほど礼節に厳しく「実るほど頭を垂れる稲穂かな」「頭は低く、信頼は高く」その通り。ただ気になったのはストレスも多く非常にお疲れの様子。ご自身の体調や日常生活をお聞きすると確かに大変さはよくわかる。長い歌手人生には栄光の影に辛い経験を幾度もされたようだ。健康産業に従事している立場としてだけではなく一ファンとして、この大歌手が心身ともにもっともっと元気になって欲しいと願い帰路に着いた。
October 1, 2005
コメント(2)
-
最近の回転寿司で・・・
新しくできた回転寿司へいった。最近の回転寿司は目の前の皿を取る人はいない。いくつかのお寿司が回っているが欲しいものを普通のお寿司屋のように注文すると親父さんが握ってくれる。値段に応じて皿に入れて渡してくれる。回転寿司でありながら回っている寿司を取るのではない。もうひとつ6,7種類のお皿は値段によって色が違う。よくある光景だと思うが、この店はビールまで皿を置きに来た。その意味がわかったのはお勘定を計算する時。このお店、センサーでお皿の枚数を感知する。5枚までしかできないらしいが、一番上の皿にセンサーを乗せるとピツと音がして、枚数が出てくる。「ああ、それでビールの皿がいるんだね!」皿をひっくり返してみると磁気が入っていた。値段によって違うらしい。すごいなと思う反面、すし屋はあまり便利さを追求して欲しくない職種のひとつではないかと思う。人間味あふれる接客がいいのではないかな
September 28, 2005
コメント(2)
-
「リズム」を観察して思うこと
週末にボサノヴァ歌手のコンサートへいった。品の良い、癒し系の音で、すぐに眠くなった。2曲目で寝てしまったが、起きても同じような曲調の歌だった。まぁ別にウトウトしながら聴くのもいいだろう。最近は会場と一体化するような感覚はなくなった。何をしているかというと、一生懸命、歌手の歌い方や演出、照明効果、お客の反応を見ている。お!今、こういう入り方したな、とか、お!ここでこの曲はいいな、とか・・・。今回、気がついたのは観客の「リズム」イチ・ニ・サン イチ・ニ・サンという3拍子がまったくできない。演奏者と一緒に乗りたいのに乗れない・・・。弾けたいのに弾けない・・・・。客層は中年~高年齢の女性が多かった。2拍子や4拍子が簡単なのはわかるが、やはり、普段から意識しないリズムなんだろう。スポーツをしても同じことなのだが、日本人には特有のリズムがある。神楽や日本舞踊などの伝統芸能にみられるように古い時代から日本独特のリズムを生活に入れていた。染み付いているといっても言い過ぎではないだろう。ダンスや格闘技にはリズムは不可欠だと思う。黒人選手が優秀な成績を挙げるのには筋肉などの身体的なレベルだけでなく先天的なリズム感がある。最近の若い世代ではヒップホップとか、ダンスミュージックとか新しいリズムを体感できている人たちが多い。前回のオリンピックでは日本選手が輝かしい成績を挙げた。競技中に自ら身体の中で打つビートが好成績を与えたのではないかな。
September 26, 2005
コメント(2)
-
脳と語感(その5)
いい歌は後世まで歌い続けられる。人々の心に深く残るといわれるが、脳に残るのだと思う。ヒットしても歌い続けられるうちに忘れられていく歌があり、その中で残った歌が何世代にも歌われるんだろう。「どんな歌をやりたいですか?」と聞かれたら、「最近は歌い継がれた歌がいいね」と答える。それは上に書いたように、人々の心に残った歌の方が響くからだ。歌には曲調によって聴こえ方が違うらしいが、音の出し方や聴こえてくる音で潜在脳への強度(働きかけ)が違うのではないだろうか・・・。長く深く潜在脳に刻まれた歌が後世までに歌い継がれているのでないかつづく
September 22, 2005
コメント(0)
-
脳と語感(その4)
「言霊(ことだま)」という言葉がある。言葉は生き物で使い続けるとそのようになる。だから、普段使っている言葉は前向きな言葉を使うように、いい言葉を使い続けることは大事だと・・・。この言霊も脳に対する暗示である。おそらく、黒川さんが言うように、これも使う言葉によって潜在脳の刺激部分が違うのだろう。もう少し欲を言うと年代毎に言語と脳の活性化を調べてみるとすごい研究データが出そうな気がする。例えばKという音ばかりをスピーカーから流したときに脳の活性化される部分が赤く表示される。ああ、ここが刺激されているのか?とうのがわかる。養老孟さんも似たようなことをいっていた。詳細は忘れたが、あることをしているときの脳の活性化される部分とまったく違う何かをしているときの脳が活性化される部分が同じである。つまり脳からしてみれば行動はまったく異なるが、刺激、感じ方は同じだという。いい言葉とある地域(例えば沖縄など)の方言が脳の刺激部分が同じなどのデータがでたら面白い。つづく
September 21, 2005
コメント(0)
-
脳と語感(その3)
こうしてみてくると、ことば自体が持つイメージ、それを受け取る人間の性別や世代、これらの組み合わせが複合的になっていろんなイメージが生まれることが良く分かる。感性というもの、潜在意識に訴えるものとか、科学的に論ぜられることは少なかった。感性というものは、分かる人にしか分からないとか、潜在意識は意識層より深いんだといわれても多分そうなんだろうとしか、わからなかった。しかし、近年、科学的なアプローチを裏付けに新説を世に出してくる人がいるとうれしい気持ちになる。数値化して、この商品のネーミングは受け入れられないよ。とか、非常にいいねこの名前!とか感覚的ではなく、マニュアル的に、しかも必然的にセンスいい名前が選別されるであろう。従来型の「俺がいいと思うからいいんだ」とかそういうのは即却下となる(笑)つづく
September 20, 2005
コメント(0)
-
脳と語感(その2)
具体例でいうと11才までの幼児は唇の刺激音、P、B、F、拗音(キャキュキョ)などが好きらしい。プリン、チュッパチャップス、プリッツなど11~17才までの男子引っ掛かりのある音G重い破裂音B、Dが好みガンダム、ゴジラ、ギア、エアガンなど11~25才までの女子爽やかなS音、クールなK音、透明感のあるR音が好みキティー、キララ、きれい、きらい、すてきシャネル、シャララ、ショートケーキ第二次性徴が大きく影響している。40~60才までの男性どっしりのD、がっちりのG、充実感のT満ち足りたイメージのMが好み。銀座、メルセデス、達成、堂々、ワイルド、ダンディつづく
September 19, 2005
コメント(0)
-
脳と語感(その1)
「女たちはなぜ「口コミ」の魔力にハマるのか」黒川 伊保子 (著)という本を読んだ。ある講演会の予告表をみたのがきっかけである。残念ながら黒川さんの生講演を聴くことはできなかったが、レジメを読んで益々興味を持った。「世界一聞きたい授業」という番組にでも紹介されていたが、黒川さんの理論はキーワードは男性脳と女性脳がベースとしてある。脳梁の太さが違うなどの脳の仕組み、物事の捉え方や考え方の男女差などだ。それに加え、男性ホルモンのテストステロン、女性ホルモンのエストロゲンやプロゲステロン、の出方によって感度が異なるというようなこと。特に女性は周期的にエストロゲンやプロゲステロンの上下を繰り返しているのだから、個人の中でも大きな差がある。こういったベースの上に音に対する独自の理論を構築され、語感というものを科学的に捉えようとしている。ことばには、「意味」「文字」「音」があるがこれらは大脳領域。4つ目の要素は「体感」である。これは小脳領域。言葉の本質は発音にあって「発音時の口腔内物理的変化がことばのイメージをつくる」という。Kは、強さ、硬さ、ドライ、スピード感Sは、爽やかさ、滞りのなさTは、充実感(中身が詰まった感じ)、 濡れた感じ、重さを感じさせる。これらを数値化させて従来はセンスがいいなどの一言で片付けられていたネーミングやキャッチコピーのイメージを評価するらしい。サブリミナルインプレッション導出法というらしい。つづく
September 18, 2005
コメント(0)
-
お召しあがりですか?
普段は行かないハンバーガーショップへ珍しくいってみた。「たまにはファーストフードの現場視察もしてみないといけない」と思ったからでもある。セットメニューを注文すると「お召しあがりですか?」と若い店員さんにいわれた。ここでもう意味がわからなかった。「ハンバーガー買いに来たら、食べるに決まってるやろ!」と思ったから怪訝そうな顔で「食べるけど何?」というと手でジェスチャをしながら「こちらでお召し上がりになりますか?」と言われてしまった。(笑)なんだ、「こちらで食べるか食べないか?」の意味か・・・・しかし、ほんとに言葉の意味がわからなかった。普段行かないからわからないのもあるが、丁寧過ぎるマニュアル用語や若者の気遣いが自分にとって非日常的だからだろう。ファミレスも行かないが、似たようなシーンが過去にもあったような気がする。思い出すのが、数年前のアエラにあった記事。ある人が「ハンバーガー十個お願いします」といったら、マニュアル店員に「こちらでお召し上がりになりますか?」といわれたらしい。今日の話はそういう話ではないが、たまには普段行かないところへ足を踏み入れないと益々、ついていけなくなるな。
September 14, 2005
コメント(0)
-
電話1本かける前に・・・・
あなたは電話派か?メール派か?と聞かれたら、即座にメール派と答える。ビジネスシーンとプライベートシーンではその割合は多少異なるが、なぜそう思うかというと、電話は相手の時間を奪う(こちらの時間は奪われる)からだ。電話をかける際はこちらの都合だけで相手の都合はわからない。暇かもしれないし、忙しいかもしれない。喜ぶ内容ならいいが、相手の仕事や行動に影響を与える。逆に集中して難しい仕事をこちらがこなしているときにくだらない電話は迷惑極まりないし、集中力をそがれる。だから電話をかけるときもかかってきたときも神経を使う。当然、自分の場合は緊急性が高い場合や相手の都合が明確なときに限定される。その点、メールの場合は細かいニュアンスは伝わりにくいが、電話のような心配はない。最近よく思うのが、優秀な人ほどこの違いや使い方を心得ている。そもそも電話でやる仕事なのか?メールで済む話なのか?相手に迷惑や仕事の効率性はどちらがいいのか?うまく使い分けている。反対にこれができてない人は見苦しいし迷惑だ。こういう人は一見、汗をかいているように見えるが実のところ処理量は非常に少ない。電話1本かける前に少し考えれば済むのにね。
September 12, 2005
コメント(0)
-
あなたはACが低い
「あなたはACが低い」といわれた。そこにいるほとんどの人にいわれた。うーん・・・・・・。ACというのは、ADAPTED CHILD;「順応した子どもの心」心理学の交流分析で使われる用語である。順応する子供の自我状態というくらいだから抑圧度と解釈してもいいかもしれない。従順で自己犠牲的な面があるので、これが高い人と低い人では長所短所がある。ACが高い人は妥協・協調・我慢・慎重・イイ子ではあるが消極的・自己犠牲・依存となる。いい例が何事にも協調しすぎて自分自身をなくしてしまうというような人。何でも我慢して人に合わせてしまうためストレスがたまる。逆にこれが低い人は頑固で融通がきかない人ということになってしまう。あくまでも一般論でいうとこうである。昨日のその場に戻ろう。「ACが低いといってるけど、例えばどういうことよ?」と問いかけてみた。すると返ってきた答えが「バンドの練習で、みんなで話をしてるときに、ひとりでギターを練習してるじゃない!」ということだった。反論として、「いやいや!それはみんなと合わすため。みんなと合わすために自分の課題がわかったら練習する。それだけ。むしろACが高いじゃないか!」というと、そこにいた他の人が「それは音合わせで(あって)、ACが高いということじゃないよ」まったく納得がいかないので、「えー!!じゃあ、バンドメンバーの中で誰がAC高いの?」と聞いてみた。一瞬凍って、誰もその答えは言わなかった。(笑)・・・・・ここからは私見であることをお断りして書く。ACには2つあると思う。勝手に自分が作った言葉だが、ひとつは迎合型のAC。残りのもうひとつは本質型のAC。迎合型ACというのは自分の意思や主張を抑えて何もかも迎合するということだ。例えば「カラスは白い」と会社の上司や権力者が言ったら「そうですね、白いですね」という行動などを指す。これに対して本質型ACは迎合や妥協をすることなくベストを尽くしある考え方や行動を受け入れること。自分にとってバンドで音を表現することはその時に集まったメンバー達と同じ時間を共有しそこにしかない音を作り上げて本質的にいいものを作るという気持ちが常にあった。しかし、自分たちの技術レベルや時間的な制約、メンバーの性格や意向など様々なファクターが実際あった。こういったものを受け入れて本質的な音を追求しようとやってきた訳である。つまり自分では迎合や妥協はしたくないが、自分なりに音は追及したい。ただ、バンドは一人で出来ることではないから順応するための努力はすごくしてきた。ということを言いたかったわけである。迎合型ACじゃなく本質型ACまで話をすれば通じたかもしれないが、おそらくこれは通じてないだろうな・・・・。協調性を過剰に意識するばかり本質的なところに踏み込めない・・・。表面的な迎合に目がいくばかりに本質的な順応を認められない・・・。そんな寂しさを感じた夜だった。
September 11, 2005
コメント(2)
-
野球部
中学時代の野球部は今ならニュースになるようなことばかりだった。体育大学を出たばかりの教師(監督)は殴る蹴るはあたりまえ。エラーしたら「何でエラーするんだ!」返事をしなかった者がいれば連帯責任でケツバット。しかし、一方で1球の大切さやこのスポーツの怖さを学んだのも事実である。実際、高校野球の強いチームを見るといまだにその精神は強く残っている。一説には、3年間という限られた時間で物事をなし遂げるためには仕方ないことだとの意見もある。自分で考えても確かにそうだと思う。ただ恐ろしいのは、このような環境だと選手は怒られないためにはどうすればいいということは考えるが「何も考えなくなる」それとこのスポーツが楽しくなくなる。考えない、楽しくない、その結果故障発生。野球生命を不本意な形で終わる。これが一番悲劇である。自分などは成長期が遅かった。中学生では誰と比べても小さい部類。体力的にも当然劣る。しかし、高校生、大学生になって身長がぐんぐん伸びた。野球をするための基礎ができてきた。つまり旬が違うのである。幸い、自分の場合は肩やひじ、足腰の故障がなかった。おかげで今でも草野球を楽しめる。あるトレーナーがいっているように将来にわたってこのスポーツを楽しめる環境を作れる指導者が必要な競技の代表かもしれない。
September 6, 2005
コメント(2)
-
夏風邪を引いてしまった・・・
先週からひどい夏風邪に苦しんでいる。草野球で1試合投げるということがかなりの重労働なのだろうか・・・。今回は2ヶ月開いたので久々の7イニング試合後は疲れてしまった。それと試合後の不摂生が祟ったのかもしれない。プロテインを補給して軽いマッサージと休息をとるべきだった。喉が痛いと思っていたが咳がなかなか止まらない。耳鼻科で抗生物質と咳止めをもらったが、なかなか効果なし。昨晩も夜中の咳で熟睡できなかったので今朝は内科へ行った。セファム系の抗生物質をペニシリン系に変えてくださった。その他にも3種類、計4種類の薬を飲んでいる。これ以上長引かせるわけにはいかないので早く治さねばな。
September 5, 2005
コメント(2)
-
ついに新しいギターを買った!!
高木ブーさんは、ご自慢のウクレレをTVの上に置いておくらしい。だんだんといい音になっていくからだそうだ。弦楽器は使い続けると音が変わってくる。木は生き物だから。温度や湿度によって膨らんだり、縮んだりを繰り返す。温度が高ければ乾いた音がでるし、湿度が高ければもわっとした音が出る。こういうことを繰り返し繰り返し、弾くことによって振動をあたえ、固有の音が作られる。ついに新しいギターを買った。その名はGIBSON。どのギターがいいか、各社の製品をひとつひとつ手にとってその中で自分が最も納得できる音、ついに見つかった。聴こえてくる生音、身体に伝わる振動、今まで弾いていたギターはオモチャこれからはもう楽器のせいにできない。自分の腕だけだ楽器と共に成長していこう。
August 31, 2005
コメント(2)
-
祭りと野球
台風の中、東京ドームで都市対抗野球を観戦した。以前から興味はあったのだが、実は初めての観戦である。都市対抗野球はその名の通り、○○市 vs △△市ということになっているが、NOMOクラブ等を除いて、実際はほとんどが実業団チーム。企業vs企業の争いだ。都市対抗野球は応援合戦も有名でチアーリーダーの熱い応援も企業同士が争う。どのチームもリーダーがマイクを持ち、大きな声で応援席をリードする。その声や踊り、パフォーマンスに乗せられ球場が盛り上がっていく。企業のお祭りとしては運動会みたいに楽しいものだ。昨晩も大いに盛り上がった。が、しかし、である。どうも野球と祭りが一緒になっている。祭りをしながら野球を楽しむという構図ではない。祭りのための野球である。いいプレーに拍手喝さいを送るのではなく、ただただ自軍のいい結果にだけ、声を上げて騒ぐのである。場所は社会人野球の最高峰である。野球の真髄、1プレーの中身、試合の流れ・・・野球の楽しいところが、祭りに打ち消される。ビールを飲みながら巨人戦ナイターを見る親父にはなりたくないが野球を祭りの神輿やだんじりにはしたくない気がした。
August 25, 2005
コメント(2)
-
次の課題曲
次の課題曲を何にしようか悩んでいる。自分が演奏している姿をビデオなどで見ると、かなりキンキン声。ときどき高温が出てない。リズムは少し走り気味。選択する曲によって聴こえ方が違う。声質と演奏曲、この時点で重要な選択だ。よくカラオケへいくと上手い人ほど歌いやすい歌を歌う。下手な人ほど難しい歌を歌う。聴こえ方は段違い。自分の場合はサビのところで声を張り上げるタイプの曲が合うような気がする。さて、今度は洋物に挑戦してみるか。
August 9, 2005
コメント(0)
-
存在対効果
ワタミ社長 渡邉美樹氏の記事を読んだ。この方のことは良く知らないが、最近、マスコミ等で見るたびに気になる方である。知っていることといえば、起業するために佐川急便で資金を貯めた。目標通り数年で居酒屋を始め成功。現在は、学校経営をやっている。お好み焼き事業は失敗した。手帳にしなければならないことと、その期限をびっしり書いて、できたことは消していく。それぐらい目標とその期限を重視している。ひと月に一度、屋久島へ行く。今回読んだ日経ベンチャー(8/4)には、「存在対効果」について書いてあった。・・・・・「人間には誰にも与えられた役割があると思っている。自分の存在対効果を最大にするのが、僕の役割だと思っている」・・・・・・(中略)存在対効果とは、「周りの人達にどれだけ良い影響を与えられるか。より多くの人々の幸せに関わる。より多くの人々の笑顔に触れる。自分の存在対効果を最大にするとは、すなわちそういう意味です」・・・・・・そうだよな。存在対効果を最大にするのが自分の役割。自分の存在対効果ってどんなものなのだろう?存在対効果を最大にするということは、自らの存在はどんなものか?その存在を最大にするためにはどうしたらいいか?そういえば、この前、結婚式で会った友人からも「強み」についての話を聞いた。自分の強みは何か?「自分の強み程、わかりにくい」とも。存在対効果を最大にするには少なくとも存在や強みは理解しておかないといけないだろうな。それを最大にする方法・・・・、これは悩むなぁ。
August 5, 2005
コメント(5)
-
「現状維持」と「現状否定」
数年前、ISOとTQC(Total Quality Control)の違いを聞いたことがある。ISOが品質維持を目的とした「現状維持」であるのに対し、TQCは利益追求のための「現状否定」であるという。つまり、ISOはこれからもこの品質を維持していくよということ。TQCは今のままではダメ、まだまだ改善していくよということ。マネジメントとリーダーシップも同じだ。マネジメントとは、既存のシステムをよりよく運営すること。リーダーシップとは、既存のシステムを変革して新しいシステムをつくること。複雑且つ変化する現在のビジネス環境のもとでは、「現状維持」と「現状否定」のどちらも必要なのである。これで思い出すのが、数ヶ月前の大阪の夜。初めて会った人に、催眠を薦められた。その時、まったく興味がなかったので、「今の自分にとって必要だと思わないし、やりたいとも思わない」とお答えしたら、「あなたは自分を知ることを恐れていますね」と、いわれた。「いえいえ、そんなんまったく恐れてないですよ。悩みがあるわけでなし、必要ないと思っているだけ。ほんとけっこうです」と、お断りした。今の自分を否定する気持ちもなかったし、変える必要性も感じていなかった。新たな気づきが欲しいわけでもなかった。要するに「現状維持」でよかったのである。しかし、その方、ご自分の経験とその良さをずっと語られていた。そういうあなたこそ、ご自身の「現状否定」をしてはどうですか?と、いえばよかったのかな。
August 2, 2005
コメント(0)
-
結婚パーティーに出てきた。
土曜日は友人の結婚パーティーに出てきた。これで今月は2度目の結婚式出席になる。最近の結婚式にはいろんな形があるが、今回の出席者は仲の良い友人の集まり。といっても、100名が集まるのだからすごい!お二人の普段からのお付き合い、愛され方がよくわかる。今回の唄は2曲、「HERAT」と「Stand By Me」友人と一緒にギター演奏した。先日、あるギタリストに、唄を聴いてもらうためには、演奏前に惹きつけることが大事といわれた。今回は、それをきっちり守って歌う前に注目してくれそうなことを話してみた。たまたま、演奏前に新婦の友人4名が話していた。新婦の名前を呼ぶ彼女達の発音は、かなりなまっていた。(笑)新婦と自分は同郷なので、懐かしさもあり思わず微笑んだ。とっさにこのネタで行こうと思った。極端な地元なまりで「○○さんの友人です」クスクスと会場も笑ってくれて、注目してくれた。おかげでよく聴いてもらえた。しかし、「こんなに方言丸出しでしゃべる人いないよ」と、この新婦さんによく言われたものだが・・・、「おいおい!あなたの友人が一番なまってるじゃないの!(笑)」
August 1, 2005
コメント(2)
-
目利きが自分で出来ない奴が利用するのがブランドや!
仕事の帰りに御茶ノ水のギターショップへ行った。あるわあるわ、いろんなギターがある。数千円単位の安価なものから、100万円近くの高価なものまで多種多様。若手の販売員が説明してくれた。前回のショップ店員とはまた違う感じ。やわらかく、有名メーカーのギターを紹介してくれた。ちょうどいい機会だと思ったので、前回ショップで気になったギターのことを聞いてみた。すると、「ああ、あのギターはそこのショップの自社製品ですよ。「うちにもあるんですけどね。」つまり、楽器会社がギター製作会社と提携して作った、オリジナルブランドというわけである。そこで、マーケティングや流通業界に詳しい友人へメールを入れた。「オリジナルブランドって、どうなん?」その答えは、「業種によって違うが、(服などは)昔は安かろう悪かろうというのもあった。そもそも、大手デパートなどが大量に購入する代わりに、原価を安く作らせるというのが始まりや。しかし、最近は変わってきて、こだわりの町工場や厨房で作るような例もある。中には、いい物を作って安く提供しているような例もある。」「そうか、だから比較的安い値段で、あの材質・デザインができるわけだね。しかし、実際に音を聴いてみるとこれがええ音する。有名ミュージシャン愛用のギターと比べたら、こっちの方が良かった・・・・。ミュージシャンに聞いても知らんというし、それで悩んでる」すると、「それやったら、メーカーの評判をネットで調べたらええ。いろんな意見があるやろうが、お前ならどれが本当で本当じゃないか判断できるやろう。それに、ブランドっちゅうもんは、目利きが自分で出来ない奴が利用するもんやからな!」ほんと、その通りだ。
July 14, 2005
コメント(0)
-
ギターの買い方
「ドラゴン桜」の中に「グローブの買い方」という章がある。親が子供にグローブを買ってやる際に、「高級なグローブを買うか?」、「手始めに安価なグローブから買うか?」という話だ。さて、どうだろう?手始めに安価なグローブから買い、上手くなるにつれて、いいグローブを買ってあげようと考えるだろうか?答えは「ノー」だ。安いグローブを手にした子供は、将来プロ野球選手になろうという高い目標設定はできない。高い目標設定ができない子供は、グローブに応じたプレー(行動)しかできない。さらに低いグローブの価値がそれでもかまわないという感情を抱かす。反対に高いグローブを手にした子供はどうか?高価なグローブを手にした喜びと同時に、このグローブを使いこなせるプロ野球選手のようになりたいと願う。そこからスタートできると云う訳である。同時に親から買ってもらった高価なグローブを粗末にできないという感情が働き、それを無駄にしない思考や行動を繰り返そうとする。だから、「高級なグローブを買ってやること」だと・・・。先日、会社の帰りに、いつも行く楽器屋へ立ち寄った。今のエレアコの限界を感じていたので、新しいギター購入を考えていた。自分の購入コンセプトとしては、「メーカーがどうのということではなく、職人が丹精込めて作ったギターを手にしたい」ということ。「どんなギターをお探しですか?」と質問してきた店員さんに、そのままこの言葉を伝え、「だから、岐阜のメーカーさんのギターがいいと思ってるんです」と答えた。すると、その店員さん、「あそこはいいギターですよね。ただ受注生産を取ってるし、丁寧に作っているので1年待ちです」「・・・・・」「でしたら、他のメーカーでもおすすめできる商品がありますよ!こちらに来てみてください。」「このギターなんですが、お客様のおっしゃるように職人肌だし、ギター作りには大手メーカーにないいいところがありますよ。木は単板ですし、木目は狭くて均一、有名ではないですが、ここの社長はギターを梱包で送ることなく、手で持ってくるんですよ!」「それとギターは弾いてみて、どんな音がするか聴いてみないと好き好きがありますからね。よかったらここで弾いてみませんか?」「是非、触らせてください!!」そのときに、隣にあった有名ミュージシャン使用のギターも合わせて弾かせてもらった。やはり、ドーンと響いてきたのは店員さんお奨めのギター。ただ、今まで聴いたことがないメーカーさん。しかし、ギターフレットに関して特許を取得している個性あるアコギ。対して、有名ミュージシャン使用のギター、やわらかい音はしたが、自分の感性には特に響かなかった。自分の演奏する曲調、弾き方、音の好み、ボリューム感、デザインetcの評価基準はあるが、どれも店員さんお奨めのギターがいい!値段は確か、8万円、10万円、28万5千円と3本あった。ダントツで28万5千円のギターがすべての面ですばらしい。オー!欲しい!!うー・・・・。ギターは大事に使えば一生もん。使い込んで振動を与え続けると、安定していい音が出てくる。長い期間で考えればそんなに高い買い物ではないか・・・。先日、プロのミュージシャンにこの件を相談したら、やはり「このメーカー、聞いたことない」とのこと。しかし、「自分のこれだと思う音があったなら、それがいい」「いいギターを買うと、うまくなるよ」とも言っていた。そうか、「グローブの買い方」ならぬ「ギターの買い方」か・・・悩むのは悩むが、うれしい悩みではある。
July 12, 2005
コメント(0)
-
ドラゴン桜
ドラゴン桜という漫画がある。ドラマ化されて先週より放映されている。倒産寸前の高校再建のため、弁護士が自らが陣頭指揮を執り、東大合格者を出そうというストーリーだ。これがとても面白い。主人公 桜木のセリフには、世の中の仕組みや不条理を上手に表現した説得力ある言葉が並ぶ。「世の中の仕組みやルールは頭のいい奴が考えるようになっている。自分達の都合のいいようにな。そうしてだまされる者は一生だまされ続ける。そうならないためにもお前らも東大へ行って、世の中のルールを作る側の人生を歩め。」ダメ高校の落ちこぼれ男女2人が東大を目指す。桜木の指導に従い、勉強の仕方を知る。それは将来こうなりたいという未来像からの逆算発想である。高校を再建する(将来像)⇒世間へアピールする⇒1年目に5名の東大合格者を出す。⇒落ちこぼれ男女2人を指導落ちこぼれ男女2人の指導には、勉強の仕方があると書いた。具体的には、「受験校(東大)の傾向」、「配点等の詳細分析」、「記憶の仕組み」、「脳の仕組み」、「からだの仕組み」、「コーチング技術」、「目標の立て方」「心理的配慮」があらゆるところに散りばめてある。つまり、受験を通して「生き方を学ぶ」ということでもある。対照的に面白いのが、他の教師陣である。おそらく作者が今の教師の現状を表現したかったのだろう、皮肉を込めた日本の高校教師の弱点・欠点を表現している。「明るく健やかで健康的な文武両道の生徒を作る」などと一見正しいかのような、抽象的表現を平気で発言する教師などはその典型であろう。これは一般社会にも通じるものが多々ある。是非一度、購読かドラマ鑑賞をされてはいかがでしょうか。
July 11, 2005
コメント(0)
-
なんとも情けない・・・。
なんとも情けない・・・。久しぶりの野球、0-4の惨敗だった。何よりも内容が悪すぎた。初回1番バッター、極度のオープンスタンス。外角へ投げておけば大丈夫だろうと不用意に投げた球をセンター前。打ち取った2番の浅いセンターフライがポテンヒット。盗塁を決められ、ノーアウト2,3塁のピンチ。次打者3番をショートライナー、ダブったと思った瞬間、サードの足が離れる。4番を歩かして満塁。5番勝負もボテボテの1塁ゴロがライト前で2点。この立ち上がりがすべてだった。やはり1番バッターへの入り方がすべてだろう。カーブのサインに首を振り、投げた安易な外角ストレート・・・。野球にはこういう怖さがある。落ち着いてやればいいのだが、守備陣にもピンチが伝わるといい影響は何もない。苦しさが伝わるので、それに連鎖反応が出る。相手の投手は速球派の好投手。チャンスを作るももう1本が出なかった。しかし、情けない・・・。悪いところばかりがでた、多くの反省が残る試合だった。
June 26, 2005
コメント(0)
-
ライブ
無事週末のライブは終了。直前に出張が入っていたため、ハードスケジュールだった。金曜日の朝に新幹線で広島入り。翌日の始発の羽田行きで帰京。そこから会場の東京郊外まで、ギターとアンプを抱えて移動。これが重いこと重いこと。都内から持ち運ぶには重労働・・・。しかも途中の駅で大雨。あらら・・・・。しかし、幸運なことにバスを降りる頃、雨が上がった。到着するとすぐに急いでライブ準備。重要な機材は運んであったので、ギターのチューニングとボーカル君と歌合わせ。最後の1分1秒までやれることはやろうということで、6曲通しで小声で練習。その曲その曲のポイントを確認しつつ、気合を入れていく。よく練習したので「いける!」という感じ。二人で声を出して、テンションを高める。開始前のこの高ぶる緊張感がたまらない。いよいよライブ。「さあ、いくぞ!」って思ったら、暗~い暗いメッセージ・・・・。またこれが長い長い(笑)。最後に紹介されて、「バンドへどうぞ」って、こっちへ振られた。「えっ??」って感じ・・・(笑)しかし、ここからドラムの名手、ベースの名手ふたりはさすが。かっこいい演奏で見事挽回。さあ、ここから歌いだし!と思ったら、今度はドラムのハイハットがずれてるとのこと(笑)「ちょっと待って」という合図に頷き、少し待つ。準備が整い、ゴーのサイン!「花びらの~♪」・・・・・そこからは、すべて順調。聴く力のすごい人たち、さすが専門家集団。いつものように大いに盛り上がってくれた。一つ一つの笑顔を見ながら演奏することはとても楽しいこと。いつもありがたいと思う。自分個人としては、ギター演奏、ハモリ、歌い方など反省は多々あるが、ライブ自体は滞りなく終了できたと思う。ただ、ライブというのは聴く位置で、聞こえてくる音が違う。自分のところでは分からない音が、聴いてくれる人たちに届いているのだろうか。そんなことを考えながら家路に着いた。
June 10, 2005
コメント(4)
-
心地よい音を奏でるために
本番まで残された日はあと1週間。ギターパート完成まであと少しだが、イマイチ出来具合に納得がいかない。最大の課題はリズム。昨晩はこの前購入したメトロノームを活用して、カッチンカッチンに合わせ演奏してみると、あらら自分のイメージと違う。初めから、この練習しておけばよかったと少し反省。ギターコードをすべて拾い上げたのが、3日前だからそれもやむを得ないことかもしれない。併せて歌も練習中。初挑戦のハモリがなかなか難しい。3度上げたり下げたりすればいいんだとのことだが、いつもは合わせてもらってばっかり。合わせるというか、ボーカルを引き立てる難しさを実感。立ててもらうことより、立てることの方が気を遣う(笑)基本的にどの曲もうまく聴かせるため、心地よく聴いてもらうためにはコツがある。特に曲の中での強弱。自分の音が小さいときは、どの楽器が映えなければならないのか。自分の音が映えるところはどこなのか。そんなことを考えながら練習している。今回はどんなライブになるか、それも楽しみである。
May 27, 2005
コメント(0)
全127件 (127件中 1-50件目)