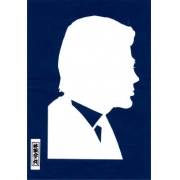【粗筋】
「頼むよ、一杯だけ……きれいだよ」
という調子で女房を拝みたおして飲んでしまう。一杯だけと言いながら、
「これで一合入っていたの……少なくないかい。少しだけなら飲まない方がいいんだ。飲ませたお前も悪いんだよ……ね、愛しているよ」
まあこんな調子でお替わりをねだり、
「おい、婆さん、お銚子が空だよ。酒飲みの女房なら空になる前に持ってこい。何年飼ってやってるんだ。無駄に年ばかりとりやがって……」
すっかりいい心持ちになってしまう。そこへ息子が帰って来るが、こちらもへべれけ。出入先の旦那に会って、「一杯飲め」「親父との約束で禁酒していますから駄目です」
「それならお前の所は出入り止めにするがどうだ」
「男同士で誓ったからには、飲めません」
「偉い、気に入った、その息で一杯やるか」
「いただ酔った以外きます」
という訳で飲んでしまったのだという。親父はすっかり腹を立てて、
「酒の毒が回って顔が三つも四つもあるぞ。そんな化け物にこの家は譲れんぞ」
「こんなグルグル回る家、もらったってしょうがねえや」
【成立】
安永2(1773)年『坐笑産』の「親子生酔」、宝永4(1707)年『露休置土産』の「親子共に大上戸』。文化4(1807)年の噺家喜久亭壽暁のネタ帳『滑稽集』に「おやじむすこ生酔
廻る家ヲ何ニする者」とある。もともとは小噺で、『円朝全集』にも「親子の生酔」という題で、小噺として載っている。
昔の 露の五郎兵衛
の速記は、「この家は譲れぬぞ」「こんなにくるくる回る家はもらいたくない」「馬鹿野郎、お前の面は二つに見えるわ」と、落ちの手順が逆である。実はこれが元の形らしく、江戸の古い書物も同じである。
顔が幾つに見えるかは適当。少ないのはこの速記と同じ「二つに見える」。聞いたので最も多いのは「七つも八つも」……ううん、多すぎないか……
酔った以外に原因があるかも。
東京では親父が飲みたくてたまらないという描写から、酔った描写、親子対面以降の酔っ払い同士の会話と、雰囲気も変化に富む。落ちの台詞が長いので、テンポを失うとぶちこわしになる。
柳家小さん(5)
は、二人の年齢の差を描き、息子は独身、結婚していれば「家なんかいらない」とは言わないだろうと、人物を設定したと言う。上方の桂枝雀は、息子の嫁に「お前にはまた酒を飲まんいい亭主をもらってやります」と言っている。
三笑亭夢丸(1)
は、親父の飲む場面をじみじみと演じ、息子が倒れ込んで来たとたんに、動きも派手になり、見事なドタバタで大爆笑となった。落ち着いた雰囲気の師匠だったから、印象に残っている。20人ほど生で見たが、この師匠が一番良かった。
三遊亭金馬(4)
は親父が飲み始めるあたりがメインかと思うほど丁寧。確かに、ここをあっさり説明で進んでしまうと、どうしてこんなに酔うまで飲ませたんだって疑問が残る。
大阪の噺は例によって思いきり明るいのだが、 桂枝雀(2)
は、親子で禁酒の約束がないようで、表で飲んで帰った親父が嫁を相手にぐずぐず言いながら寝てしまう。そこへ息子が酔っぱらって帰ってくるが明るく大騒ぎで、「うどん屋」の酔っ払いになり、家の前かごに乗る「替り目」になり、これだけ盛り込んで、それで全部でわずか20分の高座。親子の会話はあっという間で、「いらんわーい、こんなグルグル回る家」……勢いで進んだ印象。落ちの台詞も東京の説明的なものより良さそうに聞こえるが、違和感を感じたのは何だろう。要するに主人公が息子であり、詰め込み過ぎたことにより親子の心情がなくなってしまい、酔った描写だけになってしまったのが、私には物足りなかったのだと思う。
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
-
落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ) 2025.11.18
-
落語「は」の12:歯形(はがた) 2025.11.17
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List