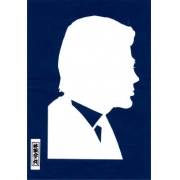テーマ: 落語について(2727)
カテゴリ: 落語
【粗筋】
質屋へ裃を入れた客が、質札を持って受け出しに来た。小僧の定吉が蔵へ取りに行くと、ちょうど隣の稽古屋で三味線の音がする。これを聞いた定吉は、蔵の中で『忠臣蔵』三段目を初めてしまう。帰りが遅いので番頭が呼びに行くよう命じられたが、これも仲間になり、定吉が勘平、番頭が伴内になって芝居の真似。旦那が呼びに来ると、これも芝居狂で、木戸番を初めてしまう。あきれた客が自分で蔵へ取りに来たが、木戸番になった主人に止められて、
「アオタはならんぞ」
「表で札わたして見ます」
【成立】
上方噺。「アオタ」はただ見のこと。質札を渡して見るという落ち。分からないから、最初に説明するか、噺の中に入れるか……似た話はあり、そういう説明が必要では、消えていく噺かも知れない。
【蘊蓄】
質屋。江戸では享保8(1771)年に組合制度をはじめ、2731戸があった。明和7(1778)年には二千戸に限るようにし、毎月2匁5分を幕府に収めさせた。土地は
10
年、他は3月から8月を期限とした。利子は月1分半(15%)と『守貞漫稿』にあるが、相場は月に4%、江戸では少し高めの金額を高めの利子で貸すこともあったらしい。京大阪では決まった額通りにしないと全財産を没収された。なお、借りるには本人と親類の証人が証書を書かなければならなかった。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[落語] カテゴリの最新記事
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
-
落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ) 2025.11.18
-
落語「は」の12:歯形(はがた) 2025.11.17
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
Freepage List
© Rakuten Group, Inc.