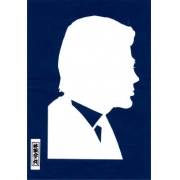【粗筋】
荻生徂徠(おぎゅうそらい)が出世前、正月だというのに貧乏で食う物もない。食う物があると思うから腹が減る、この世に食う物がないと思えば腹も減らないと学者らしい屁理屈で乗り切ろうとしたが、それでも腹が減って仕方がない。2日に豆腐屋が売り歩くのを呼び止め、2丁をぺろりと食べ、
「見事な豆腐。何、親の代から豆腐屋。実に見事じゃ。幾らじゃ。1つ4文で8文になる……今日は小さいのがない、明日一緒に払おう」
という。翌日も同じ。豆腐だけでは持つ訳がなく、日に日に弱ってくるが、3日目になると、
「今日は小さいのがない」
「そうおっしゃると思って今日は家中の銭をかき集めて来ました。大きいのでも結構で」
「小さいのがないのに、大きいものがある訳がない」
あきれかえった豆腐屋だが、食べっぷりの良さ、素直にあやまる様子に心を動かされ、明日からは腹にたまるようおからを持ってくると約束した。
それからどれくらい経ったか、豆腐屋が風邪をひいて数日休み、久しぶりに徂徠の家に行くと、引っ越した後だった。
2年後、赤穂浪士の討ち入りが評判になった頃、火事のために焼け出された豆腐屋夫婦に、大工が現れて店を建て直すから、その間は何とかつないでおけ、と大金を置いて行く。やがて店を建てたから来いといわれて行くと、立派な店が出来ている。金を出してくれたのは徂徠であった。幕府の要人の目にとまって出世したのである。
「優しい心を忘れず、うまい豆腐を作れよ」
といわれて商売に励み、お屋敷出入りの豆腐屋になるという、徂徠豆腐という一席。
【成立】
講談では「出世豆腐」という題で演じられている。2002年に人間国宝になった直後の一龍斎貞水、神田蘭ら、何人も講談で聴いた。落語で聞いたのは圓窓師匠と金太郎師匠が良かった。
【蘊蓄】
江戸の豆腐には紅葉のデザインが入っていた。『俳諧当世男』(延宝4)の
朝風や紅葉をさそふ豆腐桶 重秀
という句をとり、「紅葉」に「買うよう」の洒落をきかせたのだという。大きさも現在のものよりかなり大きい。
荻生徂徠(1666~1728)。江戸の儒学者、思想家。父親は綱吉の侍医だったが、蟄居して現在の千葉県茂原市に移る。この時徂徠も移り住んで独学、元禄3年25歳で江戸に戻り、31歳にして柳沢吉保に抜擢され、学問を教え政治に意見を述べた。赤穂浪士の討ち入りに対し、処罰を持って臨むことが忠義の道にも通じるという意見を述べ、これが採用されて全員が切腹したというのは名高い。
その後柳沢の失脚で日本橋茅場町で私塾を開くが、1722年頃、吉宗に呼ばれて出仕するようになった。弟は吉宗の侍医、北渓。
-
落語「は」の14:ばかのむき身(ばかの… 2025.11.19
-
落語「は」の13:馬鹿竹(ばかたけ) 2025.11.18
-
落語「は」の12:歯形(はがた) 2025.11.17
PR
Keyword Search
Comments
Freepage List